第3章 第4節 物価安定下の金融政策
| 第1章 世界経済の現況 | 第2章 アメリカ経済の長期拡大の要因と課題 | 第3章 物価安定下の世界経済 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 |
| 概観 | アメリカ | 欧州 | アジア | 金融・商品 | 通貨・金融システム | 特徴 | 要因 | 生産性 | 課題 | 現状 | 要因 | 特徴 | 金融政策 |
第4節 物価安定下の金融政策
90年代における物価安定の達成はマクロ経済政策の大きな成果であった。これによって、景気拡大の終期に需給のひっ迫から物価上昇率が高まり、需要を抑えようとして金融が相当引き締められる結果、景気が下降局面に入るといった形で、物価上昇率の高まりが不安定な循環の要因になるという可能性は減少したと考えられる。しかし、これによってマクロ経済が安定性を増し、景気の後退や減速を経験しないで済むようになったかというと、必ずしもそのようにはいえない。世界経済全体でみると、90年代には二度の景気の大きな減速を経験した。また、主要先進7か国のGDPギャップをみても、特に景気循環の振幅が小さくなっているようにはみえない(第3-2-14図)。さらに、92年のヨーロッパにおけるERM(Exchange Rate Mechanism)の危機、94年のメキシコのペソ危機、97年央からのアジア危機、98年のロシア、ブラジルでの危機等、世界経済は90年代に多くの重大な通貨・金融危機を経験した。
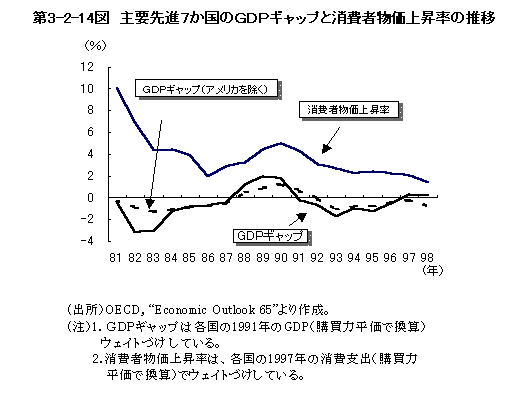
このような不安定性をもたらした背景には国際的資本移動の活発化があることは明らかであるが、マクロ経済政策の観点からみてより重要な要因としては、景気後退局面でのデフレの可能性の高まりと資産価格の大幅な変動という二つを挙げることができよう。物価安定を達成した90年代のマクロ経済政策は、この二つの新しい困難な課題に直面している。すなわち、低インフレないしゼロインフレを通り越して物価下落(デフレ)が景気後退期に生じるような場合、あるいは、財・サービスの価格が安定する中で、資産価格が大幅な変動を示す場合にどのような対応をとるか、これが物価安定下における新しい政策課題として重要となっている。
本節では、まず名目金利はマイナスにはなり得ないということが、物価安定下での金融政策にどのような制約を課すのかについてみた後、こうした二つの新しいマクロ経済政策の課題について考察する。最後に、数パーセントという低いインフレ率を達成した先進諸国にとってのゼロインフレと低インフレのコストとベネフィットを比較する。
1 金融政策の有効性
物価安定下の金融政策を考える際に最も大きな制約となるのが、名目金利はマイナスにはなり得ないということである。金利引下げにより金融を緩和しても、名目金利が極めて低い状況では、それを更に引き下げられる余地は極めて限られている。一般に金融緩和は、名目金利の引下げにより、実質金利(名目金利-期待物価上昇率)の引下げを目指すものである。したがって、物価安定が景気の後退を伴っており、それに対して金融緩和で対応しようとする場合、実質金利を引き下げることが重要となるが、名目金利の水準が低ければ低いほど名目金利の引下げ余地が限られ、また、期待物価上昇率が低ければ低いほど、実質金利の下限(名目金利が0%の場合の実質金利)は高くなる。例えば、期待物価上昇率が2%であれば、名目金利を0%まで引き下げることによって、実質金利はマイナス2%まで低下するが、期待物価上昇率が0%であれば、名目金利を0%まで引き下げても、実質金利は0%までしか低下しない。このように、名目金利のゼロ下限が制約となって、物価安定下ではそうではない場合に比べて、実質金利の下限が高まり、金利を通じた景気刺激効果には限界がある。
金融政策が実体経済に影響を与えるメカニズムには様々なものがあるが、名目金利の引下げ余地がほとんどない場合、金利ルートを通じての金融政策の伝播がほとんど期待できないことから、金融政策の効果は限定的である可能性がある。換言すれば、物価安定下では、金融政策の効果は非対称的となる可能性があり、引締め(実質金利の引上げ)により過熱する経済を抑えることに比べて、収縮している経済を緩和(実質金利の引下げ)によって回復させることは困難な場合もあるということである。そしてこのことは、以下でみるように、物価安定時代の金融政策の運営に関して重要な含意を有する。
2 デフレ懸念と金融政策
(物価安定下で高まる景気後退局面でのデフレの可能性)
物価安定が恒常化すれば、景気が後退局面にはいった時などにデフレに陥る可能性は高い。例えば、中長期的に年10%の物価上昇率を経験している時代であれば、景気の後退期においても物価上昇率は7~8%程度より低くなる可能性はそれほど高くなかったであろう。しかし、中長期的に年2%の物価上昇率を経験している場合には、景気の後退期において物価が下落する可能性は決して低いとはいえないであろう。
現実にいくつかの国ではここ数年物価上昇率はマイナスを記録している。例えば、ニュー・ジーランドでは、99年第1四半期から3四半期連続して消費者物価上昇率(前年同期比)はマイナスを記録している。また、同じく消費者物価上昇率(前年同期比)でみて、日本でも99年7月まで6か月連続、スウェーデンでも99年2月まで8か月連続、オーストラリアでも98年第1四半期まで3四半期連続で物価は下落している。さらに、これらの先進国以外でも、中国では99年9月まで18か月連続、香港では99年9月まで12か月連続、アルゼンチンでは99年9月まで7か月連続で物価は下落している。
さらに、一度デフレスパイラル(物価下落の実体経済への悪影響がはっきり現れる形で両者がスパイラル的に落ち込む状況)に陥ると、金融政策面での制約もあり、そこから抜け出すのは容易でないという意味において、政策当局は物価の下落に対しては細心の注意を払う必要がある。
ただし、物価の下落は必ずしも景気の後退によるとは限らない。例えば、生産性の向上といった供給面の要因によって下落が生じている場合には、むしろ経済にとってプラスであることには留意が必要である。
デフレスパイラルの危険性についてみる前に、ここではまず、物価上昇率の低下ではなく、物価の下落が実体経済にどのような影響を与えるかについてみてみよう。
(デフレの実体経済への影響)
物価下落は実体経済に様々な影響を与えるが、そのうち主要なものについて整理すると、以下のとおりである。
- a)実質債務残高増加効果(フィッシャー効果) 物価の下落によって実質債務残高が増加することから、家計ないし企業の支出が低下する。債権者が居住者であるかぎり、実質債権残高も同様に増加するが、一般に債務者の支出性向の方が債権者の支出性向よりも高いことから、全体としては支出抑制効果を有するものと考えられる。
- b)実質金融純資産残高増加効果(ピグー効果) 物価の下落によって金融純資産残高が増加することによって、家計ないし企業の支出が増大する。
- c)支出先送り効果 物価の下落局面において、下落が将来も続くと見込まれる場合には、家計ないし企業が財・サービスの購入を先送りする傾向がみられる。
- d)実質貨幣残高増加効果 物価の下落により実質貨幣残高が増加することから、名目金利が低下する。したがって、名目金利が支出を増加させるかぎり、実体経済にプラスの効果をもたらす。
- e)実質金利上昇効果 物価の下落によって実質金利が上昇し、投資、消費が抑制される。ただし、期待物価も下落することから、少し長い目で見ると名目金利もこれを反映して低下し、実質金利は元の水準に戻る傾向を有している。
(デフレスパイラルの危険性)
いずれにしても、物価下落が経済全体の支出を減少させるように作用する場合には、支出の減少は次に更なる物価下落につながっていく。これがデフレスパイラルである。企業は通常、金融機関等から借入をして、工場施設や機械を購入し、所有しているので、金融資産については債務超過(売り持ち)、実物資産については債権超過(買い越し)となっている。したがって、物価が下落すると、実質債務残高増加効果によってバランス・シートは悪化し、支出を切り詰めることを余儀なくされる。また、企業も家計も、物価下落が将来も続くと見込んで、財・サービスの購入を先送りするかもしれない。こうした支出の減少が更なる物価下落をもたらし、支出の減少と物価の下落とがスパイラル的に増幅する。そして、一度こうしたデフレスパイラルに陥ると、そこから抜け出すのは容易ではない。
さらに、一般物価のみならず、借入の担保としている土地等の価格も下がる場合には、企業等の債務返済能力が一層低下することになる。こうした問題が深刻化すると、金融機関全体の不良債権が多くなり、最悪の場合には一国全体の金融仲介機能の低下をも招くことになる。そしてそのことが再び実体経済に下方圧力を加えることになる。デフレ、特に資産価格の下落を伴ったデフレのこわい点である。
こうした状況を打破するためには、積極的な金融・財政政策が必要となるが、金融政策については、名目金利はゼロを下回れないという大きな制約がある。仮にデフレスパイラルから抜け出るためには非常に低い、場合によってはマイナスの実質金利が要請されるとしても、物価が下落する中では、そのような非常に低い実質金利を達成することはできないのである。このような意味において、デフレへの対応は経済政策当局、とりわけ金融政策当局にとって極めて困難な課題となっている。
(政策対応の在り方)
80年代及び90年代の前半においては、より低い水準へと物価上昇率を下げていくことが先進国における金融政策の、あるいは経済政策全般の目標であったが、数パーセントという物価上昇率が実現され、逆に景気後退期にはデフレの可能性も高まっている今日においては、物価上昇率が過度に下落することに対してはそれが過度に上昇することに対してと同様に警戒するべきと考えられる。換言すれば、インフレ目標からの下方への乖離と上方への乖離に対しては対称的な対応が必要と考えられる。ある意味では、目標を下回ることの方がより問題が大きいとも言える。なぜなら、既にみたように、物価安定下では、金融政策の効果は非対称的となる可能性があり、引締めにより過熱する経済を抑えることに比べ、収縮している経済を緩和によって回復させることは困難な場合もあるためである。
現実にインフレ・ターゲティングを採用している主要国におけるインフレ率の目標をみると、イギリスではRPIX(小売物価指数から住宅金利を除いたもの)でみて前年比2.5%、カナダでは消費者物価指数(食料、燃料、間接税の影響を除く)でみて前年比1~3%、スウェーデンでは消費者物価指数で1~3%、ニュー・ジーランドでは消費者物価指数(間接税の変更、利子率の変更等を除く)で0~3%を目標としている。また、実質的にインフレ・ターゲティングを採用しているユーロ圏(ECB)ではHICP(消費者物価から医療費、持家コストなどを除き、幾何平均で集計したもの)でみて前年比2%未満を目標としている。ほとんどの国が対称的な目標を設定しているのに対し、ECBは目標からの上方乖離を下方乖離よりも問題視しているようにみえる。
いずれにしても、需要面からの要因によってもたらされたデフレに対しては、一般論として、拡張的な金融政策及び財政政策を採るべきであり、それによってデフレスパイラルに陥ることのないよう最大限の努力を傾注するべきである。また、こうした拡張的な金融・財政政策をより実効あらしめるためには、金融システム上の問題や労働市場の硬直性等の構造問題への取組も重要と考えられる。
デフレスパイラルに陥った経済を立て直すには多大なコストがかかる。したがって、政策当局は、経済がデフレスパイラルに陥らないように、最大限の注意を払うべきであり、そのために、早期にデフレの危機を察知し、時機を失せず十分に強力な対応を採るべきである。
3 資産価格変動と金融政策
財・サービスの価格が世界的に安定を示す中で、資産価格は引き続き不安定な動きを示しており、またこのことがマクロ経済の不安定性の一因ともなっている。90年代における日本経済停滞の大きな要因は、80年代後半に高騰した資産価格が暴落したことにあった。また、資本流入及び資産価格の大きな変動は90年代の新興国経済を危機に陥れてきた。主要先進7か国の株価のボラティリティー(変動度合い)をみると、全体としては、70年代から90年代にかけて必ずしも低下しているとはいえず、また実質GDPのボラティリティーも必ずしも低下しているとはいえない(第3-4-1表)。もちろん資産価格の中には、株価のみならず、地価、債券価格、為替レートなども含まれるが、以下では特にマクロ経済の不安定性とも関連の深い、そして現在のアメリカの経済政策運営上も極めて重要な株価について、その一般物価との乖離の状況をみた後に、株価を始めとする資産価格の変動に対する経済政策の対応の在り方について検討する。
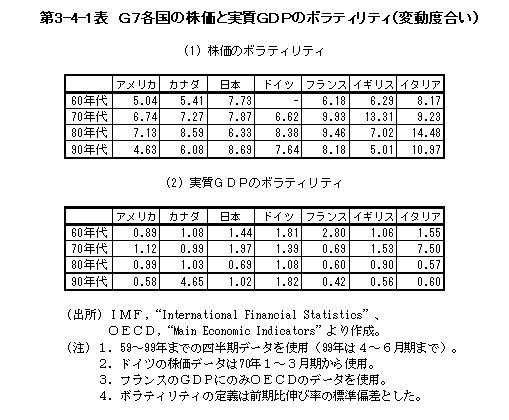
(株価と一般物価との乖離)
主要先進国のデータをみると、一般物価の上昇率と株価の上昇率とは必ずしも正の相関を示しておらず、逆に負の相関を示している場合も多くみられ、ドイツとアメリカとで特に負の相関が強くみられる。とりわけ、現時点でのアメリカでは一般物価の安定と株価の高騰との対照が際立っている(第3-4-2表)。またイギリスを始めとするヨーロッパ諸国でも、アメリカほどではないにしろ株価は高い上昇率を示している。
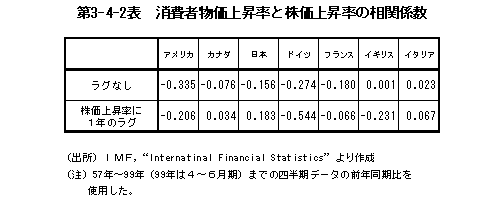
こうしたことが起こる理由としては、いくつか考えられる。まず、物価安定そのものが資産価格の上昇を促す要素となり得る。すなわち、過去の経験に照らすと、物価が安定し良好な経済環境が持続している時には、投資家は暗黙のうちに良好な経済環境が将来も持続すると考えがちであり、投資家のリスクテイクが助長され、その結果、資産価格に上昇圧力が加わるという状況がみられた。この点に関しては、アメリカ連邦準備理事会のグリーンスパン議長も、議会証言等において同様の趣旨の発言を行っている[注1]。次に、生産性の向上などのプラスのサプライ・ショックが生じた場合にも、物価の下落と株価の上昇とは両立する。しかし、現実には株価の上昇が生産性向上等のファンダメンタルズを反映したものなのか、そうではなくバブル的要素を多分に含んだものなのかを事前に判断することは極めて困難であるといわざるを得ない。
(政策対応の在り方)
いずれにしても、政策当局、とりわけ金融政策当局は、物価の安定のみならず、資産価格の動向にも注意を払う必要がある。90年代にいくつかの国で起きた金融危機の経験をみても、資産価格の大幅な変動が、マクロ経済の変動を引き起こす、あるいは増幅するということがしばしばみられた。金融政策は資産価格の安定化そのものを目標とするべきではないが、それと同時に、資産価格の動きが経済及び金融の安定性にどのような影響を与えるかということを無視して、金融政策の運営を行うことはできないであろう。
物価安定下の資産価格変動に対して金融政策当局が具体的にどのように対応するべきかについては、以下の点を指摘することができる。まず、資産価格が暴落し、金融市場が混乱して、金融システムが崩壊する危険があるような場合(例えば、87年10月のブラック・マンデー)には、中央銀行は必要な流動性を供給することによって、資産価格の暴落に対応するべきことは言うまでもない。逆に、資産価格の上昇が需要の拡大を通じて望ましくない財・サービス価格の上昇を引き起こしそうな場合も、金融引締めが必要となる。
中央銀行の対応が必要となる可能性のあるもう一つの状況は、一般物価へのインフレ圧力はほとんどみられないものの、資産価格がますます持続不可能と考えられる水準へと上昇しつつあり、それゆえ反転が起こった場合には、金融システム及び実体経済に対する大きな不安定要因になると考えられる場合である。ただし、技術的には、資産価格の上昇がファンダメンタルズの改善(例えば、生産性上昇率の高まり)によるものなのか、それともバブル的要素を多分に含んでいるものなのかを事前に知ることは極めて困難である。しかし、こうした技術的困難にもかかわらず、資産価格の上昇が一般物価にまで広がるのを待って対応することはより高いものにつくことになるであろう。例えば、イングランド銀行は99年9月に政策金利を引き上げたが、こうした政策変更の判断材料の一つとして、住宅価格の上昇等が考慮されている。
物価安定下では、財・サービスのインフレ率だけをみていても、景気の拡大等に伴って経済全体にどれほどの不均衡が広がってきているのかを把握することは困難である。中央銀行は、資産価格が大きく変動している場合には、その変動がどのような理由によって生じているのかをつきとめるよう努力するべきである。そのためには、資産価格の動向のみならず、経済の他の側面において将来突然反転する可能性があるような不均衡が発生していないかどうかを検討するべきであろう。すなわち、民間部門の貯蓄・投資バランスや経常収支に大きな不均衡は発生していないか、さらに名目生産額の伸びと比較して貨幣供給量や信用残高の伸びが高過ぎないか、又は低過ぎないかといった点に注意を払う必要がある。
(アメリカの株高懸念)
現在のアメリカの株高についても、それがニューエコノミー論の主張するように、主として生産性の向上によるものか、あるいは非合理的な期待に基づくものなのかを判断することは極めて困難である。しかし、株高と同時に、家計部門における低水準の貯蓄率や大幅な経常収支赤字(99年4~6月期GDP比3.5%)といった、中長期的に持続可能とは考えにくい不均衡も発生している。IMFの“World Capital Market 1999”も主張するように、最近では長期金利が上昇傾向にあること、今後は景気の減速を反映して企業収益の伸びも鈍化が予想されること、このところの債券市場をみてもリスク・プレミアムは低下していないことを考慮すると、この1年間で株高修正の危険性は高まったと考えざるを得ない。
4 ゼロインフレと低インフレのコストとベネフィット
既にみたように、90年代の世界経済では物価の安定化が進み、特に先進国だけを取り出すと、98年の平均消費者物価上昇率は1.4%と極めて低い水準になっている。こうした状況の下で、政策当局、とりわけ先進国の政策当局にとって低インフレとゼロインフレはどちらが望ましいのであろうか。この問いに対する答えは、当然各国の経済が置かれている状況や各種制度の在り方等に依存することから、一概に言うことは出来ない。以下では、数パーセント程度の低インフレと、究極の物価安定であるゼロインフレとのコストとベネフィットを比較秤量する。
(ゼロインフレのコスト)
ゼロインフレのコストの第一は、名目賃金に下方硬直性がある場合、労働市場の需給調整が困難になることである。何らかの外生的要因の変化により、ある産業の実質賃金が3%低下することが当該産業の労働需給の新しい均衡のために必要であったとしよう。この場合、仮に物価上昇率がゼロとすると、名目賃金は3%低下しなくてはならない。しかし、仮に物価上昇率が3%とすると、名目賃金が横ばいとしても、当該産業の労働需給は均衡することになる。名目賃金の下方硬直性を考えると、ゼロインフレよりも低インフレの方が労働市場の需給調整がしやすいのである。
コストの第二は、低インフレからゼロインフレに移行することに伴う雇用、生産面での犠牲が大きいことである。一般にフィリップス曲線は右下がりであり、物価上昇率を引き下げるためには失業率の上昇を受け入れなくてはならない。しかも、フィリップス曲線は直線ではなく、上述した名目賃金の下方硬直性がある場合、ゼロインフレに近づくにしたがって次第にフラットになり、物価上昇率を引き下げるために犠牲にしなくてはならない雇用、生産面でのコストは大きくなると考えられる。例えば、イギリス及び日本についてフィリップス曲線を見ると、物価上昇率が数パーセント以下の領域では曲線はフラットのようである(第3-4-3図)。
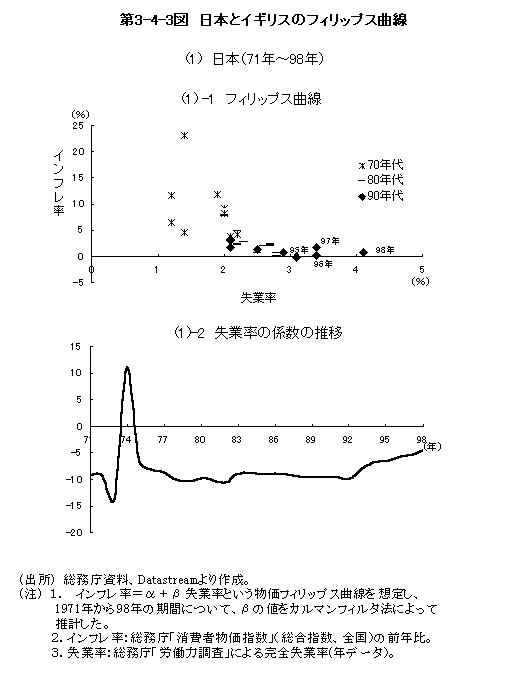
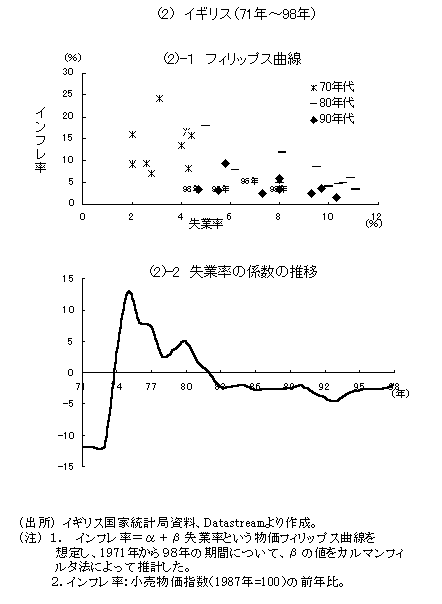
コストの第三は、名目金利が極めて低い場合、拡張的金融政策の効果がより限定的となる可能性がある。すなわち、名目金利がマイナスにはなり得ないことから、期待インフレ率がゼロの状況とプラスの状況を比較すると、前者の方が実質金利がより高くなるため、拡張的金融政策の景気刺激効果がより限定的なものとなる可能性がある。
(低インフレのコスト)
低インフレのコストとしてまず挙げられるのは以下の点である。一般にインフレは様々な資源配分上の撹乱や所得分配上の歪みをもたらすと考えられている。低インフレでも依然そのようなコストが発生するのに対し、ゼロインフレではそのようなコストは発生しないことから、ゼロインフレの方がその面では望ましいと考えられる。ただし、10パーセントを超えるようなインフレが経済に大きなマイナスの影響を与えるのは明白であるが、数パーセントのインフレがどの程度のマイナスの影響を与えるのかについては議論の分かれるところである。
次に、低インフレのコストとしてしばしば挙げられるのが、税制の歪みである。アメリカの経済学者Martin Feldsteinらによれば、アメリカの税制、特に資本所得(capital income)税制が物価上昇に対して中立的でないために、わずかなインフレであっても、資本蓄積等へのマイナスの影響を有する。すなわち、税金は名目の利子所得に課されることから、仮に実質の利子所得が同じであっても、インフレ率が高まることによって税額が増え、税引き後の実質収益率は低下する。したがって、その分人々の貯蓄は抑制され、資本蓄積も減少するというのである。Feldsteinの推計によれば、アメリカでインフレ率を2%から0%に引き下げると、一度限りの生産の低下(GDPの5%程度)を招くものの、将来の資本蓄積が進むことから、GDPの水準は恒常的に1%程度高まり、その結果、現在価値に直してGDPの約35%にあたる利益を長期的に得ることができる。したがって、長期の利益が短期の損失を大きく上回るとのことである。
ただし、実際の先進国のデータをみるかぎり、低インフレが成長率を高めるという関係は必ずしもみられない。OECD諸国の消費者物価上昇率と一人あたりGDP成長率とをプロットすると、両者の間には負の相関はみられない(第3-4-4図)。また、アメリカの経済学者Barroも、インフレ率と経済成長率の相関について、3期間(65~75年、75~85年、85~90年)のデータを高インフレ(15%以上)と低インフレ(15%未満)のグループに分けて調べた。その結果、負の相関が統計的に有意であると認められたのは高インフレのグループのみであった。
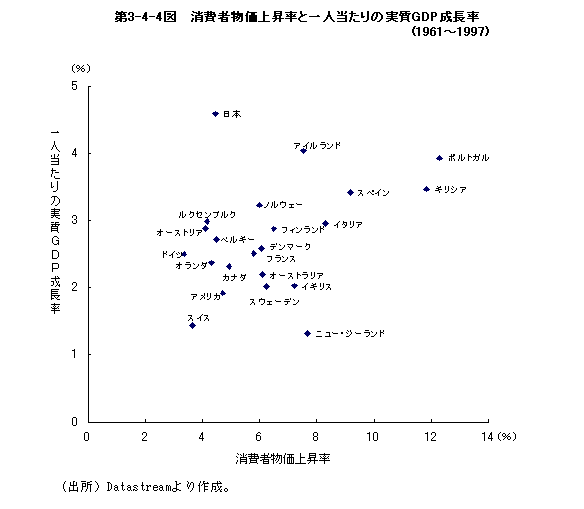
(まとめ)
こうしてみたように、ゼロインフレよりも低インフレが望ましい根拠としては、名目賃金の下方硬直性、物価安定下での犠牲率(物価上昇率を1%低下させるために必要な実質成長率の低下幅)の高さ、名目金利のゼロ下限等が挙げられる。逆に、低インフレよりゼロインフレが望ましい根拠としては、インフレの持つ資源配分撹乱効果、所得分配歪曲効果、税制の歪み等が挙げられる。また、別の観点として、公式の物価指数は、多くの場合、真の物価上昇率よりも高くでる傾向があるということも考慮する必要があろう[注2]。これらを総合してどちらが望ましいかについては、一概に言うことはできない。各国は、経済の置かれている初期条件、特にインフレ率の状況や、各種経済制度の在り方を考慮しながら、検討していくことになろう。
おわりに
世界的な物価安定は原油を始めとする一次産品価格の低下や国際的市場競争の激化等によるものであるのと同時に、80年代以降の経済政策努力の大きな成果でもあった。しかし、物価安定下でもマクロ経済の安定性は必ずしも高まっておらず、また、逆にデフレ懸念、資産価格の乱高下等の新たな政策課題も登場している。物価安定という新しい状況下で、政策当局も、各経済主体も、長らく続いた高インフレ時代の行動様式をそのまま踏襲するのではなく、新しい時代にふさわしい行動様式に切り換えていくことが肝要である。
また、インフレはマクロ的には経済にマイナスの影響を及ぼすことは言うまでもないが、個々の経済主体についてみると、逆に様々な経済的な問題について、従来はインフレがいつのまにか解決してくれるということが時としてあった。確かに、インフレは、それが予見されない場合には、金融資産の債権者から債務者への富の再分配を意味するため、個々の債務者の立場からはそのように感じられたであろう。しかし、債権者の方はその分損失を被っていたことも事実である。いずれにしても、今後はそうした解決法に頼ることはできないし、また頼るべきでもないであろう。経済全体でみれば、インフレは恣意的な富の再分配を行うに過ぎず、経済的問題は基本的には経済成長によって解決されるべきことを銘記するべきである。そして、富・所得の再分配は明確な意図を持った経済政策によってなされるべきであろう。
- 注1 Testimony of Chairman Alan Greenspan(1999年6月17日)
- 注2 OECDの資料によれば、アメリカでは0.8~1.5%ポイント、イギリスでは0.35~0.8%ポイント、カナダでは0.5%ポイント程度、ニュー・ジーランド及びノルウェーでは1.0%ポイント程度のCPIバイアスが毎年発生している。
| 第1章 世界経済の現況 | 第2章 アメリカ経済の長期拡大の要因と課題 | 第3章 物価安定下の世界経済 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 |
| 概観 | アメリカ | 欧州 | アジア | 金融・商品 | 通貨・金融システム | 特徴 | 要因 | 生産性 | 課題 | 現状 | 要因 | 特徴 | 金融政策 |

