第3章 第3節 物価安定下の経済の特徴
| 第1章 世界経済の現況 | 第2章 アメリカ経済の長期拡大の要因と課題 | 第3章 物価安定下の世界経済 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 |
| 概観 | アメリカ | 欧州 | アジア | 金融・商品 | 通貨・金融システム | 特徴 | 要因 | 生産性 | 課題 | 現状 | 要因 | 特徴 | 金融政策 |
第3節 物価安定下の経済の特徴
本節ではまず、物価安定下での経済は高インフレ下と比べどのような特徴を持っているのかについてみてみよう。期待インフレ、金利、賃金、失業率、財政収支、所得分配、為替レートといった重要な経済諸変数ないし経済構造が、物価安定下でどのように変わってきているか、またどのように変わっていくと考えられるのか、主に先進国を念頭に置きながら、実証的及び理論的観点から検討したい。これによって、今日の世界経済、特に先進国経済に共通して現れている幾つかの現象が、物価安定によって説明されることがわかる。厳密に言えば、物価の安定がどのような要因によってもたらされたのか等によって、その経済に与える影響も異なってくると考えられるが、ここではそのような点については捨象し、高インフレ下と比較して、物価安定下の経済が一般にどのような姿になるのかについて検討している。なお、物価安定下における資産価格の変動については第4節を参照されたい。
結論を先取りして言えば、物価安定下の経済は次のような特徴を持つものと考えられる。名目金利は低いが、実質金利は必ずしも低くない。逆に、景気浮揚のために実質金利を引き下げたいと思っても、名目金利はマイナスにはなり得ないので、実質金利を十分下げられない危険性がある。また、名目賃金上昇率は低いが、実質賃金上昇率は必ずしも低くなく、名目賃金の下方硬直性が強い場合には、逆に実質賃金は高めになり、その結果失業率が高めになる可能性がある。財政については、歳入面ではインフレ下でのような税の自然増収は期待できないが、名目金利が低いことから利払い費はインフレ下と比べて低くなる。分配面では、インフレによる債権者から債務者への実質的な富の再分配が抑制される。
(1)低い期待インフレ率
人々が将来のインフレ率に関しどのような期待を抱くかは、経済のパフォーマンスに大きな影響を与える。例えば、期待インフレ率が10%である場合と5%である場合では、労働者の要求する賃金上昇率も大きく異なり、その結果実際の賃金上昇率等も大きく異なってくる。この期待インフレ率は、一般には後ろ向きに形成される部分と、前向きに形成される部分とがあると考えられている。すなわち、過去の物価上昇率に引きずられる部分と、そのような過去とは独立に形成される部分とがあるということである。後者の例としては、金融政策当局への信頼が高いために、現状のインフレ率よりも低い目標インフレ率を反映したものになるといった場合がある。実際にどちらをより反映したものになるかは、様々な要因に左右されることから、一概には言えないが、いずれにしても相当程度過去の物価上昇率を反映したものになると考えられる。現実に、アメリカの期待物価上昇率の推移をみると、現実の物価上昇率と極めて似通った動きを示しており、近年は両方とも極めて低くなってきている(第3-3-1図)。また、物価上昇率が上昇する局面でも下降する局面でも、概して期待インフレ率が現実のインフレ率を後追いしていることがみてとれる。こうした実際のデータからもわかるように、物価安定の時代には、高インフレの時代と比べ、期待インフレ率も概して低いものになると考えられる。
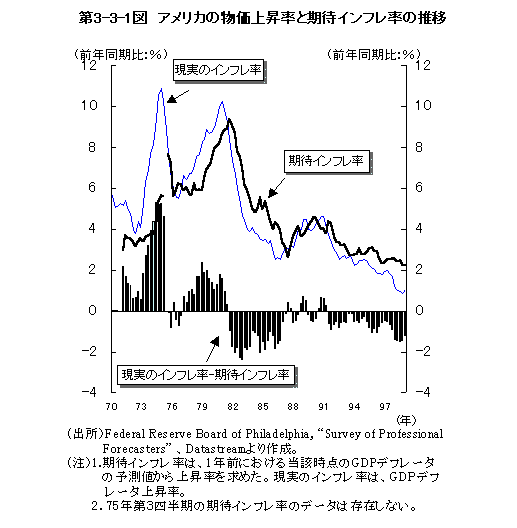
(2)低い名目金利
次に、名目金利についてみてみよう。名目金利は実質金利と期待インフレ率との和と捉えることができるが、このうち、実質金利については、その時々の物価上昇率とは直接関係なく、投資家の期待収益率や貯蓄家の将来選好等の実物的要因によって決定される。したがって、物価安定下では、期待インフレ率が低い分、概して名目金利も低くなる傾向にあると考えられる。実際に主要先進7か国の物価上昇率と名目金利との関係をみると、80年代から90年代にかけて物価上昇率が低下傾向を示す中で、名目金利も低下傾向を示していることがわかる(第3-3-2図)。近年は物価上昇率も名目金利もともに極めて低い水準にある。しかし、実質金利(実質化には期待インフレ率ではなく、実際のインフレ率を用いている)にはそうした長期的低下傾向はみられず、逆に高インフレ下の70年代には実質金利はマイナスになるなど、インフレ率との逆相関がみられる時期もある(第3-3-3図)。
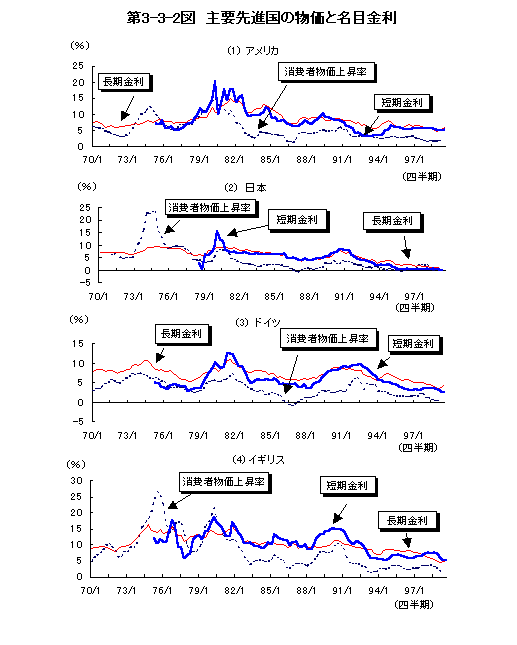
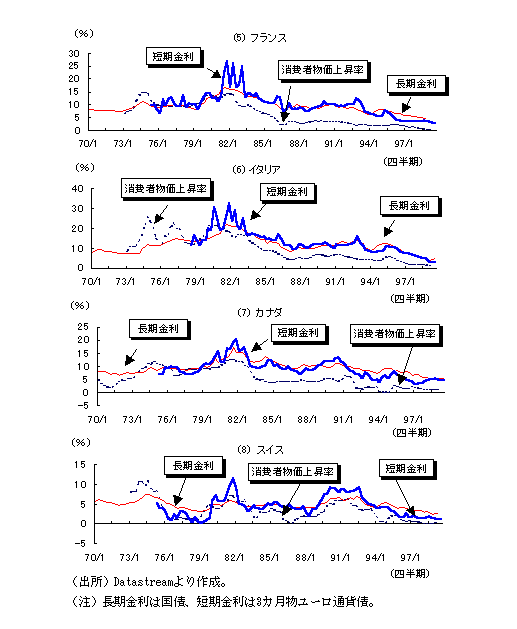
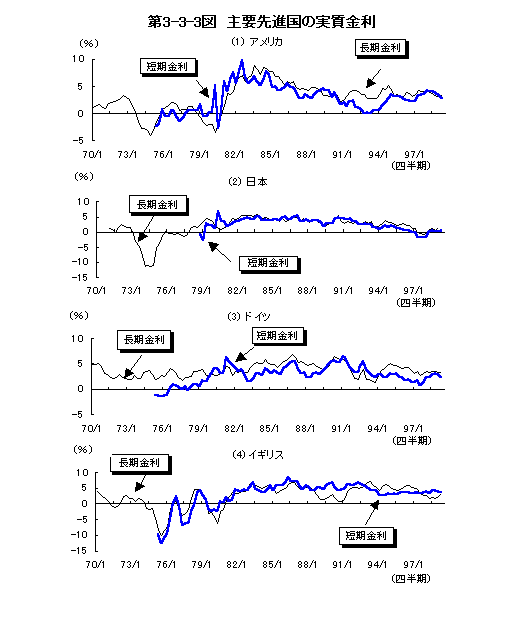
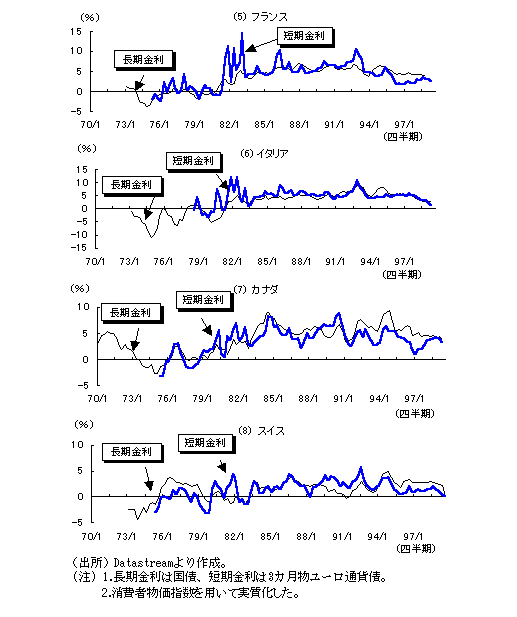
(3)低い名目賃金上昇率
一般に物価上昇率が高く、それゆえ期待インフレ率も高い状況下では、企業は物価上昇に見合う高い名目賃金上昇を認めることは可能であるし、また労働者も生計費の上昇率が高いことから、高い名目賃金上昇がなくては実質的な生活水準を維持ないし向上することができない。したがって、高インフレの時代には名目賃金上昇率は概して高くなりがちである。それと比較して、物価安定下では、名目賃金上昇率は概して低くなりがちである。実際に主要先進7か国の名目賃金上昇率の推移をみると、物価上昇率の低下を反映して、70年代から80,90年代にかけて大きく低下してきている(第3-3-4図)。そして、90年代にはいくつかの国で名目賃金が下落するケースが散見され、99年第2四半期においては日本(前年比1.7%減)及びカナダ(同1.6%減)で名目賃金が下落している。これに対し、実質賃金上昇率(実質化には期待インフレ率でなく、実際のインフレ率を用いている)には長期的な低下傾向はみられず、逆に、短期的な名目賃金の硬直性を反映して、70年代の高インフレ時代には大幅なマイナスになった時期もみられる(第3-3-5図)。
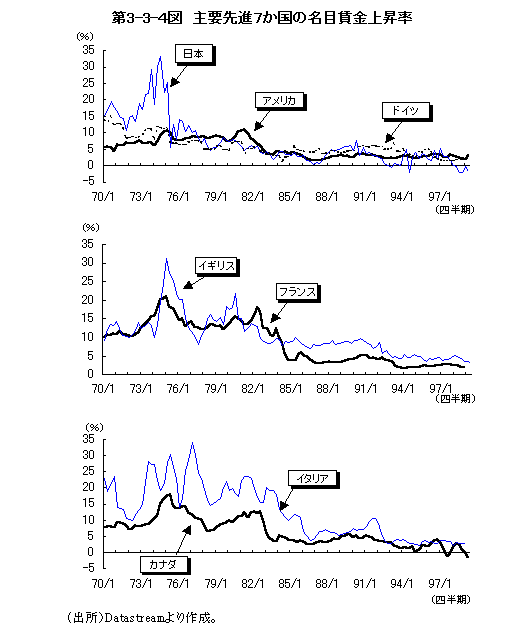
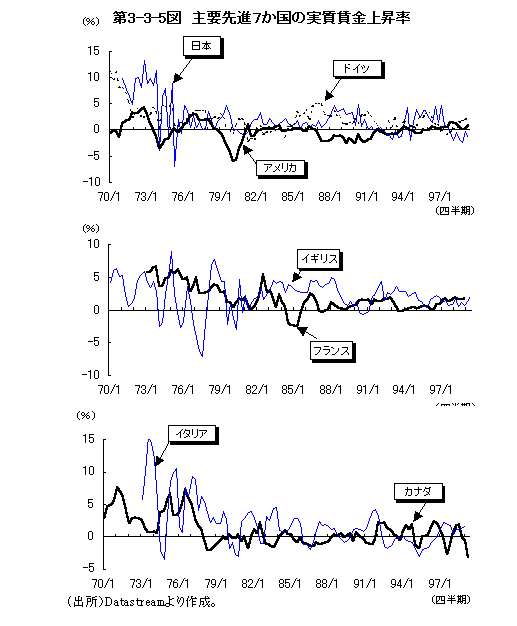
(4)名目賃金の下方硬直性とその実質賃金、失業率への影響
このように、名目賃金上昇率は物価の安定を反映して大きく低下するものの、名目賃金には下方硬直性があり、そのために本来需給を均衡させるのに必要な水準まで名目賃金(及び実質賃金)が下がらない可能性がある。そして、その結果自然失業率が高まる可能性がある。この点はマクロ経済運営上も重要な含意を有するので、以下やや詳しくみてみよう。
例えば、ある産業に対する需要が減少し、その産業の実質賃金が2%下落することが労働需給の調整のために必要だったとしよう。この場合、仮に物価上昇率が8%であれば、名目賃金は6%上昇しても必要な調整は行われる。しかし、仮に物価上昇率が1%であれば、名目賃金は1%下落しなくてはならないことになる。労働者は名目賃金の下落に対しては抵抗を示すであろうから、1%の物価上昇率の下では労働市場の調整がより困難なものとなる。そして、ある産業の実質賃金が2%下落することが必要になるという事態は決して稀有なことではなく、仮に経済全体の名目賃金上昇率が3%であったとしても、一部の産業ではそのような賃金下落が必要になることは十分に考えられる。また、経済全体の名目賃金上昇率が低くなればなるほど、名目賃金の下落が必要な産業も増えてくることになろう。こうしてみてわかるように、高インフレ下と比べ物価安定下では、相対的に実質賃金が高く、その分失業率が高くなる可能性がある。
ただし、ここで賃金と呼ぶのはいわゆる基本給だけではなく、残業代、ボーナス、フリンジベネフィット等を含めた労働コスト全体である。したがって、各国の労働コストの構成の違い等によって、その下方硬直性の程度は異なる。例えば、日本のように企業の業績をよりよく反映するボーナスの比重が高い場合には、全体としてみた名目賃金の硬直性は比較的弱いものと考えられる。
また、より厳密に考えると、労働生産性上昇率が高ければ、名目賃金の下方硬直性が労働市場の調整を困難にする度合いは低くなる。例えば、労働生産性が2%上昇していると仮定すると、そもそも実質賃金を引き下げる必要はないかもしれない。実質賃金が横ばいだったと仮定したとしても、単位労働コストを2%削減できるからである。
現実に賃金の下方硬直性がどの程度強いのかについては、実証の結果を待たなくてはならないが、アメリカのアンケート調査の結果をみると、経営者側にも労働者側にも名目賃金の引下げを嫌う傾向がみられる[注1]。
名目賃金が下方硬直性を持っていることの一つの理由は、70年代、80年代と高インフレの時代が続いたことであろう。そのような状況下で名目賃金が下がるということは実質賃金の大幅な引下げを意味した。したがって、今後物価安定の時代が続けば、名目賃金の引下げが従来と比べより受け入れられやすくなる可能性は十分ある。その場合には、労働市場での調整はより多くの部分が価格(賃金)によって行われ、その分だけ数量(雇用)での調整は少なくて済むことになる。
(5)財政
各国の租税構造をみると、ほとんどの国において個人所得税を中心に累進構造が組み込まれている。したがって、従来の高インフレ下では、仮に実質的な所得が増加していなかったとしても、課税所得がより税率の高い層(対象区分)に移ることによって、実質的な税負担が増える傾向にあった。しかし、物価安定下ではこのような自然増収は望みにくいことになる。他方、各国の歳出構造は、公債費を除けば、概して物価上昇率の影響を受けることは少なく、歳入構造と比べて物価上昇率に対してより中立的と考えてよいであろう。そのような意味において、物価安定下でプライマリー・バランス(基礎的財政収支=公債費を除く歳出と公債金収入を除いた歳入の収支)の健全化を図るには、従来以上の努力を必要とする。
次に、政府の公債費と物価上昇率との関係については、以下の点を指摘することができる。まず、物価安定下では概して名目金利が低いことから、利払い費は高インフレ時代と比べその分低くなるものと考えられる。ただし、物価安定を通り越して物価が下落するような事態に陥ると、公債残高の実質的な負担が高まる点に注意が必要である。実際にそうした事態が生ずる場合には、公債の償還費用を負担する将来世代から公債の保有者である現在世代への所得移転が発生するということを意味する。
(6)富の再分配
インフレは、それが予見されない場合には、金融資産の債権者から債務者への富の再分配を意味する。インフレによって金融資産の実質債務残高は減少し、元本及び利子の支払いが実質的に少なくなるからである。こうした意味での富の再分配は、民間の経済主体の間のみならず、民間経済主体と政府との間でも生ずる。物価安定下では、こうした恣意的な富の再分配(arbitrary redistributions of wealth)が生ずることが少なくなる。そして、後にみるように、物価が下落する場合には、逆に債務者から債権者への所得移転が発生することになる。
(7)為替レート
為替レートの決定要因についてはいくつかの理論があるが、中長期の為替レートの決定に関する有力な理論が購買力平価説である。この考え方によれば、中長期的には二国間の為替レートの変動率は両国の物価上昇率の差に等しくなる。物価上昇率の低い国の通貨が増価し、高い国の通貨が減価することになる。この理論を基に、物価安定下では概して為替の変動率は低くなるのではないかと推測する向きもある。高インフレの時代には物価上昇率の格差も大きかったのに対し、近年は各国の物価上昇率が低い水準に収斂してきており、格差が概して小さくなってきているからである。しかし、現実のデータをみると、短期の為替の変動率は必ずしも低くなってはいない(第3-3-6図、第3-3-7図)。
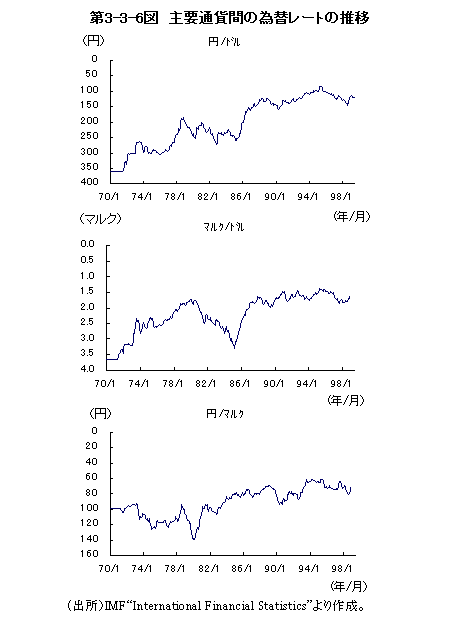
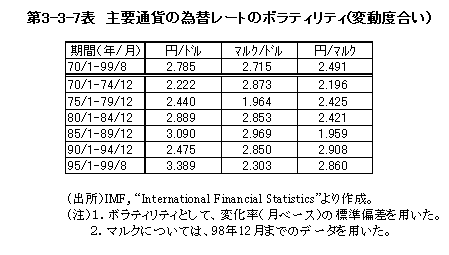
この理由としてはいくつか考えられるが、まず購買力平価説は中長期の為替変動を説明するものであって、短期の変動を説明するものでないという点が挙げられよう。このほかに、近年為替変動率が低下していない理由としては、国際的な資本移動が活発化してきていること等が考えられる。
- 注1 George A. Akerlof et al,“The Macroeconomics of Low Inflation”, Brooking Paper on Economic Activity (Jan. 1996).
| 第1章 世界経済の現況 | 第2章 アメリカ経済の長期拡大の要因と課題 | 第3章 物価安定下の世界経済 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 |
| 概観 | アメリカ | 欧州 | アジア | 金融・商品 | 通貨・金融システム | 特徴 | 要因 | 生産性 | 課題 | 現状 | 要因 | 特徴 | 金融政策 |

