第1章 第2節 戦後最長をうかがうアメリカの景気拡大
| 第1章 世界経済の現況 | 第2章 アメリカ経済の長期拡大の要因と課題 | 第3章 物価安定下の世界経済 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 |
| 概観 | アメリカ | 欧州 | アジア | 金融・商品 | 通貨・金融システム | 特徴 | 要因 | 生産性 | 課題 | 現状 | 要因 | 特徴 | 金融政策 |
第2節 戦後最長をうかがうアメリカの景気拡大
1 アメリカ:不透明感もみられるものの、景気の拡大は続く
アメリカ経済は1999年4月に9年目の景気拡大局面に入り、その後も、先行きには不透明感もみられるものの、順調に拡大を続けている。この一年間を総括して特筆すべきことは、a)98年秋の国際金融市場の混乱を乗り越えて成長を続けたこと、b)大方の予想を上回る高成長を続けていること、c)インフレ懸念が改めて高まってきていること、d)株高等がもたらす先行き不透明感が払拭されていないことである。98年秋には、ロシアの金融危機や大手ヘッジファンドの経営破綻によって国際的な信用収縮への懸念が生じ、アメリカの実体経済にも悪影響が及ぶことも危惧されたが、内需が好調だったことに加えて、迅速な政策対応や金融市場の柔軟性等により、懸念されていた影響はほとんど見られなかった。つまり、アメリカ経済は、97年のアジア危機に続き、98年の国際金融市場の混乱をも乗り越え、ここ数年、先進諸国の中では特異的に高い成長を続けている。また、その成長率は大方の予想を大幅に上回るものであり、98年も4.3%と高成長であった[注1]。その後、99年に入ってからも堅調な成長を続けている。これは、外需のマイナスが続く一方、株高や金利低下などにより消費と投資が非常に好調であることによるものである。高成長が続いているため、景気過熱によるインフレが懸念されているが、物価は総じて安定して推移している。このように好調が続くアメリカ経済であるが、失業率が98年の4.5%から更に低下し、99年9月4.2%と30年来の低水準が続き、労働需給の逼迫感が高まっていることや、石油価格の反騰などもあり、99年の春以降インフレ懸念が強まっている。また、株高や経常収支赤字の拡大など持続的な安定成長を阻害しかねない要因も引き続き存在しており、先行きに不透明感がみられることには変わりはない。以下では、全体の景気動向を俯瞰した後、上記のa)~d)について整理している。
(1) この一年間の景気動向
99年7~9月期までの1年間の実質GDPの成長率は、依然好調な内需を反映し、4.1%(年平均伸び率、以下同)であった。需要項目別にみると、個人消費は、個人所得の堅調な増加、高い水準の消費者コンフィデンス、株価の高い伸びによる資産効果や98年秋の金融緩和に伴う金利の低下などを背景に、5.1%増(寄与度3.4%)と高い伸びを示した。最近の特徴として、98年に入ってから自動車購入の伸びが高まっていることが挙げられる。この要因の一つに自動車ローン金利の大幅な低下がある[注2]。96年1~3月期には、商業銀行の新車販売金利が9.1%、自動車ディーラーの提供する新車販売金利が9.8%と高かった。97年以降、自動車販売の競争激化等を背景にディーラーの提示する金利は大幅に低下し、99年4~6月期には6.6%となっている[注3]。株高による資産効果などを背景に可処分所得の伸びを上回る消費の伸びが続いたことから、家計貯蓄率は97年4.5%、98年3.7%、99年1~3月期▲3.0%、4~6月期2.5%、7~9月期2.1%と低下を続けている。こうした中、消費者信用残高の対可処分所得比は依然として高水準で推移している。
民間住宅投資の99年7~9月期までの1年間の伸びは5.2%増(寄与度0.2%)であった。所得増や98年秋の利下げなどを受けた低金利(30年物のモーゲージ金利は97年7.6%、98年6.9%)、暖冬の影響などにより、99年1~3月期に前期比年率12.9%増と2桁台の伸びを示したが、99年4~6期は同5.5%増と拡大のテンポが鈍化し、7~9月期には同▲6.3%と減少に転じた。これは、99年初には6.8%と低水準にあったモーゲージ金利が5月以降利上げの影響などから上昇している(9月平均7.8%)こと、98年の暖冬の反動、供給制約などによるものである。住宅市場全体の活況を受けて、中古住宅販売も過去最高の件数を記録している。
民間設備投資も高い伸びを続けた。98年7~9月期には、ゼネラル・モーターズ社(GM)のストの影響を受け輸送機器投資が減少したことから、一時的に前期比年率横ばい(0.0%増)となったが、10~12月期以降は堅調に増加している(平均11.2%増、寄与度1.2%)。内訳をみると、これまで同様情報関連機器が大幅に増加しており、そのシェアもこのところ増加している。他方、構築物投資は、90年代に入り産業構造変化などを反映して低い伸びが続いており、96年10~12月期をピークに、前年同期比ベースで伸びが鈍化し続け、99年1~3月期にはマイナスの伸びとなった。
また、外需は、好調な国内経済を受けて輸入が大幅に増加しているために引続きマイナスである(寄与度▲1.0%)。経常収支赤字は、財の貿易収支赤字の拡大によって、98年は2,206億ドル(対名目GDP比2.5%)の後、99年1~3月期687億ドル(同3.0%)、4~6月期807億ドル(同3.5%)と拡大している。
雇用についてみると、民間非農業部門で、サービス部門を中心に月平均約21.5万人(99年1~8月)の雇用が創出されている (97年は月平均28.1万人、98年は同24.4万人)。ただし、製造業ではアジア危機などに伴う外需の減退やドルの増価によってもたらされた輸出減・輸入増の影響もあって雇用は減少している。失業率は、98年4月以降、4.5%以下と極めて低水準にあり、労働市場の逼迫感が続いている。
こうした中、賃金上昇や石油価格の反騰などにより、インフレ懸念が高まってきている。物価は、生産者物価指数(完成財総合)が、99月3月のOPECの減産合意による石油価格の反騰や食料品価格の上昇などを受けて、98年前年比▲0.9%の後、99年1~3月期前年同期比0.7%、4~6月期同1.4%、7~9月期同2.3%と高まりを示している。消費者物価についても、総合指数では、98年まで上昇率が下落基調にあったが、98年前年比1.6%の後、99年1~3月期前年同期比1.7%、4~6月期2.1%、7~9月期同2.3%と、このところエネルギー価格などの上昇を反映して上昇の動きがみられる。しかし、食料とエネルギーを除くコア指数は安定している。
財政収支は、1998会計年度(97年10月~98年9月)で、29年ぶりに約700億ドルの黒字に転じた。99年2月の大統領予算教書では、1999年度は、約790億ドルの黒字との見通しになっていたが、行政管理予算局(OMB:Office of Management and Budget)は、6月の年央見通しで更に予想を約200億ドル引上げ、約990億ドルに上方改定した。この見通し改定の主要因は、99年の経済成長率見通しが2.4%から3.9%へと大幅に上方修正されたことによるものである。99年度の実績値は、これを更に上回る1227億ドルとなり、黒字額としては過去最高額となった。
金融政策をみると、97年3月以来5.5%に据え置かれていたフェデラル・ファンド・レート(FFレート:Federal Fund Rate)の誘導目標水準は、98年8月のロシア金融危機以降、98年9月、10月、11月の3回のFOMC(連邦公開市場委員会:Federal Open Market Committee)で0.25%ずつ引き下げられて4.75%となり、公定歩合も、10月、11月に0.25%ずつ引き下げられて4.5%となった。しかし、海外経済の回復、金融市場の安定化、引き続き強い内需といった経済状況の変化を踏まえ、将来のインフレを未然に防止するため、99年6月、8月のFOMCでは、FFレート誘導目標水準は0.25%ずつ引き上げられて、5.25%となり、公定歩合も、8月に0.25%引き上げられて、4.75%となった。この間の金融政策バイアスをみると、98年9月には引締めから緩和に、11月には緩和から中立へと変更された後、99年5月には引締めに変更された。その後、6月にいったん中立に変更されたが、労働市場の逼迫による将来の物価上昇圧力が好調な景気を傷つけるリスクに対応することなどのため、10月には再び引締めに戻された。マネー・サプライ(M2)の動向については、98年10~12月期前期比2.8%増をピークに、99年1~3月期同1.8%増、99年4~6月期同1.4%増、7~9月期同1.2%増と伸びが鈍化している。金融市場の動向については、98年秋にロシア危機の影響を受けて、ニューヨーク株式市場で、ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価指数(以下ダウ平均)が史上2番目の下げ幅を記録した(512.61ポイント下落)。その後99年初の中南米市場の動揺に伴い、株価は一時不安定に推移したが、再び上昇を続け99年8月には過去最高値(ダウ平均:11,326.04ドル)を記録した。
(2) 予想を上回る高成長とインフレ懸念の台頭
1) 実体経済への影響は軽微だった国際金融市場の混乱
98年秋の国際金融市場の混乱が、アメリカ経済に与えた影響は次のように整理できるだろう。a)投資家がリスク回避傾向を強めたため、低位格付けの社債発行が低迷するなど、金融市場への影響が99年初頭まで比較的長期に及んだ。b)しかし、政策金利の引下げなどの迅速な政策対応が行われるとともに、企業の資金調達方法が社債発行から銀行借入へと柔軟にシフトした。さらに、企業の旺盛な投資意欲や低失業率に代表される堅調な所得環境などを背景として、実体経済にはほとんど影響がなく、高成長を続けた。c)むしろ、金融市場の回復の遅れに対処するために金融緩和が続いたことにより、潜在的なインフレ圧力を抱えていた実体面や株式市場におけるインバランスが高まったきらいがある。
(アメリカの直接金融市場への影響)
ロシア危機に始まった国際金融市場の混乱は、中南米にも波及し、通貨切下げや株価の急落といった事態を引き起こした。この間、アメリカの金融市場においては、内外の投資家が非常にリスク回避的となったため、一時的に直接金融市場の機能が低下し、企業の資金調達が困難になるという影響があった。アメリカの企業(非金融機関)は、その資金調達の過半を直接金融市場からまかなっており、社債、コマーシャル・ペーパーによる企業の資金調達割合は、70年代の45%から90年代には55%まで高まっていた。特に、大企業にとって短期資本調達の際のコマーシャル・ペーパーの発行は、銀行借入よりコスト面で有利であることから、発行残高は97年1月1,908億ドルから98年9月には2,412億ドルと着実に増加していた。しかし、国際金融市場の混乱のため、企業の資金調達方法に変化が見られた。具体的には、短期資金については、コマーシャル・ペーパーの流通金利が上昇し、発行も低迷した(第1-2-1図)。また、長期資金についても、安全資産である国債への資金逃避により、98年の8~10月にかけて国債とのスプレッドが拡大し、社債の発行が激減した(第1-2-2図)。また、発行済国債の中でも流動性の高いものが選好されるとともに、社債においても、格付けの低い社債は敬遠される傾向が鮮明となった。例えば、デフォルト・リスク(貸倒れのリスク)を反映した優良社債と低位格付け社債の流通利回り格差は、社債市場が活性化された80年代から縮小していたが、98年7月から99年1月にかけて拡大した(第1-2-3図)。
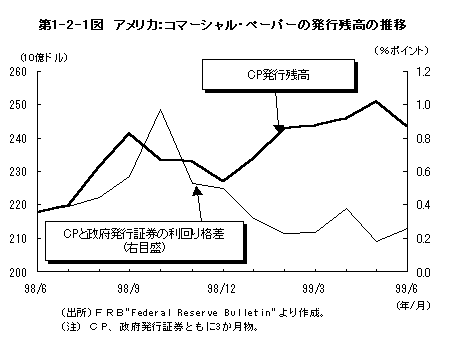
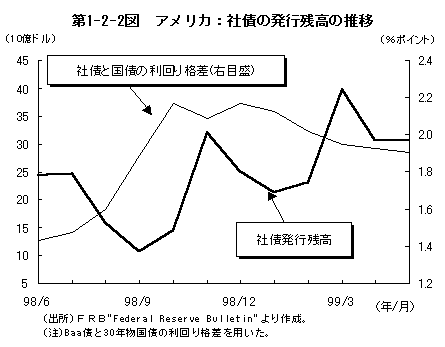
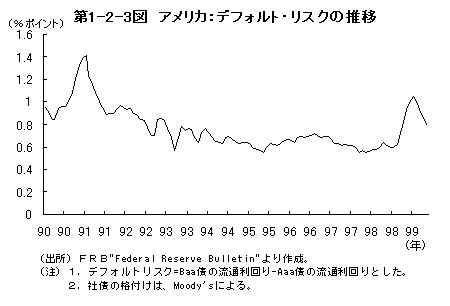
直接金融市場から資金調達ができなくなった企業の資金需要は銀行等間接金融へ向かった。銀行等による大企業向けの貸出態度が厳しくなったものの、信用収縮の懸念解消のため、11月までの都合三度にわたる政策金利引下げが行われる中で、銀行の企業向け貸出は増加した(第1-2-4図)。一連の利下げにより、年明けにかけてコマーシャル・ペーパー、社債共に発行が容易となり、各種の流通利回り格差が縮小するなど直接金融市場も年明けには正常な状態に復帰した。
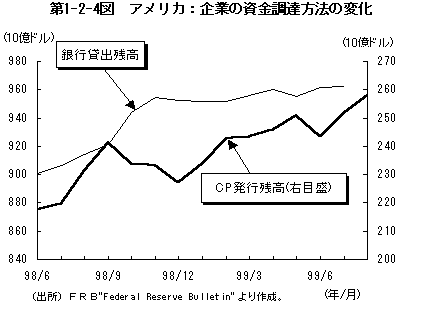
株式市場は、より早く回復した。すなわち、98年8月末にダウ平均が史上2番目の下げ幅を記録したものの、2度目の利下げが行われた10月後半以降急速に値を戻した。この背景には、ユーロ圏を含めた世界的な利下げや企業収益回復期待、国内金利低下による流動性の高まり、海外からの資金還流などがあった。株価が低迷していた7~9月期における株式の購入主体は、主に、公的年金基金、保険会社などであったが、株価が持ち直した10~12月期には、それまでの高値の相場を支えていた海外部門や投資信託が再び大きく買いに回っている(第1-2-5図)。新規株式発行件数も大幅に減少し、6月63件(9570百万ドル)だったのが、8月20件(1,528百万ドル)、9月5件(86百万ドル)となった。しかし、11月には20件(4,264百万ドル)と回復した。
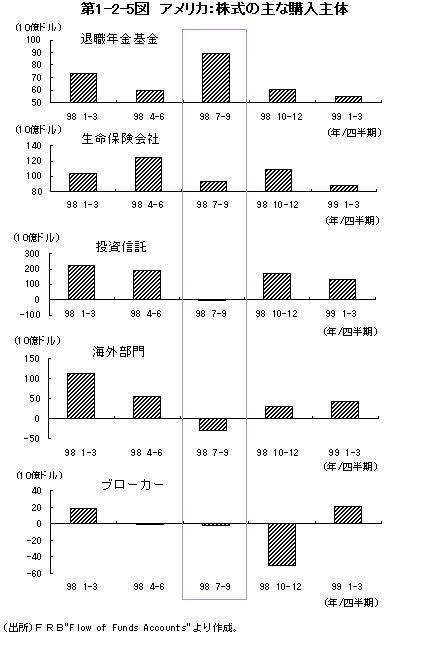
全体でみれば、金融市場における影響は年明けまで解消されなかったが、信用収縮といった大きな混乱を招くことはなかった。この理由としては、資金調達方法の多様性が確保されているといった金融市場の頑健性に加え、金融政策のクレディビリティが高かったことも挙げられる。また、上記のような金融緩和を可能としたのは、それまでの景気拡大にもかかわらずインフレの兆候がみられなかったという経済状況に負うところが大きい。すなわち安定した景気拡大がリスク対応への余地を広げていたという側面があった。
(好調だった実体面)
金融市場が99年初めまでやや不安定に推移したのとは対照的に、実体経済への影響はほとんど見られなかった。98年後半の景気動向をみると、個人消費、住宅投資、設備投資ともに好調であった。この理由としては、利下げなどの迅速な政策対応や、金融市場の柔軟性などを挙げることができる。
個人消費について詳しくみると、金融危機にともなう株価の下落から先行き不透明感(消費者信頼感指数のうち将来指数の悪化)がもたらされ、一時購買意欲が減退したが、現状指数は小幅な低下にとどまり、高水準を維持した。このように消費者コンフィデンスは底堅く、利下げによって株価が直ちに回復したこともあり、消費への影響はほとんどみられなかった(第1-2-6図)。利下げの消費への影響は、例えば、自動車ローン金利の動向でみることもできる。98年4~6月期と99年1~3月期を比べると、商業銀行新車販売金利は8.87%→8.34%、自動車ディーラーの新車販売金利は6.98%→6.43%と低下しており、前者は、この20数年で最低の水準となった。また、モーゲージ金利の低下により、ローンの借り換えが進み、家計の金利負担が低下したことも、消費を下支えした。モーゲージ申請に占める借り換え申請比率は98年6月上旬の28.1%から10月中旬には69.4%まで増加した(最近では金利上昇に伴い再び減少)。また、株価の低迷が長期化すればいわゆる逆資産効果を通じて、消費等を減退させることが懸念されていたが、直ちに株価が反転したため、消費などへの影響はみられなかった。住宅投資は、金利低下によって特に大きなプラスの影響を受けた(第1-2-7図)。
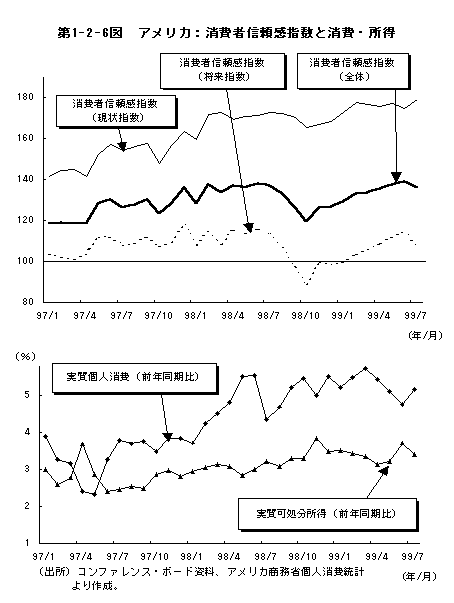
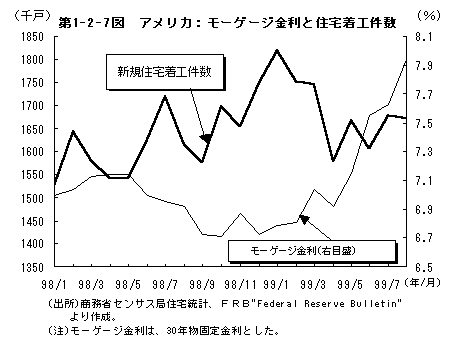
設備投資は、輸入品価格の下落に伴う価格競争の激化などによって、97年以降企業収益が圧迫されていたことに加え、社債発行の低迷により企業の資金調達が支障をきたすことで減速するのではないかと懸念されたが、実際には減少しなかった。この背景としては、実体面からみれば、旺盛な消費などを背景とした需要要因や、独立投資化している情報化投資を中心とする新規投資要因などがあった。金融面についてみると、金利が低下したこと、社債から銀行借入へのシフトが順調に行われたことなどが大きくプラスに働いた。
2) 予想を上回った景気拡大
98年後半以降の景気拡大のペースは大方の予想を超えたものだった。議会予算局(CBO:Congressional Budget Office)の見通しによれば、GDP成長率は1998年後半および1999年前半には前期比年率2%程度に鈍化すると予測されていた(98年7月レポート)。また、民間景気予測のコンセンサスであるブルーチップ[注4]によれば、98年7~9月期が同2.2%、10~12月期が同2.5%の予測であった(98年8月10日予測)。しかし、実際の成長率は、国際的な金融危機が発生したにもかかわらず、7~9月期が同3.7%(旧基準ベース、新基準では同3.8%)、10~12月期が同5.6%(同5.9%)であった。
高成長は99年に入ってからも続いている。この背景には、低金利が続いていること、株価の上昇が続いていること、インフレの兆候が明確には見られないことがある。個人消費は、99年に入ってからも、1~3月期前期比年率6.5%増、4~6月期5.1%増、7~9月期4.3%増と高い伸びが続いている。また、低金利などの影響により、住宅投資が活発である。民間住宅投資は、暖冬の影響もあり実質GDPベースで99年第1~3月期同12.9%と2桁の伸びで推移し、4~6月期も同5.5%であった。しかし、このところのモーゲージ金利の上昇などを受け、7~9月期は同▲6.3%と減少に転じた。民間設備投資も、情報化投資を中心に、99年1~3月期同7.8%、4~6月期同7.0%、7~9月期同14.9%と高い伸びが続いている。また、99年に入ってからは、コスト削減努力の効果もあり、企業収益が回復していることも設備投資拡大の要因となっている。
3) インフレ懸念の再燃
ここ数年来のアメリカ経済の高成長は、潜在成長力を大きく上回っている可能性が高く、インフレに対する懸念が指摘されている。行き過ぎたインフレは景気変動リスクを高めるため、物価は安定していることが望ましい。これまでのところ、インフレの明確な兆候は見られないが、潜在的なインフレ圧力は、景気過熱に伴う更なる労働需給の逼迫に加え、石油価格の反騰や海外経済状況の好転による一次産品等の価格の上昇等により、高まっていると考えられる。現在のアメリカでは、それが、金融引締めによる過度な景気減速に加えて、金利上昇や景気減速懸念による株価急落や、さらには株価急落に伴う実体経済(特に個人消費)の大幅な落ちこみといったハード・ランディングにつながる可能性は否定できない。
(99年春以降に生じたインフレ懸念の高まり)
99年春以降、それまでの労働需給逼迫懸念に加えて、海外要因等いくつかのインフレ加速要因が加わるようになった。労働需給逼迫は、雇用者数の堅調な増加と極めて低い失業率が続く中、最も大きなインフレ要因とされてきた。99年に入ってからも、消費と投資の高い伸びが続く中、この面からのインフレ懸念はより高まっているといえよう。失業率の動向をみると、数年来、失業率が4%台前半に定着していることから賃金上昇を通じたインフレ圧力とみられていた。99年に入り、賃金上昇の伸びが鈍化し始め、失業率の動向と相反する動きを示したが、99年夏以降は、再び賃金上昇の伸びは高まっている(第1-2-8図)。この主な理由は、99年春に金融業などで一時的に賃金の伸びが鈍化したことの反動だが、建設業などでは労働需給の逼迫から賃金の高い伸びが続いている。さらに、このところ就業率(就業者数/生産年齢人口)が横ばいとなっており、労働力が払底状態であると考えられることから、賃金の上昇圧力が一段と高まっている。
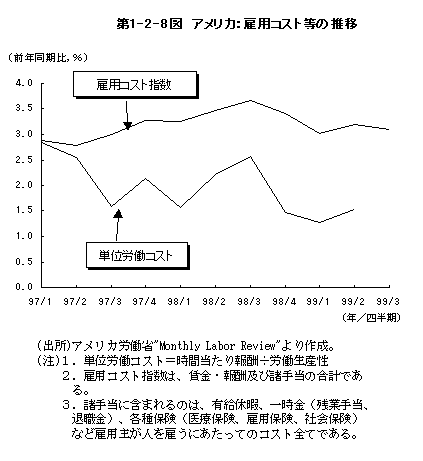
海外要因は、98年まではインフレを抑制する方向に働いていたが、99年に入ってからは抑制力が弱くなってきており、99年春からは物価上昇に寄与しつつある。すなわち、97年以降、物価が安定的に推移していた背景には、原油を始めとするエネルギー価格の大幅な低下、アジア通貨・金融危機の影響を受け低迷した国際商品市況、ドル高などがあったが、99年に入ってからは、99年3月のOPECの減産合意による石油価格の反騰、アジア経済の回復、ドル安傾向などにより物価上昇の動きが見られる(第1-2-9図)。
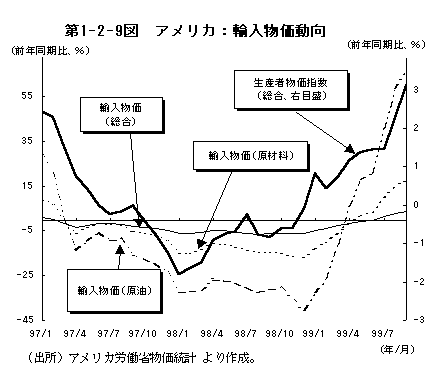
また、このところ輸出減・輸入増により低迷していた製造業が回復傾向にあることも重要な変化である。海外経済の回復に伴い、製造業の生産の伸びが高まっている。99年初頃から需要増に対応し、労働時間が持ち直しており、これに伴い、賃金の伸びが高まっている。これまでのところ製造業における雇用減が労働市場全体の雇用逼迫感を緩和していたが、今後更に需要が高まればそのような抑制力は小さくなり、労働市場全体の雇用逼迫度合いを強めることとなろう(第1-2-10図)。したがって、今後は、財の価格と賃金の両面から物価押し上げ圧力が働くこととなる可能性があると考えられる。
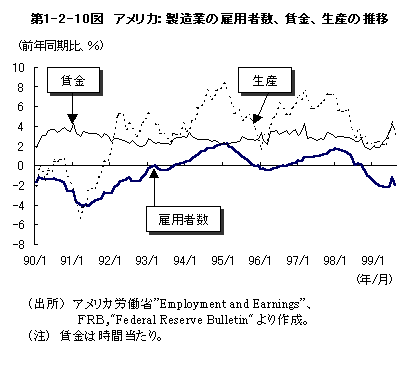
4) 依然として残る不透明感
景気過熱等に伴うインフレ懸念に加えて、アメリカ経済はいくつかのリスクを抱えている。それらは、割高感の指摘される株価、低下が続く家計貯蓄率、経常収支赤字の拡大である(より詳細については第2章第4節を参照)。
(割高感の指摘される株価)
株価の水準が適正なものであるかどうかについては、株価の指標の妥当性を含めて様々な論点があり得る。しかしながら、現在のアメリカにおける各種株価は、インターネット関連にみられる赤字企業の株価が上昇するなど企業収益等のファンダメンタルズからみて割高感があることは否めない。株価の水準が問題とされる背景は、株価とa)実体経済との結びつきが資産効果などを通じて強くなっている可能性、b)国内外の他の金融市場との結びつきも強くなっている可能性、があるためであり、株価が何らかの要因によって急落した場合、逆資産効果などを通じて大幅な下方調整の可能性がある。
(低下が続く家計貯蓄率)
最近における家計貯蓄率の推移をみると、ほぼ一貫して低下基調が続いており、99年7~9月期には2.1%と、遡及可能な59年1~3月期以来、最低水準の家計貯蓄率を記録している。これは、所得の増加を上回るペースで消費が伸びているためであり、「消費主導の高成長の裏返し」とみることもできる。この背景としては、a)低失業率等を背景とした安定的な所得の伸び、b)株高による資産効果、c)低金利が指摘されている。株高については、株価が下落した場合に消費の高い伸びを維持することが不可能になる点が懸念される。また、株高及び低金利を反映して、消費者信用残高の可処分所得に占める割合は、96年1~3月期から98年10~12月期までは20.2~20.5%であったが、その後も高水準で推移し、99年1~3月期20.5%、4~6月期20.4%となっている。債務不履行率(消費者ローン)をみると、90年代初頭の景気後退期の水準には及ばないものの、96年7~9月期以降、3%後半の高水準で推移している(第1-2-11図)。
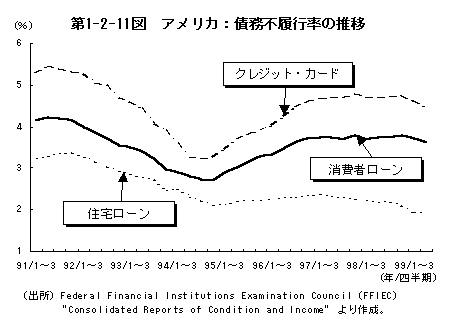
(経常収支赤字の拡大)
堅調な消費と投資を背景として、95年以降、経常収支赤字は拡大し続けており、99年4~6月期で約807億ドルの赤字となっている。これは名目GDP比で3.5%に当たり、過去のピーク(86年10~12月期3.5%)と同水準である。経常収支赤字の拡大は、基本的には旺盛な消費や投資に伴うものであるが、それが問題とされる理由は、主にa)ドル安圧力が高まること、b)保護主義圧力が高まることにある。特に、前者については、経常収支赤字の拡大に加えて、諸外国の景気見通しが次第に上方修正されていく中で、アメリカの景気減速感から資本流入が減少することになれば、金利が上昇し、投資、消費の伸びが鈍化するとともに、株価にも影響することとなろう。
2 カナダ:アメリカの好景気を背景に景気拡大
カナダ経済は、金融緩和の効果が現れた95年後半以降、個人消費や民間投資を中心とした高い経済成長が続いている。実質GDP成長率をみると、98年4~6月期から7~9月期にかけて前期比年率1.1%、2.6%とやや鈍化したものの、その後10~12月期同4.8%、99年1~3月期同4.2%、4~6月期同3.3%と、景気拡大が続いている。99年に入ってからの景気動向を需要項目別にみると、個人消費は99年1~3月期前期比年率4.3%、4~6月期同3.0%となった。民間投資(1~3月期前期比年率12.1%、4~6月期同22.0%)は、住宅投資と設備投資がともに高い伸びを示し、けん引車となった。貿易動向をみると、輸出が99年に入りアメリカ向け輸出額の増加などから拡大し、今後も一次産品市況の好転などから拡大が期待されている。
物価は、消費者物価上昇率で前年同期比1%台という低インフレ状態が続いている。カナダ中銀は消費者物価上昇率を目標幅である1~3%に抑えることを重要な目標としているが、下限を下回る場面もあった。足元ではインフレ率はやや上昇しているものの、2%以下と依然として落ち着いている。
失業率をみると、好況を反映して低下傾向となっており、98年は8%台、99年に入ってからはおおむね7%台の推移となっている。
財政収支は、97年度(97年4月~98年3月)から財政改革と好調な経済により財政均衡を達成した。99年度予算では、達成した財政余剰を基にヘルスケアの増額及び所得減税を行うことが決定されている。
また、93年以降低下してきている家計貯蓄率は、依然として低下している。所得の伸び以上に消費が伸びているということは、株高による資産効果およびそれに伴う信用(負債)増加の結果であると考えられる。しかし、カナダの代表的株価指数であるTSE300指数をみてみると、世界的な金融混乱が生じた98年半ば以降大幅に下落した後、混乱の収束とともに再度上昇を開始したものの上値は抑えられ、98年4月の高値を約10%下回る水準となっており(99年9月末現在)、個人消費の動向に影響を与えるかどうかが懸念されている。
(金融の動向及び政策)
カナダの金融情勢はアメリカの金融情勢の影響を強く受けるため、カナダの金融当局は従来から金融政策の舵取りを制限されがちである。98年の一次産品価格下落の際には、98年5月以降鉱業または燃料セクターに属する企業の割合が高い(約2割)TSE300指数が低下し始め、またカナダドルも対米ドルで減価基調で推移したことから利上げを余儀なくされた。しかし、その後ロシア危機などに伴うアメリカの三度にわたる利下げにカナダも追随し、公定歩合の引下げを行った。結果として危機的状況は回避され、為替の減価も止まったが、アメリカとの景況感の格差から、長期金利のスプレッドはこのところ拡大している。99年に入り、対ドルレートは一旦増価した。しかし、カナダが5月に利下げを行い、6月以降のアメリカの利上げにも追随しなかったため、金利差が拡大したことから減価した(第1-2-12図)。
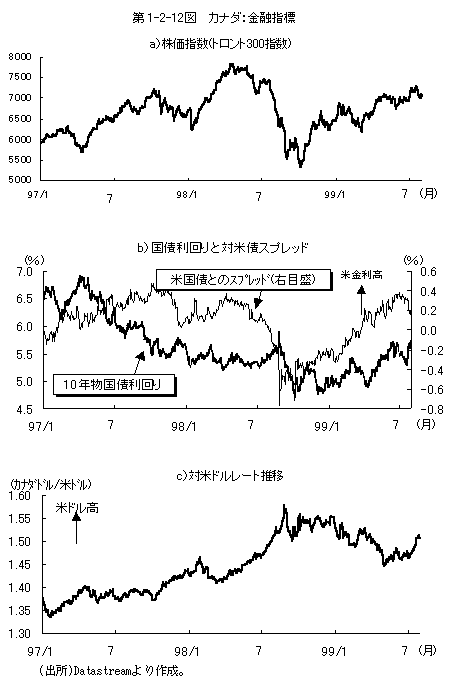
カナダ中銀は、同国の金融情勢の指針として、MCI(Monetary Condition Index)を作成している。MCIとは、金利(CP90日物、ウェイトは3/4)と為替レート(対主要6か国・地域、ウェイトは1/4)から算出され、基準時(現在は87年1月)に比べて現在の金融情勢が緩和状態にあるのかあるいは引締め状態にあるのかの示唆する。同様の指標はノルウェー、スウェーデン、ニュージーランドなどで作成されているが、最近の動向をみるとMCIは93年以降今日まで主としてインフレ率の低位安定により、基準時に比べて緩和状態にあることを示しており、現に公定歩合も引き下げられている。しかし、98年の半ばには急激な為替減価が生じたことから、カナダ中銀は利上げに動き、MCIの低下と公定歩合の上昇というかい離が進んだ。カナダを取り巻く金融情勢の不安定さが減少した現在では、再度利下げが行われ結果としてMCIと公定歩合のかい離も減少してきている(第1-2-13図)。
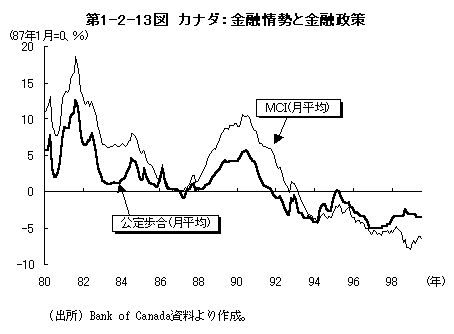
(東アジアの景気後退及び一次産品価格下落の影響)
カナダは従来から銅やアルミなどの一次産品を多く生産、輸出する国であり、97年後半以降に発生した一次産品価格の急激な下落及び東アジアの景気後退は、同国経済に対して大きなマイナス影響を及ぼすであろうと思われた。だが実際には、輸出の8割以上を占めるアメリカ向け輸出がアメリカの好況に伴って増加し、東アジア向け輸出の落ち込みをカバーした。輸入に関しても、98年にカナダドルが減価したため輸入物価が急上昇し、輸入額を押し上げたものの国内消費の伸び悩みなどから基調としての貿易黒字には変化が生じなかった。次に、一次産品価格については、カナダ中銀はBCPI(Bank of Canada Commodity Price Index)を作成、公表している。BCPIとはカナダで生産され、世界中で売買される金属、木材、穀物、エネルギーなど23品目の価格を加重平均して指数化したものである(1982~90年=100、米ドル建て)。これをみると、東アジア地域の景気後退による需要減少などから、97年6月から98年12月にかけて20.2%下落したが、同時にカナダドルの対ドルレートも減価したため、商品価格下落によるマイナスの影響を多少緩和することができた(同期間のBCPIをカナダドル建てでみると10.7%の下落にとどまる)(第1-2-14図)。生産面についても、その他のセクターが好況であったため、資源関連セクターの不況は同国経済に大きな影響を与えなかった。
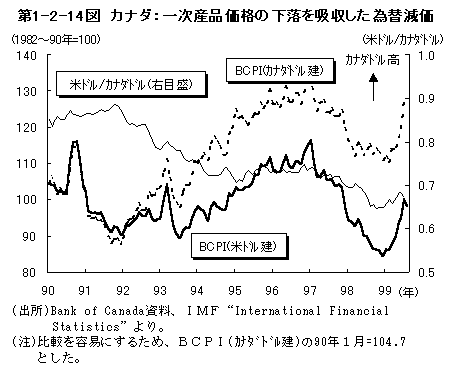
3 中南米:ブラジルの通貨危機を端緒に景気後退局面へ
(1) ブラジル:変動相場制への移行と通貨の大幅減価
通貨レアルを対ドルで固定し、あわせて緊縮財政を実施するというレアル・プランを94年7月に開始したことにより、ブラジル経済は実質GDP成長率でみて95年4.2%、96年2.8%、97年3.7%と安定的な成長を記録した。(第1-2-15図)また、90年代前半の高インフレも沈静化し、消費者物価上昇率は97年には前年比で6.0%まで低下した。
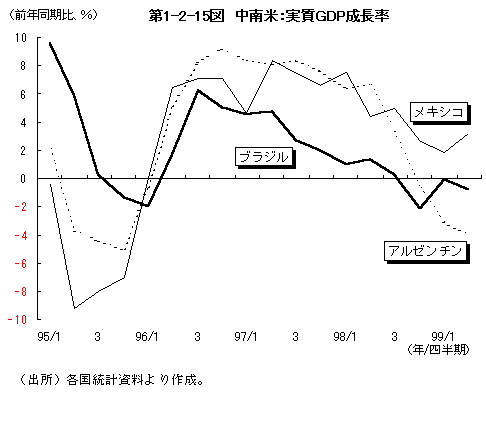
レアル・プラン以降、レアルは対ドルで中心レートから上下に月0.6%の変動幅を持ちながら緩やかに切下げられてきた。しかし、98年夏のロシア金融危機等の影響から為替市場に動揺が生じた。また、99年1月にはミナス州政府が連邦債務のモラトリアムを宣言したことにより、株価の下落や外国資本の流出など信用不安が高まり、為替市場では切下げ圧力が強まった。そして99年1月13日、ブラジル中央銀行は為替政策の変更を発表し、変動幅の拡大により事実上の変動相場制へ移行し、対ドルレートは99年1月の一ヶ月間に38%減価した(第1-2-16図)。
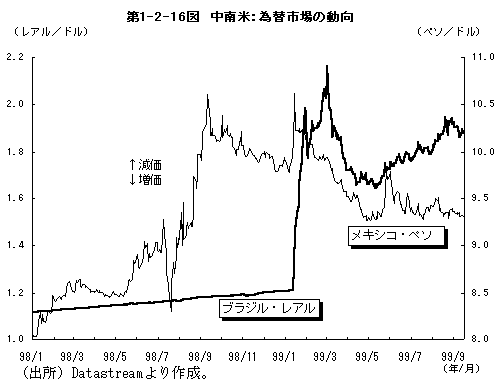
ロシア金融危機後の98年10月、ブラジルはIMF等による金融支援を受け入れ、あわせて財政健全化計画を策定したが、99年1月の変動相場制への移行を受け、ブラジル政府とIMFは99年3月に新たな経済安定化政策について協議を行った。その中でIMFはブラジル向け追加融資を承認するとともに、99年の実質GDP成長率を▲3.5~4.0%、物価上昇率を16.8%等とする見通しの改定を行った。また、この協議の中では、財政健全化による公共部門債務残高の圧縮、中銀の独立性を高めること、民営化を含む公的銀行部門の改革等についても合意がなされた。
ロシア金融危機等の影響や、通貨防衛目的の金利引上げから、98年央以降景気は後退していたが、レアルの大幅切下げ等による市場の混乱から、99年に入って成長率はマイナスに転じている。鉱工業生産は98年10~12月期に前年同期比4.9%減、99年1~3月期には同3.7%減となった。失業率は98年央以降低下傾向にあったが、98年10~12月期の7.0%を境に上昇に転じ、99年1~3月期は7.8%、4~6月期は7.9%となった。
99年3月のIMFの見通しによれば、99年の実質GDP成長率は▲3.5~4.0%と見られていたが、99年1~3月期は前年同期比▲0.1%、4~6月期は同▲0.8%(前期比年率ではプラス4.3%)と、比較的軽度の落ち込みで回復しつつある。この背景には、98年の秋以降、通貨防衛の必要から高め誘導していた金利に関して、切下げ後のレアルの相対的な安定化及びインフレの沈静化から累次の利下げが可能となったことがある。指標的金利であるSELIC金利(国債を担保とした翌日物金利)は99年3月には45.0%であったが、その後11次にわたる引下げにより、99年9月には19.0%まで低下している。また、好天候に恵まれたことから農業生産が順調なことも経済の落ち込みが比較的軽度な要因として挙げられる。
貿易面についてみると、レアル切下げ後の99年1~3月期は輸入(ドルベース)が前年同期比で33.4%減少し、4~6月期も引き続き同15.1%の減少となった。輸出も同24.5%、11.8%と減少している。貿易収支は99年1~3月期は5億ドルの赤字と、前期までと比べて赤字幅は大きく減少し、4~6月期には2億ドルの黒字に転じた。
景気は年初の予想よりも軽度の景気後退にとどまっており、好転の兆しもある。物価は引き続き落ち着いた動きを示しているものの、財政赤字等の問題は依然として大きな課題として残されている。公共部門の財政収支は、利払い費を除いたプライマリー・ベースでは98年の対GDP比0.0%の黒字に続き、99年1~5月期も同2.8%の黒字となった。しかし利払い費を含んだノミナル・ベースでは、98年は対GDP比8.0%の赤字、99年1~5月期は同17.3%の赤字となった。また5月末時点での公共部門債務残高は対GDP比49.6%となっている。
(2) アルゼンチン:デフレ傾向の中、景気は後退している
アルゼンチンは94年12月のメキシコ通貨危機の影響を脱し、96年の実質GDP成長率は5.5%、97年は8.1%と内需主導の景気拡大を続けた。98年に入りロシア金融危機、ブラジルの通貨不安、一次産品の国際市況の低迷等から景気は減速し、実質GDP成長率は98年7~9月期前年同期比3.3%の後、10~12月期は同▲0.6%とマイナスに転じた。99年に入ってからは1~3月期同▲3.0%、4~6月期同▲4.0%と景気は後退している。
通貨制度は1991年のドル兌換法により1ペソ=1米ドルに固定されている。固定相場制への移行以来、物価は安定しており、96年の消費者物価上昇率は0.2%であった。97年も需要の高まりにもかかわらず0.5%の上昇にとどまり、98年は0.9%の上昇であった。99年に入ってからは1~3月期が前年同期比0.0%、4~6月期同▲1.1%と物価は安定からやや下落に転じている。
アルゼンチンの貿易を国別に見ると、輸出相手国は1位がブラジル(31%、1997年、ドル建て)、2位がアメリカ(8%)であり、輸入相手国は1位がブラジル(23%)、2位がアメリカ(20%)である。99年1月にブラジル・レアルが切り下げられた影響もあり、99年1~3月期の対ブラジル貿易収支は6,400万ドルの赤字を記録した後、4~6月期は2億1,500万ドルの黒字となった。ブラジル向け輸出額が減少する一方、国内需要の停滞等からブラジルからの輸入額も減少しており、ブラジル・レアルの切下げ時に予想されたような対ブラジル収支の極端な悪化は発生していない。
株式市場についてみると、代表的株価指数であるMERVAL指数は、中南米各国の景気停滞懸念等から98年8月以降大きく下落し、その後一時は回復したものの、99年1月のブラジルのレアル切下げ時には再度大きく下落した。4月から5月にかけては好調なブラジル・メキシコ市場及びアメリカ市場につられる形で急回復した。
しかし99年5月には元経済財政相による変動相場制への移行を示唆した発言や、7月にはブエノスアイレス州知事(10月の大統領選挙における大統領候補)の対外債務のモラトリアムを示唆した発言により株価は下落するなど、不安定さを内包した上昇であることがうかがえる。
こうした状況下、99年5月にIMFによる拡大信用供与(98年2月承認、3年間、28億ドル)の第三次レビューが承認された。この中で、99年の成長率は▲1.5%と見込まれている。同レビューでは、アルゼンチンは厳しい外的ショックの中、慎重な政策運営を続けていることを賞賛している。しかし、今後も景気動向は、一次産品市況、周辺国、特にブラジルの景気動向といった外部環境と国際金融市場からの信任に依存した厳しい状況が続く可能性が高い。
(3) メキシコ:景気の拡大テンポは鈍化してきている
94年12月の通貨危機により95年はマイナス成長となったが、ペソ安とアメリカの景気拡大に伴う輸出増や投資の増加に支えられ、景気は急速に回復した。98年以降は民間消費、固定資本形成の伸びの鈍化及び緊縮財政による政府消費の減少から、景気の拡大テンポは鈍化してきている。(第1-2-17表)
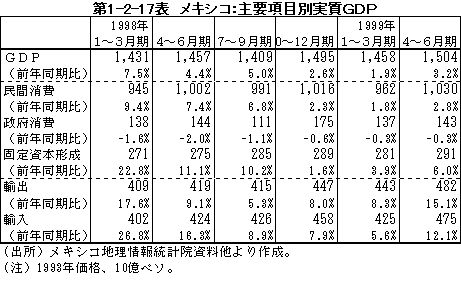
物価についてみると、消費者物価上昇率は95年は35.0%、96年は34.4%と高水準であったが、為替が安定したこと等から97年は20.6%に低下した。その後は98年10~12月期が前年同期比17.6%、99年1~3月期が同18.6%、4~6月期が同17.9%と、水準は高いものの安定的に推移している。
貿易先を相手国別にみると、輸出の86%、輸入の75%をアメリカが占めている(1997年、ドル建て)。98年は原油価格の低迷から原油輸出が37%減少したものの、工業品輸出が12%増加したことから、輸出総額は6%の増加となった。輸入も中間財、資本財輸入の増加から14%の増加となり、貿易収支は97年の6億ドルの黒字から98年は79億ドルの赤字に転じた。原油価格の回復もあり、98年10月以降は輸出の伸びが輸入の伸びを上回って推移しており、貿易赤字は減少傾向にある。
- 注1 本節におけるGDP成長率等は、断りのない限り99年10月に公表された新基準ベースの数値を用いている。
- 注2 その他の要因としては、大幅なディスカウント、ガソリン価格の下落などがある。
- 注3 消費者向けの金利は、モーゲージ金利を除くと、もともと大幅に上下することがない。したがって、自動車ローン金利が急低下したのは珍しい現象である。
- 注4 ブルーチップは、アメリカの主要シンクタンク・金融機関など約50社の経済予測の月次集計データ。
| 第1章 世界経済の現況 | 第2章 アメリカ経済の長期拡大の要因と課題 | 第3章 物価安定下の世界経済 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 |
| 概観 | アメリカ | 欧州 | アジア | 金融・商品 | 通貨・金融システム | 特徴 | 要因 | 生産性 | 課題 | 現状 | 要因 | 特徴 | 金融政策 |

