第3章 第2節 世界的なディスインフレの要因
| 第1章 世界経済の現況 | 第2章 アメリカ経済の長期拡大の要因と課題 | 第3章 物価安定下の世界経済 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 |
| 概観 | アメリカ | 欧州 | アジア | 金融・商品 | 通貨・金融システム | 特徴 | 要因 | 生産性 | 課題 | 現状 | 要因 | 特徴 | 金融政策 |
第2節 世界的なディスインフレの要因
前節で述べたように、80年代以降、先進国では70年代のような物価高騰を経験することなく現在に至っている。第2節では、他地域よりも長期にわたって物価安定を続け、また世界経済の中で大きなウェイトを占めている先進国を中心に、世界的なディスインフレの要因をみていくことにする。
先進国の物価安定の背景には、経済政策面の要因としては、a)金融政策が物価安定を最大の目標として運営されるようになったこと、b)財政の健全化によって政策当局への信頼感が高まったことなどが挙げられる。また、供給側の要因としては、a)原油を始めとする一次産品価格の下落、b)グローバリゼーションの進展による市場競争の激化、c)規制改革を始めとする経済構造改革の進展、d)技術革新、e)労働市場の変化等が挙げられる。なお、70年代と90年代とを比べて、需要要因により物価上昇率が低下しているとは必ずしも言えないものの、各時点ごとの物価上昇率の変化をみると、その時々の需要要因によって影響を受けていることはいうまでもない。
これらの要因の相対的重要度をみるために、ドイツとアメリカにおける消費者物価上昇率の低下について、貨幣数量(M3)、実効為替レート、原油価格、需要要因(GDPギャップ)を説明変数とする重回帰分析によって要因分解を行った(第3-2-1図)。これによれば、アメリカでは81年から98年にかけて、消費者物価上昇率が約12%ポイント低下したが、そのうち原油価格の低下が最も大きく寄与していること、80年代後半から90年代後半にかけてマネーサプライの伸び率の低下が物価上昇率の低下に大きく影響していることがわかる。一方、ドイツでは、81年から98年にかけて、消費者物価上昇率が約5.4%ポイント低下したが、そのうち実効為替レートの増価が最も大きく寄与したこと、近年ではマネーサプライの伸び率低下が低インフレに大きく影響していることがわかる[注1]。
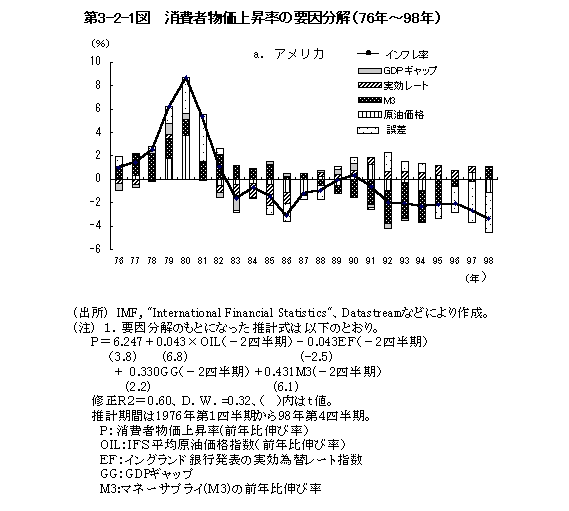
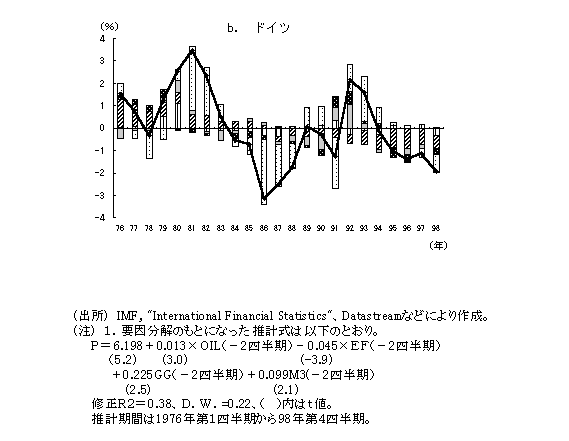
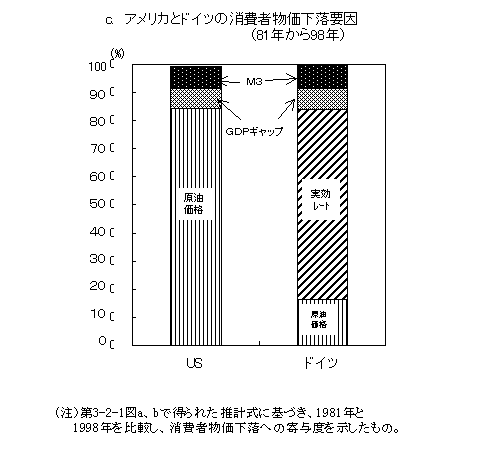
以下では、金融政策が物価安定に与えた影響を概観するとともに、一次産品価格の下落といった供給側の要因と需要要因がどのように物価に影響してきたかを検討することとする。
1 金融政策
(各国の金融政策の推移)
第1節でみたように、80年代以降のディスインフレには、物価安定を目指した金融政策が大きな役割を果たしてきた。70年代のスタグフレーションの経験から、先進国では物価と経済成長とのトレードオフは少なくとも長期には存在しないことが明らかになり、むしろ経済成長を促進するためにも物価安定が重要であると認識されるに到った。多くの国で金融政策は物価の安定を目指すようになった。
物価安定という目標を達成するためには、政策当局への信頼性を獲得することが何よりも重要である。そのための一つの方法は、金融政策に何らかの明示的なノミナル・アンカー(物価安定のための錨のような役割を担うもの)を設定することによって、期待インフレ率を低下させるとともに、金融政策当局の裁量の余地を小さくすることである。
かつては固定為替レートがこのノミナル・アンカーとしての機能を担ってきたが、1970年代前半には、ブレトンウッズ体制の崩壊により、固定為替レートがノミナル・アンカーとしての役割を果たすことができなくなった。多くの国が変動相場制に移行した70年代半ば以降、石油危機を発端としてインフレが昂進したことから、先進国を中心に、貨幣数量をノミナル・アンカーとした政策がとられることとなった。しかし、80年代に入り、金融市場の技術革新などによって、貨幣数量とインフレ率の関係が希薄化した結果、貨幣数量のみを目標とする政策の有効性が低下し、貨幣数量のほか、金利、物価、経済成長率、雇用など、様々な指標を勘案した金融政策の必要性が認識されるようになった。現在、アメリカ、日本などでこうした様々な指標を勘案した金融政策がとられている。
さらに、90年代にはいると、物価上昇率そのものをノミナル・アンカーとして採用する国が増加している。こうした金融政策の運営方法は、インフレ・ターゲティングと呼ばれるが、これは例えば、「消費者物価指数の前年比伸び率を1~3%とする」といったように、各国の物価安定の目標を明示的に設定し、金融政策をこの目標に向かって運営することである。現在、インフレ・ターゲティングを採用している国としては、イギリス、カナダ、スウェーデンなどがある(第3-2-2a表)。これら諸国の物価上昇率目標をみると、イギリスでは2.5%、カナダ、スウェーデンでは1~3%などとなっている。インフレ・ターゲティングを採用しているのは、比較的高いインフレ率に悩まされてきた国が多いが、それらの国における近年のインフレ率の推移をみると、インフレ・ターゲティング採用後におけるインフレ率の低下が観察できる。ただし、インフレ・ターゲティングを採用していない国でも、インフレ率は概して低下傾向にあり、インフレ・ターゲティングの有効性について判断するには、もう少し経験の積み重ねが必要であろう。
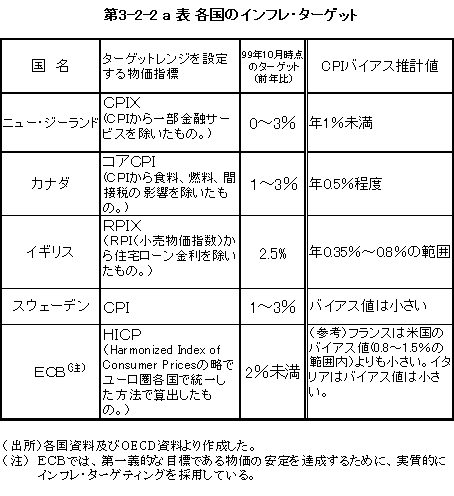
いずれにしても、物価安定を目指した金融政策は概ね成功し、80年代以降のディスインフレに大きく貢献したといえよう(第3-2-2b図)。
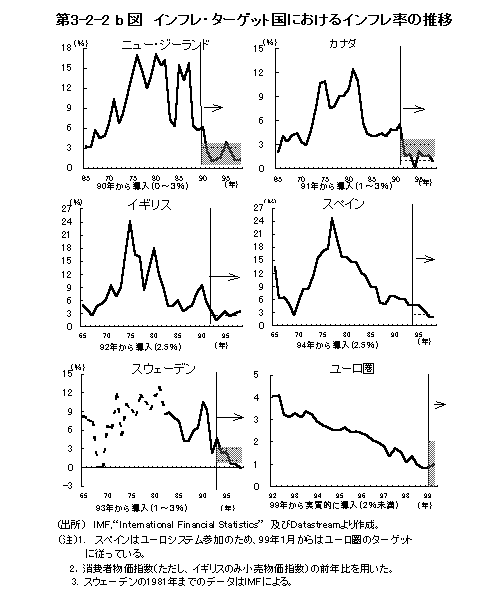
(金融制度改革)
金融政策にノミナル・アンカーを設定することは、インフレ率の低下に大きな貢献をしてきたといえるが、金融政策当局に対する信頼性の確保に役立ったのはこれだけではなく、金融制度改革と財政の健全化も大きく寄与した。
金融制度改革の一環として、中央銀行の独立性を高めるとともに、中央銀行の設立の第一義的な目的を物価の安定と明記する国が増加している。中央銀行の独立性とインフレ率の間には、中央銀行の独立性が高いほどインフレ率が低いという相関関係が指摘されている(平成9年度「世界経済白書」第2章第5節参照)。例えば、99年1月のユーロ導入と同時にユーロ圏の金融政策を一元的に運営することになった欧州中央銀行(ECB)は、第一義的な目標である物価の安定を達成するために実質的にインフレ・ターゲティングを採用し、中期的にみて消費者物価(HICP)上昇率を前年比2.0%未満に抑制することとしている。また、マーストリヒト条約では、ECBは、その任務の遂行に際して、構成国政府はじめいかなる組織にも指示を仰いだり、それらの指示を受け入れてはならないことを規定し、同時に、各国はECBの構成員に対して影響を及ぼそうとしてはならない義務を負っており(第107条)、法制的には一定の独立性が確保されているといえる。このほか、イギリスでは97年に金融政策の運営に関する権限を大蔵省からイングランド銀行に委譲し、政策決定過程を透明化するなど金融政策の枠組みを大幅に変更しした。また、ニュー・ジーランドなど各国においても同様に中央銀行の独立性を高める動きがみられる。
(財政の健全化)
一方、財政の健全化も、政策当局への信頼性の補強に重要な役割を果たしてきたといえる。政府の累積債務が巨額となると、金融当局による公債引受けの可能性が高まることなどにより、金融当局への信頼性が低下するからである。
近年の各国の財政健全化の動向をみると、アメリカでは93年以降財政収支赤字幅(対GDP比)が縮小しており、98年には対GDP比1.7%の黒字となっている。また、ヨーロッパでは、通貨統合への参加基準達成のための努力もあって、近年急速に赤字幅が減少し、物価安定を目指した政策当局への信頼性の補強に重要な役割を果たしてきたといえる(第3-2-3図)。
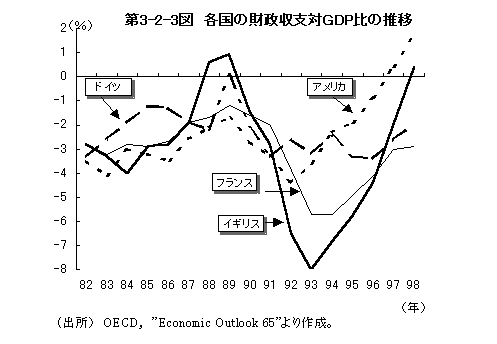
2 一次産品価格の下落
(1)物価安定に大きく寄与した一次産品価格
世界的なディスインフレの要因として、一次産品価格の低迷が挙げられる。一次産品価格の動向を表す代表的な指数であるCRB(Commodity Research Bureau)商品先物指数(1967年=100)は、80年代以降総じて下落基調で推移しており、第1章で概観したとおり、99年2月には名目ベースで1970年代半ばの水準まで下落した。1970年代には物価を押し上げる要因であった一次産品価格は、1980年代前半には大幅に低下し、その後はならしてみれば、ほぼ横ばいで推移している。その結果、80年代以降、先進国の工業製品価格との相対価格は、大幅に低下している(第3-2-4図)。この一次産品価格の低下は、先進国を中心とした一次産品輸入国の物価や賃金に下方圧力をもたらし、インフレを沈静化する方向に寄与したのである。
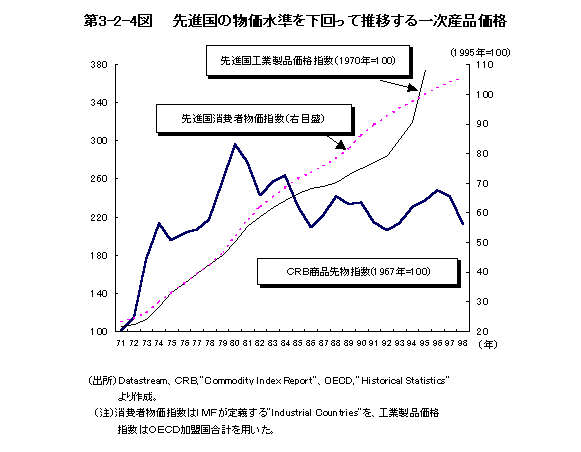
また、原油は幅広い経済主体の活動に大きな影響を与える一次産品の中の代表的な商品である。原油を除く主要な33種類の一次産品で構成された一次産品価格指数[注2]と原油価格の関係を長期的にみると、ある程度有意な相関関係を持っている(第3-2-5図)。したがって、以下では、まず原油を例にとり、価格低下の要因を供給面、需要面の双方についてやや詳しくみてみることとする。
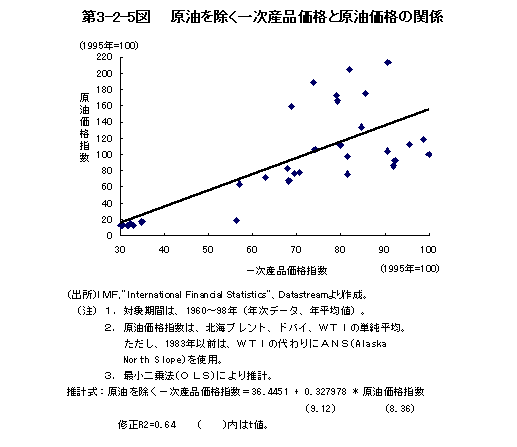
(2)原油価格下落の要因
70年代に経験した二度の石油危機を経て、原油価格は、90年の湾岸危機時にやや強含んだものの、80年代以降総じて下落傾向で推移し、前述したように一次産品価格下落の主要因となった。
(供給側の要因)
供給側の要因としては、まず非OPEC加盟国(全世界におけるOPEC加盟国以外の生産量)の生産量の増加が挙げられる。歴史的にみると、非OPEC加盟国は、OPEC加盟国が生産量を減少させる年、もしくは増加率が低い年に生産量が飛躍的に増える傾向にあり、実質的には供給のバッファー的な役割を果たしてきた(第3-2-6図)。この傾向が最も顕著となって現れたのは80年代前半である。二度のオイルショックを経験した先進国(原油消費国)が、過度のOPEC産原油への依存体質を修正すべく原油供給の分散化を積極的に図ったことに加え、オイルショックで跳ね上がった価格水準も手伝って、北海やメキシコ等の非OPEC加盟国の生産量が増加した。また、新規油田の開発などを中心とする90年代半ばから後半にかけての非OPEC加盟国の増産ラッシュは、OPEC加盟国のシェア奪回の増産インセンティブとなり、生産量の累積的な増加をもたらした。
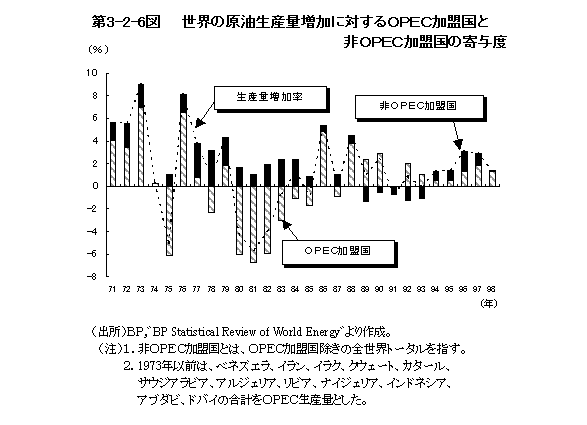
次に、探査・探鉱技術の進歩などによる、原油の確認埋蔵量の増加も供給量増加の要因に挙げられよう。確認埋蔵量とは、既存の技術により採掘することが可能な埋蔵量であり、新たな埋蔵量の発見がなければ逓減していくものである[注3]が、採掘技術力等が向上すれば増加することも有り得る。1970年以降の世界の原油確認埋蔵量をみると、80年代半ば頃までほぼ横ばいで推移した後、80年代後半に著しく増加し、90年代に入ってからも緩やかな増加傾向にある。これは、中東欧等の市場経済移行国や未開発要素を多く残した西アフリカ、中南米を中心に確認埋蔵量が増加していることに起因している。また、エクソン石油開発会社の試算によれば、新興市場国などの未開発油田などに対し民間企業が参入できる割合は、1990年以前は全体のわずか35%にすぎなかったが、98年には約80%にまで高まっている。確認埋蔵量が多く、増加率も高いこれらの地域の海外からの直接投資残高をみると、この10年間にほとんどの国で著しく増加している。直接投資の大半が石油産業へ向かっているとは限らないものの、これらの国では、90年代に入り総じて国営石油企業の民営化や規制緩和による外資の導入策等が積極的に採られたことなどかられたことなどから、先進国の技術が一気に流入し、効率的な採掘活動が行われるようになったと考えられる。
(需要側の要因)
まず、先進国の実質GDP一単位当たりの原油消費量をみると、世界的な高成長に支えられ、70年代を通じて上昇、もしくは横ばい傾向にあったものの、80年代に入ると巨大なオゾンホールの発現によりウィーン条約(オゾン層保護のための条約)やモントリオール議定書(オゾン層保護のための国際合意形成)などの国際的な環境規制措置がとられ、90年代にはCOP(Conference of the Parties:気候変動に関する国際連合枠組み条約の締約国会議)に象徴される世界的な環境規制の強化などが一層図られた結果、80年代以降一貫して低下し続けている。また、省エネルギー指向や産業のソフト化などが一層進んだ影響により、先進国の実質GDP一単位当たりの一次エネルギー消費量も、80年代半ばからは緩やかな下落基調で推移している(第3-2-7図)。
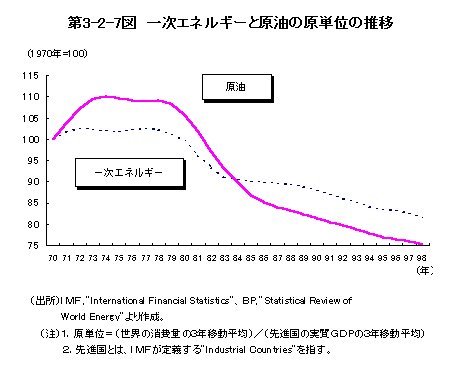
次に、一次エネルギーと原油の原単位を比較すると、80年代半ばからは一次エネルギー全体のトレンドと比較し、原油は下方に乖離する傾向にあるが、これは、代替エネルギーの堅調な伸びに支えられ、一次エネルギー全体に占める原油依存度が引き続き低下していることを示している。石油系エネルギーから代替エネルギーへのシフトは、80年代に環境問題の高まりや化石燃料系資源の枯渇に対する不安などから、先進国を中心に飛躍的に進行し、90年代も総じて代替エネルギー(原油以外の一次エネルギー)消費量伸び率は、原油消費量伸び率を上回っている(第3-2-8図)。一次エネルギー需要に占める構成比は、81年には原油、天然ガス、石炭、原子力、水力はそれぞれ、46%、21%、28%、3%、2%であったが、91年にはそれぞれ40%、23%、28%、7%、2%と80年代を通じて代替エネルギーのウエイトが高まり、98年にはそれぞれ40%、24%、26%、7%、3%となっている。代替エネルギーの伸びがやや鈍化した背景には、先進国を中心に原子力発電所の新規立地が一部で凍結されたことなどが挙げられる。一方、原油消費量伸び率がやや回復したのは、逓増するエネルギー需要を安価に賄うため、アジアや中南米ななどの途上国が原油消費量を増やしたことなどが考えられる。
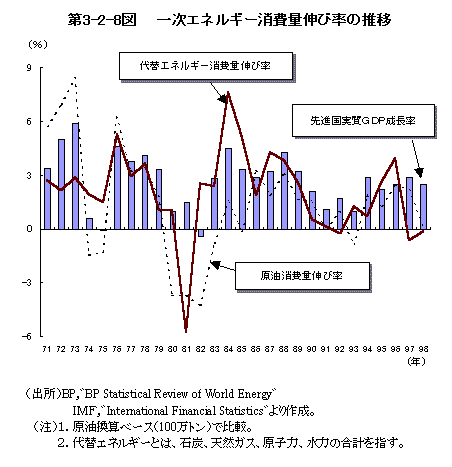
(3)他の一次産品の価格下落要因
CRB商品先物指数を構成する品目は、原油などのエネルギー関連品目以外にも、農産物、貴金属などの鉱物、非鉄金属など多岐にわたるが、ここでは、原油と同じく埋蔵量に限りがある鉱物(貴金属、非鉄金属など)は除き、若干異なる価格決定要因を持つと思われる農産物(穀物)を取り上げる。
穀物は、価格変動の最も大きいカテゴリーの一つである。米、大豆、小麦の価格動向をみると、1970年代を通じて大きく乱高下しながら大幅に上昇した後、80年以降は再び大きく乱高下しながら推移したが、80年の価格と98年の価格を比較すれば、下落している。(第3-2-9図)。
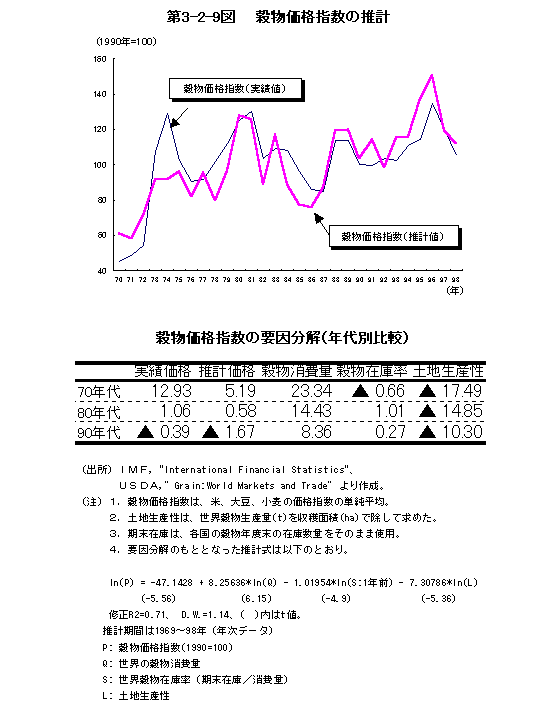
穀物価格が下落した要因をみるため、穀物価格指数を世界の穀物消費量や世界穀物在庫率、世界の穀物セクターの土地生産性といった要因で説明する推計式を作成しその変化を分析した。その結果、70年代に価格高騰の主因であった需要(消費量)の伸びが80年代、90年代と移行するにつれ次第に低下した一方、土地生産性は、向上のペースこそやや鈍化したものの、依然として上昇を続けており、価格下落に大きく寄与している。これは、aバイオ技術の進歩などによる天候異変や害虫災害への耐性が強い品種への品種改良を繰り返したこと、b機械化、コンピュータリゼーションを通じて生産効率を高めたこと、cメキシコなどの中南米諸国を中心に、農業セクターの民営化推進により量産へのインセンティブ(従来の管理的生産システムからの脱皮)が働いたことなどが要因として考えられる。
3 供給サイドの構造的要因
(1)グローバリゼーションの進展
(貿易・直接投資の拡大)
90年代は世界経済が一つの市場になった時代である。世界経済の一体化は、それまで貿易と投資の自由化が各国において政策的に進められてきたことやベルリンの壁の崩壊に象徴される旧計画経済諸国の市場経済への移行によるところが大きい。
グローバリゼーションの結果、各国間の貿易、直接投資は飛躍的に拡大した。70年から98年までの世界の貿易数量の伸び率は年平均5.5%と、同時期における世界全体の実質GDPの年平均成長率3.6%を大きく上回った。特に近年の伸びにはめざましいものがあり、90~98年の貿易数量の伸び率は年平均7.0%と80~90年の年平均3.9%の1.8倍の伸び率を示している。また、世界の直接投資の推移をみると、90年代には、アジア、中南米、東欧といった新興経済と呼ばれる国・地域に大量に流入している(第3-2-10図)。
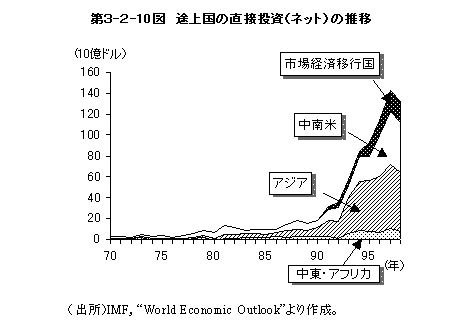
貿易の拡大は、各国が比較優位の生産に特化することにより資源配分の効率性を向上させること、市場の拡大により規模の利益を生じさせること、輸入品と国産品との競争を激化させることなどを通じて物価の安定に寄与している。
直接投資の増加は、途上国への技術移転を促進し、途上国における生産性を向上させてきた。これにより安価な工業品が大量に世界の市場に出回り、世界的な競争圧力が高まった。主要先進国の工業製品輸入浸透度の推移をみると、OECD諸国全体では85年の7.5%から95年の12.1%へと上昇している。また、その輸入先も先進国間の貿易の拡大にとどまらず、途上国からの製品輸入も着実に増加している(第3-2-11図)。
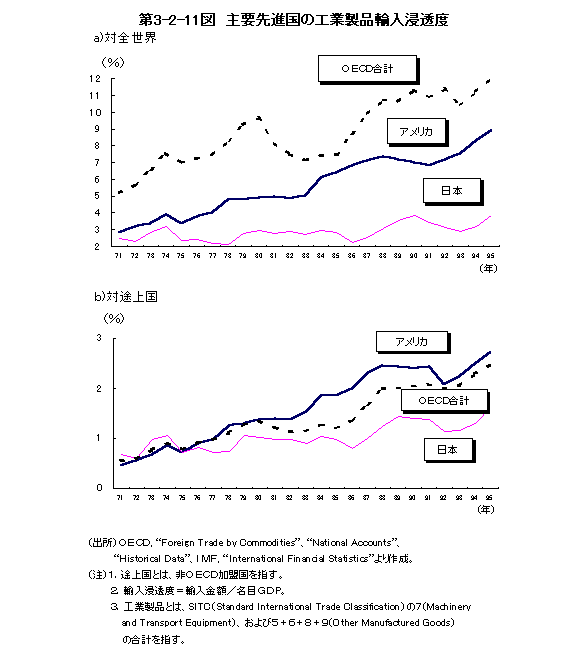
(関税率の引下げ等)
また、グローバリゼーションを促進した大きな要因であった貿易の自由化そのものが輸入物価の低下を通じて国内物価の安定に大きく寄与したという側面も無視できない。すなわち、関税率の引下げや非関税障壁の緩和・撤廃は、輸入価格を低下させるとともに、国内市場の競争を促進させるため、国内物価の安定に寄与した。
1947年以来、GATT(関税と貿易に関する一般協定)は、95年のWTO(世界貿易機関)の発足まで、8回にわたる一般関税交渉・ラウンド交渉を通じて関税率の引下げを実現させてきた。こうした貿易自由化の進展のための国際的な交渉等の結果、工業製品の単純平均の関税率は、日本では89~97年の間に6.0%から4.8%に、アメリカでは89~96年の間に6.7%から5.8%に、EUでは89~97年の間に8.2%から5.6%へとそれぞれ低下している[注4]。
(2)規制改革の進展
80年代以降、規制改革や民営化によって競争を促進し、経済を活性化させようという動きが世界的に強まってきている。規制改革は、新規参入を促進することによって、市場をより競争的にすることから、経済の活性化につながる。それだけでなく、例えば、技術革新が起こったり、効率的な生産方法が発見されても、規制により新しい市場の形成や市場参入が阻害されれば、価格の低下やサービスの多様化といったメリットがもたらされないことになる。こうしたことから、企業の自主的な活動による新たな投資や雇用の拡大を目指し、各国で規制改革が進められている。
規制改革は、市場メカニズムを有効に機能させ、競争を促進することにより、価格を低下させる機能を持つ。これは、他企業の参入が可能になることで市場がより競争的となり、価格は常に供給側の効率化を促すためのシグナルとしての働きをするためである。市場が競争的であるために、供給側は持っている経営資源を常により効率的に使おうというインセンティブが働く。また、電気通信分野のように、従来、自然独占の発生(規模の経済が強く働くために自由競争に委ねれば独占が生じ、市場の失敗が起こること)により新規参入が規制されてきた分野において、技術革新等により自然独占が必然ではなくなった状況下で競争促進のための措置がとられた結果、急激な新規需要の増加による規模の利益の発生により価格が大幅に低下している例も見られる。以下では、まずアメリカとイギリスを例に規制改革や民営化がどのように行われてきたかをみる[注5]。
アメリカでは、70年代後半の民主党政権時代から、運輸、エネルギー、金融部門等で規制改革が進んだ。さらに、80年代の共和党政権においても、規制改革は一層進展した。例えば、アメリカの電気通信市場においては、私企業であるAT&T(American Telephone & Telegraph)の独占が続いていたが、84年、AT&Tは、長距離通信及び国際通信サービスを提供するAT&T社と、地域通信サービスを提供するベビー・ベル7社に分割された。さらに1996年に改正された電気通信法では、更なるアメリカ通信市場の競争促進と規制改革を図ることとしている。この法改正により、長距離電話、地域電話、CATVの垣根がなくなり、相互に参入することが可能となった。
一方、イギリスでは、規制改革と民営化が並行して行われてきた。イギリスでは79年のブリティッシュ・ペトロリアムを始めとして、電力、電気通信、水道といった公共性の高い業種が民営化された。以下では、競争原理導入が徹底されているといわれるイギリスの電力事業を例に規制改革の動きをみてみよう。イギリスでは、89年に電力事業が民営化されたが、同時に様々な規制改革を行うことにより、自然独占が生じやすい電力事業に競争原理を働かせた。その取組のポイントは、a)新規参入の自由化、b)価格の透明化と情報開示の義務付け、c)独占事業体の分割、d)送配電網の開放義務付けにあった。このような規制改革により、電力市場における大手12配電会社の市場占有率は低下している。
OECDの規制改革レポート(1997)では、規制改革以外の要因も一部含まれているという留保をつけた上で、分野別に各国における規制改革がどの程度の価格引下げ効果を持ったかをとりまとめている。その結果によれば、例えばアメリカの航空産業では76年から93年までの間に料金が33%低下している。また、電気通信事業では、参入規制の撤廃による競争促進の結果、OECD加盟国における携帯電話の契約台数が85年の70万台から95年の7100万台へと増加するとともに、イギリスでは電話料金が63%、フィンランドでは長距離電話料金が66%低下した(第3-2-12表)。
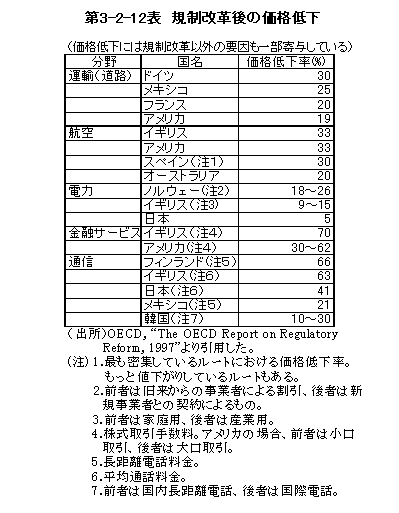
(3)技術革新
技術の進歩は新しい商品を生み出したり、従来からある商品の性能を高めたりするほかに、商品の生産コストを低下させることによって商品の価格低下に寄与する。技術進歩は経済の広範な分野において生じていることは言うまでもないが、ここでは現在の情報社会を支えている半導体について、情報化が進んでいるアメリカを例にしてみてみよう。アメリカの半導体市場におけるDRAM[注6]の価格を同じ性能(1kbit当たり)に換算して比較すると80~95年の15年間で価格が約100分の1にまで低下している。半導体の価格低下が物価上昇率に与える影響をその代表例であるコンピュータでみてみると、アメリカの「コンピュータ及び付属装置」の設備投資デフレータは基準年の92年から98年にかけて73%低下している(第3-2-13図)。
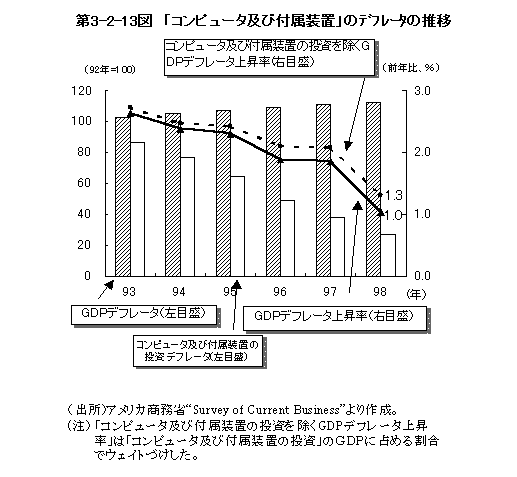
(4)労働市場の変化
賃金上昇率と物価上昇率の両者は、それぞれがお互いの原因であり結果でもある。これは、賃金決定に際して、労働者が物価上昇分を考慮に入れた賃金上昇率を主張するとともに、単位労働コスト(一人当たり雇用者所得(賃金)の伸び率から労働生産性上昇率を引いたもの)が供給側からの物価の押し上げ要因となるためである。80年代には、労働市場における変化を反映して、先進国で賃金上昇率が低下したが、以下では、労働市場改革に成功したイギリスの変化を例にとり、賃金上昇率が低下した背景をみてみよう。
平成10年度「世界経済白書」でも紹介しているとおり、79年にサッチャーが政権についた当時、「クローズド・ショップ協定」(事業主は、組合員から従業員を採用しなければならない)に代表される労働組合に有利に働く硬直的な労使関係があったため、経済の悪化にもかかわらず生産性を上回る賃上げ要求や争議行為が頻発した。このため保守党は、80年に新規にクローズド・ショップ協定を結ぶことに対して規制をかけ、90年には協定を廃止した。また、82年に合法的労働争議の範囲の縮小を行い、84年には争議行為前の手続きを制定した。さらに、93年には最低賃金も廃止している。また、80年代を通じて数回にわたり失業給付水準の実質的切下げを行った。こうした労働市場改革の結果がイギリスにおける90年代の賃金抑制と失業率の大幅な低下につながっていると考えられる。
4 需要要因
(先進国の需給と物価動向)
70年代と90年代とを比べて、需要要因が90年代の物価上昇率を低下させているとは必ずしもいえないが、需要要因はその時々の物価上昇率に影響を与えている。
80年代以降の先進国経済の動向をみると、第二次石油危機のデフレ効果とインフレ抑制のための引締め政策の影響により80年から3年続きの景気後退(82年の主要先進7か国のGDP成長率は▲0.3%)を経験した先進国では、アメリカ経済の景気拡大に先導されて83年以降には順調な景気回復をたどり、80年代後半には景気拡大を続けた。その後、89年以降成長のスピードを緩め、91年の主要先進7か国のGDP成長率は0.5%と第2次オイルショック後の82年以来の低い伸びとなった。これは、80年代後半の先進国における景気拡大や90年のドイツ統一に伴うブームの後の景気調整が総じて長引いたためである。5年間の主要国の平均成長率で比較しても、90年~95年の平均成長率は1.7%と85~90年の平均成長率3.3%から半減している。90年代後半は、アメリカ経済の好調を主要因として、主要先進7か国の95~98年の平均成長率は2.7%と堅調に推移している。
主要先進7か国のGDPギャップと消費者物価上昇率の推移を80年代以降についてみると、概して、GDPギャップがマイナスの(現実のGDPが潜在GDPを下回る)時には上昇率が低下し、プラスの(現実のGDPが潜在GDPを上回る)時には上昇率が高まるという関係がみてとれる(第3-2-14図)。ただし、97、98年については、アメリカの好調を主因にGDPギャップがプラスになっている中で、消費者物価上昇率は低下を続けている。これには、アジア通貨・金融危機後のアジア途上国の需要収縮や世界的な一次産品価格の下落が寄与しているものと考えられる。
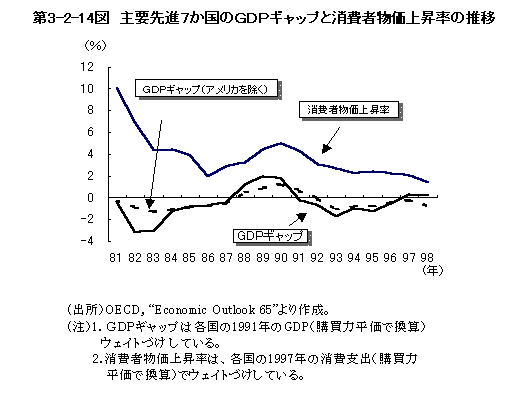
(アジア通貨・金融危機の影響)
97年7月のタイ・バーツ危機に端を発するアジア通貨・金融危機は、域内の経済収縮をもたらしただけでなく、世界経済全体にも大きな影響を及ぼし、ロシアや中南米諸国等の為替・金融市場にまで動揺が広がった。
東アジア6か国(インドネシア、韓国、シンガポール、タイ、マレーシア、フィリピン)の潜在GDPと現実のGDPからGDPギャップを推計すると、98年には6か国合計のGDP総額に対して約10%程度のマイナスのギャップが生じている。これは、世界全体のGDP総額の▲0.4%程度、主要先進7か国のGDP総額の▲0.6%程度に相当する[注7]。東アジアの経済収縮は極めて大きなものであり、これが先進国の物価引下げ要因としても大きく働いたものと考えられる。
- 注1 IMF,“World Economic Outlook”(1996年10月)では、先進国の物価変動の要因として短期(0~1年)的には為替レートや石油価格の影響が大きく、中期(3~5年)的にはこれら以外にGDPギャップや貨幣数量の影響も大きいことが分析されている。
- 注2 IMFの調査に基づく米ドル建ての指数(1995年=100)であり、原油以外に貴金属(金、銀)も含まれない。主な構成品目は、食料、飲料、農産物、金属類などとなっている。
- 注3 確認埋蔵量に関する統計は発表する機関によって異なり、様々な方面からその虚構性が指摘されていることに留意する必要がある。これは、埋蔵量が国家あるいは企業にとって機密的な情報に値することや、どの機関の発表も推定の域を越えないことなどから、作為的な要素が少なからず働いている可能性があるということに基づいている。現在、確認埋蔵量に関する国際的な統一基準を構築すべく努力が続けられているところである。
- 注4 他国の関税率についてはThe World Bank,“World Development Indicators 1998”を参照のこと。
- 注5 より詳しくは平成8年度「世界経済白書」を参照のこと。
- 注6 Dynamic Random Access Memoryの略。コンピュータのメイン・メモリーに使われている。
- 注7 東アジア6か国の潜在成長率を、インドネシア(5~6%程度)、韓国(6~7%程度)、マレイシア(5~6%程度)、フィリピン(2~5%程度)、シンガポール(5~6%程度)、タイ(5~6%程度)とした。推計方法については、「アジア経済1999」(経済企画庁)を参照のこと。なお、GDPギャップの結果についてはある程度の幅をもってみる必要がある。また、世界経済全体および主要先進7か国のGDP総額との比較においては、簡便的に1997年の名目GDPでウエイトづけした。
| 第1章 世界経済の現況 | 第2章 アメリカ経済の長期拡大の要因と課題 | 第3章 物価安定下の世界経済 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 |
| 概観 | アメリカ | 欧州 | アジア | 金融・商品 | 通貨・金融システム | 特徴 | 要因 | 生産性 | 課題 | 現状 | 要因 | 特徴 | 金融政策 |

