第2章 第1節 アメリカ経済の長期拡大の要因と課題
| 第1章 世界経済の現況 | 第2章 アメリカ経済の長期拡大の要因と課題 | 第3章 物価安定下の世界経済 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 |
| 概観 | アメリカ | 欧州 | アジア | 金融・商品 | 通貨・金融システム | 特徴 | 要因 | 生産性 | 課題 | 現状 | 要因 | 特徴 | 金融政策 |
第2章 アメリカ経済の長期拡大の要因と課題
《第2章のポイント》
[90年代の景気拡大の特徴]
アメリカ経済は、91年3月に景気回復を始め、99年10月に至るまで8年7か月もの長期にわたる景気拡大を続けている。90年代の景気拡大の特徴は、良好な状態が「安定」して「長期にわたって」続いていることである。また、今回の景気拡大局面では、物価上昇率と失業率とがともに極めて低い水準にまで低下したことも特徴である。両者の和で定義される悲惨指数は98年5月には、ほぼ33年ぶりの低水準となった。
[90年代の景気拡大の要因]
長期にわたる安定的な景気拡大の要因として、a)予防的な金融政策に代表される適切な経済運営、b)労働市場を始めとする経済構造の柔軟性の向上が挙げられる。他方、97年以降における低インフレと低失業率・高成長率の両立は、c)ドル高や一次産品価格の低下といった一時的な要因によってもたらされた部分が大きかったと考えられる。
[アメリカ経済の生産性向上]
ここ数年、経済成長率が高まる中で、景気変動要因等を取り除いても生産性の伸びが高まっている。産業別の動向をみると、製造業、特に電気機械などのハイテク産業の生産性の伸びが高い。生産性向上の要因としては、情報通信関連投資の高まり等によって資本ストックの質が向上していることなどが挙げられる。今後については、現在の投資ブームが長く続くとは考えにくいことなどから、高い伸びが持続しない可能性もある。
[アメリカ経済のアキレス腱]
アメリカ経済に存在する不透明感として、a)割高感の指摘される株価、b)低下が続く家計貯蓄率、c)経常収支赤字の拡大、d)インフレ懸念の高まりの四つがある。株価やドルの急落を招くことなく、経済を軟着陸させることが重要な課題である。
アメリカ経済は、1991年3月に景気回復を始め、99年10月に至るまで8年7か月(103か月間)もの長期にわたる景気拡大を続けている。これは61年からの景気拡大(106か月)に続き戦後二番目の長さとなっているが、このまま2000年2月まで拡大局面が続けば、戦後最長の景気拡大となる。戦前までの景気拡大は短命(平均約30か月)で終わっていたが、戦後は一部の例外を除けば長期化し、同時に景気後退局面も短期化するという傾向が見られる(第2-1-1図)。今回の景気拡大もこのような何十年にもわたって生じている大きな変化を反映したものとしてとらえることもできよう。しかし、今回の景気拡大局面では、ここ数十年間は見られなかった新しい様相を呈するようになっている。すなわち、失業率、物価上昇率がともに極めて低い水準にまで低下し、また、連邦財政収支は改善し続け、98年度には29年ぶりに黒字に転換している。さらに、株価(ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価指数(以下ダウ平均))の高い上昇が続き、99年8月25日には11,326.04ドルと過去最高値を更新した。また、1970年代以来向上のみられなかった生産性もここ数年向上している。
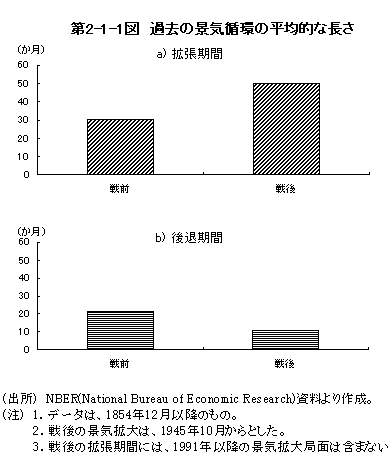
本章では、このような今回の景気拡大局面について、a)過去の景気拡大局面と比べてどのような特徴があるのか(第1節)、b)長期にわたる景気拡大をもたらしたのはどのような要因なのか(第2節)、c)生産性向上の要因は何か、またそれは経済の良好なパフォーマンスを説明するものなのか(第3節)、d)好調な経済に懸念はないのか(第4節)、という点について検討する。
第1節 90年代の景気拡大の特徴
90年代の景気拡大の特徴は、良好な状態が「安定」して「長期にわたって」続いていることである。経済成長率についてみると、2~3%台[注1]と、歴史的にはそれほど高くないが、大きな変動もなく91年以来、約9年の長期にわたって安定した成長が続いている(第2-1-2表)。さらに、需要項目別にみても、主に物価や金利の低下と安定を背景として、個人消費や設備投資、住宅投資が、過去の景気拡大局面に見られたような大きな変動を示すことなく、息の長い拡大を続けている(第2-1-3図)。特に、設備投資については、伸びが相対的に高く安定していることから、過去の景気拡大局面と比べて、成長に対する寄与度が大きくなっている。こういった特徴は、これまで変動の大きかった部分(例えば自動車購入)が安定的に推移していること、変動の大きい部分(例えば産業機械設備投資)のシェアが小さくなってきていること、などが影響しているものと考えられる。このような物価、金利動向を含めた安定した経済状況は、人々の将来の経済状況に対する期待を安定的なものとし、消費や投資といった経済活動を刺激するという側面がある。

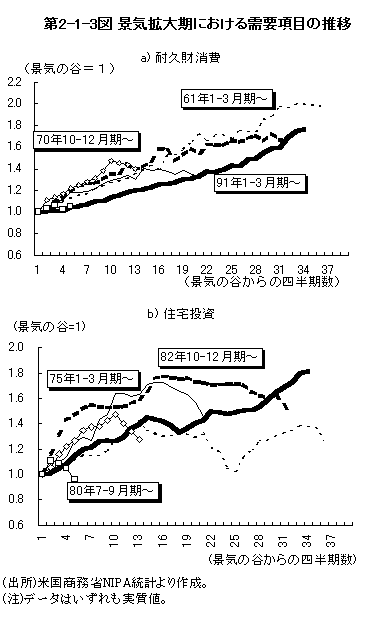
景気拡大が長期にわたる中で、低金利が続き、物価上昇率と失業率が極めて低い水準にまで下がったことも特徴である。また、株価が大幅に上昇したことも、80年代までの景気拡大と比較した今回の景気拡大の特徴の一つであった。 なお、他の先進諸国と比較した場合、経済成長率や物価上昇率が安定しており、株価については上昇率は大きいものの、変動が小さいことが特徴である(前掲第2-1-2表、第2-1-4表)。特に物価については、世界的に低インフレが進行しているため、物価上昇率はどの国でも低くなる傾向にあるが、アメリカでは安定的に推移している。
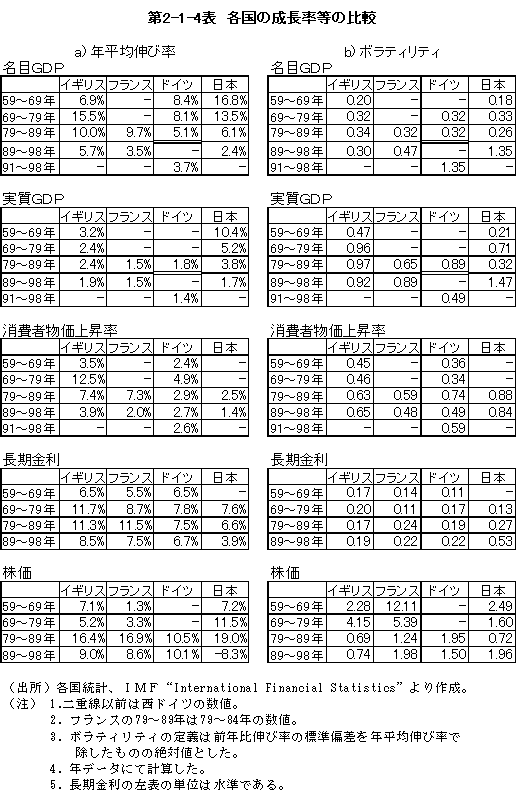
1 長期にわたる安定的な拡大
(個人消費の特徴)
GDPが安定的に推移した理由としては、その約7割を占める個人消費支出が安定的に推移したことが大きい。今次の景気拡大局面において、個人消費が安定的に推移した要因は、耐久財消費の変動が過去に比べて安定していることである。
最初に、消費全体の動向を80年代から通してみる。80年代の実質個人消費の年平均伸び率は3.4%であったが、90年代の前半は2.1%とやや伸びが鈍化した後、95年から98年にかけては同3.8%となった。名目ベースでの支出構成比をみると、80年には耐久財が12.1%、非耐久財が39.5%、サービスが48.4%であった。これが90年には耐久財12.4%、非耐久財32.4%、サービス55.2%となり、さらに1998年には耐久財12.5%、非耐久財28.6%、サービス58.9%となった。このように耐久財のシェアはそれほど変わらないものの、非耐久財のシェアは低下し、サービス化が進んでいる。
一般的に非耐久財消費とサービス消費は耐久財に比べて変動が小さく、個人消費の変動は主に耐久財消費の変動によって引き起こされる。今回の景気拡大においてはこの耐久財消費が安定的に推移した。
耐久消費財の内訳をみると、特に自動車購入の動向が過去の景気拡大局面と比べて安定的に推移していることが着目される。過去の循環局面における自動車購入の年間伸び率(実質)をみると、71年に19.1%の後74年に▲17.1%、76年に20.9%の後80年に▲13.5%、83年に19.8%の後87年に▲3.8%、88年に6.1%の後91年に▲13.8%と大幅な変動を繰り返している。それに対して、今回の景気拡大局面においては、92年に7.1%を記録した後は97年までは0~6%程度で比較的安定的に推移している(第2-1-5図)。
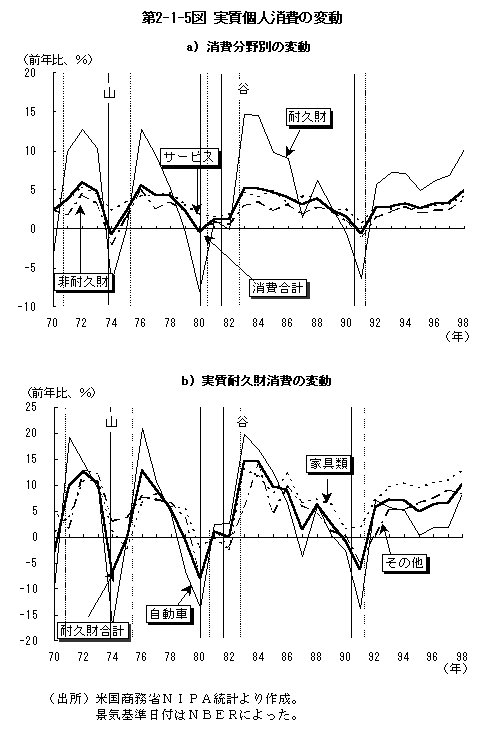
(設備投資の特徴)
民間設備投資の伸びが安定的に推移してきた背景には、変動の大きな構築物投資や産業機械投資のシェアが低下する一方で、情報化投資など景気変動の影響を受けにくい投資項目のシェアが増加するという変化があった。
名目GDPに占める割合で民間設備投資の内訳の推移をみると、工場やビルなどから構成される構築物投資は、製造業におけるファブレス化(自社では工場を所有せず他社に生産を委託する形態)や80年代の不動産ブームの反動などを反映して、80年代半ばからほとんど増加していない。一方で、機械設備投資は、全体の設備投資の伸びと平行して上昇している。機械設備投資は構築物投資に比べて安定的に推移する傾向があるため、このことが設備投資全体の推移を安定的なものにした。さらに機械設備投資の内訳をみると、情報通信関係、輸送機器が大きく伸びている(第2-1-6図)。これら、2つの項目は、90年代を通じて極めて安定的に推移している。情報関連投資は、もともと景気変動の影響を受けにくい特徴がある。また、輸送機器投資は卸・小売業の隆盛を反映したものであるが、卸・小売業は製造業や建設業などに比べると景気変動の影響を受けにくいため、輸送機器投資も安定的に推移したものと考えられる。他方、産業機器への投資は、79年から80年にかけてピークを迎えた後は、ほとんどの産業で横ばいか、下降している。これは、80年代半ば以降において、生産拠点の海外移転などが進んだためである。変動の大きな産業機器投資需要が減少したことも設備投資全体の安定的な推移に寄与した。
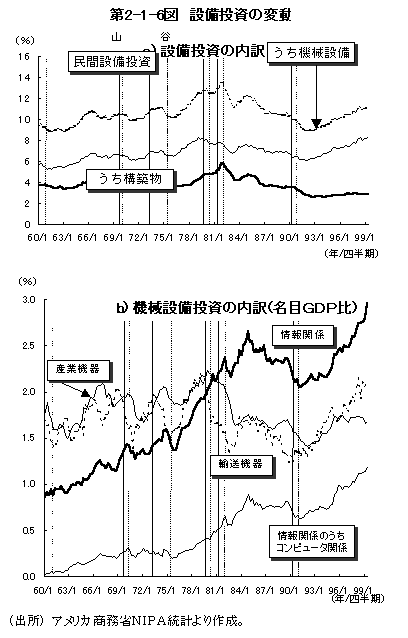
(住宅投資の特徴)
住宅投資の安定した伸びの背景には、金利の安定、所得の堅調な伸び、各種政策による需要の創出、及び80年代に購買層に達したベビーブーム世代による高額・大型住宅への買替え需要増といったものがある。
80年代までの住宅投資は、世帯数の増減と大きな相関があり、ベビーブーマー世代による一次取得の影響が大きかった。これに比べると、90年代は、人口動態はそれほど大きな潜在購買力増加要因とならなかった(第2-1-7図)。したがって、今回の景気拡大における住宅投資は過去の住宅投資に比べてその増加速度は大きくない。しかし、低金利や好調な景気が持続したことを背景として、ベビーブーマー世代によるより高額・大型住宅への買替え需要が発生したこと、家計の購買態度が全体に強気なこと、一戸建て志向が高まったこと、中低所得者層による中古住宅への需要が高まったことで、堅調な需要が長期にわたって続いている。この買替えに伴い、今回の景気拡大では、中古住宅販売件数が過去最高となった(第2-1-8図)。特に、これまで持ち家率の低かった非白人層が持ち家率を高めたことが特徴である。この結果、全体の持ち家率の上昇は顕著であり、99年4~6月期で66.6%と歴史的高水準にある。また、買替え需要や、所得の伸びに応じて、全体に新築住宅1戸あたりの質が向上していることも特徴的である(第2-1-9図)。政策要因としては、80年代後半から、住宅コミュニティ開発法による低所得者に対する支援の拡充、ARM(Adjustable Rate Mortgage)[注2]の導入など金融機関に対する規制緩和措置、ゾーニング規制や建築基準など住宅に関する諸規制の可能な限りの撤廃、などの様々な措置により住宅市場の活性化が図られてきており、こうしたことも住宅投資の息の長い拡大に貢献したと考えられる。
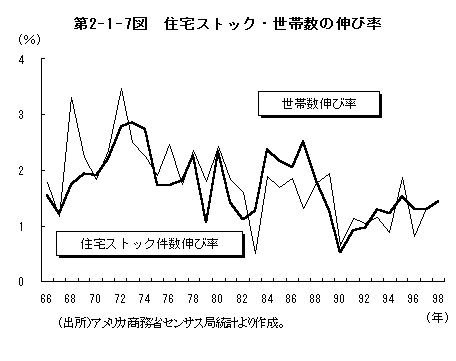
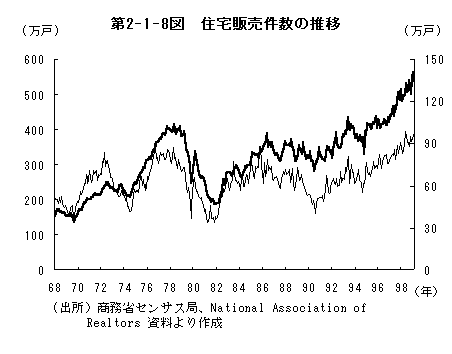
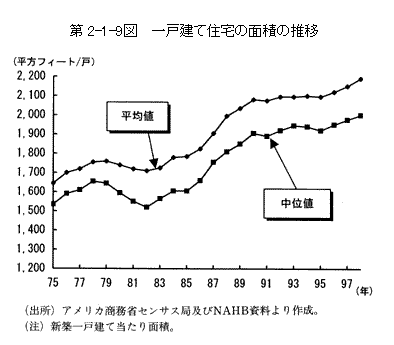
2 低金利・低インフレ・低失業率
以上のような安定した経済成長の背景には、低金利、低インフレ、低失業率が並存したことも見逃せない。実質金利は、80年代末にかけて低下した後も低水準で安定的に推移し、物価上昇率も90年代初頭に大幅に低下した後、安定して推移している(ただし、97年以降再び下落している)。
このような金利の低位安定の背景には、90年代に財政赤字が改善し、98会計年度には29年ぶりに黒字に転じたことのほか、資本の国際的移動が高まる中で、経済成長率が相対的に低い日本や欧州などから資本が流入したことなどがある。
また、物価の下落や安定の要因には、国内面では、連邦準備制度(FED:Federal Reserve System)の予防的な金融政策の効果や、1970年代以降の規制緩和や市場開放の効果、軍需産業から民需産業への転換に伴う民生市場への供給力の拡大などがある。一方、対外面では、世界的な物価の安定などがある。このように、低金利、低インフレは、安定成長の要因であるとともに、結果でもあり、相互に関連し合っている。
さらに、失業率が持続的に低下し、30年ぶりの低失業率で推移している。通常、失業率が6%を下回ると物価上昇率が加速すると考えられていたが、6%を下回った93年以降においても物価上昇率は加速していない。この要因として、91~93年以降にかけて、労働市場の柔軟化を背景にNAIRU(Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment:インフレを加速させない失業率)が低下している可能性がある。この結果、物価上昇率と失業率の和で定義される悲惨指数は98年5月には5.7と1965年12月以来33年振りの低水準となった(第2-1-10図)。
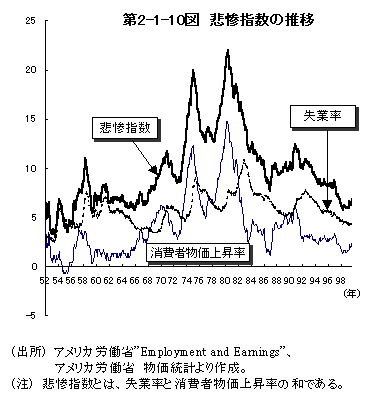
3 株高:その要因と影響
今次景気拡大局面における特徴の一つは、株価の上昇率(年率ベース)が高く、過去最大だったことである。また、こうした中、株と実体経済との結びつきはこれまでにも増して強くなっており、株価の動向が景気に与える影響も80年代までと比べて大きくなっている。また、ここ数年では、株価の水準に対して割高感も指摘されている(第2章第4節参照)。ここでは、その株価上昇の特徴と実体経済との関連について考える。
(90年代の株価上昇の特徴)
景気拡大局面ごとに株価(ダウ平均)の推移を比較する[注3]と、82年10~12月期及び91年1~3月期からの景気拡大局面では、大幅な上昇となっている(第2-1-11図)。しかしながら、80年代と90年代の景気拡大局面では、株価上昇の特徴にいくつかの違いがある。ひとつは、株価の割高感が強い中で高水準の株価が続いていること、もう一つは、株価の変動度合いが低くなっていることである。
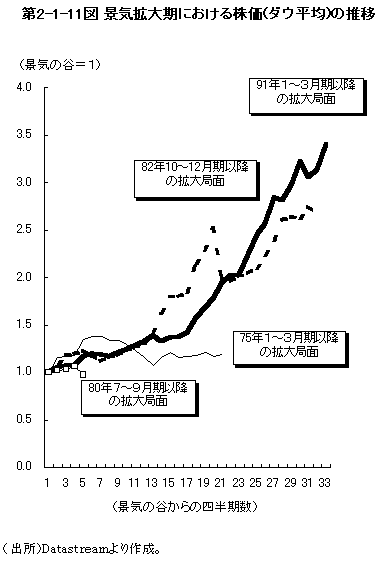
この株価の上昇には、将来の期待収益率の上昇や低金利といった要因があるが、需給という側面から見ると、需要側からは、ベビーブーマー世代の老後に向けた資金運用先として、低金利・低インフレ下で相対的に有利な株に対する需要が高まったことが挙げられる。これは、実際には、年金基金やミューチャールファンドを通じた株式購入となって表れた。90年代前半には、ミューチャルファンドブームが起こるなど個人の株式に対する関心が高まった。ブームの火付け役は企業年金制度(401k)や退職年金勘定(IRA:Individual Retirement Account)などの年金制度であった。供給側からは、企業の株式の買戻しなどが盛んであった。
(株と実体経済の関係)
上記のような株価の急激な上昇は、資産効果を通じて個人消費を押し上げ、ここ数年来の高成長をもたらしていると考えられる。景気拡大局面における年平均の実質個人消費の増加額を試算したところ、可処分所得の増加による消費増加は80年代と90年代とではほとんど変わらないのに対して、90年代は金融純資産の増加による寄与が大きい(第2-1-12図)。97、98年の実質GDP成長率3.9%のうち、それぞれ約0.3%ポイントは株高によるものである(直接保有分のみの影響を考慮した)。資産効果が大きくなっている背景には、株価が急上昇していることに加えて、先に挙げたような老後に対する備えとして株が選ばれるようになったことから、家計の金融資産と株式との結びつきが強くなったことがある。また、家計の金融資産保有額に占める株式の割合は、直接保有でみると88年末の12.4%から98年末の20.0%へ、間接保有を含むベースでみると17.2%から34.6%へと約2倍に拡大している。

- 注1 本章におけるGDP成長率等は特に断りのない限り99年9月までに公表された旧基準ベースの数字を用いている。
- 注2 変動金利型住宅ローン。金利と毎月の支払金額が特定の指標金利等によって変更される住宅ローン。
- 注3 長期で比較する場合、銘柄の入れ換えに注意する必要がある。
| 第1章 世界経済の現況 | 第2章 アメリカ経済の長期拡大の要因と課題 | 第3章 物価安定下の世界経済 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 |
| 概観 | アメリカ | 欧州 | アジア | 金融・商品 | 通貨・金融システム | 特徴 | 要因 | 生産性 | 課題 | 現状 | 要因 | 特徴 | 金融政策 |

