第1章 第5節 国際金融・商品市場動向
| 第1章 世界経済の現況 | 第2章 アメリカ経済の長期拡大の要因と課題 | 第3章 物価安定下の世界経済 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 |
| 概観 | アメリカ | 欧州 | アジア | 金融・商品 | 通貨・金融システム | 特徴 | 要因 | 生産性 | 課題 | 現状 | 要因 | 特徴 | 金融政策 |
第5節 国際金融・商品市場動向
1 為替市場の動向
米ドルは、クリントン政権のドル高政策の下、1995年以降増価基調で推移してきた。モルガン銀行発表の名目実効レート(1990年=100)をみると、98年8月に116ポイント台の高値をつけた後、ロシアのルーブル切下げに端を発する世界的な金融収縮により、10月半ばには104ポイント台まで下落した。その後は金融情勢の安定化とともに増価基調を取り戻したものの、99年7月以降は対円で大きく減価したことなどから減価基調となっている。以下では、まず過去一年間の米ドルの変動について記述する。次に、99年1月より出現したユーロは、導入当初と比べると減価基調で推移しているが、このユーロの動向について記述する。最後に、97年7月のタイ・バーツの管理変動相場制移行以来大幅な価値変動が生じたアジア通貨についてその動向を概観する。
(米ドルの動向)
対円での動きをみると、98年の後半に生じたロシア危機以降、金融危機の世界的伝播が懸念され、かつ米景気も減速、金利も低下したことから、米ドルの減価基調は99年1月頃まで継続した。2月に入り、金融危機の払拭とともに米株価の上昇基調も続き、日本の景気回復の遅れが懸念されていたことも加わって米ドルは上昇基調に転じた。その後は、日本の経済成長率がプラスに転じたことや、日本の株価が大きく上昇した一方で米株価は長期金利上昇に伴って相対的に伸び悩んだことなどから、7月以降ドル安基調に転じた(第1-5-1図)。
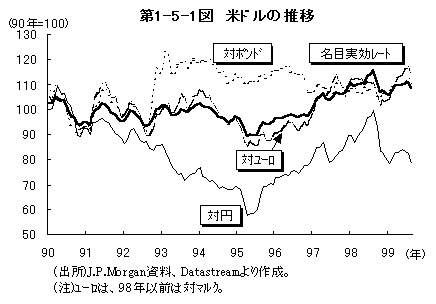
一方、対ユーロでは、99年1月のユーロ誕生直後こそ新通貨に対する期待感から1.18ドル/ユーロと、当時の安値となったものの、ユーロ圏のアメリカとの景況感格差やコソボ紛争の長期化などから一方的に増価基調で推移した。7月に入り、ユーロ圏の景気回復期待などから対ユーロでの増価基調は収まり、以後は1.05から1.06ドル/ユーロの間の推移となっている。
(欧州通貨の動向)
国際決済銀行(BIS:Bank for International Settlements)発表のユーロの名目実効レート(1990年=100)をみると、97年8月以降増価基調で推移してきたユーロ(エキュー)は、98年10月以降は総じて減価基調に転じ、今日に至っている(第1-5-2図)。また、ユーロ以外の欧州通貨についてみると、イギリス・ポンドやスイス・フランといったERM2) (Exchange Rate Mechanism:自国通貨の対ユーロの変動幅を一定以内に収める制度でデンマーク・クローネとギリシャ・ドラクマが参加している)に参加していない欧州通貨は99年初からしばらくの間は対ユーロでの変動幅が大きかったものの、このところの相場は落ち着きを取り戻しつつある(第1-5-3図)。コソボ問題等の政治的な要因が解決したことや市場がユーロに対する評価を定めつつあることが、相場の平静を取り戻させた原因として考えられる。また、イギリス・ポンドは対ユーロで年初の相場からは増価しており、通貨統合参加の動きとも合わせて、今後の対ユーロ相場の動向が注目される。また、ドルに対しては両通貨ともに減価傾向にあり、これはアメリカとイギリス、スイス両国の景況格差を反映したものと考えられる。
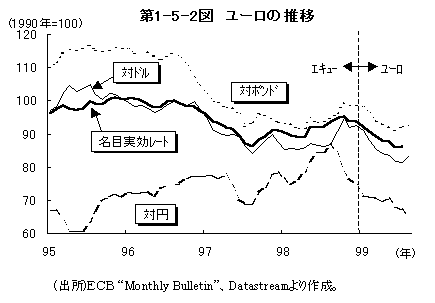
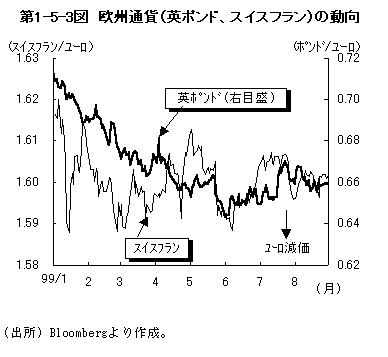
(市場におけるユーロ建て取引の割合)
国際金融市場における債券の発行額の推移を通貨建てベースでみると、99年1~3月期以降はユーロ建ての債券発行が目立って増えている。99年4~6月期には、ドル建て債券発行額が1,936億ドルであったのに対し、ユーロ建て債は1,766億ドルであった。全発行額に占める割合を比較しても、ドル43.4%に対してユーロ39.6%となった(第1-5-4図)。
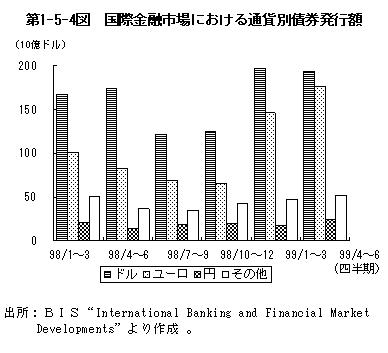
また、国際金融市場におけるBIS報告国銀行貸出しの通貨別増減額をみてみると、フローベースでみて99年1~3月期にドルでの貸出額が1,058億ドルのマイナスとなっているのに対し、ユーロ圏通貨での貸出額は3,365億ドルのプラスとなっている。残高をみてもドルが3.77兆ドルに対してユーロ圏通貨2.84兆ドルと構成割合はユーロ圏通貨がドルに近づいてきている(第1-5-5表)。
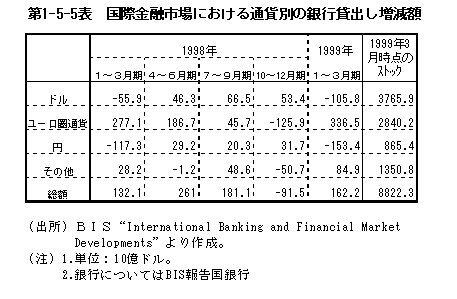
次に、内国債[注1]市場の規模を比較してみる。従来は、マルクやフランといった通貨建てで債券が発行されており、各国で独自の内国債市場を形成していた。しかし、99年1月以降はユーロ地域内では国債はすべてユーロ建てになっており、また、2002年1月までに社債などの建値移行が完了すれば、ユーロ域内の債券すべてがユーロ域内債(ユーロ圏での実質的な内国債)となる。その場合、EU11か国で発行残高は世界シェアの約2割を占め、アメリカに次いで世界で2番目の市場規模となる。
このことからも、為替相場こそ減価基調にあり、市場から十分な評価を受けているとは言い難いが、ユーロは金融・資本取引の手段としての地位を一歩一歩固めつつある。
(アジア通貨の動向)
東アジア通貨の対米ドル為替レートの推移をみると、97年7月のタイ・バーツの下落をきっかけとして、中国元、香港ドルを除き97年末にかけて大幅に減価した。特にIMFの支援を受けることとなったタイ、インドネシア、韓国の通貨下落は激しく、タイは通貨バスケット制から管理変動相場制へ、インドネシア、韓国は管理変動相場制から完全変動相場制へと為替制度を変更した。
98年に入り、IMF主導による緊縮政策や国内経済改革の進展に対する期待などから、アジア通貨は増価傾向に転じ、98年4月頃まで増価傾向で推移した。その後98年末頃まで韓国ウォンは増価基調が続き、その他の通貨は概ね横ばいの状態で推移した。しかし、インドネシア・ルピアについては、国内経済改革に対する取組の遅れや、98年5月のスハルト政権交代前後の政情不安定化などから、98年6月に1ドル=16,000ルピア台まで下落した。その後ハビビ政権の下、為替レートは強含みに推移し、11月には1ドル=7,000ルピア台となった。また、マレイシア・リンギは、98年9月に投機防止を目的として1ドル=3.8リンギに固定された。98年10月頃から円高・ドル安につれて東アジア通貨は総じて増価傾向で推移したが、99年に入ってからはおおむね横ばいで推移している。マレイシア・リンギは相対的に割安なレベルとなっており、マレイシアの輸出増加に貢献している。インドネシア・ルピアは44年ぶりの民主選挙である6月の総選挙が大きな混乱なく実施されたため、一時増価したが、8月には東ティモール情勢の混乱などから大幅に減価した(第1-5-6図)。
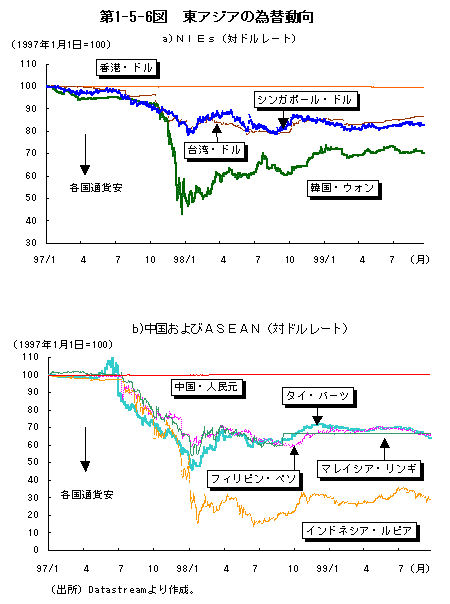
2 欧米の長期金利の動向
(アメリカの長期金利の動向)
長期的に低下基調が続く長期金利は、98年の9月から10月にかけてロシアの債務支払停止などに端を発する世界的な金融危機が発生したため、信用度の高い米国債へと資金が集まり、一層低下した。だが、FRBによる機動的な三度の利下げなどの金融緩和政策により金融収縮は収まりをみせ、99年に入ってからは景気の過熱と労働市場の逼迫によるインフレ圧力の高まりへの懸念などから長期金利は上昇を開始し、6%を超える推移となった。ここで、期間の異なる利回りの格差を表すイールドカーブをみてみると、98年9月までは好況とインフレ率の低下を反映して短期金利(FFレート)が高くなっている一方で長期金利が低くなっているが、その後は金融緩和及び利下げを反映して短期金利が低下した。しかし、金融情勢が落ち着き、またインフレ懸念が顕在してくると金利先高感の高まりにより長期金利が上昇、イールドカーブはスティープ化している(第1-5-7図)。次に、格付けの異なる債券間の利回り格差をみると、昨秋の金融市場の混乱の際に拡大した格差は、市場の正常化により縮小に向かったものの、99年8月以降2000年問題対応などを目的とした大量の社債前倒し発行などにより再び拡大している(第1-5-8図)。
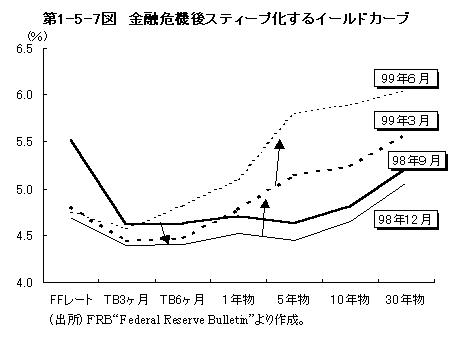
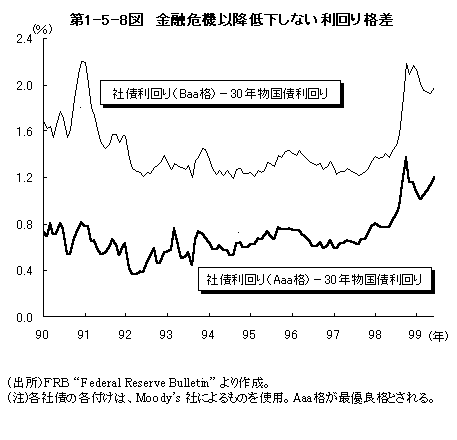
(欧州の長期金利の動向)
ユーロ誕生後、約半年間の金融指標の動向をみてみる。ドイツ10年国債をベンチマークとした長期金利の動きであるが、ドイツやイタリアなどの通貨統合中心国の景気減速懸念から利下げが期待されたものの、欧州中央銀行(ECB:European Central Bank)幹部による度重なる利下げけん制発言などで長期金利は上昇した(ECBは4月に政策金利を0.5%ポイント下げて2.5%とした)。また、ユーゴ情勢が不安定化した4月以降長期金利は上昇し、紛争が一服した後もユーロは安値圏で推移し、景気回復期待もあいまって金利は上昇している。
3 株式市場の動向
(史上最高値を更新、ダウ1万ドルが定着した米国株式市場)
アメリカの株価は、98年秋には世界的な金融収縮から一時的に大きく下げる場面があった。しかし、FRBによる迅速な金融緩和により逆資産効果などによる景気の減速は回避され、株価は再び上昇基調に復帰した。99年に入ってからも米株価は順調に推移し、最高値を更新し続けたが、5月以降は景気の過熱による長期金利の高まりとともに上値が抑えられており、ダウ平均で10,000~11,000ドル台の推移となっている。以下では、近年の株価上昇(ダウ平均の89年末から98年末にかけての上昇率233.5%)の要因について分析を行う。
(株式市場への資金流入)
近年のアメリカの株価上昇の背景として、年金基金やミューチャルファンド(投資信託)に代表される機関投資家の株式市場への参入がある。アメリカの企業株式の保有主体をみると、ミューチャルファンド及び年金基金の割合が80年には2割強であったものが、98年には4割弱に増加している。一方で家計セクターが占めている割合は6割弱から4割強へと低下しているが、このことは決して家計の株式保有が減少していることを意味しない。むしろ間接保有が促進されたことの表われであり、結局のところ機関投資家を通じた株式の保有割合が上昇していることを意味している(第1-5-9図)。現に家計の金融資産構成をみてみると、株式の占める割合は直接保有が80年には14%であったのが、98年には21%に上昇している。また、ミューチャルファンドや年金などの間接保有分を含めれば、17%から36%とより大幅に上昇している。逆に、預貯金は23%から14%へと低下しており、家計の株式選好が高まっていることが分かる(第1-5-10図)。
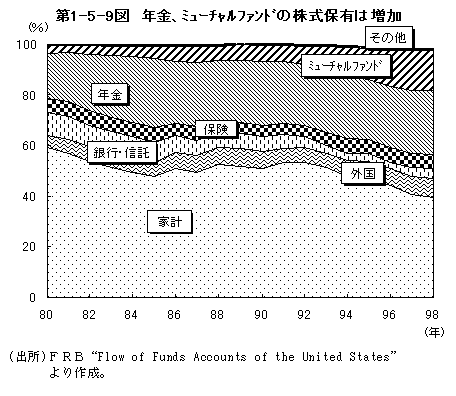
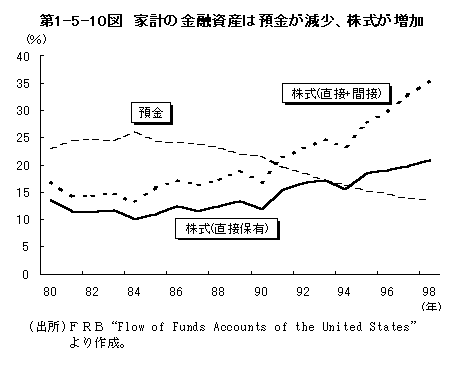
(企業収益の高まり)
アメリカの株価上昇の一因は好況を反映した企業収益の増加である。また企業には、稼得した収益を配当として社外流出させるかもしくは社内に留保して再び事業に投資するという選択肢があるが、S&P500企業について配当性向及び一株当たり利益をみると、92年以降97年まで配当性向は低下傾向を示しており、かつ一株当たり利益は増加している。また、同期間の株価も同様に上昇しており、企業が稼得した利益を配当せずに投資に充て、更なる利益を生み出して株主に報いている姿が浮かび上がる(第1-5-11図)。
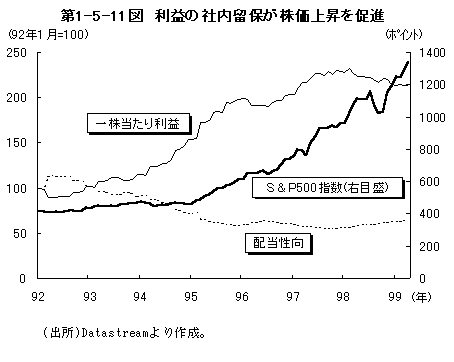
(株価指数固有の性質)
アメリカの代表的な株価指標にダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価指数(以下ダウ平均)と、S&P500総合指数(同S&P500指数)がある。ダウ平均とはニューヨーク証券取引所上場の優良企業30社の株価平均[注2]であり、S&P500指数とはアメリカの主要500社の株価を株式時価総額で加重平均して算出したものである。後者は全米の株式時価総額の約7割ほどを占めるため、前者に比べてカバレージが大きくアメリカ全体の株価の推移を表していると類推できる。そのS&P500指数をみると、99年に入ってからも順調に推移し、新値を度々更新する展開になり、90年1月に比べて約4倍に上昇している。これに対し、中小企業群で構成されるラッセル2,000指数では98年4月に最高値を更新して以来、相対的に低迷しており、90年1月以来の上昇率は150%強である。このことは、好況といえども企業セクターの全カテゴリーにおいて隆盛を謳歌しているというよりは、好不調が明確に分かれ一部の大企業を中心に上昇しているといったほうが正しいであろう(第1-5-12図)。また、日本の店頭市場に相当するナスダック株式市場に上場している企業群から構成されているナスダック総合指数(以下ナスダック指数)をみると、S&P500指数以上の上昇を示しており、同期間に約6倍の上昇を示している。しかし、ナスダック指数はS&P500指数と同様に構成銘柄の株価を株式時価総額で加重平均して算出されており、マイクロソフトやインテル、シスコ・システムズなど少数のハイテク大企業の占める割合が大きいため、これら少数の大企業の株価上昇に全体のナスダック指数が引きずられる結果となっている(第1-5-13図)。
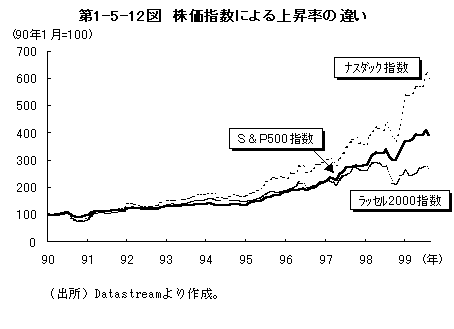
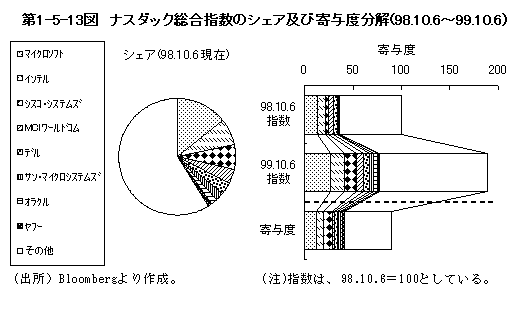
(外国人買い)
好況を背景として順調に上昇を続ける米国株式市場に、ヨーロッパなどから大量の資本が流入し、株価を押し上げる一因となったと考えられる(第1-5-14図)。図をみると、93年以降の外国人投資家は米国株式を買い越しており、98年には株価急落から騰勢が鈍化したものの、金融市場が安定した99年以降は買い越し額が増加を続けている。また、米国人の外国株式の購買動向をみると、97年までは外国株式を買い越しているものの、98年後半以降売り越しに転じている。
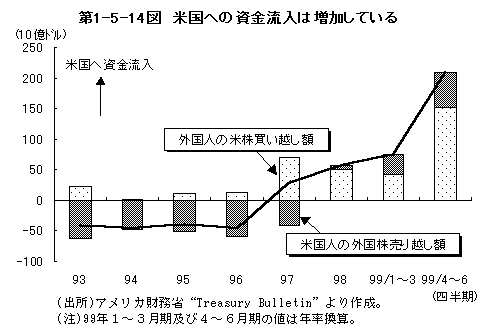
(米国株は割高か?)
近年、従来以上のペースで上昇するアメリカの株価について、グリーンスパンFRB議長を始めとして警鐘を鳴らす向きが増加している。株価が割高かどうかを示す代表的な指標としては、株価が利益の何倍まで買われているかを示す株価収益率(PER:Price-Earning Ratio)などがあるが、投資対象という観点からみると、低金利のときには債券投資は投資利回りが低下するため選好されなくなり、一方では株式が余計に選好されるため株価が上昇しやすくなる。そのため、金利水準を考慮した金利修正PER(長期金利×PER)を用いて現在の株価を評価してみると、99年10月現在ブラックマンデーに匹敵するほどの割高水準であることが読み取れる(第1-5-15図)。
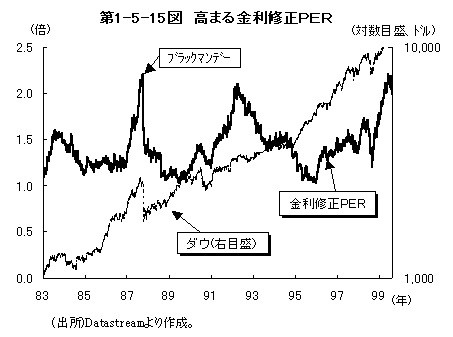
(回復期待から上昇した欧州株価)
一方、欧州株は堅調に推移している。特に内需中心に景気が堅調なフランスのCAC40指数などの上昇が目立つ。しかし、先行きには不安材料もあり、a)アメリカの株価が調整局面に入ったときの影響や、b)欧州諸国において長期金利に上昇圧力がかかっていることなどが注意すべき点である(第1-5-16図)。
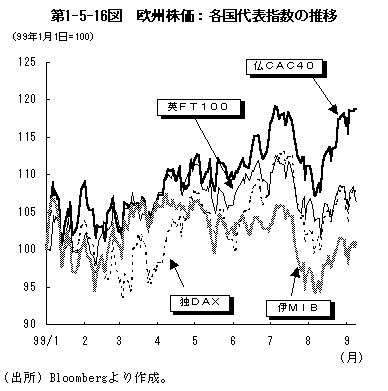
(米ドル換算後の欧州株価)
近年は金融の技術革新などで大規模資本の迅速な移動が可能となったことから、株式市場間での裁定がより一層働くようになり、米ドル換算後の米独英の株価動向は類似性が高いものとなっている(第1-5-17図)。なお、ドル換算後の日本の株価は欧米のそれとは全く異なる動きをしている。
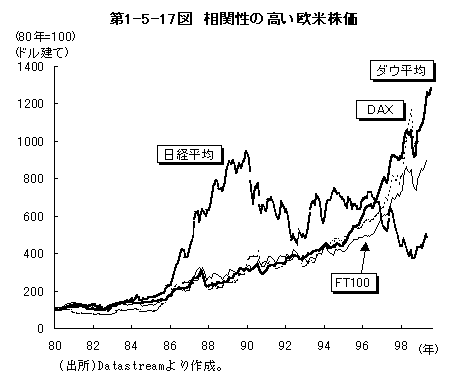
(欧州証券市場統合へ)
ユーロが今後、国際通貨あるいは基軸通貨としての地位を固めるためには、安定した為替政策とともに、ドルに匹敵する流動性の確保が必要となる。欧州証券取引所協会(FESE:Federation of European Stock Exchanges )は、99年の6月にミラノで行った総会で、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、スイス、ベルギー、オランダの8ヶ国の証券取引所を統合することで基本合意した。また9月には、2000年の11月に共通の株式市場を創設することで合意し、汎欧州統一市場はユーロの誕生を期に一気に現実化することになった。99年7月末の上場株式の時価総額で7兆ドルを超え、ニューヨーク取引市場に次ぐ世界第二位の証券取引所が誕生することになる(第1-5-18図)。既に99年1月にはイギリスとドイツ間での取引所の統合が一部開始されており、99年中にも取引端末の共通化や手数料の単一化、共同会社の設立などで8取引所の市場のシステム面を共通化することになっている。この市場統合により、取引が簡素化され売買が盛んになるとともに、イギリスのロンドン株式市場が統合の中心となっていることから、新市場はロンドン並みの規制の少ない市場になることが期待される。アメリカ、日本、アジアといった地域の投資資金が、使い勝手の良くなったこの市場にシフトしていけば、ユーロ建ての取引が増えてユーロの流動性が高まる。しかしながら、ロンドンとフランクフルト間の主導権争いなど不透明な要素もあり、今後の動向が注目される。
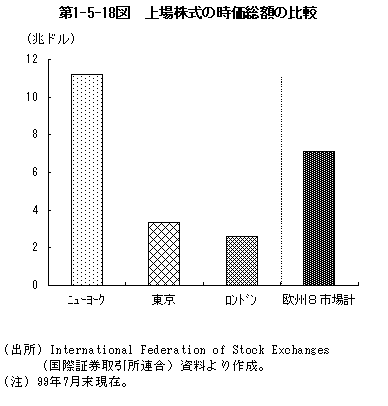
(景気回復を示唆、上昇するアジアの株価)
アジアの株式市場をみると、98年1月の主要アジア通貨の増価傾向への転換と時期を同じくして、一時的に株価は上昇に転じた。しかし、実体経済の低迷が続いたことや、多額の不良債権をかかえる金融システム不安などから企業業績が思ったほど回復せず、株価はその後下落傾向に転じ、98年10月頃まで総じて下落が続いた。特にASEAN諸国での下落が顕著で、98年3月末から9月末までの間にタイで45%、マレイシアで48%、インドネシアで49%、フィリピンで44%下落した。
98年10月頃から東アジア通貨が増価傾向で推移するにつれて株価も上昇傾向に転じた。アジアNIEsでは、景気回復への期待などから再び海外投資家の資金が流入するなど、99年に入っても株価の上昇傾向は継続し、韓国では99年4月に通貨危機前の水準に回復した。また、シンガポールでは製造業生産が大幅に回復したことなどから、7月に株価は史上最高値を更新した。ASEAN諸国でも4月以降株価が上昇した。しかし、7月にはアメリカの金融引締め政策などの影響によりアジアNIEs、ASEAN諸国ともに株価はやや下落した(第1-5-19図)。
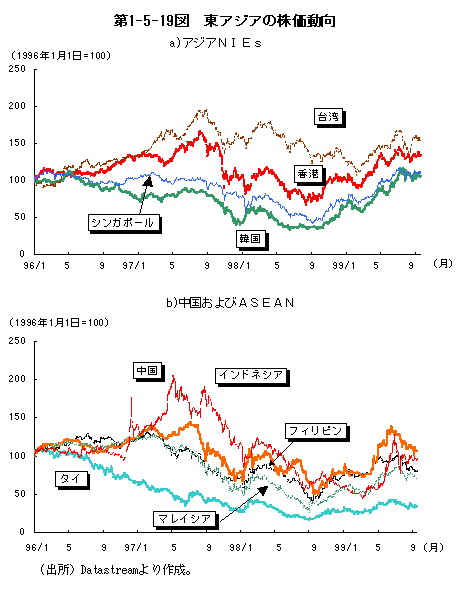
4 99年3月に上昇基調へ転じた原油価格
(国際商品価格:供給過剰等により、20年振りの低水準で推移)
生産過剰の影響等により、96年前半から下落に転じた主要な国際商品価格指数は、その後一時反発した時期があったものの、ほぼ一本調子で下げ続け、99年2月には遂に1970年代半ばの水準まで下落した。99年以降、回復の兆しをみせてはいるが、過剰在庫の解消にはなお一層の時間を要するため、回復の足取りは力強さに欠けるものとなっている。
17品目の主要な商品先物価格から算出されるCRB(Commodity Research Bureau)商品先物指数(1967年価格=100)の動きをみると、99年2月末にほぼ24年ぶりに183ポイント割れを記録した後、緩やかな上昇基調に転じたが、99年10月(月平均値)現在でも204ポイントと、依然として低水準で推移している(第1-5-20図)。
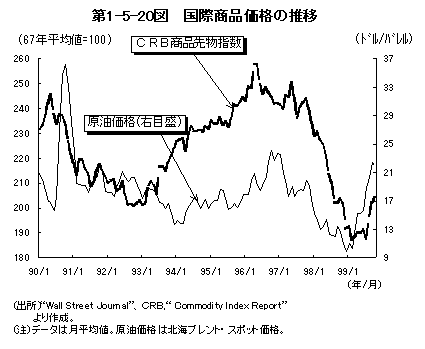
99年の動きを商品別にみると、大豆、小麦、トウモロコシなどの穀物は、97年度の豊作による供給過剰の影響に加え、99年度もまた豊作見通しが優勢であることから、総じて弱含んでいる。貴金属では、金が、IMFとスイス政府の売却計画発表に続き、99年5月に英国政府が保有金売却を発表したことから、7月から8月にかけほぼ20年ぶりの安値まで急落した。非鉄では、銅が、アジア地域の需要減退の影響から低迷していたものの、同地域の経済回復等により、99年前半から緩やかに上昇している。綿花は米国産の豊作見通しから、下落基調で推移している。コーヒー、砂糖は、南米地方の豊作等による全体的な供給過剰感から、総じて下落基調で推移している(第1-5-21図)。
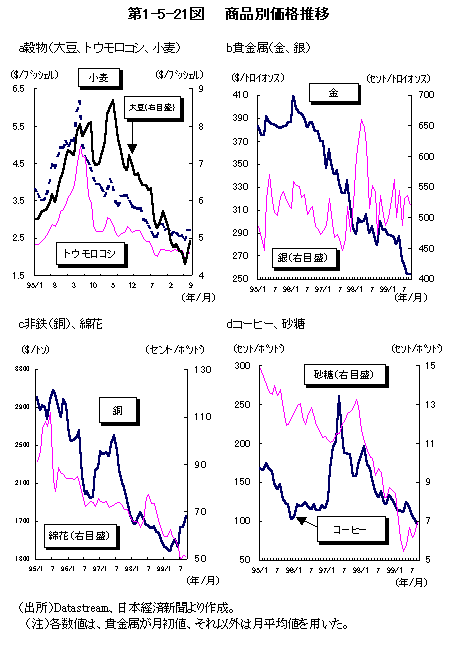
(原油価格:産油国の追加減産効果により、99年3月に上昇基調へ転換)
97年初頭を境に下落基調に転じた原油価格(北海ブレント・スポット価格)は、97年半ばから後半にかけやや反発したものの、世界的な需要の減退等によりほぼ一本調子で下落し続け、98年末には10ドル/バレルを下回る水準まで落ち込んだ。
この記録的な安値まで下落した背景には、需要面ではこれまで世界的な原油消費量の増加をけん引してきたアジア地域の需要減退や暖冬の影響、供給面においては、国連の経済制裁下にあるイラクに対し制裁の一部緩和(輸出許可金額の増加)がなされたことや、北海や中南米を中心とした非OPEC加盟国の生産量が若干ながら増加したことなどが挙げられる。原油消費量の増加率を地域別に寄与度分解すると(第1-5-22図)、高度経済成長に支えられ90年代に一貫して消費量増加に大きく寄与してきたアジア地域が、98年には一転して大幅なマイナスに寄与したことが分かる(世界全体の消費量伸び率0.1%に対し、アジア地域の寄与度は▲0.7%)。また、全世界ベースで供給量(生産量)と需要量(消費量)の伸び率を比較すると、90年代を通して需要量の伸び率が供給量の伸び率を上回ったのは、91、92、94年しかなく、とりわけ96~98年については、大幅に供給量の伸び率が需要量のそれを上回っており、需要量と供給量のアンバランスが生じた。
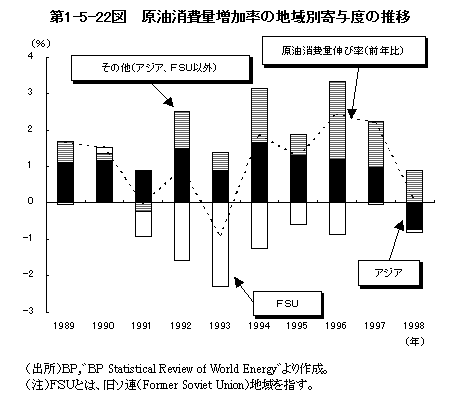
しかし、99年3月の第107回OPEC総会で追加減産(第三次減産[注3])が合意されることが明らかになると、原油価格は上昇基調に転じ、その後も、産油国が減産合意事項を比較的遵守していることが各種の在庫統計により判明したことから騰勢を一段と強めた結果、99年11月上旬には、97年初頭以来の水準となる22ドル/バレル前後で推移している(第1-5-23表)。
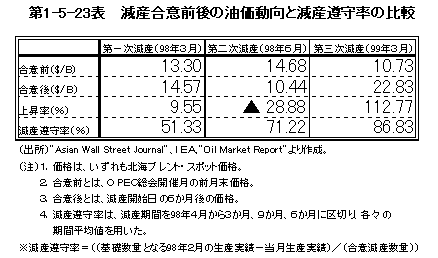
ここで、原油価格の反転上昇をもたらした最大要因と考えられる99年3月に合意された第三次減産について、やや詳しくみてみよう。98年11月のOPEC総会で何ら有効な決定がなされなかったことにより、原油価格が98年末に先述の安値まで下落したことに危機感を一段と強めたOPEC加盟国は、99年3月のOPEC総会で前二回の減産を大きく上回る規模の減産に合意し、増産によるマーケットシェア拡大路線から価格回復重視路線へ転換する姿勢を明らかにした(第1-5-24表)。財政事情の困窮が著しい国を中心に減産協定が破られてきた過去の減産の歴史にかんがみ、今回の減産に対しても懐疑的な見方をする向きもあった。しかし、国内事情が特に厳しいベネズエラの削減率を4.4%(他は一律7.3%)に設定したり、イランの減産基礎数量を同国の主張どおり引き上げるなど、前二回の減産遵守率が低く、生産シェアも大きい巨大産油国に配慮した内容となったことにより、ベネズエラ、イラン、サウジアラビアに遵守率向上の動きが顕著にみられ、99年4月以降のイラクを除くOPEC加盟10か国の減産遵守率は、それまでの遵守率を遥かに上回るものとなっている(第1-5-25図)。
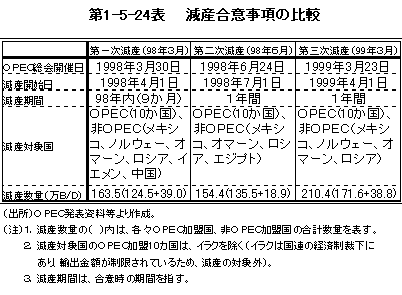
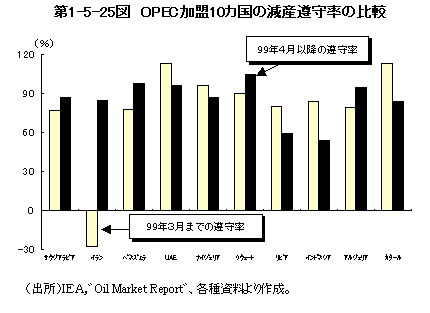
原油価格は、99年9月の第108回OPEC総会で、2000年3月まで現行規模の減産が継続されることが合意されたこともあり、OPEC加盟国が非公式の目標価格としている一バレル当たり18~20ドル(北海ブレント)を上回る水準で推移している。現在までのところ、原油価格はOPEC加盟国の思惑どおりの回復をみせているが、不安材料がないわけではない。過剰に積み上がった在庫の解消に時間を要することや、アジア地域などの需要回復動向の不確定さもあるが、最も懸念されるのは、価格の回復やシェアの喪失によって増産へのインセンティブが産油国(減産対象国)に働くことである。減産遵守率が向上することにより原油価格が回復し、その結果経済状態が好転するという産油国のシナリオどおり進むのか、あるいは増産へのインセンティブがこれを上回るのかが注目される。
- 注1 内国債とは、ある国(地域)において、その国(地域)の発行主体が自国(地域)内で発行する債券を指し、通常は自国通貨建ての場合がほとんどである。
- 注2 99年11月より構成銘柄の変更(4社)が行われたが、史上初めてニューヨーク証券取引所上場でない企業が選出された(ナスダック株式市場上場のマイクロソフト及びインテル)。
- 注3 OPEC加盟国は、その長い歴史において、過去にも幾度となく協調減産を試みた経緯はあるが、ここでは、98年3月のOPEC総会にて合意された第一次減産、98年6月の同総会にて合意された第二次減産に続く追加措置としてこのように呼ぶこととする。
| 第1章 世界経済の現況 | 第2章 アメリカ経済の長期拡大の要因と課題 | 第3章 物価安定下の世界経済 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 |
| 概観 | アメリカ | 欧州 | アジア | 金融・商品 | 通貨・金融システム | 特徴 | 要因 | 生産性 | 課題 | 現状 | 要因 | 特徴 | 金融政策 |

