第2章 第4節 アメリカ経済のアキレス腱
| 第1章 世界経済の現況 | 第2章 アメリカ経済の長期拡大の要因と課題 | 第3章 物価安定下の世界経済 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 |
| 概観 | アメリカ | 欧州 | アジア | 金融・商品 | 通貨・金融システム | 特徴 | 要因 | 生産性 | 課題 | 現状 | 要因 | 特徴 | 金融政策 |
第4節 アメリカ経済のアキレス腱
これまでみてきたように、アメリカ経済は、近年、大変良好なパフォーマンスを誇ってきた。しかし、そのようなアメリカ経済も短期的あるいは中長期的な課題を抱えている。本節では、このうち前者の短期的課題、すなわち、今後の景気動向を大きく左右しかねないいくつかの不均衡についてまとめている。これらの不均衡は、拡大を続けるアメリカ経済の、いわば「アキレス腱」とでも言うべきものであり、景気の先行きに対する一連の不透明感をもたらしている。これらアメリカ経済に存在する不透明感は、a)割高感の指摘される株価、b)低下が続く家計貯蓄率、c)経常収支赤字の拡大、d)インフレ懸念の高まり、の四つである。これらの不均衡は、長期にわたる景気拡大の中で徐々に蓄えられてきた歪みであり、特に、97年以降成長率が4%近くに高まる中で、不均衡の度合いも増していると考えられる。いかにしてこれらの不均衡を是正し、経済をソフト・ランディングさせるかがアメリカ経済の大きな課題である。
1 割高感の指摘される株価
まず最初に株価の動向について検討する。株高が資産効果を通じて家計貯蓄率を引き下げるとともに消費や投資を刺激するなどの結果、輸入の増加によって経常収支赤字が拡大し、さらに需要増によって労働需給の逼迫からインフレ懸念をもたらしているという意味において、株高は、上記の不均衡のいわば根源に位置するものである。ここで株価について考察することは以下の三つの観点から重要と考える。一つは、95年以降株価上昇率が非常に高くなっており、その結果、ここ数年は、株価の水準に関して割高感が指摘されており、株価の大幅な下落といった調整への懸念が存在しているからである。二つ目は、実体経済の中に株が深くビルトインされてきているため、株価の動向が景気動向を左右する可能性が以前より高まっているためである。もう一つは、アメリカの株式市場の動向は、アメリカにおける他の金融市場や海外の金融市場へ大きな影響を及ぼすためである。以下では、これらの点にかんがみ、株価の水準の妥当性、株価調整の可能性、実体経済や他の金融市場との関係について整理している。
(株価の水準について)
株価の水準については、96年にグリーンスパン議長が株式市場の過熱感を「根拠なき熱狂」ではないだろうかとの問題を提起したように、ここ数年来、各方面で繰り返し株価の割高感が指摘されている。しかし、98年秋の金融市場の混乱時を除けば、株価の大幅な調整は生じていない[注1]。他方で、現在の株価水準は高過ぎるわけではないという意見もある。そこで、ここでは、株価はどの程度割高と考えられるのかについて検討する。それによると、99年4~6月期の株価は企業収益や長期金利等から説明される水準からみて、少なく見積もって20%、大きければ55%ほど高い水準にあると考えられ、相当程度割高であると言える。また、98年末以降、金利が上昇する一方で、株価も上昇し続けていることから、推計値と実績値のかい離幅が拡大しており、割高感が増してきていることが指摘できる(第1章第5節参照)。
株価の水準を説明する理論は数多く存在するが、最も基本的な考え方は一般的な資産価格を説明する収益還元モデルを用いたものである。この考え方に基づけば、ダウ平均とS&P500総合指数(以下S&P500)については、99年4~6月期の株価は、企業収益と長期金利から説明できる水準から40%程度割高であると考えられる(第2-4-1図)。ところで、割引現在価値による資産価格水準は、長期的な均衡価格を説明するが、短期的な変動は説明できない。最近の株式市場の動向をみると、株式の買戻しといった需給要因や流動性の増加(経済全体で資金が豊富になれば、相対的にリターンの高い株式の需要が高まり、株価上昇要因となる)などの要因も無視できないと考えられる。そこで、次に、需給などの要因も考慮して株価の推計を行ってみると、約20%割高という結果が得られた(第2-4-2表、3図)。したがって、需給要因などを考慮しても依然として株価の割高感は解消されない。
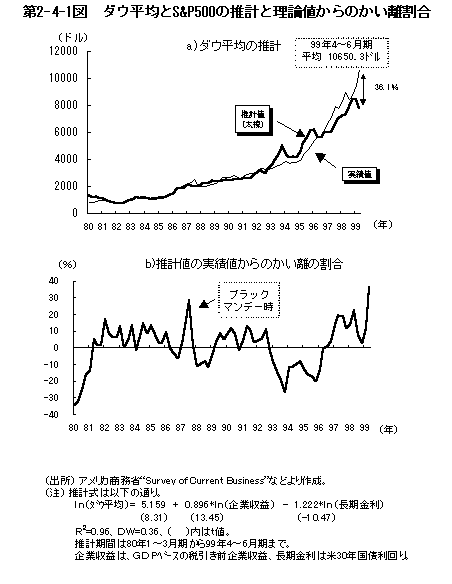
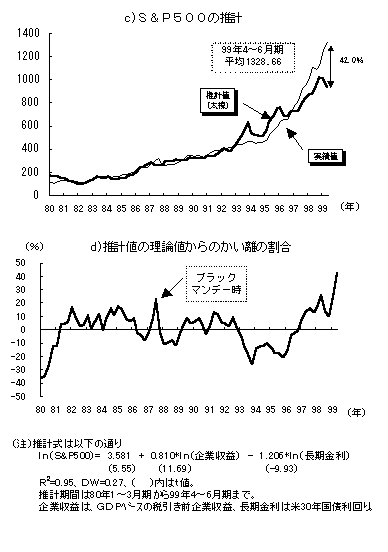
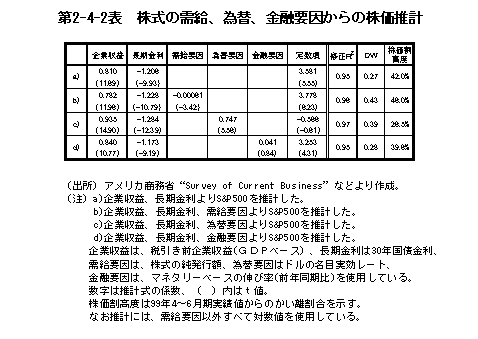
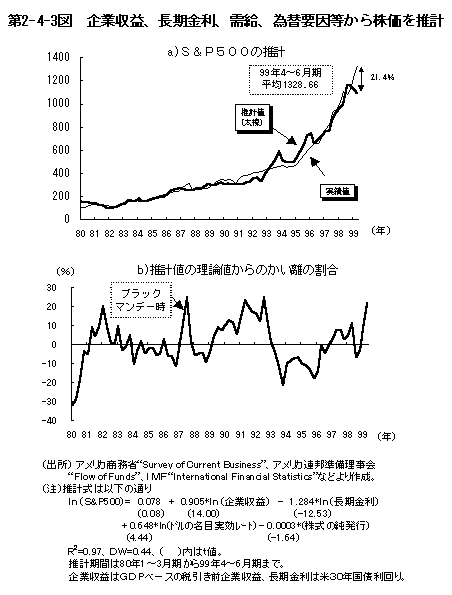
ところで、第1章5節でみたとおり、特定の株価指数と全体の企業収益を比較することには問題も多いと考えられる。例えば、優良企業やハイテク関連などの好調な企業が多く銘柄として採用されていることにより、株価の水準は平均的な企業収益から推計される水準よりも高いものとなっている可能性がある。実際、S&P500の産業別株価構成は、付加価値生産ベースの産業構成とは大幅に異なっている(第2-4-4図)。そこで、全企業を対象とした株価の代理変数として株式時価総額を用いて推計を行ったが、約40%割高との結果を得た(第2-4-5図)。全米企業数約500万社に対して株式を公開している企業は高々5~6万社程度であることから、株式時価総額を用いても、株価と企業収益の対象範囲は異なっている。そこで、企業収益の対象範囲を株価指数(S&P500)の対象範囲とそろえて推計をしてみたが、それでも5割強割高となっており、計測対象を変更しても、株価は割高である可能性を否定できないことが分かる(第2-4-6図)。
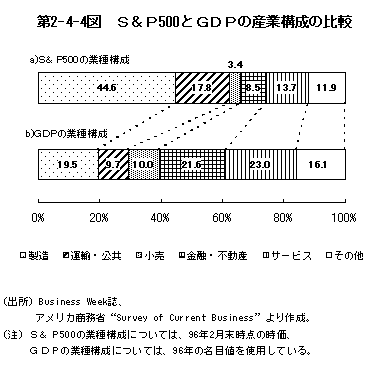
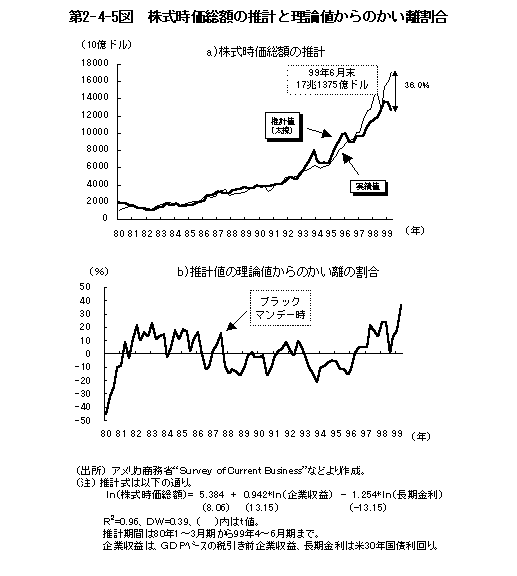
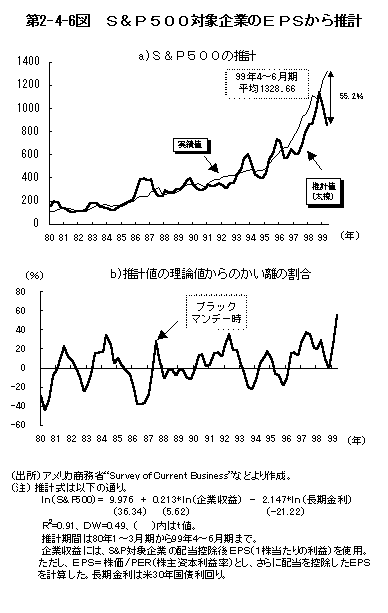
なお、80年代において、日欧などが経験した資産インフレでは、株価の上昇とともに、不動産価格の上昇が観察されたが、現在のアメリカにおいては、不動産価格の顕著な上昇はみられていない。
(高水準の株価がなぜ続くのか)
さて、いくつかの尺度を用いて、株価が割高である可能性を指摘したが、次に、株価が割高であるにもかかわらず、株価の下落(あるいは調整)がこれまで生じていない理由について考えてみたい。
第一の見方は、前述の推計結果とは逆に、株価の水準は割高でないというものである。第二の見方は、先に述べたように、株価は割高であるが、調整が先延ばしになっているというものである。
まず、株価は割高でないという見方について検討してみよう。この立場における代表的な考え方は、株式のリスクプレミアムが低下しているというものである。現在の株価水準を妥当と考えて、事後的なリスクプレミアムを計算すると、90年代半ば以降低下しており、現在の水準は過去と比べても比較的低い(第2-4-7図)。このリスクプレミアムを低下させている要因は、低インフレ、マーケットの発達に伴う資産価格の変動の縮小、人々の資産選好の変化などであると考えられる。ただし、このリスクプレミアムは歴史的に見ても安定的なものではなく、大幅に変動しうるものであるため、今後も株価が高水準で推移することを意味しているわけではない。株式のリスクプレミアムは民間セクターに投資する際に、投資家がリスクに応じて要求するリターンへの上乗せと考えられるので、株式市場と債券市場を比べることは意味があると考えられる。債券市場における信用リスク(社債と国債の流通利回り格差)は98年秋以降拡大しており、株式のリスクの動向は、この動きと整合的でないことから、株式のリスクプレミアムは過小評価(株価は割高)と見ることができる。割高でないという考え方のもう一つは、いわゆるニューエコノミー論などを踏まえ、企業の収益率が向上していることで株価を説明するものである。株価の水準から、投資家が要求する企業収益の期待成長率の推移を計算してみると実際の企業収益は95年以降伸びが鈍化している一方、収益の期待成長率は95年以降伸び続け、現在は、非常に高い水準となっており、持続可能でない水準であると言えよう(第2-4-8図)。このため、投資家が現在の期待成長率は高過ぎるのではないかと考え始めれば、株価の調整が生じる可能性がある。
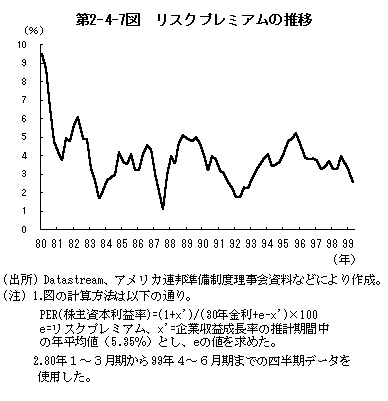
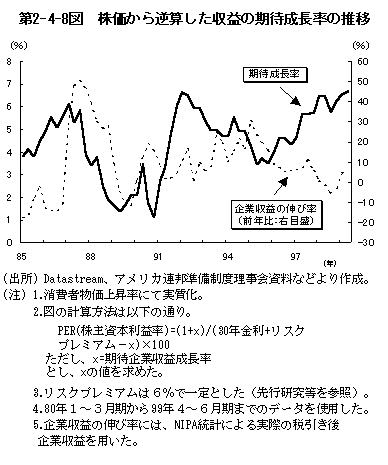
次に、後者の考え方、割高であるものの、調整局面が先延ばしになっているというものについてみてみよう。一つの有力な見方として、当局への信認の厚さが株価を上昇させているというものがある。すなわち、98年秋のように、株価が急落する局面では、金融当局はその実体経済に与える影響を回避するために、利下げに踏み切るので、安心して株を買い続けることができるという見方である。このことはある意味で、投資家の間にモラルハザードが起きているとも考えられる。こうした見方によれば、株価の調整は先延ばしになっているだけであり、かつその間割高感は高まっているということになる。
(実体経済への影響)
次に、株価下落の実体経済に与える影響について考える。株価と実体経済とのつながりを主体別にみると、株価の下落は家計においては金融資産の縮小という形で表れる。企業部門は、資本調達コストの上昇に直面する。この中で経済全体にとって、より影響の大きいと考えられるのは家計部門である。その理由は、家計の金融資産に占める株式のシェアが高まっていること、資産効果等を通じて消費と金融資産の関係が強くなっている可能性のあること、個人消費のGDPに対するシェアが約7割とその大宗を占めていることによる。家計の保有する金融資産に占める株式の割合は、直接保有で95年の18.2%から99年4~6月期の21.1%、間接保有[注2]を含むと27.6%(95年末)から34.6%(98年末)へと拡大している(第2-4-9図)。フローでみると家計は直接保有ベースでは株式を売り越しており、金融資産残高の増加は好調な株価に伴うキャピタル・ゲインによるものである(第2-4-10図)。
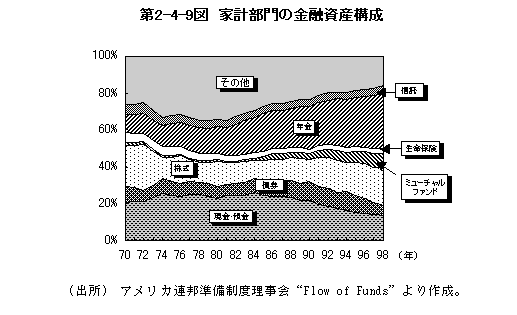
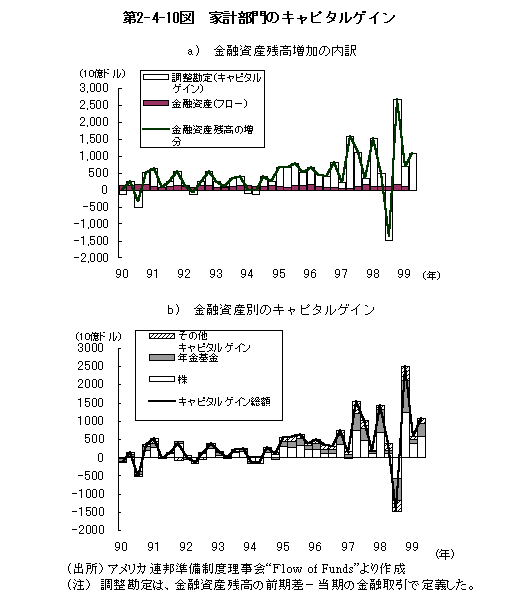
株価の下落がどのような経路を通じて、実体経済に影響を与えるかについては、様々な議論があるが、第1節でみたように、ここでは資産効果を通じた影響を考えることとする。株価がファンダメンタルズを反映した水準まで約40%下落し、その水準が続いたと考えると、直接保有のみを考慮すれば、一年間で個人消費が約1%ポイント低下する可能性があり、この結果、実質GDP成長率は約3/4%ポイント低下する(第2-4-11表)。間接保有まで含めるとそれぞれ、3/2%ポイント、1%ポイント減少すると見込まれる(直接保有の約1.7倍)。実際には、住宅投資にも逆資産効果が考えられ、株価下落は企業の資本調達コストを上昇させるため、経済全体への影響はより大きなものとなる。
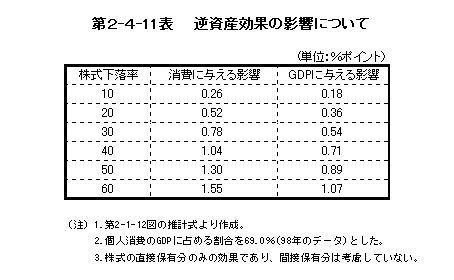
株価が急落した場合には、政策の発動余地があるかどうかによってその後の株価の動向、経済への影響は大きく異なってくるであろう。つまり、目下のところは、低インフレや財政黒字によって、金融政策面及び財政面からの余地(金融緩和、拡張的財政政策)が大きい。しかし、今後インフレ圧力が高まることがあれば、金融政策は、株価下落(金融緩和を要請)とインフレ(金融引締めを要請)の両にらみを余儀なくされ、実際には発動できなくなることも十分考えられる。その点からも後述する今後のインフレの動向には留意すべきである。
(金融市場への影響)
海外の金融市場に与える影響については、主に株式市場について見るべきであろう。各国の株価指数を用いて単純な相関関係を計算すれば、10%のダウの下落は5~11%のG7の株価下落を招く(日本を除く)ことが分かる。この相関は90年代後半に高くなっている(第2-4-12表)(第1章第5節参照)。また、回復しつつある日本やアジアの株式市場などに与える影響も懸念される。他方、米国内の金融市場へ与える影響についてみると、海外資金を含め安全資産への逃避という形で米国の債券を購入するため、金利の低下が生じる可能性がある。
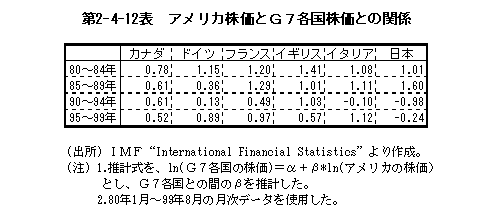
2 低下が続く家計貯蓄率[注3]
90年代に入り、家計部門においては、貯蓄率がほぼ一貫して低下し続け、データが遡及可能な59年以来では最も低い水準となっている(NIPA:National Income and Product Accounts統計ベース:99年7~9月期2.1%)。このような低水準の家計貯蓄率は、個人消費の持続性に対する懸念をもたらしている。過去においては、80~90年代にかけての日本、フィンランド、スウェーデン、イギリスなどでは、資産価格の高騰とともに、家計部門の貯蓄率の低下が観察されたが、その後、資産価格の急落とともに貯蓄率が大幅に上昇(消費性向が大幅に低下)し、消費が大幅に減退した。
(貯蓄率低下の要因)
この家計貯蓄率の大幅な低下の背景には、先に述べた株価の高騰による家計部門における資産効果の影響、失業率の低下と将来の期待所得の向上、また、これらを反映したコンフィデンスの高まりなどが挙げられる。その他にも金利(政策金利)や物価の低下、医療費負担等の増大による支出の増加、財政黒字を反映した将来減税期待からの消費拡大などが指摘されている。また、統計上の問題も指摘されている[注4]。しかしながら、なんといっても最も大きな影響を及ぼしているのは、株価高騰による資産効果である。金融資産/可処分所得の比率と貯蓄率との間には強い相関があるが、貯蓄率の推計を行うと、金融資産の増加(株価上昇の影響が大きい)が、90年代における貯蓄率低下の最大の要因となっている(第2-4-13図)。
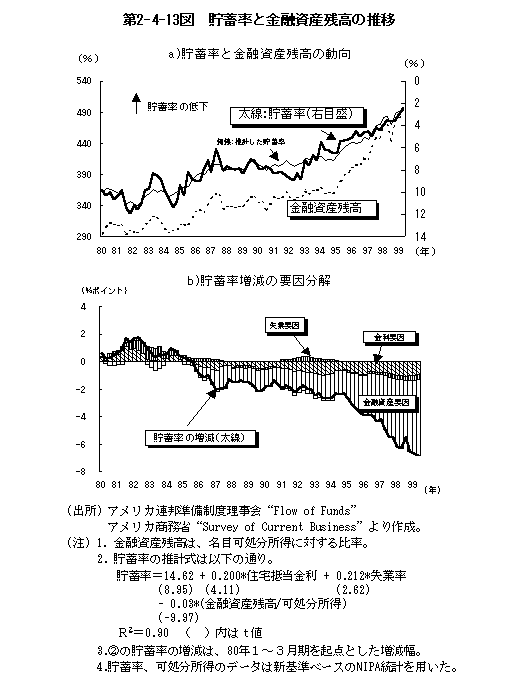
ところで、家計貯蓄率の低下は、住宅や自動車などの耐久財資産の購入を反映しており、これらの耐久財ストックの増加分を考慮すれば、家計の貯蓄率は実質的に低下していないといった見方もある。そこで、耐久財資産の購入を考慮した家計貯蓄率を計算してみると、NIPA統計の貯蓄率と同様に、90年代は低下していることが分かる。つまり、住宅や自動車などの実物資産購入額が90年代に著しく増加したために家計貯蓄率が低下したわけではなく、上記の見方は適切ではない(第2-4-14図)。
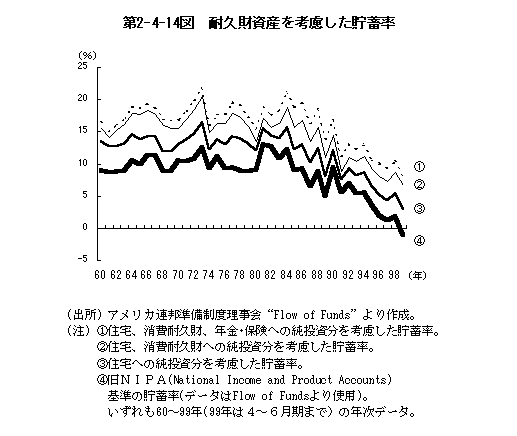
金融資産だけでなく住宅価格の上昇が実物面においても家計に資産効果をもたらしている可能性はある。住宅価格が上昇したことで、住宅所有者の資産価値が高まったことが個人消費の高まりの背景にあるとも考えられる。例えば、住宅資産を担保とした家計の借入れは住宅投資が活況を呈した96年以降大幅に増加している(第2-4-15図)。非金融資産を組み入れた消費関数を推計すると、不動産の方が資産効果の係数が小さく、不動産価格の上昇も小さかったことから資産効果は金融資産のそれに比べて小さい(第2-4-16図)。このように実物資産の積み上がりは貯蓄率の低下にそれほど大きく寄与していないと考えられる。
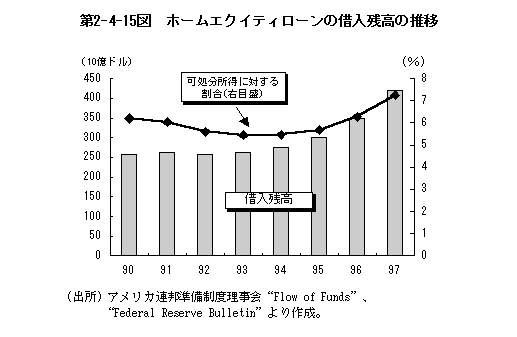
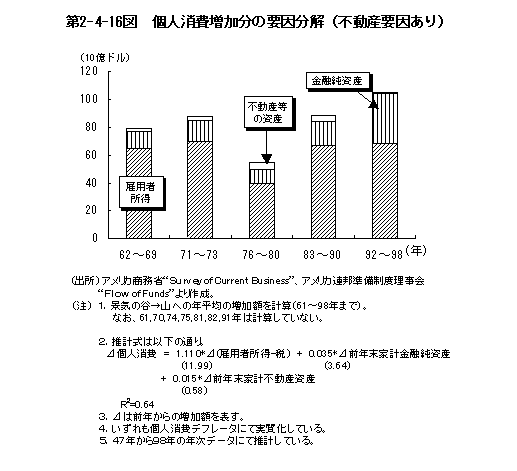
(低水準の家計貯蓄率の問題点)
低水準の貯蓄率は、前述のように、株高による資産効果による消費性向の上昇を表しているため、直接的には、株価が下落した場合には、消費性向が低下し、消費が所得の伸び以下に弱くなることを意味している。また、株価の上昇が続かない限り、低水準の貯蓄率は持続可能ではない。株価が横ばいで推移する限りにおいては、金融資産の対可処分所得比は低下傾向となると考えれられるため、消費は所得の伸びに収斂していくこととなろう。
ストック面からみると、家計の金融資産が株式によるキャピタル・ゲインで膨張していることもあり、付加的な資産取得は少ないものの、資産は増加している。他方、負債も増加しているが、これまでのところ資産/負債比率は上昇傾向にある。仮に、株価の下落があれば、この比率は急速に低下し、家計のバランスシートが悪化するため、この点からも、消費の伸びが抑制される可能性が高い(第2-4-17表)。
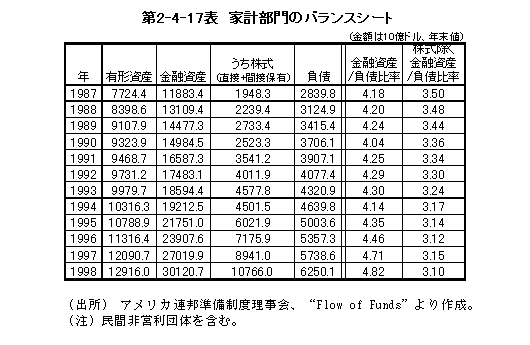
3 経常収支赤字の拡大
株高を背景とした旺盛な消費と投資により経常収支の赤字は非常に高い水準となっている。98年の経常収支赤字は約2,206億ドル(名目GDP比2.5%)と高水準にあり、99年も引き続き経常収支赤字の拡大傾向が続いている。99年4~6月期には807億ドル(同3.5%)となり、名目GDP比でみれば、86年10~12月期の3.5%と同じ過去最高となっている(以上新基準ベースのNIPA統計による)。以下では、この赤字拡大の背景とその影響について整理する。
(経常収支赤字の特徴と要因)
経常収支赤字は80年代前半にも拡大していたが、80年代と90年代では経常収支赤字に対する国内の部門別貯蓄・投資バランスに大きな相違がみられる。80年代は財政赤字が拡大していた一方で、90年代は財政再建が進んでおり、98年には財政黒字に転じている。90年代には、政府部門が貯蓄投資バランスを改善させているにもかかわらず、民間部門が大幅な投資超過になっていることが経常収支の赤字を生み出している。言い方をかえれば、80年代から90年代にかけて貯蓄不足が政府部門から民間部門に移行したということである。
貿易収支についてみると、輸入と輸出がともに伸びる中で、輸入の増加がより大きいため貿易赤字も拡大している。財別の貿易収支をみると設備や機械といった資本財の輸入が伸びており、従来黒字であった資本財の貿易収支が赤字に転じているのが特徴である(第2-4-18図)。財の輸入および輸出を所得要因と相対価格要因に分けて推計してみた(第2-4-19図)。その結果、長期的にみて、貿易収支の変動を説明する主な要因は、相対価格要因よりも、所得要因であることが分かる。つまり、90年代の貿易赤字拡大の要因も旺盛な内需や海外の需要低迷といった所得要因による面が大きい。ただし、96年以降は輸出、輸入ともに価格要因(ドル高)が高まっている。これは96年後半からドルが各国通貨に対して増価したことによる効果が大きいと思われる。次にサービス収支についてみると、ここ数年黒字の伸びが鈍化している(第2-4-20図)。投資収益収支については、対外債務の積み上がりに伴う利払い増加から、98年以降、赤字となっている。これには、ドル高によってドルベースの受取額が目減りしたことも影響している。
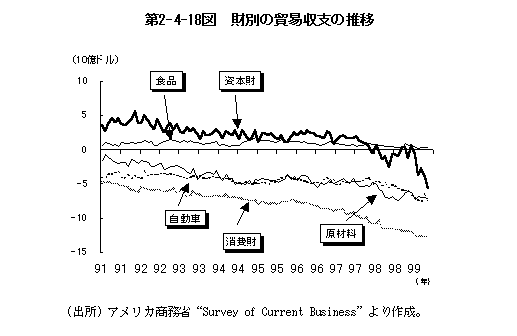
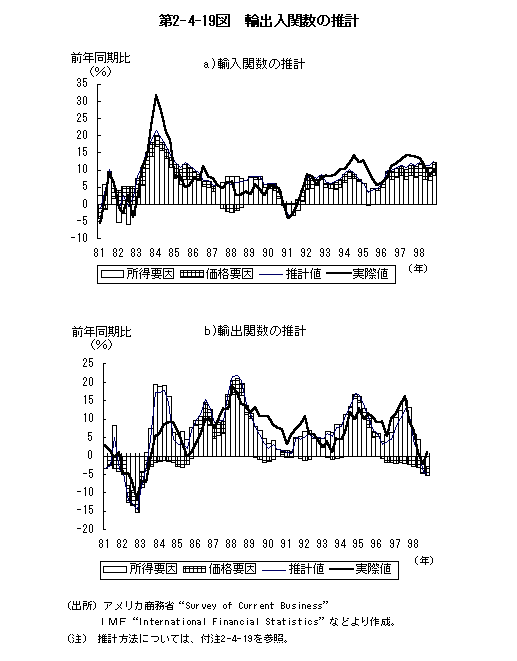
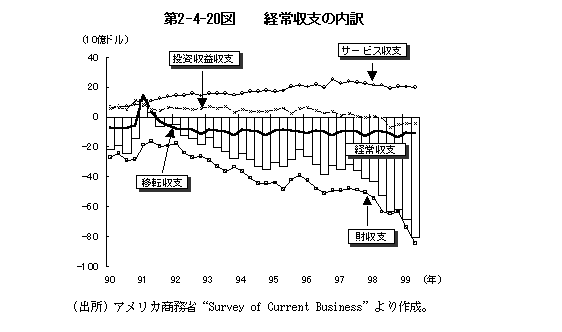
(経常収支赤字の経済に与える影響)
次に、経常収支赤字の問題点について考えてみたい。現在の名目GDP比3%半ばといった大幅な経常収支赤字は、そもそも中長期的に維持可能でないという基本的問題があるが、それ以外に、より短期的に考えても、a)ドル安圧力を生み出し、ドルが実際に減価する、あるいはそうした懸念が生ずる結果、海外からの資金流入が減少する可能性があること、b)保護主義的な圧力が高まること、という問題点がある。
前者については、ドル安がきっかけとなって、国内金利上昇圧力が高まり、さらには、株価の下落を誘発する可能性もある。また、ドル高はこれまで、輸入物価上昇率を抑制し、低インフレをもたらしていたが、この力も逆方向に作用する可能性がある。
二つ目の点についてみると、保護主義の圧力も貿易赤字の拡大を背景に強まっており、98年には鉄鋼業界において日本やロシアなどに対してアンチ・ダンピング提訴が行われた。
ただし、日本や欧州、アジア諸国をはじめとして世界の多くの国・地域が比較的大きなデフレギャップを抱える中で、好調なアメリカ経済が、各国からの輸入を増加させたため、世界経済を下支えしてきたという側面もある。
(今後の動向)
最後に今後の動向について考えてみたい。大宗を占める貿易収支の動向を考えると、所得要因が輸出入に与える影響が大きいことから、欧州やアジア等の海外経済が回復し、アメリカ経済が減速局面に入るとすれば、輸出増、輸入減により経常赤字は縮小していくと考えられる。価格要因についてみると、ドル安は赤字を縮小させる方向に働くが、その効果は即効性が薄く(Jカーブ効果)、また、インフレ懸念を高めたり、株価の下落を誘引する可能性があるなど、負の効果が大きい点に留意する必要がある。
4 インフレ懸念の高まり
高成長率での景気拡大が続き、失業率が30年ぶりの低水準となっていることなどから、インフレ懸念が高まっている。インフレは、個人消費や企業投資に直接マイナスの影響を及ぼすばかりか、長期金利の上昇や株価の下落、為替の変動を引き起こし、消費や投資の振幅を大きくする可能性もある。また、インフレの顕在化の程度とスピードが大きい場合、大幅な金融引締めが金利上昇を招き、景気後退を余儀なくする可能性も高い。現時点のアメリカ経済において懸念されるインフレ圧力は、第1章第2節及び第2章第2節でみたように、a)景気の過熱感からくる労働需給の逼迫、b)原油価格の反騰やドル安、海外経済の好転による需要増などである。
前者についてみると、NAIRU(Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment:インフレを加速させない失業率)は低下している可能性が高いものの、現在の失業率はそのNAIRUをも下回っている可能性が高い。一方で、製造業の生産が海外部門の需要拡大により増加しており、このことが雇用の増加に拍車をかける可能性がある。これまでは、リストラを進めてきた製造業の雇用減をサービス部門の雇用吸収で補ってきたが、現在の逼迫した労働市場からはむしろ賃金上昇が顕在化する可能性が高いと思われる。
海外市場の動向もまた注意すべき要因である。特に、a)石油価格の反騰をはじめとする一次産品価格の上昇、b)海外経済の好転による需要増、c)ドル安などがインフレ要因として考えられる。最近の国際商品価格の動向をみると、まだ一部に不安定な要素はあるものの、概ね価格は底入れしつつあると考えられる。日本やアジア、欧州の景気回復は、国際商品などの需要を高めて、更なるインフレ圧力を生む。
こうしたことから、今後の物価の動向には十分注意する必要がある。物価の高騰は、強度の金融引締めを余儀なくし、景気拡大に終止符を打つことになろう。また、株価の急落が生じた場合、通常であれば、金融緩和によって、実体経済へのショックを和らげることが可能であるが、物価が高騰しているような状況下では、そのような対応がとれないことから、経済のハードランディングを招くことになろう。
- 注1 98年夏に大幅下落する前の株価水準は、収益還元モデルから推計される価格からみて高いか低いか一概に言えない(第2-4-1~6図を参照)。
- 注2 間接保有とは、ミューチャルファンド、生命保険、年金、信託などを通じた株式の保有をいう。
- 注3 本項での記述は新基準ベースのNIPA統計による。
- 注4 所得から控除される税金にはキャピタルゲイン課税が含まれている等の問題がある。
| 第1章 世界経済の現況 | 第2章 アメリカ経済の長期拡大の要因と課題 | 第3章 物価安定下の世界経済 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 |
| 概観 | アメリカ | 欧州 | アジア | 金融・商品 | 通貨・金融システム | 特徴 | 要因 | 生産性 | 課題 | 現状 | 要因 | 特徴 | 金融政策 |

