第1章 第3節 ユーロ誕生を迎えたヨーロッパ経済
| 第1章 世界経済の現況 | 第2章 アメリカ経済の長期拡大の要因と課題 | 第3章 物価安定下の世界経済 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 |
| 概観 | アメリカ | 欧州 | アジア | 金融・商品 | 通貨・金融システム | 特徴 | 要因 | 生産性 | 課題 | 現状 | 要因 | 特徴 | 金融政策 |
第3節 ユーロ誕生を迎えたヨーロッパ経済
1 西ヨーロッパ:EUの深化と拡大に向けた取組
(経済通貨統合の前進)
1999年1月1日、EU加盟国のうち11カ国において単一通貨「ユーロ」が誕生し、EU統合の深化が更に一歩前進した。EU統合の深化とは、1993年に発効した欧州連合条約(マーストリヒト条約)において目標とされている、a)経済通貨統合、b)共通外交・安全保障政策、c)司法・内務協力という、三つの同盟・協力関係の深化をいう。この最初のステップとして90年7月に取組の始まった経済通貨統合(EMU:Economic and Monetary Union)が、99年1月から最終段階に入り、EU加盟国のうち11か国では、単一通貨「ユーロ(euro)」が導入された(第1-3-1表)。99年から通貨統合に参加した11か国(ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、オランダ、ベルギー、オーストリア、フィンランド、ポルトガル、アイルランド、及びルクセンブルク)は総称してユーロ圏と呼ばれる(英語では一般的に、Euro Zone, Euro Land,Euro Area等と表記される)。ユーロ圏の経済規模をみると、人口が約2.9億人(97年)、名目GDP規模が約6.5兆ドル(98年)であり、日本(約1.3億人、約3.7兆ドル)を上回り、アメリカ(約2.7億人、約8.5兆ドル)と比肩する一大通貨圏が誕生した。

ユーロの導入は、欧州委員会の下、3段階で進められており、98年の通貨統合参加国決定等のA段階を経て、99年1月からのB段階では、現金を伴わない支払いについては各国の通貨とユーロのいずれでも使用可能となっている。ユーロの紙幣とコインが実際に流通し始めるのは2002年1月からであり(C段階)、各国の通貨は、遅くとも2002年6月を最終期限として、法定通貨(Legal Tender)としての効力を失うこととなる。
(マーストリヒト条約からアムステルダム条約へ)
1999年5月1日、EU統合の更なる深化を示す「アムステルダム条約」が発効した。同条約は、マーストリヒト条約を改訂し、経済分野に関する事項、共通外交・安全保障政策、司法・内務協力の3つの柱を強化すると同時に、雇用政策などを条項として新たに明示したものであり、1997年10月に調印され、各国が批准手続を進めていた。
また、EUの財政改革やその他の分野における構造改革について、中・東欧諸国への加盟国拡大を視野にいれながら、2006年までに解決すべき課題として欧州委員会が提案した「アジェンダ2000」が、99年3月のベルリン欧州理事会で議決された。
以下では、まず(1)ユーロ圏全体の1)経済の動向を概観した後、2)ユーロ導入後の課題について考察し、最後に、3)通貨統合以外の今後のEUの課題について概観する。その後、(2)西ヨーロッパ諸国の経済動向を主要各国ごとに概観する。
(1) EU:ユーロ導入後の課題と取組
1)ユーロ圏経済の動向
ユーロ圏経済の動向をみると、個人消費及び固定投資の拡大をけん引役として、98年前半まで景気拡大を続けた。しかし98年後半以降、各国通貨の大幅な増価や、アジア通貨危機がロシアへ波及したことなどにより、外需が大幅に減少し、景気拡大が鈍化した。しかし、99年1月の発足後、ユーロが総じて減価したことや、アジアの景気の回復、ラテンアメリカ及びロシアにおける金融危機の収拾により外需が回復し、個人消費及び固定投資の好調が続いたことから、景気の減速は一時的なもので収まり、99年4~6月期頃から改善の動きが強まっている(実質GDP成長率は、98年前年比2.7%、99年1~3月期前期比0.4%、4~6月期同0.5%:第1-3-2図a)。
項目別の動向をみると、98年後半の国際経済情勢の悪化と域内諸国の通貨高によって最も大きな打撃を受けたのが輸出と生産の動向であった。輸出は、特にアジアなど新興市場向けの輸出が減少したが、98年10~12月期以降減少傾向に歯止めがかかっている(第1-3-2図b)。鉱工業生産は、景気回復の始まった97年春から98年夏まで、平均して前年同期比5%以上の伸び率で推移したが、99年1~3月期には同▲0.2%、4~6月期同▲0.5%と悪化した。同時に、製造業景況感(D.I.)も、98年8月以降、再びマイナスとなり、悪化を続けたものの、99年4月以降低水準ながらも改善がみられる。生産面の減速の一方で、個人消費は拡大を続けており、総じて消費者のコンフィデンスは良好である(第1-3-2図c)。この要因としては、失業率の低下等、雇用情勢の改善があげられる。
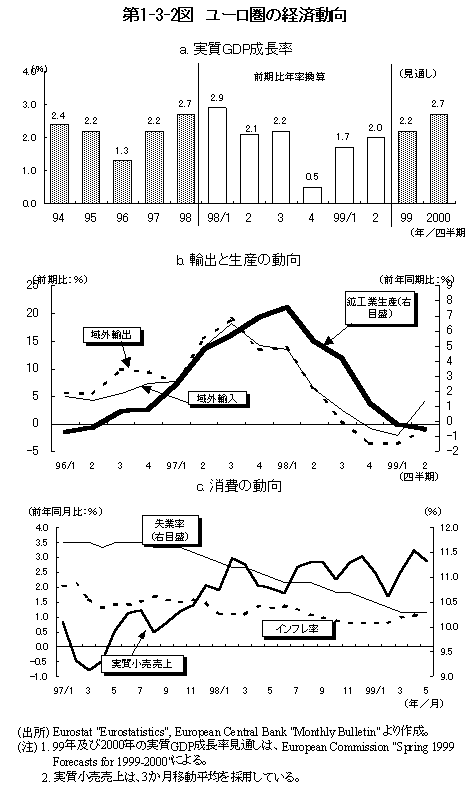
98年までの景気拡大と失業率低下にもかかわらず、ここ2~3年においては、世界的な低インフレを受け、ユーロ圏でもインフレ率は低めに推移した。こうしたなか、99年4月、欧州中央銀行(ECB:European Central Bank)は、減速傾向の景気動向をふまえ、中期的にみて物価の上昇圧力がみられないことから、単一金融政策開始後初めてとなる政策金利の引下げを実施した。この利下げにより、ユーロ圏の景気に対するマインドが上向き、結果として景気回復が早められたものと考えられる。
2)ユーロ導入後の課題
(ユーロシステムの金融政策)
マーストリヒト条約の規定に基づく欧州中央銀行制度(ESCB:European System of Central Banks)は、物価の安定を第一の目標としている。ESCBは、98年6月に設立されたECBとEU加盟15か国の中央銀行から構成され、このうち、ECBとユーロ参加11か国の中央銀行をユーロシステムと呼ぶ。ユーロシステムは、ユーロ圏内の金融政策の決定、為替政策の運営等を任務としている。ESCBは、98年10月のECB政策委員会において、ESCBの第一義的な目的である「物価の安定」を、ユーロ圏全体の統一的な消費者物価指数(HICP)の上昇率が2%を下回る(below 2%)ことと定義した。あわせて、物価の安定を維持するための対応として、ユーロ圏全体の通貨供給量と、広範な経済データをベースにした物価見通しという2つの要素を重視することとした。同年12月には、ユーロ圏全体の通貨供給量の参照値をM3の前年比4 1/2%としたうえで、ESCBはM3の3か月移動平均に基づいてこの参照値に対して金融状況を注視することを決定し、99年12月には再度その参照値を見直すこととした。
これらを参照しつつ、ECBの金利の変更等は、原則として月に2回開催されるECB政策委員会において、委員17名による単純多数決によって決定されている。
ユーロシステムの具体的な金融政策手段は、主に公開市場操作であり、2週間物の債券レポが大きな役割を演ずる。また、各国中央銀行と金融機関との間でオーバーナイトでの貸出/預金を行う常設ファシリティー(Standing Facilities)も主要金融政策手段として位置づけられている。
(長期金利の各国ごとの乖離)
単一金融政策が開始され、各国の政策金利がECBの政策金利に統一されたことにより、長期金利の各国間の格差も縮小するとの見方も生じたが、現状では依然として格差が残っている。その理由としては主に、
- a) 信用に対するリスクプレミアム:累積債務残高の違い等から、各国国債の格付けが異なり、これが金利差となって現れるもの(第1-3-3図a)
- b) 流動性に対するリスクプレミアム:格付けが同じであっても、市場における、取引量や取引コストなど、取引の行いやすさにおいて各国国債間に差があれば、これが金利差となって現れるもの(第1-3-3図b)が考えられる。今後国債市場が統合に向かうとすれば、信用に対するリスクプレミアムは残るものの、流動性に対するリスクプレミアムは小さくなっていくと考えられる。
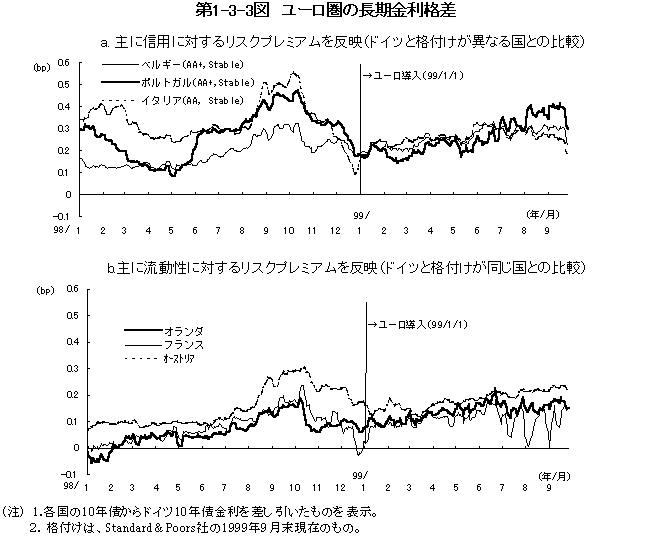
(ユーロ減価傾向の原因)
ユーロは、99年1月に導入されて以降、対ドルレートで減価を続け、発足当時の対ドルレート(1ユーロ=1.17ドル台)から、半年間で16%程度減価し、7月初めには、1ユーロ=1.01ドル台となった。こうした減価の一部は98年末におけるユーロ圏通貨高の反動とみることも可能である。すなわち、発足当初のレートがそもそも高すぎたのではないかとの見方である。通貨統合前のユーロの対ドルレートをみると(第1-3-4図)、98年秋頃から急激にユーロが増価していたことがわかるが、これは「強いユーロ」への期待の現われであったといえる。
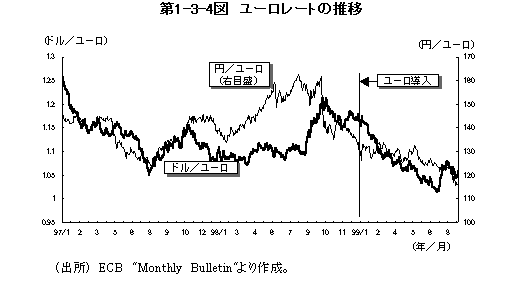
このようにユーロが減価した要因として、アメリカとの景況格差やコソボ紛争の長期化のほか、ユーロ圏経済運営の構造的問題点が挙げられる。
アメリカとユーロ圏(EMU第3段階移行11か国)の実質GDP成長率(前期比年率)をみると、アメリカは98年10~12月期5.9%、99年1~3月期3.7%、4~6月期1.9%であるのに対し、ユーロ圏では10~12月期0.5%、1~3月期1.7%、4~6月期2.0%(経済企画庁推計値)となっている(第1-3-5図)。こうした景況格差によって両地域の間の金利格差が今後も持続ないし拡大するとの見方が、ユーロ安を招いたとみられる。
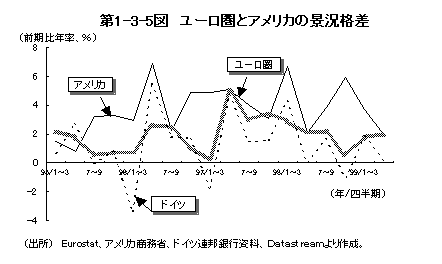
また、99年3月以降、コソボ紛争が長期化したことも減価の要因となった。6月のコソボ和平成立後もユーロ安はしばらく継続したが、ユーロ圏の景気に回復の動きがみられるようになった7月には、減価傾向は一応終息した。
(強い安定したユーロを実現するための課題)
ユーロの短期的な強弱は、ユーロ圏とその他地域との景況格差等に左右されるが、より中長期的な動向はユーロ圏の構造的な問題に対する取組に大きく依存する。
ユーロ参加国は、通貨統合によって為替変動リスクの消滅という大きな利益を獲得する一方で、国家の主権の一部である金融政策を放棄するというコストを容認しなければならない。それは景気やインフレなどの経済変動に対する一つの調整手段を失うことを意味する。したがって、例えば、ユーロ参加国が何らかの外生的な経済ショックを共通に受けた場合、その結果生じる価格や産出量の変動を調整するために一元的金融政策を採れば、参加国の経済構造に差異が残る状況では、その影響に格差が生じることとなる。
そこで、景気が相対的に悪化した国が財政政策を拡張的に運用することでショックを緩和しようとした場合には財政赤字の増大は免れない。しかし、通貨統合参加国は、「安定と成長の協定(Stability and Growth Pact)」によって、99年以降、毎年の財政赤字を名目GDP比3%以内に抑制しなければならず、容易な財政赤字の増大は許容されない。また、景気の悪化した国から良好な国への労働力の移動による調整も、言語的、文化的、社会的相違を考えると困難と言わざるを得ない。ショックへの対応手段として財政政策の発動及び労働力の移動に限度があるとすれば、労働市場の柔軟化、特に実質賃金の柔軟化、及び、各国間の経済格差を是正するためのEU域内の財政支援システム強化などが重要となってくる。以下では、こうした観点から、雇用及び財政政策に関する最近のEUの取組を紹介する。
(EUにおける雇用への取組)
99年6月、ケルンで開催されたEU首脳会議において「欧州雇用協定」(European Employment Pact)が採択されたが、これはEUにおける雇用への取組の第3プロセスと位置付けられ、「ケルン・プロセス」と呼ばれる。
EUにおける雇用への取組は、97年11月のルクセンブルク臨時首脳会議から本格化し、a)雇用可能性(Employability)の向上(職業能力を労働者自身が磨くことのできる制度の整備等)、b)起業支援(Entrepreneurship、起業のための行政手続の簡素化、税負担軽減、ベンチャーキャピタル市場の拡大など)、c)経済的・社会的な環境変化への適応能力の強化(adaptability、労働時間や賃金等の柔軟化のための既存システムの見直し等)、d)雇用機会の平等化の推進(equal opportunity)の4つの柱を掲げ、これらを明記した雇用ガイドラインを作成することとし、また、各国には毎年、行動計画を提出させることとした。これが第1のプロセス(「ルクセンブルク・プロセス」)と呼ばれる。第2のプロセスは、ルクセンブルク会合の半年後に決定された、より政治的な取組を定めたもので、財、サービス、資本に関するより包括的な構造改革の必要性を説いている。これが、「カーディフ・プロセス」と呼ばれる。
「ケルン・プロセス」における「欧州雇用協定」では、欧州の経済成長と雇用を強化するために、雇用関係者の意見交換を充実させ、信頼を醸成することを目的としている。
(EUにおける財政政策)
EUでは、欧州中央銀行制度(ESCB)のもと、欧州中央銀行(ECB)によって一元的な金融政策がとられている一方、財政政策に関する主権は各国が有している。しかし、各国は「安定と成長の協定」により、財政赤字を名目GDP比3%以内に抑制する義務を負っていると同時に、自国の財政運営に関する中期的目標を定めた「安定プログラム」を策定し、欧州委員会に提出しなければならない。このように、各国は独自に財政政策を運営する主権を有しているが、それは「安定と成長の協定」のもと、一定の制約を受けている。
一方、EU全体における経済的な基盤の安定のために、EUには、社会的・経済的な地域間格差の縮小を目的として、構造・結束基金が設置されている。このうち、構造基金は結束を達成するための加盟各国の地域政策を補完するためのものであり、結束基金は、一人当たりGNPがEU平均の90%に満たない加盟国の交通・環境インフラ整備を援助するためのものである。99年3月に議決された「アジェンダ2000」は、EUの財政構造改革に関する広範な合意となっており、より効率的な支援を可能とするために、結束基金等の補助金の枠組みを見直すことが盛り込まれている。
(ユーロの国際通貨化)
ユーロは現在、ユーロ圏内における決済通貨として限定的に機能しているにすぎないが、今後ドルと並ぶような、いわゆる国際通貨となり得るであろうか。国際通貨を考える場合、その通貨に対して通貨をペッグあるいは安定化させる公的機関が多いかどうか(基準通貨)、あるいは、その通貨が国際流動性を保有しておく準備資産としての機能(準備通貨)を有するか、また、民間取引において、外国為替市場における媒介通貨としての機能や国際取引の単位としての機能(契約・表示通貨)、国際取引の支払手段としての機能(取引・決済通貨)を有するかなどの要素が重要となる。
ユーロが十分安定し、信認の高い通貨となり、これらの機能を有する通貨として機能するようになれば、単にEU内のローカル・カレンシーでなく、米ドルと並ぶ国際通貨となる可能性がある。
ユーロ導入は、資本取引の活発化など各種の取引を活性化させることにより、金融資本市場の効率化を招き、また、中長期的な投資活動を促進し、企業部門の競争力の向上をもたらす。さらに、ユーロ圏内における為替変動リスクが消滅することによって、取引コスト低下や民間のポートフォリオ調整、欧州投資家の圏内投資の活発化、圏外投資家のユーロ建て債の発行増加といった効果が考えられる。実際、ユーロ建て債の発行は顕著な伸びを示しており、銀行貸出に占めるユーロ建ての割合がドル建てに近づくなど、金融資本市場におけるユーロの浸透は急速に進行している(第1章第5節参照)。
(EU域内における価格差)
2002年のユーロ紙幣・硬貨の流通までの移行期間においては、ユーロへの切り替え速度は、「義務なし、妨げなし(No Compulsion, No Prohibition)」の原則の下、各国の自由裁量となっている。商品価格の表示についても同様に、移行期間中を拘束するEUレベルでの規定はない。しかしながら、既にユーロ圏での二重価格表示は広く浸透してきている。
92年から始まった欧州単一市場の形成や二重価格表示は、EU域内の価格比較を容易にし、域内の財の価格差は縮小に向かうものと予想される。しかし、日本貿易振興会が行った価格調査[注1]によれば、99年9月現在、商品によっては2~5倍の価格差がある(第1-3-6図)。また、欧州委員会による、EU各国における自動車の小売価格(税抜き)を比較した調査では、車種によって価格差が約30~40%になるものも多く、その価格差は98年11月の調査から縮小していないことも指摘されている[注2]。
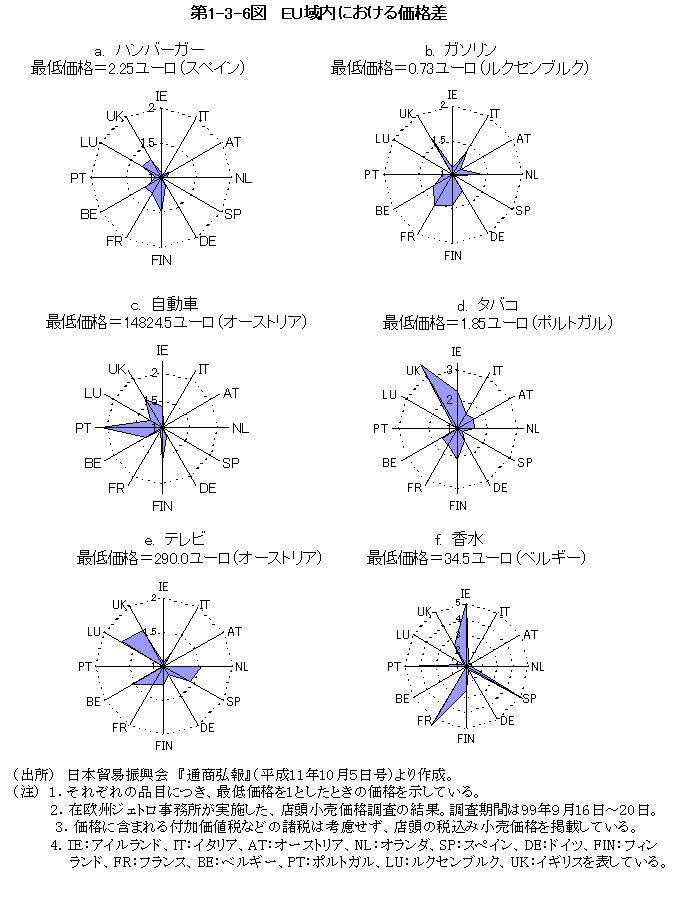
域内の価格差を生む大きな要因として、税制や規制といった制度的なハーモナイゼーションの未整備が指摘できる。付加価値税(VAT)の税率や諸手続の相違などが、他の域内国に企業が参入する際の障壁となり、価格差が残存する一因となっている。こうした法人税制の調和に関する諸問題の重要性は、EU域内でも認識されており、現在検討が進んでいる(後述の「税制のコーディネーション」参照)。欧州委員会が98年に行った、域内の4,000社以上の企業に対する調査[注3]では、域内市場で国境を越えて取引を行う際に直面する障害として、VAT税制の相違(28%)や検査、認証手続(34%)を挙げるものも多く見られた。しかし、最も回答が多かったのは、「各国市場の特性に合わせて製品を互換するためのコスト」(41%)であり、国民の嗜好による製品の差別化のみならず、パッケージなどの仕様を変更するコストが障壁となっていることがわかる。
ユーロの導入は、ユーロという共通通貨による価格表示が行われることで域内各国において価格の比較が容易になることから、取引相手や消費者からの価格の下方修正圧力を生み、価格差を縮小させることに寄与するであろう。
3)通貨統合以外のEUの課題
(税制のコーディネーション)
単一通貨の誕生によって、企業の立地を選択する際には、もはや為替リスクは無関係となる。代わって各国の法人税制や労働コスト、その他の立地上のコストが企業にとって重要となる。それら企業立地に際してのコスト計算において、とりわけ、直接税あるいは社会保障賦課金のあり方は極めて重要である。
したがって、各国政府が企業の立地を促進するために、税率の引下げ競争を行ったり、補助金の支給競争を行ったりする可能性が高い。国の歳入源として税収は必要であるが、他の諸国が直接税の税率を引き下げれば、雇用等を配慮して、自国だけが高いというわけにはいかなくなる。企業の新規立地に支障が生じるだけでなく、既存企業の流出さえ起こるからである。
こうして「有害な税競争(harmful tax competition)」の排除がEU各国の焦眉の課題となった。これまで、法人税などの直接税や社会保障賦課金などについては、EU構成各国の主権事項として、EU内で議論されることは少なかった。しかし、共通通貨ユーロ誕生を控えた96年4月、欧州委員会主導のもと、「有害な税競争」への対処策を非公式蔵相会議において初めて議論し、97年12月、EU15蔵相/経済相会議において、「企業税制に関する行動規範(Code of Conduct for Business Taxation)」など直接税に関して初めての合意を得るに至った。具体的には、企業課税、利子課税、企業間のクロスボーダーの利子・配当支払への源泉課税の三点を焦点として、検討グループを設置して議論を進めていくこととされた。これらに関して、99年6月のケルン欧州首脳会議においても、企業課税、利子課税への源泉課税等のほか、エネルギー課税に関する検討の必要性に言及するなど、税制に関する条項が盛り込まれ、現在検討が進んでいる(第1-3-7表)。
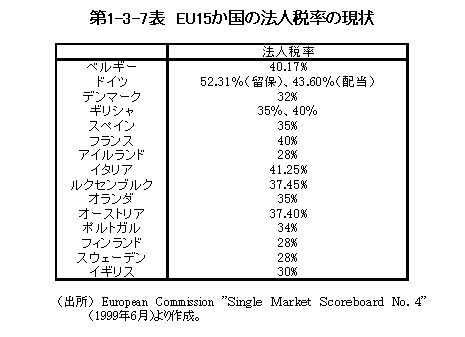
(2) ドイツ:コール政権からシュレーダー政権へ
ドイツでは、98年央まで景気拡大がみられたが、外需の低迷等により99年前半には一時的に減速したものの、後半に入り生産面での明るい動きを中心に、緩やかに改善してきている(実質GDP成長率は、98年1~6月期前期比年率2.5%、7~12月期同0.5%、99年1~6月期同0.7%、第1-3-8図)。
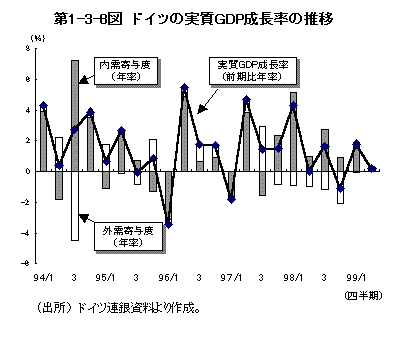
98年後半以降、アジア通貨危機のロシアへの波及などによって外需が落ち込み、98年の実質GDP成長率に対する外需寄与度はマイナスとなった。99年に入り、アジアをはじめとする世界経済の回復傾向とともに、ユーロの減価もあり、外需は回復し始めている。
しかし、98年後半以降、ドイツでは大幅に在庫が積み上がり、これが99年以降の生産の回復を遅らせる要因のひとつとなった(鉱工業生産は、98年10~12月期前期比1.7%減、99年1~3月期同0.3%増、4~6月期同0.4%増)。
一方、雇用情勢の改善が続いていること、また99年初の労使交渉が大幅な賃金上昇で妥結したことから、個人消費は増加していたが、エネルギー課税強化などをうけて、春以降、低調に推移している。また、建設投資は、98年末には寒波によって停滞したが、99年に入り、好天に恵まれたことから大幅に増加、建設業コンフィデンスも改善している。物価をみても、消費者物価上昇率は99年9月現在で前年同月比0.7%と安定している。
(シュレーダー政権の経済政策)
98年10月、社会民主党と緑の党の連立によるシュレーダー政権が誕生し、雇用問題と税制改革を重要課題として掲げ、雇用機会創出に向けた対話や雇用行動計画の策定などの施策を講じている。また、99年6月には、「ドイツの再生―雇用、成長および社会的安定を確保するための将来計画」を閣議決定し、雇用創出、累積債務の縮減と歳出削減、税制改正、年金改革、行政改革に重点的に取り組んでいくことを表明した。
a) 緊縮路線の強調
シュレーダー政権は、ラフォンテーヌ蔵相のもと、98年12月、税制改革の第一段階の一部として、所得税率の引下げと前政権の社会保障削減政策の撤回など低所得者層に手厚い税制へと転換を図った。99年1月に閣議決定された99年度(99年1月~99年12月)予算案は、予算の第一の目標を雇用創出と財政健全化に置くこととした[注4]。また、法人税制に関して、ラフォンテーヌ蔵相は法人・所得税率を引き下げる一方、租税特別措置の見直しによる課税ベースの拡大及び4月からのエネルギー課税の強化を図ることとした。これは企業にとっては実質的には課税強化となる内容であるとして、産業界から猛反発を招き、3月のラフォンテーヌ蔵相辞任の一因となった。
アイヘル新蔵相のもと6月に閣議決定された「ドイツの再生―雇用、成長および社会的安定を確保するための将来計画」及び2000年度予算案では、雇用創出、累積債務の縮減、社会保障の抑制等による歳出削減、エネルギー課税の強化などの税制改正、年金改革、行政改革に重点的に取り組んでいくことを表明し、緊縮路線を強調した(第1-3-9表)。2000年度予算案は、社会保障費の大幅削減などによる約300億マルク(約1.9兆円)の歳出削減を目標としている。8月25日には、2000年度予算案の若干の修正を含む年金改革法案等が閣議決定された。同法案では、年金改革など社会保障費の削減を中心に2000年度予算で約304億マルクの削減を目標としている。しかし、9月以降実施された地方選では、これらの財政再建案が重要な争点となったが、政府与党が惨敗を続けていることから、法案の成立には予断を許さない状況といえる。

b) シュレーダー政権の労働市場改革
ドイツでは失業率は低下傾向にあるものの依然として10%強の水準で推移している。このためコール政権においても、中小企業の創出など投資環境の改善や社会保障負担の軽減などを中心とした労働市場政策に取り組んできた。
98年10月に誕生したシュレーダー政権は、失業対策を重要課題のひとつに掲げ、98年12月、雇用創出を推進し労働市場の柔軟化について議論する場として、行政、企業、労働組合の三者からなる「雇用のための同盟」を2年半ぶりに開催した。また、99年1月には、10万人の若年失業者に対して職業訓練機会等を提供するプログラムを策定するとともに、男女の雇用機会の均等を促進すること等を柱とした行動計画を策定し欧州委員会に報告した。さらに、前述のドイツ再生プログラムにおいても雇用の安定と新規雇用創出を目標とし、職業訓練の充実を図ることとするなど、ドイツにおける失業対策の枠組みは、従来の構造改革中心の政策のみでなく、政府による直接雇用を重視するようになっている(第1-3-10図)。

ドイツ政府の公表する失業率では、職業訓練過程にある者や短期労働者は失業者ではなく就業者として扱われている。これらの"隠れた失業者(hidden unemployment)[注5]"を失業者に含めて失業率を試算(便宜上「広義の失業率」とよぶ)すると、「広義の失業率」は、政府公表の失業率を大幅に上回った水準で推移していることがわかる(第1-3-11図)。失業者等に対する職業訓練を強化することで労働者の能力を向上させることができても、投資環境の改善や産業の活性化なくしては、"隠れた失業者"を吸収できず、労働市場の構造改革には結実しないことに注意する必要がある。
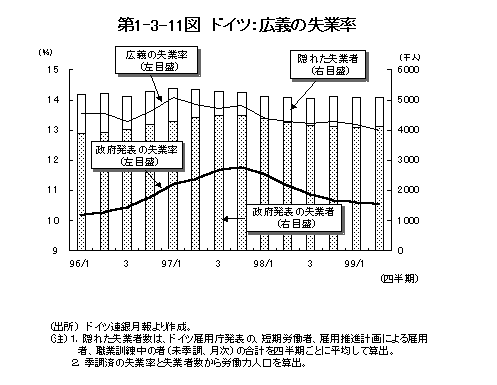
(3) フランス:週35時間労働への移行
フランス経済は、96年には実質GDP成長率が1.1%と低成長にとどまったが、97年にはフラン安の進展、アメリカ、イギリスの景気拡大などから外需主導の回復・拡大局面に入った。その後、個人消費、設備投資が増加するなど、内需主導で景気は拡大を続け、98年は3.2%[注6]という90年代に入ってから最高の成長率を記録した。98年後半から99年初めにかけて、ユーロ圏、ASEAN向けの輸出が減少するなど外需が減少したこと、在庫調整が進められたことなどにより、成長拡大のテンポは一時緩やかになった。しかし固定投資の増加傾向が継続していることや、99年4~6月期には輸出が半年ぶりに増加に転じたことなどにより、景気は緩やかな拡大を続けている。実質GDP成長率は、99年1~3月期は前期比年率1.6%、4~6月期は同2.5%となった。
失業率は、景気拡大による雇用増に加え、若年層向け雇用創出のための政策や、週35時間労働の早期導入企業への助成措置などの効果もあり、高水準ながらも97年6月の12.6%をピークに徐々に低下している(99年8月11.3%)。97年6月の総選挙でジョスパン政権が誕生して以来、消費者信頼感は好転していたが、このところの失業率低下を受けて信頼感は更に改善しており、それが個人消費増につながっている。消費者物価上昇率は、98年に入り、前年同月比1.0%以下で推移している。
国内金利の低位安定や雇用情勢の改善から、設備投資、個人消費などの内需拡大傾向は続くとみられており、98年後半から99年前半にかけてユーロ圏諸国の経済成長率が鈍化するなかで、フランス政府は99年について2.3%という比較的高い成長を見込んでいる。
(内需拡大の要因)
98年以降のフランスの好景気を支えたのは堅調に拡大する内需であった。
個人消費についてみると、98年は物価上昇率がユーロ圏平均の約半分の水準で推移する一方で、失業率の低下とともに雇用者数は順調に増加し、賃金も上昇したことが、消費の拡大に貢献した(第1-3-12図)。新車登録台数の増加率は97年▲20.7%から98年は14.5%となった。
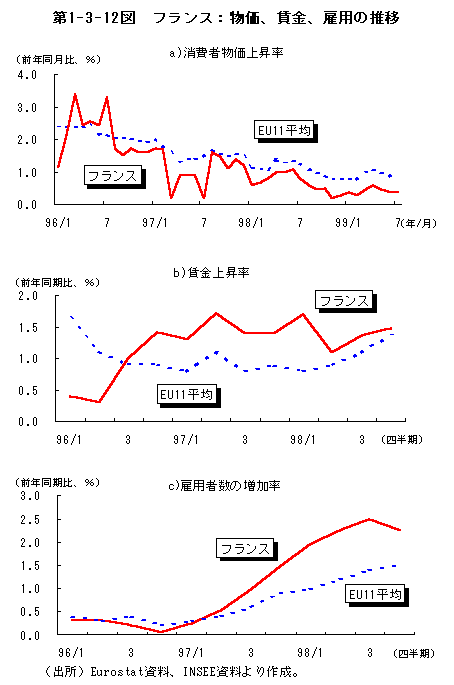
一方、固定投資については、金利の低下に加え、99年8月末までの新築の貸家への税制優遇措置であるペリソール法[注7]の実施などによって住宅投資が急増したことが牽引材料となり、固定投資家計部門は99年1~3月期前期比年率8.9%増、4~6月期は同10.3%増となった。法人部門については、4月にINSEE(国立統計経済研究所)が実施した経営者アンケート[注8]によると、99年の設備投資額は前年比4%増と見込まれている。部門別では消費財や自動車設備への投資がそれぞれ前年比10%以上の増加の見込みとなっており、増加率が際立っている。
(週35時間労働への移行)
98年6月に週法定労働時間を39時間から35時間へ短縮する法律(オブリ法)[注9]が成立した。これは97年5月に発足した社会党ジョスパン政権が、失業率引き下げのために打ち出した政策で、2000年1月1日から労働者を20名以上雇用する企業に週35時間労働の導入が義務付けられることとなった(労働者20名以下の企業は2002年1月1日より導入)。週35時間労働への早期移行を促進するため、労使協約などによって労働時間短縮を前倒しで導入し、雇用を維持又は創出した企業に対しフランス政府は助成措置を提示している。政府は、週35時間労働を早期導入した企業からの報告を基に、オブリ法成立後1年で約10万人の雇用の創出・確保が実現したと発表している(第1-3-13図)。

週35時間労働法の具体的な運用規定を定める第2法は99年末までに立法化される予定である。「賃金カットなし」の時間短縮が公約であるため、労働者の賃金保障と、企業側の負担軽減が織り込まれており、7月末に発表された第2法の草案では、a)週36~39時間の超過勤務時間当たりの法定割増賃金率を移行期間である2000年は10%へ軽減(現行25%)、b)年間残業時間の上限の設定、c)企業管理職への年間労働日数の上限設定(年俸制の企業管理職については必ずしも週35時間労働法の規定がそぐわないため)、d)低賃金労働者社会保障費の雇用主負担分の軽減、e)法定最低賃金(SMIC:Salaire Minimum Interprofessionel de Croissance)労働者の月給保証(労働時間の短縮によって収入が減少しないようにする)、などが含まれている。SMICは物価上昇率などを反映し、毎年7月に改定されているが、99年は労働時間短縮への移行期ということもあり、1時間あたり40.72フランと前年比1.24%の上昇にとどまった(98年は同2.0%上昇)。
9月に閣議決定された2000年政府予算法案においても雇用問題は教育、司法、治安、環境、文化部門とともに政策の重点分野に掲げられている。全体の予算が前年比0.9%増にとどまるなかで、雇用連帯省の予算は同4.3%増の2,536億フランとなった。この中には若年層向け雇用創出策や週35時間労働法導入に伴う企業補助金が含まれている。
(4) イギリス:改善してきているイギリス経済
イギリス経済は、97年10~12月期以降それまでの景気拡大テンポが鈍化し、実質GDPは、98年10~12月期前期比年率0.2%増の後、99年1~3月期同0.9%増となった。景気が減速した背景としては、中央銀行であるイングランド銀行が国内のインフレ率が高まっていることを懸念して、97年6月からの1年間で6回に及ぶ政策金利の引き上げを行い、利上げに伴って為替相場が上昇したことや、外需の低迷といった要因も加わり、製造業を中心とする輸出にブレーキがかかったことなどを挙げることができる。
イングランド銀行は、98年10月には一転して政策金利を引き下げ、それ以降99年6月までの間に計7回の利下げを実施し、景気の拡大策をとった。こうした政策効果もあって、99年4~6月期には景気は改善し、実質GDPは前期比年率2.6%増となった(第1-3-14図)。イギリス経済が改善し始めた要因としては、第一に、個人消費が堅調に推移していることや、為替変動の影響が少ないサービス業を中心に設備投資が増えたことが挙げられる。特に、コンピュータの急速な普及に支えられ、通信・金融部門の設備投資が好調である。第二に、ユーロ圏やアジアの景気が上向きになってきたことなどにより外需が回復していることが挙げられる。英国産業連盟(CBI:Confederation of British Industry)が行っている景況感調査でも、98年7~9月期輸出見通しが▲50ポイントであったのに対して、99年7~9月期には▲9ポイントにまでD.I.(景況感指数)は大幅に改善してきている。
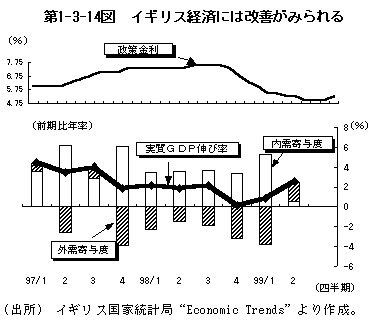
物価は、強いポンドや世界経済全体の需要減もあって安定している。雇用面では、失業率は93年をピークに一貫して低下しており、99年9月には4.2%を記録するなど、80年以来約20年ぶりの低水準で推移している。背景として、サービス部門での雇用が増加していること、また若年層の高失業率や長期失業者に対応した“Welfare to work”(福祉から就労へ)プログラムも一定の効果を示し、若年層の失業率改善に役立っていることが挙げられる。総じてイギリス経済は改善してきており、個人消費や住宅市場の過熱感から中・長期的には物価が上昇することを懸念し、イングランド銀行は9月に政策金利を0.25%ポイント引き上げ、年5.25%としている。
(通貨統合への参加に向けて)
イギリス政府は、99年1月1日から始まった欧州通貨統合第3段階への第一陣での参加を見送った。参加を見送った最大の理由として挙げられるのが、世論の強い反対である。イギリスの信用調査機関であるICMとガーディアン紙が共同で行った7月時点での世論調査によると、参加に反対している国民は6割強に達している一方、参加賛成は3割弱にとどまっており、ユーロ参加への反対は根強いものがある。自国通貨を捨てたくないとのイギリス国民のナショナリズムに加え、ユーロ参加の国民生活にとってのメリットが明らかではないということもその理由となっている。
こうした世論を受けて、イギリス政府は通貨統合には慎重に対応してきたが、99年2月にブレア首相が「参加移行計画」を発表し、通貨統合への参加準備の必要性を表明し、前向きな姿勢を示した。この「参加移行計画」では、政治的・経済的な条件が揃えば、イギリスはユーロに参加すべきであるとし、そのための官民部門別の実践的な作業などを示している。政治的な条件とは、ユーロ参加には政府、国会、国民のすべてが同意する状況が必要であり、参加の決定を政府が下した後4か月以内にその可否を国民投票にかけ最終的に判断する、というものである。現在のところ、2002年5月までに行われる次期総選挙後に国民投票を実施するというスケジュールが有力であるが、投票の実施時期は流動的である。また、経済的な条件とは、97年に打ち出された「5つの経済テスト」、すなわち、a)イギリス経済がユーロ圏の経済と収斂しているか、b)為替調整を失っても大丈夫なほど、柔軟に経済を調整できる手段を持っているか、c)ユーロの導入が投資増などビジネスチャンスを拡大させるか、d)シティの金融制度でユーロ導入の準備がなされているか、e)雇用の増加をもたらすか、を満たすことである。
また、国民投票で通貨統合への参加を肯定されれば、投票後24~30か月程度でユーロ紙幣・硬貨を流通させ、その後6か月以内にポンド通貨を回収するということになっており、先行した現参加国の経験を生かして素早い移行を目指すとしている。
(ユーロ導入をめぐる議論)
99年6月の欧州議会選挙で、通貨統合参加反対の意思表明をしている保守党が大勝したことから、労働党政権は通貨統合参加に対して消極的になっているのではないかという考え方も現われていた。しかし、ブレア首相はこうした考え方を否定し、次期総選挙後に国民投票を実施したいという方針を変えてはいない。また、99年10月には“Britain in Europe”という組織を発足させ、保守党内の通貨統合参加賛成議員を巻き込んだ親ユーロキャンペーンを開始している。しかし、イギリス国内には、2002年頃にイギリスが参加するのは困難であり参加スケジュールが数年ずれ込むだろうという見方もある。
企業の対応をみると、国内の大企業で構成される英国産業連盟(CBI)は、EU諸国は貿易相手として大きなシェアを占めており(第1-3-15図)、参加によって大陸欧州企業との競争が促進されるとして賛成の立場をとっている。一方、中小企業で構成される英経営者協会(IOD:Institute of Directors)は反対の姿勢をとるなど、産業界は必ずしも一枚岩ではない。IODの反対理由は、金融政策決定権を失うことにより、自国の経済状況に応じた政策をとれない可能性があることなどである。
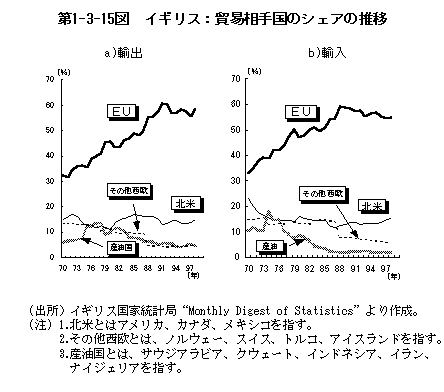
また、通貨統合が雇用に及ぼす影響を無視することはできない。柔軟な労働市場を有するイギリスでは失業率が約4~5%と低水準で推移しているのに対して、大陸欧州諸国では高失業率に苦しむなど格差があり、経済統合がイギリスの雇用にメリットをもたらすのか疑問視する意見もある。為替については、ユーロに対してポンドが高止まりしていることもあり、99年1~9月の平均相場である1ユーロ=約0.66ポンド前後での参加には輸出業者の反発が予想される。国際通貨基金(IMF)は99年5月のカントリーレポートで、「為替相場がイギリス経済に与える影響は大きい」とした上で、「誤った為替レートでイギリスが通貨統合に参加した場合、経済に対して悪い影響が及ぶことは明らかである」と警告している。
(5) イタリア:財政赤字削減テンポ弱まる
イタリア経済は、96年には実質GDP成長率が前年比0.9%の低成長となったが、個人消費の拡大により97年は同1.5%とやや回復した。しかし98年はアジア経済危機の影響、西ヨーロッパの景気減速などにより輸出が伸び悩み、外需がマイナスに寄与するとともに、98年後半に雇用情勢の悪化などから個人消費の増勢が鈍化したことにより実質GDP成長率は前年比1.3%にとどまった。 その後98年10~12月期前期比年率▲1.8%のマイナス成長から、アジアをはじめとする世界経済の回復に伴い99年1~3月期同0.7%、4~6月期同1.7%のプラス成長に転じ、景気は緩やかに改善してきている。政府は99年の実質GDP成長率を1.3%と見込んでいる。しかしながらこの成長率見通しは通貨統合参加の11か国の中で、最も低い水準となっている。
失業率は、高水準ながらもやや低下している(99年7月11.1%)。物価は生計費上昇率が99年8月前年同月比1.6%と安定している。経常収支は99年4~6月期35億1400万ユーロの黒字(名目GDP比1.3%)となった。
(財政赤字削減)
イタリアは欧州通貨統合参加のために、マーストリヒト条約に定められた経済収斂条件を満たすべく緊縮財政を実施してきた。財政赤字GDP比は96年の6.6%から、98年2.7%[注10]と大幅に縮小した。しかし、99年についてはアジア通貨・金融危機、ロシア金融危機などの影響が大きく、当初の見通しの成長率が見込めないとして、5月下旬のEU蔵相定例理事会でイタリアは1年前に合意した財政赤字削減目標GDP比2.0%を緩和することを要請したと伝えられた。イタリアの財政赤字削減目標の緩和を市場は「EUの財政収支目標は簡単に修正されるもの」と捉え、さらに「EUの『安定と成長の協定』を反故にする可能性がある」との観測にまで発展し、財政赤字拡大に対する懸念からユーロ安を引き起こした。
6月末にイタリア政府は緊縮的な財政目標を達成するための2000~2003年の経済財政4か年計画[注11]を閣議決定し、7月にはその計画は国会を通過し成立した(第1-3-16表)。
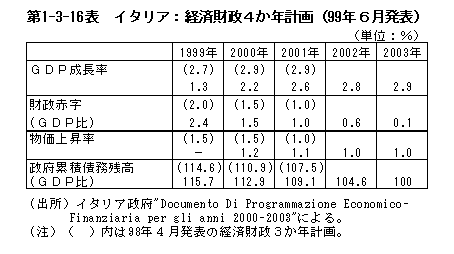
99年のGDP成長率見通しが2.7%(98年4月発表)から1.3%へ下方修正される中で、政府は緊縮財政を継続すべく、2000年予算案においては、歳入面では、脱税取締りの強化や、国営企業の民営化などにより約3兆5000億リラの増収を見込む一方、歳出面では公務員の人件費の削減、自治体への医療費支出の抑制、公的事業、公共サービスにおける民間資本の活用促進などによって、約11兆5000億リラの支出減を見込み、合計約15兆リラ(GDP比約0.7%)の財政赤字削減を計画している(第1-3-17図)。
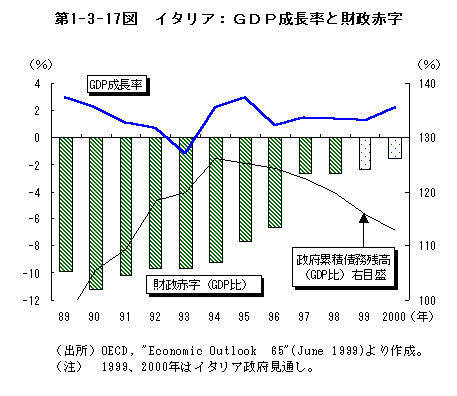
イタリアの財政赤字の第一の要因は、他のヨーロッパ諸国と比較して手厚い年金制度である。98年でGDP比14%にものぼる年金拠出は政府の社会保障費の中でも大きな負担となっている。政府の試算によると高齢化に伴い年金拠出は2003年までに年3.6%で増加していくものと予想されている。今回の経済財政4か年計画では具体的な案は提示されていないが、緊縮財政の継続のためには年金制度の見直しは長期的にみて重要な課題のひとつとなっている。第二は、利払いである。近年の金利の低下により減少傾向にあるものの、一般政府の利払いは98年GDP比8%(EU14か国平均は同4.8%)[注12]と依然として重くのしかかっている。イタリアは一般政府累積債務残高が、98年GDP比119.9%と際立っており、この債務削減が急務となっている。経済財政4か年計画では、2003年までに政府累積債務をGDP比100%まで削減する計画となっているが、98年のEU委員会の推定によるとイタリアが通貨統合参加国に課せられた政府累積債務残高の目標値であるGDP比60%を達成するためには19年を要するとされている。
99年1月のユーロ誕生に伴い、通貨統合参加国は欧州中央銀行による単一金融政策に従うこととなっており、政策金利が一本化されたことにより、ユーロ圏内では統一的な短期金利が形成されている。一方、長期金利については、各国の財政状況による信用リスクの格差によって、差が生じている。ドイツ10年国債とイタリア10年国債の金利差を比較すると、ユーロ誕生までは金利差は縮小していたものの、ユーロ発足後その格差は再び拡大し、ドイツとの信用リスクの差が依然として存在することが窺える(第1-3-18図)。ユーロ圏ではドイツ、フランスに次ぐ経済規模を有するイタリアが、今後どのようにして通貨統合参加国に課せられた財政運営の基準を達成し、足並みを揃えていくかが注目される。

(6) スペイン:インフレ再燃の懸念
スペイン経済は94年から輸出主導で回復してきた。98年はユーロ導入のために、マーストリヒト条約の経済収斂条件を満たすべく、スペイン政府は緊縮経済政策を堅持し、財政赤字削減、インフレの抑制を図った。ユーロ導入に向けた段階的な政策金利の引下げにより設備投資が増加したことに加え、雇用の創出により個人消費が順調に伸びたことによって、内需が拡大基調を維持したことがスペインの高い成長を支えている。一方で、世界的な景気低迷によって輸出相手国の経済成長が鈍化したことにより輸出が伸び悩んだため、外需はマイナスに寄与している。実質GDP成長率は、98年の4.0%から99年1~3月期は前期比年率2.5%、4~6月期同4.6%となった。
消費者物価上昇率は、99年8月前年同月比2.4%と、98年と比較してやや高まり、景気にやや過熱感が出始めている。景気拡大の恩恵を受け、非農業部門の建設、工業、サービス部門の雇用が拡大しており、失業率は94年1~3月期の24.5%をピークに低下傾向にある(99年4~6月期15.6%)[注13]。国際収支をみると、経常収支は99年4~6月期20億2900万ユーロの赤字(名目GDP比▲1.5%)、貿易収支は99年4~6月期65億5200万ユーロの赤字となった。
(ECB利下げによるインフレ懸念)
スペインはマーストリヒト条約の経済収斂条件を満たし、99年1月からユーロを導入した。通貨統合参加国の実質GDP成長率を比較すると、スペインは98年4.0%、99年見通し3.5%(8月政府発表)となり、いずれもEU11か国平均の98年2.9%、99年2.1%(EU委員会4月発表)を上回る好景気が続いている。
ユーロを導入した11か国は欧州中央銀行(ECB)による単一金融政策に従っているが、実質GDPで比較した場合、ドイツ、フランス、イタリアがEU11か国の約7割を占めており、単一金融政策の決定はその3か国の景気動向に左右されがちである。ユーロ圏では98年後半から物価上昇率の低下がみられ、景気停滞を理由にECBは99年4月に政策金利である主要オペレートを3.00%から2.50%に引下げた。一方スペインの消費者物価上昇率は、99年1月のユーロ導入まではEU11か国平均値に収斂しつつあったが、99年に入ってからはEU11か国平均値を大きく上回る上昇基調にあり(8月の消費者物価上昇率は前年同月比でEU11か国平均1.2%、スペイン2.4%)、この金利引下げによってスペインではインフレ再燃が懸念されている(第1-3-19図)。

そこでスペイン政府は4月にインフレ抑制のため政令法6/1999[注14]を公布し、政府の管理下にある電気、ガス、通信、運輸部門等の公共料金を値下げするという政策を打出している。スペインの財政赤字は98年名目GDP比1.6%とEU11か国平均の1.9%より低い水準にあるが、公共料金の引下げは政府の歳入減少を招くことになり、近い将来、比較的健全であるスペインの財政状況の悪化要因となる可能性がある。ECBの政策が域内の景気状況の違いに対しどのように対処すべきかは今後の課題となるだろう。
2 中・東ヨーロッパ : 経済状況の差顕著に
中・東ヨーロッパにおいて、計画経済から市場経済へと体制移行が進んでいるが、移行プロセスなどの違いによって各国間の経済状況の差が顕著になってきている。主要三か国であるポーランド、ハンガリー、チェッコをみると、ハンガリーでは98年に市場経済移行後最も高い成長を遂げたの対し、チェッコではマイナス成長となった。また、ポーランドは依然好調ではあるものの、景気拡大テンポは鈍化している(第1-3-20図)。ちなみに、欧州復興開発銀行(EBRD:European Bank of Reconstruction and Development)の移行国レポート1998によると、中・東ヨーロッパ及びバルト三国[注15]の実質GDP成長率は95年以降低下を続け、97年前年比3.6%、98年同3.0%となっている。

なお、99年3月から約2カ月続いたコソボ紛争により、工業施設やインフラが破壊され、ユーゴスラビア連邦セルビア共和国の経済は壊滅的な状況となっている。しかし、懸念されていた他の近隣諸国への影響は、アルバニア、ユーゴスラビア連邦マケドニア共和国でコソボ地域より難民が流出したことによる影響がみられたほかは、ほとんどなかったものとみられている。
(ポーランド:金融引締めと外需の低迷により景気拡大テンポは鈍化)
ポーランドでは、急進的な市場経済化改革とインフレ抑制のための緊縮政策を中心としたバルツェロビッチ改革が90年1月に開始され、その後次第にその成果が現れ始め、92年には実質GDP成長率がプラスに転じた。その後も順調に成長を継続してきており、95年以降は6~7%台の高成長を続け、98年1~3月期も前年同期比6.4%と好調であった。96年以降の高成長をけん引しているのは、拡大する消費や、急増する海外からの直接投資であった。98年に入ってからも、小売売上は前年比21.6%増と依然好調であり、直接投資も98年前年比48.9%増と大幅に増加している。しかし、EU加盟国の需要低迷などの影響を受けて経済成長は鈍化し、98年4~6月期の成長率は前年同期比5.4%にとどまった。また、その後発生したロシア金融危機の影響を受け、98年の実質GDP成長率は4.8%、99年1~3月期については前年同期比1.5%と景気拡大のテンポは鈍化している。
しかし、内需は好調で直接投資も増加しており、消費者物価上昇率も、97年14.9%、98年11.8%、99年9月前年同月比8.0%と低下してきている。また、政府による民営化も進展し、年金制度の改革が行われるなど構造改革も進んでいる。このようにファンダメンタルズが健全であることや、重要な貿易相手国であるドイツなどの隣国経済の改善もみられることから、実質GDP成長率は4~6月期前年同期比3%となり、また、年後半には更に高まることが予想されている。政府見通しでは99年の実質GDP成長率は4%程度とされている。
(ハンガリー:内需拡大により景気回復へ)
ハンガリーでは、95年3月以降、経常収支と財政収支の双子の赤字解消とマクロ経済の安定化を目標に、緊縮政策と構造改革政策などを主とした経済安定化計画が実施され、96年1.3%まで減速した実質GDP成長率は、97年4.6%、98年5.1%と回復してきている。98年にはOECD加盟国の中で、アイルランド、ルクセンブルクに次ぐ高い成長率となったが、これはそれまでの緊縮政策により落ち込んでいた内需がその反動で拡大したことによるところが大きいと思われる。
また、市場経済移行後、国営企業の民営化を行う際に、外国企業の有する資金、技術力、経営のノウハウなどを活用するため、政府は税の減免、補助金供与など積極的に直接投資誘致策を採ってきた。このため97年の外国からの直接投資流入額は21億ドル、98年19億ドルと中・東ヨーロッパでもポーランドに次ぐ直接投資受入れ国となっており、これが景気を下支えしている。
消費者物価上昇率も97年18.3%、98年14.4%、99年9月前年同月比10.9%と低下しており、失業率も97年末10.4%、98年末9.6%、99年10月9.2%と低下し、改革の成果が現れているが、財政赤字については97年GDP比4.9%、98年4.6%と依然として高い水準となっており、今後の課題とされている。
なお、98年後半以降、ロシア危機の影響などによりこれまでの景気のけん引力となっていた輸出が落ち込んだことから景気拡大テンポは鈍化し、実質GDP成長率は1~3月期には前年同期比3.3%まで鈍化したが、4~6月期には同3.8%となり、99年後半は外需の持ち直しなどにより更に高まるものとみられている。政府は99年の実質GDP成長率を4%と予測している。
(チェッコ:景気は著しく悪化)
チェッコ経済は95年までクラウス政権の下、「チェッコの奇跡」と呼ばれるほど好調であった。しかし、その後89年のビロード革命以降続けられてきた緊縮政策による内需の落ち込み、企業リストラの遅れから国際競争力が低下したことに起因する工業生産の不振などから景気は後退し、実質GDP成長率は、97年の0.3%の後、98年▲2.3%、99年1~3月期には前年同期比▲4.1%と大幅なマイナス成長となっている。とりわけ、98年後半からはロシア金融危機、EU経済の不振などから輸出が低迷したことが大きな影響を与えた。
98年6月にクラウス率いる市民民主党から社会民主党へ政権が移り、経済成長が大きな目標とされ、積極的な工業・農業の振興、輸出促進、外国投資促進、銀行部門の民営化などが図られ、緊縮政策から積極的財政政策へと転換した。また、最低賃金が引き上げられ、これによる家計支出の増加や、輸出の増加などによって4~6月期の実質GDP成長率は前年同期比0.3%となっており、政府は99年の見通しを▲0.5%と予測している。
物価は、消費者物価上昇率が、97年8.5%、98年10.7%の後、企業リストラや国内需要の低迷による販売不振、ディスカウント・ショップやハイパー・マーケットなど小売業の変革などにより、99年1月前年同月比3.5%、10月同1.4%と低下している。失業率は、98年に入ってから、数年に及ぶ経済の不振により企業がリストラを加速化してきたため、97年末5.2%、98年末7.5%、99年9月末9.0%と過去最高の水準となっている。
(EU統合の深化の中での中・東ヨーロッパ)
計画経済から市場経済への移行後10年が経ち、99年1月のユーロの誕生により西欧の経済統合が深化するなかで、EUとのかかわりは中東欧諸国にとってますます重要になってきている。
EUとハンガリー、ポーランド、チェッコとの関係を貿易面からみてみると、EUへの輸出依存度、輸入依存度はいずれの国も85年では20~30%であったが、90年では35~55%、98年では55~70%と大きく高まっている(第1-3-21表)。また、他の地域と比べた相対的な結びつきの強さを表す輸出結合度[注16]及び輸入結合度をみても、85年には0.6~0.8であったが、90年では0.9~1.2、98年では1.7~2.0と上昇している。
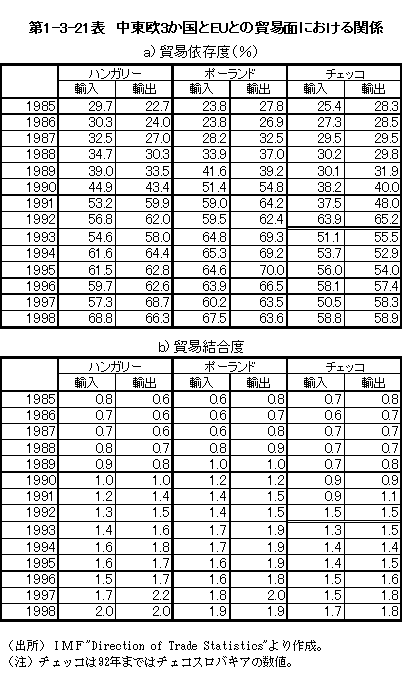
(EU加盟への動き)
92年にハンガリー、ポーランド、チェッコはEU加盟の前段階といわれる欧州協定に署名し、準加盟国となった。その後、94年にハンガリー及びポーランド、96年にチェッコがEUへの加盟申請を行い、98年3月末より三か国すべてについて正式な加盟交渉が開始されている。
他方、99年3月、ハンガリー、ポーランド、チェッコはNATOへ正式加盟し、政治面での関係も強まっており、西欧との繋がりは一層高まっている。
EUに新たに加盟するには、EU加盟国が基本条約に基づいて積み上げてきた法体系の総体である「アキ・コミュノテール」を受容し、これを遵守する意思と能力を有することが必要である。さらに、93年には欧州理事会においてEU拡大に向けて加盟申請国が満たすべき政治的・経済的基準、いわゆるコペンハーゲン基準が提示された。以下、経済面における国別のEU加盟に向けた動き及び課題をみてみることとする。
ポーランドは、98年9月にEU加盟とEMUへの参加を目標とした「通貨政策の中期戦略(1999~2003年)」を作成し、変動相場制への移行を目指している。また、基幹産業である石炭・鉄鋼のリストラがEU加盟交渉の進捗を左右する重要な政策課題となっているが、98年4月には、石炭産業のリストラ計画を作成、7月にはEUの要求により鉄鋼産業の長期リストラ計画を提出しており、今後積極的にリストラを進めていく方針を打ち出している。農業改革も課題とされ、農業部門の構造改革政策をEUに提出しているが、市場経済移行後農業分野は厳しい状況に直面している。また、EUからは、食料農業部門における近代化の促進と、適切な産業構造の確立、食料取引所や卸売市場などといった市場施設設立のための大規模な改革などが要求されているが、これらの達成は非常に困難であり、今後の加盟交渉において特に難航するものと思われる。
ハンガリーでは、構造改革がEU加盟の主要な課題とされていたが、民営化も順調に進展しており、98年1月には新年金制度を導入するなどの進展がみられた。また、EU加盟及びEMUへの参加を目指して、2000年から自国通貨のユーロ連動制移行が決定されている。他方、農業部門はこのところ生産の落ち込みが著しく、ポーランドと同様、近代化の促進などが要求されており、加盟交渉において最も難航すると思われる。
チェッコでは、97年の4月と5月の二度にわたり経済改革のための対策を公表し、構造改革の進展に努めており、経常収支赤字は縮小の方向に向かい、財政状況の改善もみられた。また、経済停滞がEU加盟交渉での問題点とされているが、98年5月に中央銀行が長期金融政策を発表し、金融政策の柱として、物価と通貨の安定を挙げ、99年から2000年に経済を深刻な景気後退から徐々に抜け出させ、EU正式加盟を目指すとしている。しかし、緊縮政策によるマクロ経済の調整と併せて、バウチャー方式による民営化問題への対応、企業の近代化、産業構造改革、不良債権を抱える銀行のリストラなどの問題が依然残されており、EU加盟に向けて困難が予想される。
では実際、ポーランド、ハンガリー、チェッコのEU加盟はいつになるのだろうか。チェッコは、EU委員会より過去一年間、加盟に向けた努力を批判されているなど遅れがみられるが、ハンガリーは法制面で他の国をリードしており、加盟交渉開始国のほとんどが2003年の加盟を目指しているなか、唯一2002年の加盟を目指すなど各国間で差がみられている。しかし、最終的には各国のEU加盟は、加盟交渉などにかかる期間を考えても2005年以前ということはほぼないという見方が一般的である。EUの正式加盟までには各国とも多くの課題が残されているが、着実に加盟への道を歩んできているようである。
3 ロシア : 景気は底入れしたとみられる
ロシアでは、97年に実質GDP成長率が、0.8%と市場経済移行後初めてプラス成長となったが、98年には金融危機に見舞われ、▲4.6%と再びマイナス成長を記録した。しかし、98年9月には前年同月比▲15.0%まで落ち込んでいた鉱工業生産が99年3月以降プラスの伸びとなっており9月では同20.2%増となった(第1-3-22図)。これは為替の大幅減価に伴い、国内産業の価格競争力が強まったことから輸入代替が進展し、また燃料などの国際価格の上昇と燃料関連品目の輸出及び生産の伸びが大きかったこと、更に決済機能が回復してきたことなどのためである。実質GDP成長率についても98年10~12月期前年同期比▲7.8%の後、99年1~3月期同▲2.8%、4~6月期同1.4%となっている。
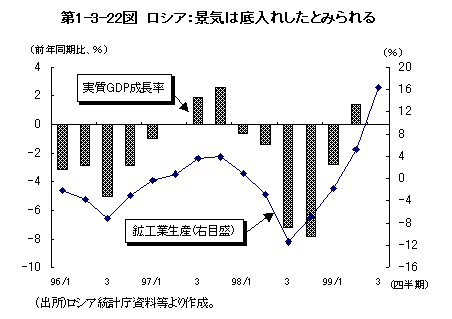
98年7月前年同月比5.6%(前月比0.1%)であった消費者物価上昇率は、通貨切下げ後、8月同9.6%(同3.7%)、9月には同52.2%(同38.4%)と急騰し、98年末まではルーブル増刷などで12月同84.4%(同11.6%)と高騰していたが、その後為替の安定などによって落ち着きを取り戻し、99年10月同57.2%(同1.4%)となっている。
雇用情勢をみると、失業率は、97年10.8%、98年11.9%と上昇しており、99年に入ってからも3月13.6%、9月12.4%と高水準で推移している。
貿易収支は、輸出の減少がみられるものの、輸入の減少が著しいため、黒字を続けており、貿易収支黒字は99年1~3月期64.7億ドル、4~6月期72.1億ドルとなっている。
(金融危機とその後の国際機関などとの交渉)
ロシア政府は慢性的な財政赤字を短期国債の発行で賄っており、大量に短期資本が市場へ流入していたが、97年央からのアジア通貨・金融危機を契機に新興市場から海外資本が引き上げられ、ロシアでも原油価格の大幅下落や国内の政治・経済問題などの要因が加わり、98年夏以降金融危機に見舞われた。8月17日には目標相場圏の変更、実質上のルーブル切下げや、民間の一部の対外債務支払いの90日間の停止などの緊急措置が発表された。
こうした措置や経済改革の進展の遅れなどから7月に決定されたIMF、世銀、我が国輸銀からの融資が凍結されていたが、99年4月に融資再開の基本合意がなされた。その後、IMFの融資を受けるための関連主要法案が、ガソリン税の新規導入法案を除き国会で採択されたことなどを受けて、7月28日にはIMF理事会で融資再開が承認され、さらに23日及び29日には世銀でも融資再開が承認された。パリクラブ(主要債権国会議)でも8月1日に債務繰り延べが合意され、我が国も日本輸出入銀行(当時)による融資の再開を表明しており、ロシア経済の最悪の時期はひとまず脱したといえよう。
(危機からの脱却)
金融危機以降、物価の急騰、生産の著しい落ち込み、消費の大幅減少、失業の増加など実物経済の悪化が進んだが、懸念された程には悪化しなかった。また、99年9月の鉱工業生産は市場経済移行後最も高い前年比増加率を示し、実質GDP成長率も99年4~6月期には前年同期比1.4%と97年以来のプラス成長になるなど景気は底入れしたものとみられている。このように、ロシア経済が懸念されたほど落ち込まず、また予想よりも早く危機から脱却しつつあるのは何故なのであろうか。
この理由としては、まず前述のように、ルーブル切下げにより輸入代替効果が生じたことに加え、燃料などの国際価格の上昇と燃料関連品目の輸出及び生産の伸びが大きかったこと、政府による公的資金投入などにより決済機能が回復してきたことなどが挙げられよう。
99年に入ってからは、ルーブルが安定してきたことなどによって物価も比較的安定してきている。マネーサプライの増加によるインフレの懸念もあったが、98年末のM2の伸び率は97年末が前年末比29.8%であったのに対し、19.8%となっている。また、M2のGDP比をみても97年14.8%、98年16.7%と、政府はM2の伸びを極力抑え、緊縮政策を維持しており、これも物価の安定要因となっている。物価上昇の国民生活への影響についても、既にハイパーインフレを経験していたため、インフレへの対応に慣れていたこと、国民がルーブルでなく外貨をタンス預金という形で保有していたことなどから、想像されたほどではなかったと思われる。
また、ロシアは多額の対外債務を抱えており、金融危機以降は幾度かデフォルト懸念の高まりがみられ、株価や為替下落の要因となっていたが、IMFなどの国際金融支援や、パリクラブによる債務繰り延べなどによってとりあえずの落ち着きがみられている。目まぐるしい政変のなかにおいても政府が市場経済化路線を維持し、構造改革に取り組む姿勢をみせていることも、こうした市場の落ち着きに寄与しているものと思われる。
(ロシアへの資本の流れ)
前述のとおり、アジア通貨・金融危機を契機とした短期資本の引揚げがロシア金融危機を引き起こした一要因となったが、ロシア金融危機の前後での資金流出入の構造がどのように変化したのかみてみよう。
まず、国際決済銀行(BIS:Bank for International Settlements)の統計より98年12月末のロシアへの金融機関の融資残高を6月末比でみると、▲22.5%減となり、融資も金融危機後大きく減少していることが分かる。次に期種別残高をみると、1年未満の短期融資が49.3%減と大幅に減少している(第1-3-23図)。一方、1年以上2年未満の融資は20.2%増、2年以上の融資は1.8%増となっており、中長期の融資については増加していることが分かる。1年未満の融資が融資全体に占める割合をみると、98年6月末では45.0%であったが、12月末では29.5%となっており、2年以上の融資については、6月末43.9%から12月末57.7%と上昇している。
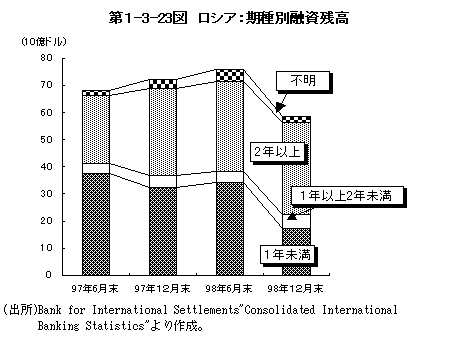
98年12月末のロシアへの国別融資額を6月末と比較してみると、ほぼ全ての国で減少しており、特にアメリカは71.3%減と著しく減少した(第1-3-24図)。しかし、ヨーロッパ全体をみると6.0%減、日本では12.0%減と、アメリカと比較するとそれほど大幅な減少はみられなかった。また、貸手銀行の国別構成比をみると、98年6月末ではヨーロッパの構成比が70.3%から12月末では82.4%へと増加している一方で、アメリカは98年6月末10.3%から12月末3.8%と減少している。ヨーロッパではドイツ、フランス、イタリアの割合が高く、三か国とも98年12月末には6月末より割合が高くなっている。特にドイツは、12月末には52.7%と世界全体[注17]の半分以上の割合を占めた。
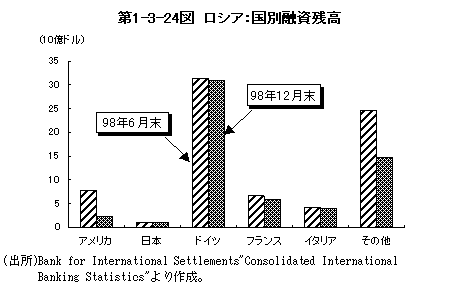
次に、外国投資(直接投資、証券投資など)の状況をみてみると、国家統計委員会のデータ(フロー)によれば、96年前年比133.7%、97年同76.4%と大幅な増加の後、98年は同▲4.2%とマイナスの伸びとなった。
また、外国投資の国別内訳をみてみると、98年はそれまで全体のおよそ四分の一の投資を行ってきたアメリカが19.0%にとどまり、ドイツの投資額が24.2%と1位となった。98年における全体の外国投資額は減少しているものの、ドイツ、フランス、オランダ、スウェーデンなどからの投資額は増加している。
98年外国投資の内訳をみてみると、直接投資が全体の28.6%、証券投資が1.6%、「その他」が69.8%となっている。「その他」には貿易信用が含まれ、これは全体の14.2%、前年の約7倍となっている。一方、直接投資は前年比37.0%減、証券投資は71.9%減と特に証券投資は大幅に減少していることが分かる。
国際収支統計で97年1~6月期から99年1~6月期まで半期ごとにみてみると、ロシアへの直接投資純流入額は97年7~12月期までは増加していたが、98年に入ってアジア危機の影響から減少し始め、またその後自らも金融危機に見舞われたため、98年1~6月期に前期のおよそ6分の1の水準まで低下した。98年7~12月期には再び増加したものの、99年1~6月期は前年同期の水準まで減少している。証券投資については、98年7~12月期に大幅に減少し、99年1~6月期には流出に転じており、金融危機の影響が著しく、いまだ尾を引いていると思われる。
なお、融資、直接投資ともアメリカと比してEU諸国との関係が深まっているが、今後も通貨統合や中・東ヨーロッパ諸国のEU加盟交渉の開始などEUの深化・拡大が進展していくなかで、ロシアとEUの結びつきが一層と強まっていくものと思われる。
- 注1 日本貿易振興会:「通商弘報」(平成11年10月5日)
- 注2 The European Commission, Directorate General 4 " Car prices in the European Union on 1 May 1999: differences remain high"
- 注3 European Commission,Single Market Scoreboard,No.3 , Oct, 1998
- 注4 99年度予算の歳出は、99年1月の閣議決定時で前年度比6.8%増であったが、政府は年金保険会計に対する補助金の見直し等の一時的要因による歳出増を考慮しなければ前年度比1.7%増の緊縮型予算となると主張。
- 注5 OECD "Economic Surveys Germany 1998" P.99参照
- 注6 チェーン方式で算出したGDP成長率。ESA95基準で算出したGDP成長率は96年1.2%、97年2.0%、98年3.4%となる。フランスでは99年5月よりGDPの算出基準を"ESA95"基準に改定している。現在は基準改定の移行期であるめ、GDPの年次データについては、ESA95基準で算出したものと、前年のデータをチェーン方式で算出したデータの2種類を発表している。本章では年次成長率についてはチェーン方式のデータ、四半期の成長率についてはESA95基準のデータを採用している。
- 注7 96年1月1日から99年8月31日までに購入した住宅が対象になる。
- 注8 Informations Rapides "Enquete sur les investissements dans l'industrie -avril 1999"
- 注9 推進者であるオブリ労相の名をとっている(1998年海外労働情勢より)。
- 注10 OECD "Economic Outlook (June, 1999)", Annex table 30. General government financial balances
- 注11 "Documento Di Programmazione Economico-Finanziaria per gli anni 2000-2003"1999年6月30日イタリア政府発表。
- 注12 European Commission "European Economy, Convergence Report 1998"による。EU15か国からルクセンブルグを除いている。
- 注13 Instituto Nacional de Estadistica "Active population survey" (1999年8月)
- 注14 Royal Decree-Law on "Urgent Liberalization and Competition-building Measures"
- 注15 アルバニア、ブルガリア、クロアチア、チェッコ、エストニア、ユーゴスラビア連邦マケドニア共和国、ハンガリー、ラトビア、リトアニア、ポーランド、ルーマニア、スロバキア、スロベニアを指す。
- 注16 輸出結合度はX国のY国への輸出依存度をY国の輸入の世界輸入全体に占める比重で除したもの。輸出結合度が1の場合、X国のY国への輸出依存度は世界全体のY国への輸出依存度に等しい。
- 注17 世界全体とはBIS統計作成に参加している国・地域を除く。
| 第1章 世界経済の現況 | 第2章 アメリカ経済の長期拡大の要因と課題 | 第3章 物価安定下の世界経済 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 |
| 概観 | アメリカ | 欧州 | アジア | 金融・商品 | 通貨・金融システム | 特徴 | 要因 | 生産性 | 課題 | 現状 | 要因 | 特徴 | 金融政策 |

