第2章 第2節 90年代の安定した景気拡大の要因
| 第1章 世界経済の現況 | 第2章 アメリカ経済の長期拡大の要因と課題 | 第3章 物価安定下の世界経済 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 |
| 概観 | アメリカ | 欧州 | アジア | 金融・商品 | 通貨・金融システム | 特徴 | 要因 | 生産性 | 課題 | 現状 | 要因 | 特徴 | 金融政策 |
第2節 90年代の安定した景気拡大の要因
第1節でみてきたように、90年代の長期景気拡大局面は、60年代以降の景気拡大局面と比べると、経済成長率や物価、金利の動向が極めて安定的であるという特徴がある。本節では、そうした長期にわたる安定的な景気拡大の背後にある要因として、a)適切な経済運営、b)経済構造における柔軟性の高まりが重要であったことを示す。他方、97年以降における低インフレと低失業率、高成長率の両立は、c)一時的な要因によってもたらされていた部分も大きかったと考えられ、この一時的要因がどの程度寄与していたのかについても検討を行っている。
1 政策の効果
アメリカ経済は、平時における景気拡大の最長記録を更新し続けているが、その特徴である安定した景気拡大は種々の適切な政策によってもたらされた面が大きい。すなわち、予防的かつ機動的な金融政策が過度の景気過熱を抑え、物価の安定をもたらした。その結果、過去みられたようなインフレの昂進に伴う急激な利上げは避けられ、景気の長期にわたる拡大が可能となった。また、政府部門の縮小と財政収支の改善が金利の低下をもたらした。さらに、70年代から行われてきた規制緩和などが物価の下落や雇用の創出、効率的な市場の形成による安定成長等をもたらした。このような一連の政策による低インフレ、低金利等によって消費や投資の拡大が長期にわたって安定的に続く素地が形成された。以下では、これらの政策がどのように安定した景気拡大に貢献したのかについてみることとする。
1)市場重視型かつ予防的な金融政策
(90年代の金融政策の特徴)
「市場重視」、「予防的」、「独立性の向上」の3つの特徴をもった90年代におけるアメリカの金融政策運営は、今次景気拡大局面における物価安定及び長期金利低下に大きく寄与している。市場重視については、金融政策当局は、市場がどのようなセンチメントを抱いているかに心を砕き、市場との齟齬をきたさないような金融政策運営を行うことを特徴としている。この背景としては、インフレ・ファイターとして名を馳せたボルカー前FRB議長の後を87年に継いだグリーンスパン議長が、民間エコノミスト出身であることも挙げられるだろう。政策や景気動向についての市場との認識のズレは情報の非対称性をもたらす。このため、政策当局へのクレディビリティが低下し、政策の効果を弱めてしまう可能性がある。また、最悪の場合には株価の急落から信用収縮を引き起こすといったような事態に発展するかもしれない。そのような事態を避けるため、グリーンスパン議長は金融政策に関する透明性を高めるよう努めている。また、金融政策の変更に関しては、その対応が迅速である一方、市場が政策の変更を徐々に織り込むよう事前に金融政策の方針をほのめかし、変更時のショックを和らげている。
次に、予防的な金融政策については、足下でインフレ圧力の高まりを示す兆候が見られなくとも、将来インフレ圧力が高まると考えられる場合には、従来に比べてより早い段階で「予防的(preemptive)」に利上げを行い、インフレを未然に防ぐようにしている。基本的に政策当局は、指標の発表と実際の景気動向との間のラグ、政策判断のラグ、政策の効果発現までのラグをなるべく解消するために景気の行方を先取りした金融政策運営を求められる。したがって、予防的であることはこのようなラグによって生じる景気の急激な変動を抑制し、物価や金利の安定に貢献していると考えられる。
最後の独立性については、クリントン政権が金融当局の政策運営に影響を及ぼすようなコメントを避けるなど、独立性を極力担保するよう努めていることが挙げられるだろう。このことは金融当局の信頼性を高めることを通じて物価の安定等に寄与していると考えられる。以下では、この三つの特徴について、具体的にみてみることとしたい。
(市場とのコミュニケーション)
まず「市場重視」型の政策運営について概観する。市場重視型の政策にはいくつかの側面があるが、90年代のそれは、市場の自律的な価格や金利等の調整機能を重視しており、そのため金融政策の運営に関する情報公開を進めたことにポイントがある。
市場の自律的調整機能の重視については、金融危機への対応が求められるような特殊な場合を除き、通常の経済環境の下では、アナウンスメント効果などによって、市場の自律的な調整機能を活用している側面がある。例えば、FF先物の金利水準は、FEDの政策スタンスの変化を予想してこれを織り込む動きとなっており、実際のFFレート誘導目標水準の変更はこれを追認する形となっている。
また、情報公開については、従来、FOMCにおける政策変更は次回FOMC数日後の議事要旨公表時まで原則非公開であったが、94年2月以降FFレート誘導目標水準の即時変更など重大な政策変更が決定された場合にはその声明文を即時公表する方針がとられた。さらに98年12月以降は、一般公表されるべきとFEDが考える場合においては、バイアス[注1]変更などの金融政策の運営スタンスの変更が即日発表されるようになった(それまでは、議事要旨が次回のFOMC後に公開されるまでFEDのスタンスは分からなかった)。同時に、公開議事要旨における金融政策運営指針の表現も簡素化されるなど、従来に比べて政策の透明性を高めるように変化してきている。また、議会証言などの法的に義務づけられている場以外においても、議長等の講演といった機会を通じ、その都度、直近の経済指標に対する見方などを提供している。
このように連銀は、操作目標としてのFFレートなどの明示的な金融政策のターゲットだけでなく、幅広い経済指標の動向についての見方を常に市場に向けて明らかにすることで、金融政策の透明性を高める努力を行っている。このことが、政策当局に対する信頼性を高め、ゆがみの少ない効率的な金融市場の形成に貢献していると考えられる。
(予防的な金融政策の効果)
次に、「予防的」な金融政策運営であるが、90年初からの金融政策の動向を振り返りながら、実際に94年前半からの予防的金融引締めがインフレを未然に防いできたことをみてみよう。まず、いわゆるテイラー・ルールやマッカラム・ルールによって、FEDの金融政策運営を検証してみる。テイラー・ルールは、ジョン・テイラーが考案した中央銀行の金融調整方式に関する理論であり、短期的なインフレ率と失業率のトレード・オフに着目して、両者の目標からの乖離を最小とすべく政策金利を変更するのが望ましいというものである。マッカラム・ルールは、ベネット・マッカラムが考案した金融政策運営方法で、名目GDPの安定的に推移させるための、ベース・マネーの伸び率を示すものである。 テイラー・ルールと実際の金融政策を比較すると、91~94年にかけてテイラー・ルールが示すよりも大幅な金融緩和が行われていたことが分かる。その後、94年にテイラー・ルールがFFレートのやや引締めを示したとほぼ同時に大幅なFFレートの引上げを開始し、95年までかけてテイラー・ルールの示す水準にまで急速に引き上げられた。それ以降については、98年秋まで、ほぼ同ルールにそった金融政策運営が行われている。90年代初めの大幅な金利引下げは、S&L(貯蓄貸付組合)の野放図な融資がもととなった金融危機や企業や家計の負債の増加などに対応したものであり、通常の金融緩和とは異なる背景があった。これは、通常は変更されない支払準備率が90年12月から92年4月にかけて低めに変更されたことからもうかがえる。この金融緩和により、民間経済主体の負債の返済等が進み、91年以降の景気回復を促すこととなった。94年から98年夏までのFFレートの金利水準はテイラー・ルールの示す上限の水準にほぼ沿っており、総じて引締め気味の金融政策運営が行われてきたことが分かる。なお、98年秋の金利引下げについては、同ルールがやや引締め気味の金利を提示する中で行われた。(第2-2-1図)。
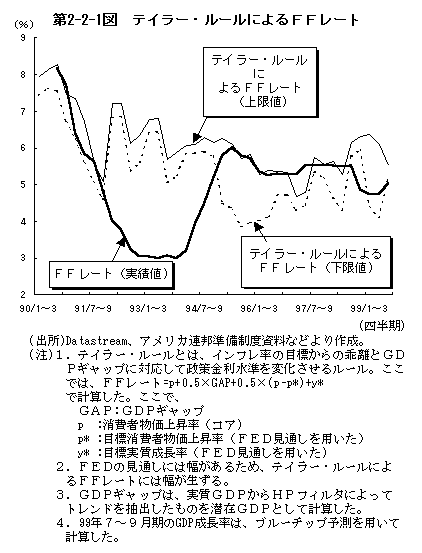
次に、マッカラム・ルールと実際の金融政策を比較すると、94年の引締めは、同ルールが示す引締めのタイミングよりもいち早くかつ大幅に行われていたと考えられる(第2-2-2図)。また、97年半ば以降は同ルールが示すよりも拡張的なスタンスがとられており、特に昨年秋には、大幅な金融緩和が行われたことを示している。
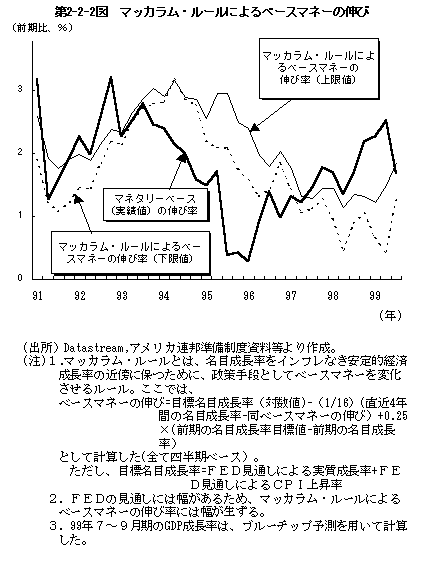
このような予防的な政策運営は、実際にどの程度効果があったのであろうか。金融政策の効果を正確に計測するのには困難が伴うが、FFレートの操作が将来の物価上昇率に与える影響をみることで、その効果を調べてみた。それによると、FFレートの引上げは、2年程度のラグを持って、将来のインフレ率を低下させる効果があることが分かる(第2-2-3図)。さらに、この金融政策の先行度合いと物価の変動率との相関関係について、簡単な分析を行うと、87年以降においては、それ以前に比べて政策発動がより早いタイミングで行われるなど予防的になっており、そのような中で、物価の安定度も高まっているということが分かる(第2-2-4図)。
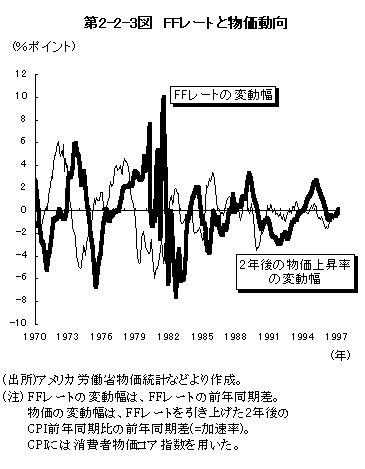
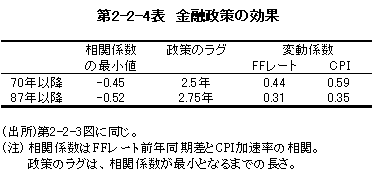
(独立性の向上)
中央銀行の独立性と物価の安定には強い関連性があることが知られている。クリントン政権は、明示的にFEDの独立性の重要性を謳いあげ、具体的には、FEDの金融政策に影響を及ぼすようなコメントを差し控えている[注2]。アメリカにおいては、過去、金融政策が行政府や議会の政治的圧力の影響を受けることが多かったといわれており、現政権におけるこのようなスタンスはFEDの政策効果を高めていると考えられる。
(信頼のジレンマ)
しかしながら、現在のFEDの金融政策運営にも問題点がある。グリーンスパン議長に対する市場の信頼が厚過ぎるため、特に株式市場において過度の楽観論が蔓延していることである(信頼のジレンマ)。すなわち、株価が急落しそうな事態になっても、FEDが巧みにそうした事態を避けてくれると信じて、人々は安心して株を買い続けている。例えば、ブラックマンデー時や98年秋の株価急落時には、いずれも迅速に大幅な金利引下げを行い、その結果、株価は早期に回復している。議長は、96年にNYダウが6000ドル台で推移していた頃から株価は高過ぎるのではないかとの問題を提起してきたが、その後のトレンドをみると、株価は力強い上昇を続けている。これは、FEDの金融政策運営がうまく行われてきたことの証左でもあるが、逆にそれだけ株価の割高感が高まってきていることを意味する。
2)財政収支の改善による好影響
(財政収支の改善による好影響)
過去、経常収支赤字とともに大きな問題となっていた財政赤字であるが、92年度以降、赤字削減への取組と好況に伴う税収増から劇的な改善を示し、98年度には財政黒字を記録するまでになった。政府の財政収支は、一般政府ベースでみても、連邦政府ベースでみてもほぼ同じような推移を示しているが、いずれでみても92年度を底として収支は改善を続け、98年度以降は黒字に転換している。このことは、直接的には、政府部門による資金需要の減少を通じて長期金利の低下をもたらし、投資や消費を刺激したと考えられる。また、財政収支の改善はその分国民経済全体の貯蓄率を上昇させた。マクロでみれば、(国際的な資本移動が完全に自由でないとすれば、)国全体の投資/GDP比率は国民貯蓄率に強く規定されることから、財政収支の改善は90年代の投資ブームをもたらす土壌を養生したといえよう。間接的には、それまでに比べて厳しい財政規律によって、FEDが将来において引締め気味の金融政策を採用する可能性を低め、期待インフレ率の低下及び将来の金利低下という市場の期待感を醸成した。
先に述べたように、財政収支の改善は国債の需給改善に繋がり、結果として長期金利の低下をもたらすが、90年代に入ってからの長期金利の低下を要因分解してみると、金融緩和や物価の下落などの要因と並んで、財政収支の改善が約3分の1を占めていることがわかる(第2-2-5図)。
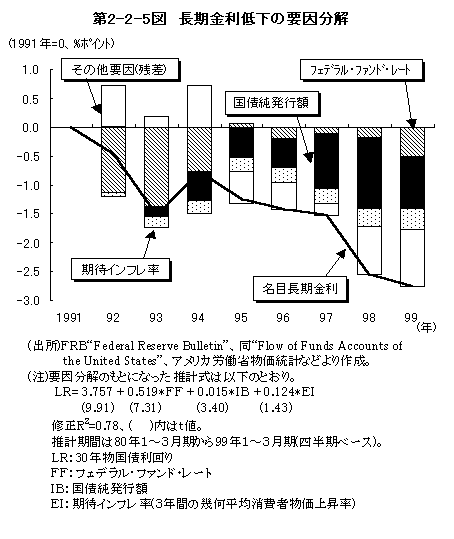
90年代初めから半ばにかけての、規律のある財政政策と緩和気味の金融政策の組み合わせは、アメリカ経済に対して民間投資と個人消費を刺激する方向に働き、安定成長の礎となった。
(90年代における財政収支改善の要因)
この財政収支改善の要因について俯瞰すると、歳出抑制による構造要因が大きな比重を占めていることが分かる。連邦財政収支は名目GDP比では、92年度に約▲4.7%(約▲2,900億ドル)を記録したが、98年度には約0.8%(約700億ドル)と黒字に転じている。このように財政収支は6年間で名目GDP比でみて約5.5%ポイント改善したが、米国議会予算局が作成した資料に基づき、財政収支改善の要因を歳出と歳入の両面において景気要因と構造要因に分解して、一定の条件の下(名目GDP比の比較)で試算すると、景気要因が約3割、構造要因が約7割となる。景気要因のほとんどは歳入増加で占められ、構造要因については、歳出抑制努力が収支改善全体の約5割、歳入増加努力が約2割となっている。全体としての歳出と歳入の収支改善への寄与は同程度である(第2-2-6表)。歳出の内訳をみると、歳出全体は増加しているものの、軍事費は大幅な減少となっている(92年度GDP比4.9%→98年度GDP比3.2%)ことから、軍事費の削減が歳出抑制努力要因の中の大きなウエイトを占めていることが分かる。また、この軍事費の削減により、軍需から民需への転換が生じており、軍事費の減少にともなって、民間投資が増加した[注3]。
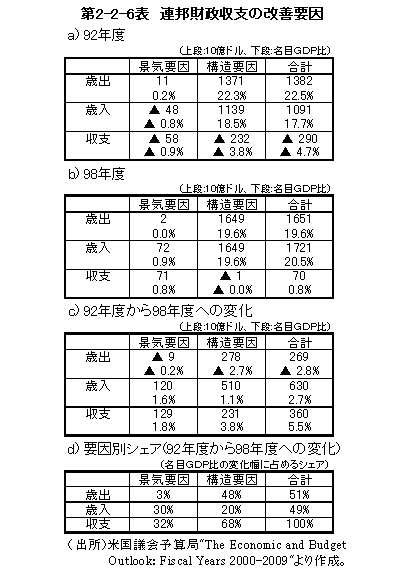
3)規制緩和等の効果
70年代から進められてきた各産業における規制緩和は、新規参入や市場競争の活発化を実現させ、それが生産効率や経営効率の向上、新技術の開発・導入等を通じて、生産性の向上と物価の低下、効率的な資源配分をもたらしてきた。
(規制緩和がもたらす物価の低下)
多くの経済的規制は、そもそも運輸、通信、エネルギー産業において規模の経済に起因する自然独占への対応策を策定したことなど、古くは30年代から始まった。こうした規制は、上限価格の設定などにより一定の目的を果たしたものの、徐々にイノベーションに対するインセンティブの欠如などの副作用をも生み出し、結果としてコスト増加やインフレ要因となった。また、技術進歩が自然独占を打ち崩す例も生じてきたことともあいまって、政府の政策は規制を緩和して自由競争を促進させる方向へと傾いていった。
代表的な例として通信分野を挙げることができる。70年代までは短距離、長距離を問わず通信分野はAT&Tが事実上独占していたが、80年代に入り、長距離電話の参入規制を外して競争を認め、短距離電話は地域を独占する子会社を分離させることで規制緩和が開始された。それ以降も料金規制の撤廃などを行い、結果としてサービスの多様化、生産性の向上、価格の下落がもたらされた(第2-2-7図)。
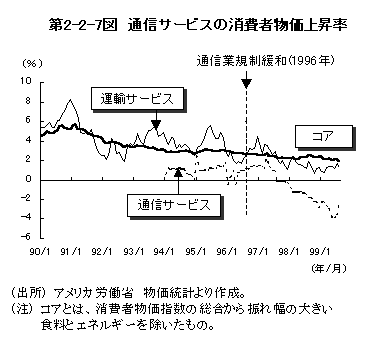
規制緩和は、通信以外の分野においても、価格低下と効率的な資源配分をもたらしている。OECDの試算によれば、規制緩和は、電力業で0.13%ポイント、通信業で0.17%ポイント生産者物価を押し下げた[注4]。 さらに、規制緩和は、市場の効率性を高め、経済構造の柔軟性を向上させると考えられる。例えば、直接金融市場についてみると、80年代初頭以降規制緩和等が進む中で、金利動向と社債発行額の相関が高まっており、市場機能の発揮を通じた資金配分の効率性が高まっていると考えられる(図2-2-8図)。このような資源配分の効率化は、長期にわたる安定成長の礎を形成しているものと考えられる。
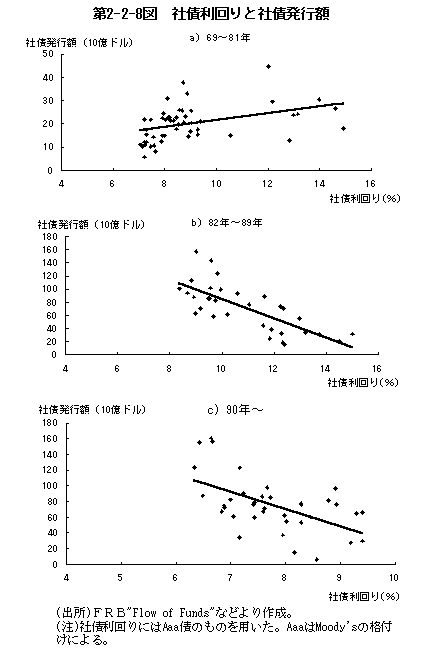
2 経済構造の柔軟性の向上
次に構造要因について検討を加えてみたい。アメリカ経済がもともと有している特徴である経済構造の柔軟性の高さが、70年代以降の規制緩和や市場開放等により一層強化されたことも、安定した景気拡大に貢献したと考えられる。つまり、経済構造の柔軟性が高まることで、様々な構造変化に対する調整速度が速くなり、経済環境の変化に対する耐性が高まり、景気の安定的な拡大がもたらされるようになっていると考えられる。また、柔軟性の向上によって政策の効果が発現しやすくなる(場合によっては、市場の自律的調整機能が政策を補完する)など、経済全体の効率性が高まっていることも、安定成長を支える重要な要素であろう。ただし、柔軟性が高いということは、内外の経済環境の変化に対して迅速に対応し得る一方、場合によっては、調整の振幅が大きくなることも意味している。さらに、マクロ経済の長期的・安定的拡大は、必ずしも労働者や企業といった個々の経済主体にとって安定的な生活ないし企業経営を意味するものではない。労働市場が柔軟で、職種間・産業間・地域間移動が多いということは、逆にいえば、個々の労働者はそれだけ頻繁に転職を余儀なくされるということである。また、企業の開廃業率が高く新陳代謝が激しいということは、企業経営者にとっては極めて厳しい経済環境を意味する。アメリカ国民はもともと変化を前向きに受け止める性向が強いと考えられるが、いずれにしても個々の経済主体がこうした変化を受け入れることが、マクロ経済の安定的成長につながっている。
以下では、アメリカ経済の柔軟性を示す代表的な事例を掲げることとしたい。
(元来柔軟性の高いアメリカ経済)
アメリカの経済構造は、もともと、他の先進諸国と比較して、柔軟性が高いという特徴を備えている。例えば、開廃業率が比較的高い上に、ネットの企業増加率は高く、企業(産業)の新陳代謝が激しい。産業構造の変化は、各企業における部署の統廃合や人材再配置等によっても達成し得るため、開廃業率等だけをみて判断できるわけではなく、また企業の設立と廃止による資源の再配分は、社内での再配分に比べて調整コストが大きくなる可能性もある。しかし、経済環境をめぐる諸条件の変化が速い昨今においては、労働資源や資本の効率的な配分を迅速に行う上で、企業の設立と廃止による資源配分の素早くかつ大幅な調整が可能なアメリカの経済構造が適している場合も多いと考えられる(第2-2-9表)。
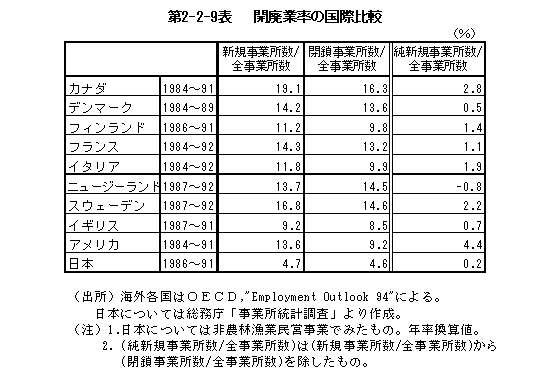
このような柔軟な経済構造は、情報通信革命のメリットを十分に経済社会の中に取り込むことを可能とし、市場ニーズによりマッチした製品開発や効率的な在庫管理技術等、技術進歩の成果が広く行き渡ることとなった。この情報通信革命の成果は、経済構造の柔軟性をより高めた。また、金融技術の発達は規制緩和と相まって、リスクマネーの供給を促した。さらに、経営手法が概してトップダウンであることもスピードと柔軟性が要求される時代にマッチしているといえよう。
在庫変動の長期的な推移をみると、製造業の在庫縮小や経済のサービス化、情報通信技術の発展による在庫管理技術の向上等を主要因として、在庫変動は縮小している。また、経済のグローバル化に伴い、アメリカの輸出財に対する需要が分散され、景気変動の波が各国ごとに異なることを反映して、意図せざる在庫投資の増加が避けられるようになったという指摘もある。
以上みたような時代の動向にマッチした経済構造が、安定した景気拡大をもたらしているといえよう。
(労働市場の柔軟化とNAIRUの低下)
労働市場の柔軟化は、90年代に生じた大きな変化の一つである。もともとアメリカの労働市場は、最低賃金、失業給付額が低いなど、ヨーロッパ諸国等に比べて柔軟であることが指摘されており、このことが、若年層を中心とした相対的に低い失業率をもたらしている(第2-2-10,11,12,13図)。さらに、90年代に入り、人材派遣業の隆盛や年金などのポータビリティ(前の事業主のもとで積み立てた資金を新しい事業主のもとへ移管することができること)が向上したことによる労働移動コストの低下などから、柔軟性がより高まっていると考えられる。また、職業訓練の充実や高学歴化による労働力の質の向上も、情報化の進展といった雇用ニーズに対応した労働力の供給を可能とし、ミスマッチを低下させたと考えられる。この結果、90年代の労働移動は、80年代のそれが主に産業間での移動であったのに比べ、産業間のみならず職種間の移動が多かった(第2-2-14図)。また、就業機会の地域分散化や地域間人口移動によって、地域間の労働ミスマッチも90年代に入り低下したと考えられる(第2-2-15図)。このように大幅な労働移動があるにもかかわらず失業率が低くなっているのは、労働需要が強いのに加え、前述した要因等によりミスマッチが小さくなっているためであると考えられ、柔軟な労働市場は、変化の速い経済状況の中で、迅速な労働資源の効率配分を可能とし、安定した景気拡大に貢献した。さらに、情報化の進展に伴う高度な労働力に対するニーズや企業間の競争の激化は、労働者の能力に見合った賃金が支払われるような効率的な労働市場の形成を促した可能性がある。また、96年に成立した福祉改革法などによって福祉対象者の就労・自立が進んだことも構造的な失業率の低下に寄与したといえよう。
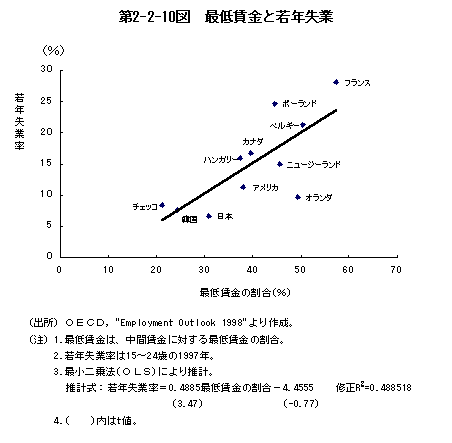
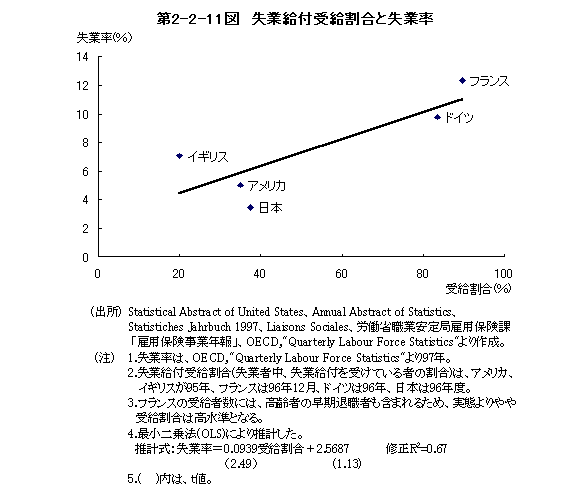
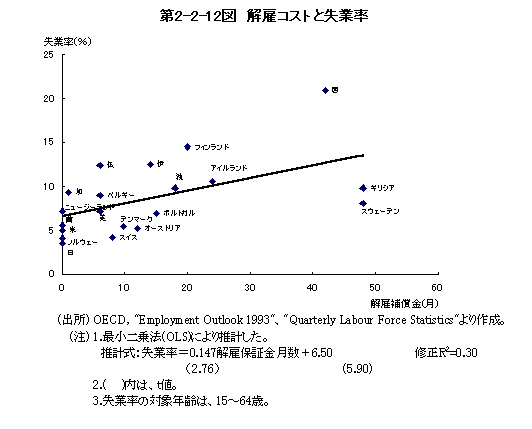
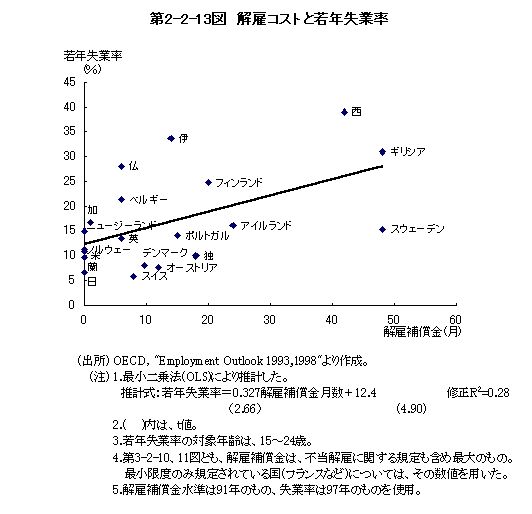
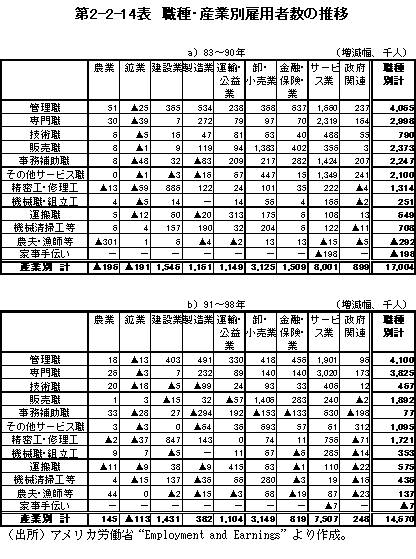
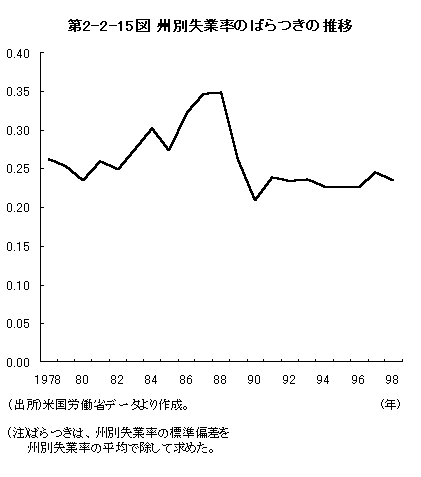
このような労働市場の柔軟性の向上は、いわゆるNAIRU(Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment:物価上昇を加速させない失業率)を低下させ、低インフレと低失業率の両立を可能としていると考えられる。そこで、96年までのデータを用いていくつかの方法によりNAIRUを推計すると、労働市場の柔軟化が進んでいること等により、90年代初めは6%前後であったNAIRUが91~93年以降に低下し、4%台となっている可能性があることが分かった(第2-2-16図)。このため、失業率が大幅に低下し、4%台前半となっている99年秋においても、物価上昇圧力はそれほど高くはないといえる。ただし、97年以降における物価上昇率の一層の低下は、以下で述べるように一時的なものであった可能性が高い。
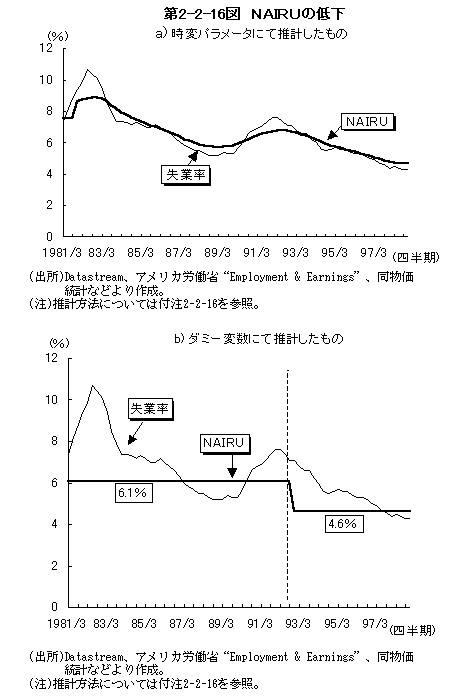
3 一時的要因が大きく寄与した低インフレと低失業率の両立
97年以降、4%近い高成長が続いた。失業率はこの間低下し続け、30年ぶりの低水準である4%台前半を記録した。他方、通常であれば賃金上昇を通じて上昇率が高まるはずの物価は、96年に入り低下し始め、97年10~12月期には10年振りに前年同期比2%以下の上昇率となった(消費者物価(総合)の前年同期比95年2.8%、96年2.9%、97年2.3%、98年1.6%)。この間、賃金(雇用コスト指数)の動向をみると、95年2.8%、96年2.9%、97年3.0%、98年3.4%と上昇率はやや高まってきている。過去の経験では、長期の景気拡大は景気過熱をもたらし、失業率の低下から賃金及び物価の上昇を招き、金利上昇(及びそれにともなう株価の下落)による景気の後退につながっていったが、今回は、長期の景気拡大(Long Expansion)が続くなかで、97年以降成長率が高まったものの、低失業率(Low Unemployment)と低インフレ(Low Inflation)が両立している。つまり、いわば「3つのL」が現在のアメリカの良好なパフォーマンスを表しているといえよう。
しかし、97年以降の高成長・低失業率と低インフレの両立は、一時的要因によってもたらされた面が大きいと考えられる。この一時的要因としては、a)ドル高や輸入原材料価格の下落に伴う物価下落及びコスト減少があったこと、b)輸入品増加に伴う価格競争激化により物価が下落したこと、c)医療費等の抑制が雇用コストの伸びを抑えたことが大きな要因であった。
一時的要因は、91~96年から97~98年にかけての消費者物価指数(総合)上昇率の低下の全てを説明している。したがって、現在の低インフレは、為替、原油をはじめとする一次産品価格等の動向如何によっては、容易にインフレ圧力に反転する可能性が高いといえよう。既に原油価格は99年に入り上昇に転じている。ただし、90年代を通してみれば、労働市場の柔軟化等による賃金上昇圧力の抑制も大きな位置を占めていた。以下では、こうした最近の低インフレの要因について整理する。
(一時的な海外要因による低インフレ)
まず最初にa)の海外要因について検討してみよう。石油をはじめとした原材料価格の下落やドル高に伴う輸入品価格の下落は、物価の下落をもたらしている。91~96年から97~98年にかけての消費者物価0.9%ポイントの下落のうち、輸入物価下落が直接与えた影響をみると、▲0.3%ポイントと推計される。原材料等を通じたコスト低下の影響についてみると、生産者物価の下落に占める輸入原材料価格の下落の影響が年1.2%ポイントであることから、輸入物価は生産者物価を通じて消費者物価を年0.5%ポイント下落させたと推計される。したがって、先の直接要因に加えて、生産者物価から消費者物価への影響を考慮すると、輸入物価の下落は、少なくとも合計で0.8%ポイント消費者物価を引き下げたと考えられる。また、この年0.8%ポイントを要因分解すると、ドル高の影響が、年▲0.3%ポイント、国際商品価格下落の影響が年▲0.3%ポイントとなる(第2-2-17図)。
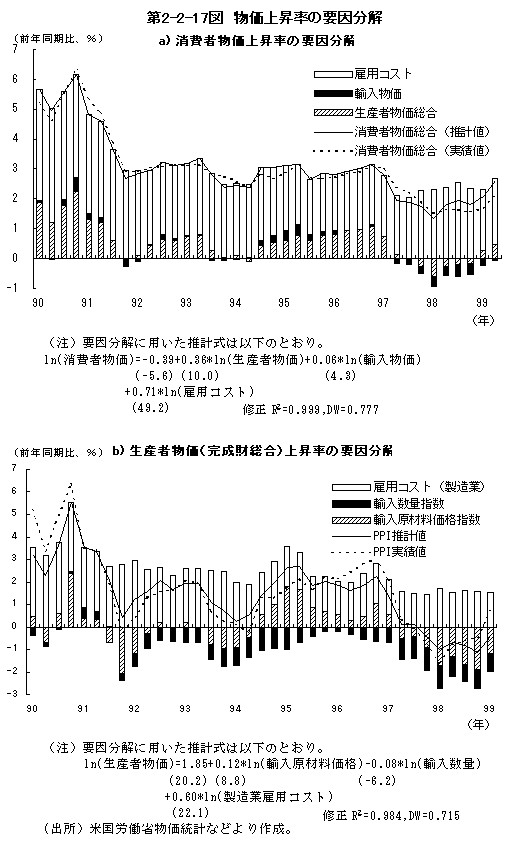
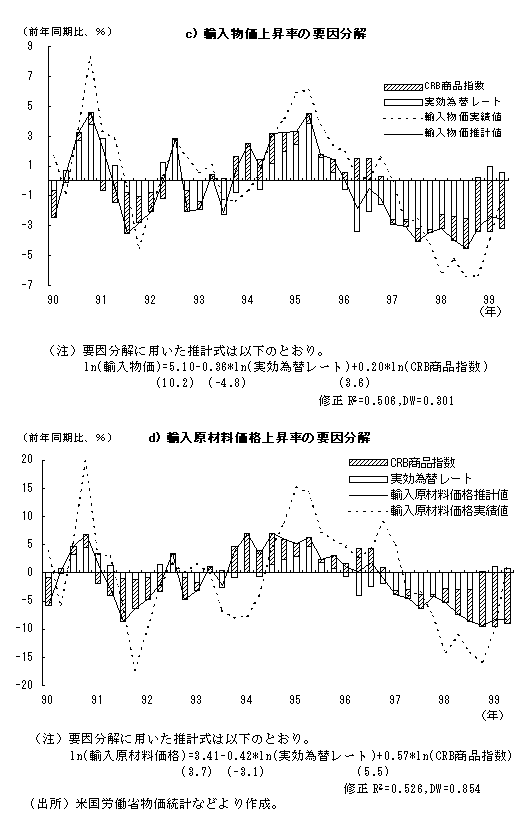
次に、b)の価格競争については、製品輸入量を代理変数として計測すると、0.1%ポイントの消費者物価下落要因となっていると推計された。この価格競争による物価下落は、安価な輸入品が増加したため、国内企業の価格決定力が落ちたことによるものである。この間の企業収益の動向は、このことを反映したものと考えられる。96~98年にかけては、製品価格が下がる一方で雇用逼迫により賃金上昇率が高まったため、企業収益が圧迫され、伸びが低下した。しかし99年に入り、海外景気動向の改善などから、国内企業の価格決定力が回復してきたことなどにより、企業収益は回復している。
(一時的要因による雇用コストの抑制)
c)の雇用コストについては、マネージドケア[注5]の普及により医療費負担が低下し、また株価の上昇により確定給付型年金の積立て額の縮小が可能となったことなどにより、諸手当(退職金や医療保険、雇用保険等、雇用主が人を雇うにあたって負担するコスト)の伸びが大幅に鈍化している。このため賃金・報酬が伸びているにもかかわらず、雇用コスト全体(賃金・報酬と諸手当の合計)の伸びが抑えられ、物価の伸びも抑制された。95年に2.9%であった賃金・報酬の伸びは、96年3.2%、97年3.4%、98年には3.8%と上昇している。他方、諸手当は95年2.5%増の後、96年1.9%増、97年2.0%増と鈍化している。このため、92~96年から97~98年にかけて雇用コストは消費者物価を0.2%ポイント低下させた(賃金・報酬は0.4%ポイントの押し上げ要因、諸手当は0.5%ポイントの押し下げ要因であった)。しかし、この要因は、医療費の抑制効果が一巡したこと、労働需給がタイトになる中で雇用者側が労働者を引きつけるため、サービス内容や質が充実しているが保険料が高額な医療保険プランを選択する動きがみられること、株価の上昇が今後続くかどうかは不確定であることなどにより、今後は物価の押し上げ要因となると考えてよいだろう。実際、98年の諸手当は前年比2.5%と伸び率が高くなっている。
(物価上昇率鈍化の要因分解)
上に掲げた一時的要因は最近における物価上昇率の低下のどの程度を説明しているのであろうか。これまで掲げた要因に基づき90年代における物価上昇率の鈍化について要因分解すると、一時的要因が全てを説明していることが分かる(第2-2-18表)。一時的要因以外の構造的要因としては、d)労働市場の柔軟性が高まり、賃金上昇圧力が抑制されたこと(92~98年の間、NAIRUの低下により物価上昇圧力が1.0%ポイント抑制された可能性がある)、e)資本稼働能力の向上により、設備稼働率が上昇せず、物価上昇圧力が生じていないこと、が挙げられる。その他、f)物価統計の改訂により、最近のインフレ率は実際以上に低下しているように見えるということも指摘できる。
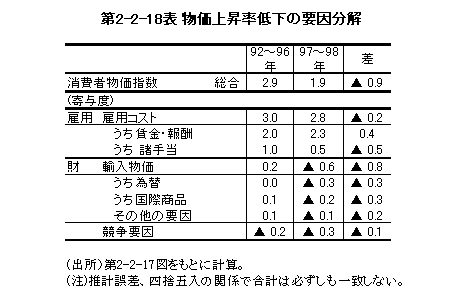
e)の資本稼働能力の向上についてみてみよう。これは、近年の旺盛な設備投資や労働需給がタイトであることから、業種によっては、企業が資本装備率を高めており、この結果、資本稼働能力が向上していることが影響している。そのため、需要が高まっているにもかかわらず、稼働率が上昇せず、物価上昇圧力が生じていない。これまでは、就業者率(就業者数/労働力人口)と稼働率との間に強い相関関係があった。また、稼働率は物価動向と強い相関関係があった(第2-2-19図)。しかし、最近では、就業者率が上昇するなかで稼働率が低下しており、過去とは異なる動きが観察される(第2-2-20図)。すなわち、労働需給がタイトになっているにもかかわらず、資本稼動能力には余裕のある状態が続いている。この最近の稼働能力の向上は耐久財製造業を中心に生じている(第2-2-21図)。業種別では、機械、金属製品といった産業が稼働能力を高めている傾向があり、こうした投資ブームの背景には国際競争力の強化という能力増強投資要因があったものと思われる(第2-2-22図)。単純に稼働率と物価との相関関係から試算すると、稼働率低下により、97年から98年までに物価上昇率(CPIコア)は、年約0.1%ポイント程度押し下げられていると考えられる。
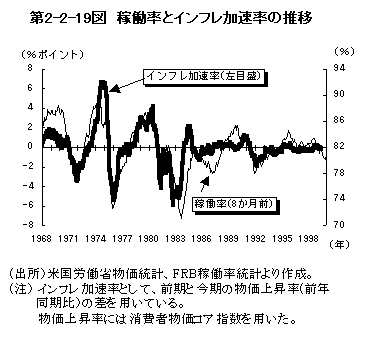
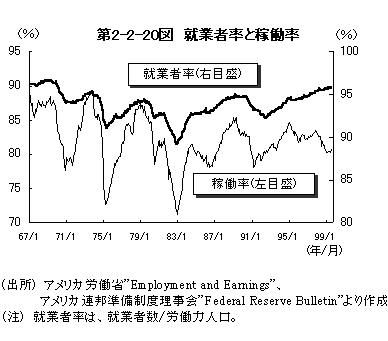
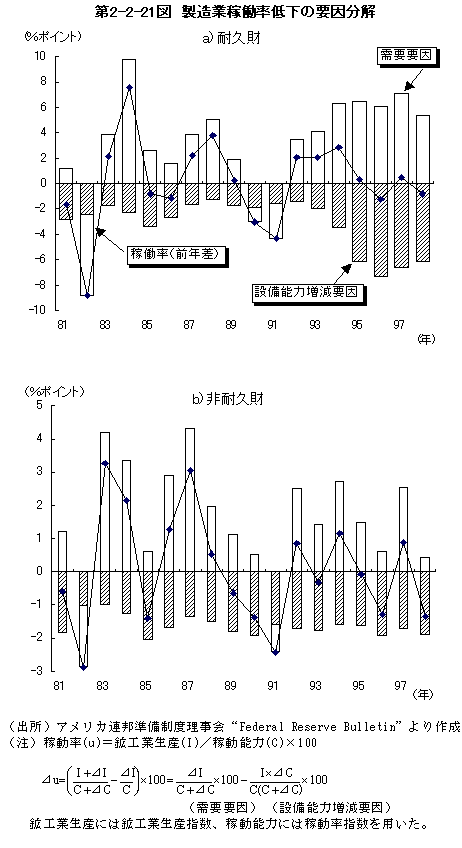
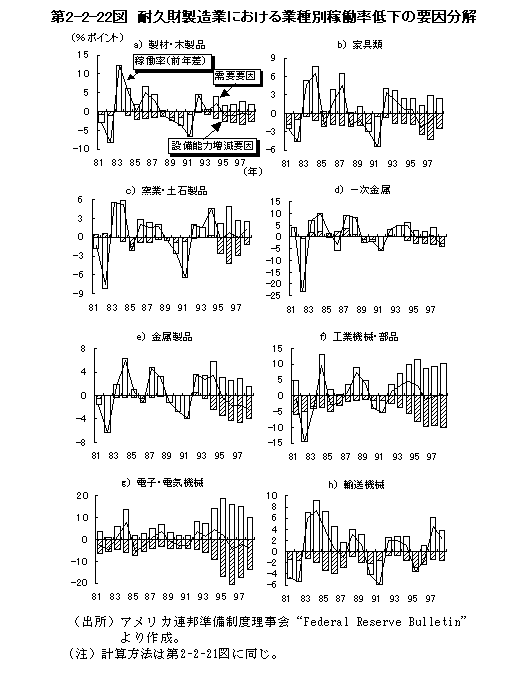
なお、労働生産性に関しては、次節でみるように、96年以降、労働生産性の上昇率が高まる傾向にあり、そのことが、年0.1%程度のインフレ抑制要因となった可能性がある(ただし、長期的には生産性が実質賃金の上昇に反映されるため、影響はない)。また、GDP統計上の問題により労働生産性が過小評価されている可能性が指摘されており(第3節参照)、そうであれば、物価を上昇させずに賃金を上げる余地がそれだけ存在すると考えられる(ただし、これも長期的に生産性が実質賃金に反映されれば中立的である。また、この場合真のGDPも現在より大きくなる)。
- 注1 バイアスは基本的には次回FOMCまでの金融政策運営の方向性を示すもの。例えば、「引締め」バイアスは、金利を変更するとすれば引上げの方向であることを示している。
- 注2 例えば、99年9月の講演で、サマーズ財務長官は、90年代の景気拡大の主要因の一つは、政府が連銀の独立性を尊重したことであると指摘。
- 注3 軍事費の削減は、短期的には成長率を押し下げる(93年のCEA報告によれば、92年について、直接効果だけで0.4%ポイントの押し下げ効果)。
- 注4 電力業では、1992年の総合エネルギー法(the Comprehensive National Energy Policy Act)が、通信業では1996年のコミュニケーション法(the 1996 Communication Act)が、それぞれ完全に施行されたと仮定して試算(OECD“Report on Regulatory Reform”1997)。
- 注5 保険者が医療機関とあらかじめサービス内容や費用について契約することにより、医療の質を維持しつつ、医療費の抑制を組織的に行う新たな民間医療保険プラン。従来、企業が利用していた団体医療保険に比べ、保険料が安価。
| 第1章 世界経済の現況 | 第2章 アメリカ経済の長期拡大の要因と課題 | 第3章 物価安定下の世界経済 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 |
| 概観 | アメリカ | 欧州 | アジア | 金融・商品 | 通貨・金融システム | 特徴 | 要因 | 生産性 | 課題 | 現状 | 要因 | 特徴 | 金融政策 |

