第1章 第5節 国際金融・商品市場動向
| 第1章 世界経済の現況 | 第2章 知識・技能の向上と労働市場 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 |
| 概観 | アメリカ | 欧州 | アジア | 金融・商品 | IT | アメリカ | 欧州 | アジア |
第5節 国際金融・商品市場動向
1 為替市場の動向
米ドル(実効相場)は、1999年7月以降は対円で大きく減価したこと等から減価基調となっていたが、99年末ごろからは、米株式市場(特にナスダック市場)の活況を背景に増価基調に転じた。以下では、まず昨年末からの米ドルの変動について記述する。次に、ユーロは、99年1月の導入以来ほぼ一貫して減価基調で推移しているが、この動向について記述する。最後に、97年7月のタイ・バーツ危機に端を発するアジア通貨・金融危機からアジア経済が全般的に回復してきている東アジア各国の通貨についてその動向を概観する。
(米ドルの動向)
対円での動きをみると、99年7月以降、日本の99年1~3月期の経済成長率が大幅なプラスであったことや、日本の株価が大きく上昇した一方で米株価は長期金利上昇に伴って相対的に伸び悩んだこと等からドル安基調が続いていたが、99年末ごろからは、米株価(特にナスダック総合指数)の上昇、2000年1月初の通貨当局の円売り介入の実施、米実質GDP成長率が高い伸びを示したこと及びそれに伴う金利差拡大懸念等から増価基調で推移した。5月に入ってもアメリカの景気の過熱感が収まらず、同月16日の連邦公開市場委員会(FOMC)で利上げが決定されたことや日本のゼロ金利政策早期解除の思惑等から減価する場面もみられたが、その後も日本の大手百貨店の民事再生法申請等に伴う日本の景気に対する不透明感や米格付け会社ムーディーズによる日本の国債格下げ等から増価基調が続いている。
一方、対ユーロでは、99年8~9月にかけてドイツの景況感指数上昇やグリーンスパンFRB議長の株価に対する警戒発言等から減価したものの、10月からはドイツの経済統計が予想を下回ったことや、イギリス大手通信会社ボダフォン・エアタッチによるドイツの大手通信会社マンネスマン買収に対してドイツ政府が否定的な態度をとったことが投資家の不安を招いたこと等から増価基調で推移した。2000年に入ってからも、欧米間の景況格差や金利格差、欧州企業による相次ぐ米企業のM&A等から増価基調で推移し、5月にはオーストリアやイタリア等ユーロ圏諸国での政治的安定への不透明感も重なり、増価し続けた。7月に入り、アメリカ景気の減速感やユーロ圏の景気拡大への期待等から減価したが、7月下旬以降再び増価し始め、9月20日には、0.84ドル台/ユーロの高値を付けた。その後、同22日の日米欧のユーロ買い協調介入により一時減価したものの、10月下旬に史上最高値(0.82ドル台/ユーロ)を付け、依然軟調に推移している(第1-5-1図)。
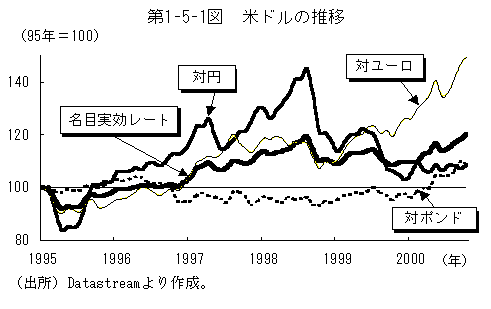
(欧州通貨の動向)
欧州中央銀行(ECB)発表のユーロの名目実効レート(99年1~3月期=100)をみると、99年1月のユーロ誕生以来ほぼ一貫して減価基調で推移した。2000年7月に入り、アメリカ景気の減速感やユーロ圏の景気拡大への期待などから増価したが、7月下旬以降再び減価し始め、9月20日には、0.84ドル台/ユーロの安値を付けた。その後、同22日の日米欧のユーロ買い協調介入により一時増価したものの、10月下旬に史上最安値(0.82ドル台/ユーロ)を付け、依然軟調に推移している。
このようなユーロ安の背景には、(1)欧米間の景況格差の他、(2)ユーロ圏の為替政策に関して金融・為替当局の信認が確立されていないと市場がみていること、(3)ユーロ圏の構造改革の遅れ等から海外への資本流出が続いていること、等が指摘されている。また、イギリス・ポンドの対ユーロでの増価基調も長期化しており、域内外の企業には生産拠点をイギリスから東欧などに移すべく戦略を見直す例も見られる。ブレア首相はユーロ参加に向け条件整備を急ぐ姿勢を表明しているが、2001年中にも予想される総選挙後に国民投票によって決定されるユーロへの参加の賛否が注目される(第1-5-2図)。
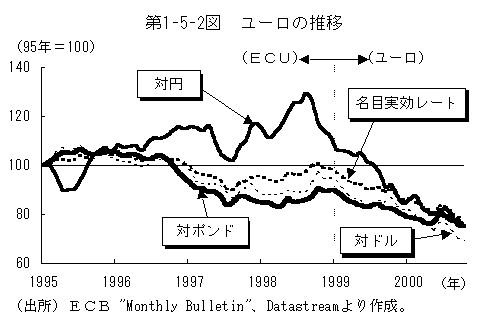
(アジア通貨の動向)
東アジア各国の対米ドル為替レートの推移をみると、99年に入ってからはおおむね横ばいで推移していたが、アジア経済が全般的に回復に向かう中で99年10月ごろから各国通貨は増価した。2000年に入ってからは、経済が好調な韓国、台湾などの通貨は増価基調で推移しているものの、政治的混乱を背景にインドネシア・ルピア、タイ・バーツ、フィリピン・ペソの3通貨は不安定に推移している(インドネシア・ルピアが2000年10月末現在で、99年1月初比16.0%減価、タイ・バーツが同16.8%減価、フィリピン・ペソが同23.5%減価)。
また、政権が安定し、国内経済も良好であるシンガポールのドルも、これら3通貨につられて減価している(2000年10月末現在で、99年1月初比5.8%減価)。インドネシアとフィリピンでは経済状況が十分でないにもかかわらず、通貨安に対抗するために金利を引き上げざるを得なくなるなどの悪影響も出ている(第1-5-3図)。
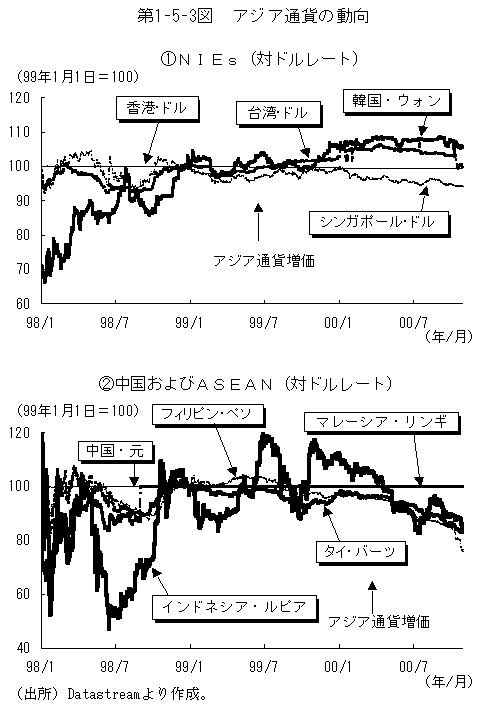
(アメリカを中心とするマネーの流れの変化)
国際的なマネーフローの動きは、90年代後半以降、日本や欧州で金融緩和が推進される環境の下で一段と活発化している。その要因としては、好調なアメリカ経済を背景とした需要の拡大、アジア地域の経済回復、ユーロ市場の発達、規制緩和の進展、金融技術の発達(デリバティブ取引の拡大)等が挙げられる。このようなグローバル・マネーフローの拡大は、円滑かつ効率的な資金調達・運用の可能性を広げ、世界経済の成長に寄与してきたといえる。
近年のグローバル・マネーフローの動きをみてみると、欧州や日本等からの余剰資金がアメリカに流入し、アメリカの経常収支赤字や貯蓄不足をファイナンスした上で、各地域へ再配分されるという構図が続いてきた。特に、欧州からアメリカへのマネーフローが金額的にも大きく、欧米間の景況格差、欧州での構造改革の遅れなどを背景として、ユーロ安をもたらした(第1-5-4図)。
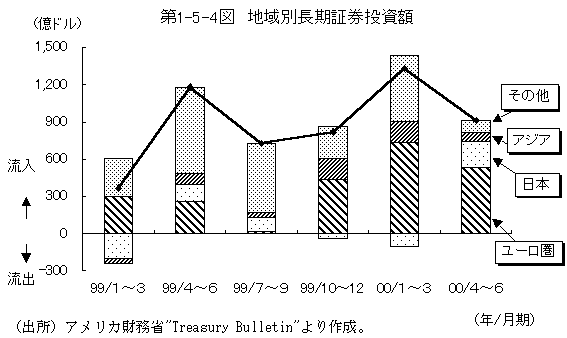
アメリカに関連するマネーフローは、昨年後半から2000年3月まで増加し続けてきたが、4月14日のアメリカ株価暴落をきっかけに4月から流入・流出とも減少している(第1-5-5図)。これは、アメリカが財政の黒字化を背景として国債の発行を減らしていることに加えて、アメリカ経済の減速の兆しやハイテク株を中心とした株式市場の調整を受けて、内外の投資家が慎重な態度を取り始めていることが原因だと考えられる。
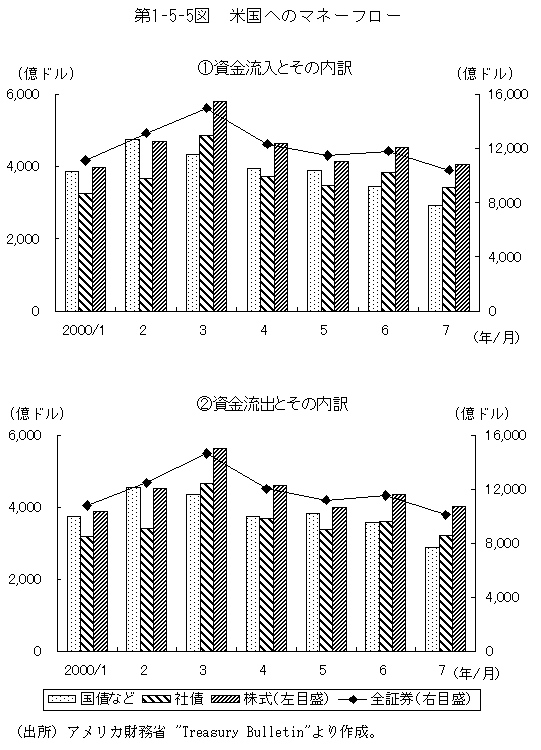
アメリカにマネーが集まり、アメリカがその資金を各地域に還流させるというグローバル・マネーフローの構図が急激に変化するとは考えにくいものの、資金のアメリカ回帰の動きが弱まれば、グローバル・マネーフローの縮小がさらに続くなかで、アメリカの巨額な経常収支赤字をファイナンスすることが困難になり、ドルが下落する可能性もある。また、欧州の景気拡大や通貨統合の深化等によりマネーがアメリカから欧州へ逆流するようなことになれば、ユーロ高をもたらすことも考えられる。
2 債券市場の動向
(アメリカの長期債の動向)
アメリカの長期金利は、景気の過熱や労働市場のひっ迫感から生ずる将来のインフレ懸念を反映して99年に入ってからは上昇傾向で推移していた。しかしながら、2000年の1月に、アメリカ財務省が300億ドル規模の国債買戻し計画を発表すると、国債の供給量が減少するという期待が働き、相場は上昇傾向に転じた(利回りは低下:第1-5-6図)。また、2月には2000年度の国債入札計画が明らかにされ、その中で30年債の発行量が今後半減することが明らかなり、更に相場が上昇したことから30年債の指標性が薄れることになった。30年債の利回りは急速に低下し、10年債との利回りスプレッドは逆転した。社債との利回り差も拡大している(第1-5-7図)。また、9月末現在の金利の期間構造をみると、国債利回りでみた利回り曲線は右下がりになっているが、スワップ金利や政府保証債の利回りでみると、よりフラットな形状となっており、アメリカでは市場における先行きのインフレ懸念が2000年初よりも抑制されつつあることを表している。(第1-5-8図)。
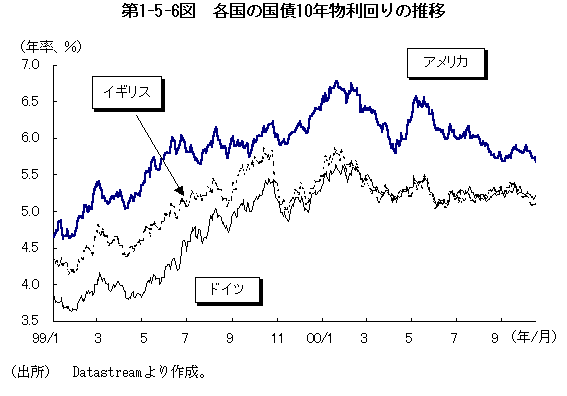
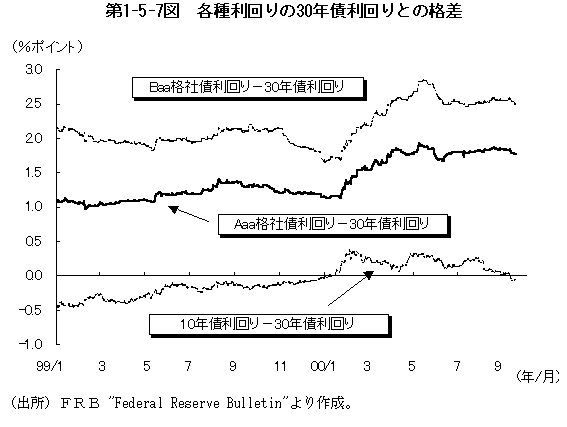
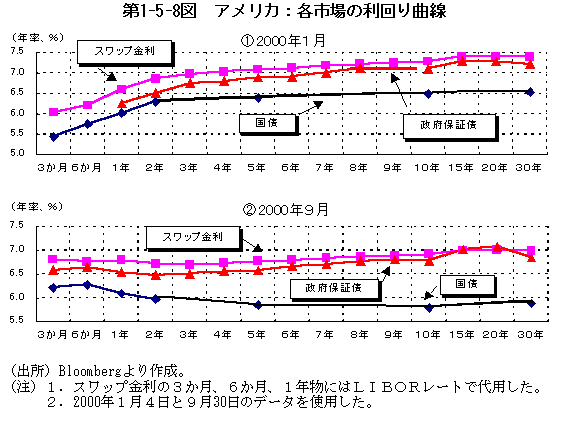
(欧州の長期債の動向)
欧州の長期金利も、アメリカと同様の動きで推移している。99年は、ユーゴ情勢の不安定化や、ユーロ安の進行によるインフレ懸念から長期金利は上昇傾向で推移した。2000年に入ってからは、アメリカの長期金利低下に追随するようにドイツ10年債、イギリス10年債ともに利回りは低下し、また、2月には一部のハイテク株を中心に株価が急落したため、安全資産である国債市場に資金が流入し相場は堅調に推移した(第1-5-6図)。9月末での利回り曲線をみると、ドイツでは、ユーロ安や原油価格高騰などにより目先のインフレ懸念が強く、短中期国債の利回りが上昇したことから、形状はフラットなものになっている。また、イギリスでは97年半ば以降、逆イールドの状態が続いているが、個人消費や設備投資の伸びが抑制されつつあることから、利回り曲線の形状はフラットに近づいてきている(第1-5-9図)。
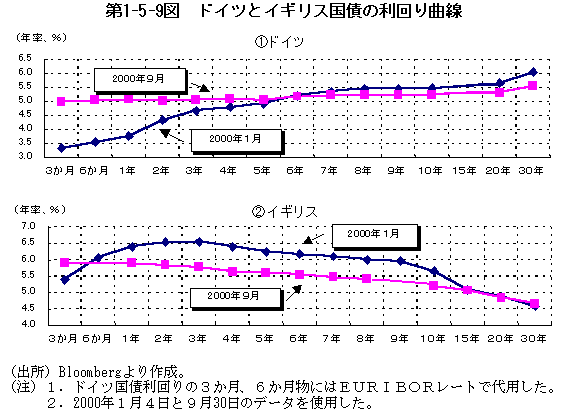
3 株式市場の動向
(欧米の株式市場の動向)
欧米の株価は、98年の秋にロシアを発端とする世界的な金融収縮の動きから、一時的に大きく下げる場面があったものの、まもなく上昇トレンドを取り戻し、各国の代表的株価指数はともに99年末から2000年3月にかけて、史上最高値を更新している。しかしながら、2000年1月半ば以降の株価の動きは軟調になり一進一退で推移した。オールドエコノミーと呼ばれる旧来型の株式からニューエコノミー銘柄と呼ばれるインターネットを中心としたハイテク関連株に投資資金が流れ、その結果、旧来型の産業の比重が高いダウ・ジョーンズ工業株30種平均やS&P500総合指数(以下S&P500指数)と、ハイテク関連株が指数の中心であるナスダック総合指数(以下ナスダック指数)は逆の動きを示すことが多くなった(第1-5-10図)。ハイテク関連株と主要銘柄株の株価は、相関が弱まっており、ドイツを除いて欧州の株価も概ね似たような推移となっている(第1-5-11表)。
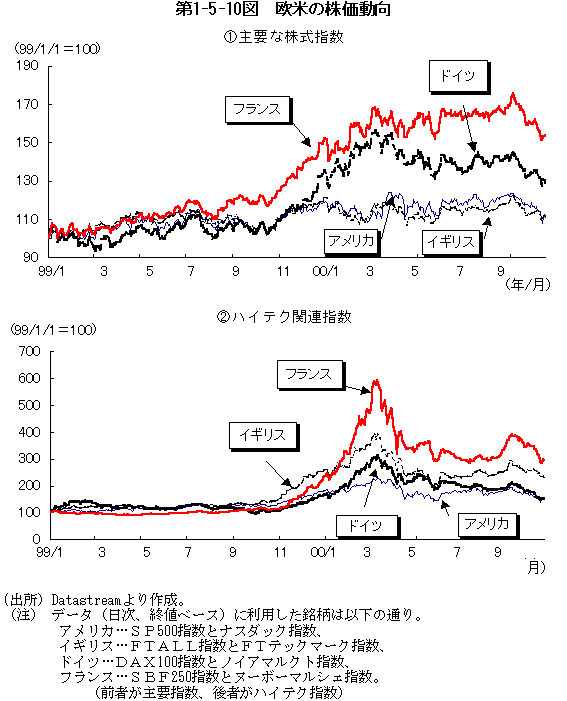
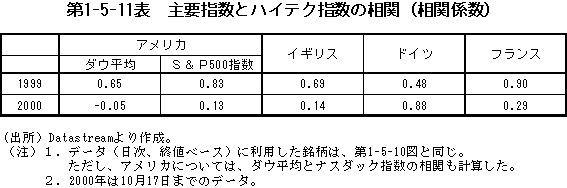
ハイテク株指数をみると、ナスダック指数は2000年に入ってからも上昇を続け、3月には5,000ポイントを突破し過去最高値を更新した。ナスダック指数は99年12月27日に4,000ポイントを突破してから10週間余りのうちに次の大台を突破したことになる。この間の投資家の株価上昇への期待は行き過ぎであったと思われ、ナスダック指数は5,000の大台を突破した翌日からバイオ関連や通信を中心に下げ足を早め、急落した。また、欧州の新興市場を対象とした指数もナスダック指数と似たような値動きをみせ、騰落率はナスダック指数よりも大きい。欧州のハイテク関連銘柄はアメリカよりも少ないため、投資資金が集中しやすいからと考えられる。
その後のハイテク指数の動向は、堅調に推移していたが、9月下旬に有力ハイテク企業の業績見通しの下方修正が相次いだことなどから、ナスダック指数は再び下落傾向で推移している。また、このところのハイテク、ベンチャーブームを反映して、アメリカでの公募増資発行は、98年秋を除けば堅調に推移している。しかし、成長有望企業等の資金調達手段である新規株式公開(IPO:Initial Public Offering)は、2000年以降、その中止件数が増加しており、これは相場の急変動を反映した結果であると考えられる(第1-5-12図)。イギリスやドイツにおいても、株価の急落後に新規株式公開を中止する企業が出てきている。
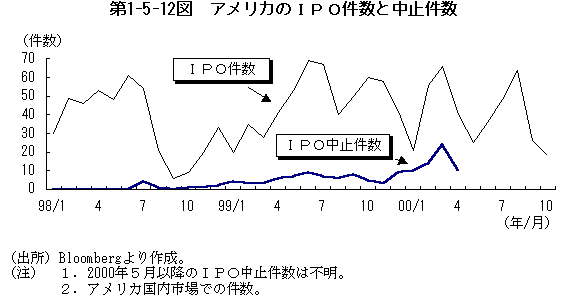
(ハイテク株急落の要因)
ハイテク関連産業では先行投資が重く、配当よりも内部留保によって新たな投資を行うことに重点が置かれる。従来型産業と配当性向を比較すると、通信部門を除けば総じて低く、投資家はインカムゲインに期待することができない(第1-5-13表)。投資家が求める利回りを「インカムゲイン+キャピタルゲイン」とすれば、株価はインカムゲインよりもキャピタルゲインに対する期待が高いという構造になっていることが分かる。また、株価が利益の何倍まで買われているかを示す株価収益率(PER:Price-Earning Ratio)は、過去と比較して高水準で推移している(第1-5-14図)。

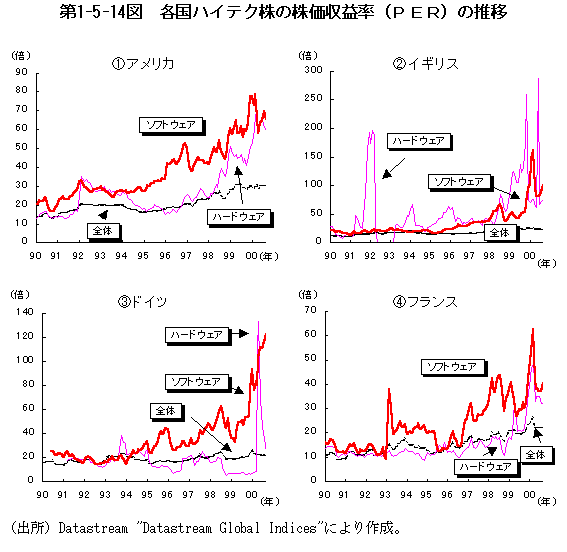
ハイテク関連株価と旧来型産業の株価を評価する基準は異なることから、同一に評価することはできない。しかし、資産価格の均衡値からのオーバーシュートは、しばしば過剰投資を引き起こし、資本の効率性及び財務体質を弱めることになる。投下した資本が付加価値を生み出し資本の生産性を高めることができれば、将来のインカムゲインが期待できることから、株価を支える裏づけとなる。逆に、新規投資が付加価値を生み出さないと投資家が判断した時点で株価は急落する可能性がある。今回の急落は、赤字決算を続けている一部のインターネット関連企業に対して、投資家がその将来に疑念を持ち始めたことが引き金の1つとなったと考えられる(第1-5-15図)。
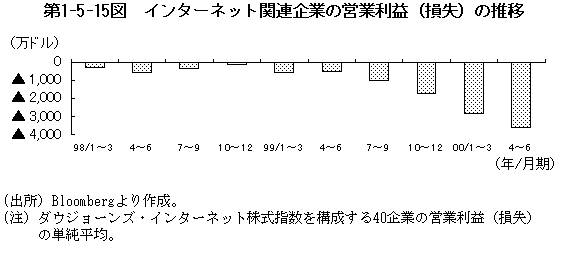
(アメリカの株高を支えた要因)
ハイテク関連株は調整局面を迎えたが、世界的な好況を反映して、株価は依然として高水準で推移している。90年代後半以降、アメリカの株高を支えた要因としては、低金利や堅調な企業収益の他に、良好な需給を挙げることができる。M&Aの活発化が株式需要を高める一方、自社の株価を高めるための自己株式の消却などが供給を減少させたと考えられる。
M&Aは近年件数が増えるとともに、今までにない巨大企業を対象とした規模の大きなものがみられるようになってきている。株式交換などの手法を用いたM&Aが大半を占めるが、このタイプのM&Aの買収プレミアム(買収価額/時価)は、このところ上昇傾向にあり、株価を吊り上げる要因となっている(第1-5-16図)。また、自社のROE(株主資本利益率)やEPS(一株当たり利益)を高めるため、企業は発行株式の買入消却を進めてきており、企業の株式純発行はマイナスで推移している。
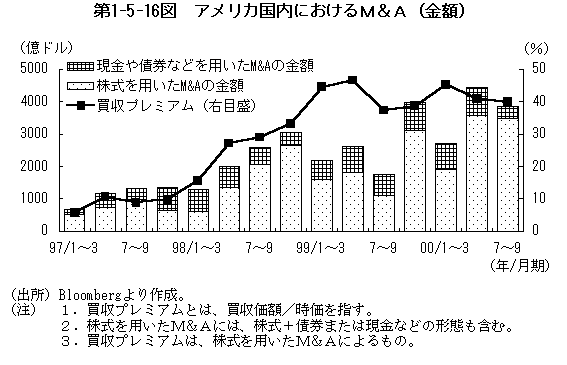
(欧州取引市場統合の動き)
99年のユーロ誕生以降、取引コストの削減など顧客の利便性向上の観点から、汎欧州市場の創設の実現が望まれていたが、各取引市場間の主導権争いなどから、先行きは不透明なものとなっている。
2000年3月にパリ、アムステルダム、ブリュッセルの3市場は合併を発表し、新市場を「Euronext」とすることで合意し、9月に正式に発足した。一方、ロンドン取引所とドイツ証券取引所は、5月に対等合併して新会社を設立することを発表し、名称を「iX」とすることで合意した。両陣営ともに他の市場との提携交渉を行うなか、8月にはストックホルム市場を保有するOMグループが、ロンドン取引市場に対して敵対的な買収を申し込んだことから混乱が生じ、「iX」計画は白紙撤回された。
(アジア株式市場の動向)
アジアの主要な株式指数は、景気回復を背景に企業収益が改善したことなどから99年にはいずれも大きく上昇した。2000年に入ってからは、世界的に株価の調整局面を迎えたことから、多くの指数が下落傾向で推移している(第1-5-17図)。アジアNIEsのハイテク関連の株価指数をみると、99年の下半期から2000年1~3月期にかけて急速に上昇したが、その後はアメリカのナスダック指数に歩調を合わせるように急落した。しかし、急落後もシンガポールを除いて株価は依然高水準を保っており、アジアNIEsにおけるハイテク部門の期待が高いことが分かる(第1-5-18図)。一方、通貨危機の影響を大きく受けた韓国、タイ、マレイシア、インドネシアの4か国は、過剰な不動産関連融資などによる多額の不良債権で苦しんでいるが、各国の不動産関連部門の株価をみると、ピークの水準からは1~6割程度の水準となっており、この部門に深い傷跡を残していることがわかる(第1-5-19図)。
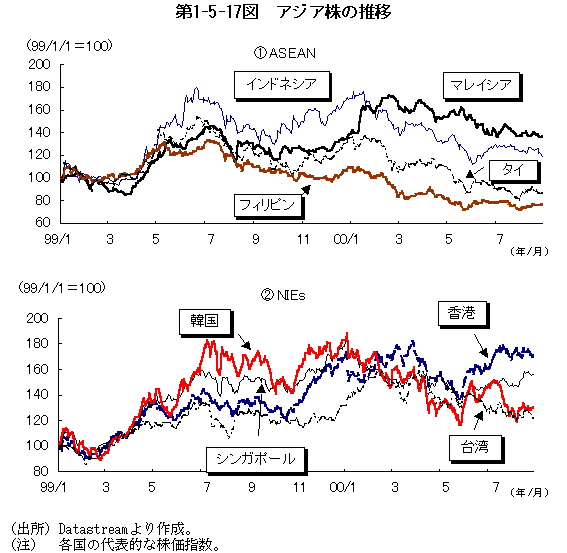
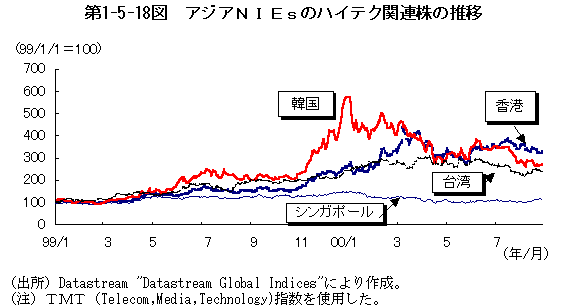
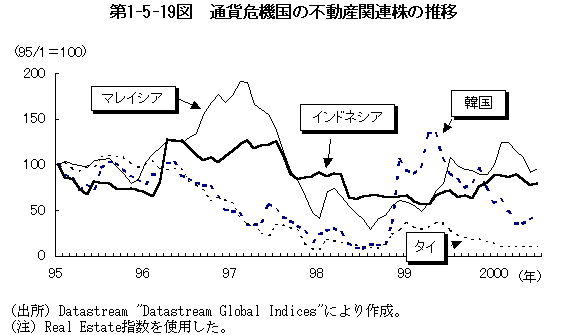
4 高騰した原油価格
(1)国際商品価格:99年半ばから上昇基調で推移
17品目の主要な商品先物価格から算出されるCRB(Commodity Research Bureau)商品先物指数(1967年価格=100)の動きをみると、生産過剰やアジア通貨・金融危機による需要減退の影響等により、99年2月末にほぼ四半世紀ぶりの低水準である183ポイント割れを記録した。99年半ばまではほぼ横ばいで推移していたが、99年後半からは、世界的な景気拡大傾向から上昇基調に転じ、2000年9月(月平均値)現在で228ポイント台にまで回復している(第1-5-20図)。
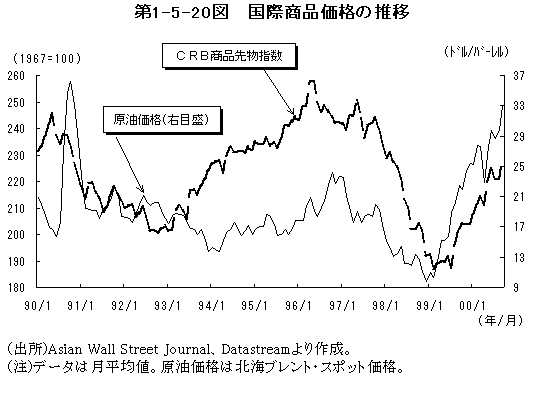
2000年の動きを商品別にみると、大豆、小麦、トウモロコシなどの穀物は、過剰在庫がやや減少したことから、一時は下げ止まりの動きがみられたが、2000年も豊作が見込まれることなどから、総じて弱含んでいる。貴金属では、金が、99年10月上旬に欧州の中央銀行などが保有金の売却を制限することを発表したことから、一時急上昇したものの、その後は下落基調で推移している。非鉄では、銅が、アジア地域の経済回復等により、99年から上昇基調に転じている。綿花は、生産量の減少により在庫水準が低下したことなどから、総じて上昇基調で推移している。砂糖は、世界的な生産量の減少が見込まれることなどから、2000年に入り急上昇している。コーヒーは、主要生産国のブラジルで豊作が見込まれることなどから、下落している。
(2)原油価格:湾岸危機以来の水準まで上昇
原油価格(北海ブレント・スポット価格)は、アジア通貨・金融危機の発生でアジア地域からの需要が減退したこと等により、98年末から99年初頭にかけ一時10ドル/バーレルを下回る水準まで落ち込んだが、99年3月のOPEC総会で追加減産が合意されたことを契機に上昇基調に転じた。その後は、98年の経済・財政状態の悪化によりOPEC加盟国が合意された減産量を比較的遵守したことや、メキシコやノルウェーなどの非OPEC加盟国が協力を表明したこと(1)、アジア地域からの需要が回復に向ったことなどから上昇を続け、2000年3月には湾岸危機以来となる30ドル/バーレルを上回った。2000年10月現在でも、先行きの需給ひっ迫懸念を主因に、30ドル/バーレル前後の高値で推移している。
1)今次価格上昇局面の特徴
1.価格動向の特徴
原油価格がこのように高騰したのは、第一次石油危機(1974年)、第二次石油危機(1979年)、湾岸危機(1990年)以来のことである。今回の価格上昇局面を過去の高騰局面と比較すると、今次上昇局面は、上昇期間が非常に長いという特徴があり、上昇を始めてから約18か月程度が経過した2000年8月現在でも、なお上昇局面を完全に脱したとはいえない。上昇幅についても、価格高騰前(99年2月)からの上昇率が約3倍を記録し、第一次石油危機(約3.5倍)に次ぐ大きさとなっている(第1-5-21図)。ただし、これは、98年の大幅な下落からの反転を含むためであり、下落前の水準からみた上昇率は2倍程度である。また、実質価格(2)でみた価格水準は相対的に低いものとなっている。
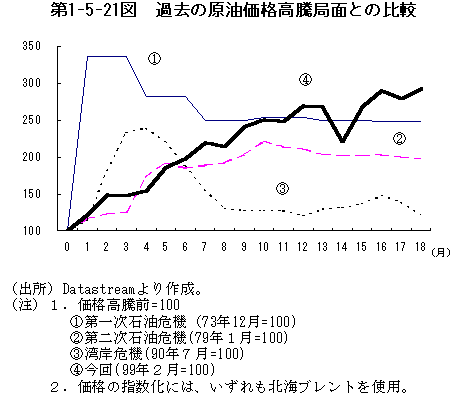
2.価格形成の特徴
原油価格を形成する主導権は、1960年代に欧米の国際石油資本(メジャー)が握り、1970年代にはOPECへ移行した。その後は、1983年に米国で原油の先物市場が創設されたこともあり、それまでの供給側主導の価格形成が崩壊し、市場に参加する多数の取引業者の動向が原油価格に大きく影響を及ぼすようになった。1990年代に入ってからは、先物市場で世界全体の原油需要量を遥かに凌駕する規模の取引(3)が行われていることなどから、この傾向はさらに強まっている。
このような中、市場は、当面の需給動向だけでなく、OPEC諸国の動向、とりわけOPEC総会での増減産に関する決議を注視するようになっている。これは、OPECの生産シェアや埋蔵量シェアなどが1990年代に入り再び高まっていることに加え、2000年に入り非公式ながらプライスバンド制(4)の導入を示唆するなど、OPECの市況に応じた生産調整を模索する動きが活発化していることによる。ただし、プライスバンド制については、機動的な増減産に対応できるだけの充分な余剰生産能力を擁する国は加盟国の一部にすぎないことや、増減産協定に参加していないイラクの情勢が不透明であることから、定着に至るかどうかは不確実なところが多い。
2)今次価格上昇の要因
過去3回の価格高騰と異なり、今次価格上昇は戦争や革命などの政治的な要因に起因するわけではなく、基本的には需給要因によるところが大きいが、それに限らず様々な要因が複雑に絡み合っている。
(短期的要因)
1.原油需給のひっ迫
今次価格上昇をもたらした要因としては、需給バランスを表す原油消費国の原油・石油製品在庫(5)が歴史的な低水準を記録したことが挙げられる。このような低水準をもたらした要因が、供給面、需要面の双方にみられる。
供給面では、99年にOPEC加盟国が大幅な減産を実施した。OPEC加盟国は、過去にも幾度となく減産を実施しているが、今回はOPEC加盟国の減産意欲が非常に強く、生産実績と目標のかい離があまりみられなかったことから、生産能力を大きく下回る生産水準をほぼ1年近くも継続した(第1-5-22図)。加えて、OPEC加盟国の中でも豊富な埋蔵量を誇るイラクは、減産協定には加わっていなかったが、国連制裁下でほぼ一定量の生産量(輸出量)しか認められていなかった。一方、歴史的には、OPEC加盟国が生産を抑制するときには増産する傾向があった非OPEC加盟国が、99年はOPEC加盟国に同調して生産量を減少させた。今後については、原油価格が上昇に転じたことにより、比較的高コストな油田の開発活動も活発化することから、非OPEC加盟国の生産量の増加が見込まれ、2000年半ば現在、既に非OPEC加盟国の生産量は増加に転じている。
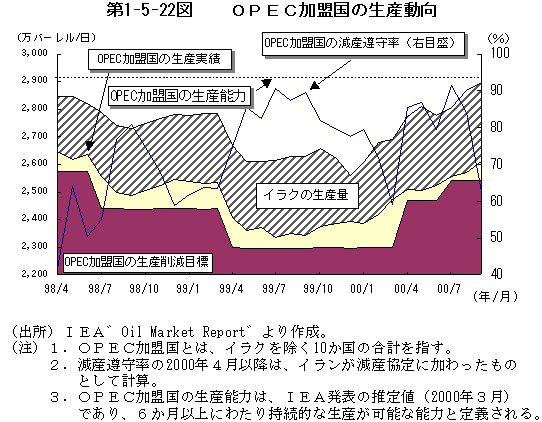
需要面では、99年後半以降に需要の増加傾向が顕著となっていた。地域別に寄与度をみると、景気が急速に回復したアジア地域と好況を維持している北米地域の寄与が大きい。アジア地域の高度経済成長とともに、同地域が世界の原油需要に占めるシェアは1970年代から一貫して増大してきている(6)。
2.製品市場からの波及
石油製品の在庫不足を主因に石油製品価格が上昇している場合などには、石油精製業者が石油製品の需給ひっ迫を緩和すべく原料(原油)の調達に動くため、石油製品価格の上昇が原油価格に上昇圧力を与えることもある。石油製品の需要期を迎える前に、石油製品在庫の現況(もしくは予測)から製品在庫積み増しのための原油需要が喚起される場合もある。2000年前半に、OPEC加盟国の増産等で原油の需給が緩和に向ったにもかかわらず、アメリカにおいてガソリン価格の高騰や冬季の暖房油不足の懸念などが原油価格の高値推移を呼んだことはその一例である。アメリカの石油精製能力の増加率をみると、90年代半ば以降増加しているものの、98年を除き石油製品需要の増加率を下回って推移した(第1-5-23図)。石油精製設備の稼働率が90年代後半にはほぼフル稼働に近い水準で推移したことを考慮すれば、2000年には需要の増加に充分対応できるだけの石油精製設備が不足していた可能性が高い。つまり、大方の予想を上回る長期の景気拡大による石油製品需要の増加に比して、石油精製能力の拡張が相対的に緩やかに進められたことの影響が顕在化したと考えられる。
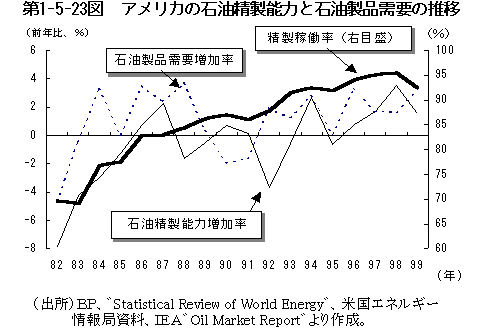
(中期的要因)
原油市場は、価格が下落すると油田開発が抑制され、供給が減ると価格が上昇に転じ、価格が上昇すると比較的高コストな油田の開発活動が促進され、再び価格が下落するというサイクルを繰り返すと指摘されている。このことは、掘削リグ稼働数の動向にも表れている。98年に価格が低迷したことから、99年の世界全体の掘削リグ稼働数が大幅に減少したが、2000年に入ってからは、稼働数は増加に転じている。
原油価格の下落が代替エネルギーへのシフトを遅らせたことに加え、先進国を中心に原子力発電所の新規立地が凍結されたことなどもあり、近年では代替エネルギー(原油以外の一次エネルギー)消費量伸び率が原油消費量伸び率を下回っている。これは、財政事情が厳しい途上国を中心に、相対的に安価なエネルギーである原油への選好が高まったことにもよると考えられる。
脚注
- 1 99年のOPECの生産シェアは約40%だが、これまでOPECの減産への協力を表明したことのある国(メキシコ、ノルウェー、オマーン、ロシア、エジプト、イエメン)を含めると、生産シェアは60%を超える。
- 2 OECDのEconomic Outlook 66(1999年12月)によれば、99年の実質原油価格は、第一次石油危機直後の水準にかろうじて達した程度にすぎない。
- 3 これには、いわゆるペーパーバレルと呼ばれ、実際のモノのやりとりに裏付けられた取引ではないものも含まれる。
- 4 OPECにおいて指標原油とされる7つの油種を平均したOPECバスケット価格で22~28ドル/バーレルというバンドを設定し、20日間連続でこのレンジを外れた場合、自動的に生産量の調整を行うシステムとされるが、詳細は明らかにされていない。
- 5 在庫統計は発表する機関によって異なり、どの機関の発表も推定であることに留意が必要である。
- 6 世界の原油消費量に占めるアジア地域のシェアは、16.6%(1974年)、17.5%(1979年)、20.8%(1990年)、26.8%(1999年)となっている。
5 原油価格の上昇が世界経済に与える影響
今次上昇局面は、過去3回の高騰と比べると、下落前の水準からの上昇率、実質価格水準とも低く、今のところ、世界経済へ与える影響はさほど大きくないものと考えられる。しかしながら、原油価格の高止まりは、物価上昇率を高め、景気にマイナスの影響を与えると懸念される。以下では、原油価格の上昇が世界経済へ与える影響として、物価への影響、実体経済への影響、通貨・金融面への影響に分け、検討を加える。
(1) 物価への影響
(一般物価への影響の低下)
国際原油価格が主要先進国の物価へ及ぼす影響は、傾向的に小さくなっている。アメリカ、フランス、日本における、国際原油価格の上昇1%当たりの(1)国内の石油製品価格、(2)国内消費者物価への影響について、それぞれ推計した(第1-5-24図(1)、(2))。まず、国際原油価格の上昇が国内石油価格へ与える影響は、各種規制緩和の進展や市場(売買・輸送・先物)機能の発達などが波及経路(タイムラグ)の縮小をもたらしたため、70年代、80年代には反応が急速に速まった。しかし、90年代以降は反応が総じてほぼ一定の水準に保たれている。次に、国内石油価格の変動が国内消費者物価上昇率へ与える影響は、70年代の石油危機後に経済の石油依存度が低下するにつれ次第に低減し、2000年は70年代を大きく下回っている。つまり、2000年には、70年代と同程度の石油価格の上昇を受けたとしても、急激な物価上昇をもたらす可能性は低くなっているといえる。
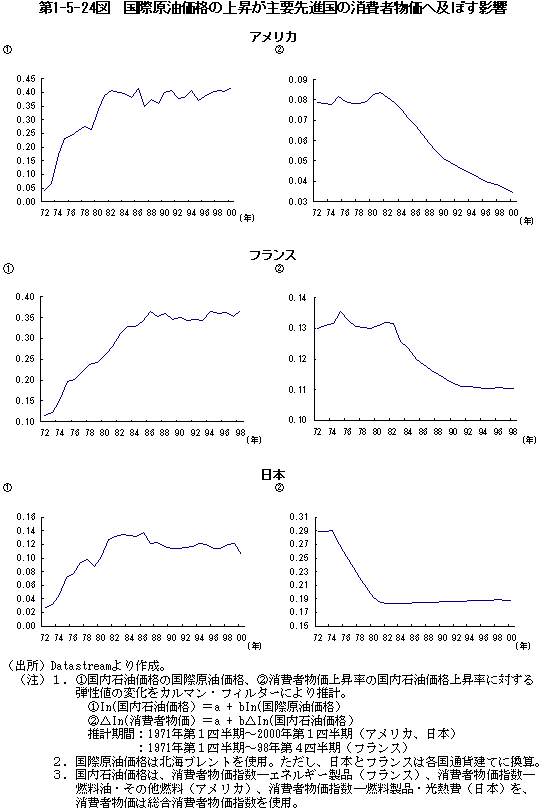
(他の一次産品価格の落ち着き)
過去3回の価格高騰は、戦争による物資の絶対的な不足もあいまって、原油以外の原材料の価格も大幅に上昇した。原油を除く一次産品価格指数の動きをみると、湾岸危機時は、多国籍軍の圧勝により短期で戦争の終結を迎えたことから、顕著な上昇はみられなかったものの、第一次、第二次の石油危機時には、ほぼ原油価格と連動するように急騰した。今次上昇局面では、他の一次産品価格は上昇傾向こそ示しているが、その上昇テンポは過去の上昇局面と比べ緩やかなものとなっており、物価上昇への影響を軽微なものにとどめる一要因となっていると考えられる。
(製品価格の上昇)
ガソリンや暖房油は国民生活を支える重要物資であり、それらの価格上昇には依然留意が必要である。特に、通貨の減価を伴う場合には、上昇が大幅なものとなり、国民生活やエネルギー多消費産業に対する打撃が大きくなる。
例えば、ユーロ圏(6月)では、エネルギー価格が消費者物価上昇率を1.3%押し上げており、アメリカ(7月)の0.8%に比べて影響が大きくなっている。これは、ユーロが1年前に比べて約15%減価していることが輸入価格をさらに上昇させているためと考えられる。ヨーロッパで抗議デモが発生した背景としては、価格上昇率が高いことに加え、ヨーロッパではもともとガソリン小売価格に占める税の割合が高く、原油価格上昇に対して負担感が高まったことが挙げられる(第1-5-25表)。
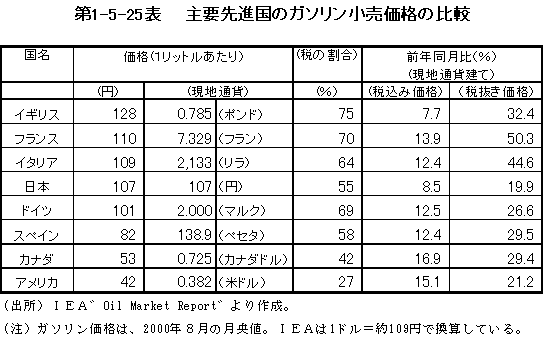
(2)実体経済への影響
(所得移転を通じた需要抑制)
原油価格の高止まりは、原油消費国から原油生産国への所得移転効果を伴う。具体的には、企業の原材料調達コストの上昇を通じて企業収益を圧迫するとともに、石油製品などの価格上昇を通じて家計の実質所得を減少させることになる。
企業収益の悪化は、企業の設備投資意欲の減退を引き起こし、所得の減少や株価の下落を通じて、消費の抑制へと波及する。株価は企業収益の期待収益率を反映しているため、企業収益見通しの下方修正が発表された場合には、実際の企業収益が悪化する前に、期待成長率の低下を通じて株価は下落し、設備投資や消費が抑制される。例えば、2000年9月には、原油価格の高騰に加え、ユーロ安の影響もあいまって、アルミ、化学の大手企業や航空会社など、燃料価格高騰の影響を受け易い企業の株価を中心に、アメリカの株式市場は軟調な展開となった。今のところ、実体経済への影響はさほど大きくないものの、今後も企業収益見通しの下方修正が相次いだ場合には、株価下落を通じて実体経済へ悪影響を及ぼすことが懸念される。
エネルギー製品は生活必需品ということもあり、エネルギー需要の価格弾力性は低い。したがって、原油価格の上昇は、名目消費支出に占めるエネルギー製品比率の上昇を招き、エネルギー以外の消費を圧迫することとなる。原油価格の上昇が一時的なものであり、やがては下落するという期待感が醸成されている場合には、実質可処分所得の減少に比して、消費が抑制されないため、消費性向は上昇する。実際、アメリカでは、実質消費の伸びは減速しているものの総じて実質可処分所得の伸びを上回っていることから、消費性向は上昇傾向にある。しかし、原油価格の高止まりが長期間に及び、消費者が現在の高値は当面続くのではないかと考え始めると、消費がこれまでにも増して抑制される可能性もある。
(原油原単位からみた影響の大きさ)
実質GDP一単位当たりの原油消費量(原単位)をみると、省エネルギー指向や産業のソフト化が進んだ結果、原単位は、主要先進国を中心に過去の高騰局面と比べ大幅に低下していることから、原油価格の上昇が主要国の実体経済へ与えるインパクトは相当程度弱まっているといえる(第1-5-26表)。

OECDの試算によれば、原油価格が急上昇した場合、一定のタイムラグを経た後、実体経済への悪影響が顕在化する。アメリカ経済に比べ原油依存度が相対的に高い日本経済やEU経済では、その影響が大きくなっている(7)。また、アジアNIEsでは、原油を多量に消費する素材型産業などの比率が相対的に高いことや、代替エネルギーへの転換を柔軟に行えない財政事情を抱えていることなどにより、原油依存度(あるいは輸入依存度)がむしろ高まっている国もある(前掲:第1-5-26表)。これらの国では、企業収益の悪化等に起因する実体経済への悪影響が相対的に大きくなる可能性があり、その動向には注意を払う必要がある。
(3)通貨・金融面への影響
原油価格の上昇は、貿易収支の改善を通じて産油国の資産を増加させる。これがオイルマネーと呼ばれるものの源泉であるが、その規模を正確に把握することは困難である(8)。過去の高騰局面においては、貿易面では、インフラやプラントなどの建設、兵器などの輸入、資本面では、外貨準備の積み上げのほか、企業買収や株式取得、不動産や市況商品への投機に向う動きがみられた。こうした産油国の行動は、原油高による先進国の貿易収支の悪化を補う面もあるが、物価上昇圧力を高めたり、金融・通貨面での不安定要因ともなった。
今次上昇局面は、産油国は、原油価格の低迷した時期に減少した外貨準備高の積み上げや巨額に膨れ上がった負債の返済を優先しているものと考えられるが、一部に先進国の資産市場へと向う動きが活発化する兆候もみられ始めている。例えば、2000年に入ってからは、OPEC加盟主要国を含む石油輸出国のアメリカ証券市場への株式投資や国債投資が大幅な買い越しとなっており、OPEC加盟国の通関ベースの輸入増加率(ドルベース)についても、99年半ばからはマイナス幅が縮小している(第1-5-27表)。
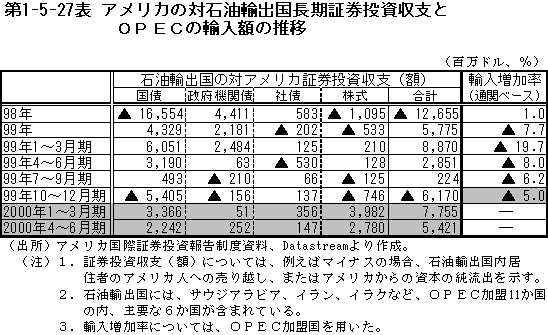
このような中、世界最大の原油輸入国であるアメリカでは、原油・石油製品の輸入増加を主因に、99年以降は貿易収支赤字が急拡大している。それにもかかわらず、米ドルの実効レートが上昇しているのは、米国市場を経由するマネーフローのためと考えられ、産油国のこうした行動がそれを支える要因の一つとなっている可能性がある。
脚注
- 7 2000年9月に開催されたIMF(国際通貨基金)、世界銀行との合同会議の際に、OECDは原油価格高騰の加盟国経済への影響を分析したレポートを公表した。それによれば、OECD加盟国の輸入平均原油価格が33ドルの水準を維持した場合、2001年の加盟国経済へ及ぼす影響として、GDP成長率の鈍化(アメリカ▲0.3%、日本▲0.6%、EU▲0.5%、OECD加盟国全体▲0.4%)と消費者物価の上昇(アメリカ0.5%、日本0.6%、EU0.8%、OECD加盟国全体0.7%)を挙げている。
- 8 OPEC加盟国の輸入、経常収支、資本の動向および対外資産内容はすぐに判明しないため、簡単な想定を置いた概算等で推測する必要がある。前提条件を、(1)原油価格:40ドル/バーレル程度、(2)比較対象:92~95年頃の15~20ドル/バーレルのレンジ、(3)OPEC加盟国の原油生産量:約2,700万バーレル/日(イラクを含めると約3,000万バーレル/日)と仮定した場合、オイルマネーの年間金額の概算は約2,000億~2,700億ドルとなる。
| 第1章 世界経済の現況 | 第2章 知識・技能の向上と労働市場 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 |
| 概観 | アメリカ | 欧州 | アジア | 金融・商品 | IT | アメリカ | 欧州 | アジア |

