第1章 第3節 景気が拡大するヨーロッパ
| 第1章 世界経済の現況 | 第2章 知識・技能の向上と労働市場 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 |
| 概観 | アメリカ | 欧州 | アジア | 金融・商品 | IT | アメリカ | 欧州 | アジア |
第3節 景気が拡大するヨーロッパ
1 西ヨーロッパ:課題の多かったユーロ導入2年目
(1)EU
1999年1月1日、EU加盟15か国のうち11か国において単一通貨ユーロが導入された。99年1月から通貨統合に参加した11か国(ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、オランダ、ベルギー、オーストリア、フィンランド、ポルトガル、アイルランド及びルクセンブルグ)は、総称してユーロ圏と呼ばれている。ユーロ圏の経済規模(99年)は、人口が約2.9億人、名目GDPが約6.5兆ドルであり、日本(約1.3億人、約4.3兆ドル)を上回りアメリカ(約2.7億人、約9.3兆ドル)に比肩する一大通貨圏となっている。
ユーロの導入により、EUの経済通貨統合(EMU:Economic and Monetary Union)は最終段階に入った。ユーロの導入は、欧州委員会主導の下で進められており、99年1月からは小切手や電子決済等、現金を伴わない取引においてユーロが使用可能となっている。2002年1月1日からはユーロ紙幣とコインが流通を始めることとなり、マルクやフラン等の各国通貨は遅くとも2002年6月末を最終期限として法定通貨の地位を喪失することとなる(1)。
以下では、ギリシャのユーロ圏加入決定などEUの深化と拡大に向けた動きや、ユーロ圏の経済動向を概観した後、ユーロ減価の要因とそれへの対応を考察し、ユーロ導入後2年目の課題を概観する。最後に西ヨーロッパ主要国の経済動向を各国ごとに概観する。
1)EUの深化と拡大
(ユーロ圏の拡大)
2000年6月、ポルトガルのフェイラで開催された欧州首脳会議において、ギリシャがユーロ圏に参加することが正式に決定した。1999年1月にEU加盟15か国のうち11か国(ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、オランダ、ベルギー、オーストリア、フィンランド、ポルトガル、アイルランド及びルクセンブルグ)で発足した単一通貨圏は、2001年1月1日から12番目の参加国を迎えることとなった。
ギリシャは、99年1月からのユーロ圏参加を希望しながらも、その審査が行われた98年時点においては、通貨統合参加のために財政健全化等を求めたマーストリヒト経済収れん基準を達成することができず、参加は見送られていた。以降、一層の財政健全化や政策金利の引下げ等、収れんのための政策努力を重ねてきた。2000年3月にはギリシャはユーロ圏参加を申請し、欧州委員会と欧州中央銀行(ECB:European Central Bank)によってそれぞれ基準達成が認められ(第1-3-1表)、フェイラ首脳会議において参加が承認された。
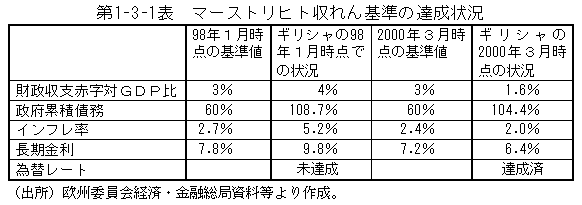
他のユーロ非参加国の動向をみると、デンマークでは2000年9月にユーロ参加の是非を国民投票に問い、反対53.1%、賛成46.9%という僅差で否決され、ユーロ参加は繰延べとなった(3)。スウェーデンやイギリスにおいても、政府レベルでは財政健全化等ユーロ参加に向けた努力は続いているものの、政治的な反対論が強く参加は容易ではない状況にある(イギリスについては後段で詳述)。
(EUの東方拡大に向けた組織改革)
ユーロ圏の拡大と同時に、EUの東方拡大に向けた動きも進展している。すでに98年からハンガリー、ポーランド、チェッコ、サイプラス、エストニア及びスロヴェニアの6か国との加盟交渉が行われている。加盟交渉国は、EU加盟国が基本条約に基づいて積み上げてきた法体系の総体である「アキ・コミュノテール」を受容し、一定の政治的・経済的基準を充足することが求められており、それぞれの交渉国において進展がみられる(ハンガリー、ポーランド、チェッコについては後段で詳述)。2000年2月には、さらにブルガリア、ラトヴィア、リトアニア、マルタ、ルーマニア、スロヴァキアとの加盟交渉が開始された。
現在の加盟交渉国が全てEUに加盟すると、現在15か国のEUは、27か国に拡大することとなる。加盟国の拡大は、合意の形成をより難しくさせることから、全会一致方式を原則とするEUの意思決定方式の見直し等が必要と指摘されるようになっている。2000年7月からのEU議長国フランスの主導の下、アムステルダム条約からニース条約制定に向けて機構改革の議論が進んでいる。
2)ユーロ圏経済の動向
(99年から2000年にかけての景気拡大に向けた動き)
1999年1月、1ユーロ=約1.17ドルでスタートしたユーロは、その後一貫して減価を続け、2000年10月には導入時と比較して対ドルで約30%、対円で約33%減価した。これらの動きはファンダメンタルズとかい離していると言及されることが多いが、ユーロ圏の景気はどのような動向を示しているのか。また、ユーロ圏の誕生はマクロ経済にどのような影響をもたらしているのであろうか。
ユーロ圏の実質GDP成長率をみると、アジア通貨・金融危機等を発端として98年後半から輸出が減少したことの影響を大きく受け、98年7~12月期前期比年率1.6%、99年1~6月期同2.4%と一時的に減速した。その後99年夏以降、世界経済の好転とユーロ安が要因となって輸出が拡大し、固定投資や個人消費が増加しており、景気は拡大している(第1-3-2図(1))。
需要項目別の動向をみると、アジア通貨・金融危機等の影響から98年10~12月期には前期比年率0.4%と大きく低迷した輸出は、世界経済の好転に加えて、発足当初来のユーロ減価による競争力向上を受けて99年夏以降大幅に増加した(99年7~12月期には同13.5%、2000年1~6月期同11.6%)。輸出の大幅増にしたがって生産は大幅に増加している(第1-3-2図(2))。このような生産面の好調もあり雇用情勢は改善しており、失業率は高水準ながらも低下している(第1-3-2図(3))。
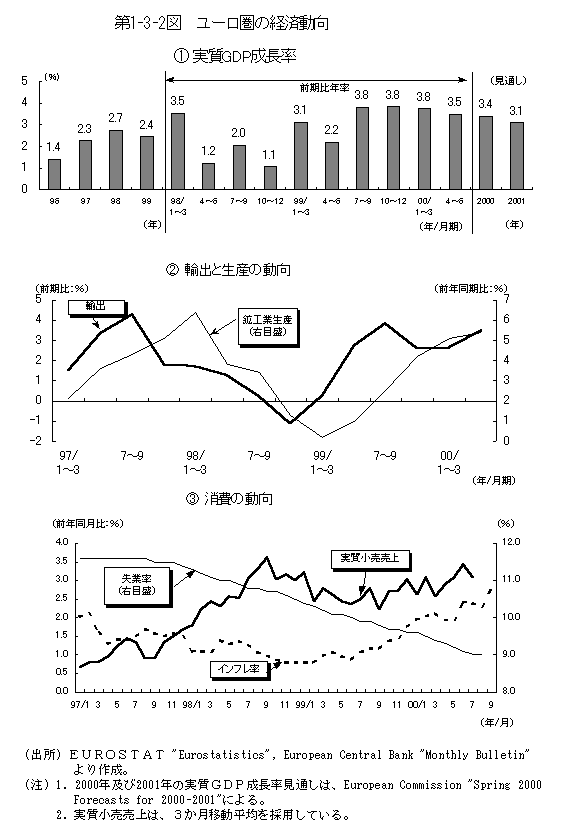
ユーロ圏の物価は、98年から99年にかけ、世界的な低インフレを背景に低水準で安定して推移してきた(消費者物価上昇率は98年前年比1.1%、99年同1.1%)。しかし、99年末以降、原油価格が上昇するにしたがって輸入価格が上昇、消費者物価に対する上昇圧力が生じることとなった。2000年2月には、ユーロ圏の金融政策の最終目標である「物価の安定」の定義である、消費者物価上昇率でみて前年同月比2.0%を上回り、ユーロ圏全体で2.1%となった。消費者物価の上昇に対する財別の寄与度をみると、2000年8月の消費者物価上昇率は2.3%であったが、そのうちエネルギー製品価格上昇の寄与度が1.1%となっており、原油価格上昇の影響の大きさがわかる。
(ユーロ圏内の景況格差)
実質GDP成長率やインフレ率などユーロ圏の景況感は、単一通貨の導入と一元的金融政策の開始によって、長期的には各国で収れんしていくと考えられる。通貨統合に入る以前には、大国の意思を反映した政策決定が行われることで小国(いわゆる周辺国)の景況感が大国に遅れをとり、小国は困難に直面するのではないかと懸念する見方があった。そこで、ユーロ圏各国の生産の伸び率のばらつき度をみると、鉱工業生産指数の伸び率は収れんしているとはいえない(第1-3-3図)。また、周辺国の成長を懸念する見方に反して、周辺国ではGDP成長率が好調に推移した一方、ドイツやイタリアといった主要国では、一時的な景気減速を経験したことから、相対的に低い成長率となった(4)。
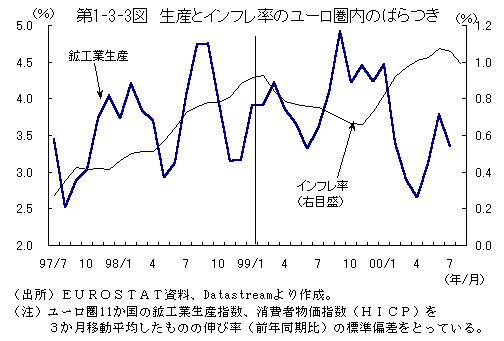
物価上昇率について同様にばらつき度をみると、99年初から年末にかけてインフレ格差が縮小していることが分かる。その後、原油価格が高騰しユーロ圏全体の物価がやや上昇するにしたがって、ユーロ圏内のインフレ格差が再び拡大している。内訳をみると、生産の動向とは反対に、主要国のインフレ率が抑制されがちであった一方、周辺国の消費者物価は大きく上昇している(5)。このように、ユーロ圏諸国の景気の状況は、各国によって異なっていることがわかる。
(結合度を高めるユーロ圏各国)
EU主要国の貿易依存度をみると、ドイツとイタリアは、フランスやスペインと比べてEU域外への輸出入依存度が高いことがわかる(第1-3-4図)。貿易依存度の差異は、外需の増減を通してユーロ圏構成国のGDP成長率格差に影響していると考えられる。ユーロ圏経済は、98年後半以降、全体として、アジア通貨・金融危機等を契機として一時的な減速をみせた。そのなかで、フランスやスペインでは比較的落ちこみが軽微であったのに対して、ドイツやイタリアでは輸出が大きく減少し景気回復が遅れた。さらに、ユーロ圏内の輸出入依存度をみると、99年1月のユーロ発足を契機として貿易結合度が高まっている。単一通貨ユーロの発足により、ユーロ圏内の貿易においては為替リスクが消滅した。一方で、域外との貿易には従来どおり為替リスクが存在する。EU域外への輸出入依存度が高い国において景気回復が遅れたことは、逆にみれば、ユーロ圏内における貿易が景気振幅に対して安定的な働きを示したとも理解できる。現に、ドイツの域内輸出入依存度は99年以降急激に上昇している(第1-3-5図)。
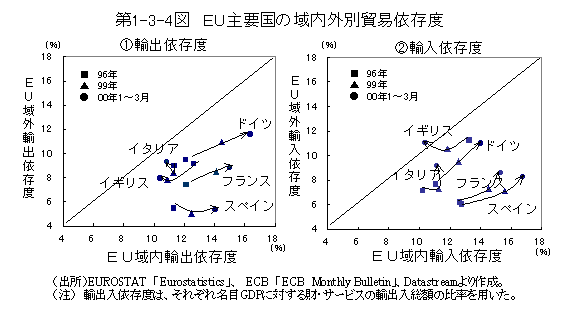
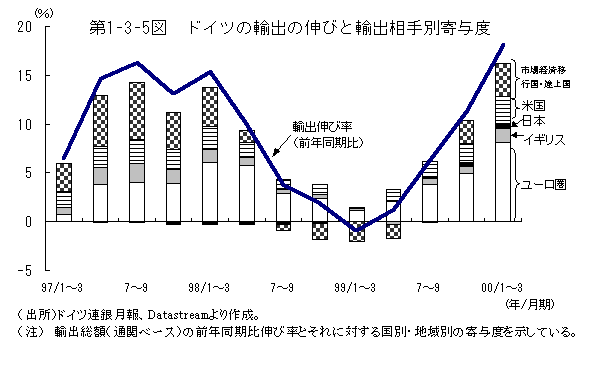
(減価を続けたユーロ)
99年1月の発足以降、単一通貨ユーロは、欧米間の景況格差を要因のひとつとして変動してきたが、総じて減価基調で推移した。2000年7月以降には急激な減価を示し、10月には発足当初と比較して対ドルでは約30%、対円では約33%の減価となった(第1-3-6図)。このように発足以降のユーロレートを変動させてきた理由として、単一通貨の発足に対する期待感から発足当初のレートがそもそも高い水準であったのではないかという見方のほかに、欧米間の景況格差とそれによる金利格差、国際資本移動(直接投資、証券投資)やECBへの信認が浅いことなどが考えられる。
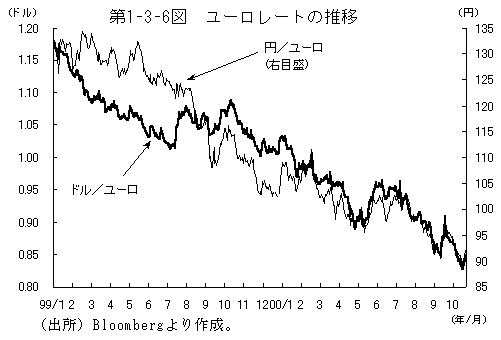
まず、欧米間の実質GDP成長率の格差をみると、99年後半にはアメリカ経済が加速したことから拡大しており、この時期には金利格差も拡大した(第1-3-7図)。この間の減価は景況格差を反映したものであるといえよう。しかし、2000年に入り、輸出の大幅増加が内需増に波及した4~6月期には両地域間の成長率は接近し、アメリカ経済の減速傾向とユーロ圏経済の拡大を受けて欧米間の金利格差は縮小した(6)。にもかかわらず、ユーロの対ドルレートは最安値を更新し続けた。急激な減価に対して、ユーロ圏通貨当局は、ユーロレートは過少評価されておりミスアラインメントが起きていると指摘している。
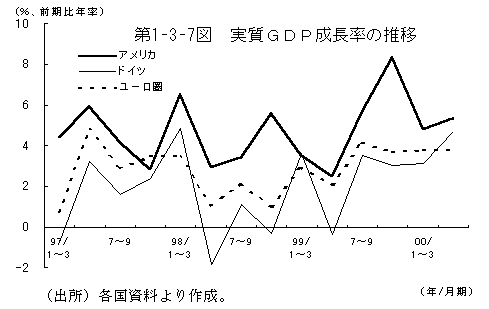
このほか、減価傾向をもたらしている構造的な要因として、ユーロ圏からアメリカへ資金が流出し続けていることが指摘されている。直接投資収支と証券投資収支の動向をみると長期にわたって赤字となっており、ユーロ圏から圏外に資金が流出している(第1-3-8図)。特に直接投資に大きく影響するM&Aの動向をアメリカとユーロ圏の間でみると、金額・件数ともに増加しており、ユーロ圏からアメリカへという資金流出が観察できる(第1-3-9図)。
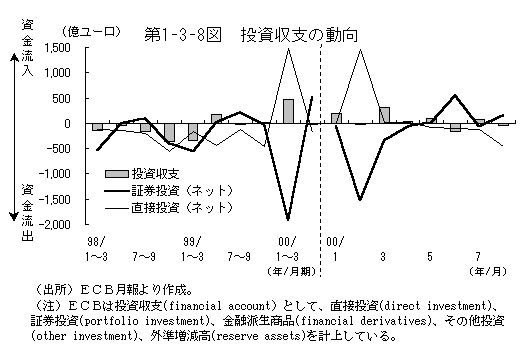
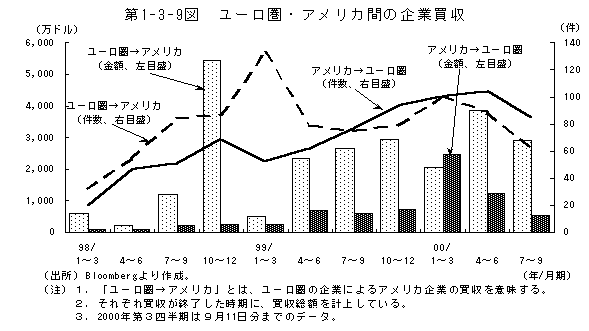
アメリカに向けて資金流出が続くという現象は、投資家がユーロ及びユーロ圏経済に構造的な脆弱性があるとの懸念を持っていることを反映したものと考えられる。例えば、98年以降、アメリカの労働生産性がユーロ圏全体のそれを大きく上回って上昇していることは、投資家にこのような認識を与える要因となりうる(第1-3-10図)。
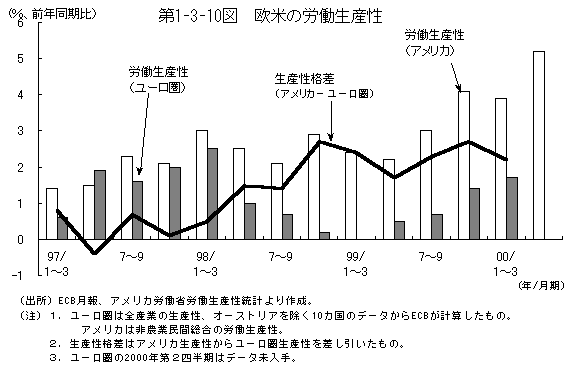
(ユーロ減価への対応)
このようなユーロ減価に、ユーロ圏の政策当局はどのように対応したのだろうか。
ECBは、99年11月、ユーロシステムによる金融政策開始以降、初めての利上げを行い、その後も原油価格上昇とユーロ安の進展による物価の中期的な上振れリスクを抑制するために、約1年の間に7回にわたって利上げを実施した(第1-3-11図)。
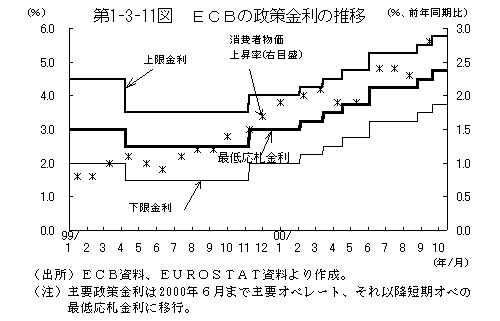
当初はユーロ安が進行するなかでありながらも、金融政策の目標は物価の安定にあるとして、ユーロ安是正そのものを政策目的とすることに消極的と受けとめられてきたECBであったが、2000年4月下旬の利上げに際しては、初めて明確にユーロ安への懸念を表明、ユーロ安がファンダメンタルズを反映していないと述べた。
5月中旬以降にはユーロ圏の景気拡大への期待が高まるにしたがってユーロの減価には一時的に収束がみられた。しかし、7月下旬には、アメリカ経済の好調が持続していることが明らかになった一方で、ユーロ圏の重なる利上げが成長を腰折れさせるのではないかという懸念が台頭したことやユーロ圏通貨当局者等のユーロ安容認発言などからユーロは急激に減価した。
8月31日にはECBが6度目の利上げを決定したものの、ユーロはさらに減価を続け、原油価格高騰とあいまって、ユーロ圏にさらなるインフレ懸念が高まった9月22日、ECBは日米欧の協調の下、初めての為替市場介入を実施した。介入実施前には、1ユーロ=0.84ドル台で推移していたユーロレートは、0.88ドル台に回復した。その後、10月5日には、市場の予想に反してECBが7度目の利上げを決定し、主要政策金利である短期オペの最低応札金利は、99年11月以降の約1年間で合計2.25%ポイント引上げられることとなった。市場では度重なる利上げがユーロ圏の景気を失速させるとの懸念から、ユーロは利上げ直後から減価基調となり、10月下旬には各市場で史上最安値を更新するなど、ユーロレートは軟調に推移している。
急激にユーロ減価が進行するなかで、ユーロ圏通貨当局者等による様々な発言がユーロレートを過度に変動させるという事態もしばしばみられた。これに対し、ECBは市場とのコミュニケーションがうまく図れていないとの批判や、ECBの信認が市場では確立されていないことがユーロ安を招いているといった見方も出ることとなった。
この間、2000年7月からのEU議長国フランス主導の下、従来非公式に実施されてきたユーロ圏11か国蔵相会合を域内の経済政策等に関して協議するための場(「ユーログループ」)として機能強化することとなった。その後、連日最安値を更新するようになった9月初旬には、ユーロ圏11か国蔵相が「ユーログループ」としてユーロ安を懸念する声明を発表した。また、9月下旬に開催されたG7の声明においては「ユーログループ」議長国蔵相としての参加も明示されるなど、為替政策の当局者として「ユーログループ」のプレゼンスを高めようとする動きが見られる。
3)ユーロ導入後の課題と取組
(ユーロ圏の財政健全化の現状)
ユーロ圏のみならず、EUではユーロ導入に向けて「安定と成長の協定」等の厳しい財政規律に基づき、財政収支赤字対GDP比を3%以下に、一般政府累積債務対GDP比を60%以下に抑制するなどの厳格な財政健全化義務を負っている。EU諸国は、加盟国による相互監視の下で、急激な財政健全化を達成してきた。各国が欧州委員会に提出した中期財政計画では、EU諸国の景気拡大を受けて、今後もさらなる健全化を見通している(第1-3-12図)。
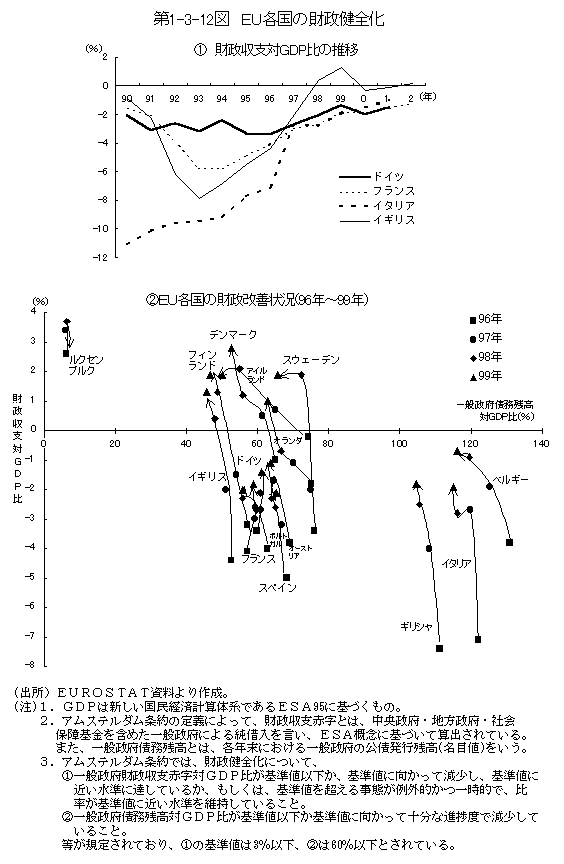
ただし、健全化のスピードは、99年のEMU第3段階移行を前に急激に進展した時期に比してやや鈍化がみられる。例えば、景気拡大による税収増を背景として、所得税減税や法人税減税などを内容とした大幅な減税案がドイツでは成立し、フランスでは公表されており、ともに2001年から実施されることとなっている。法人税率を引下げることは両国企業の競争力向上の観点からは望ましいと評価できよう。ドイツ、フランスのみならず、景気拡大による税収の自然増を受けて、ユーロ圏諸国では減税の動きが広がっている。しかし、ここ数年間で急激に財政収支が改善されてきたとはいえ、依然として財政赤字を抱えている両国が大幅減税を実施することは、外生的なショックが発生した場合に適切な措置を発動するための余地が小さくなることを意味している。金融政策はユーロシステムに一元化し、自国独自の経済政策は財政政策に大きく依存しているユーロ圏各国において、減税が財政健全化のスピードを鈍化させている。この現状に対し、欧州委員会は景気拡大による税収の自然増を財源とした減税を認めず、累積債務削減のために充てるべきとの見解を示した(7)。また、ECBも再三に渡り財政健全化の必要性を指摘している。
なお、EU諸国のなかでは、この数年の間に、次世代携帯電話に関する周波数割当権の譲渡による臨時的な歳入を得る国が多く、これらの特殊な要因も累積債務削減に寄与することに留意する必要がある(8)。
(税制のコーディネーションに向けた進展)
単一通貨ユーロの発足は、ユーロ圏内諸国の経済活動に関してもはや為替リスクを要しなくなるという変化をもたらしている。市場の競争促進や効率性向上に対する可能性が高まる一方、既存の制度の差異が経済活動の選択に与える影響の問題がクローズアップされているが、税もその例外ではない。このため、EU各国間の租税政策におけるコーディネーションの必要性が高まった。
例えば、企業活動においては、各国の法人税制や労働コスト、その他の立地上のコストが企業にとって重要となるが、とりわけ、直接税あるいは社会保障賦課金のあり方が重要になる。各国政府の立場からみると、企業立地を促進するために税率の引下げ競争や補助金の支給競争を行う可能性がある。こうした「有害な税の競争」(9)は、市場の歪みや歳入ロス、あるいは労働への相対的な重課といった問題を生むため、その排除がEU諸国の焦眉の課題のひとつとなった。
この他にも、EU域内で国境を越えて支払われる利子所得に対する適正課税をどのように確保していくのかという問題や、親子企業間における利子等の支払いに対する源泉徴収課税の問題がある。
このため、97年12月にはEU経済相・蔵相会合(ECOFIN)において、企業課税、クロスボーダー利子課税、グループ企業間のクロスボーダーの利子・配当支払への源泉課税の三点を含むパッケージについて合意され、その後、これを具体化するための指令案等が検討されてきている。
利子課税については、加盟国間の具体的利害が対立し意見調整が困難であった。特にイギリスは、匿名性を持ち、源泉課税を免除しているユーロ債の発行市場であるシティの魅力喪失につながり、資金がスイス等のEU域外の金融立国に流出するのではないかとの懸念から、ユーロ債の除外等を求め強硬に反対してきた。ユーロ債の除外は事実上利子課税をめぐる問題の解決を骨抜きとするものであるため、2000年6月の首脳会議における合意は難しいとみられていたが、事前の蔵相会合において、利子課税適正化のための大枠とタイムスケジュールについて合意に達した。具体的には、源泉徴収か情報交換を義務づけた上で、将来的には全ての国が情報交換に応じることを求めることを内容とする指令案の骨格を2000年末までにまとめ、域外国が同様の措置をとることを求める交渉を行った上で、2002年末までに指令案を採択することとしている。
(増加するユーロ圏内外の大型企業合併・買収)
1999年のEMU第3段階移行に前後して、ユーロ圏内外の大型企業の合併・買収案件は大幅に増加している。99年末に始まった、イギリスのボダフォン・エアタッチ社によるドイツ・マンネスマン社の買収に際しては、ドイツの企業文化を破壊することを憂慮する旨のシュレーダー首相の発言が報道されるなど、EU域内におけるコーポレートガバナンスや労使関係のあり方等について大陸型対アングロサクソン型という対立構図としてプレイアップされ、両社による株主に対する熾烈なCM合戦が展開されることとなった。結果的には、2000年2月、ボダフォン・エアタッチ社による買収が成立することで、欧州でも最大規模の買収劇は終結した。
このほか、金融機関も含めて企業の合併・再編の動きは加速している。例えばユーロの対外的な価値にも多大な影響を与えていると考えられる、ユーロ圏企業とアメリカ企業の間の買収についてみると、98年から件数・買収金額ともに増加している(前掲第1-3-9図、第1-3-13表)。
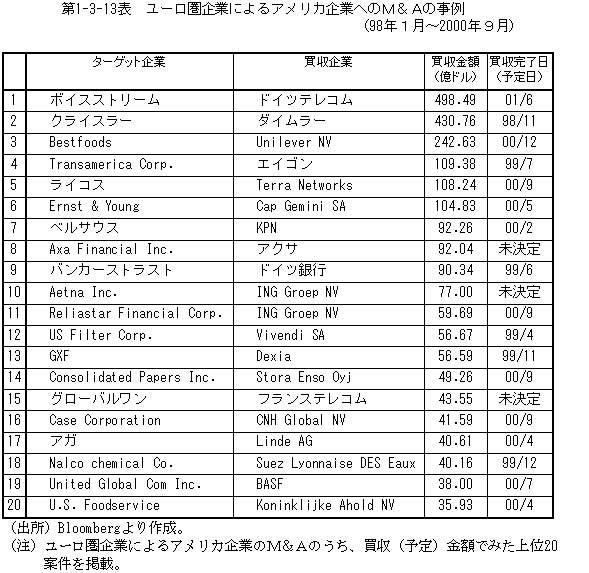
(物価の収れん動向)
2002年1月からのユーロ紙幣・硬貨の流通までの移行期間においては、ユーロへの切換え速度は、「義務なし、妨げなし(No Compulsion, No Prohibition)」の原則の下、各国の自由裁量となっている。商品価格の表示についても同様に、移行期間中を拘束するEUレベルでの規定はない。しかしながら、既にユーロ圏各国では、自国通貨とユーロによる二重価格表示が広く浸透してきている。
欧州単一市場の形成や二重価格表示は、EU域内の価格比較を容易にし、域内の財の価格差は縮小に向かうものと予想される。しかし、欧州委員会が実施した自動車の販売価格調査によれば、2000年5月現在、車種によってはユーロ圏内で30%、EU15か国まで対象を広げると50%もの価格差が存在する。1年前と比較して価格差が拡大している車種もあり、格差が縮小に向かっているとは一概にいえない(第1-3-14表)。
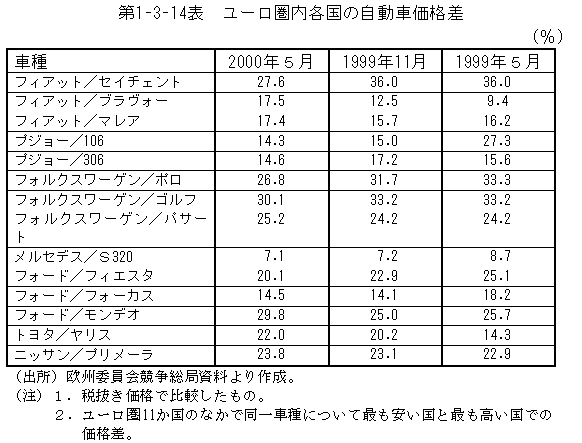
単一通貨ユーロの導入は、ユーロという共通の通貨による価格表示が行われることでユーロ圏内各国において価格の比較が容易になることから、取引相手や消費者からの価格の下方修正圧力を生み、今後、価格差を縮小させていく方向に寄与すると考えられる。
脚注
- 1 ただし、各国は、各国通貨とユーロ貨幣が併存して流通する期間を、2002年2月末まで短縮化するよう努力することとなっている。
- 2 為替レートについては、審査時点以前の2年間以上、自国のイニシアティブによる通貨切下げを行わず、欧州為替相場メカニズム(ERM)の定める変動幅を遵守することが達成基準となっている。99年1月以降は、ERMに代わり、通貨統合非参加国通貨とユーロとの間の新しい為替相場メカニズム(ERM2)が導入され、ギリシャとデンマークが参加している。ERM2に参加する通貨は、対ユーロでの中心レートをもち、上下15%の変動幅が許容されている。
- 3 デンマーク国民がユーロ参加に根強く反対する主な理由には、世界最高水準と自負する社会保障制度や雇用環境が、EUの深化・拡大によって損なわれるのではないかという不安感や、ユーロが減価を続けている現状での参加は時期尚早との見方などがあると考えられる。
- 4 例えば生産量の最も少ないルクセンブルグは、99年実質GDP成長率が5.0%、次いで少ないアイルランドでは同7.8%となった。一方、圏内最大の生産国であるドイツでは同1.3%、イタリアは同1.4%となった。
- 5 2000年4~6月期の消費者物価上昇率(HICP:EUで統一的な消費者物価指数)を比較すると、ルクセンブルグは前年同期比3.5%、アイルランド同5.1%に対してドイツ同1.8%、フランス同1.6%となっている。
- 6 ただし、2000年4月以降の急激な欧米金利格差縮小には、米国債の買戻しによって米国債金利が低下したことの影響も含まれている。
- 7 欧州委員会経済・金融総局 "Public finances in EMU-2000"(2000年5月)
- 8 すでにドイツ、スペイン、オランダ、フィンランド、イギリスにおいて次世代携帯電話(UMTS)事業に関する入札が終了している。例えば、2000年8月に終了したドイツにおける入札では、落札総額が994億マルク(約4.5兆円)と、当初予想(200億マルク程度)を大きく上回る結果となった。この免許収入は全て連邦政府に帰属することとなっている。
- 9 「有害な税の競争」については、OECDにおいても除去に向けた検討作業がなされているが、税制のコーディネーションの促進を目的としたものではなく、各国が最適な歳入・歳出構造を主権的に決定できることを前提としている。
(2)西ヨーロッパ主要国の経済動向
1)ドイツ
ドイツでは、98年初までの景気拡大の後、アジア通貨・金融危機のロシアへの波及などによって外需が低迷したことから、98年前半から99年前半にかけて景気は一時減速した。その後、世界経済の好調と99年初来のユーロ安による輸出の増大にリードされて固定投資や個人消費も増加を示し、景気は拡大している(実質GDP成長率は、98年7~12月期前期比年率0.0%、99年1~6月期同1.6%、7~12月期同2.4%、2000年1~6月期同3.6%、第1-3-15図)。
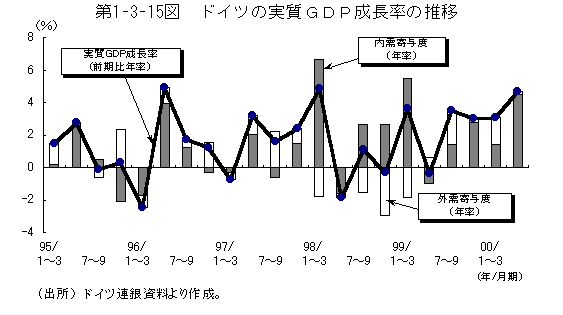
内需の動向を見ると、個人消費は、景気拡大による雇用情勢の改善が続いていることを背景に、雇用者所得が堅調に増加している(99年7~12月期前期比1.0%増、2000年1~6月期同2.0%増)ことから、増加している。固定投資は、輸出の大幅増を受けて生産が増加していることから、機械設備投資の伸びが好調であり、また、ソフトウェア等投資も好調に推移している。一方で、建設投資は減少を続けており、建設業コンフィデンスも好転の兆しは見られない。ドイツ統一後の建設ブームが終了し、公共事業も減少していることが要因となっており、建設業は長期の低迷に陥っている。
生産面からみると、建設を除く製造業(2000年1~6月期前期比年率6.8%増)、卸売・小売業・輸送業等(同5.9%増)、金融・不動産等サービス業(同5.6%増)の生産がいずれも大きく増加する一方で、建設業は同5.2%減と停滞している。
雇用をみると、失業率は97年11月の11.8%をピークに、高水準ながらも低下を続けており、2000年9月は9.4%となった。失業者数は97年には438万人であったが、99年12月以降400万人を下回り続けている(2000年9月385万人)。しかし、旧東ドイツ地域では依然として失業率が17%台と、同7%台で推移する旧西ドイツ地域を大きく上回っており、ドイツ全体の雇用情勢の改善には旧東ドイツ地域の改善が急務であるといえる。
物価の動向は、消費者物価上昇率でみて1999年には前年比0.6%と安定していたが、2000年1~3月期前年同月比には同1.7%、4~6月期は同1.6%、7~9月期同2.0%と、エネルギー価格上昇の影響から上昇率に高まりがみられる。原油価格が再び高騰した9月には、ガソリン価格上昇の影響を受けている輸送業者が鉱油税の引下げを求めるデモを行うなど抗議行動がみられた。環境対策等の観点から、99年4月より税率が引上げられている鉱油税について、2000年1月以降2003年まで、毎年ガソリン1リットルあたり0.06マルクの税率引上げが予定されていることも不満を高めたものと考えられる。
(大型減税を含む税制改革実施へ)
2000年7月、法人税及び所得税減税などを内容とした大幅減税を実施する税制改革法(「税制改革2000」)が可決され、2001年1月1日から施行されることとなった。「税制改革2000」による減税規模は625億マルク(約3.1兆円)と見込まれ、昨年の減税措置と併せると1998年から2005年の間に、減税分から増税分を差し引いたネットで930億マルク(約4.7兆円)の減税となる。
今回の大幅減税は、EU諸国の中でも高い水準となっている法人税・所得税率を引下げることにより、ドイツの国際競争力の向上や成長の持続、雇用の増大などを目的としている。シュレーダー首相は、同法成立に際し、同法がドイツ経済を改善させ、失業を引下げるとともに、ドイツの国際的なイメージ、企業の投資対象としての魅力を向上させると述べた(1)。アイヒェル蔵相は、投資家と雇用者に対して、成長と雇用の望ましい拡大のために重要なメッセージとなるとし、莫大な失業を解消し、教育や研究、環境の保護などに対して政府は一歩ずつ果敢に挑戦していくべきであると主張している(2)。
「税制改革2000」は、(1)所得税減税、(2)法人税減税と(3)課税ベースの拡大を主な内容としている(第1-3-16図)。その概要は次のとおりである。
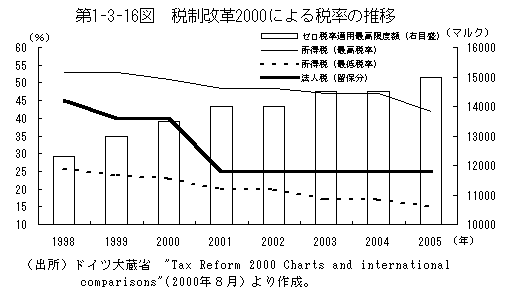
- 所得税の最低税率(98年25.9%→2005年15%)、最高税率(98年53%→2005年42%)を、ともに順次引下げる。また、諸外国における基礎控除にほぼ該当するゼロ税率適用最高限度額を約13,500マルクから2005年には約15,000マルクに引き上げる。なお、当初法案では所得税率の引下げは45%までとなっていたが、大企業が法人税の大幅減税の恩恵を享受する一方で中小の個人企業に対する配慮が不十分であるとの批判が展開されたことから、最終的には42%まで引下げることとなった。これは、ドイツでは企業全体のほとんどを、個人企業を中心とした中小企業が占めているためである。
- 法人税は、内部留保分(2000年40%)と配当利益分(2000年30%)に対して異なる税率を適用しているが、2001年からは内部留保分と配当利益分に対して統一税率25%を適用する(3)。
- 一方、代替財源を確保するため、動産に係る減価償却率を現行の30%から20%に引下げること等、企業の減価償却に対する課税を中心に課税ベースの拡大を行う。
ドイツの法人税率については、従来から、国際的にみても高く、国際競争力を阻害しているという批判があった。今回の大幅減税によってドイツの法人税率はユーロ圏内の平均的な水準となる。
ただし、今回の大幅減税の財源について、ドイツ政府は、課税ベースの拡大と経済成長による税収増(4)で補うことを基本方針としている。EUを構成する全ての国で厳しい財政規律の遵守が求められているなか、景気拡大が本格化するにしたがって、ドイツやフランス等いくつかの国で税収の自然増を見込んだ減税が計画されていることについて、欧州委員会は、景気拡大による税収自然増は累積債務削減に充てるべきとして、警鐘を鳴らしている(詳細はEU部分で記述)。
脚注
- 1 ドイツ連邦政府2000年7月13日付けニュースリリース"Chancellor Schroeder: Bundesrat approval of tax reform a good day for Germany"
- 2 ドイツ大蔵省2000年2月9日付けPress and Information "Tax policy for our country's future"
- 3 このほか、法人と株主に対する課税方法の見直しが行われ、2002年以降、現行の完全インピュテーション方式(配当所得に対する法人税と所得税の二重課税を排除する方法)を見直すこと、資本会社間における国内株式の譲渡益について、一定の制約条件(保有期間が1年以上等)を設けた上で非課税とすること、個人が株式譲渡益課税を受ける資本会社に対する持分比率を10%以上から1%以上に引下げること、などが盛りこまれている。
- 4 ドイツ経済紙の報道によると、ドイツ連銀のウェルテケ総裁は、今回の税制改革による実質GDP成長率の押上げ効果を0.5%程度とみている。
2)フランス:大型減税策を発表
フランス経済は、97年以降外需主導の回復・拡大局面に入った。その後、個人消費、設備投資が増加するなど内需主導に移行する形で景気は拡大を続け、98年は3.2%という90年代に入ってから最高の成長率を記録した。98年後半から99年初めにかけて、ユーロ圏、ASEAN向けの輸出が減少するなど外需が減少したこと、在庫調整が進められたことなどにより、成長拡大のテンポは一時緩やかになった。しかし、雇用情勢の改善が消費者信頼感の向上につながっていることなどから、個人消費は堅調に推移しており、固定投資も増加が続いていることもあって、景気は拡大している。実質GDP成長率は、2000年1~3月期は前期比年率2.6%、4~6月期は同2.9%となった。
失業率は、景気拡大に加えて、若年層向け雇用創出のための政策や、2000年2月からの週35時間労働制の本格導入の効果などもあり、97年6月の12.6%をピークに高水準ながらも低下している(2000年9月9.5%)。物価は、99年後半からエネルギー価格の上昇が続いているものの、総じて安定している。消費者物価上昇率は、99年前年比0.5%の後、2000年1~3月期前年同期比1.5%、4~6月期同1.5%、7~9月期同1.9%となった。
フランス政府は今後も景気拡大は続くとし、2000年3.4%、2001年3.3%という比較的高い成長率を見込んでいる(1)。
(雇用者数の増加と週35時間労働制の導入)
景気拡大を背景にフランスの失業率は低下しており、雇用者数も増加が続いている(第1-3-17図)。内訳をみると、特にサービス、商業分野での雇用創出が大きく、また、税制優遇措置であるペリソール法の実施(2)などから住宅着工件数が99年前年比10.5%の大幅増となり、建設部門の雇用者数もこのところ増加に転じている。フランスでは雇用創出策のひとつとして「週35時労働制」を導入し、2000年2月より従業員20名以上の企業の法定労働時間を週39時間から週35時間に短縮した。業種別にみると自動車製造部門は週労働時間が98年1~3月期38.5時間から2000年1~3月期には35.9時間となり、労働時間短縮導入が進んでいるが、建設部門やホテル、レストランなどのサービス部門では「週35時間労働制」がまだ義務付けられていない中小企業の割合が比較的高いこともあり、2000年1~3月期の週労働時間は依然として38時間を超えている。労働時間短縮の制度導入で最も懸念されたことは、短期的な賃金コストの上昇であるが、政府は移行期1年間は企業負担分の社会保障費の軽減や、超過勤務賃金の割増を抑制する特別措置をとっている。そのため、99年後半以降エネルギー価格上昇の影響などによる消費者物価上昇圧力が働いていたにもかかわらず、一人当たりの月平均賃金上昇率は比較的抑制されているといえる(第1-3-18図)。
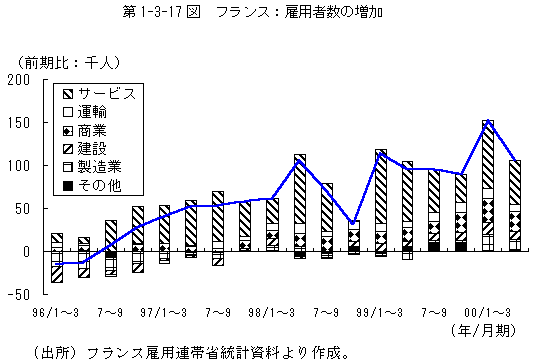
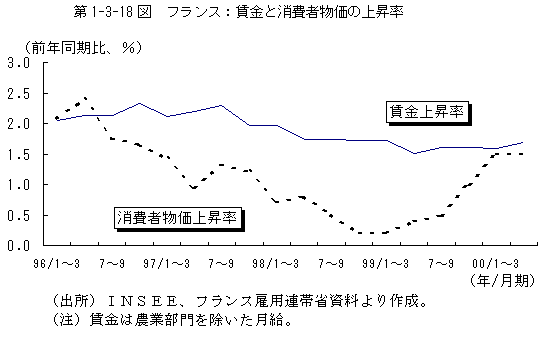
(大型減税策の内容)
フランス政府は、好景気を背景とした政府の税収の増加をうけ、8月末に2001年から2003年にかけての総額1,200億フランの大型減税策を発表した。その目的として、(1)課税の公平と効率を高めるとともに税負担の軽減を図ること、(2)社会保障費の軽減等により、雇用の促進及び、「失業のわな」に陥ることを避けること、(3)原油価格上昇による石油関連製品の価格上昇を緩和すること、(4)課税方法の簡素化を掲げている。今回の減税策は所得税、法人税、社会保障賦課税、石油製品内国消費税、自動車税の多岐にわたっており、過去50年において最大規模とされている(第1-3-19表)。撤廃が発表された法人特別税は、95年にジュペ政権の下、通貨統合参加に向けた緊縮財政実施を目的として、法人税(33.3%)に10%上乗せしていた部分(3.3%)であり、ドイツが7月にフランスに先駆けて、法人税を大幅に引下げることを発表しており、法人税負担が重いフランス企業の競争力が損われると企業団体から批判されていたものである。他方、法人税制を整理、簡素化する観点から、配当や減価償却にかかわる優遇税制は縮小される。
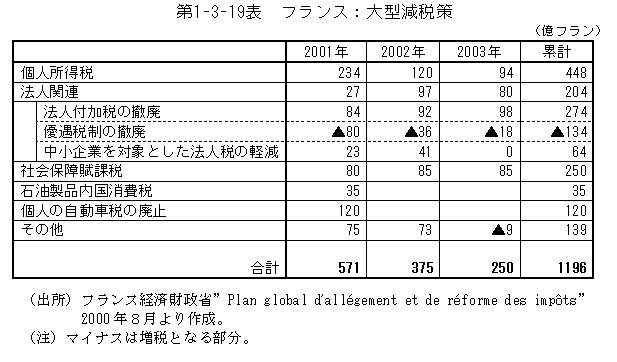
社会保障賦課税については、最低賃金(SMIC)レベルの1.3倍までの給与所得者について、一般社会税(CSG(3))と社会保障債務返済税(CRDS(4))を2003年までに軽減する。これにより、SMICレベルの労働者の月給は540フラン上昇することとなる。低所得者層への減税効果をより大きくしているのは、失業中の保障制度が手厚いという「失業のわな」を免れることを目的としているためである。しかしながら、今回の減税案は、全ての所得層を対象に、個人所得税率を引下げるなど、2001年に迫った次期選挙を強く意識したものであり、構造的な問題は解消されていないという批判もある。
(起業の促進)
フランスの新規設立企業数は94年をピークに減少していたが、99年には建設部門、サービス部門の起業が大幅に増加したため、設立総数では前年比0.9%増の16万9,700件と増加に転じた。近年の景気拡大局面においても新規設立企業数が伸び悩んでいたことの理由として、OECDは、企業設立手続きが複雑な上に、時間がかかるとの問題点を指摘し、OECD諸国の中でフランスを起業に対する障害が2番目に大きい国と評価している(5)。そこで4月に政府は、起業の促進を目指し、企業設立手続きの簡素化、費用の軽減、起業家に対して2年間の社会保障費の軽減、小規模プロジェクトに対する融資制度などを盛り込んだ政策を打ち出している。
起業の促進と新規産業の育成のためには、その資金供給源が必要となるが、政府は急速な発展をとげている新興のハイテク企業を対象としたリスク・マネーの供給のために、98年に9億フラン(1.37億ユーロ)の基金を設立したが、2000年に同基金を拡充する形で新たに1.5億ユーロの基金(6)の設立を発表している。
その他に資金調達の場として活用されているのが、ベンチャー企業の株式市場として96年に開設されたヌーボー・マルシェ(NM)である。NMの上場企業数は、順調に増加しており、2000年上半期の新規上場企業数は一部市場では9社、二部市場は9社にとどまったが、NMではIT関連企業の躍進から30社が上場した。
国立統計経済研究所(INSEE)のレポートによると、94年上半期に設立された新規企業のうち、3年後も存続しているのは59%であり、規模の小さい企業ほど、事業の存続が難しい傾向にある。したがって、特に中小企業への支援が重要であり、このため、前述の大型減税策において年間売上高5,000万フラン未満で、個人株主が75%以上の株式を保有する中小企業に対し、法人税率を2002年までに段階的に15%まで引き下げるとしている。
脚注
- 1 2000年9月発表
- 2 96年1月1日から99年8月31日までに購入した住宅が対象になる。
- 3 CSG: Contribution sociale generalisee
- 4 CRDS:Contribution au remboursement de la dette sociale
- 5 OECD "Economic Surveys France" July. 2000 起業への障害が一番大きい国はイタリア。
- 6 Fonds de Promotion pour le Capital-Risque 2000
3)イギリス:内需を中心に景気拡大
イギリス経済は、98年後半に一時的に減速したものの、中央銀行であるイングランド銀行による金利引き下げなどの政策効果もあり、99年4~6月期以降景気は改善に向かった。その後、対ユーロでのポンド相場が増価したことなどから、99年末から2000年初めにかけて、製造業の生産が鈍化したものの、個人消費や設備投資は堅調に推移しており、景気は拡大を続けている(実質GDP成長率は、1~3月期前期比年率2.1%、4~6月期同3.8%、7~9月期同2.8%(速報値))。
イングランド銀行は、強い個人消費や労働市場のひっ迫感に加え、住宅等の資産価格が高騰していたことなどから国内の中期的な物価安定が損われるとして、99年9月から4度にわたる利上げを行った。利上げによって、ポンドの対ユーロ相場は上昇し、2000年5月上旬には1ポンド=1.75ユーロと、約25年ぶりの水準を記録した(ユーロの前身のECU時代を含む)。利上げの効果もあり、住宅を中心とする資産価格の上昇は一段落し(第1-3-20図)、また実体経済面も2000年に入りやや減速し、個人消費や設備投資の伸び率はやや低下してきている(後述)。
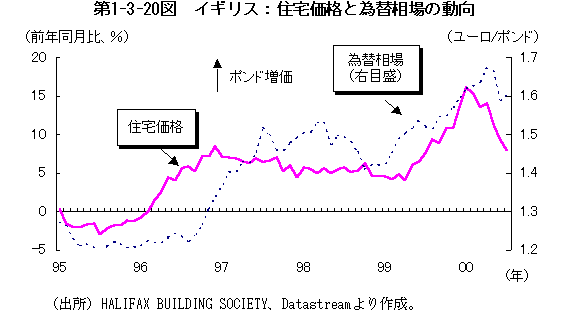
雇用は94年以降、長期に増加を続けており、失業率は9月には3.6%を記録し、約25年ぶりの水準にまで低下している。通信を始めとするサービス業に支えられ、全体の雇用者数は、ここ2年で約50万人以上増加した。一方、製造業では厳しい経営環境に対応すべく労働コストを削る動きがあり、雇用者数が減少している。また、若年層や長期失業者などに対応した雇用対策である「ニューディール」も一定の成果を上げていると考えられる(詳しくは第2章第2節を参照)。
物価をみると、小売物価上昇率(住宅金利支払いを除く)は、イングランド銀行が金融政策の目標としている2.5%の水準を下回る水準で推移している。97年5月に現行のインフレターゲットを導入して以降、イングランド銀行は政策金利を小刻みに変更し、中期的な物価動向(2年程度先)に注意を払いつつ機動的な政策運営を行っており、これが物価の抑制に貢献しているものとみられる。また、99年以降、ユーロに対してポンド高が続いたことも、ユーロ圏と比較して輸入物価の上昇率を抑制し、物価安定の一因となっている。
(個人消費と設備投資の動向)
イギリスの長期にわたる景気拡大の牽引役は個人消費と設備投資であるが、2000年に入り、ともにやや減速している。個人消費の伸びは、金利が歴史的な低水準で推移していることや雇用が拡大を続けていることなどから可処分所得の伸びを超えて推移してきており、家計貯蓄率は2000年4~6月期には3.0%にまで低下している。また、資産効果も消費増加に寄与したと考えられ、株式などの金融資産よりも住宅価格高騰による資産効果が大きいとの研究もある(1)。住宅や株式を中心に資産価格は大きく上昇しており、特に住宅市場ではその傾向が顕著で、99年には二桁の上昇率を記録した。しかしながら、金融引締効果などが表れ、2000年に入り住宅価格の上昇率はやや鈍化しており、個人消費の伸びが抑制された可能性がある。また、平均賃金上昇の鈍化を反映して、可処分所得の伸びが鈍化していることも、個人消費を落ち着かせたものと考えられる。
一方、設備投資の動向をみると、1~3月期に実質固定投資が前期比で13四半期ぶりにマイナスを記録するなど、設備投資意欲にはやや陰りがみられる。2000年問題を控えて、99年中に設備投資を積極的に行ったことの反動に加え、寡占化していた小売業で外国企業の参入により、価格競争が激化し、マージン率が低下したことや、為替相場の動向により製造業を中心として利益が減少していることも影響していると考えられている。
(ユーロ導入に対する反応)
イギリス政府は、99年1月からの経済通貨統合(EMU)第三段階への移行を見送っており、ユーロ圏に参加するか否かに対する国民投票を行うのは、経済条件が整い次第としている。他の不参加国の動きをみると、ギリシャは2001年1月からユーロ圏に参加する予定であり、デンマークでは9月に参加の是非を問う国民投票を行い、ユーロ参加は否決された。また、スウェーデンでも3月に与党社民党の党大会で国民投票を実施することを決定した(時期は未定)。これに対し、イギリスではユーロ参加に向けた動きは、このところ進展していない。欧州委員会が行った世論調査をみても、ユーロ不支持層が99年後半以降に増加してきており、ユーロ反対への国民感情は根強く、経済的な問題よりも政治的な問題となっている面もある(第1-3-21図)。
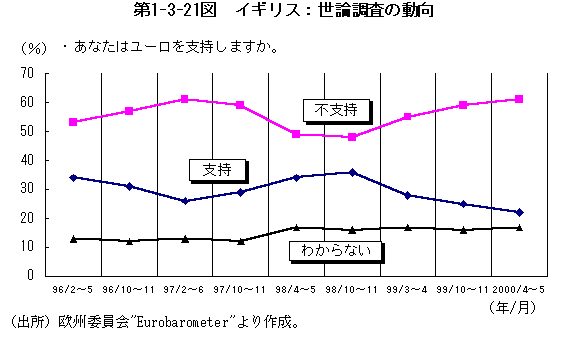
OECDは、イギリスの経済状態はかつてないくらいにドイツの経済状態と収れんしてきており、参加には絶好のチャンスであると指摘している(2)。また、IMFもここ十年でイギリスの賃金の柔軟性は増しており、ユーロ圏参加に伴うコストは少なくなっている可能性がある、としている(3)。しかしながら、99年以降の為替相場はイギリスにとって不利であり、誤った為替相場で参加した場合の経済的不利益は大きいとの指摘もある。MORI(Market & Opinion Research International)が99年中に行った企業アンケートによると、46%の企業が1ポンド=2.6~2.8マルク(1.33~1.44ユーロ)での参加を望んでおり、このところの実勢相場(1ポンド=3.1~3.2マルク)との開きは大きい。
イギリスのユーロ加盟は、国内の大企業を中心とする産業界だけでなく、大陸欧州や日本企業なども望んでいることであり、今後のイギリス政府の対応が注目される。
脚注
- 1 Boone et al. "Stock market fluctuations and consumption behaviour : some recent evidence" OECD Working Paper.
- 2 OECD "Economic Surveys United Kingdom" June 2000
- 3 IMF "Staff Report for the 1999 Article 4 Consultation"
4)イタリア:雇用情勢の南北地域格差
イタリアでは、98年はアジア通貨・金融危機の影響、西ヨーロッパの景気減速等により輸出が伸び悩むとともに、98年後半の雇用情勢の悪化等から個人消費の増勢が鈍化したことにより、景気は一進一退で推移し、実質GDP成長率は98年前年比1.5%となった。その後、99年に入り機械設備を中心とした固定投資の増加や、個人消費の回復もみられたものの、輸出の減少により外需のマイナスが続いたため、99年の実質GDP成長率は前年を下回る前年比1.4%にとどまった。その後、2000年に入り固定投資の増加が続いており、個人消費も堅調に推移していることから実質GDP成長率は1~3月期前期比年率4.3%となったが、4~6月期は、外需がマイナスに寄与したこと等から同1.1%となり、景気拡大のテンポは緩やかになってきている。
失業率は、高水準ながらもやや低下しており、2000年4月10.8%(未季調値)の後、7月10.1%となった。物価はエネルギー価格上昇により、上昇率がやや高まっており、生計費上昇率は99年前年比1.6%から、2000年1~3月期前年同期比2.3%、4~6月期同2.4%、7~9月期同2.6%となった。経常収支は2000年1~3月期18.2億ユーロの赤字の後、4~6月期同39.3億ユーロの赤字(未季調値、名目GDP比▲1.4%)となった。
(雇用情勢の南北地域格差)
イタリア経済の問題のひとつとして、南北地域格差がある。南部地域(Mezzogiorno(1))は北部・中央地域と比較し大型の産業が未発達ということもあり、所得水準が低く、南北の生活レベルの格差解消が長年の課題となっている。90年代の地域別経済成長率をみると、北部・中央地域では1.5%であったが、南部地域では0.9%とその格差は広がっている(2)。特に雇用情勢における地域格差が顕著であり、北部地域の失業率は4.7%とユーロ圏平均(7月9.1%)を下回っているのに対して、南部地域は21.0%と北部地域の約4倍の高失業率となっている(第1-3-22図)。特に、南部地域は若年層の失業率が高く、7月の失業率は南部地域53.9%(北部地域:同13.7%)と若年労働力人口の半数以上が失業中となっている。雇用者数は、北部地域においては98年以降、緩やかな増加が続いているが、南部地域では非正規労働者の割合(3)が高いことや、大型の産業の発達が遅れていること等から、雇用が不安定となっている(第1-3-23図)。
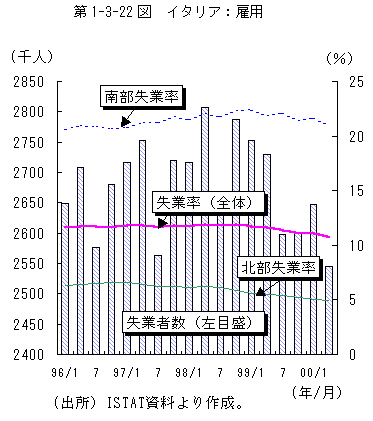
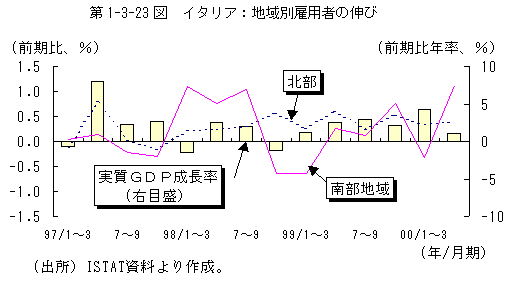
労働力率をみると、北部地域の64.2%(2000年7月)に対し、南部地域は53.3%と低くなっている。イタリアは他のEU諸国と比較し、社会保障費に占める年金拠出の割合が高いことが指摘されており(4)、高齢化が進むなか、年金の制度破綻を回避する上でも、特に南部地域の女性や若年層の労働力率引き上げが重要な課題となっている。
今後のイタリアの安定した成長にとって不可欠である南部地域の活性化のため、政府は98年に、国庫省に地域開発を担当する部門(DPS(5))を設立し、地方政府、民間の労働・産業組織との調整をより緊密にするとともに、優先プロジェクトの選定や、責任体制の明確化等により公共投資の効率を高めることを目指している。この南部地域開発の強化、見直しにより、資金不足などを理由に中断されていた約250件の公共事業が再開されている。2001~2007年の中期計画では欧州委員会の構造基金に加え、政府の公共投資予算の約44~47%を南部地域へ重点配分することとしている。
(国営企業の民営化)
イタリア政府は6月に「経済財政4か年計画-2001~2004年」を発表するとともに、2000年の経済成長率の見通しを前年比2.8%(99年時点の見通しは同2.2%)へ上方修正した(第1-3-24表)。近年イタリアは、欧州通貨統合参加のため増税と歳出の削減による緊縮財政を進めていたが、景気拡大による税収の増加に加え、国営企業の民営化や次世代携帯電話の事業認可供与による収入の増加が見込まれることから、今回の計画では歳出削減案は盛り込まれなかった。
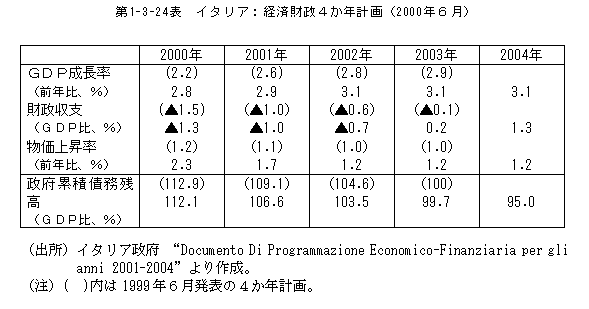
イタリアは、90年代初めから国営企業の健全化と企業の国際競争力を高めるため国営企業の民営化を進めてきた。金融、製造業、通信、エネルギー部門と順次民営化を進展させており、99年には株価の上昇もあって、国有企業の株式売却益は48兆リラ(250億ユーロ)に達している。政府の持ち株会社である産業復興公社(IRI)の傘下にあったテレコム・イタリア、ENEL(電力)、ENI(炭素水素公社)は既に民営化されているが、2000年6月末のIRIの解散により、一連の民営化計画が終了した。通貨統合の影響もあり、ユーロ圏での業界再編、企業合併が相次ぐなか、これらの旧国営企業も厳しい国際競争にさらされている。しかし、旧国営企業の政府所有株に対して「黄金株」制度が適応されており、国益に反すると判断される外資の敵対買収については、持ち株比率に関わらず政府が拒否権を発動することが可能となっている。99年にはドイツ・テレコムによるイタリア・テレコムの買収がイタリア政府によって拒否されるなど、当面は旧国営企業に対する政府の関与は続くものと予想される。
脚注
- 1 MezzogiornoとはAbruzzo、Molise、Campania、Puglia、Calabria、Basilicata、Sicily、Sardiniaの南部地域を指す。
- 2 Banca D'Italia "Sintesi delle note sull'andamento dell'economia delle regioni italiane nel 1999" 2000年
- 3 OECD "Economic Surveys Italy" (2000年5月)。98年の非正規労働者(Irregular Labor)の割合はイタリア全体では22.6%、南部地域では33.8%。
- 4 同上。社会保障費に占める年金拠出の割合は、1995年イタリア63.1%、EU平均では43.6%。
- 5 DPS: Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione (Department for Development and Cohesion Policies)
5)スペイン:実質金利の低下
スペイン経済は、雇用の増加や、所得税減税の影響等により個人消費が順調に伸びたことや、低金利により固定投資の増加が続いていること等から、内需主導の景気拡大が続いており、実質GDP成長率は98年前年比4.3%の後、99年同4.0%となった。一方、輸出の伸び以上に高い輸入の伸びが続いていることから、外需はこのところマイナスに寄与している。2000年に入り、失業率がさらに低下していること等から、消費者のコンフィデンスも高水準で推移しており、個人消費がスペインの高成長をけん引している。実質GDP成長率は1~3月期前期比年率4.9%の後、4~6月期同3.5%となった。スペイン経済の好調が持続している要因のひとつにユーロの発足がある。99年1月の通貨統合に向けてスペインは段階的に政策金利を引き下げたため、実質長期金利は急速に低下した。その後もスペインの消費者物価上昇率はユーロ圏平均よりも高い水準で推移しているにもかかわらず、欧州中央銀行の一元的金融政策により、政策金利は比較的低い水準に抑制されており、スペインの実質長期金利は低い水準で推移している(第1-3-25図)。
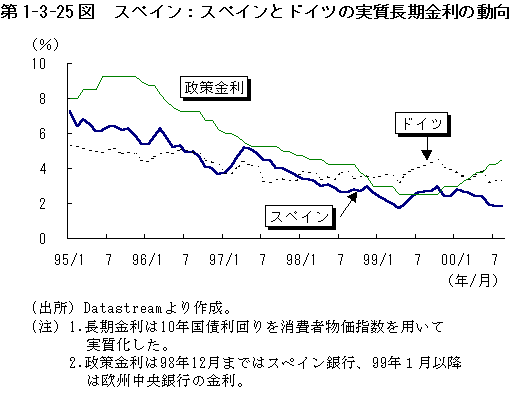
鉱工業生産は98年前年比5.4%増から、99年前半に一時伸びが鈍化したため、99年同2.6%増にとどまったものの、輸出の増加が続いていることもあり2000年は1~3月期前年同期比8.5%増、4~6月期同5.0%増と、増加が続いている。また、設備稼働率も2000年1~3月期80.5%の後、4~6月期80.7%と、97年以来の高水準に達している。物価は、エネルギー価格上昇の影響もあり、上昇率はやや高まっている。消費者物価上昇率は、2000年1~3月期前年同期比2.9%、4~6月期同3.2%の後、7~9月期同3.6%となり、生産者価格上昇率(中間財)は4~6月期前年同期比11.5%の後、7月前年同月比10.9%、8月同10.2%となった。失業率は94年1~3月期の24.6%をピークに低下傾向にある(2000年4~6月期14.0%)。特にサービス部門や建設部門を中心に雇用者数の増加が続いている。経常収支をみると、2000年1~3月期34億7,300万ユーロの赤字の後、4~6月期47億2,600万ユーロの赤字(名目GDP比▲3.1%)と赤字幅がやや拡大している。
スペイン政府は、内需の拡大傾向は続くとして、2000年の実質GDP成長率を前年比4.0%と見通している(1)。
脚注
- 1 2000年7月見通し。
2 中・東ヨーロッパ:輸出主導で景気は拡大
89年11月にドイツのベルリンの壁が崩れ、中・東ヨーロッパ諸国が市場経済の移行を開始して約10年が経過したが、各国は当初想定されていたよりも多くの時間と犠牲を払ってきた。欧州復興開発銀行(EBRD:European Bank of Reconstruction and Development)の「移行国レポート1999」によると、89年を100とした場合の98年の実質GDPは、最も高い成長を達成したポーランドで117となったが、チェッコ、ハンガリーでは95であるなど、市場経済移行以前の水準に達していない。これは体制移行初期の混乱による影響の大きさの違いと考えられる。
主要3か国でみると、景気は99年後半から堅調に拡大している(第1-3-26図)。経済成長の理由として共通しているのは、コソボ紛争やロシア通貨危機の影響が薄れつつあるなか、好調なEU経済やロシア通貨危機後の通貨安により輸出が増加したことが挙げられる。2000年4~6月期の各国輸出額(国際収支ベース、ドル建て)をみると、ハンガリーは前年同期比42.0%増、チェッコ同9.9%増、ポーランド同8.8%増と増加している。輸出先は、90年代前半はロシア向けや域内向けが多かったが、昨今はEU向けが増加しており、経済をけん引している輸出が順調に増加しているのはEUの景気拡大に伴うものといえる(第1-3-27図)。また、輸出関連産業を中心に生産が回復し、賃金上昇による消費の拡大もみられた。前述のレポートによると、中・東ヨーロッパ及びバルト三国(1)の実質GDP成長率は、98年前年比2.4%、99年同1.6%となり、2000年については同3.2%と予想されている。
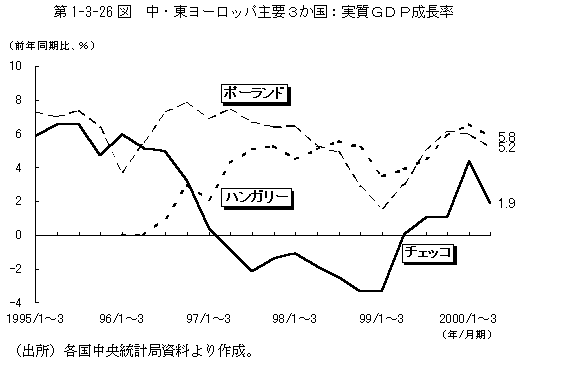
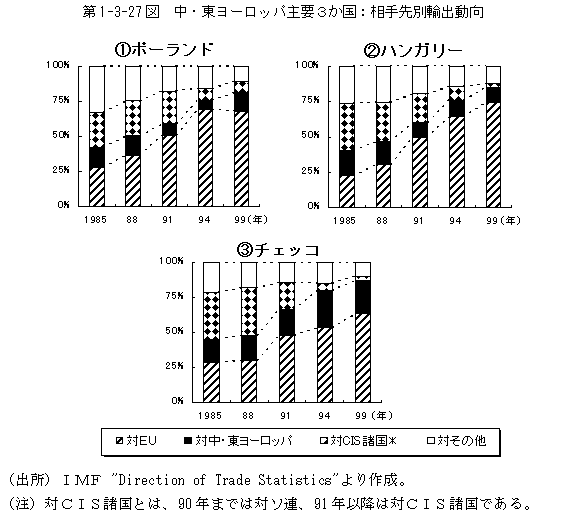
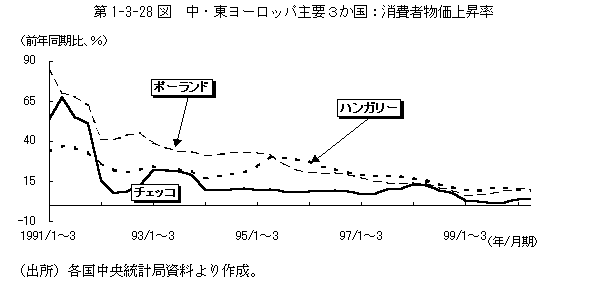
(ポーランド:景気は緩やかに拡大)
ポーランドでは、90年代初頭の急進的な市場経済化が功を奏した。実質GDP成長率は、92年から中・東ヨーロッパでいち早くプラスに転じ、97年まではこの地域で最も高い経済成長を実現してきた。99年後半にかけて、景気は堅調に拡大し、実質GDP成長率は前年比4.1%となった。高い伸びを示す外需とともに、消費、投資の国内需要も経済をけん引している。
政府はインフレ抑制のために緊縮的な財政金融政策を実施し、99年には消費者物価上昇率は前年比7.3%と、市場経済移行後初の一桁台の伸び率に低下した。しかし、2000年に入ってからは若干上昇しつつあり、前年同月比10%前後で推移している。
経常収支は赤字を続けており、99年には100億ドルを超えた。他方、海外からの対内直接投資額が98年には過去最大、中・東ヨーロッパ諸国の中でも最大の受入国となり、その後も資金が流入する傾向は続いている。しかし、こうした民営化に伴う外資の流入は次第に減少していくため、国内産業の競争力の強化を図るなどの安定化政策が今後も引き続き求められる。
通貨・金融面では、ポーランド政府は2000年4月に国際通貨市場における通貨ズロチの為替自由化を決定し、為替のクローリング・ペッグ制を廃止して変動相場制に移行した。
(ハンガリー:生産は過去最高)
ハンガリー経済は、95年3月に導入された緊縮経済政策が成果を上げ、96年以降着実な経済成長を持続しており、99年の実質GDP成長率は前年比4.5%となった。特に、鉱工業生産は2000年に入って、前年同月比20%前後の増加をみせ、5月には同29.5%増と過去最高の伸び率を記録した。
これまでの経済政策により、99年の消費者物価上昇率は前年比10.0%まで低下した。また、ハンガリー中央銀行は好調な経済を背景に、これまで国際的にみて高水準にあった金利を徐々に引き下げてきた。しかし、インフレ率の最近の推移をみると、政府や中央銀行が想定したほど低下していない。これは石油価格の上昇等が影響しているとみられる。
(チェッコ:プラス成長に転化)
97年より景気後退をみせていたチェッコ経済は、輸出の拡大や内需の好調に支えられて持ち直してきており、99年の実質GDP成長率は前年比▲0.2%と微減だったものの、2000年1~3月期は前年同期比4.4%と急伸し、4~6月期も同1.9%となった。政府は最近の経済見通しで、2000年の実質GDP成長率を上方修正し2.7%としている。
99年の消費者物価上昇率は前年比2.1%と驚くほど低水準になったが、2000年に入り前年同月比3~4%台まで上昇しつつある。しかし、インフレが再燃する懸念は少ないとみられており、中央銀行は公定歩合を引き続き低い水準に据え置いている。
失業率は、96年までは高い経済成長率に支えられ3%台を維持してきたが、構造改革の進展と景気の後退を背景に、96年の半ば以降次第に上昇し始め、99年末には9.4%となった。
(EU加盟への動向)
EU加盟交渉開始を認められる国は、93年6月の欧州理事会コペンハーゲン会議で定められた「コペンハーゲン基準」と呼ばれる加盟条件を満たす能力を有する国、とされている。具体的には、1)政治的基準、2)経済的基準、3)その他法律・制度準備基準、の3つの基準達成によって評価され、このうち経済的基準は第1基準(効果的な市場経済の存在)と第2基準(EU内での市場の力及び競争力に適応できる能力)に区分される。この基準に照らし、現在、チェッコ、ハンガリー、ポーランドを含む12か国と加盟交渉が行われている。
EU加盟交渉は、EU法体系の総体である「アキ・コミュノテール」の受容状況について、各項目ごとにスクリーニングと呼ばれる厳格な審査が行われ、この審査を経た後、実務的な加盟交渉に入る。「アキ・コミュノテール」は31項目に分かれ、政治、経済、社会の広い分野を対象としている。98年3月に第1陣として加盟申請を開始した国は、国により異なるが、99年末までに31項目のうちおよそ8~11項目の加盟交渉を終えている。
各国は審査の準備にあたり、欧州委員会が各国別に作成する「加盟パートナーシップ(Accession Partnership)」で求められる優先政策課題を中心に、加盟に向けた構造改革を推進している(第1-3-29表)。こうした経済構造改革の進捗状況は欧州委員会により評価が行われており、99年10月の「定期報告書」の中ではポーランド、ハンガリーについては比較的高い評価がなされた。しかし、各国とも一層の改善努力が求められている。
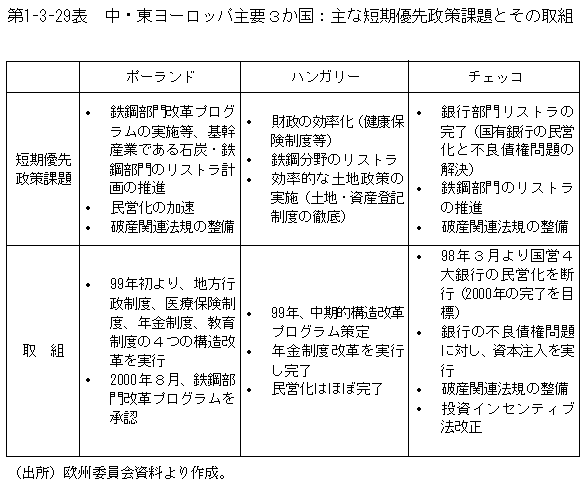
99年12月の欧州理事会ヘルシンキ会議以降、EU諸国にとってEU拡大政策は欧州全体の安定化という政治目標の重要な手段として優先課題に据えられている。加盟申請諸国にとっても加盟に向けた構造改革は中長期的に持続可能な経済成長を促すだけでなく、市場経済化を進展することにより海外からの直接投資の増加が期待できる。直接投資は設備投資や雇用機会の増大、技術移転等を通じて富を増幅させ、経済成長をさらに加速させると期待できる。
脚注
- 1 「移行国レポート1999」では中・東ヨーロッパ及びバルト三国とは、アルバニア、ブルガリア、クロアチア、チェッコ、エストニア、マケドニア旧ユーゴスラヴィア共和国、ハンガリー、ラトビア、リトアニア、ポーランド、ルーマニア、スロヴァキア、スロヴェニアを指す。
3 ロシア:景気は拡大している
ロシアでは、92年初から市場経済移行に向けて経済改革を行ってきたが、生産の低下が続き、インフレの昂進等で経済はマイナス成長を続けていた。97年には実質GDP成長率が市場経済移行後初のプラスとなったものの、98年はロシア金融危機の影響で、再びマイナス成長へと転じた。
99年にはロシア経済は回復に転じたが、これは98年8月の通貨ルーブルの切下げにより輸入代替効果の進展がみられたことや、99年後半以降は主要輸出品目である原油の国際価格の上昇を背景に金額ベースで輸出が回復したことによる。99年の実質GDP成長率は前年比3.2%と、市場経済移行以来最大の伸びを記録し、その後も2000年1~3月期前年同期比8.4%、4~6月期同6.7%と拡大が続いている(第1-3-30図)。鉱工業生産は、99年は前年比8.1%増となり、2000年に入っても増加を続けている。輸出の回復に伴い貿易黒字も大幅に拡大し、99年は362億ドル(ロシア中銀公表数値)の黒字となった。消費者物価指数上昇率は、99年12月末で前年比36.5%と、前年末の同84.4%を大きく下回った。しかし、失業率は依然高止まりしており、99年のILO基準による失業率は12.6%となった。
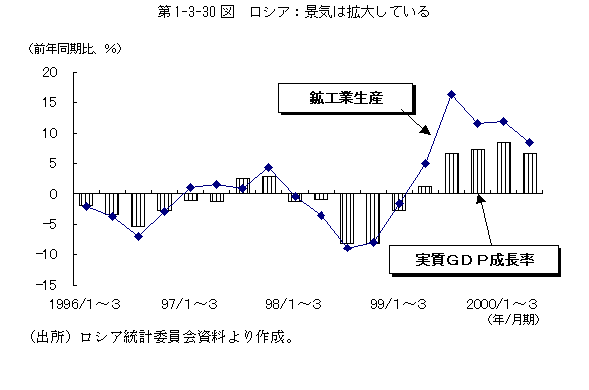
海外からの資金の流入動向(1)をみると、海外からの対内直接投資は大型案件のあった97年に比し、98年は大幅な減少を余儀なくされたが、99年は輸入代替産業を中心に再び回復基調にある。
このように、ロシア経済は拡大しているものの、原油価格動向など外的要因に大きく依存しているため経済基盤は依然ぜい弱であるといえる。今後、経済成長を持続させるために経済改革を継続する必要があり、2000年5月に新たに就任したプーチン大統領も政府社会経済プログラムを策定し、ロシア経済改革の課題に積極的に取り組んでいる。
(ロシア金融政策の動向)
ロシア中央銀行は金融政策の主要目標の中に、物価の安定及び為替レートの安定を掲げているが、マネーサプライの急増からその両立が困難となる可能性がある。
物価動向をみると、99年末の消費者物価上昇率は98年末に比し大幅に下落し、99年後半より前月比0~1%台と概ね安定して推移していたが、2000年5月から前月比はやや高まりをみせ、10月は同2.1%となった(第1-3-31図)。
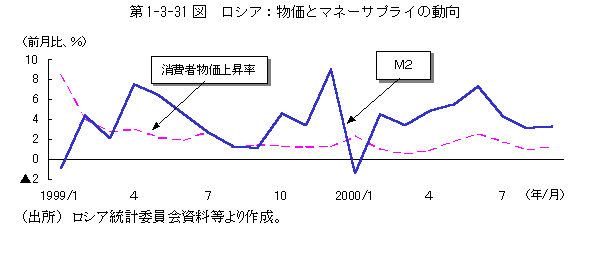
ロシアルーブルの対ドルレートは2000年9月では27ルーブル/ドルと、大幅下落が始まる前の98年8月当時の約1/4となっている。このルーブルの減価により生じた輸出需要や輸入代替効果が99年後半の景気回復をもたらしたことを考えると、ルーブルの安定はロシアの経済成長を持続させる条件として欠かせないものとなっている。このため、ロシア中銀は貿易黒字によるルーブル需要をけん制しながら為替レートを概ね安定した水準に維持するよう努めている。この結果、外貨準備高は2000年に入ってから急増し、金融危機前の水準を越え過去最高となった(第1-3-32図)。
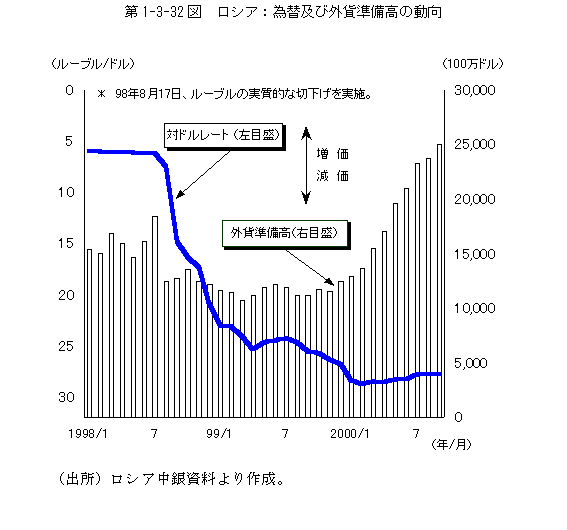
こうしたなか、マネーサプライ(M2)の増加率が加速する傾向にあり、物価への影響が懸念されている。2000年9月には前月末比3.4%、99年12月末比40.8%の大幅増となっており、この背景には外貨準備高の急増があるものと考えられる。
これまでのところ、マネーサプライの急増から物価上昇への波及は限られたものとなっているが、今後の動向には注意が必要である。物価の安定及び為替の安定を巡る金融政策の舵取りは困難さを増しつつあるといえる。
(プーチン政権のロシア社会経済プログラム)
ロシア政府は、2000年6月の閣議で政府の社会経済プログラムとして「2010年までの長期的な社会経済政策の基本方向」及び「2000~2001年の社会経済行動計画」を審議し、基本的方向性を承認した。長期プログラムである「2010年までの長期的な社会経済政策の基本方向」では、今後10年先までの社会経済政策の基本方針をまとめ、平等な競争条件の確保、所有権保護、規制緩和、税負担軽減等を推進して市場経済ルールを徹底させ、国内投資を活発化することによって経済発展の基盤を確立し、効果的で競争力のある経済を作り、ひいては国民生活の向上を図る、という理念を掲げた。政府はこの基本方針に則った政策の実行により、実質GDP成長率は2010年まで年平均で最低5%になるものと期待している。
一方、「2000~2001年の社会経済行動計画」とは、この長期プログラムを実現するために、2000~2001年の今後18か月間に優先的に取り組むべき課題とその行動計画を示した短期プログラムであり、6月の基本承認の後、政府内の調整を経て7月に正式承認された。また、長年の懸案であった税法典第二部に関しては、所得税、統一社会税をはじめとする大部分につき議会の承認が行われ、2001年1月1日から施行される。
このような経済プログラムや税法典を巡る動きをIMFや世銀も好意的に評価しているが、今後ロシアが経済基盤を確立し、競争力のある経済を形成し得るかどうかは、この方針に基づいてどの程度改革を実行できるかにかかっているといえよう。
脚注
- 1 国際金融機関との関係をみると、IMFからは2000年7月にミッションが派遣され協議を実施したが、合意には達しなかった。11月に再度派遣が予定されている。世銀からは2000年6月にミッションが派遣され、SAL3(11億ドル)等未貸付案件について協議した。SPALの最終トランシュ(2.5億ドル)が8月に供与された。
| 第1章 世界経済の現況 | 第2章 知識・技能の向上と労働市場 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 |
| 概観 | アメリカ | 欧州 | アジア | 金融・商品 | IT | アメリカ | 欧州 | アジア |

