第2章 家計部門の構造変化(第3節)
第3節 価格変動と消費行動
前節では消費動向についてやや長期的な構造変化を考察したが、本節は消費動向を左右する重要な要素の一つである価格に注目した分析を行う。消費と価格の関係については、一般に、原材料価格の上昇など供給側の要因によって価格が上昇する場合には当該財の消費は低下する一方、所得の増加などに伴い消費が増加する局面では、需要増加によって価格上昇がもたらされるという関係がある。加えて、時間軸の観点からは、将来的に価格上昇が見込まれるような際には、消費が前倒しされ、価格上昇後に消費が低下するという異時点間の消費代替も生じる。2014年4月の消費税率の5%から8%への引上げの際には、消費の低下がみられたが、これは税率引上げという供給面の影響に加え、税負担の増加が実質所得を押下げるという需要面の影響と、税率引上げ前後での駆け込み・反動という異時点間の代替の動きが同時に生じたと考えられる。
本節では、こうしたメカニズムを詳しく分析するために、まず、過去の付加価値税率引上げ時の消費への影響を国際比較した上で、日本と諸外国との動向の違いの背景について、消費の価格弾性性・所得弾性性の大きさや、消費の異時点間の代替に影響を与え得る流動性制約に直面した家計の割合を確認し、最後に一般的な経済モデル上でこれら要因の影響について検証する。
1 需要曲線・供給曲線の変化と物価動向
(POSデータによると消費税率引上げ前後の数量変化には供給要因が寄与)
経済学における一般的な需要関数と供給関数を想定すると、需要関数は右下がりの曲線(価格が上昇すると数量が減少)、供給関数は右上がりの曲線(価格が上昇すると数量が上昇)で定義することができ、両者の曲線が交わる部分で数量と価格が決定される。供給側に原材料価格の上昇(低下)等のショックが起これば、供給曲線は左方(右方)にシフトするため、価格上昇かつ数量減少(価格低下かつ数量増加)が確認される。逆に、マインドの改善(悪化)等の需要側に対するショックは、価格上昇かつ数量増加(価格低下かつ数量減少)につながる。
ここでは数量と価格変化の関係性について、スキャンデータの一種であるPOS(Point of Sale)データから観察してみよう。同データは消費者がスーパー等で商品を購入する際にレジで読み取る情報を記録したものであり、商品分類毎に数量と価格(税抜き)の変化を同時にみることができる点に強みがある。
第2-3-1図(1)は2010年1月~2018年3月の期間における「菓子パン」と「みつ・シロップ」の商品分類における定価と数量の変化(前年比)の関係性をみたものである1。菓子パンについては負の相関がみられており、小麦粉・砂糖等の原材料価格の変化等(供給曲線のシフト)により、価格上昇かつ数量減少(価格低下かつ数量増加)が生じていると思われる。一方、みつ・シロップ(はちみつ、メープルシロップ等)では、正の相関関係がみられおり、例えば、健康志向高まり等(需要曲線のシフト)により、価格と数量の双方が増加する可能性が指摘できる。
上記の商品例では、菓子パンでは供給曲線、はちみつ・シロップでは需要曲線のシフトが期間を通して多かったため、比較的明確な相関がみられたことが考えられるが、実際には同じ商品でもその時々により需要・供給要因の双方の要因で変動する。内閣府(2018)は、日用品・食料品のPOSデータ(217品目分類)における月々の価格・数量の変動2を、①価格上昇かつ数量増加、②価格上昇かつ数量減少、③価格低下かつ数量増加、④価格低下かつ数量減少の4つのカテゴリーに分解し(①・④:需要要因、②・③:供給要因)、それぞれの割合をプロットしている。この分析を本節の関心事項である2014年4月の消費税率引上げ前後でみると(第2-3-1図(2))、2014年3月では「価格低下かつ数量増加」(供給面の影響)の割合が増えているが、引上げ後においては「価格上昇かつ数量減少」と「価格低下かつ数量低下」(需要面の弱さ)の割合が増加している。
また、217品目分類それぞれの数量変化率を上記の4つのカテゴリーに分類して統合することで、POSデータ全体の数量変化に対する寄与度を算出することができる。算出した寄与度分解を同じく消費税率引上げ前後でみると(第2-3-1図(3))、2014年3月の駆け込みと4月以降の反動減がみられており、3月~6月の変動に対する寄与は、需要要因も一定程度影響しているが、全般的に供給要因の方が大きくなっている。つまり、3月においては「価格低下かつ数量増加」の寄与が大きく、4月以降においては「価格上昇かつ数量減少」の寄与が大きくなっている。こうしたことから、消費税率引上げ前後の期間においては、小売店において消費税率引上げ前に価格を下げ、増税後に価格を引上げるという行動をとっていた可能性が示唆される。ただし、ここでの分析に利用したPOSデータは日用品・食料品のみに限られているため、以降の分析ではマクロのデータを用いて、価格と消費の動向についての考察を深めていくこととしたい。
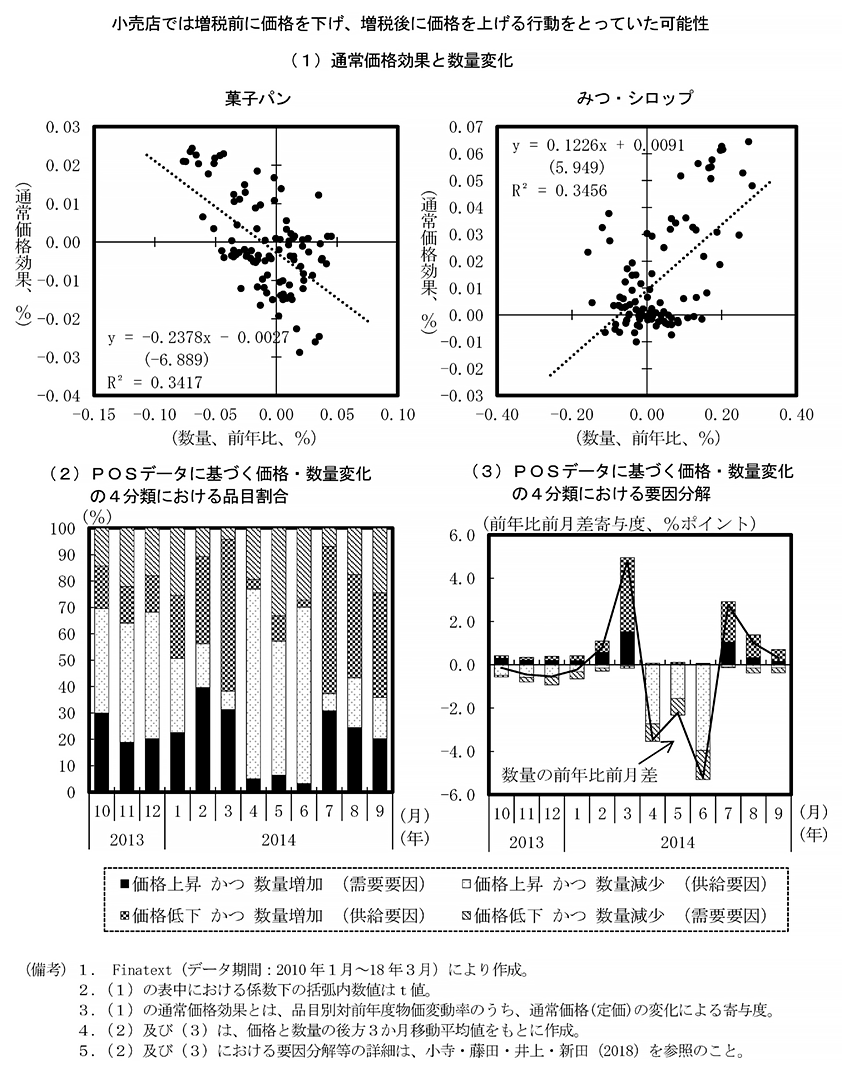
2 付加価値税率引上げの国際比較
(欧州において反動減が小さい背景には、税込価格の改定が緩やかなことが関係)
2014年4月の消費税率引上げの際には、内閣府(2015)によると、3兆円程度の駆け込み・反動が観察されたが、日本においては諸外国と比較するとこの駆け込み・反動が大きいことが指摘されている。例えばIMF(2018)では、付加価値税率引上げ時における消費の伸びがどの程度低下するかをみると、OECD平均では▲0.6%ポイントの低下であるのに対し、日本では過去3回の平均は▲4.4%ポイントの低下であると指摘している。
では実際に、諸外国と比較した消費税率引上げ前後における個人消費の動向をみてみよう。ここでの消費増税のケースは、日本は2014年4月、ドイツは2007年1月、英国は2010年1月を対象としており、税率の変化幅は日本・ドイツは+3.0%ポイント、英国は+2.5%ポイントである(第2-3-2図(1))。また、増税に先立ってドイツ・英国では軽減税率の適用等、日本でも一部減税や給付金等、各国とも増税の影響を緩和するための政策をとっていることがわかる。
まず、実質個人消費3の動向を確認すると(第2-3-2図(2))、いずれも国でも消費税率引上げ前の期において消費は上昇し、消費税率引上げ時にマイナスになっているが、消費税率引上げ時の落ち込みは日本が非常に激しい。特に、ドイツと日本を比較すると、消費税率の引上げ前(-3~-1期)・引上げ後(+1~3期)の動きは非常に似ており、個人消費の伸び率もほぼ同程度である。しかし、日本の引上げ時(0期)における減少が非常に激しいため、水準で比較すると消費税率引上げ後の日本とドイツは乖離している姿となっている。
各国における消費税率引上げ前後の背景を詳しくみると(第2-3-2図(3)~(5))、ドイツと英国において、消費税率引上げ前に増加し、引上げ後に減少というパターンが明確なものは耐久財のみである4。ドイツでは非耐久財、英国ではサービスが消費税率引上げ時(0期)に減少しているものの、耐久財の落ち込みと比較するとその寄与度は小さい。一方、0期における耐久財のマイナス寄与は日本とドイツは同程度であるものの、日本では耐久財以外のすべての分類が減少に一定程度寄与していることが、日本の減少率が大きいことにつながっている。特に、非耐久財の減少が大きく、耐久財以上に全体の減少に寄与している。
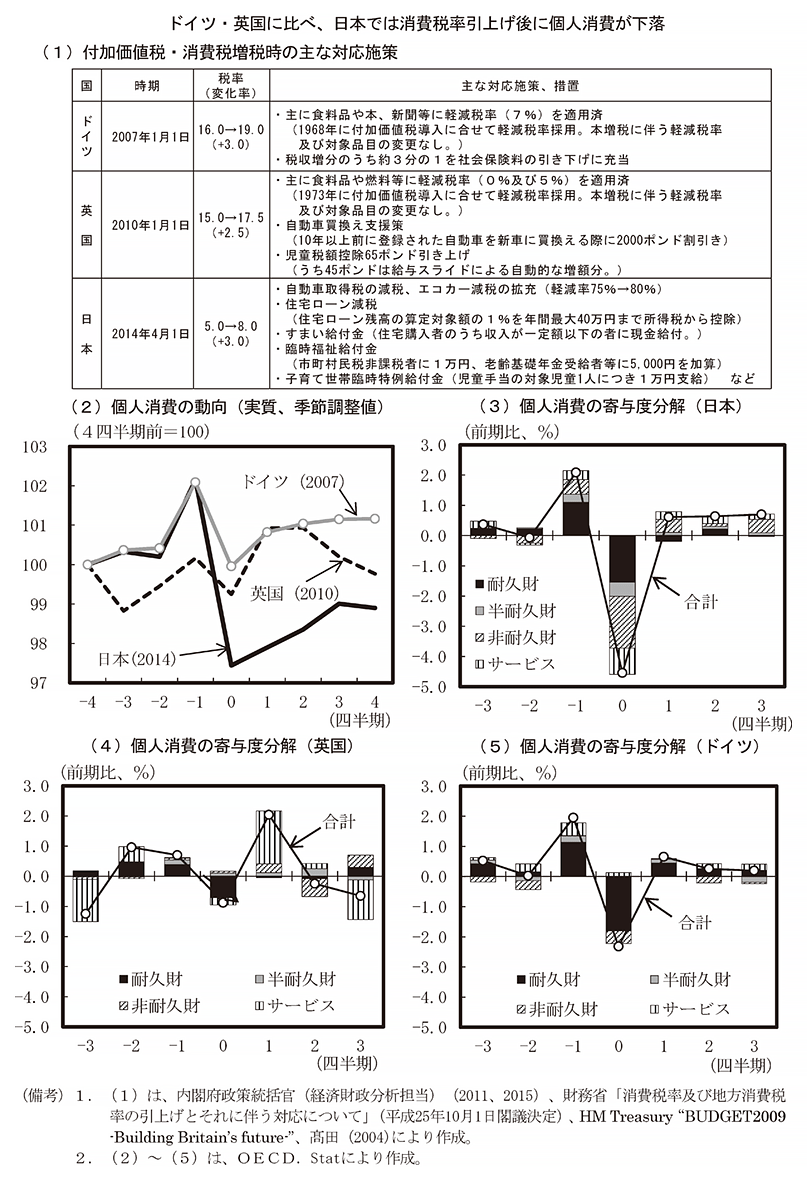
このような日本と諸外国における違いはどこから生じているのだろうか。まず、日本における非耐久財の減少という点については軽減税率が行われていなかったことが影響している可能性が考えられる。非耐久財には食料品等が主に含まれるが、こうした購入頻度の高い品目の価格上昇が消費者心理に影響を与えている可能性がある。欧州のデータを用いた実証分析によると、税率変更のみの場合は消費の減少が有意となるが、税率変更と同時に軽減税率を変更した場合、消費の落ち込みは有意でなくなるとの結果もある(小巻、2017)。
また、日本では価格が一斉に変化することも影響している可能性がある。第2-3-3図(1)は消費増税前後の物価上昇率の動きをみたものであるが、イギリス・ドイツでは消費税率引上げ前後において急激な物価変動が観察されていないが、日本では引上げ時(0期)に物価上昇率がジャンプしていることがわかる。この背景として、欧州では増税前から商売を取り巻く様々な環境を考慮して価格を徐々に改定させる傾向があり、その改定方法も需要に応じて商品毎に異なる価格改定を行うことで、全体として売上とマージンを確保できるようにしていることが指摘できる(森信、2014)。事実、ドイツの2007年の消費税率引上げを分析した研究によると、税率引上げを見越した値上げが2006年に中に行われていたため、物価上昇が平準化されたと分析している(Danninger and Carare、2008)。
さらに、日本においては、消費増税前に駆け込み需要を後押しするような環境下にあったことが、耐久財以外の形態でも駆け込み・反動が顕在化した可能性が考えられる。欧州のように価格変化が平準化された場合、駆け込むべき時期は消費者にとって必ずしも明確ではないが、一律の価格改定が予見されている環境下では、企業側も消費税率引上げ前に販売促進的な行動を行うインセンティブが生じる。例えば、前掲第2-3-1図のPOSデータの数量変化でも、2014年3月の数量増加は、「価格低下かつ数量増加」の寄与が大きかったことを指摘したが、駆け込み需要を狙ったセールが行われていた可能性が示唆される5。
また、メディアにおける消費税や駆け込みに関する報道が、消費心理に影響を与えた可能性もある。第2-3-3図(2)・(3)は全国紙6において「消費税」と「駆け込み」という用語を含む記事の件数をカウントしたものであるが7、2014年4月に向けて、「消費税」や「駆け込み」の単語を含む記事数が増加傾向にあることがわかる。メディアが企業側の販売促進的な行動や消費者の行動等を報告することで、消費者マインドに影響を及ぼした結果、消費者の駆け込み・反動が強化された可能性も考えられる。こうした消費税に対するマインドの違いを欧州と比較するため、消費税率引上げ前後において、日本語・ドイツ語8で「消費税」のキーワードがどの程度検索されていたのかを確認した(第2-3-3図(4))。図は、2014年3月における日本語の検索数を100として相対的な推移をみたものだが、増税後の水準は概ね同じであるが、引上げ前の駆け込み時期に両者は大きく乖離しており、増税1ヵ月前における検索数では、ドイツ語は日本語の半分以下である。ドイツと比較すると、日本の消費者は消費税率引上げに対する関心が非常に高かった可能性が指摘できる。
上記では日本における反動が大きい背景を考察してきたが、そもそもの税率の水準の違いが影響している可能性には留意が必要である。例えば、日本とドイツは幅でみれば同じ+3%ポイントの変更であるが、ドイツは16%から19%、日本は5%から8%の改定である。初期値が高い水準から増加させる場合と、低い水準から増加させる場合とでは、後者の方が心理的なインパクトが大きくなる可能性がある。こうした初期値の税率の違いが企業の販促戦略や報道の頻度に影響を与えたことも考えられる。
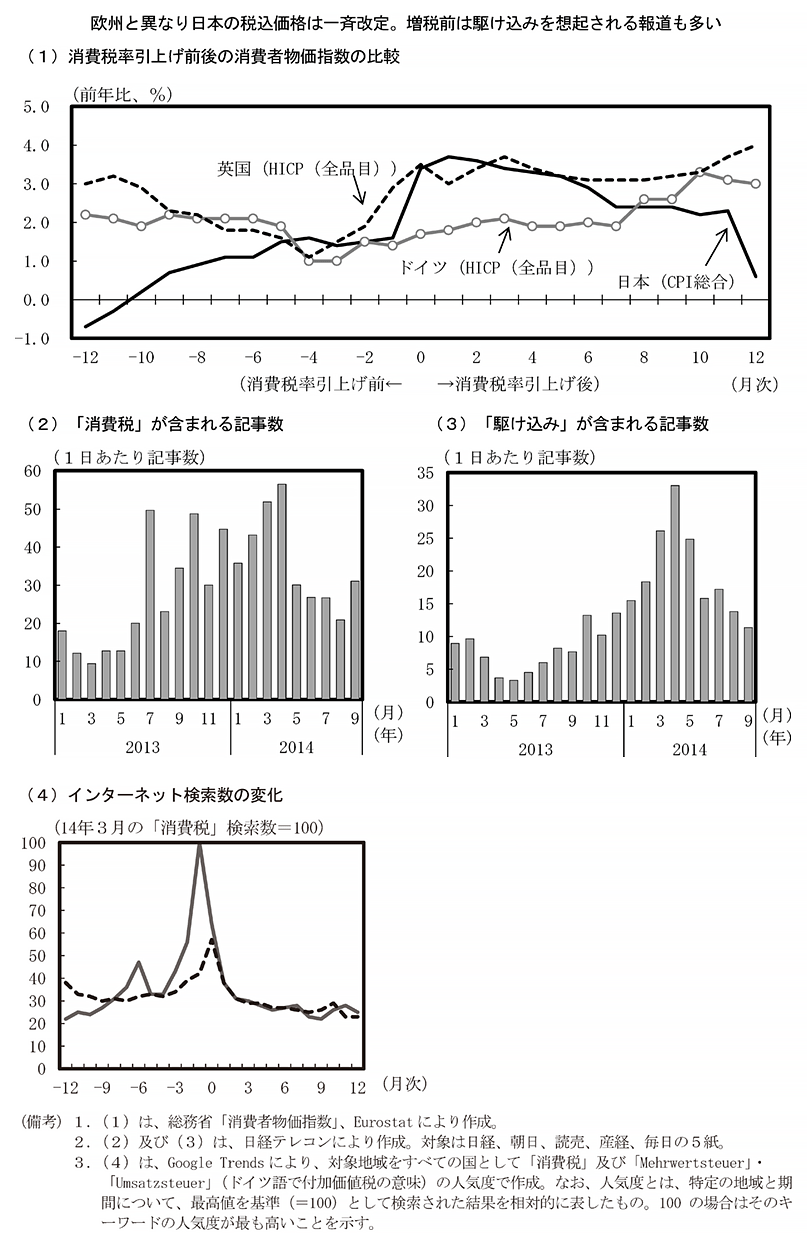
(日本は非耐久財の価格弾力性が相対的に高い可能性)
日本において消費税による落ち込みが大きくなる可能性の一つには、価格弾力性(価格が変化した際の需要(消費シェア)の変化9)の違いも考えられる。また、日本における世帯構造が変化していることを踏まえれば、世帯属性別にみた価格弾力性についても把握しておく必要があると思われる。そこで、Deaton and Muellbauer(1980)により提案され、最も一般的な関数型をもった需要関数と言われているAIDS(Almost Ideal Demand System)型の関数を推定することで、この価格弾力性を推計する10(関数の詳細については付注2-3を参照)。
まず、日本、ドイツ、英国の3か国における需要関数の推定を、国際比較の観点からSNAベースで行う。分類は耐久財・半耐久財、非耐久財、サービスの3つに分類し、1995年以降の時系列データを用いる11。推計された需要関数から価格・所得弾力性12を算出したのが第2-3-4図(1)である。(自己)価格弾力性を比較すると、各国とも耐久財・半耐久財の価格弾力性が大きい点は共通しているが、全般的に日本の価格弾力性は他の2か国と比較して大きくなっており、日本の家計はより価格変化に敏感である可能性が考えられる。特に、日本では非耐久財における価格弾力性が相対的に高くなっている。上記でみたように消費税率引上げ時には非耐久財の減少が日本では大きかったが、この背景には非耐久財の価格変化に対し日本はより敏感に反応する傾向があった可能性がある。また、所得弾力性をみると、日本では耐久財・半耐久財の弾力性が相対的に大きくなっており、所得が高くなればより多くの資金を耐久財・半耐久財に充てる動機があることが考えられる。
次に、世帯の構造変化を踏まえ、世帯主の年齢階級別に、より詳細な分類を用いて(自己)価格弾力性を推計する。具体的には、総務省「家計調査」の2人以上の世帯の時系列データを用い、分類は先行研究に倣い住宅を除く9分類を利用した13。分析結果をみると(第2-3-4図(2))、ほぼすべての分類で弾力性は負になっており、価格が上昇した財・サービスの需要は減少する傾向にあることがわかる。ただし、保険・医療については、価格が上昇すると消費シェアが高くなることがすべての年齢階級でみられていることから、医療品・診療代等の必要な支出は価格が高まっても需要を変えないことがシェアの増加につながっている可能性が考えられる。また、40~64歳の世帯における教育もほぼ非弾力的であり、価格が変化しても教育投資に対する行動を変えないことも示唆される。また、食料、光熱・水道等の生活する上で必要となる非耐久財の価格弾力性は、年齢階級別にみても大きな差がみられないが、家具・家事、被服・履物といった耐久財・半耐久財の項目においては、年齢階級別に差が見られており、全体的に若年世帯において価格上昇に敏感に反応する傾向がみられる。なお、交通・通信については、若年世帯や高齢世帯において価格弾力性が高くなっている。
上記の推計結果からは、国際比較では日本において非耐久財等の価格弾力性が相対的に高い可能性が示された。また、一部の耐久財や半耐久財は年齢による価格弾力性の差がみられたが、非耐久財の大部分を占める食料や保険・医療といった生活する上で必要となる分野の価格弾力性は年齢による差が小さいことも示唆された。
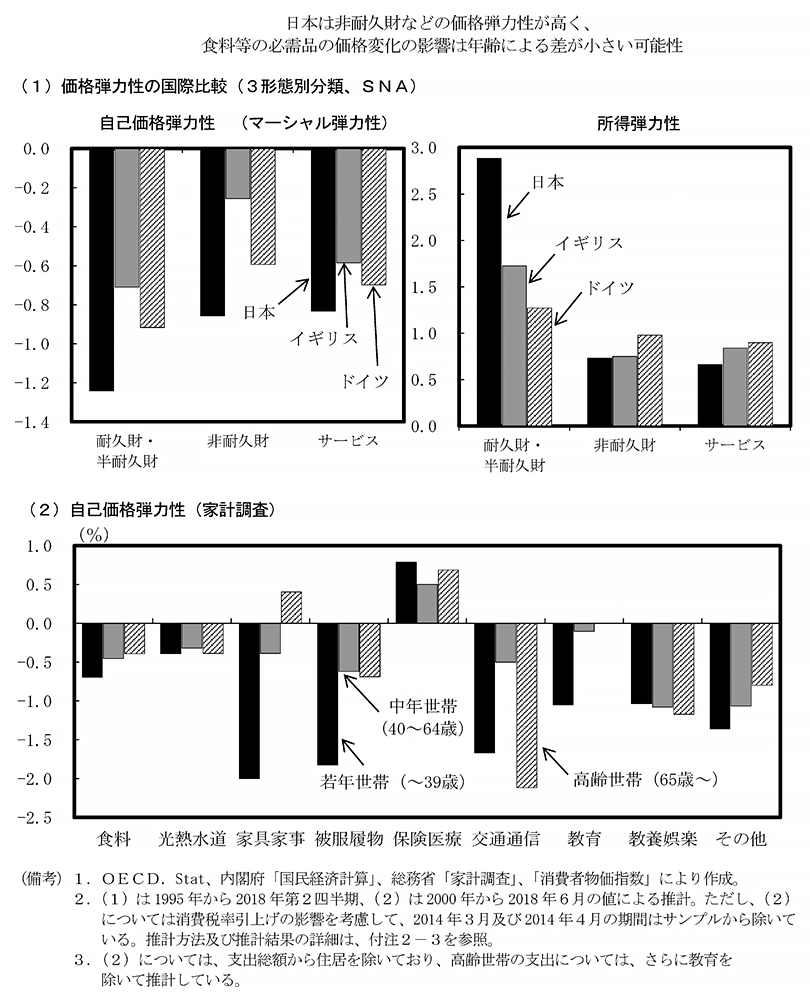
3 消費の平準化に関する考察
(日本では駆け込むことが可能な世帯が多い可能性)
消費税等の価格変動が予見されている中では、消費の平準化(異時点間における消費の最適化)を行うことが家計にとって合理的な行動であると考えられるが、すべての家計が平準化を行えるわけではない。一般的には、このような家計は金融市場からの借入ができない等の理由により、流動性制約に直面しており、消費額と所得額が等しくなる「非リカーディアン家計14」、または「その日暮らしの家計(Hand-to-Mouthの家計)」と言われる。流動性制約家計では、毎期の所得をすべて消費するため、実質所得が減少した場合、消費額も同程度減少し、税率変更等の影響を受けやすい。これに対して、流動性制約にない家計(リカーディアン家計)では、異時点間の観点から合理的な消費行動を行うことが可能となるため、一時的な所得変動には影響されない。
ここではKaplan et al.(2014)の手法を適用した宇南山・原(2015)やHara et al.(2016)を参考に、2014年と2004年の総務省「全国消費実態調査」を用いて日本における流動性制約家計の割合を計算する。具体的には、資産を流動資産(預貯金、有価証券等)と非流動資産(純不動産額、保険等)を分け、収入が家計に入り支出されるというサイクル上で収入がボトムとなる地点で流動資産がゼロとなる家計(もしくは借入限度額15まで借りた家計)を流動性制約家計と定義する。例えば、給与日に流動資産(=給与額・月収)が最も高くなり、次の給与日にかけて、そのすべての流動資産を使いきるような家計である。また、不動産等の非流動資産はすぐに現金に換算することができないため、非流動資産はプラスであっても流動資産が少なければ、流動性制約に直面している流動性制約家計となる。このような非流動資産が正である家計を「資産を保有する流動性制約家計」、逆に非流動資産もない家計は「資産を保有しない流動性制約家計」と定義する。詳細な定義については付注2-4を参照されたい。
計算結果をみると(第2-3-5図(1))、2014年における流動性制約家計の割合は2人以上の世帯で13.7%(うち資産を保有する家計8.5%、資産を保有しない家計 5.2%)、単身世帯で12.5%(うち資産を保有する家計 6.4%、資産を保有しない家計 6.0%)であり、単身世帯と2人以上の世帯の間で流動性制約家計の割合は大きく異なってはいないが、単身世帯では資産を保有しない流動性制約家計のシェアが若干高くなっている。総世帯ベースを計算すると16、13.3%(うち資産を保有する家計 7.8%、資産を保有しない家計 5.5%)となる。また、2004年では2人以上世帯・単身世帯ともに10.5%であるので、2014年にかけて若干流動性制約家計の割合が増加した姿となっている。
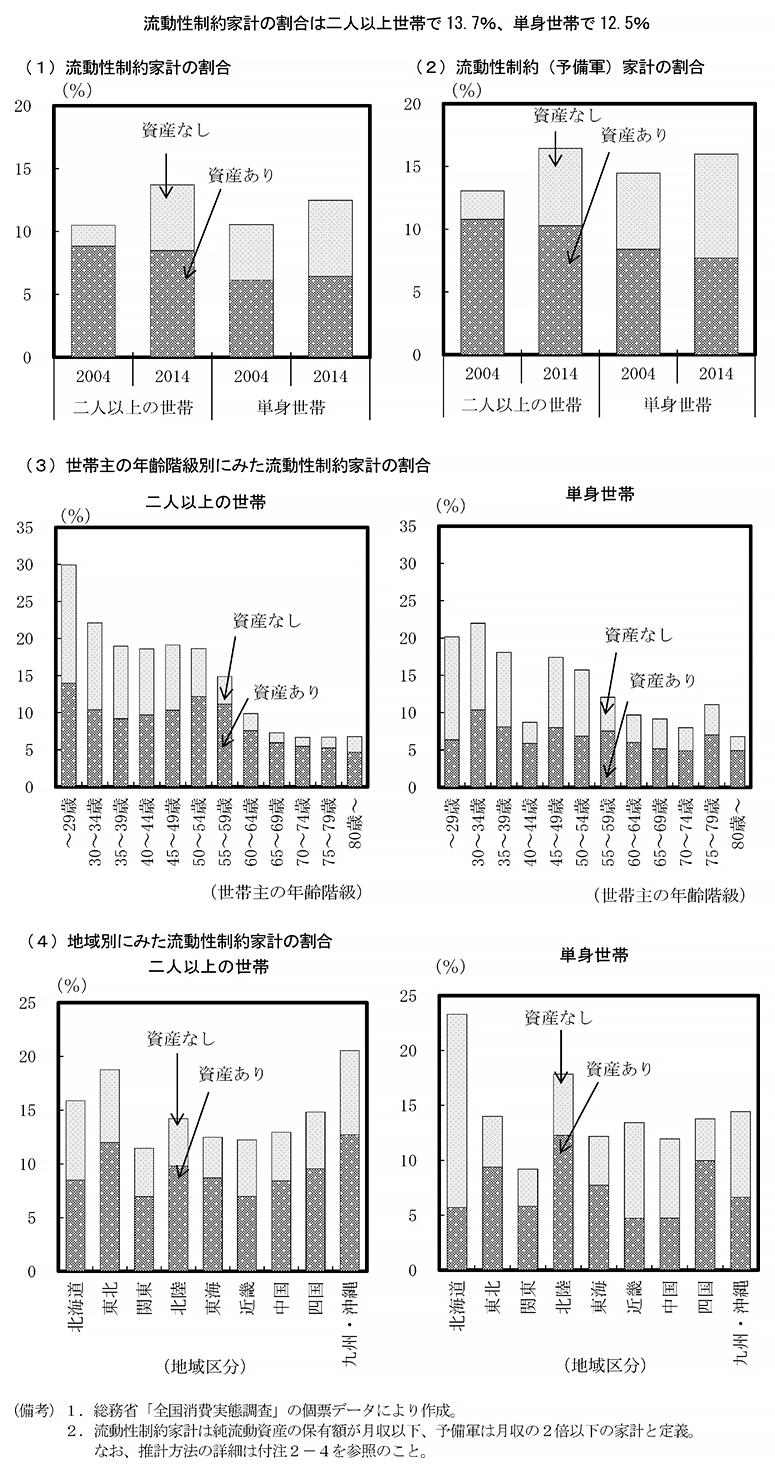
次に、上記で計算した流動性制約家計に加え、一定程度の流動資産はあるものの、その水準が低いため、まとまった消費をした際には流動性制約家計になる可能性のある世帯(流動性制約家計の予備軍)を含めた割合を計算する。流動性制約家計の予備軍は、便宜上収入サイクルの最終地点における流動資産の残額が給与額と同じ世帯と定義する。つまり、何らかの理由で月収の1か月程度の消費を追加的に行った場合、流動資産がゼロ(流動性制約)になるような世帯である。第2-3-5図(2)が推計結果であるが、2014年では2人以上の世帯で16.4%(うち資産を保有する家計:10.3%、資産を保有しない家計:6.2%)、単身世帯で16.0%(うち資産を保有する家計:7.7%、資産を保有しない家計:8.3%)、総世帯で16.3%(うち資産を保有する家計:9.4%、資産を保有しない家計:6.9%)である。総世帯で予備軍を含めた上昇幅は3%ポイント程度であり、予備軍を含めても割合は大きく変動しない結果となっている。2004年と比較すると、2014年は予備軍の割合が若干増加している点も先ほどと同じである。
日本の流動性制約家計がどのような家計なのかについて、より詳細にみていこう。まず、世帯主の年齢階級別に流動性制約家計の割合をみると(第2-3-5図(3))、若年の世帯ほど流動性制約家計の割合が多く、その中でも資産を保有しない流動性制約家計のシェアが大きいことが指摘できる。高齢世帯においても一定程度の流動性制約家計が存在しているが、そのほとんどは非流動資産を保有する流動性制約家計である。2人以上の世帯と単身世帯を比較すると、どの年齢区分でも概ね同程度の割合となっており、大きな違いはみられない。次に、流動性制約家計の割合を地域区分でみると(第2-3-5図(4))、2人以上世帯・単身世帯とも相対的に関東における割合が小さくなっていることが指摘できる。サンプルによる振れもあるが、その他の地域における流動性制約家計の割合はおおむね同程度であると考えられる。
日本の流動性制約家計の割合は13.3%、予備軍を含めても16.3%であるが、この割合は諸外国と比較しても小さい可能性が指摘できる。Kaplan et al.(2014)は、先進国8か国において同様の推計を行っているが、最も低いオーストラリアでも19%程度であり、上記でも比較した英国とドイツは30%を超えた値となっている(第2-3-6図)17(%)。日本では異時点間の観点から消費行動を行える家計が多く、消費税率引上げ前に駆け込むことが可能であった家計は諸外国と比較しても多い可能性が指摘できる。
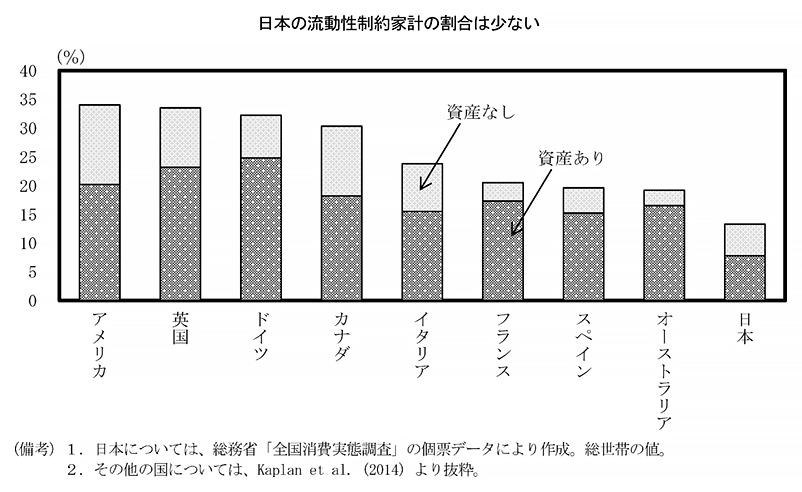
(DSGEモデルによる消費と価格のシミュレーション)
価格と消費分析の最後に、人々の予想を取りこんだ一般的なマクロ経済モデルであるDSGE(Dynamic Stochastic General Equilibrium)モデルを使って、予見された価格上昇(消費税)が消費にどのような影響を与えるのかについて考察する。DSGEモデルは、将来を予見して行動する経済主体を前提とした動学的なモデルであり、人々が合理的な行動を行うとの仮定の下で、消費税率引上げが消費等に与える影響等のシミュレーションを行うことが可能となる。ここでは江口(2011)等で使用されている一般的な「ニューケインジアンモデル」を想定する。すなわち、経済主体として、家計・企業・政府・中央銀行を想定し、(税抜き)価格の粘着性、流動性制約家計の存在等をモデルに導入している。モデル内における政策の影響を受けないパラメーターについては、先行研究18に基づき設定を行った。モデルやパラメーターの設定の詳細については付注2-5で説明しているが、あくまでも本分析は、現実経済の動向を実証的に検証したものではなく、各経済主体の行動様式等に関して様々な仮定を置いた上で、仮想的に各経済主体が理論に沿った動きをした場合の経済動向等を試算したものである。
ここでのシミュレーションのベンチマークとして、0期において定常状態19にある経済において、一定期間後(ここでは10期後としているが現実の特定の期間に対応するものではない)に消費税率を5%から8%に引上げることを第1期にアナウンスするというケースを考える。これは、前回の消費税率引上げ時の引上げ幅等を念頭には置いているものの、あくまでも仮想的な試算であることには留意する必要がある20(第2-3-7図)。図中の(A)がベンチマークケースの結果であり、図は消費の定常状態からの変化を示すものとなっている。人々は将来を予想して行動するので、1~9期においては駆け込み需要が発生することがみてとれる。また、モデル内には異時点間で消費の代替を行うことが困難な流動性制約家計が含まれるが、上記で計算した通りその割合は1割程度であると設定しているため、多くの家計では消費税率引上げ前の価格の安い時期に購入しようと消費を増やし、増税後に消費を減らしていることがみてとれる。
次に、ベンチマークケースから様々な変更を加えた際に消費動向がどのように変化するのかについて試算する。まず、第10期に消費税率を5%から8%に引上げるアナウンスを第1期ではなく第6期に遅れて行った場合にどうなるのかを見てみよう(B)。図からは、駆け込むことができる期間が短くなったため、ベンチマークと比較して駆け込み期における消費の上昇幅が高くなっていることがわかる。一方、税率を引上げた第10期以降については、駆け込んだ消費の量が多少小さくなることから、ベンチマークよりも若干反動が少なくなっている。
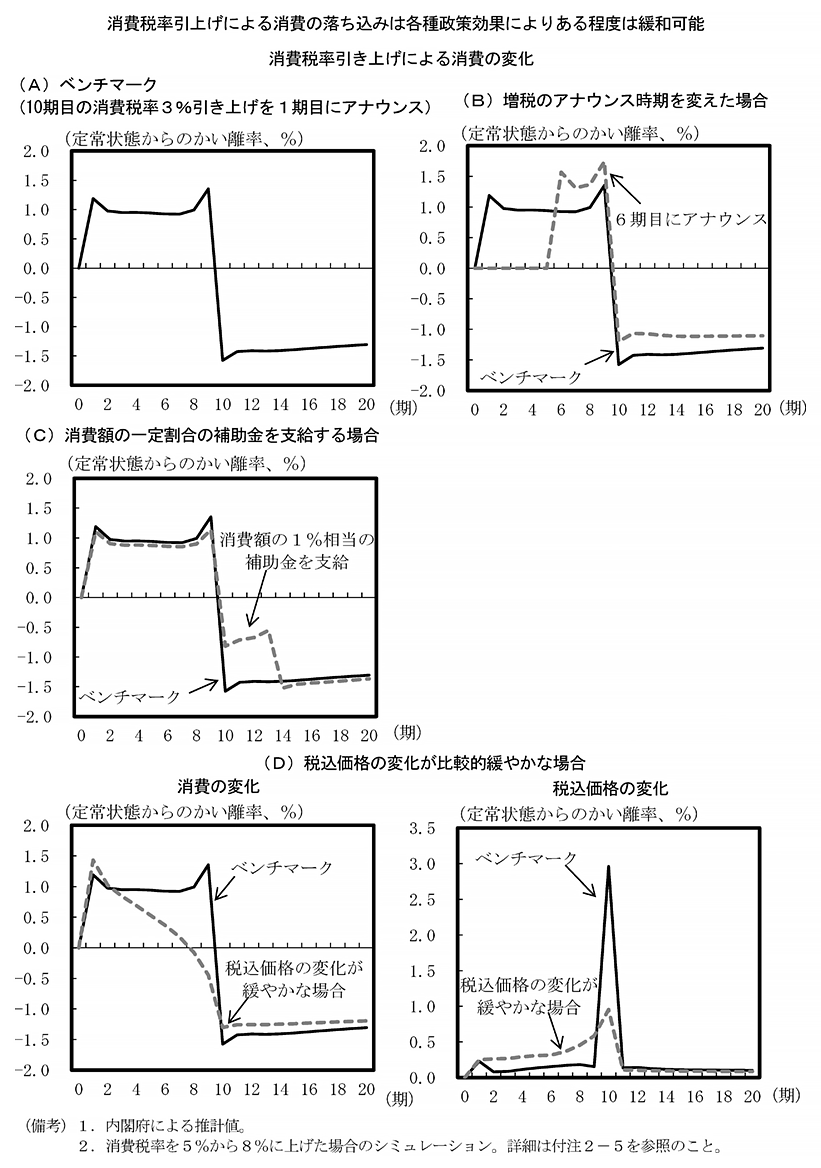
上記でみたように、消費税率引上げによる駆け込み・反動は、将来を予見する家計にとっては合理的な反応ではあるが、企業側にとっては生産や在庫調整のコストが発生するため、駆け込みと反動については出来るだけ均す方が望ましいと考えられる21。
そこで各期における消費変動(特に10期)を緩やかにする取組を行った場合の動向を試算する。具体的には、消費額の1%分の補助金(負の消費税)を第10~13期に支給した場合を考える22(C)。このケースにおいては、駆け込みから反動までがより緩やかになっており、第10期における減少もベンチマークと比較すると小さくなっていることがみてとれる。
また、欧州のケースのように、価格改定が緩やかに行われるケースについても試算した。具体的には、第1~9期において緩やかに価格を改定していき、第10期までに税率3%ポイントの上昇をすべて反映させると想定する(D)。図の価格変化は前期比の物価(税込)の伸びであるが、ベンチマークケースと比較して、価格改定が平準化されていることがわかる。このような環境下ではアナウンス時に消費は拡大するが、その後は緩やかに価格が改定されるため、消費動向に明確な駆け込みと反動がみられていないことがわかる。欧州の税率引上げ時の落ち込みが、日本より小さい背景にこの緩やかな価格上昇が関係している可能性がモデル上からも示された結果となった。
(2019年の消費税率引上げに向けた取組は、消費の平準化に寄与することが期待)
2019年10月には消費税率が8%から10%に改定されることが予定されているが、以上の分析を踏まえると、どのようなインプリケーションがあるだろうか。
まず、2014年における消費税率の引上げを欧州と比較すると、日本では税率引上げ時に一斉に価格の引上げが行われる特徴があり、このことが企業と消費者の双方に駆け込み・反動が明確に意識された可能性が指摘された。諸外国と比較して、流動性制約に直面している家計が少ない日本では、駆け込みを行うことが可能な家計が多いことも消費変動の大きさに影響したと考えられる。また、DSGEモデルによるシミュレーションでも価格改定が緩やかな場合においては、消費税率引上げ時に明確な駆け込み・反動を観察することはできなかった。
2019年の引上げ時には、消費税率引上げ前後において、事業者のそれぞれの判断によって柔軟な価格設定が行えるよう、ガイドラインが整備された。一方、下請け等の中小企業・小規模事業者に対する消費税の転嫁拒否等が行われないよう、転嫁拒否等に対する監視、取締りや、事業者等に対する指導、周知徹底等に努め、万全の転嫁対策を講じることとしている。
また、日本では消費税率引上げ時における非耐久財の押下げ寄与が耐久財以上に大きかったことや、日本の非耐久財の価格弾力性が相対的に高く、食料等の価格変動の影響は年齢によらない可能性がある等の分析結果を踏まえると、食料等について軽減税率制度を実施することは、消費の平準化に寄与することが考えられる。2019年の引上げ時には、酒類及び外食を除く飲食料品と定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞について軽減税率制度が実施される。
さらに、2019年の引上げ時には、需要平準化を図るとともに、キャッシュレス化を推進するため、経営資源が少ない中小・小規模事業者向けに、消費税率引上げ後の一定期間に限り、ポイント還元支援を行うこととしている。DSGEモデルのシミュレーション結果でも、負の消費税のように一定程度の還元を行うことで、消費税率引上げ時における反動の影響を緩和することができることが示されている。
この他にも駆け込み・反動減の平準化に向けた様々な取組が行われることが予定されているが23、これまでみてきたように本節の分析結果を踏まえれば、2019年の消費税率引上げに向けた取組は、消費の平準化に寄与することが期待される。

