第2章 家計部門の構造変化(第2節)
第2節 家計の消費行動の変化
本節では家計の消費・貯蓄サイドに焦点を当てて分析する。まず、前節同様に、SNAでみたマクロの消費動向と家計調査等でみた世帯属性別の消費動向について長期的な変化を概観する。次に、①高齢世帯、②共働き世帯、③若年世帯の3つの世帯属性別に、消費動向の構造的な変化やその特徴について分析を行う。最後に、こうした分析結果から示唆される今後の持続的な消費回復に向けた課題について考察する。
1 マクロ・世帯属性からみた消費・貯蓄動向
(少子高齢化による影響もあり、貯蓄率は減少傾向)
前節同様、マクロの観点からSNAベースの家計部門における消費と貯蓄率の動向を確認していく。まず、1980年以降の消費動向をみると(第2-2-1図(1))、名目・実質ともに、90年代前半までは高い伸びで推移し、1980~90年までの平均成長率は名目で6%、実質で4%程度の伸びで増加した。1990年代前半のバブル崩壊後は、前掲第2-1-2図にもあるように、所得の伸びの低下や負の資産効果もあり、消費の伸びも弱まり、90年代後半(1996~99年)の平均成長率は名目0.9%、実質0.7%程度の伸びにとどまった。2000年以降では、金融危機前(2007年)までの平均成長率が名目で0.5%、実質で1.2%程度と、デフレにより名目消費の伸びが弱くなっている。2014年の消費増税引上げ以降の消費は力強さを欠いていたが、2017年度の実質消費は1.1%となるなど、持ち直してきている。
次に、貯蓄率の動向をみると(第2-2-1図(2))、長期的に低下傾向にある。1980年頃には15%を超えていた貯蓄率は緩やかに低下していたが、所得の伸びが鈍化したことを主要因に貯蓄率の低下テンポは2000年頃に加速することとなった(Iwaisako and Okada、2012)。貯蓄率は2005年頃に下げ止まり、横ばい圏内で推移していたが、2014年には消費税率引上げ前の駆け込みのために消費者が一時的に貯蓄を取り崩したこと等を背景にマイナスに転じた。ただし、2017年には2.1%と再びプラス圏内に戻ってきている。
このように貯蓄率が低下傾向にある主な要因は少子高齢化によるものであることが多くの先行研究で指摘されている。後述するように、一般的に高齢世帯では貯蓄を取り崩して消費を行う(=貯蓄率がマイナスとなる)傾向があるため、世帯に占める高齢者の割合が増加すれば、マクロでみた貯蓄率は低下する傾向にある。ただし、貯蓄率の低下の背景のうち、高齢化要因で説明できる部分は2~4割程度であり、その他は年齢別の貯蓄率が変化したことが背景にあると分析している研究もある(宇南山・大野、2017)。
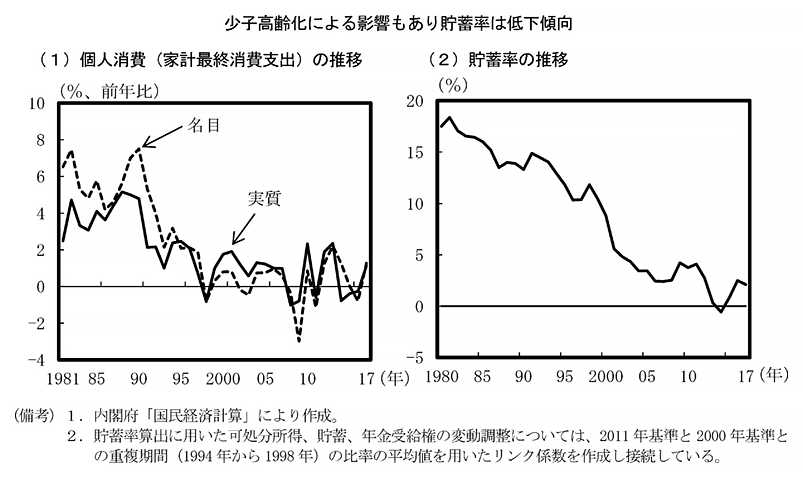
(若年世帯の平均消費性向が減少傾向)
上記のマクロでみた消費・貯蓄率の動向を踏まえた上で、世帯レベルでの動向をみるために、家計調査等を用いて、世帯主の年齢階級別に消費と平均消費性向(1から貯蓄率1を差し引くと消費性向になる)の動向を確認する。なお、可処分所得の分析時と同様、世帯人員の影響を調整するため(等価)消費支出額に変換した上で推移をみている。以下では、2人以上世帯の勤労者世帯、単身の勤労者世帯、無職世帯を含む高齢世帯の3つに分けて、それぞれの動向をみる。
まず、2人以上世帯の勤労者世帯における消費支出額・平均消費性向の推移を年齢階級別にみてみよう(第2-2-2図(1)・(2))。消費支出額の大まかな傾向としては、前掲第2-1-3図でみた可処分所得の動きと同様であり、1990年代は増加していたが、2000年頃から減少傾向に転じていることがわかる。特に、40~64歳における平均消費性向は75%程度で概ね安定して推移していることから、可処分所得と消費が同じペースで減少傾向にあると考えられる。一方、39歳以下の世帯においては、平均消費性向が長期的に低下傾向にある。1988~92年は約74%であったが、2000年頃にかけて低下し、その後横ばいで推移していたが、直近の2013~17年においては、可処分所得が増加したにも関わらず消費支出額が減少傾向のまま推移したため、平均消費性向は約67%となっている。詳しくは後述するが、こうした若年世帯における消費性向の低下は、住宅ローンや将来不安が影響している可能性がある。
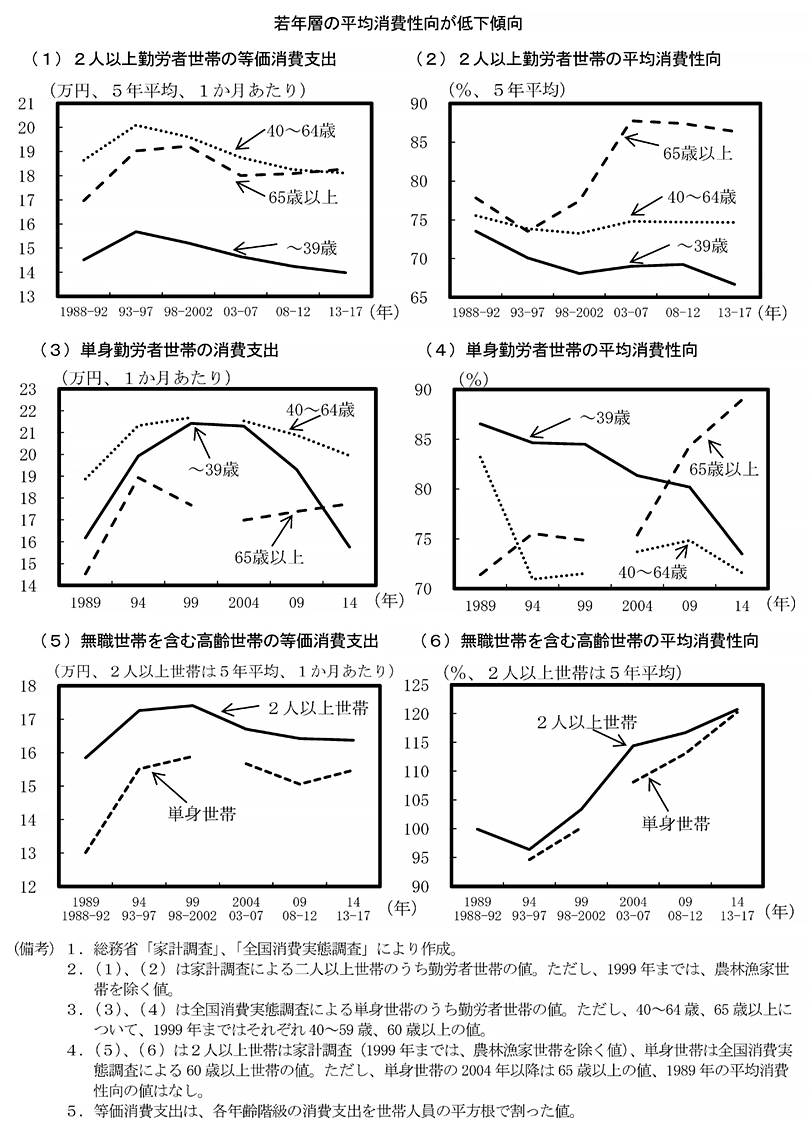
65歳以上の世帯における消費支出額をみると、2000年代前半に減少した後、2000年代後半以降は緩やかな増加傾向にあり、2013~17年では40~64歳と65歳以上で同程度となっている。これは、65歳以上の可処分所得が2000年代前半に大きく減少した後、勤め先収入の持ち直しに伴って緩やかに増加したことを反映している。
次に、単身の勤労者世帯における消費支出額・平均消費性向についてみてみると(第2-2-2図(3)・(4))、サンプルによる振れもあり変動が激しいが、概ね2人以上の世帯の動向と似たような動きとなっている。単身世帯においては、特に39歳以下の世帯における平均消費性向は低下傾向が顕著であり、2014年における39歳以下の消費支出額は、65歳以上の単身世帯の消費水準と比較しても小さくなっている。一方、65歳以上の単身世帯においては、可処分所得の水準が減少しているにもかかわらず、消費支出額が増加したことから、2014年における平均消費性向は大きく上昇している。
これまでは勤労者世帯に限定していたが、高齢者の世帯においては無職世帯の割合も大きいため、最後に60歳以上の世帯において無職世帯も含めた動向を確認する(第2-2-2図(5)・(6))。無職世帯を含む消費支出額については、勤労者世帯の消費額の9割程度となるなど、水準では差がみられるが、全般的な動向は勤労者世帯と概ね同じである。ただし、可処分所得が無職世帯では総じて低いことから平均消費性向の動向は異なっており、1990年代の平均消費性向は概ね100%程度であったが2、2000年頃から上昇傾向に転じている。2000年頃に高齢者の無職世帯において平均消費性向が上昇(=貯蓄率が低下)した背景には、消費支出の増加に加え、社会保障給付の減少、社会保険料の増加等が影響していたことが指摘されている(Horioka、2010)。
2 高齢世帯の消費水準に関する考察
(高齢者の消費水準は、ライフサイクル仮説が想定する消費水準を下回る)
以下では、高齢世帯、共働き世帯、若年世帯の3つの世帯属性別に分けて、消費動向を詳細に分析していく。まず、高齢世帯であるが、通常の「ライフサイクル仮説」に基づけば、人々は若い時に就業し、稼いだ所得の一部を貯蓄することで老後に備え、老後は貯蓄してきた資産を取り崩すことで生活費を補うとされている(Modigliani and Brumberg, 1954)。事実、前掲第2-2-2図でみたように、無職世帯を含めた高齢世帯の消費性向は100%を越えていることから、高齢世帯は貯蓄を取り崩すことで消費をしており、ライフサイクル仮説が当てはまっているようにみえる。しかし、その取り崩し額がライフサイクル仮説の想定よりも低いため、実際の消費水準は、ライフサイクル仮説における消費水準(以下、「合理的消費額」という)を下回っていることが指摘されている3。
ここでは総務省「家計調査」のデータを用いて、合理的消費額に対する実際の消費額の比率について、家計の分布を確認するとともに、資産階級別にも比較を行うことで、高齢者の消費水準について考察を行う。分析対象は65歳以上の無職世帯(2人以上の世帯)とし、合理的消費額とは、将来の可処分所得(期待値)の累積額と純金融資産額の合計額を夫婦の平均余命で割った値と定義した4。つまり、ライフサイクル仮説が想定するように、寿命までに資産をすべて使い切る場合における消費額が合理的消費額となる。なお、ここでの資産は、金融資産のみであり、住居等の実物資産は考慮していないため、リバースモーゲージ5等の制度を活用すれば消費可能な水準はさらに増加する。
実際の消費額をこの合理的消費額で割った比率を、2005~07年と2015~17年の2期間において年齢階級別にみたのが第2-2-3図(1)であるが、この値が100%であれば実際の消費額が合理的消費額と等しいことを意味する。また、世帯の分布について確認できるように、図中の横線は下から25%、50%(中央値)、75%の世帯における値をプロットしている。
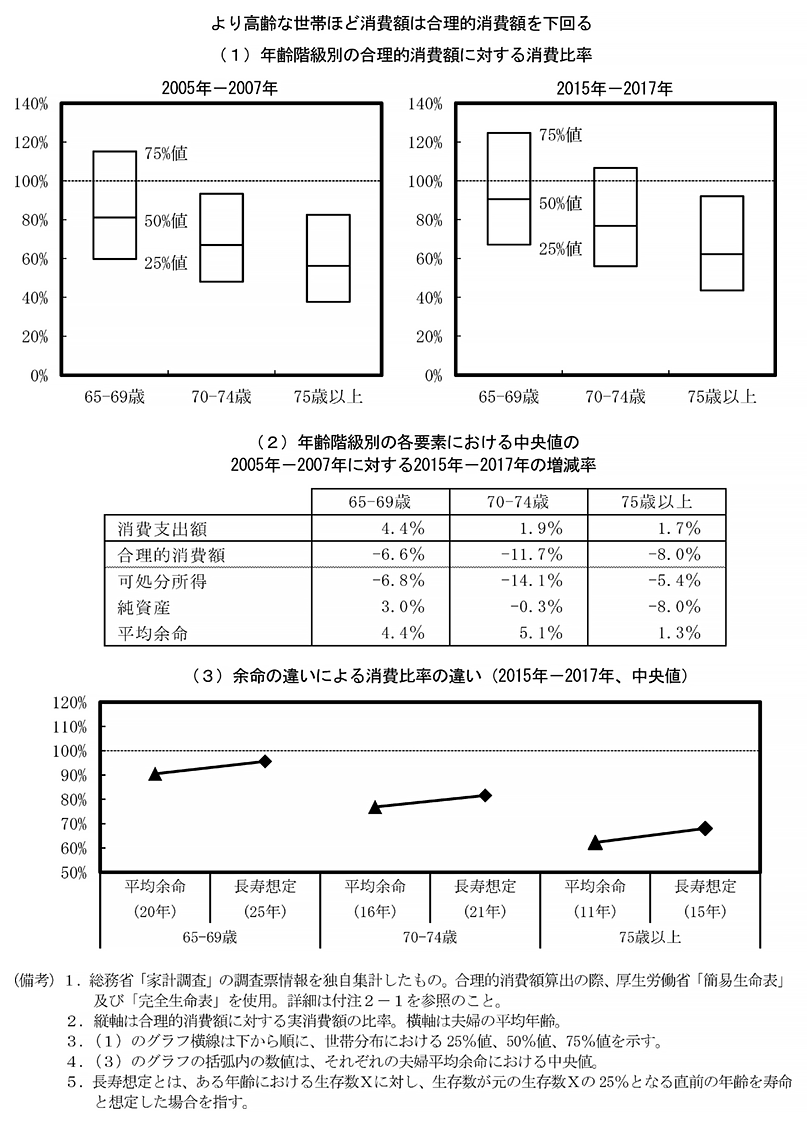
2015~17年における中央値をみると、いずれの年齢階層別にみても100%を下回っており(65~69歳:91%、70~74歳:77%、75歳以上:62%)、過半数以上の高齢世帯における消費水準は合理的な水準よりも低いことが指摘できる。また、年齢が高くなるにつれ比率が少なくなっており、例えば、75%点における世帯をみると65~74歳では100%を越えていたが、75歳以上の世帯では100%を下回っている。なお、75歳以上における25%点の世帯の値は43.5%と、合理的消費額の半分以下となっている。
次に、時系列的な変化を確認しよう。2005~07年と2015~17年を比較すると、すべての年齢階級・分位点でみて、合理的消費額に対する実消費額の比率が上昇していることが確認できる。この背景について構成要素の中央値における増減率をみると(第2-2-3図(2))、どの年齢階層においても実際の消費支出額が増加する一方、合理的消費額の水準が低下している。実際の消費額は2~4%程度増加しているが、同期間における物価の変化率が3%程度であることを踏まえれば6、実質ベースでは65~69歳の世帯では増加し、70歳以上の世帯では減少していると考えられる。また、合理的消費額の水準が低下している背景としては、平均余命が長くなったことで1年間に取り崩すことが可能な純資産額が低下したことと、可処分所得が減少したことが挙げられる。
世帯の期待形成が完全に合理的であれば、各世帯が考える余命は平均余命であると考えられるが、高齢者が平均余命よりも長く生きた場合のことも考慮して余命の期待形成を行っていた場合、余命の仮定を平均余命より長く設定することも考えられる。そこで、各年齢における生存数が、元の生存数の25%となる直前の年齢を用いて、各世帯の余命を計算した場合の分析も行った(以下、「長寿想定」という)。長寿想定の場合、世帯平均の余命は平均余命の場合と比較して5年程度長くなる。想定の違いが合理的消費額に対してどのように影響するかを確認すると(第2-2-3図(3))、2015~17年の中央値ベースで、すべての年齢階級において比率が約5%ポイント上昇している。ただし、長寿想定の場合でも、すべての年齢階級で比率は100%を下回っており、依然として実際の消費額は合理的消費額よりも低いことが指摘できる。
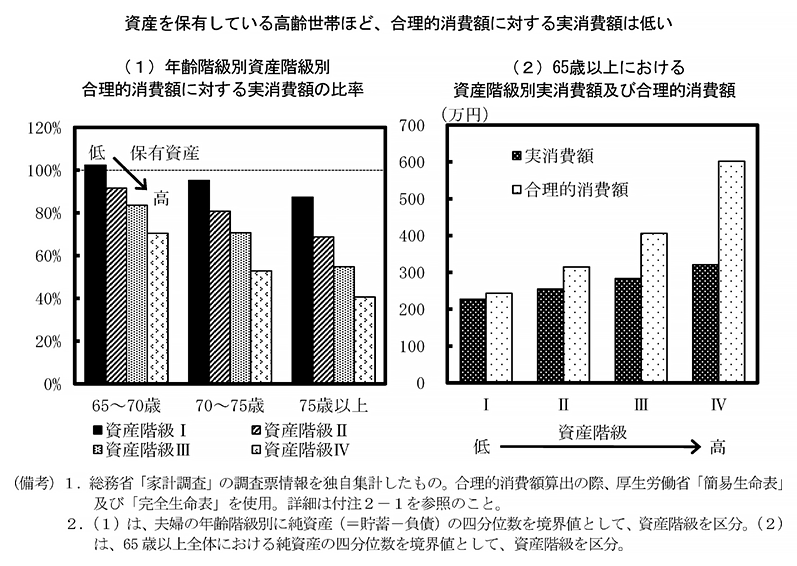
より多くの資産を持っている高齢世帯では、より高い水準の消費をすることができると考えられるが、合理的消費水準との比較ではどのような特徴があるだろうか。この点を確認するために、上記と同様の比率を2015~17年における純金融資産階級別(4分位別)に算出したのが第2-2-4図(1)である。図からは、すべての年齢層において、保有する資産が大きくなればなるほど、合理的消費水準に対する実際の消費水準が低くなっている。この背景について、実消費額と合理的消費額に分けてみると(第2-2-4図(2))、資産をより多く保有している世帯の実消費額は大きくなる傾向にあり、資産階級I(低い方から25%のグループ)と資産階級IV(高い方から25%のグループ)を比較すると、年間100万円程度の消費支出額の差がみられる。しかし、資産残高から算出される合理的消費額は、資産階級IとIVを比較すると年間360万円程度の差が存在しており、より多くの資産を持つ世帯において、実際の消費額が合理的消費額を大きく下回っていることがわかる。
(高齢者が貯蓄を取り崩さない背景は何か)
上記でみたように、高齢世帯は貯蓄を取り崩して消費しているものの、実際の消費額は合理的消費額を下回っており、特にこの傾向はより多くの資産を持っている世帯において強いことが示された。実物資産も考慮すると消費可能な額はさらに高くなるため、上記でみた比率はさらに低下することが示唆される。では、高齢者が合理的な水準まで消費しない背景にはどのようなことが考えられるだろうか。
この背景として、将来の不測の事態へ備えるための予備的動機が大きいとの説(例えばホリオカ・新見(2018))や、遺産動機の存在を強調する説(例えばMurata(2018))などがある7。ここでは60歳以上の者を対象に金融資産を保有する理由を聞いたアンケート調査(金融広報中央会)により、これらの点を確認する。第2-2-5図は、この調査における2016~18年の回答割合と、2007~09年との変化について、2人以上の世帯と単身世帯で別々にみたものである。2人以上世帯・単身世帯ともに、貯蓄理由としては、老後の生活資金との回答が最も多く、次いで病気や不時への備え(予備的動機)が多い。遺産動機の回答は2人以上の世帯で5位、単身世帯で6位であり、遺産動機の順位は決して高くない。しかし、時系列的な変化でみると、2人以上の世帯では予備的動機の割合が減少する一方、遺産動機が高くなっているほか、単身世帯でも他の理由が減少する中で遺産動機は微増しており、遺産動機による貯蓄が強まっていることが示唆される。この理由は必ずしも明確ではないが、例えば、既存の研究によると、自分たちよりも子ども世代の生活が苦しくなるとの認識の高まりが遺産動機を通じて影響している可能性が指摘されている(堀、2018)。
以上をまとめると、高齢者が合理的消費額まで消費しない理由として、予備的動機が大きいと考えられるものの、遺産動機についても近年影響力が大きくなっていることが示唆される。こうした観点からは、高齢者自身の不安や将来世代の生活に対する不安を軽減すること等により、予備的動機や遺産動機による貯蓄を減らしていくことも重要と考えられる。
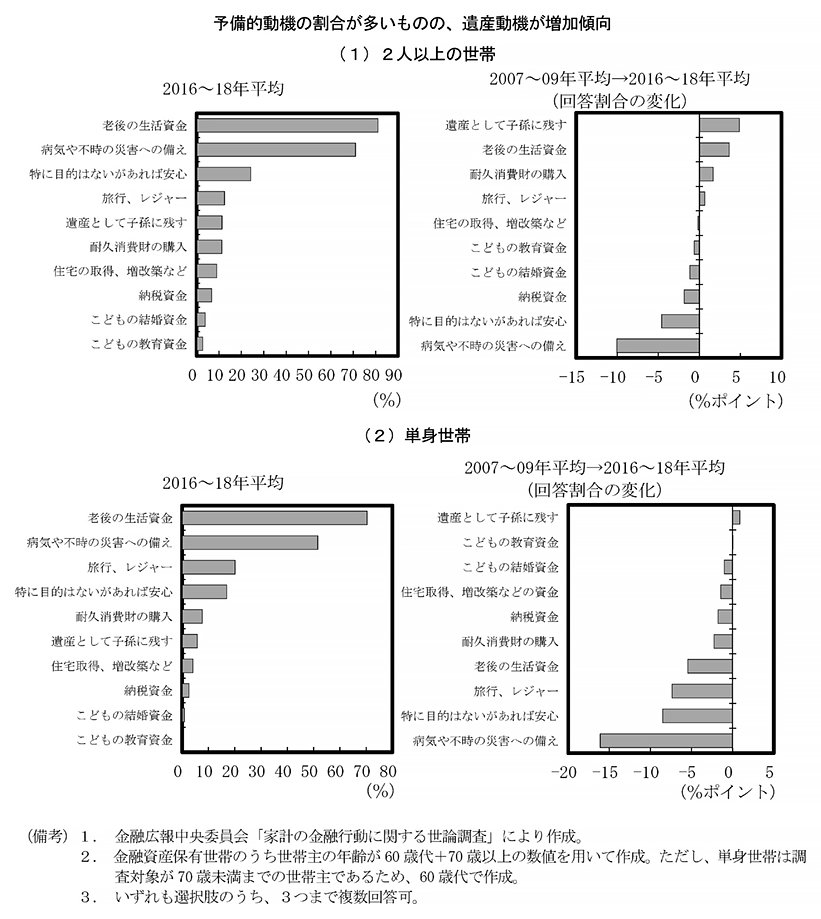
3 共働き世帯は消費にどのような変化をもたらすか
(片働き世帯から共働き世帯に移行した世帯における消費額は増加)
前掲第2-1-1図でみたように、雇用者の共働きが増加しているが、以下ではこの共働き世帯の消費に着目して分析する。1990年頃からの共働き世帯の増加には女性が短時間労働者として働くことが影響していたが、近年では夫婦ともにフルタイムで働く世帯が若年世帯で増えていることが指摘されている(大石、2017)。前掲第1-2-4図でみたように、妻が25~64歳の夫婦を対象に、2017年と2012年における妻の就業率を夫の年収階級別にみると、すべての世帯で就業率が増加していることがわかる。また、就業率の上昇は、パートタイムだけでなく、フルタイムとして働く女性の増加も寄与していることから、夫婦ともにフルタイムで働く世帯の増加が考えられる。さらに、夫の年収が高ければ妻の就業率が下がる傾向(ダグラス=有沢の法則)が、2012年と比較すると2017年は弱まっていることもみてとれる。
このように共働き世帯が増加することは、世帯所得を押上げ、消費動向にもポジティブな影響を与えることが期待される。この点をより詳しく確認するために、同一の世帯に関するデータを時系列で記録した追跡調査を用いて8、片働き世帯が共働き世帯に移行した際に、所得額と消費額が統計学的に有意に増加しているかについて検証を行う9。具体的には、共働き化と所得・消費の因果関係を把握するため、妻の年齢が64歳以下の世帯を対象に、年齢・学歴・夫の年収・世帯構成等の世帯の属性から、片働き世帯から共働き世帯に移行した世帯と、同様の属性をもっているが片働き世帯のまま変化がなかった世帯をマッチングさせ、前者の消費・所得の変化額と後者の消費・所得の変化額の差(difference in differences)を分析する。片働き世帯から共働き世帯に変化したことで消費・所得額が増加していれば、片働き世帯から変化がなかった場合の変化額と比較して有意に高くなっているはずである。
第2-2-6図(1)がこの分析結果であるが、片働き世帯が共働き世帯になったことで、一か月当たりで、夫婦の所得合計が平均約3.5万円増加(年収だと約42万円)、消費支出額が平均約2.0万円増加しており10、両者は統計的にも有意な値である。ここから算出される限界消費性向は0.56程度となり、消費関数を推計することで限界消費性向を試算した内閣府(2010)の結果(収入により約25%~40%)等11と比較しても非常に高い値となっている。この要因としては、妻が働くようになった背景として、そもそも必要な家計支出の増加を賄うために就労している可能性があると考えられる。増加した消費額の約2.0万円のうち、具体的にどの支出項目が増加したのかをみたのが第2-2-6図(2)である。上位の項目をみると、教育、食料、家賃・光熱水道となっており、子どもの教育費を捻出することや、食生活や住宅環境の改善等が、妻の就業の背景にあると考えられる。また、同時に教養娯楽のといった選択的な消費についても増加していることから、妻の就業の背景には、生活を充実しようとする意図がある可能性もある。
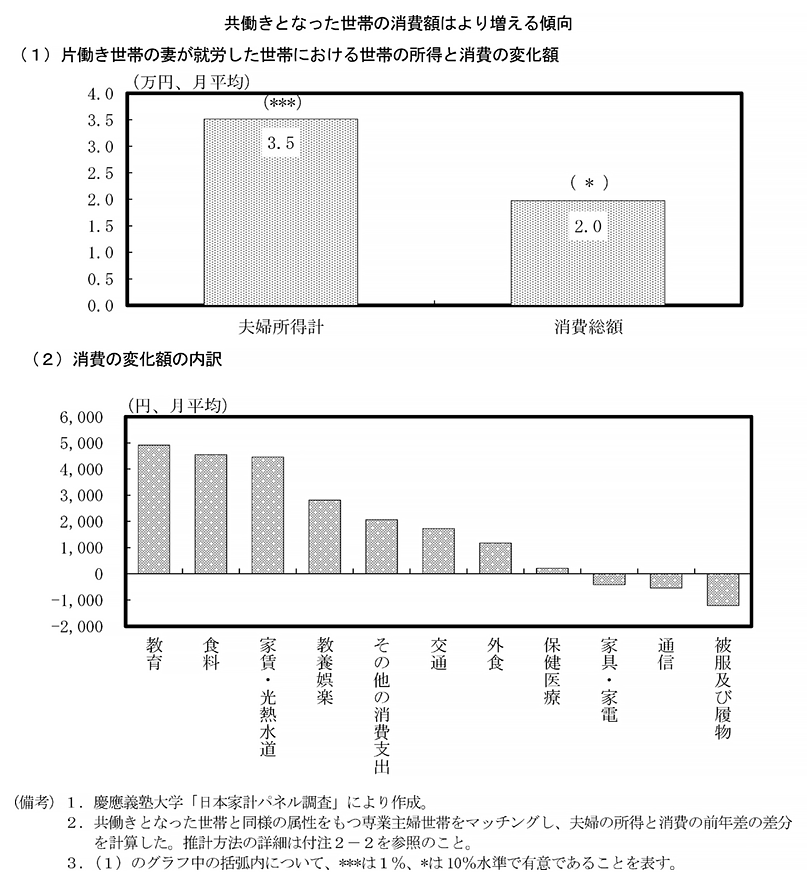
(共働き世帯は、教育関連投資、仕事関係の費用、中食などの消費等が多い)
上記の分析は、妻が未就業の状態から就業した場合に世帯の消費がどのように変化するかをみたものであるが、出産・結婚等でそもそも労働市場から退出しない女性が増えていること踏まえれば、一度も片働き世帯にならない世帯も増加していることが考えられる。そこで、総務省「全国就業実態調査」(2014年)より、世帯主が60歳未満の共働き世帯と勤労者世帯全体の平均12とを比較することで、全般的な共働き世帯の消費にどのような特徴があるのかを確認する(第2-2-7図)。
まず、可処分所得・消費支出額の水準の差を比較すると、共働き世帯の方が勤労者世帯平均と比較して、可処分所得が11~13%、消費支出額が7~8%程度高くなっている。このことは共働き世帯の消費性向が勤労者世帯平均よりも低いことを示唆しており、事実、共働き世帯の平均消費性向は3~4%程度勤労者世帯平均よりも低くなっている。
勤労者世帯の支出額を100とした場合の共働き世帯の項目別支出額について、39歳以下の世帯と40~59歳の世帯に分けてみると、共働き世帯においては、年齢階級によらずほとんどすべての項目において100を上回っていることが確認できる。夫婦ともに働いている世帯においては、家事時間の短縮に寄与する消費(以下、「時短消費」という)をする傾向が考えられるため、例えば、食料のうち調理食品の支出金額を比較すると、39歳以下の世帯では36%程度、40~59歳の世帯で10%程度ほど勤労者世帯平均と比較して高くなっており、「中食」にシフトすることで食事作りの負担を軽減していることが示唆される13。また、どちらの年齢階級でも上位にきている項目として、被服・履物、交通・通信、交際費等が指摘できる。これらの項目は、仕事関連消費として支出金額が高くなっている可能性が考えられる。例えば、仕事時の洋服、通勤のための交通費・自動車、職場での懇親会の費用等が考えられる。
年齢別の特徴をみていくと、39歳以下の共働き世帯は諸雑費が非常に高くなっている。同項目が高くなっている背景としては、単なる振れの可能性もあるが、同項目には保育費用が含まれていることから、勤務中に子どもを預けるための消費が高くなっている可能性も考えられる。40~59歳の共働き世帯の特徴としては、仕送り金や教育の支出が高いことが指摘できる。前掲第2-2-6図のように子どもの教育費の捻出のために共働きをするようになったことや、共働きの高い所得水準を活かして子どもの教育投資に力をいれていることが背景として考えられる。また、40~59歳では住居(家賃等)の支出額が非常に低くなっているが、これは共働き世帯においては持家率が高く、家賃等の支出額が少ないことが影響していると思われる14。
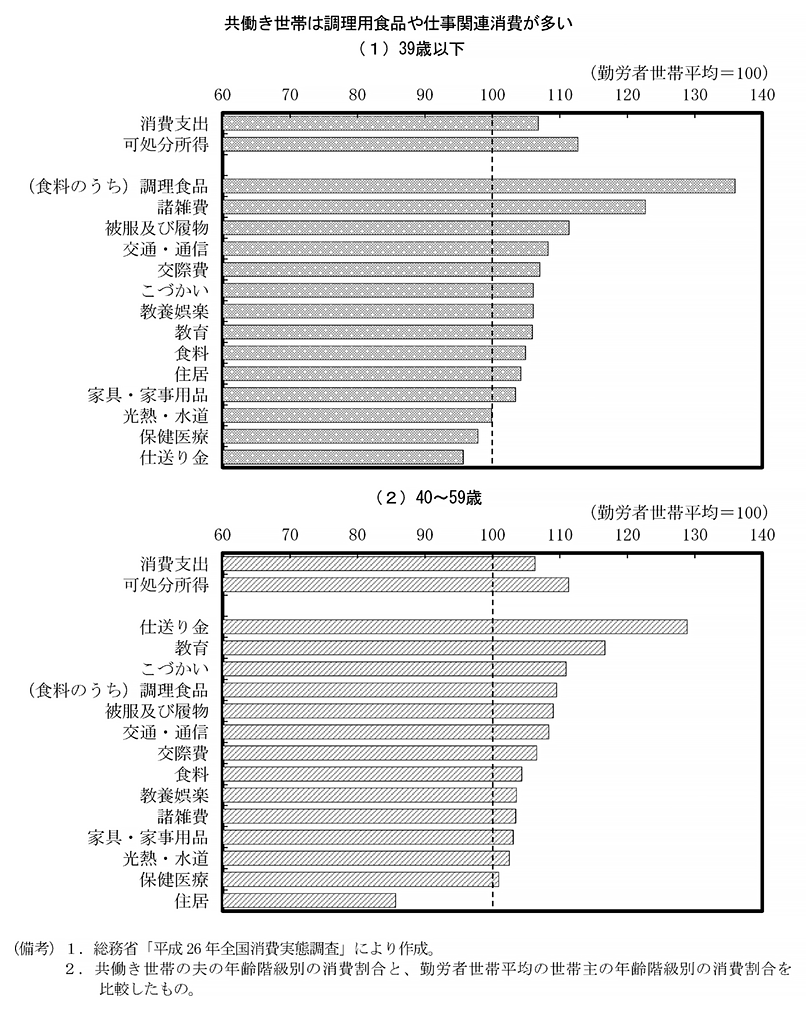
このように共働き世帯は所得額が高く、それに伴い消費額も高くなる傾向があるため、共働き世帯の増加は、マクロの消費支出の増加に対しても相応に寄与していることが示唆される15。また、共働き世帯の消費の特徴として、教育投資額、仕事関係の費用、時短消費が高いことが指摘できる。特に教育関係の費用は、片働き主婦世帯から共働き世帯に移行した際に最も増加する傾向にあるなど、共働き世帯が力を入れて投資していることが示唆される。
また、共働き世帯の増加は、消費チャネルの構造変化や、新しいサービスの拡大につながる可能性が考えられる。夫婦が共に働く場合、買い物に行ける時間が限定されるため、ネット利用を通した消費が促進されると思われる。内閣府(2018)によると、就業している者がネットショッピングを利用する確率は、就業形態に関わらず、非就業者と比較して有意に高いことが示されている。また、育児の時期においても女性ができるだけ仕事をセーブしないで済むような働き方が増加することで家事支援サービスなどがより広く利用される可能性も指摘されている(武田、2017)。
4 若年世帯の消費行動はどのように変化したか
(若年世帯の消費は、通信費・住宅支出・中食等が増加する一方、交際費等が減少)
3点目として、若年者の消費動向について分析を行う。前掲第2-2-2図でみたように、若年世帯における平均消費性向は減少傾向にあり、若者がなぜ消費しなくなっているのかについては様々な議論がされているが16、ここではより長期的な動向から若年者の消費動向を整理する。
まず、近年の若年世帯の消費パターンが、バブル期以前の高成長時代の若者世帯とどのように異なっているのかみてみよう。第2-2-8図は、39歳以下の2人以上世帯・単身世帯の各消費支出項目のシェアについて、2014年と1984年の差分をとったものである。なお、図中において値がプラスであれば、2014年における該当支出項目のウェイトが1984年より大きいことを示している。
2人以上世帯・単身世帯に共通する特徴としては、通信費、家賃・地代、上下水道料、調理食品といった項目のウェイトが高まっているのに対し、交際費のウェイトが減少していることが指摘できる。それぞれの背景について順に考察していこう。まず、通信費シェアの拡大には、インターネットやパソコン・スマートフォンの普及等が影響していると考えられる。特に20~39歳におけるスマートフォンの普及率は、2010~12年に急激に伸長し、2014年にはパソコンの普及率を超えて、2017年時点の普及率は約97%となっている(付図2-2)。
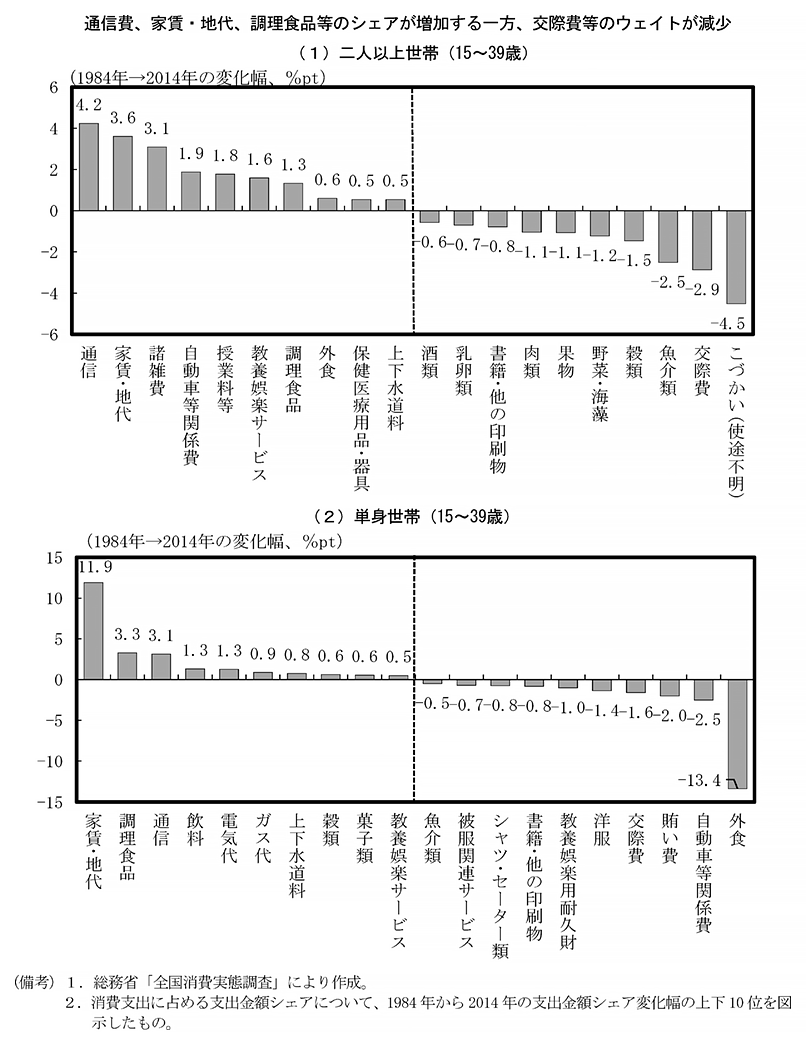
次に、家賃・地代や上下水道料シェアの増加は、特に単身世帯においてそのシェアの拡大が大きいが、この背景にはバブル崩壊後の景気の低迷を背景に、住居関係の福利厚生制度(社宅・独身寮、住宅補助等)が縮小したことや17、そのような福利厚生の利用が限定される非正社員として働く若者が増えたこと等18により、自身で家賃や光熱費を支払わざるを得なくなったことが影響していると考えられる。総務省「国勢調査」より15~39歳の単身世帯の居住状況を確認すると、給与住宅の割合が横ばいで推移するなか、独身寮等に住む割合は減少し、民営の借家に住む割合が増加していることが確認できる(付図2-3)。
さらに、調理食品の割合の増加は、共働き世帯の分析の際にも指摘したが、中食市場の拡大が関係していると思われる。特に、2人以上の世帯においては、魚介類、穀類、野菜・海藻等の調理が必要とされる支出項目が減少しており、より手軽に利用することができる中食にシフトしていることが示唆される。
最後に、交際費シェアの減少についてその内訳を詳しくみると、2人以上世帯・単身世帯ともに減少が大きいものの順に、贈与金、食料となっていることから、過去行っていた慣習が希薄になったことや、付き合いのための外食等の減少がこの背景にあることが推察される。
また、2人以上世帯・単身世帯とで、動向が異なる項目として、自動車関係費、外食が指摘できる。自動車関係費シェアの内訳をみると、単身世帯では自動車等購入シェアが大きく減少しており、この背景として若年者が車を買わなくなっていることが指摘できる19。一方、2人以上の世帯では、自動車関係費シェアが増えているものの、増加に寄与しているは自動車等維持(ガソリン、自動車保険料、駐車場代等)であり、自動車等購入シェアに関しては変化がないため、自動車購入を積極的に行っているわけではない。
外食については、単身世帯においてシェアが大きく減少しているが、この背景には前述した中食志向に加え、若年の男性において家で料理をする機会が増加していること20、外食産業の多様化・価格競争激化により安価で高品質のサービスが楽しめること等が影響していると考えられる。2人以上の世帯においては外食シェアが増加しており、家庭内で調理するよりも簡単な外食に移行していることが考えられる。
その他の特徴的な点としては、テレビ等が含まれる教養娯楽用耐久財は、単身世帯で減少しており、図では表示されていないが2人以上の世帯でも▲0.4%ポイントシェアが減少している。また、特に単身世帯を中心に、衣服関係のシェアの減少もみられている。「被服及び履物」でまとめると、単身世帯では▲3.9%ポイント、2人以上の世帯では▲1.7%ポイント、消費シェアが低下している。
以上のように長期的な若年者の消費パターンの変化をまとめると、社宅・独身寮の減少等による住宅支出の増加、スマートフォン等の普及による通信費増加、食スタイルの変化(材料品の減少と中食の増加等)、自動車・家電・衣服といった耐久財・半耐久財支出シェアの減少、社会的慣習の希薄化による交際費の減少といったことが指摘できる。大まかな傾向として、住居費・通信費等の固定費の増加と、財関係の支出シェアが減少していると言える。特に近年では、若い世代を中心にシェアリングエコノミーの一種であるフリマアプリの利用率が高まっているが、若い世代は中古品に対する抵抗感がなくなっていることや、モノを永続的に所有することにこだわらない傾向があること等が背景にあると考えられる(内閣府、2018)。
(若年者はよりゆとりある生活時間を過ごすも、消費には結び付いていない可能性)
次に、若年者の日常の生活行動変化が消費に与え得る影響について考察する。具体的には総務省「社会生活基本調査」により、39歳以下の生活時間が1986年と2016年を比較した際に変化がみられるのかについて分析を行った(第2-2-9図)。対象とする曜日は平日と日曜日、対象者は、主に仕事をしている者、家事などのかたわら仕事をしている者、家事をしている者の3者である。
曜日・対象者によらず、全般的に共通している内容として、テレビ・ラジオ等の時間、家事の時間、交際・付き合い時間が減少する一方、休養・くつろぎ21、育児、趣味・娯楽、身の回りの用事22の時間が増加している。前掲第2-2-8図では、テレビ等が含まれる教養娯楽用耐久財や交際費の消費シェアが減少していることを指摘したが、生活時間でみても同様の傾向が見られていることがわかる。また、家電の性能向上もあって、特に家事をしている者の家事時間が大幅に減少している。
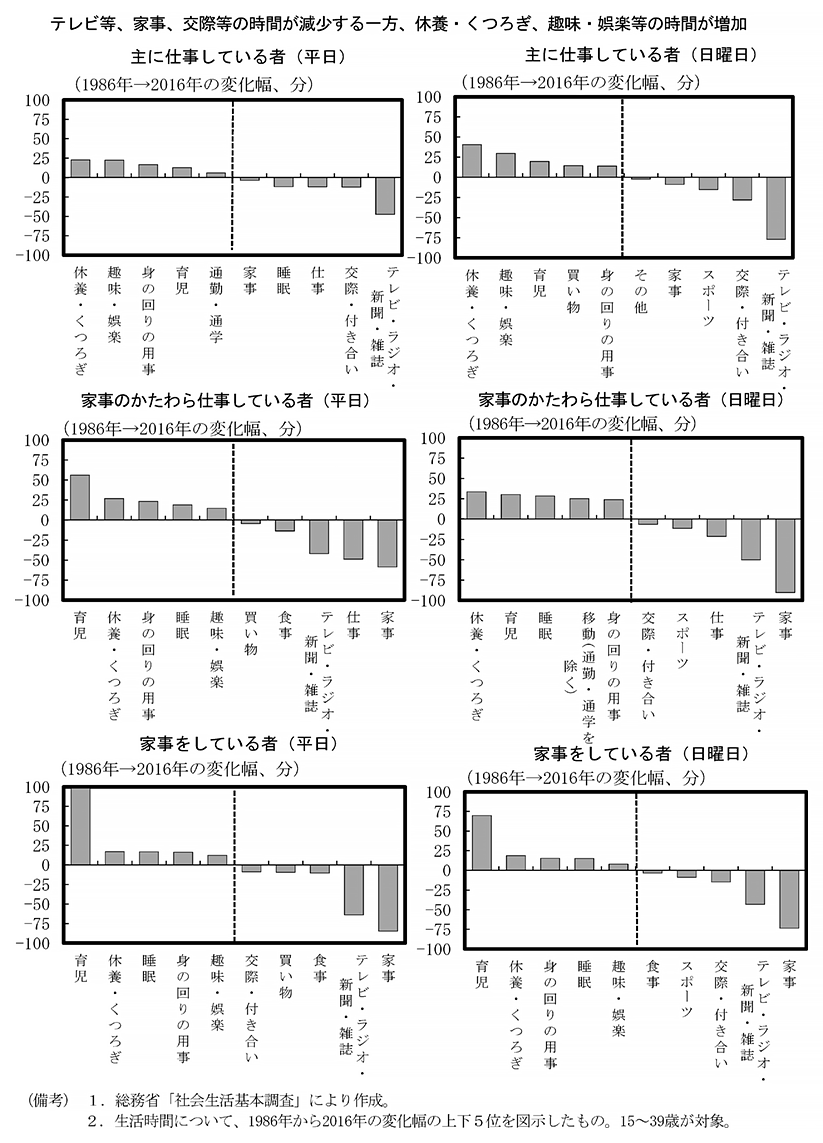
休養・くつろぎ、育児、趣味・娯楽時間の増加の背景には、よりゆとりのある生活をしていることや家族との時間・団らんを大事にしていることに加え、パソコンやスマートフォンによるゲームや動画視聴時間の増加が影響している可能性もある23。民間研究機関による2018年の調査によると、特に若年者を中心にインターネットを利用する時間が増えていることに加え、近年ではスマートフォンを利用してゲーム、動画視聴、コミュニケーションを行うといった幅広い余暇活動が行われている(松下・林、2018a)。ゲーム・動画・メッセージのやりとり等は無料で利用できるケースが多いため、このような生活時間が増加しても、通信費以外には消費を押上げる要因にならないことが示唆される。
このように30年間における生活時間の変化をみると、大まかな傾向として、生活時間が減少している項目は直接的に消費の減少につながりやすい一方、増加している生活時間は必ずしも消費の増加に結び付かない項目が多いことが指摘できる。ただし、ゆとりのある生活、家族との時間、趣味時間が増えていることは、若年者の生活の満足度の向上にはつながっていることが示唆される。内閣府「国民生活に関する世論調査」によると(第2-2-10図)、若年者において「現在の生活に対して満足」と回答した割合は増加傾向にあり、後方3か年平均でみると2018年における20代・30代の同割合は、1966年の調査開始以降で最も高い値となっている。30年前(1986~88年)では、高齢者の方が満足と回答した割合が高かったが、直近(2016~18年)においては20~29歳が最も高く、次に30~39歳が高いとの結果になっている。
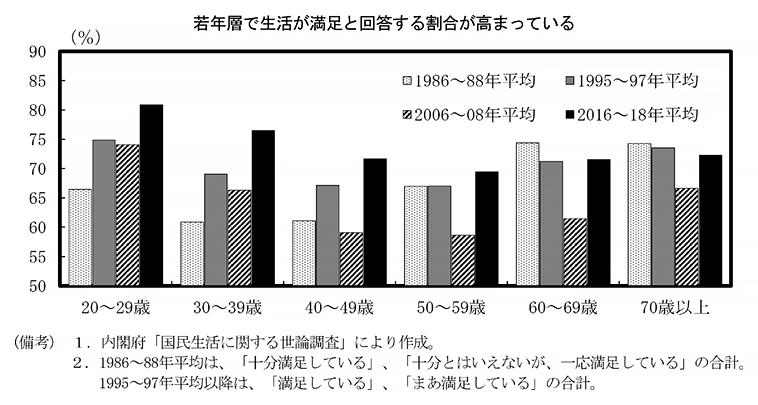
(住宅ローンや老後に対する不安が貯蓄率の上昇に寄与)
前出の内閣府の世論調査によると、若年者における生活の満足度は高いものの、将来に備えることに力を入れたいと回答する割合も高く、前掲第2-2-2図のように、若年世帯では貯蓄性向の上昇(消費性向の低下)が観察されている。消費性向が低下している要因の一つには、2人以上の若年世帯で持ち家率の上昇により住宅・土地負債が増加しており(前掲第2-1-7図)、住宅ローン返済のために消費額を減らしていることが考えられる。
ただし、単身世帯でも消費性向の低下がみられていることもあり、若年世帯における貯蓄性向の上昇には、住宅ローン以外の要因も影響している可能性が考えられる。そこで、アンケート調査(金融広報中央会)より、20・30代がどのような理由で貯蓄しているかを確認する(第2-2-11図)。2人以上の世帯においては、「こどもの教育資金」との回答割合が約70%弱と非常に高く、病気や不時の災害への備え(予備的動機)、老後の生活資金、旅行・レジャーの資金、住宅取得と続いている。単身世帯については、予備的動機や特に目的はないとの回答割合が高く、老後の生活資金、旅行・レジャーの資金と続く。2人以上の世帯では、子どもの教育や住宅取得等の将来必要となる費用を積み増しているのに対し、単身世帯では特に決まった目的がなく貯蓄しているのが特徴といえる。
2007~09年と2016~18年の時系列的な変化をみると、老後の生活資金の割合が2人以上世帯・単身世帯ともに、大きく伸びていることが確認できる。また、2人以上世帯・単身世帯ともに、特に目的はない、耐久財の購入資金を貯蓄の理由としてあげる割合が減少している。さらに、単身世帯では旅行・レジャーの資金を理由にあげる割合が、貯蓄理由の上位ではあるものの大きく減少している。
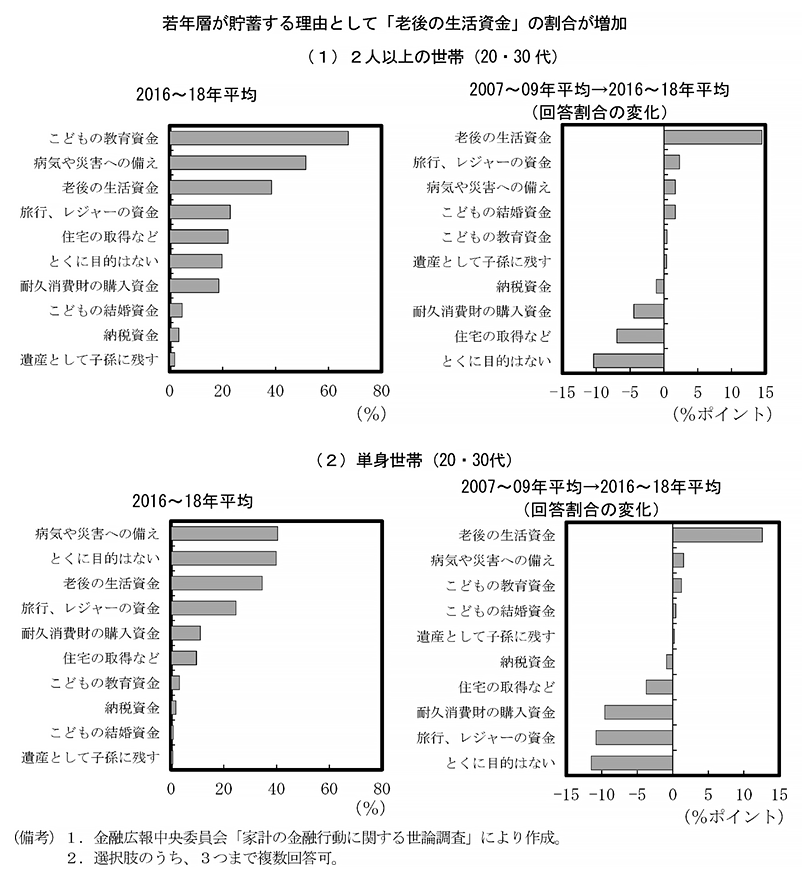
以上のように、貯蓄理由については、2人以上世帯・単身世帯にそれぞれ異なる理由もあるが、老後に備えるために目的を持って貯蓄する傾向が高まっている点では共通している。回答者は20・30代であるので、老後まで30~40年程度の時間があると考えられるが、将来の雇用や収入に対する信頼感が高まらないことを背景として24、より将来に備えて長期的な観点から資金を確保しようとしていると考えられる。このように、長期的な目的で若者が貯蓄していることは、若年消費が力強さを欠く背景の一つになっていると考えられる。
5 今後の消費に対する考察
(老後の不安を払拭することや働き方改革の取組が重要)
これまで世帯属性に分けて消費動向をみてきたが、こうした分析結果を整理するとともに、今後の消費の活性化に向けた課題を考察する。
まず、これまでの分析によれば、高齢者だけでなく若年者も含めて、平均寿命が長くなる中で、老後への備えの意識が高まっていることが現在の消費を抑制している可能性が強く示唆されており、こうした老後への不安を軽減することが重要である。高齢世帯は、本来消費可能な水準よりも低い消費を行っており、その背景には予備的動機が大きいと考えられるが、近年では遺産動機も高まっていることが示唆される。また、若年世帯についても、老後への備えもあり、長期的な観点から貯蓄しようとしている。こうした貯蓄に対する意識が高いことは他の調査結果からもみられており、支出を増やしたい項目として、20代~50代の第1位と60代の第2位で「貯蓄などの財産づくり」となっている25。貯蓄に回したいと考える背景の一つには、老後や医療等に対して将来的にどの程度の費用が必要となるのかが予想ができないという不安が予備的動機を通じた貯蓄増加につながっていることが指摘されている(吉川他、2017)。将来の不確実性を下げ、社会保障に対する不安を払拭していくことが重要となる。
また、働き方改革の取組を進めていくことは消費拡大に寄与することが考えられる。女性の労働参加率の高まりによって、共働き世帯が増加していることは消費に対してプラスの影響を与えている。今後は、正社員として働く女性が増えることで、所得・消費がさらに増加することやネットショッピングの高まり等が考えられる。さらに、ワーク・ライフ・バランスを改善し、労働時間の短縮によって自由な時間が増えることで、消費の増加につながる可能性がある。内閣府(2018)では、労働時間が減少することで、買い物、自己啓発、育児、趣味の時間が増加することが示されており、こうした生活時間の変化が消費増加に寄与する可能性が考えられる。また、各種アンケート結果をみると、貯蓄以外に支出を増やしたい支出項目に「旅行」と回答する割合が高いものの、実際に「旅行」を増やしたと回答する割合は決して高くない26。通常、旅行には一定期間の日数を確保する必要があるため、有給休暇取得の促進等の働き方改革は、積極的に消費したいができていない項目への消費拡大につながる可能性が考えられる。特に、若年者の分析でみたように、モノに対する支出シェアが減少している環境下では、旅行等の体験型の消費拡大が期待されるが、そのためには、体験するためのまとまった時間が確保できるような取組が重要となる。

