第2章 家計部門の構造変化(第1節)
第1節 家計の所得・資産面の変化
本節では、家計の世帯構造の変化、世帯属性別にみた所得・資産動向と分布について、1980年代以降の長期的な傾向とその背景について分析する。
1 世帯構造の変化
(単身世帯、共働き世帯、高齢の就業世帯が増加)
少子高齢化が進み、核家族化の動きが継続する中で、1980年代以降、世帯構造は長期的に大きく変化してきた。日本の総人口は戦後長らく増加傾向で推移していたが、少子高齢化が進む中、2008年の1億2,808万人をピークに減少に転じており、2015年には1億2,709万人となった。一方、世帯数では、核家族化の動きもあり、1980年以降増加が続いており、減少に転じるのは2025年以降となることが予想されている(第2-1-1図(1))。2015年の総人口・世帯数を1980年比でみると、総人口は1.09倍、世帯数は1.49倍となっており、総人口の伸びよりも世帯数の伸びの方が高いことがわかる。
世帯数の動向を世帯主の年齢別(64歳以下、65歳以上)に分けてその動向を確認すると、1980~2015年の伸びに対する寄与が最も高いのは65歳以上の2人以上の世帯であり、次に15~64歳の単身世帯である。また、寄与度の大きさは3番目だが、伸びが非常に高いのが65歳以上における単身世帯であり、2015年は1980年比で6.7倍にまで増加している。一方、15~64歳の2人以上の世帯は1990年頃をピークに減少しており、2015年では1990年比で0.8倍程度にまで減少している。1980年時点においては、総世帯の約70%の世帯がこの15~64歳の2人以上の世帯であったが、2005~10年頃には過半数を割り込み、2030年時点では37%程度にまで低下することが見込まれている。また、同じ2人以上の世帯でも、核家族の進展等を背景に世帯人員数が減少しており(第2-1-1図(2))、特に65歳以上の2人以上の世帯における世帯人員数が減少している1。
また、家計における働き方も変化している。妻の年齢が15~64歳の世帯における共働き世帯と片働き世帯2の世帯数がどのように変化してきたのかをみたのが、第2-1-1図(3)である3。片働き世帯は、1985年時点では936万世帯であったが、2000年頃から減少傾向で推移しており、2017年では541万世帯にまで減少している。一方、夫と妻の両方が、雇用者の共働き世帯は、上昇トレンドで推移しており、1985年では717万世帯であったが、2017年には1,136万世帯となっている。
ただし、1990年代においても、夫婦ともに就業している共働き世帯は1,200万世帯程度と数多く存在しており、この背景として当時は、妻が家族従業者・自営業者として働く就業形態が多かったことが指摘できる4。1990年代以降、家族従業者・自営業者としての女性の就業は減少したが、女性が雇用者として働く就業形態が増加した結果、夫婦とも就業者の世帯は横ばいで推移したが、夫婦とも雇用者の共働き世帯が増加することとなった5。この時期に雇用者の共働きが増加した要因として、これまでの研究によれば、バブル崩壊後の景気後退により夫の所得が伸び悩んだことで妻が家計補助のために労働市場に参入したこと6、技術革新やサービス経済化等にともなう需要構造の変化により女性の就業機会が拡大したこと等が指摘されている(大石、2017)。また、近年における雇用者の共働き世帯増加の背景として、仕事と子育ての両立等を目指す女性活躍推進の取組の成果というポジティブな要因がある一方7、老後の備えに不安を抱える40・50代が共働き比率を押上げているという側面もあるとの分析もある(三浦・東、2017)。
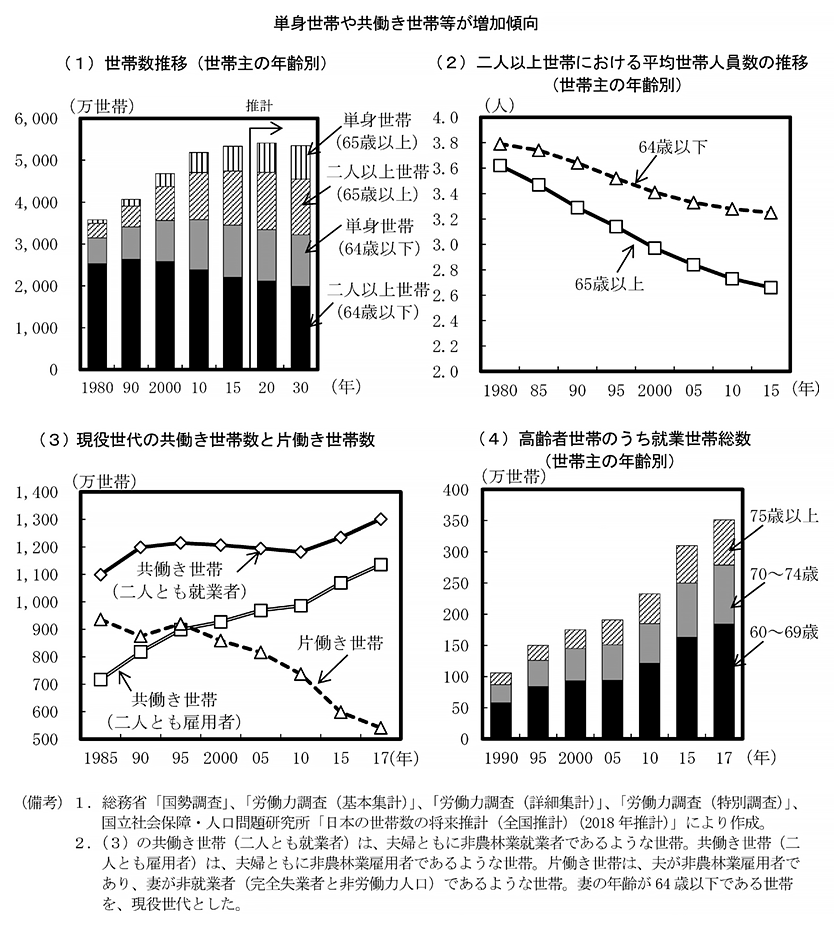
働く世帯が増えているのは、高齢世帯についても同じである。世帯主の年齢が60歳以上の世帯のうち、就業世帯数の推移をみると(第2-1-1図(4))、2005年頃以降増加テンポが加速している。2017年の就業世帯数は352万世帯と対1990年比で約3.3倍となっており、特に世帯主が60~69歳の就業世帯数の増加がこの伸びに寄与している。こうした背景には、2006年に改正された高齢者雇用安定法により60歳以降の雇用機会が確保されたことや、生産年齢人口の減少による人手不足感が高まっていることが指摘されている(近藤、2017)。
このように過去約35年程度の世帯構造の推移をみると、その構造が大きく変化していることがわかる。高齢世帯や単身世帯の増加だけでなく、同じ2人以上の世帯でも世帯人員数や夫婦の働き方の変化がみられる。家計の動向を把握する上では、このような世帯構造の変化を踏まえて考察していくことが必要となる。
2 マクロ・世帯属性からみた所得・資産動向
(可処分所得は90年代前半以降伸びが鈍化。家計は安全資産に対する選好が強い)
所得・資産動向について、まず、マクロの観点からSNAベースの家計部門における可処分所得及び金融資産残高の動向を確認する。家計の可処分所得の動向をみると(第2-1-2図(1))、実質ベースでは1980~90年の平均成長率は4%程度の伸びであったが、90年代前半以降伸びが鈍化し、2000年以降の平均成長率は0.3%程度となっている。名目ベースでみた可処分所得は、持続的に物価下落が継続する状態であるデフレの影響等から、2000年頃に減少に転じた後、2014年頃まで横ばい圏内で推移していたが、デフレではない状況になったことで、2015年以降は増加に転じている。
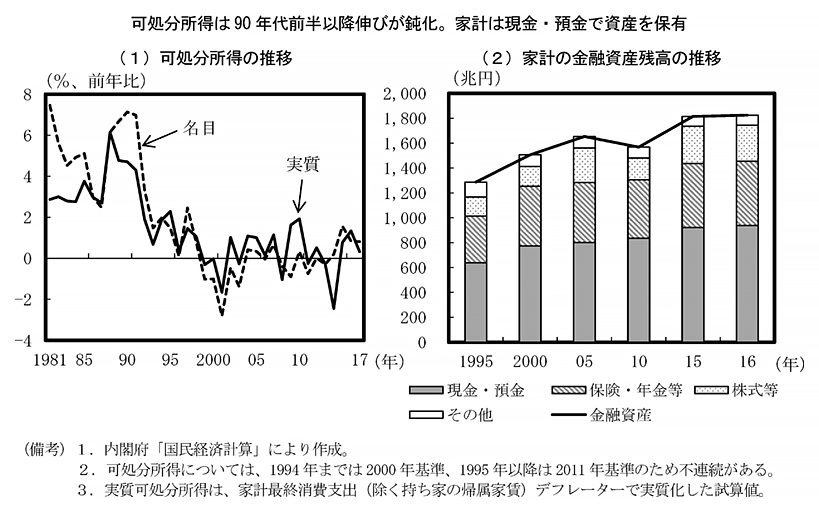
次に、家計部門における金融資産残高の動向について確認すると(第2-1-2図(2))、家計の金融資産は世界金融危機後の2010年にやや低下したものの、長期的にみれば増加傾向で推移しており、2016年時点で1,824兆円となっている。資産残高の構成比をみると、年による若干の変動はみられるものの、約半分が現金・預金であり、3割程度が保険・年金等で占められている。金融資産残高の増加は主に現金・預金によるものであり、リスク資産である株式等の割合は2016年で16%程度である。日本の家計は欧米諸国と比較してリスク資産への投資が少なく、現金・預金といった安全資産に対する選好が強い傾向があるが8、こうした状況は大きく変化していないことが指摘できる。
(可処分所得の減少には、勤め先収入の減少や社会保険料の増加などが寄与)
次に、1980年以降の世帯構成の変化を踏まえ、総務省「家計調査」等に基づき、年齢階級別に(名目)可処分所得の動向を確認する9。なお、2人以上の世帯でも世帯人員が減少していることから、可処分所得を世帯人員の平方根で割った等価可処分所得で時系列を比較する10。また、ここでは2人以上の勤労者世帯、単身勤労者世帯、無職世帯を含む高齢世帯の3つの類型別にその動向をみる。
まず、2人以上の世帯のうち勤労者世帯11における可処分所得の変化をみると(第2-1-3図(1))、どの年齢層でも大まかな傾向としては、1990年代を通じて増加し、2000年以降減少傾向に転じていることが確認できる。足下の5年間をみると、39歳以下や65歳以上の世帯では若干の増加に転じている一方、40~64歳の世帯では微減となっている。次に、単身の勤労者世帯における可処分所得の動向を確認すると(第2-1-3図(2))、サンプルの振れが大きいが、2000年頃までは増加傾向で推移し、その後減少傾向、または横ばいで推移している。
上記の推移は、2人以上世帯・単身世帯ともに勤労者世帯が対象であったが、高齢世帯では無職世帯の割合も多いため、無職世帯も含めた高齢世帯の可処分所得の動向についても確認すると(第2-1-3図(3))、高齢世帯の可処分所得は1995年頃より減少傾向が継続している。この背景は、詳しくは次でみるように勤労者世帯では非正社員として働く雇用者が増えたことや、社会保険給付の減少等が影響していることが考えられる。
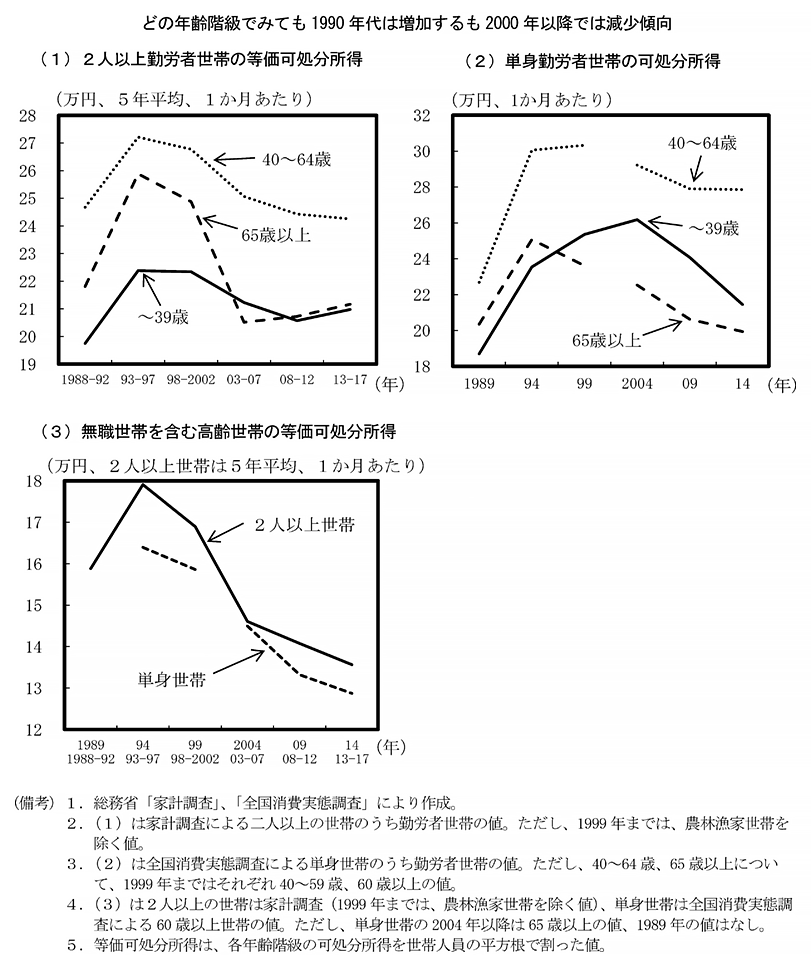
可処分所得の変動を要因分解した結果をみてみよう。相対的に振れが少ない2人以上の世帯(勤労者世帯)を対象に、1988~92年を基準とした可処分所得の累積差をプロットした(第2-1-4図(1)~(3))。上記でみたように、どの年齢階級でも2000年以降可処分所得は減少傾向であったが、特に勤め先収入の減少が寄与していることが確認できる。ただし、2013~17年の勤め先収入は増加に転じていることから、所得環境は足下では改善傾向にあるといえる。
年齢階級別に詳細にみていくと、39歳以下の世帯では、90年代に社会保険料が増加したが、それ以上に勤め先収入が増加していたことで可処分所得は増加となった。ところが、2000年代前半以降、この勤め先収入が大幅に減少したことが主因となって可処分所得は伸び悩んだ。この背景には、労働時間が短い人が多い非正社員として働く者の比率が増加していること等が影響していると考えられる。例えば、44歳以下で非正社員として働く者の割合の長期的な推移をみると(付図2-1(1))、2000年頃に急上昇していることがわかる。ただし、近年では非正社員比率の上昇が緩やかになり、2015年以降は低下に転じていることから、若年世帯の所得環境の改善に寄与していることが示唆される。
次に、40~64歳の世帯をみると、勤め先収入の動向は若年世帯と同様の動きをしているが、社会保険料が増加傾向で推移していることが可処分所得を下押ししている。例えば、2013~17年の勤め先収入は増加に転じているが、社会保険料の支払いがそれを上回っていることにより、可処分所得が低下している姿となっている。ただし、各年の動向をみると、2015年以降は、3年連続で前年比プラスとなっている。
65歳以上の世帯では、勤め先収入の減少が非常に大きく、2003~07年にマイナスに転じている。高齢世帯における雇用形態の推移をみると(付図2-1(2))、2000年代中頃から高齢者の労働参加が進むにつれ、非正社員として働く高齢者が増加していることが確認できる。正社員と比較すると、非正社員として働く高齢者の給与水準は低いため、一人(世帯)当たりに換算すると水準が低下してしまうことが影響していると考えられる12。また、2010年頃より65歳以上の勤労者世帯における有業人員数が増加傾向で推移していることもあり13、勤め先収入は増加に転じている。さらに、2003~07年においては、社会保障給付の減少や社会保険料の増加も可処分所得の押下げに寄与していたが、前者は物価下落を受けて年金額が改定されたこと14、後者は介護保険料を支払うことになったこと15が影響していると考えられる。
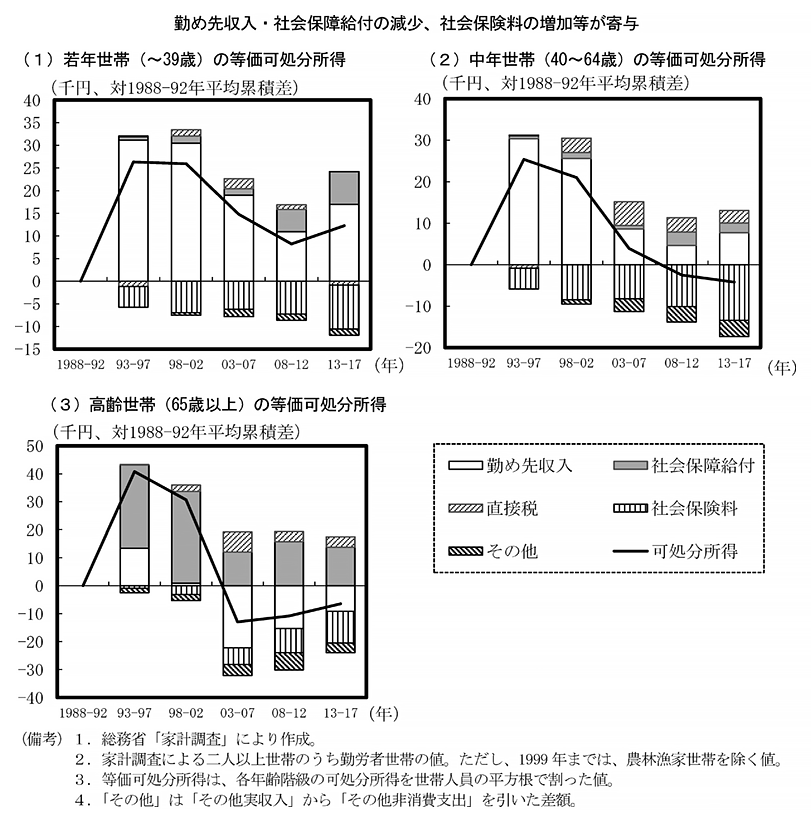
最後に年齢階級別にみた可処分所得の分布について確認する。第2-1-5図は、2014年における2人以上の世帯の勤労者世帯及び無職世帯における一か月当たりの可処分所得の分布をみたものである16。グラフの見方として、柱部分の下が25%点・上が75%点・中央の線が50%点(中央値)、上ヒゲの端が95%点・下ヒゲの端が5%点を示している。中央値と平均値を比べると、平均値の方が1~2万円程度高くなっており、所得の高い世帯の存在が平均値を若干ではあるが押上げている。年齢階級別にみると、中年世帯における所得分布が広くなっており、例えば75%点と25%点との差は約23万円となるなど、世帯ごとの差が大きい。一方、若年世帯・高齢世帯の所得分布の幅は同程度となっており、75%点と25%点との差は15~16万円程度である。また、高齢世帯では可処分所得が少ない世帯もあり、5%点における世帯の可処分所得はほぼゼロとなっている17。
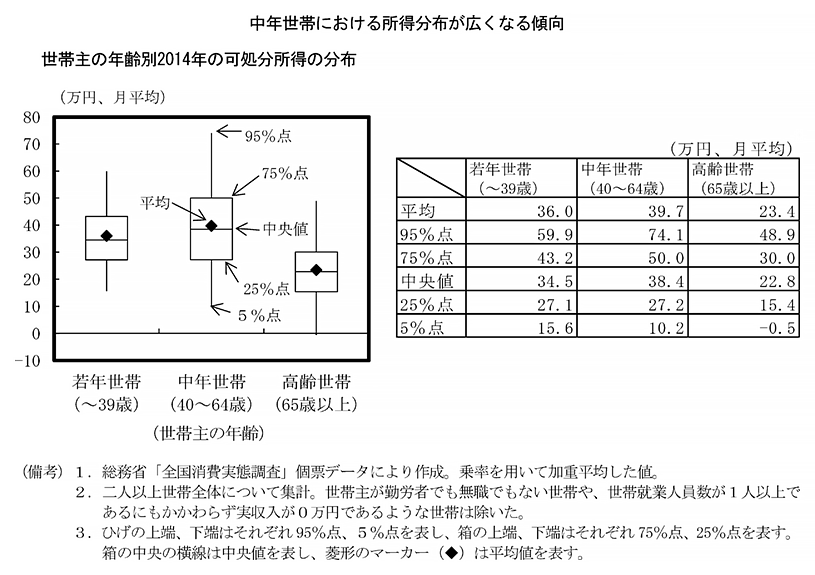
(住宅ローンの増加により、若年世帯の純金融資産はマイナスに)
所得に引き続き、家計における資産の動向についても世帯主の年齢階級別に確認する。2人以上の世帯における純金融資産18の動向をみると(第2-1-6図(1))、39歳以下の家計では、明確な下方トレンドが存在しており、特に2000年代前半には純金融資産残高がマイナスに転じ、2017年時点では▲521万円程度となっている。また、40~64歳の世帯では、大きな変動はないものの、2000年頃以降において若干の下落傾向で推移しており、2017年時点で純金融資産残高は876万円程度である。65歳以上の世帯においては、増減を繰り返しており、平均でみると2008~12年では160万円程度減少したが、2013~17年に155万円程度の増加に転じており、2017年時点の純金融資産残高は2,249万円程度である。
続いて、単身世帯における動向をみると(第2-1-6図(2))、2人以上の世帯と異なり、39歳以下の世帯の純金融資産は、横ばい圏内で推移しており、その値も一貫してプラスとなっている。また、時系列で必ずしも接続していない部分はあるが、40~64歳、65歳以上の世帯においては純金融資産が増加傾向で推移していることが伺える。
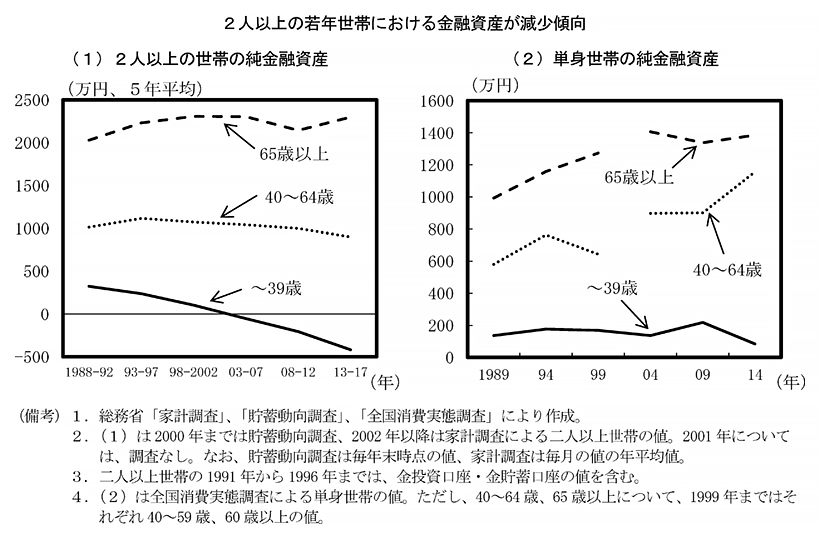
こうした貯蓄動向の背景をより詳細にみるために、2人以上の世帯における純金融資産の内訳の動向をみてみよう(第2-1-7図(1)~(3))。まず、39歳以下世帯をみると、2人以上の世帯の純資産が減少している背景には、住宅・土地の負債が増加していることが指摘できる。この背景には持家率の上昇が寄与していると考えられるが、事実、39歳以下の世帯における持ち家率の推移をみると(第2-1-7図(4))、長期的に上昇傾向にあり、1990年と2017年を比較すると43%から58%へと15%ポイント程度上昇している。2人以上の世帯と異なり単身世帯では貸家を利用する場合が多いため、若年世帯における純資産はプラスになっていると考えられる。また、生命保険等や有価証券が減少傾向にあるのに対し、現貯金は増加傾向にある点も特徴として指摘できる。次節でもみるように、若年世帯が将来に備える等の目的で貯蓄している可能性が考えられる。
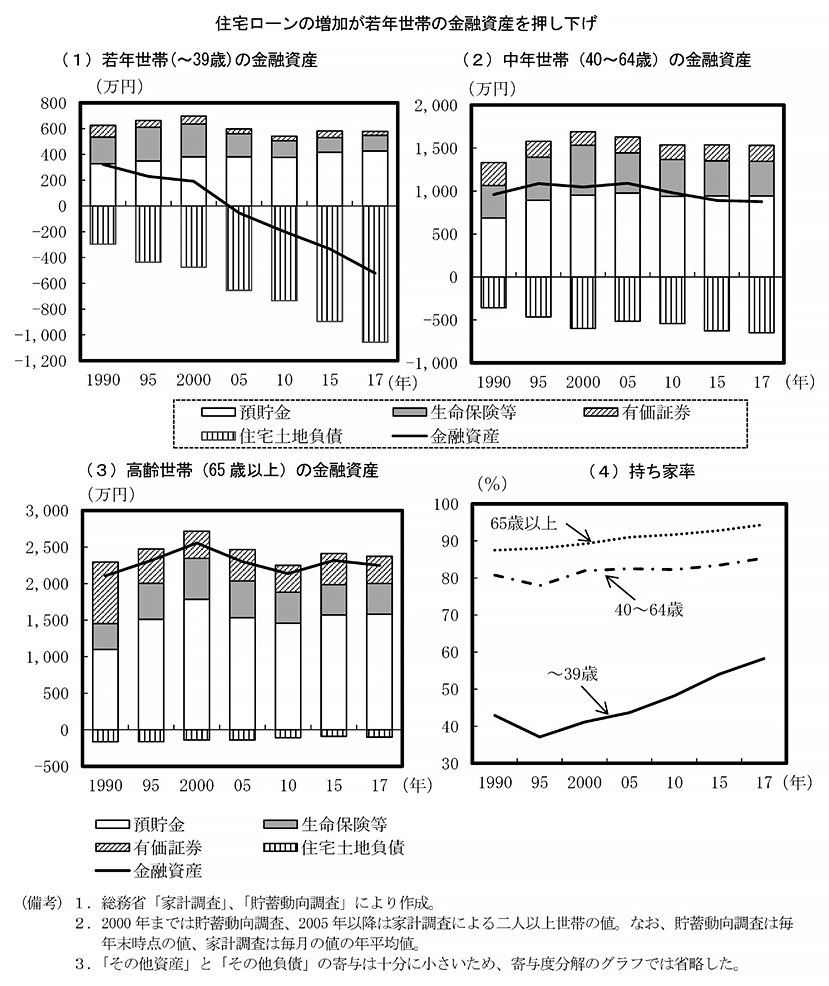
次に、40~64歳の世帯をみると、若干ではあるものの、持家率が上昇していることを受けて、住宅・土地負債が純資産に対して下押しに寄与している。その他の項目については年による増減があるものの、概ね横ばいで推移している。2017年の値を用いて金額の水準を比較すると、若年世帯と比較して預貯金が約2倍、生命保険等が約3倍、有価証券が約6倍となっており、若年世帯と比較すると、資金に余裕が出てきた中年世帯では、有価証券等のリスク資産にも投資を行うようになっている。
65歳以上の世帯をみると、増減を繰り返していることからトレンドを読み取りづらいが、2000年以降は横ばい圏内で推移していると考えられる。高齢世帯では、住宅ローンの返済が終わった世帯が多く、住宅・土地の負債が純資産に与える寄与が非常に小さくなっていることが特徴である。また、2017年の値で中年世帯と比較すると、預貯金額が約2倍、生命保険は同程度、有価証券は約2倍に拡大している。リスク資産の保有額は他の年齢階級と比較すると高いため、株価の変動等の影響が受けやすいことが示唆される。ただし、資産のうち、預貯金が7割弱を占めており、有価証券のウェイトは16%程度である。
年齢階級別に資産の分布についてもみてみよう。第2-1-8図は、前掲第2-1-5図と同様に2人以上の世帯における純金融資産の分布をみたものだが、可処所得の分布と比較すると平均値と中央値の乖離が大きく、年齢が高くなるにつれて分布が広くなっていることが指摘できる。若年世帯の純金融資産では、平均値では▲413万円程度となっているものの、中央値ではゼロとなっており、負債残高が大きい世帯が平均を押下げていることがわかる。中央値がゼロということは、2人以上の若年世帯のうち半数の世帯では純金融資産残高はマイナスであることを意味している。これに対して40~64歳では、平均値の方が中央値より372万円高くなっており、中央値・平均値ともにプラスである。この平均値と中央値の乖離幅は、65歳以上では非常に高くなり、その差は761万円程度となっている。高齢世帯では下位50%の分布と比較すると、上位50%の分布範囲が非常に大きくなっていることが特徴であり、上位5%では6,718万円と非常に高額の金融資産を保有している世帯の存在を確認することができる。
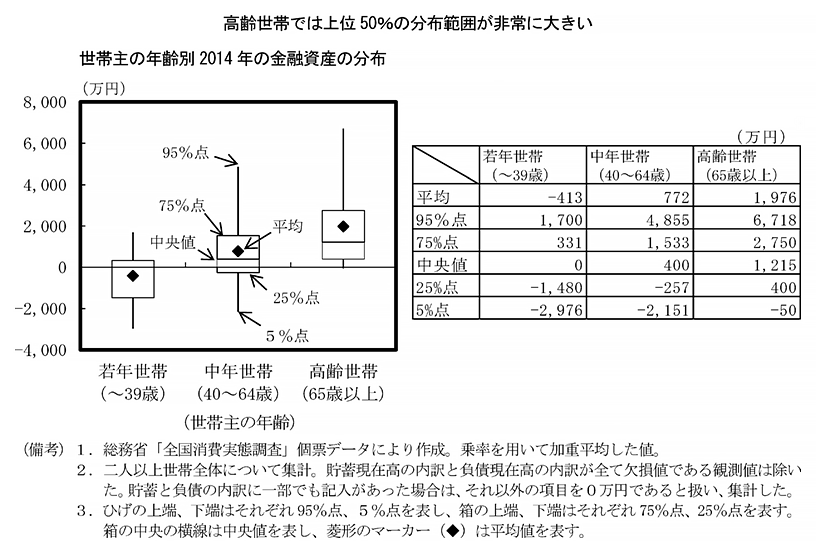
コラム2-1 所得格差の動向
所得格差の時系列的な動向についてみるため、アメリカ、ドイツ、日本における1990年代後半以降のジニ係数19の推移をみてみましょう(コラム2-1図(1))。ジニ係数とは、所得の均等度を表す指数であり、1に近いほど所得格差が大きいことを示します。再分配前の所得によるジニ係数は、ドイツ、アメリカ、日本20ともに緩やかに上昇しています。再分配前の所得には、公的年金などの社会保障給付が含まれていないため、高齢化が進み公的年金を受給する高齢世帯の割合が増えると(前掲第2-1-1図)、所得格差が拡大してしまうという問題があります。そこで、年金などによる再分配後の可処分所得によるジニ係数の推移をみると、日本は2000年代半ばにかけてやや上昇した後、直近の値は低下に転じています。また、ドイツ、アメリカが緩やかに増加しているのと比較すると、日本の変動幅は限定的であることも指摘できます。つまり、再分配後の所得でみると、日本における格差は拡大傾向にはないと考えられます。
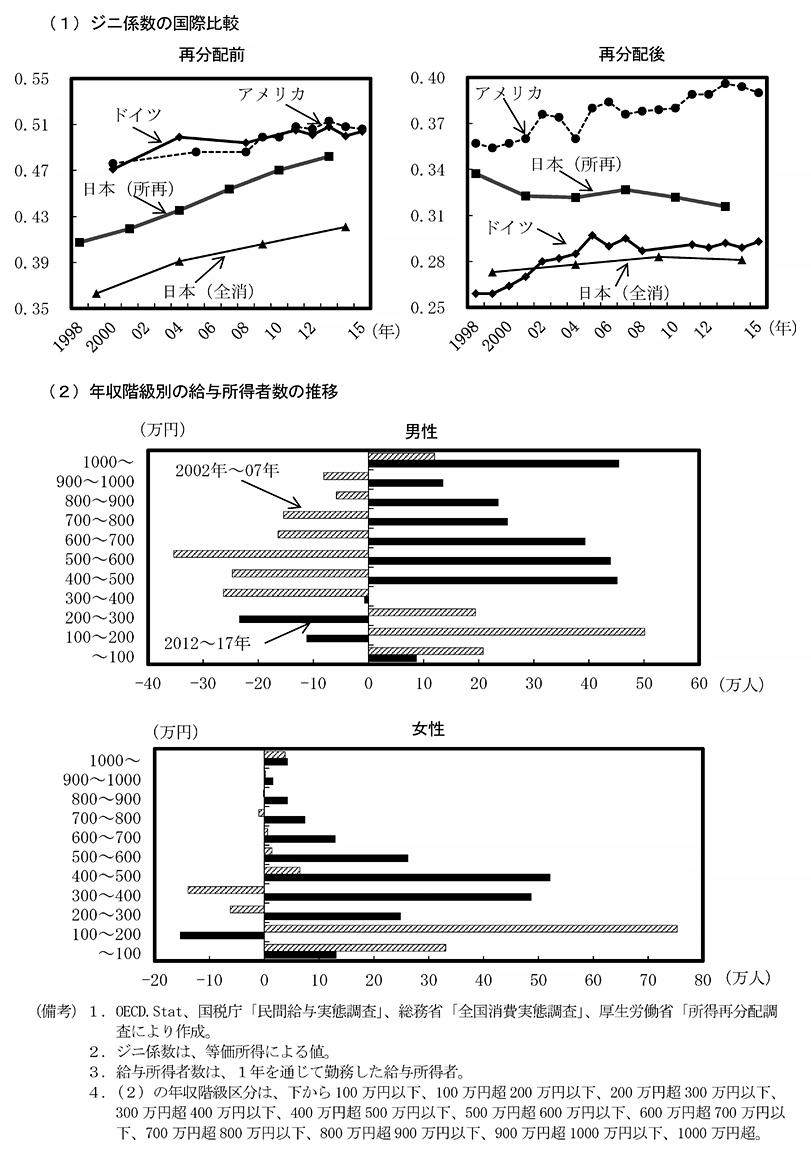
ジニ係数は、所得格差を把握できる代表的な指標ですが、中間層の所得分布に影響を受けやすいことや、世帯へのサンプル調査をもとにしているため高所得者の捕捉が難しいなどの欠点もあることが指摘されています21。そこで、事業所のサンプル調査である国税庁「民間給与実態調査」を用いて、年収階級別・性別の給与所得者数の増減数について、2012年以降の景気回復局面と2002~07年の景気回復局面とで比較を行うことで、より直近の動向を詳細に確認してみましょう(コラム2-1図(2))。
まず、男性についてみると、2002~07年においては、年収300万円~1000万円の幅広い層の給与所得者が減少に転じる一方、1000万円以上の高所得者と年収300万円未満の低所得者がやや増加しており、二極化の傾向にあったことが示唆されます。直近の2012~17年においては、年収1000万円以上の高所得者が大きく増加しているだけでなく、年収400万~700万円の中間層も大きく増加していることが指摘できます。女性については、2002年から07年は年収200万円未満の給与所得者が大きく増加していましたが、2012年から17年においては年収200万円~600万円の中間層が大きく増加し、年収600万円以上の中高所得者も増加しており、より高い給与所得を得る女性が増えていることが確認できます。このように、今回の景気回復局面においては、高所得者も増加傾向にあるものの、雇用情勢の着実な改善に伴い中間所得者がそれ以上に増加しているため、所得格差は拡大していないことが考えられます。

