第1節 世界金融危機後の成長構造の変化
本節では、世界金融危機を経て主要国で生じた成長の構造的な変化やその要因を分析する。危機直後の内外の需要の急減に対応するための雇用や投資の抑制が、その後にも影響を残す履歴効果となって引き続き各投入要素の縮小につながり、ひいては潜在成長率をも低下させている可能性がないか検証することが本節の課題である。また、特に2000年代の成長を支えてきたICT資本財の寄与も危機後低下に転じているのか、あるいは危機前から中長期的なトレンドとして既に定着している国外生産へのシフトの状況にも変化がみられるかも併せて確認することとする。
1.総じて低下した製造業の成長寄与
世界金融危機後の先進国における成長構造の変化を分析するに当たり、それぞれ特徴的な産業構造を持ち、かつデータの利用可能性を考慮してアメリカ、英国、ドイツ、フィンランド、韓国(以下主要国)を比較対象に取り上げることとする。
これらの国における産業の特徴としては、例えばアメリカや英国は、情報通信・金融等の非製造業に強みを持つ一方、ドイツは自動車を始めとする機械等を中心とした成熟した製造業を有することが挙げられる。また、フィンランドは輸出主導型のICTに特化した製造業を特徴とし、韓国は財閥に代表される大企業による輸出主導型の製造業を持ち、電気・電子機器や輸送機械等に強みがあることで知られる。
こうした特徴を持った主要国間の比較を通じて、世界金融危機による内外の需要の縮小により、特にどの産業が影響をより被っているか、そしてそれが各国の全体的なパフォーマンスに違いをもたらしているかどうか、などについてみることができる。
主要国の経済成長を供給サイドから探るため、最初に産業別にみた付加価値生産の変化をみてみよう。これによると、各国で程度の差はあるものの世界金融危機前は製造業、小売等、情報通信、金融といった幅広い産業がプラスの寄与を示していたものの、危機後は総じてそれらが低下していることが分かる(第2-1-1図)。
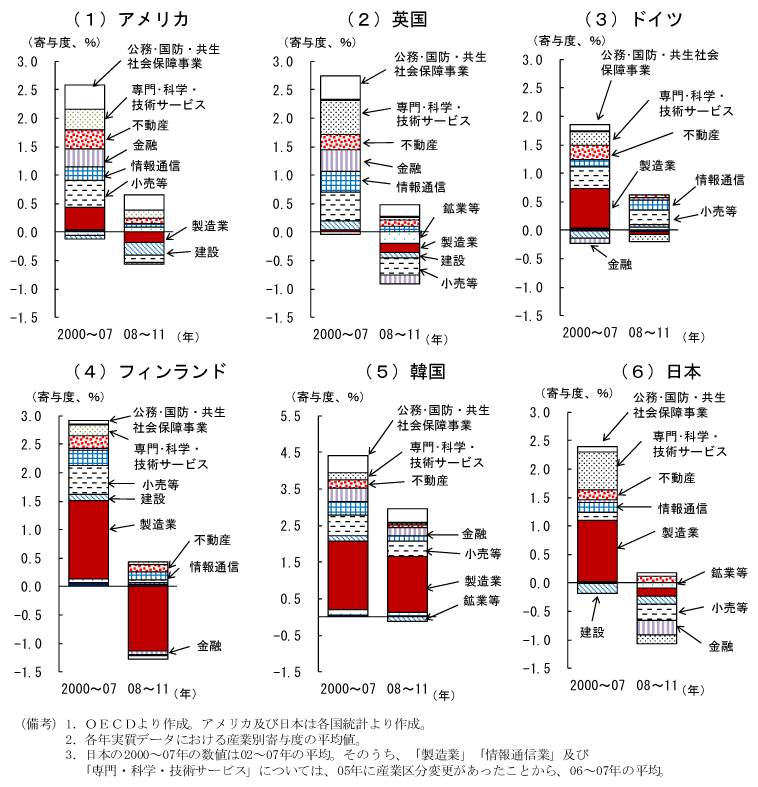
特に製造業に着目すると、それが産業構造上重要な位置を占めているドイツ、フィンランド、韓国では危機前の成長寄与の半分を占めていたところが、危機後は韓国を除きその落ち込みが顕著となっている。また、アメリカや英国でも製造業はマイナスの寄与に転じており、このことは金融危機後の世界貿易の縮小がどの主要国でも製造業を直撃していたことがうかがわれる。
主要各国の産業構造の変化にもその影響が表れている。2000年以降の製造業の実質付加価値額の水準の推移をみると、危機前の07年までは英国を除くどの主要国でも製造業は各年とも比較的安定的に成長し、付加価値生産額全体に占める製造業のシェアも高まっていたことが分かる。しかし、危機後は韓国を除き、11年段階でも危機前の水準まで回復しておらず、シェアも低下している(第2-1-2図)。
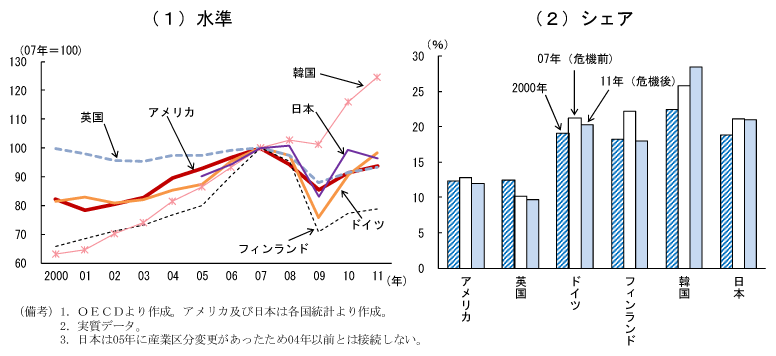
一方、主要国の非製造業についてみると、全体的にみて危機の影響は製造業に比べ比較的軽微だったといえる。しかし、非製造業への依存度がほかの主要国に比べ高いアメリカや英国では、小売等や金融が大きく寄与を下げる中でほかの非製造業も軒並み成長に対する寄与を縮小させていることが分かる。
なお、非製造業のうち情報通信業に着目すると、経済社会のIT化の進展に伴い世界金融危機前には同産業が各国とも共通して着実に伸びていることが分かる(第2-1-3図)。危機直後は成長が足踏みする国もみられたものの、その後持ち直し11年時点ではどの国も危機前水準を既に上回っており製造業の動きと対照的である。その結果、情報通信業のシェアもいずれの国においても上昇する傾向が続いており、各国産業で共通した成長分野の一つとなっている点について変わりはないといえる。
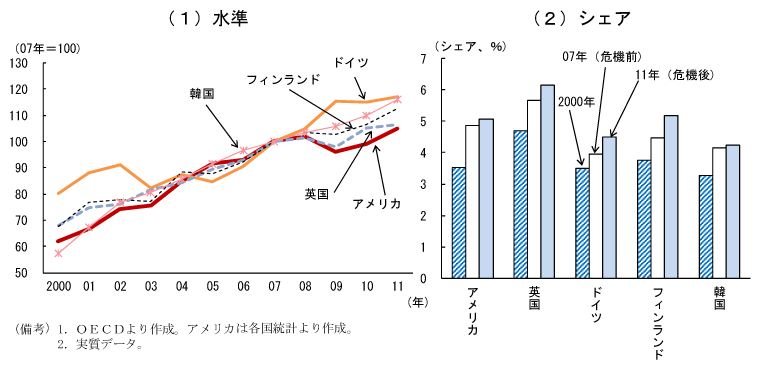
このように世界金融危機後、産業の成長率が全般的に低下する中、韓国を除き特に製造業の成長寄与の低下が著しく、非製造業依存の高い国では危機前の成長けん引役であった金融や小売業といった産業の成長寄与が大きく低下し、産業構造上も危機前までのトレンドが変化していることがうかがえる。
こうした各国の主力ともいえる産業が世界金融危機によって影響を受ける中で、当該産業の成長が需要面からまず抑制され、財やサービスの生産に投入される労働や設備投資の縮小がその後の人的・物的資本の蓄積の鈍化をもたらし、それが供給力をも低下させてしまっている可能性も考えられる。
以下では、危機後、主要国における各産業の成長率の低下をもたらした要因について、成長会計の枠組みをもちいて付加価値生産の変化を労働、資本及び全要素生産性の変化に分解し、それぞれの変化を規定する要因について順に分析する。
2.供給面からみた主要国の成長力の変化
本項では、産業別の付加価値生産の変化について、(1)雇用量と労働時間の積からなる労働投入量(以下労働時間)及び高スキル化を考慮した労働の質(以下労働構成)、(2)ICT資本財及び非ICT資本財から構成される資本ストックの増について資本稼働率を調整した上で算出される資本投入、(3)技術進歩による効果を含む全要素生産性(以下TFP)に寄与度分解1する。これによって、世界金融危機後の成長率鈍化の要因を要素投入面から明らかにすることができるが、危機後に構造的失業率の上昇、国内投資の抑制あるいはTFPの伸び悩み等の形で表れる履歴効果が観察されるかどうかも併せて確認する。
(1)主要国の労働・資本・TFPはいずれも総じて鈍化
まず、主要国の産業全体について各投入量による成長に対する寄与が世界金融危機前後でどのように変化したか概観してみよう。
これによると、主要国では総じていずれの生産要素も危機前はプラスに寄与する中で、特にTFPや資本投入が高い成長要因となっていたことが分かる(第2-1-4図)。しかし、危機後はTFPの伸びがアメリカを除き軒並みマイナスに転じるとともに、資本投入も韓国を除き寄与を落としている。なお、多くの国がICT資本財、非ICT資本財ともにパラレルに寄与を落とす中で、フィンランドでは非ICT資本財の寄与が大きくマイナスに転じている点が目立つ。また、労働投入面をみると、アメリカでは労働時間や労働構成要因ともに成長のマイナス要因となっているのに対し、ほかの国ではTFPや資本にくらべ軽度の変動にとどまっており、ドイツや韓国ではむしろ労働投入の寄与が危機後高まっているという様子も分かる。
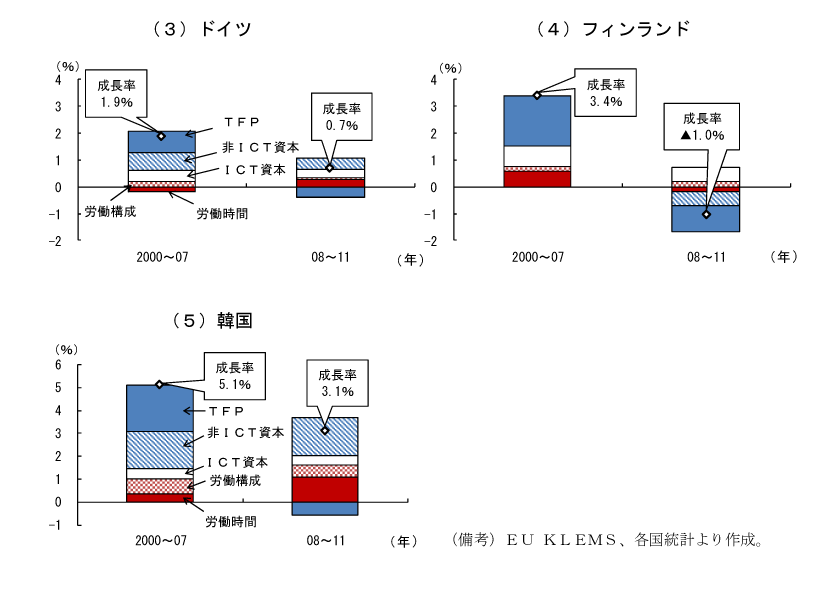
こうしたことから、産業全体でみると危機後の成長率の低下は労働投入の抑制よりもTFPの減退や資本投入の抑制によってもたらされている面が強いといえる2。TFPや資本に比べ労働投入の調整が緩慢となっている影響は、労働生産性の低下という形でも表れると予想される。
以下では、各国における産業全体の動きを個別産業に分解して、特に世界金融危機前において成長寄与が高かった製造業、小売等、情報通信、金融の各産業に着目し、それぞれの産業で生産要素投入ごとにどのような変化がみられたか検証する。
(2)労働投入面からの成長寄与の変化
前項までの分析から労働投入面からの成長寄与の世界金融危機前後の変化はアメリカを除き相対的に軽微であったことが示唆された。ここでは、各国の個別産業についてもそれが当てはまるのかどうか、あるいは、国によっては世界金融危機後、雇用情勢が悪化する中で、製造業等の主力産業で労働投入量が抑制されたままで推移し構造的な失業率の高まりにつながっているか確認する。加えて、労働投入量が抑制されているとすれば、その背景として労働コストの調整の遅れが考えられ、この点についても併せて検証する。
(i)労働時間の減少は一貫して続くも雇用者数3 減少は局所的
減少は局所的
主要国の産業別の労働投入について、危機前と危機後でどのように変化しているかをみるため、雇用者数及び一人当たりの労働時間の寄与に分解してみよう。
まず雇用者数についてみると、アメリカ、英国では危機前から製造業の雇用者数の減少傾向は顕著であったが、危機後、小売等や金融といった同国の主力産業である非製造業でも雇用者数を減らしていることが分かる。これらの国では従来から雇用吸収源となってきた産業でも雇用者数による労働投入の調整が広く行われたことがうかがわれる。
一方、危機後、製造業のダメージが特に大きかったフィンランド、ドイツでは両国で雇用調整の程度が大きく異なっていることがみてとれる。すなわち、ドイツでは他産業同様、雇用者数による調整がほとんど行われていないのに対し、フィンランドでは製造業で雇用者数の顕著な減少がみられ、他方、同国の金融や情報通信で雇用者数が伸びているなど産業間で雇用の大幅な移動が生じている可能性がうかがわれる。同じく製造業を主力としながら危機後の影響が相対的に軽微であった韓国では、ほとんどの産業で危機後雇用者数の伸びがむしろ上昇する傾向にあり、産業全体の動きとも一致している(第2-1-5図)。
次に各産業の労働者一人当たりの労働時間についてみると、危機後のアメリカや英国の小売等を除き、各国どの産業でも危機前後を通じて雇用者数の増減にかかわらず、労働時間が総じて減少する傾向が続いているといえる。こうした中、フィンランドで製造業や金融が危機後、労働時間が特に落ち込んでいることが分かる。同国の産業間の雇用調整のプロセスで、雇用者数のみならず労働時間についても大幅な調整が行われていることが示唆される。
このように、労働時間の減少は総じてどの国の産業でも一貫して続いているものの、雇用者数における危機後の新たな動きは、アメリカ及び英国の非製造業における減少の広がりとフィンランドの製造業における減少等に限定されていることが明らかとなった。
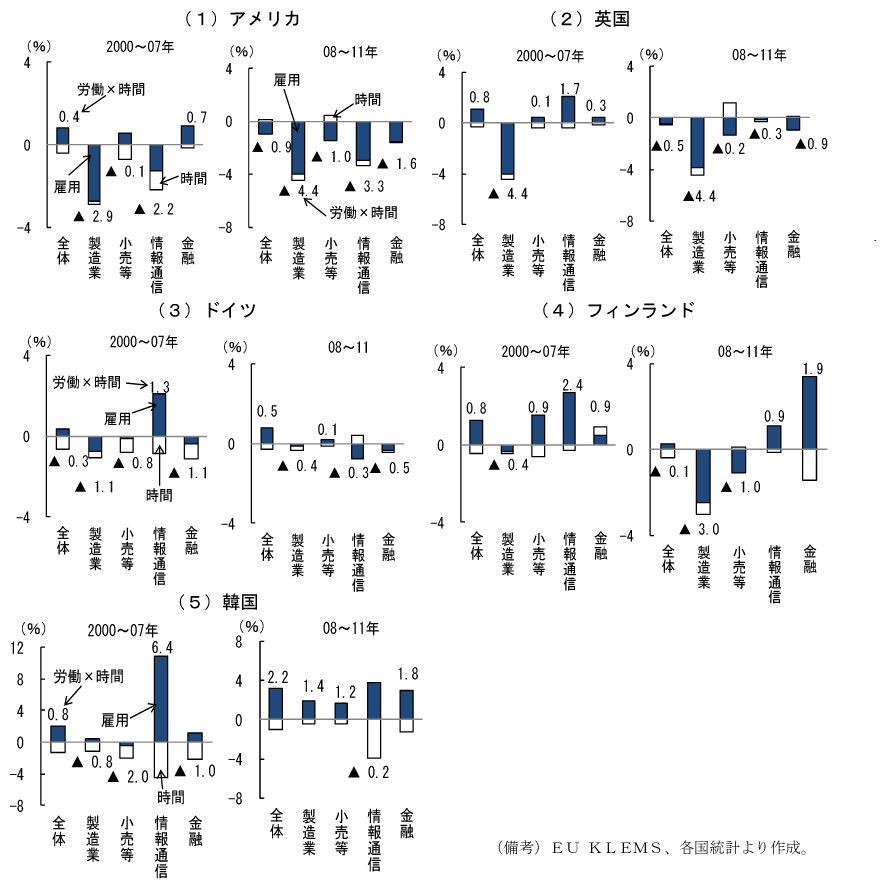
以上のような世界金融危機前後における労働投入面での変化が、危機後、履歴効果となって各国の労働市場の動向に表れているかどうか次にみてみよう。履歴効果が発生している場合は、各産業における労働投入が鈍化ないしは減少するのと並行して、失業が構造化し長期失業率が上昇する現象が観察されるはずである。
そこで、長期失業率についてみると、従来からの製造業に加え危機後は非製造業も含め雇用者数の減少が広く及んでいたアメリカや英国では、危機後はそれが上昇しているのが確認できる。一方、その他の国ではフィンランドも含めむしろ低下しており、韓国では長期失業率そのものが危機前後を通して極めて低水準であることが分かる(第2-1-6図)。
こうしたことから、アメリカや英国において労働投入面で履歴効果が生じている可能性は示唆されるものの、世界金融危機が主要国一般にそうした履歴効果をもたらしたとは言い切れないとみられる。
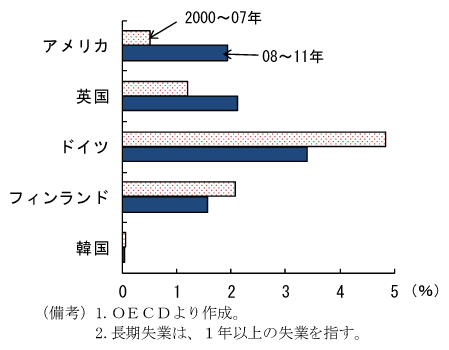
(ii)労働投入抑制の背景にある高止まりしている単位労働コスト
前項でアメリカや英国、フィンランドの製造業で、危機後、主として雇用者数の減少による労働投入の調整が行われたことをみた(前掲第2-1-5図)が、ここではそうした各産業の労働投入の変化と労働コストとの関係を探る。例えば、危機後、労働生産性の落ち込みにも関わらず賃金の調整が遅れているとすると、単位労働コストの上昇や高止まりが発生し、労働投入が抑制される力が強まると考えられる。
そこで、単位労働コストを労働生産性要因と賃金要因に分解し4、危機前後でそれぞれの要因がどのように作用しているかみてみる。これによると、危機前はどの国でも全体として単位労働コストは上昇傾向にある中で、製造業や情報通信では労働生産性の伸びが高く、当該産業の単位労働コストは総じて低下していることが分かる(第2-1-7図)。
しかし、危機後は、アメリカ、英国における小売等、ドイツ、フィンランドにおける製造業、英国、フィンランドにおける金融業等、危機前にはいずれも高い成長がみられた産業において労働生産性の落ち込みと賃金の上昇が同時に生じ、結果として単位労働コストが双方の要因から押し上げられている。なお、韓国では、どの産業でも労働生産性が危機前後を通じ一貫して上昇する一方で、それを上回る賃金の上昇により総じて単位労働コストが上昇している。ただし、危機後は金融では賃金上昇が抑えられる一方、労働生産性の伸びがもともと高い情報通信では賃金上昇が逆に労働生産性の伸びを上回り、両者の単位労働コストの動きが危機前後で逆転するなどの現象もみられている。
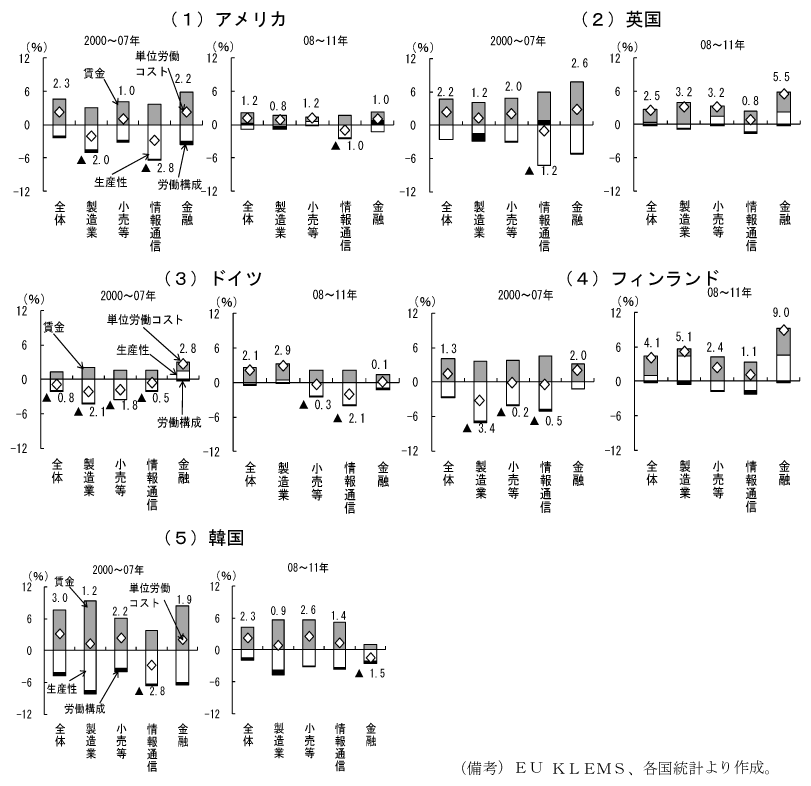
こうした単位労働コストの動きと前述の労働投入との対応関係についてみると、危機後、総じて単位労働コストが上昇している産業では労働投入が低下していることが分かる。具体的には、アメリカの製造業については、危機後に単位労働コストの上昇と雇用者数のマイナス幅の拡大がみられ、危機後、労働投入が大きく減少した小売等、金融でも単位労働コストの上昇が続いている。また、英国でも危機後、どの産業でも単位労働コストが上昇しており、各産業の労働投入の減少の動きと付合している。フィンランドの製造業についても危機後、単位労働コストが大幅な上昇に転じており、それが同産業の労働投入の大幅な減少につながっているとみられる。また、韓国では特に情報通信において危機前から危機後にかけて単位労働コストが上昇に転じており、同産業での労働投入量の低下につながっていると考えられる。
なお、各国とも多くの産業で危機前後を通じて教育水準でみた労働構成の変化5にみられる労働の質的面での向上が労働生産性の上昇とともに単位労働コストを引き下げる方向に働いていることが分かる。しかし、高スキル化は一定程度進んでいることはうかがえるものの、その効果は賃金の伸びと比較すると極めて限定的なものにとどまっており、単位労働コストの上昇抑制に大きく寄与しているとはいえない。
以上から、金融危機後の主要国の各産業における労働投入抑制の背景として、賃金調整の遅れに伴う単位労働コストの上昇が一因となっていると考えることができる。
(3)資本投入面からの成長寄与の変化
前項では、労働投入面では労働時間の減少傾向が危機前後を通じて主要国全般で続いているのに対し、危機後、雇用者数の減少はアメリカや英国の各産業、及びフィンランドの一部産業に限られていることが明らかとなった。他方、前述したように、産業全体でみると危機後の供給面からみた成長のより大きな低下要因は資本投入量の伸びの鈍化に求められる。
ここでは資本投入面の変化について、主要国の各産業の状況を確認するとともに、資本投入が鈍化した背景についても検証する。特に、(1)非製造業は製造業に比してICT資本財による成長に対する寄与が従前から大きかったとみられるが、危機後それが剥落しているのではないか、(2)製造業については国内設備投資から対外直接投資へのシフトが危機後更に加速したのではないか、(3)非ICT資本財の設備年齢の上昇等による資本ストックの質の劣化が生じているのではないかといった問題意識から、これらについても順に検証していくこととする6。
(i)伸びが鈍化した資本ストック
主要国における世界金融危機前後における資本投入の動きについて、まず、資本ストックの伸び率の推移をみてみよう。
全体的にみると、世界金融危機後、各国とも国内の設備投資が低迷した影響もあり、各産業の資本ストックの伸びが鈍化していることがはっきりと分かる。
さらに詳しくみると、世界金融危機前は、アメリカ、英国及びドイツでは情報通信や金融を始めとする非製造業、フィンランド及び韓国では特に製造業や情報通信で資本ストックの顕著な増加がみられていた(第2-1-8図)。しかし、危機後はいずれの産業においても資本ストックの伸びが鈍化しており、特にアメリカの金融やフィンランドの製造業のように当該国の主力産業でマイナスに転じているものもある。一方、韓国では、危機後も資本ストックの伸びの堅調さは保たれているものの、やはりいずれの産業でもやや鈍化していることが分かる。
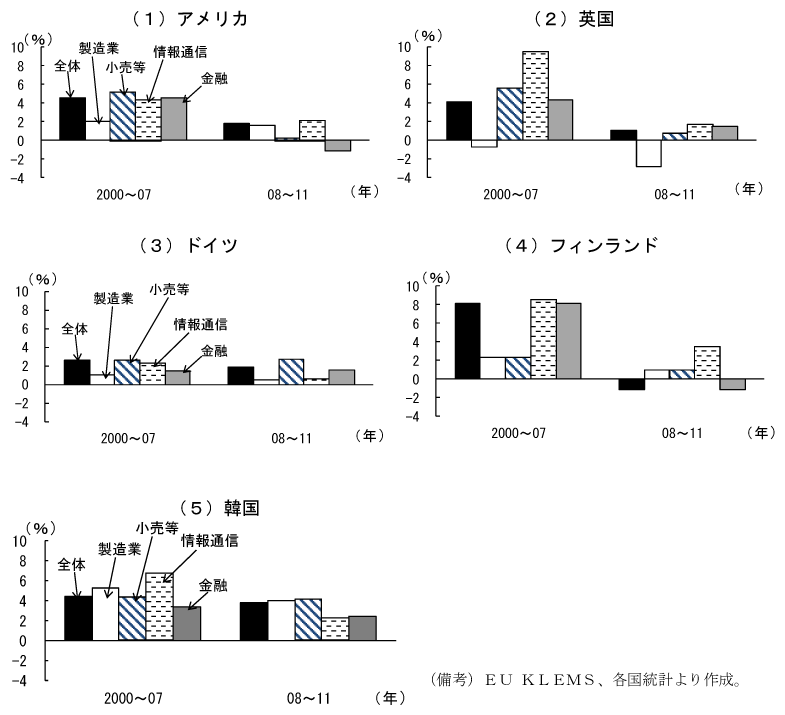
次に資本ストックをICT資本財/非ICT資本財に分解して、それぞれの動きをみると、危機後、全体としてICT資本財/非ICT資本財ともに低下傾向にあり両者で大きな違いはないといえる。例えば、製造業では、フィンランドや韓国を始め各国ともに非ICT資本財が低下ないし減少に転じており、生産のために使用する機械設備等の国内での投資抑制が影響したものと考えられる。同様に、アメリカや英国を始めとして危機前は小売等、情報通信、金融といった非製造業でICT資本財の伸びが製造業よりも比較的高い国が多くみられた中、危機後はそれらも含めて総じて低下傾向にあることが分かる(第2-1-9図)。
こうしたことから、危機前には特に非製造業の資本ストックのけん引役を果たしていたICT資本財による寄与が、非ICT資本財同様、危機後剥落していることが確認された。
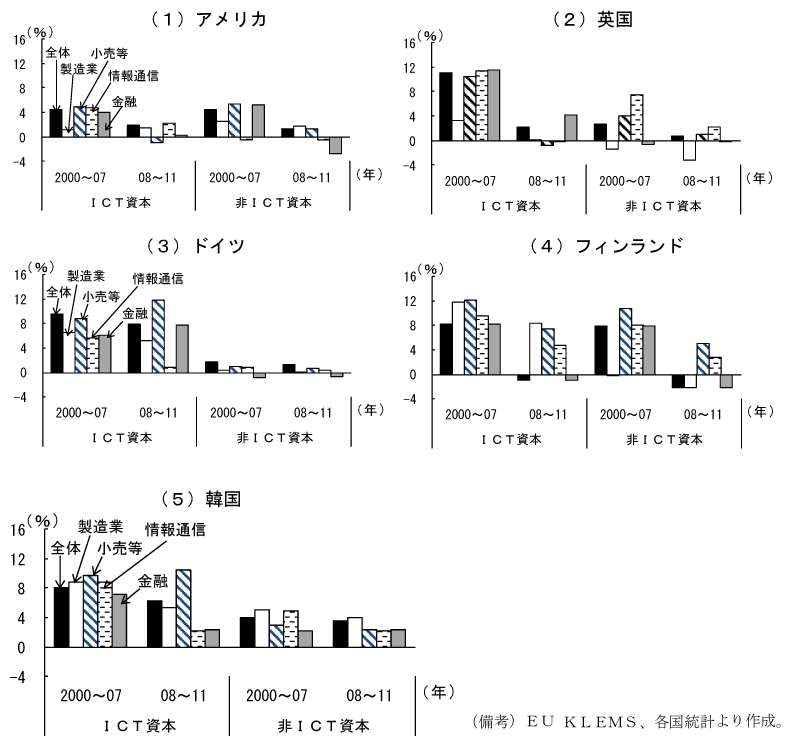
(ii)高まる対外投資収益依存
次に前述のように資本ストックの伸びが鈍化している背景として、国外生産への代替が可能な製造業を中心として、危機後、国内投資から対外直接投資へのシフトが特に進んでいるかについて検証する。
まず、各国の対外直接投資全体のフローをみると、アメリカ及び韓国では危機後は名目GDP比で増加している一方、危機前には比較的高い水準にあった英国、ドイツ及びフィンランドでは、危機後はその割合がむしろ低下している(第2-1-10図)。
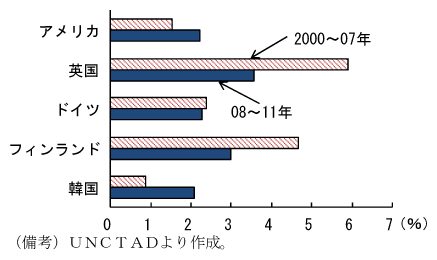
さらに対外直接投資の産業別の内訳が入手可能なアメリカと韓国についてみると、アメリカでは、従来から対外直接投資全体に対する多国籍企業の寄与が高く、危機後やや落ち込んだものの増加傾向にあることに変わりはない(第2-1-11図)。多国籍企業以外の国内企業については、製造業及び小売等が増加傾向にある。また、韓国では、企業の海外売上高が増大するとともに海外事業の黒字傾向が定着したことを受け、07年を境に特に中国向けの対外直接投資規模が増大している。世界金融危機後、投資額全体はやや減少に転じているものの、10年以降は鉱業や製造業を中心に堅調に推移している。
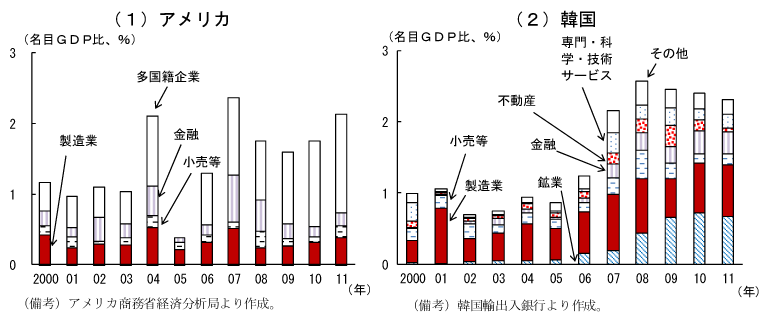
こうした対外直接投資による収益面の成果については、国内の付加価値生産と比べた対外所得の動きからそれを確認することができる。具体的には、GDPとGNIのかい離に相当する海外からの純所得をGDPとの対比でみると、主要国では危機前後を通じてそれが拡大する傾向が続いている(第2-1-12図)。また、海外からの純所得のうち直接投資収益に着目しても、韓国のみ赤字で推移するものの、その他の主要国は総じて増加傾向にあり、対外投資による収益依存7を高める傾向に大きな変化はないと考えられる。
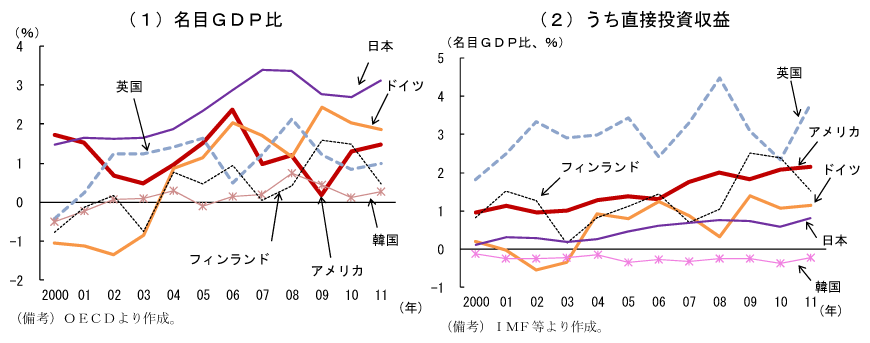
このように主要国全般を通じて世界金融危機後、対外直接投資を特に加速させたという事実ははっきりとは読み取れないものの、危機前までに既に対外で蓄積された投資による収益依存を相対的に高めていることについては確認された。このことは少なくとも国内における資本ストックを蓄積する誘因を弱めている可能性があると考えられる。一方、直接投資収益が赤字で推移している韓国ではそうした誘因がまだ弱まっていないことが、前述の同国の資本ストックの伸びの他国との違いに表れているとみることも出来よう。
(iii)高まる設備年齢と資本の質の劣化
前項でみたような資本投入の量的な鈍化とともに、資本の質的な変化が生じていないか確認するため、以下では設備年齢(以下、ビンテージ)についてみてみよう。なお、ここではKLEMSの延長推計で得られた各国の資本ストックと資本フローを用いてビンテージを試算している8。
この試算によると主要国の各産業の資本のビンテージは、総じて上昇傾向にあるといえる。特に世界金融危機後の国内投資の伸び悩みを背景に、例えばアメリカの小売等やフィンランドの製造業等は、ICT資本財、非ICT資本財ともに上昇を加速させているものも散見される(第2-1-13図)。他方、ドイツの小売等、金融のICT資本財、フィンランドの金融の非ICT資本財は比較的堅調な投資に支えられ、危機後ビンテージが低下しているものもあるが極めて例外的な動きであるといえよう。
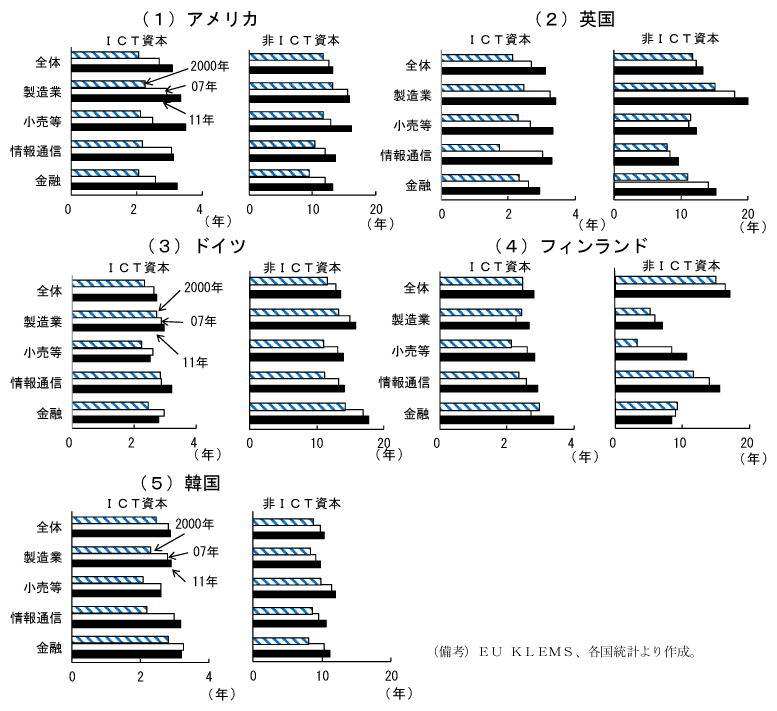
こうしたビンテージの上昇は資本ストックの質の劣化につながるとみられるが、その成長に対する効果を従来の量的な資本ストック指標に含めて測ることは難しい。そのため、TFPに資本ストックの質の劣化による効果も表れている可能性があり、両者の因果関係についても後に考察する。
(4)TFPの成長寄与の変化
TFPの伸びは、本来であれば、量だけでなく質的な面も考慮した労働や資本の要素投入の増加だけでは説明できない生産性の向上を示すものである。しかし、前述したように投入要素に質的側面を含める指標が作成できない場合、計測上、TFPに各投入要素の質的効果が含められることになる。その点も踏まえながら、以下では、主要国の各産業別にみたTFPの変化とそれを生じさせている背景について検証する9。
(i)製造業で低下の目立つTFP
前述の(1)でみたように産業全体では、アメリカを除いて各主要国でそれまで大きな成長寄与要因となっていたTFPが世界金融危機後にはマイナスに転じている。これを産業別にみると、国によってばらつきはあるものの、危機前には各主要国とも製造業はもとより、情報通信、金融、小売等といった非製造業でも幅広くTFPの上昇がみられていた。しかし、危機後は逆に製造業を中心に総じて鈍化傾向にあるが、情報通信ではどの主要国でもプラスの寄与が維持されており、前述のように同産業が各国の成長産業としての位置付けを保っている一面がここにも表れているとみられる(第2-1-14図)。
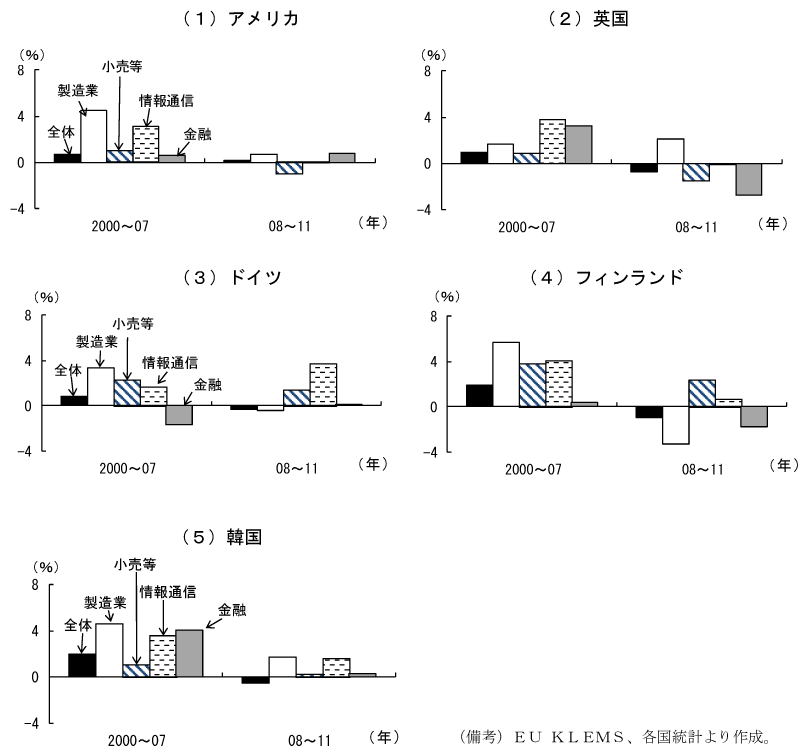
各国別にみると、特にドイツやフィンランドでは、小売等は危機後も比較的高い伸びを維持しているが、同国の主力産業である製造業では逆にマイナスの伸びとなっており、それが同国の産業全体のTFPの押し下げ要因となっているのが分かる。また、韓国では、危機後も製造業や情報通信を中心にプラスの伸びを維持しているものの、やはりどの産業でもその伸びが鈍化していることが分かる。
(ii)製造業リーディング業種で目立つTFPの低下
前項で世界金融危機後、各主要国とも製造業のTFPの低下が顕著となっていることが明らかになったが、その背景を更に詳細に探るため、ここでは製造業のうち危機前特に成長が目立っていた業種(コンピュータ等10、輸送機器)を選択してそれぞれのTFPの変化11
をみてみよう。
まず、コンピュータ等は、主要国では英国を除き危機前は高い伸びを示していたところ、危機後は伸びがどの国でも大きく鈍化しており、特にICT製造業に特化していたフィンランドではマイナスに転じているのが分かる(第2-1-15図)。また、自動車等を含む輸送機器は危機前にはアメリカ、ドイツ及び韓国で伸びが特に高かったところ、危機後は韓国を除きいずれも低い伸び又はマイナスに転じているほか、韓国でも伸びの低下がみられる。
このように主要国における製造業のTFPは、各国のリーディング業種においてもほぼ例外なく大きく低下しており、前項までにみたような産業全体のTFPの低下につながっていることがうかがわれる。
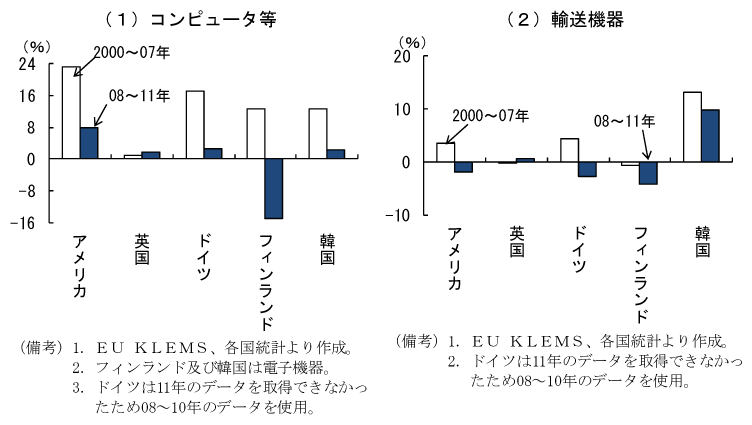
(iii)TFPの決定要素
次に、こうした危機後のTFPの伸びの低下がどのような要因によってもたらされているか検証しよう。過去の研究と同様にTFPを規定する要素として研究開発投資による無形資産による影響が考えられるほか、これまでみた労働や資本の量的指標ではとらえきれていない質的な効果が反映される可能性がある。
そこで、資本の質的向上の代理変数としてICT資本財及び非ICT資本財のビンテージ、無形資産の代理変数として研究開発費を取り上げ、それぞれの要素がTFPの伸びを有意に説明するか回帰分析を行った12。なお、TFPの変動は資本ストックの量的変化によって影響される面もあるため、各資本財の成長寄与も加えて推計している13
。
それによると、各主要国の産業全体についてみると研究開発費が有意にプラス、ICT資本財ビンテージが有意にマイナスとなった(第2-1-16図)。すなわち、研究開発費が増加するほど、あるいはICT資本財のビンテージが低下するほど、TFPの伸びが高まる傾向が観察されることになる。各国別にみると、前述の世界金融危機後のTFPの低下についてフィンランド及び韓国では、研究開発費の低下が大きく影響している可能性があることが分かる。
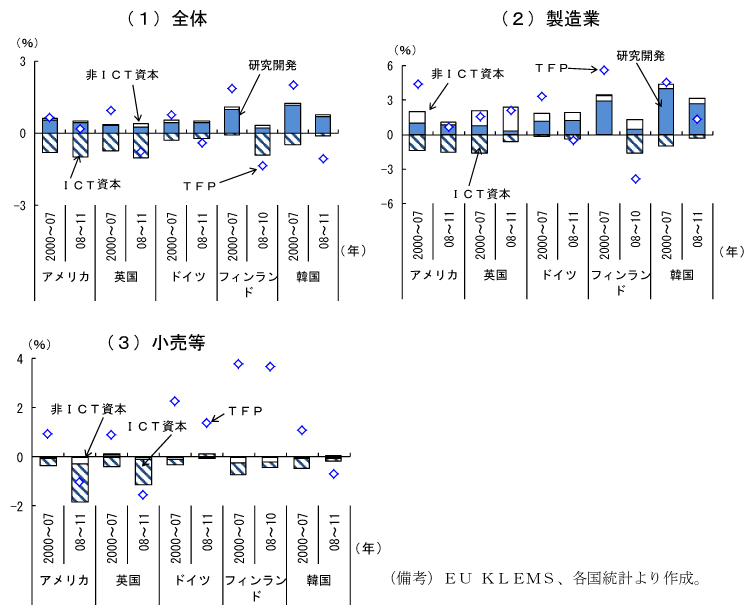
また、同じモデルを用いて産業別に分析したところ、製造業では研究開発費が有意にプラス、小売等ではICT資本財ビンテージが有意にマイナスとなることが分かった。したがって、製造業の研究開発費、小売等のICT資本財投資は各国とも総じて伸びが鈍化又は減少に転じており、それぞれがTFPの低下をもたらしていることがうかがえる。一方、情報通信、金融は、ICT資本財のビンテージ及び研究開発費に加え、各産業の非ICT資本財のビンテージについてはいずれも有意にならなかった。
以上から、世界金融危機後のTFPの伸びの低下については製造業を中心に研究開発費を通じた無形資産の構築や小売等におけるICT資本財のビンテージの上昇が影響している可能性があることが明らかとなった14。同時に、この分析からは研究開発等がTFPの伸びを一定程度説明するとしても、必ずしもそれだけで説明し尽せるものでは決してないことも分かる。TFPは次節で取り上げるような研究開発に限らず幅広いイノベーション活動による複合的な成果を表すと考えられ、上記の分析には限界があることに留意すべきである。
3.主要国の潜在成長率の推移と展望
本節の最後に、これまで経済成長を供給面からアプローチした結果を適用して主要国の今後の潜在成長率を試算してみよう。
供給面から中長期の経済成長率の試算を行った例としてOECD15の試算が挙げられる。これによると、15~17年及び18~30年までの中長期の成長率について、アメリカではそれぞれ年率2.1%、2.4%、英国では同1.6%、2.2%、ドイツでは同1.6%、1.2%、フィンランドでは同2.1%、2.3%、韓国では同3.4%、2.4%となっている。ただし、これには将来の労働人口の高齢化による影響は反映されているものの、TFPについては世界金融危機前の実績平均値が用いられているために、危機後の状況を踏まえると高めの成長予測となっていることが予想される。
そこで本節では、前項までみてきたようなTFPの低下の影響も含め主要国の成長率が、世界金融危機により屈折が生じていると仮定した場合、危機前のすう勢が続いた場合と比して、どの程度潜在成長率が落ち込むこととなるかみてみる。
前節までの分析から、主要国では世界金融危機後は労働・資本・TFPいずれの生産要素も潜在成長率を低下させる方向に作用していることが明らかとなった。これらの要素について、TFPについて危機後の状況が持続するなどの一定の仮定を置いて計算した場合16、アメリカの12~20年の潜在成長率は平均で年率1.5%、英国は年率0.9%、ドイツは年率1.1%、フィンランドは年率1.2%、韓国は年率3.0%となった。特に英国の潜在成長率の落ち込みが目立っており、TFPの伸びの鈍化が潜在成長率の大きな押下げ要因となっていることがうかがえる(第2-1-17図)。
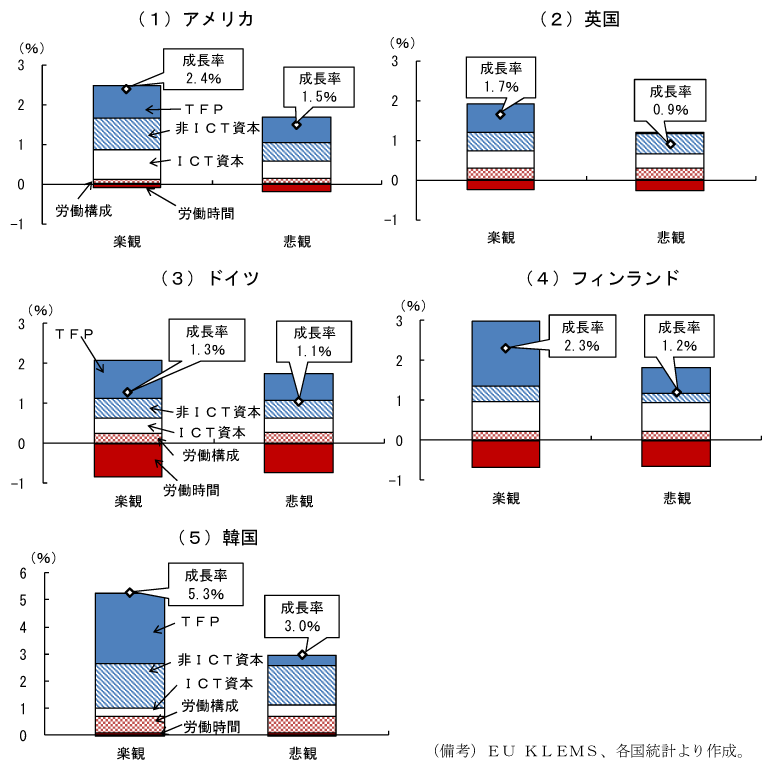
上記の推計はやや悲観的ともいえる仮定に基づくものであるが、TFPの伸びについて、世界金融危機後にみられた屈折の影響を取り除いた楽観的ともいえるケースでは17、潜在成長率の見通しは、アメリカは12~20年平均で年率2.4%、英国は年率1.7%、ドイツは年率1.3%、フィンランドは年率2.3%、韓国は年率5.3%と試算され、韓国を除き上述のOECD試算に近づく姿となる(前掲第2-1-17図)。
また、主要国の潜在成長率を産業別の寄与度に分解すると、危機前後の実績と同様、その他の非製造業が韓国を除いて大きな寄与を占めているものの、アメリカでは情報通信、英国では金融、ドイツ、フィンランド及び韓国では製造業の寄与が悲観的結果と楽観的結果の差をもたらしていることが分かる。このことは、今後の潜在成長率は各国の従来からの主力ともいえる産業の動向がやはり鍵を握るということを意味している(第2-1-18図)。
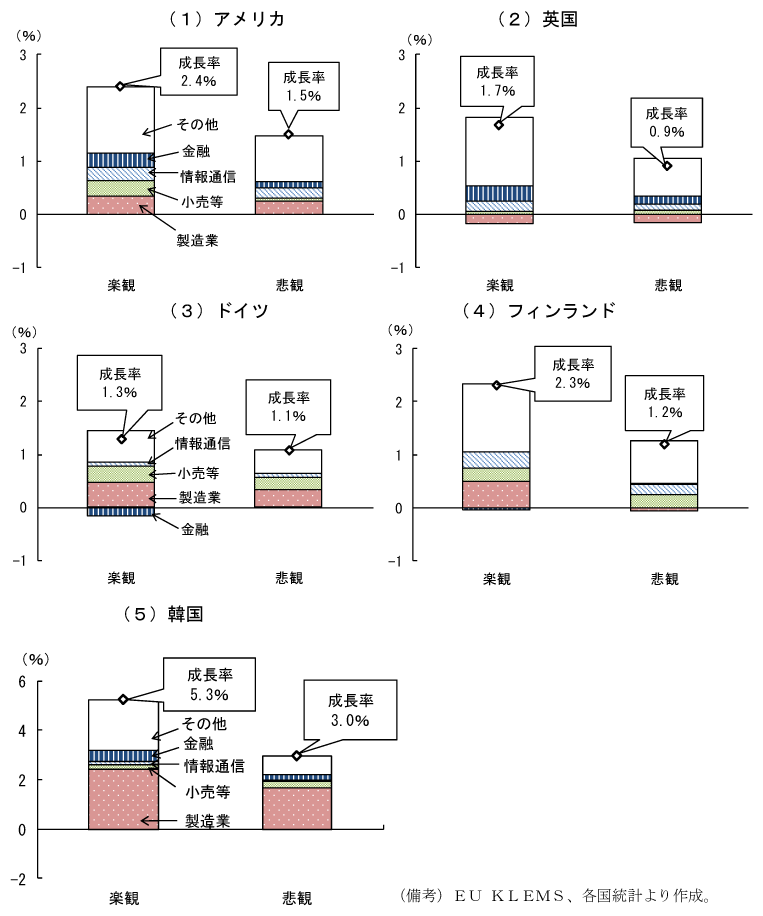
以上までの分析を通じて、世界金融危機後は、非ICT資本財はもとより2000年代の成長を支えてきたICT資本財も投資が低迷することにより資本ストックも伸び悩み、こうした傾向は資本投入の量的抑制とともに資本の質の劣化として小売等の非製造業のTFPの低下にも表れていることが分かった。そして、仮にこの傾向が続くとした場合、特にこれら産業を主力としている主要国において潜在成長率が更に低下する可能性があることも推察される。

