第3節 通貨制度に関するアジア地域の経験
1.アジアにおける通貨制度の選択とその評価
第1節では、欧州政府債務危機はユーロという共通通貨のもとで各国の経済的不均衡が拡大しそれが持続可能でなかったことが原因となっている点を確認した。アジア諸国でも、かつて固定的な通貨制度の採用により経済的不均衡が拡大しこれが持続可能でなくなった結果、変動相場制に移行せざるを得なくなったという経験をしている。
本節では、まず、1997年から98年のアジア通貨危機発生の背景と危機後の対応について、通貨危機で大きく被害を受け為替制度を変更したタイ、韓国、インドネシア及び危機後も固定相場制を維持した香港に焦点を当てて分析する。
また、その後のアジアにおける通貨協力の取組と目的を概観する。それらを通じて、アジア地域の経験とユーロ参加国が現在直面している問題と共通する点があるか明らかにする。
さらに、固定的な為替制度の影響に関しては、現在でもその制度が維持されている人民元についても、不均衡拡大等の影響の有無や今後の当該通貨をめぐる動きを併せて確認する。
(1)アジア通貨危機発生の背景
通貨危機を経験したタイ、インドネシア、韓国においては、主に2つの共通点が存在していたと考えられる。
一点目は、米ドルとの事実上のペッグ制(以下、ペッグ制)で固定的な為替制度が採られていたことである39。
二点目が、経常収支が赤字で、資本収支が黒字という状態が続いていたことである。
この背景として、経済発展の初期段階にあったこれらの国では投資意欲が旺盛であったため、国内だけで投資資金をまかなうことが困難であり、国外から積極的に資金を調達していたことが考えられる。ペッグ制によって為替変動リスクが低減されていたことや成長期待の高さが、これらの国への投資を加速させたが、後述のように、一部の国では住宅価格の高騰ももたらした。
こうした発展初期段階にある国が国外から資金調達すること自体は問題ではない。しかし、以下にみるように、これらの国では当時、主に国外から短期資金を借入れ、それを長期で国内に貸出していたため、突然の国外資金の引揚げに対して脆弱な構造であった。加えて、借入れた資金が必ずしも当該国の潜在成長力の向上に繋がっていなかった点も指摘される。
(i)米ドルとの事実上のペッグ制の採用
タイ、インドネシア、韓国及び香港では、国外資本を呼び込むことや、為替変動リスクを低減して貿易取引を拡大させる目的で、米ドルとの事実上のペッグ制を採用していた。これらの国は、ペッグ制を導入することにより、為替レートの安定化等のメリットを享受した。
また、ペッグ制の下、国外の投資家は為替変動リスクに晒されずに投資が可能となったため、これらの国への資本流入が加速することとなった。その結果、流動性需要が満たされやすくなり、それが国内の設備投資や民間消費の増加に寄与することで、高い経済成長がもたらされた。通貨危機を経験した上記各国において共通している点は、経済成長に対する総固定資本形成の寄与の高さである(第2-3-1図)。特にタイ及び韓国は、1990年からアジア通貨危機前年の96年まで実質経済成長率(前年比)が平均でそれぞれ8.6%、8.0%に対して、同時期の総固定資産形成の平均寄与度はそれぞれ4.8%、4.1%と、成長の半分以上を占める高い寄与となっている。しかし、通貨危機前後の96年から98年には各国とも実質経済成長率がマイナス成長に転じる中、総固定資本形成も大きなマイナスの寄与となっており、それまでの成長パターンが持続可能でなかったことがうかがわれる。
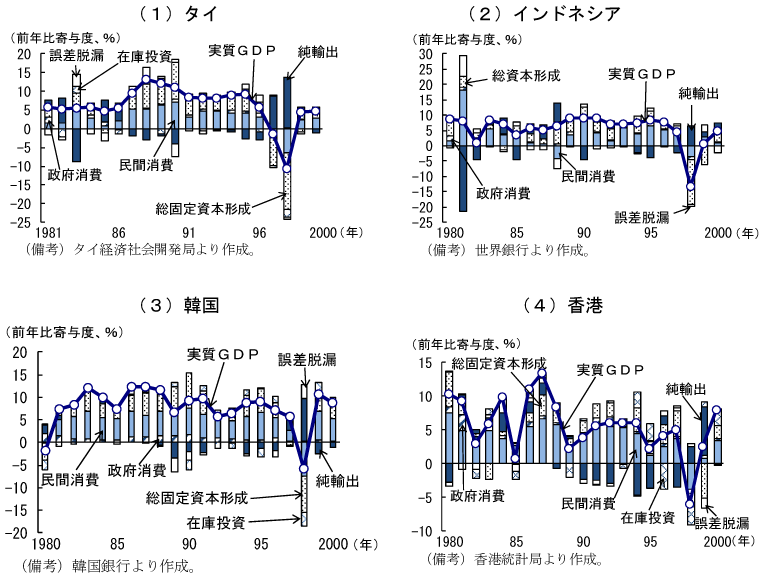
さらに、ペッグ制に加えて、そのほかの政策によって資本流入が後押しされた。例えば、タイやインドネシアでは、80年半ばに直接投資の流入規制が大幅に緩和され、韓国では90年代に資本流入規制が相次いで緩和されるなどの措置が採られ40、前述の為替変動リスクの低下と相まって、資本流入を加速させることになった。また、香港は資本流入規制がなかったため、元々資金が流入しやすい環境にあった。
加えて、これらの国では先進国と比べれば金利が高水準であったため、利ざやを稼ぐための資金が流入しやすい環境でもあったことになる(第2-3-2図)。
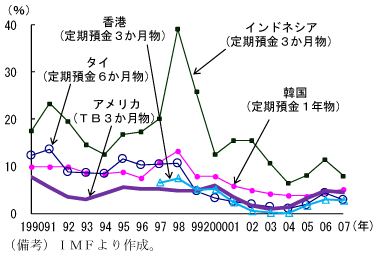
この動きを資本収支からみると、通貨危機経験国では97年の通貨危機前までにかけて、証券投資やその他投資(金融派生商品、貸付・借入等)の形で流入が大幅に拡大しており、前述の利ざやを稼ぐための資金が流入していたことが確認できる(第2-3-3図)。
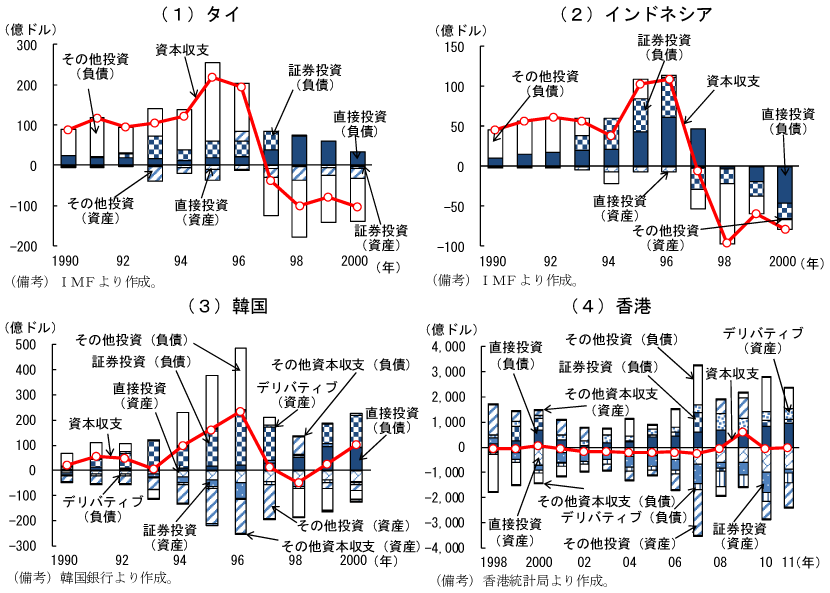
こうした資本流入の結果、各国では自国通貨がドルに対して増価しやすい環境がつくられていた(第2-3-4図)。その背景には、タイ等に投資する際、海外投資家がこれらの国の通貨で資金を調達する必要があったことが挙げられる。また、これらの国では海外からドル建てで資金を借入れて自国通貨建てで国内に貸出する動きもみられ、貸出の際には最終的には自国通貨が買い求められることとなり、それが増価圧力となった点も考えられる。一方、香港では1ドル=7.8香港ドルという固定相場が採られていたため、横ばいで推移している。
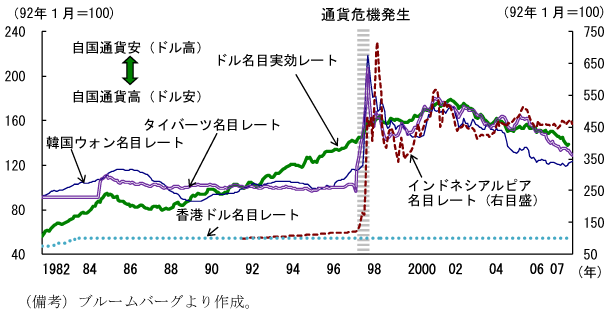
そのような状況のもと、各国通貨当局は、絶えず自国通貨に増価圧力がかかる中でペッグ制を維持するため、自国通貨売りの為替介入を行っていた。このため、各国の外貨準備高は積み上がった(第2-3-5図(1))。実体経済の規模とマネーサプライの関係を表わすマーシャルのkをみると、トレンドから大きくかけ離れて上昇はしていないことから、為替介入によって生じる流動性増加を吸収するために不胎化を行っていたとみられる。しかし、それにもかかわらず通貨危機前には各国とも総じて90年代前半までのマーシャルのkが大幅に上昇して推移しており、過剰流動性が発生していた可能性をうかがわせている(第2-3-5図(2))。
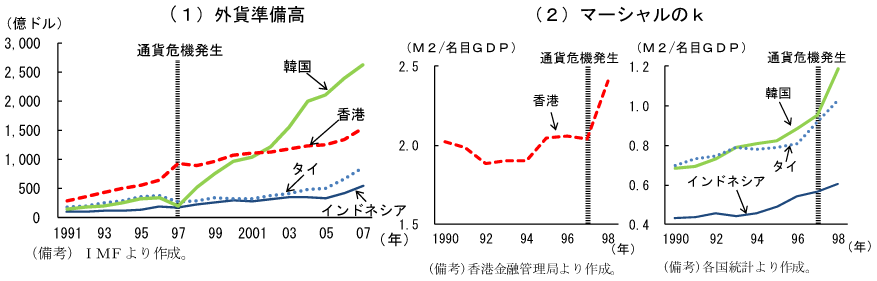
こうした過剰流動性による影響は、株価や物価の高騰、住宅市場の過熱等の形で現れたと考えられる。実際、株式市場においては、90年からアジア通貨危機前にかけて、タイやインドネシア、香港において株高の動きがみられる(第2-3-6図)。
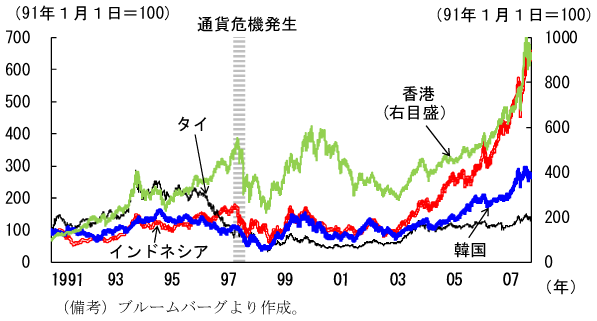
また、各国で投資が拡大する中、特にタイや香港では不動産価格の上昇もみられた(第2-3-7図(1)、第2-3-7図(2))。こうした状況は、第1節で指摘したように、ユーロ導入によって圏内の為替リスクが消滅したことなどで南欧諸国等に証券投資等比較的足の速い資金が大量に流れ込み、そうした資金が当該諸国の潜在成長率を高めるのではなく、住宅市場に流入して住宅価格高騰をもたらす一因となった状況と酷似している41。
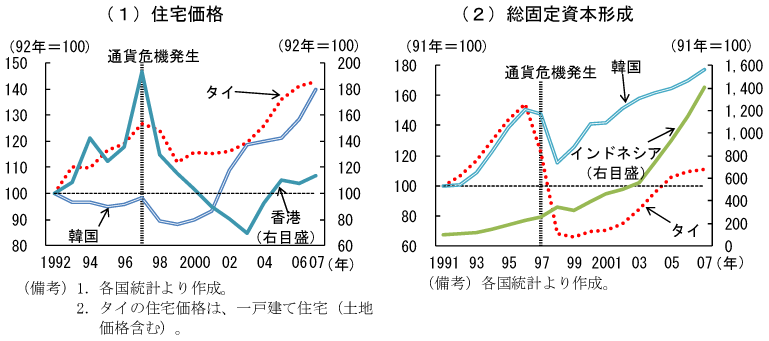
ドル・ペッグ制の弊害は、国外の短期資本に依存するという脆弱な経済構造だけではなく、金融政策の面でもみられた。前述のとおり、資本流入を拡大させるため、通貨危機経験国は名目金利が先進国と比べて高い水準となっていた。こうした中、タイでは通貨危機前の96年から既に景気の減速が始まっており、金融機関の破たん等により不動産などの資産価格も下落42していたが、中央銀行は緩和策を実施することができず、高い金利水準が維持されることになった。一般に、景気減速の際には、金融緩和策が講じられるが、それによって利回りが低下し、アメリカとの利回り差が縮小すれば、自国通貨が減価する要因となってドル・ペッグ制が維持できなくなる可能性があるからである。そのため、タイでは自国経済の状況を踏まえた裁量的な金融政策を実施できず、実体経済の悪化を抑制することができなかった。
前述のとおり、海外からの資本流入は経済発展の初期段階にある国が、経済発展のために海外から資本を導入すること自体は問題ではないが、アジア通貨危機が発生する97年まで、タイ等は海外から特に短期資金の借入れに依存していたことに問題があった。
こうした資本流入による為替増価に対抗するために自国通貨売り外貨買いの為替介入が繰り返された結果、外貨準備高は増加していた(前掲第2-3-5図(1))。しかし、短期資金の流入が急ピッチで進んだことから、通貨危機の発生する97年までにかけて、タイ、インドネシア及び韓国では対外短期債務残高が外貨準備高を大きく上回ることになった(第2-3-8図)。
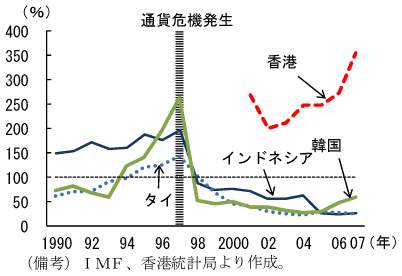
外貨準備が十分でないため、こうした状況下で資本が急速に国外へ引き揚げられれば、国外債権者への債務返済に必要なドル資金需要に対応できず、当該国の通貨危機につながることになる。本来であれば、国外からの借入に占める長期資金の割合を高めることや、大量の資本流入を未然に防ぐための規制を設けることなどが重要であったといえよう。
(ii)実質為替レートの増価による経常赤字の拡大
93年以降、短期資金の流入による経済の過熱により国内のインフレ圧力が強まったことに加え、ペッグ制の下でドル増価に伴う自国通貨高を容認せざるを得なかったことにより、価格面での輸出競争力は低下することになった。その結果、後述の生産性の低下と相まって、特にタイや韓国の経常収支は、貿易収支の赤字を主因として赤字傾向で推移していた(第2-3-9図)。
こうした状況は、共通通貨を導入したことで、自国通貨の減価を通じて輸出競争力を高めることが事実上不可能となった南欧諸国等とも同様であった(前述第1節参照)。
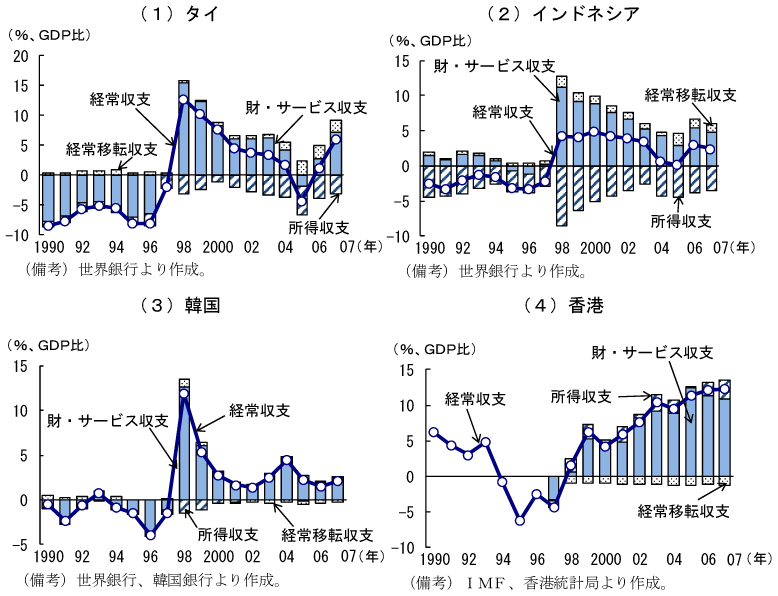
経済発展段階の初期において、経常収支赤字と資本収支黒字が続くことは不自然ではないが、流入した資本が経済のどの分野に配分されどう活用されるかが重要である。国外からの借入によって行われた投資が効率的に利用され、生産性の向上等に結び付けば、中長期的にその国の潜在成長率を高めることにつながると考えられる。その場合、輸出競争力の向上を通じ、経常収支赤字が常態化する状況から脱却出来ると考えられる。
しかし、90年以降のアジア諸国では、TFP (全要素生産性)が90年代を通じて伸び悩み、実質経済成長率に対してわずかな寄与にとどまっており、更に通貨危機後の98年にかけて大きく低下している(第2-3-10図)。通貨危機までのアジア諸国では、国外からの資金は特にタイや韓国において投資に向けられたものの、それが必ずしも技術革新(イノベーション)等とそれを通じた潜在成長率の向上に結び付かなかったことが示唆される。
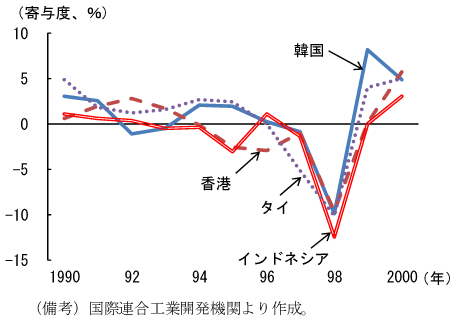
こうした中で、タイでは96年に建設投資等が急減し(前掲第2-3-7図)、景気は減速に転じた。そして、投資収益の悪化により資金繰りに窮した金融機関の破綻をきっかけに、国外資金が急激に引き揚げられることになった。前述のとおり、タイでは十分な外貨準備を持ち合わせていなかったほか、国内には長期で貸付を行っていたため 、このような急激な資金引揚げに対応できず、タイバーツは売りが進み、通貨危機に陥った。
タイバーツ売りの動きは、インドネシアルピーや韓国ウォンにも波及した。その背景には、これらの国々においても、経常収支赤字と短期の海外資金に依存するというタイと共通した構造問題を抱えていたことが考えられる。インドネシアや韓国でも短期債務は外貨準備を上回る規模となっており、突然の資金引揚げが生じると、返済が困難となるリスクを抱えていた。
こうした影響は香港にも波及し、香港も投機筋の売り圧力に直面することになった。しかし、香港通貨当局は大規模な為替介入を実施し、管理変動相場制への移行を回避した。
このような資本引揚げに対する対応については、通貨危機前のアジア諸国とユーロ圏とでは状況が異なる。世界金融危機やその後の欧州政府債務危機によって、南欧諸国等は急激な資本流出に直面し、それらの国の金融機関は資金調達難に陥った。しかし、ユーロ圏全体をカバーする欧州中央銀行(ECB)が積極的に利下げや無制限の流動性供給オペを行い、資金調達難に対応することが可能であった。共通通貨か否かの違いもあるが、通貨危機時のアジア諸国では通貨安定を図るための安全網や国内金融システムが十分に整備されていなかったことも、アジア通貨危機の背景にあったと考えられる。
(2)通貨危機後の制度変更と構造改革の進展
97年8月にタイがIMFに支援を要請したことを皮切りに、この動きはインドネシア(同年10月)、そして韓国にまで広がった(同年11~12月)。これら3国はIMFとの合意の下、財政再建に取組むこととなり、為替政策の変更と金融政策の枠組みの整備、インフレ目標の導入等を実施している43。
こうしたアジア各国の対応は、金融政策への透明性を担保し、市場の期待の安定化を図るという観点から評価できよう。
さらにアジア域内においては、後述のように、変動相場制に制度変更したことによって高まる通貨のボラティリティを抑えるために、金融監督機関の新設・機能強化といった、金融システムの強化策の実施や、地域協力の取組も進められている。また、通貨危機を経験した諸国では、危機発生の要因ともなった、常態化していた経常収支の赤字からの脱却や、対外短期債務残高の削減、着実な外貨準備の積み上げ等の改革が実施された44。
08年の世界金融危機発生に伴い、韓国やインドネシアで再び短期的資金の流出が起こるなど、為替制度の変更後も依然として問題は発生している。しかし、アジア通貨危機を契機とする構造改革、前述の外貨準備の積増し等の結果、資本流出による影響は通貨危機時と比べて限定的なものとなった。
このように、為替制度のその後の顛末は異なるものの、アジア各国が90年代の通貨危機以降取り組んだIMFの構造改革の要求内容45は、現在南欧諸国を中心とするユーロ諸国が取り組むべき課題と類似しており、通貨をめぐる危機の抜本的な解決には経済構造改革が不可欠であることが改めて確認できる。
なお、IMF支援の条件となるコンディショナリティについては、アジア通貨危機当時は前述の財政及び金融の構造改革に加え、貿易・資本・労働市場の幅広い改革を求める内容となっていた。このような条件付けは、必要以上に国内の反発を招くことで却って改革の妨げになっているという批判があったことなどを踏まえ、その後、IMFは目標達成に不可欠な分野のみについてコンディショナリティを課すこととしている。例えば、今般の欧州政府債務危機においても、銀行及び公的セクターの改革はコンディショナリティに位置づけられているが、財政赤字を一定期間は許容しているなど、その内容は、アジア通貨危機当時と比べるとマクロ経済状況を踏まえた柔軟な内容となっている46。
コラム2-5:韓国の構造改革とその後の動向
1.構造改革の実施
97年11月にIMFに緊急支援を要請した韓国(注1)では、その後IMFからのコンディショナリティ(支援条件)として、金融、企業部門を中心に構造改革を実施した(表1)。
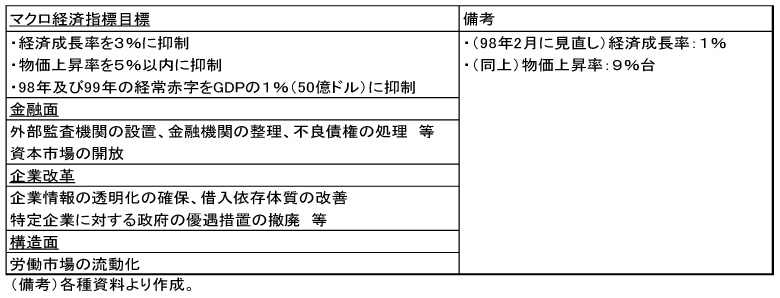
これら改革の実施は当然痛みを伴い、98年の実質経済成長率は前年比▲5.7%を記録するなど、経済は大きく減速した(注2)。しかし、その後は、ITブーム等に支えられ、輸出を中心に経済は回復し、99年の実質経済成長率は前年比10.7%増と高成長を記録するなど、文字通りV字回復を果たした(図2)(注3)。

その後も幾度かの循環的な成長鈍化はあったものの、07年まで年平均5%程度の成長を続ける中、通貨危機時に短期的な対外債務に比して脆弱だった外貨準備を着実に積み増したほか、対外短期債務の削減等を積極的に進めた。外貨準備高は、12年7~9月期で3,200億ドルを超える水準まで積み増されており(注4)、対外短期債務の外貨準備高に占める比率は、12年4~6月期で47%程度まで低下している(図3)。
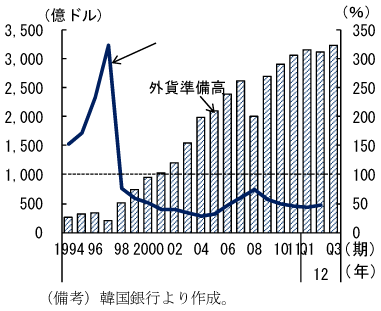
2.外的要因による金融市場の不安定化、実体経済への影響
構造改革の推進や外貨準備の積極的な積み増しを行う中、発生したのが08年の世界金融危機である。97年のアジア通貨危機時と比較すればその影響は限定的だったものの、世界金融危機により国際金融市場が不安定化し為替等金融市場に少なからず影響を与えた(図4)。
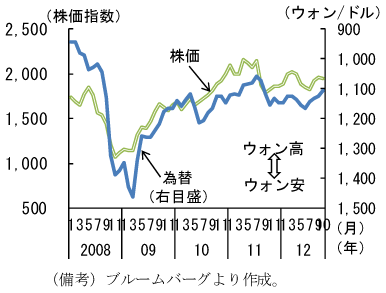
こうした外的要因に弱い理由の一つとして、92年以降、外国人による国内株式に対する投資等の資本移動規制の撤廃を進め、通貨危機後の98年までに完全自由化を行うなど、韓国は資本市場に関して完全に開かれた市場となっている(注5)ことが挙げられる。
加えて、自国通貨の流通度が低いという構造的な問題が挙げられる(図5)。世界の為替市場におけるウォンの取引量は10年で2%にも満たず、経済規模(名目GDP(実額))で4倍以上の差があるにもかかわらずシンガポールと同等の取引量となっており、韓国ウォンの為替市場における取引量の少なさが際立っている(図5)。
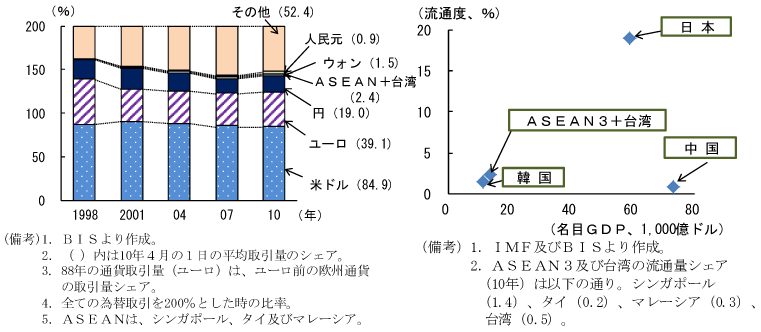
また、実体経済面においても、韓国の対外依存度は通貨危機以前から大きく上昇し、08年で45%を超えている。そのため、外的要因として、例えば金融危機の影響等により輸出先の経済が落ち込んだ場合、自国経済も影響を受けるリスクは年々上昇しているといえる(図6)。こうした構造を持つ中で、08年に世界金融危機等が起こった際、投資家がリスク回避のため、ウォン等の流通度の低い通貨が真っ先に売られ、結果として資本収支、為替動向に影響が及び、その影響が実体経済まで波及したといえる。
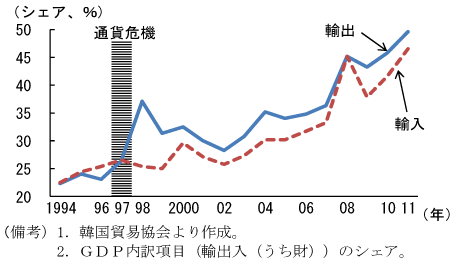
金融不安への対応としての外貨準備の積増しや対外債務の削減等の他の方策として、2国間での通貨スワップ協定の締結も考えられる。
実際、08年の世界金融危機時に資本流出の動きが止まったのは同年10月のアメリカとのスワップ協定を締結したことも要因の一つとしていわれている(その後、10年2月にはアメリカとの協定は終了)(図7)。アメリカとのスワップ協定の延長がかなわない中、その後日本との間でスワップ協定の拡充を行ったものの、今年10月までに満期を迎え、11月以降は拡充前の130億ドル相当まで戻っている。
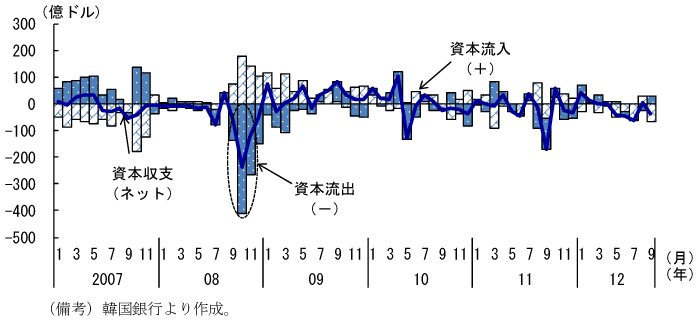
前述のように構造的問題が存在する中、韓国経済は中国の景気鈍化やヨーロッパを始めとした世界経済の減速により足踏み状態が続いている。今後、欧州債務危機が深刻化した場合、同国の金融為替市場や実体経済への影響は必至であり、経済が一層下振れする可能性は高く、今後も動向を注視していく必要がある。
(注1)韓国政府の要請を受け、12月にIMFが210億ドルの融資を決定した以外にも、日本、アメリカがそれぞれ100億ドル、50億ドル融資を行うなど、総計570億ドルの融資パッケージを行った。
(注2)こうしたことから、IMFが通貨危機国に対して要求した高金利政策下での金融機関の整理、統廃合等の構造改革は、景気後退をより深いものにしたという指摘もある。
(注3)IMFからの融資は、01年8月までに完済した。
(注4)外貨準備の積み増しには、為替を安定させるための自国通貨売りによる為替介入も一定程度積み増しに寄与していると考えられる。政府は為替介入の有無については基本的に非公表としているものの、アメリカが12年上半期の為替報告書で「11年9月に韓国が為替介入したと思われる」と韓国に対して為替介入を控えるよう指摘したとの報道がされている。
(注5)金融危機後、資本規制に関する見直しが行われ、10年6月に先物為替ポジション限度の設定、外国為替健全性負担金の導入が行われた。
(3)人民元の動向
(i)アジア通貨危機と人民元
アジア通貨危機時、中国は管理変動相場制を採用47していた。しかし、その後の中国経済の動きはかつての他のアジアの固定的通貨制採用国とは大きく異なっている。当時、人民元の変動範囲は前日比48
±0.3%以内と厳しく規制していたため、人民元の急落は起こらなかった。
アジア通貨危機の際に、他のアジアの国のように投機的な売り圧力を受けずに済んだ背景として、「外国為替管理条例49」によって、国際的な短期資金の移動を厳しく規制していたために、地場銀行が短期資金の対外借入れに多くの制約を課されていたことが挙げられる。そのため、前述の他のアジア諸国のように対外短期債務残高が外貨準備を大きく上回ることがなかった(第2-3-11図)。
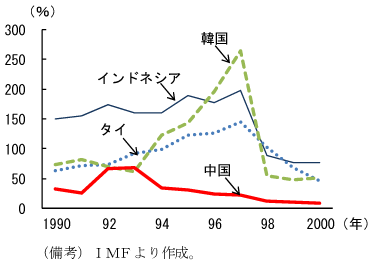
アジア通貨危機を契機に、変動幅は前日比±0.1%に更に狭められ、1ドル=8.28元に固定された実質的なドル・ペッグ制となった。このように固定的な為替レートの下、貿易や投資の際の為替リスクが軽減されることは、輸出等の拡大の後押しとなり、経済成長に結び付くという利点があった。
(ii)為替制度の歪み
01年12月のWTO加盟等を受け、先進国向けを中心に中国の輸出が増加し、経常収支黒字額が拡大する中、世界最大の経常収支赤字国であるアメリカを始めとする先進国各国が03年頃より人民元への切上げ要求を頻繁に行うようになった。
こうした中、市場では人民元相場の切上げを見越した投機資金の流入50により、人民元への増価圧力が強まることになった。中国人民銀行は人民元売りドル買いの為替介入を繰り返してこうした圧力を和らげようとし、その結果、外貨準備は大幅に積み上がった(第2-3-12図)。しかし、その多くがドル建てで運用されているといわれており、人民元がドルに対して大幅に切り上がれば、外貨準備高が目減りするというリスクも抱えている。
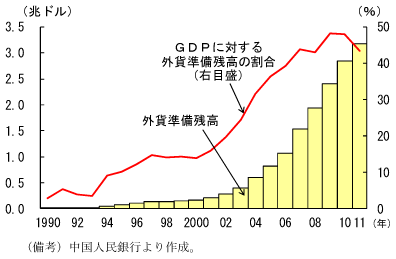
中国では人民元売り介入によって大量の人民元が市場に供給されるのを避けるため、為替介入の影響は不胎化によって吸収されていると考えられる。しかし、実体経済の拡大以上にマネーサプライの増加が続いている。このマネーサプライの増加が具体的にどういった経済主体によってもたらされているかを特定することは難しいが、海外からの資金の流入も影響した可能性がある。マーシャルのkから、この点について確認すると、アジア通貨危機後も02年にかけては金融緩和が行われた結果として、上昇基調が続いている。その後は世界金融危機が発生した08年に低下したが、同年11月の貸出総量規制撤廃を受け、09年以降の銀行貸出の急増に伴いマネーサプライも増加51し、それ以降も再び上昇している(第2-3-13図、第2-3-14図)。このように、マーシャルのkの動きには金融政策そのものの影響もあることには注意が必要だが、固定的為替制度の維持が過剰流動性を生みやすい環境を醸成している可能性がある。
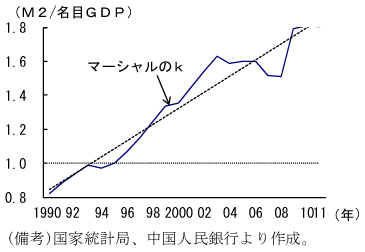
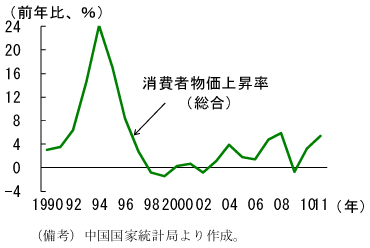
05年には、人民元の対ドルレートは1ドル=8.28元から1ドル=8.11元に切り上げられ、同時に為替制度はそれまでの事実上ドルにペッグした管理変動相場制から、前日比±0.3%までの変動が認められ、通貨バスケットを参考とした管理変動相場制へと移行された。その後07年には更に変動幅が±0.3%から±0.5%に拡大され、より弾力的な為替相場政策が採用されている。08年7月には世界経済の悪化を背景に一時的に1ドル=6.83元前後に固定するドル・ペッグ制が事実上復活した時期もあったが、10年6月には為替レートの柔軟化が発表52され、人民元は再び増価した。12年には変動幅を前日比±1.0%に拡大するなど、少しずつではあるが柔軟性を高める動きもみられるようになった。
本来、人民元の切上げは経常収支の不均衡を是正すると共に、為替介入によるマネーサプライの増加圧力や切上げ期待によって流入する短期資金の流れを抑制することにもなり、インフレリスクを軽減する効果が期待される。
もっとも03年から07年にかけて国内の物価上昇率が高まっていたことから、名目では固定的な人民元も実質レートでみればドルに対して増価が続いており、中国の価格面での輸出競争力が一定に維持されていたわけではない点には留意が必要である(第2-3-15図)。
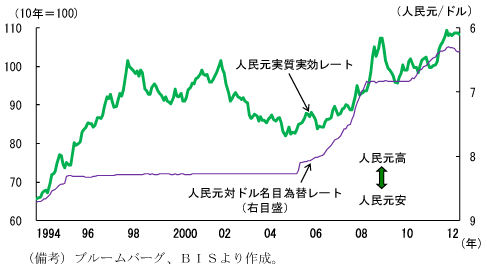
(iii)資本取引の流れ
資本取引の状況をみると、中国は外国からの受け入れる投資のうち直接投資のウェイトが高いことが大きな特徴となっている。これは、最終製品の組立て先として、外国企業が中国へ生産拠点をシフトしていることなどを反映しており、海外からの証券投資が資本流入の主因であった他のアジア通貨危機経験国とは様相が異なっている。また、資本流出に対する規制が厳しいため、外国への投資が抑えられていることも特徴的である(第2-3-16図(1)、第2-3-16(2))。
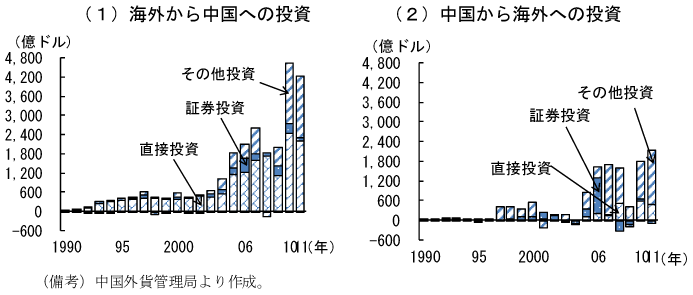
前述したとおり、中国の為替制度は徐々に柔軟化されてはいるものの、厳しい資本規制が存在し、外国為替市場参加者は限られている。この結果、中国の資本収支は直接投資を中心に黒字幅が拡大している(第2-3-17図)。
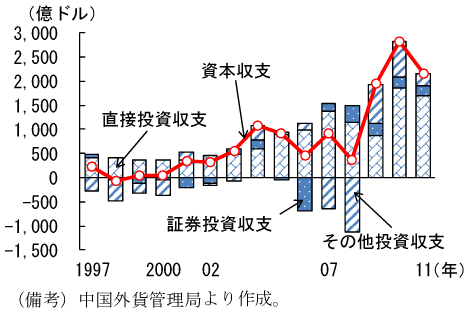
(iv)貿易黒字の拡大
中国の経常収支は、財・サービス収支の黒字によって、資本収支と同様に黒字が続いている。90年には約120億ドルであった経常収支黒字は08年には約4,200億ドルまで拡大し、その後は縮小したとはいえ、11年には約2,000億ドルと、経常収支の面でも大きな対外不均衡の状態が続いていることが分かる(第2-3-18図)。中国の経済のプレゼンスが世界的に高まる中で、いつ、どの程度までこうした不均衡状態が対外・対内的に持続可能なのかますます問われることになると思われる。
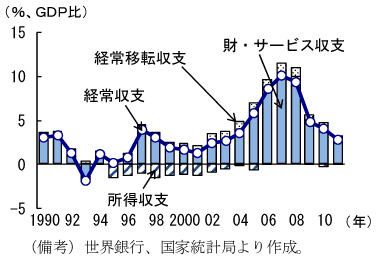
こうした中国をめぐる対外経済環境の下で、09年7月から香港との間で人民元建て貿易決済のテストがスタートし、貿易決済における人民元の活用を段階的に進められるなど、「人民元の国際化」に向けた動きもみられるようになった(第2-3-19表)。中国政府はその後も人民元建て貿易決済に関する規制を緩和しており、その結果、人民元建ての貿易決済額は増加傾向となっている(第2-3-20図)。
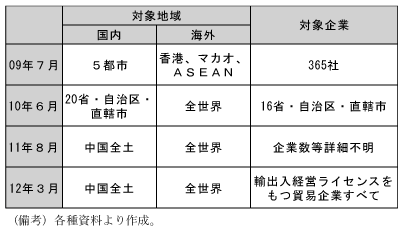
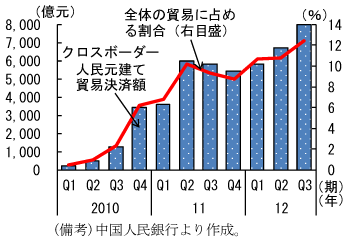
(v)人民元の国際化
前述のように、中国の資本・貿易取引は拡大を続けており、経済規模では既に世界第二位の経済大国にまで成長している。こうした中で、人民元の国際化を図る背景には、中国企業が第三国の為替変動リスクを負うのは望ましくなく、人民元決済の拡大を通じて為替リスクや両替コストを減らそうという中国政府の意向もあると考えらえる。
12年1月の全国金融工作会議でも、香港オフショア人民元市場の整備やオフショア人民元による中国本土での運用等に注力することなどの「人民元の国際化」に関する目標が確認された。
クロスボーダー取引で人民元を使用することは、中国企業にとってはメリットがある。しかし、海外企業にとっては新たな通貨への切替えコストが生じる他、人民元オフショア市場の規模が小さいことから、香港以外の海外企業にとって人民元建融資を獲得するには障害があるのが現状である。そのため、人民元建貿易決済額をみると90%程度が中国の輸入53となっており、輸出に関しては依然7%程度と限られた利用にとどまっている。
一方で、オフショア市場の拡大により、海外企業にとっては人民元融資を獲得する可能性が広がることになる。これは、海外企業による人民元決済の拡大にもつながり、結果的に人民元の国際化に貢献すると考えられる。オフショア市場拡大の動きは進んでおり、04年には香港で人民元建預金が解禁され、10年から預金残高が急増している(第2-3-21図)。この背景には、人民元高観測の中、人民元保有への需要が高まっていることが考えられる。
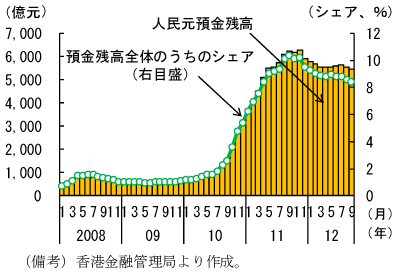
また、07年には人民銀行の認可の下、中国の銀行が香港で人民元建債券を発行することが許可された。09年には中国政府が香港で人民元建国債を発行し、10年には非居住者が香港で人民元建債券を発行し、その額は増加している(第2-3-22図)。
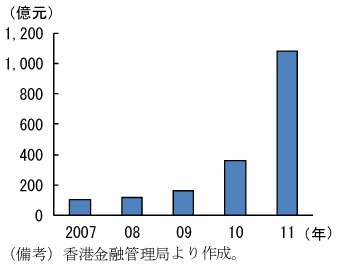
こうした動きは今後も続くとみられ、オフショア市場は拡大していくことが見込まれる。ただし、それだけで直ちに人民元の国際化が達成されるわけではなく、将来、人民元が世界の基軸的な通貨となるまで成長するには、外貨準備高として各国で運用されるような流動性の高い国債市場を整備することなどが必要である。現在のオフショア市場拡大の動きがこうした契機となるかどうか注目される。
このように、人民元はユーロ等と違って、資本取引に対する規制の下に置かれている。そうした中、南欧諸国と類似した動きとして、インフレ基調の中で実質為替レートが増価していたことが挙げられる。もっとも、それにもかかわらず価格競争力を維持して輸出を増大させ、経常収支黒字を拡大させている点は大きく異なっている。
コラム2-6:香港の為替制度
香港は、1983年よりアメリカドルにペッグした(1ドル=7.8香港ドル)カレンシーボード制を採用し(注1)、05年からは1ドル=7.75~7.85香港ドルに変更した(図1)。カレンシーボード制は、固定相場制と同様、自国通貨を特定の外貨に固定されたレートで連動させる制度である。ただし、基本的には自国通貨の発行額と同額の外貨準備を保有し、自国通貨を外貨との交換が保証されている点が異なる。十分な外貨準備を保有しているため、突然の投機売りといった事態にも円滑に対処することが可能となる。しかし、後述するとおり、中央銀行が裁量的な金融政策を行う余地はほぼ失われる。
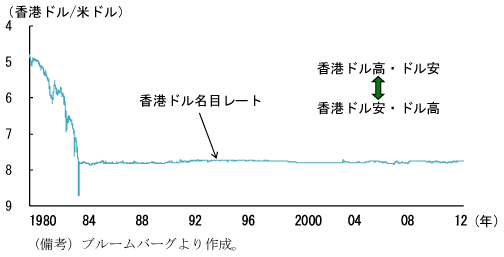
97年のアジア通貨危機時は、金融市場が混乱する中、香港ドルも投機売りに直面することになった。しかし、98年には大規模な市場介入が実施されて投機売りに対応すると共に、短期金利上昇を抑制するなどの為替制度改革も実施された。その結果、カレンシーボード制は維持されており、IMF(2007)も香港の同制度を支持すると述べている。
一方、ドルにペッグする香港のカレンシーボード制の下では、固定レートを維持するため、アメリカに追従した金融政策が必要となる。なぜならば、アメリカが政策金利を引上げた時に香港が金利を据え置いたままであれば、両国の金利差が拡大し、香港ドルが減価する要因となって、固定レートの維持が難しくなるからである。
83年にカレンシーボード制が導入された時には、アメリカ向け輸出は中国向けを上回り、最大の輸出先であった(図2)。しかし、01年頃以降はアメリカ向けの割合が大幅に低下し、輸出入の両面で中国のプレゼンスが高まっている。また、アメリカと香港の実質経済成長率を比べても、2000年以降は香港がアメリカを大きく上回る状況が続いており、制度導入当時の前提が満たされているか不透明な部分もある(図3)。
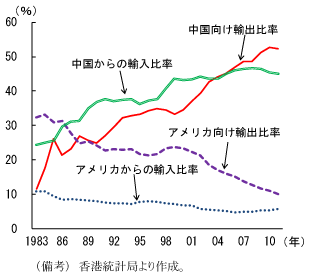
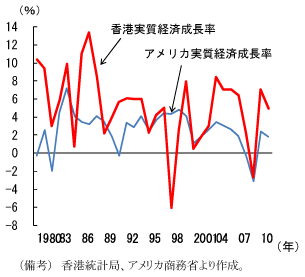
実際、香港とアメリカの政策金利を比べると、2000年以降は連動して推移している(図4)。しかし、その弊害として、2000年から04年の間、香港がデフレ状態に陥った時も、大胆な利下げを行うことができなかった。一方、10年からは物価上昇が続くものの、アメリカが金融緩和策を実施しているため、香港の政策金利も08年12月以降は0.5%という歴史的低水準に据え置かれたままとなっている。そのため、過剰流動性が生じ、一部の資産価格の上昇に結び付いた可能性も指摘されている。住宅価格をみると、03年の底から12年にかけて3倍近く上昇したほか、住宅価格の対可処分所得比も同時期に60%ポイント程度高まっている(図5)。
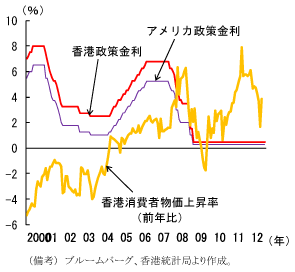
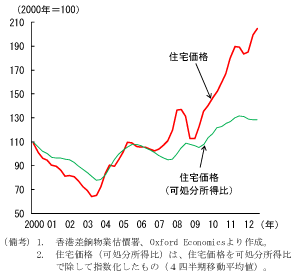
こうした中、カレンシーボード制に代わる新たな制度を導入する考えも現れるようになった。しかし、香港政府は現制度を継続する意向を示しているほか、IMF(2011)も慎重な意見(注2)を述べており、当面はカレンシーボード制が維持されることが考えられる。今後もこうした議論は続くとみられるため、その動向を注視していく必要がある。
(注1)香港は35年よりポンドにペッグしたカレンシーボード制を導入、72年より米ドル固定相場制を採用し、ブレトンウッズ体制崩壊によって先進国が変動相場制となる中、74年より変動相場制を導入していた。その後、82年に始まった英中間の香港返還交渉において両国の対立が明らかとなる中で、香港ドルに対する信認が低下し、相場が急落したことを受け、83年に現在の制度を用いている。
(注2)IMF(2011)は、何らかの通貨にペッグすることは香港の金融政策の裁量性を高めることはなく、低金利が続くだけと指摘している。変動相場制に関しては、金融政策の独立性の範囲が広がるものの、香港のような小国開放経済には適さず、国際金融センターとしての地位からも香港ドルが大規模・急激な資本流出入に晒されるリスクに言及している。段階的に平価を切り上げる案については、やはり金融政策の裁量性を高めることにはつながらない他、現在の実質為替レート水準がファンダメンタルから大きくかい離しているとの証拠がない点を踏まえれば正当化されないと述べている。
2.アジアにおける通貨協力の取組
(1)通貨危機後の為替レート変動
通貨危機前後でアジア通貨のボラティリティがどのように変化しているかをみるため、各国の名目実効為替レート(月次変化率)の変動について、アジア通貨危機の影響を受ける前(90年~97年4月)、アジア通貨危機発生からチェンマイ・イニシアチブ合意まで(97年5月~2000年4月)及び合意後(2000年5月~07年)の三つの期間に分けて比較する。
まず、対象期間の各国通貨の前月比の最大値と最小値をみると、事実上のドル・ペッグ制を採用していた90年~97年4月の前月比変化率は固定相場制だったことから低く、香港を除く各国で危機発生からチェンマイ・イニシアチブ合意までの期間の変化率は高まり、通貨の変動が上下幅共に拡大していたのが確認できる。しかし、チェンマイ・イニシアチブ合意後は総じて変動幅は縮小しており、安定している。香港では、依然ペッグ制を維持しているため、変動はしているものの、その変動幅は従前から狭いものとなっている(第2-3-23図)。
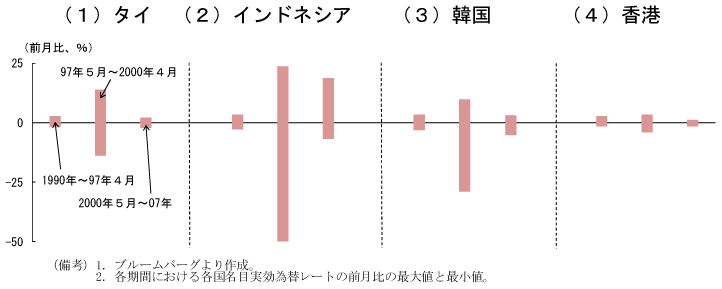
次に、各期間の尖度をみると、通貨危機後、韓国、タイ及び香港ではボラティリティが上昇しているが、チェンマイ・イニシアチブ合意後は低下しており、やはり為替相場が安定化に向かっていることがみられる。一方、インドネシアでは、尖度が引き続き上昇していることからボラティリティが拡大しており、依然不安定な状態が確認できる(第2-3-24図)。
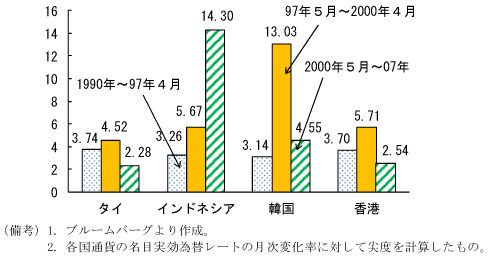
(2)アジア通貨をめぐる国際的な協力体制
タイ、インドネシア及び韓国では変動相場制を維持しつつ、短期的なボラティリティに対して通貨価値の安定を確保する必要性が高まったため、以下のような国際的な協力体制が検討・構築されている。
(i)アジア通貨基金(AMF)構想
通貨危機を境として、アジア域内での金融協力が進展している中、その最初の構想となったのが、アジア通貨基金構想(AMF)である。97年9月のアジア欧州会合(ASEM)蔵相会合や7ヵ国蔵相・中央銀行総裁会議、世界銀行・IMF年次総会等で、設立構想が提唱された。
本構想はタイが提唱し、特定のアジア通貨が不安定化することを防ぐため、地域における監視の強化や加盟国が危機に陥った場合に為替市場への介入、外貨支援の実施を目的とし、IMFによる救済を側面から支援するものとして位置付けられていた。
しかしこの構想は、日本が設立に向けて積極的に各方面にはたらきかけたものの、IMF、アメリカや中国等と、日本を中心としたアジア諸国の間で調整が終了しなかった。
その後、11月にフィリピンで財務大臣代理会合が開催され、IMFを補完する融資支援の枠組みを決めるにとどまり(マニラ合意)、基金の設立自体は今後の課題とされた。
(ii)チェンマイ・イニシアチブ(2国間協力から多国間協力へ)
現在、アジア域内における通貨協力の中心的位置をなすのが、チェンマイ・イニシアチブである。
この枠組みは、99年11月のASEAN+3首脳会議の「東アジアにおける自助・支援メカニズム強化」の必要性の合意を受け議論が開始され、タイのチェンマイで開催された2000年5月の第2回ASEAN+3財務大臣会議において合意されたものである。
具体的には、加盟国の外貨準備を使って短期的な外貨資金の融通を行うもので、短期流動性問題への対処、既存の国際的枠組みの補完を目的としている。
10年3月には、通貨スワップ発動のための当局間の意思決定の手続きを共通化し、支援の迅速化・円滑化を図るため、発動時に多国間の外貨準備の融通が可能な仕組みとなるマルチ化契約が発効された。
欧州債務危機再燃による国際金融資本市場の不安定化の動きが続く中、12年5月、第15回財務大臣・中央銀行総裁会議が開催された。
会議において、チェンマイ・イニシアチブの資金拠出の拡大(1,200億ドルから2,400億ドル)等が決定するなど、地域間協力の枠組みの役割は、拡大、深化している。
本枠組みの資金拠出割合は、日本及び中国が全体の約3分の2を占めるなど、日本、中国の両国が本枠組みにおける中心的な役割を果たしている54(第2-3-25図)。
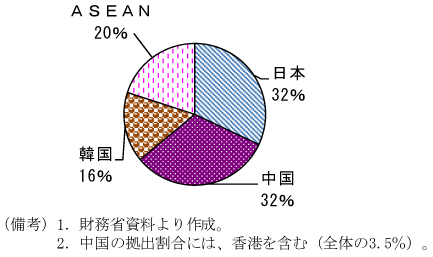
(3)アジアにおける通貨統合の議論
97年の通貨危機後、アジアでは、域内の通貨協力の枠組みが構築されてきたが、同時に、共通通貨の創設や更に通貨統合まで議論されるようになっている。これは、99年のヨーロッパにおける通貨統合の実現に大きく影響されていると考えられ、ユーロ導入にいたる経緯や背景と比較され、実現性が議論されることが多い。
アジア地域55においては、国際分業体制及び貿易ネットワークが構築され、域内FTA(自由貿易協定)の締結により、各国の貿易の域内依存度が高まっており、域内通貨間の為替相場の安定化の重要性が高まっている56
。
ただし、最適通貨圏理論(第2章第1節コラム参照)にかんがみると、アジアはユーロ導入前のヨーロッパ以上に経済の発展段階の相違が大きく、域内において最適通貨理論の諸条件が満たされているとはいい難く、近い将来における通貨統合は困難であると考えられる。現実的なのは、地域通貨単位であるACU(Asian Currency Unit)57の創設である。
06年5月の第9回ASEAN+3財務大臣会議の共同声明においては、通貨統合を視野に入れた地域通貨単位の活用と、その構築手順に関する研究が盛り込まれている。また、ADBでは、地域通貨単位として、東アジア各国の通貨の加重平均値として算出されるACUの使用が検討されている。ACUは、各国通貨をGDPや貿易量でウェイト付けして、バスケット方式で合成された計算上の共通通貨である58。
ACUを創設するメリットは幾つか考えられる。まず、各国通貨とACUとのかい離幅を監視することで、危機につながるような異常な通貨の動きを把握する目安になる。また、ACU建ての資金の調達・運用が可能になれば、為替リスク低減効果がある一方、高金利国において低金利での資金調達、低金利国において高金利での資金運用が可能となる。さらに、決済通貨として取引可能になれば、アジア域内での為替取引コストを最小限に抑えられ、アジア域内に展開している企業が、各拠点で発生した資金需要・供給を効率的に融通しあうことが可能になる。
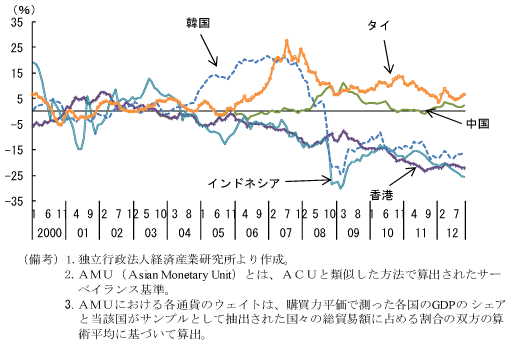
その一方で、ヨーロッパにおけるECUの実績をみると、現金通貨をもたないために商取引に限界があったことや決済コストや時間の問題等の欠陥が挙げられている。
ヨーロッパにおける共通通貨単位としてのECUは、あくまで通貨統合を見据えた一過程という意義が大きかった。アジアにおいて共通通貨単位を導入する場合も、域内諸国がどのような政策目標を共有していくかが重要である。

