第1章 マクロ経済の動向(第2節)
第2節 物価・賃金の動向とデフレ脱却に向けた現在地
本節では、2024年における物価動向を様々な指標から振り返るとともに、デフレ脱却に向けた現状を確認する。1990年代のバブル崩壊以降、企業は短期的な収益確保のため、賃金や成長の源泉である投資を抑制し、結果として、消費の停滞や物価の低迷、さらには経済成長の抑制がもたらされ、我が国経済は、「低物価・低賃金・低成長」という悪循環に陥っていた。こうした悪循環の中で、家計にはデフレマインド、企業にはコストカットの縮み志向が染みついてきた。第1節でみたように、日本経済にはこれまでにない前向きな動きがみられており、こうしたデフレやコストカット型経済に後戻りしないか、長年のデフレマインドを払拭し、「賃上げと投資が牽引する成長型経済」に移行できるかどうかの分岐点にある。
デフレからの脱却の判断について、政府は、内閣府が2006年3月に参議院予算委員会に提出した「デフレ脱却の定義と判断」において、「物価が持続的に下落する状況」を「デフレ」と定義し、また、「物価が持続的に下落する状況を脱し、再びそうした状況に戻る見込みがないこと」を「デフレ脱却」と定義している1。足下の物価動向をみると、消費者物価は上昇を続けており、この意味で、我が国は明らかにデフレの状況にはないが、「物価が持続的に下落する状況に戻る見込みがない」かどうかについては、物価の基調や背景を総合的に判断し、確認する必要がある。上記の「デフレ脱却の定義と判断」においては、物価の基調として、消費者物価やGDPデフレーター等に言及され、物価の背景については、例示として、マクロ的な物価変動要因である需給ギャップ(GDPギャップ)や単位労働費用が挙げられていることから、これらの4つの指標が全てプラスになったか否かのみに注目が集まることがある。しかしながら、過去、アベノミクス期においても、2015年1-3月期や、2018年1-3月期~4-6月期、2019年1-3月期~7-9月期と、これらの指標が全てプラスになったことはあるが2、いずれも1年以上継続することはなく、また、その後、消費者物価上昇率がマイナス圏に戻ることとなった。こうした点も踏まえ、政府においては、デフレに後戻りしないかを判断するに当たって、消費者物価やGDPデフレーター等の物価の基調とともに、物価の背景として、GDPギャップや単位労働費用といったマクロ的な物価変動要因のみならず、企業の賃金設定行動が変化し、賃金上昇が持続的なものとなっているか、原材料や人件費など企業の価格転嫁は進んでいるか、特定の限られた品目のみではなくサービスを含め幅広い品目で物価上昇の広がりがみられるか、家計や企業等の予想物価上昇率は安定しているか、といった経済主体の行動や認識の変化に係るミクロ的観点を含め、様々な指標やデータを総合的に考慮し、慎重に判断することとしている。以下では、こうした物価の基調や背景を丁寧に検証し、デフレ脱却に向けた現在地を確認する。
1 2024年における物価動向
(輸入物価は契約通貨ベースでは横ばいの一方、円ベースは円安進行の影響が大きい)
まず、国際商品市況の動向について確認する。原油や銅、小麦といった各種国際商品価格は、ドルベースでは、中東情勢や世界経済の先行きに関する市場の期待、天候要因等によって変動したものの、2024年中としては、おおむね横ばい圏内で推移した(第1-2-1図(1))。こうしたこともあり、我が国の輸入物価指数は、契約通貨ベースでは、2024年末にかけて横ばい傾向で推移してきた(第1-2-1図(2))。
他方、円ベースの輸入物価指数をみると、2023年に続き、2024年においても、為替レートの変動の影響を大きく受けた。2024年7月にかけては、対米ドル名目為替レートが1ドル160円程度まで、急速に円安ドル高が進み、輸入物価もこれを反映して上昇傾向が続いた。その後、2024年8月初めには、7月31日の日本銀行による政策金利の引上げや、米国における経済統計が市場予想を下回ったこと等から円安是正が進み、輸入物価指数も一旦下落した。その後、2024年10月以降は、内外金利差の高止まりが意識される中で、為替レートが再び円安ドル高方向で推移した結果、円ベースの輸入物価も下げ止まり、横ばい圏内の動きとなっている。先行きについても、ドルベースの国際商品価格が安定的に推移していくことを前提とすると、為替レートの動向によって、円ベースの輸入物価が変動しやすい状況が続くと考えられる。

(企業物価は、財・サービスともに緩やかな上昇が続く)
次に、国内物価について、企業間(BtoB)の財取引価格を示す国内企業物価指数をみると、2023年から2024年初にかけておおむね横ばい傾向で推移した後、2024年春以降は、電気・ガス代に係る補助措置の変更等の影響を受けながら、総じて緩やかな上昇傾向が続いた(第1-2-2図(1)、(2))。こうした背景には、主に、①既往の円安の進行を通じた円ベースの輸入物価の上昇がラグを伴いながら国内の財物価に波及してきていることに加え、②国内企業物価指数の約2%を占める米3が、2024年夏における需給のひっ迫4や、令和6年産米価格における生産コストの上昇の反映等により、前年比1.6倍程度まで上昇したこと等がある。
また、企業間(BtoB)のサービス取引価格を示す企業向けサービス価格指数は、2023年に続いて、2024年も総じてみれば緩やかな上昇傾向で推移した(第1-2-2図(3)、(4))。BtoBのサービス価格は、幅広い品目で上昇しているが、特に、後述するように、運輸・郵便や諸サービス等の人件費比率の高い品目を中心に伸び率が拡大しており、賃金の販売価格への転嫁が着実に進展していることを示している。

(消費者物価はおおむね2%台の伸びが続いたが、直近では食料品の上昇幅が拡大)
次に、企業対消費者(BtoC)の物価である消費者物価指数については、全ての財・サービスを含む総合の前年比でみて、2023年11月以降、約1年にわたり、おおむね2%台が継続した後、2024年12月は生鮮食品の価格上昇が加速したこと等により前年比3.6%に高まった(第1-2-3図(1))。このうち、エネルギーについては、政府によるガソリン・灯油等に係る激変緩和措置5が価格水準を抑制しているほか、電気・ガス代については、2024年半ばにかけての激変緩和措置の終了や、その後の酷暑乗り切り緊急支援の実施と縮小6によって、大きく影響を受けている。こうした政策要因を除いてみると、2024年の消費者物価上昇率の動向の特徴は、①振れの大きい生鮮食品において、今夏以降の高気温や12月の気温低下による野菜の生育不良等を背景に価格上昇の加速がみられること、②生鮮食品を除く食料品について、7月までは価格上昇幅が縮小してきたが、8月以降、価格上昇幅の拡大に転じていること、③サービス物価について、人件費の転嫁もあって、緩やかな上昇が続いていること、が挙げられる。このうち、①の生鮮食品(野菜)の価格動向や背景についてはコラム1-5、③のサービス物価の動向については、後述、特に価格転嫁や物価上昇の広がり等において議論することとし、ここでは②の生鮮食品を除く食料品価格の動向について確認する。
2024年8月以降の生鮮食品を除く食料品の価格上昇幅の拡大については、POSデータをみると(第1-2-3図(2)、(3))、米類やチョコレート等の菓子類、10月以降は飲料や加工肉類等の価格上昇が影響している。このうち米類7については、上述のとおり、夏場における需給のひっ迫や令和6年産米における生産コスト増の反映等が影響し、2024年12月には前年比64.5%の記録的な水準まで上昇幅が拡大した。チョコレートについては、原料のカカオ豆の価格が、産地であるガーナ等の異常気象による生産減の影響を受けて世界的に高騰しており、円安も相まって、国内製品価格の上昇につながっている。このように品目ごとには、様々な要因が価格動向に影響している中、食品メーカーによる価格引上げの要因をみると(第1-2-3図(4))、2024年は、2023年に比べて、円安や人件費、包装・資材、物流費を挙げる企業が増加していたことが分かる。さらに、2025年(2024年12月時点の1-4月見通し)にかけては、物流費や人件費を価格引上げの要因として挙げる企業が更に増加している。このように、食料品については、一般的には、①円安進行が、包装・資材費の上昇も伴って、ラグをもって最終製品価格に波及していること、②生産コストに占めるシェアは高くないものの8、33年ぶりの高水準の賃上げの中で、人件費の転嫁が進んでいること、さらに、③物流費については、いわゆる「物流の2024年問題」もあって、2024年以降、道路運送料の上昇が顕著であり、これらコストの販売価格への転嫁が進んでいること等が価格上昇に影響しているとみられる9。

食料品を含む財の消費者物価について先行きを考えると、エネルギー価格については、①ガソリン・灯油の激変緩和措置については段階的に補助が縮小されていくことから、物価上昇率に対しては徐々に押上げ方向に働いていくとみられる10一方、②電気・ガス代については、2025年1~3月に負担軽減事業が実施されるため、2月以降の物価上昇率の抑制要因となると見込まれる11。食料品については、夏以降の大きな上昇要因となった米は、前年比でみた上昇率は高止まると考えられる一方、その他の食料品については、円安を通じた輸入物価の上昇が波及していく効果のほか、物流費や人件費の転嫁等もあって、上昇幅の拡大が続く可能性に留意が必要である。また、野菜など生鮮食品の価格動向にも引き続き注意が必要である。
コラム1-5 消費者物価における生鮮食品の動向と背景について
ここでは、消費者物価指数のうち、消費者の生活に身近な品目の一つである生鮮食品(消費者物価の総合に占めるウエイトは4%12)の価格動向や背景を確認していく13。消費者物価の基調を捉える上では、天候要因等により価格変動が大きい生鮮食品を除いたコア(生鮮食品を除く総合)やコアコア(生鮮食品及びエネルギーを除く総合)が参照されることが多いが、生鮮食品を含む総合は、消費者が直面する財・サービスの価格を包括的に表すものとして、より生活実感に近い指標と言える。
消費者物価の総合とコアの前年比上昇率を比較すると、近年、総合の伸びがコアの伸びを上回るケースが多くみられる(2024年1月から12月までの伸び率のかい離の平均は約0.2%ptと、総合がコアを上回る)(コラム1-5-1図(1))。より長期に、生鮮食品とコアの指数を比較すると、2010年頃までは、振れはありながらも、生鮮食品とこれを除くコアはおおむね同様に推移してきたが、その後は、生鮮食品がコアを上回って推移してきた(コラム1-5-1図(2))。生鮮食品の内訳をみると、生鮮野菜、生鮮果物、生鮮魚介のいずれについても2010年以降上昇傾向にあることが分かる(コラム1-5-1図(3))。

こうした生鮮食品価格の上昇トレンドについては、いくつかの要因が考えられるが、その一つは天候不順の影響である。地球温暖化の影響もあって、長期的に平均気温は上昇傾向にあるが、2010年代以降、こうした長期トレンドを上回って、気温が高まる傾向がみられる(コラム1-5-2図(1))。加えて、日中の最高気温が35度を超える猛暑日数も2010年代以降、長期的なトレンドを大きく上回る傾向にある(コラム1-5-2図(2))。時間降水量50mmを超える豪雨の発生頻度についても、長期的な増加傾向が観測される(コラム1-5-2図(3))。生鮮食品は、天候不順の影響を受けやすく、高温や降雨量の増加による生育不良等が供給の不安定化を招き、価格の上昇につながっているとみられる。

また、生産資材の高騰や人件費の上昇も、農林水産事業者の生産コストに影響を及ぼしているとみられる(コラム1-5-3図(1))。例えば、野菜作経営における費用割合(2022年)をみると、荷造運賃手数料や雇人費が3割、エネルギーや原材料高の影響を特に受ける動力光熱費や肥料費といった主要生産費用は全体の4割程度を占めている(コラム1-5-3図(2))。「物流の2024年問題」もあって農林水産関係でも物流関係費が上昇しているとみられるほか、農業生産資材価格をみると、2010年代以降上昇傾向にある中で、2022年2月のロシアによるウクライナ侵略等を背景とした肥料価格の急騰14、さらには円安の急速な進行もあって、近年の価格上昇が著しく、これらが生鮮食品の上昇に影響している可能性がある(コラム1-5-3図(3)、(4))。

物価の基調をみる上では、一般に、変動の大きい生鮮食品を除くコアや、生鮮食品に加えてエネルギーを除いたコアコアが重視されることが多いが、消費者の生活実感の上では、生鮮食品を含め日ごろの購入頻度が高い身近な品目の価格の動向が重要であり15、これらの価格上昇が、今後の物価上昇予想も通じて、消費者マインドを下押ししうるという点に留意すべきである。上述したように、生鮮食品の物価は、近年頻度が高まっている天候不順や各種生産コスト増の影響で上昇傾向が続いており、生鮮食品及びこれを含む総合についても、物価指標として従来以上に重視していくことが重要と言える。
(サービス物価の上昇率は欧米よりは低位であるが、プラスの上昇率が定着へ)
我が国の消費者物価において、財の前年比は2022年末の8%程度をピークに縮小傾向となり、2024年に入って3%前後で下げ止まって推移した後、2024年12月は生鮮食品価格の上昇が加速し、4%程度となっている(第1-2-4図(1))。一方、欧米においては、2024年中は、ゼロ%近傍ないし1%程度のプラス圏内で推移している。これに対し、サービスの消費者物価は、欧米では前年比4%ないしそれ以上の上昇が続き、物価上昇の主な要因となっている一方、日本のサービス物価は前年比1%台半ばから後半の緩やかな上昇が続いている(第1-2-4図(2))。日本のサービス物価について、公共料金16、家賃、それ以外の一般サービス(以下、「一般サービス」という。)に分けると、公共料金は、基本的には前年比ゼロ近傍で横ばい傾向が続いているが、2024年10月は火災・地震保険料の引上げもあって1%程度の伸びとなっている17(第1-2-4図(3))。家賃も、東京圏を中心にわずかながら上昇率が高まっているが、前年比0.3%程度にとどまる。一方、一般サービスは、2023年から2024年前半にかけて、前年比4%程度で推移した後、やや上昇幅が縮小し、3%程度で推移している。一般サービスについては、過去、長期間にわたり、物価上昇率が基本的にゼロ%前後で動かなかったことと比べると、近年は、人件費の転嫁もあってプラスの上昇率が定着してきていると考えられる。今後、賃金と物価の好循環が実現していくためには、人件費割合が相対的に大きいサービス部門において、賃金の継続的な上昇と、その価格転嫁を通じて、物価の安定的な上昇が継続していくことが重要であり、この点については、本節後段で議論する。
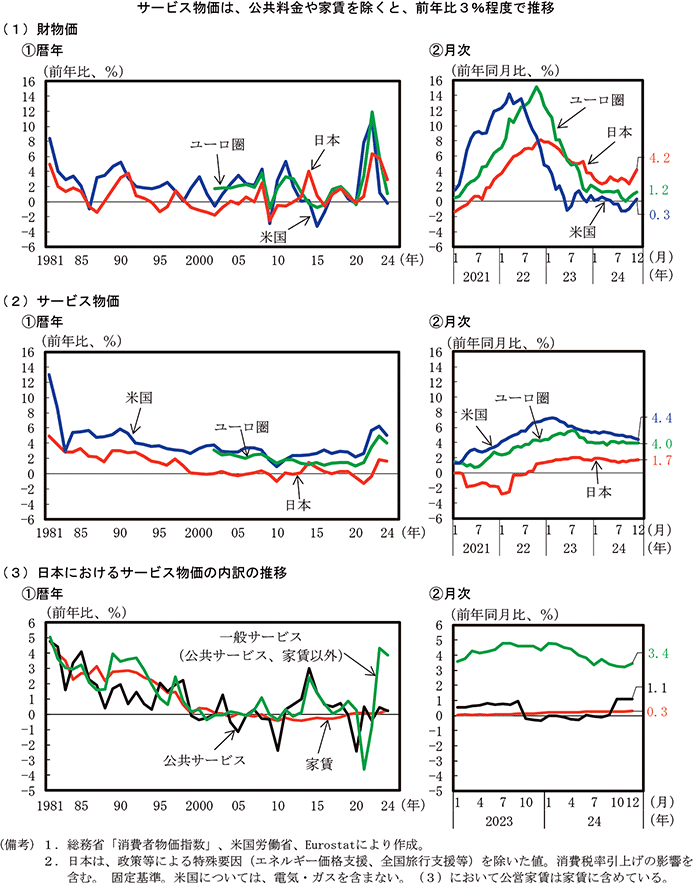
(GDPデフレーターは、内需を中心に2%台で推移)
物価動向に関して、最後に、GDPデフレーターの動向を確認する(第1-2-5図)。GDPデフレーターは、国内で生産された付加価値の価格である一方、輸入品は、海外で生産された付加価値に由来するものであり、輸入物価はGDPデフレーターの算定の際には控除される。このため、輸入物価が上昇(下落)する局面では、一義的に、GDPデフレーターを押し下げる(押し上げる)方向に作用する。近年の動向を振り返ると、2022年7-9月期にかけては、輸入物価の上昇幅が高まる中で、GDPデフレーターの押下げ幅が拡大した一方で、輸入物価の価格転嫁を通じた輸出物価や消費や投資といった国内需要デフレーターの上昇幅の拡大が相殺し、結果としてGDPデフレーターの伸び率はゼロ近傍で推移した。その後、2023年7-9月期にかけては、国内需要デフレーターの上昇率は3%台半ばから2%台後半に縮小した一方、輸入物価の上昇幅が縮小し、下落へ転じる中で、GDPデフレーターの上昇率は押し上げられ、1981年以降最も高い5.6%まで達した。その後、2024年7-9月期にかけては、輸入物価の前年比下落幅が縮小し、上昇に転じる中で、国内需要デフレーターは2%台で推移し、GDPデフレーター上昇率も2%台半ばまで縮小した。このように、輸入物価が上昇する中にあっても、国内要因での物価動向を示すGDPデフレーターの上昇率が安定的にプラスになっていることは、長期的に遡ってみても、我が国がデフレ状況に陥る前の1980年代初頭と1990年前後以来のことであり18、これまでとは物価の基調が着実に変わりつつあることを示していると言える。

2 デフレ脱却に向けた物価の背景
以上の物価の基調に加えて、ここでは、物価の背景について、GDPギャップや単位労働費用といったマクロ的な物価変動要因のほか、2024年における賃金上昇の詳細、原材料や人件費の価格転嫁の動向、サービス分野を含む物価上昇の広がり、企業や家計、市場参加者の予想物価上昇率、といった経済主体の価格・賃金設定行動や物価に対する認識に係るミクロ的な観点を含む各種の指標やデータを総合的に確認し、デフレ脱却に向けた現在地を確認する。なお、賃金上昇の持続性に係る詳細な議論については、コロナ禍前に人手不足感が高かった時期との比較を含めた分析を含め、第2章第2節において行う。
(GDPギャップのマイナス幅は縮小傾向、単位労働費用は賃上げ効果で前年比上昇)
まず、経済全体の需給の過不足を示すGDPギャップと、賃金に由来する物価上昇圧力を示す単位労働費用(以下、「ULC」という。)の動向について確認する。GDPギャップについては、2020年のコロナ禍による急速な悪化の後、長い目でみれば、振れを伴いながらも改善傾向で推移し、2024年7-9月期にはマイナス0.4%程度までマイナス幅が縮小している(第1-2-6図(1))。このように、現状は、需要不足の拡大によって物価が下落していくような環境にはないと考えられるが、今後、景気の緩やかな回復基調が続き、GDPギャップの改善傾向が継続するかどうか、慎重に見極めていく必要がある。なお、内閣府政策統括官(経済財政分析担当)(2024)にも示されているとおり、GDPギャップと消費者物価上昇率(コアコア)の関係(フィリップス曲線)をみると、デフレに陥る以前においては、切片が有意にプラスであり、かつ傾きについても明確な正の関係がみられていたが、デフレに陥って以降、コロナ禍前までの期間をみると、曲線が下方にシフトし、切片がゼロ近傍まで低下したほか、傾きもフラット化していったことが分かる(第1-2-6図(2))。このうち、切片の低下については、家計や企業といった経済主体の予想物価上昇率が低下したこと等を示唆している19。GDPギャップが負の領域にないということは、物価下落につながる蓋然性が低いという意味では重要であるが、安定的な物価上昇の実現にとってより重要なのは、経済主体の予想物価上昇率が2%前後で推移し、フィリップス曲線がデフレに陥る前のように安定的に上方に位置していることである。つまり、賃上げや価格転嫁の促進によって、賃金と物価が共に安定的に上昇していくというノルムが確立していくことが重要であり、こうした点も、デフレ脱却の判断に当たって、GDPギャップ等に限らず物価の背景を総合的かつ丁寧に確認していくことが必要であるとする所以である。
次に、ULCの前年比上昇率は、2023年は均してみればゼロ近傍のプラスで推移していたが、2024年4-6月期以降は、33年ぶりの高水準となった2024年春季労使交渉の賃上げの効果や堅調だった夏のボーナスを反映して、雇用者一人当たりの名目賃金の伸びが高まったことから、明確なプラス領域で推移している(第1-2-6図(3))。ここで、上述のGDPデフレーター上昇率について、ULCの変動による部分(ULC要因)とそれ以外の要素による部分(その他要因)20に分解したものをみると、2023年中は、GDPデフレーター上昇率が高まる中で、ULC要因以外が支配的であったが、2024年以降、特に4-6月期以降は、賃金上昇の効果を反映して、ULC要因が主たる要素となっていることが確認される(第1-2-6図(4))。

コラム1-6 グローバル・バリュー・チェーンとのつながりとフィリップス曲線
本論では、GDPギャップと消費者物価上昇率の関係(フィリップス曲線)のフラット化について述べたが、日本のみならず、欧米諸国においても、世界金融危機前後において、需給バランスの急激な悪化とその後の回復の中でも、物価上昇率は緩やかな状態が続き、フィリップス曲線のフラット化が生じていたとされる。この背景には、様々な要因が考えられる。例えば、伊達・中島・西崎・大山(2016)では、①中央銀行のコミュニケーションによる物価上昇予想のアンカーの強化、②メニューコストや名目賃金の下方硬直性によるフィリップス曲線の非線形性、③グローバル化や規制緩和による環境変化が挙げられている。本コラムでは、このうち、③に関係するグローバル・バリュー・チェーンとフィリップス曲線との関係について、諸外国に係る先行研究を踏まえつつ、我が国を対象に考察する。
まず、グローバル・バリュー・チェーンとのつながりの深さを示す指標の一つである、産業の中間投入に占める輸入割合を確認すると、製造業・非製造業ともに緩やかに上昇しており、かつ、その割合は製造業の方が一貫して高い状態が続いている(コラム1-6-1図(1))。また、国・地域別の輸入割合をみると、製造業・非製造業ともに、中国・ASEANの伸びが顕著であり、中間投入に占める輸入割合の上昇はこれらの地域からの輸入増加が主因となっていることが分かる(コラム1-6-1図(2))。

次に、Gilchrist and Zakrajsek(2019)やAquilante et al.(2024)の手法を参考に、産業別パネルデータを用いて、国内企業物価(財・サービス)と、鉱工業生産指数や第3次産業活動指数を用いて推計した需給ギャップとの関係をフィリップス曲線として推定する。推定に当たっては、需給ギャップ以外の要因が物価上昇率に与える影響を除くことが重要であり、Aquilante et al.(2024)では、産業別のパネルデータを用いることにより産業ごとの固定効果を考慮するとともに、時系列の固定効果も考慮し、Ball and Mazumder(2014)やMcLeay and Tenreyro(2019)等でフィリップス曲線に影響を及ぼすことが指摘されている予想物価上昇率や金融政策による影響など全産業共通に関わる要素についてもコントロールしている。本分析でも同様の処理を行った。
産業別フィリップス曲線の推定結果を示しているのが、コラム1-6-2図である。まず、製造業については、2003年から2012年は、物価と需給ギャップとの間に統計的に有意な関係性は認められなかったものの、2013年から2019年にかけては、有意に正の関係が認められるようになっている。コロナ禍の 中にあった2020年から2021年には有意な関係性は失われたものの、コロナ禍後の2022年から2024年にかけては、再度、有意に正の関係性が確認できるようになっており、その傾きもアベノミクス期と同程度になっている。
次に非製造業については、いずれの時期も統計的に正に有意な関係性が認められており、2012年以前と2013年から2019年にかけての時期を比較すると、後者の方がより物価と需給ギャップの関係性が強くなっている。コロナ禍においては、フィリップス曲線は大きくフラット化したものの、2022年以降にかけては、コロナ禍以前の姿に近づきつつある。また、製造業と非製造業を比較すると、コロナ禍以前においては、製造業の方が、フィリップス曲線がよりフラットであったことが分かる。

ここで推定されたフィリップス曲線に、中間投入に占める輸入割合の要素を加え、グローバル・バリュー・チェーンとのつながりが、我が国のフィリップス曲線に対してどのような影響を与えたのかについて検証した結果がコラム1-6-3図である。製造業の結果をみると、中間投入に占める中国・ASEANからの輸入割合の上昇が、フィリップス曲線をフラット化させていることが分かる。これは、中間投入に占める輸入割合が増加するほど、国外における需給バランスの変動の影響を受けるようになり、国内物価と国内における需給バランスとの関係性が希薄化する結果であると考えられる。一方、非製造業では、中国からの輸入割合の上昇が、フィリップス曲線をフラット化させていることが確認されたものの、製造業と比べるとその程度はやや小さく、ASEANについては、統計的に有意な関係は確認されない。
以上の分析を踏まえると、フィリップス曲線のフラット化に影響した要因は様々ではあるものの、グローバル化の進展に伴い、トレンドとして、中間投入の輸入割合、特に中国・ASEANからの輸入割合が高まった中、こうしたグローバル・バリュー・チェーンとのつながりの深化が、製造業を中心に、我が国のフィリップス曲線をフラット化させてきた可能性があると言える。

(過去四半世紀にわたる賃金も物価も据え置きで動かない状況から大きく変化)
次に、賃金上昇の状況を確認する。我が国の名目賃金の上昇率は、1990年代末以降、物価上昇率と同様におおむね0%前後で推移してきた。2021年以降は、上述のとおり、輸入物価上昇を起点とするコストプッシュ型の物価上昇が生じたが、これに対し、2022年から価格転嫁や賃上げを強力に促進してきた結果、賃金上昇率は着実に高まっている(第1-2-7図(1))。「毎月勤労統計」における就業形態計の名目賃金(現金給与総額)をみると、後述するように、2024年6~8月は夏のボーナスが堅調だったことが上昇率の押上げに寄与したが、これを除いても賃金の伸びは着実に高まっており、2024年5月以降、8か月連続で2%以上の伸びが続いている(第1-2-7図(2))。これは、1992年以来のこととなる。このように、過去長期にわたり賃金も物価も据え置きで動かなかったという状況からは大きく変化している。次に、現金給与総額の上昇率を、フルタイム労働者(労働者の約7割)、パートタイム労働者(労働者の約3割)それぞれの現金給与総額の上昇率と、パートタイム労働者比率に要因分解すると、フルタイム労働者、パートタイム労働者ともに、前年比増加が続く一方で、給与水準が相対的に低いパートタイム労働者比率が上昇傾向にあることが賃金上昇率の下押し要因となっている状況が続いていることが分かる(第1-2-7図(3)、(4))。雇用者一人一人の賃金の伸びという観点では、フルタイム労働者とパートタイム労働者の就業形態別に分けてみることが適切であり、以下、詳細を確認していく。

(フルタイム労働者の所定内給与は高まるも、春季労使交渉ベアを下回る)
まず、フルタイム労働者の所定内給与の動向を確認する。日本労働組合総連合会(連合)の春季労使交渉結果の集計においては、2024年は定期昇給を含む賃上げ率で5.10%、ベアで3.56%と33年ぶりの高水準となり、実際の給与支払である所定内給与も2024年4月以降賃上げが反映され始め、夏頃にかけて着実に伸びが高まった。2024年12月時点では前年同月比2.6%と、同年5月以降、8か月連続で2.5%を超える伸びが定着している(第1-2-8図(1))。これは、統計上比較可能な1994年以降で初めてとなる。
次に、賃上げ率が相対的に高い年における春季労使交渉におけるベアと「毎月勤労統計」の所定内給与の伸び率の関係を確認する。所定内給与の伸び率は、春季労使交渉のベアに相当21するものであり、ベアが3%台であった1990年代初頭は、両者はおおむね整合的であった22。2023年も、所定内給与の伸びは、ベア(2.12%)をやや下回ったものの、ほぼ同程度であったが、2024年についてみると、ベア3.56%に対し、所定給与の伸びはこれを下回り、2023年よりもかい離が拡大していることが分かる(第1-2-8図(2))。

では、こうした春季労使交渉のベアと所定内給与の伸びの差はなぜ生じるのであろうか。仮説としては、①労働組合の有無によって賃上げ率が異なり、労働組合を持たない企業においては、組合がある企業に比べて賃金上昇率が低い可能性、②これと関連するが、中小企業においては、より規模の大きい企業に比べて賃上げが遅れている可能性がある。また、労働組合を持つ企業の中でも、③組合員である労働者の賃金改定率を示す春季労使交渉結果に対し、「毎月勤労統計」等の賃金統計では企業・事業所の常用雇用者全体の賃金を対象としているため、非組合員の管理職等の賃金引上げ率が、組合員労働者のそれを下回る可能性、④連合に加盟している組合を持つ企業とそれ以外の組合を持つ企業とでは賃上げ率に差がある可能性、これとも関係するが、⑤産業によって賃上げ率が異なり、特に公定価格部門など公的セクターにおいては、民間セクターに比べて賃金上昇率が低くとどまっている可能性等がある。
(労働組合を持たない企業の賃上げ率は、組合を持つ賃上げ率に比べ1%pt近く低い)
まず、①の労働組合の有無による賃金上昇率の違いについて、厚生労働省「賃金引上げ等の実態に関する調査」の結果を確認する。同統計においては、ベアを取り出すことは難しく、定期昇給を含む賃金改定率全体のみ把握可能であるが23、労働組合を持つ企業と持たない企業に分けた賃金改定率をみることができる。これによると、2023年においても一定のかい離はみられたが、2024年については、労働組合を持つ企業の賃金改定率が4.5%であったのに対し、労働組合がない企業は3.6%と、1%pt近いかい離があり、その差は、労働組合の有無別の調査開始の1999年以降で最も大きいことが分かる(第1-2-9図)。このように、2024年については、労働組合を持たない企業においては、賃上げ率が相対的に低く抑えられ、これが一因となって、フルタイム労働者全体の所定内給与の伸び率がベアに比べて低くとどまっているものと考えられる。

(中小企業の賃金上昇には遅れがみられ、価格転嫁対策等が引き続き重要)
次に、労働組合の有無による賃金上昇率の違いという点に関連して、企業規模による賃上げ率の違い、とりわけ中小の企業・事業所において、賃金上昇の遅れがみられているかどうかを確認する。まず、「賃金引上げ等の実態に関する調査」の賃金改定率(定期昇給を含む)をみると、規模の大きい企業ほど賃上げ率が高く、特に、賃金が動き出した2023年以降は、1000人以上企業と、100~299人企業の差が拡大している(第1-2-10図(1))。また、「毎月勤労統計」から、事業所規模別のフルタイム労働者の所定内給与の伸び率をみると(第1-2-10図(2))、比較的規模の小さい5~29人事業所では、より規模の大きい事業所に比べて、賃金上昇率が低位にとどまっていることが分かる。このように、中小企業・事業所では賃金上昇に遅れがみられている点には十分な留意が必要であり、引き続き、省力化投資等を通じた生産性向上の支援とともに、労務費の価格転嫁を促進し、中小企業が賃上げを進めやすい環境を整備することが重要であると言える。

(2023年に比べ、2024年は賃上げが中年層にも広がり。産業別の賃上げにばらつき)
次に、労働組合が存在する企業であっても、賃金改定率が春季労使交渉の賃上げ率を下回っている背景に係る仮説のうち、上述③の組合員労働者と管理職等の非組合員の賃金上昇率の差が影響している可能性に関連して、厚生労働省「賃金構造基本統計調査」により、年齢別のフルタイム労働者の賃金上昇率(所定内給与の伸び率)の違いを確認する。同統計では、労働組合を持つ企業を取り出し、組合員と非組合員の賃金上昇率を比較することはできないが、若年層の賃金は組合員の賃金を、中年層の賃金は非組合員である管理職層の賃金を近似しているとの仮定の下で、年齢別の賃金上昇率を比較する(第1-2-11図)。これによると、30年ぶりの賃上げ率となった2023年は、大学卒を中心に、中年層の所定内給与の伸びが、若年層に比べて低い状況にあった。一方、2024年における「賃金構造基本統計」(速報)をみると、2023年と異なり、大学卒において、中年層の賃金の伸びが総じて若年層の伸びを超えて高まるなど、むしろ賃金上昇に広がりがみられる姿となっている。よって、2024年において、管理職などの非組合員の賃金上昇率が低いために、賃金統計上のフルタイム労働者の所定内給与の伸び率がベアを下回ったという可能性は高くないと考えられる。

続いて、④の労働組合を持つ企業でも、連合加盟組合を持つ企業とそれ以外の組合を持つ企業との間の賃上げ率の差について検討する24。上述の「賃金引上げ等の実態に関する調査」における労働組合がある企業の賃金改定率と、連合の春闘結果を企業規模別に比較すると25、2024年は、企業の規模を問わず、連合集計の賃上げ率の方が、労働組合がある企業の賃上げ率を上回っており、この傾向は2023年には必ずしも観察されなかった事象である(第1-2-12図)。連合加盟組合とそうでない組合との間のバーゲニングパワーの違い等が要因として考えられ、日本全体の賃上げ状況の把握に当たっては、連合集計の賃上げ率のみならず、賃金や給与所得の動向に係る多様な統計・データをできるだけ早期に、総合的に把握していくことが重要と言える26。

最後に、⑤の公的セクターと民間セクターにおける賃金上昇率の違いについて確認する。具体的には、「毎月勤労統計」(所定内給与)や「賃金引上げ等の実態に関する調査」(定期昇給を含む賃金改定率)について、産業別の動向を確認すると、公定価格分野である医療や介護等を含む医療・福祉、国公立の学校教員を含む教育・学習支援業は、2023年に比べれば、総じて賃金上昇率が高まっているが27、他の産業と比べると依然として低位であることが分かる(第1-2-13図)。こうした産業では労働組合があったとしても連合に加入している可能性が低い28と考えられ、前述④で確認した、労働組合ありの企業の中でも賃金上昇率が異なるという影響と一定の重複があるが、公定セクターの賃金上昇率の相対的な低さは、春季労使交渉の賃上げ率よりも、賃金統計上の賃金上昇率(改定率)が低い一因となっていると考えられる。
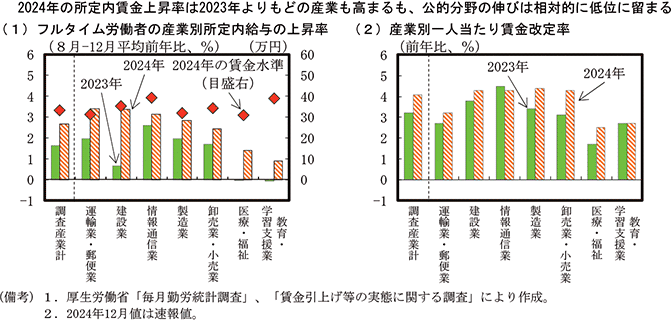
(2024年に入り、建設業や運輸業等の残業時間の減少が所定外給与の押下げに寄与)
次に、所定外給与(残業代等)の動向を確認する。所定外給与の伸びは、残業手当の割増率が一定等の仮定の下では、所定内給与の伸びと所定外労働時間(残業時間)の伸びの和で近似されると考えられる。所定内給与については、上述のとおり、着実に伸びが高まっている一方、所定外労働時間については、2024年に入って以降、減少傾向が強まっている(第1-2-14図(1))。産業別に分解すると、製造業は、一部自動車メーカーの認証不正問題の影響もあって2024年前半にかけて減少していたほか、建設業や運輸・郵便業において、「2024年問題」の影響によって減少傾向にあることが分かる(第1-2-14図(2))。2025年以降は、こうした一部業種への影響は一巡すると考えられる一方、働き方改革の推進の下で、所定外労働時間が構造的に増加していく環境にはないことから、当面、所定外給与の伸びは、所定内給与の伸びの範囲で推移していくことが見込まれる。

(2024年夏のボーナスは、中小事業所を中心に支給事業所が増加し、堅調に推移)
次に、フルタイム労働者の特別給与(ボーナス等)の動向についてみると、2024年の夏(6~8月平均)は前年比7.8%となった。1993年以前は就業形態計のみ把握可能であるが、前年比7.5%と同様の伸びとなり、33年ぶりの高い増加率となった(第1-2-15図(1))。特別給与の伸びを、事業所規模別に分解すると、所定内給与とは対照的に、5~29人の事業所の寄与が特に大きなものであったことが分かる。ここで、特別給与のうちボーナスのみを取り出した「毎月勤労統計」の賞与集計結果から、夏のボーナスを支給した事業所の労働者29についての一人当たり平均ボーナス支給額の伸びをみると、2024年は2.3%と2023年の2.0%より高いものの大きな変化はない。上述の特別給与の伸び(就業形態計7.5%)についてはボーナスが支給されていない事業所の労働者も含む全体の平均値であり、新たに特別給与が支給される労働者の増加分が押上げに寄与するのに対し、後者(2.3%)は、新たにボーナスが支給された労働者数の増加分の影響は受けないという違いがある。実際、ボーナスを支給した事業所の割合は2023年の65.9%から2024年は73.0%に高まっている。ボーナス支給事業所割合について、事業所規模別にみると、30人以上の事業所では支給事業所割合が横ばいだったのに対し、5~29人の事業所においては、2024年に支給割合が大きく上昇しており、このことが2024年夏のボーナスの伸びの押上げに大きく寄与したと推察される(第1-2-15図(2))。上述したとおり、比較的規模の小さい5~29人の事業所においては、所定内給与で見た賃金上昇率が遅れている一方で、こうした事業所においては、毎月の賃金よりも、ボーナスの支払によって、労働者の待遇改善を図り、人材の確保・維持に努めていると考えられる。
冬のボーナスについては、連合の調査30では前年比プラス0.42%である一方、厚生労働省「令和6年民間主要企業年末一時金妥結状況」31では前年比プラス4.93%(前年と同一企業による集計でプラス5.31%)、日本経済新聞社の調査32で前年比プラス3.49%、日本経済団体連合会の調査33で前年比プラス2.11%となるなど、引き続き堅調な増加が見込まれている(第1-2-15図(3))。上述のように、中小規模の事業所において、ボーナス支給割合が高まっていることも踏まえると、冬のボーナスによって、引き続き所得環境の改善が続いているものと期待される。実際、「毎月勤労統計調査」における就業形態計のボーナスを含む特別給与は、ボーナス支給事業所割合の上昇もあって、2024年11-12月平均34で前年同期比7.8%の増加(フルタイム労働者は7.7%の増加)と堅調に推移していることが確認できる。

(パート労働者の時給は、最低賃金の引上げもあって高い伸び)
次に、パートタイム労働者の名目賃金(現金給与総額)の動向を確認すると、総実労働時間については緩やかな減少傾向が続いているものの、時給の伸びが2023年夏頃から前年比4~5%程度で推移するなど、これを大きく上回り、現金給与総額としては、4%を超える伸びとなっている35(第1-2-16図(1))。パートタイム労働者の時給は、労働需給のひっ迫に加え、最低賃金の引上げもあって、高い伸びが続いている。ビッグデータにより、パート・アルバイトの募集賃金の動向をみると、毎年、最低賃金の引上げが行われる10月初め前後において、募集賃金が高まる傾向が確認される(第1-2-16図(2))。2024年についても、過去最大の最低賃金の引上げ幅(全国加重平均プラス51円)となる中、9月末以降、募集賃金は各都道府県で一段と高まっており、全国平均1,185円(2025年1月中旬時点)となっている。

次に、募集賃金の各年8-9月平均から11-12月平均にかけての変化率と、最低賃金の変化率(第1-2-17図(1))から、最低賃金の伸び率に対する募集賃金の伸び率(弾性値)36を求めると、2017~19年(コロナ禍前)平均は0.40(最低賃金の1%上昇に対し、実際の賃金は0.4%増加)であったのに対し、コロナ禍後の平均は0.47とやや上昇している。これは、最低賃金が上昇してきた中で、最低賃金近傍で働くパートタイム労働者の割合がコロナ禍前より増加していることを反映しているとみられる。また、業種ごとの募集賃金の最低賃金に対する弾力性について、コロナ禍前とコロナ禍後で比較すると(第1-2-17図(2))、特に人手不足感の高い建設業や賃金水準が相対的に低い宿泊・飲食サービス業等で伸びが高いことが分かる37。こうした募集賃金上昇は、パートタイム労働者の採用を経て、徐々に「毎月勤労統計」の時給の伸びに反映されることが期待される。

(実質でパート時給は安定的に上昇、フルタイムの月給はボーナス込みでは増加傾向)
次に、就業形態別の実質賃金について、名目賃金を消費者物価の総合指数で除した実質賃金38についてみると、パートタイム労働者の時給は、2023年7月に前年比でプラスに転じた後、徐々に上昇率が高まる傾向にある(第1-2-18図)。パート労働者の賃金は、時給ベースでは安定的に物価上昇率を上回る状況が実現していると評価できる。また、フルタイム労働者の月給について、現金給与総額の実質値をみると、2024年6~7月は、夏のボーナスが堅調だったこともあり、前年比1~2%のプラスとなった後、ボーナスの効果の剥落とともに伸び率は縮小したものの、引き続きプラス傾向で推移し、2024年11~12月も、冬のボーナスが堅調であることから、前年比1%程度の伸びとなっている。振れの大きいボーナスを除く定期給与でみると、ロシアによるウクライナ侵略直後の2022年4月以降、前年比の減少が2年半にわたり続いてきたが、33年ぶりの高水準となった春季労使交渉の賃上げが実際の給与に着実に反映される中で、ゼロ近傍まで回復し、2024年10月には2年7か月ぶりにプラスとなった。ただし、2024年12月にかけては、生鮮食品の価格上昇が加速したこと等により消費者物価上昇率が高まった結果、フルタイム労働者の実質定期給与は前年比で再び減少となった。フルタイム労働者の実質定期給与について30人以上の事業所でみると、同様の傾向であるが、上述のとおり、規模が相対的に大きい事業所では賃金上昇の伸びが高いことから、2024年夏以降、名目賃金の伸びが消費者物価上昇率を上回る傾向となっている。

先行きについては、パートタイム労働者は、最低賃金引上げの効果もあって、時給は実質で見ても、前年比プラスの状況が続くと考えられる。フルタイム労働者については、2025年度の春季労使交渉に向けた労使の方針39として、高い賃上げの継続を目指していく旨が掲げられており、所得環境の改善が続くことが期待される。ただし、実質賃金としては、前述したように、消費者物価上昇率における生鮮食品を含む各種食料品の価格上昇幅の拡大等が下押し要因となることに留意が必要である。2%程度の安定的な物価上昇の下、名目賃金の伸びがこれを安定的に上回るという流れを、着実なものとしていくことが不可欠である。物価の安定に加え、労務費の円滑な価格転嫁や、生産性向上のための省力化・デジタル化投資やリ・スキリング支援、経営基盤の強化に資する事業承継・M&Aの支援によって、中小企業を含めて賃金を底上げしていくことが引き続き重要となる。
(仕入価格の販売価格への転嫁は着実に進展)
次に、企業の価格転嫁の状況を確認する。まず、原材料等の企業の仕入価格が、企業が産出する財・サービスの販売価格にどの程度転嫁されているかについて、日銀短観の仕入価格判断DI、販売価格判断DIの推移を確認する(第1-2-19図)。今回の物価上昇局面においては、企業の規模を問わず、仕入価格判断DIが過去最高の水準に上昇すると同時に、販売価格判断DIも上昇し、過去40年間には見られなかったプラスの水準を維持している40。2000年代後半の世界金融危機前の原油等資源価格上昇の局面では、仕入価格判断DIが今回局面と同程度に上昇した一方で、販売価格判断DIがほとんどプラスにならなかったことと比べると違いは顕著であり、仕入価格の販売価格への転嫁が着実に進展していると考えられる。
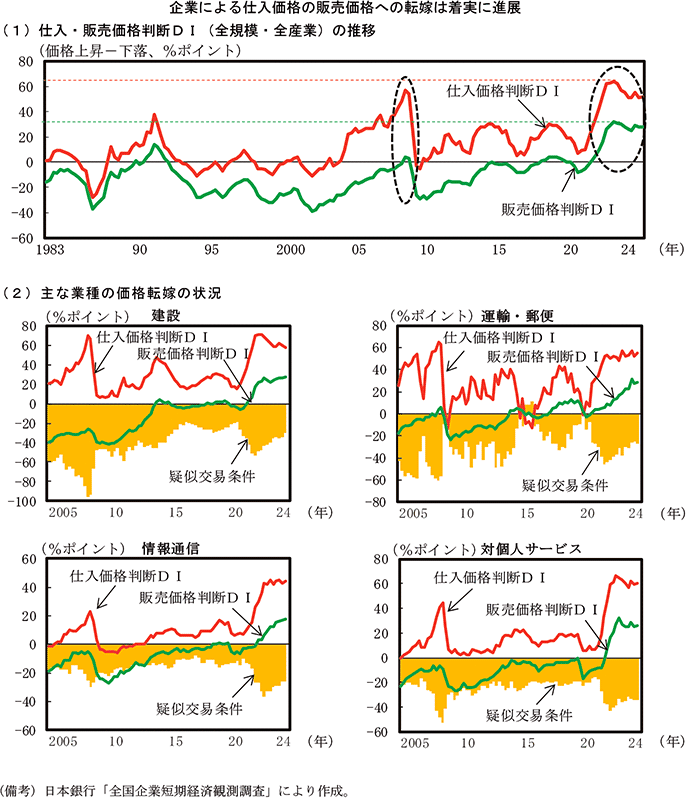
この点を、仕入価格が上昇したと回答した企業割合に対する販売価格が上昇したと回答した企業割合の比(以下、「価格転嫁性向」という。)から評価する。例えば、全規模全産業において、仕入価格が上昇したと答えた企業の割合が20%を超えていた期間を仕入物価上昇局面として、その期間における価格転嫁性向をみると、1980年代初頭や1990年代初頭の期間では0.5程度であったものが、デフレに陥って以降の仕入価格上昇局面(2000年代後半、2010年代前半、2010年代後半)ではいずれも0.3前後に低下していた。これに対し、2021年以降の今回物価上昇局面では、0.3程度から始まり、最近期では0.6弱の水準で安定的に推移していることが分かる(第1-2-20図(1))。これを業種別でみると、素材型・加工型ともに、製造業においては、価格転嫁性向は1980年以降で最も高い水準となり、非製造業については、1980年代初頭や1990年代初頭の水準は下回るものの、デフレに陥って以降の期間よりも高く、最近期には0.6程度にまで着実に上昇傾向にある(第1-2-20図(2)、(3)、(4))。特に、製造業では、直近の2024年末の水準は、今回の仕入価格上昇局面のピークよりはやや低い水準で安定的に推移しており、非製造業の方が、総じて、仕入価格対比での販売価格の上昇が足下で堅調となっている。これは、非製造業の方が、一般に人件費比率が高く、賃金上昇の中で、これを販売価格に転嫁させる動きが広がっていることが一因と考えられる。

そこで、非製造業の各業種について、仕入価格判断DIと販売価格判断DIの近年の動向をみると、建設や運輸、情報通信といった業種では、仕入価格判断DIが高水準で横ばい傾向の中で、販売価格判断DIが着実に上昇傾向にあることが分かる(前掲第1-2-19図(2))。これらの業種では、人手不足への対応もあって賃金上昇率が相対的に大きく、人件費の販売価格への転嫁が進んでいることが分かる。他方、よりBtoC向けのサービスである対個人サービスでは、2023年初めにかけて、仕入価格判断DIが販売価格判断DIよりも急速に上昇した後、両者共に横ばい傾向で推移した結果、仕入価格判断DIと販売価格判断DIの差がさほど縮小しておらず、建設や運輸等と比べると、価格転嫁が遅れている可能性があることに留意が必要である。
(高人件費率のサービスでは、より高い物価上昇がみられる)
こうしたサービス分野を含め、賃金上昇に伴う人件費の販売価格への転嫁の進捗について、以下、複数の角度から確認したい。まず、消費者物価指数全体の変動要因を、賃金要因、国内需給要因、輸入物価要因等に分解し、時系列における変化を確認する41。第1-2-21図がその結果であるが、コロナ禍前までの期間をみると、賃金要因や国内需給要因の寄与は総じてゼロ近傍であり、物価上昇率の変動は主に輸入物価要因により説明されていたことが分かる。これに対し、近年の物価上昇局面においては、この輸入物価要因が過去と比べても大きく物価上昇率に影響した一方で、過去とは異なり、賃金要因が物価上昇率の押上げに影響するようになっている点が確認できる。こうした賃金から物価への流れが、今後着実に強まり、定着していくかどうかが、賃金と物価の好循環の実現において重要な論点となる。

次に、サービス分野に着目し、BtoBの企業向けサービス価格と、BtoCの消費者物価のサービス価格について、人件費率の高低で2グループに分けた上で、それぞれ物価上昇率の動向を、第1-2-22図でみていく42。BtoBのサービス価格については、人件費率の高低に関わらず、2024年10月時点で前年比3%程度の高い伸びとなっているが、低人件費グループについては、2%台後半での横ばい傾向が続いているのに対し、高人件費グループでは、土木建築サービスなどを含む専門サービス(諸サービスに含まれる)を中心に、着実に伸び率が高まる傾向にあることが分かる43。これに対し、BtoCのサービス価格をみると、低人件費率グループについては、総じて前年比1%程度ないしそれ以下の伸びで推移している(2024年10月に伸び率が高まっているのは、主に、公共料金である火災・地震保険料の引上げ等による)。一方、BtoCの高人件費グループについては、2023年半ばに前年比3%台半ばまで伸びが高まった後、やや伸び率が縮小し、2024年末にかけては3%弱で推移している。このように、高人件費グループのサービス価格は、低人件費グループと比べると、より高い伸び率で着実に推移しており、賃上げに伴う人件費の上昇が、総じて販売サービス価格に転嫁されつつある様子が見てとれる。内訳をみると、交通・通信や住居、教育の寄与が大きく、それぞれ、交通・通信は自動車整備費、住居は工事費や修理費、教育は補習教育(塾)等が主に寄与している44。ただし、高人件費グループの品目の中でも、教育に含まれる私立中学校授業料は0%台、教養・娯楽に含まれる習い事等の月謝講習料は2023年には2%台半ばまで高まったものの、直近では1%台前半まで低下するなど、分野によっては価格上昇が限定的な分野も含まれる。このように、BtoCサービスの一部では、人件費割合は高い一方で、競争的な市場環境もあって、販売価格の引上げが進まない分野もみられる点には留意が必要である。

次に、賃金から物価への流れが、サービスの各分野において確認できるかを検証する。ここでは、賃金として、「毎月勤労統計」の産業別の所定内給与の伸び率、物価として、産業連関表の品目別の需要構造(中間需要か最終需要か)をもとに企業物価や消費者物価を合成した物価指数の伸び率を用いる。これに、需給要因(GDPギャップ)を加え、時変パラメータのVARを推計し、賃金から物価への因果関係を確認する。第1-2-23図が主な結果であり、賃金が1%pt上昇した際の4期後の物価上昇率の累積インパルス関数となる。運輸サービスでは、過去は賃金から物価へのパススルーが統計的に有意ではなかったが、近年は有意にプラスとなっているほか、情報通信でも過去に比べて、安定的に賃金から物価への経路が有意にプラスとなっている。一方、宿泊サービスについては、1990年代初頭は賃金から物価へのパススルーが有意であったものが、その後は有意ではなくなり、近年においても賃金から物価への経路が回復したとまでは言えない状況にある。このように、賃金から物価への波及経路は、サービス分野によっては観測されてきているものの、ばらつきがあり、今後、広範な分野で、賃金から物価へのパススルーが確立されていくか、注視が必要である45。

(物価上昇の広がりは着実にみられ、サービスではより多くの品目で物価上昇領域に)
以上の価格転嫁の動向も踏まえ、物価上昇の広がりについて確認する(第1-2-24図)。まず、国内企業物価、企業向けサービス価格、消費者物価それぞれにおける、物価上昇品目割合をみると、BtoB価格では、財・サービスともに8割近くと、1980年代を超えた水準で推移している。特に、サービス価格では、物価上昇品目割合は着実に上昇し続けている。BtoCの消費者物価については、物価上昇品目割合は、2023年半ば頃のピークである8割からは幾分低下しているものの、やはり70%台半ばで推移しており、デフレに陥る前の1980年代半ばとほぼ同様となっている。このように、物価上昇品目割合でみると、物価上昇の広がりは、デフレ以前の状況に回帰していると言える。

次に、国内企業物価、企業向けサービス価格、消費者物価それぞれについて、品目別の物価上昇率の分布と変化をみる。具体的には、コロナ禍前の2018年、今回物価上昇局面初期の2021年、直近の2024年の三時点で、品目数ベースの分布と物価指数に占めるウエイトベースの分布の双方を確認するとともに、サービスについて、デフレに陥る前の1980年代半ば46との比較も行う。まず、品目数ベースでは、財については、2018年や2021年に比べて、2024年は、国内企業物価(BtoB)、消費者物価(BtoC)ともにゼロ%の山が大きく低下するとともに、ピークがプラスの領域に移行し、分布もプラス領域にシフトしていることが分かる。サービスについても、企業向けサービス価格(BtoB)、消費者物価(BtoC)のいずれも、2018年、2021年に見られたゼロ%の山が崩れ、BtoBにおいてはプラス3%付近にピークが形成されているほか、BtoCにおいても、プラス2%付近と3%付近とゼロ%付近の割合が同程度となるなど、着実にプラス領域に分布が広がっていることが確認できる(第1-2-25図(1)、(2))。1980年代半ばと比較すると、BtoBのサービスは、1980年代半ばにおいてもプラス領域への分布がみられたものの、ピークがゼロ%付近であったのに対し、2024年はピークがプラス3%付近にあるなど、より物価上昇に広がりがみられている。BtoCのサービスは、1980年代半ばではプラス2%付近が明確なピークであったという違いはあるが、2024年の分布は相当程度、1980年代半ばの姿に近づいていると言える。
また、ウエイトベースの分布をみると、財については、BtoB、BtoCともに、分布の山が2018年、2021年の0%付近から、2024年は、BtoBがプラス1%、BtoCはプラス2%付近にシフトするとともに、全体としてプラス領域への広がりがみられる(第1-2-25図(3)、(4))。サービスについては、BtoBでは、おおむね品目数ベースと同様に、プラス2、3%付近に分布の山が形成されている。これに対し、BtoCでは、2018年・2021年のゼロ%付近の山は2024年には低下し、プラス領域への広がりも確認できる一方で、依然ゼロ%付近への集積が相対的に大きい。品目数ベースと同様に、デフレに陥る前の1980年代をみると、分布の山がプラス2%付近に位置していたことを踏まえると、消費者物価のサービスにおける物価上昇の広がりは、デフレ前の状況に回復しきったとまでは言えない。引き続き、BtoCのサービス分野を中心に、物価上昇の広がりがより明確に確認されるようになるか、引き続き注視していくことが重要である。

(企業の予想物価上昇率は2%程度に安定化の一方、家計の予想物価上昇率は上振れ)
最後に、各経済主体(企業、家計、市場参加者)の予想物価上昇率の動向について確認する。まず、企業の予想物価上昇率について、日銀短観の物価見通しをみると(第1-2-26(1))、企業による3年後、5年後という中期的な予想物価上昇率は、2022年半ばからレベルシフトし、物価安定目標と整合的な2%台で安定的に推移している。具体的に、企業がどの程度の水準の(5年後の)物価上昇率を予想しているのかについて、「イメージを持っていない」と回答した企業47を除いた回答毎の分布をみると、コロナ禍前の2018年は、+1%程度が最も多く、次いで0%程度だったのに対し、2024年時点では+2%程度が最も多くなり、+3%程度も2018年時点よりも増加している。このように企業の予想物価上昇率は2%前後が着実に定着しているとみられる。
次に、市場参加者の予想物価上昇率として、10年物の国債利回りと物価連動債利回りの差から計算されるブレーク・イーブン・インフレ率(BEI)をみると(第1-2-26図(2))、2020年頃から上昇し、直近では1%台半ばとなっている。BEIについては、物価連動債の発行が少なく流動性が低いことから、流動性リスクプレミアムがあり、これらによりBEIが真の予想物価上昇率より低くなる傾向があるとされるが48、その点を除けば、推移としては、企業の予想物価上昇率と近しい動きとなっている。また、ESPフォーキャスト調査によるエコノミストの2~6年後の中期的な予想物価上昇率をみると、同様に2020年以降徐々に高まり、1%台半ばとなっている。総じて、市場参加者の予想物価上昇率も、2%程度に向けて安定化しつつあるとみることができる。
他方、家計部門の予想物価上昇率については、①内閣府「消費動向調査」における「あなたの世帯で日ごろよく購入する品物の価格について、1年後どの程度になると思いますか」という質問に対する回答49から加重平均により算出するものと、②日本銀行「生活意識に関するアンケート調査」における「1年後の物価は現在と比べ何%程度変化すると思うか」あるいは「これから5年間で物価は現在と比べ毎年、平均何%程度変化すると思うか」という質問に対する具体的な数値による回答を集計したもの(平均値ないし中央値)がある。1年後の予想物価上昇率について比較すると(第1-2-26図(3))、「消費動向調査」から算出された予想物価上昇率50は2023年初に6%超まで高まった後、直近では5%台となっているのに対し、「生活意識に関するアンケート調査」の集計値は、2023年初にかけて平均値で11%半ば、中央値で10%程度に高まった姿となっており、後者の方が総じて高い水準を示している。なお、それぞれの調査について回答の分布をみると、10%以上を予想する家計の割合が増加傾向にあるなど、おおむね同様の傾向であるが、「生活意識に関するアンケート調査」の方が、10%以上や5%~10%の回答割合が高いという特徴がみられる(第1-2-26図(4)、(5))。
また、「生活意識に関するアンケート調査」から中期的な5年後の予想物価上昇率をみると、2010年代は、平均値4%程度、中央値2%程度で推移していたものが、今回物価上昇局面においては、平均値8~9%程度、中央値5%程度と水準がレベルシフトしていることが分かる。ここで、予想物価上昇率に関して米国の状況をみると、家計は、5~10年後の上昇率の予想が3%強(中央値)であるのに対し、BEIは2%強と51、家計の方が高く、過去期間におけるかい離の平均値は0.74%pt程度となっている。このように、家計の予想物価上昇率は、市場参加者等のそれに比べて高めとなる傾向があると考えられる。日本の場合、企業の予想物価上昇率をベンチマークとして考え、家計の予想物価上昇率のベンチマークに対する上振れが米国並みと仮定すると、2021年半ば頃までは2%台、2023年以降は3%程度となる(第1-2-26図(6))。2021年半ば頃までは、実際の家計の予想の中央値と整合的であるが、近年は、実際の予想の中央値が大きく上振れしていることが分かる。家計の予想物価上昇率は、食料品など身近な物価動向に反応する傾向があるという研究もあり52、現下においては、食料品価格の上昇・高止まりが続いていることが、家計の予想物価上昇率を大きく押し上げている可能性がある。その観点でも、コストプッシュによる食料品等を中心とした物価上昇から、賃金と物価の好循環の下、サービスを中心とした安定的な物価上昇が実現し、家計の予想物価上昇率が3%程度に安定化されていくことが重要と言える。

以上、本節では、物価の基調と背景を詳細に確認し、デフレ脱却に向けた現状を点検した。消費者物価上昇率(総合)については、2023年1月の前年比4.3%をピークとして、政策効果もあって、伸び率が徐々に縮小傾向で推移し、2023年11月以降は、おおむね2%台で推移してきた。ただし、2024年夏以降の天候不順の影響等により生鮮食品の高騰が続き、2024年12月には総合で前年比3.6%に高まったほか、円安の進行の影響もあって、2024年夏頃以降、それまで落ち着きつつあった食料品価格の上昇率が拡大傾向に転じている点には注意が必要である。
デフレに後戻りしないかどうかという点について、物価の背景を詳細にみると、需給ギャップはマイナスが継続しているものの、景気の緩やかな回復の中でマイナス幅は縮小傾向にある。景気の下振れリスクに留意が必要であるが、現時点で、需給バランスの面から物価が下落する蓋然性は高くない。仕入価格の販売価格への転嫁の状況をみると、非製造業を含めて、おおむねデフレに陥る前の姿に回復している。人件費の割合が相対的に高いサービス分野において、賃金から販売価格への転嫁の流れが進みつつあり、物価上昇の広がりとしても、デフレ以前の状況に近づきつつある。その賃金については、パートタイム労働者の時給は、最低賃金の引上げの効果もあって前年比4~5%での増加が続き、フルタイム労働者についても、33年ぶりの高水準となった春季労使交渉の賃上げの効果が、所定内給与の2%台後半の伸びという形で着実に発現している。ただし、フルタイム労働者の所定内給与については、中小企業や公的セクター等で賃金上昇の遅れがみられる。また、実質ベースのフルタイム労働者の定期給与は、2024年10月には2年7か月ぶりに前年比で増加に転じたが、同年11・12月には消費者物価上昇率の高まりから再び前年比で減少するなど、安定的にゼロを上回る状況には至っていない点にも留意が必要である。経済主体の予想物価上昇率をみると、企業は2%程度にレベルシフトした状態が継続し、市場参加者についても2%程度に向けて安定化しつつある。一方、家計の予想物価上昇率は、食料品など身近な商品の価格上昇が影響して上振れした状態にあり、消費者マインドを下押しし、GDPの過半を占める個人消費の力強い回復に至らない一因にもなっている。
総じてみれば、過去、四半世紀にわたり続いた、賃金も物価も据え置きで動かないという凍りついた状況が変化し、賃金と物価の好循環が回り始め、デフレ脱却に向けた歩みは着実に進んでいる。こうした背景には、輸入物価を通じたコストプッシュを契機とするものではあるが、2021年以降、国内物価の上昇率が高まり、約40年ぶりの物価上昇に直面する中で、政府による価格転嫁の円滑化の取組という後押しもあって、企業による原材料等の価格転嫁行動が変容したこと、そして、歴史的な水準への人手不足感の高まりの中で、賃上げ促進のための政策的後押しもあって、企業の賃金設定行動が変化してきていることがあると考えられる。こうした中で、企業や家計など経済主体において、物価と賃金が共に上昇するというノルムが形成されつつあるという変化もうかがわれる。このように、物価と賃金の設定や見通しに係る経済主体の行動や認識が過去とは大きく変わりつつある中で、日本経済はデフレやコストカット型経済に後戻りしないか、「賃上げと投資が牽引する成長型経済」に移行できるかどうかの分岐点にあり、物価・賃金の観点では、2%程度の物価上昇と、これを安定的に上回る賃金上昇の実現が極めて重要である。第2章においては、個人消費の背景を分析するとともに、その安定的な回復に不可欠な賃金上昇の持続性について議論することとする。
○「デフレ脱却」とは、「物価が持続的に下落する状況を脱し、再びそうした状況に戻る見込みがないこと」
○その実際の判断に当たっては、足元の物価の状況に加えて、再び後戻りしないという状況を把握するためにも、消費者物価やGDPデフレーター等の物価の基調や背景(注)を総合的に考慮し慎重に判断する必要がある。
(注)例えば、需給ギャップやユニット・レーバー・コスト(単位当たりの労働費用)といったマクロ的な物価変動要因
○したがって、ある指標が一定の基準を満たせばデフレを脱却したといった一義的な基準をお示しすることは難しく、慎重な検討を必要とする。
○デフレ脱却を政府部内で判断する場合には、経済財政政策や経済分析を担当する内閣府が関係省庁とも認識を共有した上で、政府として判断することとなる。

