第1章 マクロ経済の動向(第1節)
第1節 2024年の日本経済の動向と持続的回復に向けた課題
1 GDP等の動向
(我が国の名目GDPは初めて600兆円を超え、景気は緩やかな回復が続く)
はじめに、2024年における我が国のGDPの動きを確認する。名目GDPの長期的な動向を振り返ると、第1-1-1図(1)のとおり、1973年に100兆円を超えて以降1、およそ5年ごとに100兆円ずつ増加し、1991年中には500兆円となった。しかし、1990年代初頭にいわゆるバブルが崩壊し、1997~1998年のアジア通貨危機や日本の金融システム危機を経て、デフレに陥ったこと、2000年代後半には世界金融危機、2011年の東日本大震災、さらに2020年には新型コロナウイルス感染症の感染拡大など、外的ショックにも見舞われたことから、名目GDPは30年超にわたって500兆円台ないしその前後の推移が続いた。この間、賃金・物価が共に据え置きで動かないという状況が続いてきたが、コロナ禍後の世界的な需要回復や、2022年2月のロシアによるウクライナ侵略に伴う資源価格の高騰を背景とする輸入物価の上昇を起点として、国内物価の上昇が始まった。こうしたコストプッシュ型の物価上昇に対し、政府において価格転嫁と賃上げの取組を強力に推進したこともあって、2024年の春季労使交渉では33年ぶりとなる高い賃上げ率が実現し、賃金と物価がともに上昇する状況に至った。こうした中、名目GDPは2024年4-6月期には600兆円を超え、同年7-9月期には610兆円と過去最高の状況にある2。
次に、物価変動の影響を除いた実質GDPについて、2024年にかけての動向を確認する。2023年は、新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行もあって、日本経済は自律的な回復メカニズムを取り戻すに至ったものの、賃金の伸びが物価上昇に追いつかない状況の中、一進一退の状況が続いた。こうした状況に加え、2024年1-3月期には、一部自動車メーカーの認証不正問題や令和6年能登半島地震の影響といった特殊要因が重なった結果、個人消費や設備投資が落ち込んだことなどから、前期比マイナス0.6%のマイナス成長となった。その後、4-6月期以降は、賃上げの効果や堅調な夏のボーナスにより実質雇用者報酬が前年比で2021年7-9月期以来、2年3四半期ぶり増加に転じる中で、定額減税による可処分所得の押上げもあって、個人消費を中心に、前期比0.5%、0.3%と2四半期連続のプラス成長となった(第1-1-1図(2))。

(今回の景気回復局面は、製造業の輸出や生産ではなく、非製造業部門の改善が主因)
このように、日本経済は、引き続き緩やかな回復基調にあると考えられるが、2020年5月を谷とする今回の景気回復局面は、2024年12月時点において、55か月(4年半超)に達しており、戦後の景気回復(拡張)局面の中では、4番目に長い期間となっている3。このように、回復局面が長期化する中にあって、今後の持続性を展望する上で、近年の回復局面との比較を行い、今次の回復局面の特徴を改めて確認したい。比較の対象としては、戦後最長の拡張期間となった①第14循環(2002年1月~2008年2月の73か月)と、これに次ぐ②第16循環(2012年11月~2018年10月、71か月)とした(③は今回回復局面(2020年5月~))。まず、実質GDPについて、各回復局面の始点(谷)に当たる四半期の値を100として、その後のパスを描くと、③今回の回復局面はコロナ禍の大きな落ち込みからの回復から始まったこともあり、当初のGDP拡大ペースが大きいという違いはあるが、いずれの循環においても、緩やかな回復軌道をたどっていることが分かる(第1-1-2図(1))。GDPの過半を占める個人消費については、②第16循環では、2014年4月の消費税率引上げ前後の変動が大きいほか、個人消費の持ち直しのペースは他の循環に比べて緩やかであった(第1-1-2図(2))。③今次の回復局面は、実質GDPと同様、コロナ禍の落ち込みからの立ち上がりが強かったが、それ以降は、振れを伴いながらも、①第14循環と同様の緩やかな回復パスをたどっている。
これに対して、大きな違いがみられるのが、輸出の動向である。財貨・サービスを合わせた輸出でみると、①第14循環は、他に比べて、回復局面における伸びが突出して高く、輸出主導の景気回復であった姿が改めて確認できる4(第1-1-2図(3))。これに対し、③今回局面は、コロナ禍直後を除いて、②第16循環と近い回復ペースであるが、財輸出のみに着目すると、谷から1年経過して以降はほぼ横ばい圏内の推移であり、輸出全体の回復は、財輸出ではなく、コロナ禍の大きな落ち込みから回復したインバウンドを含むサービス輸出の力強い増加にけん引されていることが分かる(第1-1-2図(4)、(5))。また、①第14循環は、力強い財輸出の回復の後、2008年9月のリーマンブラザーズ破綻に端を発する世界金融危機に伴い輸出が急減し、②第16循環においては、景気の山(2018年10月)に先立つ2018年4-6月期に財輸出がピークを打っており、後述するように、米中間の貿易摩擦の高まりが影響した様子が確認される。
財輸出に関連して、製造業の実質付加価値の動向を確認する。ここでは、国民経済計算の参考系列として公表されている生産側系列の四半期速報(生産QNA)の計数を参照する。製造業GDPについては、各循環で財輸出とほぼ同様の推移をたどっており、①第14循環、②第16循環では、それぞれ世界金融危機、米中貿易摩擦の影響で、製造業の回復がとん挫した姿となっている(第1-1-2図(6))。これに対し、③今次の回復局面において製造業GDPは、コロナ禍直後を除いてほぼ横ばい圏内であり5、むしろ回復をけん引しているのは、サービス(第三次)産業である。第三次産業のGDPの回復経路を比較すると、③今回の回復局面は、コロナ禍での対面型サービスの大幅な悪化が谷となっていることから、その後の正常化の過程の中で、過去の回復局面と比べて相対的に高いペースで改善し、景気回復をけん引してきたことが分かる(第1-1-2図(7))。なお、①第14循環においては、世界金融危機の影響により、サービス業でも大きく付加価値が減少した一方、②第16循環では、景気の山を越えた後も比較的底堅く推移していたことが分かる。
最後に、民間設備投資を比較すると、それぞれ若干の違いはあるものの、回復局面において総じて緩やかな増加傾向をたどっているという点については共通している(第1-1-2図(8))。過去2回の回復局面、特に①第14循環は、財輸出の増加が主因となって、製造業の生産と設備投資が景気回復を支える姿が鮮明であった一方、③今回の局面は、製造業部門は横ばい傾向である中にあっても、設備投資の持ち直し基調が実現している。こうした背景には、例えば、非製造業を含め、DX・デジタル化の推進や、人手不足対応の省力化投資、さらにはコロナ禍を機に更に高まったEC需要対応の倉庫施設やインバウンド需要対応の宿泊施設の建設投資など、循環的というよりは、より構造的な観点で投資の成長が実現していることが考えられる。また、製造業については、今回の局面では、輸出・生産の増加はみられないものの、為替レートの急速な円安の進行の中で、企業収益が過去の回復局面と比べてより強く増加し、こうした堅調な収益の範囲内で、将来の成長に向けた投資が実行されてきた、という可能性もある。
以上のように、今回の景気回復局面は、コロナ禍での落ち込みからの回復を起点としたこともあり、サービス部門中心の回復であり、製造部門の輸出・生産にけん引された近年の長期的な回復局面とは、特徴を異にするものとなっている。その意味において、海外景気の下振れに対する脆弱性は過去とは異なっていると考えられる。ただし、例えば、後述するように、第16循環において景気後退の要因となった貿易摩擦については、直接・間接的に製造業を下押ししうるものであり、こうしたショックの大きさによっては、景気後退に入るリスクがあるという点には、十分注意する必要がある。

コラム1-1 2020年産業連関表とGDP統計の基準改定
GDP統計(国民経済計算)においては、おおよそ5年に一度公表される大規模な基礎統計を反映して、過去の計数を再推計・改定する「基準改定」が約5年ごとに行われる。こうした基礎統計のうち、GDPやその内訳項目の水準に大きな影響を与えるものが「産業連関表」(総務省等10府省庁)であり、直近の2020年を対象とする産業連関表(2024年6月公表。以下、「2020年表」という。)を取り込んだGDP統計の次回の基準改定(以下、「2020年基準改定」という。)は、2025年度中に予定されている。
2020年表においては、多くの部門の生産額推計の作成の基となる総務省・経済産業省「経済センサス-活動調査」におけるサービス分野の生産物分類の導入といった改善や、建設部門の推計に用いられる国土交通省「建設工事施工統計」における母集団推計の改善の結果などが反映され、精度の向上が図られている。ここでは、総固定資本形成に係る、いくつかの部門について、新たに2020年表を取り込むことにより、2020年時点の総固定資本形成の水準に生じうる改定の程度を簡易的に把握する観点から、現行基準のGDP統計の基となっている2015年産業連関表における、これら部門の最終需要先としての総固定資本形成額について、現行基準のGDP統計における2015年から2020年にかけての伸び率で延伸した場合の2020年値(延伸2020年値)と、2020年表における値(2020年表値)とを比較する。この場合、例えば、①建設部門については1兆円強、②不動産(仲介手数料)部門では2.5兆円、③情報サービス(ソフトウェア)部門では8兆円弱、2020年表値が延伸した2020年値を上回っていることが分かる。このうち、①は「建設工事施工統計」における母集団推計の改善、②・③は精度が向上した「経済センサス-活動調査」の反映に拠る。
これらは、GDP統計の2020年基準改定に際して、総固定資本形成の改定につながりうるものであるが、以下の点に留意が必要である。すなわち、第一に、上記は、総固定資本形成について改定要因となる主な部門を例示として取り出したものであり、ここで取り上げていない他の部門、あるいは最終消費支出等について、産業連関表以外の基礎統計が取り込まれることなどの影響も相まって、各需要項目の水準は上方・下方のいずれにも改定されうる。第二に、上記の改定要因は、過去に遡って適用されうるものであり、2011年や2015年との「接続産業連関表」において、同様の改定が行われる可能性があるため、総固定資本形成の伸び率という観点では基本的には改定要因とはならないと考えられる。このほか、GDP統計の2020年基準改定においては、建設投資に係るデフレーターについて、従来の人件費や資材価格といった投入コストに基づくインプット型から、建設業のマークアップ率の変化を一部加味したアウトプット型に切り替えられるなど、実質GDPの改定要因となる変更も実施されることにも留意が必要である。
2 家計部門の動向
(実質所得が増加に転じる中、個人消費も増加に転じているが、力強さに欠ける)
次に、家計部門の動向を個人消費、住宅投資、雇用情勢から確認する。ここではまず、GDPの約54%を占める個人消費の2024年後半にかけての動向を整理する(第1-1-3図)。2023年は、5月の新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行や、春季労使交渉におけるベアで2.12%という30年ぶりの賃上げという後押しがあったものの、名目所得の伸びが物価上昇に追いつかない中で、個人消費は力強さを欠く状況が続いた。さらに、2024年1-3月期には、令和6年能登半島地震の影響のほか、一部自動車メーカーの認証不正問題に伴う出荷停止の影響により新車販売台数が大きく落ち込み、個人消費は下押しされたが、その後、2024年4-6月期以降は、自動車販売の出荷停止からの回復を含む一時的要因もあって、2四半期連続の増加となった。

個人消費の背景は、主に消費者マインドと賃金・所得環境からなり、消費者マインドについては、第2章で詳述するように、食料品など身近な品目の価格上昇の影響などによる予想物価上昇率の高まりを通じて、足踏みがみられる状況にある。賃金・所得環境については、ベアで3.56%という33年ぶりの高水準となった春季労使交渉の賃上げの反映や、堅調であった夏のボーナスの効果、さらには雇用者数の緩やかな増勢もあり、総雇用者所得(雇用者数×一人当たり賃金)は、名目で着実に増加し、実質でも2024年6月に34か月ぶりに前年比プラスに転じた後、5か月連続で増加している(第1-1-4図)。また、GDPベースの家計の可処分所得は、2022年4-6月期以降、実質で前年比減少が続いていたが、賃上げの効果に加え、定額減税やこれと一体的に措置された給付金の効果もあって、2024年1-3月期以降、前年比プラスに転じている。
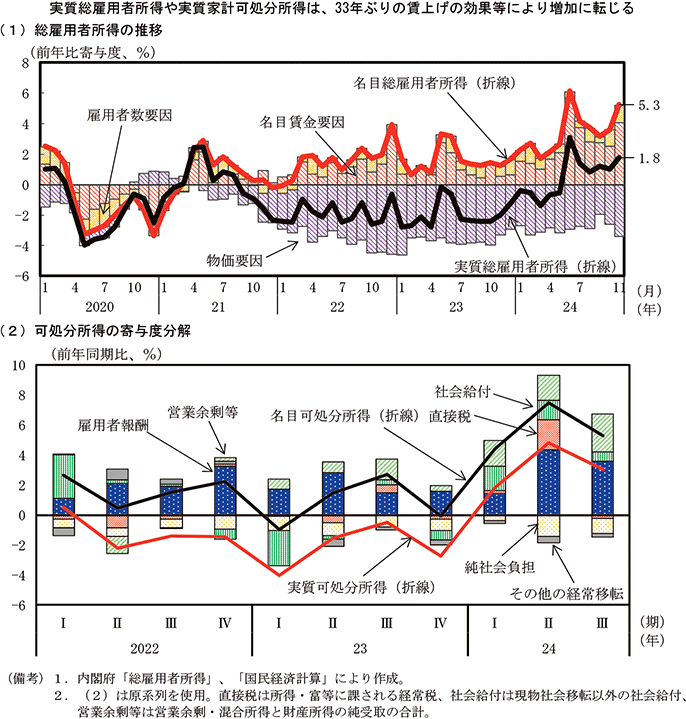
個人消費を主な形態別にみると、6割弱を占めるサービス消費は、緩やかな持ち直し傾向が続いている。外食については、売上高の増加傾向が続いており、客単価上昇の影響もある一方で、客数でみても、着実に持ち直し傾向が続き、コロナ禍前の水準近くまで回復しつつある(第1-1-5図(1))。また、旅行に関して、日本人延べ宿泊者数は、インバウンド需要の増加と宿泊業の人手不足による供給制約という需給ひっ迫を背景とした宿泊単価の上昇が、家計の実質所得の減少傾向と相まって、需要の下押し要因となっていたが、賃金・所得環境の改善もあって、2024年秋には増加傾向を示している(第1-1-5図(2))。また、2024年度の年末年始は、9連休という日並びの効果もあって、交通機関の利用者数が堅調に推移している(第1-1-5図(3))。海外旅行者数(出国日本人数)も、2024年末時点でコロナ禍前の水準を依然3割程度下回っているが、緩やかな増加傾向にあるなど(第1-1-5図(4))、旅行消費は全体として持ち直しの動きがみられている。

一方、2024年4-6月期以降の個人消費の増加には、前述したとおり、各種の一時的要因が影響した面もある点には留意が必要である。前掲第1-1-3図のとおり、2024年4-6月期以降、耐久財(個人消費の約8%)と非耐久財(同約3割)が2四半期連続で増加に寄与しているが、このうち、耐久財については、猛暑を背景としたエアコン、新製品の発売を背景とした携帯電話も増加に寄与したとみられる6一方で、上述の自動車出荷の認証不正問題の影響からの回復も消費の押上げにつながった(第1-1-6図)。加えて、非耐久財については、2024年8月に、南海トラフ地震臨時情報が発表されるとともに、台風が相次いで日本列島に接近したことから、飲料や即席食品といった食料品をはじめ防災関連財の備蓄需要が増加したことが、2024年7-9月期の消費の押上げに寄与した7。

以上のように、2024年度に入り、個人消費は増加傾向に転じているものの、賃金や所得の増加に比べれば、その伸びは抑制的であり、さらに、上記のような一時的要因による押上げ効果を考慮すれば、消費の伸びは力強いものであるとは言い難い。この結果、家計全体の貯蓄率は、2024年に入って以降上昇し、コロナ禍前より高い水準で推移している(第1-1-7図(1))。世帯属性別にみると、高齢無職世帯では、相対的に低収入の世帯を中心に、コロナ禍前の貯蓄率の水準を下回っており、年金等の所得の伸びが物価上昇に追いつかない中で、貯蓄を取り崩し、必要な消費に充てていることがうかがわれる(第1-1-7図(2)①)。一方、勤労者世帯については、収入の多寡を問わず、貯蓄率が、総じてコロナ禍前の水準より切り上がった状態で緩やかに上昇している(第1-1-7図(2)②)。このように、貯蓄率が上昇、もしくは平均消費性向が低下している背景には老後不安を含めて様々な要因があり得る。この点については、コロナ禍以前からの勤労者世帯の平均消費性向の緩やかな低下傾向についての分析と合わせて、第2章において詳述する。

コラム1-2 2024年夏における猛暑や台風等の影響
2024年の夏は記録的な猛暑となったことに加え、8月には台風が相次いで日本列島に接近・上陸した。また、8月初旬には、宮崎県日向灘を震源とする地震に伴い南海トラフ地震臨時情報が初めて発表されるに至った。本コラムでは、こうした天候や災害の要因が個人消費にどのような影響を与えたかについて整理する。
まず、今夏は全国各地で連日猛暑日(最高気温が35℃以上)が記録され、全国に914ある観測所のうち、猛暑日を記録した地点数は、2024年7月から9月のいずれも、2021年以降で最も多くなるとともに、9月の猛暑日の日数は近年で特出して多く、残暑が長引いた(コラム1-2-1図)。

こうした猛暑の消費への影響は、プラス・マイナス両面あったと考えられる。内閣府「景気ウォッチャー調査」の家計動向関連の現状判断DIについて、「暑」や「温」に言及したウォッチャーのDIと平均の差をみると(2024年7月調査、コラム1-2-2図)、業種によってばらつきがある。エアコンやアイスクリーム、飲料の売上が好調だったことから、家電量販店やコンビニにおいてはプラスとなった一方、猛暑による外出控えにより客足が遠のいた影響でテーマパークなどのサービス、レストランなどの飲食においてはマイナスとなった。後述するように、防災関連商品の備蓄需要の影響で売上が伸びたスーパーも、猛暑はマイナス要因に働いたとみられる。
次に、自然災害については、8月8日に宮崎県日向灘を震源とするマグニチュード7.1の地震が発生したことに伴い、気象庁より、南海トラフ地震の想定震源域では、大規模地震の発生可能性が平常時に比べて相対的に高まっているとして、同日、「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」が発表された。これに伴い、政府から、日頃からの地震への備えの再確認や、地震が発生した際にすぐに避難できる準備することなどの「特別な注意の呼びかけ」が行われた(8月15日に「特別な注意の呼びかけ」は終了)。さらに、8月中旬には台風8号が日本列島に接近したほか、8月30日から9月1日には台風10号が接近・上陸し、8月28日から31日にかけて、気象庁より暴風等の特別警報が発表された。
こうした自然災害は2024年夏の経済の動きに様々な影響を与えた。マイナス面としては、例えば、台風10号の接近に際し、東海道新幹線の計画運休(8月30日~9月1日)が行われるなどにより旅客者数が下押しされるとともに、宿泊予約のキャンセルにもつながったとみられる(コラム1-2-3図)。また、南海トラフ地震臨時情報の発表やこれに伴う「特別な注意の呼びかけ」に関しては、太平洋側を中心に各種のイベントが中止となり、宿泊予約のキャンセルも発生した。そこで、ビッグデータにより、宿泊稼働指数の動向をみると、2024年8月は、南海トラフ地震臨時情報が発表された後、中旬にかけて例年より幾分低下がみられたとともに、台風が接近した8月末にかけては、大きく低下したことが分かる。ただし、9月に入って以降は早期に例年並みに回復した。


他方、南海トラフ地震臨時情報や台風接近については、人々の防災への意識につながり、飲食料品をはじめとする防災関連商品の備蓄需要が増加する面もあった。POSデータから、スーパー等の売上高をみると、2024年8月は、前月よりも販売数量が増加することにより、売上高が増加したことが分かる(コラム1-2-4図)。個別商品についてみると、特に、水や即席食品、電池などの防災関連商品の売上高が、8月8日直後、中旬、末に大きく伸びていることが確認される。こうした防災関連財の備蓄需要の高まりは、本論でも述べたとおり、2024年7-9月期の非耐久財消費を押し上げる要因となった。

(住宅投資は、建築コストの高止まりの中で、横ばい圏内の動きが継続)
次に、GDPの4%程度を占める住宅投資の動向を確認する。住宅は、家計が持家として購入する場合は同部門の投資として、借家の場合は貸主部門(民間ないし公的の企業、もしくは家計)の投資として計上されるが、住宅投資の8割超は家計であることから8、ここでは家計部門の支出として扱う。
まず、住宅投資の動向を先行的に把握することのできる新設住宅着工戸数の動向をみると、全体としては、2023年秋以降、主に建築費の上昇・高止まり等の影響から、弱含みの動きが続いていたが、2024年半ば頃からはおおむね横ばいで推移している(第1-1-8図(1))。戸建住宅のうち、持家(注文住宅)の着工は、建築費の高止まりが続く中で、弱含みから横ばい圏内で推移していたが、価格が高止まる中にあって、高付加価値住宅への需要など、受注が底堅く推移していることから、2024年半ば以降は底堅く推移している。また、分譲戸建(建売住宅)も、建築費の高止まりによる販売不調から在庫の過剰感がみられ、着工戸数の減少が続いていたが、在庫調整が一服する中、2024年秋時点では下げ止まっているとみられる。
次に、共同住宅のうち、分譲共同住宅(マンション等)については、他の形態と同じく建築費の高止まりに加え、マンションに適した大規模土地取得が近年容易ではないという事情もあって、大規模土地取引件数を均してみると、緩やかな減少傾向にあり、着工戸数は振れを伴いながら、トレンドとしてはおおむね土地取引件数と整合的に推移している。貸家についても、月々の振れが大きいが、法人(不動産会社やREIT)による建設は底堅い一方で、家計(個人)による建設は低調に推移している(付図1-1)。背景には、賃料が上昇傾向にあるものの、建築費の高止まりなどもあって、賃貸利回りが低下していることがあると考えられる。
ここで、各形態の着工戸数に影響を与えている建築費の動向をみると、木造、RC造を問わず上昇傾向が続いている(第1-1-8図(2))。建設工事費デフレーターの内訳をみると、原材料コストの上昇は一服する一方で、人件費要因が拡大傾向にある。建設業では、中小企業を含めて労務費を含むコストの価格転嫁が相対的に進んでいることを反映していると考えられる(第1-1-8図(3))。

次に、住宅ローン金利の動向を確認する(第1-1-9図(1))。我が国では、新規貸出額の8割弱が変動金利型9であることから、まず、変動金利の動向をみる。住宅ローン変動金利は、短期プライムレートが参照され、短期プライムレートは政策金利(無担保コールレート(オーバーナイト物))に連動する。政策金利は、日本銀行による2024年3月のマイナス金利政策の解除10の後、同年7月に0.25%程度への引上げが行われ、短期プライムレートは、2024年9月に、2007年3月以来17年半ぶり上昇した11。この中で、変動金利も2024年10月にメガバンクを含む各行が基準金利を0.15%程度引き上げた影響で足下ではやや上昇している。また、固定金利については、長期金利(新発10年債利回り)が緩やかに上昇する中、これに連動して上昇しているが、長い目でみれば低い水準にある。
こうした中で、日本銀行「主要銀行貸出動向アンケート調査」における個人向け住宅ローンの資金需要判断DIをみると、2024年10月時点ではおおむねゼロ近傍で推移しており、悪化しているという姿にはない(第1-1-9図(2))。このように、現時点では、住宅ローン金利の上昇は限定的であり12、今後の動向は注視する必要があるものの、住宅投資需要への影響は顕在化しているとはみられない。

次に、新設着工以外の住宅投資の動向について確認する。GDPの住宅投資には、新設着工に伴う投資額のほか、既存住宅の耐用年数の延伸など機能向上につながるリフォーム投資や、所有権移転費用として中古住宅の売買に伴う仲介手数料13が含まれる。こうしたリフォームは住宅投資の1割強、仲介手数料は1割台半ばと、合わせて住宅投資の4分の1程度を占めている(付図1-1)。中古住宅の販売量14については、建築費による新築住宅価格の上昇の中で、価格面での相対的な優位性から、新築の着工戸数とは対称的に、戸建・マンションともに増加傾向で推移している(第1-1-10図(1))。仲介手数料の代理指標として、不動産取引業の売上高を対応する物価指数で除した実質値でみると、販売量には遅行しているものの、このところ緩やかな増加がみられている(第1-1-10図(2))。
リフォームについても、受注高をみると、省エネリフォームへの各種補助金の効果もあって、振れを伴いながらも増加傾向にある(第1-1-10図(3))。ただし、建設補修の建設デフレーターで除した実質値については、工事費の上昇継続により、横ばい圏内となっている。人口減少や単身世帯の増加など人口・世帯構造が変化する中で、持家を中心に住宅需要は長期的には減少傾向で推移することが見込まれる一方、住宅ストック戸数は世帯数を上回る状況が続いており、今後は、リフォームの促進を含め、中古住宅取引市場の活性化を進め、豊かなストックを有効活用していくことが一層重要となる15。比較的安価な既存住宅ストックを有効活用することにより、ゆとりある暮らしと豊かさを感じられる経済社会につなげていくという視点が必要となろう。

(高い人手不足感が続く中、女性の正規雇用を中心に、就業率は上昇が続く)
次に、雇用情勢を確認する16。まず、企業の人手不足感について、日銀短観の雇用人員判断DIをみると、非製造業において、バブル期以来の過去最大水準の不足超過であるなど、引き続き歴史的な高水準にある(第1-1-11図(1))。非製造業の中では、インバウンド需要が旺盛な宿泊・飲食サービス、医療・介護を含む個人サービスのほか、いわゆる2024年問題17もあって建設や運輸・郵便といった産業で人手不足感が特に高い状況にある(第1-1-11図(2))。

厚生労働省「労働経済動向調査」により、雇用形態別の人手不足感をみると、正社員・パートタイム労働者ともに高い不足感がみられるが、特に正社員の不足感が強い(第1-1-12図(1))。ビッグデータにより、求人数の推移を確認すると、正社員では、ハローワーク経由の求人は横ばい傾向で推移している一方、民間職業紹介経由の求人は増加傾向が続いている(第1-1-12図(2)①)。転職求人倍率については、事務職では1倍を下回る低位で推移している18ものの、エンジニア等の職種で労働需給が特にひっ迫している(第1-1-12図(3))。他方、パートタイム労働者の求人数は、ハローワーク経由に比べると、民間職業紹介経由では、より明確な増加傾向で推移してきたが、2024年末にかけては前年比で減少に転じている(第1-1-12図(2)②)。職種別には、飲食や販売・接客が前年比の減少傾向の主因となっていることが分かる(第1-1-12図(4))。こうしたパート求人数の減少傾向の背景には、女性を中心とした正規雇用者数の増加という流れのほか、自動レジや配膳ロボット等に代表される省力化投資が奏功している表れという可能性もある。このほか、飲食関係等では、近年増加傾向にあるアプリを活用したスポットワークへのシフトが進んでいることも考えられる(第1-1-12図(5))。一方で、パートタイム労働者の時給が高まる中で、人件費上昇による収益下押しを回避する観点から新規の求人を手控えている可能性もあり、今後の動向には留意が必要である。

このように、労働市場が総じてひっ迫している中、完全失業率は、2%台半ばという低い水準で安定して推移している(第1-1-13図(1))。就業者数を15歳以上人口で除した就業率も緩やかな増加傾向が続いている(第1-1-13図(2))。性別・雇用形態別に雇用者数をみると、女性が全体の上昇をけん引しており、女性の中では、非正規雇用者がおおむね横ばいの一方で、正規雇用者は増加傾向が継続している(第1-1-13図(3)、(4))。女性の正規雇用者の近年の増加について、産業別の内訳をみると、医療・福祉や情報通信業のほか、製造業や教育・学習支援業等で増加傾向にある(第1-1-14図(1))。製造業や教育・学習支援業については、女性の非正規雇用者数は緩やかな減少傾向(第1-1-14図(2))にあることから、女性の正規雇用者比率が高まっていると言える。一方、女性の非正規雇用者について、世帯主である非正規雇用者の推移をみると、高齢化もあって、単身を中心に増加傾向にあり、2023年時点では約300万人(女性の非正規雇用者の約2割)に高まっている(第1-1-14図(3))。二人以上世帯の世帯主は、54歳以下のシェアが6割弱と多く、子育て世代に当たることから、ひとり親世帯が相応の割合を占めると考えられ、所得環境が厳しい状況に置かれているとみられる(第1-1-14図(4))。こうした世帯の動向について引き続き注視するとともに、男女間賃金格差の縮小や、リ・スキリング、正規化の促進等を通じて所得の向上を支援していくことが重要である。


3 企業部門の動向
(企業の業況感は、幅広い業種で改善が継続)
次に、企業部門の動向について確認する。企業部門は、業況感、収益、設備投資計画など総じてみて堅調さが続いているが、上述したように、景気回復局面が2020年5月を谷として、約4年半と長期間に入り成熟化している中で、変調の兆しが表れていないか、以下では2024年の動向を確認していきたい19。
まず、企業の業況感を日銀短観の業況判断DIから確認する。全体としては、改善が続いており、特に売上高の7割を占める非製造業は、大企業や中小企業を含めて、1990年代初めのバブル期以降で最高水準を維持している20(第1-1-15図(1))。製造業については、2024年初めには、自動車認証不正問題に伴う出荷・生産の停止事案により、4四半期ぶりにDIが一時的に低下する局面もみられたが、その後の自動車生産の回復や、世界的な半導体需要の回復に伴う半導体製造装置の堅調な売上にけん引されて改善傾向が続いている(第1-1-15図(2))。
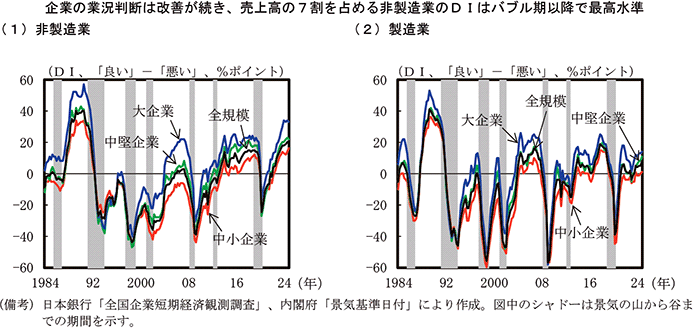
このように企業の業況感は総じて改善しているが、より詳細な業種をみると、製造業については、多くの業種でDIは安定している中で、鉄鋼や食料品ではDIが低下傾向にある(第1-1-16図(1))。鉄鋼は、中国経済の足踏みなど、市況の悪化等から、業況が悪いという回答割合が増加傾向にあり、「悪い」超となっている。食料品は、DIは低下しているものの、「良い」超の状態は続いており、過去よりも原材料等の価格転嫁が進展していることを示している21。一方、直近では、「悪い」の回答割合がやや増加するとともに、「良い」の回答割合がより減少しており22、食料品価格の上昇に直面する消費者の節約志向が業況感の下押しに影響している可能性がある。
非製造業については、運輸、建設、不動産といった広範な産業で「良い」の回答割合が「悪い」の回答割合を大きく上回り、改善傾向が続いている(第1-1-16図(2))。この中で、宿泊・飲食サービス等は、コロナ禍の落ち込みの後、経済活動の正常化やインバウンドの回復により大きく改善し、DIは過去最高水準の「良い」超となっているが、過去1年程度は横ばい圏内であり頭打ちの兆しもみられる。背景には、人手不足に伴う人件費の上昇による収益の下押しという要因も考えられるが、BtoC主体のサービス分野であり、家計部門の賃金・所得の伸びが安定的に物価上昇を上回る状況には至っていない中で、国内消費需要が力強さに欠ける点を反映している可能性もある。
以上のように、一部の業種を除けば、全体的に業況感は良好な状態が続いていると評価できるが、海外経済の下振れによっては、製造業を中心に業況感が下押しされるリスクもあり、注視が必要である23。

(企業収益は総じて改善しているが、そのテンポは緩やかになっている)
次に、企業収益の動向を、財務省「四半期別法人企業統計」からみると、全体として、経常利益や営業利益はいずれも増加傾向がこれまで続いてきたが、直近2024年7-9月期は、経常利益を中心に対前期比で減少するなど、増加のテンポが緩やかになっている(第1-1-17図)。前年同期比でみると、経常利益は2023年1-3月期から2024年4-6月期まで6四半期連続の増益となった後、2024年7-9月期は減益となり、営業利益は7四半期連続の増益となったものの、2024年7-9月期の伸びは大きく縮小している。

この間の経常利益の動向を要因別にみると(第1-1-18図)、製造業では、売上高は恒常的に増加に寄与する中で、2023年末には、輸入物価の下落もあって原材料費等が減少し、変動費要因がプラスに寄与していたが、輸入物価の下落幅が縮小し、上昇に転じる中で、プラス寄与が縮小している。このほか、賃金が上昇する中で、2023年半ば以降、人件費が利益に対して下押しに寄与したほか、2024年7―9月期は営業外収益が大きく減少に寄与した。これは、それまで急速に進んだ円安が是正され、企業の保有する外貨建て資産の評価損(為替差損)が生じたことによるものとみられる。以上の状況は、規模別にみてもおおむね同様であるが、中小企業においては、変動費要因がほぼ一貫して大幅な減益方向に寄与しており、この間の円安の急速な進行の中で、輸入原材料費等の増加が収益を下押しした様子がうかがえる。
非製造業についても、売上高の増益への寄与が続く中で、変動費の減少によるプラス寄与は足下にかけて縮小している。人件費要因も、製造業に比べ、人手不足感がより強く、業種によっては賃金上昇が大きいこともあり、より減益要因に寄与している。このうち、中小の非製造業については、売上高による増益寄与が相対的に小さい中で、人件費を含むコスト要因が、利益の減少に寄与している。

(円安の企業収益押上げ効果は、大企業にはみられるが、中小企業にはみられず)
このように、企業収益は、総じてみれば改善が続いているものの、円安進行も通じた変動費増加や賃上げに伴う人件費増加といったコスト要因が中小企業24の利益を下押しする状況にある。為替レートの動向をみると、2022年初めには1ドル110円台半ばであったが、その後、振れを伴いながら円安ドル高方向に進行し、2024年7月上旬には1ドル161円台を記録した。その後、米国における市場予想を下回る経済指標等もあって、一旦円安が是正されたが、2024年末にかけては再び1ドル150円台後半となっており、この3年間で3割程度、円安ドル高が進んだ。為替レートと収益の関係について確認すると、まず、内閣府「企業行動に関するアンケート調査」においては、2024年1月調査時点で、上場企業の輸出企業における採算為替レートは1ドル120円台半ばとなっている。採算為替レートは、調査時点における実際の為替レートに影響を受けるという面はあるが、2024年12月時点の実勢レートは、採算レートよりも2割程度円安であり、大企業の輸出企業にとっては引き続き増益に寄与する要因であることが分かる(第1-1-19図(1))。また、日銀短観における輸出企業の想定為替レートは、2024年度下期で1ドル145円程度であり、現状の為替レートの水準は、これよりもやや円安であることから、やはり、輸出企業の収益にとって為替レートは押上げ要因と言える(第1-1-19図(2))。

一方、中小企業に関しては、日本商工会議所の調査(2024年6月末時点)によると(第1-1-20図)、円安基調が業績に与える影響として、中小企業の55%が「デメリットが大きい」とし、その背景としては、原材料等の価格上昇が多く挙げられている。また、中小企業が自社にとって望ましい為替レートとして、1ドル110円から135円を挙げる企業が約7割と大宗であり、中小企業においては十分に価格転嫁が進んでいない現状を踏まえると、現在の実勢レートは、中小企業の収益にとっては好ましいものとはなっていない。

為替レートの変動が企業収益に与える影響として、2000年代以降について、短観における経常利益の修正率を、想定為替レートの変化等で回帰分析した結果をみてみると、大企業製造業では、期間を通じて一貫して、円安方向への変化は、経常利益を有意に押し上げる傾向がある。また、大企業非製造業でも、期間前半は有意な関係性がみられないが、2010年代前半以降は有意な正の関係がみられ、これはインバウンド需要の収益への重要度が増してきたことを反映している可能性がある25(第1-1-21図(1))。一方、中小企業については、非製造業は期間を問わず為替と収益の間に有意な関係がみられず、製造業についても、2000年代には円安が企業収益を有意に押し上げていた一方、近年はこうした関係がみられない(第1-1-21図(2))。このように、為替レートの円安は、中小企業では、製造業を含めて、収益面での好影響が必ずしもみられないことが確認される26。

なお、企業収益が総じて堅調に推移する中で、企業の資金余剰の状況を確認すると、まず、フロー面として、非金融法人企業の貯蓄投資差額は、1990年代後半以降、貯蓄超過、すなわち資金余剰状態が続いている。直近では縮小傾向にあるが、多くの主要国では、20年以上にわたり企業部門が資金余剰という状態にはなく、これと比べると日本のこの四半世紀は異質であることが分かる(第1-1-22図(1))。また、ストック面として現預金の売上高比率をみると、2000年代後半の世界金融危機を経て、上昇傾向で推移し、さらに、コロナ禍の2020年を経て、中小企業を中心に切り上がり、過去最高水準で推移していることが分かる(第1-1-22図(2)①)。主要国と比較すると、日本の非金融法人企業の現預金残高はGDPの6割(367兆円)と突出しており、高止まった状況にある(第1-1-22図(2)②)。企業の資金余剰については、危機やショックに対して、金融機関からの資金繰りが悪化するリスクへの備えとして流動性資産を積み上げているという予備的な側面もあるとみられるが、豊富な資金が、賃金や投資に十分には回っていないということでもあり、こうした資金を賃上げや投資拡大に回すことにより、民需主導の成長型経済を実現することが極めて重要である。

(製造業の生産は持ち直していくことが期待されるが海外経済の不確実性に留意)
次に、生産の動向について、鉱工業指数をみると、2024年初以降、世界的なシリコンサイクルの回復の中で、半導体製造装置やICにけん引されて持ち直しの動きがみられた後、同年末にかけては、全体として横ばい傾向で推移している(第1-1-23図(1))27。主要な業種の動向をみると、輸送用機械は、2024年初には、一部自動車メーカーの認証不正問題に伴う生産・出荷停止の影響で大きく落ち込んだ後、出荷停止が徐々に解除される中で、同年半ばにかけて回復していった。その後、一部メーカーにおける、8月末の台風10号の接近に伴う数日間の稼働停止の影響等による振れを伴いながら、おおむね横ばいで推移している。その背景には、メーカーにおいて、認証不正問題を踏まえ生産体制を見直し、余裕をもった生産を行う動きが続いてきたことがあるが、今後は徐々に稼働率が引き上がっていくことが期待される。
生産用機械については、品目によってばらつきがみられるが、全体としては横ばい圏内で推移している(第1-1-23図(2))。半導体製造装置は、上述のとおり、世界的な半導体市場の回復の中で、生成AI向けの半導体製造装置の需要増や、半導体の国産化を進める中国向けの輸出増によって、2023年後半から2024年半ば頃にかけて増加傾向で推移した。その後、車載向けや産業機械向けの半導体需要に弱さがみられるほか、中国向け輸出の増加ペースが一服する中で、2024年夏頃には横ばい圏内で推移する局面もあったが、2024年末にかけては再び緩やかな増加傾向にある。先行きも、生成AI向けを中心とする半導体需要は引き続き旺盛とみられることから、半導体製造装置の生産は基調としては底堅く推移することが期待される。一方、建設・鉱山機械は、2023年秋頃にかけて増加傾向で推移してきたが、その後、欧米における既往の高金利水準の影響による建設投資需要の弱まりもあって、これら地域向けの輸出が減少傾向となり、在庫の増加及び生産の減少がみられた。2024年末には、欧米における金利引下げの影響もあって、海外需要の下げ止まりの兆しがみられる。また、産業用ロボットや金属加工機械等の工作機械は、中国経済の足踏みの影響もあって、2024年春頃にかけて減少傾向で推移してきたが、中国からの受注が持ち直す中で下げ止まっており、増加に向かうことが期待される。ただし、景気が足踏みしているドイツなど欧州からの受注は前年比で減少傾向にあるなど、先行きには不透明感がある。
また、電子部品・デバイスについては、2023年半ば以降、世界的な半導体需要の回復の中で、生産が増加傾向に転じ、2024年後半にかけて持ち直しが続いてきたが、その後は、このところ弱含みとなっている(再掲第1-1-23図(1))。これは、世界の半導体サイクルの中で、半導体の用途に応じて、動向にばらつきがみられることを反映している。具体的には、現状、世界的な半導体需要の増加を支えているのは、生成AIやサーバー向けに用いられる最先端品のメモリやロジックである一方、自動車や産業機械向けの需要は低調である。また、PCやスマートフォンといった家電向けは生成AI向け等ほどの力強い増勢はみられておらず、2024年末にかけては、世界のPC・スマートフォンの出荷台数の増加が頭打ちとなっている(第1-1-23図(3))。世界全体としては、2023年の半導体の売上高のうち、主に生成AIやサーバー向けに用いられるロジックのシェアが約3分の1と最も大きく、2025年には更なる需要の増加が予測されているのに対し、日本メーカーにおいては、現時点ではこれらの生産は限定的であり、需要の弱い自動車・産業機械や家電向けに強みがあるとされる(第1-1-23図(4)、(5))。こうした状況を映じて、日本の電子部品・デバイスにおいては、出荷の伸びが頭打ちとなり、出荷・在庫ギャップ(出荷の前年比-在庫の前年比)のプラス幅が縮小している(第1-1-23図(6))。
製造業の生産の先行きとしては、海外景気の持ち直しが継続する下で、持ち直しに向かうことが期待されるが、中国経済をはじめとする海外景気の下振れリスクや、後述するように米国の政策動向による影響等には十分注意が必要である。

(知的財産投資が設備投資の増勢をけん引、国際的にみれば更なる拡大余地)
設備投資については、名目では、2024年4-6月期に33年ぶりに過去最高を更新し、約106兆円まで増加している(第1-1-24図(1))。物価変動を除いた実質でも緩やかな増加傾向が続いている。名目設備投資の形態別の動きを試算すると、ソフトウェアや研究開発を含む知的財産生産物が一貫して増加し、設備投資全体の増加基調をけん引している(第1-1-24図(2))。2024年9月調査時点の日銀短観に基づく2024年度設備投資計画(前年度比)と、「四半期別法人企業統計」に基づく2024年度上半期の設備投資実績(前年同期比)を比較すると、近年は、実績が計画の伸びを下回る状況が続いてきたが、2024年度については、非製造業の設備投資が堅調であったことから、上半期時点では計画対比で遜色のない実績となっている(第1-1-24図(3)①)。設備投資計画は、2024年12月調査時点でも前年度比+10.0%と、9月調査時点と同様であり、+9.4%と高い伸びだった2023年度から更に増加する計画となっており、企業の投資意欲は引き続き旺盛であると評価できる(第1-1-24図(3)②)。

形態別に詳細を確認すると、設備投資の約44%を占める機械投資については、一致指数の資本財総供給は、半導体製造装置を中心に振れを伴いながら、おおむね横ばいで推移し、先行指数の機械受注(船舶・電力を除く民需)は、持ち直しの動きに足踏みがみられる状況が続いた(第1-1-25図(1))。原材料コストの上昇や、中国経済など海外景気の先行き不透明感を背景に、製造業を中心に設備投資の先送りや手控えが生じていた可能性がある。ただし、機械受注は、2024年末には製造業を中心に持ち直しの動きがみられ、また、外需や官公需等を含むことに留意は必要であるが、機械受注残高は高水準で増加傾向にあり、これらが実際に発注企業に納入されていけば、設備投資として着実に顕在化していくことが期待される(第1-1-25図(2))。

建設投資(設備投資の約27%)については、先行指標の建設工事費予定額は、2023年半ば以降、製造業の生産能力増強やEC需要に対応した運輸業の倉庫需要等から急速に増加した後、2024年夏以降にこうした動きは一服したが、インバウンド需要に対応した宿泊施設の新増設もあって、緩やかなテンポでの増勢が続いた(第1-1-26図(1))。このように着工額は増加傾向の一方、民間非住宅建設工事の出来高は2023年末以降横ばい圏内の動きであったことから、結果として、民間非住宅建設工事の手持ち高は遡及可能な2011年4月以降で見て最高水準まで増加してきた(第1-1-26図(2))。こうした背景には、前掲第1-1-8図でみたような建設コストの高止まりの影響のほか、建設業における高水準の人手不足感から予定工期が長期化し、出来高として発現するペースに遅れが出ていることが考えられる。実際、民間非住宅建設について、工期別の受注額をみると、近年にかけて工期の長い工事の受注が増加している(第1-1-26図(3))。今後は、高水準の手持ち高が、工事の進捗に伴って、徐々に実際の出来高として発現していくことが期待される。

最後に、設備投資の約29%を占める知的財産生産物投資のうち、ソフトウェアの動向をみると、受注ソフトウェアの売上は、名目・実質ともに着実に増加傾向が続いており、人手不足への対応としての企業の省力化投資やDXの推進が背景にあるとみられる(第1-1-27図(1))。研究開発投資については、日銀短観の2024年12月調査時点で、2024年度の投資計画は前年度比+6.5%と、2017年度の調査開始以降では、2022年度に次いで高い伸び率となっており、堅調さを維持している(第1-1-27図(2))。民間設備投資に占める知的財産投資のシェアは、主要先進国と比較すると、米国や英国に比べて低く、官民の投資としても、日本はドイツとともに、他国よりも低位にとどまっている(第1-1-27図(3))。ソフトウェアについては、米国では、コロナ禍を経て、デジタル化の進展の中で、民間設備投資に占めるシェアが切り上がっている一方、日本では、1割程度で横ばいにとどまっている(第1-1-27図(4))。また、我が国の研究開発投資は、GDPに対する比率は諸外国に比べて高いが、韓国や米国、英国等が過去10年間でシェアを高めているのに対し、日本の伸びは限定的である(第1-1-27図(5))。産業別にみると、英米では、情報通信や専門・科学技術サービス等のサービス業のウエイトが高い一方、日本はドイツとともに製造業に偏重した姿となっている(第1-1-27図(6))。このように、知的財産投資は増加傾向にあるとはいえ、国際的に見れば、依然として拡大余地があると考えられる。こうした無形資産投資を促進することにより、資本投入や全要素生産性の向上につなげ、潜在成長率の引上げに努めることが重要である。

4 対外部門の動向
最後に、対外部門の動向について確認する。まず、全体像として、経常収支の推移をみると、我が国の経常収支は黒字が継続している中で、第一次所得収支のみが黒字となっており、その黒字幅は年々拡大傾向にある(第1-1-28図)。これは、長期的に企業の海外直接投資が進んだ結果であり、現地子会社における利益が、配当や現地子会社における留保利益(海外直接投資に関する再投資収益)28という形で、海外からの所得の受取増加につながっているためである。また、近年は、海外の高金利に加えて、為替レートの円安進行もあいまって、海外からの債券利子の受取も増加傾向にある。一方、貿易収支(財の純輸出)の黒字は縮小傾向にあり、資源価格の高騰等により、赤字に転じやすい構造に変化している。また、サービス収支については、インバウンドの拡大傾向により旅行収支は黒字の一方、デジタル関連分野や保険分野において赤字が拡大傾向にあり、全体では赤字が継続している。29

(財の輸出は、全体として横ばいの中で、景気の足踏みがみられる中国向けは停滞)
次に、財の輸出の動向を確認する。財の輸出について、輸出数量指数でみると、持ち直しの動きがみられる局面もあったが、2024年を通じて横ばい圏内で推移してきた。名目輸出金額を、輸出物価指数でデフレートした実質輸出についても、おおむね同様の動きであるものの、2022年以降両者のかい離は広がり、実質輸出の方が、輸出数量よりも相対的に底堅く推移する姿となっている(第1-1-29図(1))。これは、コラム1-3のとおり、デフレーターである価格指数において、品質調整が行われているか否かの違いに起因し、品質調整が施されている輸出物価指数を用いた実質輸出においては、輸出商品の品質向上・高付加価値化が反映されていることによる。
こうした違いを踏まえつつ、ここでは、国・地域別に輸出数量指数の動きをみると、過半を占めるアジア向け輸出は、全体としては横ばい圏内で推移してきたが、国・地域によってばらつきがみられる(第1-1-29図(2))。具体的には、中国向けについては、同国における景気の足踏みもあって、機械機器を中心に2024年中は減少傾向で推移した(第1-1-29図(3))。機械機器の中では、情報関連財では、ICが増加したほか、中国における半導体の国産化の進展を背景に半導体製造装置が底堅く推移した一方、自動車は、世界的なEV化の流れもあって弱い動きが続いた。金属加工機械等の工作機械も低水準での推移が続いたが、2024年末にかけては、受注が増加に転じ、下げ止まりの兆しがみられている。一方、ASEAN、韓国、台湾向けの輸出は、総じて持ち直しの動きがみられた(第1-1-29図(4)、(5))。ASEAN向けは自動車のほか、船舶の輸出が均してみると堅調に推移した。韓国・台湾等向けは、半導体需要回復を受けて、半導体製造装置等が比較的堅調に推移したが、ICについては、上述のとおり、2024年末にかけて、PCやスマートフォンの出荷の動きを反映して、頭打ちもみられている。
米国向けの輸出(全体の約2割)は、2024年においては、同国の堅調な景気を反映して、総じて高水準を維持する中、横ばい傾向で推移した(第1-1-29図(6))。米国向け輸出の3割弱を占める乗用車は、自動車運搬船の需給ひっ迫や、日本国内の認証不正問題等による出荷停止の影響もあって、軟調に推移した。ただし、米国国内の新車販売台数は底堅く推移していることから、需要面で弱さがみられるわけではなく、2024年12月は乗用車の輸出は増加に転じた。生産用機械のうち、半導体製造装置は、世界的な半導体需要の回復や、米国国内における半導体生産の強化策の影響もあり比較的堅調に推移している一方、建設用・鉱山用機械は、既往の高金利水準の影響もあって、弱い動きが続いた。
EU向け(全体の約1割)は、ドイツの景気足踏みなど経済が力強さを欠く中で、2024年は、自動車や建設用・鉱山用機械を中心に弱含み、夏以降横ばい圏内で推移した(第1-1-29図(7))。中東などその他地域向け(全体の2割弱)は、中東向けの自動車が底堅く推移するなど、総じて横ばい圏内で推移した(第1-1-29図(8))。

次に、財の輸入について、輸入数量指数30の動向をみると、2024年は、世界全体及び約5割を占めるアジアからの輸入は、総じて横ばいから持ち直し傾向で推移した(第1-1-30図(1)、(2))。財輸入の約3割を占める機械機器は、新製品発売の効果もあって、アジアからの携帯電話31や電算機類の輸入が堅調に推移したほか、2024年初以降、一部自動車メーカーの認証不正問題に伴う生産・出荷停止事案により落ち込んでいた自動車用の絶縁電線・ケーブルが、自動車生産の回復に伴って年末にかけて持ち直した(第1-1-30図(3)①)。輸入全体の約4分の1を占める鉱物性燃料は、我が国のエネルギー効率の改善や、鉱物性燃料から他のエネルギーへの代替を背景に、長期的に減少トレンド32にある中で、2024年はおおむね横ばいで推移した(第1-1-30図(3)②)。

(日本の輸出に占めるサービス比率は上昇しているが、主要先進国の中では低位)
次に、サービスの輸出入について確認する。まず、世界の貿易構造をみると、財貨・サービスの輸出に占めるサービス輸出のシェアは、1980年代前半の19%から2023年には26%に高まっているが、特に先進国では、同期間の20%から29%に拡大しており、貿易のサービス化が進んでいる(第1-1-31図(1))。サービス貿易の内訳は、経済のグローバル化の進展の中で、輸送や旅行についても、コロナ禍による国境を越えた移動の停滞による落ち込みを除けば拡大傾向にある一方、デジタル関連を含むその他のサービスが全体の約65%と大宗を占め、経済のデジタル化の流れの中で、コンピュータサービス等をはじめ、一貫して拡大傾向にある(第1-1-31図(2)、(3))。主要先進国の輸出に占めるサービスの比率をみると、日本を含め上昇傾向にあるが、日本はドイツとともに2割程度と、英国やフランス、米国に比べて低位にとどまっており、後述するような貿易摩擦の影響を受けやすい構造であると言える(第1-1-31図(4))。
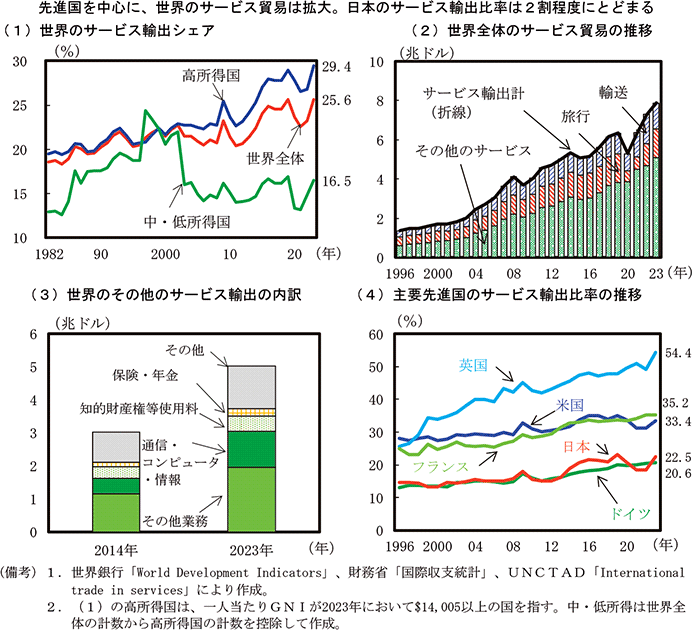
このように、経済活動において重要性を増しつつあるサービス貿易については、「国際収支統計」(月次、名目)やGDPのサービス輸出入(四半期、名目・実質)により把握が可能であるが、よりきめ細かく動向を確認し、四半期GDP速報におけるサービス輸出入の動向をより早期に予測する観点から、これらの統計をもとに、月次で名目・実質のサービス輸出入を把握する「サービス輸出入指数」を試算した(指数の詳細は、付注1-1を参照)。
まず、サービス輸出指数をみると、コロナ禍以前は緩やかに増加し、コロナ禍でインバウンドが大きく落ち込んだ後、インバウンドの急速な回復もあって、名目・実質ともにコロナ禍前よりも高いペースで増加傾向が続いている(第1-1-32図(1))。2024年夏場は減少したが、11月まで含めてみると増加傾向が確認される。「国際収支統計」における名目値の内訳をみると、輸出の2024年夏における鈍化は、主に旅行によるものであり、2024年夏にインバウンドが短期的に一服したことを反映している(第1-1-32図(2))。その他のサービスの中では、サービス輸出の2割強を占める特許等の産業財産権等使用料が最近の増加をけん引している。
また、輸入については、輸送、旅行以外のその他のサービスが大きな動きを規定しており、サービス輸入の1割強を占める専門・経営コンサルティングサービスをはじめデジタル関連サービスや保険サービスがけん引していることが分かる(第1-1-32図(3))。特に、デジタル関連サービスは、コロナ禍を契機としたデジタル化の進展も反映し、サービス輸入全体のコロナ禍後における増加ペースの高まりの主な要因となっている。33

(インバウンドは各国の所得等の影響が大きく、為替の影響は国により異なる)
ここで、日本のサービス輸出をけん引している分野の一つであるインバウンドについて、訪日外客数をみると、コロナ禍の落ち込みから、2022年10月以降の水際対策の緩和・撤廃を経て急速に回復し、2024年3月以降、コロナ禍前の2019年を超えて過去最高の水準に達している。2024年夏は、それまでの急回復後の反動等により、訪日外客数やインバウンド消費額の増加が一服したが、同年末にかけては再び増加している(第1-1-33図(1)、(2))。ここで、我が国のインバウンドの持続性を展望する観点から、各国別のインバウンド需要(訪日外客数)を、各国の所得(実質GDP)や二国間為替レート(実質為替レート)、ビザ緩和や水際措置等の各種要因から説明する回帰式を推計する34。推計の対象は、2023年時点でインバウンド客数が多い上位15か国・地域とした35。推計結果のうち、所得、為替レートに対する弾性値を確認すると、まず、所得弾性値については、いずれの国・地域でも有意にプラスであり、フランスが突出して高いことなどが分かる(第1-1-33図(3))。一方、中国の所得弾性値は最も低い結果となっているが、中国の場合、国境を越えた自由な往来が政策的に制限されてきた経緯があるため、所得弾性値の解釈には留意が必要である。次に、為替弾性値をみると、符号は多くの国でマイナスであり、各国通貨が円に対して増価すれば、客数が増加する形となっているが、国・地域によって、統計的に有意でない場合もある。おおまかな傾向としては、近隣アジア地域からの訪日外客数は相対的に為替レートに反応しやすい結果となっているが、全体として必ずしも為替の影響が大きいわけではないと考えられる。ここで、主要な国について、回帰式による推計値と実績値の推移を比較しつつ、訪日外客数の要因分解を行うと(第1-1-33図(4)、付図1-5)、例えば、韓国等では、為替レートの要因が相応に影響しているのに対し、米国等では所得要因の寄与が大きいことが分かる。また、中国については、ビザ緩和など各種制度変更等の特殊要因の影響が大きいなど、全体として、インバウンド需要が為替レートに大きく左右されるわけではないことが示唆される。

コラム1-3 実質輸出入と輸出入数量指数の関係について
物価変動の影響を除いた輸出入の動向を把握するための指標としては、日本銀行が算出している実質輸出入と貿易統計(財務省)における輸出入数量指数がある。両者は、基本的には同様の動きとなるが、本論でみたように、最近になって両者のかい離が大きくなっている。
ここで、輸出入数量指数は数量の変化を表しているのに対して、実質輸出入は実質的な価値の変化も反映したものであり、実質輸出入が輸出入数量指数を上回っているということは、輸出入財の価値が高度化、すなわち品質が向上していることを意味していると考えられる。
具体的には、輸出入数量指数、実質輸出入ともに、分子に貿易統計の通関輸出入額を用いていることは共通しているが、輸出入数量指数は貿易統計における輸出入「価格」指数を分母にしているのに対して、実質輸出入は企業物価指数などから作成される輸出入「物価」指数を分母に用いている。輸出入「価格」指数は品目ごとに輸出金額÷数量によって求められるのに対して、輸出入「物価」指数は製品に品質の変化があった場合、その品質に関する調整を行い、指数に反映するという特徴がある。例えば、製品の品質が向上したにも関わらず、価格は据え置かれた場合には、実質的に値下げが行われているとみなされ、輸出入「物価」指数では指数が下落するが、金額÷数量で算出される「価格」指数では変化がないということになる。この場合、輸出入数量指数は不変であるのに対して、実質輸出入は増加することとなる。こうした品質調整に起因した両者の違いが、輸出入数量指数と実質輸出入のかい離につながっている。
ここで、輸出入価格指数を輸出入物価指数で除した「高付加価値化指数」の動向を確認する(コラム1-3-1図)。まず、輸出では、輸送用機械や電気機器は、全体品目の総合指数よりも上昇傾向となっている。詳細品目をみると、半導体等製造装置やIC、乗用車で上昇度が強いものとなっており、これらの品目においては、品質向上が特に顕著であると考えられる。また、輸入をみると、化学製品、一般機械、電気機器等において、全体品目における総合よりも上昇度が強い。詳細品目をみると、化学製品においては医薬品、機械類では電算機類やIC等で特に上昇していることが分かる。
このように輸出入財の品質変化によって、実質輸出入と輸出入数量指数は異なる動きとなりうる。ここで、GDP統計における財の輸出入は付加価値の概念であるため、品質向上分は付加価値の増加として記録されている。このため、実質輸出入は、輸出入数量指数よりも、GDPベースの計数の動きに近しいものとなっている36(コラム1-3-2図)。付加価値の変化を正確に捉えるという観点や、四半期別GDP速報の輸出入動向を早期に予測するという観点では、品質調整を考慮した指標をみることが重要と考えられる。


5 景気の先行きとリスク要因
(先行きも緩やかな回復が期待されるが、海外景気の下振れリスク等に留意)
ここまで、2024年の動向を中心に日本経済の動向を振り返り、非製造業を中心とした企業部門の堅調さが続いていることに加え、賃金・所得環境が好転する中で、個人消費も持ち直しの動きがみられており、我が国経済は、引き続き緩やかな回復基調にあることを確認した。先行きについても、引き続き雇用・所得環境が改善する下で、経済対策37の効果もあって、緩やかな回復が続くことが見込まれる。一方、先行きを展望する上では、各種の下振れ要因に十分注意する必要がある。
特に重要なものの一つとして、海外景気の下振れリスクがある。中国においては、政策効果により生産の増加はみられるものの、2022年頃から続く不動産価格の下落を背景に、消費等の内需の伸びが弱く、景気の足踏みが続いており、不動産市場停滞の継続の影響等によっては景気が更に下振れするリスクがある。また、欧米経済においても、物価上昇率が2%台に落ち着いてきたことから、2024年から政策金利の引下げ局面に入っているが、当面、高い金利水準が継続する可能性があり、これら国・地域の国内需要を下振れさせる可能性もある。こうした海外景気の下振れは、外需を通じて、我が国経済の下振れにつながりうることから、その動向には十分注意する必要がある。また、2023年後半から緊張が続いてきた中東情勢の動向等によっては原油価格が上昇する可能性や、為替レートの動向によっては、円建ての輸入物価の上昇を通じて、コストプッシュ型の国内物価上昇が再び進む可能性等にも十分留意が必要である。
(米中貿易摩擦再燃輸出や製造業の生産が影響を受ける可能性に留意)
これらに加えて、ここでは、今後の通商政策の動向とその影響が我が国経済に影響を及ぼしうる点について取り上げる。
米国では、2024年11月の大統領選挙の結果、2025年1月に第2次トランプ政権が発足した。トランプ大統領は、大統領選挙期間中あるいは大統領選出後において、通商政策や法人税率の引下げ、不法移民対策等の政策に言及してきた38。これらが実際に実行される場合、例えば、減税や規制緩和については、米国の実体経済の押上げ要因となり、世界経済への波及を通じて間接的あるいは直接的に日本経済にも好影響を与える可能性がある一方、各種政策動向によっては、米国の物価動向や、為替や金利、株価など金融資本市場にも様々な影響が生じうる。
この中で、通商政策については、メキシコ・カナダからの輸入品に対し25%の追加関税を課すことについて大統領令への署名が行われた39ほか、2025年2月4日以降、中国からの輸入品全品目に対する10%の追加関税が課されることとなった。これに対し、中国は、米国から輸入される石炭、天然ガス、大型自動車等への関税率引上げを2月10日から実施するなど対抗措置をとることとしている。2017年以降の第1次トランプ政権時を振り返ると、2018年7月に中国からの輸入品のうち340億ドル相当、818項目に25%の追加関税を実施したことを皮切りに、これ以降累次にわたり、米中間で相互に関税が引き上げられた(第1-1-34図)。その結果、2018年半ば以降、米中ともに財輸出は頭打ちとなり、中国の対米輸出の停滞は、日本からの財輸出の下押しにもつながった(第1-1-35図)。こうした中で、日本においては、2018年10月には景気の山を迎え、景気後退局面に入った。


ここで、2018年当時と直近の2023年時点における日本と中国、中国と米国の貿易構造を確認すると、日本から中国への財輸出は、2018年時点では、世界向け全体の19.5%から、2023年時点では17.6%とやや低下しているが、品目構成をみると、半導体製造装置を含む一般機械やICを含む電気機器が2割弱と比較的大きな割合を占めるという構造に変化はない40。また、中国から米国への財輸出は、2018年時点では、中国から世界向け全体の19.2%から、2023年時点では14.8%と一定程度低下しているが、輸出の多くが携帯電話やコンピューターなど情報関連の最終製品が多いという構造にも変化がない(第1-1-36図)。このように、米中間の貿易摩擦が仮に高じることとなった場合、中国から米国への財輸出、中国国内の製造業生産への影響を通じて、我が国製造業を下押しする可能性に注意が必要である41。

(中国の情報関連最終製品輸出に占める日本の付加価値シェアの低下はわずか)
次に、米中間の貿易摩擦の再燃が、中国への影響を通じて我が国に与える間接的な影響について、2010年代後半からの変化をより詳細に見ていく。こうした影響には、主に、中国が対米輸出に際して最終製品を生産するための日本からの中間財や資本財の輸入を通じた影響が含まれる。このうち中間財を通じた影響として、付加価値貿易統計の状況を確認する。一般的な貿易統計においては、ある国からの輸出について、その国で生み出された付加価値のみならず、他国で創出された付加価値分も含めた全体の金額が計上されている。具体的には、貿易統計上の中国からの財輸出額の中には、日本など他国から輸入した中間財を用いて生産されている部分も含まれ、二重計上が存在する。グローバル・バリュー・チェーン(GVC)が進展している状況では、こうした重複が繰り返され、二重計上分が拡大していると考えられる。これに対し、国際機関が開発している付加価値貿易統計は、こうした二重計上分を取り除いたものとなっており、貿易統計と比べ、純粋な一国の付加価値貿易額を評価するのに適したデータといえる42。付加価値貿易統計には、OECD TiVAとUNCTAD-Eora GVCの二つのデータベースがあり、作成方法の違いから両者の計数には相違があるが、ここでは長期の時系列が利用可能で、比較的近年(2022年)まで計数が存在する後者を使用する。
まず、中国からの輸出全体に占める中国国内で生み出された付加価値の割合をみると、海外企業による中国への直接投資及び現地生産が増加する中で、これら現地企業の海外からの中間財の輸入拡大から、2000年代前半までは長期的に低下傾向にあったとみられる(第1-1-37図(1))。一方、2010年代半ば以降は、中国における重点分野の製造業の高度化を目指す産業政策の影響もあって、国内付加価値比率の上昇がみられる。このように、近年にかけて、中国の輸出に占める各国で生み出された付加価値の割合は低下しており、日本についても同様である。中国の輸出に占める海外付加価値分の合計を100%として、日本で生み出された付加価値分のシェアをみると2022年で約10%となり、長期的には低下傾向であるが、2018年時点と比較すると大きな変化はみられない(第1-1-37図(3))。さらに、中国からの輸出財のうちコンピューターや携帯電話等の情報関連製品の輸出に占める日本からの付加価値分のシェアをみると、全ての中国からの輸出財の平均値よりは高く、2018年時点から2022年時点にかけては総じて低下はしているものの、大きな変化が生じたとまでは言えない(第1-1-37図(4))。

このように、貿易統計や付加価値貿易統計からみると、貿易摩擦による中国の財輸出への需要低下が、日本への派生需要の減少を通じて、日本の製造業生産を下押しする蓋然性は、2018年当時と比べて高まっているわけではないものの、顕著に低下しているわけでもないと言える。また、上述のとおり、付加価値貿易統計は、あくまで当該国の生産に使用される中間財に係る付加価値を見たものであり、例えば、日本が中国に生産用機械等の資本財を輸出し、これが中国の輸出製品の生産に使用された場合、本来は、日本の付加価値分に記録されるべきものが、付加価値貿易統計上は、中国の付加価値分に含まれて計上されるという限界がある。中国における半導体生産の国産化の進展の下で、日本から中国への半導体製造装置の輸出が拡大してきたこと等を踏まえると、貿易摩擦による経済の下押しリスクは、付加価値貿易統計で把握されるよりも大きなものとなりうる点に留意が必要であろう。
この点に関連して、OECDの国際産業連関表を用いて、中国の最終需要からの影響度、つまり、各国・地域が生産した財のうち中国の最終需要によって誘発される生産額の割合を計算した43。同産業連関表は、直近年がコロナ禍に当たる2020年までであることに留意が必要であるが、これによると、日本の生産の中国の最終需要からの影響度は、台湾やベトナム、マレーシア、韓国、タイといったアジア諸国よりは小さいものの、2015年の3.1%から2020年には3.6%に若干上昇している(第1-1-38図(1))。また、産業別にみると、半導体等を含む電子機器・情報通信機械が15.9%と最も高く、2015年から2020年にかけて依存度が高まっている(第1-1-38図(2))。このほか、化学、一次金属に加え、半導体製造装置を含む一般機械も中国の最終需要からの影響度が大きく高まっている。このように、一般論として、中国の最終需要の下振れは、各種製造業の輸出・生産への影響を通じて、我が国経済に直接的な影響を及ぼしうるほか、中国経済からの影響度が高いアジア諸国への悪影響を通じて、間接的に我が国経済の下押しともなりうる点に注意が必要と言える。

このほか、米国のメキシコ・カナダからの輸入品に対する関税引上げについても、仮にこれが実現された場合には、ニア・ショアリングという形で同地域での現地生産を活発に行っている輸送用機械を中心に、我が国製造業に与える影響にも留意が必要である(コラム1-4)。このように、我が国経済の先行きを展望するに当たって、各種のリスク要因とともに、米国の政策動向やその影響にはきめ細かい目配りが必要と言える。
コラム1-4 メキシコ・カナダとの貿易・投資関係について
ここでは、本論の補足として、日本からメキシコ・カナダへの輸出の構造や直接投資の動向等について整理する。まず、日本からメキシコ、カナダ両国への財輸出については、それぞれ世界向けの1.8%、1.5%と、あわせて3%程度となっている。品目構成をみると、輸送用機械が大きく、特にメキシコ向けについては、最大の販売市場である米国と近接し、自由貿易協定を締結する地域の拠点で現地生産を行うニア・ショアリングが盛んであることから、自動車部品のウエイトが高く、また関連財として鉄鋼等のウエイトも高いことが分かる(コラム1-4-1図)。

日本の製造業における海外直接投資残高の構成をみると、中国向けのシェアがやや低下する一方、欧州向けが高まっているほか、メキシコ・カナダについても全体に対するシェアは2023年末時点で3%以下であるが、2016年末と比較するとやや上昇していることが分かる(コラム1-4-2図(1))。実際、企業の拠点数は、この間1.3倍に増加している(コラム1-4-2図(2))。製造業直接投資残高に占める主要業種のシェアをみると、最大である輸送機械が、2016年末から2023年末にかけて低下する中、鉄鋼を含む金属や、家電等を扱う電気機械ではシェアが高まっており、同地域における現地生産は多様化していることが確認できる。
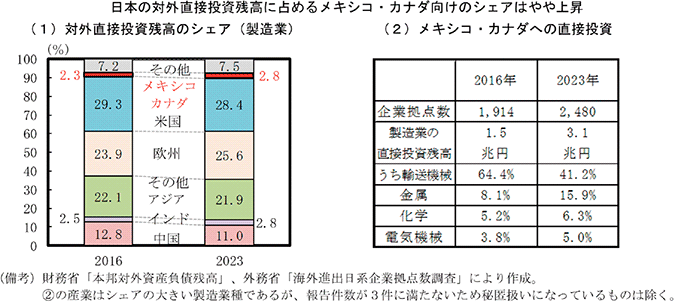
このように、米国によるメキシコ・カナダからの輸入品への関税引上げが実施された場合には、自動車の現地生産等のための中間財の輸出を中心に、日本の製造業の活動に影響が及ぶ可能性がある。この点は、第1次トランプ政権時には生じなかった事象であることから、政策動向とその影響には十分留意する必要がある。
(潜在成長率引上げの取組も賃上げと投資がけん引する成長型経済実現に不可欠)
こうした景気の下振れ要因を注視するとともに、我が国経済の持続的な成長を実現する観点では、需給ギャップのマイナス幅が縮小傾向にあり(後掲第1-2-6図(1))、また、 人手不足が供給面での制約要因となる中、経済の供給力、すなわち潜在成長率の引上げが不可欠の課題である。推計方法によって幅があることに留意が必要であるが、我が国の潜在成長率は、依然、直近で0%台半ばと低い水準にとどまっている。内訳をみると、生産年齢人口が減少する中にあっても、2010年代前半以降、女性や高齢者の労働参加が進み、就業者数要因は押上げに寄与している一方で、長期的な総実労働時間の縮減の取組や、高齢雇用者の短時間での就業の増加等により、労働時間要因は傾向的に下押しに働いている。また、企業部門のコストカットの結果、収益の増加に比して、将来の成長のために必要な投資が抑制されてきた結果、資本投入の寄与が縮小し、先進各国の中でも極めて低い水準にある。全要素生産性(TFP)上昇率については、先進各国と比べて遜色ない水準にあるものの、過去に比べれば低下している状況にある(第1-1-39図)。こうした潜在成長率の引上げに向けては、労働、資本、全要素生産性の各側面からの対応が必要であり、①女性や高齢者をはじめ人々の就業意欲を後押しする取組や、②国内設備投資の拡大や研究開発等の無形資産投資の促進によって、資本ストックの蓄積を図るとともに、新しい価値の創造を通じて、全要素生産性を高める取組が不可欠である。


