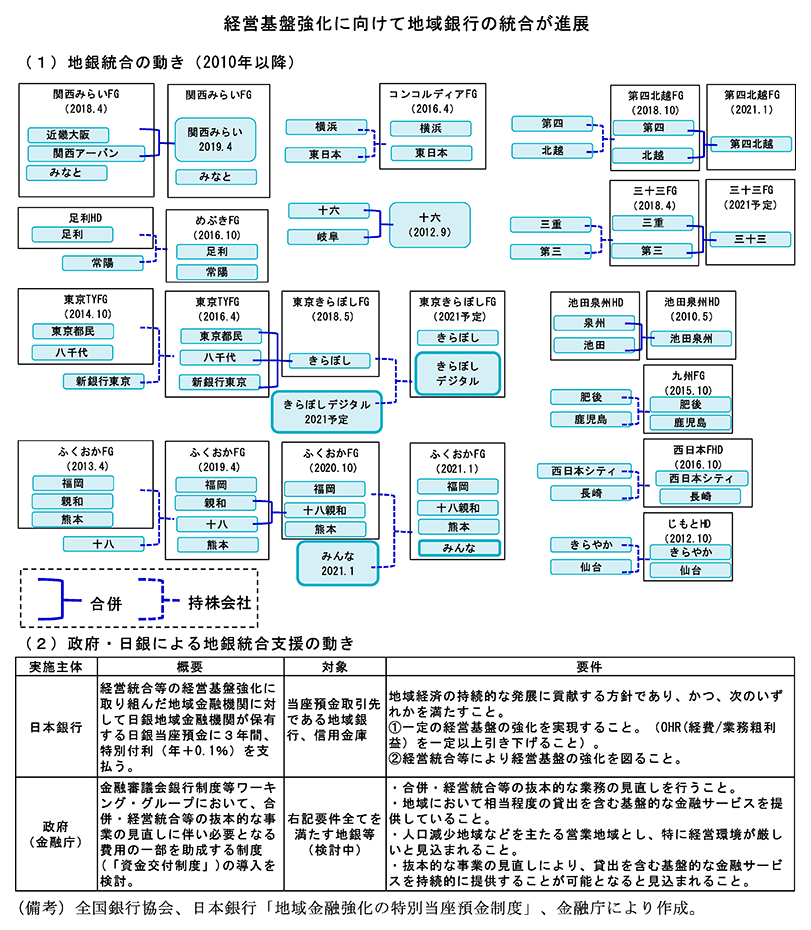第3章 ポストコロナに向けた企業活動の活性化と課題(第3節)
第3節 企業活動の活性化に向けた課題
最後の本節では、高齢化と人口減少が進むなかで、我が国の企業活動を活性化させるために必要な課題について検討する。
1 我が国中小企業の生産性と課題
(中小企業が従業者数に占める比率は8割、付加価値に占める比率は5割程度)
我が国の企業活動を概観するに当たり、企業活動を表す各種データについて規模別の割合をみると、事業所数のほとんどを、また、従業者数の8割を中小企業が占めている。他方、ソフトウェアや研究開発、有形設備といった投資活動についてみると、中小企業の割合は1~4割程度と低下する。こうしたこともあり、中小企業が従業員賃金に占める割合は55%、付加価値では同5割弱であるなど、事業所・従業者に占める比率に比べて小さく、中小企業の付加価値を引上げることは、我が国全体の付加価値を引上げることにつながる(第3-3-1図)。
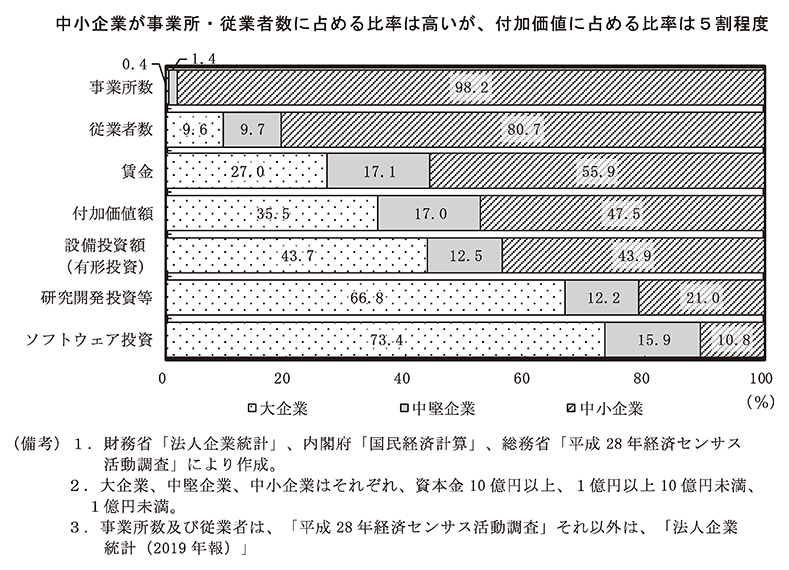
続いて、企業規模・業種別に従業員一人当たりの付加価値及び賃金(2017-19年度平均)を確認する。まず、従業員一人当たりの付加価値と賃金は、企業規模にかかわらず比例関係にあり、その比は分配率になるが、均してみると安定的である。賃金の上昇には、当然ながら付加価値を高めることが重要となる(第3-2-2図(1))。
次に、従業員一人当たりの付加価値をみると、何れの業種も企業規模が大きいほど高い。ただし、大企業と中小企業との差は業種によってばらつきがある。最も差が大きいのは情報通信業であり、14.6百万円に上る。また、建設業や運輸・郵便業、製造業でも比較的大きな差があるが、小売業、宿泊・飲食サービス業では、大企業の付加価値が他業種と比べて低く、企業規模間の差は小さい(第3-2-2図(2))。
従業員一人当たり賃金も企業規模が大きくなるほど高いが、小売業、宿泊・飲食サービス業は、付加価値同様、企業規模間の差が小さい。これら2業種は、資本装備率についても企業規模間で大きな差はなく、業種全体として、資本装備率の高まりとそれを受けた生産性の向上、賃金上昇といった循環があまり働いていない可能性がある。また、情報通信業では、大企業の資本装備率および従業員一人当たり付加価値は中小企業と比べて高いが、賃金差は付加価差と比べると小さく、企業規模が大きくなるにつれ、資本装備率および付加価値は高まるが、賃金はそこまで大きく上昇していない点もみてとれる(第3-2-2図(3)(4))。
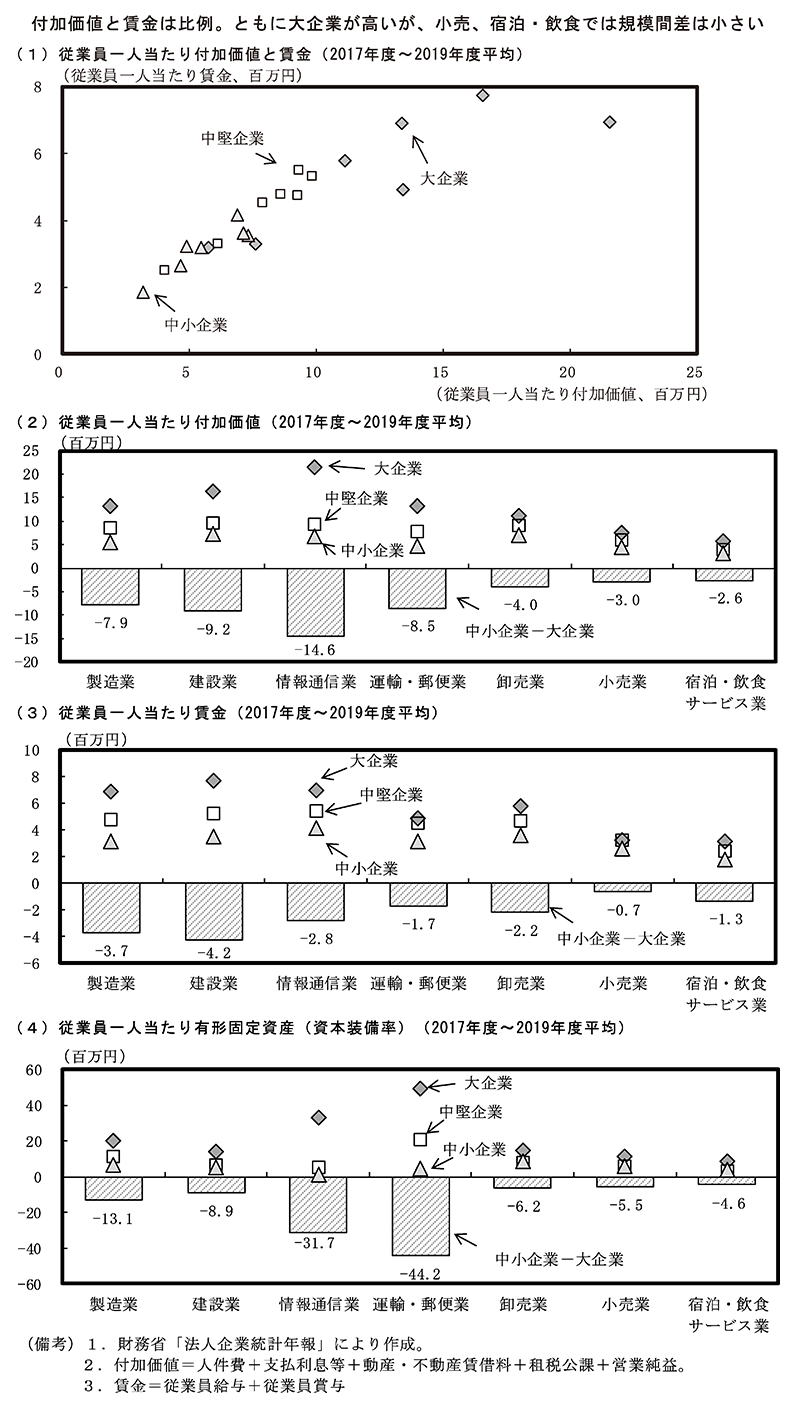
(2010年代の中小企業は、TFP要因も含めて生産性が伸び悩みの状況)
続いて、成長会計に基づき、各年代の平均成長率を資本や労働といった投入要素の増減による寄与と、技術進歩や生産の効率化などを表す全要素生産性(以下、TFP)の増減による寄与に分解し、企業規模ごとの特徴をみる1(第3-3-3図)。
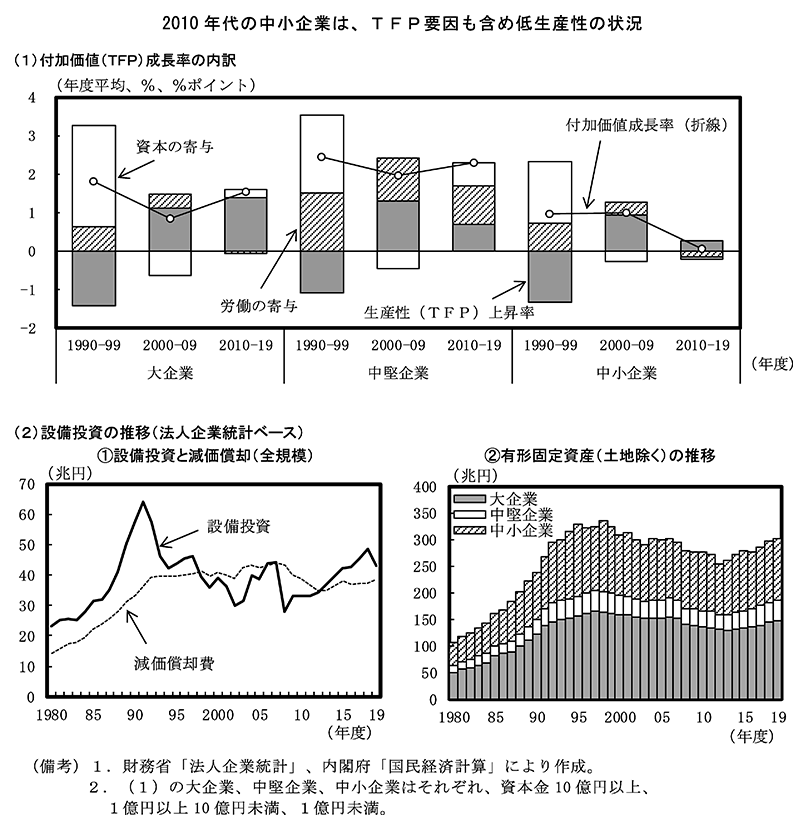
まず、1990年代(90~99年)の付加価値成長率は、大企業で1.5%、中堅企業で2%強、中小企業で1%弱であった。いずれの規模でも資本のプラス寄与が最も大きく、TFPの寄与はマイナスであった。同時期における民間企業設備投資(法人企業統計ベース)の動向を振り返ると、いわゆるバブル崩壊後の過剰設備の調整過程にあり、91年をピークに2000年前半にかけて減少傾向が続いていた。しかし、98年までは減価償却を超える投資水準となっており、資本ストックは緩やかに増加しため、付加価値成長率にはプラスの寄与となっていた。ただし、付加価値増加に生産要素投入の増加が寄与することは、残差として計測されるTFPの低下を意味する。言い換えると、付加価値の伸び率が資本ストックの伸びを下回る状況では資本稼働率の低下、効率性の低下が生じていたことになり、TFPはマイナス寄与となっていた。
次に、リーマンショックを含む2000年代(2000~09年)の付加価値成長率は、大企業で0.9%、中堅企業で2.0%、中小企業で1.0%であった。寄与の内訳は前期と異なり、資本ストックは、設備投資が減価償却の範囲内に抑えられ、マイナス寄与へと転じた。一方、リーマンショック前までの緩やかな景気回復とともに資本稼働率が上昇したことで、TFPはプラス寄与に転じた。
最後に、長期の景気拡張局面を含む2010年代(2010~19年)の付加価成長率は、大・中堅企業では2000年代よりも上昇したが、中小企業ではほぼゼロ成長となっている。成長寄与の内訳では、2012年に漸く減価償却を超える設備投資が行われるようになったことから、大・中堅企業では資本の寄与がプラスに転じ、TFPの寄与もプラスである。他方、中小企業では、資本の寄与が極僅かながらもマイナスであり、TFPのプラス寄与は大・中堅企業と比べて小幅に止まっている。
(ソフトウェアを含む無形資産投資はTFPの押上に寄与)
TFPは、技術進歩や生産効率の変化を包含するものであり、既存の実証研究においても、研究開発投資やソフトウェア投資2といった無形資産の蓄積がその上昇をもたらすとされている3。そこで、企業レベルのデータを用いて、企業規模・特定の業種ごとに無形資産がTFPに与える影響について確認すると、無形資産装備率は、TFPに有意にプラスであることが確認できる(第3-3-4図)。これは、製造業、小売業、宿泊・飲食サービス業における全ての企業規模で確認できており、中小企業においても、IT投資などの無形資産投資を積極的に行うことでTFPを押し上げることが可能である。
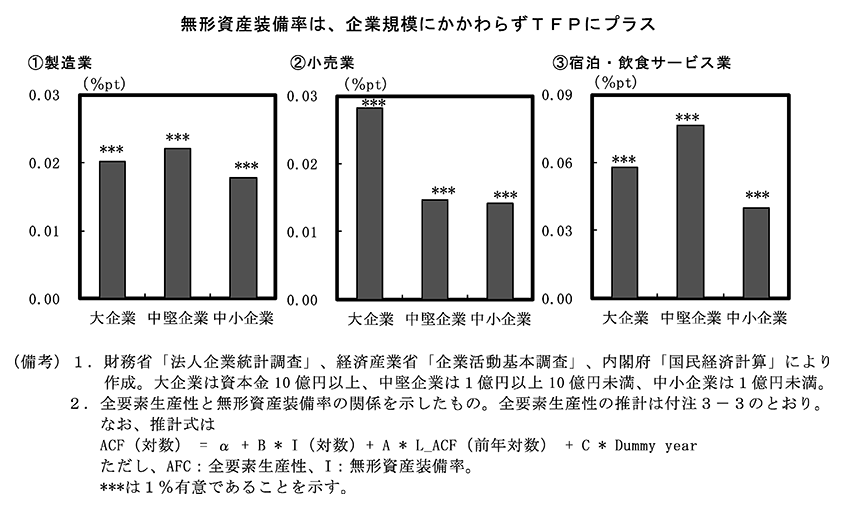
次に、ソフトウェア投資の動向を確認しよう。先ず、企業規模・特定の業種ごとに収益のうちどの程度をソフトウェア投資に充てているのか(キャッシュフローのうちソフトウェア投資に充てられた比率を)を確認すると、製造・加工業では大企業、中堅企業でソフトウェア投資比率が上昇傾向にある一方、中小企業では2%以下と低位にとどまっている4。小売業については、中小企業の2019年度を除き、全ての規模でソフトウェア投資比率は上昇傾向にある。宿泊・飲食サービス業については、振れが大きいものの、中小企業で2016年度以降上昇傾向にある(第3-3-5図(1))。
なお、規模別の設備投資合計に占めるソフトウェア投資比率(2010~2019年度平均)をみると、製造・加工業や小売業では大企業に比べて中小企業での投資比率が低い一方、宿泊・飲食業については、企業規模間における差はほとんどない(第3-3-5図(2))。
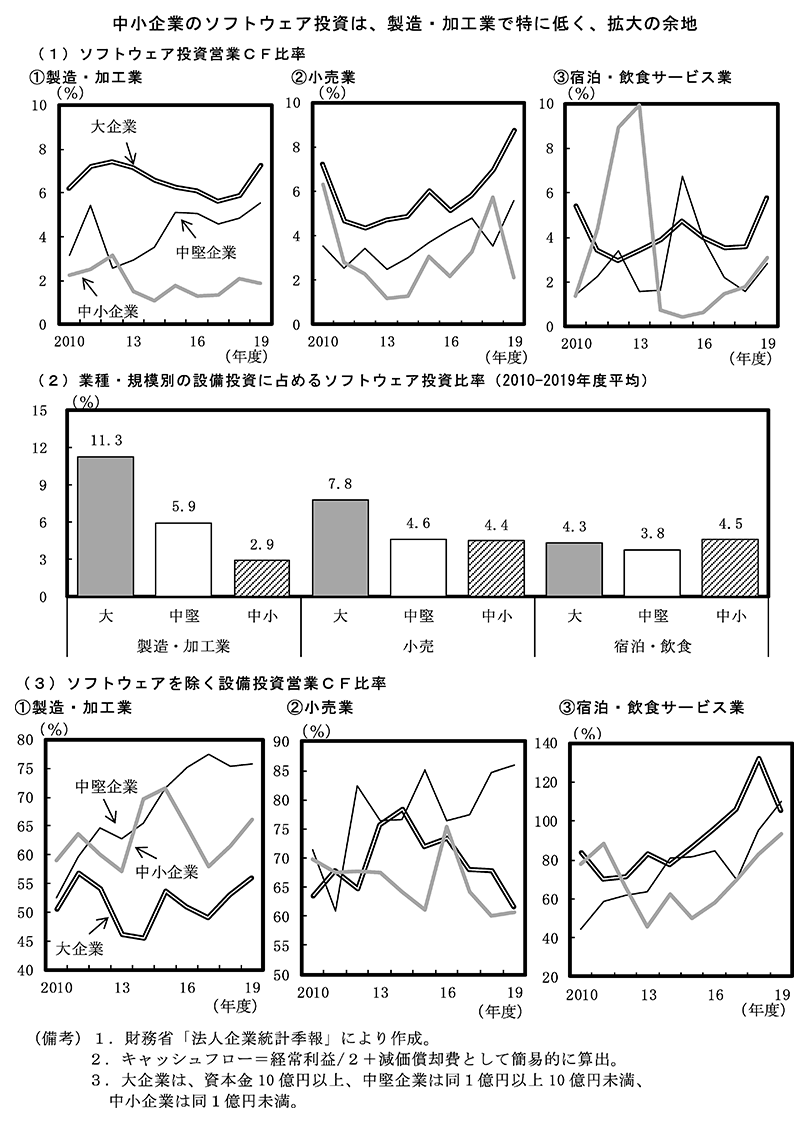
2020年12月に閣議決定された「国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策」では、対策の柱の一つにデジタル改革を掲げ、データ主導型の「超スマート社会」の実現に向けたデジタル分野の研究開発支援や、インフラ、交通、物流分野等におけるデジタル化を推し進める方針が示されている。社会全体のデジタル化が加速する下、企業規模にかかわらずソフトウェア投資を加速させることが期待される。
特に、中小企業におけるソフトウェア投資については、有形資産に偏っている投資配分の見直しのほか、感染拡大という特殊要因も加わった極めて緩和的な資金調達環境にある現状を活かして加速することが期待される。資金面については、例えば、中小企業・自営業者を対象に、ITツール導入に活用できるIT導入補助金など、デジタル投資支援策も複数措置されており、こうした制度の積極的な活用を促す必要がある(第3-3-6図)。
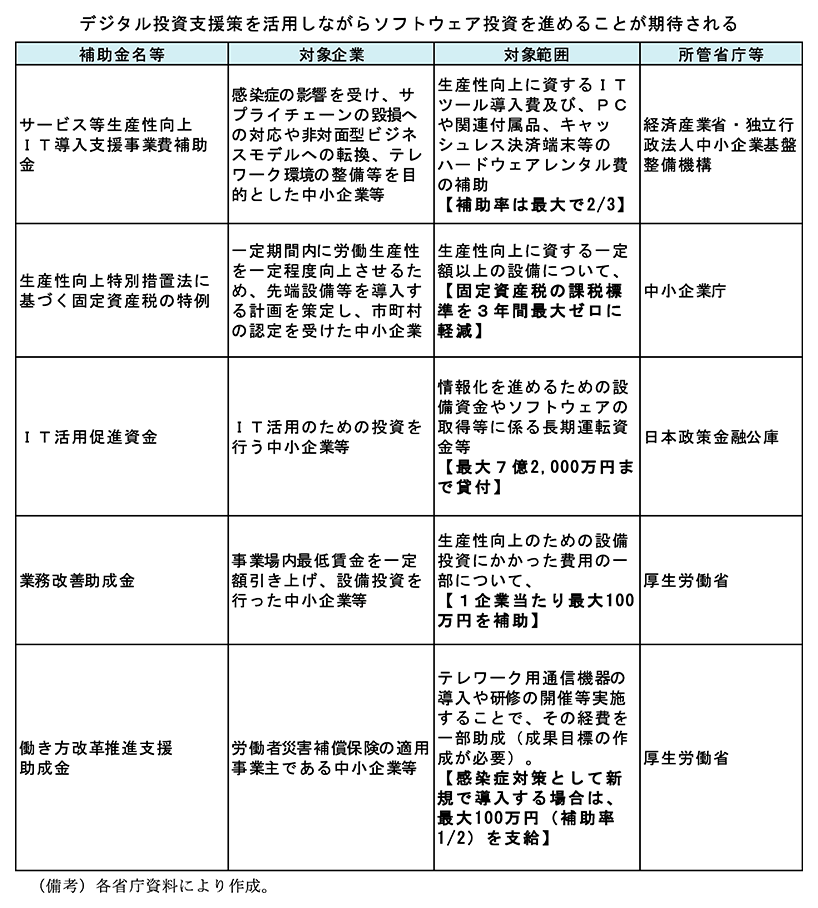
(中小・製造業の価格転嫁力指標は前期比マイナスも、大企業との差は縮小)
中小企業のTFPや労働生産性の低さの背景の一つとして、価格転嫁力の弱さもしばし指摘される5。そこで、日銀短観の販売価格DI及び仕入価格DIを用いて企業規模別の価格転嫁力指標を確認する6(第3-3-7図)。
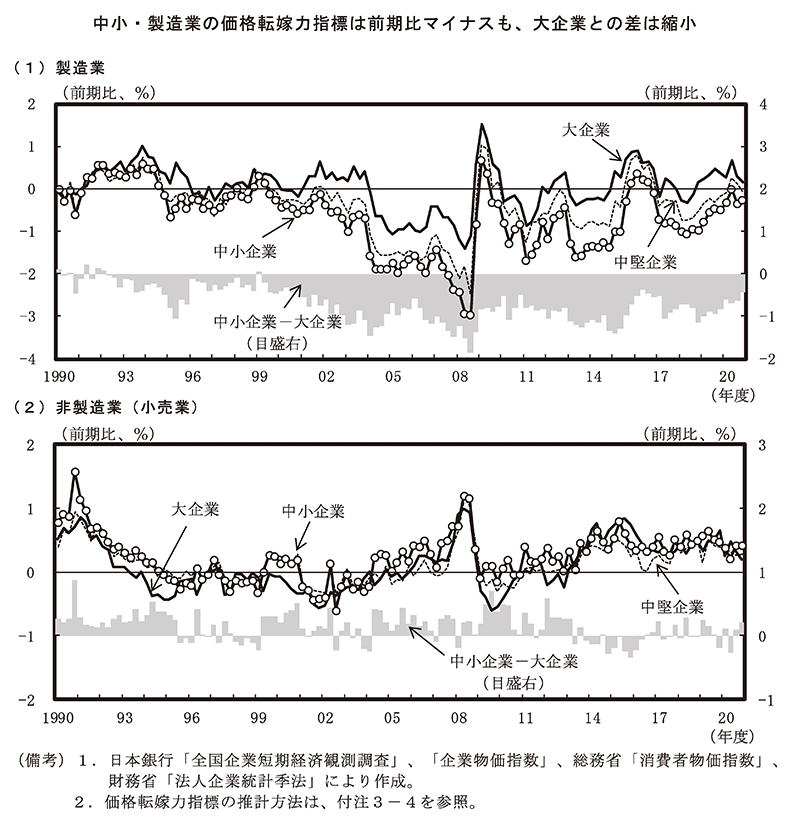
まず、製造業についてみると、1990年代までは企業規模間に価格転嫁力指標の差はそこまで大きなものではなかったが、2000年代に入り、中堅・中小企業の価格転嫁力指標が徐々に低下し、大企業との差は拡大していった。2018年頃から大企業と中小企業の価格転嫁力指標の差は徐々に縮まっているが、中小企業の価格転嫁力指標は依然として前期比マイナスが続いているほか、2020年度は感染症の影響により厳しい収益環境に直面する中で、大企業も価格転嫁指標の前期比プラス幅が縮小している。
次に、非製造業のうち、物価データ7を入手可能な小売業についてみると、企業規模ごとの価格転嫁力指標に大きな違いはなく、2014年度頃から、何れの企業規模においても、1%未満と僅かながら前期比プラスで推移している8。製造業との違いがみられる背景の一つとして、小売業という業態が、仕入れコストに一定のマージンを上乗せして販売するという基本的な商慣行が影響しているとの指摘もある9。
こうした価格転嫁力指標の動きのうち、特に製造・中小企業における価格転嫁力の弱さの要因をみると、仕入価格が下落傾向にあった1990年代後半では、仕入価格の下落以上に販売価格を下げる傾向にあった。また、仕入価格が上昇傾向に転じた2000年代半ば以降は、仕入価格の上昇分を販売価格に十分転嫁できていない傾向にある(第3-3-8図)。なお、民間金融機関によるアンケート調査10では、2020年においても、親事業者などの取引先から自社の製・商品、サービス等の値下げ圧力を感じているとの回答が76.6%、仕入価格の上昇分を十分に転嫁できていないとの回答が81.0%となるなど11、中小企業は下請け事業者の立場から、十分な価格転嫁が行えていない実態もうかがえる。
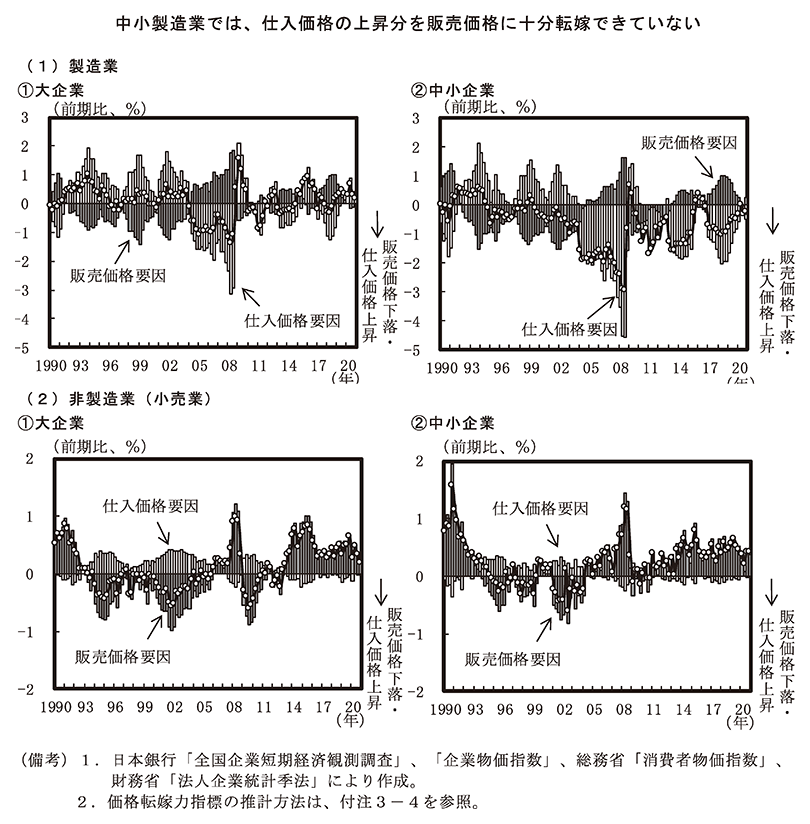
経済産業省では、このような取引実態を是正するため、2016年に親事業者と下請事業者双方の「適正取引」や「付加価値向上」、サプライチェーン全体にわたる取引環境の改善を図ること等を目的とした「未来志向型の取引慣行に向けて」を策定12している。その中の重点課題の1つとして「価格決定方法の適正化」を掲げているが、実効性のある取組により、上記のような課題の是正につながることが期待される。
2 企業活動の活性化に向けた事業承継
(TFP成長率と経営者の年齢に有意な差はみられない)
次に、事業承継を巡る課題について検討する。まず、経営者の年齢と企業業績等に関する先行研究を確認すると、非上場企業のデータを用いた研究では、経営者の年齢と企業業績の間に負の相関関係があり、その背景には認知能力の低下がある点を指摘している13。また、別の研究では、経営者の年齢が上がるにつれ、設備投資や研究開発投資といったリスクテイク姿勢が後退し、株価収益率が低くなる傾向にあるとの指摘もある14。
こうした先行研究も踏まえ、TFPで測った企業の生産性が、経営者の年齢によって影響されるのか否かを確認しよう。具体的には、内閣府「令和元年度 働き方改革の取組に関する企業調査」の個票データにより、2015年度から2018年度の3年平均のTFP成長率を計算し、企業経営者の年齢別に比べる。その結果、経営者の意向がよりダイレクトに経営に反映されると考えられる中堅・中小企業をみると、経営者年齢が70歳以上の企業では、経営者年齢が70歳未満の企業と比べてTFP成長率の平均値は低下しているものの、その差は統計的に有意ではなく、TFP成長率と経営者の年齢に有意な差はみられない。
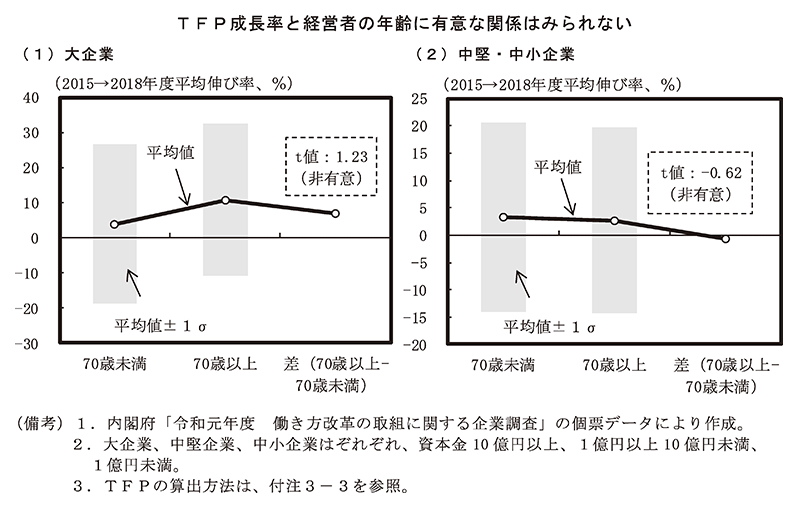
(事業承継ニーズは旺盛ながら、担い手の減少や後継者不足が課題)
経営者年齢とTFP成長率との間に有意な差はみられなかったが、高齢の経営者にとって、事業承継が経営課題の一つであることは間違いない。金融庁の「企業アンケート調査」によると、経営者による事業承継の意思として、「事業を承継したい」との回答は、8割弱に上る一方、「自分の代で廃業したい」との回答は、僅か3%しかない15。また、「事業を承継したい」との回答割合は、事業承継が現実味を帯びてくる60歳代以上の経営者で一層高くなっている。一方、事業承継にあたっての課題としては、「事業は安定しているが担い手や働き手が減少する」「後継者の経営能力が十分備わっていない」との回答割合が高くなっているほか、「後継者が決まらない、見つからない」との回答割合も2割強に上っており、能力面も含めた人材不足が懸念材料として挙げられている(第3-3-10図)。
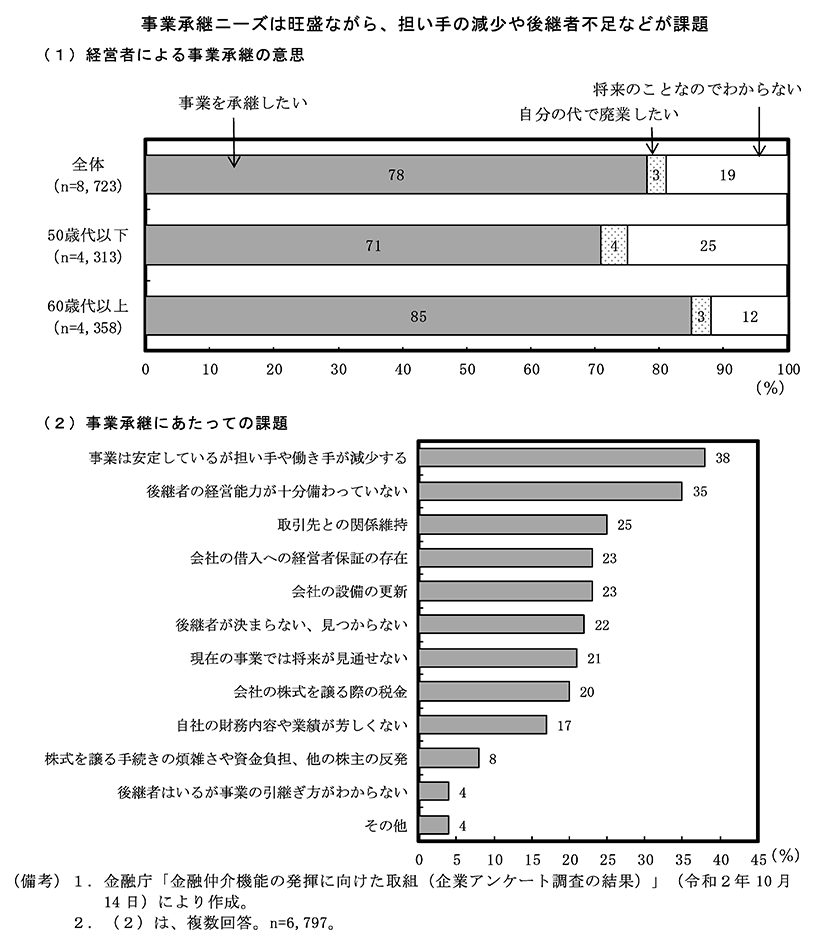
(事業承継を目的としたM&Aは、大都市圏を中心に増加傾向)
このような事業承継ニーズを満たす手段の一つがM&A(Mergers(合併)and Acquisitions(買収)))である。M&A総数は2011年を底に増加傾向にある。形態別では、国内企業同士の案件(IN-IN)が増加をけん引しているほか、企業の属性別では、上場企業による未上場企業の買収、未上場企業同士の買収が増加している。事業承継を目的としたM&Aも増加傾向にあり、2018年以降、年間600件前後と過去に比べて高い水準となっている。都道府県別では、事業所数の多い東京都が圧倒的に多く、次いで大阪府、愛知県、神奈川県といった大都市圏で多くなっている(第3-3-11図)。事業の将来性や相応の技術力がある企業について、そのノウハウや雇用をM&Aという形で存続させることは、我が国全体の技術力等の維持にもつながると考えられる16。
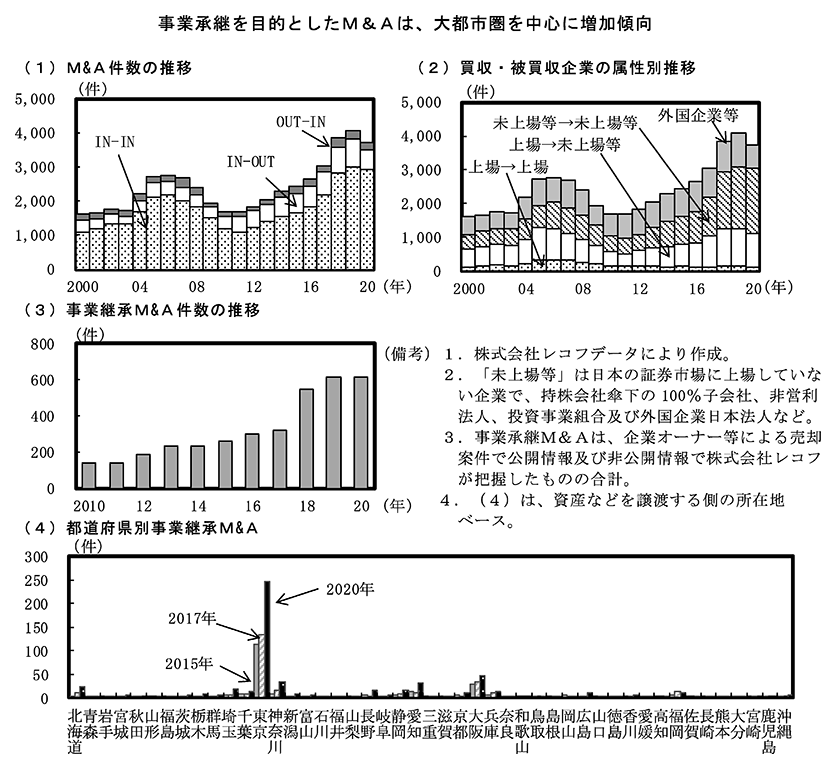
3 地域経済を支える地域銀行の収益性
(地域銀行の収益力は低下傾向。感染症による貸出増も、信用コスト増は限定的)
最後に、人口減少が進む地域経済を支える地域銀行に求められる機能とその収益性について検討する。地域銀行は、金融仲介サービスを通じて地域経済の活性化に貢献し、地域企業との持続的な共存・共栄を図ることが求められるが、当該金融機関の健全性確保はその前提となる。
まず、貸出の長期推移をみると、2000年から2009年までの10年間は、関東で-6.6%、中部・北陸で-7.7%、近畿で-23.7%、北海道・東北で-4.2%、中国・四国で-0.8%、九州・沖縄で-4.8%と減少傾向にあった。その後、2010年から2019年までの10年間をみると、関東で+27.6%、中部・北陸で+17.0%、近畿で+10.1%、北海道・東北で+23.6%、中国・四国で+28.6%、九州・沖縄で+37.6%と、総じて増加傾向にある。特に、九州・沖縄における増加が目立つ。
また、最近の推移を月次でみると、緊急事態宣言を発出した2020年4月以降、1節でも触れたように、前年比+5%前後~+10%前後の積極的な貸出が行われており、地域経済を支える金融仲介機能を発揮している(第3-3-12図)。
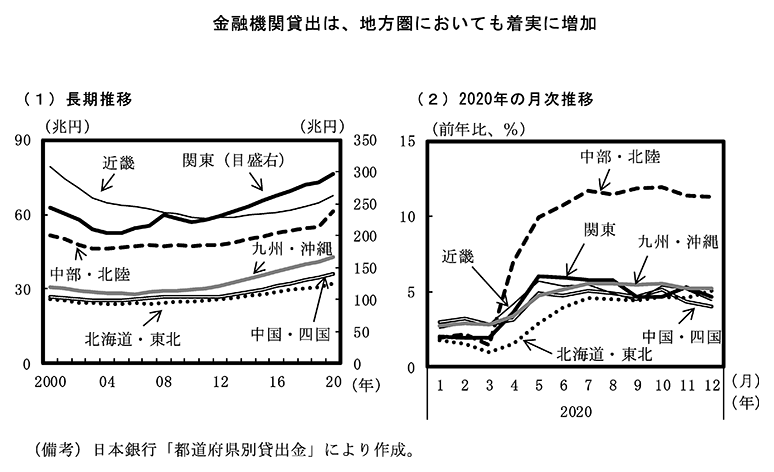
一方、収益性を示す総資金利ざやの推移をみると、低下傾向が続いている。低金利環境が継続する中で、その水準は「北海道・東北」で都銀の4割程度、「中部・北陸」でも6割程度で、いずれも1%に満たない。総資金利ざやの内訳では、いずれの地域においても、貸出金利ざやの低下が目立つ(第3-3-13図)。
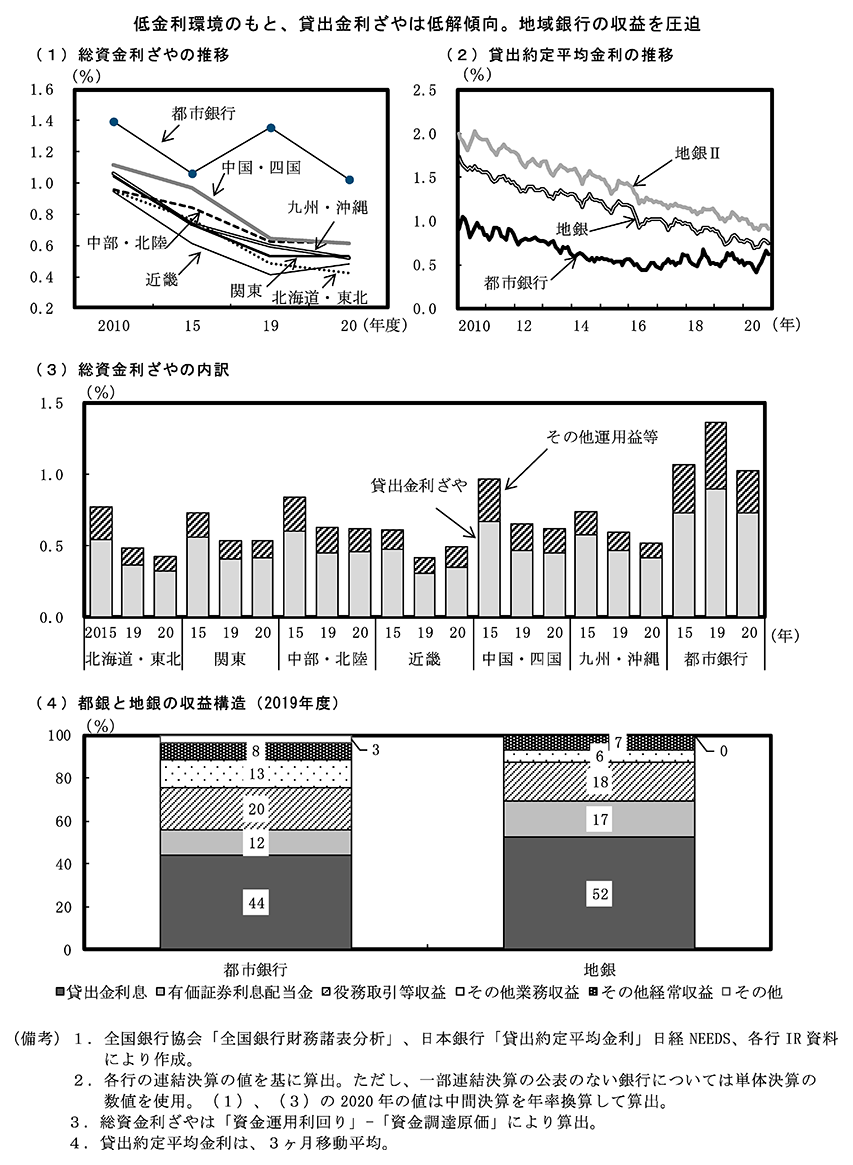
地域銀行の収益に占める貸出利息の比率は5割超と、依然として収益の柱となるなかで、これまでは、低金利環境が続いても、貸出増加と、倒産減少による信用コストの低下から、地域銀行は収益を確保してきた。しかし、感染症の影響により融資先の収益悪化が続くことになれば、信用コストが今後増加する可能性も考えられる。
そこで、2008年度から2020年度上期までの信用コストの状況について確認する。2009年以降、金融円滑化法やその後の緩やかな景気回復と低金利環境の継続により、企業倒産が減少を続ける中、信用コスト及び信用コスト率17は低下を続け、2016年度には、両者ともにリーマンショック時の2008年度の20分の1程度の水準となった。その後、2018年度は、個別行の不動産融資に絡む信用コストの多額計上から地域銀行全体でも増加し、2019年度も同程度の水準となった。
これまでは、過去の貸倒実績等を基に一定の計算式に基づく引当実務が定着していたが、金融機関が認識している将来の貸倒れリスクを適切に反映し切れない等の弊害が認識されるもと、2019年12月に金融検査マニュアルが廃止された18。こうした流れもあり、地域銀行でも、将来の信用リスク評価をより的確に引当に反映するための工夫が広がっている。こうしたことから、2019年度の信用コストは2018年度と同程度の水準となっている。
感染拡大による資金繰り支援融資が大幅に増加した2020年度の信用コスト(上期実績)は、感染症ショックの将来影響を加味した引当を行う地域銀行が増加したこともあり19、2019年度上期対比3割弱増加した。ただし、信用保証協会承諾融資が、年度前半だけで例年の3倍弱まで増加し、信用リスクを肩代わりしていることもあり、地域銀行における信用コスト及び信用コスト率の増加は限定的となっている20。
また、2010年度以降、地域銀行の自己資本比率はごく緩やかに低下してきたが、BIS規制の基準(国内基準行4%、国際基準行8%)は十分達している(第3-3-14図)。
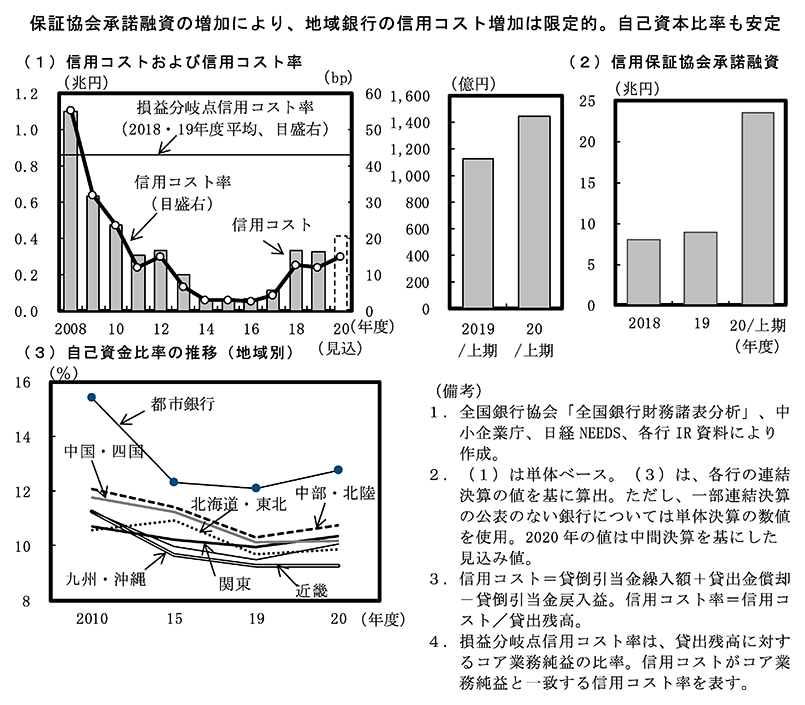
(人口減少地域店舗を削減、人口集中地域に進出し、貸出利息収入を確保)
低金利環境が続く中、地域銀行が取り得る収益確保の手段としては、①経費削減、②貸出増加、③貸出以外(手数料ビジネス)の収益拡大、④リスク性資産運用の拡大などが考えられる。ここでは、①経費の削減と②貸出の増加について、地域銀行の店舗展開の観点から確認する。
地域銀行の経費率(OHR)21の推移をみると、利益が減少傾向を続ける中で、営業経費の削減を続けている(第3-3-15図(1))。営業経費の大部分は人件費と物件費が占めており22、店舗展開はその動きを決める重要な要素である。そこで、2010年度から2018年度にかけての地域銀行の店舗展開をみると、関東に本店を構える銀行以外の地域銀行は、県外店舗を増加させる一方で県内店舗を削減し、総店舗数は削減する傾向にある(第3-3-15図(2))。
県内店舗数増減と本店所在地(都道府県レベル)の人口増減には正の相関があり、店舗数増減と営業経費増減にも正の相関があることから、地域銀行は、人口減少に直面している県内店舗数を削減していることがうかがえる。ただし、こうした経費削減によっても利益縮小は補いきれず、2010年度に比べて、経費率は上昇している(第3-3-15図(3)、(4))。
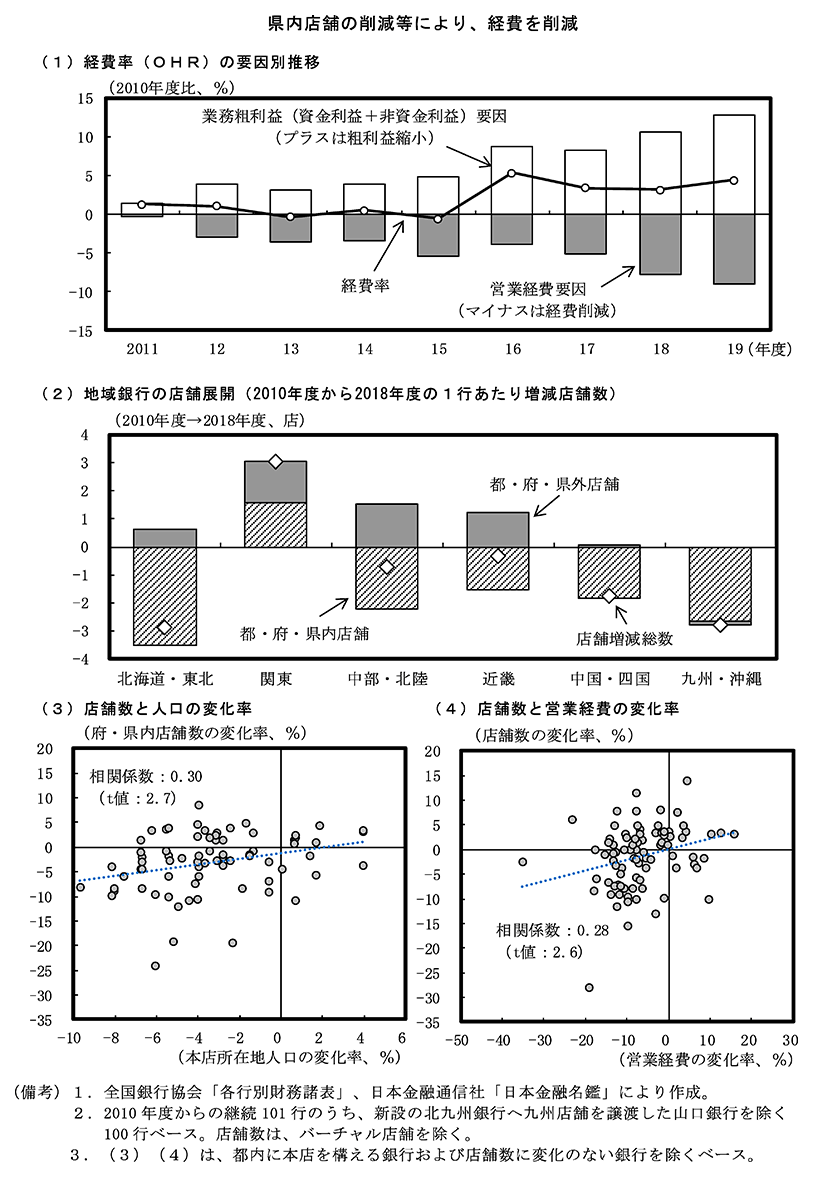
関東圏を除く地域の地域銀行が、本店所在県内の店舗を削減し、県外へ進出していることを確認したが、進出先は、人口が多く、それに伴う事業性融資の機会も多いと考えられる人口集中地域(人口密度が4,000人/km2以上の市区町村23)が自然である。実際、地域銀行による人口集中地域への店舗数及び出店舗割合は、ともに緩やかに増加している(第3-3-16図)。
県外人口集中地域にある地域銀行の店舗割合の変化と当該銀行の貸出残高の伸び率の間には、緩やかではあるが、正の相関がみられる(第3-3-16図(2))。ただし、県外人口集中地域の店舗割合の変化と当該銀行の貸出利回りには相関はみられず、人口集中地区への進出は、量的な拡大とそれに伴う収益改善には貢献しているものの、収益率(利鞘)の改善に貢献しているとはいえない(第3-3-16図(3))24。
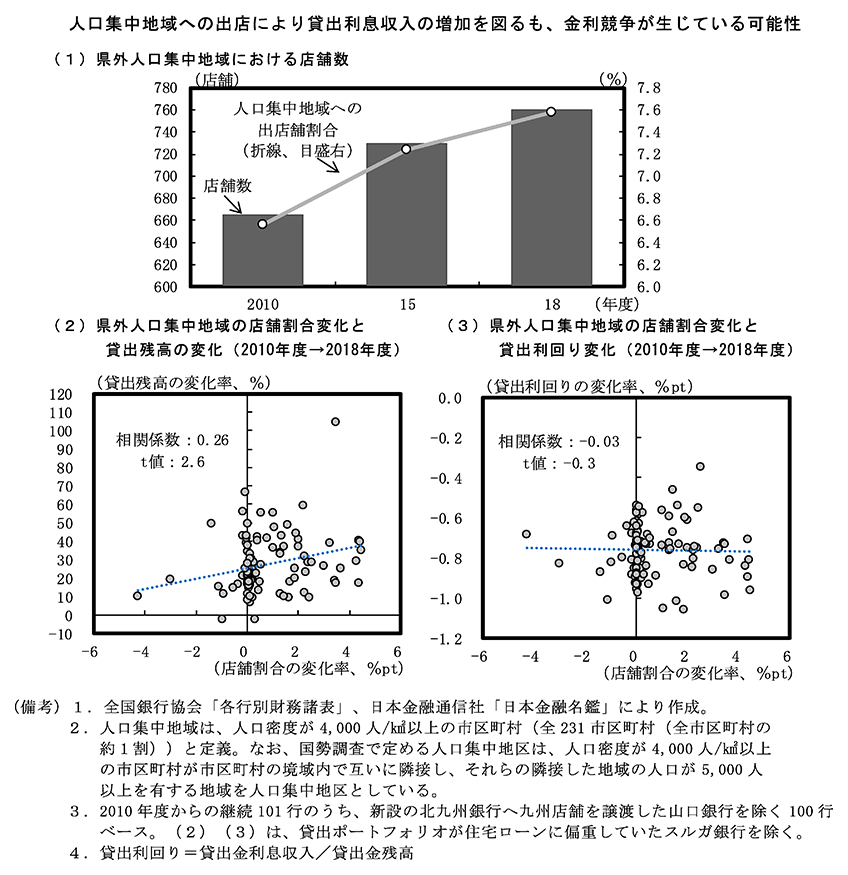
(地域経済活性化に資する仲介機能を発揮することで、収益の多角化を図る必要)
我が国全体が高齢化と人口減少に直面していることを踏まえれば、地域銀行の店舗戦略(県内(人口減少地域)の店舗を減少させて、需要の見込める県外(人口集中地域)に進出し、貸出量の増加による収入の獲得を図る)の有効性も次第に失われていくと見込まれる。
金融庁のアンケート調査によれば、企業がメインバンクから提案された融資・サービスの利用率は、当然ながら、設備・運転資金等の借入の利用率が最も高いが、付随サービスは伸び悩んでいる(第3-3-17図)。例えば、取引先・販売先や経営人材の紹介、財務内容改善や事業計画作成などの各種支援策は1割程度、M&Aなど、金融仲介機能以外のヒト・モノ・情報の仲介機能の利用率は5%程度に止まっている。こうしたサービスを強化・充実させることは、地域経済の活性化とともに、手数料ビジネスといった収益の多角化にも資すると考えられる。今後は、より地域に密着するなかで、金融・ヒト・モノ・情報の仲介機能を発揮し、地域内での新規事業や雇用機会を創出することで、地域経済とともに成長していくことが求められる。
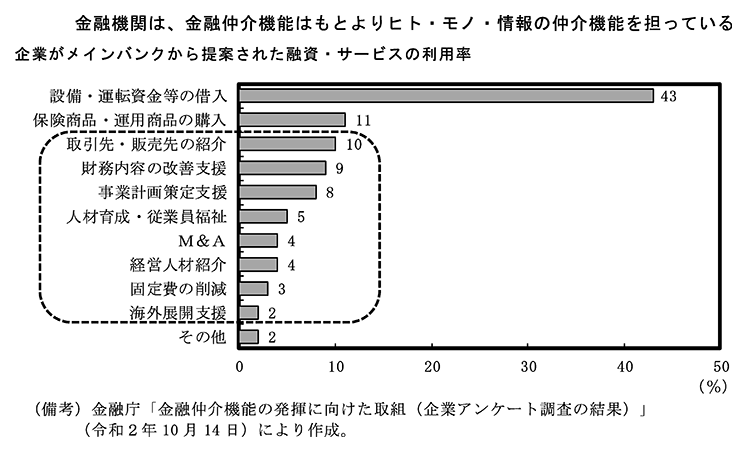
なお、過去10年程度を振り返ると、経営基盤強化に向けた地域銀行の統合が進展している(第3-3-18図)。2021年は、地域銀行が主体となるデジタル銀行が2社開業するなど、IT化の潮流を捉えたビジネスモデルの確立に向けた動きも出ている。こうした経営基盤強化と収益の多角化を同時に進めることで、地域経済と地域銀行の持続可能性を高めていくことが求められている。