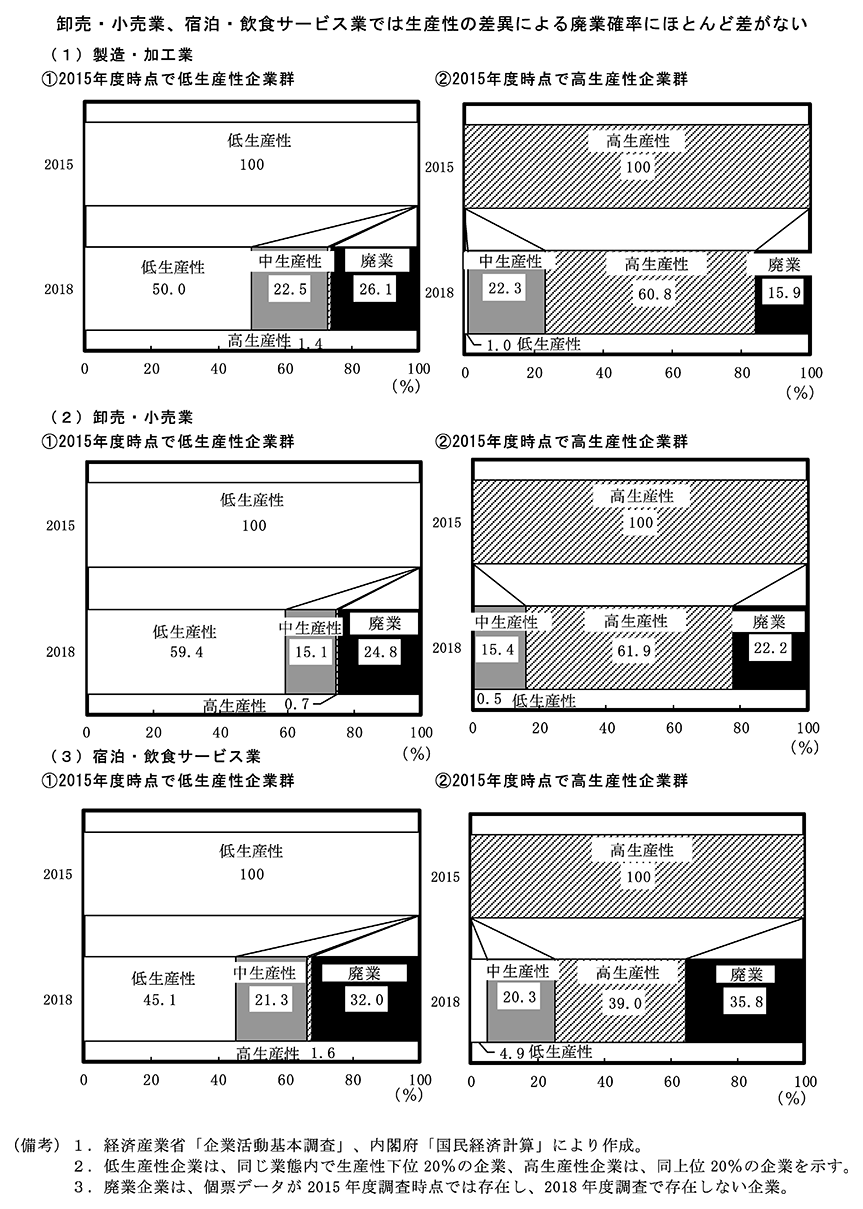第3章 ポストコロナに向けた企業活動の活性化と課題(第2節)
第2節 倒産・廃業と開業
前節では、感染拡大とその防止策により大幅に悪化した企業収益が、金融支援や経済活動の再開によって、著しい資金繰り難は回避できている点を確認した。本節では、こうした状況下における、倒産・廃業や開業の状況を確認する1,2,3。また、長期的な観点から、国際比較も交えた動向と、我が国の特徴についても整理する。
1 倒産・廃業の動向
(倒産件数は長期的に減少するも、人手不足関連倒産比率は上昇)
我が国の倒産件数は、景気拡張局面の持続や緩和的な金融環境の効果もあり、これまで減少傾向が続いていた。リーマンショック以降をみると、業種別では、「不動産・建設」や「卸売業」の減少が特に目立つが、いずれの業種も総じて減少傾向にある。また、資本金1億円以上の大・中堅企業の倒産は、2015年以降、100件未満に止まっており、1億円未満の中小企業も減少傾向が続いている(第3-2-1図(1))。
一方、倒産全体に占める人手不足関連倒産比率は上昇傾向にあり、なかでも後継者難による倒産比率が高い(第3-2-1図(2))。帝国データバンク「全国・後継者不在動向調査」によれば、社長の年代別にみた後継者不在率は、70・80歳代でも3~4割程度に上る。我が国の生産年齢人口は1995年をピークに、総人口は2008年をピークに減少へと転じ、中小企業における後継者不足は積年の課題である。実際、2011年調査と2020年調査を比較しても、後継者不在率はほとんど変わっておらず、依然、有効な手立てが講じられていないことが示唆される(第3-2-1図(3))。
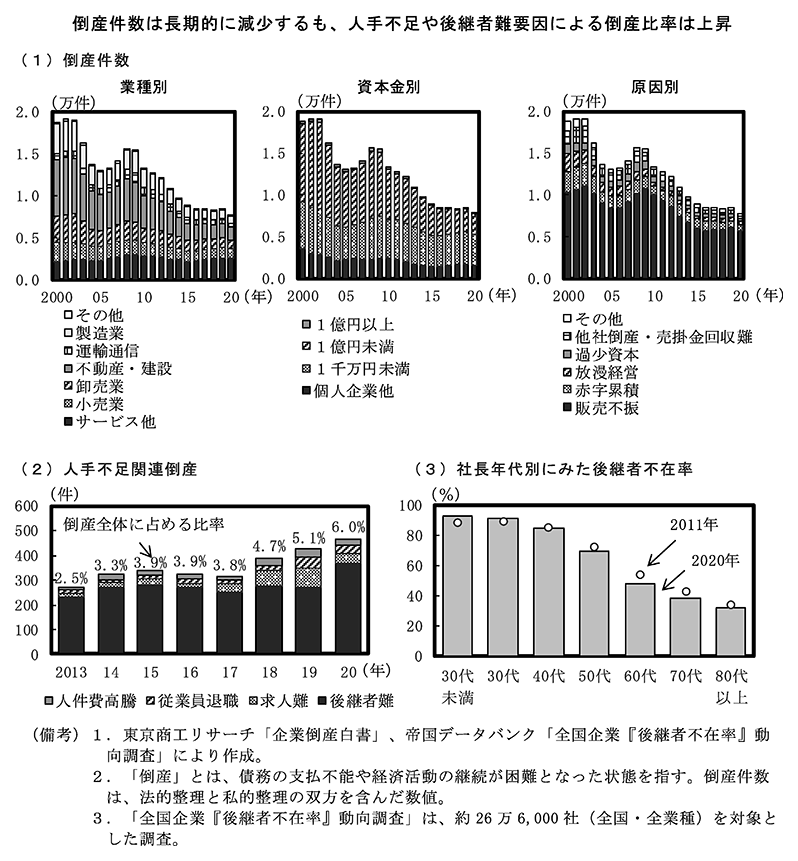
また、廃業の推移をみると、2000年代半ば以降、経営実態のない「みなし解散」が増加、「休廃業」及び「解散(みなし解散を除く)」はおおむね横ばいの動きとなっている(第3-2-2図(1))。また、代表者の年齢別内訳をみると、経営実態のない「みなし解散」の増加によって年齢不明の件数が増加しているが、年齢不明者を除いた構成比では、70歳代以上の比率が年々高まっている(第3-2-2図(2))。倒産件数が減少傾向であるのに対し、みなし解散の扱いや各種調査の違いにより振れはあるものの、「休廃業」や「解散」は、少なくとも年間1~3万件程度で横ばい、「みなし解散」を含めると増加傾向が続いており、その背景には、経営者の高齢化と後継者不足の問題があると考えられる。
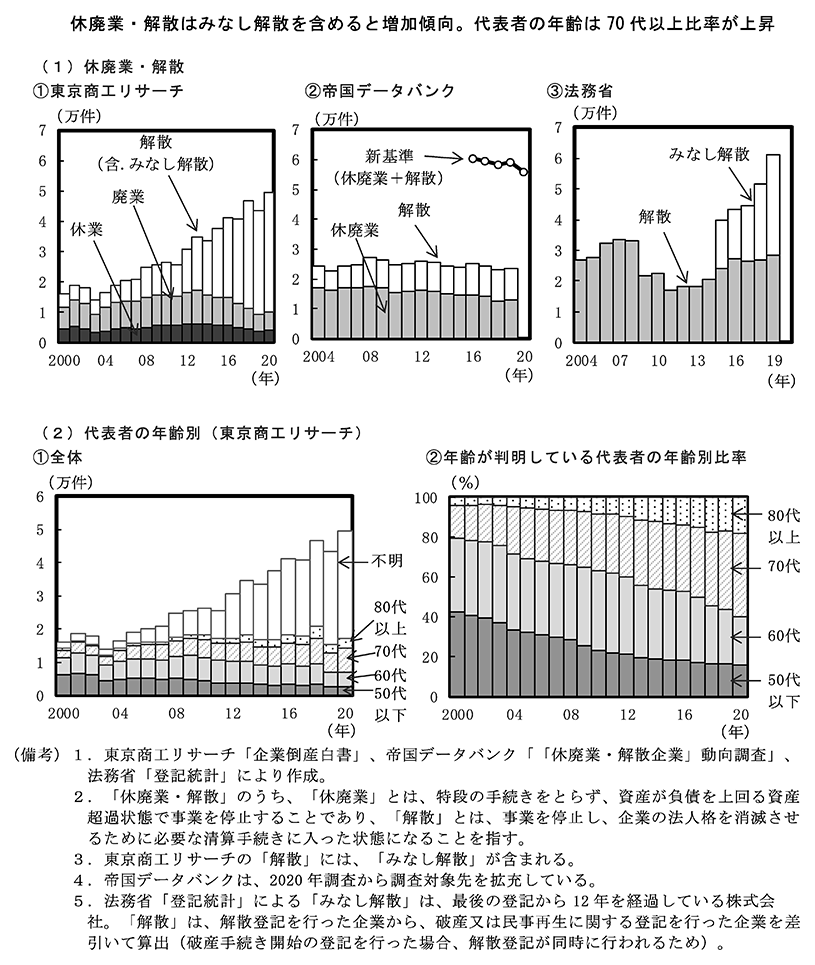
(感染拡大の影響により企業収益は悪化したが、2020年の倒産件数は減少)
2020年における倒産件数の累積月次推移をみると、感染症による業績悪化を理由とする倒産件数4は増加傾向にあったが、倒産全体としては、5月以降、前年比横ばいないし減少傾向であった5。なお、感染症の影響を理由とする倒産件数は、大幅な減収となった飲食・宿泊業や生活関連サービス・娯楽を含む「サービス他」が最も多く、次いで「卸売業」、「製造業」が多い(第3-2-3図(1))。
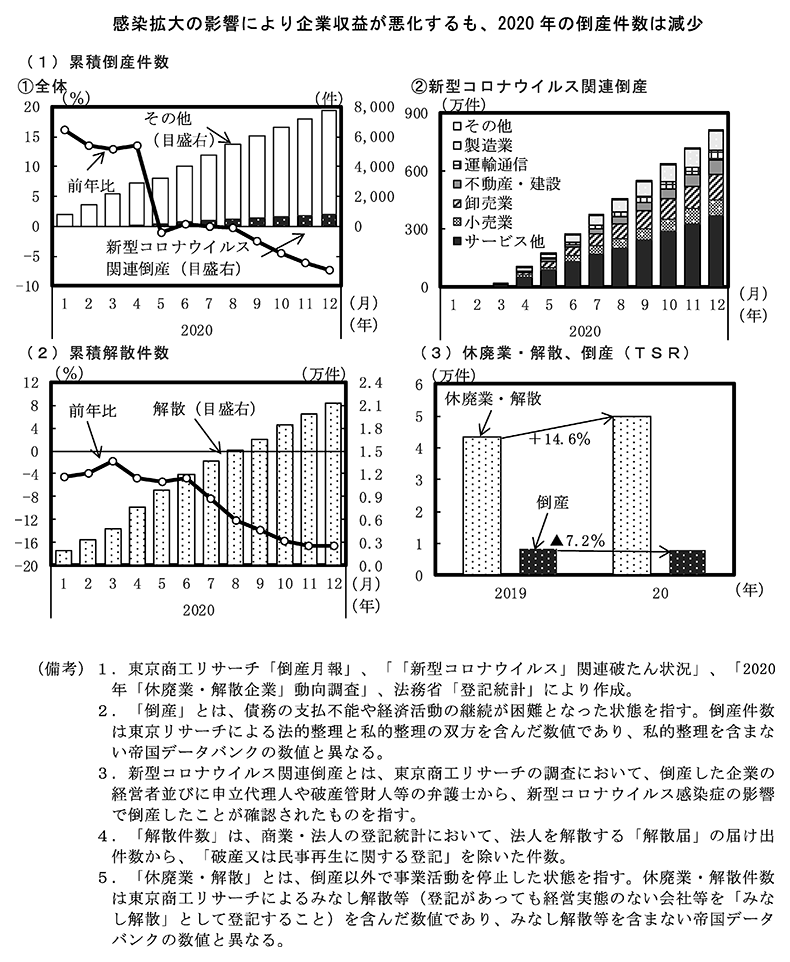
また、法務省「登記統計」により、法人を解散する「解散登記」件数から「破産又は民事再生に関する登記」件数を差引き、債務超過による倒産を除いた廃業(解散)件数をみると6、その前年比は減少傾向で推移している(第3-2-3図(2))。一方、東京商工リサーチの「休廃業・解散企業」動向調査によれば、2020年の休廃業・解散件数は大幅に増加している(第3-2-3図(3))。登記統計では、法的解散手続を取っていない休業状態の企業や経営実態のない「みなし解散」の企業を把握できない7ことから、感染拡大により休業を余儀なくされた企業や、その後「解散登記」を行うことなく経営を諦めた企業が増加している可能性がある。
(企業収益が悪化しても倒産件数が減少した要因の一つは手元流動性の増加)
感染拡大の影響により企業収益が悪化する中にあっても、倒産件数は非常に抑制されていた。倒産件数が増加しなかった要因の一つは、政府による金融支援であろう。実際、倒産件数と企業の手元流動性とを比較すると、倒産件数が大幅に減少した2020年4-6月期に企業の手元流動性は大幅に増加している(第3-2-4図(1))。そこで、両者の関係について回帰分析を行ったところ、手元流動性の増加は、倒産件数を有意に減少させる点が確認された(第3-2-4図(2))8。
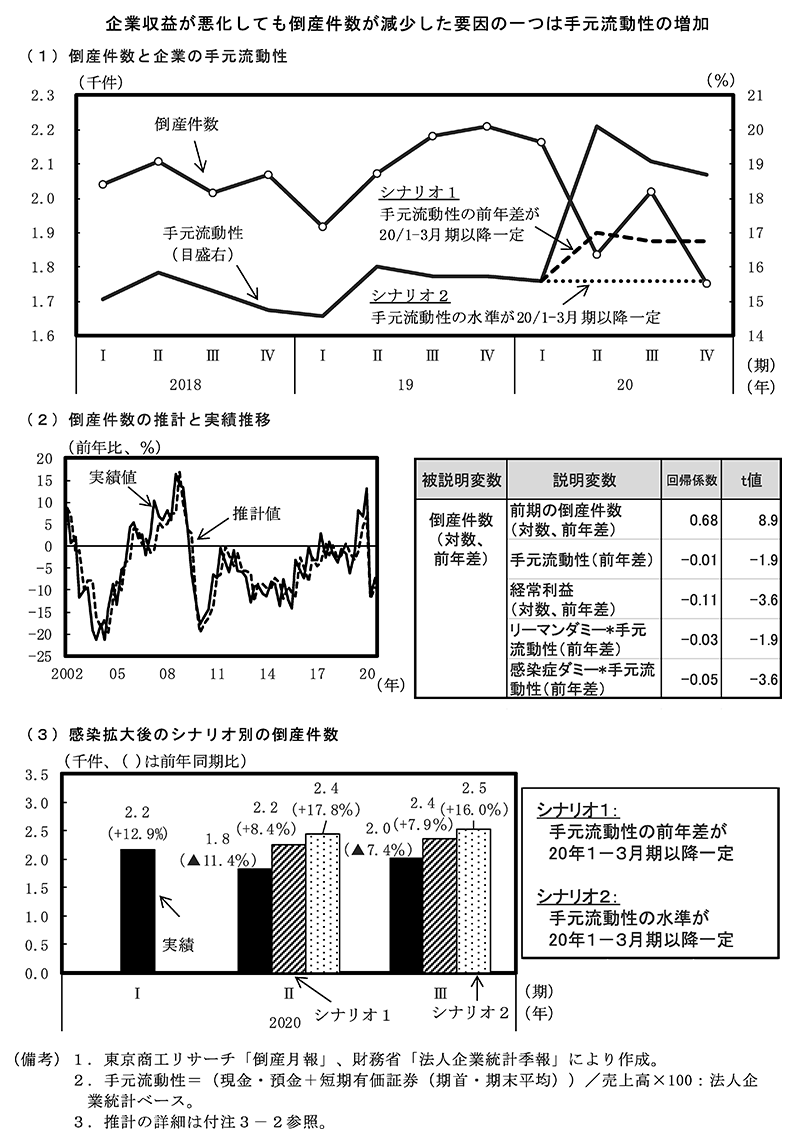
手元流動性の増加による倒産抑制効果を定量的に把握するために、2つのシナリオを想定しよう。シナリオ1は、手元流動性の前年差が、金融支援がなされる前の2020年1-3月期以降一定とした場合、シナリオ2は、手元流動性の水準が2020年1-3月期以降一定とした場合である。これら2つのシナリオに沿った倒産件数を試算すると、2020年4-6月期の実績値が前年比-11.4%であるのに対し、シナリオ1では同+8.4%、シナリオ2では同+17.8%となる。この結果からは、手元流動性の増加により、倒産件数が前年比で20~30%ポイント程度、件数では4~6百件程度は抑制されたと推察できる。7-9月期についても同様に試算すると、実績値が前年比-7.4%であるのに対し、シナリオ1では同+7.9%、シナリオ2では同+16.0%となっており、やはり、手元流動性の増加により15~23%ポイント程度、件数では4~5百件程度の倒産が抑制されたと推察できる(第3-2-4図(3))。
このように、流動性供給は、倒産抑制に有効であるが、実質無利子であっても返済義務はあるため、過度な負債は将来の企業経営リスクになり得る。そうしたことから、資本とみなせる劣後ローンの利用拡大、感染状況を踏まえた需要喚起による企業業績の回復を図ることが重要である。
2 開廃業の動向
(我が国の開業率は、廃業率を上回って推移)
前項では、市場から退出する企業動向について、特に2020年の動きに注目して整理したが、ここではすう勢的な傾向に着目し、開廃業と成長の関係について整理する。まず、開業率及び廃業率の長期的推移を法務省「登記統計」によって確認すると、1997年以降、一貫して開業率が廃業率を上回っている9。加えて、開業率は2009年を底に緩やかな増加傾向にある(第3-2-5図(1))。2020年は厳しい経営環境に見舞われたが、それでも開業数は2019年と同じペースで月を追うごとに増加し、2020年計で118,999件と、東京商工リサーチ調べによる年間の倒産、休廃業・解散件数(57,471件)を上回っている(第3-2-5図(2))。
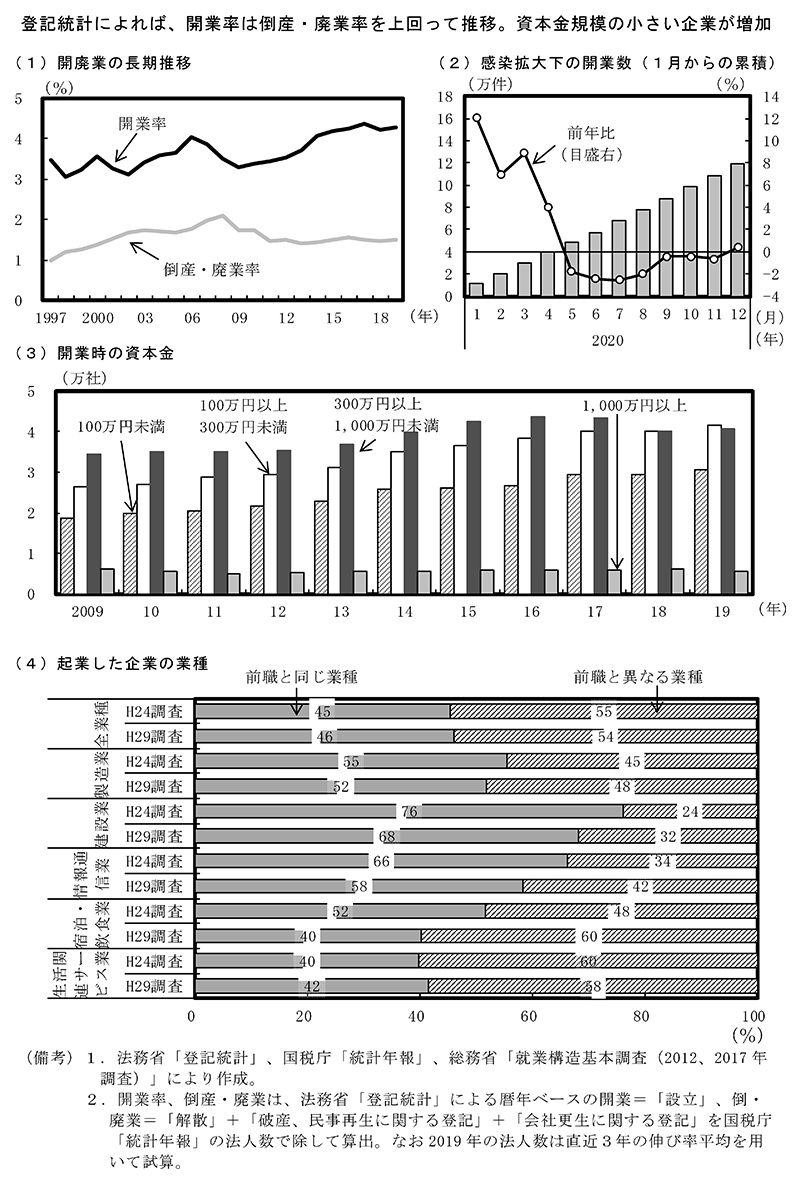
開業数を開業時の資本金別にみると、2006年の会社法施行により、最低資本金の規制が廃止されたことで10、資本金300万円未満での開業が増加している(第3-2-5図(3))。2019年の資本金金額別の開業数割合は、資本金100万円未満が26%、同100万円以上300万円未満が35%となっており、同1,000万円以上は僅か5%にすぎない。資本金1,000万円未満の小規模事業者は、法人企業統計調査や短期企業経済観測調査、企業活動基本調査といった公的統計の調査対象外であり、その動向を把握するのは難しい。
そこで、動向の一部が事業主から把握できる総務省「就業構造基本調査(2012、2017年調査)」によって、起業業種をみると、製造業、建設業、情報通信業では、これまでのスキルを活かし、前職と同じ業種で起業する者の割合が比較的高い(第3-2-5図(4))。一方、宿泊・飲食業や生活関連サービス業では、前職は異なる業種に属していた者による起業割合が比較的高い。サービス関連業種は、製造業、建設業、情報通信業といった業種と比べ、参入障壁が比較的低い結果となっている。
(我が国の開廃業率は、他の主要先進国よりも低い)
こうした開廃業の状況を他の主要先進国と比較してみると、開業率は、最も高い英国で13%程度、アメリカで9%程度である一方、我が国は4%程度と、これらの国の半数にも満たない。また、廃業率は、英国が11%程度、アメリカが8%程度と、開業率と同程度の廃業率となっているなかで、我が国の廃業率は1.5%程度と圧倒的に低い。この結果、開廃業率の和も、主要先進国と比べて小さく、我が国企業の新陳代謝は非常に低くなっている(第3-2-6図)。
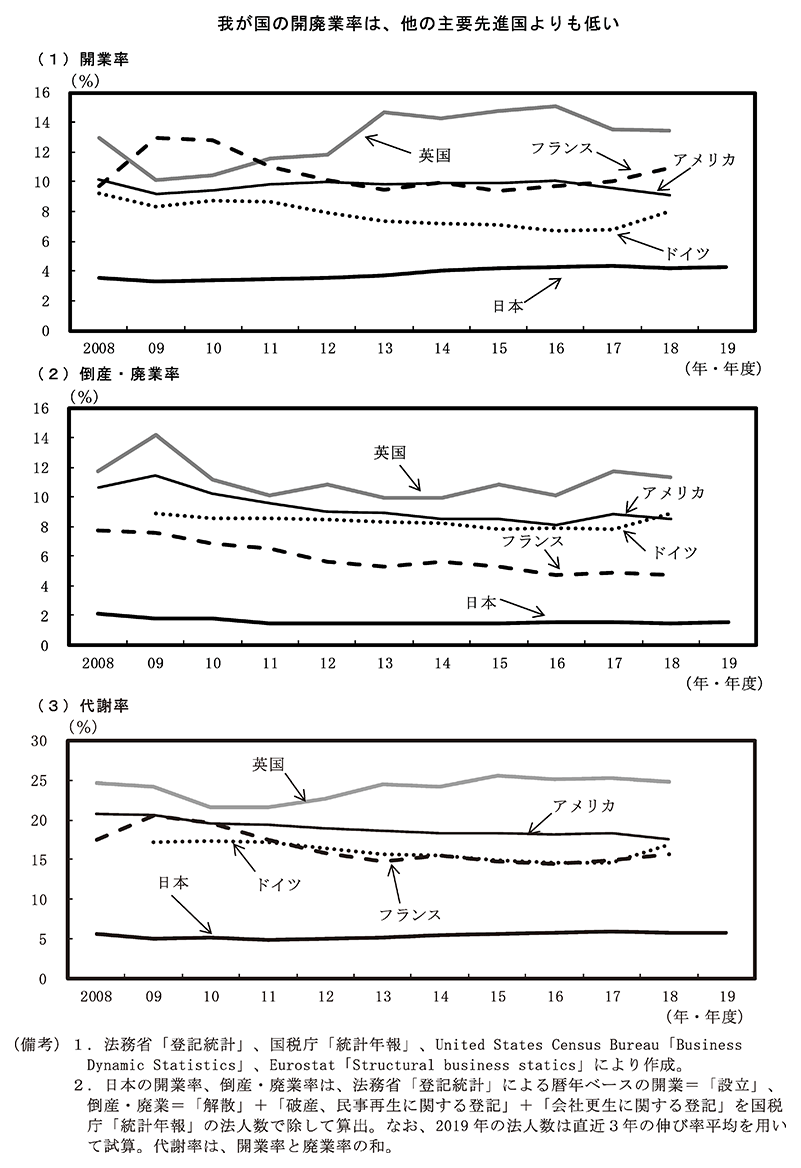
(起業年齢が高まるなか、後継者問題は今後さらに深刻化する可能性)
我が国の開業動向について、起業年齢を1990年代、2000年代、2010年代で比較すると、39歳以下の比率が低下し、60歳以上の比率が上昇している。この結果、開業時の平均年齢は、1990年代の39.6歳から2010年代の42.4歳へ3歳弱上昇している。この間、我が国の平均年齢も、39.0歳から45.7歳と、7歳弱上昇しており、全体の高齢化によって起業年齢が上昇した面もある。また、再雇用制度が拡充されているとはいえ、人生100年時代を見据える中で、雇用に限らない働き方の模索が、中高年の起業を促している面もあろう(第3-2-7図(1))。
就業者全体の年齢分布と自ら起業した経営者(以下、起業経営者)の年齢分布を比べると、起業経営者は60歳代以上の比率が高く、特に、製造業では7割弱を占める。こうした起業経営者の高齢化は、スムーズな事業承継が行われない限り、培った有形・無形の資産喪失に直結するリスクが高まっていることを示唆しており、今後の潜在成長力に影響する可能性がある(第3-2-7図(2))。
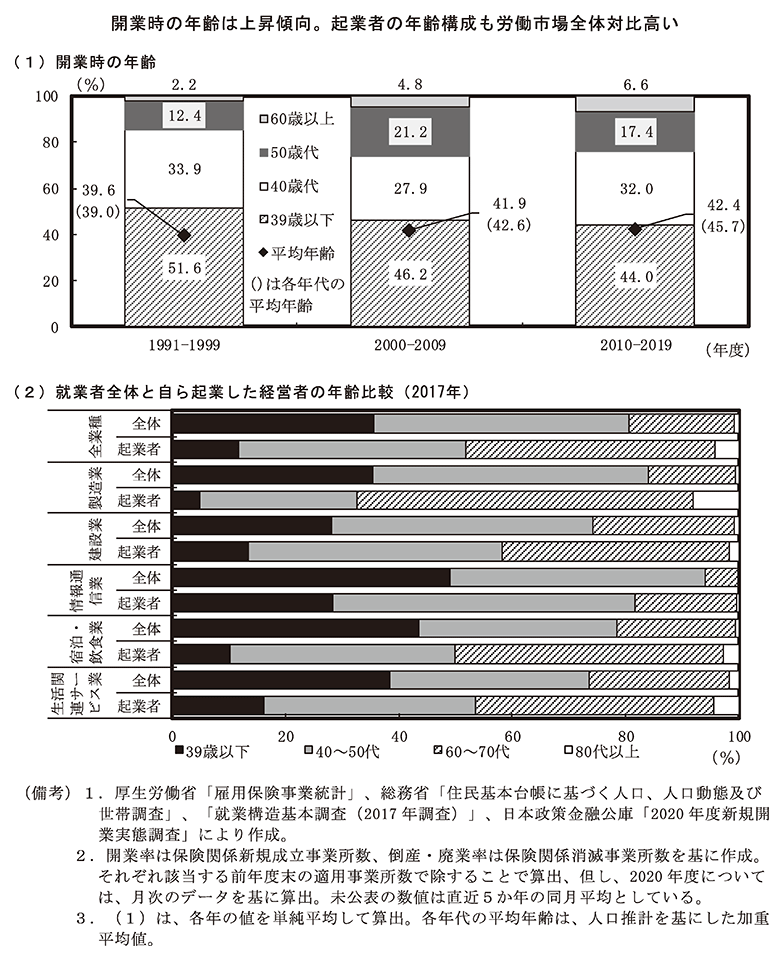
3 経済成長との関係
(企業の活発な開業は経済成長とプラスの関係)
我が国企業の開業は、何れも他の主要先進国よりも低いが、これは、経済成長率と関係があるのだろうか。OECDの主要先進国について、2013年から2017年の5年平均の開廃業率及びそれらの和を代謝率と定義して、それぞれと経済成長率の関係を描くと、開業率が高い国は、GDP成長率が高い傾向にある(第3-2-8図)。
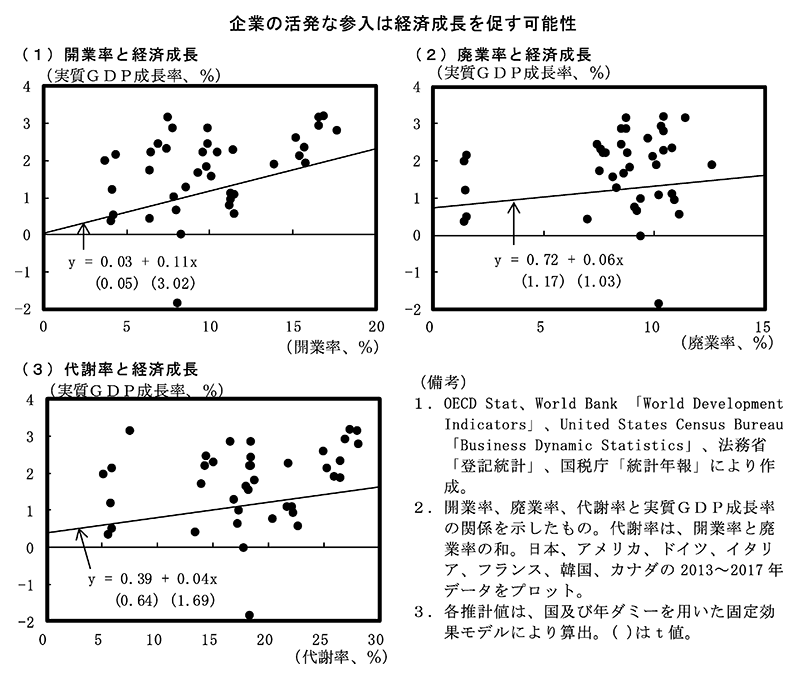
この関係は統計的にも有意であるが、廃業率や代謝率とGDP成長率との間には、こうした有意な相関はみられない。少なくとも、企業の活発な開業とマクロ的な経済成長にはプラスの関係があるといえる。
(存続企業と廃業企業の付加価値成長率、TFP成長率の差は縮小傾向)
企業の活発な開業は、経済成長率の高低と相関しているが、その背景にあるメカニズムは、成長力が劣る企業が市場から退出し、より高い成長を実現する企業が参入して存続することが、マクロの経済成長をもたらすということである。この点をミクロで確認するため、経済産業省「企業活動基本調査」の個票データを用いて、事業を継続する存続企業と廃業企業との付加価値成長率及びTFP成長率の差について比較しよう。なお、ここでは、T年に存在していた企業のうち、T+1年も存在している企業を存続企業としている。
まず、付加価値成長率とTFP成長率はともに、存続企業の方が廃業企業よりも高いことから(マイナスの場合はマイナス幅が小さく)、付加価値成長率やTFP成長率が低い企業は廃業しやすい傾向にある。ただし、両者の付加価値成長率やTFP成長率の差は縮小傾向にある。この背景には、収益以外の要因、例えば、後継者不足や人手不足といった要因により、高成長企業が廃業している可能性も示唆される(第3-2-9図)。
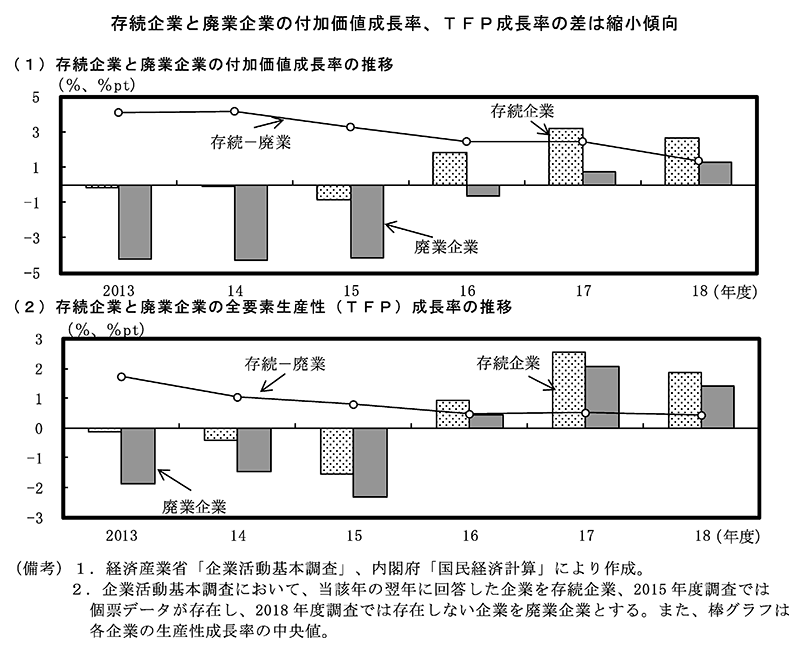
(卸売・小売、宿泊・飲食サービスは生産性による廃業確率差がほとんどない)
では、廃業企業と存続企業の成長率格差に業種の違いはあるだろうか。そこで、主要業種ごとの企業別TFP水準について、上位20%と下位20%の企業群が3年後に継続したか廃業したかを確認しよう。具体的には、2015年度時点で低生産性企業ないし高生産性企業であった企業が、2018年度に廃業を含むどの生産性分位に変遷したかを確認する。
製造・加工業について、2015年度時点で低生産性群の企業(2,426社)が3年後に廃業している確率は26%程度であり、同業同時点における高生産性群の企業(2,427社)の廃業確率の約1.6倍と高く、過去の生産性水準がその後の継続・廃業の違いになっている(第3-2-10図(1))。しかし、卸売・小売業(1,781社、1,782社)や宿泊・飲食サービス業(122社、123社)については、こうした差がほとんどみられない(第3-2-10図(2)、(3))。宿泊・飲食サービス業はサンプル数が小さい点に留意が必要であるが、これらの業種では、TFP水準が高い優良企業であっても、新陳代謝が進むことで継続が困難になる、あるいは、人手不足や後継者不足を含む、他の理由により廃業を選択する企業が相当数あることを示している。