第1章 感染症の危機から立ち上がる日本経済(第3節)
第3節 感染拡大後の対外経済の動き
感染症の影響により厳しい状況に置かれた日本経済が持ち直していくためには、海外経済の改善を国内に取り込んでいくことが不可欠である。その際、単に輸出入を通じた外需の動向だけではなく、海外との投資関係を通じた収益面の状況や、グローバルな生産体制の構築といったサプライチェーンの在り方も重要な論点となる。同時に、為替レートの変動やエネルギー輸入のコストといった対外的なリスクにも目配りすることが求められる。
そこで、本節では、感染症の影響下における対外経済の動きとその我が国への影響について、財・サービス貿易等の対外収支と海外投資の動向や為替レートの変動要因と我が国経済に与える影響等を確認する。
1 外需の動向
(輸出の持ち直しをけん引した自動車等には一服感がみられるが、情報関連財は堅調)
まず、外需の動向をみていくと、2020年前半は、感染拡大前から弱含みで推移していた輸出が4、5月に急減したが、各国・地域における経済活動の再開に伴って持ち直し、年後半は増加となった(前掲、第1-1-1図)。財務省「貿易統計」を利用して月次推移をみていくと、対世界輸出の数量指数は5月を底に増加に転じた(第1-3-1図(1))。地域別にみると、大きく減少したアメリカ向けの輸出が急速に回復したことが特徴的ではあるが、11月以降はEU向けと同様に反落している。しかし、全体の5割を占めるアジア向け輸出が順調に増勢を維持していることが底堅さにつながっており、中国、NIES、ASEANの何れにも増加基調が確認できる(第1-3-1図(2))。
品目別にみると、自動車関連財の持ち直しが顕著ではあり、10月には感染拡大前の2月水準を回復したものの、その後は減少に転じている(第1-3-1図(3))。ただし、海外市場の自動車販売は堅調な地域が多いことから、当面は在庫変動の影響等を受けた振れを伴いながらも、底堅い動きになると期待される(第1-3-1図(4))。資本財も自動車関連財と同様の動きとなっているが、2021年1月は大きく増加した。機械受注の外需には増勢がみられることから、こちらも当面は堅調さを維持できるとみられる(第1-3-1図(5))。これらの品目とは対照的に、情報関連財は、年前半の下落幅も小幅であり、その後の増勢も顕著である。世界の半導体市場の見通しも上向きであり、こうした半導体と同製造装置等は、特にアジア向けを中心に、堅調に推移することが見込まれている(第1-3-1図(6))。
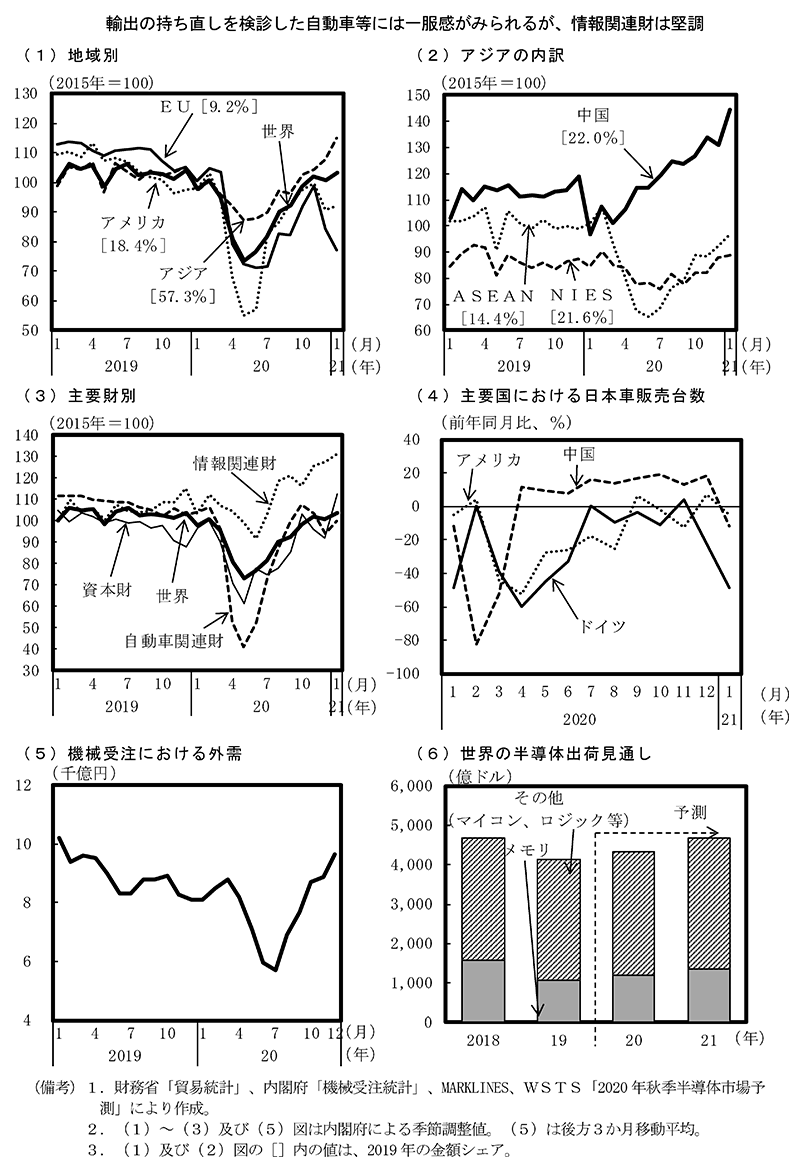
(輸入も内需の持ち直しに応じて下げ止まったが、先行きは感染拡大次第)
財輸入については、2月に中国において生産活動が停止したことに伴い、大幅に減少したものの、同国の経済活動の再開によって急激な増加がみられた(第1-3-2図(1)、(2))。地域別にみると、足下ではアジアやアメリカからの輸入が増加している。また、品目別にみると、内需の持ち直しに伴い、通信機や原動機等の一般機械・電気機器が増加している(第1-3-2図(3))。一方で、食料品輸入については、感染症の再拡大により、外食を中心とした内需の減少が影響を与えることが考えられることから、注視が必要である。
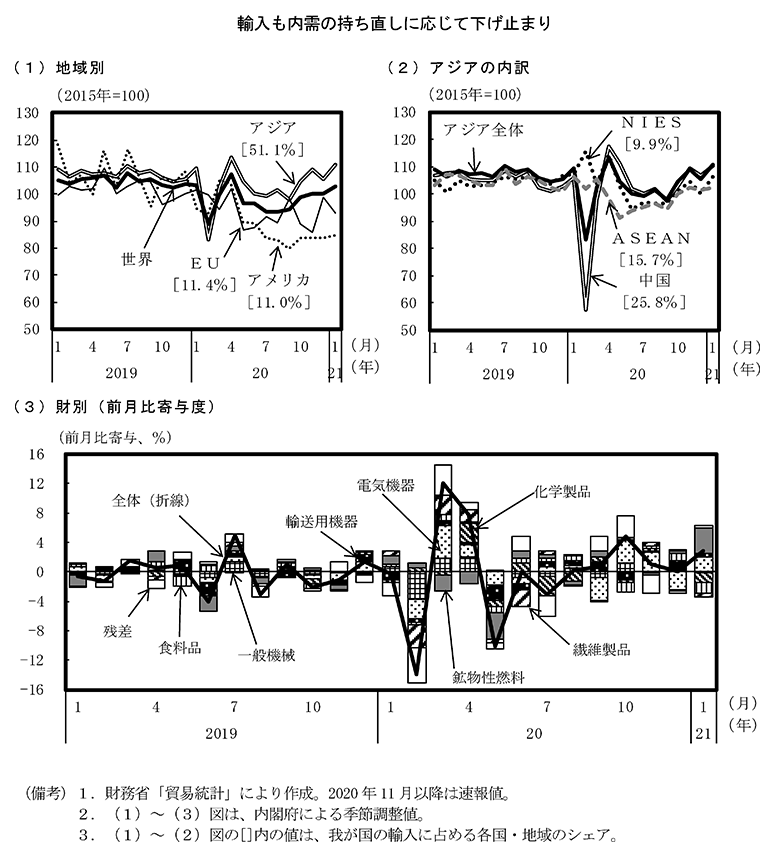
コラム1-5 エネルギー輸入の動向と課題
我が国の対外エネルギー依存度は、東日本大震災後の原子力発電の停止により化石燃料由来の電源比率が高まったことで、2014年度に94%まで達した。その後、原子力発電所の一部再稼働や再生可能エネルギーの緩やかな増加により、2018年度には88%まで低下したが、それでも対外エネルギー依存度は極めて高い。また、エネルギー源の多くを化石電源に依存する状況は、2050年のカーボンニュートラル1を実現する観点からも望ましくない(コラム1-5-1図)。
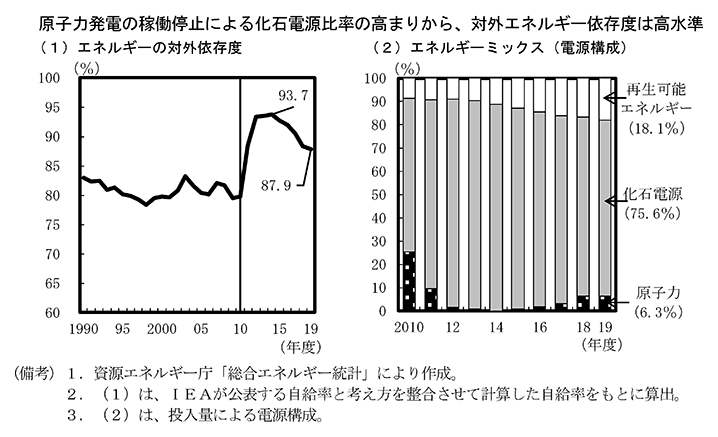
現実的な化石電源の代替先は、再生可能エネルギーと原子力発電であろう。再生可能エネルギーは、太陽光発電を中心に設備設置容量は急速に増加しているが、買取価格は毎年低下しているものの、企業・家計の電力コスト負担は増加している。再生可能エネルギー発電促進賦課金を通じた負担は世帯当たり月額774円(年間9,288円)(2020年度)となっており、日本全体(5,907万世帯)では実に約5,500億円/年の負担増になっている2。仕組み上、こうした負担は、今後とも増加が続く見通しにある(コラム1-5-2図)。
原子力発電は、2030年のエネルギーミックス(電源構成)目標の20~22%を担う予定であるが、現状では、国内原発33基中9基しか稼働できておらず、6%程度にとどまっている(コラム1-5-1図(2))。目標達成に向けて、適切な安全評価はもちろんのこと、国民の理解を得るために、より丁寧な説明を根気強く行う必要がある。カーボンニュートラルを実現する観点からも、より経済的な再生可能エネルギーの活用が期待される。
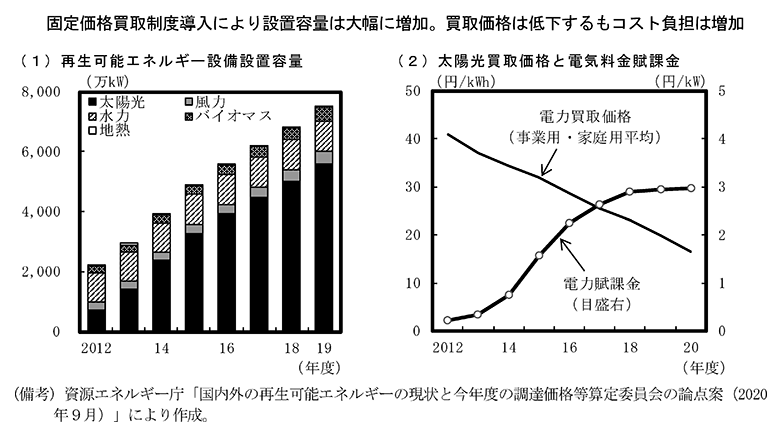
(インバウンド需要の回復時期は、国内外の感染動向や感染防止方法の確立次第)
最後に、サービス輸出入についてみていこう。2020年第1~4四半期の輸出及び輸入の前期比を財とサービスに分解すると、第3四半期までマイナスに寄与してきたサービス輸出は、10-12月期にプラス寄与に転じたものの、サービス輸入も弱い動きが続いている(第1-3-3図(1))。サービス収支の動きをみても、旅行収支の悪化により、感染拡大後は赤字が継続している(第1-3-3図(2))。サービス貿易に密接に関係する訪日外国人数と出国邦人数の動きをみると、各国政府が入国制限や渡航自粛勧告等を行ったことから、いずれも2020年1月から急速に減少し、4月以降も非常に低い水準で推移した(第1-3-3図(3))。その後、ビジネス目的や在留資格を持つ外国人の入国等について段階的な緩和が図られるなど、感染拡大防止と両立する形での国際的な人の往来の再開が徐々に進んだことから、訪日外国人数は僅かながら増加した。しかし、再度の緊急事態宣言発出に伴い、外国人の新規入国は特段の事情がない限り、停止されている。今後の取組として、感染状況が落ち着いている国・地域から、防疫措置を徹底した形での管理された小規模分散型パッケージツアーを試行的に実施することなどが検討されているが3、インバウンド需要の回復時期は、国内外の感染動向や感染防止措置の確立次第であり、不透明である。
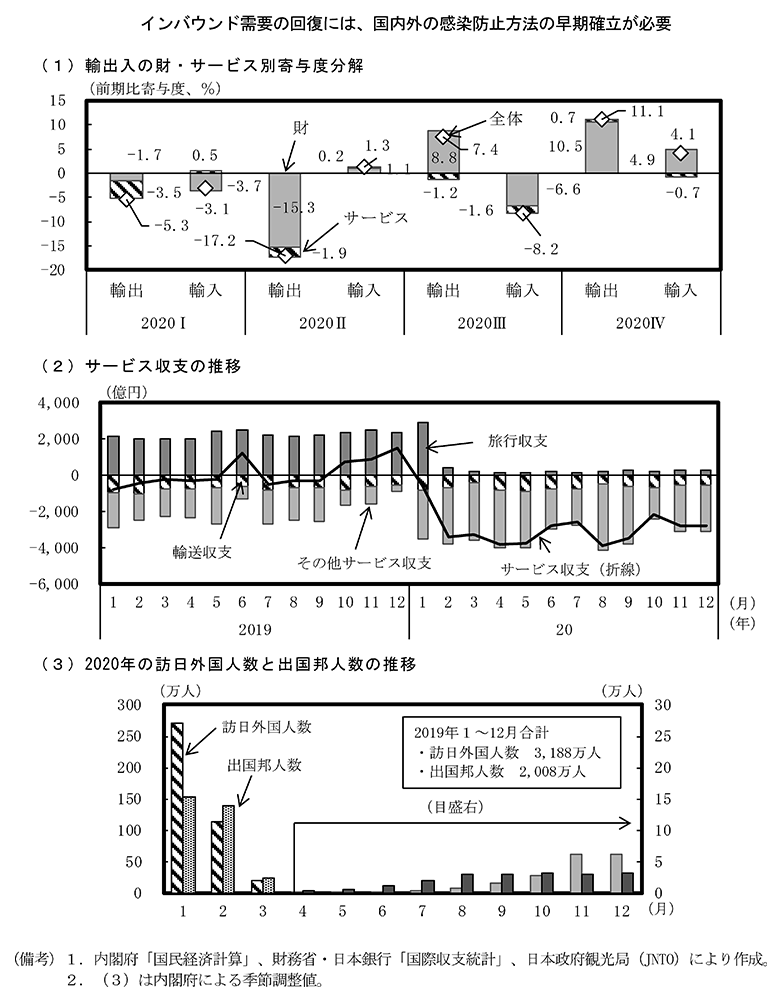
2 対外経済取引の動向
(感染症の影響下でも経常収支は黒字を維持)
感染症の影響を受ける前の我が国の経常収支は、貿易・サービス収支(財・サービスの受払)がゼロ近傍で推移する一方、第一次所得収支(海外への投資に伴う受払)の大幅かつ安定的な黒字により4、全体として黒字で推移する構造にあった5(第1-3-4図)。
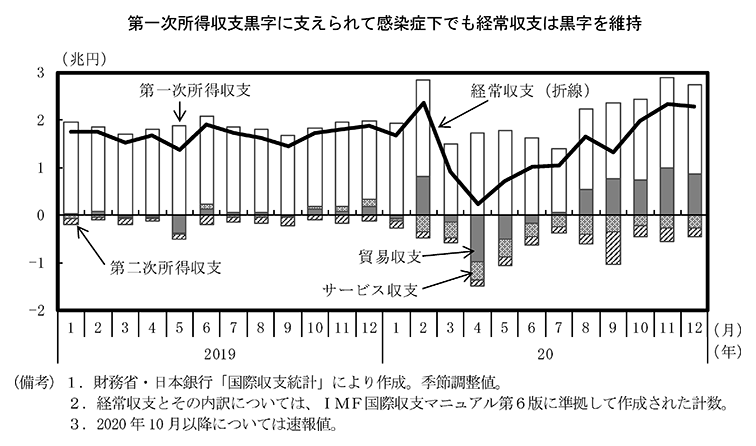
2020年は、国際的な人の移動が制限されて訪日外客数が減少したことを受け、先ずは2月にサービス収支がマイナスとなった。それに続き、海外経済の減速から、我が国の財輸出も弱まったことで、3月に貿易収支も赤字に転じ、4月には赤字幅が拡大した。その後、貿易収支は、財輸出が持ち直したことで7月以降は黒字に転じたのに対し、サービス収支は、国際的な人の移動が引き続き厳しく制限されていることから、赤字のまま推移している。
このように、貿易・サービス収支には感染症の影響による大きな変動がみられたものの、第一次所得収支は、一貫して安定的な黒字が維持された。これにより、一時期の貿易・サービス収支赤字が補てんされ、経常収支全体は、2020年を通じて赤字に陥ることなく推移した。
第一次所得収支の内訳は、直接投資収益と証券投資収益に大別される(第1-3-5図(1))。直接投資収益は第一次所得収支黒字の約半分を占めるが、海外子会社の設立やM&Aなど企業の海外進出の進展により、そのウエイトは近年上昇している6。月次の推移では、内訳の配当金・配分済支店収益が、2020年半ばに弱含んだものの、海外現地法人の収益が反映されたことから、年末にかけて持ち直しの動きがみられている(第1-3-5図(2))。
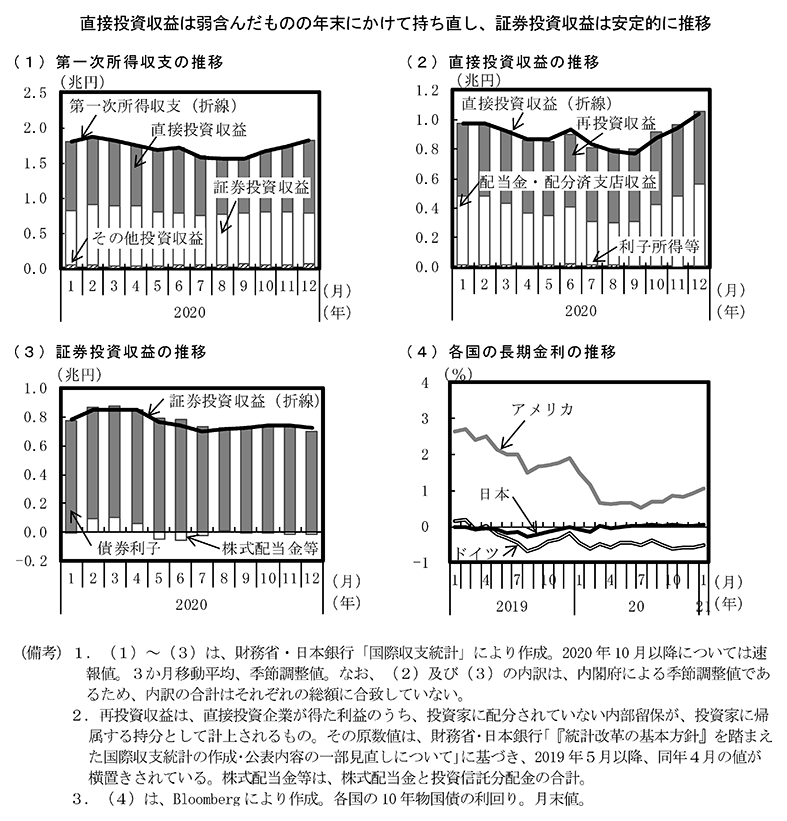
また、証券投資収益は、株式配当金等に直接投資収益と同様の動きがみられたものの、各国の長期金利が安定していることから、利子受取は大きく変動することなく推移しており、全体として落ち着いた動きとなっている(第1-3-5図(3)、(4))。
(感染症の影響は、対外直接投資・証券投資ともに下押し)
こうした対外的な収益を継続して確保できたのは、これまでの資本蓄積の賜物であるが、足下の投資動向はどのような影響を受けているだろうか。まず対外直接投資について確認すると、我が国の対外直接投資残高は、2019年末までアジア向けを始めとして増加を続けてきた(第1-3-6図(1))。
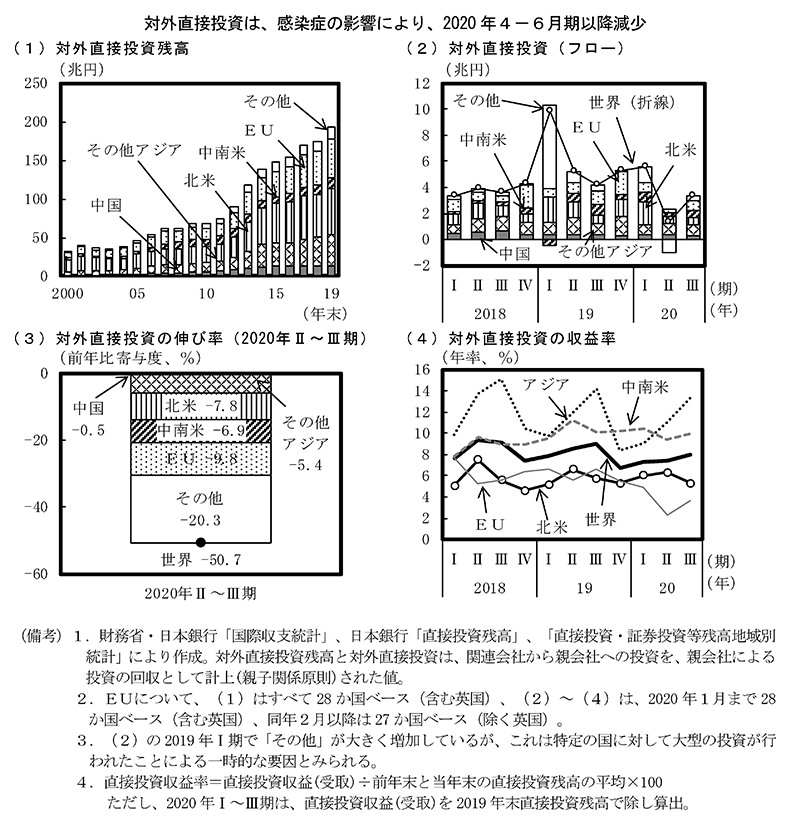
他方、2020年のフローの動向をみると、4-6月期から7-9月期にかけて、プラスは維持されているものの、そのペースは鈍化している。この時期の前年同期比寄与度をみると、どの地域向けもマイナスとなっているが、その中でもEU、北米、中南米向けのマイナス寄与が大きく、他方で、アジア向け、とりわけ中国向けのマイナス寄与が小さい(第1-3-6図(2)、(3))。このことから、企業は、感染症の影響が比較的軽微なアジア向けの直接投資を当面は優先させている姿が浮かび上がる。ただし、直接投資の収益率には総じて大きな変化はみられないことから、感染症の影響によって投資先の選好に構造的な変化が生じるかどうかは、今後の動向を更に見極める必要がある(第1-3-6図(4))。
対外証券投資についても、対外直接投資とおおむね同様の傾向がみられる。我が国の対外証券投資残高は、北米向けを中心にすう勢的に増加しており、足下のフローでみても、2020年1-3月期までは高い収益率を誇る北米向けの証券投資が盛んに行われていた。他方、4-6月期及び7-9月期には、EU、北米、中南米向けが弱い動きとなっている(第1-3-7図(1)~(3))。北米の投資収益率は依然として高く、資産市場が堅調に推移している現状を踏まえれば、こうした弱い動きは短期的な調整に留まる可能性はあるものの、今後の動向に注意する必要がある(第1-3-7図(4))。
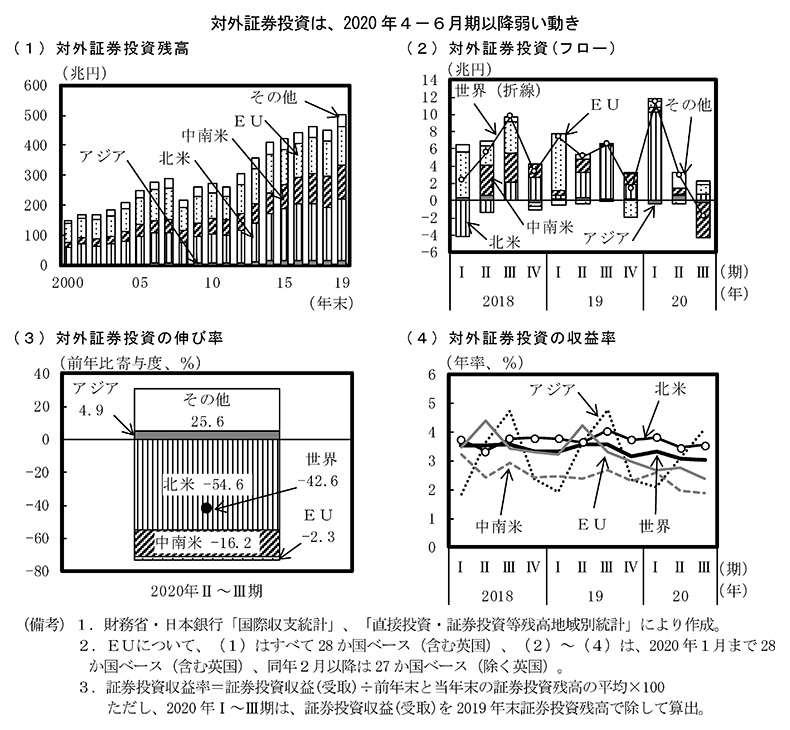
(旺盛な海外投資の原資として企業は内部留保を活用)
こうした対外直接投資や対外証券投資の動向は、企業のバランスシートでも確認することができる。2012年末以降における我が国企業(金融保険業を除く全産業)の資産をみると、2020年7-9月期末時点で、投資有価証券が最も増加している。この項目には、関係会社株式や長期保有する株式・公社債等が含まれ、対外直接・証券投資の積極的な増進が読み取れる7(第1-3-8図(1))。その一方、有形・無形固定資産の蓄積は、国内設備投資の伸びが緩やかであったことを反映して抑制的な水準にとどまっており、我が国企業が、国内設備投資よりも対外投資に積極的であったことがうかがえる8。
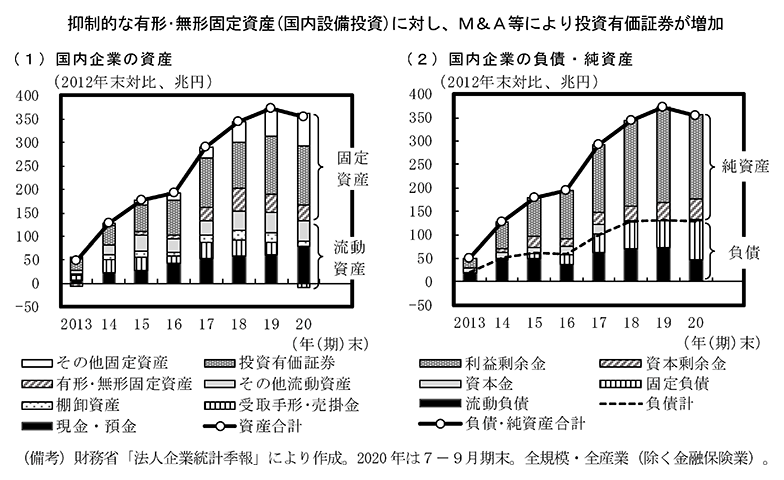
なお、バランスシートの負債及び純資産の動向をみれば、我が国企業がこうした資産形成に係る費用をどのように調達していたかが分かる。負債及び純資産のうち2012年末から2020年7-9月期までに最も増加しているのは、利益剰余金である(第1-3-8図(2))。利益剰余金は、内部留保とも呼ばれ、その名称から企業内部で使用されずに溜まっている資金という印象を持たれることがあるが、実際には、この利益剰余金が元手となって国内外の投資や手元流動性の確保が行われている9。
(企業は海外投資の先行きにやや慎重姿勢)
以上をまとめると、我が国企業は、これまで利益剰余金等を基に直接投資や証券投資を通じて海外資本の蓄積を積極的に進め、それによる収益を国内に還流させてきた。マクロ的には、こうした企業行動が、安定的な所得収支黒字、ひいては経常収支黒字をもたらした。一方で、欧米向けを中心に対外直接投資・証券投資の下押しも確認されており、こうした動きが海外の投資先の変更や国内への投資回帰をもたらすのかが注目される。
海外投資の今後について、国際協力銀行が2020年8月から9月にかけて実施したアンケート調査から企業の意向を確認してみよう。同調査によれば、我が国の製造業企業は、海外事業に関する向こう3年程度の中期的な見通しとして、「現状程度を維持する」と回答した企業割合が、2019年の26.7%から37.9%に上昇し、その分、「強化・拡大する」との回答割合が低下する結果となっている。今後、企業収益や海外経済の改善に伴い、海外投資は持ち直すことが期待されるが、企業は海外投資の先行きにやや慎重姿勢をみせており、当面、そのペースが緩やかなものとなる可能性を示唆している(第1-3-9図(1))。
また、海外投資の総量に加え、投資先国の配分変化も注目される。特に、中国から世界各国に感染症が広がった2020年の初期には、国際的なサプライチェーンの寸断を通じた供給制約という問題が生じ、生産拠点の国内回帰を求める声もあがった。同調査によれば、こうしたサプライチェーンに関する対応について、「同一製品の複数の生産拠点確保」、「生産工程の自動化・省人化投資」等、サプライチェーンの頑健性を高める投資を考えている企業が一定数存在することが分かる。他方、この調査時点では「国内生産拠点への回帰」、「海外拠点の他国への移転」を検討している企業は少ない。2020年の後半時点では、サプライチェーンを大きく見直すという選択肢は、感染症対応として主たる選択肢とはなっていない様子がうかがえる。
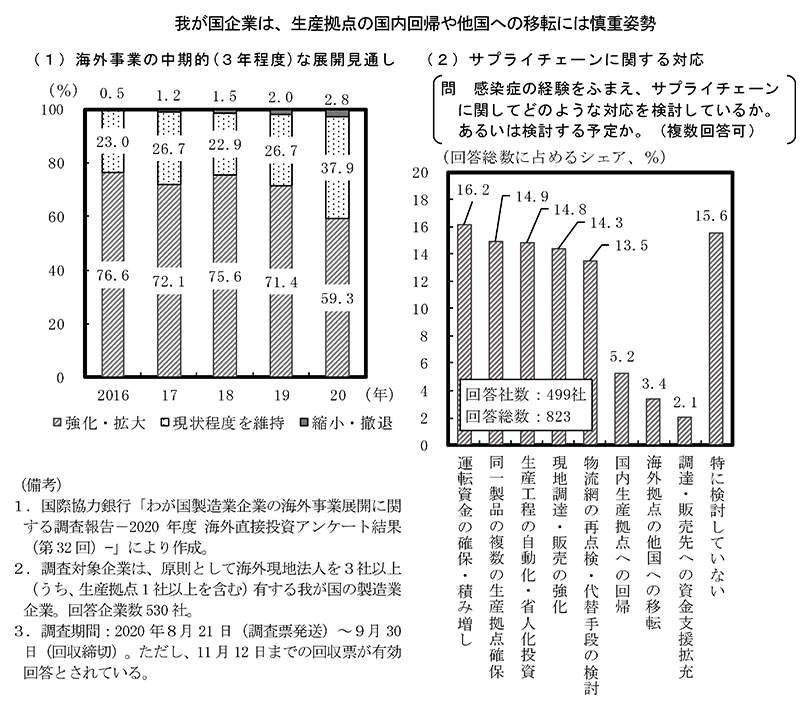
3 為替と日本経済
感染拡大は世界的な事象であるが、我が国の主要貿易相手国通貨と円の相対的な交換比率である為替レートは、経済変動の大きさに鑑みれば、比較的落ち着いた動きをみせている。為替レートの安定は、企業活動やグローバルな投資に伴う不確実性を減らすことを通じて成長の礎になる。ここでは、安定的な為替レートの背景にある経済的な動きや、我が国企業の為替レート変動に対する耐性等について分析する。
(為替レートは長期的には国内外のインフレ格差に沿って推移)
はじめに近年の実効為替レートをみると、名目・実質ともに、2013年から2015年半ばにかけて円安方向、その後は、すう勢的に円高方向に推移している(第1-3-10図(1))。名目実効為替レートに着目して、為替変動を通貨別に分解すると、この期間の円高には、中国元及び米ドルの下落寄与が大きい。中国元については、2015年8月に日本円を含む11通貨に対して切り下げが行われたことが大きく影響している(第1-3-10図(2))。
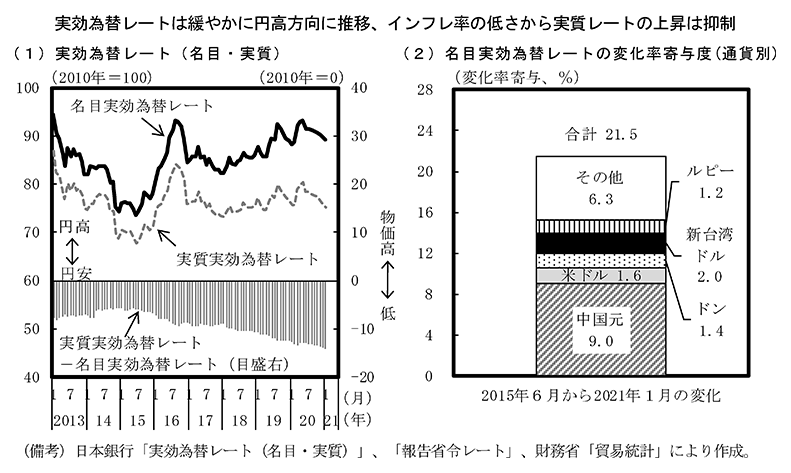
また、実効為替レートの名目と実質の差から、為替レートの変動要因に関する別の示唆も得られる(第1-3-10図(1))。この差は、自国と貿易相手国全体の物価水準のかい離を示しており、2010年を基準とすると、我が国の物価水準が相手国よりも低いため、マイナスの値となっている。さらに、このマイナス幅は、2015年以降、すう勢的に拡大しており、我が国のインフレ率が他国に比べ相対的に低い状態が続いていることを示している。
財の交換比率に通貨の交換比率が収れんするという購買力平価説に基づけば、このようなインフレ格差が長期的な為替レートの決定要因となる。そこで、日米の購買力平価を企業物価の比としてドル円レートとの関係をみると、振れを伴いながらも、すう勢として、こうした購買力平価に沿う形で為替レートが動いている(第1-3-11図)。
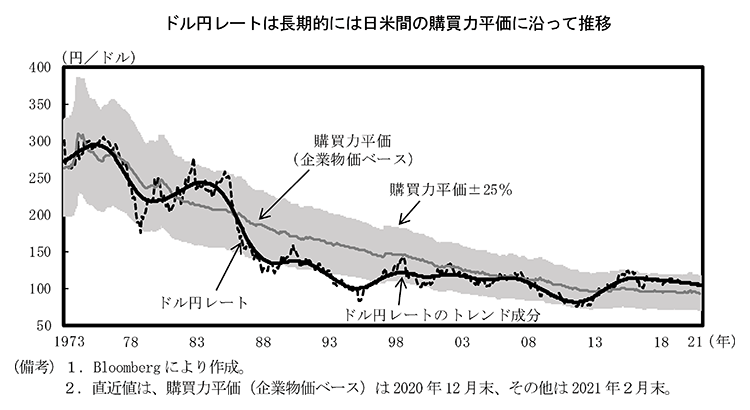
(金融政策の変化に伴い為替の決定要因は内外金利差からマネタリーベースへ)
為替レートが長期的に購買力平価のすう勢に沿って動くとしても、短期的にはかい離することも多い。為替変動の要因は様々あるが、ここでは、ドル円レートに関し、実質金利差、マネタリーベース差、米株高インデックス(資産価格)等が為替に与える影響について考察する10。まず、ドル円レート、日米金利差、日米マネタリーベース比、米株高インデックスのそれぞれについて、投機的な動きを含んだノイズや循環的な動きを除いたすう勢、言い換えればトレンドを取り出して関係をみていこう(第1-3-12図)。長期的な関係を踏まえると、推計期間中における被説明変数と説明変数との関係にある程度の長さを伴った変化、レジームのシフトが生じることもあるため、検定を行って期間を区切っている11。
分析結果をみるといずれも多くの期間でドル円レートに対し、有意な関係となっている。しかしながら、日米金利差は、2014年12月以降の直近期間で統計上有意との結果が得られなかった。実際の動きをみても、この期間の日米金利差はおおむねゼロ近傍にあり、為替の変化に対し、説明力が低下していた。また、米株高インデックスは、基本的にドル円レートに対してプラス、すなわち、米株高はドル高/円安要因であったが、2015年6月以降の期間においては、米株高は見かけ上は円高要因となっていた。これは、金利差の説明力が弱くなったと考えられる期間とも重なるが、米株高が円高を招いているというよりも、米株高、米金利高、米ドル高、という関係が崩れており、日米のマネタリーベースの比を勘案すれば、金利上昇を伴わないアメリカの相対的な緩和傾向が株高だけに作用したようにみられる。
伝統的には、為替変動の主たる要因として指摘される内外金利差だが、近年、多くの先進国によってゼロ金利・量的緩和政策が採用されるようになったことで、推計期間では、内外の金利差よりもマネタリーベースの差が為替レートの変動に対し、相対的に大きな影響を及ぼしていたことが示唆される。ただし、推計結果からも明らかなとおり、変数間の因果関係とその程度は、一定期間において観察されるものであり、政策フレームの枠組み変化等に応じて変化していくものと考えられる。
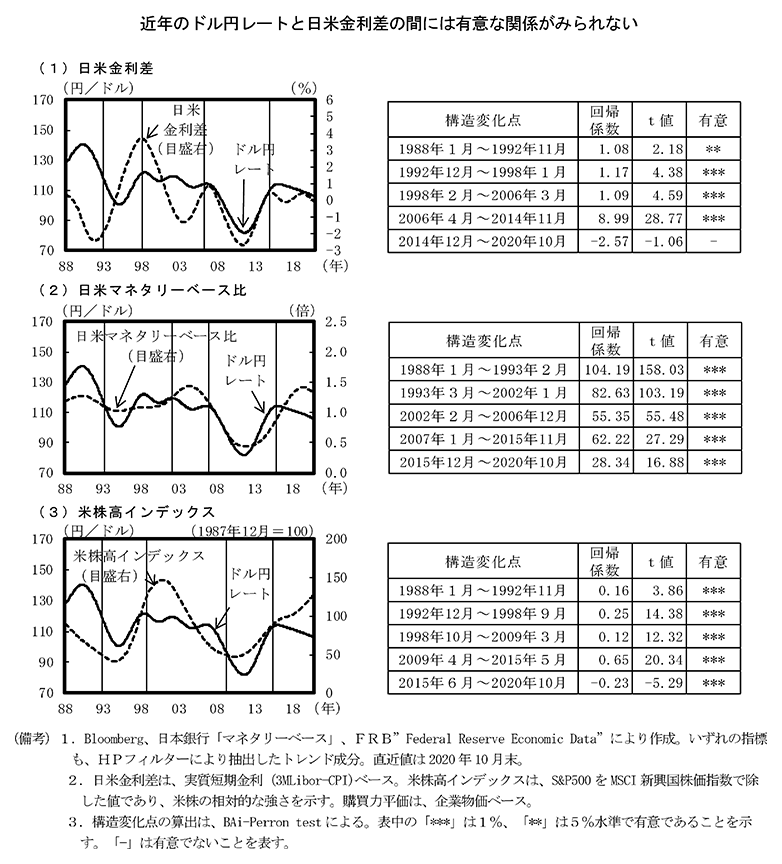
(我が国輸出企業の為替変動に応じた価格設定行動に変化)
こうした為替の変動は金融的な世界だけではなく、我が国経済に広く影響を与える。主な波及経路としては、輸出と企業収益が考えられるため、順に確認してみよう。
まず輸出について、為替レートの変動は、輸出財の価格変化を通じて影響を及ぼす。例えば、円安局面を例に為替と輸出企業の価格設定行動の関係を整理すると、輸出企業としては、①円安分だけ現地通貨の売価を下げて、数量で稼ぐ戦略(円ベースの価格は不変)、②現地通貨の売価は維持したまま、円安分だけ利幅を上乗せする戦略(円ベースの価格を引上げ)が考えられる。過去の輸出金額の増減を価格要因と数量要因に分解すると、2005年から2007年の円安局面では、価格要因の上昇が緩やかに進み、同時に、数量要因も上昇した。その結果、2007年末時点では、輸出金額の増加幅のうち、価格要因と数量要因の寄与が同程度となっている(第1-3-13図)。
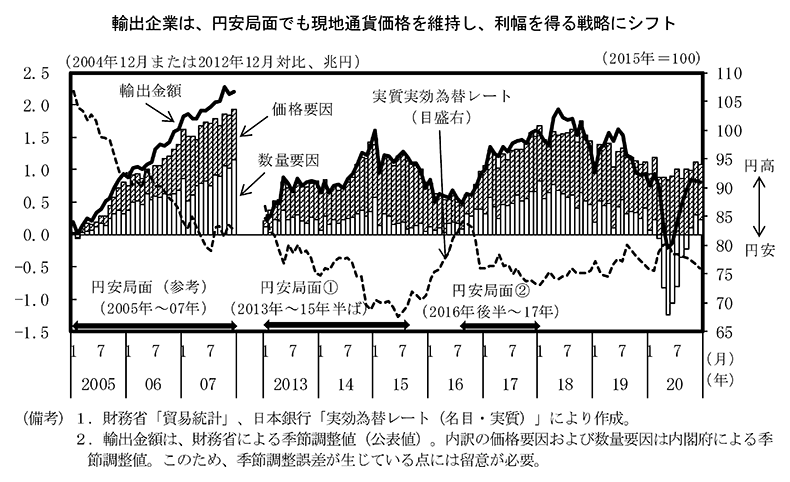
他方、2013年から2015年半ば及び2016年後半から2017年の円安局面では、企業は、為替レートの変化に応じて、価格を急速に調整しており、その結果、数量要因の上昇は小幅なものにとどまった。輸出品目の変化等もあるが、このことからは、輸出企業の価格設定行動が、上記①の数量増を意図したものから②の価格を勘案した付加価値増を意図したものへとシフトしているように思われる。何れにせよ、こうした数量から価格を動かす企業行動の変化は、為替レートによる輸出数量ひいては実質GDPへの影響を小さくする効果を持つと考えられる。
(為替レートの変化が企業収益に与える影響は近年低下)
次に、為替レートの変化が企業収益に与える影響について確認しよう。企業の想定為替レートが1円円安になった場合の経常利益の変化について、リーマンショック前の景気循環(2002~2008年度)と現在の景気循環(2013~2019年度)の2期間に分けると、全産業、製造業(更に製造業の内訳として素材業と加工業)、非製造業のいずれも企業の想定よりも円安が進めば経常利益を押し上げる効果を持つことが分かる(第1-3-14図(1))。
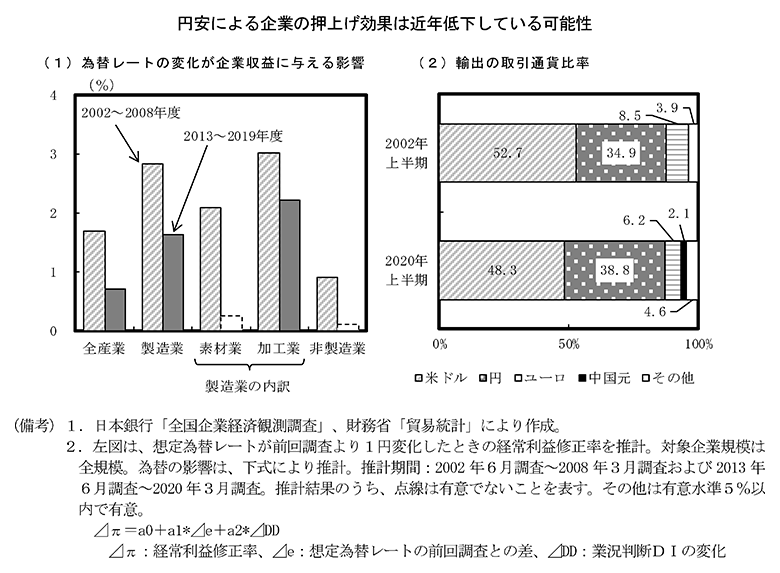
ただし、その効果の程度は、過去の期間よりも現在の期間の方が低下しており、特に、素材型の製造業や非製造業は、現在では統計的に有意な関係がみられない収益構造となっている。この背景には、前項で紹介した海外直接投資の増進とそれに伴う海外での現地生産体制構築の進展や、為替予約等のリスクヘッジ手法の発達などがあるとも考えられる12。また、輸出取引に占める円比率も高まっており、このことも為替レートの変動に対する収益の安定性の確保につながっていると考えられる(第1-3-14図(2))。以上のとおり、為替レート変動によって我が国経済が影響される程度は、企業の行動変化や対応策の進展により、緩和されている可能性がある。


