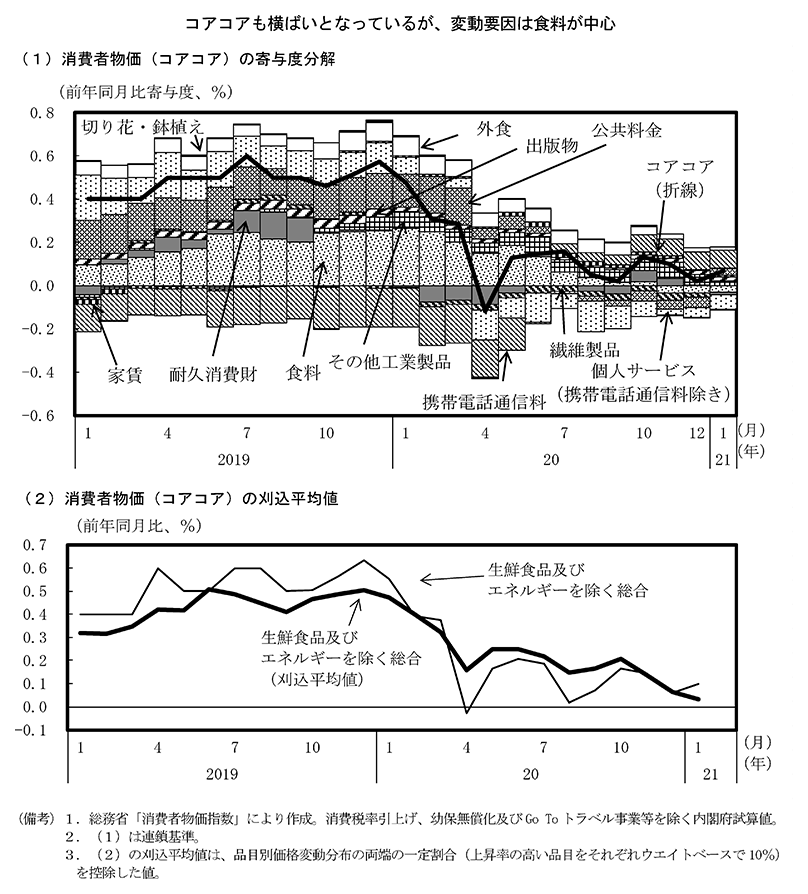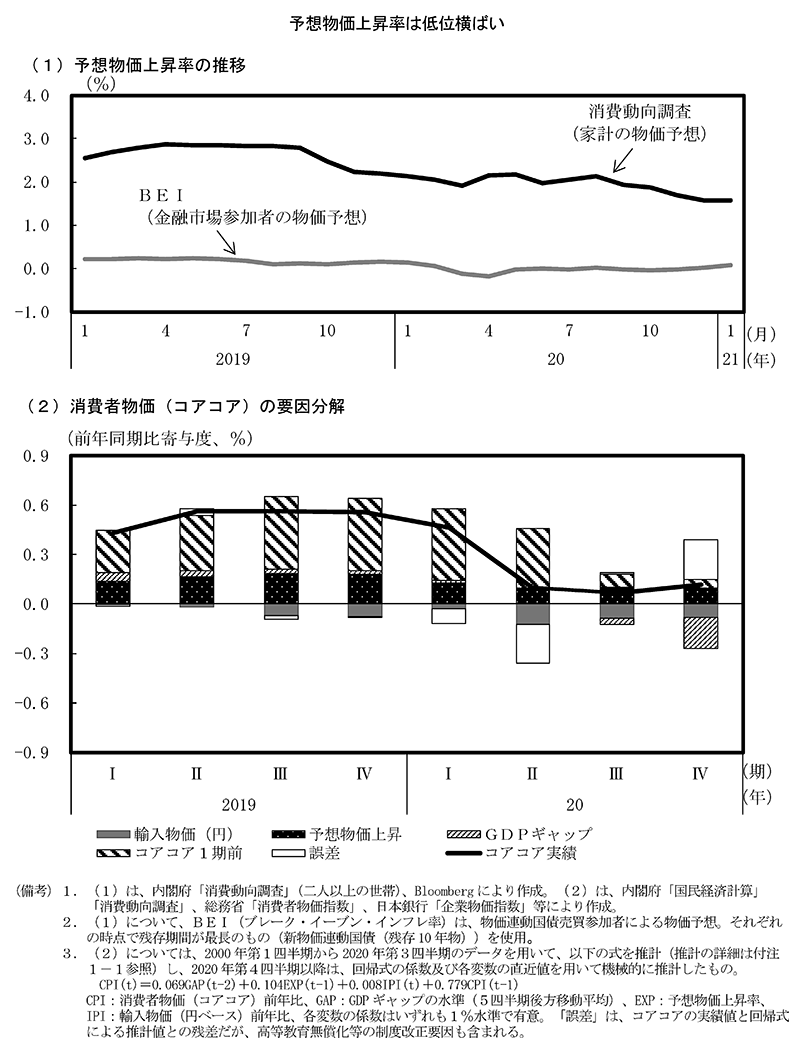第1章 感染症の危機から立ち上がる日本経済(第2節)
第2節 需給バランスとデフレリスクの確認
前節では、総需要の持ち直し基調が、消費を中心に、新規感染者数の再拡大とそれを受けた経済活動制限の再導入による下押しに直面していることを確認した。今のところ、2020年4-6月期ほどの下振れには至っていないとみられるものの、需要抑制の継続はデフレ懸念を惹起することから、本節では、マクロ及び個別市場の需給動向とそれを示す物価や賃金動向を概観することで、デフレリスクを確認する。
1 需給バランスの動向
(GDPギャップは縮小したが、いまだデフレギャップが残る)
まず、需給状況をGDPギャップの動きから確認すると、2020年4-6月期に-10.5%と大幅に悪化した後、7-9月期は-6%程度、10-12月期は-3%程度と改善が続いている(第1-2-1図)。ただし、GDPギャップの水準は、依然として大きなマイナスとなっており、労働や資本の有効活用を図るには、需要水準の押上げが必要な状況である1,2。
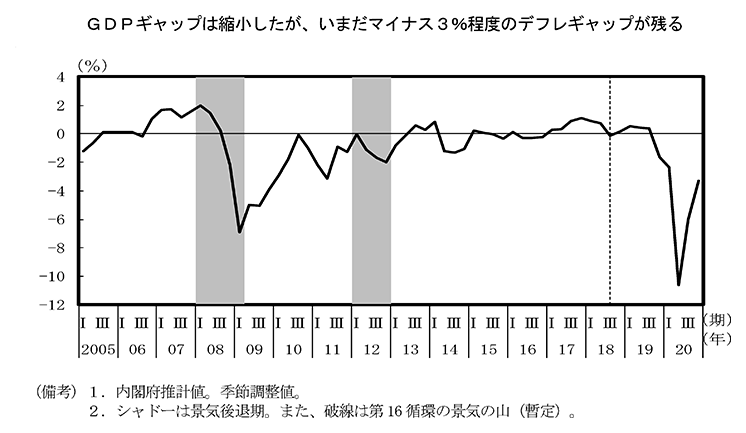
(緩和傾向が続いた労働市場の需給は年後半に反転の動き)
GDPギャップが示唆する需要不足は、労働市場においては、新規求人の減少、そして就業者や雇用者の労働時間や人数の減少、その後に失業者数の増加と失業率の上昇、という量的な指標の変化に現れる。ただし、我が国では労働時間による雇用調整が機動的に動くことから人数への波及は抑制されやすいこと、また、賞与制度を通じて一定のリスクシェアリングを労働者もしていることから賃金が変動し、GDPギャップの変動ほど量的な指標は振れない傾向にある(詳細は2章を参照)。
まず、労働需給を示す集計的な指標とみていくと、有効求人倍率は、2019年の1.6倍台から、感染症の影響により大幅に低下したが、9月や10月の1.04倍を底に反転し、本年1月には1.10倍となっている。(第1-2-2図(1))。こうした有効求人倍率の低下は、専ら求人数の変動によってもたらされたが、経済活動の段階的引上げが始まった夏場以降、次第に持ち直しの動きをみせていた(第1-2-2図(2))。
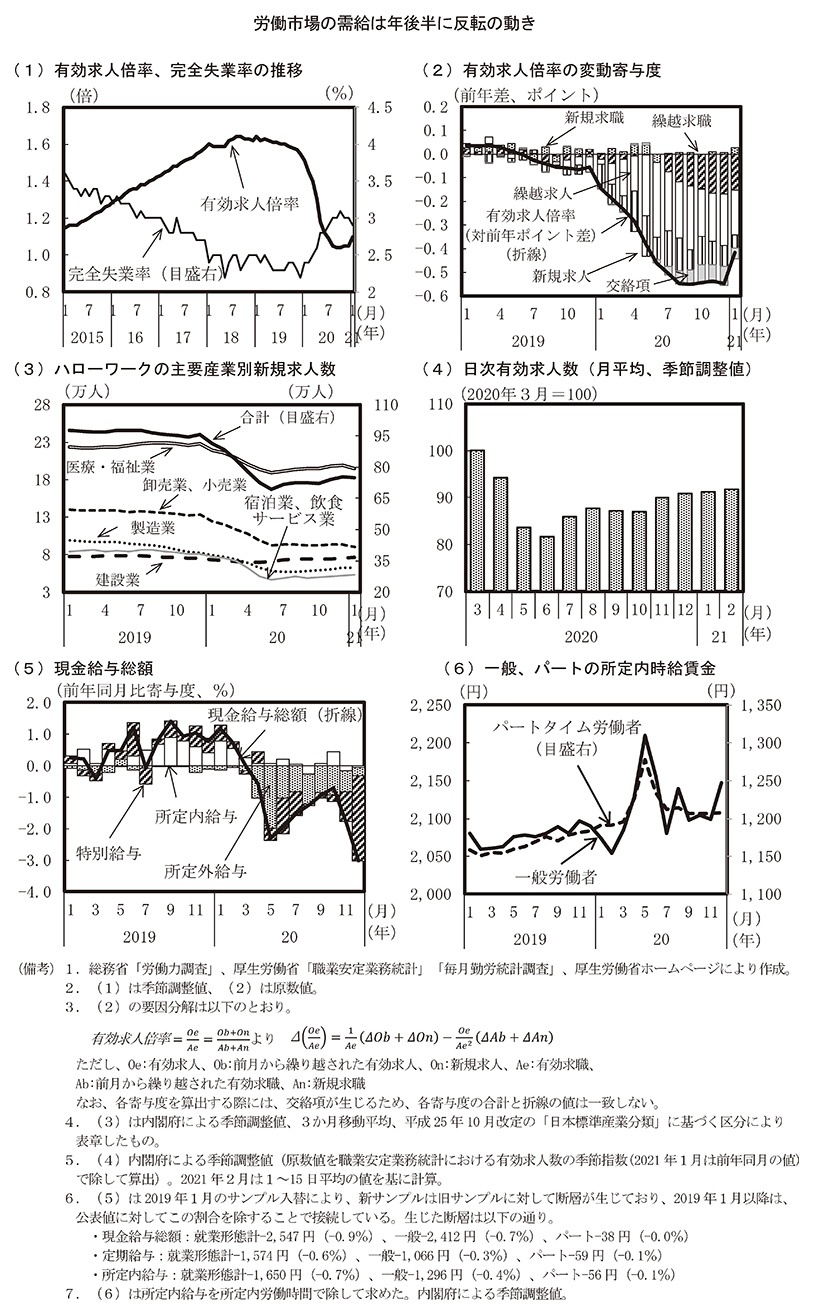
ただし、求職者数も同時に増加に転じたことから、倍率の動きが反転したのは数か月後になっている。新規求人数の動きをみると、サービス業を中心に大きく低下したが、個人向けサービス業は総じて感染症の影響を受け続けており、持ち直しの動きに力強さを欠いている。年末にかけて、再び新規感染者数が増加していることや、1月から再び緊急事態宣言が一部の都府県に発せられたこともあり、求人数にみられた持ち直しの動きには足踏み感が生じている(第1-2-2図(3))。ただし、月平均での日次有効求人数をみると、12月以降は横ばいとなったものの、2月には再び増加の動きもみられることから、ある程度の底堅さが続いている(第1-2-2図(4))。
また、景気に対して遅行性のある失業率は、長期に渡った景気拡張という循環要因もあり、2%台の低位で推移していたが、4-6月以降上昇し、10月には3.1%と4年2か月ぶりの水準へと高まった。本年1月は2.9%に止まっているが、拡充された雇用調整助成金等の政策支援によって抑制されている状態である(前掲、第1-2-2図(1))。
賃金面での動きを確認すると、現金給与総額の所定内給与はおおむね横ばいとなっているが、感染症の影響による休業増加や残業時間の減少により、所定外給与や賞与を含む特別給与の減少が大きい(第1-2-2図(5))。一般、パートとも、所定内給与の時給賃金はすう勢的な増勢を維持しており、時給賃金の切下げはみられないものの、2章で詳細に分析するが、飲食業等、産業別には労働時間の減少が続いており、所得面での厳しさが続いている(第1-2-2図(6))。
(旺盛な資金需要を政策的に吸収し、金融市場は引き続き緩和傾向)
次に資金需給を示す金融市場の動向についてみていく。融資等の動きをみると、感染拡大後、CP・社債といった市場からの資金調達3に加えて、銀行貸出残高は大きく増加しており、その使途の多くが運転資金となっている(第1-2-3図(1)、(2))。また、民間企業の資金繰り動向を企業規模別にみると、いずれも資金繰り判断DIの低下は、リーマンショック時点と比べても小幅なものにとどまっている(第1-2-3図(3))。この背景としては、金融緩和政策の実施があり、感染症対策として実施されている資金繰り支援(実質無利子・無担保融資)の累積額をみても、公的金融機関のみならず、民間金融機関においても大幅に増加しており(第1-2-3図(4))、企業の資金需要の高まりを吸収している。
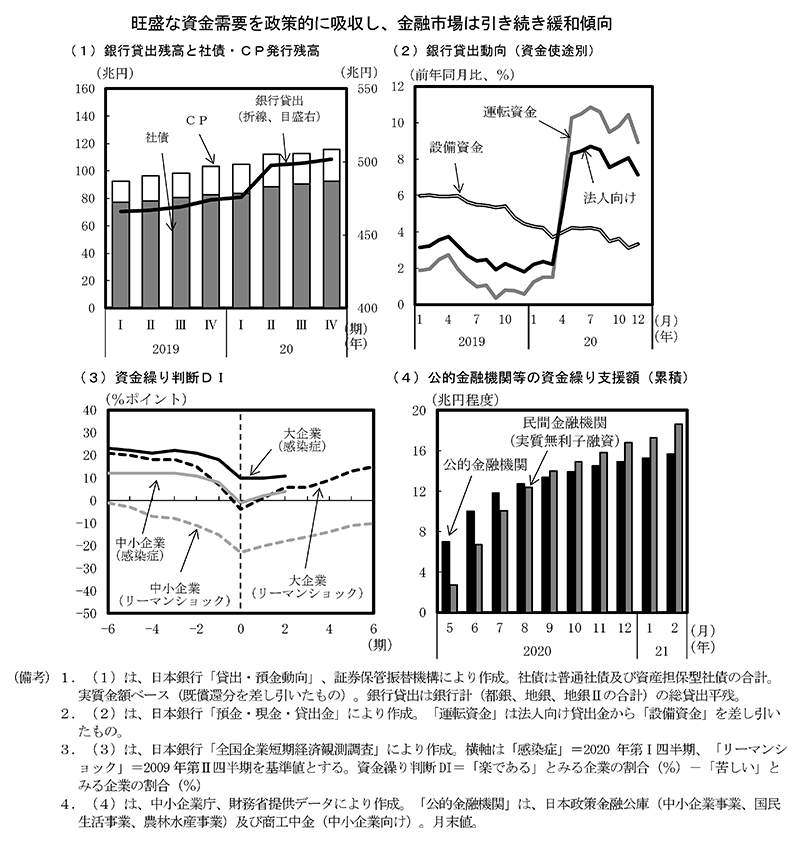
2 企業物価の動向
(国内企業物価は上昇傾向)
国内企業物価は、輸入財、特に原油価格に左右される。2020年前半の原油価格は、世界的な経済活動の低下を背景に急速に弱い動きとなったが、活動制限の緩和や解除、各国の大規模な財政措置と金融緩和の効果もあり、次第に持ち直していった。こうした動きは、石油・石炭製品等だけでなく、非鉄金属等の資源価格にもみられており、輸入物価の上昇へとつながっている(第1-2-4図(1))。
国内企業物価に占める石油・石炭製品等のウエイトは25%程度と高いこともあり、原油価格の下落は国内企業物価を大きく下押しした(第1-2-4図(2))。下押しは月を追うごとに小さくなったが、年央以降、原燃料費調整制度を通じて電力料金等を押し下げ、電力・都市ガス・水道のマイナス寄与は拡大した。ただし、非鉄金属等の市況品や化学製品の価格が強含みで推移したことから、企業物価には次第に上向きの動きがみられることとなった。
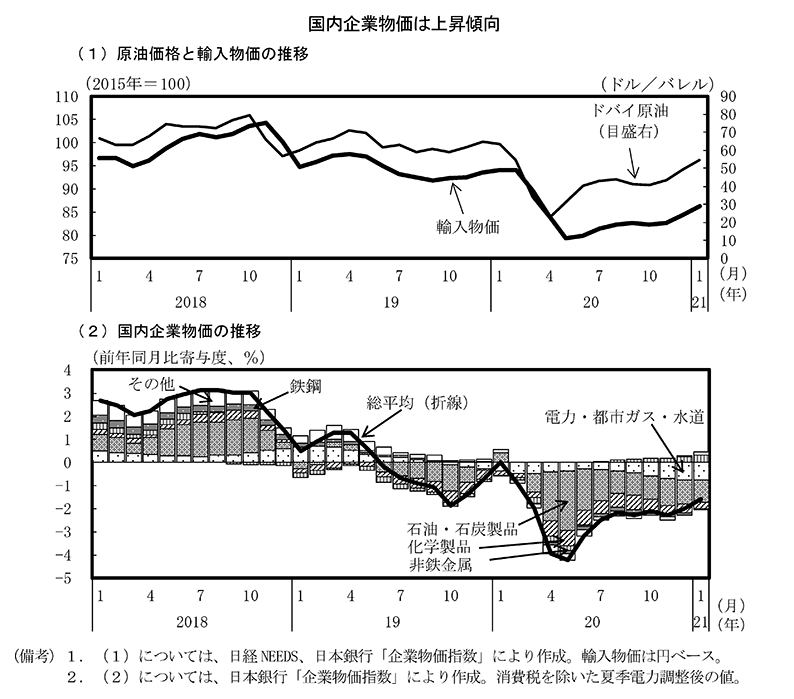
(サービス価格を中心に企業の価格設定には需給ギャップの影響が残る)
企業間取引にはサービスも多く、一部のサービス価格は国際市況等の影響を受けるものの、大きなウエイトは需給や人件費等を背景とした価格改定といった国内要因によって左右される。したがって、サービス価格は、事業活動が大きく抑制された緊急事態宣言の時期等は大幅に下落し、その後の活動再開に合わせて持ち直している(第1-2-5図(1))。2020年を通じて、変動が大きい品目は広告であり、消費活動の自粛や店舗・施設の休業、再開に伴う需要の増減を反映している。年末にかけて、広告の下落も相当解消したが、1月には若干ながら再び弱含んでいる。こうした需給に起因する変動は、不動産賃料や宿泊料等にもみられる(第1-2-5図(1))。
また、機械修理や法務・会計サービス、宿泊サービスといった人件費要因が影響しやすい諸サービスのうち、労働者派遣サービスは、同一労働同一賃金の実施を反映し、4月に水準の切上げがみられた。同時に、緊急事態宣言下においても専門職などの必要性が高く、高単価の派遣サービスは継続されたとみられ、その後も高い水準で推移しており、諸サービスのプラス寄与に影響を与えている(第1-2-5図(2))。
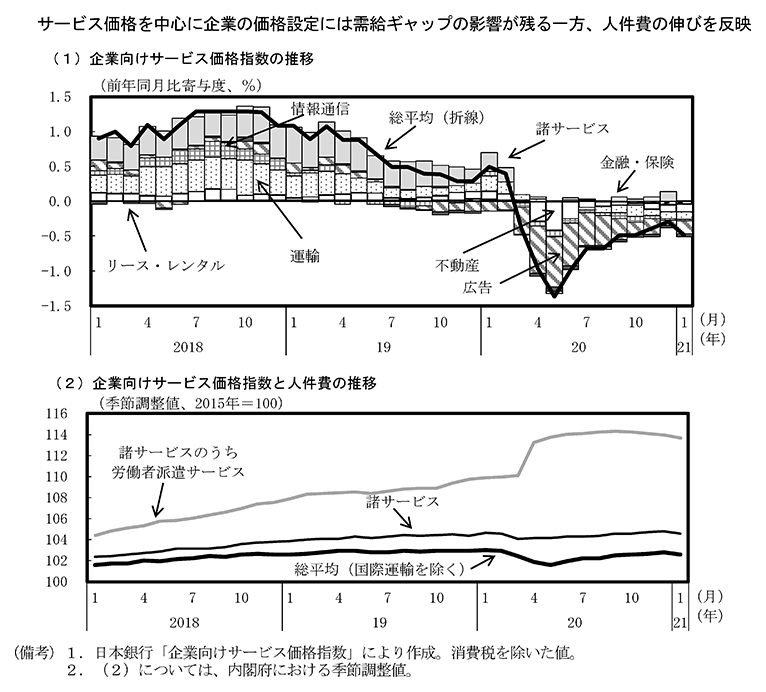
(企業の販売価格見通しは未だマイナス圏)
こうした企業物価の変動を受けて、企業の物価見通しにも変化が生じている。日銀短観における、企業による販売価格や物価の1年後の見通しの動きをみると、特に販売価格については、4-6月時点で大幅に低下し、前年比がマイナスに転じることになった。その後はマイナス幅に縮小傾向がみられるものの、12月調査時点でもマイナスに止まっている(第1-2-6図(1))。1年後の販売価格の見通しについて、製造業・非製造業に分けてみると、何れもマイナス圏内に止まっており、製造業の下振れがいまだ大きい(第1-2-6図(2))。企業の販売価格見通しは、企業内の資本や労働の稼働状況と強い相関を持っており、稼働率の低さは販売価格の低下要因となる4。2020年後半の持ち直しを反映して多少は上昇したものの、稼働水準の回復は道半ばである。したがって、企業が価格を下げて販売数量を増やし、稼働率を引き上げるような販売戦略を選択する可能性も否定できない。
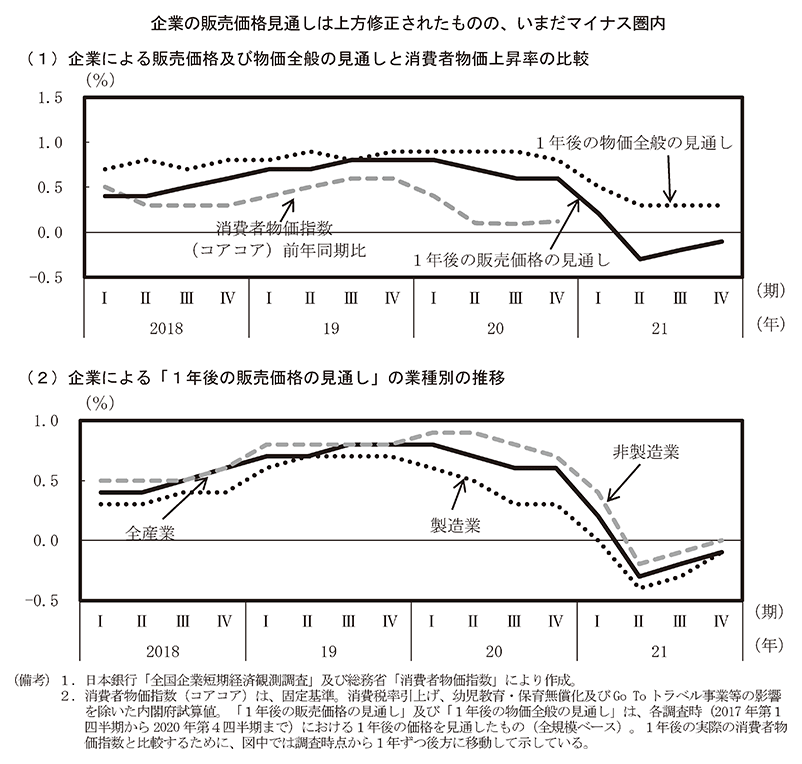
3 消費者物価の動向
(消費者物価の基調は横ばいで推移)
消費者物価の動きは、変動の大きい生鮮食品を除いたコア、さらに、外生的な要因によって変動する各種エネルギー品目を除いたコアコア、によって評価している。過去2年の推移をみると、生鮮食品を除く総合(コア)は、エネルギー品目のうち、ガソリン価格の急落により水準を下げたが、その後はおおむね横ばいで推移している。コアからエネルギー品目を除いた総合(コアコア)も横ばいで推移している(第1-2-7図(1))。
これらの指数は、公表系列からいわゆる一時要因を取り除いている。そこで、前年比の動きを分解した図を用いて、2019年から2020年は、政策変更に伴って物価変動が大きく生じたことを振り返ろう。まず、2019年10月は、消費税率が引き上げられると同時に幼児教育・保育無償化が実施された。また、2020年7月に開始されたGo To トラベルは宿泊料に反映され、物価の押下げ要因となった。平年においても、公共料金改定等を通じて政策による物価変動は生じているが、これら3つの影響は大きく、公表元である総務省においても、各々の影響を別途試算して開示している(第1-2-7図(2))5。
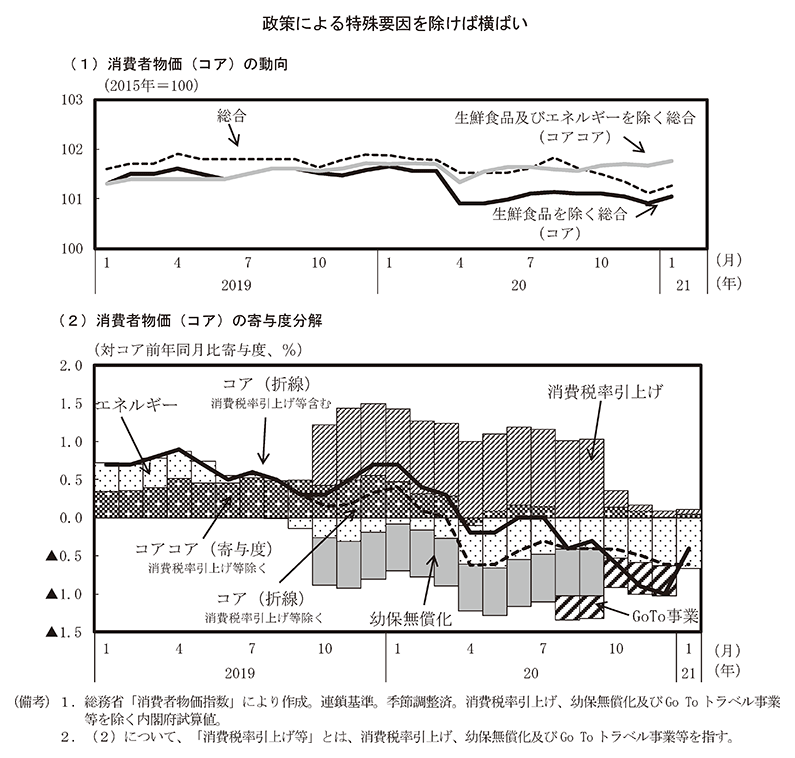
(コアコアも横ばいとなっているが、その変動要因は、食料が中心)
同様に、コアコアの前年同月比も品目レベルで寄与度分解すると、2020年4月以降、何れの品目の増減寄与も小幅になっており、価格変動自体が小さいという特徴がみられる。これには、感染症の影響により、いわゆる価格に訴求するバーゲンセールの機会が減少していることが影響している面がある6。品目別の動きをみると、「食料」は年初来プラスに寄与していたが、2019年の値上げも年末に到り一巡し、マイナス寄与に転じている。また、「耐久消費財」は、多少の振れもあるが、おおむね横ばいとなっている。携帯電話通信料を除く「個人サービス」については、4月以降、感染症の影響により宿泊需要の低迷が押下げに寄与した一方、「携帯電話通信料」は、2019年6月の通信料値下げによるマイナス寄与がはく落し、押上げに転じたこともあって、プラスの寄与となっている(第1-2-8図(1))。こうした個別要因から、価格変動のかい離が大きい品目を除外(刈込み)した指数の動きをみると、2020年の月次前年比はおおむね小幅のプラスで推移していたことが確認できる(第1-2-8図(2))。
(予想物価上昇率は低位横ばいで、デフレリスクへの注意が必要)
消費動向調査から予想物価上昇率の動きを確認すると、おおむね2%近傍で推移し、金融市場参加者の予想物価上昇率は、おおむね0%近傍で推移している(第1-2-9図(1))。何れの指標にも感染症の影響とみられる水準変化は読み取れないが、消費動向調査から求めた予想物価上昇率は、2020年後半に低下傾向もみられる。こうした予想物価上昇率に加え、需給ギャップがもたらす物価下落圧力や輸入物価の影響によってコアコアの動きを推計すると、これまでのところ、予想物価上昇率の押上げ寄与が続いており、輸入物価は僅かにプラス寄与となっている。他方、需給ギャップは、7-9月期から押下げ寄与に転じている(第1-2-9図(2))。2021年前半は、需給ギャップによるコアコアへの下押し圧力が続くと見込まれ、今後のデフレリスクへの注意が必要である。