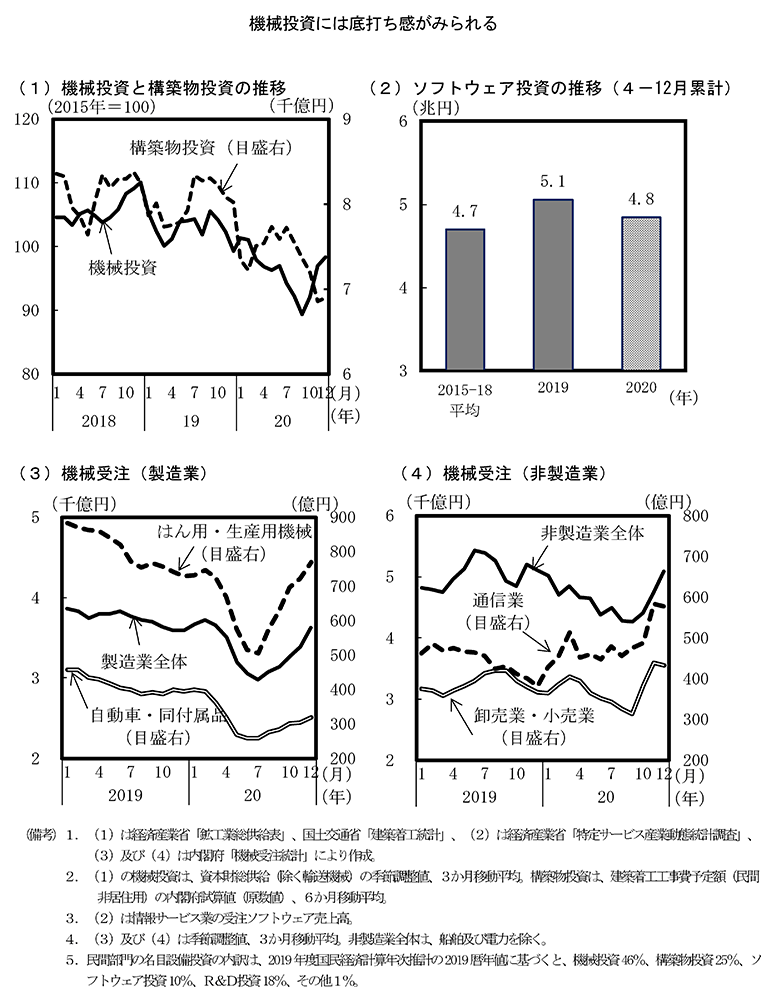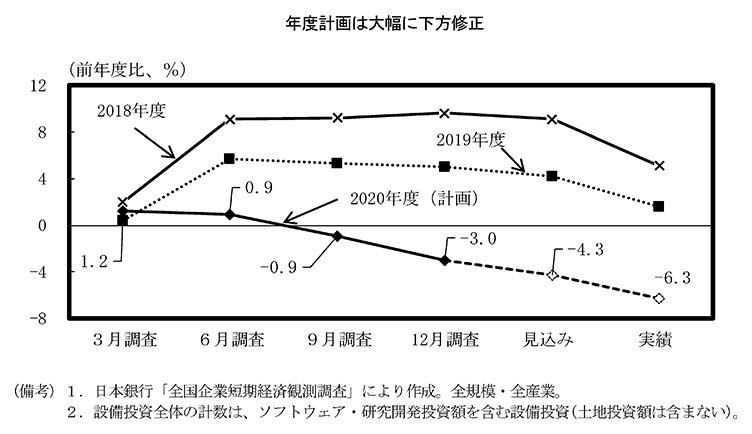第1章 感染症の危機から立ち上がる日本経済(第1節)
第1節 2020年後半の経済動向
本節では、GDPなどの集計データを基に、2020年後半以降のマクロ的なすう勢と変動を確認しよう。その際、内需・外需の状況や、家計部門、企業部門での特徴的な動きについても触れる。
1 マクロ経済の動向
(2020年後半は内外需の増加に支えられて持ち直し基調で推移)
まず、実質GDPの推移をみると、諸外国で感染拡大防止策としてのロックダウンが実施され、我が国でも緊急事態宣言が発出された4-6月期は、内外需双方から大きく下押しされ、前期比-8.3%(前期比年率-29.3%)と比較可能な1994年以降で最大の落ち込みとなった(第1-1-1図)。その後、国内においては、5月25日までに全国で緊急事態宣言が解除され、社会経済活動の段階的引上げが図られた。また、諸外国でもロックダウンの緩和や解除が進んだ。加えて、我が国を含む主要先進国では、大規模な財政出動と緩和的な金融措置が講じられており1、総需要の下支えが図られていた。我が国の場合、対策規模は対GDP比52%程度である。こうした一連の動きを受けて、7-9月期の我が国経済は、内需・外需ともに大きく持ち直し、前期比5.3%(前期比年率22.8%)と4期ぶりのプラス成長となった。持ち直しの動きはその後も続き、10-12月期も前期比2.8%(年率11.7%)と2四半期連続の増加となった2。
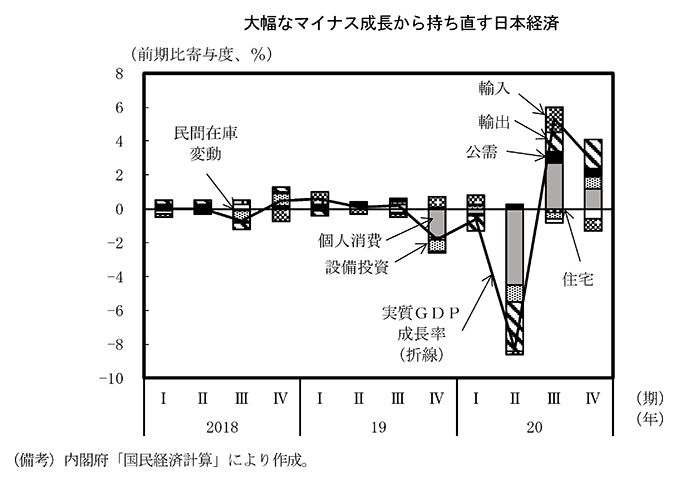
(ただし、10-12月期後半は感染者数増加による活動抑制が拡大)
しかし、四半期平均で評価した10-12月期は増勢がみられるものの、月次の動向をみると、新規感染者数が増加し、経済活動の制限が地域レベルで拡がっていたこともあり、消費には足踏み感が次第に増す動きとなった(第1-1-2図(1))。例えば、新型コロナウイルス感染症対策分科会の提言を踏まえ、11月以降順次、各都道府県においてGo To Eatの停止が実施され、また、Go To トラベルについても、11月24日から、札幌市及び大阪市を目的地とする旅行について一時停止したほか、東京都、名古屋市、広島市について一時停止等の措置が講じられた。その上で、12月14日には、年末年始におけるGo To トラベルの一時停止も決定された。2021年1月には、年末に感染者数の記録的な増加と医療提供体制のひっ迫が確認されたことから、2月7日までを期限として、11都府県3を対象とした2回目の緊急事態宣言が発出された4。なお、2月2日に、この措置は対象地域を減らして3月7日まで延長されることになった5。その後、首都圏以外の6府県6は、期限を2月28日までに前倒しして解除された一方、首都圏の1都3県7は、期限を3月21日までとして、再度延長されることになった。
今回の緊急事態宣言では、これまでの経験・知見や専門家の分析を踏まえて、感染の起点といわれる飲食とそれにつながる人流を抑える措置を講じた。昨年4、5月の時のように全国において経済活動を幅広く人為的に止めたわけではないことから、経済的な影響も抑制されたと見込まれる。
なお、感染者数の増加は、欧米主要国においても生じていた。その結果、2020年前半ほどではないものの、欧州を中心として、2020年11月頃から、外出制限を中心とした経済活動の制限措置が実施された。実際、google mobility indexでみた外出先での訪問滞在時間は、ドイツ等の欧州各国では大きく減少している(第1-1-2図(2))。
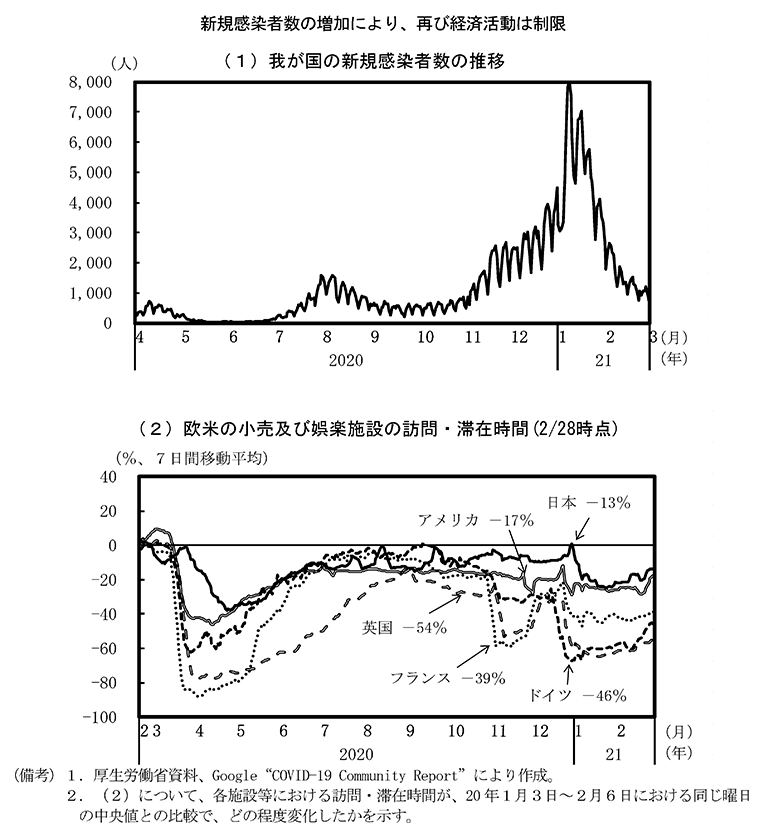
(輸出の持ち直しは2四半期続いたが、先行きは不透明)
2020年前半の外需動向を振り返ると、我が国の主たる輸出先である国・地域の4-6月期の成長率は、1-2月に感染拡大で経済活動を抑制した中国を除き、感染症の影響を受けて大幅に悪化した(第1-1-3図(1))。
その後は経済活動の再開や大規模な財政措置と金融緩和により、成長率はプラスに転じることとなったが、第4四半期の回復ペースは緩やかである。3つの国際機関のうち、最初に公表されたOECDの見通し(2020年12月)によると、感染拡大を踏まえて、ユーロ圏は10-12月にマイナス成長になることを想定し、2021年の見通しは3.6%と9月から1.5%ポイントの下方修正となった。その後、2021年1月上旬に公表された世界銀行の見通しでは、ユーロ圏の2021年の見通しは3.6%とOECDと同程度、1月下旬に公表されたIMFの世界経済見通し改訂版では、4.2%と10月時点から1.0%ポイントの下方修正であった。
感染拡大による経済活動の抑制が続く欧州については慎重な見方となっているが、世界全体の2021年見通しは、10月時点の5.2%から5.5%へ上方修正されている。全体としては、ワクチン普及への期待や大型の財政出動の実施などの政策効果への期待が強くみられるが、今後の感染動向に依るところが大きく、先行きは不透明である(第1-1-3図(2))。
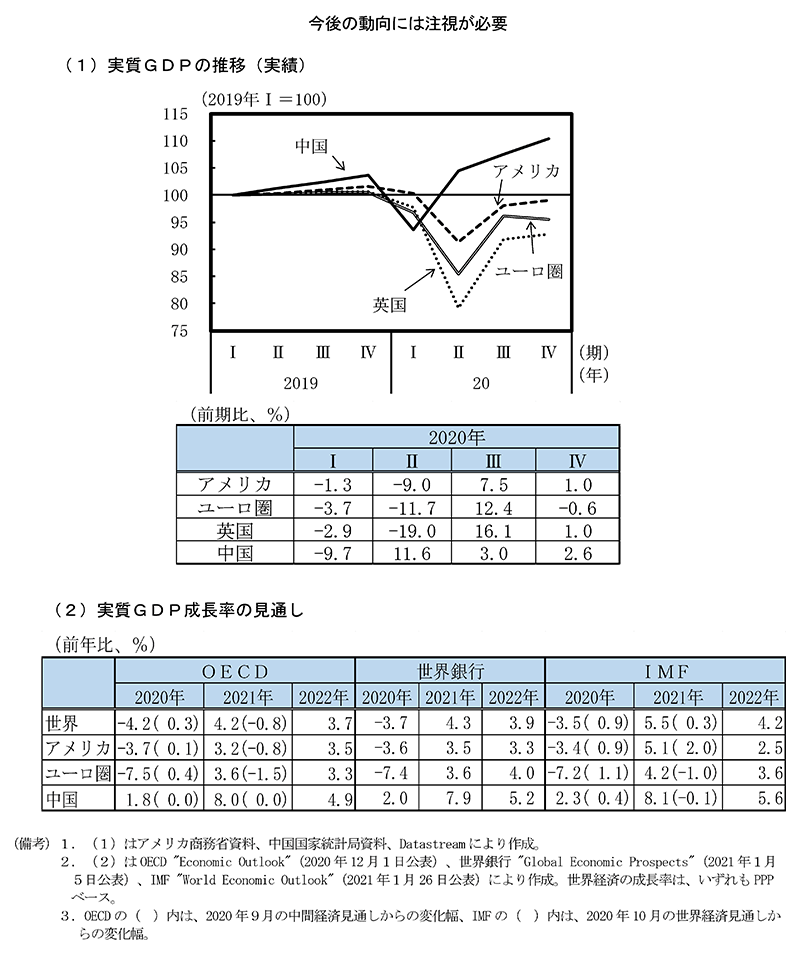
コラム1-1 感染拡大と医療提供体制
新規感染者数は、秋が深まるにつれて増加し、1月7日には全国で7,721人を記録した。こうした中、病床や医療機器、医師など医療提供体制がひっ迫し、医療従事者の負担増も大きな問題と指摘された。確かに増加は顕著ではあるものの、入院・療養者数は、諸外国に比べると少ない(コラム1-1-1図)。なお、感染症以外の原因による死亡数を含めた総死亡者数(1-9月)の増減をみると、手洗いの励行やマスクの着用等の効果も含め、総死亡者数は、呼吸器系疾患の死亡者数の減少等により前年同期から減少している(コラム1-1-2図)。
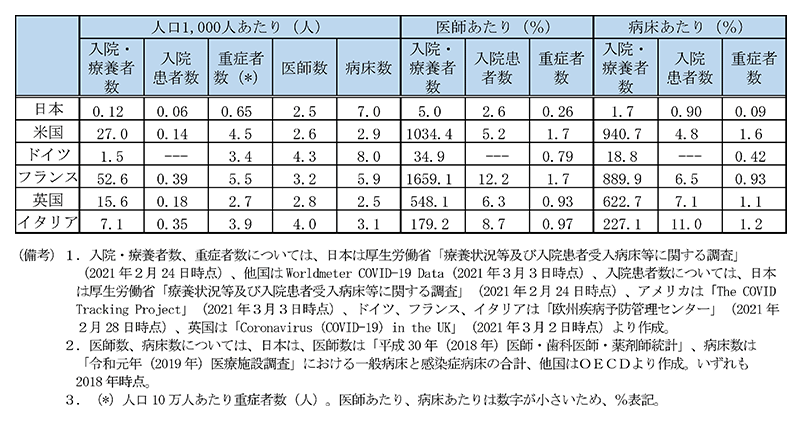
では、諸外国よりも医療資源が豊富であり、患者数も少ないにもかかわらず、医療提供体制がひっ迫するのは何故だろうか。幾つか原因があると考えられるが、ここでは医療資源の有効利用や配置、流動性の欠如という課題を紹介したい。まず、指定感染症の場合には、感染症法8や新型インフルエンザ等対策特別措置法により、一定程度の要請はできるものの、医療機関側の応諾義務は無かった。国や都道府県が医療機関に対し、病床等の整備や感染症患者の受入れについて指示・命令はできず、医療機関側にも受け入れる法的義務は無いことから、実際に患者を受け入れるか否かは医療機関の裁量による。こうしたこともあり、2021年2月に改正された感染症法においては、国及び都道府県が緊急時に医療機関・医療関係者等に対して協力を求め、求められた者が正当な理由なく応じなかった場合には、勧告・公表できることが規定された。ただし、医療機関側に、受け入れる法的義務は引き続き規定されていない。
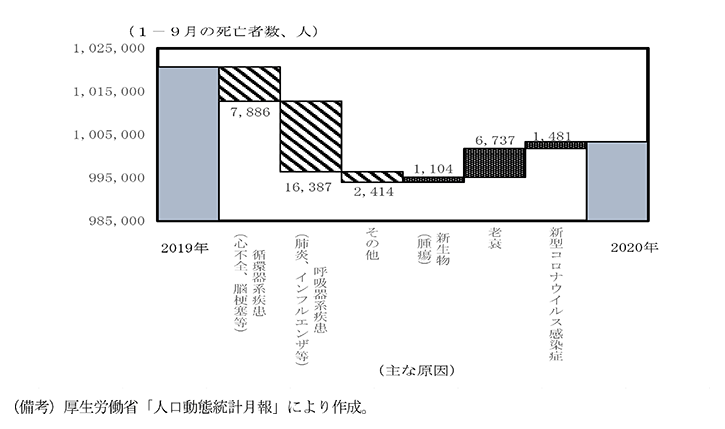
加えて、民間医療機関を中心として感染症患者の受入れに消極的であった背景には、他の患者への対応や医療従事者の負担増だけでなく、医業収益の悪化が課題との指摘もある9。いずれの理由にせよ、多くの医療圏内で新たな感染症患者の受入れ先が増加せず、一部の医療機関に患者が集中し、医療提供体制のひっ迫状況が発生した。ただし、我が国の病床あたり10の入院患者数(病床使用率)は0.9%と、フランスやアメリカの2割以下である(前掲、コラム1-1-1図)。
全国平均ではなく、都道府県別の確保病床使用率(感染症のために確保している病床数に占める使用病床数)をみると、最上位の埼玉県では、全国平均より28%ポイント程度高く、相対的にひっ迫している(コラム1-1-3図)。全国平均を上回っているのは13都府県であり、そのうち9都府県が1月の緊急事態宣言対象自治体となっている。
確保病床使用率(使用病床数/確保病床数)を動かす要因は、定義的に「潜在病床使用率」(入院・療養者数/全病床数)、「入院割合」(使用病床数/入院・療養者数)、「病床確保率」(確保病床数/全病床数)に分解できる。一定数の入院・療養者が存在し、重症化等の要因で入院させる傾向が強い場合は、入院割合が高まり、病床がひっ迫する。また、全病床に対して確保している病床が少ない場合は、病床確保率が低く、病床のひっ迫が生じる11。患者数や重症度は政策で操作できる変数ではないことから、病床確保率を引き上げるのが最も有効な対応策となる。
また、医療資源の有効利用を図ること、地域的に偏在の生じている患者と医療資源の何れかを再配置することで、ひっ迫の程度は緩和することができる。前者については、感染症以外の患者の転院や一時的な定員超過入院を認めるといった取組が挙げられる。また、後者については、医療資源を医療圏内外で最適化することを意味している。民間病院も含めた機能分担、病床用途を設定し、事業継続に必要な財政支援も講じつつ、医療従事者の確保に取り組むことが必要である。特に、重症者を受け入れる病院への医療資源の集約化や医療機関を超えた医療従事者の派遣支援、あるいは都道府県域を超えた患者の機動的・柔軟な受入れ調整などを行うことにより、安心を確保し、感染拡大防止と経済活動の両立を目指していくことが求められる。
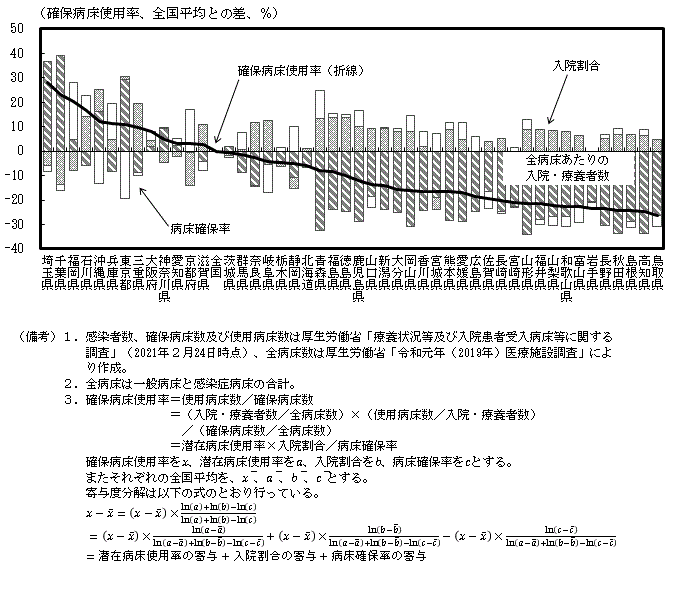
2 家計関連の需要動向
(家計の所得は持ち直しの動き)
家計の所得動向を実質総雇用者所得でみると、2020年年初までは、緩やかに増加していたが、その後は感染症の影響により大きく落ち込んだ(第1-1-4図(1))。実質総雇用者所得の動きは雇用者数、一人当たり賃金、物価の動きに分解できるが、緊急事態宣言下の4-5月は、雇用者数要因、名目賃金要因ともに大幅なマイナス寄与となった(第1-1-4図(2))。その後は経済活動再開にともない、雇用者数や賃金動向の改善を受けて、徐々に持ち直しの動きがみられている。2020年12月は年末賞与が大きく減少したことで名目賃金要因のマイナス寄与が拡大したが、今後は雇用者数の底堅さなどを反映し、実質総雇用者所得の持ち直しは続いていくものと期待される。
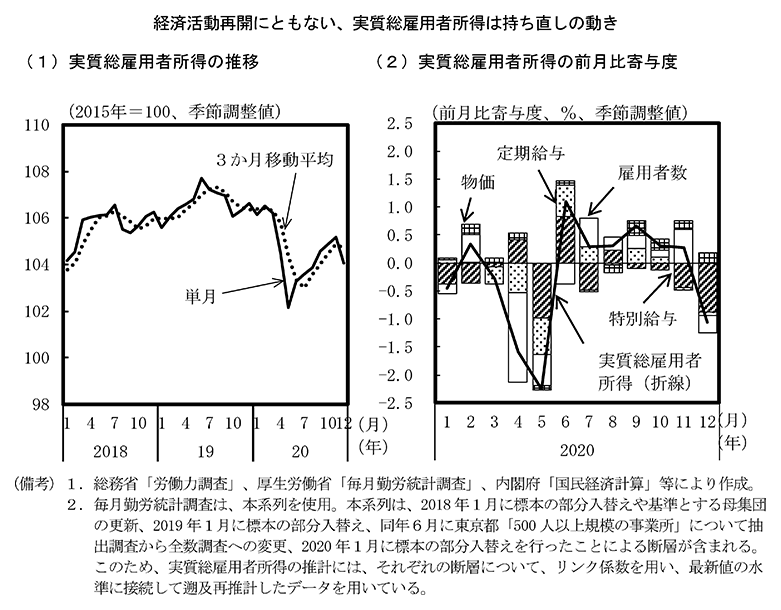
(家計の貯蓄は増加)
雇用者所得は感染症の影響によって大きく変動したが、2020年は特別定額給付金が家計所得を下支えした。総務省の「家計調査」を用いて世帯の家計貯蓄をみると、2020年は前年差プラスで推移しており、勤労者世帯(総世帯)の貯蓄超過額は、12月までの累積で、43.2万円程度となっている(第1-1-5図(1))。この貯蓄超過額を要因分解すると、可処分所得の増加要因が約46%、消費支出の減少要因が約54%となるが、可処分所得には、特別定額給付金の効果が含まれている(第1-1-5図(2))。個人消費の動向については後述するが、感染状況が落ち着くことにより、これまで控えられてきた旅行や外食などのサービス関連分野についての消費が活性化することが期待される。
なお、こうした「家計調査」にみられる貯蓄の動きについて、日本銀行の「資金循環統計」を用いてマクロでみた家計の現預金保有について確認すると、2020年4-6月期以降、前年以上のペースで増加しており、7-9月期では、前年同期と比べて48.6兆円の増加となっている。2019年の平均前年差や借入金の動きを除外すると、トレンドを26兆円程度上回る額を保有している(第1-1-5図(3))12,13。
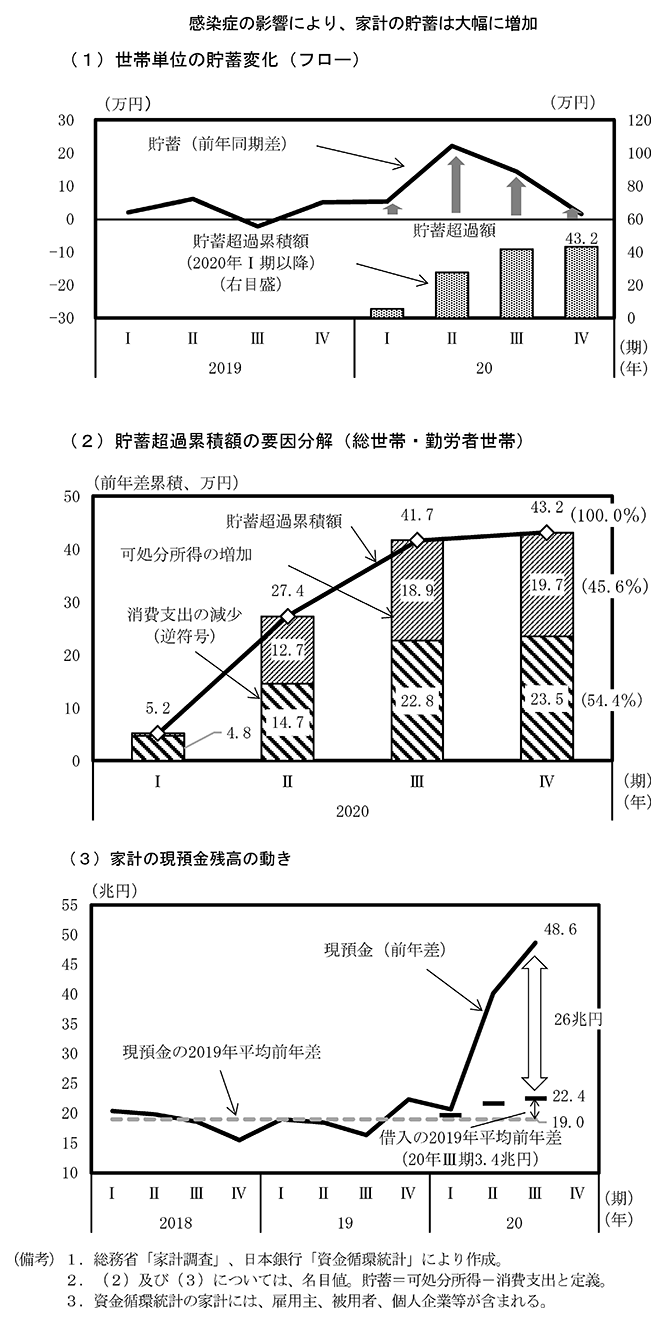
(個人消費は持ち直してきたものの、感染拡大による下押しに直面)
2020年後半の持ち直しは、内需面では個人消費の増加によって実現した(前掲、第1-1-1図)。形態別実質消費の動きをみると、食料品等必需品の非耐久財は底堅く推移し、急落した形態のうち、7-9月以降の戻りは耐久財が中心となっている。衣料品等の半耐久財については、テレワークの増加や外出自粛の影響により低迷している。サービス支出は、社会経済活動の再開とともにある程度は持ち直したが、10-12月期には増勢が鈍化している(第1-1-6図(1))。
業態別実質消費の動きを具体的な品目や業種別売上動向からみていこう。非耐久財の動きについて飲食料品を主に取り扱うスーパーの販売額で確認すると、家庭での食事などのいわゆる「巣ごもり需要」の増加により、前年比でおおむねプラスと堅調に推移した(第1-1-6図(2))14。次に、耐久財の動きを家電販売額と自動車の販売台数で確認すると、家電販売額は、4月は落ち込んだものの、テレワークの普及などに伴うパソコン需要15の高まりや、在宅時間の長期化に伴うテレビ、冷蔵庫、洗濯機等の需要が高まって、増勢が続いた。特に、特別定額給付金支給後には、こうした需要の顕在化がみられる(第1-1-6図(3))。他方、自動車販売(登録)台数は、店舗における営業機会を喪失した4、5月は大きく落ち込んだが、夏場から持ち直し基調が続き、おおむね平年並みの販売台数へと持ち直し、年初段階では横ばいとなっている(第1-1-6図(4))。
このように、財向けの支出はある程度回復が進んでいるものの、接触機会を伴うサービス消費の戻りは遅れている。旅行関連支出について、事業者の旅行取扱高からみると、国内外で移動が制限されたことから、4月には国内旅行・海外旅行ともにゼロ近傍まで減少した。その後、緊急事態宣言の解除に伴い、国内旅行については徐々に持ち直していったが、海外旅行については持ち直しの兆しもみられない状態が続いている(第1-1-7図(1))。
国内旅行の動きを宿泊旅行者数の推移でみると、新規感染者数に増加がみられ、お盆の旅行自粛要請がみられた8月に改善テンポが緩んだものの、9月に入り加速した(第1-1-7図(2))。10月には、7月22日から開始されたGo Toトラベルの対象に東京も加わったことから、一段と持ち直しが進んだ。しかし、北海道における新規感染者数の急増がみられた11月以降、感染リスク懸念もあって宿泊旅行者数は次第に弱い動きとなっていった16。
旅行支出の動きと同様に、外食支出の動きも感染動向に左右される結果となった。事業者側の外食売上高からみていくと、緊急事態宣言下の落ち込み以降、旅行と同様に8月には弱さがみられたものの、その後は持ち直し傾向が続いた(第1-1-7図(3))。しかし、晩秋以降に発生した新規感染者数の増加とそれに伴う営業時間の短縮要請の増加等もあり、足踏み感が増していき、年末年始以降は大幅に減少している。
ただし、厳しさには外食の業態間で大きな違いがみられる(第1-1-7図(4))。ファーストフード店は持ち帰り需要が堅調となったことから、底堅い結果となったものの、居酒屋など酒類を提供する業態では、立地地域における休業や営業時間短縮の要請が年内に複数回生じたことから、極めて厳しい売上水準となっている。
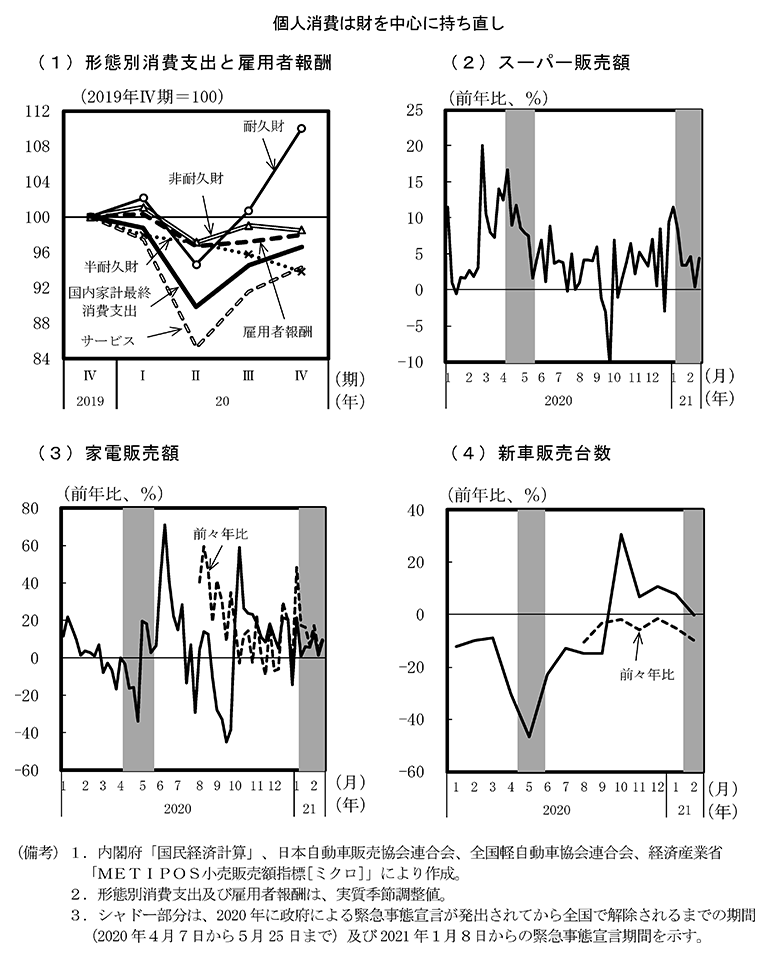
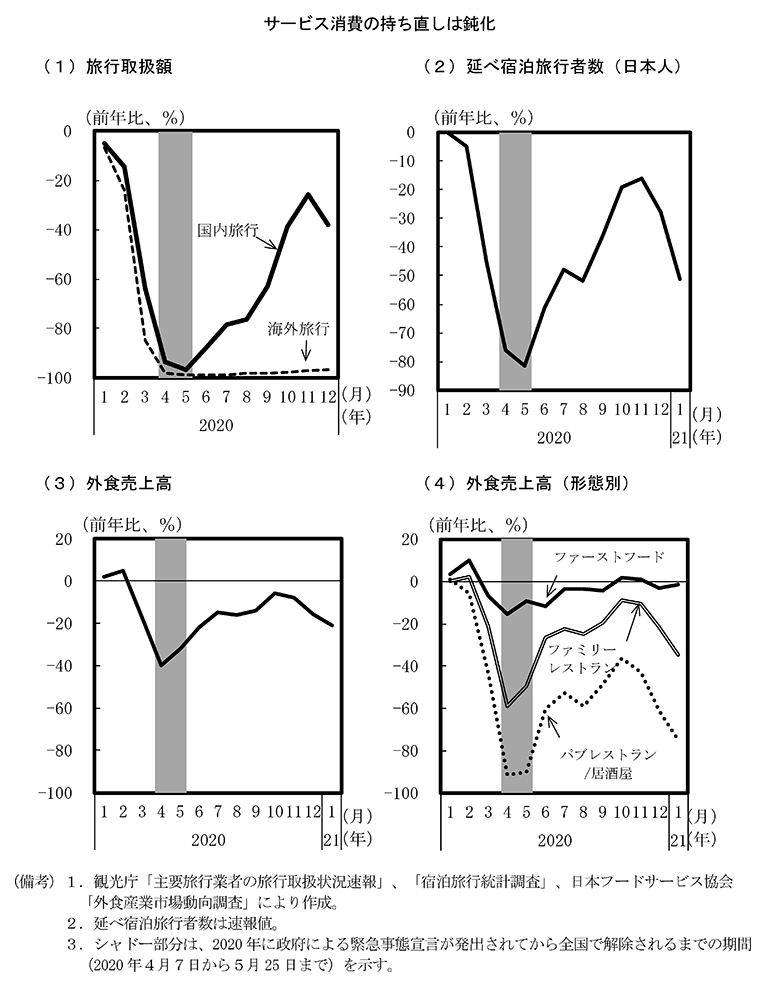
コラム1-2 感染拡大と国内旅行行動の変化17
感染症は人流に影響を与え、旅行消費は大きく下押しされている。観光庁によると、2020年4-6月期の国内旅行消費額は、前年に比べて約5兆円の減少となった。7-9月期は前期に比べて増加したものの、非常に低い水準であった(コラム図1-2)。ただし、「観光・レクリエーション」を目的とする旅行支出は、7月22日からGo Toトラベルが開始されたこともあり、水準は低いものの、7-9月期は大きく改善した。10-12月期は、Go To トラベルの段階的縮小や全国一斉停止発表を受け、前期と同程度に止まっている。
感染拡大後の「観光・レクリエーション」目的の旅行には、特徴的な変化がみられる。具体的には、①日帰り旅行の割合が相対的に上昇、②宿泊旅行においても旅行期間が短期化、③居住地と同一都道府県内への旅行の割合が上昇、④自分ひとりや夫婦・パートナーとの旅行といった少人数の旅行割合が上昇、⑤公共交通機関の利用割合が大幅に低下し、自家用車やレンタカーなど自動車の利用割合が上昇、などが観察され、旅行形態や旅行者の選好に変化が生じている。旅行の「短期化」、「少人数化」、「近距離化」などがうかがえる。感染症を契機とした、マイクロツーリズム需要の高まりや、アウトバウンド需要の国内旅行への振替などにも注目していきたい。
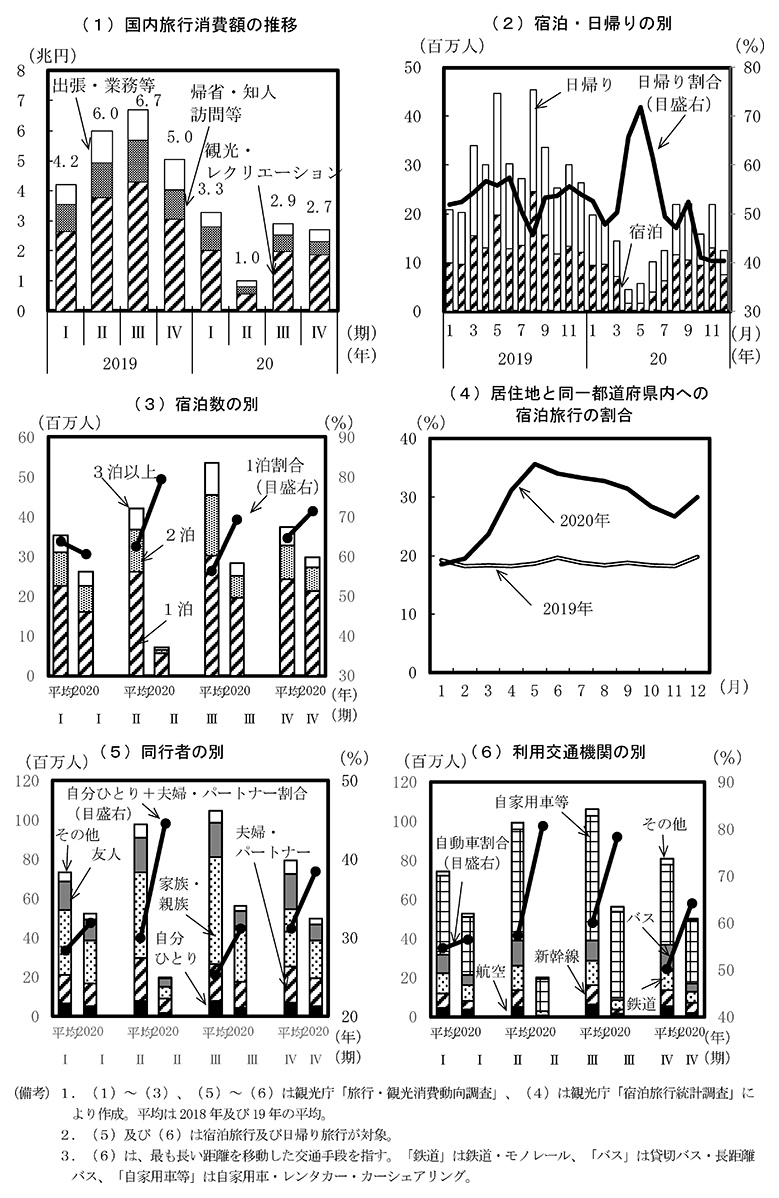
(2020年後半以降もEC市場とEC経由の消費は拡大)
2020年の形態別消費支出にみられる動きは、所得や雇用環境の動向といった、消費を決める一般的な経済要因だけでなく、感染リスクの高低が大きく影響したことを示している18。
こうした状況の下、接触機会を相当程度削減できるEC消費は、2020年後半も増勢が続いている。利用総額を利用世帯数と世帯当たりEC購入金額に分解すると、利用世帯数は引き続き大幅なプラス寄与となっており、利用者のすそ野が広がっている。また、2019年10月の消費税率引上げ前に生じていた駆け込み需要の反動からマイナス寄与になっていた世帯当たりEC購入金額も、10月以降はプラス寄与に転じている(第1-1-8図(1))。
利用者のすそ野が広がっている点について、ECを利用する世帯の世帯主年齢別寄与から特徴をみると、利用割合が低い高齢世帯(60歳~)の寄与が大きく、年後半においても一定以上の増加寄与を記録している(第1-1-8図(2))。
さらに、世帯当たりのEC消費支出をみても、大多数の品目で、おおむね前年比プラスの伸びとなっており、特に「食料品・飲料」の増加寄与が引き続き大きい。さらに、「家具・家電」や「書籍・ソフト」などの増加寄与も大きく、いわゆる巣ごもり需要といった、生活スタイルの変化が引き続き購買活動に影響していると考えられる。なお、大幅に減少していた「旅行関係費」は、Go Toトラベルの効果もあり、9月及び10月にはマイナス幅も縮小したが、感染拡大により、11月以降は再びマイナス幅が拡大している(第1-1-8図(3))。
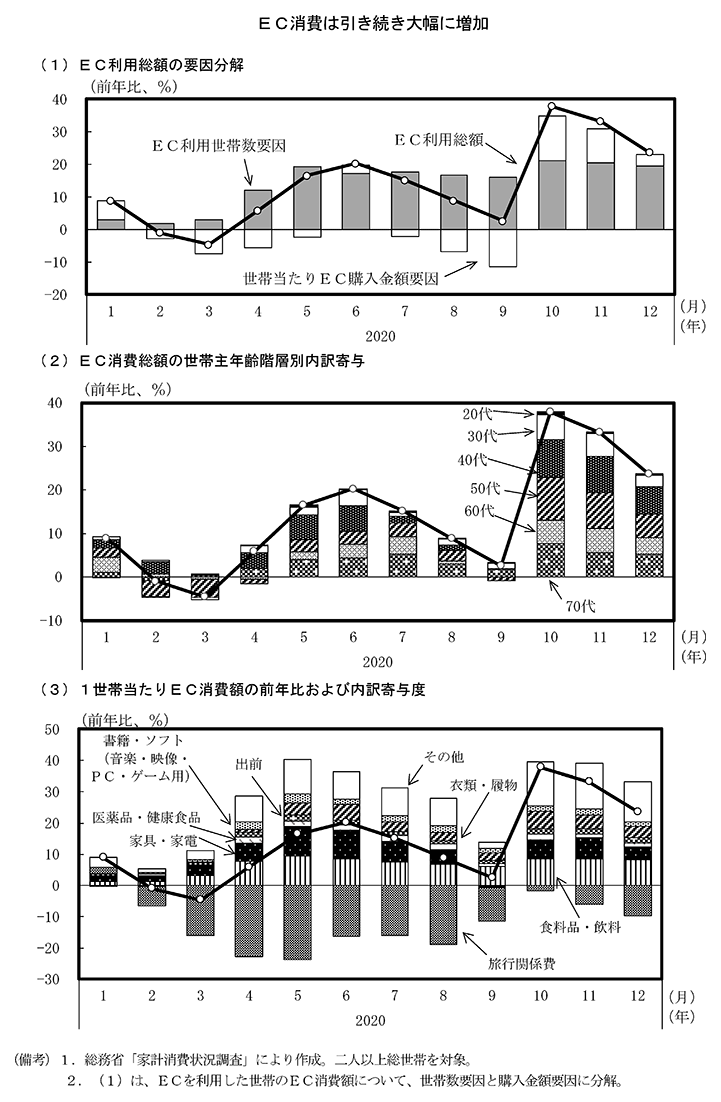
コラム1-3 高齢化と消費の関係について
我が国の個人消費動向を考える上で、高齢化は重要な構造変化であるが、消費はもっぱら所得(GDP)によって決まる19。例えば、2010年以降のOECD諸国における一人当たり実質消費成長率と一人当たり実質GDP成長率の間には、安定的な関係がみられる(コラム1-3-1図(1))。したがって、先ずはGDPに高齢化が影響を与えるのかどうかを確認しよう。単純に一人当たり実質GDP成長率と65歳以上人口比率を平面に描くと、低下傾向は示されるが、10%水準でも有意にならない(コラム1-3-1図(2))。
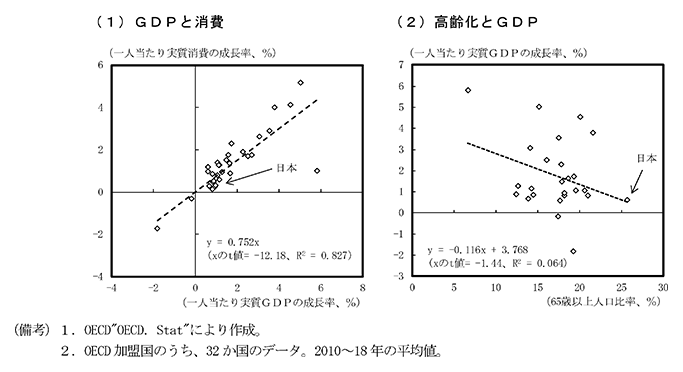
実際、こうした高齢化が経済活動に与える影響については、多くの研究が示されているが、両者の関係は、分析で勘案する制度や慣行、あるいはデータによって結果は異なっており、明確な結論が出ているとは言い難い面がある20。例えば、高齢化と経済成長の関係は、高齢者の就業率低下などのマイナス面が想定されるが、高齢者の就業の進展や、イノベーションの発生といった他の動きによって、必ずしもそのような動きが現れるとは限らない。他方、退職等の年齢依存型の仕組みや慣行等が強く残れば、マイナス面はより顕在化するといったことがある。
では、消費、所得、高齢化の関係をミクロのデータでみた場合はどうなるだろうか。総務省の「家計調査(二人以上世帯・勤労者世帯)」から世帯主年齢が39歳以下と60歳以上のグループを取り出し、感染症の影響が表れる前までの平均消費性向の違いをみると、いくつかの傾向がみられる。
まず、加齢に伴い平均消費性向は上昇する。高齢世帯も勤労者世帯であるが、全体としては貯蓄の積み増し期よりも取り崩し期に入っている世帯も多いことから、ライフサイクル仮説どおり、消費性向は高まる(コラム1-3-2(1)図)。
第二に、高齢世帯の平均消費性向は高いものの、このところ低下傾向がみられる。そこで、消費要因と可処分所得要因に分解すると、消費の減少に加え、可処分所得の増加が平均消費性向の低下要因となっている(コラム1-3-2(2)図)。
第三に、世帯単位の所得や消費は、有業人員数と世帯人員数の影響を受ける。高齢世帯では、世帯人員数が減少傾向、有業人員数は増加傾向にある(コラム1-3-2(3)図)。こうした世帯人員等の変化を除いた平均消費性向21をみると、感染症の影響を受ける前まではおおむね横ばいの動きになる。まとめると、平均消費性向の低下は、所得の増加と消費の減少によるが、その背景には、有業人員(共働き世帯)の増加や世帯人員の減少が影響していることがわかる(コラム1-3-2(4)図)。
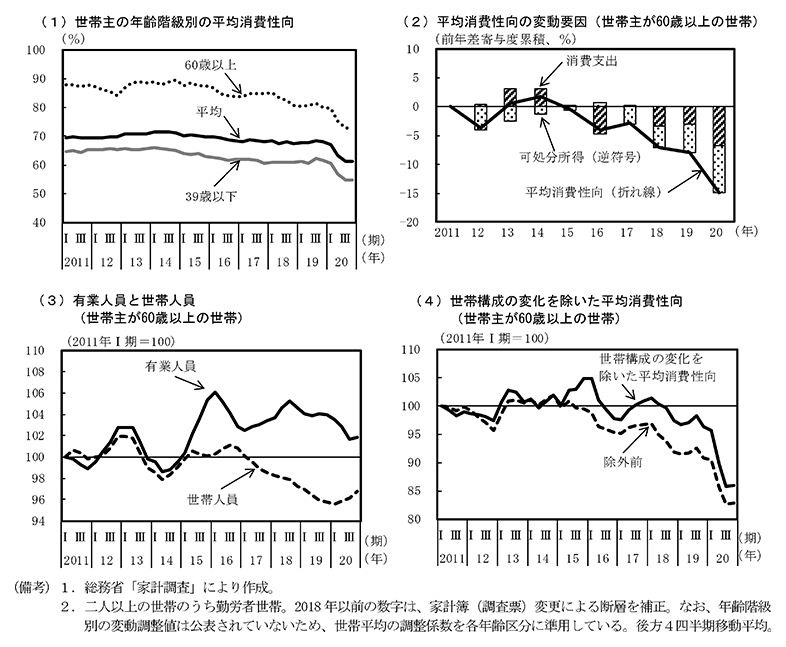
(貸家の着工戸数は減少傾向だが持家や戸建分譲には持ち直しの動きも)
GDPに占める住宅投資の割合は4%程度と大きくはないものの、家具や身の回り品、そして家電等の耐久財需要への波及効果もある22ことから、家計消費と関連した重要な支出項目である。月次で公表される新設住宅着工戸数の動きから、そのすう勢と変動をみていくと、総戸数にはこのところ下げ止まりから横ばい圏内の動きがみられるが、利用形態別にみると、減少傾向が続いている貸家と持ち直し傾向のみられる持家、あるいは戸建分譲の動きが拮抗する姿となっている(第1-1-9図(1)(2))。
貸家については、事業者の不正建築問題や金融機関の融資態度厳格化などにより、感染拡大以前から減少傾向は続いていたが、そのすう勢は大きく変わっていない。一方の持家については、4、5月の緊急事態宣言下に新規受注が減少していたが、同時期に着工の遅延も発生していた可能性がある。また、住宅ローン減税の適用要件の弾力化23により、8-9月の受注が好調だったことから、3か月程度のラグを経て、11月以降の着工に現れてきている面もある(第1-1-9図(3))。
こうした中、住宅展示場来場者組数は6月以降、持ち直してきており(第1-1-9図(4))、また、事業者においては、感染防止の観点から、インターネットを用いた営業を強化しているとの声もある24。いずれにせよ、持家の持ち直しの動きは続くことが期待される。
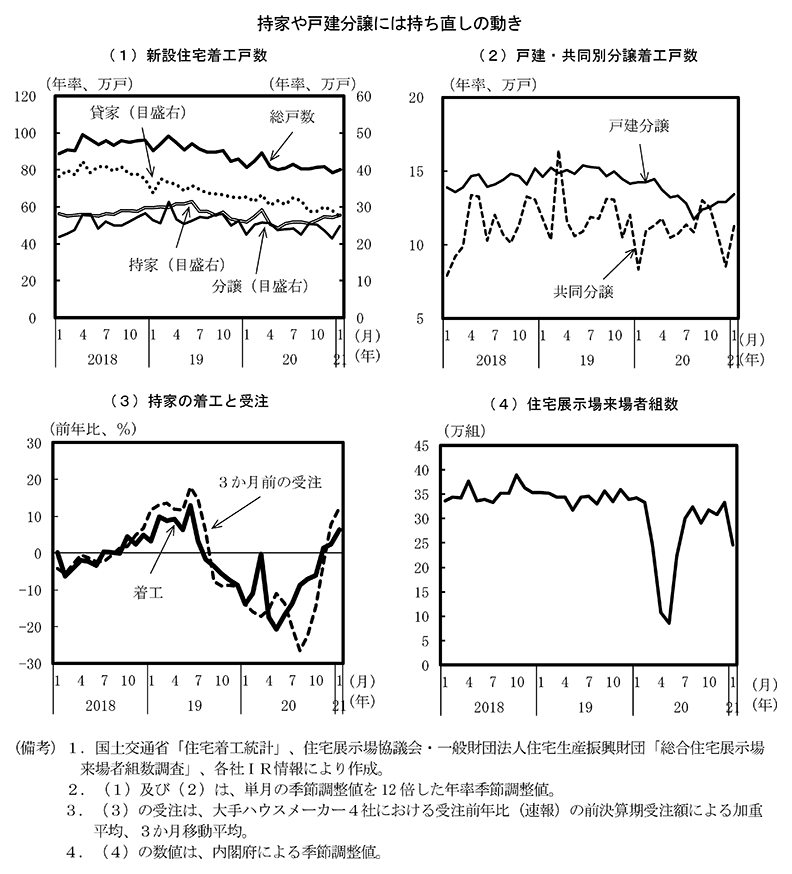
(首都圏の住宅需要に変化の兆しはみられないが、意識調査には二極化の動き)
感染拡大以降、テレワークの広がりを含めた働き方の変化もあり、住宅需要にも変化が生じる可能性もある。そこで、首都圏内の23区及び都下並びに各県別に持家着工戸数やマンション新規発売戸数の動きをみると、持家の着工数に大幅な順位の変動は生じていないが、3県の動きには底堅さがみられる(第1-1-10図(1))。マンションの新規発売戸数の場合、内覧の制限が生じた2020年前半以降、何れの地域においても持ち直しがみられているが、こちらも相対的な順位の変動は生じていない(第1-1-10図(2))25。
新築だけでなく、中古物件の動向も確認すると、中古マンションの価格指数は、都内物件を筆頭に全体的に持ち直し傾向がみられる(第1-1-10図(3))。中古マンション価格の持ち直しには、好立地物件への需要の根強さを指摘する向きもある26。新築マンションの平均価格が6,000万円前後で推移する中で、例えば、リフォームを行うことでより利便性の高い物件を購入したいという層が増えていることが背景にある27。
また、賃貸住宅の空室率をみると、これまですう勢的に低下していた都下(23区外)、神奈川、埼玉において、このところ若干上昇の動きがみられる(第1-1-10図(4))。賃貸住宅需要の弱さは、これまでの貸家供給の増加による影響と考えられる一方、需要側の要因も考えられる。具体的には、感染拡大を経験して以降、住民基本台帳の人口増減では、東京都から近郊県への転出超過となっていることもあり28、例えば、大学のリモート授業等による学生の賃貸需要の弱さや一般労働者の首都圏への転勤減少、テレワーク対応が進んだことによる都区部からの転出等、人流の変化が影響している可能性も考えられる29。
変化の生じやすい賃貸物件には動きがみられるが、アンケート調査における住宅購買予定者の回答にも意識の変化がみられる(第1-1-10図(5)、(6))。首都圏在住の20~69歳を対象とした民間企業による調査について、2019年と2020年の結果を比べると、戸建てに対する選好が若干高まったように見受けられ、通勤時間の意向についても、公共交通機関で60分以内・超の回答比率が高まっている。こうした回答の動きには、テレワークに伴う自宅での個室需要の高まりといった働き方を踏まえた住宅ニーズの潜在的な変化が表れていると考えられる。こうした働く側の住宅ニーズの変化は、企業側がどのような勤務環境を提供するのか、あるいは商談等の慣行がどのように変化するのかということに依存することから、オフィスの動向についても注意を払う必要がある(コラム1-4)。
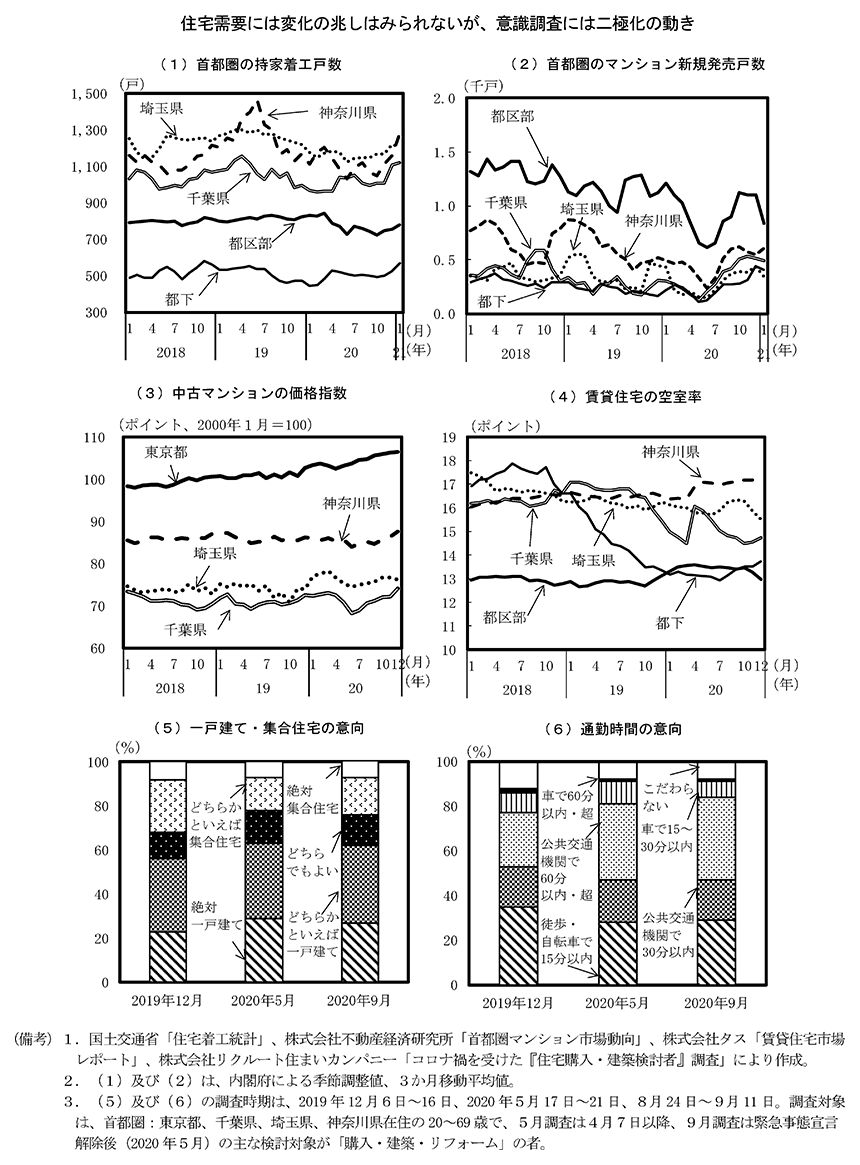
コラム1-4 感染症とオフィス需要30
感染症の影響により、オフィスの需要にも変化がみられている。2012年以降低下が続いていた東京ビジネス地区31の空室率は、2020年2月の1.49%を底に11か月連続で上昇し、2021年1月には4.82%となった(コラム1-4図)。空室率は、主に、企業の人員増減によるオフィス面積の拡張・縮小といった需要面と新規オフィスビルの竣工などの供給面の2つの要因により影響を受けると考えられる。また、企業の好業績時に増員がなされると考えられることから、企業業績を表す指標として売上高の前年度比、新規オフィスビルの供給量の前年度差、空室率の一期ラグを説明変数として、21年度の空室率を推計し、その前年度差を寄与度分解すると、21年度の空室率は、21年度のオフィス供給量の大幅な減少が押下げ要因となる一方で、20年度の売上高の減少が押上げ要因となることから、空室率は20年度よりもさらに上昇することが見込まれる。
ただし、需要要因は売上高のような景気動向だけではない。民間機関のアンケート調査32によると、過去1年間(2019年10月から2020年9月)に面積を縮小したと回答した企業は4.7%あり、その理由として、「コスト削減」(59.5%)のほか、「テレワークにより必要面積が減る」と回答した企業が4割にのぼっている。また、別の調査33では、オフィス面積の縮小を検討していると回答した企業が21.4%あり、その理由・目的として「テレワークにより必要面積が減る」と回答した企業が約9割に達するなど、感染拡大によるテレワークの普及が、オフィス需要の意向にも影響を与えている。今後の空室率動向には、テレワークの普及をはじめとする働き方の変化が需要に与える点にも注目していきたい。
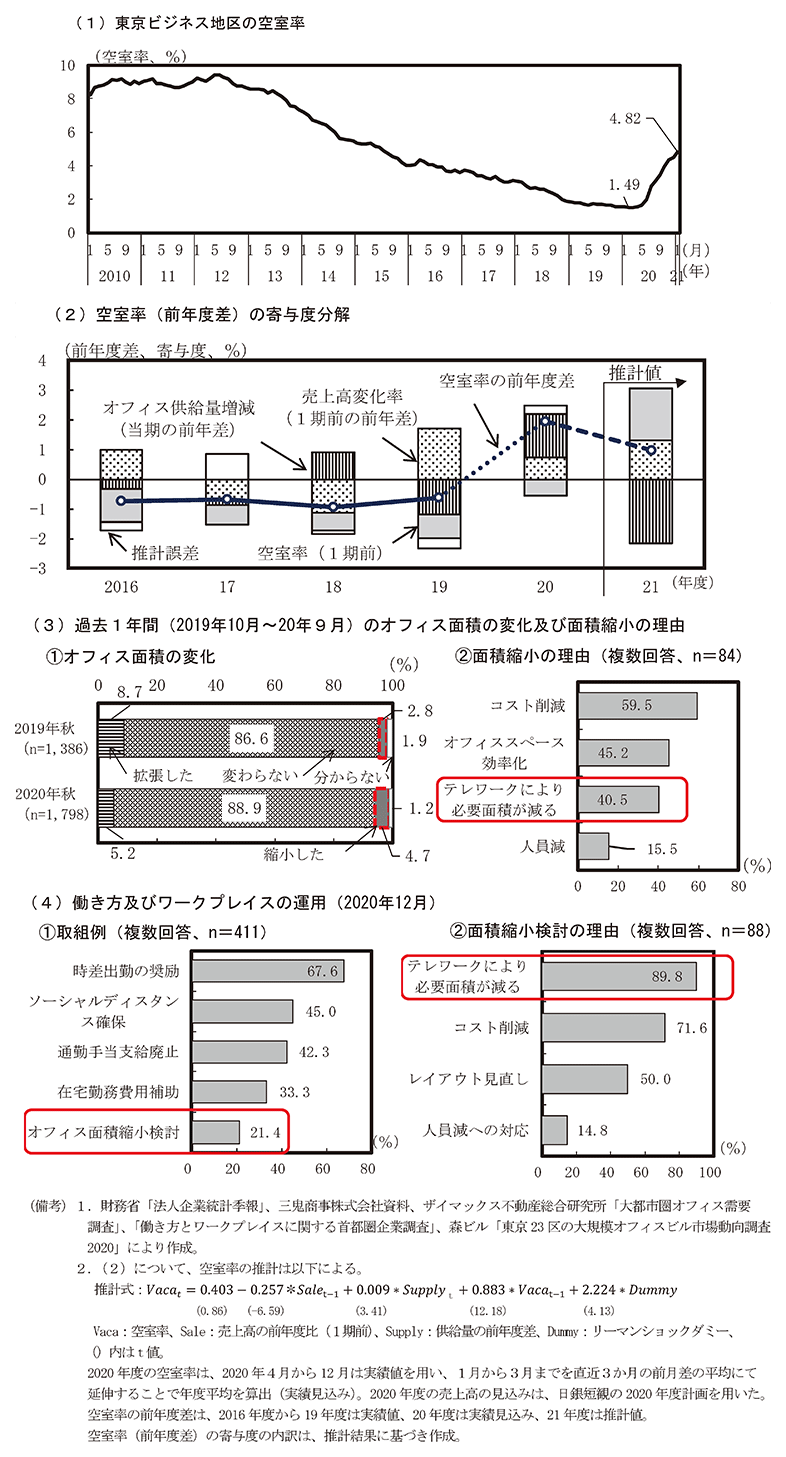
3 企業の生産活動と投資動向
(在庫循環も回復局面入りしたが、生産の増勢には鈍化もみられる)
家計に続き、企業の生産活動や投資動向をみていこう。短期的な景気変動が表れる在庫循環を確認しよう。2018年10-12月期(第16循環の景気の山(暫定))以降の動向をみると、我が国の製造業は、在庫の積み上がり局面から調整局面で推移していたが、2020年4-6月期に出荷が大きく減少し、在庫も減少に転じた。その後、出荷の減少幅は縮小に転じ、10-12月期には回復局面に入ったとみられる(第1-1-11図)。
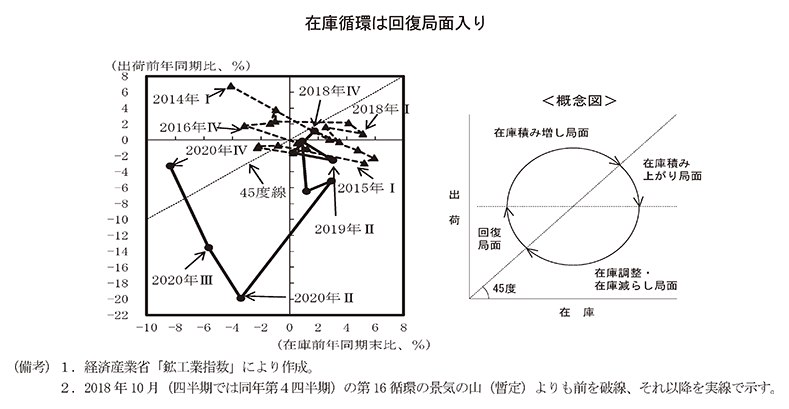
こうした循環的な出荷と在庫の動きと並行し、鉱工業生産指数は、10月にかけて増加基調が続いていた。指数は11月から2か月連続で減少したが、輸出と同様、輸送機械の一服感が要因であり、足下では横ばいの動きとなっている。電子部品・デバイスは、アジア向けの輸出が好調で、増勢が続いている。生産用機械は、海外における設備投資の増勢を受けて、持ち直している(第1-1-12図(1)、(2))。
また、非製造業について、業種別に活動指数の動きをみると、2020年後半は持ち直しの動きが続いている業種が多いものの、10月以降、横ばい感の増した動きとなっている。第3次活動の多くは、個人消費のサービス支出動向と対になっているが、「生活関連サービス業、娯楽業」や「宿泊業、飲食サービス業」は活動水準を次第に高めてきたものの、12月段階でも感染拡大前の1-3月に比べると、3割程度低い水準にとどまっている(第1-1-13図)。
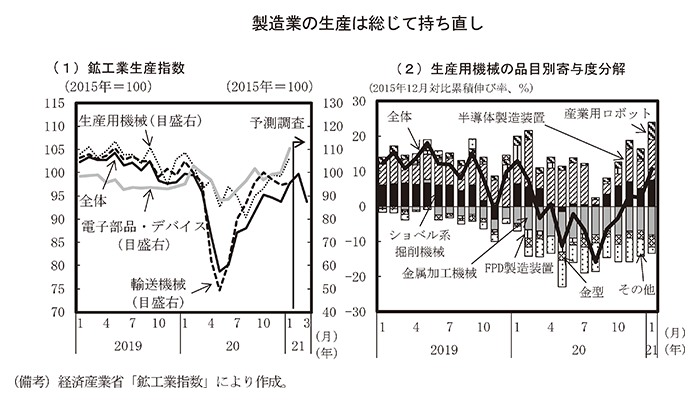
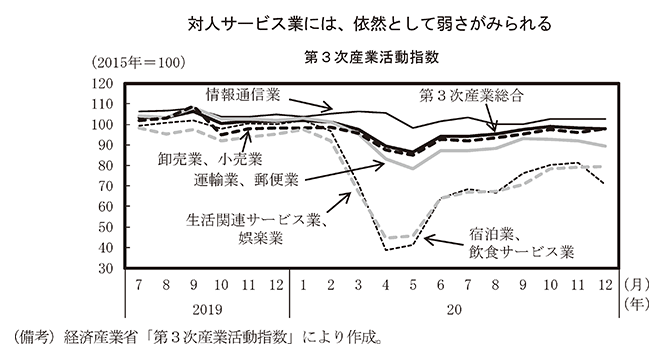
(生産拡大にともなって企業収益も増加に転じたが、非製造業は低位)
大幅に減少していた企業収益は、7-9月期には若干ではあるものの増加に転じ、10-12月期においても増加が続いた(第1-1-14図(1))。なお、上場企業決算の経常利益からも動きをみると、非製造業は前年比マイナスが続くものの、減少幅は縮小している。また、製造業は、前年比プラスに転じている(第1-1-14図(2))。
こうした経常利益の変動を製造業と非製造業に分けて要因分解すると、いずれにおいても、感染症の影響によって大幅に減少寄与が拡大した売上高要因が、7-9月期以降も引き続き大きく下押ししていた(詳細は3章を参照)。他方、製造業では4-6月期から変動費要因がプラスに寄与(仕入れコストの低下)しており、売上高要因のマイナス寄与の一部を相殺している。労働時間の減少や賞与の抑制等を通じて、賃金総額が抑制されていることから、人件費要因はプラスに寄与している(詳細は2章を参照)(第1-1-14図(3))。
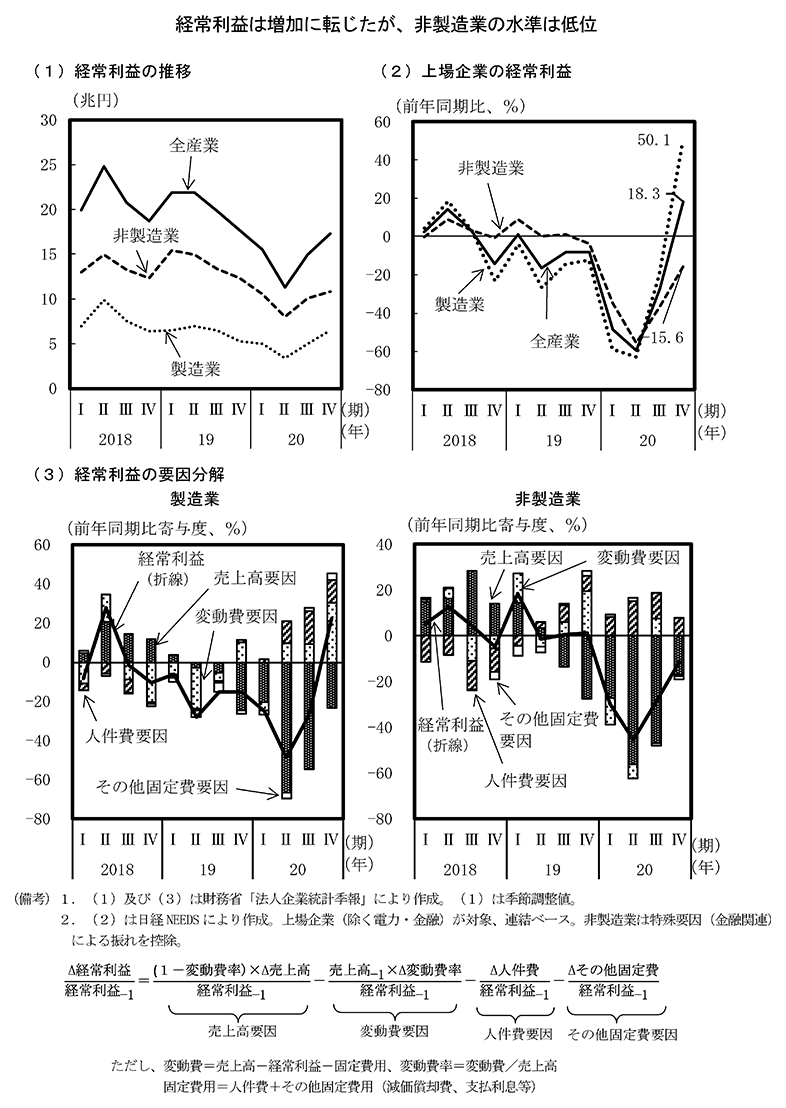
(機械投資には底打ち感が出てきたものの、年度計画は大幅に下方修正)
次に設備投資をみていこう。投資においては経常利益が重要であり、当期の経常利益水準は4四半期後の全産業の設備投資水準と相関が高い傾向がある34。売上減少を起因とした利益減少は、その後1年間程度は投資にはマイナスに働く可能性がある。こうした中、構築物投資は弱く、またソフトウェア投資も12月までの累計で前年度を下回っているものの、足下では、機械投資に持ち直しの動きがみられる(第1-1-15図(1)、(2))。機械投資の先行指標である機械受注動向をみても、製造業では自動車産業や生産用機械業、非製造業では通信業や卸売業・小売業からの受注が増加しており、製造業・非製造業ともに持ち直しの動きがみられる(第1-1-15図(3)、(4))。
ただし、日銀短観(2020年12月調査)における設備投資計画では、2020年度の計画は、3月調査から期を追うごとに下方修正され、前年度を大幅に下回る見込みとなっていることから、企業には慎重さが残っていると考えられる(第1-1-16図)。設備投資計画は、実績に向けて下方修正される傾向があり、直近5年(2015-19年)の修正パターンを基に試算すると、2020年度は前年度から-6%程度の減少となる可能性がある。