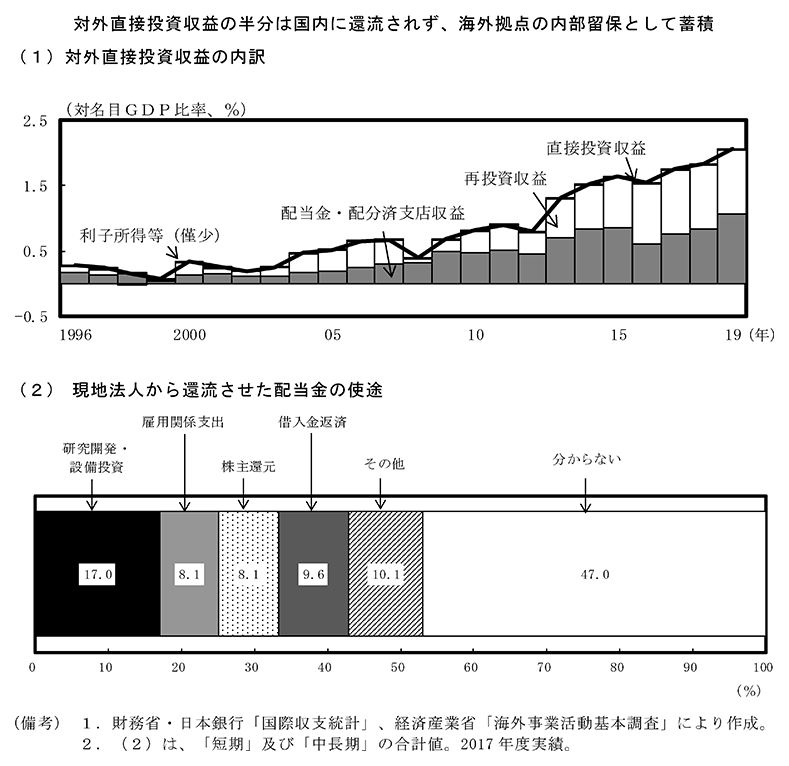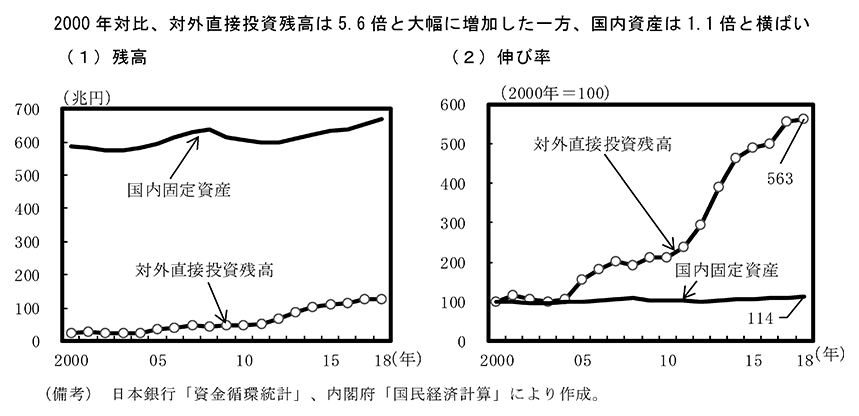第3章 人口減少時代における対外経済構造の変化と課題(第2節)
第2節 人口減少時代における対外経済構造変化と資産の運用
前節では、日本の対外収支の中心が貿易から投資に移行しつつある点について確認した。こうした我が国と海外経済とのかかわりは、人口減少、とりわけ総人口よりも生産年齢人口が一足先に減少する中で今後どのように変遷する可能性があるだろうか。本節では、先行分析事例をサーベイすることで、今後我が国が向かうであろう姿について考察する。具体的には、国際収支をCrowther(1957)が提唱した国際収支の発展段階説でみた場合に、成熟した債権国に差し掛かっている点を確認する。その後、増加している海外資産からの収益力強化によってGNIベースでみた成長を継続するためには何が必要かについて検討する。
1 人口動態と対外経済構造
(我が国では総人口よりも生産年齢人口が一足先に減少)
まず、人口の影響について考える前に、我が国の人口動態を確認すると、既に総人口の減少よりも生産年齢人口の減少が進んでおり、こうした構造は変わらずに推移すると見込まれる(第3-2-1図(1)。また、こうした生産年齢人口の減少を伴う総人口の減少の結果、高齢化も加速するが、その動きについて、世界と比較すると、2010年代半ばまでは我が国の高齢化は世界よりも速く進展していたが、その後は世界の高齢化が加速する中で、その差は縮小する見通しとなっている(第3-2-1図(2))。
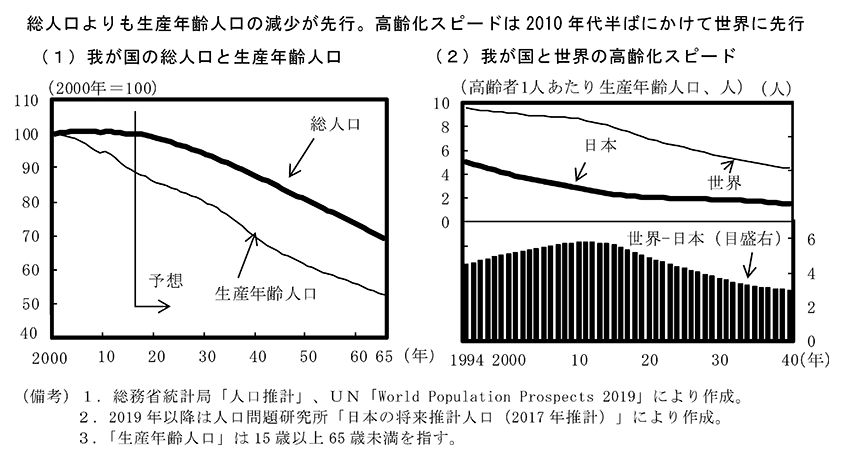
(国際収支の「発展段階説」によれば我が国は成熟した債権国に)
Crowther1による国際収支の「発展段階説」は、一国の経済発展に伴う国際収支パターンを、対外純資産負債残高(ストック)と資金流出入(フロー)の状況から6つのパターンに分類し、人の成長過程になぞらえて捉えようとする考え方である。
同説の考え方を簡単に整理すると、以下のようになる(第3-2-2図(1))
「I.未成熟な2債務国」では、一国の経済が未発達の段階にあり、資本蓄積が不足していることから、貯蓄を上回る投資をするために海外資金を借り入れる状況にある(⇒対外純資産が負債超、第一次所得収支が赤字)。また、輸出財に競争力がないため、財・サービス収支も赤字となり、経常収支全体も赤字となる。
「II.成熟した3債務国」では、依然として海外資金を活用しながら国内資本蓄積を進めているが(⇒対外純資産が負債超過、第一次所得収支が赤字)、ある程度の資本蓄積が進んだことで輸出財の競争力が高まり、財・サービス収支は黒字となる。ただし、第一次所得収支の赤字が財・サービス収支の黒字を上回り、経常収支全体としては依然、赤字である。
「III.債務返済国」では、更に資本蓄積が進むことで工業生産能力がピークを迎え、財・サービス収支が大幅な黒字となるほか、債務の返済が可能となる。依然として対外純資産は負債超過にあり、第一次所得収支も赤字だが、財・サービス収支の大幅な黒字により、経常収支は黒字に転じる。
「IV.未成熟な債権国」では、工業生産能力はピークアウトするが、財・サービス収支は依然黒字を維持する。加えて、対外純資産が資産超過となることで、第一次所得収支も初めて黒字となり、当然ながら経常収支も黒字となる。
「V.成熟した債権国」では財の国際競争力の低下により工業生産能力は衰退し、財・サービス収支が再び赤字に転じる一方、蓄積した対外純資産の大幅な資産超過により第一次所得収支が大幅な黒字となる中で、経常収支は黒字を維持する。
「VI.債権取り崩し国」は最終段階に位置づけられ、財・サービス収支の赤字が所得収支の赤字を上回り、経常収支が赤字となる。対外純資産は依然として資産超過であり、債権国は維持しているが、経常収支の赤字を通じて債権残高は減少していく。
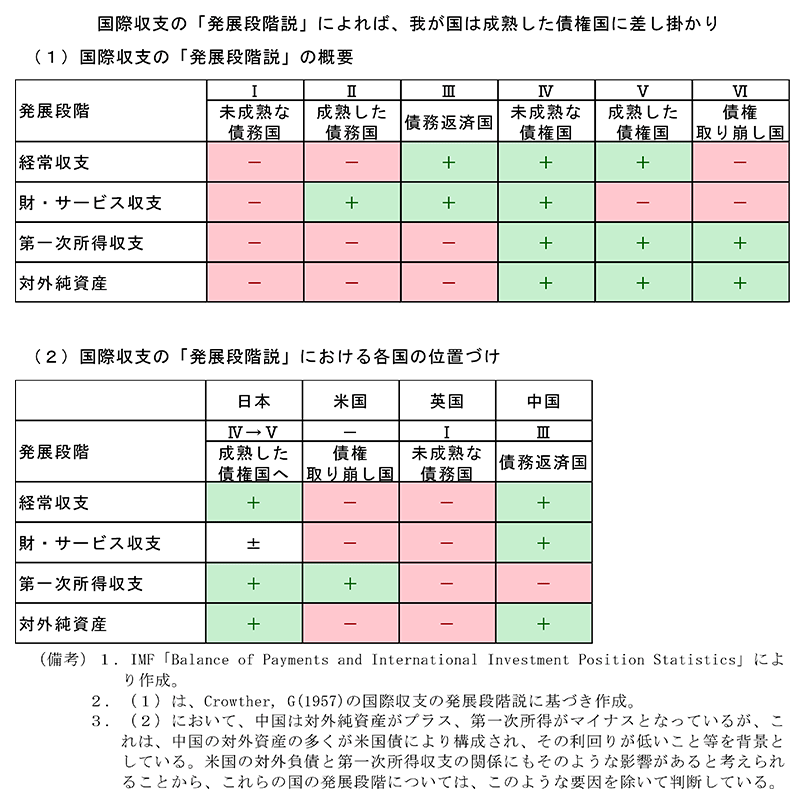
我が国の経常収支を「発展段階説」に当てはめてみると、第1節で確認したとおり、世界最大の対外純資産を背景に、第一次所得収支は大幅な黒字となっている。サービス収支の赤字は縮小傾向にあるものの、依然として赤字であるほか貿易収支がおおむね均衡するもと、財・サービス収支は貿易収支の黒字幅次第で小幅の黒字ないし赤字を行き来する状況にあり、未成熟な債権国から成熟した債権国への移行期にある。なお、他国も同様に当てはめると、中国は「債務返済国」、アメリカは「債権取り崩し国」、英国は一回りし、「未成熟な債務国」に位置づけられる(第3-2-2図(2))。
(人口減少が進むと、資本は海外へ移動)
成熟した債権国にさしかかっている我が国の国際収支は、人口減少、とりわけ生産年齢人口が総人口よりも先に減少する下で、どのように変遷する可能性があるだろうか。これまでの研究によると、人口動態が経常収支の水準に有意な影響を与えることが示されている(第3-2-3図)。
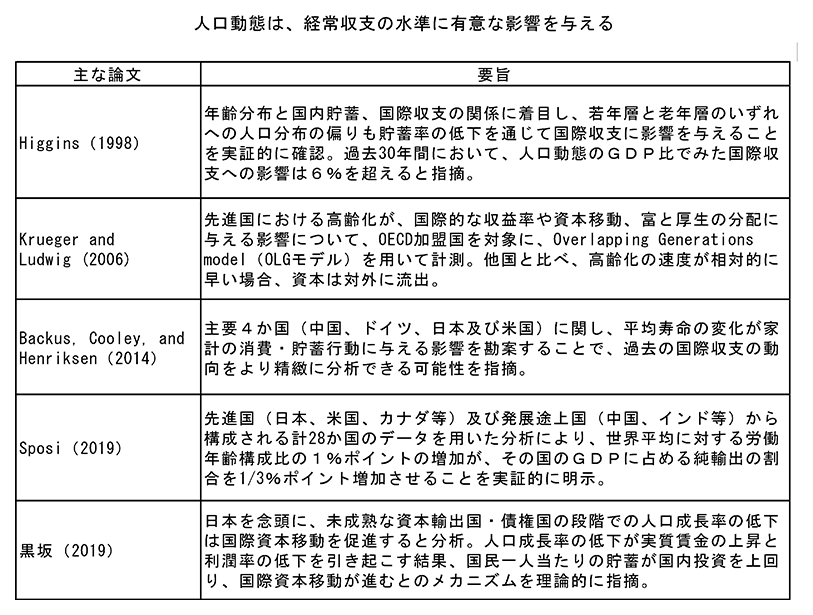
コラム3-2 我が国と世界の人口動態を踏まえた経常収支の先行き
Krueger and Ludwig(2006)は、人口動態と社会保障の規模が資本収益率や国際資本移動に与える影響について、多国間の世代重複モデル(multi-country Overlapping-Generation Model: multi-country OLGモデル)と均斉成長経路(Balanced Growth Path Analysis、以下GBP)を用いた理論モデルを構築し、定量分析を行っている。同論文で定式化された理論モデルを簡略にすると、まず、人口動態、とりわけ若年人口(生産年齢人口)比率の低下が貯蓄や投資を介して金利に与える影響を考える。今、若年者と高齢者という単純な世代を考え、若年者は、社会保障(税)を支払った後の賃金から消費を行い、その残りを貯蓄する。高齢者は金利収入を含む貯蓄と社会保障(年金等)を原資に消費すると仮定する。一国全体での貯蓄主体は若年者であり、若年の減少(若年人口比率の低下)は貯蓄の減少を意味する。貯蓄減少は資金市場における供給曲線を左にシフトさせる(金利は上昇)。他方、若年の減少は、労働人口の減少でもあり、資本ストックが労働人口対比で過剰となり、投資減少は資金市場の需要曲線を左にシフトさせる(金利は低下)。同論文では、単純なコブ・ダブラス型の生産関数の下でのGBPを仮定しているため、貯蓄投資の減少は均衡金利を押し下げる要因となっている4。
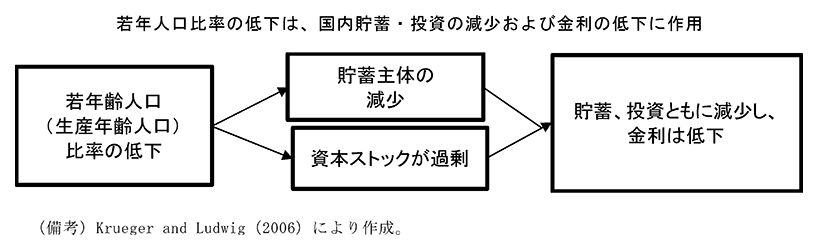
次に、開放経済の下での資本移動について考える。貯蓄は、開放経済の下でも、自国の若年人口比率の変動にのみ依存するが、投資は他国との相対的な高齢化スピードの影響も受ける。前述したように、若年人口比率の低下は資本労働比率の上昇により、自国金利の低下要因となるが、加えて、自国の相対的な高齢化スピードが他国に比べて速い場合、他国の金利は自国と比べて相対的に高くなるため、より金利(期待収益率)の高い他国への資本移動が生じる。若年人口比率が低下している場合において、自国の相対的な高齢化スピードが他国に比べて速い場合は、そうでない場合に比べて他国への資本移動が生じる分、より国内投資は減少し、金利低下圧力が生じることになる。この時、国内投資の減少スピードが貯蓄の減少スピードを上回り、経常収支は黒字化する。
同論文の手法を参考にしながら、我が国と世界の人口動態が、貯蓄・投資および経常収支に及ぼす影響を計算した。純粋に人口動態のみに着目する観点から、社会保障率の仮定は省略した。また、推計対象は我が国と我が国以外の2国を想定し、世界の技術進歩は一定と仮定した5。
我が国では、2040年にかけて緩やかに高齢化が進む見通しにあり、国内貯蓄は、高齢化要因で減少する。ただし、外生的に仮定した技術進歩によるGDP成長が進む分、若年者1人当たりの賃金は増加するため、貯蓄の減少スピードはその分だけ緩和される。また、国内投資は、国内の人口動態に加え海外との相対的な人口動態の影響も受けるため、2010年代半ばにかけて、我が国と世界の高齢化スピードの差が拡大するもとでは、相対的に金利(投資収益率)が高い海外への資本移動圧力が生じ、貯蓄より速いスピードで減少する。その結果、経常収支は2010年代半ばにかけて緩やかに黒字化する。その後、2030年にかけて我が国と世界の高齢化スピードの差が縮小することで海外への資本移動圧力は減少するため、国内投資および、経常収支はおおむね横ばいで推移する。さらに、2040年にかけて、我が国と世界の高齢化スピード差が横ばいとなる中、海外への資本移動圧力も横ばいとなり、国内投資は国内の高齢化を受け減少する。この結果、経常収支の黒字幅は縮小する(コラム3-2-2図)。
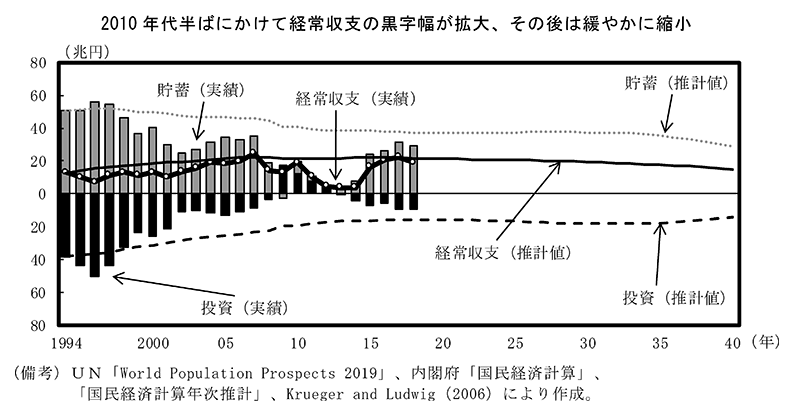
2 国富の最適な対外投資とホームバイアスの克服
(対外資産の利回りは他の先進国よりも高いが、投資規模が小さい)
第1節2項において、マクロでみた対外純資産の収益率は、6%程度と高く、非常に良好なパフォーマンスであることを確認した。では、我が国は効率的に対外資産の収益力を活かしているといえるだろうか。
この点について、まず対外資産の利回りを他の先進国と比較する。対外資産全体の利回りをみると、利回りの高い対外直接投資が進んだ2012年頃を境に、ドイツを上回り、アメリカに次いで2番目の水準となっている(第3-2-4図(1))。対外資産利回りを対外直接投資、対外証券投資別にみると、対外直接投資については、2013年頃からアメリカを上回っているほか、対外証券投資も他の先進国を上回っており(2018年は何れもアメリカと同程度の利回り)、我が国の対外資産の収益力は他の先進国と比べて高いことが確認できる(第3-2-4(2)(3))。
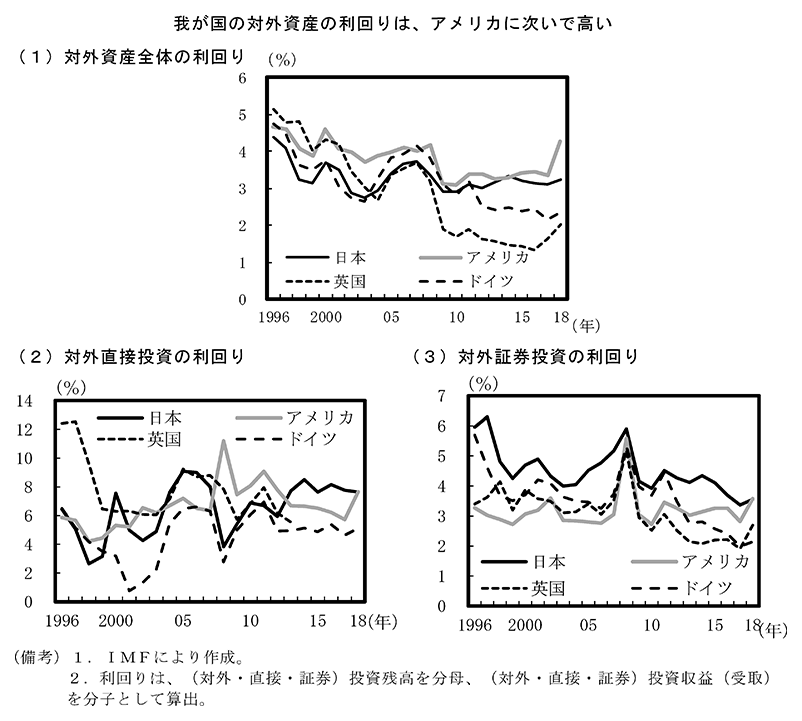
我が国の対外投資の利回りは、対外直接投資、対外証券投資ともに他の主要先進国と比べて高いことが確認できたが、収益を名目GDP対比でみるとどうだろうか。
主要先進国の対外直接投資と対外証券投資の収益及び残高を対名目GDP比でみると、対外直接投資残高は、他の主要先進国に比してまだ少ないが、収益規模はアメリカ、ドイツと比べて若干低いものの、遜色ない水準まで高まりつつある(第3-3-2図)。これは、利回りの高い地域へ効率よく投資できている証左と言えよう。今後は、高い利回りを維持しながら投資残高を増やすことで、対外直接投資の収益を一層増やすことが期待される(第3-2-5図(1))。
次に、対外証券投資をみると、対名目GDP比でドイツと同程度の投資規模ながら、収益額の名目GDP比はドイツの1.5倍となっており、証券投資も効率的に収益を上げているといえる(第3-2-5図(2))。
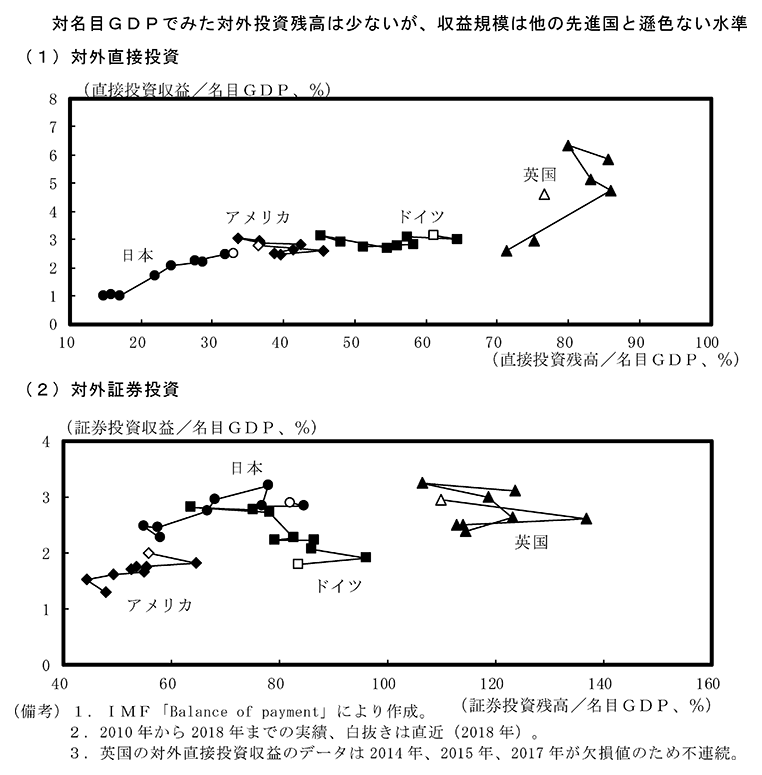
(対外証券投資のホームバイアスは、国内銀行を中心に強い)
前述のように、対名目GDP比でみた対外証券投資は、比較的良好な収益を上げているが、主要先進国と比較した我が国のホームバイアスは依然として強い。特に、株式投資においてそうした傾向がうかがえる(第3-2-6図(1)(2))。対外証券投資を保有主体別にみると、年金や農林水産金融機関の対外証券比率が緩やかに上昇している一方、国内銀行や保険の対外証券比率は、依然として低い。国内銀行は、各種規制により保有できるリスク量に一定の制約があるほか、保険は負債である保険契約とのデュレーション・マッチングの観点から超長期国債の保有ニーズが高いなど業態特有の事情がある(第3-2-6図(3))。
ホームバイアスの原因について、これまでの既存研究では為替変動や言語の違い、あるいは海外支店の有無といった例を挙げる場合が多い6。しかし、こうした金融資産の保有主体が抱える規制上の制約もホームバイアスが強い要因と考えられる。実際、金融機関負債に占める預金取扱機関比率と対外証券比率との関係には負の相関があり、いまだ銀行偏重の我が国が利回りの良い対外証券投資比率を高められない要因になっていると考えられる(第3-2-7図)。いわゆる「貯蓄から投資へ」という金融行政上の取組は長年に渡っているが、運用資産をホームバイアスが弱い主体にゆだねることで、対外投資効率を一層高めることが期待される。
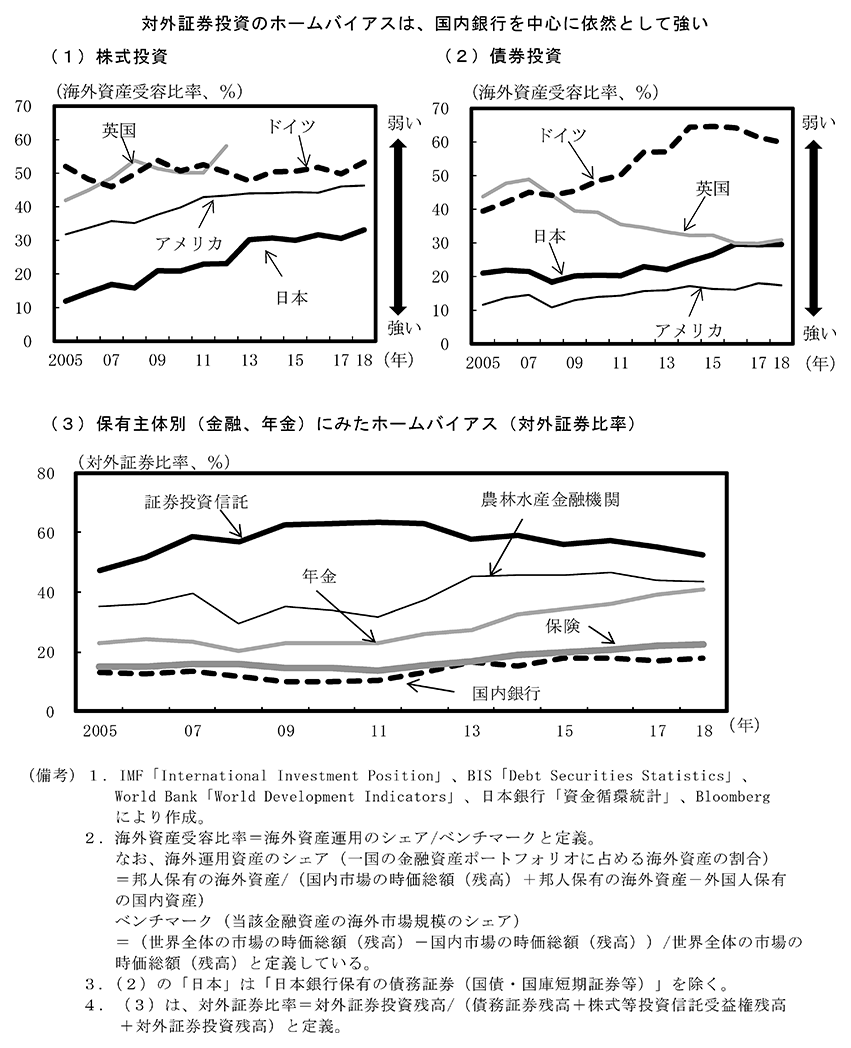
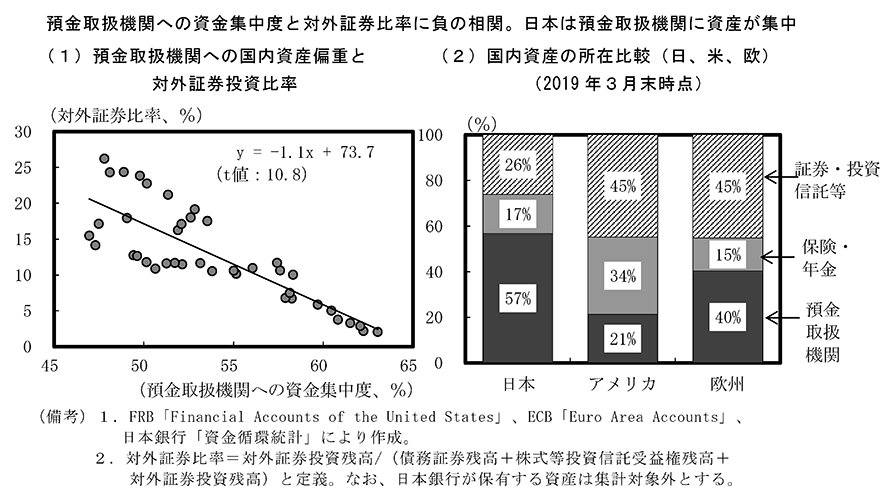
3 対外直接投資の拡大と国内経済への影響
(対外直接投資残高は、低リスク中リターンの欧米諸国に5割弱が集中)
最後に、我が国の直接投資残高とリスク・リターンの関係をみてみよう(第3-2-8図)。これによると、我が国の直接投資残高の5割弱は、ボラティリティ(標準偏差)が比較的低く、収益率も中程度の「低リスク中リターン」の欧米諸国に集中していることが確認できる。アジアを中心とした新興国は、工業化や人口増加を背景に高い成長を実現しており、その分、直接投資収益率も高くなっている(第3-2-9図)。このため、対外直接投資の収益率を更に高めるには「中リスク高リターン」の新興国への投資比率を高めていくことが、有効な手段の一つと考えられる。実際、効率的フロンティアを描写すると、先進国のみを直接投資対象先とするよりも、アジアを含む新興国も投資対象とした方が、ポートフォリオ全体として同じリスクで高い収益を得られる姿となる(第3-2-10図)。
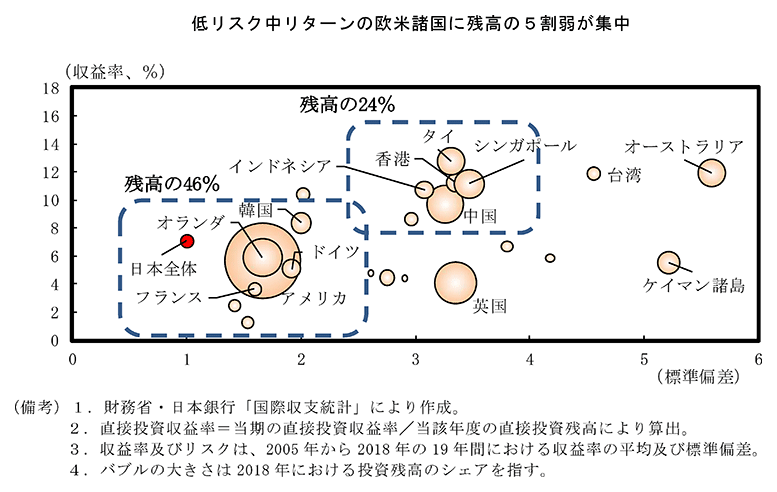
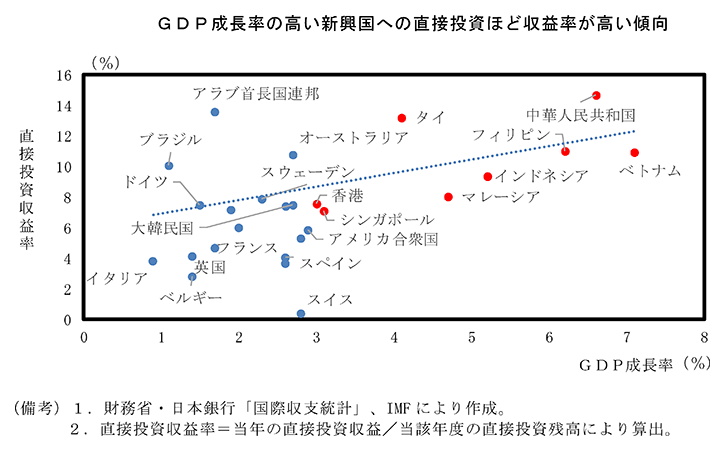
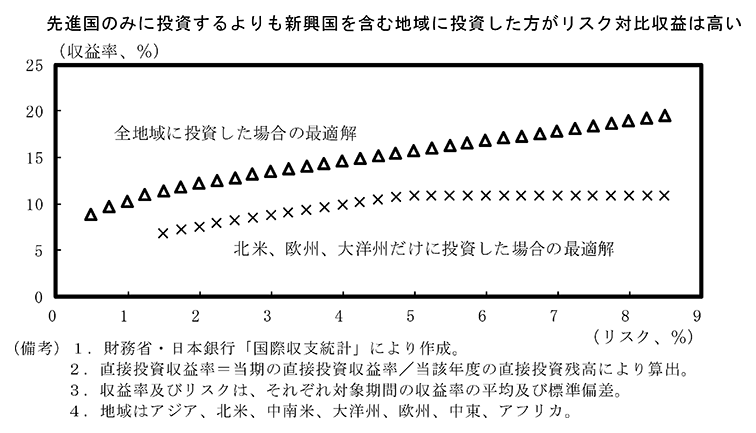
一方で、新興国は自国産業保護の観点等から対内直接投資に対し、先進国に比べて厳しい規制をかけている。経済協力開発機構(OECD)が公表しているFDI制限指数7の推移をみると、対内直接投資に対する規制は各国ともに緩やかに弱まっているが、先進国と新興国との比較では、新興国の規制の強さが目立つ(3-2-11図)。先進国は、OECDにより規定された投資協定により、対外開放的な政策合意がなされているため、外国資本による投資障壁が低く保たれている(第3-2-12図)。新興国との間でもこうした枠組み合意を進めていくことが期待される。
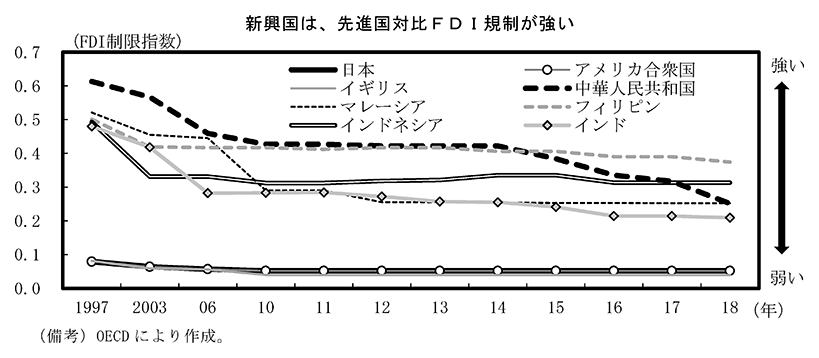
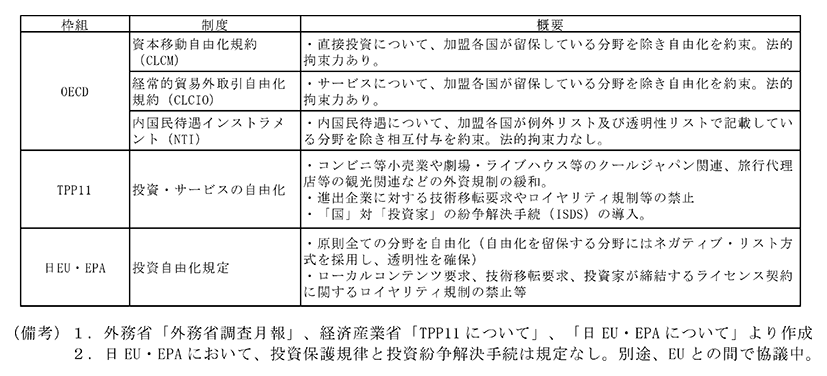
(対外直接投資の開始は、国内企業業績や雇用など国内経済にもプラスの効果)
対外直接投資については、産業空洞化に対する懸念など国内経済に負の影響を与えるという文脈で語られることも多い。我が国企業の業績を単体ベースで確認すると、2000年代半ば以降は海外子会社からの受取配当金を含む経常利益が営業利益を上回って推移している(第3-2-13図)。
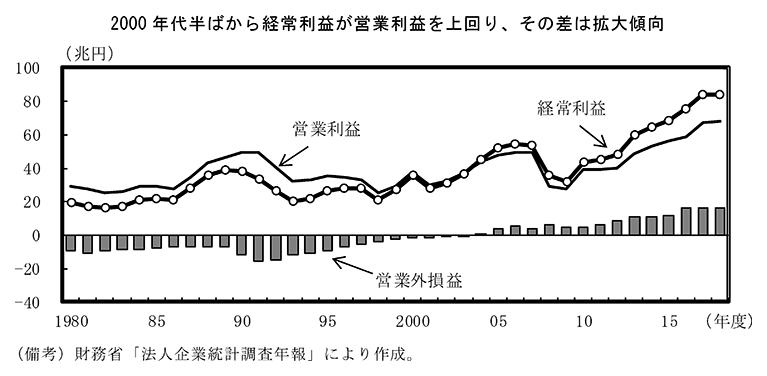
対外直接投資の増加は、国内企業の利益にプラスとなっているが、それ以外の売上高や雇用、TFPや一人当たり賃金などにどのような影響を与えているのだろうか。そこで、対外直接投資の開始が国内企業に与える影響について、企業データを用いた定量的分析を試みた。分析結果によると、対外直接投資を開始した企業は、開始しなかった企業と比べて時間の経過とともに売上高や雇用、売上高利益率やTFPなど様々な要素で有意にプラスの効果がある。また、一人当たり賃金についても、有意水準は10%未満ながら、直接投資開始から4年後には対外直接投資開始企業が有意に高くなることも確認できた(第3-2-14図)。
このような結果となる背景として、売上高の増加は、海外の関連企業に向けた取引が寄与すると考えられるほか、海外との取引増加による業容拡大から、国内雇用も増加すると考えられる。また、海外直接投資により得られた新たなノウハウの獲得がTFP上昇に寄与すると考えられる。その結果、一人当たり賃金も対外直接投資を行わない企業と比較すると直接投資開始から数年後には有意なプラスの差が現れると考えられる。
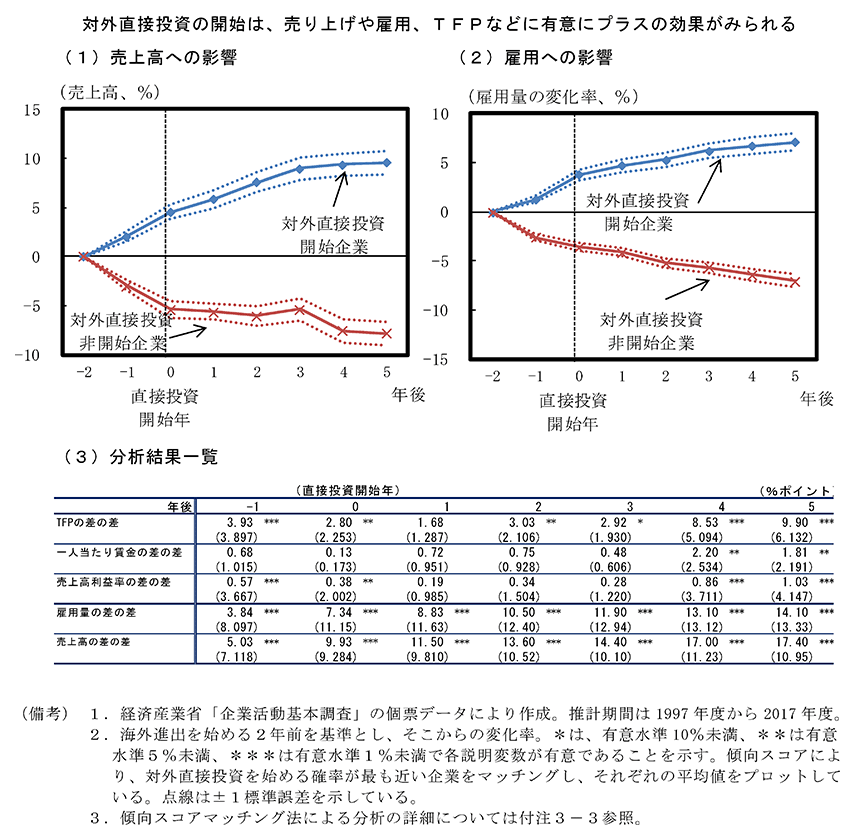
(対外直接投資収益の半分は海外拠点の内部留保として蓄積)
以上でみたように、対外直接投資収益はある程度国内に還元され、国内経済にもプラスの効果をもたらすことが認められる。ただし、対外直接投資収益のうち、約半分は国内には還元されず、再投資収益として海外拠点の内部留保として蓄積されている(第3-2-15図(1))。また、配当として国内に還流した資金の使途を確認すると、2割弱が「研究開発・設備投資」、1割弱が「雇用関係支出」となっている一方、「分からない」とする回答が5割弱に上っている(第3-2-15図(2))。
なお、民間非金融機関の対外直接投資が2000年から18年間で5.6倍と大幅に増加した一方で、国内固定資産は1.1倍と、ほぼ横ばいとなっている(第3-2-16図)。海外から得た利得をいかに国内に還元し、有効活用するかも課題の1つである。