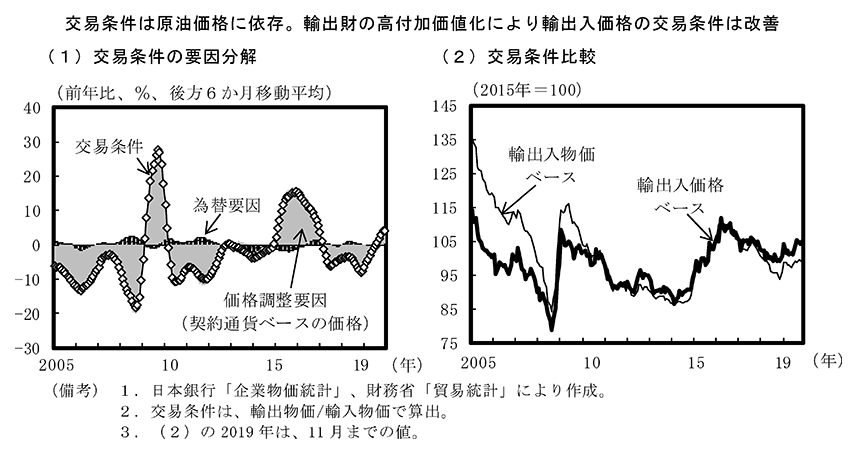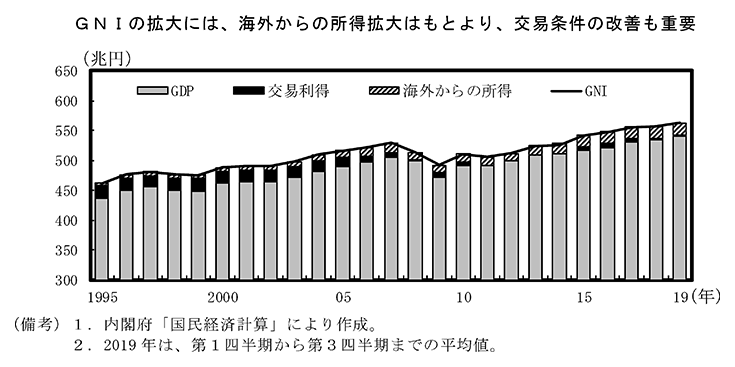第3章 人口減少時代における対外経済構造の変化と課題(第1節)
第1節 我が国経済の対外経済構造の変化
本節では、対外経済構造の変化をフロー(対外収支)面、ストック(対外資産残高)面から確認したのち、国内総生産(GDP)に海外からの所得と交易利得を加えた国民総所得(GNI)の成長に必要な課題について整理する。
まず、1項において、対外収支の長期的な構造変化について概観する。次に、2項において、経常収支黒字の主体となった第一次所得収支の黒字の背景となる対外資産負債残高の推移や対外資産の収益力について検証する。最後に、3項において、経常収支への黒字寄与を失いつつある貿易収支について、伸び悩む輸出の背景と交易利得について考察を加え、国民総所得(GNI)の成長に必要な課題について整理する。
1 対外収支の構造変化
(経常収支黒字の主因は、貿易収支から所得収支へ)
一定期間における海外との財・サービスの受払(貿易・サービス収支)や海外への投資に伴う受払(第一次所得収支)などで構成される経常収支は、長らく黒字で推移しているが、その内訳は大きく変化している。これまで経常収支黒字をけん引してきた貿易収支は、2000年代半ば以降、徐々に黒字幅が縮小し、2012年から2015年にかけては赤字に転じるなど、常態的な黒字ではなくなっている。一方、第一次所得収支の黒字幅は徐々に拡大し、2000年代半ば以降は経常収支黒字の主因となっている。この間、サービス収支は赤字幅が縮小し、近年では収支がおおむね均衡している(第3-1-1図(1))。以下では、貿易収支、サービス収支、第一次所得収支について簡単に概観する。
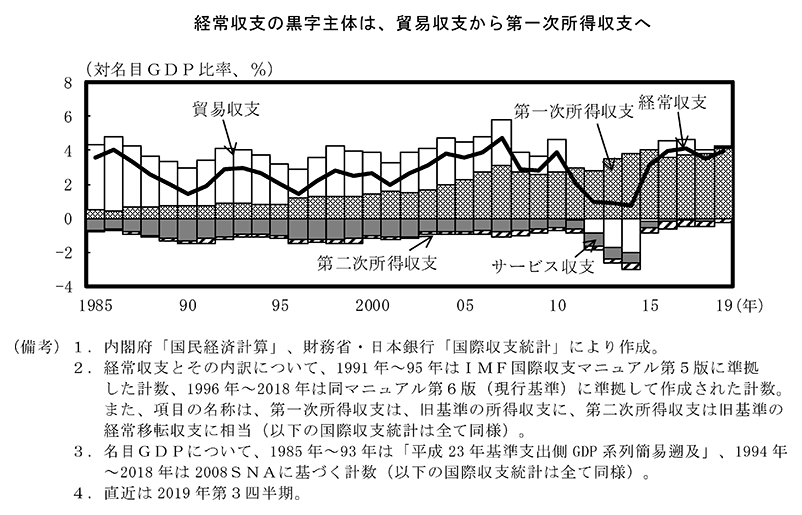
(貿易収支の黒字は、エネルギー輸入の増加と輸出の伸び悩みにより解消)
貿易収支の内訳のうち輸入は、1990年代は対名目GDP比-6%程度で推移してきたが、2000年代半ば以降は原油価格の上昇により同-9%程度までマイナス寄与が拡大した。さらに、原子力発電の停止による原油・天然ガスの輸入増加などにより、2010年以降は同-14%程度までマイナス寄与が拡大している。一方、輸出については、90年代は対名目GDP比+8%程度で推移したのち、2000年代半ばにかけて同+11%程度まで寄与が拡大したが、それ以降は輸出の伸び悩みがあったものの、2010年以降は+14%弱程度で推移している。その結果、2010年以降で均してみると、輸出入の対名目GDP比はおおむね均衡している1(第3-1-2図)。
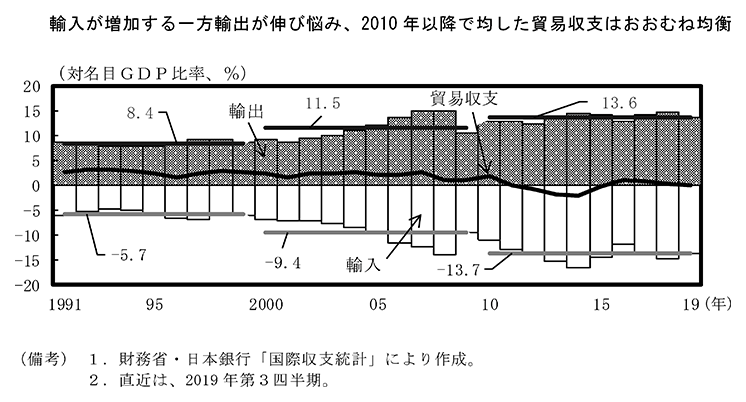
(赤字が継続していたサービス収支は、旅行収支の黒字拡大によりおおむね均衡)
貿易収支に次いで、サービス収支の動向を確認する。長らく赤字が続いていたサービス収支は、訪日外客数の増加により旅行収支の受取が増える中で旅行収支のマイナス寄与が徐々に低下した。2015年以降は黒字に転じ、その後も年々黒字幅を拡大させている(第3-1-3図)。また、我が国企業の海外進出が増加したことより、その他サービス収支のうち知的財産権等使用料2の受取が増加し、黒字化に寄与している(第3-1-4図)。なお、訪日外客数の増加による我が国経済への影響については、(コラム3-1)を参照されたい。
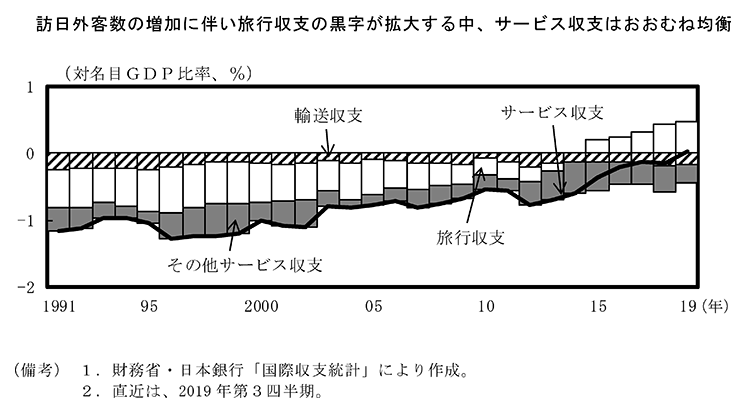
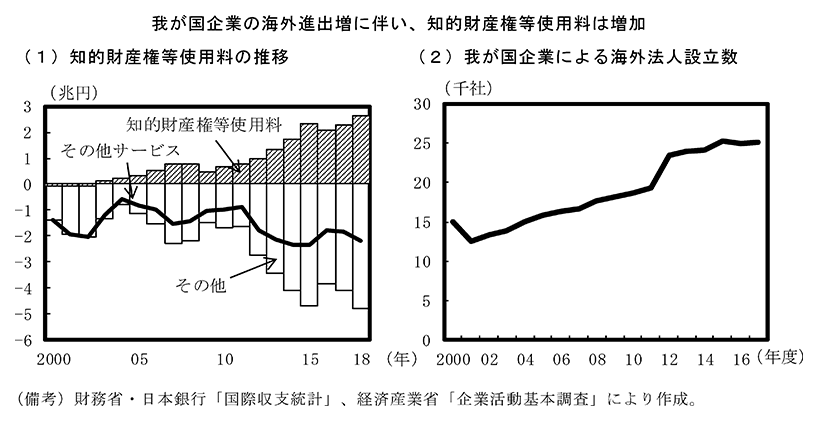
(所得収支の黒字は年々拡大)
最後に、経常収支の黒字をけん引している第一次所得収支の動向を確認する。第一次所得収支の内訳をみると、債券利子・株式配当金を計上する証券投資収支の黒字幅は、2000年以降徐々に拡大している。リーマンショック後、各国中央銀行が金融緩和を進める下で債券利回りが低下していることなどから、証券投資収支の黒字拡大テンポは鈍化しているものの、依然として対名目GDP比でみた第一次所得収支の黒字の半分程度を占めている。また、海外子会社からの配当金等を計上する直接投資収支は、海外子会社の設立やM&Aなど企業の海外進出の進展により、その対名目GDP比への寄与が1991年から19年間で17倍も拡大し、2019年は証券投資収支を若干上回る寄与となった(第3-1-5図)。
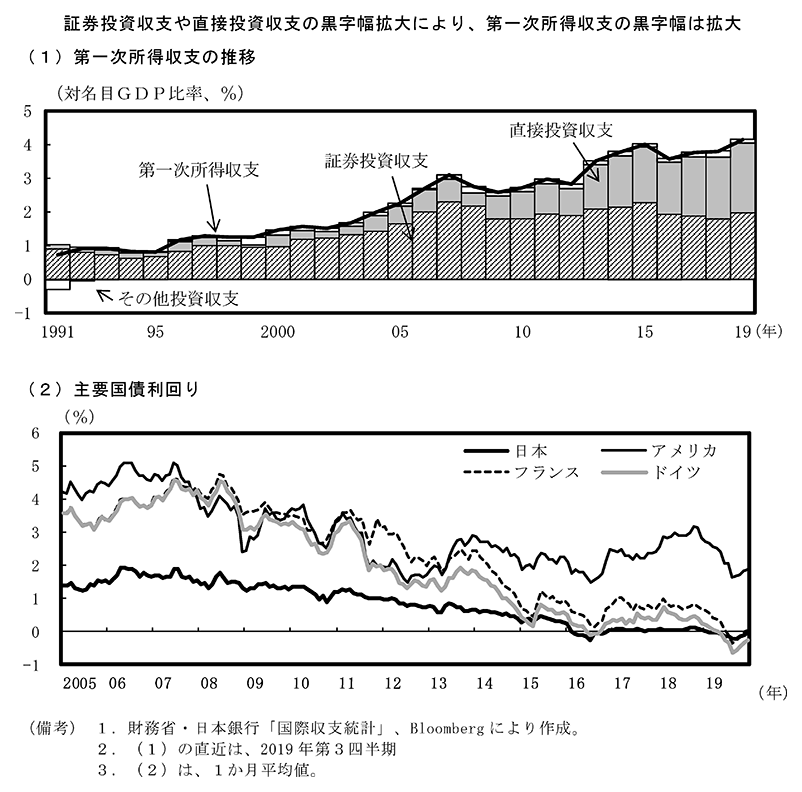
コラム3-1 インバウンド需要増加の効果
我が国への訪日外客数が大きく伸びている。この背景にはいくつかの要因が指摘されているが、大きい例として中国人の個人観光客へのビザ発給要件の緩和がある(2009年:「一定の職業上の地位及び経済力を有する者」という条件付きで初めて発給、2010年:「一定の職業上の地位」から「一定の経済職を有する者」に要件緩和、その後も段階的に緩和を実施)。また、2013年以降は為替レートの下落等もあり、韓国や台湾、香港、タイなどアジア諸国に加え、欧米からの客数も増加した。これに伴い、訪日外客による旅行消費額も増加し、我が国の旅行収支は、2015年に黒字に転じて以降、黒字幅の拡大が続いている。また、訪日外客は、首都圏のみならず地方都市でも増加している(コラム3-1-1図)。
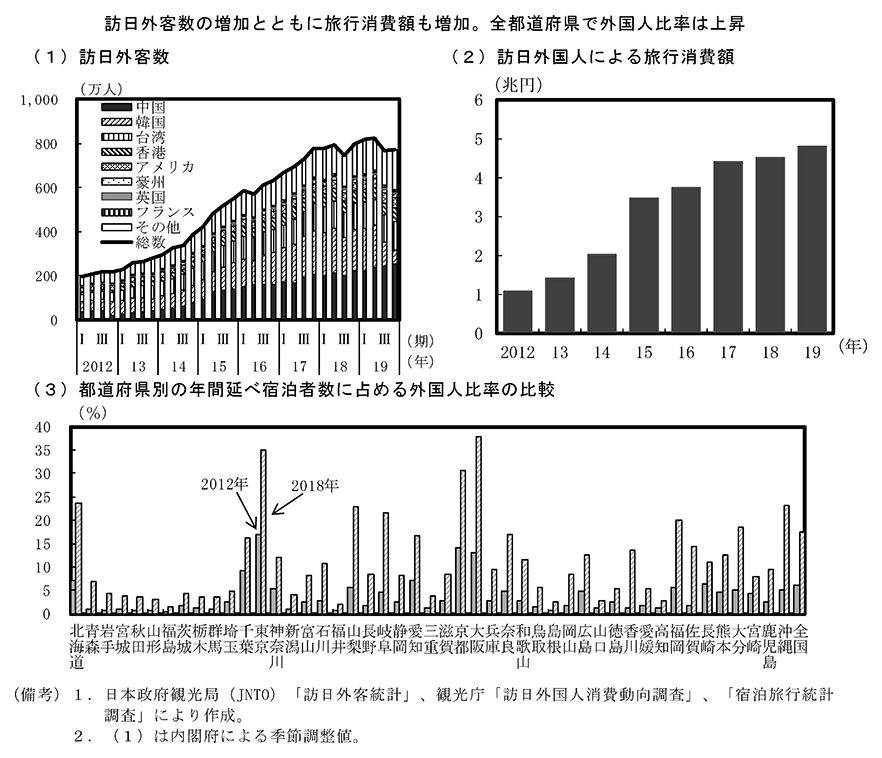
地方都市における訪日外国人旅行者の増加は、プラスの経済効果をもたらしている。都道府県における延べ宿泊者数外国人比率と「宿泊、飲食サービス業の売上高」、「新規求人」、「宿泊業の建設工事費予定額」の間にはプラスの関係があるようにえる。そこで、これら変数を被説明変数、延べ宿泊者数に占める外国人比率、各都道府県の人口、地価等を説明変数とした47都道府県のパネルデータを推計したところ、延べ宿泊者数に占める外国人比率が1%高まると、「宿泊、飲食サービス業の売上高」は0.018%ポイント、「新規求人」0.029%ポイント、「宿泊業の建設工事費予定額」は0.043%ポイント増加するとの結果を得た(コラム3-1-2図)。
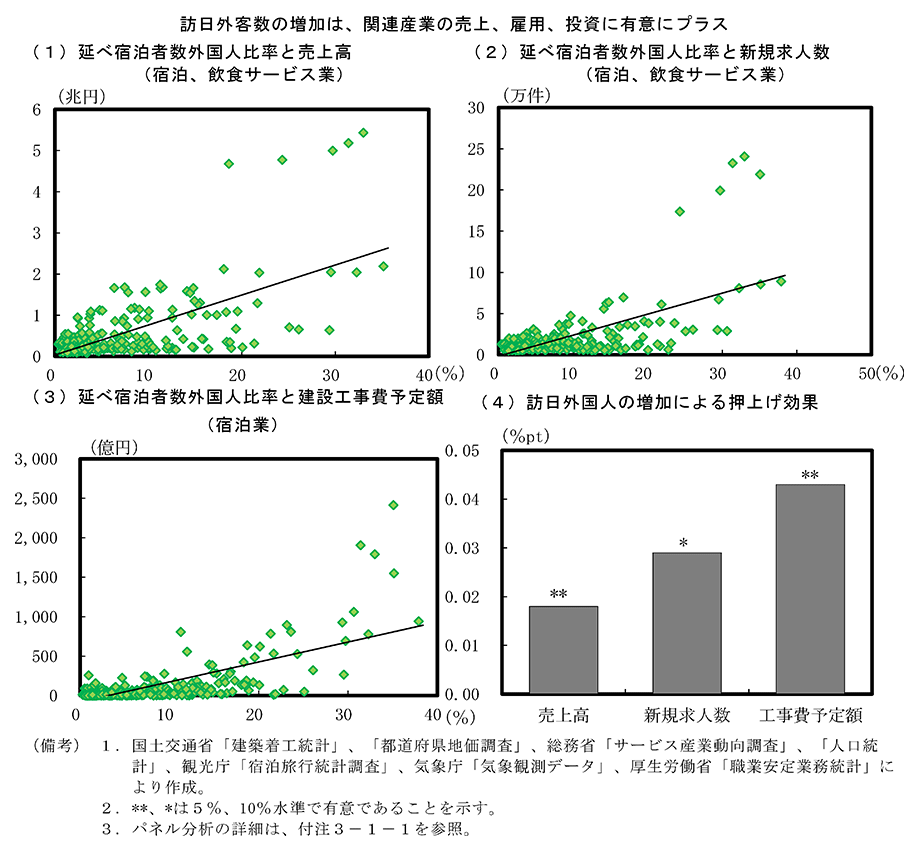
また、訪日外国人による日本での消費体験は、新たな需要を生み出し、インバウンド関連製品の輸出や生産活動にも繋がっている(コラム3-1-3図)。
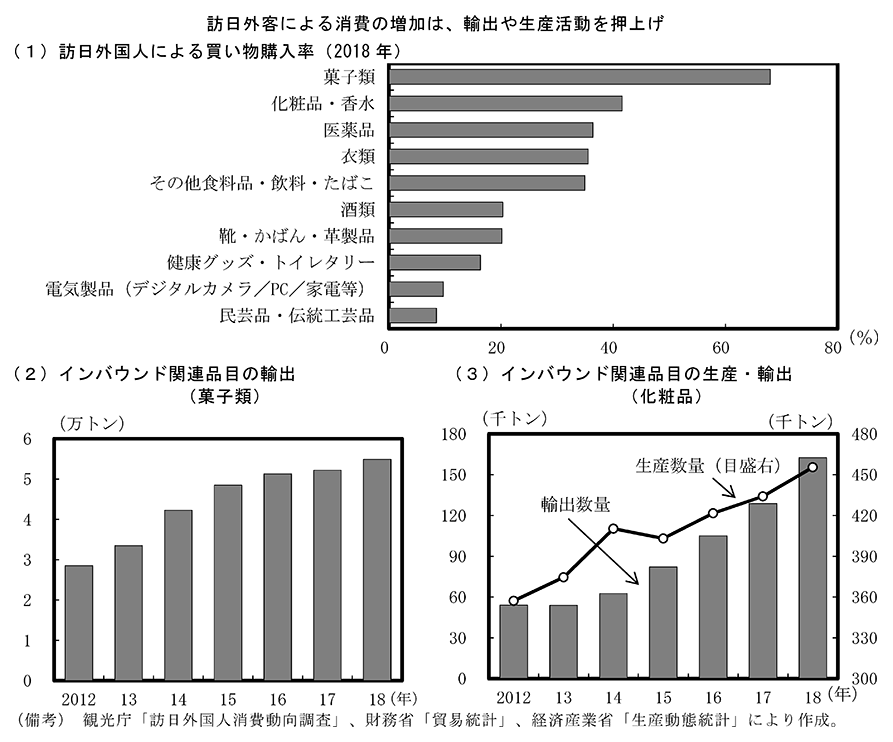
2020年の夏季オリンピック・パラリンピックもあり、更に多くの外国人が来日すると想定されるが、引き続き日本の魅力発信を積極的に行うことで、その後の更なる輸出・生産の拡大に繋げることが期待される。
2 我が国の対外資産負債の動向
1項では、経常収支の黒字主体が貿易収支から第一次所得収支へと変化した点について触れたが、本項では、第一次所得収支の増加の背景となる我が国の対外資産負債の動向について概観する。
(我が国の対外資産は大幅に増加。28年連続で世界最大の純債権国を維持)
我が国の対外資産残高の推移をみると、証券投資及び直接投資を中心に増加しており、2018年時点の対外資産残高の構成は、証券投資が4割強、貸出などのその他投資が2割強、直接投資が2割弱、外貨準備が1割強、金融派生商品が3%程度となっている(第3-1-6図(1))。非居住者が保有する日本の資産(対外負債)を除いた純資産ベースでは、直接投資残高が2012年頃から急増し、2014年に証券投資残高を初めて上回った。その後、2018年には直接投資残高が証券投資残高の1.5倍まで増加している(第3-1-6図(2))。
対外純資産は、2000年対比で約3倍に増加している。そのうち、証券投資残高は約2倍、外貨準備は約3倍とそれぞれ相応に増加しているが、直接投資は約6倍と他の資産を遙かに凌ぐスピードで増加している。とりわけ、東日本大震災以降、対外直接投資はそれまでのトレンドを上回って増加している3。当時のアンケート調査4や報道などから海外進出の背景について確認すると、①サプライチェーンの海外移転によるリスク分散、②当時進んだ円高や電力制約による生産コスト高の回避、の2点が浮かんでくる。2012年から2013年にかけて直接投資残高がとりわけ高い伸びとなった要因は、こうした震災後特有の動きもあると考えられるが、その後も海外需要の取り込みを意図した直接投資の増加は継続しており、後述するような高い収益率にも結びついている(第3-1-6図(3))。こうした結果、我が国は28年連続で世界最大の純債権国となっている(第3-1-6図(4))。
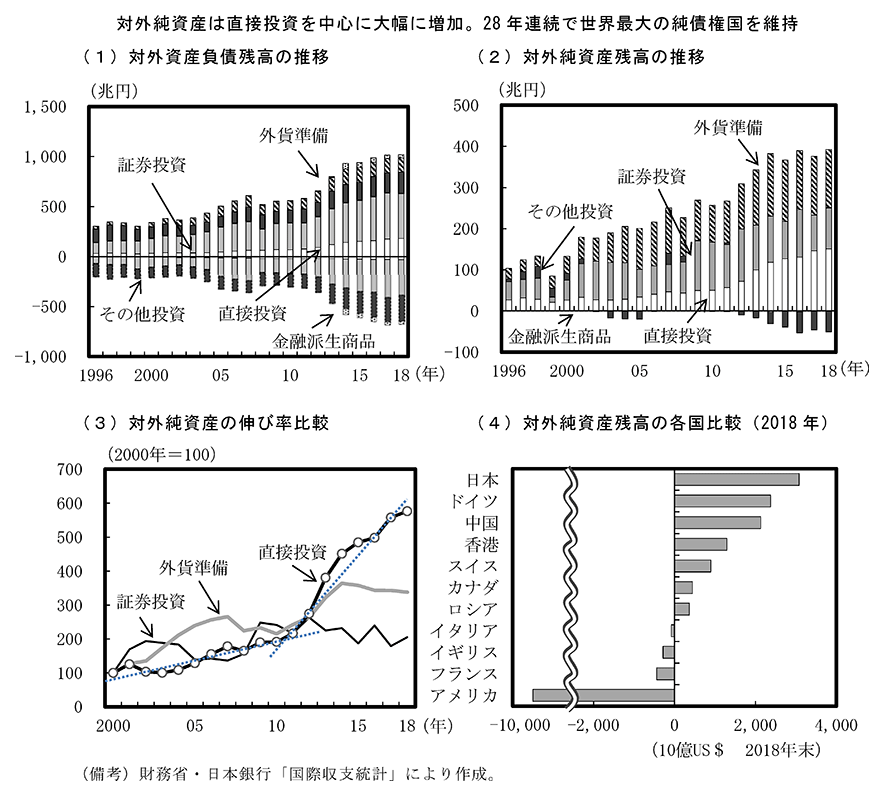
(対外直接、証券投資ともにアジア向けで増加)
我が国の対外投資先国・地域をみると、直接投資はアメリカ、欧州、その他アジア向けの順で残高が多くなっている。一方、2000年からの比較では、中国向けの伸び率が最も高く、次いでその他アジア、欧州が高くなっている。特に中国を含むアジア向けについては、東日本大震災後に急速に伸びを高めており、サプライチェーンの分散を意図した投資が加速したと考えられる。なお、中国向けの投資については2014年頃を境にやや一服感がみられている(第3-1-7図(1))。
証券投資は、アメリカ、欧州、中南米の順で残高が多くなっている。一方、2000年からの比較では、中国、その他アジアや中南米等の発展途上国向けが大幅に増加している。世界の中央銀行が金融緩和を推し進め、先進国を中心に金利が大幅に低下する中、中南米向け5を除き金額としては僅かであるが、リスク資産への投資を進めている姿がうかがえる(第3-1-7(2))。
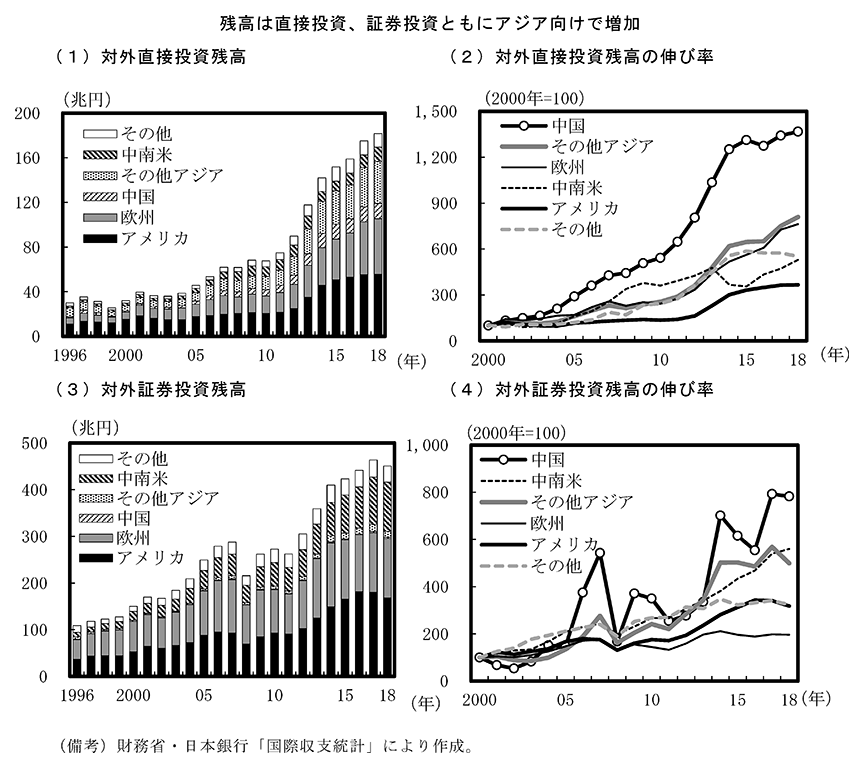
対外投資残高を保有主体別でみると、直接投資は非金融法人の残高が、証券投資は金融機関や一般政府(公的年金等)の残高が大幅に増加している(第3-1-8図)。
非金融法人の直接投資残高を業種別でみると、製造業では、輸送機械や電気機械、一般機械といった機械関連業種に加え、化学・医薬品も増加している。非製造業では、商社を含む卸売・小売や通信、サービス業、最近では不動産業も増加している(第3-1-9図)。
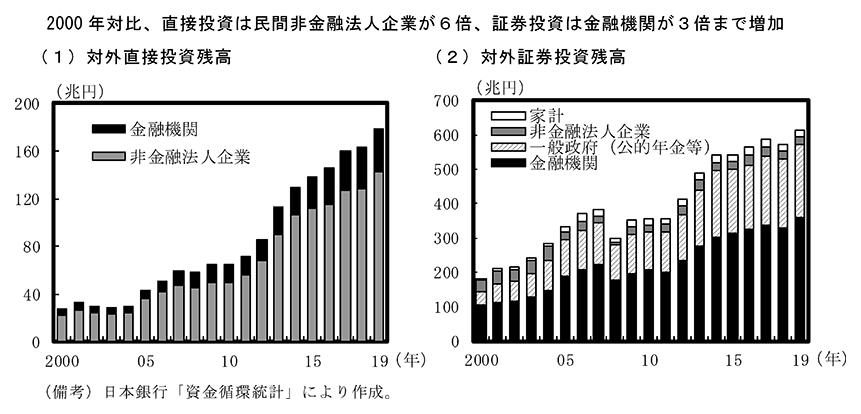
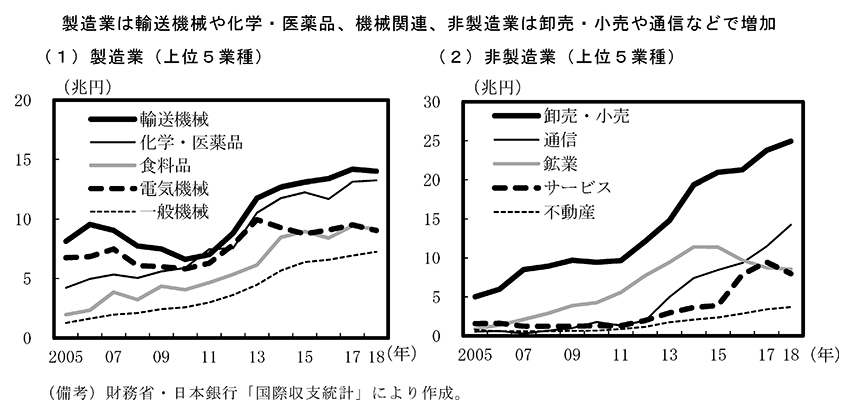
金融機関及び公的年金の対外証券投資残高をみると、証券投資信託や年金保険は残高を大きく増やしているが、国内銀行の残高増加は限定的である(第3-1-10図)。背景には、金融規制などを背景にリスク量の小さい国内債を選好するホームバイアスがあると考えられるが、この点については第3節1項を参照されたい。
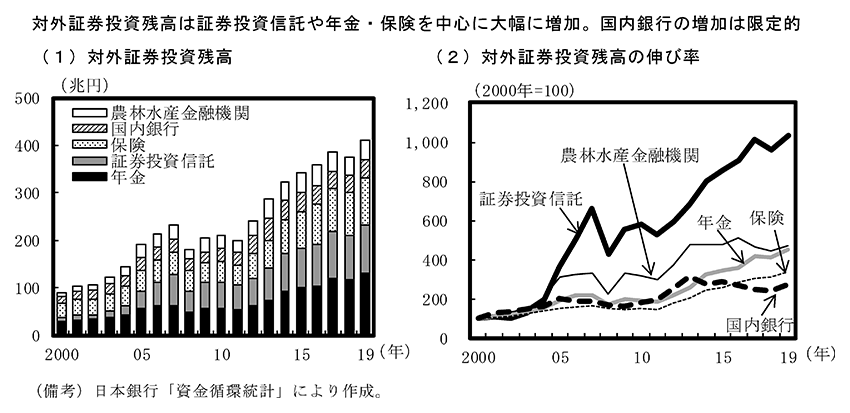
(対外資産の収益率は高い)
最後に、急速に増えている対外投資の収益率について確認する。まず、対外資産の投資利回りを直接投資、証券投資別でみると、直接投資の利回りは振れを伴いながらも増加している一方、証券投資の利回りは徐々に低下している。先に述べたように、利回りの高い直接投資残高の増加により、証券投資の利回り低下はカバーされ、対外資産全体の利回りはおおむね3%半ば程度で安定的に推移している。この結果、対名目GDP比でみた対外資産の収益受取額は6%程度と、日本一国としてみれば非常に高く、対外純資産の収益率も6%程度となっている(第3-1-11図)。
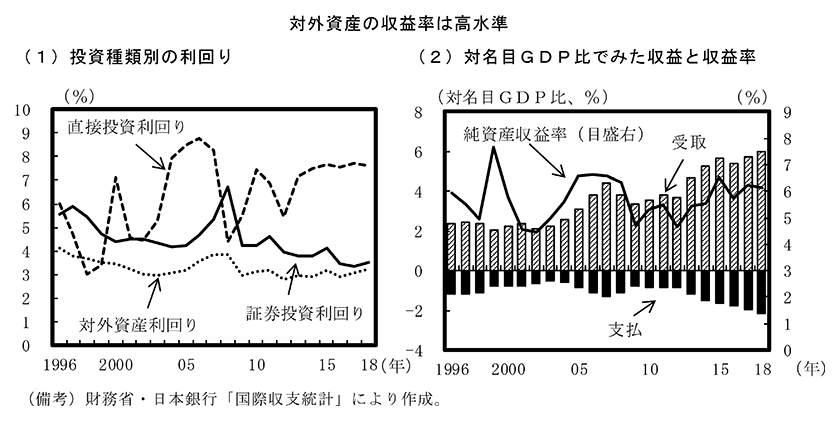
3 貿易収支の恒常的な黒字解消の背景と交易利得
第1節の締めくくりとして、本項では、かつては経常収支黒字の主体であった貿易収支の恒常的な黒字解消の背景と交易利得について考察を加えることにより、国内総生産(GDP)に海外からの所得と交易利得を加えた国民総所得(GNI)の成長に必要な課題について整理する。
(輸出は世界貿易の鈍化により伸び悩むも、輸出シェアの低下は相対的に小さい)
貿易収支の恒常的な黒字が解消された要因として、輸出の伸び悩みが挙げられる。その背景は、大別すると①輸出シェアの低下(日本製品の競争力低下や生産拠点の海外移転)、②世界貿易量の縮小、③物価変動の3点が考えられる。このうち、物価変動を除いた実質ベースの変動要因である①、②について確認するために、オランダ経済政策分析局が公表している世界貿易量を基に、日本の輸出数量を①我が国の輸出シェア要因と②世界貿易量要因に分解することを試みた(第3-1-12図(1))。
リーマンショック前は、世界貿易量の増加に加え、輸出シェアも拡大し、我が国の輸出数量は前年比+10%程度の伸びがみられていた。しかし、リーマンショックを境に、世界貿易量の伸びが大幅に鈍化6したことに加え、2011年から2014年にかけては中国を始めとするアジア諸国が世界の工場として台頭する中、輸出シェアの低下もみられた。また、海外進出企業による中間財の現地調達比率の高まりも輸出シェアの低下に繋がったと考えられる(第3-1-12図(2))。
ここで、2000年から2019年にかけての世界貿易量に対するシェアの変化を確認すると、先進国が1割程度低下した一方、アジアを始めとする新興国は同程度拡大している。ただし、先進国のシェアは、欧州が-6%程度、アメリカが-1%低下する中で、日本は-0.5%の低下にとどまっており、先進国における相対的なシェア低下は小さかったことが確認できる(第3-1-12図(3))。
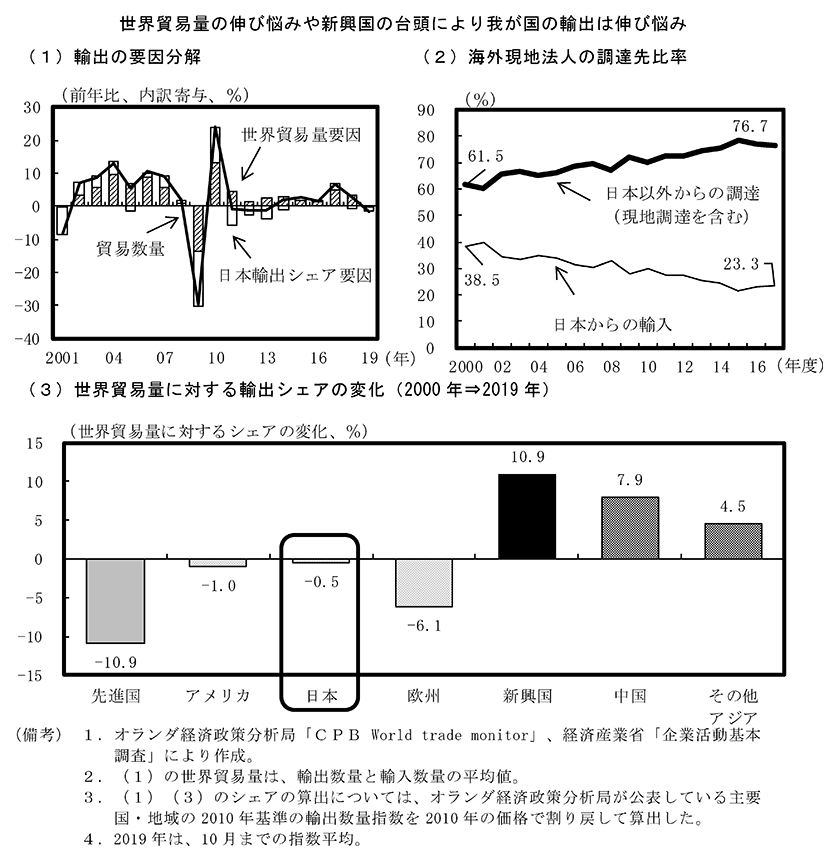
(リーマンショック以降、輸出入金額に対する価格の寄与が上昇)
我が国輸出の伸び悩みの背景について、数量ベース(実質ベース)で確認したが、金額ベース(名目ベース)でみるとどうだろうか。この点を確認するために、財務省が公表している通関ベースの輸出入金額の推移を、1999年以降の累積差で数量要因、価格要因に分解した(第3-1-13図)。
これをみると、前述で確認したとおり、リーマンショック前は、輸出数量の増加が輸出金額全体の増加をけん引してきたことが分かる。しかし、リーマンショックを境に、輸出数量が伸び悩む中、輸出金額の変動は輸出価格の変動により規定される傾向が強まっている。また、輸入についても、2000年代半ば以降、数量は90年からの累積差で、10兆円程度で安定的に推移している一方、輸入価格の変動が輸入金額全体を大きく左右していることが分かる。
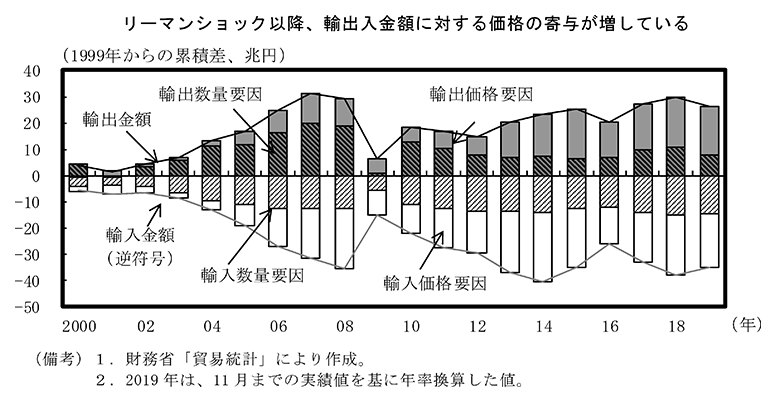
このように、輸出入金額に与える価格の影響が近年大きくなっていることが確認されたが、輸出入価格を規定するのは何であろうか。まず考えられるのが、為替レートの変動である。すなわち、輸出入の税関申告においては、外貨建てで表示された輸出入額を税関が公示した為替換算レートで円建てに換算することが義務付けられているため、円安(円高)になれば、円建ての輸出入価格は上昇(下落)する。次に考えられるのが、為替レートの変動や需給を加味した事業者による価格調整である。加えて、製品の付加価値向上による価格上昇も輸出入価格に影響する。
まず初めに、輸出入価格に与える為替及び価格調整の影響について確認する。第3-1-13図で用いた輸出入価格指数(財務省)は、製品の単位価格の変動を示すものであるため、財の品質向上による価格上昇が調整されていない。品質向上による価格上昇の影響を排除するため、品質調整を行っている輸出入物価指数(日本銀行)を用いて、同指数を為替要因と価格調整要因に分解した(第3-1-14図、第3-1-16図)。
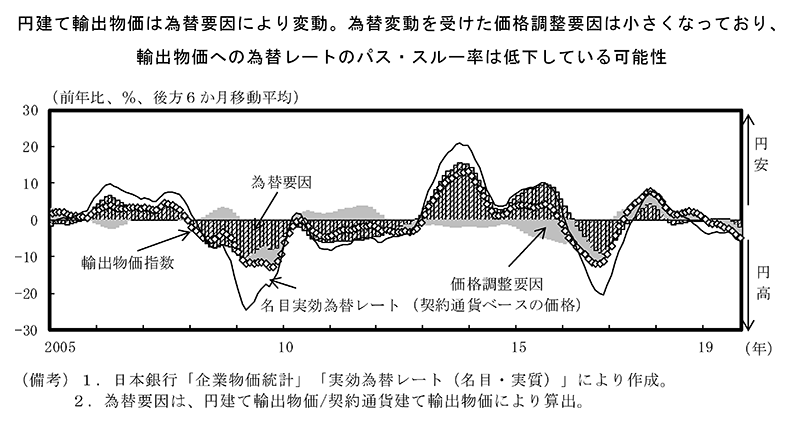
改めて輸出物価と為替レート変動の関係を整理すると、円安局面では、円建ての輸出物価は上昇するが、その分、契約通貨建ての輸出価格を下げることで輸出財の競争力を高めることが考えられる。その観点から、円建て輸出物価の要因分解をみると、基本的には、為替要因がプラスの場合は、価格調整要因がマイナスとなっているが、例えば、リーマンショック時の2009年や中国輸入の減速がみられた2015年半ばから2016年にかけては、需要低迷により、円高にもかかわらず契約通貨建て輸出物価を切り下げていたことが分かる。輸出が弱含んでいる2018年後半から足下にかけても、同様の動きが確認できる。一方で、IT財や資本財など広く需要回復がみられた2017年から2018年半ばにかけては、円安局面でも契約通貨建て物価を引き上げている。また期間を通して、輸出物価に与える影響は為替要因による価格調整要因が小さくなっており、為替レートのパス・スルー率7が低下している可能性が示唆される8(第3-1-14図)。
では、なぜ企業は為替レートの変動を契約通貨建ての輸出価格であまり調整しなくなったのだろうか。その答えの一つとして、輸出財の高付加価値化が挙げられる。先述したように、輸出価格指数は財の付加価値上昇分を含む一方、輸出物価指数は、財の付加価値の上昇分を調整しているため9、両者を比較することで財の付加価値の変動を把握することができる。輸出価格指数を輸出物価指数で除した高付加価値化指数をみると、2000年以降趨勢的に上昇しており、日本の輸出財は高付加価値化により輸出価格を維持していることがうかがえる(第3-1-15図)。
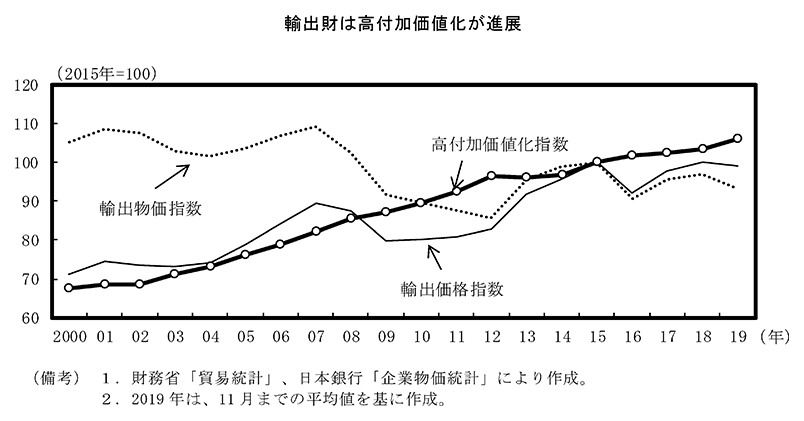
続いて、円建て輸入物価の動向についても確認してみよう。円建て輸出物価と同様に、その変動を為替要因と価格調整要因に分けてみると、価格調整要因の変動が大きく寄与していることが分かる。これは、価格調整要因が比較的小さかった輸出物価とは対照的な動きである(第3-1-16図)。もっとも、輸入の価格調整要因は原油価格の動向によるところが大きい(第3-1-17図)。
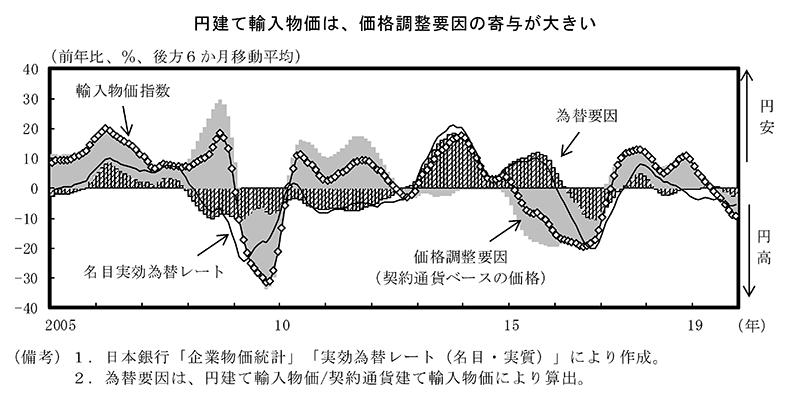
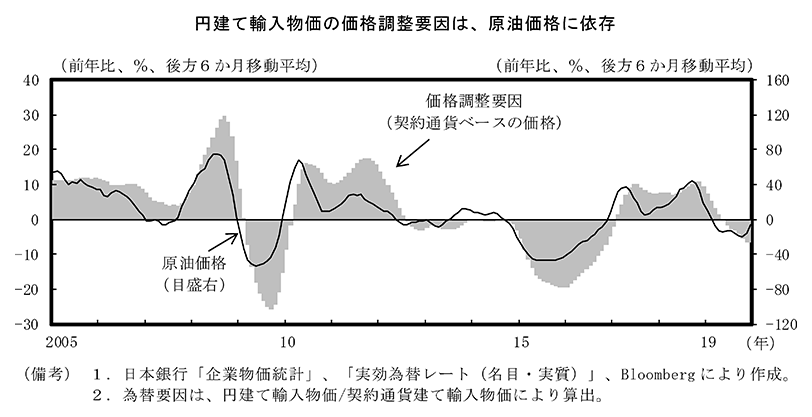
(交易利条件は原油輸入価格の抑制、輸出財の価格上昇が重要)
最後に、交易条件を確認する(第3-1-18図)。輸出物価を輸入物価で除して得られるのが交易条件である。また、交易利得は、ある基準年から交易条件が変化することによって生じる国内居住者の実質購買力の海外流出入を示す。なお、為替要因は輸出物価と輸入物価でおおむねキャンセルアウトされるため、交易条件に与える影響は限定的である。このため、交易条件は価格調整要因に左右されることになるが、前述のとおり輸出の価格調整要因に比べて輸入の価格調整要因、すなわち原油価格の変動による影響が大きく、輸入の多くを原油・天然ガスなどのエネルギーが占める我が国にとって、原油価格の安定は重要である。また、財の品質向上による価格変化を含む輸出入価格ベースでみた交易条件は、輸出入物価ベースの交易条件よりも輸出財の高付加価値化分だけ高くなっている。
貿易収支の常態的な黒字が解消する中で、国内総生産(GDP)に海外からの所得及び交易利得を加えた国民総所得(GNI)を拡大させるためには、海外からの所得を拡大させることはもとより、生産・輸出する財の高付加価値化や値上げによる輸出価格の上昇や、エネルギーの対外依存抑制による交易利得の改善も重要である(第3-1-19図)。海外からの所得拡大やエネルギーの対外依存抑制については、第3節で改めて議論する。