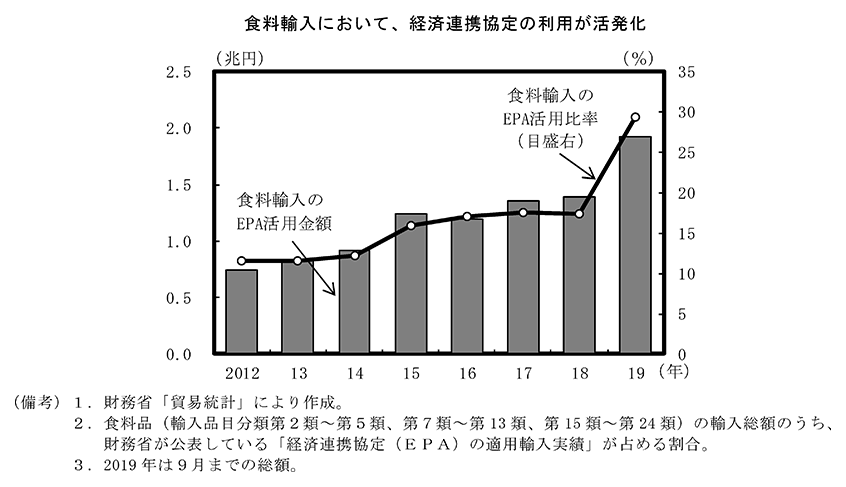第3章 人口減少時代における対外経済構造の変化と課題(第3節)
第3節 人口減少時代における対外経済構造変化と対外依存リスクの低減
本節では、人口減少時代の対外経済構造を踏まえた課題と対応のうち、輸入依存度が高いエネルギーや食料について、対外依存をコスト面も含めて抑制するためには何が必要かについて検討する。
1 対外エネルギー依存のリスク低減に向けた課題
(対外エネルギー依存度は9割弱で、地域的には中東依存度が9割弱)
輸出入バランスをみると、資源を持たない我が国にとって必須輸入品である食料品や原料品、鉱物性燃料の輸入超過を、機械類を中心とした製造業部門の輸出超過により賄う構造が定着している(第3-3-1図)。特に鉱物性燃料の輸入金額は大きく、原油価格等の市況に輸入物価が大きく左右されるため、交易利得の悪化にも繋がりやすい(第1節3項参照)。
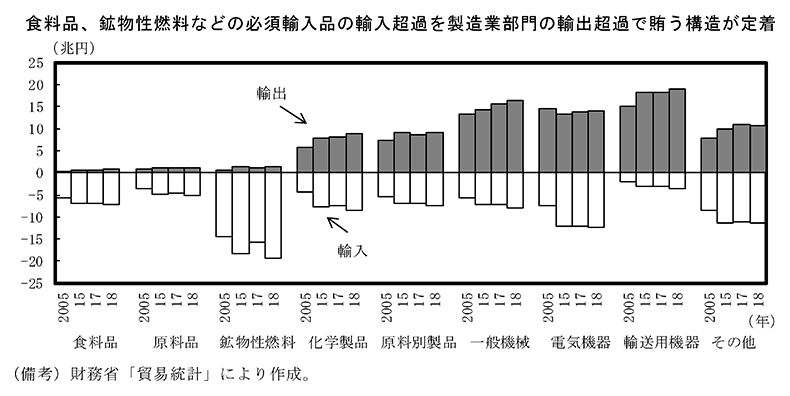
こうした下で、我が国の対外エネルギー依存度は、長らく80%前後で推移してきたが、東日本大震災後の原子力発電の停止により、火力発電などの石化電源比率が高まったことで、2014年度には対外エネルギー依存度は94%にまで達した。その後、原子力発電所の一部再稼働や再生可能エネルギーの緩やかな増加により、2018年度には88%まで低下したが、それでも対外エネルギー依存度は極めて高い。IEAの2017年推計によると、我が国の対外エネルギー依存度はOECD加盟国35か国中ルクセンブルグの次に高く、世界的にみてもエネルギー供給に脆弱性を抱えている。さらに、石化電源の大部分を占める原油は、9割弱を中東からの輸入に頼っているほか、原油輸入全体の約8割が輸送時にホルムズ海峡を通過するなど、中東の地政学リスクも常に抱えている。また、エネルギー源の多くを温室効果ガス排出量の多い石化電源に依存している状況は、持続可能な開発目標(SDGs)を実現する観点からも望ましくない(第3-3-2図、第3-3-3図)。
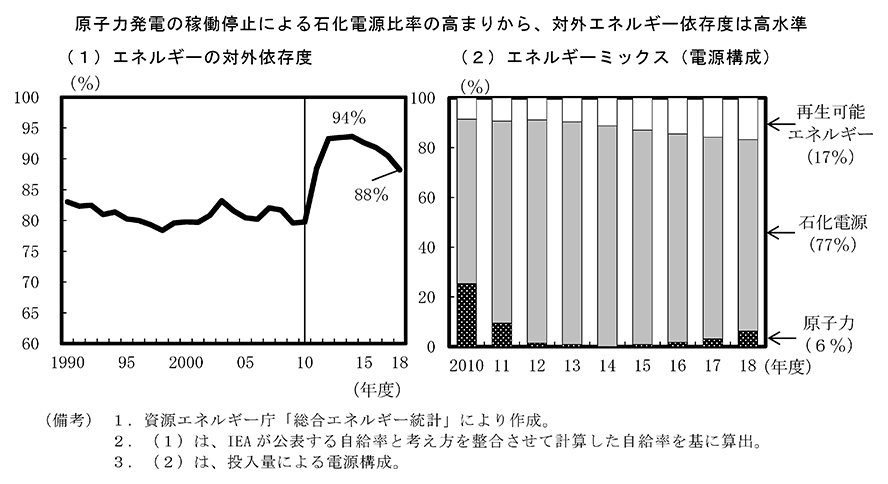
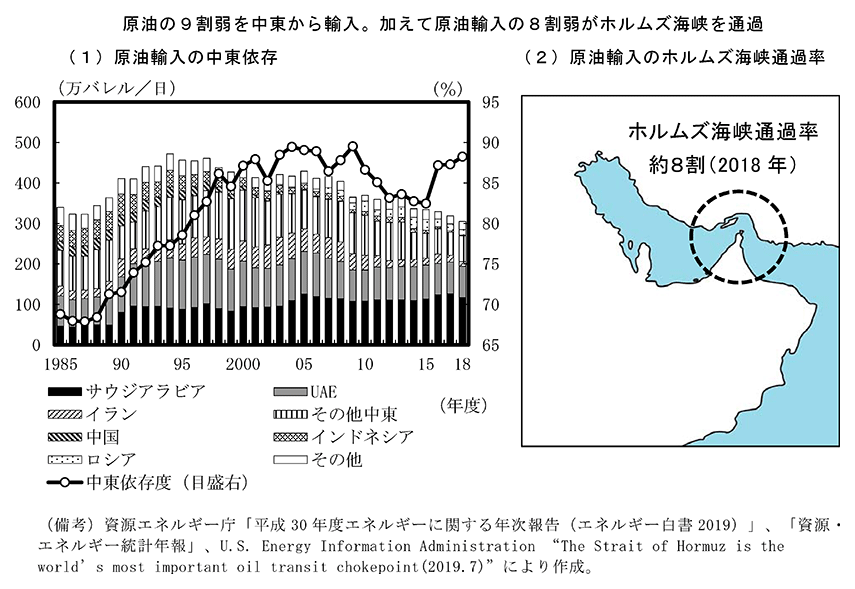
(企業・家計のエネルギーコスト負担は高く、負担低減に向けた対策が必要)
エネルギーの供給安定化には、対外依存度を低減させることが効果的であるが、そうした場合、エネルギーコスト負担がどうなるかを確認してみよう。
まず、各種電源別の発電コストを比較すると、発電コストは原子力が最も低く、次いで石炭火力、LNG火力が低くなっている。一方で、石油火力や再生可能エネルギーの発電コストは高い(第3-3-4図)。
電力・ガス各社は経済性を考慮し、石化電源の中では低コストの天然ガス(LNG等)や石炭を多く利用しているが、輸送コストがかかることなどから国際的にみればLNGの平均輸入価格は欧米対比で高い。この結果、電力・ガス料金など企業・家計のエネルギーコスト負担も欧米対比で高く、とりわけ、家計の負担が高い(第3-3-5図)。
現状で利用可能な技術を前提としてエネルギーの対外依存度を低減するためには、原子力発電ないし再生可能エネルギーへと電源をシフトしていく必要がある。ただし、原子力発電については、安全性確保の必要性などから、すぐに震災前のレベルにまで稼働率を高めることは困難と考えられるため、再生可能エネルギーへのシフトを推進することが現実的であるようにも思われる。もっとも、その場合、再生可能エネルギーは石化電源よりも発電コストが高いため、現状でさえ欧米対比で高いエネルギーコスト負担を、更に企業・家計に強いることとなる。このため、エネルギーの対外依存度低減を実現するには、電源構成の変更だけでなく企業・家計といった需要側のコスト負担に配慮した対応も求められる。
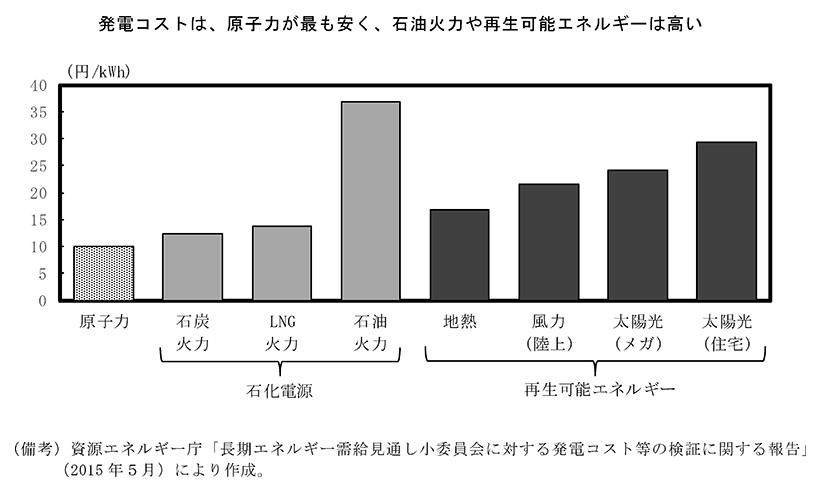
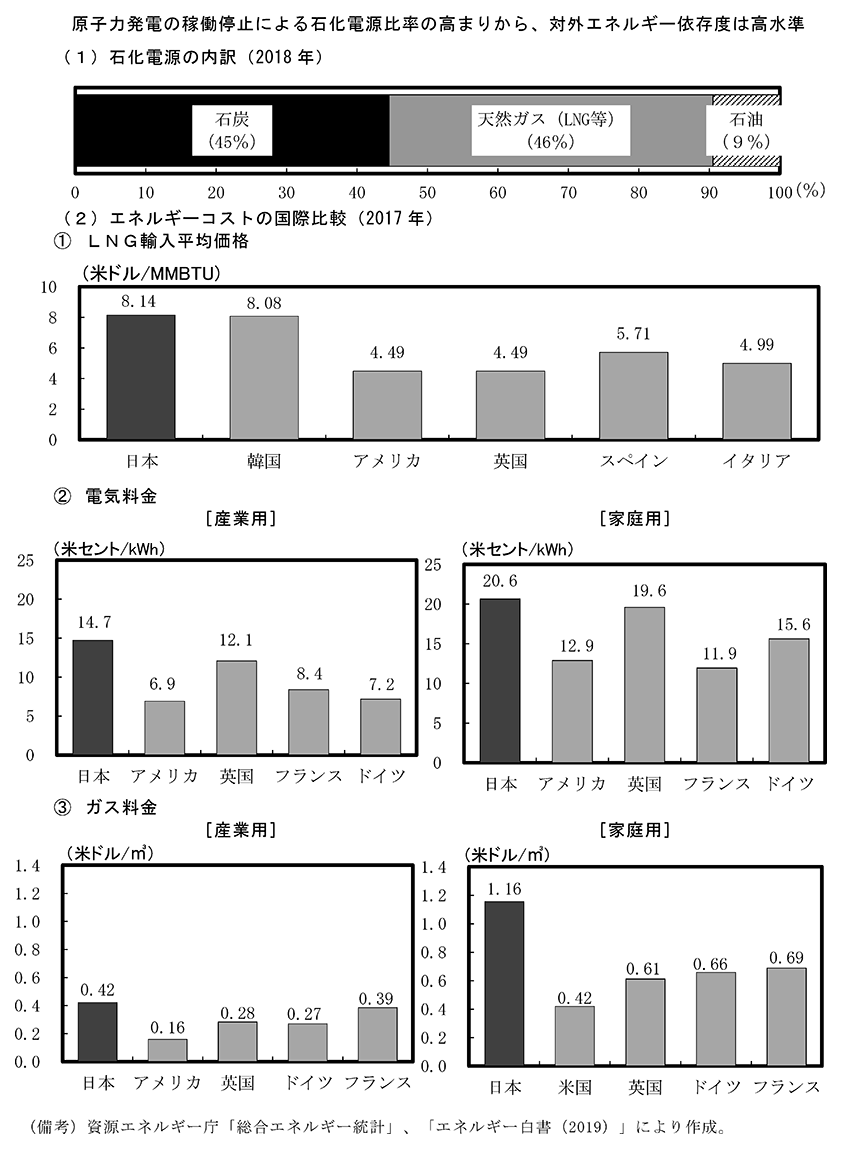
(エネルギーの権益の拡大・分散と、コストの低下の両方が必要)
2018年に政府が策定した「第5次エネルギー基本計画」によると、安全優先(Safety;技術・ガバナンス改革による安全の革新)、資源自給率(Energy security;技術自給率向上/選択肢の多様化確保)、環境適合(Environment;脱炭素化への挑戦)、国民負担軽減(Economic efficiency;自国産業競争力の強化)の「3E+S」原則の下で、長期的に安定した持続的・自立的なエネルギー供給を目指している。具体的には、2030年及び2050年に向けた中・長期のロードマップを描き、2050年には再生可能エネルギーを低コスト化し、主力電源に見据えるほか、原子力も脱炭素化の選択肢として残す。石化燃料は、自主開発を促進し、資源外交を強化するとともに、低炭素のガス利用へのシフトや非効率石炭フェードアウトを目指すとしている(第3-3-6図)。こうした政府のエネルギー政策は、エネルギーの対外依存度とコスト低下(権益拡大・分散、再生エネルギーのコスト低下、原子力発電の安全稼働)を目指すものであり、方向性としては望ましい。
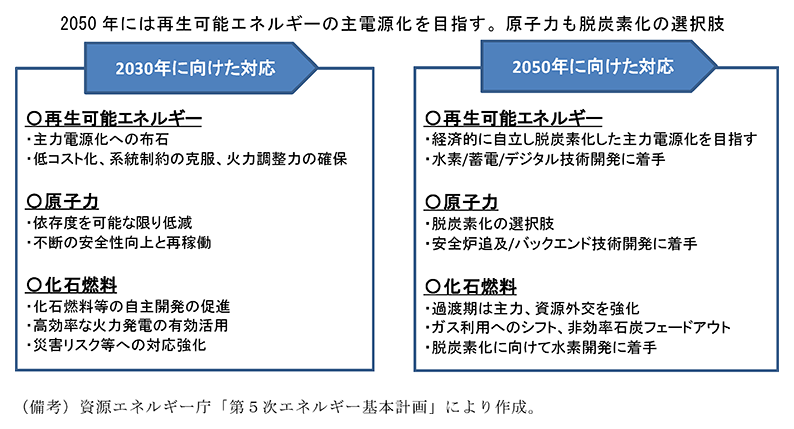
では、これらの目標に向けた現状を確認しよう。まず、石化燃料の権益拡大の状況について、我が国の石油・天然ガスの自主開発比率の推移をみると、緩やかに上昇し、2009年度からの8年間で6%増加している(第3-3-7図)。商社や電力・ガス各社、石油天然ガス・金属鉱物資源機構(JOGMEC)など官民一体となって、アメリカ、カナダ、オーストラリアなどでの権益拡大を積極的に進めており、目標としている「2030年に自主開発比率40%以上」の実現に向けて一層の取組が期待される。
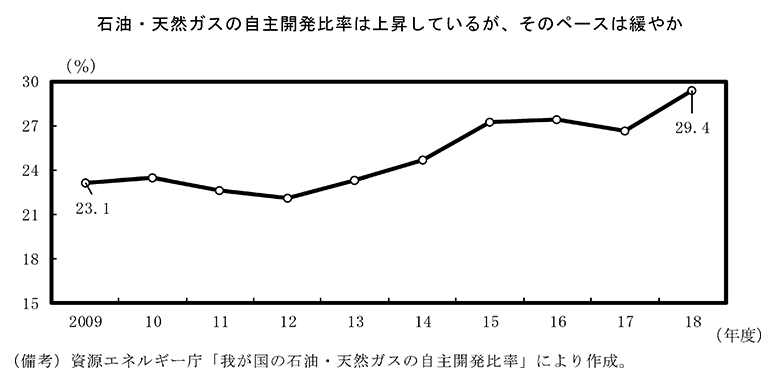
次に、再生可能エネルギーについて確認する。固定価格買取制度1が2012年に導入されて以降、再生可能エネルギーは、太陽光発電を中心に設備設置容量は急速に増加している。また、太陽光発電電力の買取価格は毎年低下しているものの、エネルギーミックスに占める再生可能エネルギーの比率が高まる下で、企業・家計の電力コスト負担は増加している。再生可能エネルギー発電促進賦課金を通じた負担は世帯当たり月額767円2(年間9,204円)(2019年度)となっており、日本全体(5,340万世帯:15年国勢調査時点)では実に4,900億円/年もの負担増になっている。再生可能エネルギーの負担は、仕組み上、今後とも増加が続く見通しにある。また、太陽光発電システムの設置費用(工事費+モジュール価格)は欧州の約2倍と高く、非効率なエネルギー源となっている。設置コストの低減や電力買取価格の引下げに今後も取り組む必要がある(第3-3-8図)。
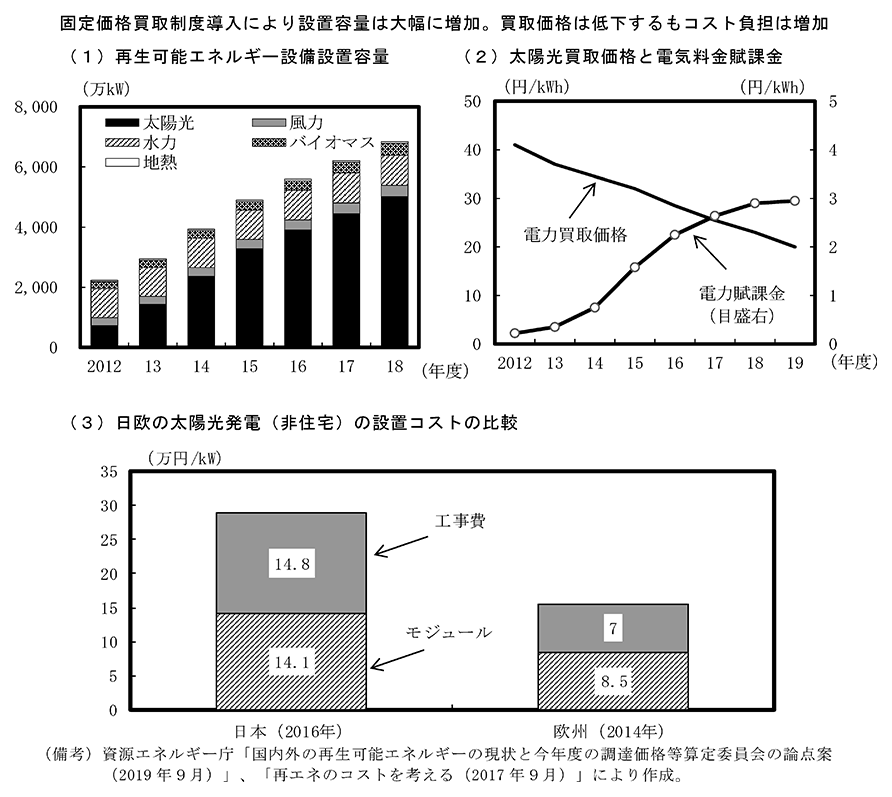
最後に、原子力発電についてみると、2030年のエネルギーミックスの政府目標(電源構成)は原子力が20~22%となっている。この政府目標に対し、現状では、国内原発33基中8基しか稼働できておらず3、エネルギーミックスに占める原子力の割合は6%程度にとどまっている(第3-3-2図(2))。政府目標を達成するには30基程度稼働させる必要があり、目標達成に向けて、適切な安全評価はもちろんのこと、国民の理解を得るために、より丁寧な説明を根気強く行う必要がある。
また、原子力発電の再稼働や再生可能エネルギーの活用は、気候変動問題の原因の一つと考えられている温室効果ガスの削減にもつながる。世界的に持続可能な開発目標(SDGs)の実現が課題となる中、我が国にとっても温室効果ガス排出量の削減は重要な課題の一つである。我が国の温室効果ガス排出量をみると、原子力発電の稼働停止により2013年にかけて増加したが、その後は原子力発電の再稼働や再生可能エネルギーの増加、省エネへの取組とともに減少し、2018年には経済活動が著しく停滞した2009年の水準を僅かに下回っている。世界では、地球温暖化対策や再生エネルギーなど、環境分野への取組に特化した資金調達を目的に発行するグリーンボンドの市場規模が拡大しており、企業経営の観点からも注目されるなか、温室効果ガス排出量削減に向けて、より経済的な再生可能エネルギーの活用と安全な原発再稼働が期待される(第3-3-9図)。
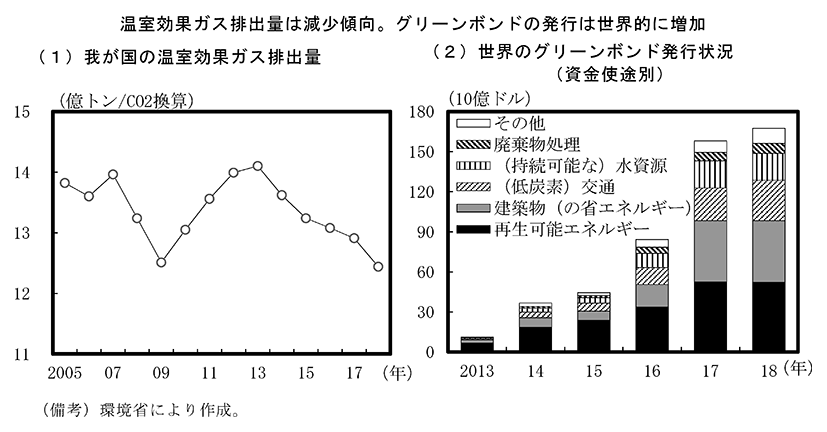
2 対外食料依存のリスク低減に向けた課題
(現状の食料自給率は4割弱であり、低下には高齢化の影響もある)
最後に、エネルギーに次ぐ必須輸入品目である食料の対外依存低減に向けた課題について検討する。我が国の食料自給率4は、1960年代から90年代半ばにかけて低下し、その後はおおむね横ばいとなり、近年では4割弱、すなわち6割強を海外からの食料供給に依存する状態となっている。食料自給率は、主要先進国の中でも最低水準となっている。また、品目別では、大豆や小麦の9割程度、果実の6割程度、肉類の5割程度を海外に依存しているが、食生活の変化に伴い自給率の高い米や野菜の消費量が減少傾向にある一方、乳製品や肉類の消費量が増加傾向にある(第3-3-10図)。
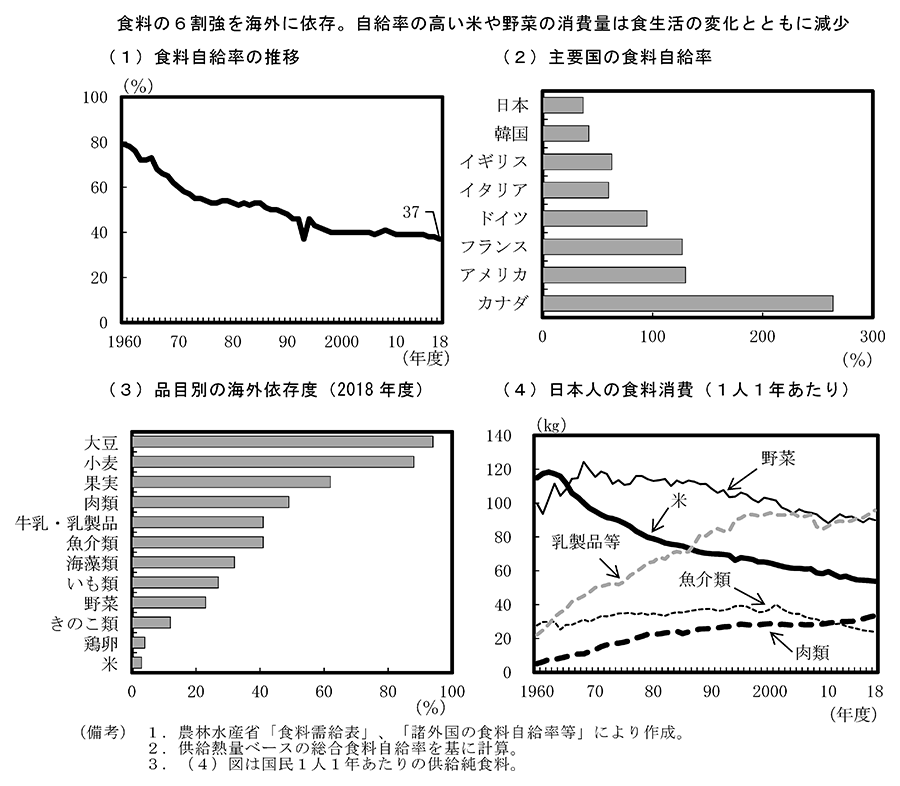
こうした食料自給率の将来を考えるにあたり、人口動態は無視できない。人口減少は食料需要自体を減少させると考えられるが、同時に、農業就業人口も減少すれば、自給率は更に低下する。
実績を振り返ると、需要要因となる総人口は、2005年から2015年の10年間で1%弱と緩やかに減少してきた(前項 第3-2-1図)。他方、供給の前提となる農業の就業人口は4割弱も減少している。また、就業人口の年齢構成別に確認すると、特に40~50歳台層が大幅に減少し、2015年時点でも60歳以上の比率が6割弱にまで高まっている(第3-3-11図(1))。農業就業人口の減少が一人当たり農地の増加になれば、生産性の上昇という形を通じて供給能力に悪影響を及ぼさないとも考えられるが、農業就業人口の平均年齢が66歳という現状に鑑みれば、耕作放棄地が増える可能性等も否めない(第3-3-11図(2))。このため、特段の対策を取らない限りは、人口減少以上に農業の担い手不足が進むと考えられる。
実際、2000年の自給率について、分子である国内生産を生産年齢人口の変化、分母である消費を総人口で変化させて実績値と比べると、両者はおおむね実績値と一致しており、食料自給率の下落は概ね人口要因と符合している。ただし、実績値は推計値よりも僅かながら高く、生産性の向上といったその他の影響もある(第3-3-12図)。今後も、食料自給率は人口要因に影響されると見込まれるが、農業の生産性を高めることで自給率を押し上げることは可能である。
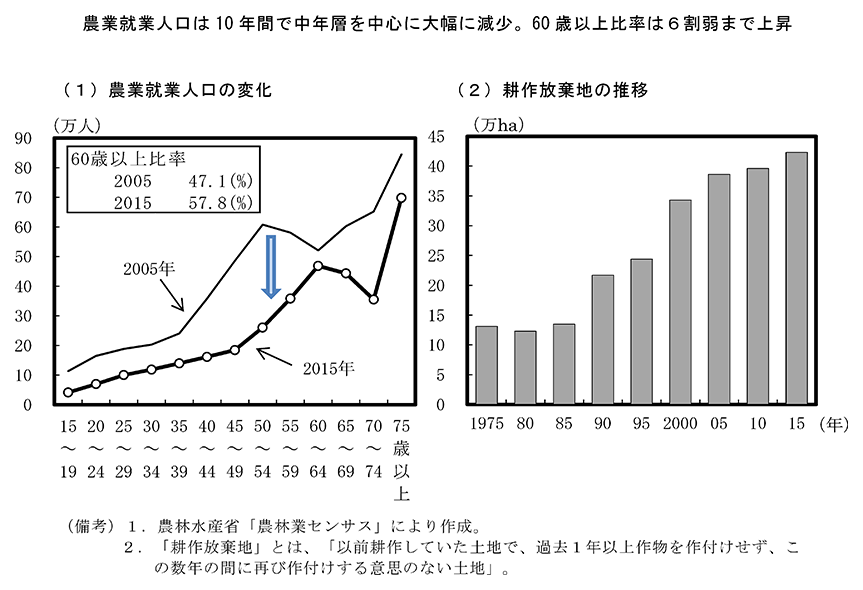
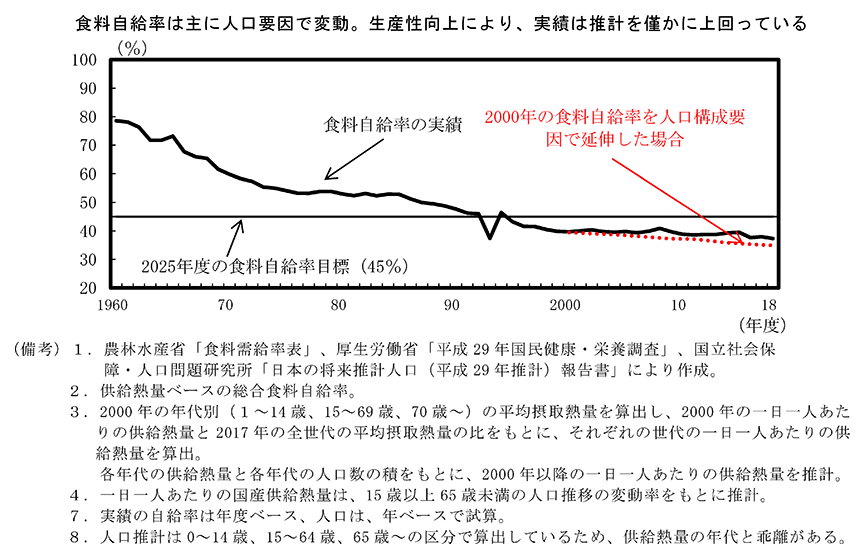
(他方、食料輸入先の分散は進み、輸出が増加して国内生産は下げ止まり)
食料自給率が低い場合であっても、輸入先を多様化、分散することで、輸入先の地政学リスクや天候等による供給制約のリスクを低減することはできる。その際、対外直接投資を通じて海外における生産過程から関与することで、より供給の安定化を図ることも可能だろう。また、輸入を減少させずとも、輸出を拡大することが出来れば国内生産は増加し、一定の農業基盤を維持することは可能となる。すなわち、「輸出」の強化は食料自給率の上昇要因であり、我が国の食料生産能力を強化することにもつながる。
まず、輸入先の多様化・分散について、我が国の食料品輸入の推移を主要地域別にみると、アジアや北米からの輸入が過半を占めるが、1990年からの約30年間で中南米や欧州、大洋州など他の地域からの輸入も着実に増やしている(第3-3-13図)。
その結果、食料の輸入先数は約30年間で欧州、アジア、太平洋州など様々な地域で約30か国増加したほか、輸入先の集中度(HHI指数5)は低下傾向にあるなど、食料輸入先の分散化が進んでいる(第3-3-14図)。
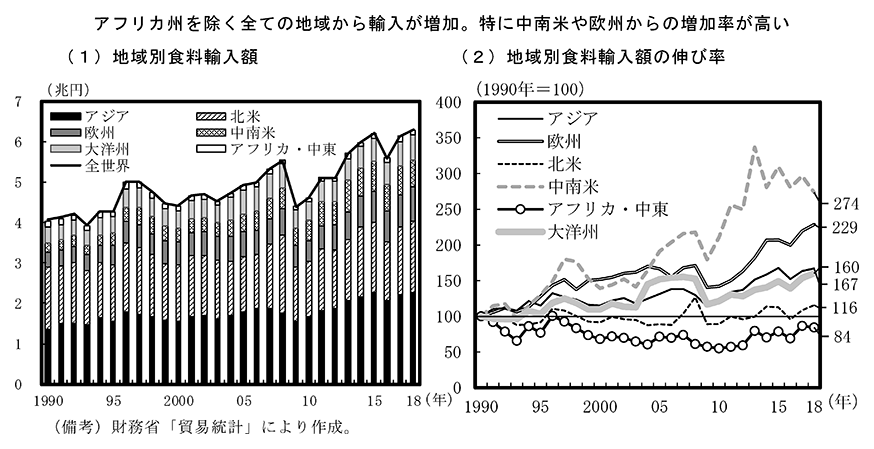
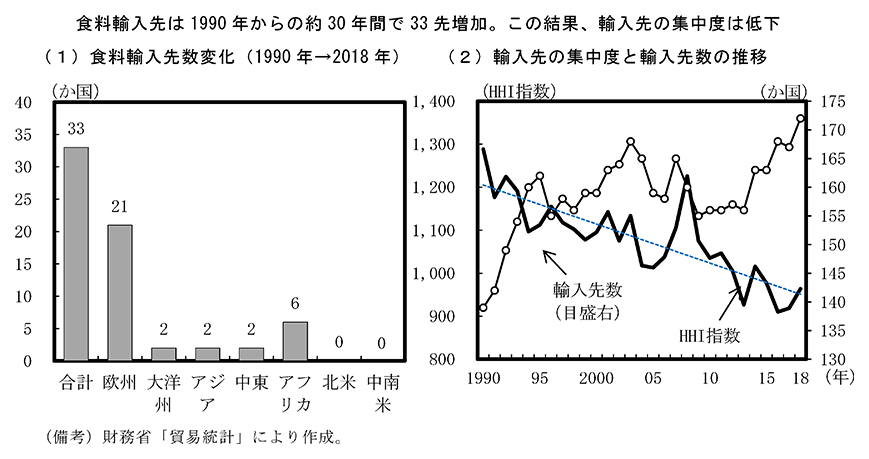
世界に目を転じると、世界人口の増加とともに世界の食料需要は右肩上がりで増えており、生産量もそれに連れて増加している。もっとも、世界の主要産地における天候不良など様々な要因により、生産量が需要量を下回る年も見受けられる。我が国がその多くを輸入に頼っている大豆や小麦などの主要食料品価格は2000年代に入ると上昇し、90年代から比べれば今も高い水準にある(第3-3-15図)。このように、世界的に需要が拡大している食料を、安価で安定的に確保するかは、我が国のみならず世界的にも重要な課題の一つとなっている。例えば、中国では、国内需要の増加とともに、主要穀物の輸出が減少する一方、輸入が増加するなど、時代の変遷とともに世界の食料事情は変化している(第3-3-16図)。そうしたことも視野に、安価で安定的な食料輸入に努める必要がある。
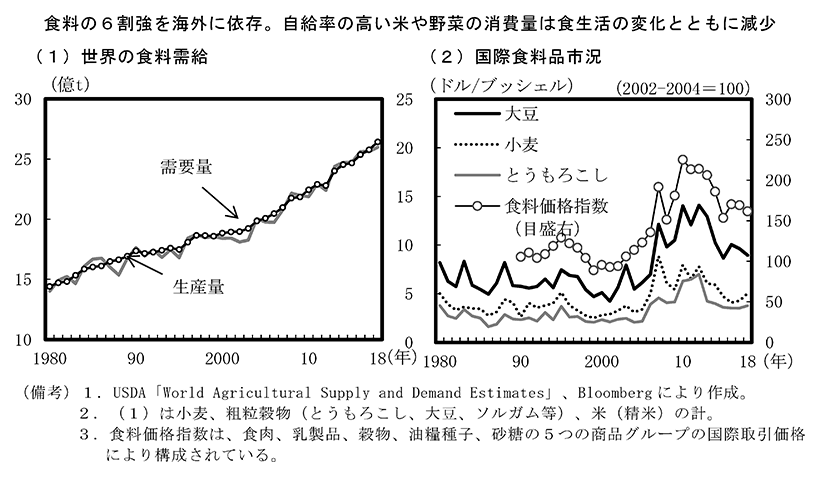
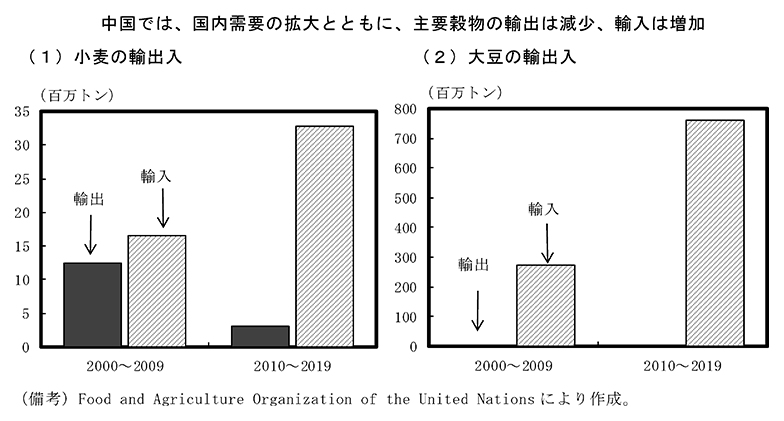
食料自給率を考えるうえで、もう一つのポイントとなる食料の「国内生産」と「輸出」について検討する。これらを検討するにあたり、我が国農業のGDPや食料品輸出の動向を確認してみよう。
まず、我が国農業の名目GDPは、1990年度代以降減少傾向にあったが、2015年度以降は耕種や畜産を中心に増加に転じており、下げ止まったようにみられる。また、一人当たりの農業実質GDPは増加を続けている(第3-3-17図)。
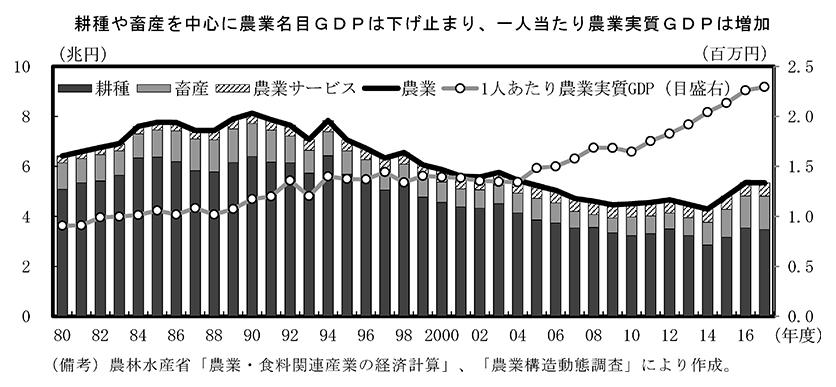
次に、我が国の飲食料品輸出の推移をみると、2013年頃を境に急速に拡大し、2018年には、90年対比で約3倍まで増加している。個別の主要品目別に90年からの伸び率をみると、和牛などを中心に肉類(加工品含む)が約20倍、日本酒などのアルコール類を中心に飲料が約9.5倍と政府によるPRやインバウンドの増加による日本食ブランドの認知及びブームがこうした輸出の増加を後押ししていると考えられる。また、健康志向や食の安全に対する意識が世界的に高まるなかで、果実(4.6倍)、魚介類(調製品含む、2.6倍)や米(358倍)6などの輸出も増加している(第3-3-18図)。
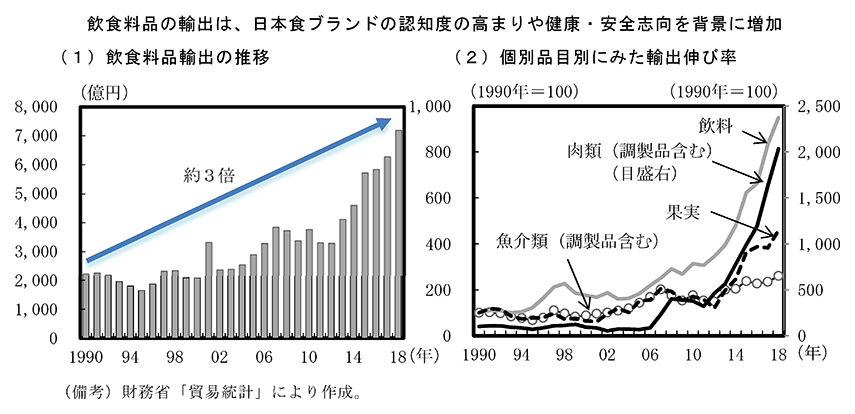
このように、我が国の農業は、農業就業者が減少する中にあっても、飲食料品輸出の増加などに後押しされながら、近年では国内総生産を増やしているほか、生産効率を高めながら一人当たり生産額を増加させている。このような輸出も含めた国内食料生産増加のメカニズムは、我が国の食料自給率上昇(対外食料依存の低減)には不可欠である。
(経済連携協定の利活用促進に向けた手続簡素化やPRを進める必要)
これまでみたように、食料の対外依存のリスクを低減させるためには、①食料輸入の安定化・多角化や②国内食料生産の強化及びそれを支える柱の一つとなる食料輸出力強化が重要である。
食料貿易にも関連するが、我が国は様々な国・地域と経済連携協定7を締結し、関税及び非関税障壁の低減に努めている。2019年12月現在、22か国・地域と18の経済連携協定(EPA)が発効・署名されており、それらの国・地域との食料貿易額が我が国の食料貿易総額に占める割合(2018年度)は7割弱を占めている(第3-3-19図)。ここでは、近年発効・署名されたTPP11、日欧EPA、日米貿易協定の3つの経済連携協定のうち、食料関連部分について紹介し、本項の締めくくりとしたい。
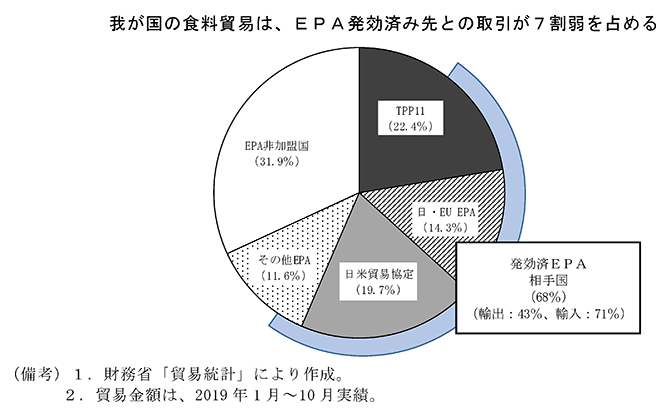
近年発効された3つの経済連携協定のうち、最も早く合意提携に至ったのがTPP11である。同協定は、ベトナム、マレーシアなどのASEAN諸国の一部とカナダ、オーストラリア、メキシコなど計11カ国との間で合意し、2018年12月に発効された。次いで、日EU・EPAは、EU加盟国(28カ国、2019年12月現在)との間で合意し、2019年2月に発効した。日米貿易協定は、2019年10月に正式署名され、2020年1月に発効した。食料品輸出に関しては、協定加盟各国の事情はあるものの、多くの品目で即時撤廃や数年の経過措置を経た後の撤廃が合意されている。他方、食料品輸入については、日EU・EPAにおいて、ワインの輸入関税即時撤廃などはあるが、基本的には国家貿易制度や差額関税制度の維持やセーフガードの導入など、国内生産者に配慮がなされている。なお、米については、日EU・EPA及び日米貿易協定において、関税削減・撤廃等からの「除外」を確保している(第3-3-20図)。
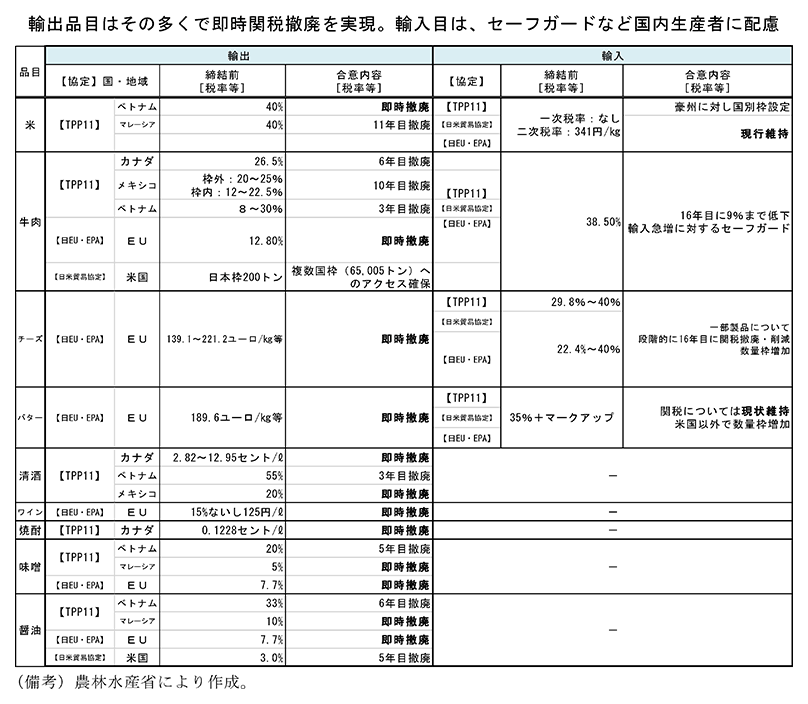
我が国の食料輸入における経済連携協定の活用状況を確認すると、EPAの締結とともに活用率は上昇している。特に、2019年2月に日EU・EPAが発行されると、利活用率は大幅に高まった。ただし、食料貿易総額に占めるEPA締結国の比率が7割弱(2020年1月に発効された日米貿易協定を除けば5割弱)(第3-3-19図)であるのに対し、実際にEPAを活用して輸入している比率は3割程度にとどまっているため、今後は手続の簡素化やPR活動による認知度向上などにより、より一層の利用を促進し、対外食料依存のリスク低減に繋げることが期待される(第3-3-21図)。