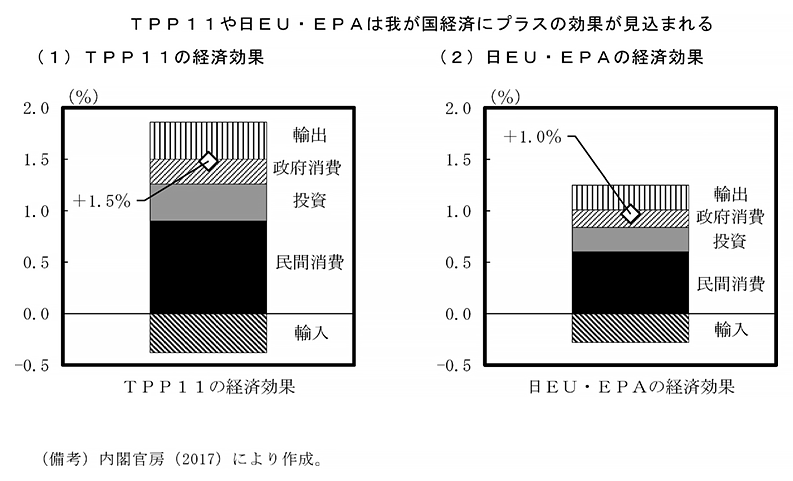第3章 世界貿易の動向と日本経済(第3節)
第3節 最近の通商問題の動向と日本経済への影響
本節では、最近の通商問題の動向等が世界経済や日本経済に与える影響を考察する。
具体的には、アメリカと中国との通商問題の動向や英国のEU離脱交渉の動向について、それらが世界経済や日本経済に与える影響を考察する。その際、サプライチェーンのグローバル化が進み、各国・地域の間の経済的な結び付きが強まっていることを考慮し、こうしたサプライチェーンを通じて生産される工業製品に含まれる各国・地域の付加価値の構成を、付加価値の創出源を区別した貿易データを用いて示す。また、世界経済を巡る不確実性の高まりによる我が国の設備投資への影響について、企業レベルのパネルデータを用いて、実証的に分析する。
最後に、我が国の経済連携協定の取組を整理するとともに、自由で公正な共通ルールに基づく貿易・投資の環境整備を一段と進め、企業活動をより活性化することの重要性を述べる。
1 米中間の通商問題の動向とその影響
アメリカは2018年に入ってから貿易制限措置を次々と発動しているが、それに対して、中国をはじめ対抗措置をとる国・地域もあり、国際的に通商問題が大きな争点となっている。ここでは、こうしたアメリカや中国を中心とした通商問題の動向が世界経済や日本経済に与える影響について考察する。
(アメリカと中国の2国間における追加関税・対抗措置)
アメリカは、中国等との間で貿易収支の赤字が拡大していることを背景に、「公正かつ互恵的な貿易取引の実現」を目指し、「既存の貿易慣行を見直す」として新たな通商交渉を進めている。具体的には、2018年3月に安全保障上の脅威を理由に通商拡大法232条に基づき鉄鋼・アルミニウムへの追加関税措置を実施したほか、7月から9月にかけては、知的財産権の侵害を理由に通商法301条に基づき、総計で2,500億ドルにのぼる中国製品の輸入に追加関税を課した1。これに対して、中国も対抗措置として、総計で年間1,100億ドル相当のアメリカ製品に5~25%の追加関税を適用した(第3-3-1図)。
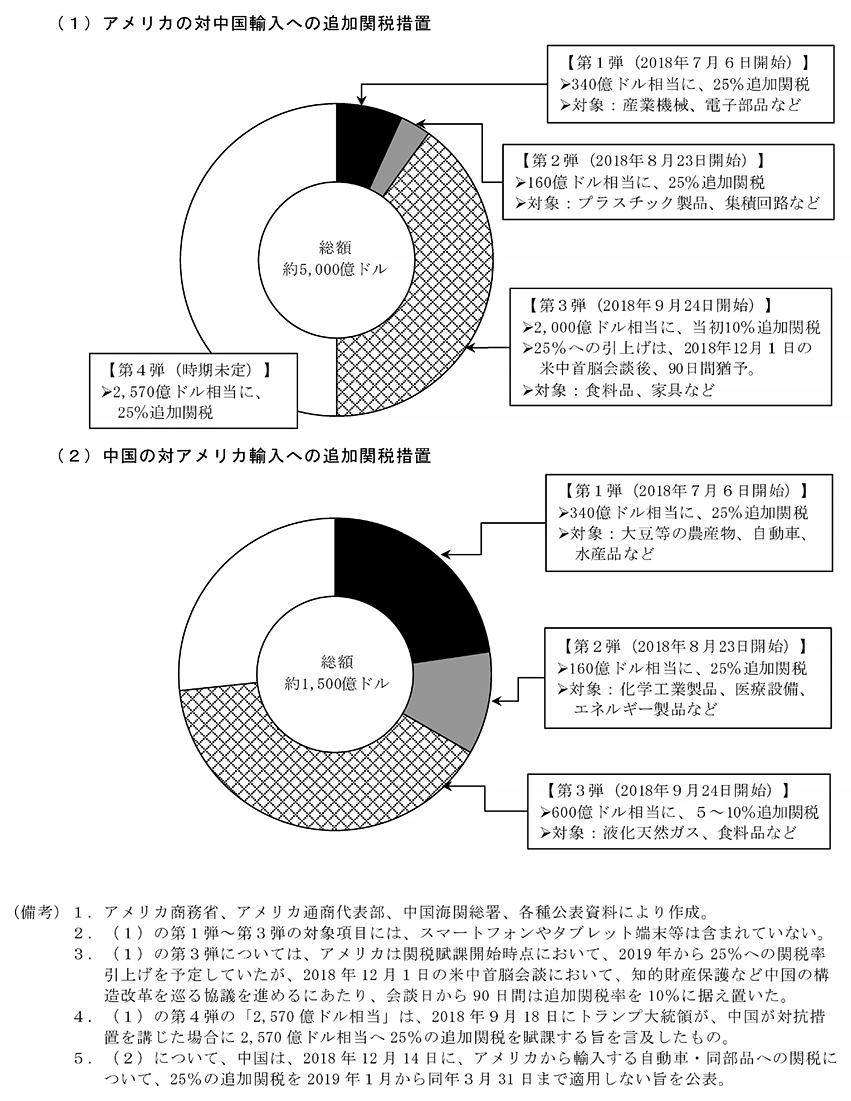
こうした米中間の通商問題の背景をみるために、事実関係を確認する。
まず、第3-3-2図(1)は、アメリカの財とサービスの輸出入をグロスベースで示したものであるが、サービス貿易は、財(モノ)の貿易と比べると、相対的に金額が小さい。また、2017年のアメリカのサービス収支の相手先国・地域別の構成をみると、受取、支払ともに、対EUが3割台と最も大きなシェアを占めていることが分かる(第3-3-2図(2))。
次に、アメリカの貿易収支の赤字をみると、1997年の約▲1,800億ドルから2000年半ばにかけて約▲8,200億ドルまで、赤字額が約4~5倍程度に拡大しており、2010年以降も大幅な赤字が継続している。また、2017年時点の国・地域別の収支の構成をみると、NAFTA2加盟国である対カナダの赤字が▲5,717億ドル程度で最も大きく、対中国の赤字は▲3,752億ドル程度で二番目に大きくなっている(第3-3-2図(3))。アメリカと中国との貿易の内訳について、2017年の品目別構成をみると、アメリカが中国から輸入する財の約5割が電気機器やコンピュータ等となっており、このうち、今回の追加関税措置では、スマートフォンやタブレット端末を除く電気機器、コンピュータ、産業機械などがその対象となっている。また、アメリカから中国への財の輸出については、約2割が航空機や輸送車両、約1割が大豆等の農産物となっており、このうち、自動車や大豆などが今回の対抗措置で追加関税の対象となっている(第3-3-2図(4))。
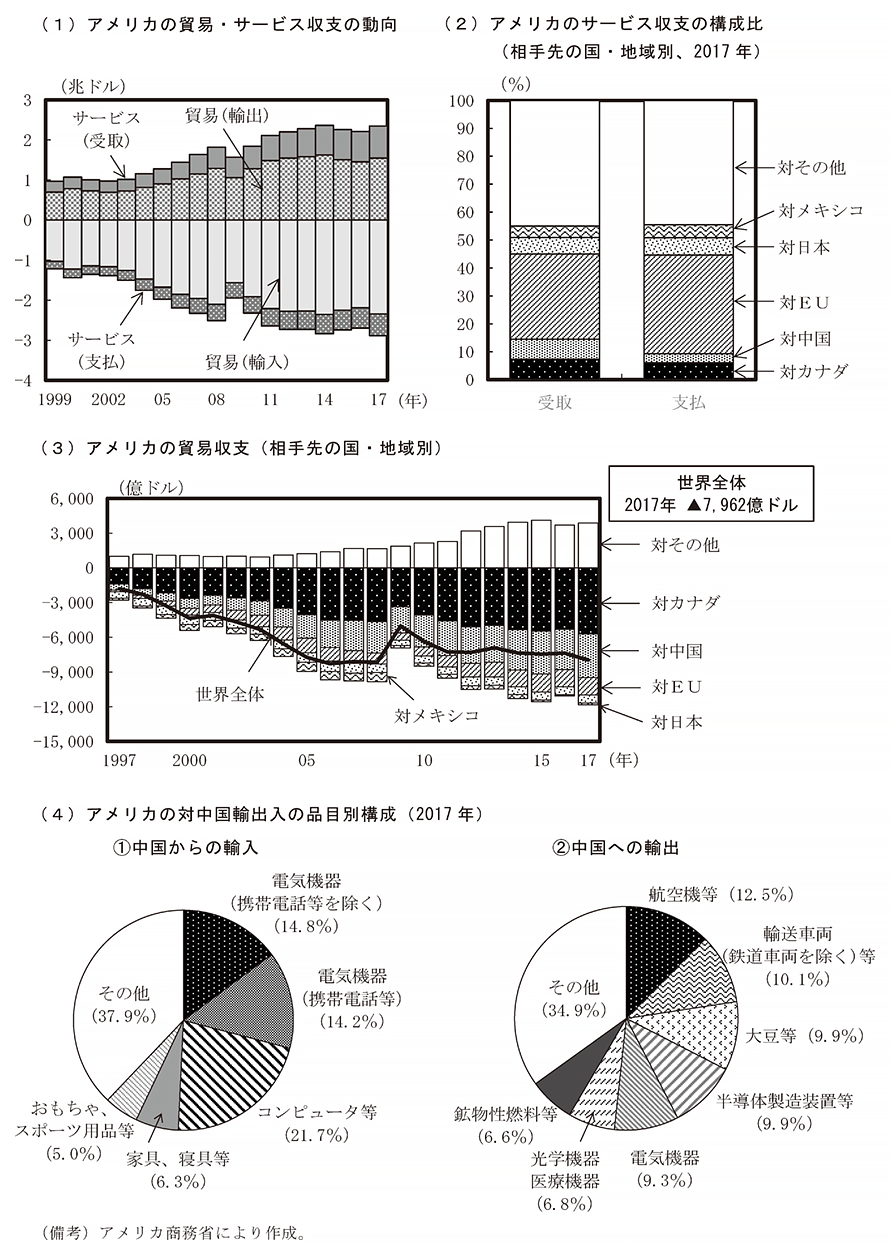
(米中間の通商問題は様々な経路で世界経済や日本経済に影響する可能性)
こうした米中2国間の追加関税・対抗措置は、様々な経路で世界経済や日本経済に影響を与える可能性がある。
第一は、追加関税措置がその財の貿易に与える直接的な影響である。関税率の引上げが当該財の販売価格に転嫁された場合には、当事国以外の国・地域からの輸入によって代替されるか、あるいは代替が困難な場合でも価格上昇によって需要が低下することにより、その財の輸入が減少することになる。この場合、当該財を輸出していた国では、輸出と国内生産がともに減少する。他方、当事国以外の国・地域については、関税率引上げ国で輸入代替が生じることによって逆に輸出が増加する可能性もある。
第二は、追加関税措置によって当事国の輸出財の生産が減少した場合に、それがサプライチェーンを通じて、当該財の部品等を供給している当事国以外の国・地域にも影響を及ぼす可能性である。第2節でみたように、近年は国際的な生産ネットワークが形成され、複数の国・地域にまたがって生産工程が分散化しているため、サプライチェーンの一部の国・地域の財の貿易が追加関税措置によって大きく減少した場合には、代替的なネットワーク形成には時間とコストがかかることから、他の国・地域にも影響が及ぶ可能性が考えられる。
第三は、通商問題の先行きの展開が不透明な中で、貿易や経済動向の先行きに関する不確実性が高まることにより、企業活動が慎重化したり、金融資本市場の変動が高まる可能性が考えられる。
こうした3つの経路によって通商問題の当事国のマクロ経済動向が下押しされた場合には、当事国以外の国・地域にも輸出入や投資の変動を通じて影響が及び、世界経済全体が下押しされる可能性があるほか、通商問題による貿易制限措置が長期化すれば、貿易制限措置がない場合に比べて投資水準が低下することや、最適なサプライチェーンの形成が妨げられることによる資源配分の非効率化が生じ、潜在成長力が低下する可能性も考えられる。
以下では、これらの3つの経路に沿って、それぞれの観点から米中間の通商問題が経済に与える影響の可能性について考察する。
(追加関税措置の影響は現在限定的だが長期化すれば当事国に大きな影響)
まず、米中間の追加関税措置が、当該財の貿易に与え得る影響についてみてみよう。米中間で関税措置がとられたのは2018年7月以降であるため、データが入手可能な2018年10月時点では、その影響は一部にとどまっている。アメリカの中国からの輸入動向をみると、引き続き高い伸びが続いており、むしろ追加関税措置がとられた7月以降に伸びが加速している様子がみられる。これは、為替レートが2018年に入って人民元安の方向で推移したことに加え、2019年1月から追加関税率が10%から25%に引き上げられる予定であったために駆け込み的な輸入がみられたことが背景にあるとみられる(第3-3-3図(1))(ただし、2018年12月の米中首脳会談において追加関税率の25%への引上げは90日間の交渉期間中は猶予されることとなった)。他方、アメリカから中国への輸出については7月以降大きく低下しているが、これは、為替レートがドル高方向で推移したことに加え、大豆など一部の品目については関税率引上げの影響が出ている可能性が考えられる(第3-3-3図(2))。
このように米中間の貿易をみる限りは、通商問題の影響は今のところ限定的であり、日本の対米輸出、対中輸出の動向をみても、7月以降に大きく変化した様子はみられない。対中輸出については、米中の追加関税措置がとられる前の2018年春頃から増勢が鈍化しているが、これは、第1節でも述べたとおり、スマートフォンやデータセンター向け需要の一服から情報関連財の輸出が鈍化したこと等を反映したものである(第3-3-3図(3)、(4))。ただし、2018年後半からは、中国の製造業の輸出入に関する業況判断がやや低下しているほか、日本においても中国向け工作機械の受注が減少しており、中国経済の動向には留意する必要がある(第3-3-3図(5)、(6))。
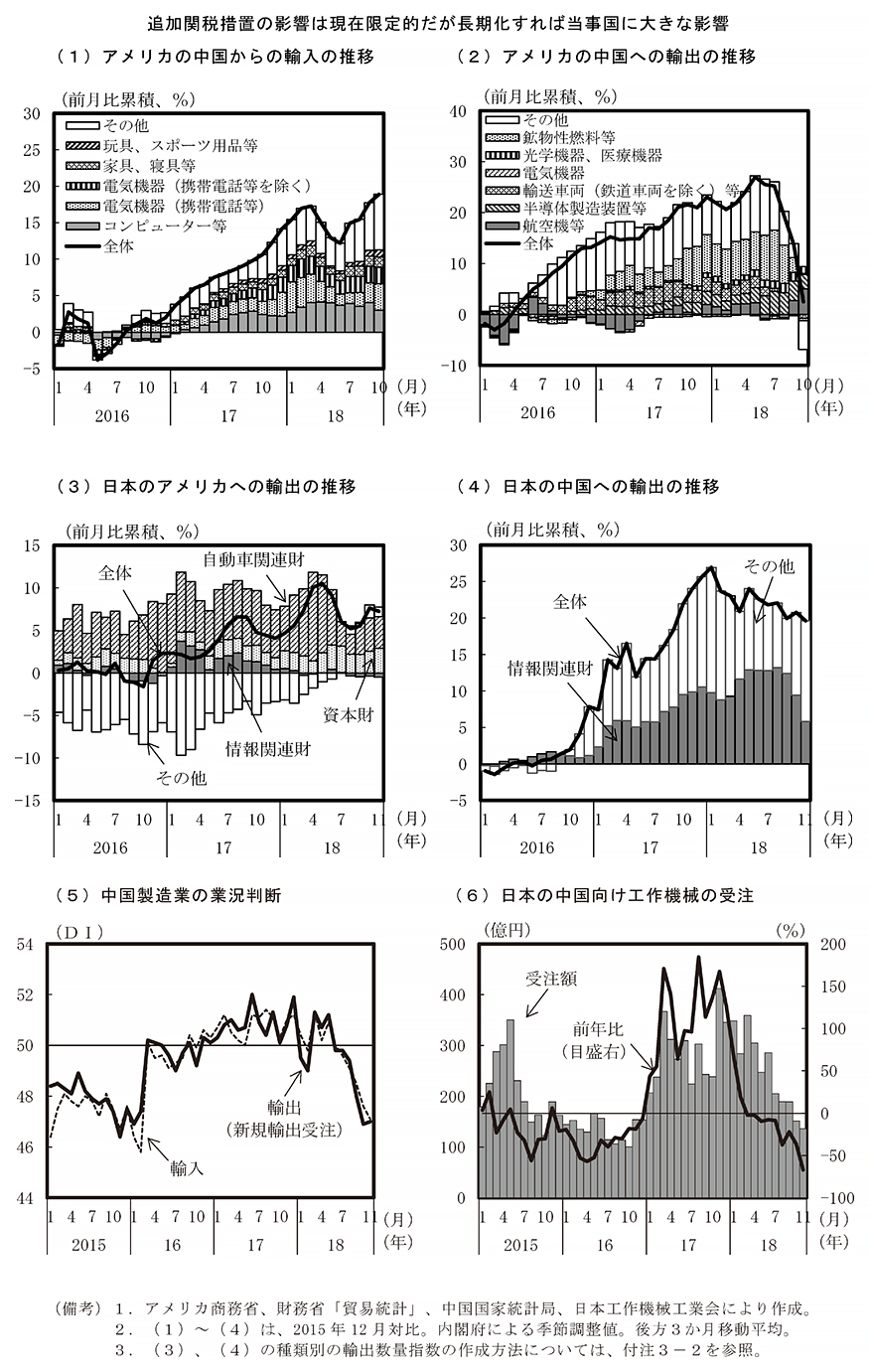
仮に米中間の追加関税措置が今後も長期的に継続した場合には、関税率引上げの対象となった財の輸入代替等の影響も顕在化する可能性が考えられる。
この点については、OECDやIMFなどの国際機関による試算が公表されている。
いずれの試算においても、直接的な関税率引上げの影響については、アメリカ、中国の経済成長率を押し下げる可能性が示唆されている一方、当事国以外の国・地域への影響は限定的である3(第3-3-4図)。
ただし、後述するように、不確実性の高まりが企業マインドに与える影響等が設備投資などの企業活動を慎重化することにより、当事国以外の国・地域でも影響が及ぶ可能性があることには留意する必要がある。
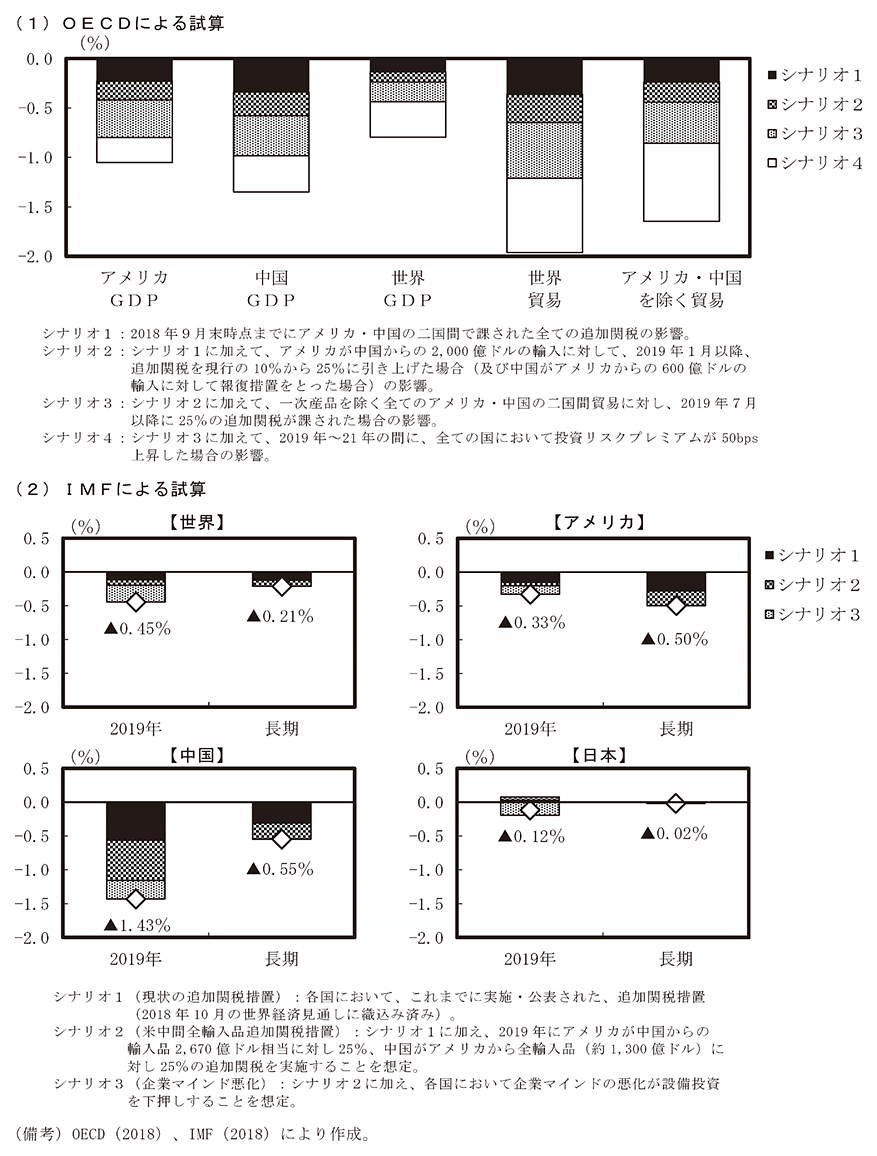
(財・産業別にみると影響の度合いに濃淡)
米中間の追加関税措置が直接的に各国・地域の生産動向に与える影響について、より詳細に財・産業別に確認してみよう。OECDやIMFなどのマクロ経済モデルによる影響試算では、詳細な産業別の影響をみることは困難であることから、ここでは、各国・地域の産業連関表を組み込んだ応用一般均衡モデル(GTAP<Global Trade Analysis Project>モデル)による試算例(堤[2018])を紹介する。
まず、これまでに実際に課された米中間の追加関税措置により、財・産業別にみた米中の実効追加税率をみてみよう(付図3-3)。アメリカにおける中国からの輸入への実効追加税率は、追加関税の対象外の品目が多い繊維アパレル等で2%程度となっているほかは、比較的満遍なく追加課税されており、輸送機械などが20%程度、電気機械・一般機械などが10%程度となっている。これに対し、中国のアメリカからの輸入に対する実効追加税率については、貿易量が多く追加関税対象範囲も広い農林水産・食品加工が20%程度となっている一方、貿易量の最も多い電気機械・一般機械については5%程度となっており、品目によってかなり差がつけられている。
こうした財・産業別の実効追加税率を踏まえて、これまでの米中間でとられた追加関税措置(アメリカは2,500億ドル相当の中国からの輸入に課税、中国は1,100億ドル相当のアメリカからの輸入に課税)が各国・地域の生産に与える影響をみてみよう。
追加関税措置による相対価格の変化がもたらす一次的な影響についての試算結果をみると、アメリカでは、木材パルプ等軽工業や電気機械・一般機械がプラスとなる一方、農林水産・食品加工、輸送機械などで生産が減少する可能性が示されている(第3-3-5図(1))。中国では、アメリカとは逆に、木材パルプ等軽工業や電気機械・一般機械が減少する一方、繊維アパレル等、農林水産・食品加工が増加する可能性が示されている。
関税率引上げが財・産業別の生産に与える影響としては、①関税引上げにより対象国からの輸入が他国からの輸入へ代替される効果、②輸入品の価格が相対的に上昇することにより国内で生産された財の優位性が高まり輸入が国内品に代替される効果、③中間財の輸入への関税率引上げに伴い自国製品の競争力が低下する効果、といった3つの経路が考えられる。例えば、アメリカで中国からの電気機械の輸入に追加関税が課された場合、①の輸入代替効果で他のアジアからの輸入に置き換わるとともに、②の国内品代替効果によりアメリカでの電気機械の生産も増加することとなる。また、アメリカの輸送機械の生産が低下するのは、①の関税引上げの効果に加え、③の中間財価格上昇の効果によって、輸入される鉄鋼等の価格上昇がアメリカで製造される自動車の価格競争力を低下させることによって生じると考えられる。
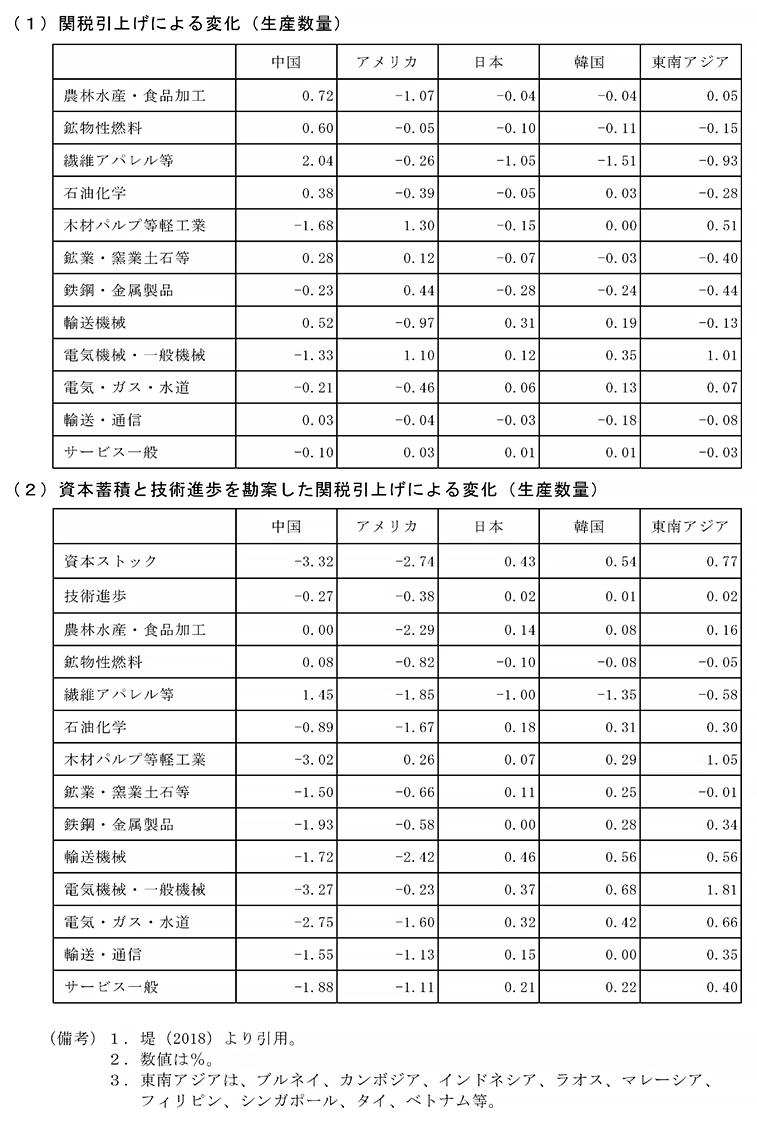
日本を含む当事国以外の国・地域の生産への影響は、総じてみれば限定的である。ただし、日本についてみれば、電気機械や輸送機械などで輸入代替による生産へのプラス効果がみられる一方、繊維アパレル等に関しては、追加関税の対象から外れている品目が多いために中国国内でのアパレル生産の優位性が相対的に高まる結果、若干マイナスの影響が出る可能性が示唆される。
最後に、関税引上げの影響に加え、中長期的な影響として、資本蓄積と技術進歩を勘案した場合の試算結果を紹介する(前掲第3-3-5図(2))。まず、内生化した資本ストックの変化率は、所得と投資の低下を反映し、アメリカで2.7%、中国で3.3%の減少となり、長期的な潜在生産水準は、関税引上げがない場合と比べて低下することを裏付けている。また、業種別にみると、アメリカでは木材パルプ等軽工業の生産が若干増加するだけであり、それ以外の業種の生産は減少し、特に、輸送機械生産の減少率は2.4%と最大である。中国においても、生産が増加する業種は鉱物性燃料や繊維アパレル等に限られており、他の業種の生産は減少する。特に、電気機械・一般機械の生産は3.3%の減少となる。前掲第3-3-5図(1)で示した関税引上げに伴う貿易転換効果によって生じた生産面の実質的な動きは、時を経ることで投資の減少と資本蓄積の減退につながり、一国の資本装備率が低下することで、いわゆる産業の高度化が阻害されることを示唆している。また、貿易量の減少に伴って生じるマイナスの技術進歩により、経済全体の生産性が低下することによって、こうした動きがさらに下押しされる結果となっている。
(中国から輸出される主要な品目には、日本の付加価値が相応に含まれている)
次に、追加関税措置による当事国の生産の変化が、サプライチェーンを通じて、部品等を供給している当事国以外の国・地域にも影響を及ぼす経路について考察する。第2節で詳しく論じたように、中国は日本を含む東アジア地域から部品などの中間財を輸入し、それを用いて生産した最終財の多くをアメリカに輸出しており、中国の工業製品の輸出の付加価値のうち、約2割が部品供給等を通じて海外が創出したものとなっている。
第3-3-6図は、中国から輸出される工業製品のうち、2015年時点での輸出額の大きい4品目(情報通信機器、繊維・衣服等、電気機械、一般機械)について、前掲第3-2-7図と同様に、中国国内及び海外の主要な国・地域の付加価値の構成を図示したものである。品目別に付加価値の構成を比較すると、中国における内製化が進展しているため、中国国内の付加価値の割合がどの品目でも7割以上となっているが、そうした中にあっても、情報通信機器については、海外の付加価値の割合が約3割と相対的に高くなっている。また、電気機械と一般機械は海外の付加価値の割合が2割程度となっている。一方、繊維製品については、中国国内の付加価値が約9割、海外の付加価値が約1割と、自国の付加価値による貢献が比較的高くなっている。これら4品目の海外による付加価値の創出分について、国・地域別に寄与の大きさを確認すると、日本は、いずれの品目についても付加価値の割合が相対的に高く、シェアは第2位ないし第3位となっている。
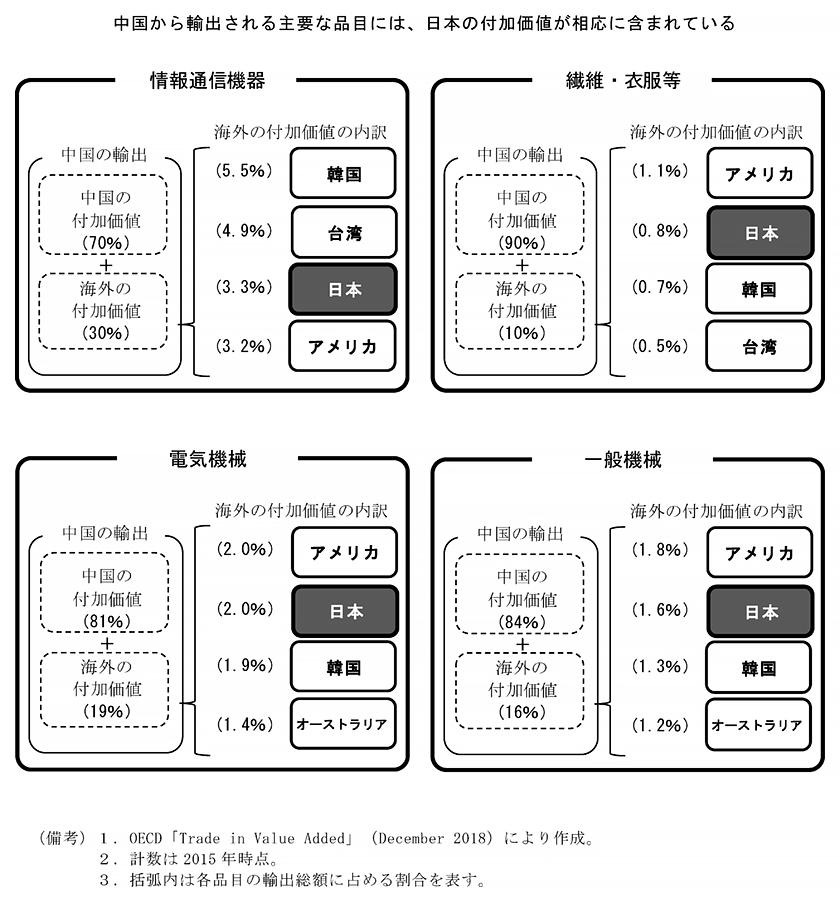
さらに、中国から輸出される工業製品の全品目について、2015年時点における輸出額と、輸出額に含まれる海外の付加価値の割合を確認すると、情報通信機器の輸出額が約4,900億ドルで、輸出全体の約25%を占めて最大となっており、それに含まれる海外の付加価値の割合についても、約30%と、石油・石炭製品に次いで2番目に大きいことが分かる(第3-3-7図)。
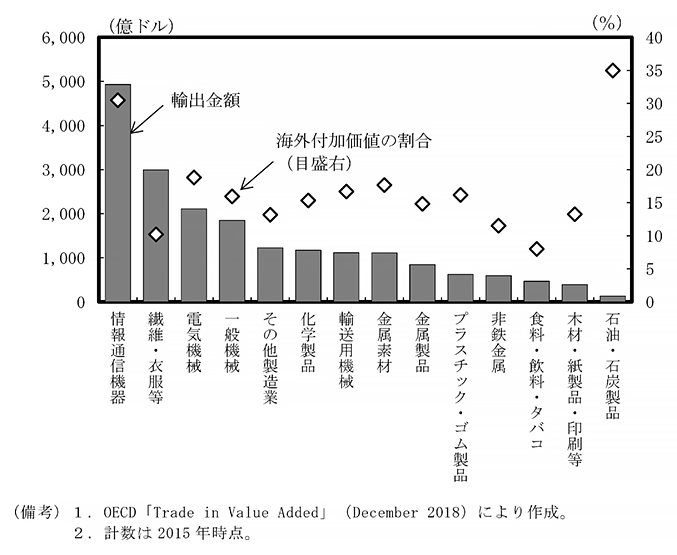
以上を踏まえると、日本をはじめとする主要な国・地域が、中国を中心とするサプライチェーンにおいて重要な立ち位置を占めているため、関税引上げにより中国の輸出が減少すると、サプライチェーンを通じて、中国だけでなく、日本も影響を受ける可能性があることが示唆される。ただし、これまでのアメリカによる追加関税措置には、日本からの部品供給が多く含まれるスマートフォンやタブレット端末が除外されていることから、今のところ影響は限定的なものにとどまっているが、さらに追加関税措置の対象が拡大された場合には、その影響に十分留意する必要がある。
(日系現地企業への影響は現在のところ限定的)
ここでは、サプライチェーンと関連して、中国に進出している日本企業への影響について確認する。
経済産業省「海外事業活動基本調査」によると、中国に進出している日本企業の現地法人(以下、日系現地企業)の数は2000年以降、大きく増加しており、直近の2016年時点では約8,000社まで増加している(第3-3-8図(1))。また、同調査の個票データを用いて、直近の2016年度の日系現地企業の売上高の構成をみると、輸送機械が約4割と最も多く、次いで情報通信機械などの割合が高い(第3-3-8図(2))。
次に、JETRO(日本貿易振興機構)の調査をみると、日系現地企業の販売先の構成は、中国国内向けが約7割、海外向けが約3割となっている。このように、主に中国国内での販売に重点が置かれており、中国経済の成長に伴い、その割合が高まっている(第3-3-8図(3))。また、輸出について、仕向け先の構成をみると、日本向けの割合は、製造業では5割以上、非製造業でも約7割と、最も高い一方、アメリカ向けの割合は、製造業では約6%、非製造業では約3%程度となっている。ただし、業種別にみると、アメリカ向けの割合は、輸送機械では約10%、電気機械では約7%と相対的にやや高い(第3-3-8図(4))。
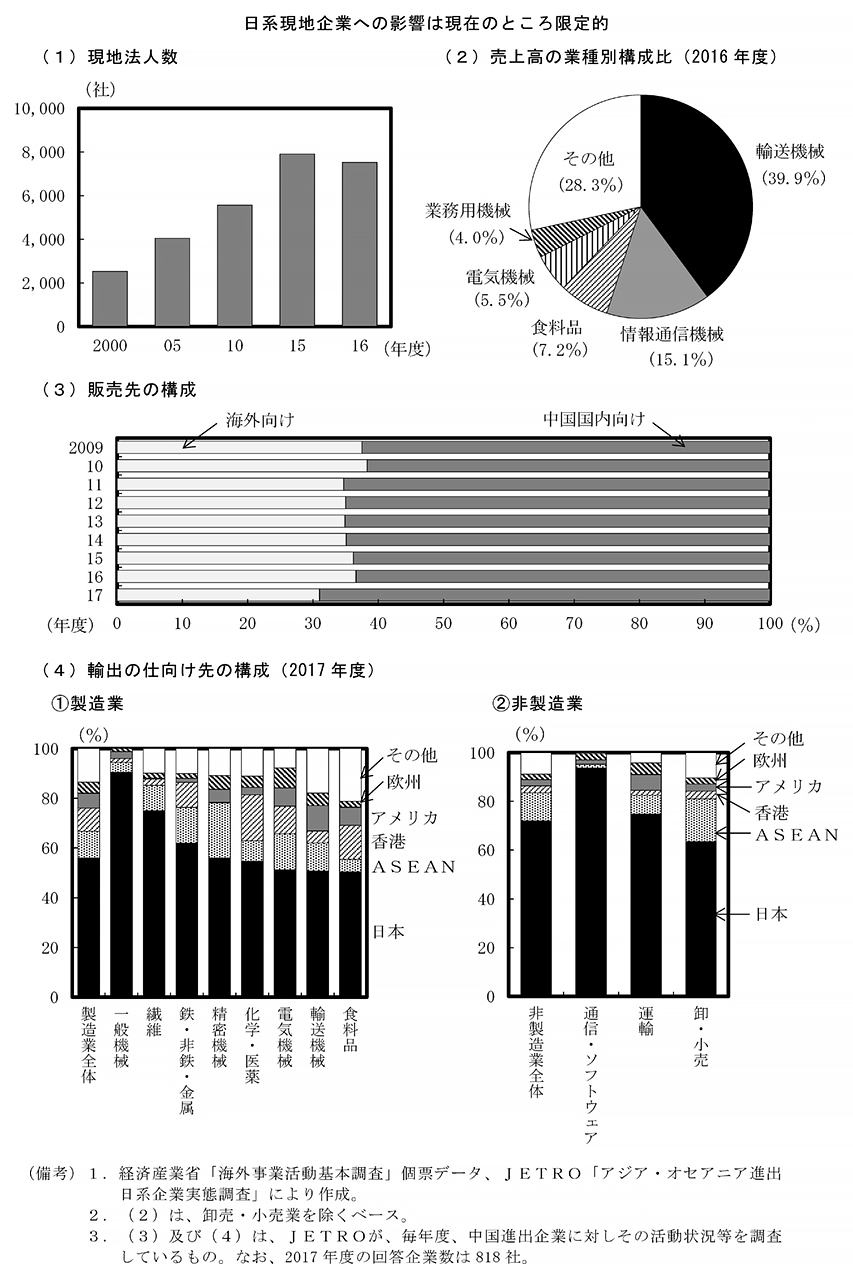
このように、中国に進出している日本企業については、輸出向けの販売が比較的小さく、かつ、その輸出先についてもアメリカ向けは限られていることから、米中間の追加関税措置によって中国における生産拠点等を大きく見直す動きは一部の産業に限られるとみられる。しかし、仮に追加関税措置の対象が広がれば影響も大きくなる可能性がある。また、日系現地企業の販売先の約7割が中国国内向けであり、中国のマクロ経済動向による影響も大きいことから、中国のマクロ経済が減速した場合の影響には十分に留意する必要がある。
(不確実性の高まりは企業の投資活動を慎重化させる可能性)
最後に、通商問題の先行きの展開が不透明な中で、貿易や経済動向の先行きに関する不確実性が高まり、企業活動が慎重化する可能性について考察する。前掲第3-3-4図の国際機関の試算によれば、関税率引上げの影響は当事国にほぼ限定されるものの、不確実性の高まりの影響については、当事国以外の国・地域でも相応の影響が生じることが示唆されている。
そこで、不確実性の高まりが設備投資にどのような影響を与えるかについて分析するために、内閣府・財務省「法人企業景気予測調査」の個票データを用いて、設備投資の年度計画が、個別企業の1四半期先の業況見通しの不確実性に応じてどのように修正されるかを推計した。具体的には、設備投資の年度計画の対数値を被説明変数とする2種類のモデルを推計した。
第1のモデルは、説明変数として、次期(1四半期後)の業況見通しについて、①「上昇」と回答したときに1となるダミー、②「低下」と回答したときに1となるダミー、③「不明」と回答したときに1となるダミー、の3つを取り入れたモデルである。特に、③の「不明」ダミーの回帰係数が有意にマイナスとなっていれば、企業の先行き見通しに関する不確実性が、設備投資に負の影響を与えていることが、実証的に示唆される4。
第2のモデルは、説明変数として、第1のモデルに加えて、金融危機後(2008年4-6月期以降)に1となるダミーと、第1のモデルの各説明変数との交差項を追加したモデルである5。この交差項の回帰係数が有意にマイナスとなっていれば、金融危機の経験を踏まえ、それ以降、企業の設備投資スタンスが慎重化した可能性が実証的に示唆される6。
推計結果をみると、まず、第1のモデルについて、次期の業況見通しが「不明」の場合の回帰係数が有意にマイナスとなっており、上述の仮説のとおり、企業の先行き見通しに関する不確実性が、当該企業の設備投資計画を押し下げている可能性が示唆される。なお、次期の業況見通しが「上昇」の場合の回帰係数は有意にプラスとなっており、業況の見通しが良ければ、当該企業の設備投資計画が押し上げられる可能性を示している(第3-3-9図①)。
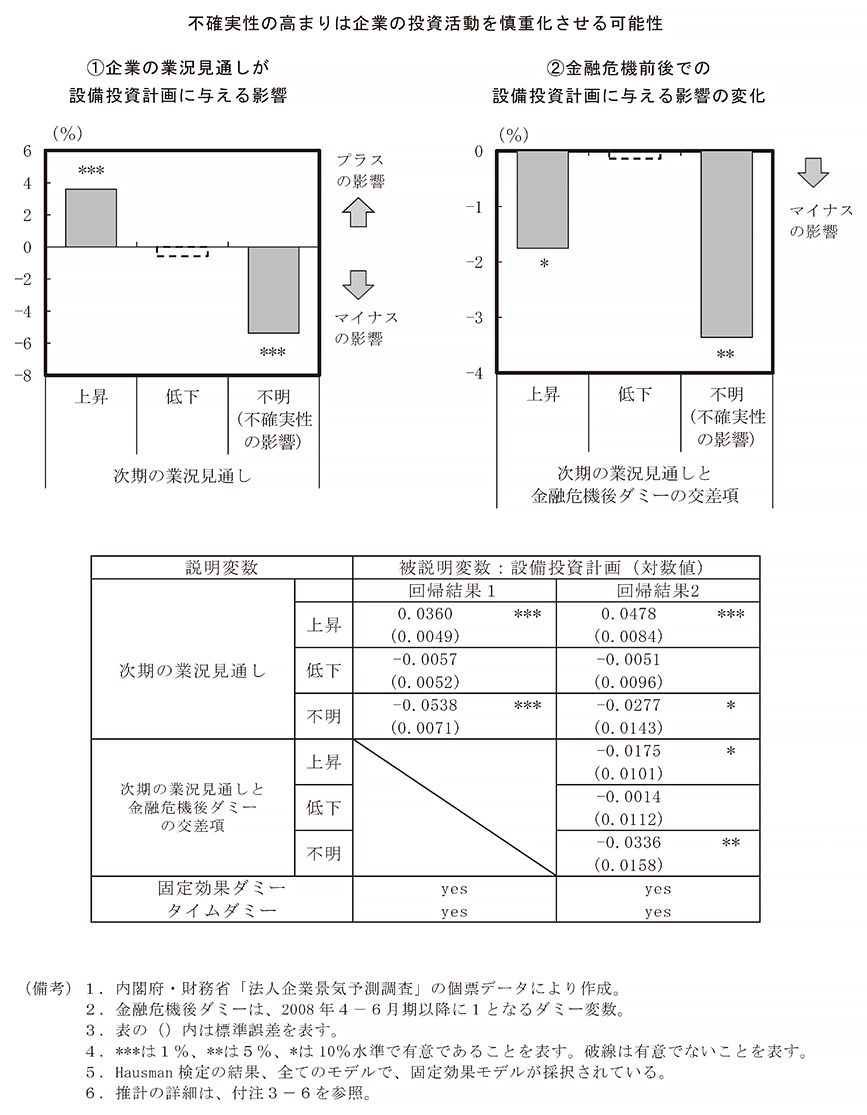
次に、第2のモデルの推計結果をみると、金融危機後ダミーとの交差項について、次期の業況見通しが「不明」の場合の回帰係数が有意にマイナスとなっている。このことは、上述の仮説のとおり、ある企業の業況見通しに不確実性が生じた場合、当該企業の設備投資計画が下方修正されるが、その修正幅は金融危機後の方が大きくなっている可能性を示唆している(前掲第3-3-9図②)。
また、第2のモデルの推計結果において、金融危機後ダミーと、次期の業況見通しが「上昇」の場合の交差項をみると、その回帰係数も有意にマイナスとなっており、金融危機以降は、企業の業況見通しが良くても、設備投資計画の上方修正幅が一部押し下げられていることを示しており、企業の設備投資スタンスが、金融危機以降、慎重化した可能性が示唆される。
ただし、次期の業況見通し「上昇」×金融危機後ダミーの係数の絶対値は、次期の業況見通し「不明」×金融危機後ダミーの係数の絶対値よりも小さいため、やはり第1のモデルでみたように、業況見通しが「不明」となった場合の影響度の方が金融危機後においても大きいことが分かる。
以上の推計結果からは、業況見通しの不確実性が設備投資計画にマイナスの影響を持っていることが示唆されるが、直近の日銀短観(2018年12月調査)の結果をみると、景況感は良好な水準となっており、設備投資計画も前回調査から上方修正され、過去と比べても強めとなっている7。
また、各種の企業ヒアリング調査の結果などをみても、これまでのところ、我が国経済に及ぼす影響は限定的であるとの指摘が多い。ただし、今後も通商問題の動向を巡る不透明感が長引く場合には影響を及ぼす可能性もあり、注意が必要である。
コラム3-1 アメリカ・メキシコ・カナダの新たな協定
アメリカ政府は、2017年8月に、「北米における貿易不均衡」を是正し公正な取引を確保することを目的として、NAFTA(北米自由貿易協定)の再交渉を開始しました。2018年8月末には、アメリカとメキシコとの間で基本方針に関する暫定合意が成立し、さらに2018年9月末には、アメリカとカナダとの間でも合意がなされ、アメリカ・メキシコ・カナダの3か国間で新たな協定が合意されました8(コラム3-1図(1))。
新協定の主な内容として、乗用車の原産地規則については、域内での乗用車部品の調達比率を現行の62.5%から75%へ引き上げるほか9、40%の乗用車部品は時給16ドル以上の労働者によって生産することを合意しました10。また、アメリカへの乗用車の輸入について、カナダ及びメキシコに対し、それぞれ年間260万台の数量制限を設定したほか11、アメリカへの自動車部品の輸入について、カナダに年間324億ドル、メキシコに年間1,080億ドルの輸入枠を設定しました。
なお、懸案であった自動車への追加関税については、カナダとメキシコは当面適用除外となりました。
こうした北米の新たな協定が日本経済に与える影響として、特に自動車産業への影響を中心に確認してみましょう。コラム3-1図(2)のとおり、アメリカの自動車・同部品の主な輸入相手国をみると、日本は、メキシコとカナダに次いで、第3位となっています。この点をより詳しくみると、2017年においてアメリカでの日本車の販売台数は約670万台ですが、このうちアメリカでの現地生産が約380万台、日本からの輸入が約170万台、残りの約150万台がメキシコ及びカナダからの輸入となっています12(コラム3-1図(3))。
また、北米における日本企業の現地法人の数は約3,600社と多く存在するほか、その売上高の構成をみると、自動車などの輸送機械が約半分を占めています(コラム3-1図(4)、(5))。アメリカに進出している日系企業に対するJETRO(日本貿易振興機構)のアンケート調査では、NAFTA再交渉に関して、影響を受ける内容として「通関・貿易円滑化・原産地規則」が最も多く、輸送用機器・同部品や原材料を供給する鉄鋼などでは、原産地規則改定に伴うコスト変動等への懸念を指摘するコメントが多く見受けられます。一方で、化学製品・石油製品などでは、材料をほぼ米国内で調達しているために、再交渉の影響はないとするコメントもみられており、産業によって対応には差異もみられます。いずれにせよ、自動車産業への影響を中心に今後の動向には留意が必要です(コラム3-1図(6))。
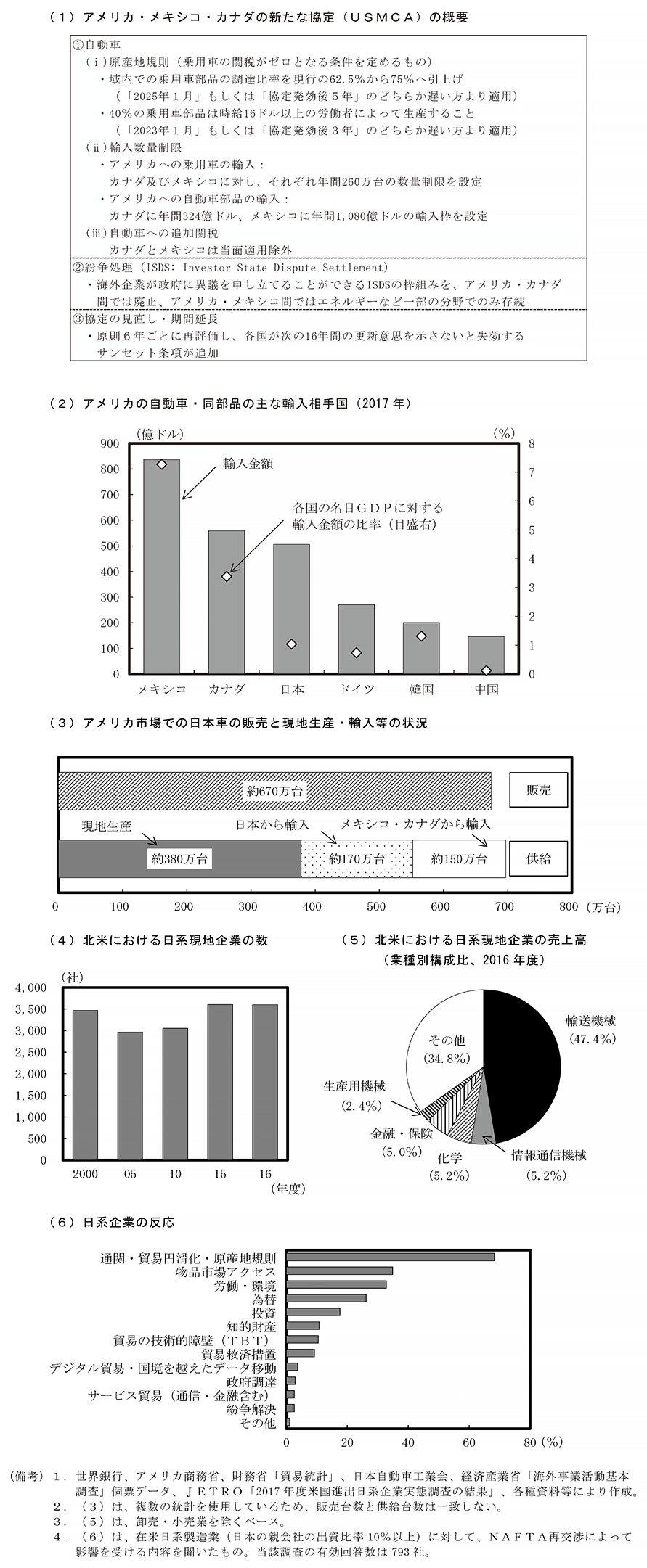
2 英国のEU離脱交渉の動向とその影響
本項では、米中間の通商問題のほかに考え得る世界経済のリスク要因として、英国のEU離脱交渉の動向とその日本経済への影響について整理する。
(日本は貿易・投資の面で英国と関係が深く、英国のEU離脱の帰趨に注意が必要)
まず、英国のEU離脱交渉の経緯を確認する。英国は、2016年6月の国民投票でEU離脱を決め、2017年3月には正式にEUに離脱を通告した。その後は、2019年3月の離脱に向けて、離脱協定及びEUとの将来関係の大枠を示す政治宣言の協議を進めてきた。こうした中、2018年11月末に、臨時の欧州理事会が開催され、離脱協定案及び政治宣言案が英EUの首脳レベルで合意された。この合意内容については、英国議会と欧州議会の承認を得る必要がある状況となっている(2018年12月末時点)(第3-3-10図(1))。
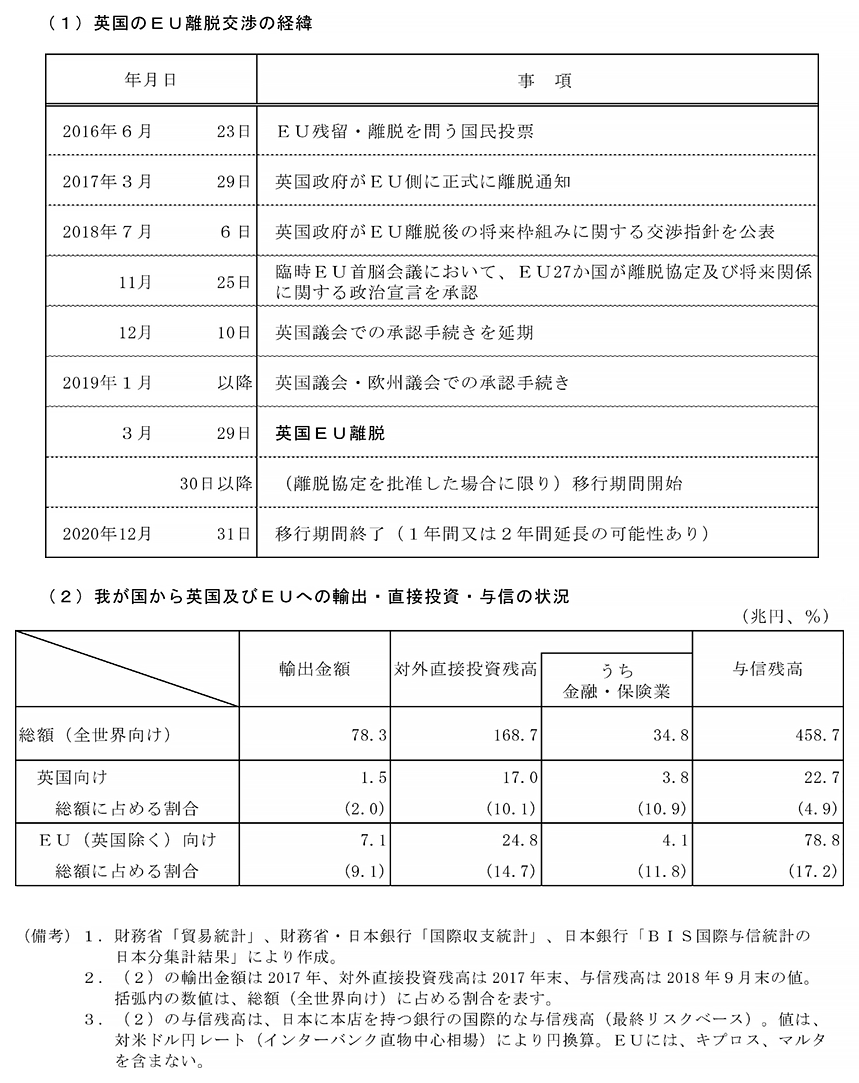
次に、日本と英国との貿易や投資などの構造を確認する。日本からの輸出金額(2017年時点)をみると、英国を除くEU向けが占める割合は全体の9.1%であるのに対し、英国向けの割合は2.0%と相対的に小さい。他方、日本からの直接投資残高(2017年末時点)をみると、英国を除くEU向けの割合は全体の約15%であるのに対し、英国向けの割合は約10%となっており、投資先としては大きな位置付けを占めている。特に、業種別にみると、金融・保険業の直接投資残高の割合は、英国向け(10.9%)と、英国を除くEU向け(11.8%)がほぼ同程度の割合となっている。また、日本の海外向け与信残高(2018年9月末時点)をみると、英国向け(4.9%)は、英国を除くEU向け(17.2%)よりも割合が小さいが日本企業の進出に伴い一定程度の割合を占めている(前掲第3-3-10図(2))。
さらに、日本企業の進出状況をみると、英国に進出している日本企業の現地法人(以下、日系現地企業)の数は600社強となっている。売上高の業種別構成をみると、製造業では、自動車などの輸送機械が3割弱、窯業・土石が1割程度を占めているほか、非製造業では、情報通信業が1割強、金融・保険が1割弱を占めており、欧州における拠点的な役割を果たしているところも多い(第3-3-11図(1)、(2))。
英国のEU離脱による日本経済への影響については、英国議会や欧州議会の対応を含め、英国とEUとの間の交渉結果次第であり、現時点で正確に見通すことは困難である。ただし、仮に英国が何の取り決めもないままにEUから離脱した場合には、2019年3月末以降、直ちに、英国とその他EU加盟国との貿易において、通関手続きや関税の支払いが生じるほか、英国・EU双方の規制・ルールへの対応が必要になるなど、合意に基づいて離脱する場合よりも日本企業への影響は大きいと考えられる。また、マクロ経済的にみても、EU離脱による英国への経済的影響は大きいとみられることから、それによる貿易・投資への影響、金融資本市場を通じた影響などが懸念される。
英国のEU離脱と日本企業への影響に関するJETRO(日本貿易振興機構)の調査によると、2018年2月時点で、離脱によるマイナスの影響があるとした企業は3割、プラスの影響があるとしたのが3%弱であり、半分以上の企業は分からないとしている。また、回答企業が抱える懸念としては、「英国の規制・法制への影響」を挙げる企業が4割と最も多く、次いで、「英国経済の不振」が3割強、「為替への影響」が3割弱となっている(第3-3-11図(3))。
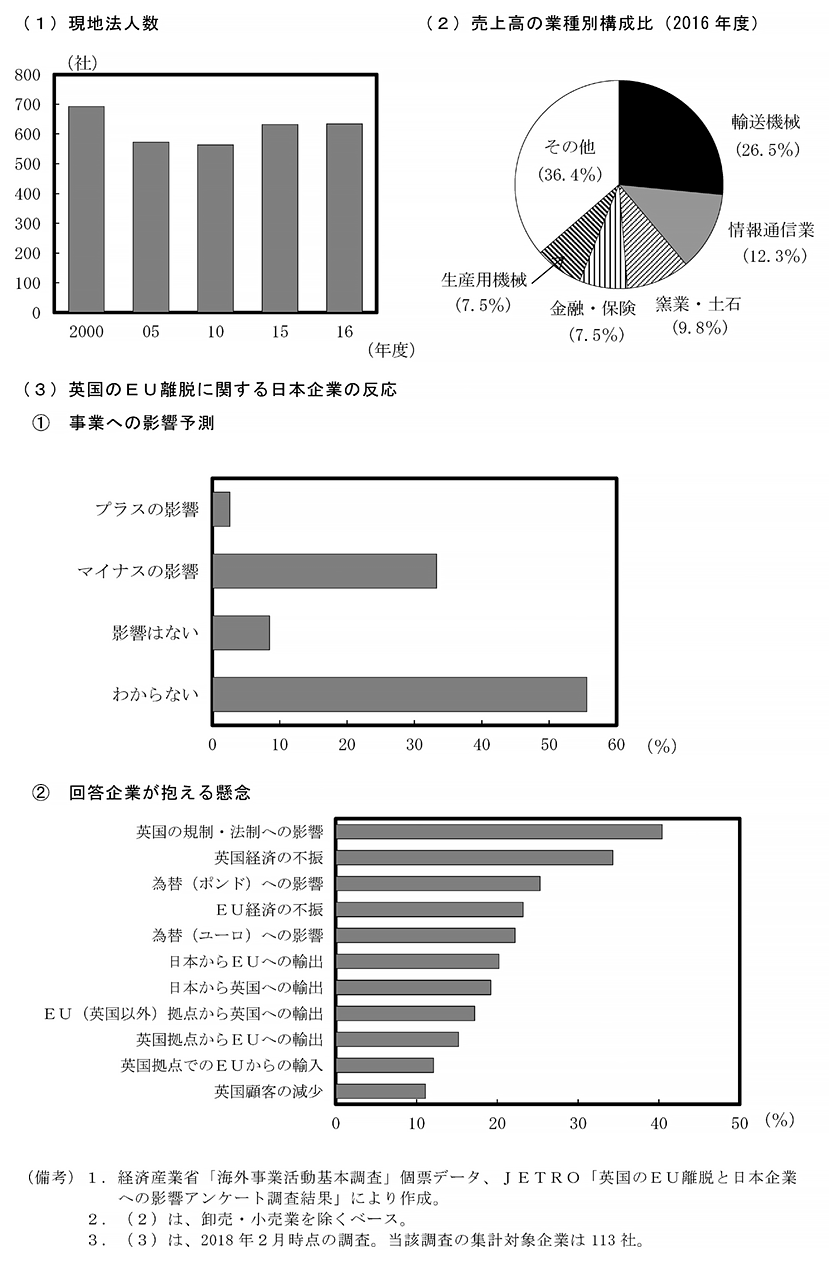
我が国としては、これまで、英国のEU離脱が日本経済や日本企業の現地法人の経済活動に与える影響を最小化すべく、英国・EU双方にあらゆるレベルで働きかけてきたところであり、引き続き、英国とEUの間の離脱交渉の動向を注視する必要があると考えられる13。
(英国のEU離脱による日本の自動車産業への影響)
英国のEU離脱が日本経済に与える影響を考察する上での一つの参考として、英国における日系現地企業の売上高が最も大きい自動車産業に着目し、英国が欧州のサプライチェーンにおける主要な生産拠点となっていることを確認する。
まず、欧州14の各国について、2016年における自動車の販売台数をみると、ドイツが約371万台で最大となっているが、それに次いで、英国が約312万台と2番目に大きい(第3-3-12図(1))。また、同様に、2016年における自動車の生産台数をみると、ドイツが約606万台で最大となっており、次いで、スペイン(約289万台)、フランス(約208万台)、英国(約182万台)の順となっている(第3-3-12図(2))。
ただし、日系メーカーの販売台数や生産台数でみると、英国は、販売台数が約47万台と最大となっているほか、生産台数も約82万台と最大となっており、そのシェアは欧州における現地生産の約半分(46%)を占めていることから、英国は日系メーカーの最大のマーケットであると同時に、重要な生産拠点であることが分かる(第3-3-12図(3))。
次に、日系メーカーに着目して、2016年時点における自動車の需給構造を確認すると、欧州全体については、供給側は約261万台(内訳は、現地生産が約179万台、日本からの輸出が約82万台)となっており、需要側の販売台数も約260万台とおおむね見合っている。他方、英国については、供給側が約97万台(内訳は、現地生産が約82万台、日本からの輸出が約15万台)となっている一方、需要側の販売台数は約47万台となっていることから、差分である50万台程度が英国から他のEU加盟国に輸出されているとみられる。このことからは、日系メーカーの自動車については、英国が主要な生産拠点となっており、英国で生産された自動車が、その他のEU加盟国向けに輸出されている構造となっていることが示唆される(第3-3-12図(4))。
また、OECDの付加価値の創出源を区別した貿易データであるTiVAを用いて、英国から輸出される自動車の輸出額に含まれる付加価値の構成をみると、2015年時点において、英国国内による付加価値は全体の約71%、海外の付加価値が約29%となっている。このうち、海外の付加価値について国・地域別の内訳をみると、英国を除くEU加盟国の割合が輸出全体の付加価値の約16%を占めるほどの大きさとなっている(第3-3-12図(5))。このように、英国で生産されて輸出される自動車には、他のEU加盟国で作られた部品等が多く用いられている。
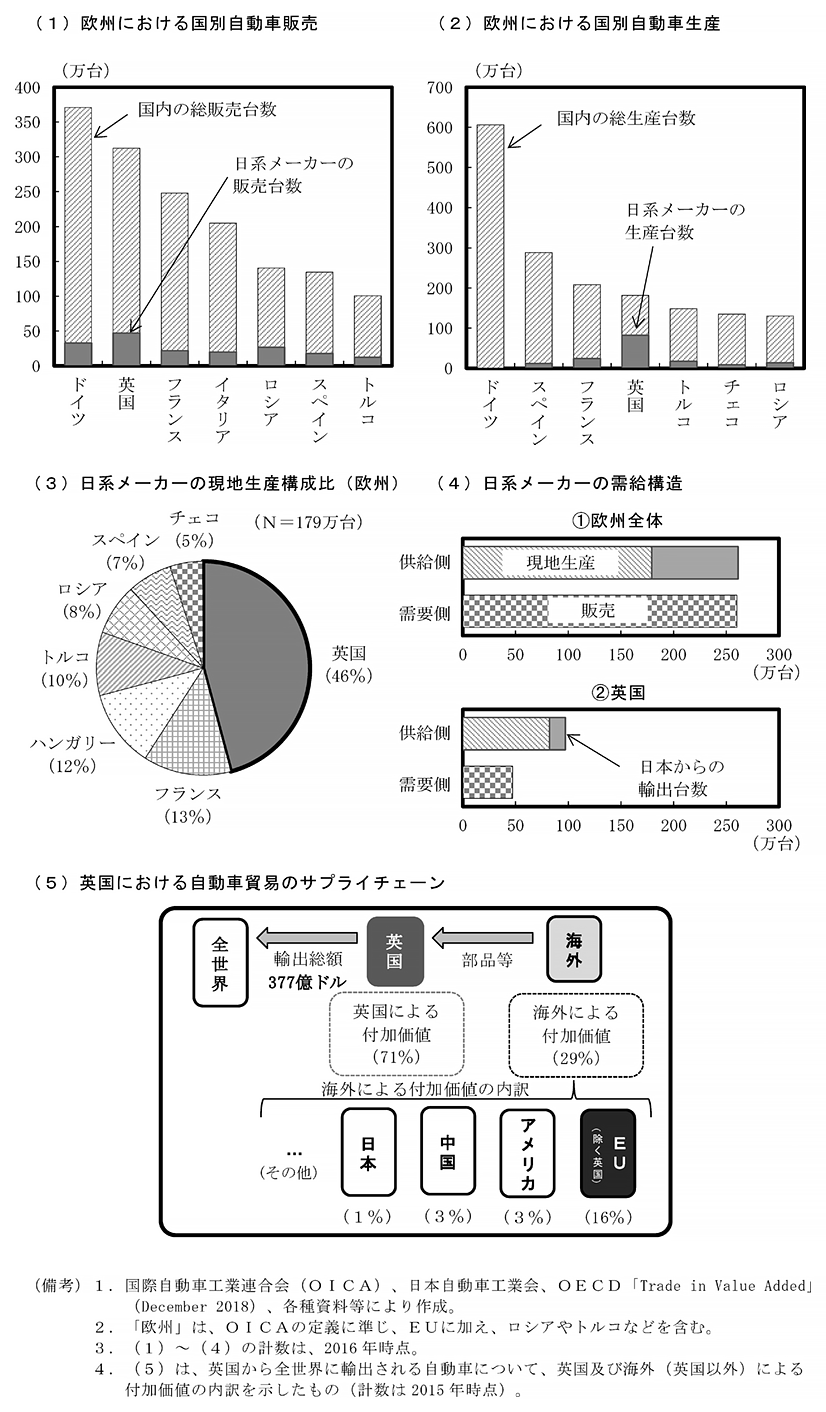
以上を踏まえると、欧州の日系現地企業の自動車のサプライチェーンにおいて、英国が主要な生産拠点となっていることや、英国とその他のEU加盟国との間で密接なサプライチェーンが形成されていることが示唆される。仮に、英国が「合意なきEU離脱」に追い込まれた場合には、通関手続き等に要する時間やコストによって、こうしたサプライチェーンの維持が困難となる可能性もあり、離脱交渉の動向には引き続き注意が必要である。
3 我が国の経済連携協定の取組と自由貿易のメリット
前項まででは、米中間の通商問題や英国のEU離脱について、それらの動向と日本経済に与える影響を考察した。本項では、本章全体の締め括りとして、2018年12月に発効したTPP11(環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定)や2019年2月に発効予定の日EU・EPA(日EU経済連携協定)などをはじめとする我が国の経済連携協定の取組を整理するとともに、自由で公正な共通ルールに基づく貿易・投資の環境整備を一段と進め、企業活動をより活性化することの重要性を述べる。
(日本は、数多くの貿易相手国との間で、経済連携協定の取組を推進)
経済連携協定(EPA:Economic Partnership Agreement)とは、2つ以上の国・地域の間で、貿易の自由化に加え、投資、人の移動、知的財産の保護や競争政策におけるルール作り、様々な分野での協力の要素等を含む、幅広い経済関係の強化を目的とする協定である。
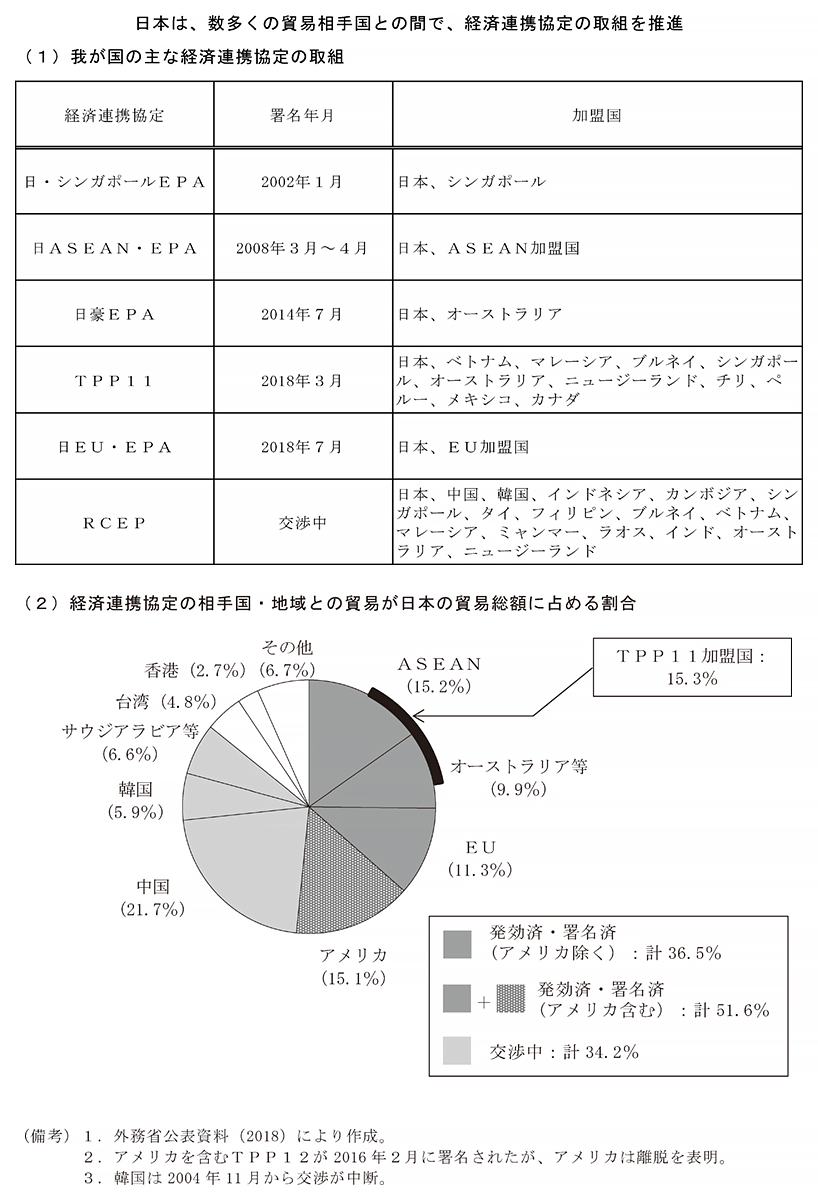
こうした多国・地域に亘る協定について、我が国の取組をみると、2000年代から、シンガポールやASEAN、オーストラリアをはじめ各国・地域との間でEPAを締結してきたことに加え、最近ではTPP11、日EU・EPA、RCEP(東アジア地域包括的経済連携)など、より幅広い分野を含むEPAを推進している(前掲第3-3-13図(1))。我が国は、これまで21か国・地域との間で、18のEPAが発効済・署名済となっている。こうした発効済・署名済のEPA相手国との貿易が、日本の貿易総額に占める割合は約51.6%(アメリカを除くTPP11の場合は約36.5%)となっているほか、発効済・署名済EPAに加えて交渉中EPA相手国との貿易が貿易総額に占める割合は約85.8%に達している15(前掲第3-3-13図(2))。
(TPP11や日EU・EPAは我が国経済にプラスの効果が見込まれる)
2018年12月から2019年2月にかけて、TPP11及び日EU・EPAという巨大な地域を包括する経済連携が発効することになる。TPP11は、アジア太平洋地域においてモノの関税だけでなく、サービス、投資の自由化を進め、さらには知的財産、金融サービス、電子商取引、国有企業の規律など、幅広い分野で21世紀型のルールを構築する経済連携協定であり、参加国の世界のGDPに占めるシェアは約13.5%に達する。また、日EU・EPAについては、日本とEUとの間で、自由で、公正な、開かれた国際貿易経済システムの強固な基礎の構築を目指し、物品市場アクセスの改善、サービス貿易・投資の自由化、国有企業・知的財産・規制協力などルールの構築等を含むものであり、日EUを合わせると世界GDPの約28.3%のシェアを占める。
こうしたTPP11及び日EU・EPAの経済的な効果については、内閣官房(2017)で分析結果が示されている。具体的には、応用一般均衡モデル(GTAPモデル)を用いて、TPP11及び日EU・EPAの効果により、日本経済が新たな成長経路(均衡状態)に移行した時点(10~20年を想定)におけるGDP水準の押上げ効果のシミュレーションを実施している。このシミュレーションでは、関税率等の外生的な変化を契機として、価格や貿易数量に変化が生じ、それを受けて、国内における各種主体の行動が変化し、①所得増が需要増、投資増へとつながり、②貿易開放度上昇が生産性を押し上げ、③実質賃金率上昇が労働供給を拡大する、といった動きにつながる成長メカニズムを内生させている。
分析結果をみると、まず、TPP11の効果について、我が国の実質GDPは、TPP11が無い場合に比べて、約1.5%押し上げられると見込まれる。これは、2016年度のGDP水準で換算すると、約8兆円に相当する。その際、労働供給は約0.7%増加すると見込まれ、これは2016年の就業者数ベースに人数換算すると、約46万人に相当する(第3-3-14図(1))。
次に、日EU・EPAの効果について、我が国の実質GDPは、日EU・EPAが無い場合に比べて約1%押し上げられると見込まれる。これは、2016年度のGDP水準で換算すると約5兆円に相当する。その際、労働供給は約0.5%増加すると見込まれ、これは2016年の就業者数ベースに人数換算すると、約29万人に相当する(第3-3-14図(2))。
これらの分析結果は相当な幅をもってみる必要はあるものの、経済連携協定によって、貿易面でのメリットに加え、マクロ経済全体でのプラスの効果が見込まれることから、自由で公正な共通ルールに基づく貿易・投資の環境整備を一段と進め、企業活動をより活性化することの重要性が改めて示唆される。