第1章 日本経済の現状と課題(第3節)
第3節 景気回復の持続性とリスク
本節では、戦後最長の景気回復期間に並んだ可能性が高い今回の景気回復の特徴についてこれまでの長期の景気回復期と比較することで確認するとともに、景気回復の持続性とそのリスクについて検証する。
1 現在の景気回復の特徴
2012年末から続く今回の景気回復局面は、2018年末で6年となり、戦後最長の景気回復と並んだ可能性があるが、今回の景気回復の特徴を、6年間景気回復が続いた第14循環(2002年1月を谷とし2008年2月まで)やバブル景気(第11循環:1986年11月を谷とし1991年2月まで)など長期間続いた景気回復と比較することなどにより確認する。
(過去の長期景気回復局面との主要指標の比較)
今回の景気回復期間(2012年11月を谷)は、第14循環(2002年1月を谷とし2008年2月までの73か月)と並んで戦後最長となった可能性がある。ここでは、今回の景気回復局面について、いざなぎ景気(1965年10月を谷とし1970年7月までの57か月)、バブル景気(1986年11月を谷とし1991年2月までの51か月)、第14循環と比較する。
まず、各回復期における名目GDPの平均成長率をみると、高度経済成長期のいざなぎ景気では年率18.4%、バブル景気では同7.0%と圧倒的に高い伸びとなっている(第1-3-1図(1)(2))。これは実質GDPが高い伸びだったことに加え、GDPデフレーターがいざなぎ景気で約6%、バブル景気で2%弱上昇したことも要因である。ただし、第14循環と今回の景気回復局面とを比較すると、実質GDPの伸びは今回が年率1.2%とやや低いものの、デフレではない状況を実現したことで、名目GDPの伸びは年率1.8%と今回の景気回復局面の方が高くなっている。
次に消費者物価の動向をみると、デフレの期間を含む第14循環では、年率でほぼ横ばいだったのに対し、今回の景気回復局面では年率1%弱とバブル景気とおおむね同程度の上昇を実現している(第1-3-1図(3))。
さらに、就業者数の期間累計での増加幅をみると、今回は375万人と、いざなぎ景気の期間よりも多く、バブル景気とおおむね同程度の高い増加幅となっている(第1-3-1図(4))。
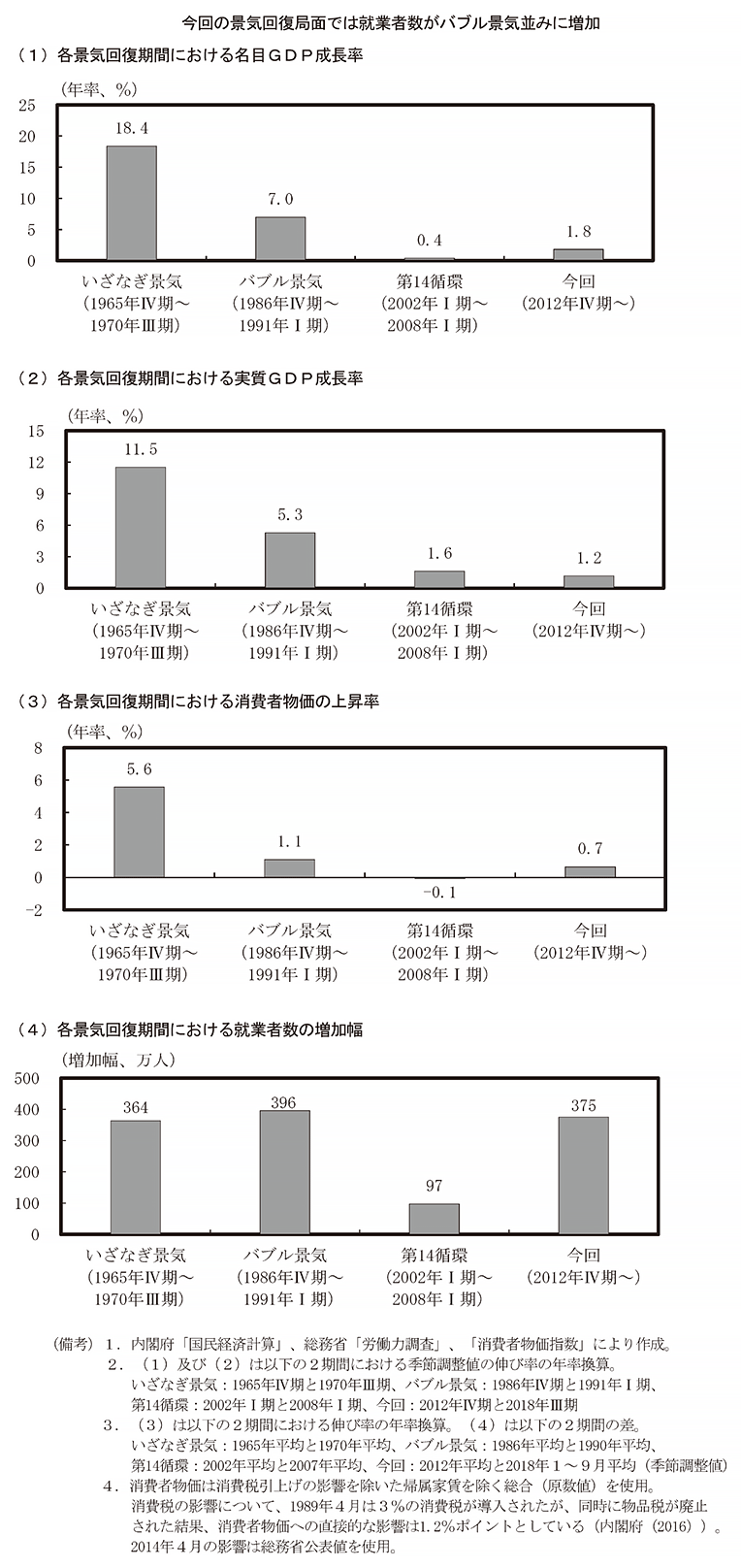
(潜在成長率の動向)
潜在成長率の動向を長期的にみると、バブル期にあたる1990年頃までは4%台で推移していたが、バブル崩壊以降、1%台に大きく低下した(第1-3-2図)。この背景には、①バブル期の大幅な投資によって積み上がった資本ストックの過剰が意識されるようになり、資本投入の伸びの寄与が低下したこと、②労働時間の短縮や生産年齢人口の伸びの低下もあり、労働投入の伸びの寄与が大きく低下したこと、③ICT資本の利活用の遅れや設備の老朽化等により、全要素生産性の伸びが低下したことがある。こうした潜在成長率の低下傾向は、2000年代においても、デフレ・マインドが定着し設備投資が伸び悩むなど資本投入の伸びが鈍化することや、生産年齢人口が減少を続け労働投入が減少する中で継続した。他方、2012年末から始まる今回の景気回復局面においては、潜在成長率が上昇に転じている。この背景には、保育の受け皿拡大や高齢者雇用の促進などの各種政策の効果もあって、女性や高齢者の労働参加が増加したこと等により、少子高齢化に伴う人口減少の中で就業者数が増加し、長期的に潜在成長率を下押ししていた労働投入要因がプラス寄与に転じたことや、企業の投資意欲の回復から資本の成長寄与がプラスに転じたことが挙げられる。
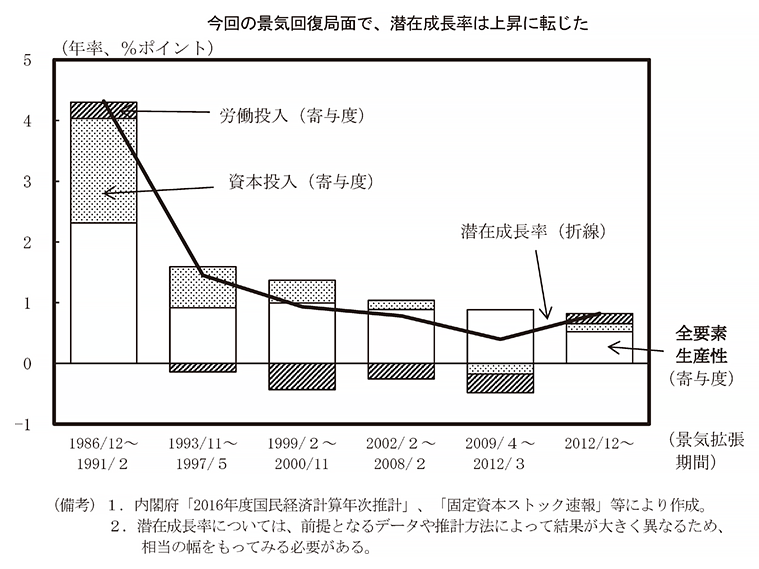
(地域別の景況感)
これまで我が国経済全体の動向をみてきたが、ここでは、地域別の景況感をみることで、今回の景気回復が各地域にどのように広がっているかを確認する。
地域別の企業の業況判断DIをみると(第1-3-3図)、第14循環では、外需の寄与が大きかったこともあり、業況判断DIがマイナスからプラスまで地域ごとに大きなばらつきがみられた。その後、世界金融危機の影響を受けた2008年後半から2009年前半にかけて、また、東日本大震災のあった2011年には全ての地域で大きなマイナスとなった。今回の景気回復局面では、雇用・所得環境が大幅に改善し、内需主導の成長となる中、全ての地域でプラスとなり、地域ごとのばらつきも小さく、景気回復の各地域への広がりが確認できる。
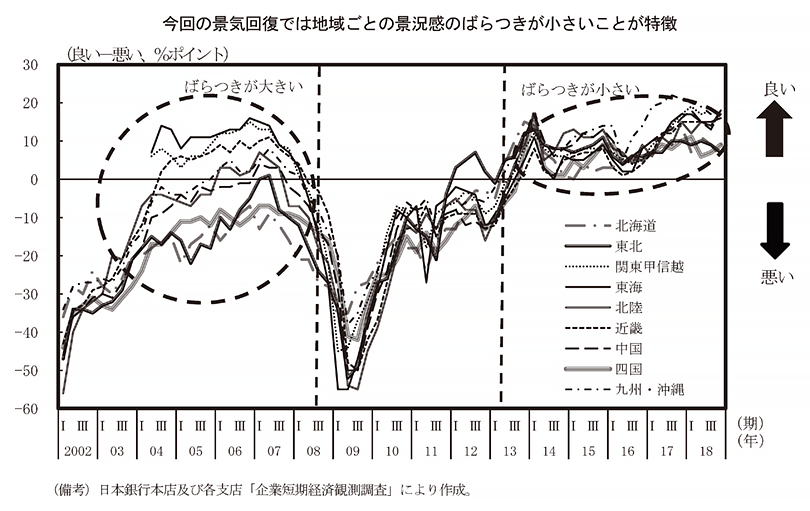
(設備投資の長期動向)
設備投資(名目ベース)の動向を長期的にみると、2009年度以降、設備投資は増加基調で推移している(第1-3-4図)。設備投資の水準も第14循環の景気回復期を上回り、1994年以降のSNAの現行基準で最高水準となっている1。
設備投資の対GDP比の推移をみると、景気の悪化局面ではGDPの減少以上に設備投資が減少するので、GDP比は低下し、景気回復期には上昇する傾向があるが、今回の景気回復局面ではおおむね15%程度となっており、この水準は2000年代半ばと同程度であり、バブル期に比べると低くなっている。
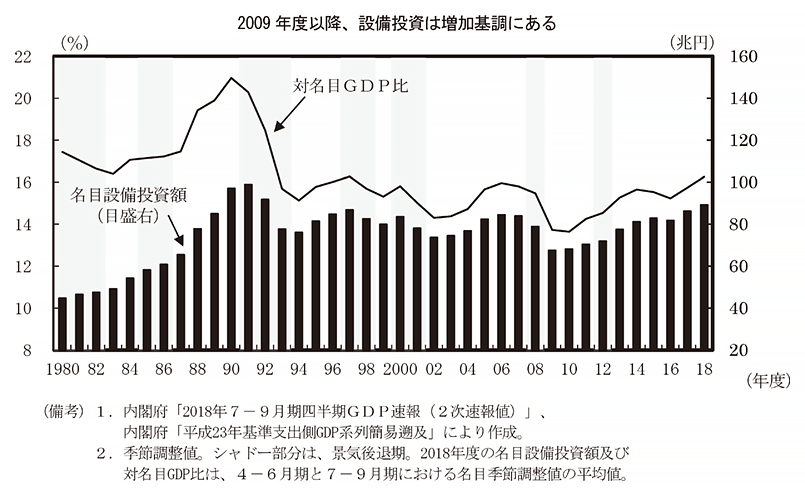
このように、設備投資額が高い水準となっている背景には、既に第1節で述べたように、IoTや電気自動車などの技術革新に対応した投資が活発になっていることに加え、建設投資が、民間部門におけるインバウンド需要を背景としたホテルの建設や都市部の再開発の進展などもあって堅調となっていることがある。建設投資は、住宅や商業施設の建替等を背景に20年程度の周期(クズネッツ循環)があることが知られている。民間非住宅事業の建設投資について、長期循環とそれ以外に分けてみると、長期循環にあたる建替需要による押上げがみられるほか、長期循環を除いた動きをみても、2010年代初めから建設投資額が増加しており、事業所、商業、宿泊施設など幅広い用途で開発事業が進んでいると考えられる(第1-3-5図)。
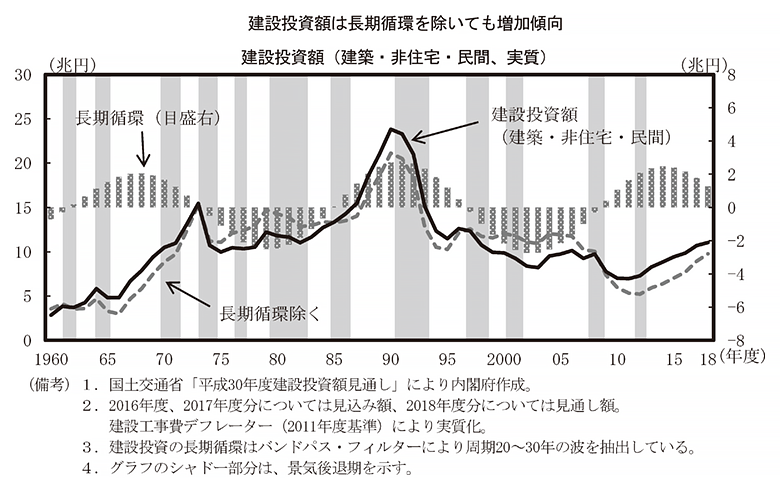
(企業収益の長期動向)
企業収益の動向をみると、景気回復の長期化もあり企業収益は改善を続け、2000年代の景気回復期の水準も大きく超え、過去最高水準となっている。経常利益のGDP比をみても上昇を続けており、2000代半ば頃は10%程度であったが、2017年度には15%と大きく水準を高めている(第1-3-6図)。
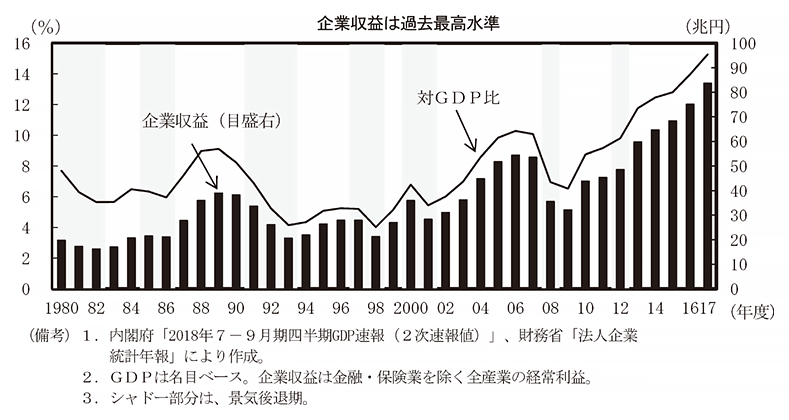
こうした企業収益の改善の背景には、企業の稼ぐ力の回復とともに、外部環境である交易条件の改善、実質実効レートの減価傾向、金利の低下等も影響していると考えられる。
輸出価格を輸入価格で除した交易条件の動向をみると(第1-3-7図(1))、2000年代初めから2008年にかけて原油価格が1バレル当たり30ドル台から110ドルを超える水準まで上昇したこともあり、交易条件は大きく悪化した。リーマンショックの影響もあり原油価格が一時急落したことにより、交易条件は2009年にかけて大きく改善したものの、その後は、再び悪化した。今回の景気回復局面では、原油価格が、新興国の景気減速による需要の伸び悩みや主要産油国における生産量の増加などにより、2014年後半から2016年にかけて大きく下落したことなどを背景に、交易条件は大きく改善した。こうした交易条件の改善は、企業収益が改善を続けた一因にもなっていると考えられる。ただし、ドバイ原油価格は、OPEC等の減産合意の進展や、アメリカによる対イラン経済制裁の再開懸念などから2018年10月には1バレル80ドル程度まで上昇した後、イラン産原油の継続輸入が一部の国に許可されたこと等を背景に12月には60ドル程度まで下落するなど、大きく変動している点には留意が必要である。
実質実効為替レートの動向を長期的にみると、プラザ合意後の1980年代後半、90年代半ば、2000年代初、2000年代末のリーマンショック後に急速に円高方向となる局面があったが、傾向としては徐々に円安方向に推移しており、今回の景気回復局面ではさらに円安方向で推移している(第1-3-7図(2))。このように為替レートが円安方向で安定して推移していることは、輸出企業を中心に業績の改善に寄与していると見られる。
金利について、短期金利の動向をみると、2000年代前半から半ばにかけてゼロ金利政策をとっていたことからおおむね0%で推移した。その後、金利引上げにより2000年代後半に0.5%程度まで上昇したものの、2008年末頃から、再び0%程度で推移し、景気を下支えしている(第1-3-7図(3))。長期金利の動向をみると2000年代はおおむね1.5%程度で推移したが、今回の景気回復局面では、日本銀行の金融政策の効果もあり0%程度にまで低下しており、長期金利の低さも企業の利払い負担の軽減に寄与している。
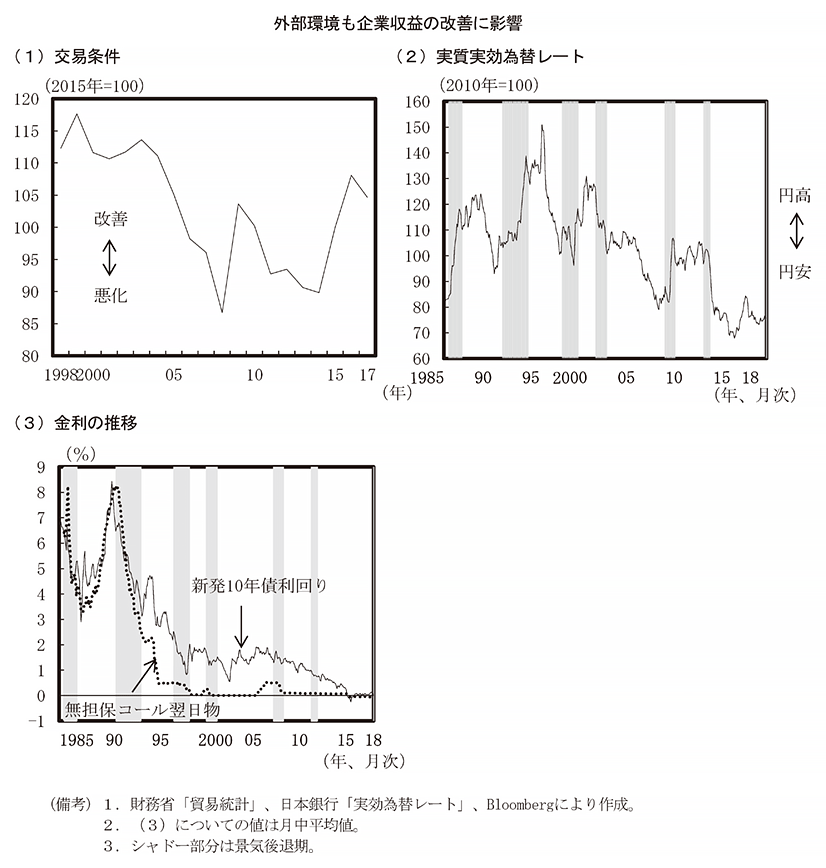
(雇用環境の長期動向)
今回の景気回復の特徴の一つは、雇用環境が大きく改善したことにある。失業率と有効求人倍率の長期的な推移をみると(第1-3-8図)、有効求人倍率は、バブル期の91年には1.4倍程度まで上昇し、第14循環の際は2006年頃に1倍を超える水準にまで達したが、今回の景気回復局面では、1.6倍を超える水準にまで上昇しており1974年以来の水準となっている。この水準はいざなぎ景気の水準よりも高く、歴史的にも高水準であることがわかる。
失業率は、2000年代初頭やリーマンショック後の2009年から2010年にかけて5%程度まで上昇したが、その後は改善を続け、足下では2%台前半とバブル期並の低水準となっている。
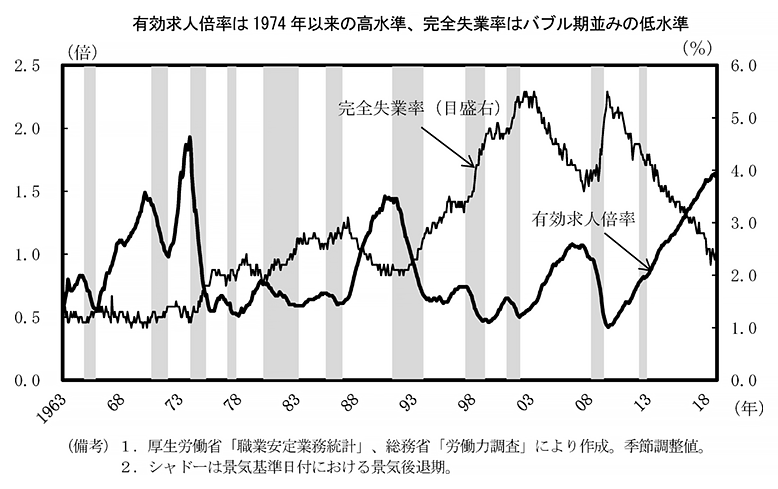
このように、今回の景気回復局面では、有効求人倍率が1974年以来の高水準となっているが、人手不足への対応は今回の景気回復の大きな課題でもある。そこで、有効求人倍率と労働生産性の上昇率を過去の長期の景気循環(バブル期、第14循環)と比較する。
有効求人倍率をみると、すでにみたとおり、今回の景気回復局面では、バブル期のピークである1.45倍や第14循環のピークである1.07倍を超える高水準となっている(第1-3-9図)。
一方、労働生産性の伸びを比較すると、今回の局面では年率0.6%にとどまっており、4%程度だったバブル期はもとより、1.3%であった第14循環よりも低くなっている。
人手不足感が高まる中、限られた労働力を効率的に活用し、経済活動を高めることが不可欠であり、労働生産性の向上が現在の日本経済にとって最重要課題の一つである。
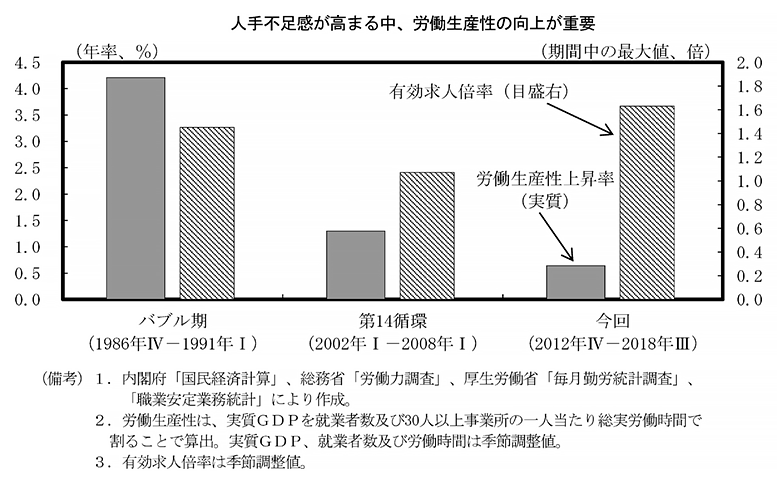
(技術革新に伴う新たな財・サービスによるによる牽引)
これまでの長期間続く景気回復局面に共通する事象として、技術革新に伴う新たな財・サービスによる牽引があったことが考えられる。
技術革新による財・サービスの普及について、長期的な景気回復期間と併せてみると(第1-3-10図)、いざなぎ景気の期間にはカラーテレビや乗用車、クーラーのいわゆる3Cが大きく伸びることで景気を下支えした。
バブル期においては、乗用車の普及率が増加を続けるとともに、ルームエアコンの普及も大きく上昇した。この時期には、カラーテレビは100%に近い普及率となっており、乗用車やルームエアコンも半分以上の世帯に普及した。
第14循環の景気回復期には、90年代からのインターネットの普及を引き続き受け、いわゆるIT革命が進展する中、パソコンやインターネットが急速に普及し、企業でもインターネット関連の会社が大きく業績を伸ばした。
今回の景気回復局面(2012年11月を谷)では、スマートフォン、eコマースの急速な普及に代表される第4次産業革命の技術革新が新商品・サービスを生み出しており、ライフスタイルの急速な変化や新たなビジネス機会の飛躍的拡大がもたらされている。
今後は2020年頃を目途に第5世代の通信も予定されており、それに伴いSociety 5.0の実現がより一層進むと見込まれる。こうした新技術の進展は、投資を喚起するのみならず、我々の生活をより豊かで便利なものにするとともに生産性向上などを通じて潜在成長率の引き上げももたらすと期待される。
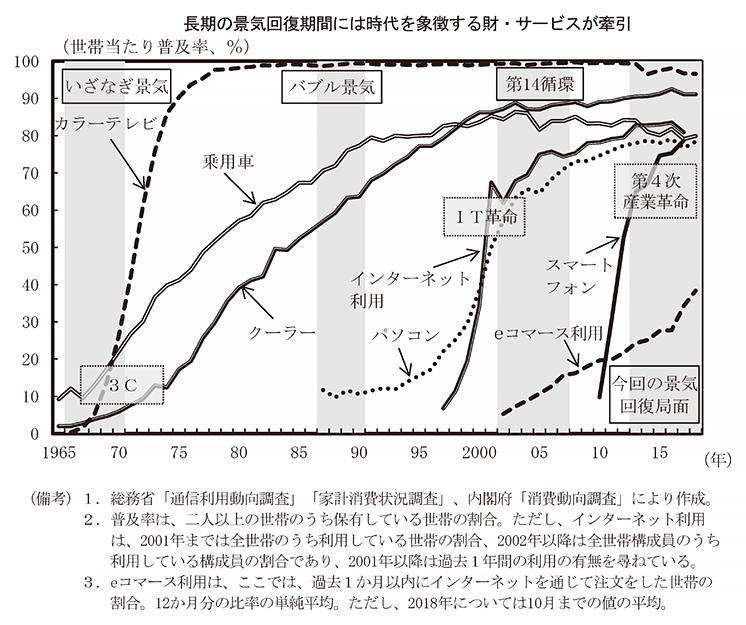
2 景気回復の持続力の展望とリスク
ここでは戦後最長の景気回復となった可能性が高い今回の景気回復の持続力について、景気循環の観点から考察するとともに、リスク要因として海外の動向を中心に確認する。
(在庫循環の動向)
自律的な景気循環を引き起こす要因としては、短期的には在庫循環要因、中期的には設備投資循環要因が指摘されることが多い。まず、在庫循環の状況について確認する。
在庫循環の典型的なパターンとしては、景気回復の初期には、まず出荷の増加に伴ってそれまで積み上がっていた製品在庫が減少に転じ、次に在庫調整が進展して在庫が適正水準に近づくと生産の増加テンポが速まって在庫の減少が止まり、さらに景気が成熟化して出荷の増勢が鈍化すると在庫が増加に転じる。景気後退局面に入ると、出荷が減少する中で、在庫が積み上がっていく。こうした動きを、出荷と製品在庫の増加率について、グラフ上にプロットすると、期を追って右回りに回転する図が描かれることになる。在庫管理の厳格化などもあり、かつてと比べて明確な循環を示さなくなっているとの指摘もあり、あくまで出荷在庫動向の背景にある実際の経済の動向をみることが重要ではあるものの、ここではこれまでの長期の景気回復の在庫循環の状況を確認する。
バブル期の動向をみると、初期は出荷の増加に伴い、在庫の減少が続き、その後は生産増が在庫の増加を上回ることで出荷、在庫ともに前年よりも増加した(第1-3-11図)。1989年には出荷の増加ペースが鈍化する中、在庫の増加が大きくなり、その後、出荷の増加は続いていたものの在庫の増加が上回り1991年に景気の山をつけた。
第14循環は、景気回復の初期段階では出荷の減少が続く中、生産調整をそれ以上に行うことで在庫を減らし、出荷が増加に転じた後も在庫の水準が減少した。その後、出荷の増勢が鈍化するとともに在庫は増加に転じ、リーマンショック直前の2008年に景気の山を迎えた。
今回の景気回復局面では、13年半ばまでは出荷が減少する中、生産調整が進むことで在庫は減少し、13年半ば以降出荷がプラスに転じる中、消費税率引上げ前の駆け込みもあり在庫は大きく減少した。14年半ばからは出荷が減少に転じる中、在庫が大きく増加した。16年後半からは世界経済の回復もあり出荷がプラスに転じる中、在庫が減少していたが、17年後半からは再び在庫がやや増加している。また、18年7-9月期には自然災害の影響もあり、出荷が減少したが、その後は出荷がプラスに戻っている。
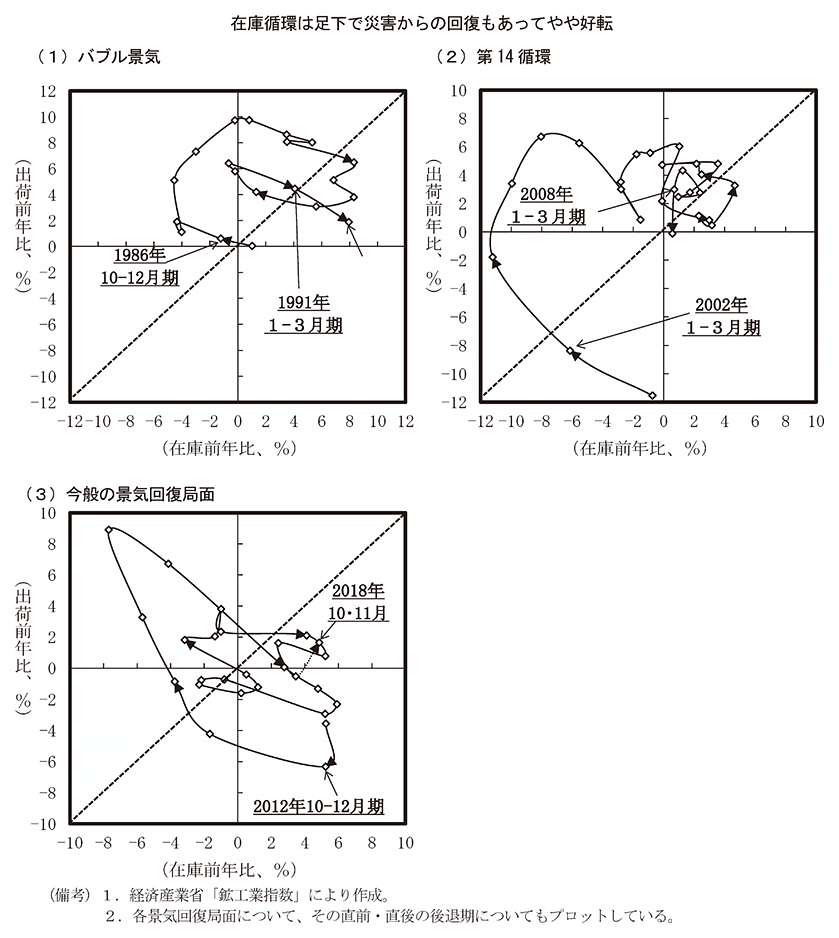
(設備投資の循環の動向)
今回の景気回復局面において、設備投資は増加を続けており、景気回復の寄与度も最も高くなっている。民間設備投資は国内総生産に占めるウェイトが大きいだけでなくその変動も大きく、景気循環でも大きな役割を果たしている。また、設備投資は、GDPを構成する最終需要であるとともに、企業の資本ストックの追加であり、供給能力の強化に直接つながるものである。
こうした特徴のある設備投資の資本ストック循環図をみると、バブル景気も第14循環においても景気回復の前半においては設備投資が増加するにつれ、資本ストックに対する投資の割合も上昇し、資本ストックが高まり新規の投資の伸びが鈍化するとともにグラフ上で右下の方向にシフトしている(第1-3-12図)。
今回の局面では、設備投資の増加が続いており、資本ストックに対する新規の投資の割合も基本的には上昇を続けている。少し詳しくみると、2013年以降、設備投資が前年比で大きく伸びることで資本ストックに対する設備投資の割合が上昇し、右方向にシフトしている。一時的に投資の伸びがやや鈍化する中、資本ストックに対する投資の割合の上昇が止まったが、2017年後半から再び設備投資の伸びが大きくなっている。
資本ストック循環において右上への移動が続いていることは、企業の予想成長率が高まっていることが考えられる。設備不足感はバブル期並みの不足感となっていること、設備投資計画も高水準を維持し、かつ幅広い業種での増加が見込まれていること、人手不足感の高まりにより省力化投資のニーズが高いこと、さらには電気自動車の開発やSociety 5.0に向けた投資の必要性が高まっていることを踏まえると、当面、設備投資は増加が続くと見込まれる(付図1-14)。
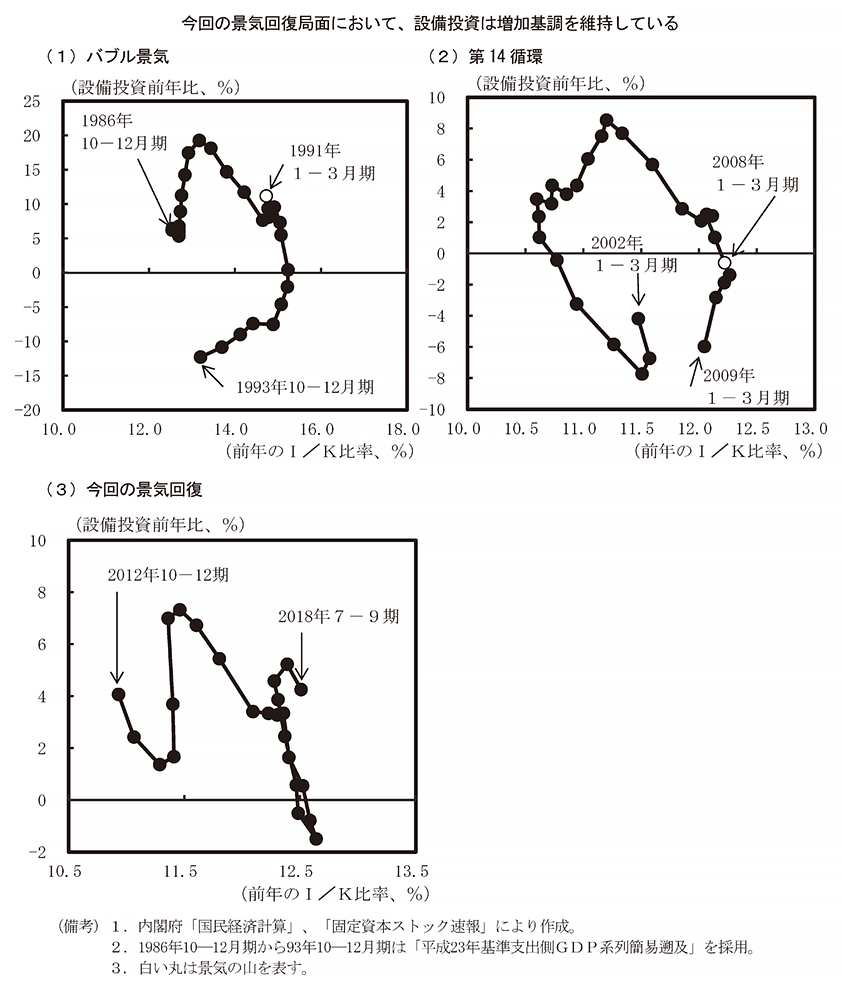
(東京大会後の主なプロジェクト)
また、今回の景気回復局面では建設投資が長期的な傾向からみても強い動きとなっていることを既に述べたが、2020年東京大会後はその反動によって建設投資が縮小するのではないかとの懸念を指摘する声もある。そこで、2020年東京大会後の建設投資の主な計画をみると、リニア中央新幹線や整備新幹線、高速道路、市街地再開発事業といった生産誘発効果の高い大規模プロジェクトが継続ないし計画されており、特に鉄道関係は総事業費1兆円を超えるプロジェクトが長期にわたって継続的に施工されることが予定されている。こうしたことから、引き続き国際競争力の強化や地域の活性化など中長期的な成長につながるインフラ投資が官民資金によって行われていくことが見込まれる。(付表1-15)。さらに2025年に大阪での万博開催が決まり、会場建設費で1,250億円などの事業が予定されている。
また、内閣府の「インフラ維持補修・更新費の中長期展望」によると、社会資本の維持補修・更新費は2015年度時点で約9兆円であるのに対し、およそ40年後の2054年度時点には約16兆円にまで上昇すると試算されている2。高度経済成長期以降に集中的に整備されたインフラが一斉に老朽化していく中で、今後インフラ維持補修・更新の需要は長期的に高まっていくものと見込まれる。
こうした大規模プロジェクトの進行、さらにはインフラ維持補修・更新の需要増加がプラスに寄与することにより、2020年東京大会後の建設投資は日本経済を一定程度押し上げていくと期待される。
(海外経済のリスク及び今後の見通し)
第1節でも述べたように、情報関連財の調整や中国経済の持ち直しの動きに足踏みがみられることもあり、輸出の伸びが鈍化する中で、現下の景気回復の大きなリスクとしては、米中間の通商問題の動向の影響、海外経済の不確実性、金融資本市場の変動の影響が挙げられる。
まず、国際機関による世界経済の見通しをみると、2018年、2019年ともに3%台半ばと緩やかな成長が続くと見込まれている(第1-3-13図(1))。ただし、2019年の見通しについては、成長率の見通しを若干下方修正していること、またマクロ経済政策による下支えが次第に弱まるとともに、通商問題の影響、金融環境の引き締まり等の逆風が続くと見込んでいる点には注意が必要である。
世界貿易の見通しについても、世界経済の緩やかな回復を背景に、経済成長率を若干上回る程度の伸びが見込まれているが、通商問題の動向や先進国における金利引上げによる新興国からの資金流出などのリスクが指摘されている(第1-3-13図(2))。
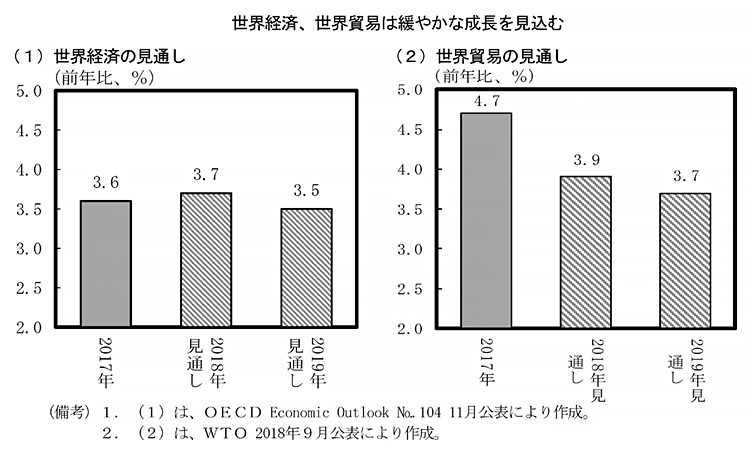
こうした国際機関による予測を踏まえた上で、個別のリスク要因について考察してみよう。
第一は、米中間の通商問題の動向が世界経済や我が国経済に与える影響である。詳しくは第3章第3節において分析を行うが、現状においては、中国からアメリカへの輸出は引き続き増加し、日本の中国への輸出動向にも大きな変動はないことから、米中間の追加関税引上げによる直接的な影響は、現時点では限定的なものと考えられる。ただし、追加関税措置が長期化したり、さらに関税率引上げの対象範囲が拡大するような場合には、当事国・地域の経済により深刻な影響が生じるとともに、日本を含む当事国以外の国に対しても、グローバルなサプライチェーンなどを通じて影響を及ぼす可能性がある。また、通商問題を巡る不透明感が長く継続することによって、各国・地域の企業活動が慎重化し、設備投資等にも影響が及ぶ可能性があることには留意する必要がある。
第二に、中国経済の動向である。中国政府が、民間部門の過剰債務に対応するため債務の削減を進めているが、中国経済の持ち直しの動きに足踏みがみられる中、中国政府は企業の資金調達緩和のための対応を進めるなど、景気安定に配慮する姿勢を強めている。今後、再び債務が急増することがないか、その動向に留意する必要がある。また、不動産価格についても、価格抑制策がとられている。過剰債務問題の深刻化や不動産価格の大幅な変動は、銀行のバランスシートの毀損や融資態度の慎重化につながり、中国経済を下押しする可能性がある。また、過剰債務の削減や不動産価格の上昇抑制のため、中国政府が過度の金融引締めや急速な金融規制の強化を行った場合も中国の経済成長を押し下げる要因となり得る。こうした問題が顕在化し、中国経済が減速した場合、その影響が我が国との貿易や世界経済への影響を通じて我が国経済にも大きな影響を及ぼす可能性もあるため、その動向に注視が必要である。
第三に、アメリカの金融引締めが過度になった場合の金融資本市場への影響である。アメリカでは、景気回復に伴い物価が緩やかに上昇する中で、2015年から政策金利を累次にわたり引き上げており、2018年には四度の引上げが行われた。今後もアメリカでは堅調な景気回復を背景に政策金利の引き上げと保有資産の縮小金融政策の正常化に向けた動きが継続することが見込まれているが、その際、引締めのペースが景気回復の持続性と整合的なペースであるのか、また、アメリカにおける拡張的な財政政策による財政赤字の拡大などにより長期金利の上昇テンポが急激なものにならないかといった点は注視する必要がある。
加えて、アメリカの金利上昇による新興国からの資本流出など新興国経済への影響についても注視が必要である。この点については、2018年夏には、トルコとアメリカの政治的対立やトルコの政策の不透明感を背景にトルコ通貨リラが急落したほか、アルゼンチン通貨ペソも急落するなど、新興国の中でも経済のファンダメンタルズが脆弱な国の通貨の下落や、資金流出が懸念されている。そこで、新興国の脆弱性をみるために、経常収支、外貨準備高、短期債務の状況を確認すると、トルコ、アルゼンチンでは、経常収支が大幅な赤字となっている一方で、外貨準備高の短期対外債務残高に対する比率も1倍程度となっており、他の新興国と比べて脆弱性が高い状況がみられている(第1-3-14図(1)(2))。アルゼンチンではIMFの支援により、また、トルコでは大幅な利上げ等の安定化策によって、その後は通貨の安定が図られているほか、他の新興国も比較的安定した状況となっているが、引き続き注視が必要である。
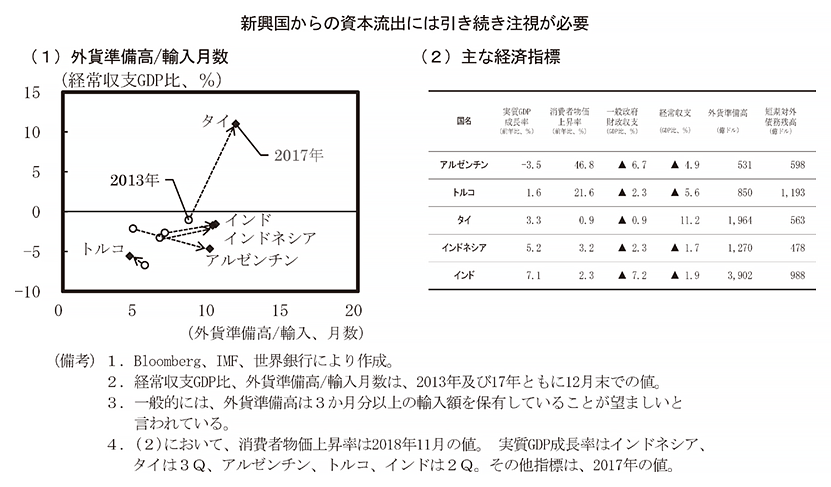
第四に、英国のEU離脱の行方をはじめとする欧州経済の動向についても注視が必要である。この点について、第3章第3節において分析を行うが、仮に、英国が何の取り決めもないままにEUから離脱した場合には、2019年3月29日以降、英国とその他EU加盟国との貿易において、通関手続きや関税の支払いが生じるほか、英国・EU双方の規制・ルールへの対応が必要になるなど、現地に進出している日本企業への影響は大きいと考えられる。また、マクロ経済的にみても、EU離脱による英国への経済的影響は大きいとみられることから、英国のEU離脱による我が国の貿易・投資への影響、金融資本市場を通じた影響などが懸念される。我が国としては、これまで、英国のEU離脱が日本経済や日本企業の現地法人の経済活動に与える影響を最小化すべく、英国・EU双方にあらゆるレベルで働きかけてきたところであり、引き続き、英国とEUの間の離脱交渉の動向を注視する必要がある。またイタリアやフランスなどで財政政策の動向が不透明になっており、こうした動向にも注視が必要である。

