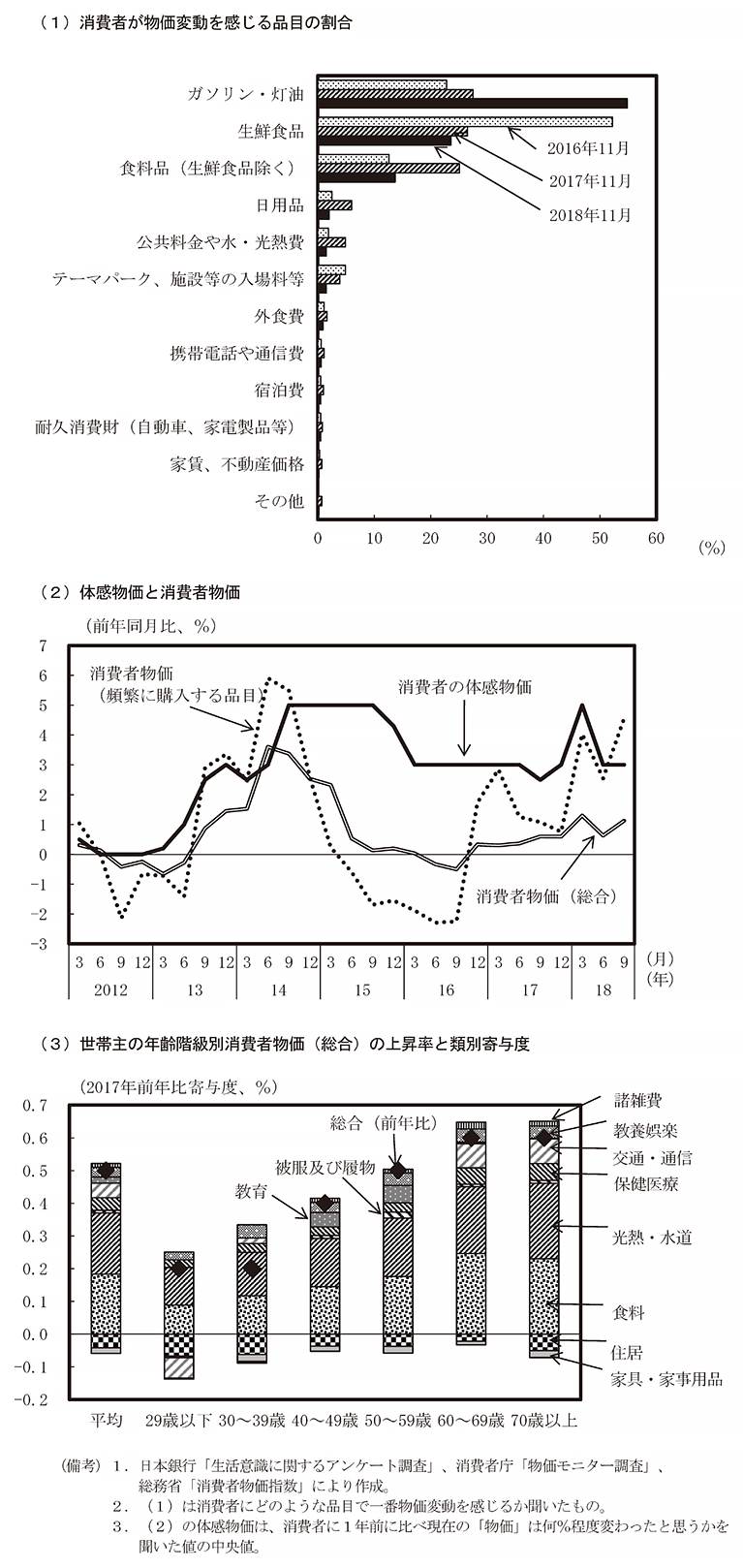第1章 日本経済の現状と課題(第2節)
第2節 労働市場と物価の現状と課題
我が国経済が長期にわたる景気回復を続ける中で、雇用環境は着実に改善しているものの、企業の人手不足感は四半世紀ぶりの高水準となっており、人手不足への対応が大きな課題となっている。一方、物価を取り巻く環境をみると、長期にわたる景気回復によりGDPギャップがプラス傾向で推移し、企業の人手不足感も高まる中で、人件費が緩やかながら上昇するなど、物価上昇圧力は高まってきているとみられるものの、物価上昇のテンポは2018年に入って鈍化している。
本節では、労働市場について、最近の雇用の動向や企業の人手不足感の高まりの状況を概観するとともに、女性や高齢者等の今後の労働供給拡大の余地について確認する。また、物価の状況について、2018年春以降に消費者物価の上昇テンポが鈍化している要因を分析し、今後の物価上昇に向けた課題を探る。
1 労働市場の状況
最近の労働市場をみると、就業者数が2018年に入ってから大幅に増加し、失業率も2%台前半まで低下するなど雇用は着実に改善を続けている。他方で、企業の人手不足感も四半世紀ぶりの水準に高まっており、一部の企業の業況にも影響がみられている。こうした人手不足感の高まりに対応するためには、技術革新による省力化を進めつつ、労働供給の増加をさらに促していくことが必要となっている。近年の就業者数の増加には、特に、女性や高齢者の労働参加が大きく寄与しているが、就業を希望する非労働力人口もまだ多く存在していることから、就労環境の整備や求人と求職のミスマッチの改善等を図ることで、就労をさらに促進する余地があると考えられる。
また、近年は外国人労働者数も増加している。人手不足感が極めて高い業種において外国人労働者を受け入れていく仕組みの構築が進んでおり、2019年4月より新たな在留資格の導入が予定されている。
以下では、最近の雇用動向や企業の人手不足感の高まりの状況について概観するとともに、特に近年増加が著しい女性や高齢者の就業状況や外国人労働者の動向を確認した上で、今後の労働供給のさらなる拡大に向けた課題について考える。
(雇用者数は2018年も大きく増加)
雇用者数は、2012年から17年の5年間で280万人増加し、年率60万人弱程度の増加ペースであったが、2018年に入ってからは増加幅が大きく高まり、1月から9月までの平均で2017年平均を102万人上回る高い伸びとなっている1(第1-2-1図(1))。特に15~24歳の若年の雇用者数の伸びが大きい。2018年1月から9月までの雇用者数の増加の内訳をみると、男性については、25~64歳の非正社員が前年比で9万人減少する中で、25~64歳の正社員が15万人増加しており、女性についても、25~64歳の正社員が19万人増加するなど、正社員として就労する者が増加している。他方、非正社員については、男性の15~24歳及び65歳以上で増加しており、女性については、全ての年齢階層で増加している。こうした雇用動向の背景については、労働需要の一層の高まりを反映して、定着率の高い正社員としての雇用が高まるとともに、非正社員の賃金面等での待遇が改善する中で新たに労働参加が進んだ可能性が考えられる2。
また、産業別の雇用者数をみると(付図1-6)、過去5年間の傾向としては、医療・福祉、卸売・小売業、情報通信業、学術研究・専門技術サービス業などで堅調に増加しており、2018年は特に宿泊・飲食サービス業の伸びが大きくなっている。正社員、非正社員別に産業別の雇用者数をみると、情報通信業、学術研究・専門技術サービス業では正社員の雇用の伸びが高く、卸売・小売業、宿泊・飲食サービス業では非正社員の伸び高く、医療・福祉では正社員・非正社員ともに伸びが高い傾向がみられる。
全体の労働供給量をみる上では、雇用者数だけでなく、それぞれの雇用者が働く労働時間も考慮する必要がある。そこで、雇用者数に1人当たりの労働時間を乗じたマンアワーの労働供給の推移をみてみると(第1-2-1図(2))、2013年以降は雇用者数が増加する中でマンアワーの労働供給も増加傾向にあるが、一人当たりの労働時間が減少傾向にあるため、マンアワーベースでみた労働供給は雇用者数の伸びと比べて緩やかな増加にとどまっている。こうした一人当たりの労働時間の減少には、パートタイム労働者比率の上昇などが背景にあると考えられる。後述するように、就業時間の増加を希望しているパートタイム労働者も多くいることから、労働供給を増やしていくためにも、就業時間の壁となっている諸制度を見直していくことも重要である。
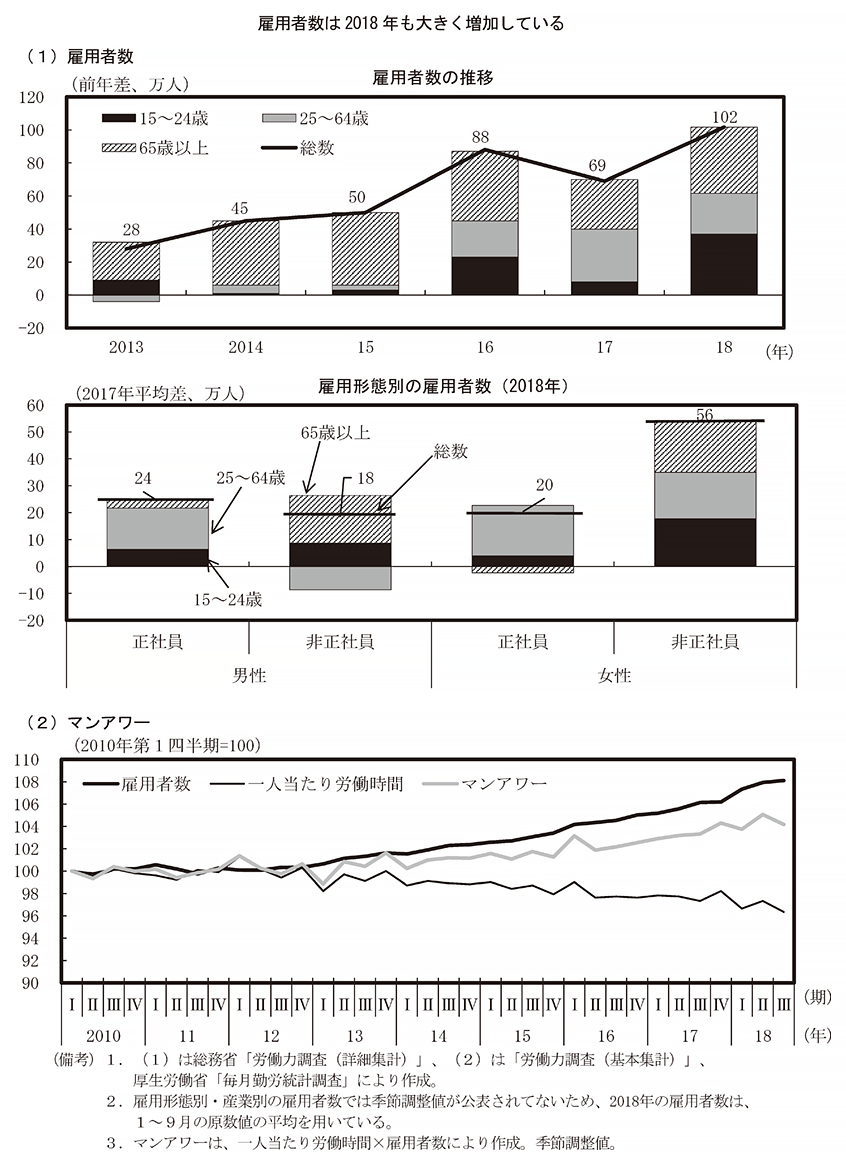
(完全失業率は低下しているが、ミスマッチの解消が重要)
完全失業率は2018年11月時点で2.5%と、約25年ぶりの低水準となっている。こうした完全失業率の低下の背景について、労働需給の改善や企業の求人条件の内容の変化等がどのように影響しているかをみるために、総務省「労働力調査(詳細集計)」により、仕事につけなかった理由別の完全失業者を2012年と18年で比較すると(第1-2-2図)、「希望する種類・内容の仕事がない」及び「求人の年齢と自分の年齢とがあわない」、「条件にこだわらないが仕事がない」と答えた者の減少幅が大きくなっている。そこで、「希望する種類・内容の仕事がない」と答えた者を年齢階級別にみると、15~34歳の若年層や35~44歳の中年層での減少幅が大きく、好調な新卒採用市場等を背景として自身が希望する仕事に就きやすくなっていることがうかがえる。また、「求人の年齢と自分の年齢があわない」と答えた者を年齢階級別にみると、35~64歳の中高年者の減少幅が大きくなっており、人手不足への対応策として、求人における年齢要件を緩和し、転職市場における中高年者の採用に積極的になっている企業も増えてきていることが推測できる。
一方で、「勤務時間・休日などが希望とあわない」、「賃金・給料が希望とあわない」等の理由を答えた者は小幅な減少でとどまっており、求人と求職のミスマッチが存在していることもうかがわれる。こうしたミスマッチを解消するためには、柔軟な働き方の普及や募集賃金の引上げ等が課題である。
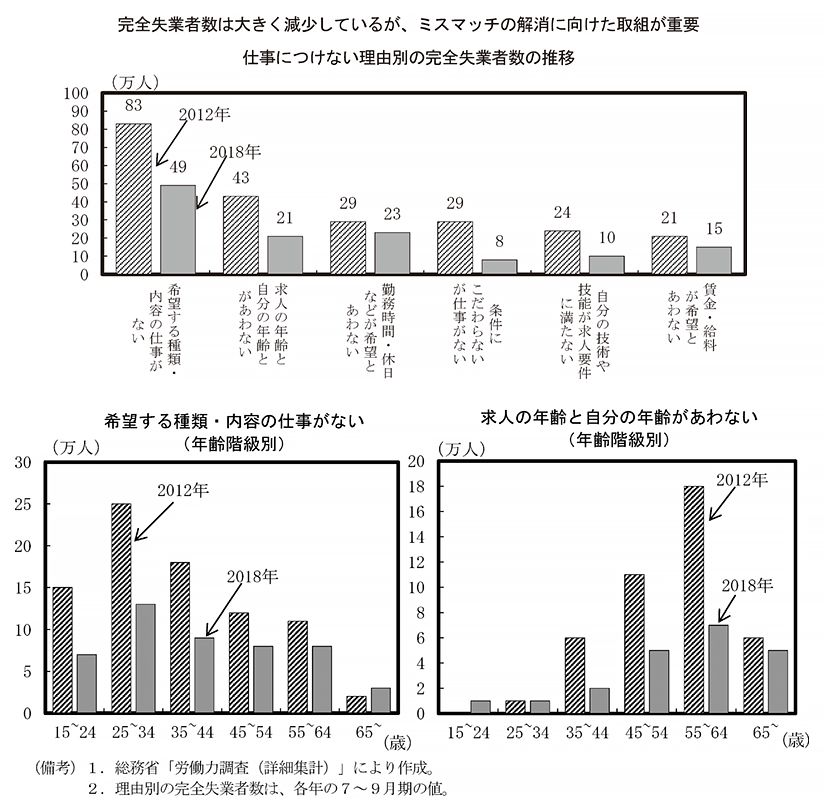
(人手不足感が高まっているが、業況判断との差も拡がっている)
雇用者数の増加や完全失業者数の減少により労働供給が増加しているものの、長期にわたる景気回復を背景として労働需要が高まっていることから、日銀短観でみた雇用人員判断による人手不足感は、1980年代後半から1990年代初めのバブル期以来の水準となっている(第1-2-3図(1))。ただし、雇用人員判断と業況判断の推移をみると、バブル期には、業況判断と雇用人員判断の水準が同程度となっていたのに対して、今回の景気回復局面においては、業況判断の水準以上に人手不足感が高まっている。
産業別に業況判断と人手不足感とを比較すると、宿泊・飲食サービス業、対個人サービス(医療・福祉など)、運輸・郵便業、卸売・小売業などのサービス業で差が大きくなっている。これらの産業では、バブル期においても業況判断と人手不足感に差がみられており、こうした業種がバブル期と比べて経済に占める比率が高まっていることも、マクロでみた人手不足感と業況判断の乖離につながっていると考えられる3。一方で、製造業や建設業では、雇用人員判断と業況判断の水準の差が小さく、好調な業績や景気回復等に伴う業務量の増加が人手不足感の高まりにつながっていることがうかがえる。
次に、人手がどれだけ不足しているのかについて、厚生労働省「雇用動向調査」により未充足求人を産業別にみると(第1-2-3図(2))、卸売・小売業や宿泊・飲食サービス業で多く、それに医療・福祉や製造業、建設業が続いており、製造業や建設業では従業員100人未満の小企業での未充足求人が多くなっている。また、職業別にみると、サービス職や専門・技術職4、販売職などで未充足求人が多くなっている。専門・技術職では、小企業での未充足求人が特に多くなっており、大企業と比べて小企業では専門・技術職の人材を確保することが難しくなっていることがうかがえる。
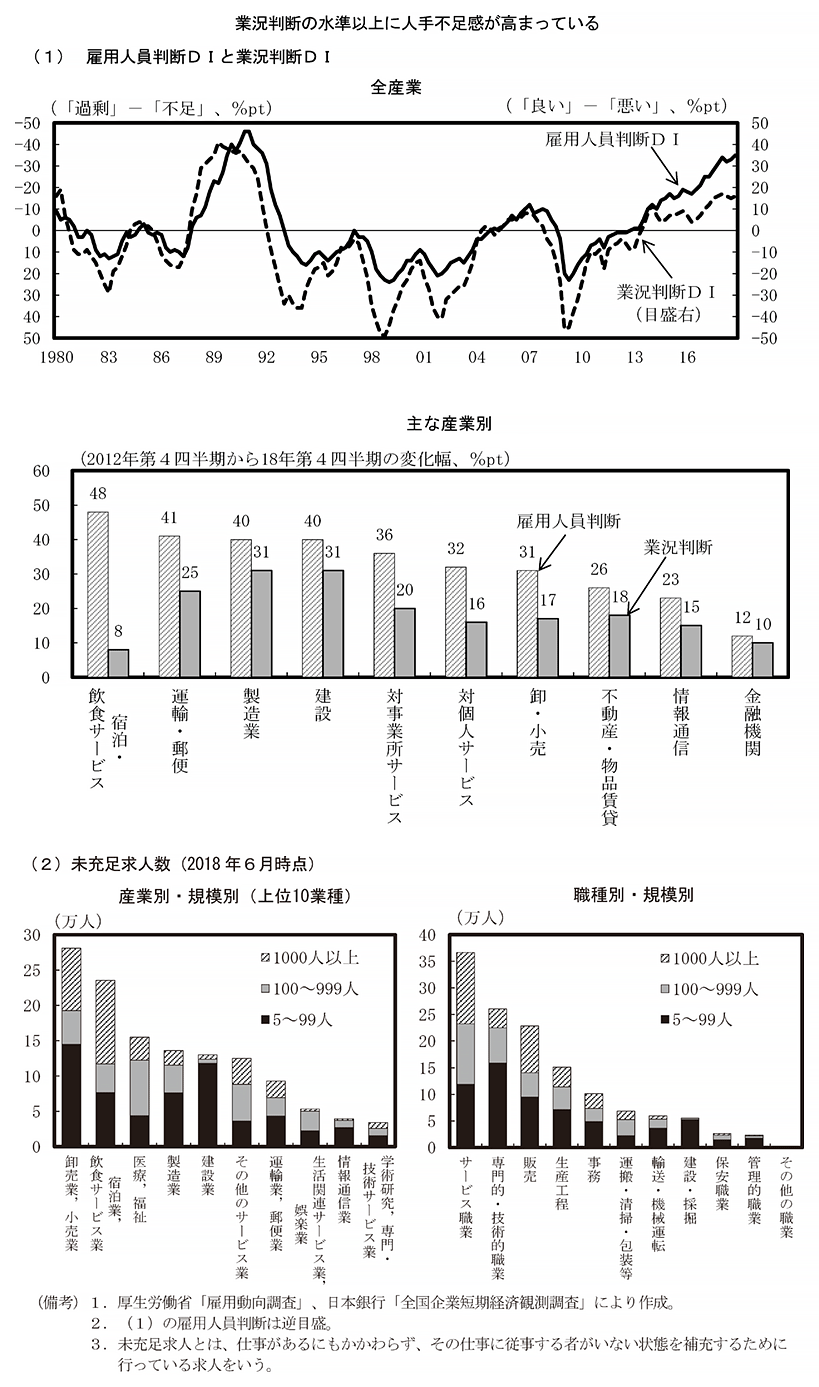
(育児をしている女性の有業率は大きく上昇している)
2012年から2017年かけての雇用者数の増加280万人のうち、15~64歳の女性や65歳以上の高齢者の雇用者の増加寄与は、それぞれ132万人、178万人となっており、女性や高齢者の就業が近年の雇用増加を牽引している5。以下では、女性及び高齢者の雇用増加の背景について確認する。
2012年から17年にかけての女性の就業者数の増加の背景についてみるため、総務省「就業構造基本調査」により、25~44歳の6歳未満の子の育児をしている女性の有業率と育児をしていない女性の有業率の推移とを比較すると(第1-2-4図(1))、両者共に有業率は上昇しているものの、育児をしている女性の有業率の増加幅は12%と、育児をしていない女性の増加幅4.5%よりもかなり大きくなっている。ただし、育児をしている女性の有業率は、2017年時点で64.4%と、依然として育児をしていない女性の有業率83.6%よりも低くなっている。今後も、柔軟な働き方の普及や待機児童解消に向けた取組の促進等により、育児をしながらでも働きやすい環境の整備をより一層進めていくことが重要である。
同様に、結婚している女性と独身の女性の有業率の推移を比較すると(付図1-8)、25~44歳で結婚している女性の有業率の増加幅が大きくなっている。そこで、結婚している女性の就労動機の背景を確認するために、夫の年収と妻の就業率との関係をみると(第1-2-4図(2))、夫の年収が高いほど妻の就業率が低下するとともに6、フルタイム・短時間労働比率については、夫の年収が高いほど短時間労働比率が高くなる傾向がみられる。ただし、2012年と2017年を比較すると、全ての年収階級で就業率が高まっており、特に年収500万円以上の中高所得者層で短時間労働での就労比率が大きく高まっている。
リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査2018」により夫の年収階級別にパート・アルバイトとして働いている理由をみると(第1-2-4図(3))、夫の年収が高いと、「自分の都合の良い時間に働きたいから」と答える割合が多く、「家計の補助・生活費・学費等を得たいから」と答える割合が小さくなっている。総務省「労働力調査(詳細集計)」によると、2013年以降は「自分の都合の良い時間に働きたいから」と答える非正社員の女性が増加していることから、人手不足への対応などから都合の良い時間に高い時給で働けるような職場環境が増えていることもあり、高所得世帯においても、短時間労働者としての就業が増加している可能性がある。
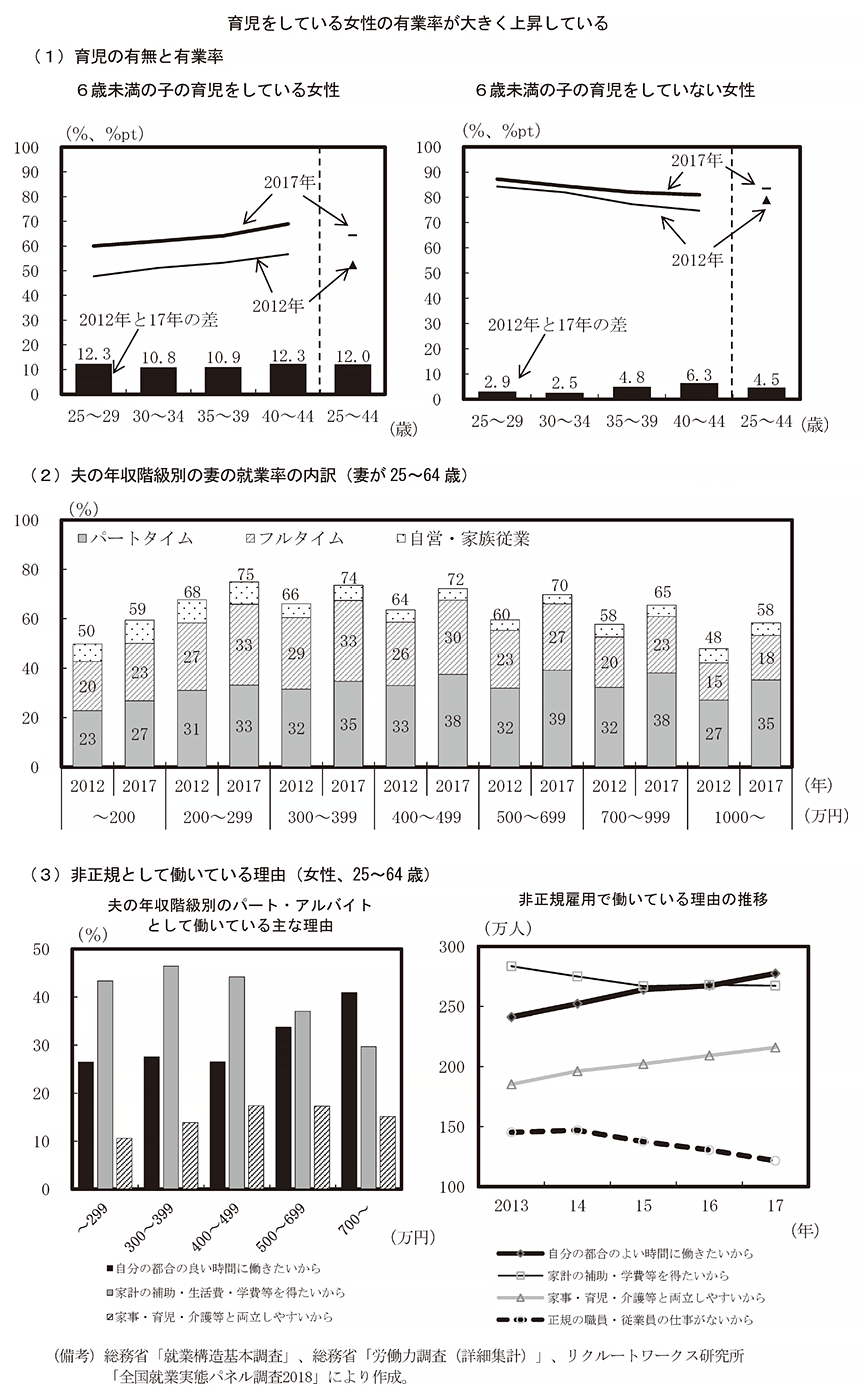
(高齢者の就業者数は増加しているが、経験や技能の活用には課題もある)
次に、高齢者の就業状況をみると(第1-2-5図(1))、2012年から17年にかけての年齢階級別の就業率は、65~69歳では37%から44%、70~74歳では23%から27%、75歳~79歳では13%から15%と上昇しているが、80歳以上の高齢者の就業率についてはほとんど変化していない。ただし、60~64歳から65~69歳にかけての就業率の低下幅は依然として大きい。高齢者の就業を促進していく観点からは、60歳代後半を中心として、さらに、70歳代にかけての就業率を高めていくことが課題である。65歳以上の高齢者の就業者数は、2002年の482万人から17年は807万人にまで達している。これには、各年齢階級における就業率の上昇に加えて、団塊の世代(1947年~1949年生まれ)が2012年から17年にかけて65歳~70歳へとなっていることも影響している。一方で、2017年以降は団塊の世代が70歳に達しており、2022年には75歳、2027年には80歳と就業率が大幅に低下する年代へと達することから、高齢者の就業者数の伸びを維持していくためには、高齢者のスキルアップや健康維持の促進とともに、より一層高齢者が就業しやすい環境整備を進めていくことが必要となる。
65歳以上の高齢者が就業している産業別の割合を男女別にみると(第1-2-5図(2))、男女ともに卸売・小売業や農林業、製造業での就業割合が高くなっているが、男性については運輸・郵便業や建設業で就業する者も多く、女性については医療・福祉、宿泊・飲食サービス業で就業する者が多くなっている。職業別にみると、女性では運搬・清掃・包装等、サービス職、事務職で就業する者が多くなっているが、男性については、幅広い職業で就業していることがわかる。
高齢者雇用安定法に基づき7、継続雇用制度等による65歳までの高年齢者雇用確保措置は導入されているが、66歳以上で働ける制度のある企業は3割程度となっており8、65歳以上で就業している高齢者の多くは、離職後に再就職しているものと推測される。そこで、リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査2018」を用いて、定年により離職して転職した高齢者が離職後に就いている業種・職種の転換状況をみると(第1-2-6図(1))、業種・職種ともに転換している高齢者が約半数となっている。一方で、業種・職種の転換状況別の年収をみると、業種・職種ともに転換している高齢者の年収が低くなっている。定年後に専門性を活かした仕事ができるよう、高齢者が学び直しを行う機会を充実させていくことが重要である。
また、高齢者が仕事をしている理由をみると(第1-2-6図(2))、「現在の生活費のため」、「現在の生活費を補うため」という収入面を挙げる人が多いが、他方で、より高齢の人ほど「健康を維持するため」、「社会とのつながりを維持したい」、「社会に役立ちたいから」と答える高齢者も一定数いるため、このような高齢者の多様なニーズに応じた就労機会を企業が提供していくことも重要である。
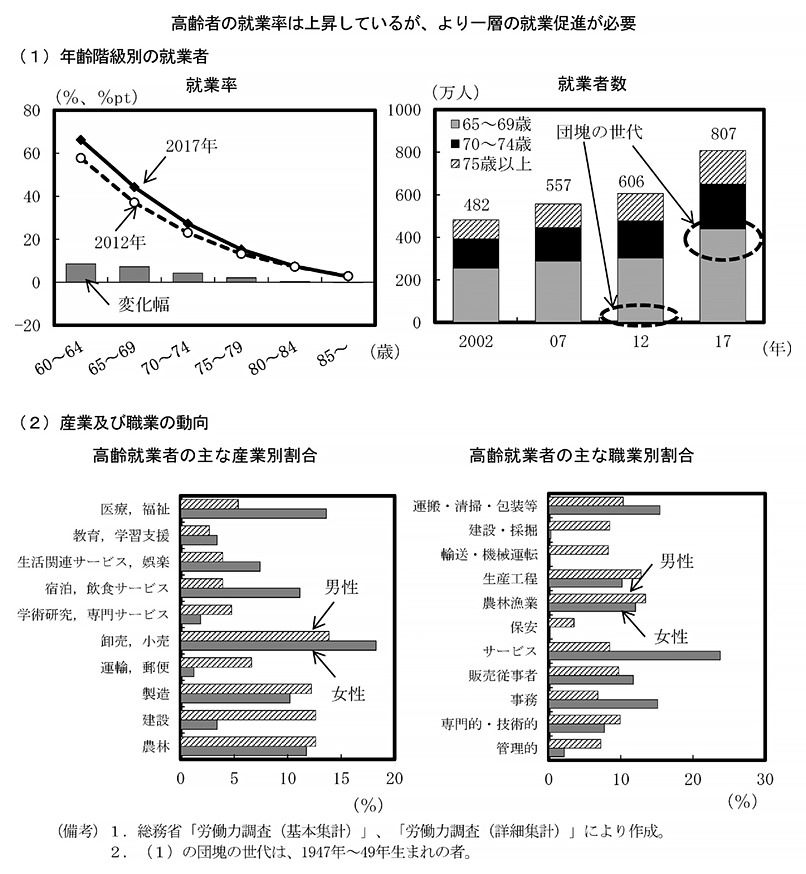
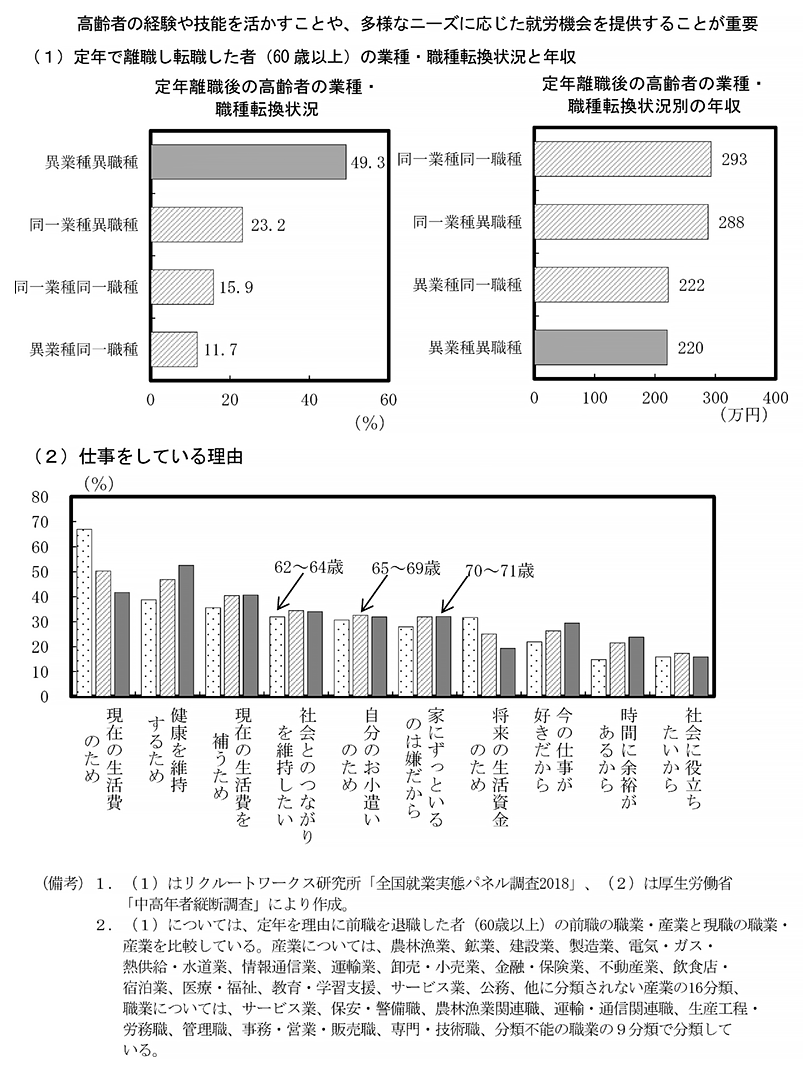
(外国人労働者は5年間で60万人増加している)
我が国で就労する外国人労働者は、2012年の68万人から2017年には128万人に達しており、5年間で60万人増加している(第1-2-7図(1))。外国人労働者の半数以上は、従業員数が100人未満の小規模事業所で就労しているが、従業員数500人以上の大規模事業所での就労も徐々に進んでおり、2017年では2割を超えている。雇用者の総数に占める外国人労働者の割合を算出すると、2012年の1.0%から2017年には1.9%まで増加しており、労働市場に与える影響も大きくなりつつある。
産業別にみると(第1-2-7図(2))、技能実習生が多い製造業で就労する外国人労働者が2017年で39万人と最も多く、伸び幅でみても5年間で13万人増と最大となっている。人数では製造業には及ばないものの、5年間の伸び率でみると、建設業では5倍、卸売・小売業、飲食・宿泊業、運輸・郵便業及び医療福祉では2倍程度となっており、人手不足感の高い業種で外国人労働者の就労が進んでいることがうかがえる。
在留資格別の外国人労働者をみると(第1-2-7図(3))、日本人の配偶者等の身分に基づく在留資格が2017年で46万人と最も多くなっており、次いで、留学生のアルバイトなどの資格外活動が30万人、技能実習が26万人、専門的・技術的分野の在留資格が24万人となっている。在留資格ごとに産業別の就労状況をみると(付図1-9)、身分に基づく在留資格及び技能実習では製造業に従事する者が最も多いが、留学生のアルバイトなど資格外活動では、飲食・宿泊サービス業、卸売・小売業で就業する者が半数以上を占めている。
2019年4月より、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を対象とした新しい在留資格の導入が予定されており、受け入れた外国人労働者が就労しやすい環境を整備していくことが重要である。
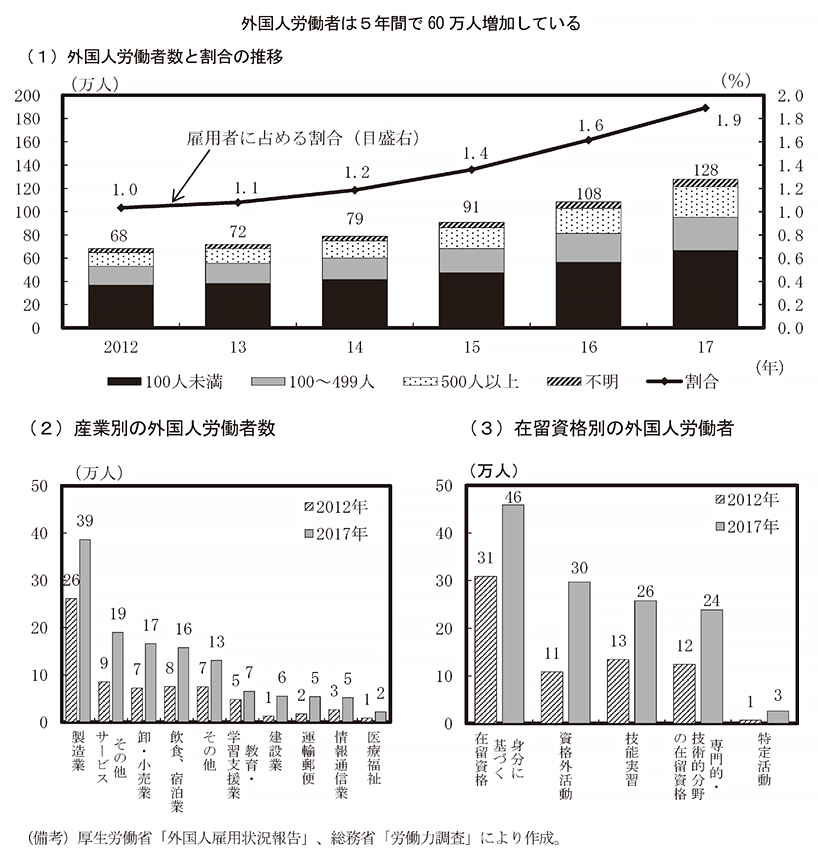
(労働時間の追加を希望する就業者は183万人、就職希望の非労働力人口は275万人)
女性や高齢者など労働参加が進んでいることをみてきたが、今後どれほどの労働供給増加の余地があるかについて、短時間労働者で追加の就業時間を希望する追加就労希望就業者9と就業希望の非労働力人口をみると(第1-2-8図(1))、前者は男性で58万人、女性で125万人となっており、後者は、男性で67万人、女性で208万人となっている。
追加就労希望就業者がいる背景としては、正社員を希望しているにもかかわらず非正社員として就労していることや、就業調整を行っていることが考えられる10。総務省「就業構造基本調査」により、労働時間の就業調整を行っているパート・アルバイトの割合を男女別にみると(第1-2-8図(2))、女性の25~64歳では4割ともっとも高くなっているが、男女ともに、15~24歳では3割程度、65歳以上でも2割程度のパート・アルバイトが就業調整を行っている。2017年に行われたJILPTの調査11によると、必要な労働力を確保するにあたって就業調整が影響していると3割以上の企業が答えている。就業時間の増加を希望する人が就業しやすい環境を整備していくことや、企業が必要な労働力を確保していくためにも、働き方に中立的な税・社会保障制度としていくことが重要である。
また、就業を希望している非労働力人口の非求職理由をみると(第1-2-8図(3))、男性については、「健康上の理由」のほか、「希望する種類・内容の仕事がない」、「自分の知識・能力にあう仕事がない」といった回答が多くなっており、女性については、「勤務時間・休日が希望にあわない」、「育児・子育て」と回答が多くなっている。ミスマッチの解消に向けた取組や子育てをしながらでも就業しやすい環境整備を進めていくことにより、就業を希望している者が就業できるようにしていくことが重要である。
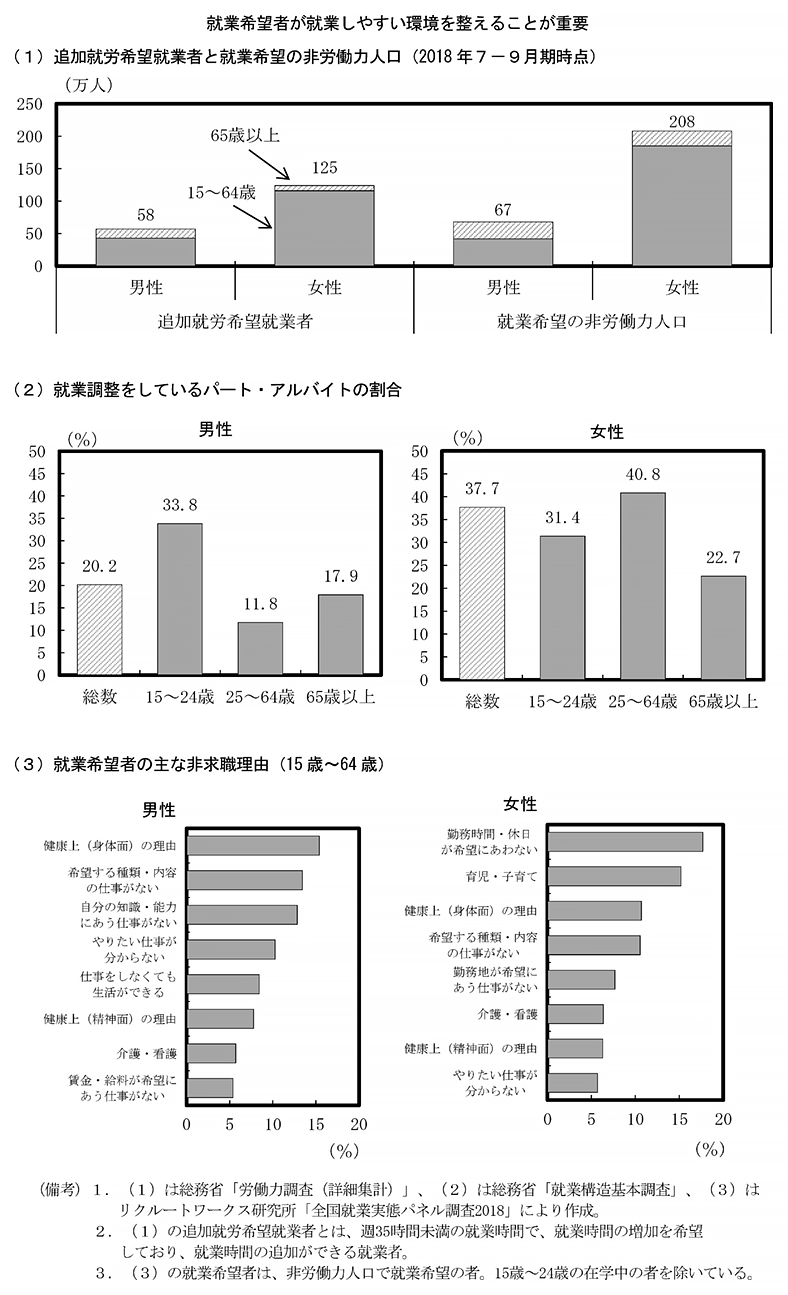
2 物価動向の現状
消費者物価は、振れの大きい生鮮食品及びエネルギーの影響を除くと2017年夏以降は前年比上昇幅が拡大傾向で推移したが、2018年春以降、上昇テンポが鈍化している。以下では、近年の物価動向について確認するとともに、上昇テンポが鈍化している要因について検証する。
(近年の物価の動向)
消費者物価の動向について、生鮮食品を除く総合の前年比(以下「コア」という。)でみると(第1-2-9図(1))、2016年には原油価格低下の影響もありマイナスとなっていたが、原油価格が上昇に転じ、ガソリン等のエネルギーがプラスに寄与したことにより、2017年以降前年比プラスで推移している。2018年に入ってからもエネルギー価格がプラスに寄与しており、2018年後半には原油価格が一段と高水準となったことから、前年比1%程度までコアは緩やかに上昇している。
次に消費者物価の基調について、生鮮食品及びエネルギーを除く総合の前年比(以下「コアコア」という。)でみると(第1-2-9図(2))、2016年における為替の円高方向への動きによる耐久消費財の押下げ効果が2017年央以降徐々に剥落するとともに、人手不足に伴う人件費の上昇や原材料費高騰、宿泊や外食といったサービスに対する需要の高まりなどを背景に、食料品、外食、個人サービス等がプラスに寄与したことなどから、2017年夏以降は前年比上昇幅が拡大傾向で推移した。しかし、2018年春以降、食料品を中心に企業の価格引上げの動きに一服感がみられるほか、家事用耐久財等の耐久消費財や携帯電話通信料による押下げが影響し、コアコアの上昇テンポは鈍化した。
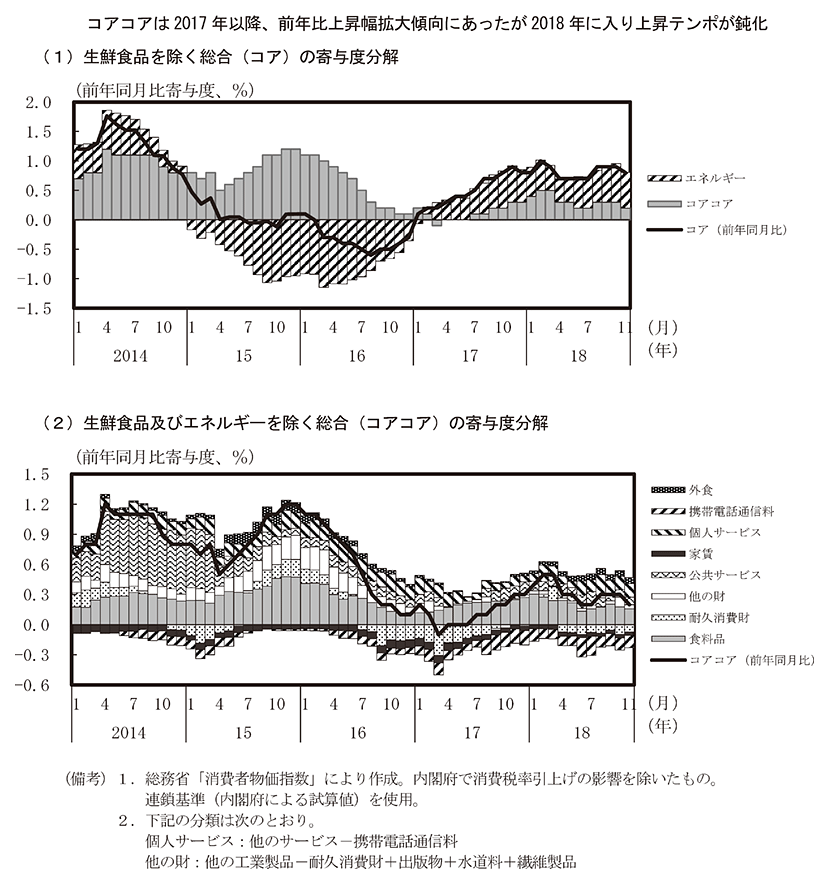
(品目別にみたコアコアの上昇鈍化の背景)
2018年春以降、コアコアの上昇テンポが鈍化したことは上述のとおりであるが、ここでは品目ごとの価格動向について、2017年と比較し詳細に確認する。
コアコアの動向を食料品、耐久消費財、個人サービス、外食に分けてみると、食料品(第1-2-10図(1))は、需要の増加を背景とした牛肉など生鮮肉価格の上昇や、魚介類等の原材料価格の上昇のほか、制度的な要因12による酒類や米などの価格押上げも寄与し、2017年以降、前年比上昇幅は拡大傾向で推移した。ただし、2018年に入り、生鮮肉価格の上昇が一服したことや、酒類価格が徐々に下落したことなどから、同年半ばまで上昇幅が縮小した。ただし、その後、原材料の小麦粉価格上昇等によりパン価格が上昇するなど、やや上昇幅は拡大している。
次に、耐久消費財をみると(第1-2-10図(2))、2016年における為替の円高方向への動きによる耐久消費財の押下げ効果が、2017年後半に剥落し、2017年後半から前年並で推移した。ただし、2018年春以降、耐久消費財は再びマイナス寄与となっている13。その要因としては、特に家事用耐久財による押下げが大きく、電気掃除機、電気冷蔵庫や電子レンジなどがマイナスに寄与した。また、教養娯楽用耐久財については、テレビがマイナス寄与となっており、液晶パネル価格の下落や企業間での価格競争が一因と考えられる(付図1-10)。
個人サービスをみると(第1-2-10図(3))、携帯電話通信料が一貫して大きくマイナスに寄与しているものの、これを除けば前年比プラスで推移している。この背景としてはインバウンド需要の高まりによる宿泊料の上昇や、特に需要が高まっている欧州方面行きの外国パック旅行費の上昇などが挙げられる。また、テーマパーク入場料、月謝額、補習教育なども上昇しており、需要の高まりや人件費上昇を背景とした値上がりがみられる。ただし、上昇テンポについては2018年に入ってからも緩やかなものにとどまっている。
外食をみると(第1-2-10図(4))、2017年夏頃までは前年比上昇幅は縮小傾向にあったが、需要の高まり、原材料費高騰、人件費の上昇を背景に、同年秋以降は上昇幅拡大傾向で推移している。
これらのことから、2017年と比較して2018年以降の上昇テンポが鈍化した背景には、食料品価格の伸びが一時弱まったことや、耐久消費財がマイナスに寄与したことが大きく寄与しており、また、個人サービスの上昇幅も緩やかなものにとどまっていることがあると考えられる。
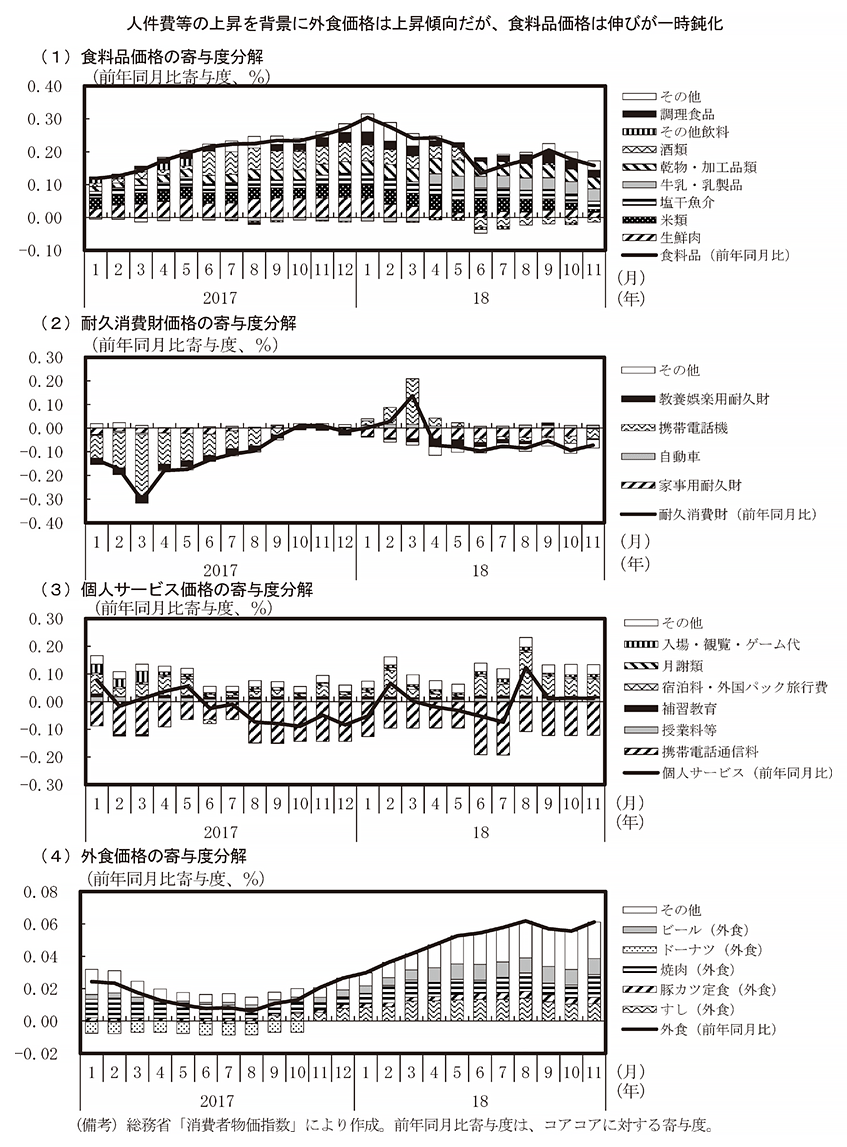
(物価動向の背景にあるマクロ経済的な要因)
こうした物価動向の背景にあるマクロ経済的な要因をみるために、物価変動をもたらす様々な要因と消費者物価上昇率(コアコア)との関係について、時差相関をとると、GDPギャップの拡大は3四半期程度、名目実効為替レートの下落(円の減価)は4四半期程度、消費者の1年後の予想物価上昇率は1四半期程度のラグを伴ってコアコアを押し上げ、輸入比率の拡大は3四半期程度のラグを伴ってコアコアを押し下げることが推計される。この結果を基に、コアコア上昇率の変動を各要因に分解すると(第1-2-11図)、為替レートの影響については、2015年10-12月期以降に円高方向に推移したことにより、2016年7-9月期以降コアコアが押し下げられていたが、為替レートが円安方向に転じたことから、2017年4-6月期をピークに押下げ効果が剥落し、2018年に入り押上げ方向に働いている。また、予想物価上昇率による押上げ効果は、2014年から2016年にかけて縮小傾向にあったが、2017年以降は拡大傾向にある。さらに、GDPギャップが2017年1-3月期にプラスに転じたことにより、2017年10-12月期以降、GDPギャップによる押上げ効果がみられる。ただし、コアコアのGDPギャップに対する弾性値は0.2程度と限定的である。なお、輸入比率は1990年代には10%程度で推移したが、2010年代半ばには20%に迫っており、輸入比率の拡大は、足下では2018年以降押下げ要因となっている。
こうしたマクロ経済的な要因と品目別の動向を併せてみると、GDPギャップがプラス傾向で推移し、労働需給も引き締まり方向にあるなど物価上昇圧力が高まりつつある中で、コアコアの上昇率が加速しない背景としては、①GDPギャップ等による押上げがみられるものの、その効果は限定的であること②為替の円安方向への動きによる押上げがみられるものの、耐久消費財などの価格がむしろ下落していることが挙げられる。また、こうした背景には、今年に入って消費者マインドが弱含む中で、企業による消費者が直面する小売価格への転嫁の動きが一服している可能性が考えられる。以下では、これらの点について、詳しく分析する。
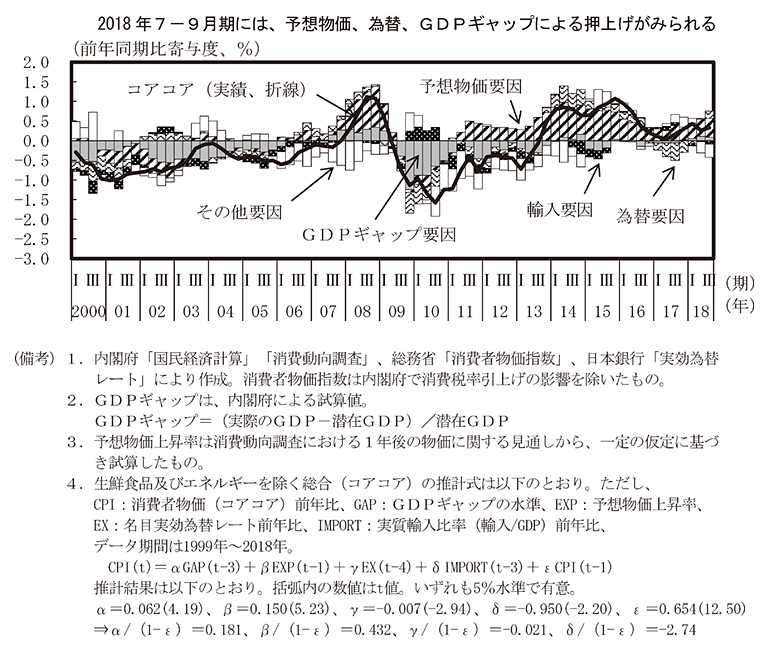
(コアコアに対するGDPギャップ及びULCの影響)
ここでは、GDPギャップがプラス傾向で推移し、経済全体や労働市場の需給が引き締まり方向にある中で、そうした動きが消費者物価に与える影響が弱くなっている可能性について確認する。経済全体の需給動向を示すGDPギャップと、賃金面での物価上昇圧力を示すユニット・レーバー・コスト(以下「ULC」という。)の最近の動向を確認すると、GDPギャップは2017年1-3月期以降プラス傾向で推移し、ULCは賃金の上昇とともに2016年1-3月期以降、前年比でプラス傾向となっている(付図1-11)。
GDPギャップの縮小とULCの上昇が、コアコアの上昇にどの程度影響を及ぼすかについて、物価下落期に入る以前(ここでは1990年~1998年の期間で分析。)、物価下落期(ここでは1999年~2006年の期間で分析。)、今回の景気回復局面(ここでは2013年以降の期間で分析。)の3期間に分け、コアコア全体及び財・サービス別に比較する(第1-2-12図)。
まず、コアコア全体の前年同期比とGDPギャップ、ULCの前年同期比との関係をみると、物価下落期に入る以前は正の相関関係がみられたが、物価下落期には有意な関係がみられなくなり、今回の景気回復局面では、再び正の相関関係が確認できる。ただし、その関係性は物価下落期に入る以前に比べて今回の景気回復局面の方が弱い。
次にコアコアの財価格の前年同期比とGDPギャップ、ULCの前年同期比との関係をみると、物価下落期に入る以前はGDPギャップ、ULCともに正の相関関係がみられたが、物価下落期には有意な関係がみられなくなった。今回の景気回復局面では、GDPギャップとは再び正の相関関係が確認できるが、その関係は、物価下落期に入る以前に比べて弱い。また、ULCについては、今回の景気回復局面においても有意な関係がみられない。同様にサービス価格の前年同期比とGDPギャップ、ULCの前年同期比との関係をみると、物価下落期に入る以前はGDPギャップ、ULCともに正の相関関係がみられたが、物価下落期には有意な関係がみられなくなった。今回の景気回復局面では、ともに正の相関関係が確認でき、その関係性はGDPギャップでは今回の景気回復局面の方が強い一方、ULCでは今回の景気回復局面の方が弱い。
これらを俯瞰的にみると、物価下落期に入る以前に比べ今回の景気回復局面の方がGDPギャップ、ULCとの関係は弱いが、正の相関関係は保たれている。ULCは財価格よりもサービス価格に影響を及ぼし、GDPギャップはサービス価格よりも財価格に影響を及ぼす傾向にあるといえる。消費者物価の安定的な上昇のためには、経済全体の需要の高まりや賃金の上昇が重要であり、特にサービス価格の上昇のためにも力強い賃金上昇が重要である。
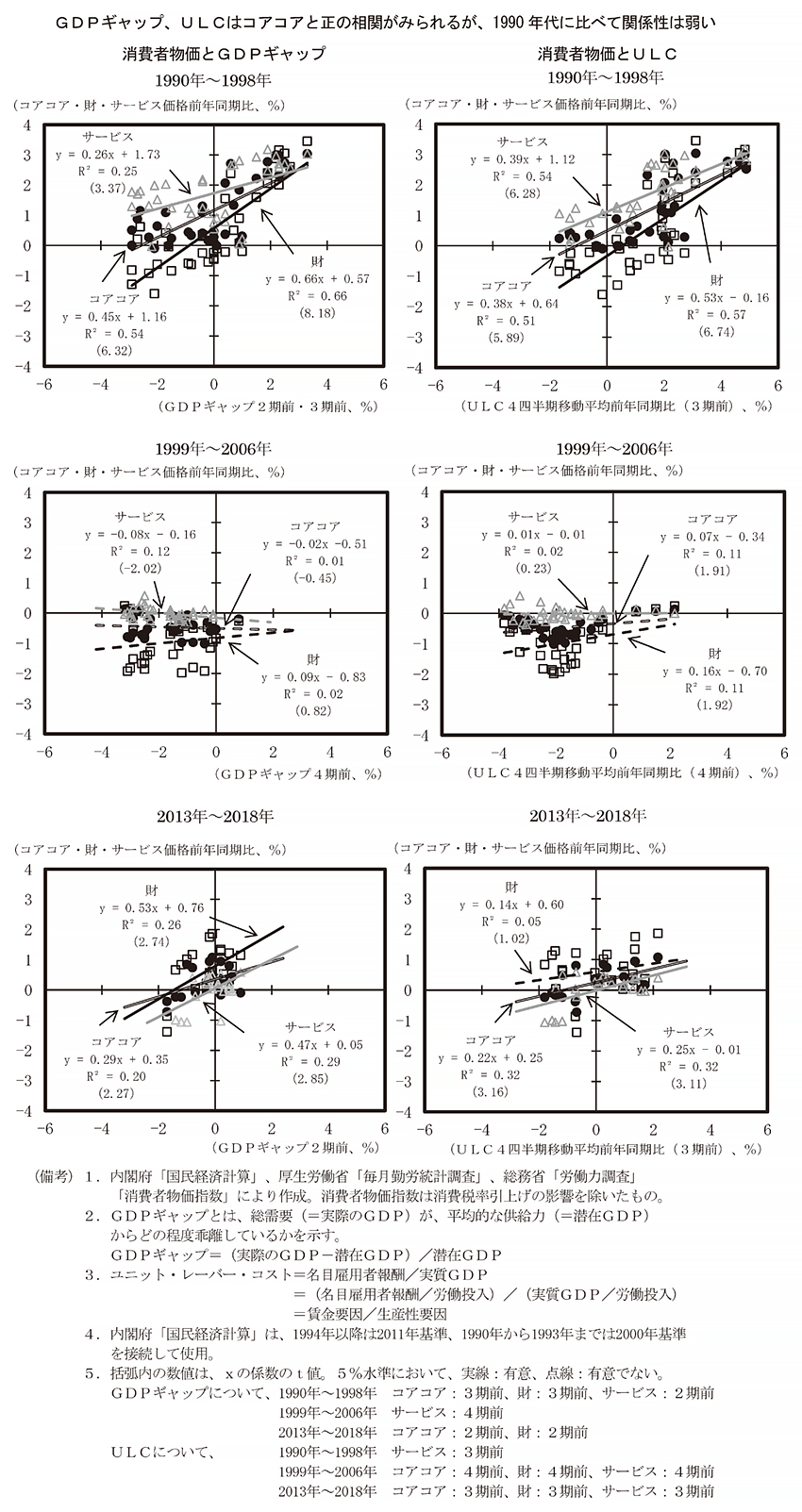
(サービス価格の国際比較)
以上でみたように、ULCとサービス価格の関係は正の相関が保たれているものの、そもそも賃金上昇圧力が緩やかなものにとどまっていることも、コアコアの上昇率が加速しない背景の一つにある。サービス価格について、アメリカやユーロ圏と比べると、日本の伸びは前年比0%近傍とわずかにプラスとなっている程度である(第1-2-13図(1))。サービス物価は生産コストに占める人件費の割合が高く14、財に比べて賃金の影響を受けやすい。そこで各地域の賃金の動向をみると、2017年はアメリカやユーロ圏に比べ、日本の賃金の伸びは小さく、そのためサービス物価も伸びが小さいと考えられる。2008年においても、欧米に比べ日本の賃金の伸びは弱くサービス物価の伸びも弱くなっており、今回の景気回復局面だけでなく、過去も同様の傾向だったと考えらえる。
そこで、日本の賃金、サービス物価の動向を長期的にみると(第1-2-13図(2))、1980年~1990年代には賃金、サービス物価ともに大きく伸びていたものの、2000年代に入りパートタイム労働者比率の高まり等により賃金の伸びが低下するとともにサービス物価の伸びも低下していることが分かる。以上を踏まえると、サービス物価の安定的な伸びには、賃金の安定的な伸びが重要であると考えられる。
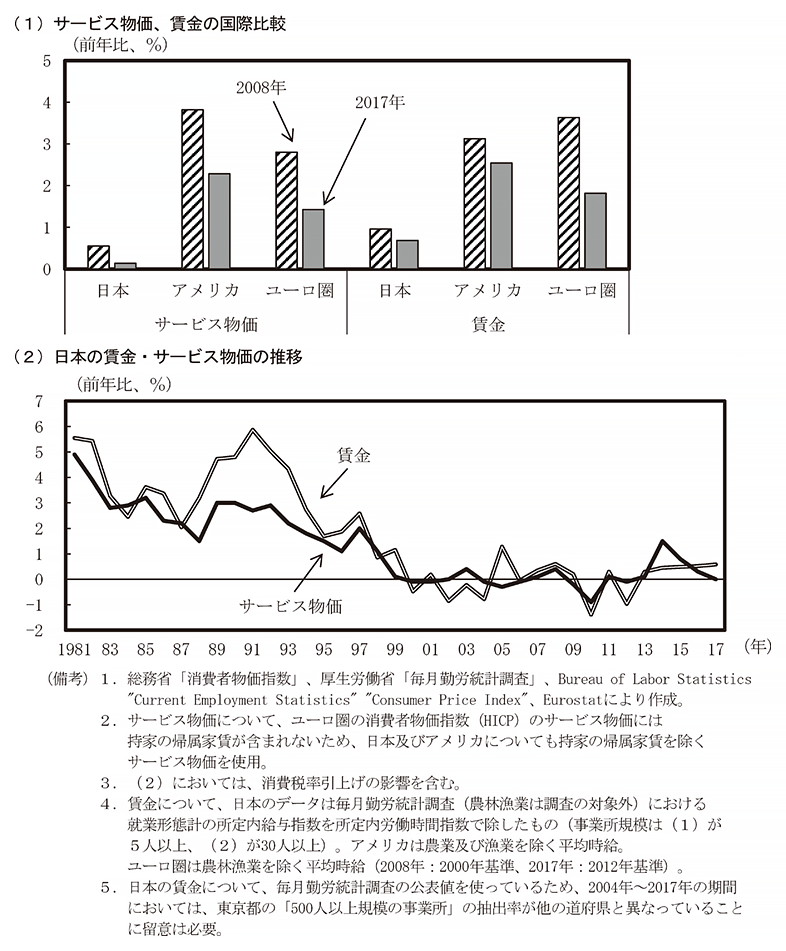
(消費者物価に対する為替の影響)
2018年に入ってから、耐久消費財などの価格は下落しており、これまでの円安による価格押し上げ効果が確認しにくくなっているが、ここでは為替の変化が企業段階の物価にどの程度の影響をもたらし、その結果どの程度消費者物価に影響をもたらす関係となっているかについて分析する。
まず、コアコアの財価格の為替感応度(ここでは物価変化率を、名目実効為替レート変化率及びGDPギャップで重回帰した推計式における名目実効為替レート変化率の係数の逆符号の値)をみると(第1-2-14図(1))、0.03程度である。そこで、企業物価のうち最終的に消費者が購入することとなる消費財価格の為替感応度をみると、消費財のうち輸入品の為替感応度は0.63程度であるのに対し、消費財のうち国内生産品の為替感応度は統計的に有意とならない。この要因を確認するために、製造業の生産のために投入される財・サービスの価格を示す投入物価と産出される財の価格を示す産出物価の為替感応度をみると(第1-2-14図(2))、投入物価の為替感応度は0.24程度であるのに対し、産出物価の為替感応度は有意にならなかった。
これらの結果から、企業の生産段階で原材料が受ける為替の影響が製品価格に十分転嫁されておらず、その結果、消費者物価でみても為替感応度は小さいといえる。つまり、第1-2-11図でみた為替の円安方向の動きによるコアコアの押上げ効果は、為替の円安方向の動きによる原材料価格上昇を製品価格に転嫁した影響よりも、最終製品として輸入される製品価格が為替の円安方向の動きから直接受ける影響の方が大きい可能性がある。
以上はマクロ的にみた為替感応度であるが、具体的に類別の消費者物価と為替との関係をみると(第1-2-14図(3))、教養娯楽用耐久財、家事用耐久財、食料工業製品等で為替感応度が高くなっているほか、財以外でも、食材などに輸入品を多く使うと考えられる外食においても、価格が為替の影響を受けており、円安時にはこれらの財やサービスを中心に消費者物価を押し上げていると考えられる。
次に、マイナス寄与が大きい耐久消費財について、為替等で要因分解すると(付図1-12)、2018年1-3月期以降、為替の円安方向の動きによる押上げ効果がみられるものの、同年4-6月期以降、為替やGDPギャップ等で説明できないその他要因による押下げが大きく、耐久消費財は前年同期比でマイナスとなっており、消費者物価押し下げの一因となっている。その他要因には、既述の液晶パネル価格下落等によるテレビの価格動向など、各品目特有の動きも関係していると考えられる。
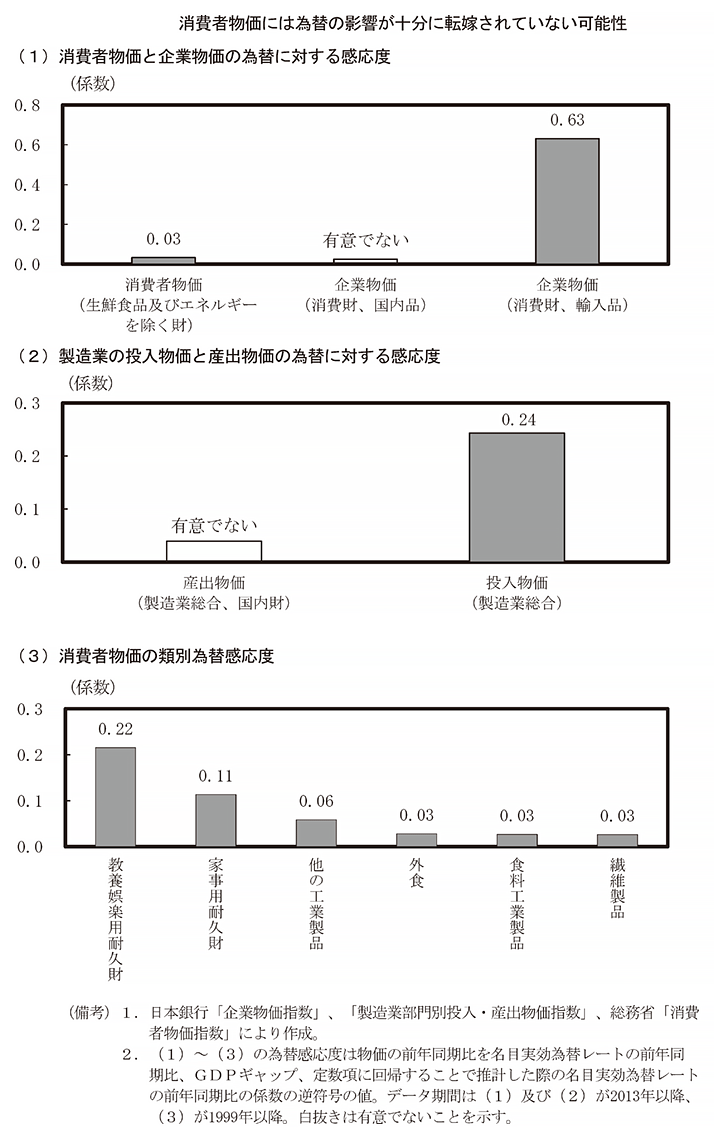
(企業にみられる価格転嫁に慎重な傾向と消費の価格弾力性)
最後に、企業のコスト上昇等による価格転嫁の動向について確認する。既にみたように、企業は為替等の影響により原材料価格が上昇しているときでさえ製品価格への転嫁に慎重な傾向がある。この点は、生産段階だけでなく小売段階においてもいえることが、販売価格判断DIと仕入価格判断DIとの乖離が1990年代に比べて拡大していることから確認できる(第1-2-15図(1))。
このように企業が価格引上げに慎重となっている背景には、消費者が長期間のデフレを経験したことにより未だデフレ・マインドが払拭されておらず、価格変化に敏感になっている可能性があると考えられる。そこで、価格変化に対して消費がどの程度変化するかを示す消費の価格弾力性について、物価下落期に入る以前(ここでは1990年~1998年の期間で分析)と今回の景気回復局面(ここでは2013年以降の期間で分析)に分け、家計の品目別支出額の実質変化率を品目別消費者物価変化率及び可処分所得の実質変化率で回帰することにより推計した。
この結果、今回の景気回復局面では、食料品など必需品を多く含む非耐久消費財で価格弾力性が確認できる品目数が増加しており、消費者が価格変化に敏感になっているため、企業が価格引上げに慎重になっている可能性が示唆される(第1-2-15図(2))。
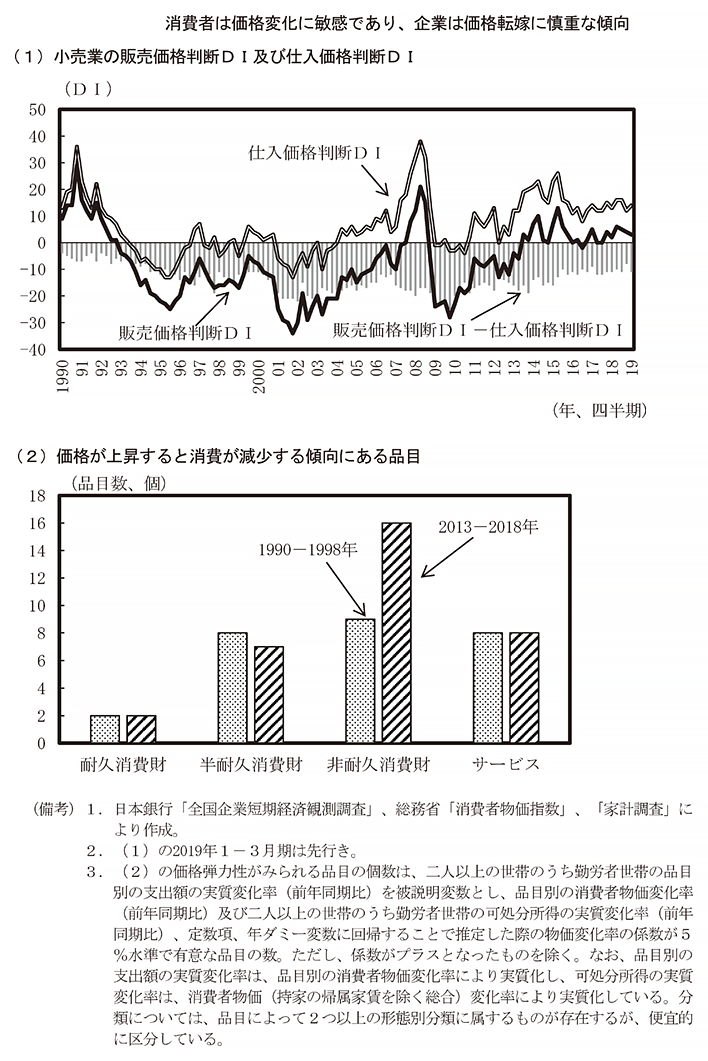
(消費者の低価格志向)
このように消費者が価格変化に敏感になっている可能性がある中、消費者がどのような商品を選択しているかについて検証するため、消費者が実際に支払った購入金額を購入数量で除した平均購入単価の動きと消費者物価指数の動きを比較してみよう。消費者物価指数は、品目毎に代表的な銘柄を指定し、その価格を継続的に調査しているものであるのに対し、平均購入単価は消費者が実際に購入した商品の単価を示しているため、平均購入単価上昇率が消費者物価上昇率を下回っている際には、消費者が例えばプライベートブランド商品等のより安価な商品を選択する傾向が強い状態にあるといえる。第1-2-16図(1)をみると、消費者物価上昇率がプラスで推移しているのに対し、2018年に入り、平均購入単価上昇率がマイナスに転じ、その下落幅は拡大傾向にある。この結果、消費者物価上率と平均購入単価上昇率には大きな乖離が生じており、2018年以降、低価格指向が強まっている可能性が示唆される。
そこで2018年以降、具体的にどのような品目でこのような動きがみられるかについてみると(第1-2-16図(2))、点線で示した45度線よりも下にプロットされている品目、すなわち、消費者物価上昇率よりも平均購入単価上昇率の方が低い品目には、牛肉、ビールなど商品の選択肢の多い食料品やカット代などが挙げられ、これらの品目で低価格志向がみられる。一方、電気掃除機、電気冷蔵庫、テレビ等の家電製品では、消費者物価が前年比マイナスで推移する中、低価格志向はみられず、より高機能な高額商品にも一定のニーズがあると考えられる15(付図1-13)。なお、2018年以降低価格志向が強まっている背景には、天候不順による生鮮野菜や原油価格上昇によるガソリンなど頻繁に購入する品目の価格が2018年に大きく上昇したことも一因となっている可能性がある(前掲第1-1-11図(3))。
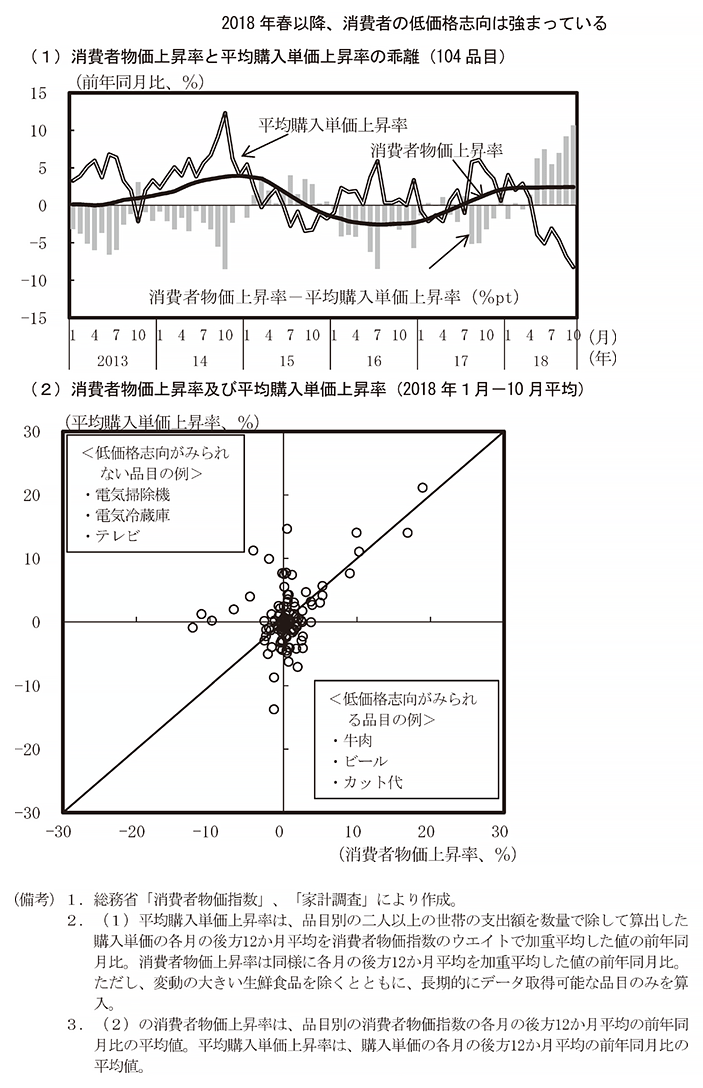
(購入頻度別にみた消費者物価)
ガソリンなど頻繁に購入する品目の価格が上昇する中で、消費者物価全体としてみると、価格上昇がその他の品目に広がらない状況となっている。消費者物価(持家の帰属家賃を除く総合)を年間購入頻度別に寄与度分解すると(第1-2-17図(1))、2018年以降、頻繁に購入する品目のプラス寄与が大きく、一方、購入頻度の低い品目(1年に1回程度購入、まれに購入)はプラスに寄与してはいるものの、押上げ幅は小さい。
両者を実際にプロットしてみると、1期前の頻繁に購入する品目価格上昇率16が高いときには購入頻度の低い品目価格上昇率が低い傾向がみられる(第1-2-17図(2))。また、2018年の動きをみると、頻繁に購入する品目の価格が上昇する一方で、購入頻度の低い品目の価格の上昇幅は低下している。このように、頻繁に購入する品目、特にガソリンや生鮮野菜価格などの供給要因による価格上昇は、実質的な購買力の低下や消費者マインドへの影響を通じて、物価上昇圧力を減殺する可能性もある点には留意する必要がある。
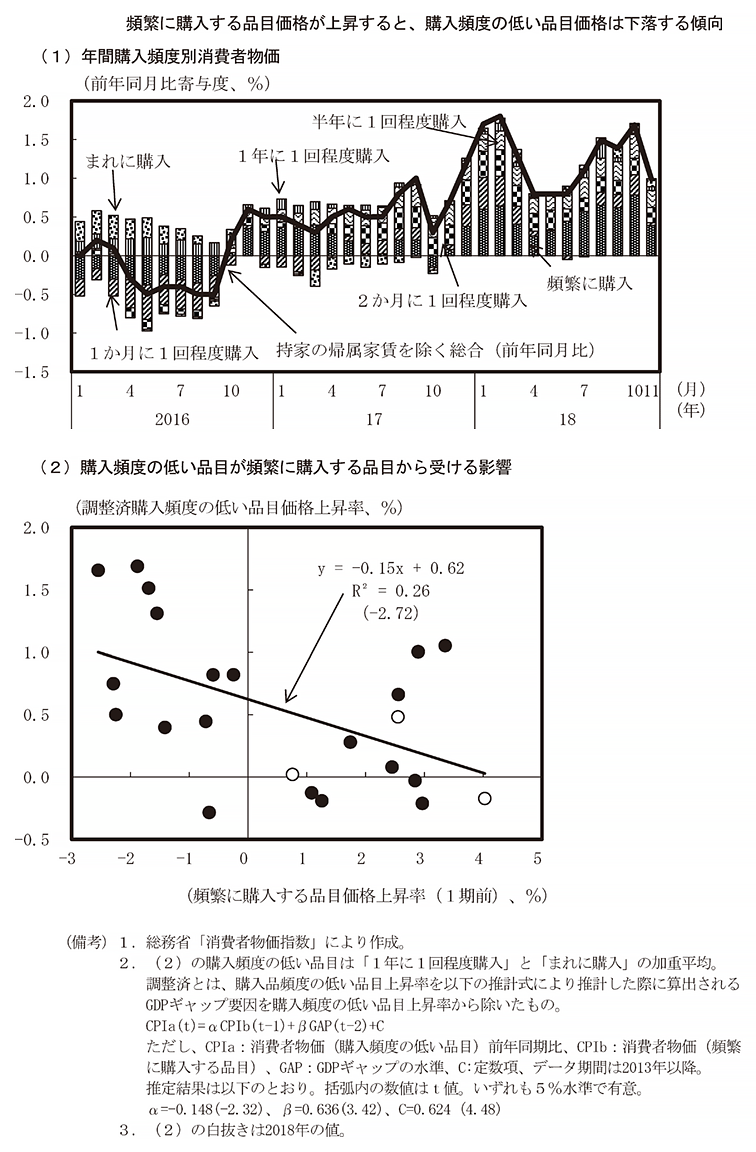
(物価動向の展望と留意点)
以上の分析を踏まえると、今後、物価が再び緩やかに上昇し、それが持続するためには、人件費や原材料価格等の上昇による物価上昇圧力を小売価格に転嫁できるよう、景気回復による更なる賃金上昇によって、価格変化に敏感な消費者の低価格志向を和らげることが重要である。これにより、消費者の購買意欲が高まれば、人件費上昇などによりサービス価格を中心に価格が上昇していくことが期待される。
コラム1-2 消費者の体感物価
既にみたように、コアコアは上昇テンポが鈍化していますが、ここでは、消費者がどのように物価を受け止めているかについてみてみましょう。
まず、消費者がどのような品目で一番物価変動を感じるかについてみると(コラム1-2図)、ガソリン・灯油、生鮮食品、食料品(生鮮食品を除く)の順で割合が高く、この3分類の合計が、2018年には9割を超えています。次に、コラム1-2図(2)をみると、消費者が1年前に比べて現在の物価がどの程度変わったと感じるかを示す体感物価17は、ガソリンや生鮮野菜など消費者が物価変動を感じやすい頻繁に購入する品目の価格上昇に伴い2012年以降上昇しました。ただし、その後、頻繁に購入する品目が下落しても、体感物価は高水準を維持しており、体感物価は一度上がると下がりにくく、実際の消費者物価上昇率との差が生じています。
さらに、世帯主の年齢階級別に家計の支出額でウエイト付けした消費者物価をみると、60代以上の物価上昇率が50代以下の物価上昇率よりも高いことが分かります。これは、60代以上の方が、支出に占める食料や光熱・水道の割合が高く、野菜やガソリン等の価格が上昇しているときには直面する物価も上がりやすい傾向があることを示しています。このため、第1節でみたように、消費者にとって身近な品目の価格上昇が、高齢者の消費マインドに影響を及ぼしていると考えられます。