第1章 日本経済の現状と課題(第1節)
第1節 戦後最長に並ぶ景気回復
今回の景気回復は、①世界経済の緩やかな回復、②企業部門の高い収益力や技術革新を背景にした設備投資意欲の高まり、③雇用・所得環境の改善という3つの大きな推進力に支えられ、戦後最長と並ぶまで景気回復が続いてきた。他方で、2018年の動きをみると、緩やかな回復が続いているものの、年初には大雪などの影響、また夏場には自然災害の影響もあり消費が下押しされたことや世界的に情報関連財需要が一服したことから1-3月期や7-9月期はマイナス成長となるなどやや弱めの動きも見られた。ここでは、今回の景気回復を支えている3つの推進力が引き続き牽引していることに加えて、2018年央以降の輸出の伸びの鈍化の背景や自然災害の影響等について確認する。
1 日本経済の現状
(景気の現状及びその背景)
我が国経済は2012年11月を底に緩やかな回復を続けている。実質GDP成長率は、2014年度に消費税率引上げの影響もあってマイナスとなったものの、2015年度1.3%増、2016年度0.9%増と持ち直し、2017年度も世界経済の緩やかな回復を背景とした外需の伸び、また雇用・所得環境の改善や好調な企業収益を背景とした個人消費や民間設備投資の伸びにより前年度比1.9%増と2%程度の成長を実現した(第1-1-1図(1))。
2018年に入ってからの経済動向について、四半期の実質GDP成長率の動向を見ると、2018年1-3月期は冬場の天候不順による野菜価格高騰等による消費の減少もありマイナス成長となった後、4-6月期には個人消費や設備投資の増加を中心に前期比0.7%増と高めの伸びとなった。7-9月期は、相次ぐ自然災害による生産・物流の滞りや客足の減少を背景に消費が減少し、輸出も減少したことなどにより0.6%減となったが、自然災害等の一時的な影響を除けば消費や設備投資など内需を中心にした緩やかな成長が続いている。他方、輸出については、これまで高い伸びを続けたスマートフォンやデータセンター向け需要の一服から情報関連財輸出の増勢が鈍化し、中国経済の持ち直しの動きに足踏みがみられることによる資本財受注の弱まりもみられることから、基調としても横ばいとなっている。
今回の回復局面における各需要項目の成長の寄与を2012年末からの累積でみると、個人消費や設備投資といった民需が大きく寄与しているほか、アベノミクスの機動的な財政政策の効果もあり公需もプラスとなっている(第1-1-1図(2))。外需をみると、情報関連財需要の一服もあり18年になり輸出が伸び悩んでいるものの、プラスを維持している。
緩やかな景気回復が続く中で、一国の総需要(実際のGDP)と景気循環の影響を均してみた平均的な供給力(潜在GDP)との差であるGDPギャップは、2017年以降、プラス傾向(需要超過)となっている(第1-1-1図(3))。潜在GDPの成長率は1%程度であり、実際のGDP成長率はそれを上回る傾向にある。GDPギャップがプラス傾向にある中、生産性を高めることにより潜在成長率を引き上げていくことが課題となっている。
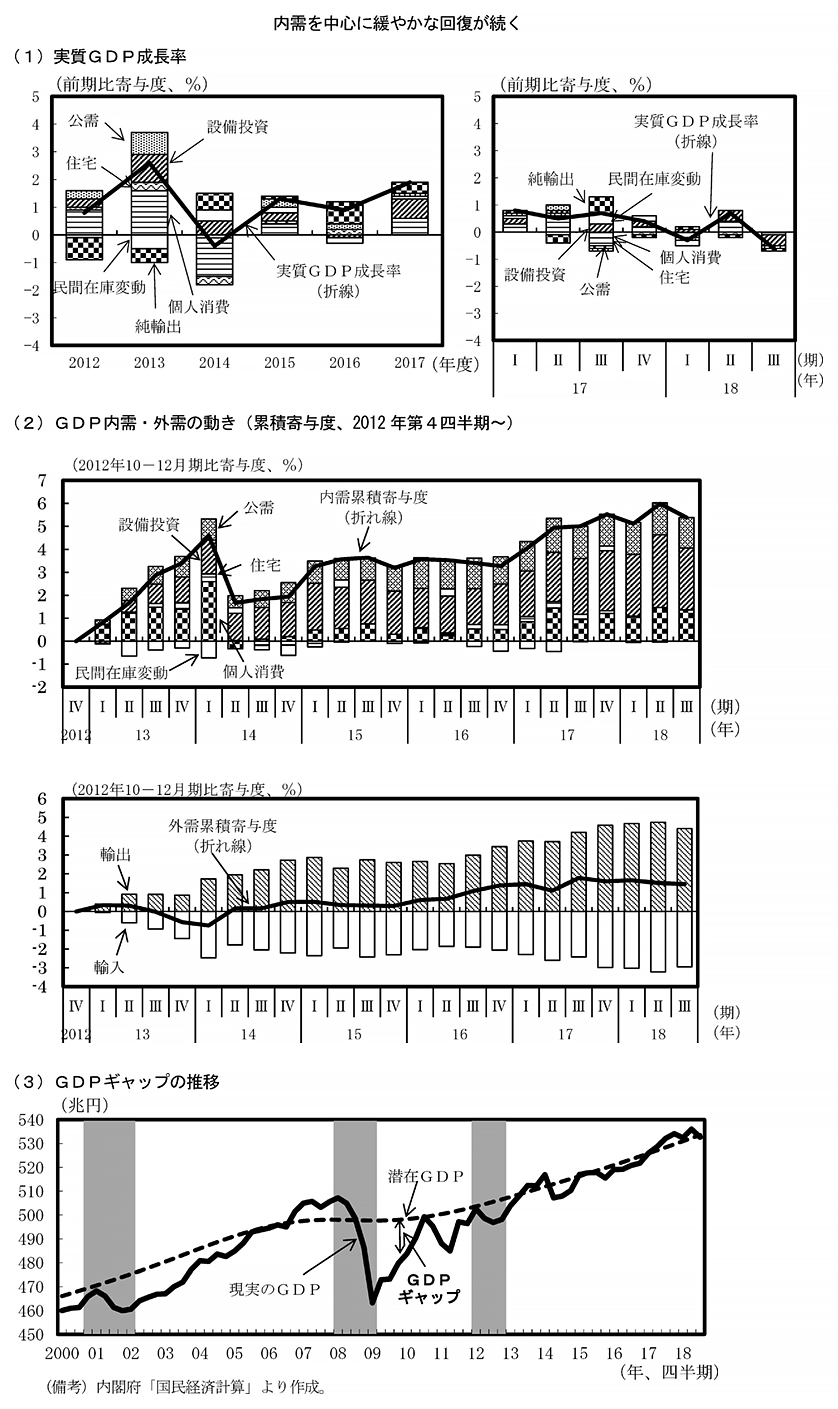
今回の景気回復を牽引している大きな推進力としては、以下の3点が挙げられる。
1点目は、世界経済の同時回復である。世界の企業の景況感をみると、2015年頃からの中国経済の減速もあり新興国経済に弱さが見られていたが、2016年後半からは先進国、新興国ともに景況感が改善し、2017年は世界経済同時回復を実現した(第1-1-2図(1))。こうした世界経済の回復が、輸出の押し上げ等を通じて我が国経済を下支えしている。ただし、2018年後半からは先進国、新興国ともに景況感がやや低下しており、世界経済の今後の動向に注視が必要である。
2点目は、企業収益の改善と旺盛な設備投資需要である。企業収益が過去最高水準となる中、人手不足や新技術への対応などもあり企業の設備投資は増加を続けている。日本銀行「全国企業短期経済観測調査」(以下「日銀短観」という。)における2018年度の設備投資計画をみても、前年度比9.6%増とこれまでに比べても高い水準となっており、今後も設備投資が我が国経済を牽引することが期待される(第1-1-2図(2))。
3点目は、景気回復の長期化もあり、雇用・所得環境が大幅に改善している点である。有効求人倍率は、2018年11月時点で1.63倍と1974年1月以来の水準となっており、失業率も2.5%と1993年8月以来の低水準である。正社員の有効求人倍率も1.13倍と1倍を上回っており、雇用情勢は着実に改善している(第1-1-2図(3))。また、失業者数も減少を続けており、リーマンショック後に一時期大きく増加した失業期間が1年以上の完全失業者(以下、「長期失業者」という。)の数、割合ともに減少(例えば、2012年10-12月期に失業者全体に占める長期失業者の割合は4割程度であったが、2018年7-9月期は3割弱となっている)しており、多くの人々が働く場を得やすくなっている。ただし、人手不足感の高まりによる負の影響が一部の企業ではみられていること、また雇用のミスマッチも依然として残っている点には留意が必要である。こうした中で、賃上げ率は5年連続で高い水準となり、一人当たりの賃金は緩やかに増加している(第1-1-2図(4))。こうした雇用・所得環境の改善は消費の持ち直しにつながっていると考えられる。
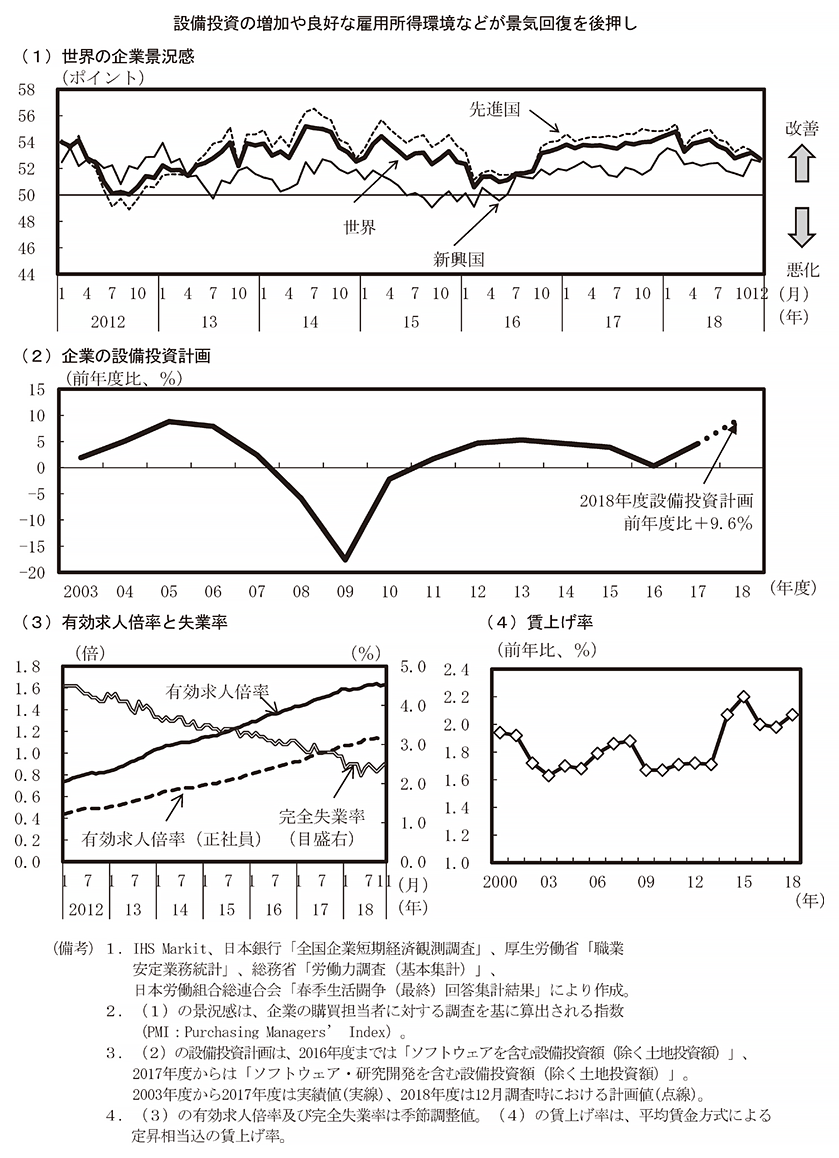
2 景気回復の推進力とその動向
以下では、世界経済の回復、企業部門の収益性と設備投資意欲の高まり、雇用・所得環境の改善といった3つの景気回復の推進力について、より詳細に最近の動向を概観する。
(世界経済と我が国の輸出の動向)
世界経済は緩やかな回復が続いている。2015年後半から2016年にかけては世界のGDPの伸びは2%台半ばにまで低下したものの、2017年に入ると3%を超える成長となった(第1-1-3図(1))。こうした中、世界の貿易量の伸びも2016年までは低水準にとどまり、一時期は貿易の伸びが経済成長を下回る「スロー・トレード」と言われたが、2017年に入ると世界の貿易量は大きく伸び、5%程度の伸びとなった。2018年に入ってからは、中国などの成長率が若干鈍化する中で、世界の貿易量の伸びは4%台にやや鈍化している。先行きについても、米中間の通商問題などによる不透明感が高まっており、世界の貿易量の伸びの低下が懸念される。
我が国の輸出先としての大きな割合を占めるアメリカと中国の輸入の動向1をみると、アメリカ、中国ともに2015年から2016年にかけて前年比でマイナスとなっていたが、2017年に入ると前年比でプラスとなった(第1-1-3図(2))。2018年に入ってもアメリカで10%程度、中国で20%程度と高い伸びが続いているが、今後の動向には注視する必要がある。
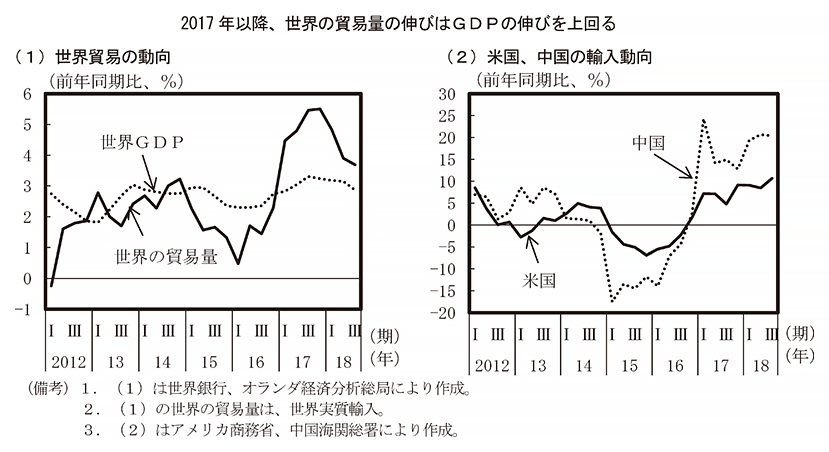
こうした世界の貿易量の伸びも背景に、我が国の輸出は2018年前半まで持ち直しが続いた(第1-1-4図(1))。特にアジア向け輸出が2017年には大きく伸びたが、その要因の一つとして情報関連財の伸びがある。情報関連財は、スマートフォン向けに加え、データセンター向け2などの用途でも利用が増え、大きく伸びた。ただし2018年半ばからは、スマートフォンやデータセンター向け需要が一服したことにより低下している。
今後の動向としては、IoT、ビッグデータの利用拡大に伴い、幅広い用途での電子部品の利用が見込まれるため、情報関連財の需要は、伸び率でみれば鈍化するものの、引き続き高い水準を維持することが見込まれている。WSTS(世界半導体市場統計)による世界の半導体需要の予測(2018年11月公表)によると、2018年の実績見込み及び2019年の予測値ともに2018年6月の予測から上方修正されたものの、2018年から2019年にかけて伸びは鈍化する形になっている(第1-1-4図(2))。メモリの需要については2019年にかけて若干の減少が見込まれているが、その背景として、メモリ価格の動向をみると、2017年半ばから低下傾向となっていたNANDに加え、2018年に入ってからDRAMでも低下傾向がみられており、一時期の過熱状況からやや需給が緩んでいることがうかがわれる。(第1-1-4(3)図)。
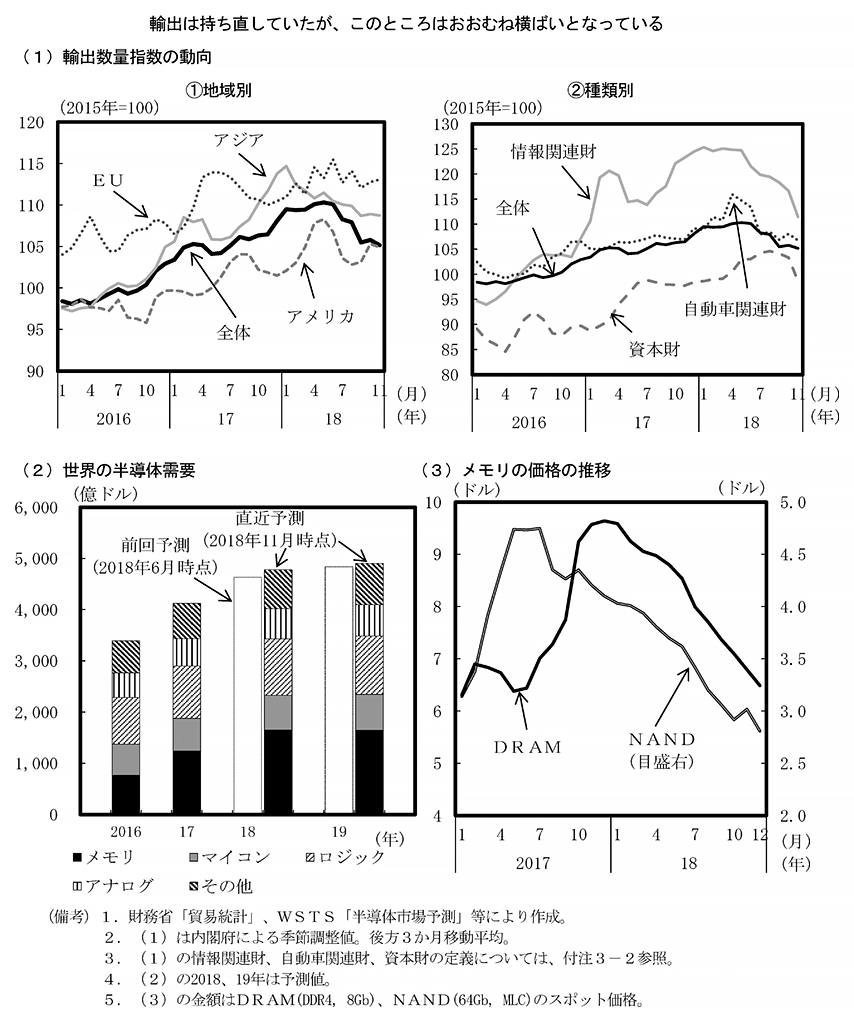
我が国の輸出の約2割を占める中国向けの輸出動向をみると、2017年はスマートフォン向けやデータセンター用などの需要の高まりを背景に、集積回路や半導体等製造装置などの情報関連財輸出が大きく伸びることで中国向け輸出は大きく伸びた(第1-1-5図(1))。また2017年は、中国経済の持ち直しの動きとともに工作機械受注が増加するなど資本財も大きく増加した。
しかし2018年に入ると中国経済の持ち直しの動きに足踏みがみられることにより工作機械受注の伸びが鈍化し(第1-1-5図(2)、資本財輸出が横ばいとなるとともに、中国における携帯電話の生産の減少(第1-1-5図(3))やデータセンター向けの需要の一服から情報関連財輸出も伸びが鈍化し、横ばいで推移している。こうした中国向け輸出が鈍化した背景には、中国において過剰債務の解消のために迂回融資(いわゆるシャドーバンキング)が絞られる中で固定資本投資が抑制されたことや、中国国内の携帯電話の普及が一巡したこと等があると考えられる。
中国向け輸出の先行きについては、情報関連財はIoTの利活用進展等に伴う需要は長期的には堅調に推移するものと考えられ、また、資本財についても人件費高騰に伴う省力化投資の需要も引き続き根強いと考えられるが、他方で、米中間の通商問題の今後の動向によっては、サプライチェーンを通じた影響や、不透明感の高まりによる中国における設備投資の慎重化などの影響が出てくる可能性もあり、その動向には注意が必要である。
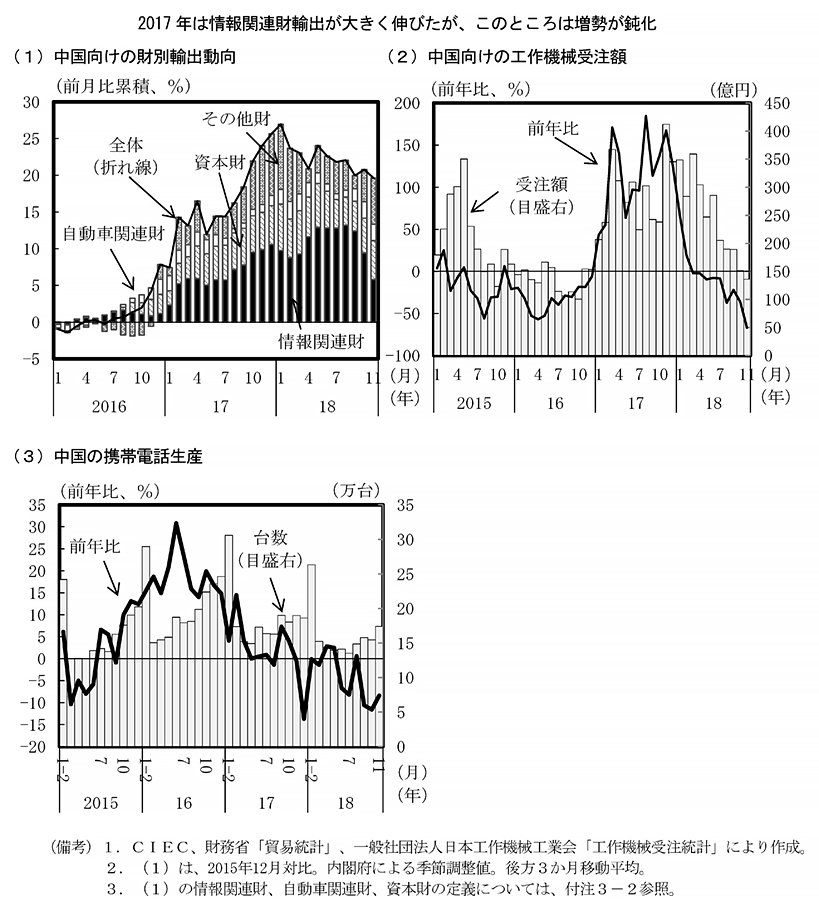
(企業収益の改善、技術革新への取組などを背景に設備投資は増加)
景気回復が長期化する中で企業の業況は大きく改善している。製造業、非製造業ともに2016年半ば以降改善を続け、特に製造業では為替が円安方向に推移したこともあり大幅に改善した。ただし、2018年に入ると、原油など原材料価格の高騰、人手不足感の高まり、米中間の通商問題の影響への懸念に加え、7-9月期には自然災害の影響もあり、景況感は、高水準でおおむね横ばいとなっている(第1-1-6図(1))。
企業収益も景気回復の長期化により改善を続け、過去最高の水準となっている。2018年に入ってからも製造業、非製造業ともに改善が続いている(第1-1-6図(2))。この背景として、製造業においては、世界経済の回復や設備投資需要を反映して一般機械などを中心に収益が改善している。また、非製造業においては、情報通信事業の需要が堅調であることや、インバウンドやEコマース需要の高まりにより、運輸・通信業を中心に改善を続けている。
生産の動向をみると、電子部品・デバイス工業は従来のスマートフォン向け部材需要に加え、電子部品が家電や車など幅広い用途で使われるようになったことやデータセンター向け需要が伸びたことから、2016年後半から緩やかに増加している(第1-1-6図(3))。また、生産用機械工業は、国内外の旺盛な設備投資需要に加え、世界的な半導体需要の高まりを背景にした半導体等製造装置の生産拡大もあって2016年後半から大きく増加した。ただし、2018年に入ると半導体需要に一服感がみられることに加え、供給面では一部の基幹部品で供給が十分にできない3といった供給制約などもあり2018年前半からは増勢がやや鈍化している。また、2018年7月の西日本における豪雨(以下、「平成30年7月豪雨」という。)により自動車産業や生産用機械などで、また9月の北海道で発生した地震(以下、「平成30年北海道胆振東部地震」という。)により自動車産業などで生産活動に影響がでたが、2018年10月以降回復しつつあり、これらの影響も薄らいできている。
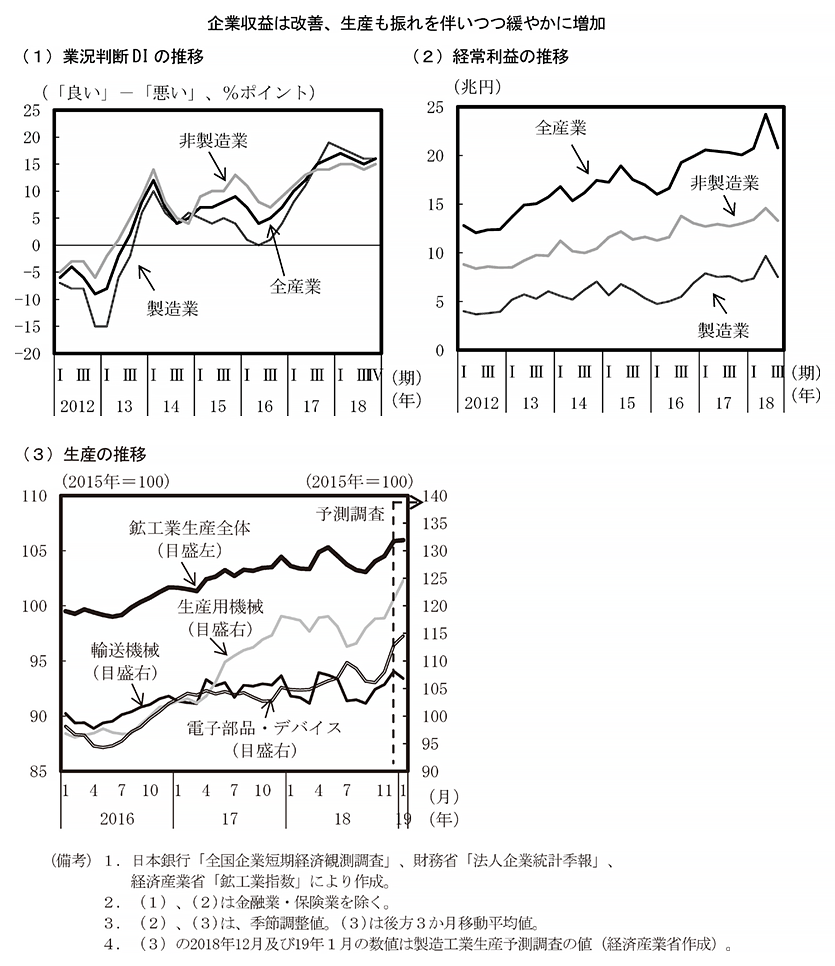
好調な企業収益を背景に、技術革新への取組や人手不足感の高まりに対応した省力化投資の取組などもあり設備投資は増加を続けている。最近の設備投資の動向をみると、大きく増加した4-6月期の反動もあり2018年7-9月期は減少したものの、2018年4-6月期まで7四半期連続で増加し、その水準も1990年代初め以来の高水準となっている(第1-1-7図(1))。また、2018年度の設備投資計画(日銀短観)をみると12月時点で前年度比9.6%増とこれまでの計画に比べても高い水準となっており、今後も設備投資は増加していくと見込まれる(第1-1-7図(2))。
設備投資計画を業種ごとにみると、幅広い業種で増加している(第1-1-7図(3))。このところ電気自動車や自動運転に向けた研究開発が盛んになっている自動車産業で伸びが高まっており、それにつれて電気自動車に使われるリチウムイオン電池の部材の生産で化学産業でも設備投資が増えるなど関連産業にも広く設備投資が広がっている(付図1-1)。加えて、設備投資に用いる生産用機械の増産のために一般機械産業での投資も増加が見込まれているほか、インバウンド需要が好調な運輸・郵便でも、鉄道高速化や駅の再開発などの投資が見込まれている。
また省力化に向けた設備投資も進んでいる。自動車産業ではIoTを導入し効率化を進めたり、食品業では無人運搬車の導入、さらに小売業では自動レジの導入など様々な産業において、省力化に向けた設備投資も進んでおり、設備投資の押し上げに寄与している(第1-1-7図(4))
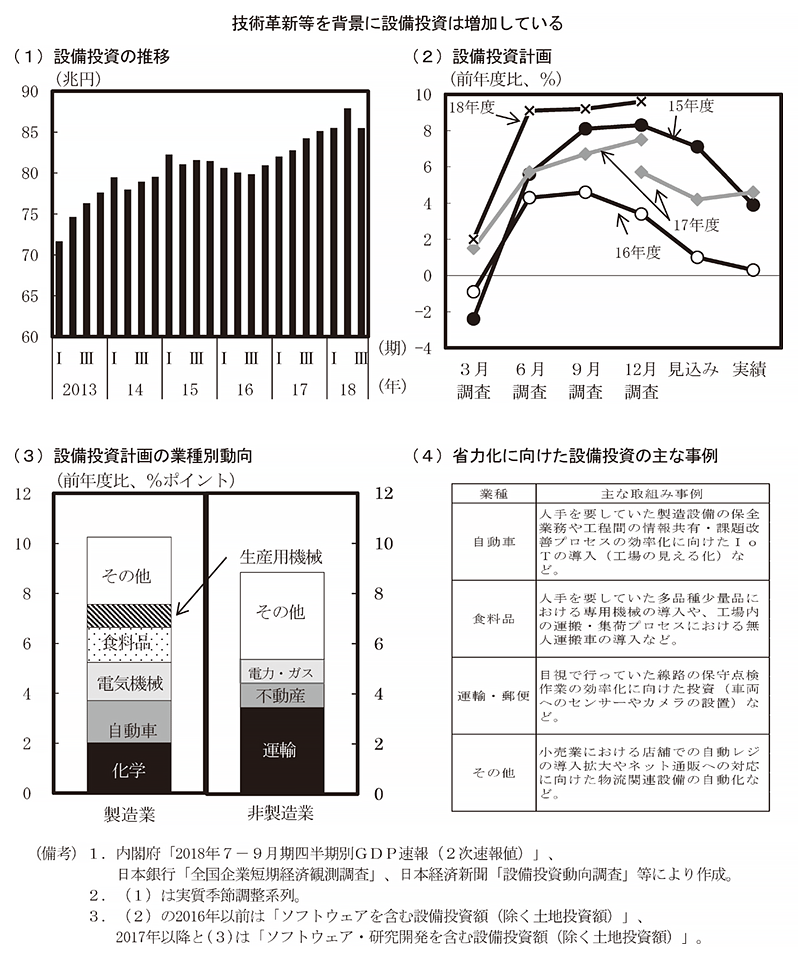
設備投資の内訳4として、機械系の設備投資である資本財総供給の動向をみると、横ばい傾向で推移した時期もあったものの、2017年以降持ち直しが続いている(第1-1-8図(1))。他方で、機械受注残高の動向をみると、工作機械や産業用ロボットなど省力化につながる設備において2017年以降受注残高が大きく高まっており、受注の伸びに対して生産が追いつかず、結果として手持ちの受注残高が溜まっている状況がみられる(第1-1-8(2)図)。
こうした背景の一つとして、設備投資に用いる生産用機械等の需要が旺盛である中で、その生産に用いられるボールねじやリニアガイドなどの基幹部品の供給が追い付いていない状況があった可能性がある。基幹部品の生産の推移をみると、2016年末までは低水準で推移していたものの、設備投資需要の加速に伴い2017年生産が大きく増加している(第1-1-8(3)図)。基幹部品の生産については、最近は生産能力増強が図られるようになっていることから、部品不足による生産用機械の供給制約は緩和されることが期待される。一方、中国経済の持ち直しの動きに足踏みがみられる中、受注の勢いが鈍化しているので、今後は、供給面のみならず需要面の動向にも注視が必要である。
建設投資の動向を建設工事費出来高で確認すると、インバウンド需要の高まりに伴うホテル建設、都市の再開発、さらには製造業における工場建設などにより建設工事費出来高は増加を続けている(第1-1-8図(4))。景気回復の長期化や企業収益の大幅な改善もあり、都心オフィス用の建設も好調が続いており、今後も、堅調に推移することが見込まれる。
また、研究開発投資も増加が続いており、企業が新技術への取組を進めている可能性がある(第1-1-8図(5))。日本政策投資銀行「全国設備投資計画調査」の連結研究開発費における産業ごとの動きをみると、2017年度及び2018年度で特に輸送機械において研究開発費の伸びが高くなっており、その背景として電気自動車に向けた研究開発がけん引しているとみられる。
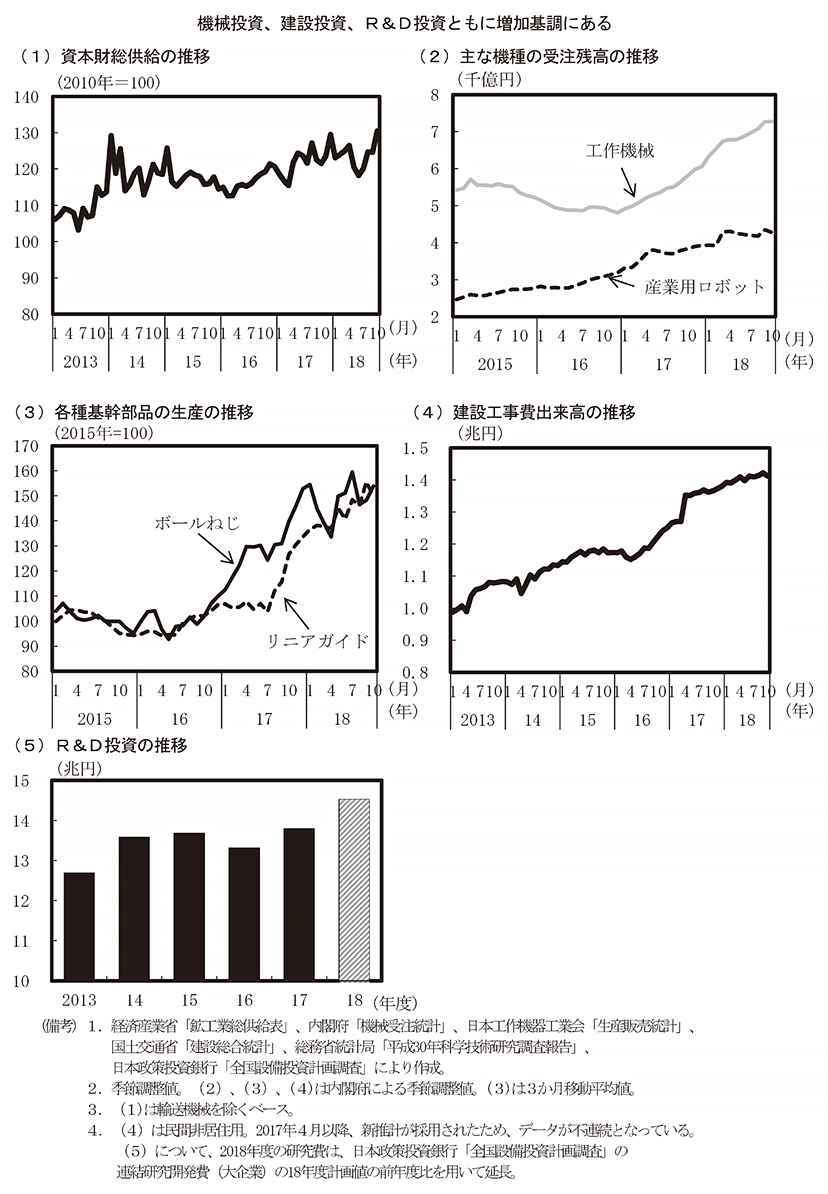
(雇用・所得環境の改善と消費の持ち直し)
雇用・所得環境の動向をみると、生産年齢人口が減少する中、女性や高齢者の労働参加により雇用者数が大きく増加する(第1-1-9図(1))とともに、賃上げ率が5年連続で高い水準となる(前掲第1-1-2図(4)))など、改善が続いている。
こうした雇用・所得環境の改善の動きは、賞与でも確認でき、夏のボーナスの動向をみると、過去最高の企業収益を背景に2018年夏のボーナスは各調査で5%を超えており、過去の伸びに比べても特に高い伸びとなっている(第1-1-9図(2))。冬のボーナスをみても、2018年は連合調査では前年比5.9%増、経団連調査では前年比6.1%増と高い伸びとなっている。
また、国税庁「民間給与実態調査」を利用し、2013年と2017年の平均年収を比較すると、雇用者一人当たりの平均年収は414万円から432万円に上昇している。内訳をみても、正規、非正規のどちらの区分でも年収は増加しており、賃金上昇の恩恵は雇用形態によらず幅広く及んでいることが確認できる(第1-1-9図(3))。
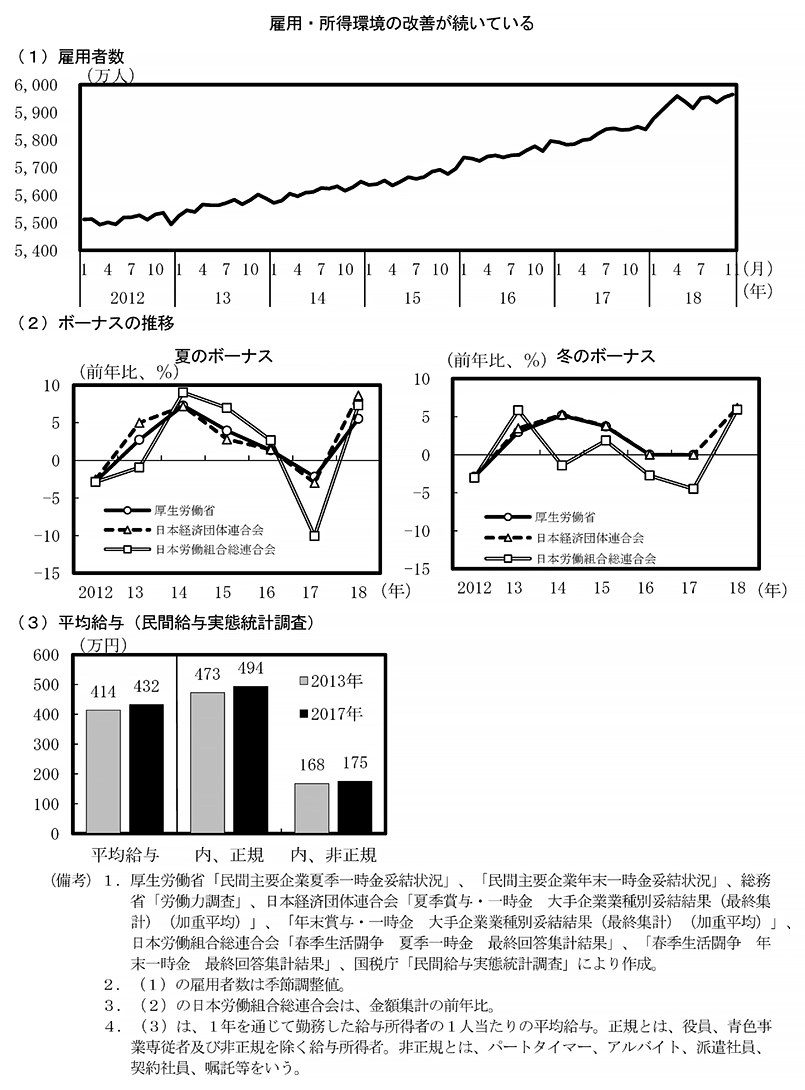
こうした雇用・所得環境の改善が進む中で、個人消費は持ち直している。実質民間最終消費支出(実質個人消費)の推移を見ると、2014年度は消費税率引上げの影響もあって前年比2.6%減と大きく減少したものの、2015年度には0.7%増と持ち直した。その後、2016年度は熊本地震等の一時的な下押し要因もあって前年比0.0%増と横ばいとなったが、2017年度には1.0%増と伸びを高めている(第1-1-10図(1))。
2018年度についても、実質個人消費は、4-6月期前期比0.7%増の後、7-9月期前期比0.2%減と自然災害の影響で2四半期ぶりのマイナス成長となったものの、そうした一時的な下押しの影響を除いてみれば、持ち直しが続いている。
財・サービス別に個人消費の内訳をみると、財、サービスともに堅調に推移しているが、2018年7-9月期については、自然災害の影響もあって旅行やレジャーなどのサービス消費は一時的に減少した一方、財の消費は微増であった5(第1-1-10図(2))。2018年に入ってからのサービス消費の動向をみると、外食については、自然災害による下押しがある中でも底堅さがみられ、2018年度初めには足踏みとなっていた客単価がこのところ上昇に転じていることもあり、足元では持ち直しの動きがみられる(第1-1-10図(3))。他方、旅行消費は2018年に入ってからも持ち直しが続いていたが、7-9月期には、自然災害の影響により大幅減となった(1-1-10図(4))6。ただし、10月以降大きく増加に転じており、今後は、自然災害からの復旧に伴って持ち直していくことが期待される。
財消費については、2018年に入ってから、1-3月期に天候不順による生鮮野菜等の食料品価格の高騰の影響や自動車販売の弱さからマイナスとなったものの4-6月期以降は、猛暑もありエアコンなど家電販売が増加に寄与したほか、自動車販売についても買い替え需要の高まる購入後7年~9年目を迎える車の台数が増加するなど買い替えサイクルが上向く中で持ち直している(第1-1-10図(5)(6))。
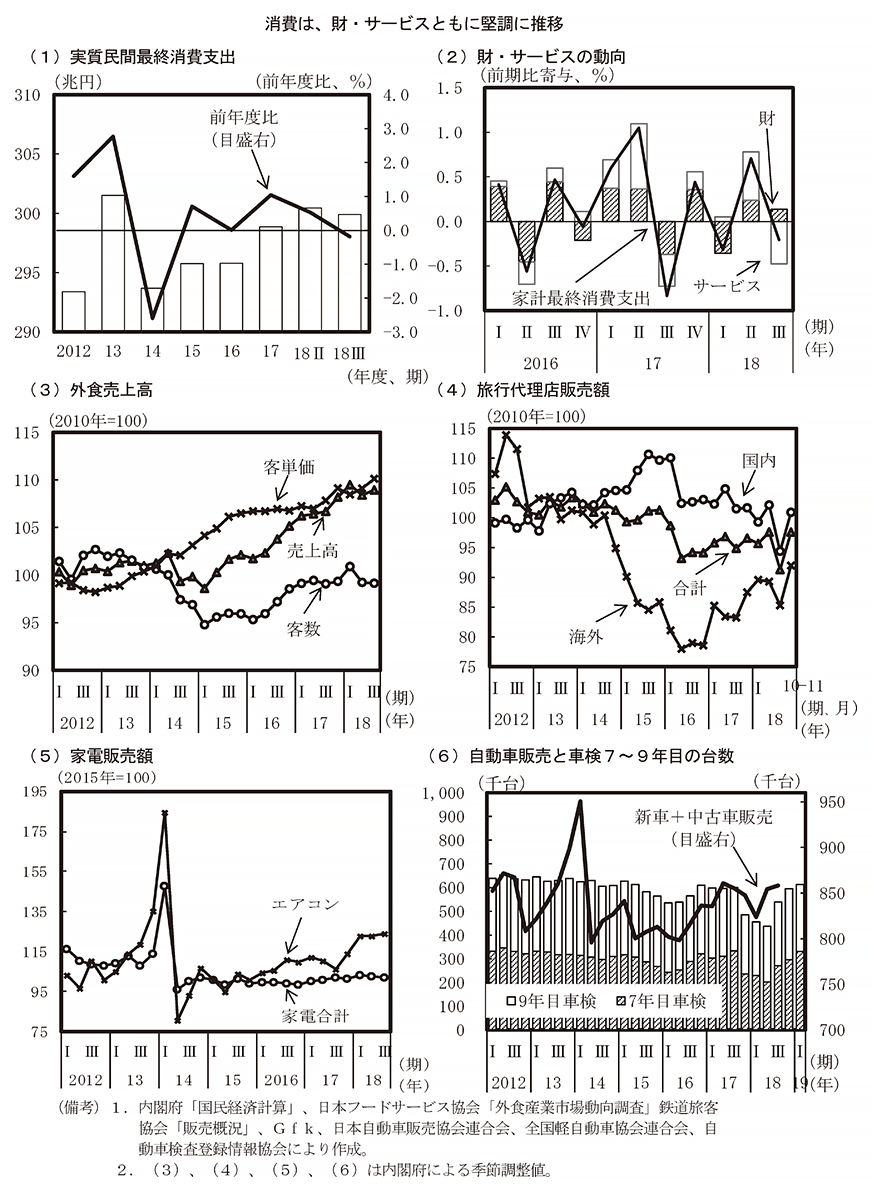
消費は持ち直しているものの、2018年に入ってから消費者マインドに力強さが欠けることは懸念材料である。消費者態度指数は、2018年央以降弱含んでいるが、消費者態度指数の前年差について世帯主の年齢別にみると、59歳以下の層ではマインドは改善しているものの、60歳以上の高齢者世帯のマインドが悪化していることが分かる(第1-1-11図(1))。
日本銀行「生活意識に関するアンケート調査」によれば、所得の増加が消費者マインドの改善に大きく寄与しているのに対し、マインドの悪化には物価上昇の影響が最も大きく寄与している(第1-1-11図(2))。実際に、ガソリン価格や野菜価格といった消費者の購入頻度の高い品物の価格動向をみると、2018年に入ってから、原油価格の上昇や天候不順による生鮮野菜の高騰などを背景に高い上昇率が続いた(第1-1-11図(3))。消費者マインドと雇用・物価などの関連の深い経済指標との相関について統計的に分析すると、付図1-2で示すように、消費者態度指数は、完全失業率や有効求人倍率、日経平均株価と関係性が強いが、世帯主が60歳以上の世帯では、消費者物価指数からも影響を受けていることがわかる。年金生活者の多い高齢者世帯は、消費に占める食料品の割合が高いため、食料品価格上昇の影響を受けやすくマインドと消費者物価との関係性が現役世代よりも強いとみられる。今後については、原油価格が2018年10月以降低下傾向にあることや野菜価格も平年並みに落ち着いていることもあり、購入頻度の高い品目の物価上昇率は落ち着いてくるとみられるが、消費者マインドの動向には引き続き留意する必要がある。
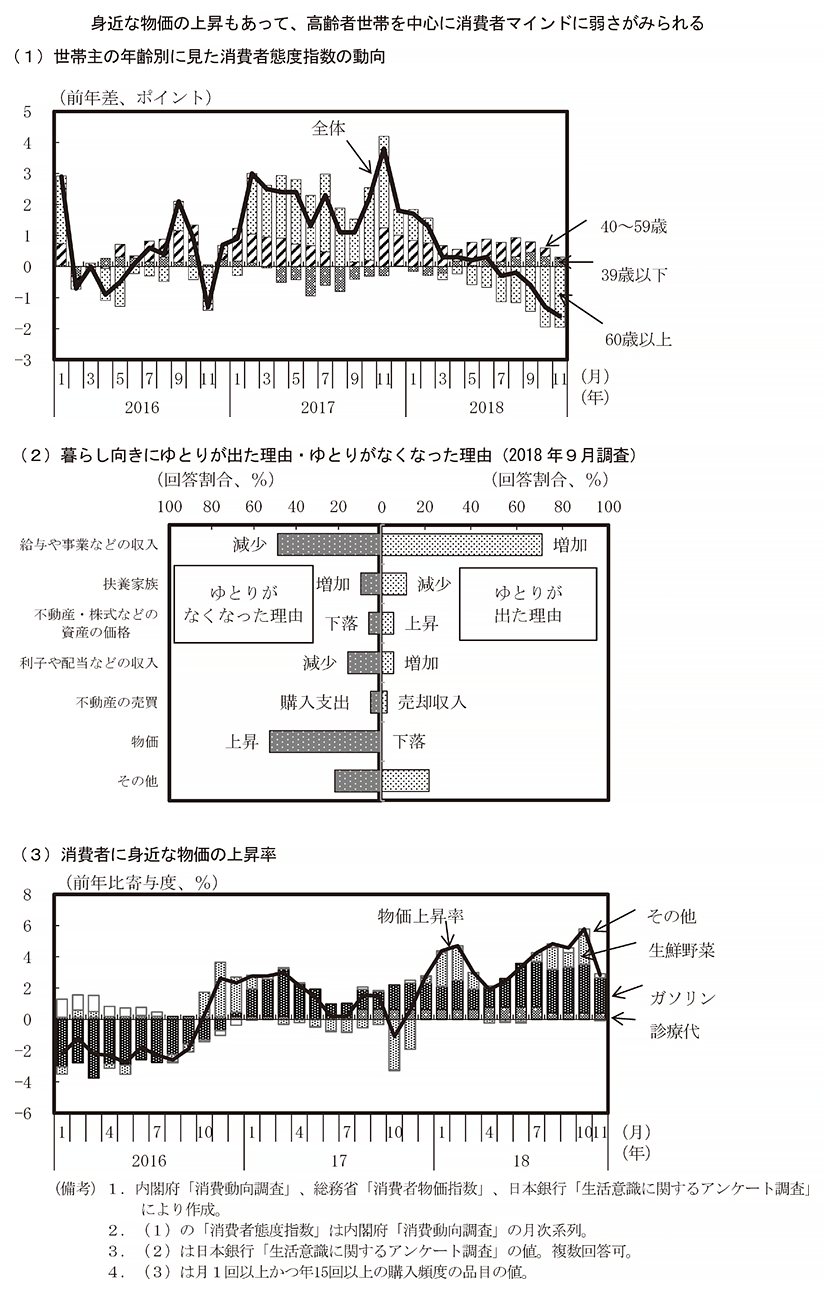
3 住宅、公共投資、金融市場の動向
(住宅の動向)
住宅着工の動向をみると、2016年には、金利低下による貸家建設の採算改善に加え、2015年の相続税に係る税制改正の影響もあり貸家建設が増加し、総戸数も増加した(第1-1-12図(1))。しかし、2017年以降は、金融機関の個人による貸家業への貸出の慎重化7などを背景に貸家の着工が減少する中で、住宅着工も弱含み、2018年半ば以降はおおむね横ばいで推移している(付図1-3)。住宅ローン金利の低下により家計の住宅購入が後押しされたことなどから、持家や分譲戸建(いわゆる建売住宅)は底堅く推移しているものの、共同分譲(マンション)については、建設用地の取得難や建設資材価格及び人件費の上昇等により販売価格が大きく上昇8したこともあり(第1-1-12図(2))、振れを伴いつつも傾向として弱含んでいる。
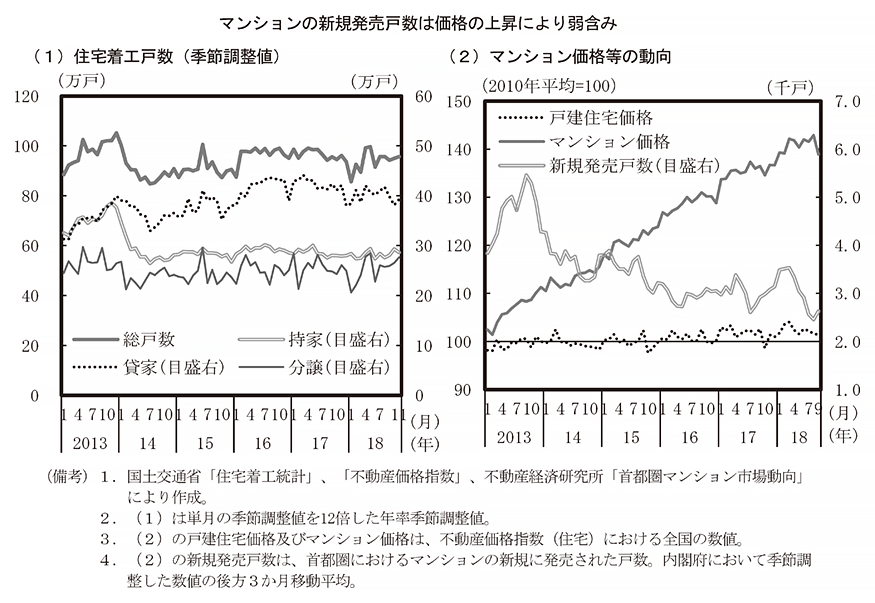
2019年10月には消費税率の8%から10%への引上げが予定されているが、過去の消費税率引上げ時には、税率引上げ前の駆け込み的な増加とその後の反動減がみられた(第1-1-13図(1)(2))。前々回の消費税率引上げ(1997年4月:税率3%から5%)の際には、消費税率引上げの1年半前頃から持家や貸家を中心に新設住宅着工数が増加傾向となり、増税前の税率が適用される契約期限である消費税率引上げの半年前頃をピークに減少傾向となっている。また、前回の消費税率引上げ(2014年4月:税率5%から8%)の際にも同様の傾向がみられ、消費税率引上げの1年半前頃から新設住宅着工数が増加傾向となり、消費税率引上げの半年前頃にピークをつけた。ただし、持家について総じてみると、前回は駆け込み反動対策を行った結果、駆け込みの程度は、前々回と比べると小さめであった。
今回の消費税率引上げ(2019年10月予定:税率8%から10%)については、税率引上げの1年前を切った時点(2018年11月)でも明確な上昇は確認できていないが、いずれにせよ、住宅着工に大きな変動が生じることは景気全体の変動も大きくなり景気動向の上でも望ましくないものであり、今回の対応策としても、住宅ローン減税やすまい給付金などが予定されている(付図1-4)。こうした対策によって、消費税率引上げ時の住宅建設の動向が平準化されることが期待される。
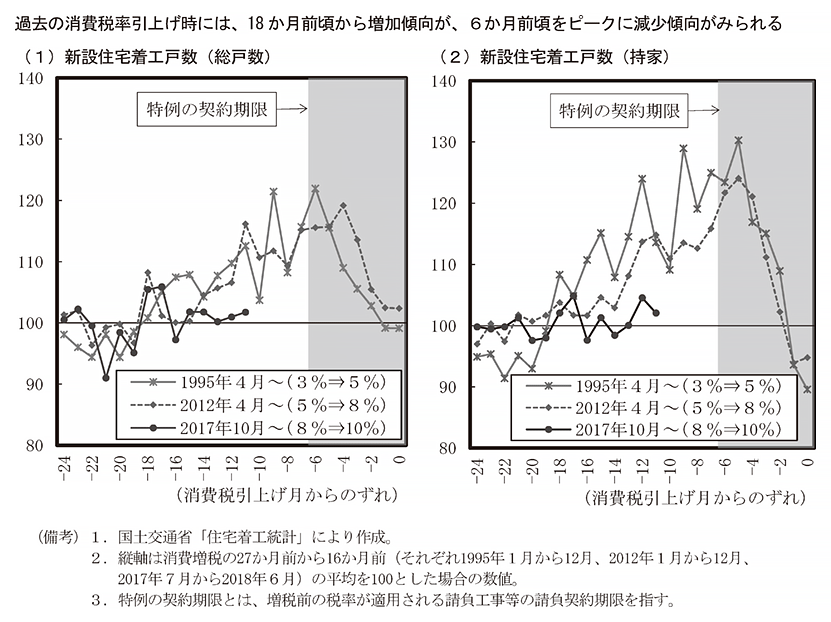
(公共投資の動向)
公共投資のこの数年の動向を公共工事出来高により確認すると、「未来への投資を実現する経済対策」(2016年8月2日)を踏まえた平成28年度第2次補正予算の効果もあり、2017年春頃から夏にかけて増加した。その後、補正予算の効果がはく落する中で、底堅く推移したものの、年末には弱含みとなっている(第1-1-14図(1))。ただし、平成30年度補正予算が措置されることにより、一定の事業量は確保される見込みである9。また、近年は交通インフラ等を中心に複数年にわたる大型工事の受注が増加していること等を反映して手持ち工事高が高水準となっているが、2018年に入ってやや低下していることから、大型案件が徐々に進捗している10とみられるほか、2018年夏頃には九州豪雨対策などを柱とした平成29年度補正予算の効果が九州地方などで現れていることも、公共投資を下支えしている(第1-1-14図(2)(3)(4)(5))。
「建設業景況調査」(平成30年9月)によると、近年の建設業における経営上の問題点として、受注の減少や競争激化を挙げる企業の割合が低下しているのに対して、人手不足を挙げる企業が増加を続け最も多く、深刻さを増している(第1-1-14図(6))。また、従業員の高齢化についても経営上の問題として指摘する企業が多いことから、若い世代の従業員の確保が難しいことがうかがえる11。深刻化する建設業の人手不足を解消するため、働き方改革による一層魅力的な職場づくり、i-Constructionによる生産性向上などの政策を進めることにより、企業が円滑な工事を進められるようにすることが、今後重要である。
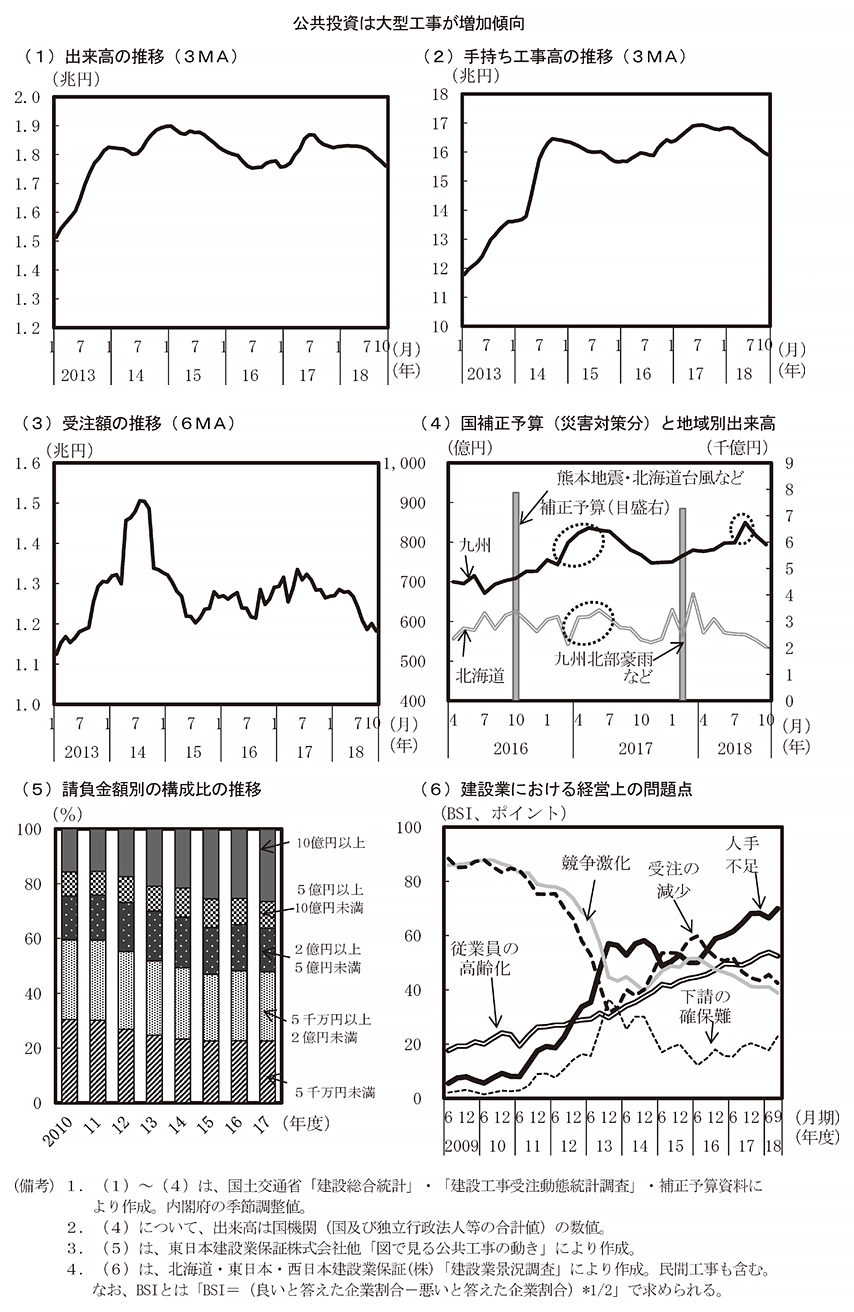
(金融資本市場の動向)
日本銀行は2%の物価安定目標の実現を目指し、累次の金融緩和の強化策を行っている。2016年以降においては、2016年1月に「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入を決定し、同年9月には「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」を導入した。さらに、2018年7月には、強力な金融緩和を粘り強く続けていく観点から、政策金利のフォワードガイダンスを導入することにより「物価安定目標」の実現に対するコミットメントを強めるとともに、「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」の持続性を強化する措置を決定した。このフォワードガイダンスの中で、「日本銀行は、2019年10月に予定されている消費税率引上げの影響を含めた経済・物価の不確実性を踏まえ、当分の間、現在の極めて低い長短金利の水準を維持することを想定している」とされたほか、長期金利については、「10年物国債金利がゼロ%程度で推移するよう、長期金利の買入を行うことを維持しつつ、その際、金利は、経済・物価情勢等に応じて上下にある程度変動しうる」とし、イールドカーブ・コントロールに一定の弾力性を持たせることとされた。
2016年以降の国債利回りの動向をイールドカーブの変化を通じてみると、2016年1月のマイナス金利政策の導入によって、金利にさらなる下押し圧力が加わったことで、イールドカーブ全体が低下したほか、特に長い年限の金利水準が大きく低下したことによって、イールドカーブはフラット化した。その後は、2016年9月に導入された「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」の下で、短い年限の金利水準は小幅のマイナス圏で推移する中で、10年債利回りはおおむねゼロ%程度のプラス圏で安定的に推移し、長い年限の金利水準は上昇した。2018年7月の金融政策決定会合で「強力な金融緩和継続のための枠組み強化」を導入した後、長期金利は上昇したが10月上旬をピークにその後は下落した(第1-1-15図(1)(2))。
2018年に入ってからの日経平均株価の動きをみると、年初は好調な企業収益を背景に上昇したものの、その後は、アメリカの長期金利の上昇や米中間の通商問題への懸念などを背景にアメリカの株価が大きく下落したことを受け、投資家のリスク回避姿勢の強まりから下落し、3月末には、1月末の高値から約15%下落した(第1-1-15図(3))。4月以降は、好調な国内企業の業績やアメリカ経済の回復に支えられ、10月には1991年11月以来、27年ぶりに24,200円台まで上昇したものの、その後は、米中間の通商問題への懸念や、アメリカの一部企業の業績への懸念などを背景としたアメリカの株価下落の影響により、水準を下げて推移している。
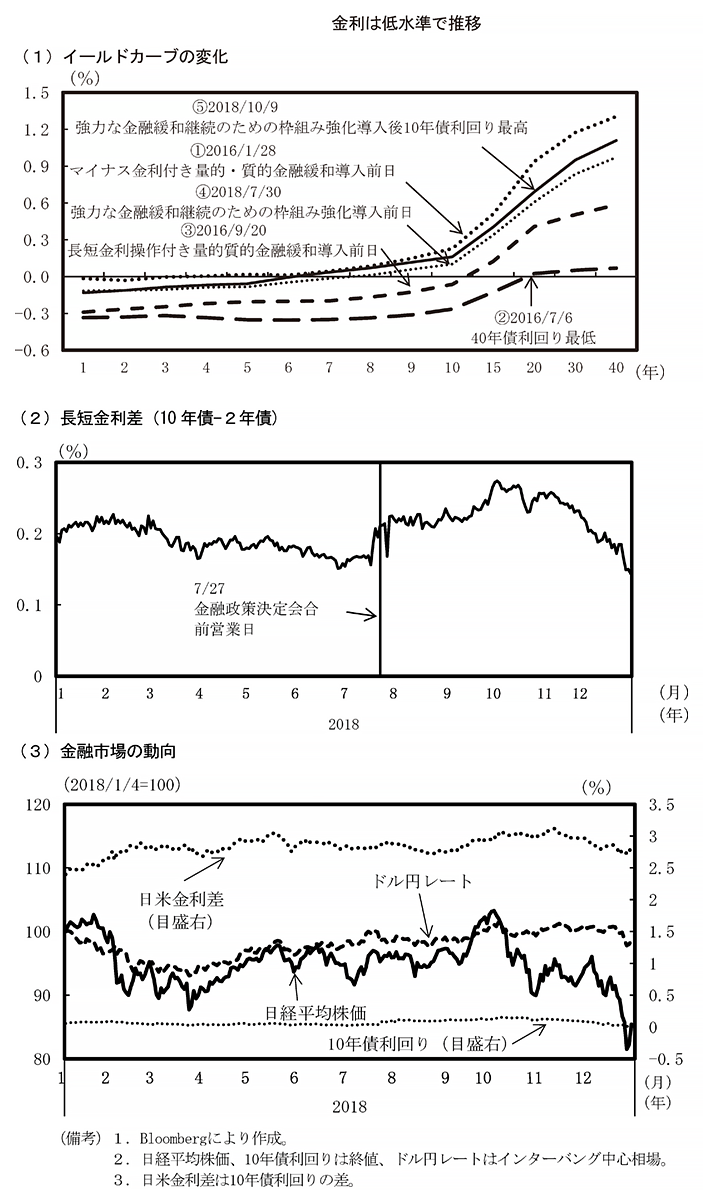
(金融機関の貸出の動向)
民間金融機関のバランスシートの動向をみると、日本銀行の長期国債などの資産買入の対象が、主に民間金融機関が保有する資産であったことから、民間金融機関の保有する国債を含む債務証券は2013年以降大きく減少した一方、日銀当座預金がその分大きく増加したほか、貸出も緩やかながら増加している。(第1-1-16図(1))。
次に、国内銀行の預金金利と貸出金利の動向をみると、マイナス金利が導入された2016年1月以降、国内銀行の貸出金利が一段と低下し、マイナス金利政策は企業の資金調達のコストの低下という効果を一定程度もたらしている。一方で、預金金利は、マイナス金利導入前から低位で推移しており、貸出金利ほど下げることができなかったことから、もともと低かった預貸スプレッドがさらに低下し、国内銀行の収益を下押し12することとなった(第1-1-16図(2))。ただし、2018年7月に日本銀行がイールドカーブ・コントロールに一定の弾力性を持たせる変更を行ったこともあり、預貸スプレッドはやや拡大した。
国内銀行の貸出残高の動向をみると、おおむね前年比3%程度の伸びを実現しており、緩やかに伸びている。貸出先の内訳をみると、これまで個人向けや中小企業向けの貸出残高の寄与が高かったものの、2018年半ば以降、運転資金向けを中心に大・中堅企業の寄与が高くなっている。(第1-1-16図(3))。
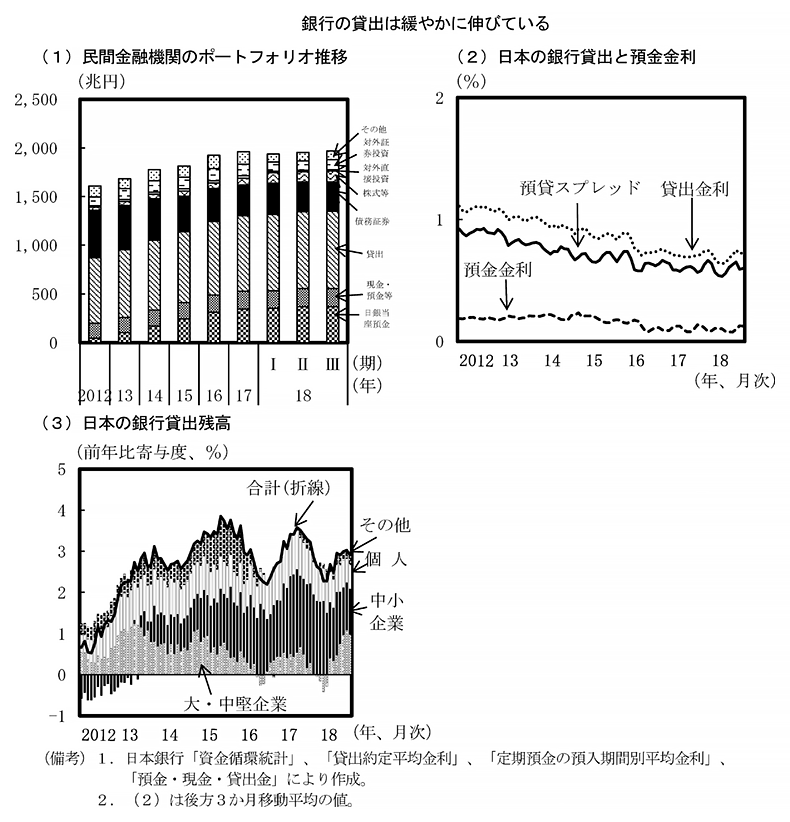
コラム1-1 邦銀の海外貸出の動向
邦銀の貸出動向をみると、国内向けの貸出が緩やかに伸びている中、日本企業の海外進出が進むにつれ、海外向けの貸出は国内向け以上に伸びており、海外への貸出割合は都市銀行で3割弱となっています(コラム1-1図)。
銀行の国際与信総額の推移をみると、邦銀は増加傾向で推移し、リーマンショック後、欧米の銀行が伸び悩む中、日本の銀行の国際与信総額は世界一となっています。また、邦銀の国際与信残高を地域別にみると、アメリカ向けが最も大きく、次いで欧州向け、アジア・太平洋向けとなっているものの、伸び率でみるとアジア・太平洋向けが近年高くなっています。
この背景として、邦銀はこれまで日本企業の海外進出に対して金融面でサポートしてきたこともあり、海外現地法人数が増加傾向にあることがあげられます。地域別にみると、アジア地域が他地域に比べて、特に製造業の現地法人の売上高経常利益率が高い13など、収益性の高さも一因となり、現地法人数が大きく増加しています。
このように邦銀は、国内での貸出を伸ばすのみならず、融資先として成長が続く海外市場にも積極的に進出しています。ただし、海外融資には相応のリスクを伴うことから、財務体質を強固にし、安定的な収益をあげるためにも、今後も適切な融資先の選定等によりリスクを管理することが重要と考えられます。
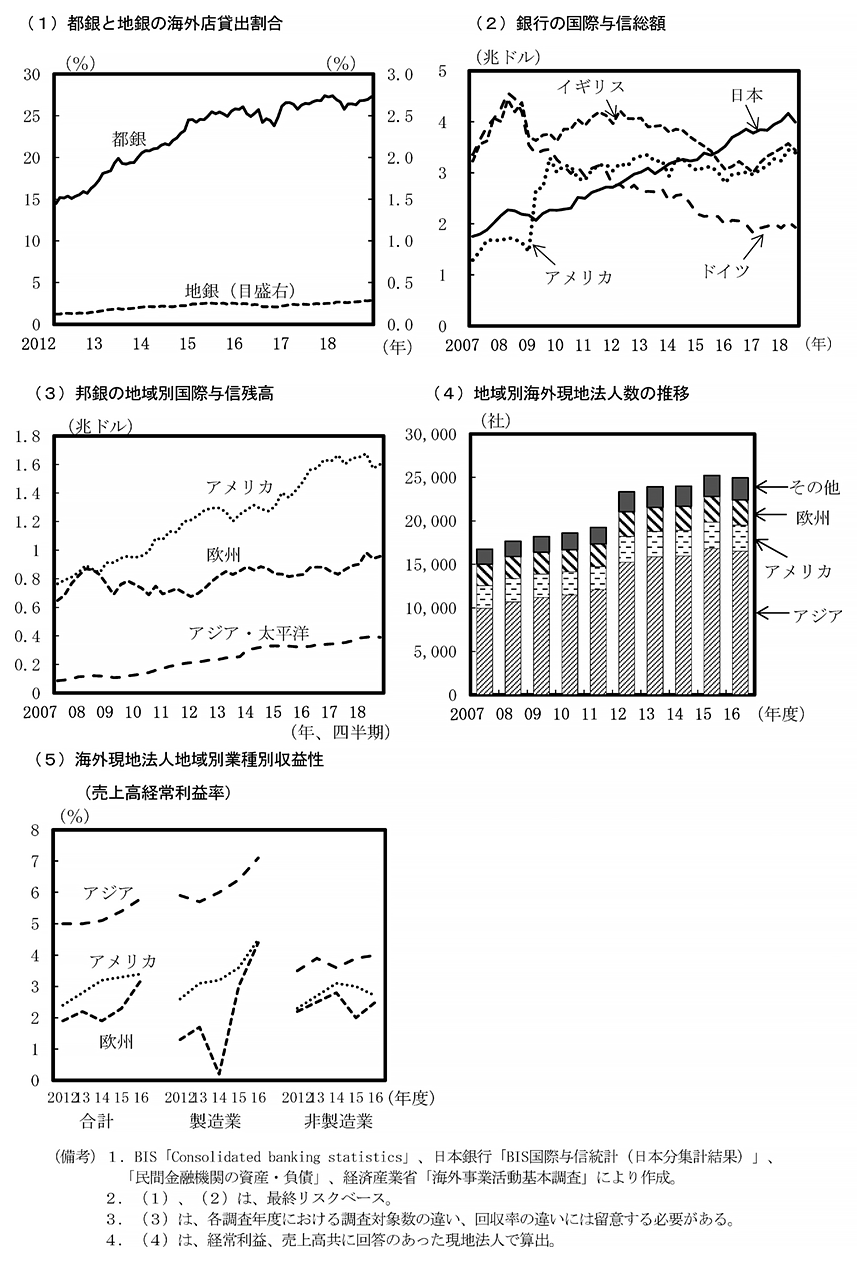
4 自然災害の影響
(自然災害の影響)
2018年の我が国経済は、6月末から7月上旬にかけて西日本を中心に発生した平成30年7月豪雨、9月4日に四国地方、近畿地方を中心に上陸した台風21号、9月6日に発生した平成30年北海道胆振東部地震など、相次ぐ自然災害により、大きな被害を被った。
地域別の生産動向をみると(第1-1-17図)、中国地方では平成30年7月豪雨の影響により、自動車会社や建設機材の製造会社が被害を受けたため7月に大きく減少した。ただし、その後は、復旧が進み、8月以降生産が徐々に回復している。
北海道では、平成30年北海道胆振東部地震の影響により、石油・石炭、紙パルプ、食料品などで生産が減少したことで生産活動が大きく低下した。また自動車会社の北海道工場が一時稼働停止となったことや同工場の部品供給が止まったことによるサプライチェーンの影響もあり、全国的に自動車の生産が減少した。
一方、平成30年7月豪雨や9月の台風21号の影響を大きく受けた近畿地方の生産は、若干の影響を受けたものの、他の被災地域に比べると減少が限定的となっている。
2018年10月の動きをみると、各地域とも生産活動が戻ってきており、自然災害の影響から着実に回復している姿が確認できる。
なお、参考までに、2016年熊本地震の際の九州地方における鉱工業生産の動きをみると、地震発生時の2016年4月に大きく落ち込んだが、6月にはほぼ元の水準に回復した。
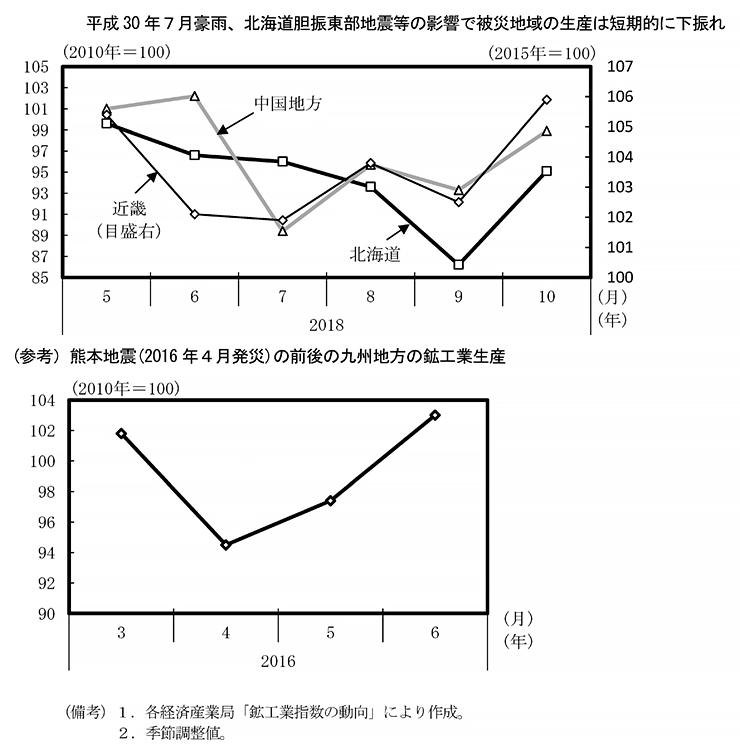
次に訪日外国人数の動向をみると(第1-1-18図(1))、増加傾向にあったが、2018年夏の自然災害の影響で旅行客のキャンセルが相次ぎ、2018年9月には215万9,600人(推計値)と前年同月比5.3%減となり、2013年1月以来、5年8か月ぶりにマイナスに転じた。ただし10月以降は戻ってきており、今後も増勢が回復することが期待される。
空港別の訪日外国人数をみると(第1-1-18図(2))、関西国際空港や新千歳空港から入国した訪日外国人数が9月に大きく減少しており、関西国際空港の一時閉鎖や平成30年北海道胆振東部地震が影響したと考えられる。ただし関西国際空港では、10月には前年比でプラスに戻っており、回復の早さがうかがえる。なお中部国際空港の利用者は増加しており、一部では空港を代替したとみられる。貨物額(輸出)の推移をみると、関西国際空港14では9月に大きく落ち込み10月時点でも若干のマイナスとなっており、自然災害の影響の大きさがわかるが15、新千歳空港ではいずれの月もプラスとなっており、貨物輸出への影響はあまりなかったとみられる。
地域別の宿泊者数の動向をみると、2016年の熊本地震の際は、2016年4月、5月と大きく落ち込み、6月、7月もその影響が残ったが、今回は2018年7月の西日本豪雨の影響を受けた中国地方では9月時点で前年比プラスに回復しており、比較的早く回復している(第1-1-18図(3))。近畿地方についても、9月にマイナス幅が若干拡大したものの10月にはプラスに戻っている。北海道は9月に前年比で2割を超える大きな落ち込みとなり、10月でも前年比約5%の減少となっている。
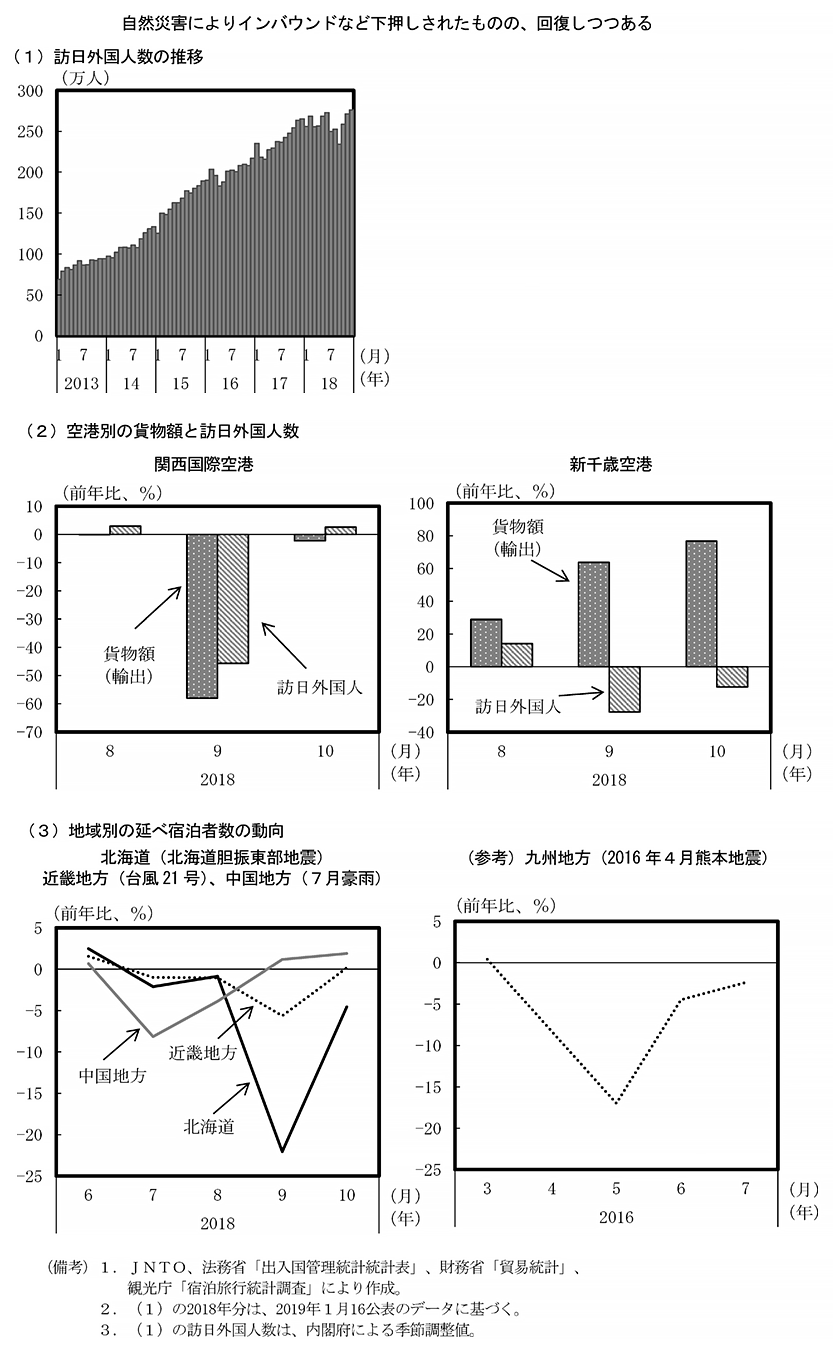
地域別の景況について、景気ウォッチャー調査の現状判断DIでみると、平成30年7月豪雨で大きな被害を受けた中国地方は7月に大きく落ち込み、北海道胆振東部地震で大きな被害を受けた北海道は9月に大きく落ち込むなど、一時的な悪化がみられたが、その後、徐々に回復し、中国地方では10月以降、北海道では11月には全国平均を上回っている(第1-1-19図)。
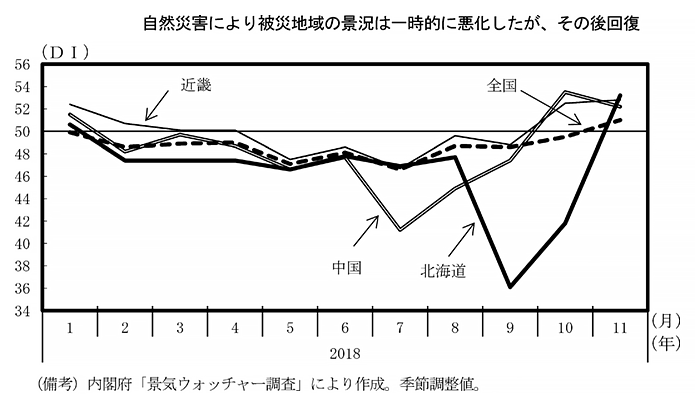
平成30年7月豪雨では、西日本を中心に多くの地域に被害をもたらしたが、影響試算の推計方法の開発について解説した田中・新田(2018)では、住宅や民間企業保有の機械設備・建屋等、社会インフラを含むストック全般の損壊額を約0.9~1.7兆円、フローの直接的な損失額を約1,000~1,300億円、サプライチェーンを通じた生産波及効果も合わせた自地域・他地域へのフローの損失の合計額を約1,500~1,900億円と試算している16。
9月の台風21号は、近畿地方を中心に大きな被害をもたらし、特に関西国際空港が一時閉鎖となったことを通じ、輸出への影響を及ぼした17。
9月の平成30年北海道胆振東部地震では、北海道庁公表資料によると(付表1-5)、公共土木施設、農林水産業、商工業等における地震と停電による被害総額は約2,312億円、停電により影響を取りやめたことによる商工業の売上への影響額は約1,318億円、宿泊施設のキャンセル数をもとに、交通費や飲食店土産物消費などを含めた観光消費影響額は約356億円となった。

