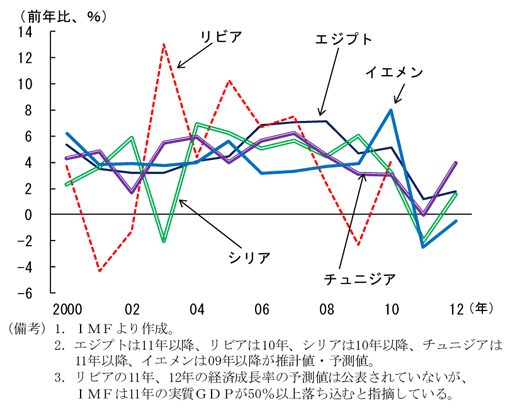2.金融資本市場の緊張:質への逃避
(1)金融資本市場の緊迫とボラティリティの上昇
2011年7月以降、欧州政府債務問題(第2章第1節参照)、アメリカ経済の減速懸念や連邦債務法定上限引上げ問題(第2章第2節参照)を背景に、市場参加者の投資意欲が急速に悪化し、リスク回避姿勢が強まり、投資家の資金はリスク資産とされる株や原油を回避し、安全資産とされる米国債や金に流れた。
各資産の価格の推移をみると、株価及び原油価格が下落する一方で、安全資産とされる米国債の価格は大幅に上昇(長期金利は大幅に低下)し、金価格は史上最高値を更新し続けた後、一度下落したものの、再び上昇に転じている(第1-1-13図)。
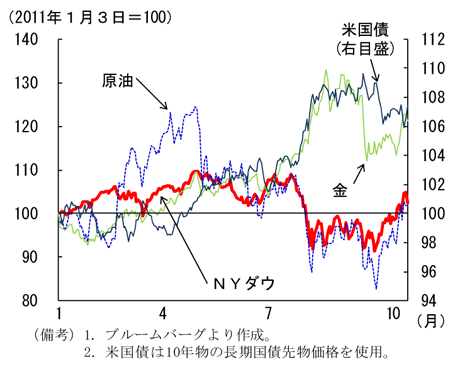
この間の投資家のリスク回避姿勢の高まりについては、市場で取引されている金融資産の価格変動の大きさを表すボラティリティが大幅に上昇したことからも見て取れる。例えば、VIX指数をみると、11年夏の変動は10年5月のギリシャ財政危機時の水準を大きく超えている(第1-1-14図)。ボラティリティの急上昇は、それ自体が金融機関等の市場参加者のリスク許容度を低下させることで、市場参加者のリスク回避的な動きを更に惹起する。しかし、市場参加者がリスク資産を売却し安全資産を購入することで、市場が更に一方向に動き、結果として、一層のボラティリティ上昇をもたらすことになる。この時期に、このような悪循環が起きたと考えられる。
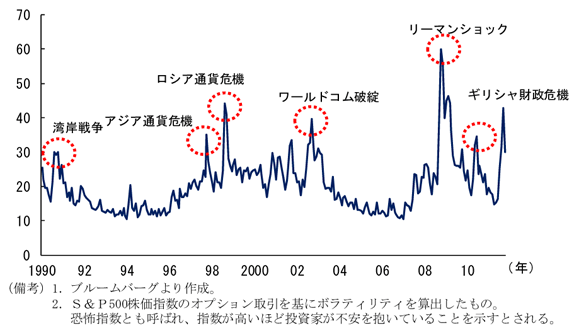
このようにボラティリティが上昇し、リスク回避的な動きが発生した11年夏の局面における各資産の動きについて、以下、具体的に見ていく。
(2)世界的な株価下落
主要国の株価は、10年夏以降、世界経済が全体として回復基調を維持していたことなどから上昇していたが、11年夏に入ってからは、軒並み大幅下落となった。11年7月から8月初めにかけては、アメリカ経済の減速懸念により特にNYダウ平均株価(以下「NYダウ」という。)が下落し、8月後半から9月にかけてはギリシャのデフォルト懸念により特にドイツ株価指数(以下「DAX」という。)が下落した。その後も乱高下を繰り返した後、10月下旬のEU首脳会議における合意等を背景に、上昇した(第1-1-15図)。
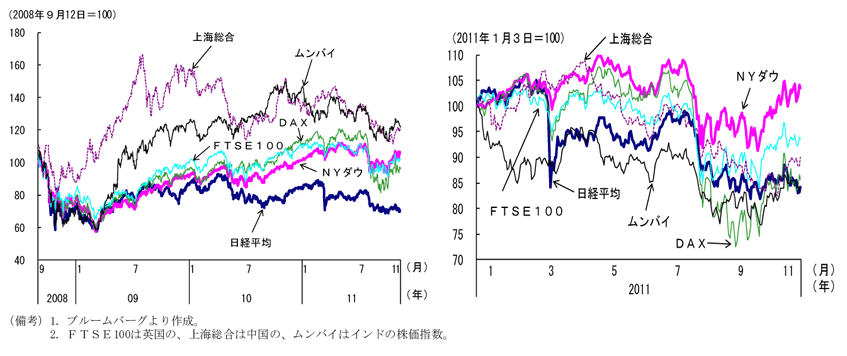
11年夏のNYダウとDAXの下落局面を、08年9月の世界金融危機発生直後の下落局面と比較すると、今回の局面においては、DAXにおける変動がNYダウより大きいことが特徴的である。(第1-1-16図)。これは、世界経済の減速に対する懸念もさることながら、やはり、欧州政府債務問題に対する懸念が強いことにより、震源地であるヨーロッパの市場がより強く影響を受けていることによるものと考えられる。
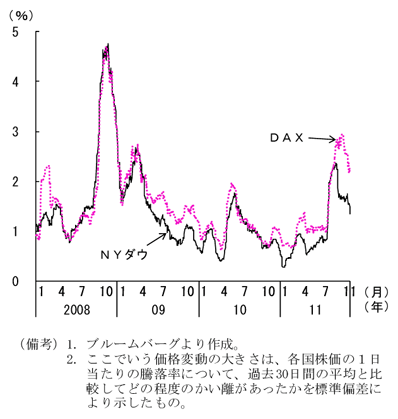
(3)リスク資産である原油の価格下落
かつて原油価格は株式等の動きとはほぼ無相関であったが、商品ETFの開発等により金融商品化が進み2、幅広い投資家の運用先としてポートフォリオに組み入れられるようになった。その結果、リスクオン(投資家が積極的にリスクを取ること)の局面では株と原油がともに買われ、リスクオフ(投資家がリスクを回避すること)の局面ではともに売られる傾向がみられるようになった。
主に投機的な目的で売買を行う投資家(以下「非当業者」という。)が原油相場に与える影響は年々強まっている。非当業者の取引量は増加し、建玉(先物取引等において未決済である契約)全体に占める割合は1990~99年に7.8%、2000年~09年に14.8%、10年以降は21.7%と上昇しており、買い越し高と原油価格との相関は強まっている(第1-1-17図)。
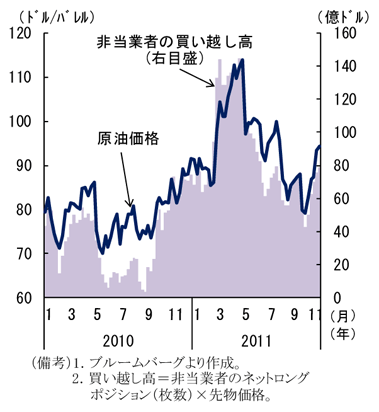
非当業者はリスクオンの際には原油の買い持ちを大きく増やすが、リスクオフの場合は大幅に持ち高を縮小させる。そのため原油価格は振れやすくなり、変化幅は大きくなっている。原油価格変化率のカーネル密度関数3をみると、2000年代前半よりも2000年代後半の方が平均より離れた値が発生する確率が高まっている(第1-1-18図)。
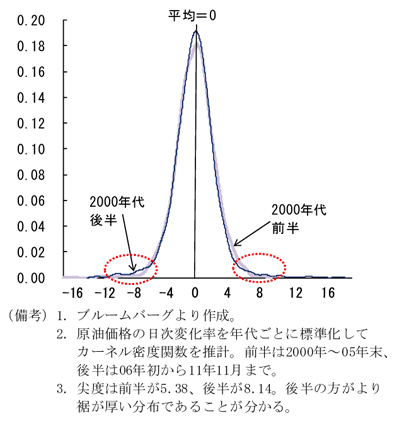
このようにリスク資産としての性格を強めた原油は、10年を通じて上昇基調で推移し、11年に入ってからも4月までは騰勢を強めた。この間、非当業者の買い越し高は増加しており、株価上昇や世界景気の回復等を背景に、リスクオンの動きが強まっていた様子がうかがえる。しかし、5月からは調整局面に入り、その後、欧州政府債務問題等を受けて一転してリスクオフの動きとなり、8月には約10カ月ぶりに80ドル台を割るなど原油価格は急落した。
コラム1-1:WTI原油と北海ブレント原油の価格差はなぜ拡大しているか?
WTI原油と北海ブレント原油(注1)の価格は、WTIが北海ブレントを上回る状態が続く中で、2010年末まではおおむね同様の動きとなっており、価格差も安定していた(図1)。しかし、11年に入ってからは、両者の価格差(北海ブレント‐WTI)は拡大を続け、同年9月には約25ドルとなった。基本的に北海ブレントと連動した値決めがなされるドバイ原油に関しても、WTIとの価格差が開いた。
硫黄含有量がより低い(より良質な)WTI(注2)の価格が、北海ブレントやドバイの価格を上回るのが自然とも考えられるが、実際には、北海ブレントやドバイの価格がWTIを上回り、かつ、価格差が拡大している。その理由として、主に中東・北アフリカ情勢の緊迫化とアメリカの原油在庫の動向の2つが挙げられる。
中東・北アフリカ地域で産出される原油の多くはヨーロッパに輸出されていた。中でもリビア等では軽質油が産出されることから、ヨーロッパにとって重要な供給源の一つとなっていた。しかし、内戦等を背景にリビアの原油生産が停止されたことなどから対ヨーロッパ輸出が滞り、北海ブレントへの需要が強まった。図2に示す通り、11年の初めから春先にかけては、中東・北アフリカでのデモ等が報道されるほど北海ブレントは上昇し、原油価格差は拡大した。これが第一の要因である。
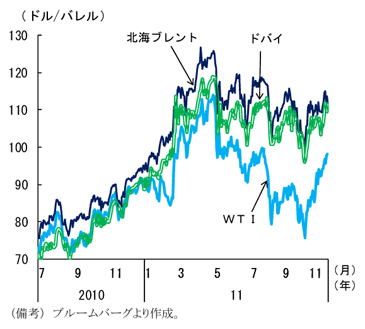
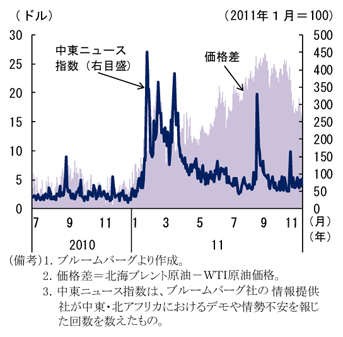
しかし、11年4月頃より政情不安がおさまりつつあるにも関わらず、価格差は拡大を続けており、中東・北アフリカ情勢以外の要因も、価格差拡大に影響していることが示唆される。
第二の要因は、アメリカの原油在庫の動向である。同国の原油在庫は、11年に入ってからはやや頭打ち感がみられるが、歴史的にみて高い水準にある(図3)。その背景には、アメリカ企業がカナダで採掘した原油の流入が続く一方で、WTI原油の引渡し場所であるオクラホマ州からメキシコ湾へのパイプライン(注3)整備が遅れており、在庫が高水準となっていることがある。他方、ヨーロッパでは北海ブレントへの需要が高まる中で生産量が減少しており、原油在庫は低水準にある。北海ブレントに連動した値決めとなっているドバイに関しても、アジア新興国をはじめとする需要が堅調である。したがって、WTIには価格下落圧力がかかりやすい一方で、北海ブレントやドバイには上昇圧力が作用しやすく、価格差が拡大したと考えられる。
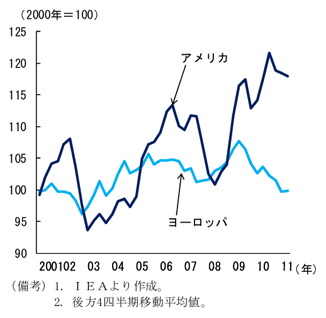
これほど価格差が開けば、裁定が働いて価格差が是正されてもおかしくないのではないかとも考えられる。しかし、IEA(2011b)によれば、原油をアメリカからヨーロッパに輸送する際のコストは15ドル/バレル程度とされている。価格差が20ドル以上開いている状態が続いていることを踏まえると、裁定は働いていないと考えられる。その背景として、既述したようなアメリカ国内のパイプライン整備の遅れといった物理的な制約がある中で、安全性の面からパイプライン以外の輸送が行われにくいとの見方がある。
もっとも、市場では、中長期的には価格差が是正されるとの見方もある。WTIと北海ブレントの先物カーブをみると、11年8月の時点では両者の価格差は17年になっても開いたままであった(図4)。しかし、11年11月の時点では、両者の価格が17年に同水準となっている。中西部とメキシコ湾岸を結ぶパイプラインが開通すれば、アメリカ国内の原油在庫の積み上がりが解消され、北海ブレントとWTIの価格差が縮小していくことが織り込まれていると考えられる。
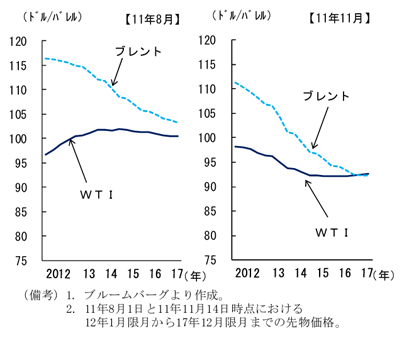
コラム1-2:高まるシェールガスの存在感
世界的に原子力発電に対する見直し気運が高まる中、火力発電に用いられる天然ガスへの注目が高まっている。天然ガスは、かつては原油の代替品として位置付けられており、両者の価格はおおむね連動していた(図1)。しかし、2000年代の半ばより、アメリカでは両者の価格はかい離している。その背景として、シェールガスの存在が指摘されている。
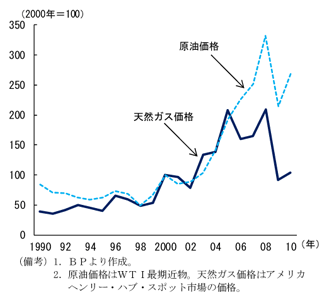
シェールガスは、メタンを主成分とした天然ガスであり、従来の採掘方法で掘り出すことが極めて難しい頁岩(けつがん)層に存在する「非伝統ガス」の一種である。その存在は1800年代から知られていたものの、当時の採掘方法では採掘コストが高く、採掘が進まなかった。しかし、2000年代に入り、地層と水平に掘る「水平掘削法」や圧力をかけて頁岩に亀裂を入れる「水圧破砕法」といった新しい技術の開発に伴って採掘コストが低下し、アメリカで採掘が進められるようになった。その結果、同国の天然ガスの需給バランスが緩み、原油価格と連動しなくなった。また、シェールガスの採掘が進むようになり、1990年代には増加の一途をたどっていたアメリカの天然ガス輸入も、08年の世界金融危機後は減少基調となった。
シェールガスのプレゼンスは大きい。世界の天然ガス資源量(注1)は10年初時点で2京2,600兆立方フィートであり、そのうちの約30%(6,622兆立方フィート)がシェールガスとなっている(注2)。そして、シェールガスの地域別分布をみると、アメリカを中心に北米が29.2%を占め、最大の資源賦存地域となっている(表2)。それ以外の地域に関しては、中国等のアジア(21.0%)、アルゼンチン等の南米(18.5%)のシェアが大きい。
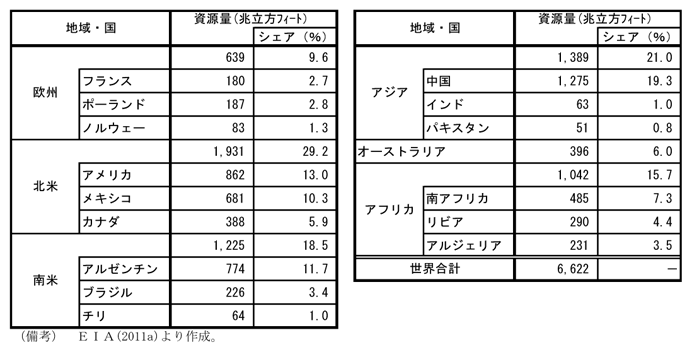
今後もアメリカではシェールガスの採掘が進むと見込まれており、09年時点で13.9%であった同国の天然ガス供給に占めるシェールガスの割合は、35年には46.1%まで拡大すると予測されている(図3)。その結果、アメリカでは原油価格と天然ガス価格は乖離し続けることが見込まれている(図4)。2000年を100とすると、原油価格は35年に約370と4倍近くまで上昇するのに対し、天然ガスは約140と2倍にも満たないと見通されている。
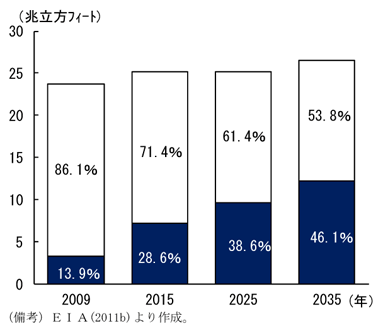
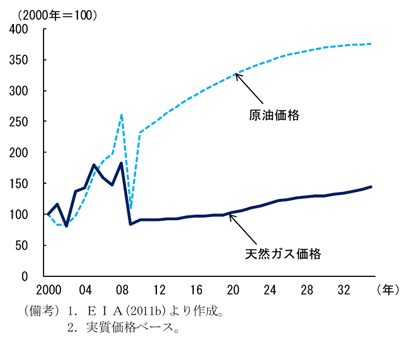
また、アメリカ以外の国でも多くのシェールガスが存在しており、今後は、中国等でもその採掘が進む可能性もある(表2)。IEAは、中国やインド等でシェールガスの採掘が行われれば、世界全体の天然ガス供給に占めるシェールガスの割合は、08年の2%から35年には11%まで拡大するとの見方を示している(注3)。採掘によって地下水が汚染されるなど環境汚染のおそれが一つの懸念材料とされ、一部の国ではシェールガス生産を禁止しているが、国連が環境問題を起こさない採掘方法の基準を作成する方針を示すなど、世界的にシェールガスの普及を後押しする動きもある。
現在、日本をはじめとするアジア諸国は、原油価格連動型の長期契約で天然ガスを調達している。しかし、このようにシェールガスのプレゼンスが拡大を続ければ、世界の需給バランスが変化し、より安価に天然ガスを輸入できる可能性もあるだろう。
(4)歴史的な低金利、CDSプレミアムの上昇
前述の通り、世界的に株価が下落する中、安全資産とされている米国債やドイツ国債に資金が流入し、両国の国債利回りは大幅に低下した(第1-1-19図)。11年9月には米国債(10年物)の利回りが史上最低水準となる2%割れを記録するなど、両国の国債利回りは歴史的低水準に達した。
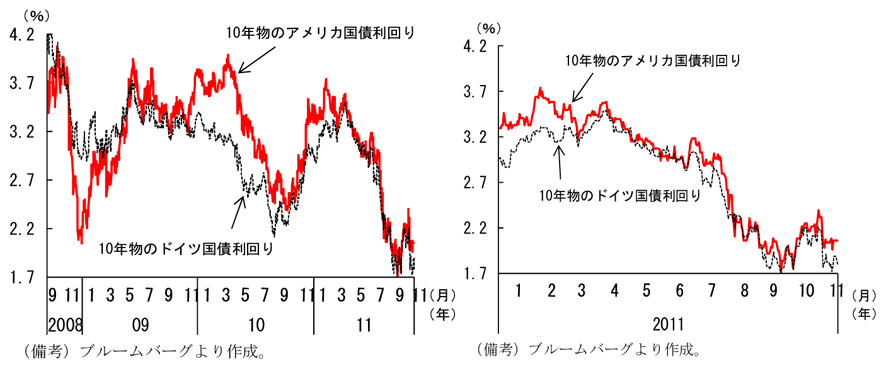
このような中、11年夏の欧米の国債市場及び国債CDS4が取引される市場(ソブリンCDSマーケット)では、長期債券の利回りやCDSプレミアムが短期のそれと比べ高いのが通常5であるところ、当該債券のデフォルトリスクを市場が織り込むことで、それらが逆転するという不思議な現象が見られた。
まず、アメリカでは、7月に債務上限引上げ問題の混迷から米国債のデフォルト懸念が高まり、米国債のCDSについては、1年物のCDSプレミアムが5年物のCDSプレミアムを上回った(第1-1-20図)。連邦債務の法定上限が期限までに引き上げられない場合において一時的に利払いや償還がされない可能性を市場参加者が織り込んで、1年物のCDSプレミアムが上昇した。その一方で、仮に一時的に債務不履行に陥ったとしても、いずれ法定上限が引き上げられることで中期的な悪影響は限定的との見方から、5年物のCDSプレミアムは一定の水準にとどまっていたと考えられる。同時期のアメリカの国債市場でも、短期金利は急上昇する一方で、長期金利は大幅に低下していた(第1-1-21図)。この背景としては、CDSプレミアムの逆転現象の場合と同様の思惑が働いたことに加え、アメリカ経済の減速懸念により市場参加者の期待経済成長率や期待インフレ率が低下したことなどが考えられる。
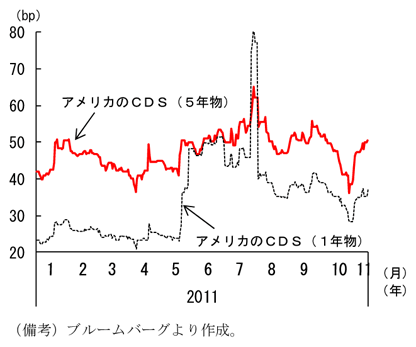
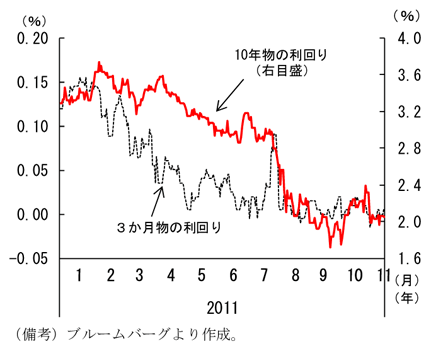
同様の現象は、ギリシャ債務問題への先行き不安や、欧州各国へのコンテイジョン(伝染)に対する懸念を背景に、欧州の国債市場とソブリンCDSマーケットでも見られた。例えば、ドイツ国債については、10年物の利回りが低下を続ける一方で、CDSプレミアムが上昇した。これは、ギリシャ債務問題への懸念から安全資産とみなされているドイツ国債に対する需要が高まり、ドイツ国債の価格が上昇(利回りが低下)する一方、ギリシャをはじめとする欧州周辺国が仮に債務不履行となった場合のドイツ等主要国に対する負の影響をCDSマーケットが多少なりとも織り込んでいたからと考えられる。また、ギリシャやポルトガルの国債利回りは、年限の短い国債の利回りが年限の長い国債の利回りを上回る状態(逆イールド化)となっている。これは市場参加者が、短期については債務不履行が起こった場合の償還や利払いがなされないリスクを、長期については仮に一時的に債務不履行となったとしてもEU等の支援や財政再建の進捗等により将来的には償還可能性が高まることを、それぞれ織り込んでいたことを示唆している(第1-1-22図)。
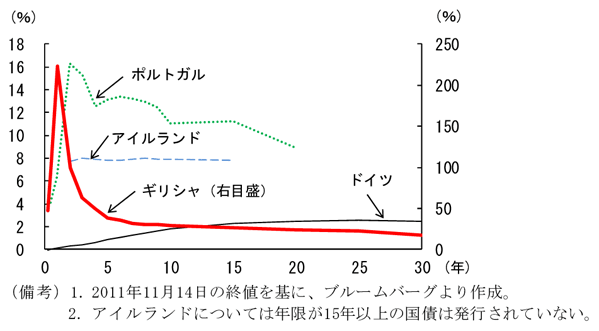
(5)史上最高値を更新し続けた金価格
このようなリスク回避的な流れの中で需要が高まった金融商品の一つに、金がある。11年4月から9月にかけて金価格は騰勢を強め、この間だけでも、史上最高値を32回も更新した6。
元々、金に対する実需は堅調であった。アジア諸国が、プレゼンス拡大とあいまって、外貨準備や宝飾品として金を求める中、金の需要は増加していた(第1-1-24図)。そのため、11年の春先のように投機筋の買い越し高が縮小しても金価格が上昇する局面もあった。さらに、市場がリスクオフになって安全資産を追い求めるようになったことが追い風となり、騰勢を強めることになった(第1-1-23図)。
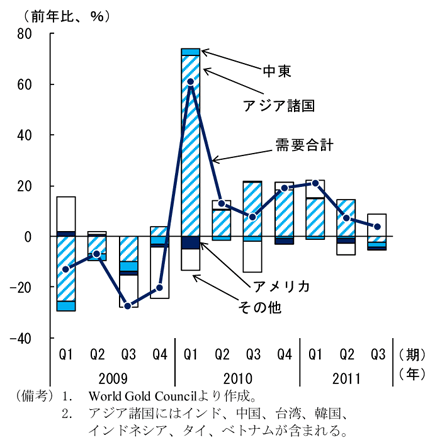
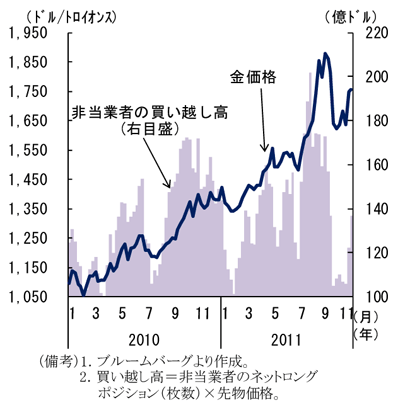
その後、9月半ばになると金価格は急落した。この背景として、株価や商品価格が下落する中、利益を確定するために金が売られたという指摘がある。
(6)ユーロからの逃避、ドルへの回帰
為替市場では11年7月から8月頭にかけて、ギリシャのデフォルト懸念の高まりやアメリカの景気減速懸念、連邦債務法定上限引上げ問題による混乱を背景として、ユーロやドルが減価し、円やスイスフランが増価した(第1-1-25図)。
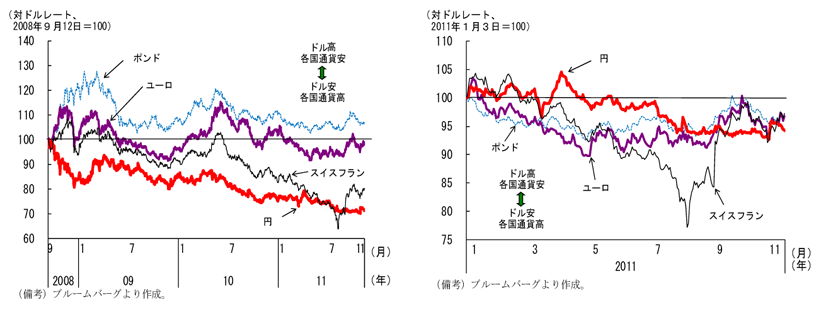
その後、9月に入ると、欧州政府債務問題への根強い懸念から引き続きユーロは弱含む一方で、金融資本市場の不安定な動きを反映し、安全資産としてのドルに資金が回帰し、ドルは10年末の水準まで増価した。
なお、スイスフランは9月以降大幅に減価したが、これはスイスの中央銀行にあたるスイス国立銀行が9月6日に、足元のスイスフラン高がスイス経済の失速やデフレリスクをもたらす恐れがあるとして、1ユーロ=1.20スイスフランの上限を設け、それ以上のスイスフラン高にならないように無制限の為替介入を行う旨を表明したことによる。
この間の為替市場における資金の流れを把握するために投機筋の為替ポジションをみてみると、ユーロのロングポジション(ユーロの買い、ドルの売り)が縮小する一方で、円やスイスフランのロングポジション(円・スイスフランの買い、ドルの売り)が拡大していることが分かる(第1-1-26図)。
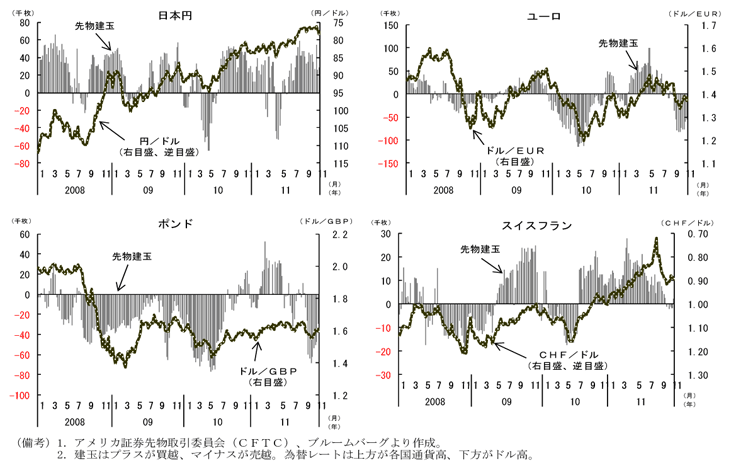
アジア・資源国通貨の多くは、11年に入ってからドルに対して増価していた。しかし、9月、新興国経済を含め世界経済の減速懸念や欧州政府債務問題に対する懸念が強まり、リスク回避のためのアジア・新興国通貨売りによりドルに対して減価の動きが急速にみられた。その後、ギリシャ債務問題へのユーロ圏各国等の対処が進展するにつれ、再び増価した。(第1-1-27図)
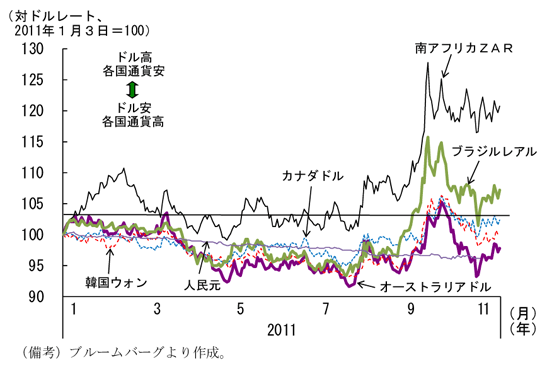
以上みてきたように、為替市場においてはドル全面安からドル全面高へと局面の大きな変化があったが、どちらの局面でも買われていた唯一の主要通貨が円である。円は、11年夏に限らず、08年の世界金融危機、10年のギリシャ財政危機など金融資本市場が不安定になるたびに買われてきた。その理由として、流動性リスクや信用リスクという観点において円がドルと比べても遜色のない通貨であることなどが挙げられる。
市場参加者は、金融資本市場に緊張が走ると、流動性リスクや信用リスクの高い資産の削減に動く。すなわち、為替市場では新興国通貨のような使用頻度が低い通貨や国際的に信用が低い(対外支払い能力が低い)通貨は売られることになる。
流動性という観点では、円はドル、ユーロに次いで世界第3位の取引量となっている。国際的な信用力という観点では、日本は対外債権国であるため、対外支払い能力が高いとされている。これらにより、ドルの動き如何にかかわらず、継続的に円が買われる状況となっていたと考えられる。
コラム1-3:依然として混乱が続く中東・北アフリカ情勢
2010年末にチュニジアでデモが発生したのを皮切りに、中東・北アフリカの多くの国でデモが発生した。チュニジアのデモは、一人の青年が警察に抗議するため自殺を図り、それに対して若者の不満が爆発したことがきっかけで始まったが、政権の長期化や低所得からの改善が見られないことに対する不満が蓄積されていたことから、デモ隊はベンアリ大統領の退陣を求めるようになった。そして、他の中東・北アフリカの多くの国でも、長期政権下で貧困に苦しむ(図1)など、チュニジアと同様の不満が蓄積されていたことから、チュニジアのデモは周辺国に波及していった。中東・北アフリカ諸国は所得水準が低い一方、携帯電話の普及率は高い国が多い(図2)。そのため、携帯電話を用いたSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)等を通じてデモの情報が即座に大人数に伝わり、デモは短期間で広範に拡大することになったと言われている。
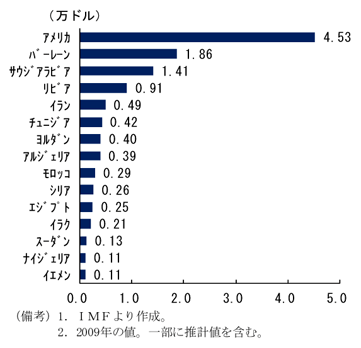
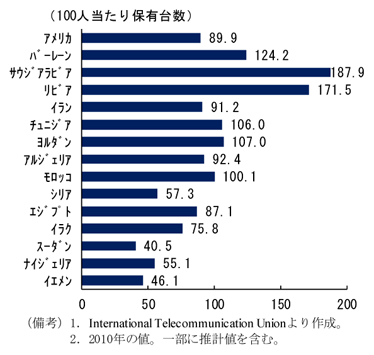
その結果、一部の国では政権が崩壊に追い込まれるに至った。チュニジアでは11年1月にベンアリ大統領が国外に逃亡して閣僚が次々に辞任した後、3月に暫定大統領が就任し、新首相が内閣を組閣した。エジプトでは2月にムバラク大統領が辞任し、3月に新たな内閣が発足した。また、3月以降、軍事衝突が続いていたリビアでも、政権側と反体制側との戦闘の末、8月には首都トリポリが陥落し、カダフィ政権は事実上崩壊した。カダフィ大佐はその後も逃亡生活を続けていたが、10月には死亡が確認され、40年以上に及んだリビアの独裁政権は終焉を迎えた。
これらの国では、不透明な部分が残るものの、新たな政治体制への移行が進みつつある。チュニジアでは10月に憲法制定議会選挙が実施された。同議会では今後、新憲法の起草や新大統領の選出等が行われることになっている。エジプトでは11月末以降に人民議会選挙が段階的に実施される予定となっている。リビアでは10月末に暫定首相が選出されたほか、12年に憲法制定議会選挙が行われるとみられる。
一方、イエメンでは、反体制派の攻撃で負傷し、サウジアラビアで治療を受けていたサレハ大統領が9月に帰国したものの、依然として即時退陣を拒否する姿勢を貫いている。国連安全保障理事会が国民弾圧を非難する決議を採択するなど、国際社会からの圧力は強まっているが、事態打開の糸口はみえない。シリアでは、11月に入ってアサド大統領がデモ弾圧を停止する意向を示した。しかし、その後も戦車の銃撃で市民が死亡するなど混乱は続いている。
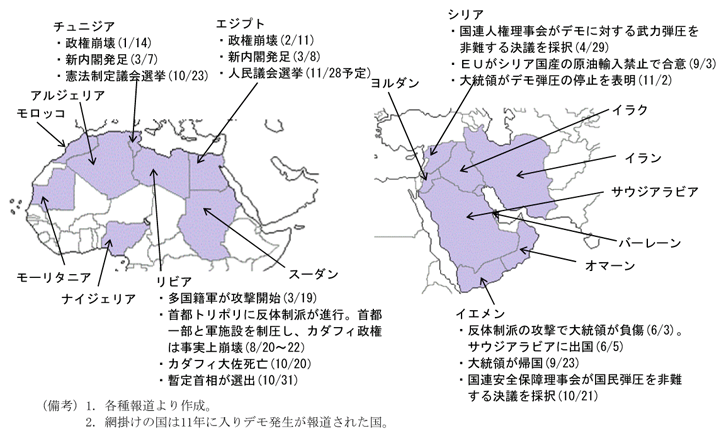
このように事態に沈静化の兆しがみえない国はもちろん、政権が崩壊した国でも、政治的な安定までの道のりが長期化するリスクがある。政情不安の長期化は、中東・北アフリカ諸国の実体経済に悪影響を及ぼすことになる。IMF(2011)によると、これらの国では11年、12年の実質経済成長率が10年より減速したり、マイナス成長に転じる見通しとなっており、景気は当面低迷すると考えられる(図4)。中東・北アフリカ諸国のデモは貧困に対する不満もその背景にあり、国民は、新たな国家体制の下で貧困から脱却するための政策を実施することを政府に期待しているはずである。新政権は、そうした国民の期待を裏切らないよう、政治不安を払拭するとともに、経済改革を着実に実行していくことが求められている。