第3章 コロナ禍を経た企業の倒産・起業の動向(第1節)
第1節 コロナ禍を経た企業の資金繰り・業績と倒産の動向
我が国企業の長期的な倒産件数1を振り返ると、バブルに至る前の1980年代前半は、年平均で18,000件を超えて推移した後、バブル期の1991年には年6,500件程度に減少した。バブル崩壊や1990年代後半の金融システム危機等を経て、2000年代初頭には年19,000件程度まで増加した後、2000年代後半の世界金融危機時に増加する局面はあったが、緩和的な金融環境の下で、長期的に減少傾向で推移した。2020年のコロナ禍に際しては、中小・小規模事業者に対する実質無利子無担保融資(ゼロゼロ融資)2をはじめ、各種の資金繰り支援策が講じられる中、倒産件数は2021年には年6,000件程度まで大きく抑制された。その後、経済社会活動の正常化が進み、各種支援策が縮小・終了する中で、2022年後半以降、倒産件数は増加傾向に転じ、2024年には年10,006件と、2013年以来11年ぶりに年1万件台となっている。本節では、こうした企業倒産に関して、コロナ禍を経た企業の資金繰り状況や業績を確認するとともに、倒産企業の特徴に変化が表れているかを確認する3。
1 企業の資金調達や収益等の動向
(緩和的な金融環境が継続する下で、企業の資金繰り状況は総じて安定的に推移)
ここではまず、コロナ禍前から2024年後半にかけての企業の資金繰り状況について、日銀短観をもとに確認する。全規模・全産業の動向をみると、コロナ禍期間の初期においては、資金繰りが「楽である」と答える企業割合から「苦しい」と答える企業割合を差し引いた資金繰り判断DIのプラス幅が大きく低下したが、マイナスに転じることはなく、1年程度で回復し、総じてみれば安定的に推移してきたことが分かる(第3-1-1図(1))。製造業・非製造業別に見ても大きな違いはないが、非製造業が高い水準で改善傾向であるのに対し、製造業は相対的に低い水準にとどまっており、両者の差がコロナ禍前よりも拡大している。この点の詳細は後述する。
企業規模別にみると、資金繰り判断DIのトレンドに大きな違いはみられない(第3-1-1図(2))4。一般に、相対的に資金力が低い中小企業において、資金繰り判断DIの水準が低い傾向があり、コロナ禍初期(2020年6月調査)においてDIが小幅のマイナス(「苦しい」と答える企業が「楽である」と答える企業割合を上回る)に転じる局面もみられた。ただし、その後、各種資金繰り支援策の効果もあって資金繰りは回復し、大・中堅企業との差は、コロナ禍以前を含め、歴史的にみても縮小した状態が続いている。
この間の金利動向について確認すると、日本銀行は、2024年3月に、2%の物価安定目標の持続的・安定的な実現を見通せる状況に至ったとの判断の下、長短金利操作付き量的・質的金融緩和の枠組みの見直しやマイナス金利政策の解除を決定し、政策金利を短期金利(無担保コールレート(オーバーナイト物))とした上で、マイナス0.1%~0%で推移していた短期金利について、0~0.1%程度で推移するよう促すこととした(第3-1-2図(1))。また、同年7月には、賃上げの動きに広がりがみられることや、輸入物価の上昇を背景に先行き物価が上振れするリスクを踏まえ、政策金利を0.25%程度に引き上げた。さらに、2025年1月には、2%の「物価安定の目標」の持続的・安定的な実現という観点から、金融緩和の度合いを調整することが適切として、政策金利を0.5%程度に引き上げた。貸出金利について、短期の貸出約定金利をみると、2024年9月に多くの金融機関において短期プライムレートが引き上げられたことから、やや上昇したが、0.7%程度と歴史的に見れば極めて低水準で推移している。長期の貸出約定金利についても、長期金利(新発10年物国債利回り)の上昇5を受けて、緩やかに上昇し、2025年1月末時点で1.2%程度と2010年代前半以来の水準になっているが、やはり歴史的には低い水準である(第3-1-2図(2)、(3))。この間、日銀短観に基づく企業の予想物価上昇率は2%程度で推移していることから、名目金利から予想物価上昇率を差し引いた実質金利としては、マイナスが継続している状況にある。こうした金利動向もあり、企業の資金繰りを巡る環境は、総じて安定的に推移していると考えられる。
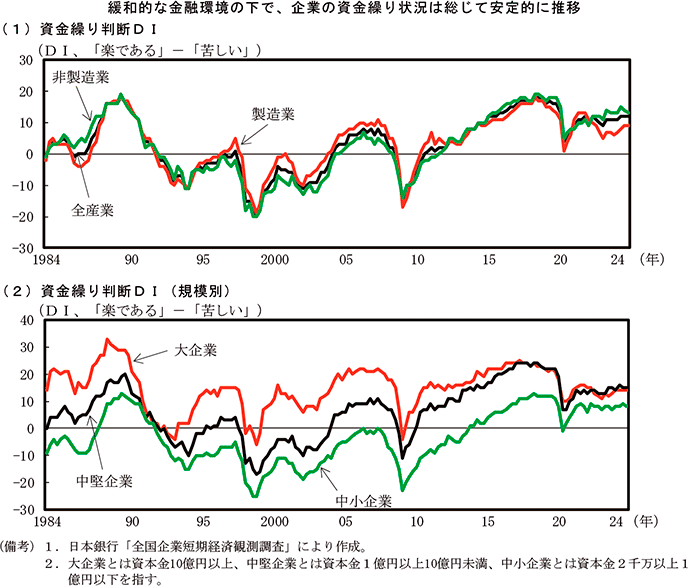

(ただし、業種別には資金繰り判断DIの格差が幾分拡大)
一方、業種別に仔細にみると、企業の資金繰り状況は、ばらつきがあることに注意が必要である。ここでは、資金繰り判断DIが最も高い(相対的に最も資金繰りが楽であるとする)業種と、最もDIが低い(相対的に最も資金繰りが苦しいとする)業種の差を取ると、コロナ禍で大きく拡大した後、縮小傾向で推移しているものの、コロナ禍前の2010年代後半に比べると、業種間格差が幾分拡大していることが分かる(第3-1-3図(1))。この間のDI格差の拡大の背景をみると、コロナ禍初期には、いわゆる対面型サービスである宿泊・飲食サービスや、娯楽等を含む個人向けサービス業といった非製造業の一部において、資金繰りが突出して悪化したことが影響した(第3-1-3図(2)③)。これに対して、直近にかけては、これら対面型サービス業の資金繰り判断DIは、おおむねコロナ禍前の状況に戻りつつあり、DI格差を拡大する要因とはなっていない。他方、化学などの一部の製造業において、資金繰り判断DIが低下傾向にあり、業種間の差の拡大に影響している(第3-1-3図(2)①、②)。こうした結果として、前掲第3-1-1図(1)にもあるとおり、近年の製造業全般と非製造業全般の資金繰り判断DIの格差は、コロナ禍前に比べて拡大している状況にある。なお、企業規模別に資金繰り判断DIの業種間のばらつきをみると、企業規模別の違いはさほどなく、各種資金繰り支援策の効果もあって、中小企業において業種間のばらつきが拡大しているというわけではないことがうかがえる(付図3-2)。
では、コロナ禍を経た近年において、資金繰り動向の業種間格差が拡大した状況が続いている背景はどこにあるのであろうか。ここで、日銀短観で公表されている30業種のうち、資金繰り動向の下位5業種と資金繰り動向の上位5業種について、2014年以降の仕入れ価格判断DIと資金繰り判断DIの分布を描くと、資金繰り動向が下位の業種については、仕入価格判断DIと資金繰り判断DIに緩やかな負の関係がみられる(第3-1-4図(1)、(2))。資金繰り判断DIの業種間格差の拡大には、各業種における個別事情も影響していると考えられるが、近年の円安の急速な進行も相まって、輸入物価の上昇を起点として生じた物価上昇局面において、原材料コスト比率が相応に高い業種等では、資金繰りにも影響が生じている可能性もあると考えられる。

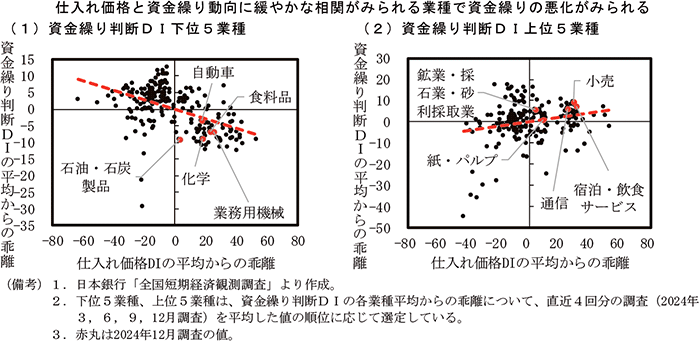
(大・中堅企業について、収益格差は拡大傾向の一方で、財務状況は総じて改善傾向)
次に、コロナ禍を経た企業の収益やバランスシートの状況について、企業間の分布状況を含めて確認していく。ここでは、後述する倒産に関する分析と連携した考察を行う観点に加え、企業の合併・買収といった要因をコントロールする観点から、経済産業省の「経済産業省企業活動基本調査」や「中小企業実態基本調査」をもとに、同一企業の収益・資産負債の状況をみていきたい。
まず、比較的規模の大きい企業を対象とする「経済産業省企業活動基本調査」の調査票情報から、大・中堅企業6の状況を確認する。売上高について、データ初年度の2012年度における上位25%、中央値、下位25%をそれぞれ100の指数とし、各パーセンタイル別の売上高の推移をみると、コロナ禍を経る中で、上位企業と下位企業の格差が広がっていることが分かる(第3-1-5図(1))。売上高経常利益率についても、過去10年で中央値としては2.7%から3.6%に緩やかに上昇している中で、利益率上位10%の企業の利益率は9.8%から12.9%と相対的に大きく上昇している。一方、利益率下位10%の企業については、コロナ禍直後の大きな落ち込みからは回復しているものの、コロナ禍前の0%程度と比べると、直近はマイナス0.8%となっており、上位企業と下位企業の収益率について差が広がっていることが確認できる(第3-1-5図(2))。
続いて、バランスシート情報から得られる純資産比率や流動資産比率をみると、純資産比率の中央値については、過去10年で緩やかに上昇し、上位10%と下位10%の企業の差はおおむね変化なく推移していると言える(第3-1-5図(3))。流動資産比率の中央値については、コロナ禍に幾分上昇しているが、期間を通じてみればおおむね横ばいで推移し、上位10%と下位10%の企業の差に大きな変化はない(第3-1-5図(4))。
一方、有利子負債比率については、中央値でみて、過去10年で緩やかな低下傾向で推移しているほか、有利子負債が高い企業においても、コロナ禍後の上昇はみられるものの、長い目でみれば僅かながら低下した状態にあることが確認できる(第3-1-5図(5))。なお、有利子負債比率が低い企業は、過去10年間で有利子負債がゼロになっているが、これは大・中堅企業の一定部分は有利子負債のない、いわゆる無借金企業であることを示している。こうした有利子負債比率がゼロの無借金企業の大・中堅企業全体に占める割合をみると、2012年時点で3割を超えた状態から、上昇傾向で推移し、コロナ禍で一旦低下したものの、直近では36%まで高まっている(第3-1-5図(6))。関連して、企業の借入金利負担7(支払利息/有利子負債額)をみると、平均金利負担が少ない上位企業(信用力が相対的に高い企業)では、2012年前時点で既に0.6%程度と極めて低位であることから、直近の0%程度にかけて低下の程度が相対的に緩やかなものとなっている一方、金利負担が高い企業(信用力が相対的に低い企業)では緩和的な金融環境の下でより大幅に金利負担が低下している(第3-1-5図(7))。例えば、金利負担の高い上位10%企業では、平均利回りはこの10年間で3.3%から2.2%に1%ポイントほど低下している。
このように売上高や利益率といった収益面では、コロナ禍を経て、上位企業と下位企業の間で差が広がっている一方で、この間の金利低下もあって、バランスシート面の諸指標については、上位企業も下位企業の差が拡大することなく、同様に推移していることが分かる。

(中小企業については、下位企業の負債比率、純資産比率がコロナ禍前より悪化)
続いて、中小企業の収益やバランスシートの状況について、「中小企業実態基本調査」の調査票情報を用いて確認する8。まず、前掲第3-1-5図(1)と同様に、データ初年度(ここでは2018年度)の売上高上位25%、中央値、下位25%をそれぞれ100とし、各パーセンタイル別の売上高の推移を確認する。これによると、コロナ禍後、大・中堅企業と同様、上位と下位の企業における売上高の格差が広がっているほか、上位企業ではコロナ禍前の水準を超えている一方、中央値や下位企業ではコロナ禍前の水準に回復していないことが分かる(第3-1-6図(1)①)。費用面についても、商品仕入原価・材料費、労務費・人件費別に、同様にそれぞれのパーセンタイル別に指数化して2018年度以降の推移をみると、原材料コスト(商品仕入原価・材料費)については、近年において総じて上昇がみられる一方、労務費・人件費については、労務費・人件費の下位企業では横ばい傾向で推移しているものの、労務費・人件費の上位・中位の企業では上昇し、企業間の差が顕著に拡大している9(第3-1-6図(1)②③)。また、売上高パーセンタイル別にみた場合、売上規模の大きい企業(上位企業)では、労務費・人件費の上昇がみられる(第3-1-6図(1)④)。こうした売上高や費用の状況の中、売上高経常利益率については、上位企業では、大・中堅企業の上位企業と異なり、上昇がみられず、おおむね横ばいで推移している。これに対し、下位企業の利益率は、特に下位10%企業では、コロナ禍を経て低下した水準にあり、大・中堅企業の下位企業と近しい姿となっている(第3-1-6図(1)⑤)。
次に、中小企業のバランスシートをコロナ禍前と比較する。総資産残高は、平均的には増加しており、その中で、資産側では主に現預金等が、負債側では有利子負債等が増加するとともに、純資産も増加している(第3-1-6図(2))。バランスシートの変化の詳細を確認するため、資産項目のうち現預金をみると、現預金の保有上位企業が、コロナ禍を経て大きくその金額を伸ばしていることが分かる(第3-1-6図(3))。コロナ禍で実施された実質無利子無担保融資等を活用して予防的に資金を借り入れ、現預金として保有する企業が相応に存在してきたことを示していると言える。また、現預金比率(総資産に占める比率)も、上位企業を中心に、コロナ禍前よりも高い水準で横ばい傾向となっている。
他方、負債や純資産項目について確認すると、有利子負債額や有利子負債比率、純資産比率については、大・中堅企業とは異なり、下位10%(負債額が大きい、負債率が高い)企業でそれぞれ有利子負債が11%増加し、有利子負債比率としては8%ポイント上昇しているほか、純資産比率が下位企業で12%ポイント低下するなど、いずれの指標もコロナ禍前と比べ悪化し、上位企業(相対的に財務状況が健全な企業)との差が拡大していることが分かる(第3-1-6図(4)、(5))。一部企業においては、各種支援策の活用等により負債が増加した一方、収益が十分に回復しない中で、純資産比率が悪化しているものと考えられる。なお、借入金利負担10(平均金利)をみると、コロナ禍を経て、金利負担が高い下位10%企業では、4年間で0.8%ポイント低下しており、大・中堅企業の下位企業より低下幅が大きい。これは、コロナ禍の際には、一定の条件を満たす中小企業においては、上述のゼロゼロ融資を活用した借入を行うことができたことが背景にある。もっとも、実質無利子期間は3年間となっていることから、返済を終えていない下位10%企業においては、信用リスクの変化や金利上昇に応じて、平均金利は今後相応に上昇していくと見込まれる点には留意が必要である。一方で、大・中堅企業よりも少ないものの、中小企業でも2割弱の企業は有利子負債がゼロ(無借金企業)となっており、こうした企業にとって金利上昇は預金利息等の増加を通じた収益押上げ要因となる。
このように、大・中堅企業と異なり、中小企業ではコロナ禍を経て、売上高や利益率といった収益面に加え、バランスシート面の諸指標についても、上位企業と下位企業との間の差が広がっているとみられる。

2 近年の倒産動向、倒産企業の特徴とその変化
コロナ禍で行われてきた各種支援策が終了する中で、2022年後半以降、倒産企業は増加傾向で推移してきた。こうした中で、コロナ禍後の倒産企業について、コロナ禍前と質的な変化が発生しているのかを確認する。また、倒産企業の特徴を分析することにより、今後、倒産の可能性が相応に高い企業がコロナ禍前と比べて増加しているのか等を考察する。
(各種支援策により倒産件数は極めて低位に抑制されたが、経済正常化に伴い増加)
まず、改めて、倒産件数の長期的な推移を確認すると11、1980年代初から半ばにかけては、月平均1,500件程度で推移した後、バブル期には大きく減少し、1990年には月平均500件程度の水準となった。その後、バブル崩壊に伴い、倒産件数は増加に転じ、1990年代後半のアジア通貨危機や金融システム不安に伴う景気停滞の影響から、2000年前後には月平均1,600件程度まで増加した。その後は、2000年代前半の景気回復下での減少を経て、2000年代後半の世界金融危機時には倒産件数は再び増加したが、2010年代には景気が緩やかに回復し、また緩和的な金融環境が継続する下で、コロナ禍前の2019年には月平均700件程度まで減少傾向で推移していた(第3-1-7図(1))。2020年初以降のコロナ禍においては、中小・小規模事業者向けのゼロゼロ融資や持続化給付金、雇用調整助成金といった支援策の効果により、倒産件数は月平均500件程度と、コロナ禍前の水準を大きく下回る極めて低位の水準に抑制された。その後、経済活動の正常化が進み、コロナ禍における各種支援措置が縮小される中で、2022年後半以降は倒産件数が増加に転じ、その傾向が続いたことにより、2024年を通してみると月平均834件と、11年ぶりの水準となった。民間金融機関を通じたゼロゼロ融資における返済開始時期のピークが2024年4月であったこともあり、同年5月には、倒産件数は原数値で月1,000件超に高まったが、その後増加ペースはピークアウトし、2024年秋以降増勢が鈍化した後、足もとではおおむね横ばいとなっている。
次に、2022年後半以降の倒産件数の増加の特徴について、まず業種別にみると、コロナ禍で大きな影響を受けたサービス業、特に飲食業を中心に大きく増加に寄与した(第3-1-7図(2)、(3))。ただし、経済活動が正常化し、外食売上高の緩やかな増加傾向が続くなど業況が良好な下で、2024年後半にかけては、飲食業等の倒産件数の増加率は縮小している。次に、倒産企業の負債金額や従業員規模別にみると、負債金額5,000万円未満の企業の倒産が5割超、従業員数5人未満の企業の倒産が6割超を占めるなど相対的に小規模の企業での倒産の割合が高い(第3-1-7図(4))。取引先を含めた連鎖倒産につながるような負債金額10億円以上の大規模企業の倒産は2001年のピークは年間1,410件だったが2024年は年間222件と限定的という状況が続いている。
倒産の理由別にみると、全体の7割超を占める「販売不振」が増加の主因であり、「他社倒産の余波」等の要因は限定的であったことが分かる(第3-1-7図(5))。詳細は後に確認するが、コロナ禍の前後を問わず、基本的には売上の減少とともに倒産に至るという姿が一般的にみられる倒産の形であり、これを映じたものとなっている。もっとも、「販売不振」は、倒産理由の主たるものではあるが、実際には、様々な要因が複合的に重なっているとも考えられる。この点に関し、東京商工リサーチにおいて、別途集計されている物価上昇や人手不足に係る倒産状況についても確認する。まず、原材料価格上昇等に伴ういわゆる「物価高倒産」12についてみると、世界的な物価上昇が輸入物価を経由して国内に波及してきた2022年以降、2023年半ばにかけて増加し、その後はおおむね横ばい圏内で推移している。ただし、倒産件数全体に占める割合は1割未満であり、均してみれば横ばいとなっている(第3-1-7図(6))。次に、いわゆる「人手不足関連倒産」13についてみると、コロナ禍前は増加傾向にあり、コロナ禍で一旦減少したが、2023年にはコロナ禍前のピークを超え、賃金上昇に伴う人件費の増加、人材獲得競争の激化の中で採用や引き留めの難しさを背景に、引き続き増加している(第3-1-7図(7))。倒産件数全体に占める割合は、直近2024年で3%程度となっている。人手不足への対応に関しては、引き続き、省力化投資等を通じた中小企業の生産性向上の支援等の取組が重要な課題と言える。

コラム3-1 企業の休廃業・解散の動向
本論においては、倒産に焦点を当てて分析を行っているが、企業が消滅するという観点では、倒産だけでなく、休廃業や解散の動向も注目される。休廃業とは、特段の手続きをとらず、資産が負債を上回る資産超過状態で事業を停止することであり、また、解散とは、事業を停止し、企業の法人格を消滅させるために必要な清算手続きに入った状態にあることを指す。もっとも、破産手続きや民事再生手続きを裁判所で行う倒産と異なり、企業の休廃業や解散は、経営者が登記抹消といった作業を行わない場合、外形的に必ずしも把握が容易でないほか、依拠するデータや集計基準によって、その動向は異なることに注意が必要である(コラム3-1-1図(1))。例えば、東京商工リサーチの発表する休廃業は、同社が保有する企業データベースから、「休廃業・解散」が判明した企業を抽出したものであり、倒産(法的整理のほか私的整理を含む)以外で、事業活動を停止した企業と定義している。他方、帝国データバンクの公表する休廃業は、同社が保有する企業データベースのほか、各種法人データベースを基に集計したものであり、「休廃業・解散」は、倒産(法的整理)を除き、特段の手続きを取らずに企業活動が停止した状態の確認(休廃業)、もしくは商業登記等で解散(「みなし解散」を除く)を確認した企業と定義している。両データの動向は互いに異なるが、いずれの場合も、倒産件数に比べると休廃業や解散の件数は相当程度大きいことが確認される。
こうした休廃業や解散企業について、近年において、どのような特徴がみられるのか確認したい。まず、休廃業企業の財務状況として、黒字企業割合を見ると、帝国データバンク、東京商工リサーチのいずれにおいても、依然として5割を超えているものの、ここ数年間でやや低下しており、ここ数年の輸入物価上昇に伴う原材料コスト等の費用面からの業績下押しが影響している可能性がある(コラム3-1-1図(2))。ただし、帝国データバンクによると、休廃業のうち資産超過かつ黒字の状態で休廃業が判明した企業は16%程度と、過去5年間で2020年に次ぐ高さとされている。

また、帝国データバンクを基に、休廃業や解散を行った企業の代表者年齢の分布をみると、70歳以上の割合が、この10年で、4割弱から6割超(最頻値は74歳)となるなど高齢化が進んでいることが分かる(コラム3-1-2図)。このように、コロナ禍における資金繰り支援が終了した後、経営者の高齢化が進む中で、コスト面からの業績の圧迫もあって、いわゆる「あきらめ型」を中心に、今後も休廃業件数の増加傾向が続く可能性には留意が必要である。一方で、代表者が高齢である企業における後継者不在率は低下傾向にあり、ここ10年程度で、中小企業のM&Aも増加傾向で推移するなど、新陳代謝に係る前向きな動きもみられている(コラム3-1-3図、コラム3-1-4図)。第三者承継など経営者の世代交代やM&Aは、企業の売上や生産性の向上等につながる可能性が高いとされ、引き続き、事業承継等を円滑に進める取組や、これを契機として生産性の向上につながるよう適切な支援を、官民が連携して進めることが重要であろう。14
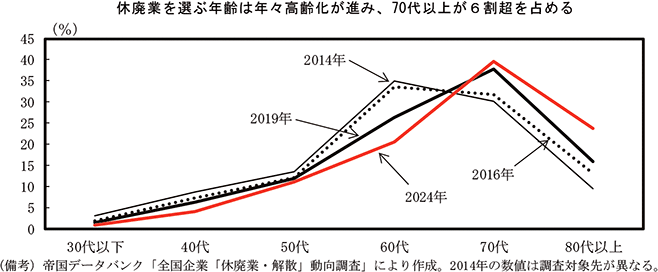


(低金利環境下で、倒産企業のバランスシート毀損のスピードは緩やかであった)
次に、より詳細に倒産企業の特徴について確認していく。具体的には、まず大・中堅企業について、「経済産業省企業活動基本調査」の調査票情報と、報道情報を突き合わせ、倒産企業約300社を抽出し、それぞれ倒産時点を0期として、そこから遡る10年前(以下、グラフ上の評価は「10期」と記載)、あるいは5年前(同じく「5期」と記載)からどのような財務状況をたどったかを分析する。比較対象として、存続企業についても、倒産企業との比較可能性を担保するため、倒産企業と同一会計期間で財務状況を集計している15。
倒産企業について倒産の10年前からの状況をみると、売上高は10年間にわたって継続的に減少している一方、当期純利益については、倒産の9年前の時点で赤字に転じていることが分かる(第3-1-8図(1))。また、営業利益や経常利益については、倒産の6年前の時点で赤字に転じている。こうした中で、次第に純資産が減少し、倒産直前に債務超過に陥り、倒産に至っている(第3-1-8図(2))。
一方、倒産企業と同じ期間について、存続企業の動向をみると、利益率は総じて上昇傾向で推移しており、平均的な存続企業の業績は、堅調に推移していたことが確認される。また、純資産比率も緩やかに上昇しており、堅調に推移していたことが分かる。
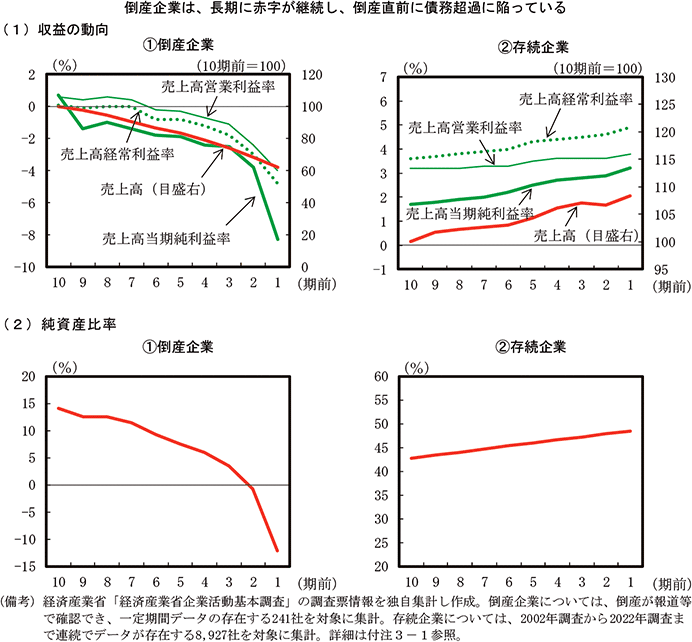
次に、長期にわたって業績不振な企業が、近年になって倒産に至っていることが指摘される16が、先述の「経済産業省企業活動基本調査」を用いた分析を踏まえ、当期純利益の赤字が倒産に至るまでの一定期間継続する中で、事業継続がなされている背景を確認する。
倒産企業と存続企業の債務状況を比較すると、倒産企業は、倒産の10年前の時点で、有利子負債比率が存続企業に比べ3倍弱と高いものの、倒産直前期まではおおむね一定で推移し、借入金利負担は緩やかな低下傾向で推移していることが分かる(第3-1-9図)。倒産企業は、信用力が悪化する下で、追加の新規借入を大きく増やすことはないものの17、借換えに当たって、借換え前より低い利率で資金調達を行うことができているとみられる。この間の存続企業の支払い利回りが大きく低下していることを踏まえると、市場金利の低下による利回りの低下と、信用力の悪化による利回り上昇が相殺され、前者が上回った結果、倒産企業の支払い利回りは緩やかに低下していたと考えられる。一般的には、収益の悪化とそれによる信用力低下に伴う借換え利回りの上昇(支払利息の増加)による負の悪循環により、急速な資金繰りの悪化が発生することが想定されるが、長期間にわたる極めて緩和的な金融環境の下で、倒産企業のバランスシートの毀損のスピードは緩やかなものにとどまっていた可能性がある。

(コロナ禍前に比べ倒産企業の利益率の悪化ペースはやや早まっている)
続いて、倒産企業について、コロナ前(2020年3月以前)に倒産した企業と、コロナ後(2020年4月以降)に倒産した企業を分けて、倒産に至る5年間の企業パフォーマンスにどのような差異がみられるのかを確認する。まず、倒産5年前からの売上高の減少率をみると、両者でほぼ同様である一方、経常利益率でみると、コロナ禍後に倒産した企業の方が、やや急速な悪化が観察されており、結果として純資産比率も、やや速いペースで悪化する傾向がみられる(第3-1-10図(1)、(2)①)。
有利子負債比率をみると、倒産の3年前までは、コロナ禍前に倒産した企業の方が、コロナ禍後に倒産した企業に比べ、有利子負債比率が高い一方で、倒産2年前以降は、コロナ禍後に倒産した企業の方が、有利子負債比率が高くなっていることが分かる(第3-1-10図(2)②、③)。これは、今回集計におけるコロナ禍後倒産企業は、倒産2年前に当たる2020年における実質無利子無担保融資による借入増加の影響とみられる。また、支払い利回りについては、コロナ禍前倒産企業とコロナ禍後倒産企業の間で大きな差はなく(第3-1-10図(2)④)、倒産企業からみた資金調達環境は、資金繰り支援の影響もあり、総じてコロナ禍後倒産企業の方が良好であったと考えられる。
このように負債の増加が可能かという観点からみれば、金融環境はコロナ禍後倒産企業の方が良好であり、また、売上高の減少の度合は、コロナ禍前倒産企業とおおむね同程度であるにも関わらず、コロナ禍後倒産企業は、コロナ禍前倒産企業に比べて利益率のより急速な低下がみられている。これは、コロナ禍での事業環境の変化による売上減少に起因した倒産というよりも、コロナ禍後に生じた様々な変化、例えば、世界的な物価上昇を起点とした、原材料など各種コストの増加等が倒産に影響するようになっている可能性を示している。前掲第3-1-4図でみたように、仕入価格判断DIと資金繰り判断DIの間に負の関係がみられる業種において、資金繰り判断DIが低くなっている点と整合的と考えられる。なお、給与総額の売上高に対する比率は、コロナ禍後倒産企業の方が平均して0.8%ポイントほど高いものの、今回対象とした財務データが、賃金上昇が本格的に始まる前の2022年調査までということもあり、倒産5年前から倒産直前にかけて、コロナ禍前倒産企業との間でさほど差は拡大しておらず、賃金上昇による人件費増加の影響はこの時点では確認できない(第3-1-10図(1)③)。
今後、物価と賃金が共に上昇していく経済が実現していく中にあって、各企業にとって、人件費を含む各種コストの継続的な上昇は不可避なものと考える必要がある。こうした中で、コストの適切な販売価格への転嫁や、収益率の高い事業への再編等を通じて付加価値の高い財やサービスを生み出す取組が一層重要となっていると考えられる。

(コロナ前の2020年3月以前に比べて倒産の蓋然性が高い企業は増加)
次に、今後、倒産の可能性が相対的に高いと見込まれる企業が潜在的にどの程度存在し、コロナ禍前に比べてどの程度増加しているか確認したい。ここでは、企業の償還資源18(疑似的なキャッシュフロー)を計算し、償還資源が継続的に赤字(マイナス)になっている企業を倒産の蓋然性が高い企業群として定義して、その動向について確認する。
まず、「経済産業省企業活動基本調査」の2014年調査時点で、償還資源が3年連続でマイナスの企業は、対象企業8,978社の中で139社(約1.6%)となっていた(第3-1-11図(1))。こうした企業について、その後の事業継続を確認すると、2024年9月までの約10年間で、その約4割が倒産に至っていたことが分かる。こうした償還資源が3年連続でマイナスの企業は、コロナ禍前の2018年調査時点では約1.4%に減少していた。前掲第3-1-9図で確認したように、緩和的な金融環境が長く続いたことも背景に、倒産の蓋然性が高い企業の数が減少したものと考えられる。実際、前掲第3-1-7図のとおり、2014年から2018年にかけて、倒産件数は減少傾向で推移していた。これに対し、直近の2022年調査時点では、償還資源が3年連続でマイナスの企業が全体に占める割合は約2.5%となり、2014年調査時点よりも高く、2018年調査時点に比べると約1.1%ポイント増加している。ここで、2022年調査時点で償還資源が3年連続でマイナスの企業群のうち、直近(2024年9月時点)までに倒産した企業は、12%となっている(第3-1-11図(2))。2013年度時点(2014年調査)や2017年度時点(2018年調査)において、倒産の蓋然性が高い企業のその後の推移をみると、5、6年をかけて3割程度が倒産するという傾向がみられる。その後は、(2013年度時点で償還資源が継続的にマイナスだった企業をみると、)増加ペースは緩やかになり、最終的には4割弱が倒産に至るという姿となっている。2021年度時点(2022年調査時点)の倒産の蓋然性が高い企業群の倒産は、現時点で1割程度にとどまっており、これまでの傾向を踏まえると、今後数年間をかけて相応の件数が倒産に至るという可能性には留意しておく必要がある。

(金利上昇による倒産の蓋然性が高い企業の増加は一定程度にとどまる)
さらに、こうした数年をかけて倒産する蓋然性が相応に高い企業群が、この先、金利の上昇が生じた場合に、どの程度増加する可能性があるか確認したい。
ここでは金利の上昇により、前述したような償還資源がマイナスとなる企業がどの程度増加するのかを機械的に試算する。具体的には、前掲第3-1-10図の償還資源の計算において、有利子負債部分の金利が政策金利に連動して上昇し、支払い利息が増えるという前提を組み込み、金利上昇幅に応じて、償還資源が3年連続でマイナスになる企業がどの程度増加するか試算した。なお、本試算は、企業が変動金利で資金調達を行うことを前提としており、固定金利調達を考慮していないという点で、やや強い仮定に基づくものであることに留意が必要である。
2024年12月時点の政策金利0.25%程度で試算すると、償還資源が継続的にマイナスとなる企業は、2022年調査時点と比べて、0.1%ポイント程度の増加に抑制されている(第3-1-12図)。足下では、総じてみれば企業の資金繰りに大きな変化がみられないことと整合的であると言える。逆に言えば、この間の実際の倒産件数の増加は、販売不振による売上高減少を背景とした倒産に加え、コロナ前からコロナ後にかけての生産コスト上昇の定着など企業を取り巻く経済環境の変化によるところが大きいと言える。次に、現状からの金利上昇ケースをみると、政策金利が1%の場合には、償還資源が継続してマイナスとなる企業は、0.25%の場合と比べて、0.6%ポイント増加するが、調査対象企業の約3%程度となっている。現状に比べて、金利上昇によって倒産可能性が相応に高い企業数が大幅に増えるわけではない。このように、「経済産業省企業活動基本調査」が対象とする大・中堅企業においては、相応に金利上昇への耐性を備えているとみることができる。なお、本試算上、政策金利がより高まるようになると、償還資源が継続的にマイナスとなる倒産可能性が高い企業数の増加は加速することとなるが、そうした金利水準と整合的な経済環境は、経済が安定的に成長し、賃金・物価が持続的に上昇しているような状況であり、適切な価格転嫁が可能な企業等においては、収益の増加を通じて償還資源も相応に確保されると考えられ、必ずしも本試算に沿って、倒産可能性の高い企業が増加するわけではないと言える。金利が長期間にわたり極めて低位な水準で推移してきたことから、今後の金利上昇の影響は慎重に見極める必要があるが、経済・物価動向と整合的な形に、緩やかな金利上昇が進む下では、大・中堅企業において、大幅に倒産が増加するという蓋然性は高くないと考えられる。
(中小企業では、倒産の蓋然性が高い企業の割合は大中堅企業より高く、増加傾向)
前述の大・中堅企業における分析を援用し、中小企業において、償還資源が継続的にマイナスとなっている企業の動向を確認する。ここでは、「中小企業実態基本調査」を用いるが、悉皆調査ではなく、継続的に財務データを確認できる企業が「企業活動基本調査」に比べ、10分の1程度と少ないことから、大・中堅企業での分析のように、これまでに実際に倒産した企業の割合を確認することはできないほか、時系列の比較も一部に留まる。そうした限界も踏まえた上で、大・中堅企業と同じ基準で倒産の蓋然性が高い企業を抽出した場合、どのような傾向がみられるかを確認したい。
中小企業全体のうち、コロナ禍以降の期間において、償還資源が3年続けてマイナスとなっている企業群が占める割合は直近で8%弱と、前掲第3-1-11図で確認した大・中堅企業と比べて高い水準となっている(第3-1-13図(1))。これは、前掲第3-1-6図でみたように、中小企業の場合、大・中堅企業と比べ、コロナ禍を経てバランスシートの状況が上位と下位の企業のばらつきが広がっており、下位の企業については、大・中堅企業と比べて、コロナ禍前よりも状態が悪化していることが影響していると考えられる。また、大・中堅企業と同様に、コロナ禍を経て収益面での格差が広がっていることもあり、倒産可能性が相応に高い企業の割合が増加傾向で推移している。
また、金利上昇による影響について、前掲第3-1-12図と同様の手法により機械的に試算すると、政策金利が0.5%の場合、2022年実績に比べて、償還資源が継続的にマイナスの企業割合の増加はわずかなものにとどまる。仮に金利が1.0%まで上昇した場合は、同企業の割合は、2022年実績に比べて、+2%ポイント程度の10%程度に高まる形となる(第3-1-13図(2))。大・中堅企業の結果と同様に、金利が上昇する場合においては、償還資源が継続的にマイナスの企業は一定程度増加すると見込まれるものの、上述のとおり、金利の上昇が、経済状況の改善と整合的に生じるような場合、適切な価格転嫁が可能な企業等においては、収益拡大を通じて償還資源の減少は抑えられることから、倒産の大幅な増加に至る蓋然性が必ずしも高いというわけではないと考えられる。
その上で、中小企業については、大・中堅企業に比べて、2022年度時点で償還資源が継続的に赤字の企業が相応に多く存在することから、(大・中堅企業の分析に基づけば、)現時点で既にその一部は倒産件数に表れているほか、今後数年をかけて一定程度の倒産件数の増加の可能性が見込まれるところであり、状況を注視していくことが重要である。


(倒産を経て効率化を図った再構築企業の業績は堅調に推移)
最後に、企業再生の重要性・意義を確認する観点から、倒産後に事業再構築を図った企業について、その倒産前後の業績の推移をみてみたい。「経済産業省企業活動基本調査」の調査票情報を確認すると、倒産後も同じ企業番号や社名で事業活動を継続している企業(以下、「再構築企業」と言う。)が一定数存在することが分かる。これらは、企業が倒産した後、当該企業の中で収益が見込める事業について、スポンサー企業が出資するなどして、新会社を設立しているケースとみられる。こうした企業の事業状況を確認しつつ、倒産と事業再構築に関する含意を考えたい。
まず再構築企業について、倒産に至るまでの過程をみると、それ以外の倒産企業と同じように、売上高が減少傾向で推移していることが分かる(第3-1-14図(1))。倒産後の再構築企業の売上高をみると、倒産直前の水準からは、やや回復した程度の水準に留まっているが、売上高経常利益率は、倒産の5年前から3年前の平均である1.2%程度から大きく改善して、再構築後の平均は4.1%となっていることが確認される。
こうした点の背景について確認するため、再構築企業のバランスシートや資金調達動向をみる。倒産前と比べて、再構築企業の総資産規模は3割程度になっており、スリム化がなされているほか、有利子負債比率は、倒産直前の50%程度から、倒産後3年で10%程度にまで大きく低下していることが分かる(第3-1-14図(2))。また、借入平均金利については、倒産直前は3%程度だったものが、再構築後は0%台まで大きく低下している。また、売上高支払利息率をみると、有利子負債の減少と借入利回りの低下により、大きく低下している。倒産後の過剰債務の解消が、収益改善に大きく寄与していることが確認される。こうした結果、バランスシートにおける純資産比率は、倒産後3年で倒産の5年前の水準を上回るまで回復している。「経済産業省企業活動基本調査」上の限られたサンプルに基づく分析結果であるという点には留意が必要であるが、以上のように、倒産後に何らかの形で再構築を図った企業においては、倒産前の売上減は、倒産企業全体と同様であるものの、利益率を改善させ、債務整理を通じてバランスシートも大きく改善させていることが分かる。
これまで、当期純利益の赤字や償還資源マイナスを繰り返すなど一定の業績悪化がみられるものの、純資産はプラスを保ち、直ちに倒産するほど経営状況が悪化しているわけではない企業は、金融機関にとっては、低金利環境の下で貸出先が限られる中において、相対的に高めの貸出利回りの設定により利益確保が可能であったと言える。一方、業績不振の企業にとっては、借入による資金調達により事業継続が可能であるという点で、金融機関・企業双方にとって一定のメリットがあったと考えられる。一方、今後は、物価と賃金が共に上昇する経済に移行し、金利の一定の上昇も見込まれる中で、償還資源マイナスの決算を繰り返し、有利子負債比率が上昇を続けているような企業における早期の債務整理と事業再構築の促進が重要な課題と言える。前掲第3-1-10図で確認したように、企業経営については、コロナ禍後においては、コロナ禍前には見られなかったコスト増の要因等から収益が悪化しやすい環境に変化している可能性がある。一部でも収益が見込める事業を有するような過剰債務企業については、業績不振に陥った場合に、債権者が早い段階で債務整理に応じ、事業の再構築を進めることにより、最終的な債権回収額を高めることが可能となるほか、企業部門全体としての生産性向上につながるものと考えられる。

以上、本節では、我が国企業の近年の資金繰りや業績動向を確認するとともに、倒産件数の動向、倒産企業の特徴、コロナ禍前後での変化、倒産後の再構築企業のパフォーマンス等について確認してきた。分析によれば、我が国の倒産企業は、10年近くにわたる業績不振を経て倒産に至る傾向があり、業績不振から倒産までかなり期間があるのは、これまで長きにわたって継続してきた緩和的な金融環境が背景にあると考えられる。コロナ禍前とコロナ禍後で倒産企業の変化について比較すると、売上の減少は同様のペースである一方で、コロナ禍後は利益率のやや速い悪化が確認されており、昨今の輸入物価を中心とする原材料価格等の上昇の影響により、倒産までの業績悪化が進みやすい状況になっている可能性がみられる。また、倒産企業のうち、スポンサー企業による出資などにより再構築した形で事業が継続している企業の動向を確認すると、過剰債務が整理されたことにより安定的な利益計上ができるようになっていることが分かった。
こうした分析結果から得られる含意は大きく2点ある。第一に、賃金と物価の上昇が続く経済の中では、人件費も加えた各種コストの継続的な上昇を前提とする必要があり、業績不振企業の経営において、販売数量を回復させるという視点だけなく、適切な価格転嫁を進め、付加価値の高い商品を生み出すという戦略がより一層重要となっている。第二に、一部の業績不振企業では、これまでの緩和的な金融環境やコロナ禍における資金繰り支援策もあって、債務が膨らんだ状態となっている。また、コロナ禍前に比べると、適切な価格転嫁ができなければ、コスト要因による収益悪化が生じやすい環境になっている。こうした中にあっては、一部でも収益が見込める事業を持つ過剰債務企業について、業績不振になった場合、債権者が早期の段階で債務整理に応じて、事業再編や経営再建を進めることは、最終的な債権回収額の増加につながるほか、マクロ的にみた場合、日本企業全体の生産性向上につながると言える。

