第2章 賃金の持続的な上昇と個人消費の力強い回復に向けて(第1節)
第1節 平均消費性向の低下とその背景
本節では、世帯統計である「家計調査」等をもとに、平均消費性向の長期的な動態を確認するとともに、コロナ禍前からの低下傾向について、様々な角度から分析を行う。前半では、平均消費性向が低い共働き世帯の増加や持ち家率の増加といった要素が、平均消費性向の低下に一定程度の影響を与えてきたことをみる。後半では、こうした影響を除いても世帯ごとの平均消費性向の低下がみられる背景として、理論的な整理とこれに係るいくつかの分析を行う。
1 家計の平均消費性向の動向
(平均消費性向は、全ての年齢層で2010年代前半以降、低下傾向)
ここでは世帯種類ごとの平均消費性向の姿を振り返る観点から、総務省「家計調査」に基づき、世帯当たりの平均消費性向の長期的な動向を確認する。まず、全世帯の4割弱を占める二人以上勤労者世帯について、世帯主年齢別の平均消費性向をみると1、各年齢層でおおむね似通った動きとなっている(第2-1-1図(1))。すなわち、平均消費性向は、1980年代から1990年代後半にかけて緩やかな低下傾向にあった後、2010年代前半までにかけてはおおむね横ばいで推移したが、2010年代前半以降は再び低下傾向で推移した。2020年には新型コロナウイルス感染症の感染拡大による消費の減少や、特別定額給付金等による可処分所得の増加もあって、平均消費性向が大きく低下した後、やや上昇傾向で推移しているが、2023年時点においてもコロナ禍前の水準には回帰していない。特に、34歳以下や35~39歳といった相対的に若い年齢層における平均消費性向の切り下がりが大きい。

(米国と異なり、日本の家計の平均消費性向は、コロナ禍前の水準を回復してない)
次に、二人以上の高齢無職世帯2や単身勤労者世帯の平均消費性向を確認する(第2-1-1図(2))。全世帯の2割程度を占める二人以上高齢無職世帯の平均消費性向は、統計が存在する2010年以降、おおむね115~120%程度3で推移している。コロナ禍の2020年には低下したものの、その後2023年にはおおむねコロナ禍前の水準まで戻っている。一方、全世帯の2割程度を占める単身勤労者世帯では、「家計調査」におけるサンプルサイズが小さく4振れが大きい点に留意が必要であるが、2007年以降、低下から横ばい傾向で推移し、コロナ禍で大きく低下した後、二人以上勤労者世帯と同様に、幾分回復しているものの、コロナ禍前を下回る水準となっている。
ここで、日本の家計の平均消費性向のコロナ禍前後の動きについて、米国のそれと比較したものが第2-1-2図である。米国は総世帯、日本は二人以上世帯であるという違いがある点に留意が必要であるが5、65歳以上の高齢世帯については、日米共に、コロナ禍直後に平均消費性向が低下した一方で、2023年にかけてはおおむねコロナ禍前の水準に回帰している点において共通している。一方、64歳以下のいわば現役年齢層の世帯については、日米共にコロナ禍で大きく平均消費性向が落ち込んだ後、米国では2023年にはおおむねコロナ禍前の水準に戻っている一方、日本については、コロナ禍前の水準より切り下がった状態が続いている。

以上のように、我が国の家計の平均消費性向は、勤労者世帯を中心に、長期的に低下傾向にあり、コロナ禍で大きく落ち込んだ後に、コロナ禍前の水準に回復しない状況となっているが、こうした背景にはどのような要因があるのであろうか。以下では、長期時系列の比較が可能であり、相対的にサンプルサイズが確保されている二人以上勤労者世帯に焦点を当てて分析を行うこととする。
(平均消費性向が低い共働き世帯の増加により、全体の平均消費性向が低下した面も)
次に、「家計調査」における二人以上勤労者世帯の平均消費性向の変化の背景について、より詳細に確認する。同世帯全体の平均消費性向は2013年以降低下傾向にあり、2023年までの10年間で、70.8%から64.4%へと6.4%ポイント低下している(第2-1-3図(1))。これを世帯における有業人員の人数別にみると、有業人員1人世帯に比べ、有業人員2人以上世帯の平均消費性向は一貫して低い水準にあり、2013年以降の低下幅も相対的に大きなものとなっている。有業人員1人と2人以上の世帯の平均消費性向の分子(消費支出)と分母(可処分所得)を比較すると、有業人員2人以上世帯の消費額は有業人員1人世帯に比べて1.14倍(2023年時点)とやや大きいのに対し、可処分所得は1.34倍(同時点)とより差が大きい(第2-1-3図(2))。有業人員2人以上世帯は、共働きの世帯が多いと考えられるが、こうした世帯においては、同じ世帯人員数の有業人員1人世帯に比べて、可処分所得が増加しても基礎的な支出を増やしにくい(増やす必要がない)ことから、共働き世帯は平均消費性向が低くなる傾向があると考えられる6。
こうした有業人員2人以上世帯の二人以上勤労者世帯全体に占めるシェアは、2003年の50%程度から2023年には66%に大きく上昇している(第2-1-3図(3))。これは、特に2010年代以降、女性の労働市場への参加が進み、共働き世帯が増加したことによる。実際、総務省「労働力調査」によると、「男性就業者と無業の妻からなる世帯」が2003年時点では約1,000万世帯であったものが、2023年時点では582万世帯と、20年間でほぼ一貫して減少してきたのに対し、「就業者の共働き世帯」は、2003年時点の1,285万世帯から、2023年時点で1,529万世帯と大きく増加している(第2-1-3図(4))。先述のとおり、有業人員2人以上の家計は相対的に平均消費性向が低い傾向にあることから、これら世帯のシェアの上昇は、全体平均としての平均消費性向の押下げに影響することとなる。その影響の程度をみるために、仮に有業人員2人以上の家計のシェアが2003年から変化しなかった場合に、平均消費性向がどのように推移したかを試算すると、2023年時点で、現実の平均消費性向よりも1.7%ポイント程度高かったことになる。このように、二人以上勤労者世帯の平均消費性向の低下の一部は、共働き世帯など有業人員2人以上の家計のシェアの上昇という構成変化要因によって説明されると言える。
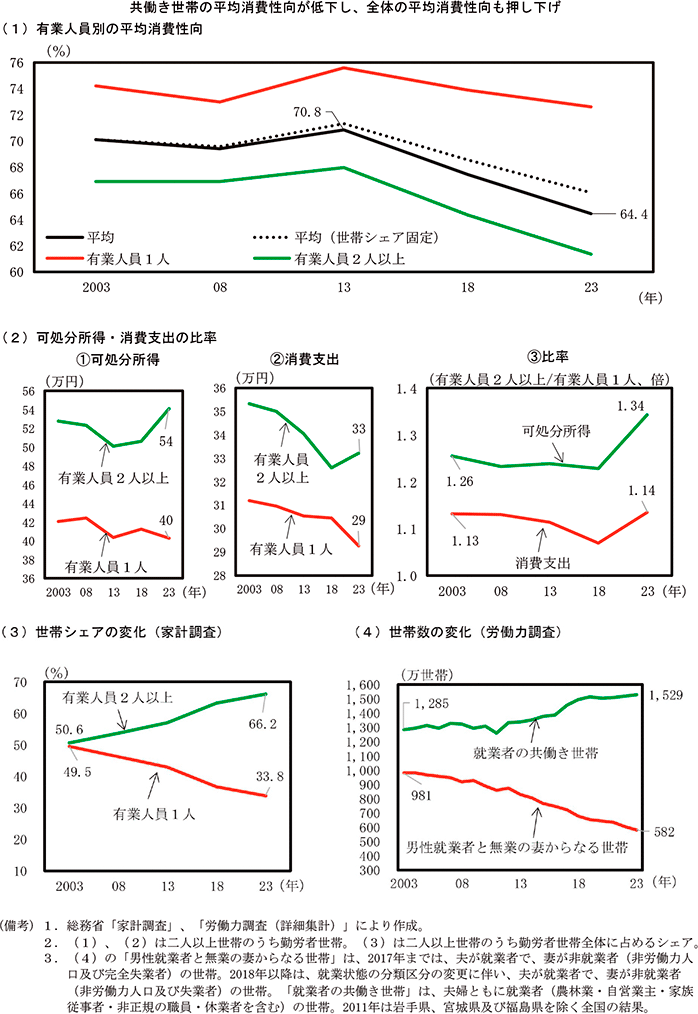
(有業人員によらず、平均消費性向は、消費支出の減少により低下)
次に、有業人員1人、有業人員2人以上のいずれの世帯においても、前掲第2-1-3図(1)のとおり、平均消費性向が長期的に低下している背景について確認していく。まず、平均消費性向の分子と分母である消費支出と可処分所得について、2003年を起点の100とする指数とし、過去20年の動きをみると(第2-1-4図)、有業人員1人世帯では、消費支出・可処分所得が共に減少する中で、消費支出の減少の方が相対的に大きかったため、結果として平均消費性向がやや低下している。一方、有業人員2人以上世帯では、可処分所得が2010年代前半以降増加する中で、消費支出が減少傾向で推移しており、結果として、より大きく平均消費性向が低下していることが分かる。

(持ち家比率の上昇も、統計上、平均消費性向を低下させる)
ここで、有業人員別の消費性向の低下傾向について議論を深める前に、「家計調査」上の消費支出や平均消費性向が低下傾向にある背景の一つとして、住居関連費用の扱いが影響していることを確認する。住居関連費用は、主に「賃貸住宅に住み、家賃を支払う」か、「住宅ローンなどを組んで住宅を購入し、ローンを返済する」かの2種類がある7。「家計調査」においては、前者の家賃は、「家賃・地代」として消費支出に含まれる一方、後者のローン返済は、金融取引(「土地家屋借金返済」)として扱われ、消費支出には計上されない。そのため、賃貸住宅に居住し、家賃を支払っていた家計が、持ち家を購入し、家賃の支払いがなくなる一方、家賃と同額の住宅ローン返済額が生じた場合、家計のキャッシュフローが同じであったとしても、統計上は消費支出が減少し、平均消費性向が低下することになる。
ここで、「家計調査」における二人以上勤労者世帯の持ち家比率をみると、長期的に上昇傾向で推移している8(第2-1-5図(1))。既にローンを払い終えていたり、相続等で引き継いだりといった理由で住宅ローンを支払っていない世帯を含めると、持ち家に住む比率は2003年の70%程度から2023年には80%程度に高まっており、家賃・地代を支払っている世帯は30%程度から20%程度に低下している。世帯類型平均の家賃・地代や住宅ローン支払の推移をみると、家賃・地代は、これを支払っている世帯のシェアの低下により減少している(第2-1-5図(2))9。ただし、家賃・地代を支払っている世帯の割合で割り戻した、「家賃・地代を支払っている世帯」の一世帯当たりの家賃・地代は20年間で5.2万円から6.7万円に増加しており、家賃を支払っている世帯が実際に支払っている家賃は上昇していることが分かる。一方、土地家屋借金返済の推移をみると、住宅ローンを支払っている家計の比率の上昇もあって、有業人員2人以上世帯を中心に増加している。一方、住宅ローンを支払っている家計の割合で割り戻した、「住宅ローンを支払っている家計」の世帯あたりのローン支払をみると、低金利環境の影響もあって、20年間で10.2万円から9.4万円に減少している(第2-1-5図(3))。
結果として、住居関連の支出全体としては、過去20年間で若干増加している中で、消費支出に含まれない土地家屋借金返済の比率が上昇したことにより、「家計調査」上の二人以上勤労者世帯の平均消費性向を押し下げている面があると考えられる(第2-1-5図(4))。

そこで、持ち家取得による住宅ローン支払の増加による二人以上勤労者世帯の平均消費性向への影響(以下「貸家・持ち家比率要因」)を試算すると10、20年間の累計で2023年時点において1.4%ポイント程度、消費性向を押し下げているとみられる。また、共働き世帯の増加による影響(以下「共働き世帯比率要因」)は、貸家・持ち家比率要因と重複する部分があるため、これを除外して試算すると11、平均消費性向を1.3%ポイント程度押し下げており、2つの要因を合わせると、2003年から2023年にかけての平均消費性向の低下(マイナス5.7%ポイント)の半分弱となる。逆に、残りの半分強(3%ポイント程度の低下分)は、内部効果、つまり共働き世帯の増加や持ち家比率の上昇の影響を除去した世帯ごとの平均消費性向の低下に起因するものと言える(第2-1-6図)。
こうした動きを、2013年から2018年にかけてと、2018年からコロナ禍を経た2023年にかけての2期間にわけてみると、まず、平均消費性向全体の変化は、2013年から2018年にかけてマイナス3.4%ポイント程度、2018年から2023年にかけてマイナス3.0%ポイント程度と、おおむね同程度となっている。ただし、内訳をみると、共働き世帯比率要因はいずれの期間もマイナス0.5%ポイント程度と同程度であるのに対し、貸家・持ち家比率要因は2013年から2018年にかけてマイナス0.2ポイント程度、2018年から2023年にかけてマイナス0.5%ポイント程度と、2018年から2023年にかけての方が押下げ幅がやや大きくなっている。これは、期間後半の方が、より低金利の環境となった中で、住宅ローンを組んで持ち家を購入することが相対的に有利になったことなどが背景にあると考えられる。また、内部効果に関しては、2013年から2018年にかけてマイナス2.7%ポイント程度、2018年から2023年にかけてマイナス2.0%ポイント程度と、2013年から2018年にかけての方が大きかったことが分かる。

(有業人員2人以上世帯は、世帯主の配偶者の収入が可処分所得増加に寄与)
それでは、有業人員別にみた世帯類型ごとの平均消費性向は、どのような要因で低下しているのであろうか。まず、分母の可処分所得の動向について、有業人員1人世帯と有業人員2人以上世帯のそれぞれについて、内訳別の寄与度を確認する。有業人員1人世帯の可処分所得については、2003年から2023年にかけて、世帯主の高齢化もあり、有業者である世帯主の勤め先の収入が減少する12一方、公的年金の増加が一定程度それを相殺し、結果的に2003年比で2023年の可処分所得はやや減少している(第2-1-7図(1))。公的年金給付の増加は、世帯主の高齢化が進む13中で、配偶者が年金を受給する、あるいは世帯主が働きながら年金を受給する世帯が増加していることがあるとみられる。こうした年金受給世帯の増加は、有業人員1人世帯の平均消費性向を押し上げる効果もあると考えられる。すなわち、勤労者世帯であっても、65歳以上など高齢世帯については、平均消費性向が相対的に高く、定年後に再雇用され、短時間勤務による就業継続等により勤め先収入が減少する中で、貯蓄を取り崩して消費にあてていると考えられる。こうしたことは、有業人員1人世帯の平均消費性向が有業人員2人以上世帯と比べて高い水準にあることのみならず、平均消費性向が低下傾向にはあるものの、低下の度合が相対的には小さいことの背景にあると考えられる。次に、有業人員2人以上世帯の可処分所得について、同様に内訳別の寄与度をみると、世帯主の勤め先収入については2010年代にかけて低迷した後、2023年にかけては2003年を若干上回るまで持ち直している(第2-1-7図(2))。これに加えて、世帯主の配偶者の収入が、2023年にかけて大きく上昇し、有業人員2人以上世帯における可処分所得の改善に寄与していることが分かる。なお、有業人員2人以上世帯においては、有業人員1人世帯と同様に、高齢世帯主のシェアが増加し、世帯主の平均年齢が上昇しているものの、その上昇ペースはより緩やかなものにとどまっている(2003年48.4歳から2018年に50.2歳と上昇した後、2023年50.1歳とやや低下。付図2-2)。これは、人口の高齢化により世帯主の平均年齢が全体的に上昇する中にあっても、若年層の共働きが増加したことにより、有業人員2人以上世帯の平均年齢の上昇が抑えられていたと考えられる。実際、「就業構造基本調査」から世帯主が雇用者である世帯における世帯主年齢別のシェアをみると、有業人員2人以上世帯では、有業人員1人世帯と同様に、2002年から2022年にかけて、世帯主が60歳以上の世帯が占める割合は増加している一方で、40代以下の世帯が占める割合はほぼ横ばいとなっている。

(消費支出側の要因としては、基礎的支出が横ばいの中で、選択的支出が減少)
次に、有業人員別の世帯類型について、平均消費性向の分子である消費支出側の変化を要因別に確認する。まず、上述したように、持ち家比率の変化による影響があるため、住居関連の支出14を除いた消費支出の動きをみると、2003年から2023年の20年間で、有業人員1人世帯ではマイナス5.2%、2人以上世帯ではマイナス5.7%減少している(第2-1-8図(1))。内訳項目別にみると15、有業人員別を問わず、消費支出の最大の減少寄与となっているのは「その他の消費支出」である。これは、「こづかい」、「交際費」、「仕送り金」の3つからなる項目であるが、このうち特に「こづかい」の減少が顕著であり、2003年から2023年にかけて、有業人員1人世帯では24.8万円から7.2万円に、有業人員2人以上世帯では35.0万円から9.1万円に、70%程度の減少となっている。「こづかい」は、「家計調査」上、「使途不明金」が該当することから、何らかの形で消費されていることには違いがないが、「家計調査」ではこれ以上の分解は不可能である。このため、5年に一度行われる「全国家計構造調査」(2014年までは「全国消費実態調査」)における「個人収支簿」から、こづかいやつきあい費に対応すると考えられる「個人的な支出」の集計結果をみると(第2-1-8図(2))、「個人的な支出」のうち3~4割程度は「食料」が占めており、その過半は外食である。そのほか、「交通・通信」や「教養娯楽」といった、個人単位で支払うことが多いと考えられる費目が上位を占めている。これらが、「こづかい」等の内訳に近似するものと推察される16。
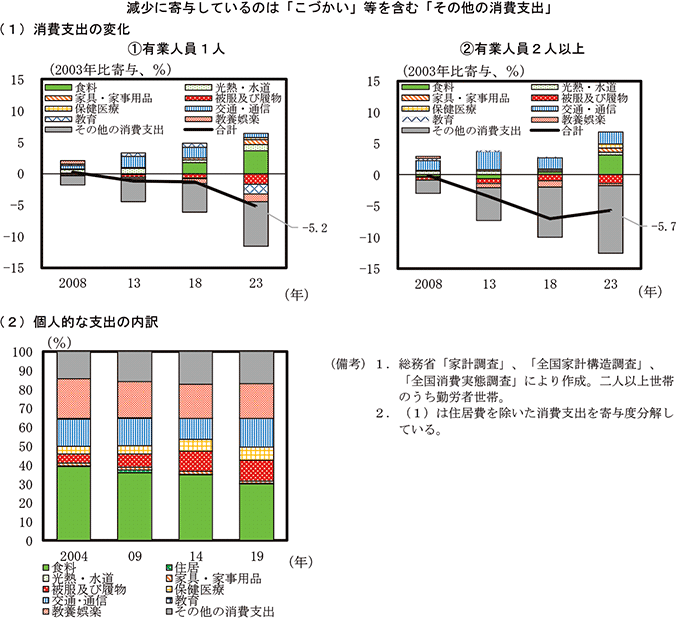
そこで、「こづかい」の総額17を各品目に按分した上で、費目別の消費支出の長期的な動向を確認すると(第2-1-9図(1))、「被服及び履物」や「教養娯楽」の減少が相対的に大きいことが分かる18。一方、消費全体に占めるシェアが3割弱と大きい「食料」は、変動が相対的に小さく、2003年比で2023年はやや増加となっている。これに対し、物価の変動を除いた実質ベースの消費支出をみると、物価要因が押下げに寄与したほか、世帯人員が少ない家計が増加したこともあって、「食料」は2023年において、2003年比で20~30%程度の減少となっている(第2-1-9図(2)、(3))。一方、「教養娯楽」については、近年の価格上昇が食料に比べて緩やかであったものの、実質ベースの消費支出は「食料」と同程度の減少幅となっている。「食料」の方が「教養娯楽」に比べてより価格上昇が大きいという相対価格の変化を考慮すれば、価格以外の理由により、「教養娯楽」の消費を減らしている可能性が高い。また、「被服及び履物」は、価格の上昇も加味すると、2003年比で40%程度の減少となっており、実質ベースでみても一貫して消費を押し下げていると考えられる。
なお、こづかいを按分した後の「その他」も引き続き減少している。こづかいを按分した後の「その他」の減少に寄与しているのは、有業人員1人世帯でも有業人員2人以上世帯でも「交際費」であるが、有業人員2人以上世帯では、「仕送り金」も大きく減少している(第2-1-9図(4))。

ここで、例えば「教養娯楽」や「被服及び履物」に分類される財・サービスは、一般に、必需品に該当せず、価格動向を踏まえながら、消費者が選択的に消費を決定している側面が強いものと考えられる。「家計調査」においては、消費支出全体の1%の変化に対する各品目の消費支出の変化(支出弾力性)が1未満の場合は「基礎的支出」、1以上の場合は「選択的支出」と分類している。この「基礎的支出」か「選択的支出」の定義に沿って分類し、長期の消費支出の動向をみると19(第2-1-10図)、まず、名目額では、基礎的支出は期間を通じて変動が相対的に小さくおおむね横ばいの範囲内にある中、2018年から2023年にかけては、食料品等の物価上昇もあって、2003年比で増加に転じている。一方、選択的支出については、一貫して減少傾向にあり、特に2023年にかけては、基礎的支出とは対照的に、大きく減少していることが確認される。実質でみても、2018年頃までは基礎的支出と選択的支出の変化は同程度であるが、2023年にかけて、選択的支出のマイナス幅が大きくなっている。2020年代以降、食料品等を中心に、40年ぶりの物価上昇に直面する中で、消費者が節約意識を高め、教養娯楽関連や衣料品を中心に選択的支出を相対的に減らしているとみられる。

以上をまとめると、「家計調査」の二人以上勤労者世帯における過去20年程度の平均消費性向の低下の半分弱は、平均消費性向の相対的に低い共働き世帯の増加や、持ち家率の上昇により消費支出に計上されない住宅ローン支払が増加したことにより説明できる。一方で、これらだけでは説明しきれない、消費の減少に伴う平均消費性向の低下が、特に選択的支出を中心にみられたことが確認される。選択的支出は基礎的支出よりも価格弾力性が高く、また消費時期や量を調整しやすいものが多いと考えられることから、平均消費性向の低下は、何らかの理由により家計が消費を意識的に抑制したことによるという可能性が考えられる。
2 個人消費の伸びが所得の伸びを下回る理論的背景と分析
前項では、二人以上勤労者世帯について、共働き世帯の増加といった世帯構造の変化や持ち家(住宅ローン支払)比率の上昇といった要因を取り除いてもなお、平均消費性向の低下がみられることをみた20。こうした点は、消費者への意識調査からも間接的に確認できる。内閣府「国民生活に関する世論調査」においては、毎年、今後の生活において、貯蓄や投資など将来に備えることに力を入れたいと思うか、毎日の生活を充実させて楽しむことに力を入れたいと思うかを聞いている。60歳未満の層についての結果をみると、2000年代後半以降、「貯蓄や投資など将来に備える」と答えた割合は一貫して上昇していることが分かる(第2-1-11図)。さらに、コロナ禍後の2021年以降、回答選択肢から「どちらともいえない」が削除され、「どちらかといえば貯蓄や投資など将来に備える」や「どちらかといえば毎日の生活を充実させて楽しむ」が追加される中で、「貯蓄や投資など将来に備える」(「どちらかといえば」を含む)と答えた割合は更に上昇している。2020年前後の調査変更の影響がどの程度かを把握することは難しいが、従前の「どちらともいえない」の回答が、新設された「どちらかといえば」(貯蓄や投資など将来に備える、もしくは毎日の生活を充実させて楽しむ)のいずれかに分かれるとすれば、他の条件が一定の下では、「貯蓄や投資など将来に備える」や「毎日の生活を充実させて楽しむ」(いずれも、「どちらかといえば」を含む)は、調査変更前よりもそれぞれ増加すると想定される。しかし、実際の結果は、「貯蓄や投資など将来に備える」は増加する一方、「毎日の生活を充実させて楽しむ」は減少しており、コロナ禍を挟んで、将来に備える意向を持った層が有意に増加した可能性が高いことを示唆している。このように、長期的な傾向として、我が国の消費者は、足下の消費を抑制して、将来に備える傾向を強めていると言える。こうした背景について、理論的な仮説を確認するとともに、これらに関するいくつかの事実を確認していく。

(恒常所得仮説に基づけば、一時的な所得の増加が消費に回る程度は小さい)
第一は、「恒常所得仮説」である。恒常所得仮説は、消費の水準は、足下の所得のみならず、生涯にわたっての所得によって決定されるとする考え方である。具体的には、例えば、コロナ禍の2020年に支給された一人10万円の特別定額給付金等は、消費者にとって一時的な所得の増加ではあるが、生涯所得を増加させる効果は限定的である。恒常所得仮説の下では、消費者が一時的な所得から消費支出に充てる割合は低くなり、貯蓄に充てる割合が高くなる。一方、例えば、生産性の向上等により賃金水準が上昇した場合、その所得増は将来にわたって継続すると想定できる。こうした所得は、恒常所得と呼ばれ、この増加分については、生涯所得を押し上げることを通じて、より多くの割合が消費に充てられると想定される。
こうした点に関連して、金融広報中央委員会の「家計の金融行動に関する世論調査」21においては、収入全般や臨時収入等(ボーナスや臨時収入)から貯蓄に回す割合を調査している(第2-1-12図)22。このうち、収入全般について、そこから貯蓄に回す割合は11%(二人以上世帯の平均)となっている一方で、ボーナス・臨時収入から貯蓄に回す割合は27%と相対的に高くなっている23。この結果は、恒常所得の増加はすぐに消費に回りやすい一方で、一時的な所得の増加はその多くが貯蓄に回るとする恒常所得仮説と整合的であると言える。また、世帯主の年齢別にみると、ボーナス・臨時収入からの貯蓄割合に大きな違いはないが、収入全般については、高齢層ほど貯蓄に充てる割合が低い(消費に回す割合が高い)。さらに、収入階級別にみると、収入が相対的に低い世帯ほど、ボーナス・臨時収入から貯蓄に回す割合が低い(消費に回す割合が高い)姿となっており、いわゆる流動性制約に直面24している世帯においては、(恒常所得よりも)その時点の所得が消費に影響する程度が大きいという考え方と整合的であることが分かる。一方、こうした流動性制約に直面している家計の割合について、先行研究によると1割台前半と推計されており25、国際的にみても高くないとされる26。他方で流動性制約に直面している家計の割合が2004年から2014年にかけて3%ポイント程度上昇している27との推計結果もあり、足下にかけても更に上昇している可能性には留意が必要であるが28、我が国においては、潜在的には、恒常所得仮説に基づいて行動する世帯が相応に多く存在する可能性が高いと考えられる。

それでは、我が国の近年の所得の増加傾向を、恒常所得、一時的所得という観点でみるとどのようになっているであろうか。まず、改めて「家計調査」により、2002年以降の二人以上勤労者世帯における勤め先収入の動向を年ごとにみると(第2-1-13図(1))、有業人員2人以上世帯については、2003年以降、2010年代前半まで減少した後増加に転じ、足下2023年には2002年と同程度の水準まで回復している。内訳をみると世帯主の定期収入の持ち直しのほか、上述のとおり、世帯主の配偶者の収入の増加が大きく影響している29。
次に、勤め先収入を測る統計として、より適当な「毎月勤労統計調査」により、フルタイム労働者の賃金(現金給与総額)の内訳をみると、2002年以降2010年代半ばまで所定内給与がほぼ横ばい傾向で推移する中で、賃金は主に特別給与の増減で変動しており、一時的所得の変動が相対的に大きかったと言える(第2-1-13図(2))。勤労者世帯の平均消費性向が低下していた2010年代前半から後半にかけての期間をみると、賃金の増加に占める特別給与の寄与が相応に大きく、家計が賃金所得の増加を必ずしも恒常所得の増加とは捉えなかったことが、平均消費性向を下押しした一因と考えることができる。恒常所得に相当する所定内給与は、近年にかけては、賃金全体の変動の多くを占める形で増加傾向にある。恒常所得仮説に基づけば、所定内給与が安定的に増加していくという見通しを家計が持つことができるようになれば、平均消費性向は安定化するものと想定される。
また、共働き世帯が増加する中にあって、必ずしも世帯主・配偶者が共にフルタイムや正規雇用者というわけではなく、例えば正規雇用の男性世帯主の妻で有業である者の過半は、パートタイムなど非正規雇用者30である。共働きによる所得の増加が、こうしたパートタイム等の有期契約での配偶者の勤労によるものである場合、消費行動の意思決定単位としての世帯が、これを一時的な所得の増加と捉えることにより、平均消費性向が低下し、消費支出の伸びが所得の伸びよりも抑制される可能性もある31。ここで、「毎月勤労統計調査」において、パートタイム労働者の賃金は、2002年以降、着実に増加していたが、こうした所得の増加が消費の伸びを高める効果は限定的であったという可能性が考えられる。
さらに、賃金所得に加え、税や社会保障負担、年金給付やその他の移転収入等を加味した可処分所得の推移をみると、2000年代以降、厚生年金保険料など社会保険料の引上げもあって、恒常的な可処分所得の伸びは抑制される傾向にあった(第2-1-13図(3))。これに対し、先述のとおり、近年までは、賃金の調整が恒常所得的な所定内給与よりは主にボーナス等の一時所得で行われたことに加え、コロナ禍における特別定額給付金や、その後の定額減税及びこれと一体的に措置された給付金など所得の下支えとしてとられてきた施策は、一時的な所得を押し上げるものであった。こうしたことから、結果として、恒常的な可処分所得増よりも消費に回る割合が小さく32、平均消費性向を下押しする要素となった可能性があると考えられる33。

(予想物価上昇率の高まりは足下の消費を押し上げるか)
次に、予想物価上昇率を通じた影響である。予想物価上昇率の高まりは、(予想される)将来の財・サービスの価格の上昇率が高まることを意味するものであり、一般的には、名目金利が一定の下では、実質金利を低下させ、異時点間の代替効果を通じて、現在の消費を押し上げる方向に働くとされる。一方で、予想物価上昇率の高まりによる実質金利の低下は、収益率の低下による将来の所得(及び生涯の所得)の減少を通じて消費を下押しするという所得効果ももたらしうる。この2つの効果のどちらが大きいかにより、足下の消費への影響が変わることとなる。ここで、代替効果を示す異時点間の代替弾力性については、先行研究では試算方法や期間等によって幅があるが34、日本の場合については0.1~0.2という試算結果があるなど、必ずしも高くないと指摘される。また、財・サービスの種類によって弾力性は異なるとされ、一般に、備蓄性がある耐久財では弾力性が高い一方、食料品等の非耐久財では低いことが指摘される35ほか、異時点間の代替弾力性の推計においては、耐久財を非耐久財と区別して効用関数に明確に含めることにより、弾力性が高まるとされる36。家計の予想物価上昇率が上昇し始めた2021年後半以降においては、他の形態に比べて、非耐久財の物価上昇が相対的に大きく(第2-1-14図)、予想物価上昇率の上昇が、必ずしも異時点間の代替効果を通じて、足下の消費の増加に結びつかない一因となっていると考えられる37。

また、内閣府「消費動向調査」における消費者マインド(消費者態度指数)を通じた影響をみる観点から、同調査から計算される家計の予想物価上昇率38との関係を相関係数により確認すると、必ずしも予想物価上昇率が高まる局面で、消費者マインドとの負の相関が常に高まるわけではないが39、2007年から2008年10月にかけてや、2021年以降の予想物価上昇率が上昇する局面において、消費者マインドとの負の相関が高まっていることが分かる(第2-1-15図(1))。ここで、「消費動向調査」においては、物価上昇に対する予想について、日ごろよく購入する商品について一年後に物価がどの程度上昇すると考えるかを調査しており、食料品等の購入頻度が高い品目の価格動向が意識されているとみられる。この点、OECD(2024)では、日本を含む主要先進国について、食料やエネルギー価格の上昇率や他の商品と比べた相対的な物価水準の高まりが、消費者マインドを下押しする効果があることを示し、身近な商品の物価上昇が消費者マインドの低下を通じて個人消費を下押しする可能性を指摘している。
また、「消費者態度指数」を構成する4つの指標(「暮らし向き」「収入の増え方」「雇用環境」「耐久消費財の買い時判断」)について、予想物価上昇率との相関係数を個別にみると、近年の物価上昇局面においては、「暮らし向き」と「耐久消費財の買い時判断」で負の相関が相対的に高いことが分かる(第2-1-15図(1)、(2))。「耐久消費財の買い時判断」は、異時点間の代替の弾力性を示す項目と考えられるが、予想物価上昇率の高まりに対して、同指数が低下する傾向がある(買い時でないと判断している)ことからも、我が国の消費者においては、予想物価上昇率の高まりが、代替効果を通じた消費の増加につながっていない可能性を示していると言える40。

関連して、日本銀行「生活意識に関するアンケート調査」から、消費者が認識する過去1年間の物価上昇率に対する認識や、消費者が予想する1年後の物価上昇率の予想と、暮らし向きの変化(前年比)について「ゆとりが出てきた」と答えた割合から「ゆとりがなくなってきた」と答えた割合を差し引いたDIとの関係をみると、2007年から2008年にかけてや2021年から2023年にかけてのように、家計が認識ないし予想する物価上昇率が高まる局面においては、暮らし向きに対する意識が悪化する傾向が確認される(第2-1-16図(1))。物価上昇の認識や予想の高まりが、暮らし向きに関する意識の悪化を通じて、消費意欲を低下させている可能性を示している。同じ調査から、今後1年間の支出を考えるにあたって特に重視すること(複数回答)をみると、2021年以前は「収入の増減」が最大の要素であったものが、2022年頃以降は、「今後の物価の動向」が最大の要素となり、その状態が継続している(第2-1-16図(2))。この点も、物価上昇率が30年ぶりの高さとなる中で、予想物価上昇率の高まりが、消費意欲の低下を通じて、消費を下押ししている可能性を示していると言える41。

(老後不安の高まりが予備的貯蓄の増加を促進する可能性)
以上に加えて、将来の不確実性や不安といった要素が、消費を抑制させる可能性もあり、最後に、この点に関して分析を進める。代表的なケースは、いわゆる長生きリスクによる老後の生活への不安である。これは、一般に、消費者が想定よりも長生きすることにより医療や介護への支出を含め各種の生活費用が増加するなどの不確実性に対し、現役時代において必要な資金を積み増す行動をとることから、貯蓄率が上昇(平均消費性向が低下)するという「予備的貯蓄動機」の考え方に対応する(ホリオカ・新見(2017)等42)。例えば、Hubbard et al.(1994)では、いつまで生きるかという点に不確実性がない場合と比べて、寿命のほか、老後の収入や支出に関する不確実性がある場合には、老後における金融資産の取崩しが緩やかになるとともに、現役時代からより金融資産を蓄積することから、貯蓄率が高まるとしている。厚生労働省の「令和5年簡易生命表」によれば、男性、女性共に、平均寿命よりも死亡年齢の最頻値の方が6~7歳程度高くなっているほか、90歳以上まで生きる可能性がある人は、男性で約4分の1、女性で約半数となっているなど、長生きリスクはより意識されるようになっている可能性がある(付図2-5)。
ここで、家計はどの程度将来を意識して消費・貯蓄行動を行っているのかを確認する。金融広報中央委員会の「家計の金融行動に関する世論調査」によると、「生活設計を立てている」と答えた家計が全体の3割程度、「現在生活設計を立てていないが、今後は立てるつもりである」と答えた家計が全体の5割弱となっている。このように、何らかの形で将来を意識して消費や貯蓄を決定している(あるいは、決定することを予定している)と考えられる家計は多数を占めている(第2-1-17図(1))。また、「生活設計を立てている」とした家計のうち、その期間について「20年先まで」や「20年より先まで」と答えた家計は4割程度と少なくない割合であることが分かる(第2-1-17図(2))。
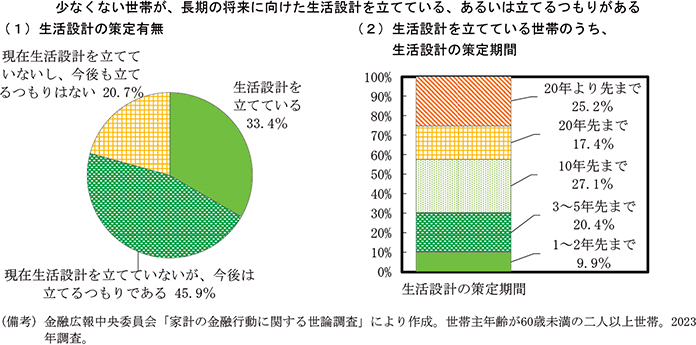
(老後への不安は2000年代後半高止まりし、目標とする金融資産残高は上昇傾向)
次に、同じ「家計の金融行動に関する世論調査」をもとに、家計の老後不安の動向について確認する。「老後の暮らしについて、経済面でどのようになると考えるか」という質問に対して、世帯主60歳未満の世帯において、「非常に心配」もしくは「多少心配」と答えた人の割合を確認すると、1990年代に増加した後、2000年代以降はおおむね80~90%の範囲で横ばいとなっている43(第2-1-18図(1))。ただし、このうち「非常に心配」と答えた人の割合は2000年代後半以降、「多少心配」と答えた人をおおむね上回って推移しており、2000年代後半以降、不安の度合いが高まったという可能性がうかがえる。
また、老後の生活を心配する理由についての回答を確認すると、「十分な金融資産がないから」と答えた人の割合が、70%前後と一貫して高水準にあり、直近の2023年調査では最も回答割合が高い項目となっている(第2-1-18図(2))。これに対し、2007年調査時点では「年金や保険が十分ではないから」と答えた人が70%近くと高かったが、この回答の比率は2023年には40%程度にまで低下している44。一方、「生活の見通しが立たないほど物価が上昇することがあり得ると考えられるから」と答えた人の割合は、2007年調査時点では20%程度だったものが、2022年以降高まり、2023年調査時点では40%程度に上昇している。この間、輸入物価の上昇を起点とする国内物価の上昇が生じる中で、(短期というより中長期的な意味での)将来の物価上昇率への見立てについても、老後不安の源泉の一つとなっていることを示していると言える。

このように、老後の生活に係る将来不安に対しては、十分な金融資産を蓄積できているかどうかが重要な影響を及ぼしているとみられる。そこで、この点について、家計が目標としている金融資産残高の平均値をみると、2010年代後半から上昇傾向にあることが確認される(第2-1-19図(1))。目標金融資産残高を世帯主の年齢別にみると、特に30代以上で増加傾向にある(第2-1-19図(2))。また、目標としている金融資産残高から、現在保有している金融資産残高を差し引いた額(いずれも平均値)についても、目標金融資産残高とおおむね同様に拡大傾向にある(第2-1-19図(1))。

(将来を意識した消費者は貯蓄率が高まる傾向)
以上でみたような老後不安は、貯蓄率あるいは平均消費性向に対して、どの程度の影響を及ぼしているのだろうか。ここでは、先行研究45を参考に、2007年から2023年までの「家計の金融行動に関する世論調査」の二人以上世帯調査における調査票情報をもとに老後不安に関する変数を含め、家計の貯蓄率に影響する要因を分析する。具体的には、前掲第2-1-12図でも確認した「年間手取り収入からの貯蓄割合」を貯蓄率とみなし、これを被説明変数として、世帯属性(世帯主年齢、世帯人員、共働きか否か、世帯収入、金融資産・負債、持ち家の有無等)をコントロールしつつ46、各種の老後不安に関する変数を説明変数として、推計を行った。
まず、先行研究と同様に、老後不安について「多少心配」または「非常に心配」と回答した人について1をとるダミー変数(以下「老後不安ダミー」)を説明変数とした推計結果をみる(第2-1-20図(1)①)47。まず、各種のコントロール変数の貯蓄率への影響をみると、世帯収入、年齢、金融資産、住宅購入予定ダミーはプラス、負債と世帯人員はマイナスとなっている。例えば、住宅購入予定ダミーの係数のプラスからは、住宅購入に備えて貯蓄している家計の姿が、世帯人員の係数のマイナスからは、子育てのための支出を増やしている姿が確認される。また、「家計調査」に基づく前掲第2-1-3図と整合的に、共働きの世帯はそうでない世帯と比べて、貯蓄率が1.4%ポイント程度高い結果となっている。その上で、ここでの主たる関心である老後不安ダミーについてみると、貯蓄率に対する影響は統計的に有意にプラスとなっており、老後不安を持っている世帯は、そうでない世帯に比べて、貯蓄率が0.5%ポイント程度高いことが示唆される。
次に、「老後不安ダミー」の場合、老後不安の有無のみの影響となり、その程度の違いが貯蓄率にもたらす影響を把握できないことから、代替的な指標として、前掲第2-1-19図でみたように、世帯ごとの目標とする金融資産残高と実際の金融資産残高の差(以下「必要貯蓄額」)を説明変数に用いた推計48を行った。先述のとおり、老後の生活を心配する理由として「十分な金融資産がないから」を挙げる人は安定的に7割程度を占めていることから、当該変数が、老後不安の程度を相応に表しているとみなして差し支えないと考えられる。この結果をみると、各種のコントロール変数の影響は、「老後不安ダミー」を用いた場合とおおむね同様であることに加え、「必要貯蓄額」は貯蓄率に対する影響は統計的に有意にプラスとなっており、単純な計算では、1,000万円の不足は貯蓄率を0.19%ポイント程度押し上げる形となっている(第2-1-20図(1)②)。このように、老後の生活に係る将来不安は、予備的貯蓄動機という経路を通じて、貯蓄率の押上げ、平均消費性向の押下げに影響しているものと考えられる。
さらに、老後の不安が貯蓄率を引き上げる程度について時系列での変化をみるため、各年のサンプルごとに、上記と同様の回帰式を推計した(第2-1-20図(2))。その結果によると、「老後不安ダミー」については、対象年によって、統計的に有意でない場合も相応に多く観察されるものの、「必要貯蓄額」を用いた場合には、2010年代後半以降、貯蓄率に与える正のインパクトがおおむね拡大傾向にあることが分かる49。このように、老後の生活に係る将来不安は、近年になるほど、貯蓄率を引き上げ、所得の伸びに比べて消費の伸びを抑制する程度が高まっている可能性が見てとれる50。

関連して、前掲第2-1-17図でみた消費者の将来の生活設計に対する姿勢が、貯蓄行動にどのような影響を与えているのかを確認する。具体的には、第2-1-20図の推計式について、老後不安を表す変数を、生活設計の有無やその長さを示すダミー変数に置き換えて、回帰分析を行った。結果をみると、生活設計を立てている世帯は、そうでない世帯に比べて、貯蓄率が統計的に有意に高いほか、長期的なスパンにわたり生活設計を立てている世帯ほど、貯蓄率が高い傾向があることが分かる(第2-1-21図)。この点について、いくつかの解釈が考えられるが、一つには、家計が、将来にかけて所得が増加していくとは予想していないということがあり得る。すなわち、将来所得が増加すると考える場合、消費の平準化の観点からは、最適な消費水準は現在の所得水準が続くと考えている場合よりも高くなると想定される。よって、その場合には、将来期間を考慮した生活設計を行っていない世帯よりも、将来を見据えた生活設計を行っている世帯の方が、所得のうち消費に回す割合が高くなる(貯蓄率は低くなる)と考えられる。しかし、ここでの推計結果は、こうした推論とは逆の動き、つまり、将来を見据えて生活設計を行っている世帯の方が、そうでない世帯に比べて、所得から消費に回す割合が低い(貯蓄率が高い)状況になっており、将来を見据えて生活設計を行っている世帯は、将来にかけて所得が増加していくとは考えていない可能性があるものと解釈される。

コラム2-1 マクロの個人消費に対して不確実性の上昇が与える影響について
本論では、ミクロデータを用いて、老後生活に関する将来不安を示す変数が、貯蓄率に与える影響を分析した。本コラムでは、こうした分析に関連して、マクロの観点から、不確実性が家計の消費や貯蓄行動に及ぼす影響についても確認する。具体的には、実質消費を被説明変数とし、実質可処分所得や実質金融資産残高、高齢化率等を説明変数とする回帰式について、不確実性の程度を表す指数を説明変数として追加する。不確実性を示す変数には、様々なものがあり得るが、ここでは、Arbatli et al.(2019)に基づき経済産業研究所が公表している「政策不確実性指数」を用いる。これは、新聞記事のテキスト情報から経済政策の不確実性を示す単語51を抽出し、その頻度をもとに定量化したものとなっており、時系列の推移は、コラム2-1図のとおりとなっている。この政策不確実性指数に係る係数が、有意に負であれば、不確実性が高まることにより、消費が抑制される効果を示すこととなる。
2002年からコロナ禍前の2019年までを対象期間とした推計結果をみると、政策不確実性指数の係数は統計的に有意に負となっており、推計期間を通じて、不確実性が10%高まると、消費が0.13%程度押し下げられる関係が確認される。不確実性が高まった例として、2008年9月のリーマンショックに起因する世界金融危機時を取り上げると、不確実性が大きく拡大し、影響が最も多い月で、所得や金融資産を通じた効果とは別に、個人消費を2%弱ほど押し下げた可能性があることが分かる。こうした政策不確実性指標は、本論でみたような長生きリスクに起因する老後不安の影響とは異なるものであるが、消費など実体経済への影響は小さくないとみられることから、その動向についても注視していくことが重要と言える。

以上でみたように、2010年代半ば以降の現役世代における平均消費性向の低下傾向には、①これまで、一時的ではない恒常的な所得の増加が十分ではなかったこと、②足下では、食料品を中心とする物価上昇が、暮らし向きの実感や消費者マインドを下押ししていること、さらには、③長生きリスクなど将来の老後の生活に関する不安が貯蓄率を押し上げていることなど様々な要因が複合的に影響している可能性があることが確認された。GDPの過半を占める個人消費が安定的に回復していくためには、2%程度の安定的な物価上昇の下で、賃金・所得の伸びが、物価上昇を持続的に上回る状況を実現し、家計がこれを前提として、安心して意思決定ができる環境を整備することが肝要である。こうした観点から、次節においては、2024年の春季労使交渉において、33年ぶりの高水準の賃上げが実現した中で、今後の賃金上昇の持続性について検討することとする。

