第2章 労働供給の拡大と家計所得の向上に向けた課題(第2節)
第2節 転職や最低賃金引上げを通じた家計所得拡大に係る課題
第1節では、潜在成長率に影響する労働投入量の引上げの可能性という観点から、労働供給の拡大余地について議論したが、本節では、賃金を中心とする家計所得拡大に向けた論点を扱う。具体的には、第一に、我が国において、特に正規労働者間の転職市場が活性化しつつあり、転職の拡大は、企業の人手不足感が深刻化する中で、人材の引留め等の観点から企業による賃金引上げにつながり得る要素である。ここでは、転職に伴う賃金変化の実態と課題について確認する。第二に、パート労働者の賃金に大きな影響を与える最低賃金について、我が国では全国加重平均1,000円を目指し、大幅な引上げを実現してきたが、こうした最低賃金引上げの効果を確認するとともに、かつてと異なり物価上昇が定着する環境に変わりつつある中で、諸外国のプラクティスも踏まえながら、今後の最低賃金の設定の在り方についての論点を示す。第三に、最低賃金に関連して、時給が増加しても、年収の壁を超えないために労働時間が抑制されるという就業調整について、これまでの実態を確認し、今後の課題を展望する。
1 労働移動(転職)を通じた所得向上の可能性
(正規雇用者(正社員)を中心に転職活動は活発化)
コロナ禍以前から、正規雇用労働者(正社員)を中心に転職者数は増加傾向にあり、コロナ禍後は、男性全般や女性の非正規雇用労働者間等の転職が減少したが、近年では、男女を問わず、再び正社員を中心に転職活動が活発になっている(第2-2-1図(1))。また、転職を希望する就業者は、コロナ禍を経て、男女共に正社員を中心に、1,000万人を超える水準まで増加し、就業者の15%が転職を希望する状況になっている(第2-2-1図(2))1。転職を通じた賃金の上昇も多くみられるようになっており、転職を通じて賃金が1割以上上昇した転職者の割合は、デジタル化が進展する下で引き合いの強い情報通信関係の労働者(IT系エンジニア)を中心に、2020年末以降着実に増加している(第2-2-2図)。転職を通じた労働移動の活発化は、企業に対し労働者を引き留めるために賃金を引き上げる誘因となり、マクロの賃金の底上げにつながり得る。ここでは、コロナ禍を経た転職やこれを通じた賃金変化の動向と課題について考察したい。


(コロナ禍後、高所得層では転職により年収が増加する割合が高まっている)
まず、「雇用動向調査」から、年齢階層別に、転職によって賃金が1割以上増加した労働者及び1割以上減少した労働者の割合の推移を確認する(第2-2-3図(1)、(2))。労働者全体では、転職によって賃金が1割以上増加した労働者の割合は、29歳以下の若年層で約37%に達するなど、40代以下で近年上昇傾向にある。一方、転職によって賃金が1割以上減少した割合は、29歳以下の層では近年12%程度にまで縮小しているほか、30代や40代では2割前後で横ばい傾向となっている。ここには非正規雇用から正規雇用への転職の効果が含まれるため、一般労働者間の転職に限定してみると、転職により賃金が1割以上増加した労働者の割合は、29歳以下や30代で近年約33%に高まっているほか、40代でも約27%に達している。一方、転職によって賃金が1割以上減少した労働者の割合は、これらの年齢層で近年緩やかな低下傾向にあり、直近では20%以下となっている。他方で、定年が近づく50歳以上については、賃金が増加した割合は緩やかに高まっているものの、賃金が減少した割合が40%程度と高止まりしており、他の年齢層とは動態が異なる。
上記の結果として、転職により賃金が1割以上増加した労働者の割合から1割以上減少した割合を差し引いたDIをみると、40代以下のいずれの年齢層でもゼロを上回り、近年改善傾向にあることがわかる(第2-2-3図(3))。以下では、より詳細なデータを活用して、近年、転職市場が活性化する中で、転職前後の賃金の変化にどのような特徴がみられているのかを確認していく。

具体的には、リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査」を用い、サンプルを50歳以下に限定した上で、コロナ禍前(2017年から2018年までとする。)とコロナ禍後(2021年から2022年までとする。)に転職した正規雇用労働者の転職前後の年収の変化をみる(第2-2-4図)。この結果によると、コロナ禍前からコロナ禍後にかけて、転職前収入・転職後収入ともに、400万円未満の年収層の割合が低下し、400万円以上の年収層の割合が上昇している。ただし、転職前の年収層ごとに、転職前後で年収が上昇した割合をみると、転職前収入が600万円以上の層で明確に高まっているが、600万円未満では、コロナ禍前と比べ、おおむね変化がない(第2-2-5図)。コロナ禍前からコロナ禍後にかけて、特に年収が高い層において、転職により賃金が増加するケースが増えていることがわかる。


(正規雇用間の転職の更なる促進に向けリ・スキリング支援が重要)
この背景をみるため、正規雇用労働者の転職の際の職種の変化に注目すると、コロナ禍前後を問わず、転職者に占める構成比の高い医療関係では同職種間の転職が過半数を占めており、専門性の高さから同職種間の転職が中心になっているとみられる(第2-2-6図(1))。また、転職前後の職種ごとの構成割合をみると、比較的年収の高い情報通信は、特にコロナ禍後において、転職前の構成割合に比べ、転職後の構成割合が高くなっており、他職種からの転職者も相応に集めているとみられる。一方、比較的年収の低い一般事務職も、コロナ禍前後を問わず、転職前の構成割合よりも転職後の構成割合が高く、他職種から人を集めていることがわかる。こうした背景もあって転職前後で年収が下落する労働者も相応にいると考えられる。
次に、一定の規模で発生している職種間移動に焦点を当ててみると、①理系専門職から情報通信、②運輸・郵便から生産工程で、一定規模の職種間移動がみられる。①は年収が同程度か高い職種への移動であり、逆に②は年収の低い職種への移動となる。これらの職種間移動の理由をみると、①の年収の高い職種へ移動している層は賃金や労働条件への不満から転職している割合が最も高い一方、②は人間関係や仕事内容への不満などから転職している割合が最も高いことがわかる(第2-2-6図(2))。
このほか、年収が相対的に高い職種のうち、管理職等は比較的幅広い職種から転職者を集めている一方、理系専門職は多くが同職種からの転職であり、情報通信は同職種と理系専門職からの転職でほとんどを占めるほか、企画・財務・金融は同職種のほか一般事務からの転職がほとんどを占めており、この状況はコロナ禍前後で大きくは変わっていない(付図2-4)。正規雇用労働者のうち年収の高い職種は一定の専門性が求められる可能性がある。

以上の結果をまとめると、第一に、正規雇用労働者の転職による職種間移動には一定の困難さがあるものの、互いに親和性の高い職種間では流出入がみられ、そうした職種では、転職行動の活発化による賃金上昇圧力がかかりやすいとみられる。第二に、年収が低い職種についても、人間関係・仕事内容といった職場環境の観点から転職先として一定の人気があり、その意味では、転職市場全体としての賃金上昇圧力を抑制する要因になっているとみられる。もっとも、コロナ禍を経て、転職後の年収層は400万円以上の年収層の割合がおおむね高まっており、相対的に年収が高めの層での転職が広がりつつある。物価とともに賃金が動き出し、価格メカニズムが働く下で、転職による労働移動の活発化は、限られた労働力が適切に配分されることを促し、経済のダイナミズムにつながる。今後、更なる家計所得向上に向け、需給がひっ迫しているものの、その専門性ゆえに参入が難しい情報通信分野等の職種への転入が可能になるような効果的なリ・スキリング支援等が重要になると考えられる。
(非正規雇用間の転職では職場環境を異業種転職の理由にする割合が高い)
最後に、一般的に熟練度が低く、職種間移動のハードルが低いと考えられる非正規雇用の転職行動をみてみる2。薬剤師などの資格職を含む「その他専門職」を除き、平均時給はどの職種もおおむね同水準である(第2-2-7図(1))。正規雇用労働者と同様に、同じ職種間の転職も多いが、正規雇用労働者と異なり、コロナ禍後にかけて、近年、物流倉庫の建設などで需要が高まっていると考えられる倉庫・警備清掃業により多くの人が移動するようになっていることがわかる。また、倉庫・警備清掃業は生産工程から人を集めており、翻って生産工程は運輸・郵便から人を集めている。転職理由をみると、非正規雇用の雇用形態に照らして多くみられる雇用期間満了を含む会社都合を除くと、人間関係や仕事内容で転職している割合が高いことがわかる(第2-2-7図(2))。このように、賃金水準に大きな差がない非正規雇用では、人間関係・仕事内容といった職場環境を転職の基準にする割合が相対的に高いとみられる。人手不足感が高いとされるものの、人材が流出している運輸・郵便などの業態においては、賃金水準の改善に加え、省力化投資の拡大や勤務制度の見直し等による職場環境の改善も重要である可能性が示唆される。

2 最低賃金の引上げの影響と物価上昇下での最低賃金設定の在り方
(年々最低賃金上昇の影響を直接受ける労働者は増加している)
次に、最低賃金の引上げを通じた所得向上への影響と課題について検討する。我が国における最低賃金3の動向をみると、近年は、2020年を除き、引上げ率が上昇し、これに伴いパート労働者の平均時給も増加傾向にある(第2-2-8図)。実際、これまでの実績を踏まえると、最低賃金1%の引上げはパート労働者平均時給0.4%弱の増加と相関がある(第2-2-9図)。
こうした中、最低賃金引上げの直接的な影響を受ける労働者が増加している。具体的には、非正規雇用者の賃金分布をみると、最低賃金近傍で働く労働者は年々増加していることがわかる(第2-2-10図)。さらに、内閣府政策統括官(経済財政分析担当)(2023a)と同様に、非正規雇用者の時給を上位から下位にかけて10%刻みで分けて、70%分位点(下位から数えて70%に位置する雇用者の賃金)を基準に、他の分位点の動きを検証すると、基準点より低い幅広い雇用者の賃金に対して、統計的に有意に時給の上昇効果をもたらすとともに、より低賃金の雇用者ほど上昇効果が高く、賃金分布の圧縮に貢献していることが改めて確認される(第2-2-11図)。このように、最低賃金の引上げは、相対的に低めの賃金で働いている労働者に対して、賃金水準を引き上げるという観点からは一定の効果があることが確認される。前節でも述べたように、少子高齢化の下で、我が国では、高齢者の就業拡大が進んできたが、非正規雇用形態での短時間勤務が多い高齢者は、最低賃金近傍で働いている労働者の割合が他の年齢層に比べて高い4とされ(2015年時点の厚生労働省の調査によると、60歳以上の労働者の2割超が最低賃金近傍で働いている)5、最低賃金引上げによる賃金上昇効果は、高齢化が進む下で、中長期的に拡大する可能性もある。




(地方での最低賃金引上げの影響は大きい)
次に、地域別に、最低賃金引上げの影響を直接受ける労働者の割合の違いや変化をみてみる。我が国では、中央最低賃金審議会が、地方最低賃金審議会に対し、各都道府県の地域別最低賃金額の改定についての目安を示し、地方最低賃金審議会がそれぞれの都道府県の最低賃金引上げ幅を決定している。目安制度は、1978年から始まり、2022年以前までは、所得・消費、給与、企業経営に関する指標を踏まえ、47都道府県をAランク、Bランク、Cランク、Dランクの四つのランクに分けて目安額が提示されてきた6。2023年からは、ランク間の格差是正の一環として、最低賃金のランク区分は四つから三つに削減されることとなった7。
ここでは、従前の四区分のランクごとに、近年の最低賃金の引上げによる影響を確認する。前掲第2-2-10図を、ランク区分ごとに分けると、Dランクを始め最低賃金水準が相対的に低い都道府県において、最低賃金上昇の影響を直接的に受ける労働者が多い傾向があることがわかる(第2-2-12図(1))。また、最低賃金上昇の影響を直接的に受ける労働者の割合の変化をみると、最低賃金が相対的に低いDランクでは最低賃金引上げの影響を直接的に受ける労働者が、他のランクに比べて、2022年では、相対的により増加していることがわかる(第2-2-12図(2))。このように、パート労働者を中心に、地方部ほど賃金の底上げ効果が高いものとなっている8一方で、企業側からみた場合、地方の方が、最低賃金引上げによる人件費負担の上昇の影響をより受けるとみられる。最低賃金の労働需要・雇用への影響の有無や程度については、各種研究でも議論が分かれており、引き続き、効果の検証を行いながら、地域別最低賃金の設定の在り方について議論を深めていく必要がある。

(諸外国では日本を上回るペースで最低賃金の引上げが行われている)
次に、主要先進国と日本の最低賃金の動向を比較する。日本を含め主要先進国では、継続的な最低賃金の引上げが行われているが、2000年以降の最低賃金水準の推移をみると、日本は相対的に低めの伸び幅となっている(第2-2-13図(1))。日本の場合、この間の名目賃金の伸びが他の主要国対比で低いこともあって、最低賃金の上昇度合いも相対的に低い。また、OECDが公表するフルタイム労働者の賃金中央値対比でみても、着実な上昇傾向にはあるものの、他の主要国に比べると直近の2022年でも低い水準となっている(第2-2-13図(2))。
日本の長期的な最低賃金の推移の背景を振り返ると、2007年までは、最低賃金の設定が、賃金改定状況調査による賃金上昇率とおおむね同程度であった。このため、我が国のフルタイム労働者の賃金中央値対比での最低賃金の推移をみると、2000年代後半までは、微増の範囲内で推移していた。その後、最低賃金法改正により、生活保護の受給金額との逆転を目指すことが示されたほか、2015年以降は、一億総活躍社会の実現に向けた対策の中で、2020年までに全国平均1,000円の最低賃金を目指すことが掲げられたことから、賃金中央値対比での最低賃金は上昇傾向で推移してきた。
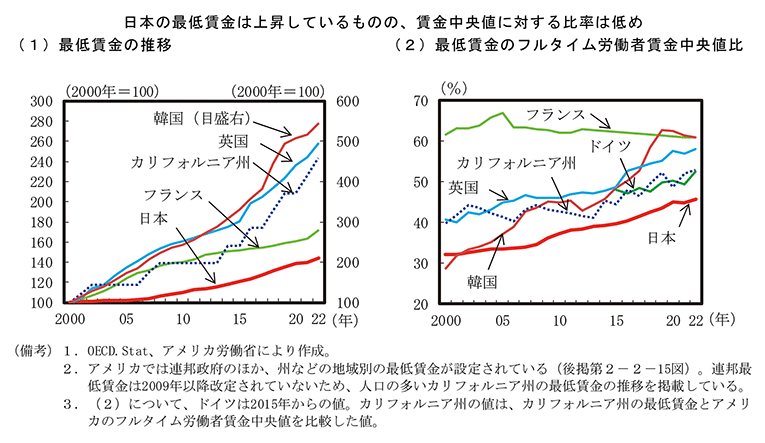
(日本の最低賃金は、近年の物価上昇に対して実質時給ベースで購買力を維持)
次に、今回の物価上昇局面に焦点を当て、最低賃金の上昇度合いを国際的に比較する。ここでは、2020年12月を起点とし、主要国の名目最低賃金の累積変化をみると、日本は、2023年10月の最低賃金の引上げもあり、物価上昇前の2020年12月比で+11%となっているが、依然として、欧州各国はこれを超える最低賃金の上昇となっている(第2-2-14図)。他方、この間の物価上昇分を差し引いた実質ベースの最低賃金での累積変化をみると、日本の場合、他国に比べて物価上昇率が相対的に抑制されていたことから、物価上昇前の水準をやや超える実質水準が維持されていることがわかる。他の主要国についても、足下では、おおむね物価上昇前と同程度の水準の実質最低賃金となっているが、①ドイツでは、2023年の名目最低賃金の引上げ幅が大きく、実質水準は物価上昇前の水準を上回っている、②英国では、年一回の引上げまでの間、物価上昇が相対的に大きく、実質最低賃金の水準が物価上昇前を下回る状況が生じている、③フランスは、名目の最低賃金の改定頻度が高く、実質の最低賃金水準はおおむね一定に維持されている、といった特徴がみられる。今回のように、急速な物価上昇が生じた局面において、最低賃金近傍の賃金で働く労働者の生活水準を維持する観点から、最低賃金の設定の在り方がいかにあるべきか、という点は、国際的にも議論がなされている9。

(海外の最低賃金の設定方法と日本への含意:物価上昇を前提とした制度の検討が重要)
そこで、最低賃金の設定の仕組み等について、日本と主要国を比較することで、日本の今後の最低賃金の設定に向けた含意を検討したい(第2-2-15図)。
まず、最低賃金制度の導入時期をみると、日本は1959年の最低賃金法により全国的に最低賃金が設定されるなど比較的以前から最低賃金制度が存在する一方、ドイツは2015年、英国は1998年と比較的近年に導入されている。ドイツや英国では、労使交渉による賃金決定が弱まる中で、実質賃金を維持・引き上げる目的もあり最低賃金が導入された10。こうした背景もあり、これらの国では、賃金中央値対比でみた最低賃金は高めの水準となっている。欧州各国の中で1950年と比較的古くから導入されているフランスは、第二次世界大戦後の戦後混乱期の激しいインフレ進行に際し、国民の購買力の維持を図る観点から導入された経緯もあり、賃金中央値対比でみた最低賃金は、以前からドイツや英国よりも高めの水準となっていた。一方、韓国は、零細事業所の低賃金労働者を保護する目的で1988年以降、最低賃金が導入されたという背景11もあり、最低賃金の設定に当たっては、競争力の低い事業所が目安となっていたことから、2000年代の賃金中央値対比でみた最低賃金は低めで推移していたが、2017年に文政権が時給10,000ウォン達成を公約とし、2018年、2019年は10%を超える大幅な引上げが実施されたことで、急速に最低賃金が上昇した。
最低賃金の決定プロセスをみると、各国とも、労使代表及び有識者が参加する審議会等で決定するなど似通っているが、改定頻度については、日本のほか、英国、韓国は年一回であるのに対し、ドイツは不定期ながら最近においては年二回程度、フランスは原則年一回であるものの、後述するように、物価上昇が前回の引上げから2%を超えると物価上昇分を引き上げる制度となっており、物価上昇局面での改定頻度が高くなるという特徴がある。
また、最低賃金の目標水準の置き方や、最低賃金の改定が物価上昇率等の何らかの指標に連動したものであるか否かについては各国で状況が異なる。まず、最低賃金の目標について、欧州においては、2022年10月に採択されたEU指令「適切な最低賃金の考え方」の中で、国際的に共通の参照水準として、名目賃金水準の中央値の6割や平均値の5割等が例示されている。フランスでは、従前からこの水準を超えた最低賃金設定がなされているが、ドイツでは、2022年にショルツ政権が名目賃金中央値の60%を目標とし、最低賃金の引上げを行っている。また、英国では、2024年までに、最低賃金を名目賃金中央値の3分の2相当に引き上げるとの目標を掲げている12。これに対し、日本や韓国では、名目賃金中央値の一定割合といった相対的な水準目標ではなく、1,000円や10,000ウォンのように、直感的に理解しやすい最低賃金の絶対的な水準を目標に設定しているという特徴がある。
他方、各回における具体的な最低賃金の引上げ幅が、物価など何らかの指標に連動しているか、という点でみると、日本を含め多くの国では、労働者の生計費、事業者の賃金支払能力、雇用や経済への影響、所得分布等の定性的な基準であり、明示的な参照指標があるわけではない。一方、フランスにおいては、物価や賃金との連動があり、物価については、毎年一回の定例改定に加え、直近の改定から物価上昇率が2%を超えた場合、物価上昇分だけ自動的に改定される制度となっている13。また、賃金については、名目の最低賃金上昇率が年間実質賃金上昇率の2分の1を下回る場合は、上回るように設定するとされているほか、政府の政治的判断によって最低賃金上昇率が上乗せされる場合もあるとされている。物価との連動という点では、連邦レベルの最低賃金のほか州別に最低賃金が設定されるアメリカにおいては、これまでカリフォルニアなど13の州とワシントンD.C.において、最低賃金の物価スライド制が導入され、2024年以降はさらに六つの州で導入予定となっている。こうした州では、近年、物価が高まる中で、州議会の改定手続きを経ずに最低賃金を自動的に改定することが可能となっている。物価連動制については、物価上昇率が高い下で、交渉力の低い低賃金労働者の購買力を維持することで労働者の生活保障、働く意欲の向上、内需の維持につながるといったメリットがある一方で、賃金の上昇が人件費の増加を通じて価格に転嫁され、物価上昇が加速するという懸念点もあるとされる14。
このように、最低賃金設定の目標や具体的な設定の考え方は各国においてそれぞれ異なる。それぞれメリット・デメリットがあり、必ずしもベストプラクティスが確立しているとも言い難いが、我が国において、1990年代後半以降長期にわたり「物価や賃金は動かない」ことがノルムとなっていた状態から、「物価や賃金は上昇する」というノルムに移行していく中にあっては、最低賃金の設定の考え方についても、時代に即した制度に見直していくための検討が必要になると考えられる。具体的には、近年の我が国の最低賃金引上げが労働者の賃金水準の底上げを目的に行われてきていることも踏まえつつ、例えば、国際的にみられるように賃金中央値との対比での水準目標の導入を検討することや、最低賃金水準を物価・賃金動向に何らか連動させる仕組み、特に、フランスのように、物価上昇が急速に進んだ場合に、年一回の機会を待つことなく最低賃金の改定が随時可能になるような仕組みの導入の是非について検討していくことには一定の意義があると考えられる。

3 就業調整の実態と課題
(これまで最低賃金の上昇に伴い就業調整が増加してきた可能性)
最低賃金の引上げもあり、我が国のパート労働者の賃金は、時給ベースではこれまで着実に増加してきた一方、労働時間は減少傾向で推移していることから、これらを合わせた年収ベースでは伸び幅は小幅にとどまっている(第2-2-16図)。時給増加の効果を打ち消すようにパート労働者の労働時間が減少傾向にある背景の一つと指摘されるのが、「年収の壁」である。具体的には、まず、税制上、給与収入が103万円(基礎控除48万円と給与所得控除55万円)を超えると、住民税に加えて所得税の納税義務が発生する。主たる稼得者の配偶者として、給与収入が103万円以下であれば主たる稼得者には配偶者控除が適用され、103万円超150万円以下であれば、主たる稼得者が一定の年収以下であれば年収に応じて配偶者特別控除が満額適用される。次に、社会保険制度について、第3号被保険者として配偶者の扶養に入りパート等の形態で従業員101人以上の企業において働く労働者は、年収が106万円を超えると扶養を外れ、厚生年金や健康保険に加入する必要があることから、保険料の支払によって手取り収入が減少するため、壁を超えないように労働時間の抑制、すなわち就業調整を行うインセンティブが発生する。一例として、家計の主稼得者が年収400万円の夫婦二人世帯について、配偶者が家計補助者として就業し、収入を得る場合に、年収106万円の壁前後における家計全体の手取りの変化をみると、約15万円の減少が生じることがわかる(第2-2-17図)。加えて、従業員が100人以下の企業など厚生年金の適用対象になっていない企業で働く労働者は、年収が130万円を超えると扶養を外れ、国民年金や国民健康保険の保険料を支払うこととなるため、やはり壁を超えないように就業調整を行う誘因が生じる。社会保険料については事業者側の負担もあることから、企業側も労働者に対して就業調整を働きかけるインセンティブがある。こうした税・社会保険制度以外にも、各企業で独自に実施されている配偶者手当もこうした年収の壁を基準に支給の有無が決められている。このため、短時間労働を希望する就業者は、各人の状況に応じて、年収を100万円前後から200万円の範囲に意図的に抑えているとされる。
こうした年収の壁の存在により就業調整を行っている労働者は、2022年時点で、約540万人おり、その過半を15~64歳の有配偶女性が占めている(第2-2-18図)。また、近年では高齢化の進展もあり、65歳以上女性の非正規雇用労働者の割合も拡大している。最低賃金の上昇などを背景にパート労働者の平均賃金も上昇してきた一方、年収の壁となる106万円等の収入水準は、現行制度上、平均時給の上昇に伴い毎年度変化することはないため、年々、非正規雇用で働く有配偶者の女性を中心に、年収の壁を意識しながら働く短時間労働者の割合が増えてきたと考えられる。15~64歳の非正規雇用労働者のうち、年収の壁前後の収入階層である年収100万円~149万円のグループをみると、2017年から2022年にかけて5年で就業調整の実施率は約4%ポイント上昇している(第2-2-19図(1))。その中でも15~64歳の非正規雇用で働く有配偶者の女性の就業調整の実施率をみると、年収50万円~149万円の労働者では就業調整の実施率が50%を超えており、特に100万円~149万円の層では就業調整の実施率が過去5年間で約4%ポイント上昇していることがわかる(第2-2-19図(2))。




(年収の壁を背景とした就業調整は大幅な労働時間の減少を生む)
次に、就業調整の開始時期を確認するため、女性の結婚前後の年収の分布をみる。まず、正規雇用で働く女性は、結婚の前後で年収の壁付近での年収分布の変化はみられない一方で、非正規雇用の女性は、結婚の前後で年収のピークが200万円から100万円に変化している(第2-2-20図(1)、(2))。このように、非正規雇用の女性は、結婚を機に年収の壁を意識した働き方を選択しているとみられる。同様に、女性の結婚前後の週当たり労働時間の分布の変化をみると、正規雇用の女性では、結婚前後でおおむね分布に変化がみられないが、非正規雇用の女性では、結婚前はピークが週35~40時間であるところ、結婚後はその山が崩れ、週15~20時間等のより短い労働時間にシフトしていることがわかる(第2-2-20図(3)、(4))。非正規雇用の女性は、結婚前は正規雇用の女性と同じく週40時間勤務していたが、結婚を機に週20時間勤務を選択する女性が増加しているとみられる15。非正規雇用の未婚女性の場合、最頻値の年収が200万円程度となっている。こうした女性が結婚後、自身の労働時間を短縮すれば、年収の壁の効果により、世帯として税や社会保険料の各種負担を抑え、主稼得者である配偶者が勤務している企業から配偶者手当を受給できる場合もあることから、就業調整を行っている可能性がある。前掲第2-1-7図のとおり、非正規雇用の女性の追加就業希望の有無と配偶者の年収に関係がみられなかったことと併せて考えると、各種の制度要因により、労働インセンティブが低下しているとみられる。
最低賃金の引上げは、最低賃金近傍で働く非正規雇用者の時給を増加させ、労働のインセンティブを向上させる効果がある一方、年収の壁が固定されていることから、「壁」に到達するまでの総労働時間が短くなり、労働供給を押し下げる効果がある点に留意が必要である。後述するように、最低賃金の引上げが家計所得の向上と労働供給の増加につながるように、年収の壁による就業調整を緩和するための対策が極めて重要である。

(高齢者の労働参加が進む中、高齢者の就業調整にも留意が必要)
次に、高齢就業者に着目して、就業調整の実態を確認する。65歳以上の非正規雇用で働く高齢者の就業調整の状況をみると、男女で異なる結果がみてとれる(第2-2-21図)。
まず、女性については、15~64歳の有配偶女性と同様に、2017年から2022年にかけて、賃金の上昇に加え、高齢化の進展という人口要因もあり、就業調整の実施率、実施人数共に50万円~149万円の層で大幅に増加している。高齢者のうち年収の壁を超えた場合に厚生年金保険料の支払義務が発生する65~69歳は、年金加入期間は基礎年金の満額支給が可能な40年を超えている可能性が高く、追加的に厚生年金保険料を支払っても年金全体の収入額が大きく増えるわけではないため、年収の壁を前にした就業調整のインセンティブは現役世代よりも高くなっていると考えられる。
一方、男性高齢者では、年収50~149万円の層の就業調整の実施者数は少なく、過去5年で実施率も低下しているが、逆に、300万円以上の層で実施率、実施人数ともやや増加していることがわかる。この背景には、月給に加え賞与や年金などを含めた月収総額が48万円を超えると、段階的に年金支給額が減額される在職老齢年金制度による年金支給の停止といった制度要因があると考えられる。具体的には、現在の平均年金受給状況16をみると、厚生年金と国民年金の平均受給額の合計は約20万円であり、こうしたケースの場合、勤務先からの年収が340万円程度で年金支給額の減額が始まることになる。こうした年金支給額が減額される年収基準は、同世代の平均年収17とほぼ同額で、フルタイムで勤務している場合、この基準に抵触しやすい状況にある。また、「就業構造基本調査」では、主に非正規雇用労働者の就業調整の状況を調査しているが、年収300万円を超えると、正規雇用労働者の割合も増える中で、高齢者の正規雇用労働者の中にも就業調整を行っている者が一定数いるとみられる。2021年の高年齢者雇用安定法の改正により、70歳までの雇用継続が努力義務となり、65歳以上でもフルタイムで働く労働者が増える中で、40年を超えて保険料を支払った場合には基礎年金の支給額を増額する、あるいは、在職老齢年金制度による年金支給の停止が始まる年収基準の閾値を引き上げるなど、高齢者の就労インセンティブを高めていく制度の在り方を検討することが重要である。

(短時間労働の割合は、社会保険制度にも依存している可能性)
ここでは、諸外国との比較を通じて、社会保険制度が、短時間労働者の労働時間にどのような影響を与えているか確認する。まず、週当たりの労働時間をみると、日本を含む多くの国で週40時間から48時間(1日当たり8時間から10時間)の分布が最も多く、フルタイムで働く労働者の標準的な勤務時間は各国でほぼ同様である(第2-2-22図(1))。一方で、短時間労働者については、各国で動向が異なる。具体的には、一般的に、短時間労働者は家事・育児の負担が重い女性を中心に多くみられることから、女性の労働者に占める短時間労働者の割合に焦点を絞って比較すると、日本は、週20~29時間を中心に他国対比で短時間労働の割合が高い(第2-2-22図(2))。ドイツ、英国では、日本ほどではないが、週当たり労働時間が20~29時間の労働者の割合が相対的に高いこともわかる。
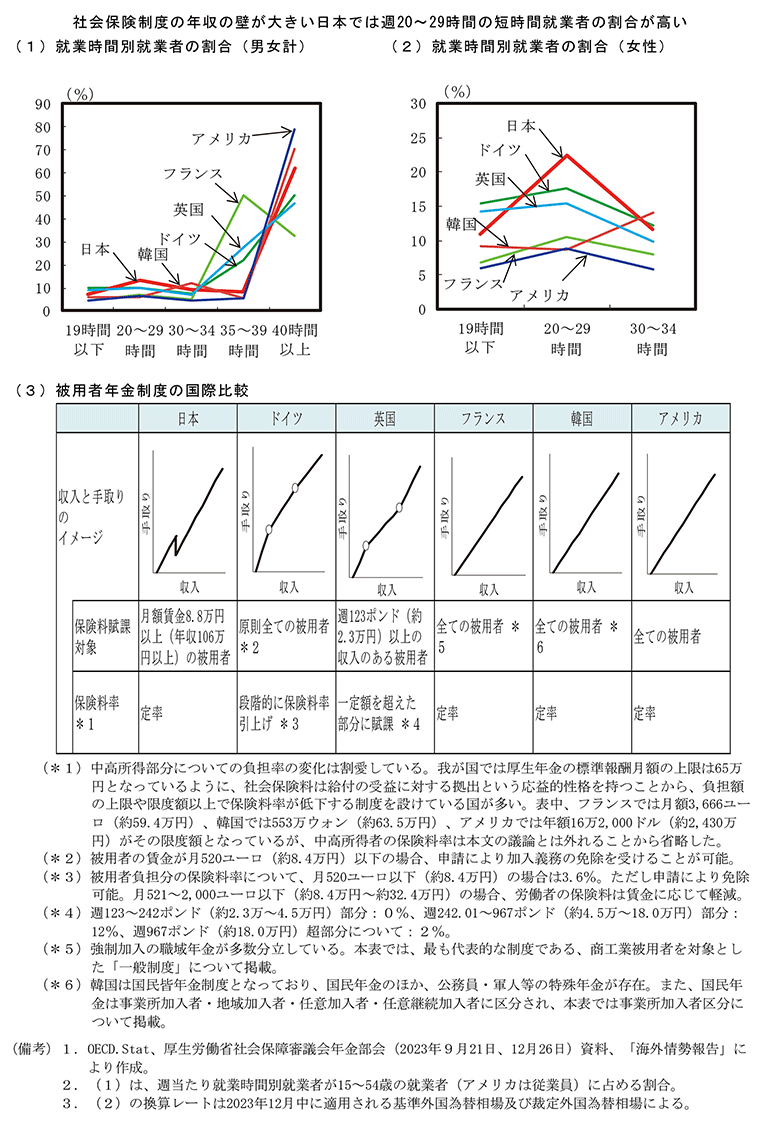
次に、各国の社会保険制度を比較し、各国における短時間労働者の労働時間の分布の差に係る背景を確認する。各国の制度を基に、社会保険料控除前の勤労収入(以下「額面収入」という。)と控除後の手取り収入の関係をみると、大きく三つのカテゴリーに分かれる(第2-2-22図(3))。ここでは、日本については、後述する2023年10月以降の年収の壁への対策を講じる前の姿としている。一つ目は、一定の額面収入を超えると年収の壁の効果により一旦手取り収入が減少する日本、二つ目は、一定の額面収入を超えると手取り収入の伸びが鈍化するドイツや英国、三つ目は、額面収入と手取りが定率で変化するアメリカ、フランス、韓国である。こうした制度上の類型は、前述の週当たり労働時間が20~29時間の短時間労働者の割合における各国の違いとも整合的である。額面収入と手取りが定率のアメリカ、フランス、韓国では20~29時間の短時間労働者は女性労働者の10%以下である一方、日本のほか、手取り収入の鈍化という意味での壁があるドイツや英国では相応の割合で短時間労働者が存在する。このように、労働者の勤務時間の選択には、社会保険制度が影響を与えている可能性がある。
なお、ここでは社会保険料にのみ着目したが、これに限らず、額面収入の増加に対して、税負担の増加や各種給付の削減が生じると、これらをネットアウトした手取り収入の増加が抑制され、労働インセンティブを阻害する点にも留意が必要である。OECD(2022)は、一定のモデル世帯について、税・社会保険制度を踏まえ、最低賃金の増加のうち、どの程度の割合が手取り収入として残るのかを国際比較しているが、日本については、後述する年収の壁対策前の制度を前提としている面もあるが、この割合が低くとどまっている(第2-2-23図)。ここでも指摘されているとおり、短時間労働者の賃金に強く影響を与える最低賃金の在り方を考えるに当たっては、税制や社会保険制度との相互関係も踏まえた総合的な検討が重要である。

(年収の壁・支援強化パッケージの効果が表れ始めている可能性)
年収の壁への対策として、2023年9月に「年収の壁・支援強化パッケージ」が公表された。これにより、2023年10月からの2年間の措置として、「106万円の壁」に対しては、パート・アルバイトで勤務する人の社会保険の新規加入に伴い手取り収入を減らさない取組(社会保険加入促進手当、賃上げなど)を実施する企業に対して、労働者一人当たり最大50万円の補助金を支給することとなり、また、「130万円の壁」に対しては、パート・アルバイトで勤務する労働者の収入が繁忙期に労働時間の延長などで一時的に上がった場合でも、事業主がその旨を証明することで、被扶養者認定の継続が可能となった。
こうした対策が実際に就業調整の緩和につながっているかの検証を行うことは、今回の2年間の時限措置後の制度を検討していく上で極めて重要となる。現時点においては、利用可能なデータは限られているため、ここでは、「労働力調査」を用い、就業調整の実施率が高い有配偶女性の非正規雇用者における月間労働時間の変化をみることとする。具体的には、これら女性雇用者について、ここ数年の9月と10月から11月における月間労働時間別のシェアの前年からの変化をみると、2023年9月は、106万円の年収の壁を超えない範囲の労働時間とみられる月間41~60時間や61~80時間の労働者の割合は、前年比で増加した一方、年収の壁を超える労働時間が含まれる月間80~100時間ないし月間100時間以上働く労働者の割合は減少していた。「年収の壁・支援強化パッケージ」が導入された後の2023年10月から11月については、61~80時間の労働者の割合は対前年比でやや減少している一方、月間100時間以上働く労働者の割合は、2021年と2022年の10月から11月は対前年で減少していたのに対し、2023年は増加に転じていることがわかる(第2-2-24図)。このように、今回の年収の壁対策は、就業調整の抑制という点で、一定の効果を生んでいる可能性はある。
ただし、上述の分析は、あくまで単月の動向であり「労働力調査」におけるサンプルの振れの影響を受けている可能性もあるため、引き続き、給与計算代行サービスデータといったリアルタイムデータを含む各種データを用いた分析を通じて、今回の年収の壁対策による就業調整の抑制効果に係る詳細な検証が課題となる。また、今回の対策は、人手不足にも配慮して当面の措置として実施されたものであるが、今後の中長期的な年収の壁対策に当たっては、共働き世帯の増加や女性の正規雇用者の増加といった大きな流れがある中で、女性は被扶養者、あるいは短時間労働者であるといった前提に拠らない各種制度の構築も視野に入れていくことが重要である。


