第2章 労働供給の拡大と家計所得の向上に向けた課題(第1節)
第1節 コロナ禍を経た労働供給の動向
我が国では、少子高齢化の進行や労働時間の縮減の中で、1990年代初頭以降、就業者数と労働時間から成る労働投入(労働供給)は全体として緩やかな減少傾向で推移してきた。2010年代前半以降は、女性や高齢者の労働参加の促進による就業者数の増加と、労働時間が相対的に短い女性、高齢者の増加等による一人当たり平均労働時間の減少が相殺し、労働投入全体の伸びとしてはゼロ近傍となってきた。しかし、今後、人口減少圧力が労働参加向上効果を上回ることで労働投入が減少していけば、経済の供給力である潜在成長率を押し下げる要因となる。一方、人手不足の状況が強まる中で、女性や高齢者による労働参加が限界を迎えれば、本格的な賃金上昇とこれを通じた物価上昇につながるという、いわゆる「ルイスの転換点1」が近づいているという議論もある。こうした点を踏まえ、本節では、今後、女性や高齢者を中心とした就業者数や労働時間の拡大余地があるのか否か考察するとともに、柔軟な働き方の促進を通じた就業希望の実現の可能性を確認していく。
1 労働供給の増加余地
我が国では、少子高齢化の進行に伴い、1995年をピークに生産年齢人口(15~64歳人口)が減少に転じ、総人口も2008年をピークに減少が始まった。こうした中で、15歳以上人口に占める就業者の割合である就業率をみると、コロナ禍で一時的に落ち込んだ後、女性の正規雇用者の増加を中心に回復し、2023年春以降は、コロナ禍前の水準を超え、改善傾向が続いている。人口減少にもかかわらず、2010年代前半以降、女性、さらには高齢者の労働参加の拡大により、就業者数は増加傾向を続けてきたわけであるが、こうした動きは将来にわたっても続くものであろうか。
(2010年代半ばからコロナ禍前までは、実際の労働投入は潜在的な投入を上回っていた)
まず、労働供給が経済成長に与える影響について確認するため、潜在成長率に就業者数と労働時間がどの程度寄与してきたかみてみよう(第2-1-1図(1))2。1990年代は、1988年の労働基準法改正により、週法定労働時間が48時間制から40時間制に段階的に移行することになり、週休2日制度の導入企業の増加による労働時間の減少を主因に、就業者数要因と労働時間要因の合計である労働投入量の潜在成長率への寄与は継続的にマイナスであった。2000年代は長時間労働の是正の動きによる長時間労働者の減少やパートタイム労働者の増加などによる労働時間の減少に加え、生産年齢人口の減少による就業者の減少もあって、1990年代に引き続き、労働投入部分の潜在成長率への寄与はマイナスであった。また、実際の労働投入量をみると、バブル経済崩壊後の経済の停滞、需要不足もあり、潜在的な労働投入量を下回って推移していた(第2-1-1図(2))。
一方、2013年からコロナ禍までの期間においては、アベノミクスの下で、女性や高齢者を中心に就業者の裾野が広がった。これらの就業者には短時間労働の就業者が多いこともあって、労働時間要因は引き続き潜在成長率の下押しに寄与したものの、就業者数要因は潜在成長率の押上げに寄与し、結果として、両者が相殺する形で労働投入の潜在成長率への寄与はおおむねゼロ近傍で推移していた。実際の労働投入をみると、トレンドを上回る就業率の向上もあり、コロナ禍前は潜在的な労働投入を大きく上回っていた。

(女性の就業の拡大は継続している)
2013年以降、女性活躍の取組が進展し、高齢者を含め幅広い年齢層で女性の就業率が上昇してきた(第2-1-2図(1))。この中で、女性の正規雇用者数は2014年以降継続的に増加し、非正規雇用者については、コロナ禍の影響で一時的な減少がみられたものの、その後はコロナ禍前の増加トレンドに復帰している。
2008年には我が国の人口は減少に転じ、これ以降、労働参加率が年齢別・男女別で一定であれば、人口構造を含む人口要因のみでは労働力人口は減少することが想定されていたが、実際には、労働力人口は増加傾向で推移してきた。この点について、2012年以降の三時点(2012年、2017年、2023年)で公表された「日本の将来推計人口」を基に、それぞれのベンチマークとなる国勢調査対象年である2010年、2015年、2020年時点以降、人口要因だけで女性の労働力人口がどのように推移するか推計したもの(以下「推計値」という。)と、実際の女性の労働力人口の推移を比較した(第2-1-2図(2))。この結果、①2010年を起点とした場合、実際の労働力人口が2011年以降推計値を上回り、②2015年を起点とした場合、コロナ禍での停滞はあるものの、実際の労働力人口が推計値を大きく上回っていることがわかる。例えば、2010年起点の場合、5年後の2015年時点では実際の労働力人口が推計値を180万人程度、2015年起点の場合、同じく5年後の2020年時点では320万人程度上回っている。③2020年を起点とする場合についても、2022年時点では、引き続き、実際の労働力人口が推計値を上回っている。このように、女性の労働参加率の上昇は、これまでの間、人口減少圧力を跳ね返し、労働力人口の増加につながってきた。
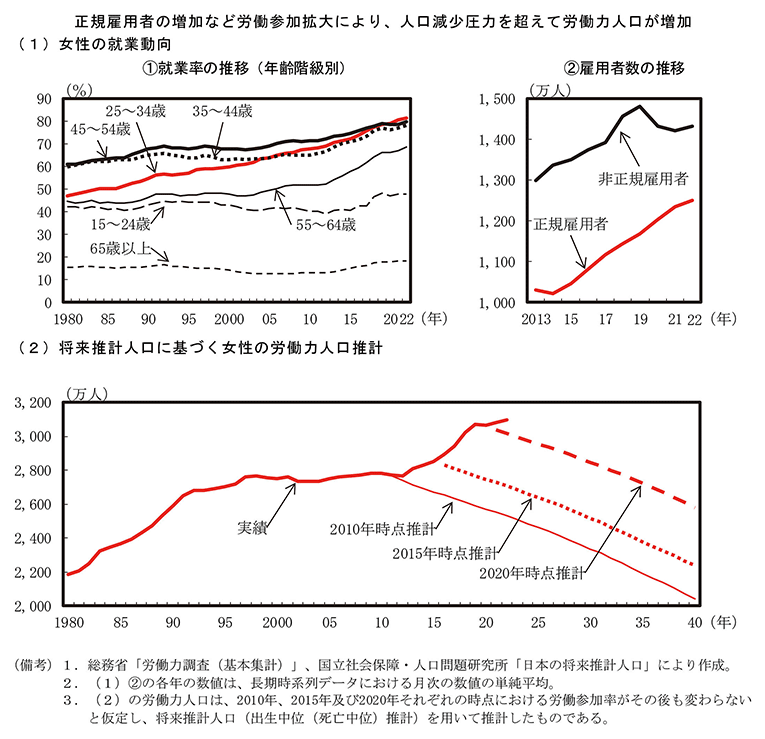
(コロナ禍前まで60~75歳を中心に就業率は上昇してきた)
次に、高齢者の就業動向を確認する。2013年から開始された公的年金の支給開始年齢の引上げや65歳までの継続雇用の義務化を背景に、正規雇用や非正規雇用の労働者を中心に就業者が増えており、2010年以降、60代を中心に就業率は上昇してきた(第2-1-3図(1))。ただし、いわゆる団塊の世代(1947~49年生まれ)が2022年以降、後期高齢者に差し掛かり始める中で、上昇ペースが鈍化している点に留意する必要がある。
上述の女性のケースと同様、男性についても、2010年以降、各将来推計人口の基準時点ごとに人口要因だけで労働力人口がどのように推移するか推計したもの(推計値)と実際の労働力人口の推移を比較した(第2-1-3図(2))。高齢者に比べ、高齢者以外の男性の労働参加率は上昇トレンドにはなく、人口要因のみを考慮した労働力人口の推計値と実際の値のかい離は、主に男性高齢者の就業促進の効果と考えられる。2010年起点の場合、2015年時点で60万人程度、2015年起点の場合、2020年時点で200万人程度、実際の労働力人口が推計値を上回って推移し、2013年以降の高齢者雇用促進策の影響がみてとれる。一方、2020年時点を起点とした場合については、実際の労働力人口と推計値がおおむね同様に推移しており、高齢者就業の拡大ペースが鈍化していることが確認される。

(近年、高齢者の非労働力化は減少し、女性の非労働力から労働力への移行が増加)
次に、過去10年程度における非労働力人口と労働力人口の間のダイナミクスをみるために、尾崎・玄田(2019)を参考に、「労働力調査」における前月の就業状態(労働力人口か非労働力人口か)から当月への就業状態(同)への遷移(フロー)のデータを利用し、労働力人口から非労働力人口へのフロー、非労働力人口から労働力人口へのフローについて、人口ストック要因及び男性、女性(それぞれ15~54歳)、高齢者(55歳以上3)の遷移確率4の要因に分解する(第2-1-4図)。ここで、人口ストック要因は、非労働力から労働力へのフローの場合は、非労働力人口の増減がどの程度影響しているかをみるもので、非労働力人口が減少していれば、それ自体は労働力人口へのフローを小さくするため、フロー総数のマイナス要因となる。ここでは、月々の振れをならすため、12か月移動平均をとり、また、2014年1月を起点とした累積値を示している。
まず、労働力人口から非労働力人口へのフローをみると、コロナ禍前にかけて、人口ストック要因は、労働力人口がこの間増加してきたため押上げ要因となった一方、女性や高齢者の労働力人口から非労働力人口への遷移確率が低下し、押下げ要因となってきた(第2-1-4図(1))。これは、女性の場合、子育て年齢層での労働力率が低下するというM字カーブが解消してきたこと、高齢者の場合、雇用の確保・促進策5がとられ、引退が後ずれしたことが影響しているとみられる。また、コロナ禍を経て、人口ストック要因はおおむね横ばいの中で、女性の遷移確率の押下げ寄与は低い水準に縮小している一方、高齢者の遷移確率の押下げ寄与は、コロナ禍で一時縮小した後、再び高まっているとみられる。これは、2021年4月より70歳までの雇用確保の努力義務が導入された影響の可能性もある。
また、非労働力人口から労働力人口へのフローをみると、人口ストック要因は、非労働力人口の減少継続により、押下げ要因が傾向的に拡大している中で、女性の非労働力人口から労働力人口への遷移確率は、2017年頃以降、押上げ要因となり、コロナ禍で一時縮小した際を除けば、一貫して押上げ幅を拡大してきていることがわかる(第2-1-4図(2))。女性の遷移確率については、この間、女性の労働参加が進み、非労働力状態から新たに就業機会を求めて労働市場に参加する者が増加する傾向が継続してきたことを示している。高齢者の遷移確率については、2016年頃以降、マイナス幅が縮小し、非労働力人口から労働力人口へのフローの押上げに寄与する傾向にあった6。コロナ禍後は、2022年頃から2023年初にかけて押下げ幅が拡大したが、2023年末にかけては再び押下げ幅が縮小傾向に転じている。
このように、①女性については、これまでほぼ一貫して続いてきた非労働力人口から労働力人口への遷移確率の高まりによる労働力人口の押上げ傾向がどの程度続くのか、②高齢者については、ここ最近の労働力人口から非労働力人口への遷移確率の低下による非労働力人口の押下げ傾向(引退の抑制傾向の拡大)がどの程度続くのか等が重要と考えられる7。

(人数ベースで見て、再び労働供給が労働需要に追い付かなくなりつつある)
以上みてきたように、これまでは、人口減少が進む下でも、女性や高齢者の就業拡大を背景に労働供給は一定程度維持されてきたが、足下では企業の人手不足感が深刻化しつつある。第1章でもみたように、日銀短観の雇用判断DIをみると、コロナ禍の期間中一時的に需給が緩んでいたものの、2023年半ば以降は、非製造業を中心にバブル期の既往ピークに近い状況となっている。
人数ベースでのマクロの労働需給として、労働供給(労働力人口)と労働需要(就業者数+未充足求人数)の状況をみると、コロナ禍前においても、人手不足感が高まる中で、労働需要が労働供給に追い付こうとしていた。コロナ禍の始まった2020年以降は、労働供給がおおむね横ばいで推移する中で、労働需要が一旦落ち込み、需給は緩和したが、2022年以降には、未充足求人の増加を背景に、再び、労働需要が労働供給に近づきつつある状況がみられる(第2-1-5図)。
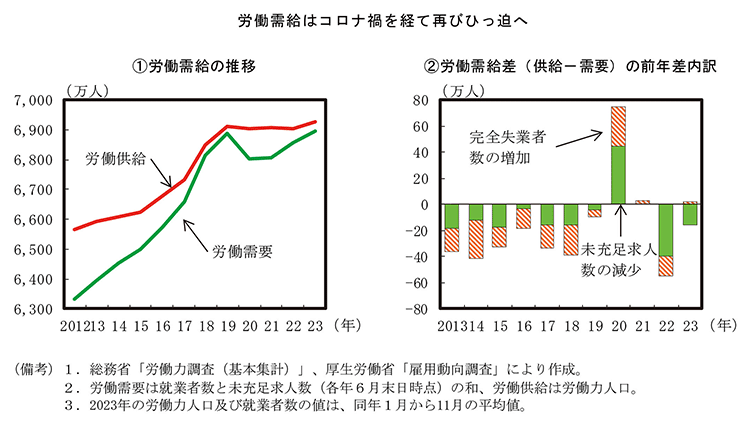
(潜在的な新規就業希望者は少なくとも260万人程度)
このように、人数ベースでみると、労働の需給がマクロレベルで再びひっ迫に向かいつつある中で、労働投入面からの我が国の供給力の下押し要因を緩和していくために更なる労働力活用の余地がないか検討する。
現在、我が国の就業者は約6,800万人いる中で、①完全失業者、すなわち労働力人口ではあるが、就業状態にはなく、求職活動を行っている者は約178万人(うち男性約105万人、女性約74万人)、②現在、非労働力人口であるが就業希望を持っている者は約226万人(うち男性約72万人、女性約155万人)存在する(第2-1-6図(1))。③後者の非労働力の就業希望者のうち、実際に就業可能であるとしている者は、約88万人(うち男性約27万人、女性約61万人)となる。これらの人々の就業希望が実現した場合、①と③の合計(求職活動中及び就業希望がある非労働力人口で就業可能な者)と低めに見積もっても、潜在的に約266万人(うち男性約132万人、女性約135万人)、現在の就業者数に対して約3.9%、15歳以上人口に対して約2.4%の就業者数の拡大余地が存在することになる。このうち①完全失業者の「仕事につけない理由」は、希望する種類・内容の仕事がないといった回答が多い。また、③非労働力人口の就業希望者(かつ実際に働ける者)について「求職活動をしない理由」を確認すると、健康上の理由や出産育児を除くと、勤務時間や賃金等の希望があわない、自分の知識・能力等が要件とあわない等の回答が多い(付図2-1)。これらは、個人へのリ・スキリング支援の充実や効果的なマッチング等によってある程度緩和し得るものではあるが、少子高齢化による人口要因のみによる労働力人口の減少圧力8が男女計で年間約40万人規模あり、2030年以降はさらに強まる中にあっては、就業者数の増加によって将来の人口減少圧力を跳ね返すには一定の限界があることも事実である。

(子どもを持つ非正規雇用の女性を中心に、追加就業希望の実現が課題)
他方、労働時間という観点でみると、仕事時間の追加を希望する就業者は、約410万人(就業者数の約6%)存在する(第2-1-6図(2))。このうち、労働時間の追加が可能とする者は、約280万人(就業者の約4%)存在する。また、追加就業を希望し、かつ可能な人の属性をみると、女性の短時間労働者が半数近くと最も多く、次いで、男性の一般労働者(2割程度)、男性の短時間労働者(2割弱)が続いている。
追加就業を希望しているが実施できない理由を尋ねた調査結果をみると、「社会制度の制約のため」が約1割で、これは、所得税や社会保険料がかからないようにするため、年収を抑えるよう労働時間を調整する年収の壁の問題が一つの背景になっていると考えられる。一方、「勤務制度など会社都合」を背景と答える回答者が約5割、「適した仕事がないため」と答える回答者が約2割おり、労働市場におけるミスマッチが影響していることもわかる(第2-1-6図(3))。後述するように、副業の促進等を通じた労働時間の拡大が、追加就業希望の実現に向けた重要な課題の一つとなる。
次に、就業希望がかなう職場に転職することが理想であるものの、何かしらの阻害要因があるという想定の下、希望するにもかかわらず追加就業ができない要因を探るために、追加就業の希望が多い非正規雇用の女性を対象に、どのような要因が追加就業希望につながっているのかについて回帰分析を行った(第2-1-7図)。具体的には、末子の属性、年収、配偶者の年収、現職に就いた理由などを説明変数とした。
結果をみると、まず、末子の属性については、子どもがいる場合はいない場合に比べ追加就業希望確率が有意に高い。また、その程度は子どもが小学生になるまで上昇し、中学生になるとやや低下している。これは、子どもを持つ女性非正規雇用者は子どもの成長に伴いより長く働くことを希望する一方、子育て支援は進みつつあるものの、子どもがいない女性に比べて時間制約が多い中で希望に沿った就職先が見つかりにくい可能性を示唆している。また、106万円という年収の壁未満の労働時間で働く女性は、追加就業の希望を持つ確率が有意に高く、制度による障壁がなくなれば、労働時間の増加を通じて労働供給が増加する可能性を示している。また、現職に就いた理由と追加就業の希望との関係をみると、正規の仕事を求めているもののやむを得ず非正規の職に就いている人や、家計補助、家事育児等を理由に現職に就いている人において、より追加就業を希望していることがわかる。後述するように、末子の年齢が上がるにつれて就業率は上昇する一方、正規雇用は減少し、非正規雇用が増加する傾向がある。上述のとおり、非正規雇用の女性は、正規の仕事がないから現職に就いていると答える人ほど追加就業を希望していることを併せて考えると、育児を背景に一度離職した女性が再度、正規雇用でキャリアを築くことが難しいことを示唆している。なお、「年収の壁」に関しては本章第2節で詳細に議論することとする。

(女性の出産・育児を背景とした正規雇用率の低下への対応の必要性)
女性の就業は拡大傾向にあるものの、前掲第2-1-6図で確認したとおり、追加就業を希望する非正規の女性は多くみられる。年齢階級別の就業率をみると、これまでの女性就業の後押しなどもあり、女性の就業率は10年前より全ての年代で上昇しており、出産や育児をしている女性の多い30代の就業率の落ち込みも以前に比べると、小さくなっている(第2-1-8図(1))。実際、6歳未満の未就学児を持つ女性の就業率は2002年の36%から2022年に70%まで高まり、6歳未満の子がいない女性の78%より低い状態は変わっていないものの、その差は10年前の23%ポイントから8%ポイントまで縮小している(第2-1-8図(2))。こうしたいわゆるM字カーブの解消傾向に対し、女性の年齢階級別にみた正規雇用率の動向をみると、就業率と同様に幅広い年齢層で10年前と比べると上昇しているものの、30代を境に大きく正規雇用率が低下する、いわゆるL字カーブの構造は変わっていない(第2-1-8図(3))。

では、女性の正規雇用から非正規雇用や離職への転換タイミングはどこで発生しているのだろうか。まず、第1子出産前に正規雇用者であった女性の出産後にかけての就業形態の変化をみると、1990年代までは出産を機に無業・学生(主に専業主婦と考えられる)になるケースが多かった(第2-1-9図)が、1991年の育児・介護休業法の成立もあって、育児休業制度を利用し、就業を継続する人が徐々に増加してきた。この結果、2010年代後半には、出産後に就業を継続する女性は8割を超えるようになっただけでなく、就業を継続した人の9割以上が出産後も正規雇用となっており、出産時の就業の壁は小さくなりつつあることがわかる。次に、子育てのステージ別の就業形態の変化を確認する(第2-1-10図)。子どもの年齢別に女性の就業形態をみると、本来負担が重いと考えられる末子が0歳時点での正規雇用者割合は35%と最も高く、8~11歳辺りにかけて20%前後まで低下しており、育児休業制度の活用もあり幼児期には正規雇用に留まる者が一定数存在しているものの、末子が成長し休業期間が終了する中、その他の就業形態の割合が高まっている。育児休業から復帰した女性が、保育園等に子どもを通わせながらの子育てと正規雇用との両立のハードルや、いわゆる「小1の壁9」による子育てと仕事の両立の困難さ等を背景に、正規雇用から非正規雇用に転換した可能性があるとみられる。また、正規・非正規等を合計した就業率は、末子が1歳の時点で最も低く、末子が小学校高学年になるまで上昇するが、この間、正規雇用率は低下しており、子育ての負担が軽くなり再度就業する人の多くが非正規雇用を選択しているとみられる。さらに、正規雇用者割合は末子の年齢が18歳になってもさほど上昇せずに推移している。子育てステージを経るにつれて正規雇用から非正規雇用に振り替わっていることに加え、再就業する女性の多くが非正規雇用となっていることから、正規雇用者比率は30代を境に急激に低下し、40、50代でも回復していないと考えられる。前掲第2-1-7図でみたように、非正規雇用者で現職に就いている背景に正規の仕事がないからと答える女性も多い。2022年の「労働力調査」では女性の不本意非正規雇用労働者が107万人いるが、子育てを理由に一度離職した女性の中には再就職の際に不本意に非正規雇用に就いている者も相応にいる可能性がある。
女性の就業率は以前に比べてある程度の水準まで上昇した中で、今後は、正規雇用を希望するが、意図せず非正規雇用に就いている女性への対応を強化していく必要がある。正規雇用を継続するための子育て支援に加え、子育てが一段落して、正規雇用への復職を希望する女性に対するリ・スキリングの支援などにより、一定年齢以上の女性の正規雇用を広げていく施策を推進することが、追加就業希望の実現による労働供給の拡大のために重要である。


(高齢者の就業意欲を引き出す取組が重要)
次に、高齢者の就業拡大余地について検討する。実際の就業率と日常生活の機能制限状況や健康状態を併せてみると、高齢者のうち65~74歳では健康な人は8~9割程度で、就業率は男性で約40~60%、女性で約25~40%であることを考えると、いわば健康人口対比でみた就業率は低いといえる(第2-1-11図(1))。
これに対し、就業意欲と就業率の関係を年齢階層別にみると、男性について、両者の相関は高く、水準としても就業意欲がある者の割合と就業率との差は大きくない。男性高齢者の場合、就業するかどうかの決定には、健康状態よりも就業意欲の方が重要であると考えられる(第2-1-11図(2))。一方、女性は、就労意欲と実際の就業率の相関はみられるものの、就業意欲がある者の割合が就業率を20~25%程度上回り、かい離がみられる。介護や家事のため就業できないといった事情を持つ者は、65~74歳の男性で1割以下なのに対し女性で2~3割程度と高いことから、就業率と就業意欲のかい離はこうした事情が背景にある可能性がある(第2-1-11図(3))。
健康な高齢者は、65~74歳のみならず75歳以上でも男女共に多く、後述するように社会保障制度において高齢者の就業意欲を阻害しない仕組みを構築していくこと等により、就業意欲そのものを引き上げていくことが65歳以上の就業率向上につながると考えられる。加えて、女性については、介護や家事のために就業していない割合が男性に比べて高く、より若い世代における子育て・家事負担と同様に、高齢者においても女性に負担が偏っている可能性にも留意する必要がある。

2 新しい働き方の広がりと経済的な影響
ここでは、労働供給の拡大余地、とりわけ、前項の追加就業希望の実現という観点から、近年増加傾向にある副業(雇用者のみならず、個人事業主に当たるフリーランスによる副業を含む)の動向について、労働供給や所得の向上といった面での経済的な影響を整理する。また、新たな働き方として、コロナ禍で急速に普及が進んだテレワークは、通勤時間の縮減から、余裕時間を活用し副業につなげられるという観点も重要であり、その現状や経済活動への影響について確認する。
(近年の副業実施者の増加は高齢者がけん引しているが、広がりもみられる)
副業実施者数の長期的な推移を「就業構造基本調査」から確認すると、1990年代から2000年代初頭にかけて副業実施者数は減少傾向で推移し、2000年代は横ばいであったが、2017年以降は増加傾向に転じている(第2-1-12図(1))。特に、直近の2022年にかけての5年間では、268万人から332万人へと64万人増加し、副業実施率も4.0%から5.0%に1%ポイント増加している。ただし、「就業構造基本調査」では、調査対象者に対して副業の有無のみを調査しているため、複数の副業を掛け持つ動きが広がっている場合には、延べ副業者数は更に増加している可能性もある。
また、年齢階級別にみると、2012年以降の過去10年においては、65歳以上の高齢層の増加が全体の副業実施者数の増加に最も大きく寄与していることがわかる(第2-1-12図(2))。65歳以上の高齢層は定年や再雇用を通じた職責の変化による本業からの制約の緩和や、勤務時間短縮による就労余力増加が副業の実施を可能したと考えられる。こうした65歳以上の高齢層だけでなく、2012年から2017年、さらに2022年にかけて、65歳未満の幅広い年齢層でも副業実施者数の増加がみられる。2017年から2022年にかけての副業実施者数の64万人の増加について、年齢階級別に、有業者数要因(就業者数の変化)と副業実施率要因(副業実施率の変化)に分けると、50歳以上では有業者数要因、副業実施率要因が共に副業実施者数の増加につながっている一方、40代以下の年齢層では、人口減少により有業者数要因がマイナスに寄与する中で、副業実施率要因が副業実施者数の増加に大きく寄与していることがわかる(第2-1-12図(3)、(4))。
次に、本業における従業上の地位別に副業実施者数をみると、女性の非正規雇用者が83万人と最も多く、次いで、男性の正規雇用者が63万人となっている(第2-1-13図(1))。本業が非正規雇用の女性について、副業における従業上の地位をみると、非正規雇用が48万人(約6割)と多くを占めている(第2-1-13図(2))。本業の産業別にみると、医療・福祉、卸・小売、宿泊・飲食で半数超を占め、副業の産業としては、本業が医療・福祉の場合は、同じ医療・福祉のほか、教育・学習支援等が、本業が卸・小売の場合は、同じ卸・小売のほか、宿泊・飲食が、本業が宿泊・飲食の場合は、同じ宿泊・飲食のほか、卸・小売が多いことがわかる(付図2-2)。医療・福祉を本業とする場合は、その専門性を活かし、病院の掛け持ち等を行っている可能性がうかがわれるほか、教育機関での非常勤の講師等を行っている可能性がある。
一方、男性の中で構成割合の高い本業が正規雇用の男性について、副業における従業上の地位をみると、フリーランスを含む自営業主が22万人(約35%)、次いで非正規雇用が20万人(約32%)となっている(第2-1-13図(3))。前者について、本業の産業別にみると、情報通信、製造業、卸・小売業の順で多く、副業の産業としては、本業が情報通信の場合、同じ情報通信、次いで学術研究・専門・技術サービス等が、本業が製造業の場合は、農林業が、本業が卸・小売の場合は、同じ卸・小売のほか、農林業が多いことがわかる(付図2-2)。本業が情報通信の場合は、専門性を活かし、副業ではウェブ広告や技術系の分野等のフリーランスで活動する者が多い一方、本業が製造業等の場合は、副業として農業に従事する兼業農家が相応に存在することがわかる。また、本業が正規雇用で副業が非正規雇用の場合は、本業の産業は、医療・福祉、教育・学習支援で多く、それぞれ副業の産業としては同じ医療・福祉、教育・学習支援の割合が大きく、やはり専門性を活かした病院や教育機関での掛け持ちが多いとみられる10。


(主たる勤務先の理解などが副業拡大の壁となっている)
ここで、副業実施による労働供給拡大余地の可能性を探るために、正規雇用で勤務している労働者について、副業の実施意向があるものの、副業を実施していない人について、副業実施の阻害要因がどこにあるかをみると、勤務先からの制約を挙げる回答者の割合が突出して高いことが確認される(第2-1-14図(1))。副業実施に際して勤務先からの制約にはどういった背景があるか検討する。回答者の属性をみると、金融・保険など一般的に就業規則が厳しいと考えられる業種に勤めている雇用者のほか、従業員規模が大きい会社に勤めている人ほど、本業から副業の制約を受けていると回答している(第2-1-14図(2))。一方で、農林漁業や建設業等の従事者は本業からの制約を受けている雇用者は少ない。1990年代以降、これらの産業の従事者が減少していたことは、前述のとおり、この間に副業実施者数が減少していた動きと整合的である。副業実施による労働時間の追加希望を実現するためには、大企業を中心に雇用者の副業可能な範囲を広げることが重要であり、2018年に厚生労働省が「モデル就業規則」を改訂し、「許可なく他の会社などの業務に従事しないこと」の文言を削除したが、多くの大企業ではこうした就業規則や運用が残っているとみられる。労働者の健康への配慮と利益相反行為の禁止等は引き続き留意しつつ、副業による労働時間と所得の増加の希望を阻害しないためには、行政側の対応として、就業規則において副業の禁止規定を設けることを原則取りやめることを企業に促す、あるいは、本業の業務時間外の就労について、労働者側に職業選択の自由があることを明示していくこともあり得るだろう。

(新しい働き方を通じた労働投入、所得増加の可能性)
副業実施による労働供給への影響について確認したい。正規雇用者のうち、副業実施者はそうでない人に比べ、就業時間が8~13時間程度有意に長い(第2-1-15図)。すき間時間などを効果的に活用できれば、副業を通じた週当たりの労働時間の押上げによる所得増加が見込むことができる。第1項でみてきたとおり、人数ベースでの高齢者や女性の就業者増加の限界が近づきつつある中にあっては、希望する人に対して、副業など多様な働き方を通じた労働時間の追加が可能となる環境整備が重要であり、これにより、少子高齢化の中でマンアワーベースでの労働供給を底上げし、家計所得の向上につながることが期待される。
さらに、マクロの雇用者報酬の主たる内訳である賃金・俸給へのインパクトという観点をみてみる。国民経済計算における賃金・俸給は、産業別に、副業を加味した仕事数という意味での雇用者数と、事業所統計から得られる仕事当たりの賃金の積を求め、その総和として推計されている。このうち、副業については、現行の2015年基準の国民経済計算では、2017年の「就業構造基本調査」に基づいて副業者比率を使用している。この間、2022年に副業の雇用者数は5年間で154万人から195万人へと41万人程度増加しており、就業者に対する副業の雇用者数の割合も0.5%ポイント程度高まっているため、マクロの賃金・俸給は、この5年間で現行よりも0.5%程度大きくなっている可能性がある。賃金・俸給を人数ベースの雇用者数で割った一人当たりの賃金・俸給という意味でも同様に、実態は、現行よりも0.5%程度は高い水準にある可能性がある。さらに、上述のとおり、「就業構造基本調査」では、一人の就業者に対して一つの副業のみ把握しているが、実際には、複数の副業を実施している場合も少なからずあると考えられる。実際、リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査」によると、副業実施者のうち役員で3割、非正規雇用者では25%、正規雇用者では2割超で2つ以上の副業を実施しているなど、無視できない数で複数副業者がいる(第2-1-16図)。雇用者の所得をより的確に捉える観点から、副業実施者に関するタイムリーで、実態をより正確に捕捉する統計の整備も重要な課題と考えられる。


(テレワークの定着により出勤率は1割程度減少)
次に、コロナ禍を機に、新しい働き方として広がったテレワークの実態とその影響について概観する。コロナ禍以降、2020年から2021年にかけ、雇用者のテレワークの実施回数は大きく増加した(第2-1-17図(1))。その後、テレワーク実施回数は2022年に減少したが、コロナ禍前よりは高い水準にある。また、2023年に入って以降は、東京都内の企業ベースの実施率でしか確認できないが、緩やかな減少傾向にはあるものの、コロナ禍前よりも高い水準で下げ止まりつつあり、テレワークがコロナ禍を経て一定程度定着していることがわかる(第2-1-17図(2))。2022年における全国でのテレワーク実施状況を出勤日ベースで加重平均すると、1週間(5営業日)当たり0.44回の実施となっており、全国的に出社率を1割程度引き下げているとみることができる。実際、JRと民営鉄道の鉄道輸送人員のうち、定期輸送をみると、コロナ禍以前を1割から2割程度下回ったままとなっており、テレワーク定着の影響がうかがわれる(第2-1-17図(3))。

(テレワークは一部の対面型サービス消費の減少と代替分野の活性化につながっている)
次に、テレワークの定着が経済的な影響を与えているかみてみる。形態別の実質国内家計最終消費支出をみると、サービスのみがコロナ禍前を大きく下回って推移している(付図2-3(1))。この背景には、テレワークの浸透を背景とした外出機会の減少により、出社によって発生する外食などの消費機会が失われたことがあるとみられる。実際、人流とサービス消費の動向をみると、強い相関がある(付図2-3(2))。外出と関連が高いと考えられる一般外食の客数はコロナ禍前の水準を回復しておらず、また、半耐久財等の財に含まれる被服・履物の実質消費も同様にコロナ禍前の水準を下回っており、テレワークの浸透を背景に、消費の一部が下押しされている可能性がある(第2-1-18図(1))。
もっとも、テレワークの進展により、一部の消費への需要が失われたと結論づけるのは早計と考えられる。財関係のEC消費は、コロナ禍による外出自粛が徐々に剥落する下、コロナ禍前対比で2倍弱の水準で推移している一方、出前(デリバリー)の消費の動向をみると、新型コロナウイルス感染症の5類移行後も、コロナ禍前対比で3倍以上という高い水準が維持され、振れはあるものの引き続き増加傾向で推移している(第2-1-18図(2))。こうしたことから、コロナ禍を通じて減少したと考えられる外食などの一部消費は別の形態の消費支出に振り替わっている可能性がある。

(テレワークによるすき間時間拡大と副業促進の可能性)
テレワークは外出機会減少によるサービス消費の減少など経済的にはマイナスの影響が指摘されることもある一方で、通勤時間減少による労働者の余裕時間の拡大に寄与する。実際、東京圏など通勤時間の長い都市部を中心に、テレワークが浸透しており、こうした地域を中心に通勤時間の縮減効果は高いとみられる(第2-1-19図)。コラム2-1でも後述するとおり、既婚女性の有業率は通勤時間と逆相関の関係があると指摘されることから、家庭の総就労時間の選択は通勤時間も含めて検討されているとみられる。テレワークの浸透は、通勤時間も含めた実質的な家庭の本業での総就労時間の減少につながり、余裕時間における副業実施の拡大を通じて、労働投入量の増加につながる可能性もある。
また、東京都や周辺都市圏では、他の地域に比べてテレワーク実施率が高いが、これら地域は、他の地域と比べて第3次産業のウエイトが大きく、テレワークとの親和性が高い業種が多いことも影響していると考えられる。一方、テレワークの実施状況は、そうした産業構造の違い以上に差がある可能性も考えられることから、産業構造をコントロールした上で、他の道府県は東京都対比でどの程度テレワークの余地があるのかを確認した。
推計結果をみると、多くの道府県において、産業構造の差では説明できない水準で、東京都とのテレワークの実施率の差があることがわかる(第2-1-20図)。すなわち、首都圏などの都市圏以外の地方部では、産業構造の差では説明できないレベルでテレワークの実施率が低くなっており、裏を返せば、これらの地域におけるテレワークの潜在的な押上げ余地は、実施率ベースで3%ポイントから10%ポイント程度あると示唆される。
こうした結果を踏まえると、地方部でのテレワークの活用余地は高く、子育て世代の就労促進、副業の実施拡大など新しい柔軟な働き方を実施するためにもテレワークを地方部にも広げていくことが重要である。また、各地域の職業選択時の訴求力を高める観点からも可能な範囲でテレワーク実施率を高めることは、若年層の都市部への人口流出を緩和する要因となる可能性がある。


コラム2-1 子育て世帯の住居選択について
理想の人数の子どもを持たない理由として住宅の狭さを挙げる人が2015年の調査の18.0%から2021年の調査では21.4%に増加している11。ここでは、首都圏など大都市圏を中心に、2020年以降拍車がかかっている住宅価格の上昇が若年世帯の住居選択にどのような影響をもたらすのかについてみていく。
まず、直近5年の人口移動の動向を確認する。20歳前後の進学・就職を機に東京都に流入する人口はコロナ禍期間において一時的に減少したものの、直近ではコロナ禍前の2018、2019年と同水準まで回復している(コラム2-1-1図)。他方で、子育て世帯に当たる25~44歳とその子どもと考えられる0~14歳は、東京都から東京都を除く首都圏への人口流出が増加する傾向もみられる。さらに、東京都においては、単身向けの賃貸価格にあまり変化がない一方で、ファミリー向けの賃貸やマンション価格が上昇を続けており、東京都内の住宅価格が上昇し、子育て世代が住宅価格や賃料の低い首都圏近郊へ向かっていることを示唆している12。

次に、住宅取得能力指数についてみると、低下傾向が続いており、収入の伸び幅を上回る住宅価格の上昇が確認できる。最近の住宅取得能力指数の低下に対して、既婚世帯がどのように対応しているかを確認するため、住宅能力指数の変化を、購入住居の質(利便性、広さなど)、購入者の年収倍率(価格に対する年収比率)、購入層の年収の3つの要因に分解する13。まず、負担変化要因は小幅にプラス要因に寄与していることから、年収対比で借入れを増やすといった行動はさほどみられていないと考えられる。一方、取得層変化要因は、住宅取得能力指数の低下に寄与しており、住宅の購入がこれまでよりも年収の高い層に限られるようになっていることを示唆している。また、質変化要因の押下げ幅が拡大しており、質(利便性や広さ)を犠牲することで物件を購入している可能性があることがわかる(コラム2-1-2図)。この傾向は子どものいる既婚世帯に限ってみても共通しており、前述した東京都から東京都以外の首都圏への子育て世代の人口流出は、住宅価格が上昇する環境において、購入に際し以前より高い年収が必要になる中で、利便性や広さといった住宅の質を妥協せざるを得ない結果として発生している可能性がある。実際、新築マンション契約者の平均占有面積は低下しているほか、東京23区内の物件の占める割合は低下傾向で推移している(コラム2-1-3図)。


住宅の利便性に関して、通勤時間と20代後半から40代前半までの既婚女性の有業率の関係をみると、通勤時間が15分長いと、有業率は5.0%ポイント低下するという研究14もあり、子育てなどの時間制約が厳しい子育て世帯では、郊外物件の取得に伴う平均通勤時間の増加は女性の就業率押下げに影響する可能性がある。また、近年、理想の人数の子ども数を持たない理由の一つに家の広さを挙げる人も一定数いる15中で、郊外物件を取得せず、希望よりも狭い都心の住宅を取得せざるを得なかった世帯は2人目、3人目の子どもを諦める可能性もある。
子育て世帯が希望する質の住宅を購入できない場合、中長期的に就業率や出生率の低下につながる可能性がある。これに対する政策対応として、更なる価格上昇につながる補助金や各種控除よりは、子育て世帯が安く借りることができる公的住宅の供給拡大といった供給面の施策を着実に進めることで、子育て世帯が希望の場所に住めるようにする必要がある。こうした施策の積み重ねが女性の就業率、労働時間の向上にもつながるものと考えられる。

