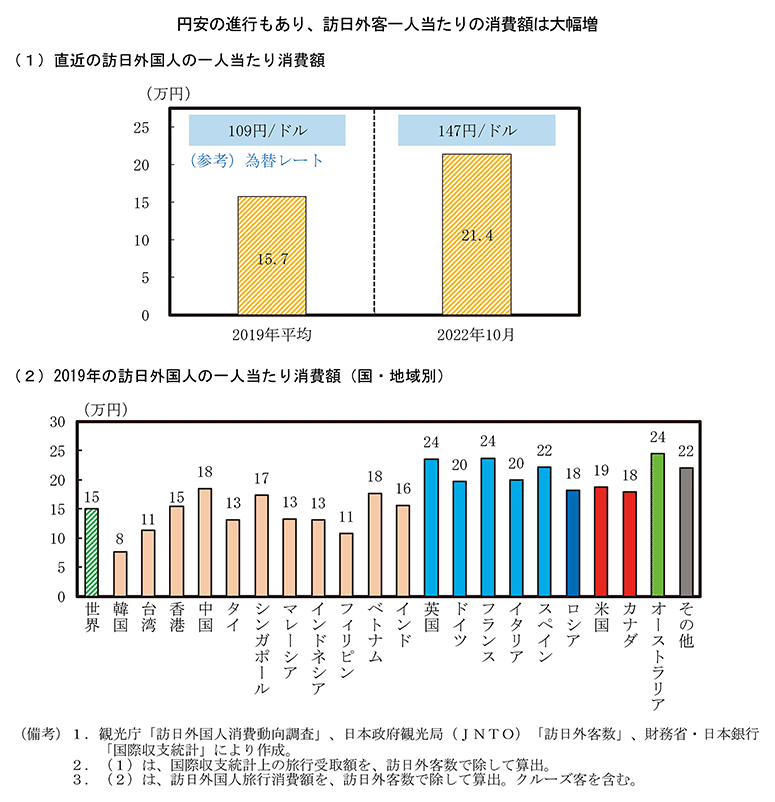第3章 企業部門の動向と海外で稼ぐ力(第3節)
第3節 輸出を通じた海外で稼ぐ力の強化
前節では、我が国の対外経済構造についてみてきたが、国内では少子高齢化と人口減少が進展する中、成長する海外市場の需要を取り込んでいくことは、我が国経済にとって今後も重要な取組であろう。その際、我が国が長年にわたり比較優位を持つ機械類等の競争力の維持、対外資産の収益性確保、海外から我が国への直接投資の呼び込みなど、様々な面での取組が考えられるが、以下では、現状において海外需要の取り込みが十分ではなく、今後の成長余地が大きいと考えられる分野の可能性を検討しよう。具体的には、中小企業及び農林水産物の輸出拡大、さらにはコロナ禍で失われたインバウンドの回復について考えていく。
1 中小企業の輸出動向
(中小企業の輸出は伸びておらず、大企業に比べ海外で稼ぐ力は限定的)
まず、中小企業1の我が国経済における立ち位置について確認する。我が国の中小企業の数は357.8万者、大企業を含めた全企業等に占める割合は99.7%であり、従業員数は同68.8%、付加価値額は同52.9%と、我が国経済にとって重要な役割を担う主体である(第3-3-1図)。
一方で、中小企業の海外で稼ぐ力は非常に限定的である。海外からの所得受取については、前節でみたとおり、本社が中小企業である海外現地法人が生み出す売上高と経常利益は、それぞれ全体の2.7%と2.4%に過ぎず、したがって、現地法人から得られる所得の還流も大中堅企業に比べてごく僅かと考えられる。では、日本から海外への財・サービスの直接的な販売、すなわち輸出の動向はどうであろうか。以下では、経済産業省「企業活動基本調査」の調査票情報を独自に集計した結果を基に、中小企業の輸出の実態を確認していく2。
過去10年間における中小企業に占める輸出企業割合をみると、2011年度には19.7%だったものが2017年度には21.7%へと上昇したが、2020年度には21.2%と僅かながら低下し、過去10年間を通じた上昇は1.5%ポイントとなっている。一方、この間、大企業の輸出企業割合は、2011年度には25.1%だったものが2020年度には28.3%へと、10年間で3.2%ポイントの上昇となっている(第3-3-2図(1))。
また、大企業と中小企業との比較という観点から、我が国輸出に占める中小企業のシェアを確認すると、輸出企業数では中小企業が約7割、大企業が約3割であるのに対し、輸出額では中小企業の占めるシェアは約7%に過ぎない(第3-3-2図(2))。海外からの所得受取と同様、輸出面でみても、海外で稼ぐ力は大企業に偏在している。
では、こうした状況が現在の立ち位置でありながらも、過去10年間で中小企業は輸出を増加させてきただろうか。中小企業の輸出額は、2012年度以降2016年度までは拡大を続け、その後は減少3しているものの、過去10年間を通じておおむね5兆円程度で推移しており、大きな変化はみられない。売上高に対する輸出額の比率もおおむね同じ動きとなっており、2011年度には3.1%だったものが2020年度には3.3%とおおむね横ばいの動きとなっている(第3-3-2図(3))。これに対し、大企業では、世界経済の減速と新型コロナの影響を受けて2019年度と2020年度に大きく減少しているが、その期間を除けば、2011年度から2018年度にかけて輸出額を13兆円増加させており、売上高輸出比率も2011年度の12.2%から2018年度の13.3%へと1%ポイント程度上昇している(第3-3-2図(4))。このように、大企業と比べ、中小企業は輸出企業割合・輸出額共に過去10年間で増加させることができていない。
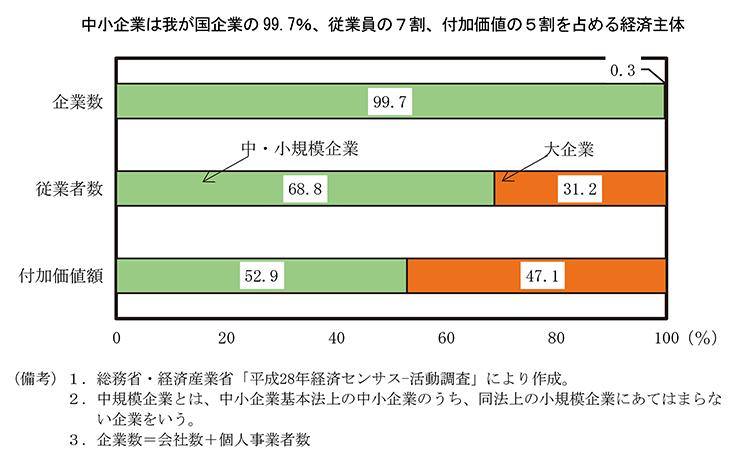
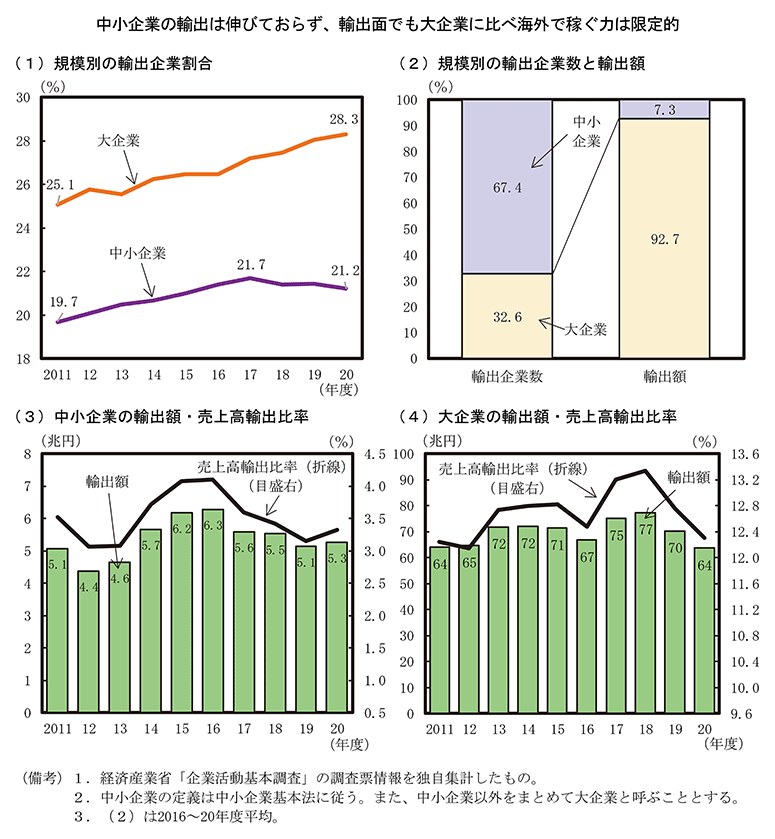
(輸出企業の稼ぐ力は、輸出を行っていない企業に比べて強い)
次に、輸出を行っている企業と行っていない企業との間に、売上や利益、生産性などの面でどのような差があるのかを、先と同じく企業活動基本調査の調査票情報を独自に集計した結果を基に確認しよう。
輸出を行っている企業の過去5年間平均の1社当たり売上額は、輸出を行っていない企業に比べて、大企業では全産業ベースで約2.6倍、製造業では約1.6倍、中小企業では全産業・製造業ともに約1.4倍と、いずれも非輸出企業よりも大きくなっている。内訳をみると、輸出を除いた分の売上高で、大企業では全産業ベースで約2倍、製造業で約1.1倍、中小企業では全産業・製造業ともに約1.2倍であり、国内売上高でも輸出を行っている企業の方が輸出を行っていない企業を上回っている。これに海外需要を取り込んだ結果である輸出分の売上が上乗せされており、その規模は、大企業では全産業ベースで輸出を行っていない企業の売上高の約7割、製造業では約5割、中小企業では全産業・製造業いずれも約2割となっている。なお、大企業で非製造業を含む全産業ベースの値が特に大きくなっているのは、海外展開が著しい大手総合商社の影響が強く出ているものと考えられる(第3-3-3図(1))。
同様に、経常利益についても確認してみよう。経常利益は、企業が通常行っている事業全体から経常的に得た利益のことであり、企業の稼ぐ力を端的に示している。輸出を行っている企業の1社当たりの経常利益は、輸出を行っていない企業対比で、大企業では全産業ベースで約3.5倍、製造業で約2.2倍、中小企業では全産業ベースで約1.9倍、製造業で約2.1倍となっており、売上高以上に輸出企業と輸出を行っていない企業の稼ぐ力に差があることがわかる(第3-3-3図(2))。
また、輸出企業の付加価値生産性についても確認すると、輸出を行っていない企業に比べ、大企業では全産業ベースで約1.4倍、製造業で約1.1倍、中小企業では全産業・製造業共に約1.2倍と、いずれも輸出企業の方が高い生産性を有しており、売上と経常利益と同様の結果である(第3-3-3図(3))。
高い生産性を有するなど稼ぐ力のある企業が輸出を行っており、また輸出を通じて更に稼ぐ力を高めているといった面もあるものと考えられる4が、輸出企業と非輸出企業との間で研究開発実施率に差がみられることは、両者の稼ぐ力の差の背景の一つであろう。全産業ベースでは、輸出を行っていない企業のうち研究開発投資を行っている企業は約2割に過ぎないのに対し、輸出企業では大企業で約7割、中小企業で約6割と大きな差が生まれている。製造業でも同様に、輸出を行っていない企業の研究開発実施企業の割合は大企業で約7割、中小企業で約3割であるのに対し、輸出企業では大企業で96%とほぼすべて、中小企業で約7割となっている。輸出企業においては、海外企業との競争環境の中で自社の製品に競争力をもたせるための研究開発が積極的に行われており、こうした取組の結果が、売上高や経常利益、付加価値生産性の高さにもつながっている可能性がうかがえる(第3-3-3図(4))。
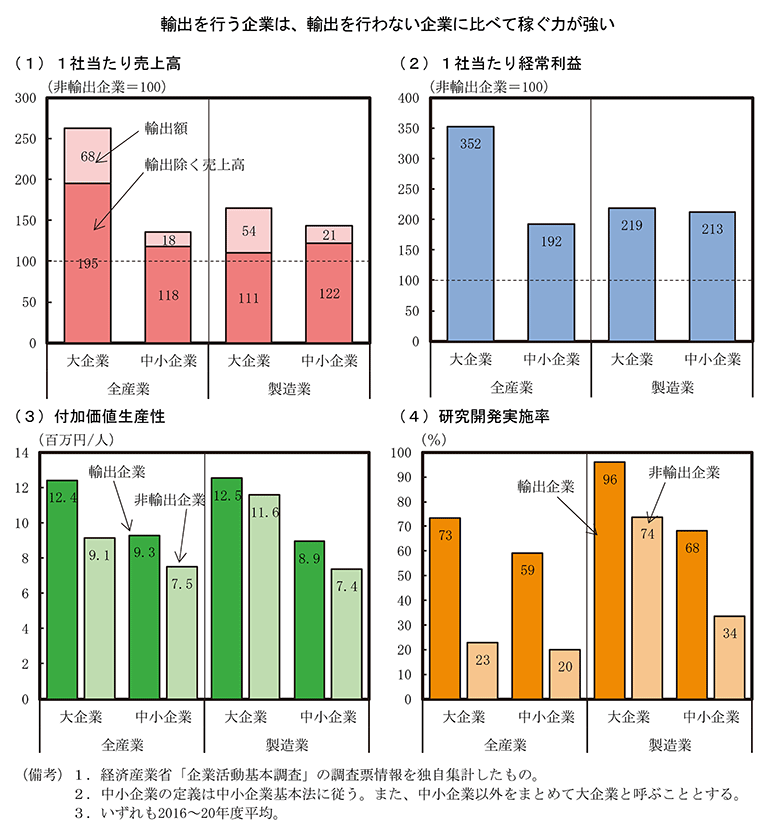
(中小企業の輸出にはマーケティングや人材面での課題)
このように、輸出企業の稼ぐ力は輸出を行っていない企業に比べて企業規模を問わず強いことから、輸出は中小企業にとっても稼ぐ力を高める有力な方法の一つであると考えられる。一方で、大企業と対照的に、中小企業では輸出企業の割合が高まらず、輸出額も増加していない。ここで生まれる素朴な疑問は、なぜ中小企業は輸出を伸ばすことができていないのか、ということであろう。
民間調査会社によるアンケート調査によると、海外展開をしていない中小企業が最も強く感じている課題として挙げている項目(単一回答)は、「販売先の確保」が最も多く、次いで「現地の市場動向やニーズの調査」、「海外展開を主導する人材の確保」、「信頼できる提携先・アドバイザーの確保」であり、これらの項目で6割以上を占める結果となっている。大企業に比べて人員や資本力等が限られる中で、販路の開拓や現地の動向調査といったマーケティングに十分に対応できず、また、言語の差もある中で海外展開を行うに当たっての人材やアドバイザーを確保することが難しいことが大きなハードルになっている(第3-3-4図)。
こうしたマーケティングや人材といった課題に対応するものとして機能するのが海外事業所等の海外拠点である。実際、JETROが実施したアンケート調査によると、大企業・中小企業ともに海外拠点の機能として最も多く挙げられているのは「販売拠点」、「生産拠点」としての機能である(第3-3-5図(1))。ここで、海外事業所の保有有無と輸出企業の割合についての相関を見てみよう。第3-3-5図(2)は、企業規模及び業種別に、縦軸に海外事業所を保有している企業群の輸出割合を、横軸に海外事業所を保有していない企業群の輸出割合をとったものである。交点は45度線より上方に偏在しており、海外事業所を保有している企業の方が、保有していない企業よりも輸出を行う割合が高くなっている。特に、大企業と比べて取引先企業を通じたネットワークや人材面で乏しい中、中小企業は輸出を行う上での海外拠点の必要性が相対的に高い可能性がある。言い換えれば、海外事業所を設けて人材等を配置する余力がないと輸出のハードルが高い状況ともいえ、こうしたハードルの高さが、中小企業における輸出の伸び悩みの要因となっている可能性がある。
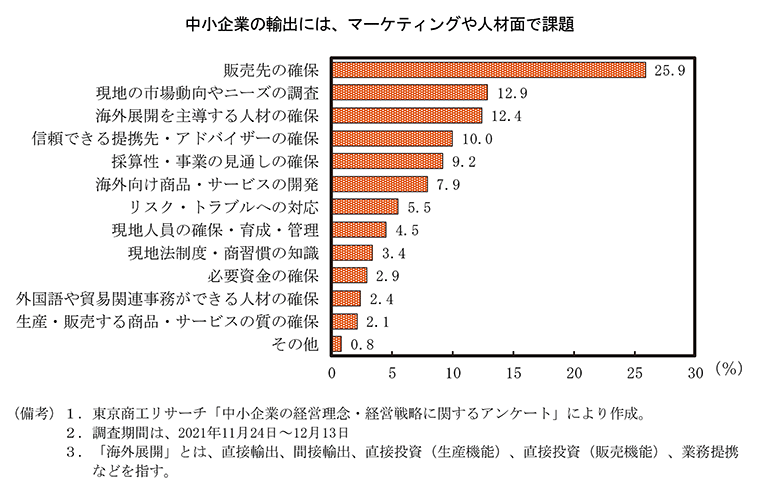
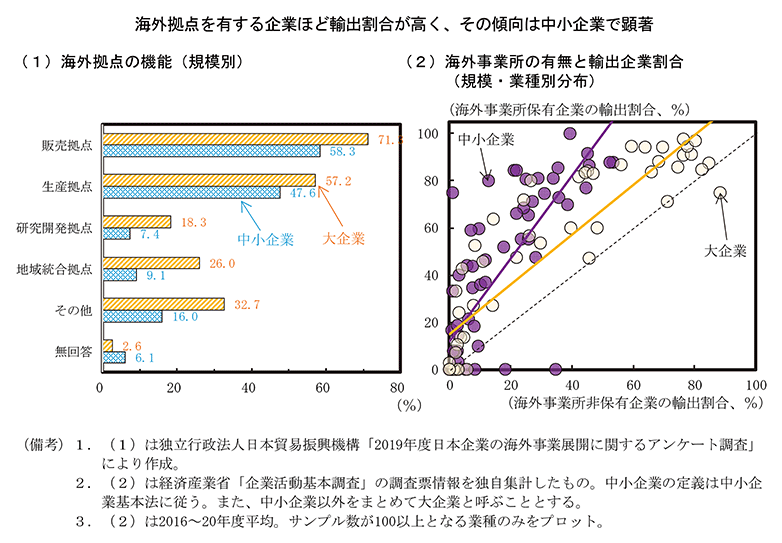
(ECを利用した海外展開の機運は中小企業で高まり)
こうした中において、海外に事業所を設けずとも輸出を行う手段の一つとして、近年はEC(電子商取引)の活用機運が高まっている。JETROが実施したアンケート調査によると、ECを利用したことがあると回答した企業は、大企業では2021年度に増加したものの、2016年度から2020年度まではおおむね横ばいであったのに対し、中小企業では一貫して増加を続けている。また、ECを利用したことがある又は利用を検討している企業のうち、今後ECの利用を拡大すると回答した企業も特に中小企業において増加している(第3-3-6図(1))。
また、同調査では、海外販売へのECの利用状況についても調査している。海外への販売を行っていると回答した企業の割合は、大企業・中小企業ともに増加を続けているが、その手段として越境ECを挙げている企業は中小企業において高い割合となっている。大企業においても越境ECの利用は拡大しているが、割合としては海外拠点での販売が依然として大きい。逆に、中小企業では、資金や人材面でのハードルにより、海外拠点での販売割合は低水準でおおむね横ばいとなっている(第3-3-6図(2))。
このように、ICT化の進展に伴い、海外拠点に拠らずとも輸出を行うことができる環境は整備されてきており、それを利用して海外展開を行う機運が特に中小企業において高まっている。また、SNSの発展等も、自社製品の海外向けプロモーションの費用を著しく低下させているものと考えられ、こうした手段を最大限活用した輸出促進が求められるだろう。
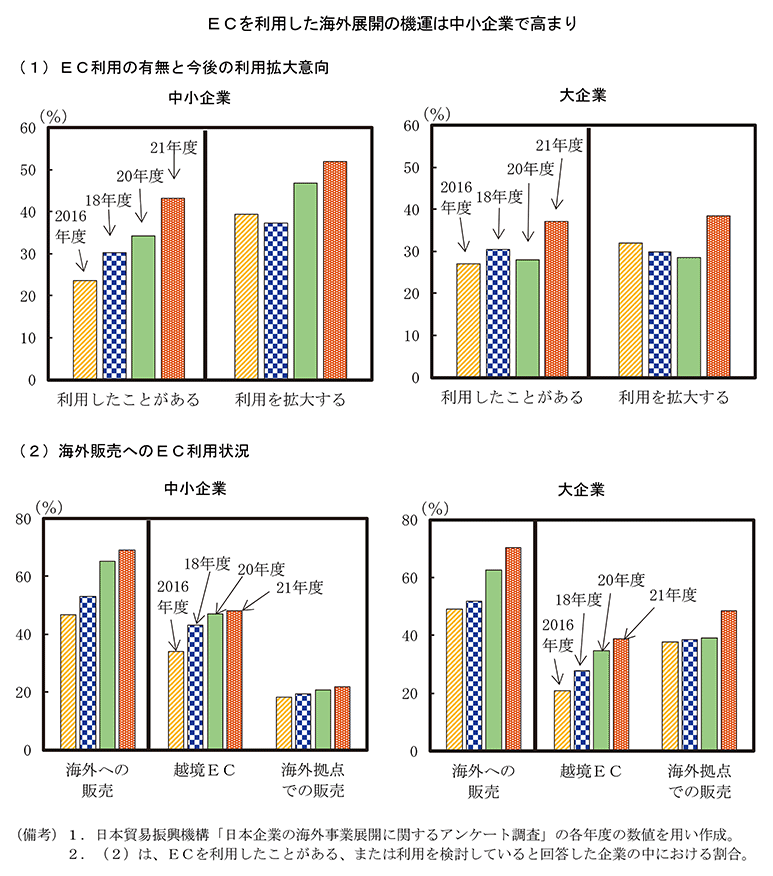
(多様な主体のネットワークによる伴走支援で中小企業の輸出を促進)
以上でみてきたように、中小企業が輸出を行う際に直面する課題は、マーケティングや人材面などの体制面に関するものが主であり、資金や人材などで制約が大きい中小企業が自社のみで乗り越えることは困難な課題であるといえる。近年ではECの利用等によってそうした参入障壁ともいえるハードルが低下しているとはいえ、輸出をする意向はあるものの、具体的に何をどのように取り組めばいいのかといった面で行き詰る企業も少なくないであろう。こうした中で中小企業の輸出を促進するためには、認定支援機関等を含めた中小企業を取り巻く多様な主体が支援ネットワークを形成して、中小企業が抱える課題を乗り越えるためのバックアップをしていくことが必要である。
この点、総合経済対策5に盛り込まれた「新規輸出1万者支援プログラム」は中小企業の輸出を促進する上で期待感をもたせるものである。具体的には、多様な主体が連携し①新たに輸出に挑戦する事業者の掘り起こし、②専門家による事前の輸出相談、③輸出用の商品開発や売込みにかかる費用の補助、④輸出商社とのマッチングやECサイト出展支援、などを一気通貫で実施することとしている6。
輸出相談では、輸出意向はあるものの何に取り組めばいいかわからない企業に対し専門家が個別相談を行い、輸出に向けた経営計画の立案から具体的な準備まで伴走支援を行うなど、きめ細かな支援が期待される。また、輸出に際して必要な費用については、輸出向け商品の生産に必要な設備導入のみならず、ブランディングやプロモーション等に要する費用も含め、輸出促進を資金面でも後押し7する。販売先の確保に向けては、JETROによる海外ECサイトを活用した販路開拓支援や輸出商社とのマッチング支援のほか、各国・地域に精通した専門家による商談同席や海外への同行、現地に精通したコーディネーターによる市場調査・相談や商談アポイントメントの取得支援、海外見本市・展示会や商談会への出展支援等を行うこととしている。
このように、各種の支援策は、先述した中小企業が輸出に際して直面する自社のみでは解決することが難しい課題に対して包括的かつきめ細かく支援するものであり、中小企業の輸出促進につながることが期待される8。
2 農林水産物・食品の輸出動向
(農林水産物・食品の輸出額は2013年以降堅調に増加)
次に、中小企業と並んで、海外需要の取り込みによって輸出額を大きく拡大させる可能性がある農林水産物・食品の輸出動向をみていく。
農林水産物・食品の輸出額は、2000年代はおおむね横ばいで推移していたが、その後、2013年からは増加を続けている。輸出額は2012年には4,497億円であったが、2021年には1兆1,626億円と9年間で約2.6倍に拡大した。内訳をみると、2012年から2021年にかけて、農産物は約3倍、林産物は約4.8倍、水産物は約1.8倍へと、いずれの分野でも増加している9(第3-3-7図(1))。さらに、2022年に入っても輸出の増加は続いており、1月から10月までの累計で1兆857億円、前年比で15.3%増となっている。2021年は初めて1兆円を超え、前年比で25.6%増となるなど、近年でも輸出額が著しく増加した年であったが、2022年はそれを更に上回る見込みである(第3-3-7図(2))。
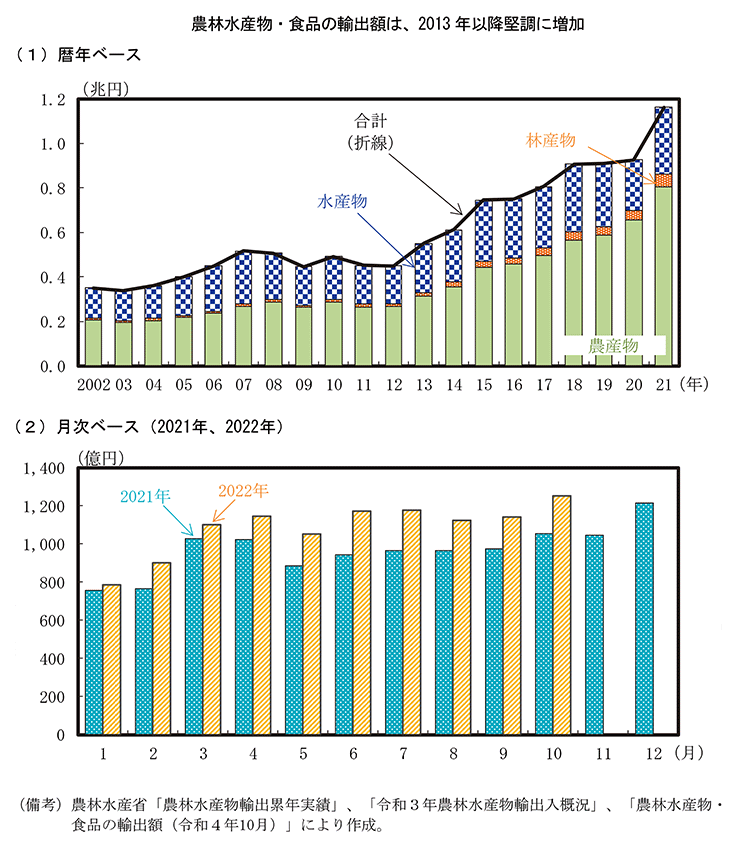
(世界的に知名度が向上する品目での輸出拡大が顕著)
品目別の動向をみると、農産物では、特にアルコール飲料や調味料等の加工食品、肉類等の畜産品の寄与度が高く、水産物では、冷凍技術が向上したこと等も背景として、調整品を除く水産物の寄与度が高い(第3-3-8図(1))。個別品目でみると、特に、ウイスキー、日本酒、牛肉の輸出額は、それまでも堅調な増加を続けてきたが、2021年は更に大幅に増加している(第3-3-8図(2))。背景としては、我が国の農林水産物や食品の知名度が世界的に向上する中で、ブランド力を高めて単価を上げることができている10ほか、小売店向けやEC販売が好調であったこと、また、アメリカや中国等の外食需要が回復したこと等が挙げられる。
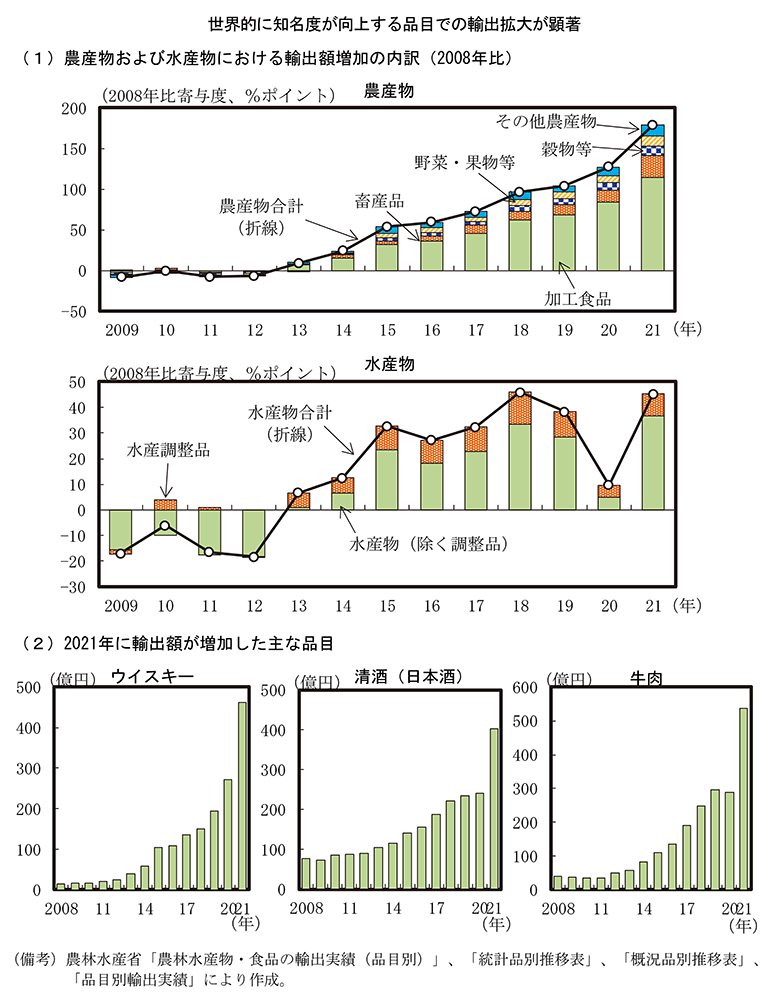
このように、農林水産物・食品の分野では、輸出額が近年大きく増加しており、海外需要の取り込みの好事例となっている。こうした輸出拡大の背景としては、アジアを中心に海外の消費者の所得が向上して潜在的な購買層が顕在化したことや、訪日外国人の増加等を通じて日本産の農林水産物・食品の魅力が海外に広まったこと等の環境変化が挙げられる。特に、世界的に新型コロナの影響が生じた2020年以降、商談の機会が減少するなど厳しい環境の中においても輸出額が増加していることは、日本産の農林水産物・食品に対するニーズが強いことを示唆している。もちろん、こうした環境変化は、国内の農林水産事業者を中心とする関係者が様々な形で輸出事業に取り組んできた成果の表れともいえよう。
政府は、農林水産物・食品の輸出額を2025年に2兆円、2030年に5兆円とする目標を定め11、その実現に向けて取組を進めているが、総合経済対策においては、2025年に2兆円の目標を前倒しで達成すべく様々な支援措置を盛り込んでおり12、こうした取組の下、海外需要の取り込みが今後一層進むことが期待される。
3 インバウンド需要の動向
(堅調に拡大してきたインバウンド需要はコロナ禍で消失)
最後に、インバウンド需要(訪日外客による消費)の動向をみていこう。まず過去の状況を振り返ると、訪日外客数は2012年には836万人、その消費額は1.1兆円に過ぎなかったが、2013年以降は徐々に増加し、過去最高水準である2019年にはそれぞれ3,188万人、4.8兆円となった(第3-3-9図(1))。7年間で訪日外客数は約3.8倍、その消費額は約4.4倍と大幅に拡大しており、海外需要の取り込みの代表であったといえる。訪日外客数の国・地域別の内訳をみると、中国、韓国、台湾、香港の順に多く、これらの地域で全体の7割を占め、アメリカと欧州は併せて約1割、その他の国・地域で約2割となっており、近隣諸国・地域が中心となっている(第3-3-9図(2))。
しかしながら、こうしたインバウンド需要は世界的な新型コロナの感染拡大が生じた2020年に急減した。日本を含む各国の水際対策の下で国際的な人の往来には大きな制限が課され、2021年の訪日外客数は25万人、その消費額は0.1兆円となるなど、7年間で徐々に取り込んできた海外需要は新型コロナの影響によって消失した。
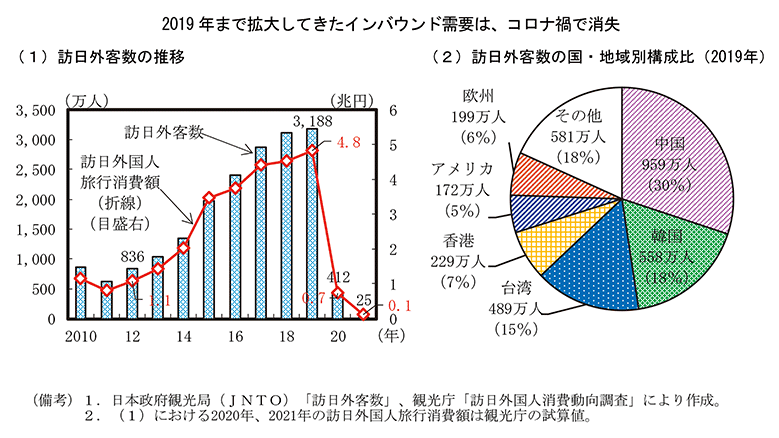
(2022年10月以降、水際対策の緩和によって訪日外客数が急回復)
2022年後半に入り、こうした状況がようやく変化しだしている。具体的には、同年10月11日から我が国の水際対策が緩和された13ことに伴い、訪日外客数は10月に50万人、11月に93万人と大幅に増加した(第3-3-10図(1))。観光を目的とした訪日外客の割合は、2022年1月から6月まではゼロ、パッケージツアーの受入れを再開し入国者上限も引き上げていた7月から9月でも1割未満であったのに対し、10月は約6割、11月は約8割と大きく上昇しており、水際対策の緩和によって観光客が大幅に増加したことがわかる(第3-3-10図(2))。
11月の訪日外客数を国・地域別にみると、過去最高水準である2019年の月平均と比べ、世界全体ではいまだ35%程度の水準であるが、韓国では約7割、香港では約4割、アメリカでは約6割、アジア・アメリカ・欧州を除くその他地域では約6割と、水際対策の緩和からわずかな期間で大幅に回復している。一方、2019年に我が国訪日外客数全体の3割を占めていた中国については、中国政府による規制と感染再拡大の下で訪日外客数は2019年比で2.6%といまだ回復していない(第3-3-10図(3))。中国政府は、2023年1月8日から自国の水際対策を緩和し、中国入国時の隔離も不要とすることを発表14し、また「国際的な感染情勢を踏まえつつ、中国人の海外旅行を秩序立てて回復させる」との方針を示した。しかし、中国における感染動向は情報に乏しく、我が国15だけでなく他の先進諸国においても水際対策の緩和に必要な条件はいまだ整っていない。今後、中国において適切な感染対策と情報開示が行われるなど必要な条件が整備されていけば、訪日外客数も増加していくことが期待される。
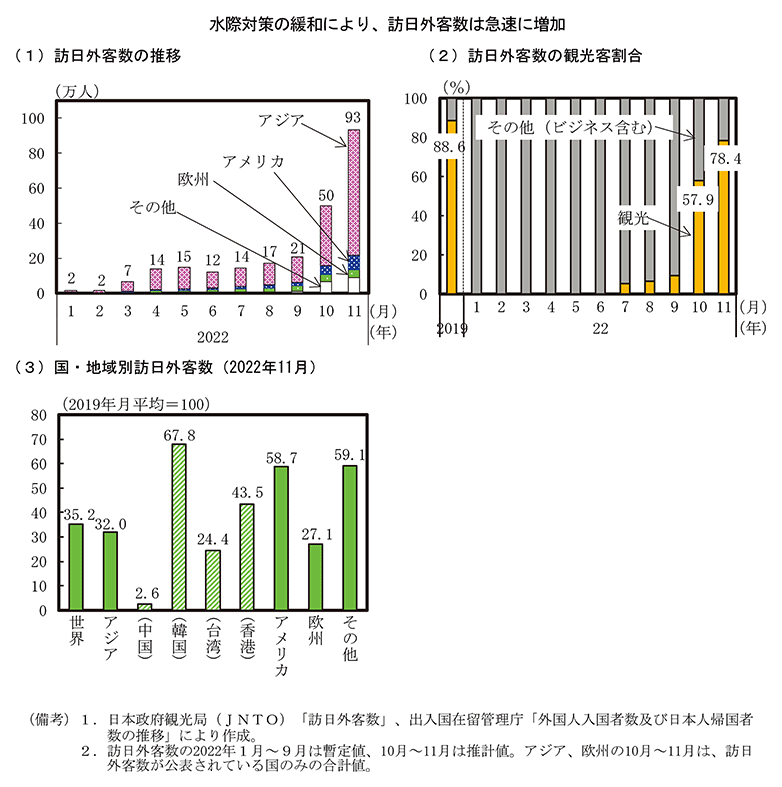
(円安の進行もあり、訪日外客一人当たりの消費額は大幅増)
このように、訪日外客数が2022年10月以降大幅に回復する中、訪日外客一人当たりの消費額を見てみると、2019年には一人当たり平均が15.7万円であったのに対し、2022年10月には21.4万円と約4割上昇している(第3-3-11図(1))。この間、為替レートを円ドル相場でみると、2019年は年間平均が1ドル109円であったのに対し、2022年10月は1ドル147円へと約35%円安になっている。仮に訪日外客一人当たりの旅行時の予算が各国通貨建てで大きく変化しないとすれば、円安は円換算の消費額を押し上げることとなる。
特に、欧州、アメリカ、オーストラリア等からの訪日外客は、2019年の実績をみると、滞在日数の長さ等も背景に一人当たり消費額が相対的に大きく、これらの国・地域からの人流回復は消費額の回復にも大きく寄与するであろう。アジアの中では、中国、シンガポール、ベトナムの消費額が高く、韓国や台湾などは相対的に低くなっている(第3-3-11図(2))。今後の中国からの観光客の回復動向は、観光客数・消費額いずれの面で見ても、我が国のインバウンド需要の回復に大きな影響を与えると考えられる。
こうした中、政府は総合経済対策において「訪日外国人旅行消費額の年間5兆円超の速やかな達成を目指し、集中的な政策パッケージを推進する」こととしている。円安のメリットを最大限活かしながらもサービスの高付加価値化を推進し、世界に対する訪日プロモーションなどの取組を通じて長期滞在者やリピーターを呼び込み、インバウンド需要を有効に取り込んでいくことが重要である。