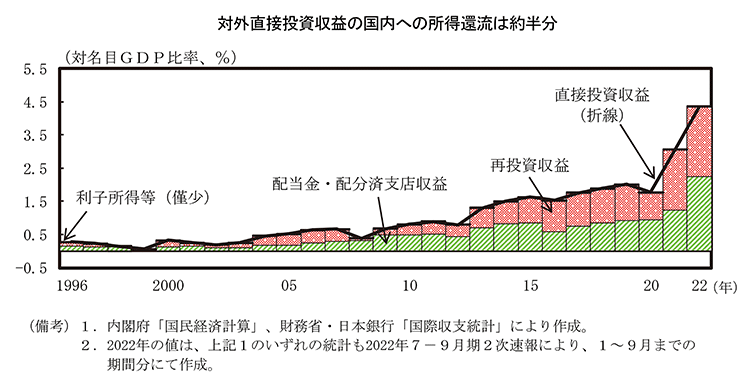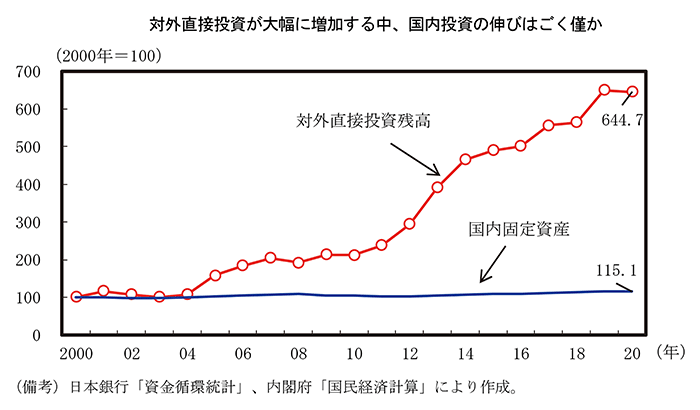第3章 企業部門の動向と海外で稼ぐ力(第2節)
第2節 我が国経済の対外経済構造
前節では、コロナ禍における企業部門の回復過程をみてきたが、コロナ禍において製造業の生産・企業収益が海外需要の取り込みを背景にいち早く回復したことや、2021年夏のデルタ株の流行等、海外の感染拡大による生産活動の停滞が我が国の生産活動に大きく影響を及ぼしたこと等からも明らかなように、我が国企業部門、特に製造業の活動はグローバルバリューチェーンを通じて、世界の様々な地域の経済と密接に結びついている。本節では、こうした我が国経済と海外経済との結びつき、すなわち対外経済構造について、中長期的な経常収支の動向に着目してその変化をみていくこととする。
1 貿易収支の動向
(経常収支の黒字の主因は、貿易収支から所得収支へと変化)
一定期間における海外との財・サービスの受払(貿易・サービス収支)や海外への投資に伴う受払(第一次所得収支)等で構成される経常収支は、我が国では長きにわたって黒字で推移しているが、その内訳は大きく変化してきた(第3-2-1図)。経常収支の黒字を長らくけん引してきた貿易収支は、2000年代後半、リーマンショック頃を境に構造が変化し、2012年から2015年、2022年には赤字となるなど、常態的な黒字ではなくなっている。一方で、第一次所得収支の黒字幅は徐々に拡大を続けており、リーマンショック以後は経常収支黒字の主たる要因となっている。すなわち、我が国の対外収支の黒字要因は、貿易中心から投資中心へと変化してきた。なお、この間、サービス収支は徐々に赤字幅を縮小し、特に2010年代後半からコロナ禍前まではおおむね均衡する程度までになっていたが、第1章でみたように2020年以降は赤字幅が拡大した。
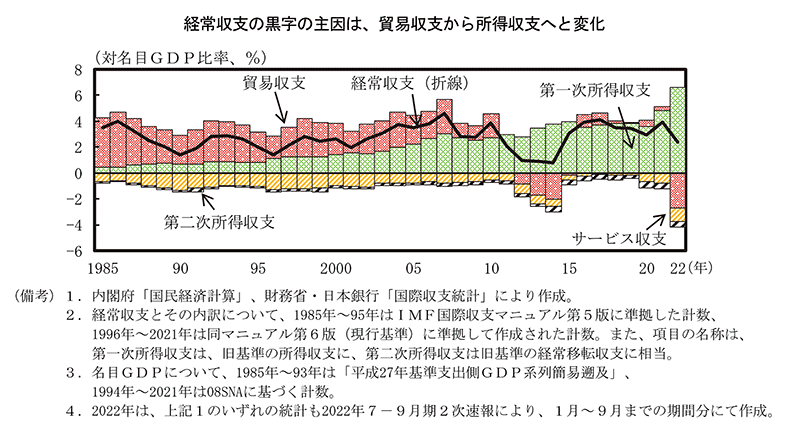
(貿易収支は、リーマンショック以降を均してみるとおおむね均衡)
こうした経常収支の構造変化がどのように生じてきたのかを確認するため、貿易収支、所得収支それぞれの動向を確認していく。
まずは、貿易収支の構造についてみていく。海外への支払いである輸入は、1990年代は名目GDP比でみて6%程度で推移していたが、2000年代は9%程度、2010年以降は13%程度と拡大し、貿易収支へのマイナス寄与を拡大してきた。一方で、海外からの受取である輸出は、名目GDP比で1990年代は8%程度、2000年代は11%程度、2010年以降は13%程度と、貿易収支へのプラス幅を拡大してきたが、増加ペースは輸入のそれを下回る動きであった。その結果、2000年代まで黒字で推移してきた貿易収支は、2010年以降を均してみるとおおむね均衡している(第3-2-2図)。
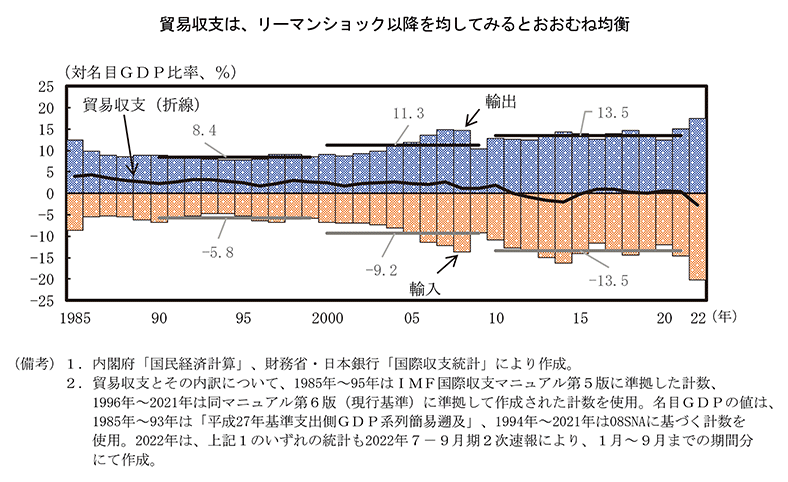
(品目別にみた輸出入バランスの構造は、長期にわたって不変)
こうした貿易収支の変化がいかなる要因によってもたらされているかを確認するため、品目別の輸出入バランスの動向を見てみよう。輸送機器や一般機械では一貫して輸出超過となっている一方で、資源をもたない我が国にとって必須輸入品である鉱物性燃料、食料品、原料品については、一貫して輸入超過となっており、特に鉱物性燃料については輸入金額が大きく、ゆえに貿易収支に与える影響も大きい。そのほかの品目については、化学製品や原料別製品等では輸出と輸入がバランスしており、電気機器については、2000年代は輸出超過であったが、アジアを中心とした新興国への生産拠点の移転が進展したこと等に伴い、徐々に輸入金額が多くなり、おおむねバランスするようになった。このように、我が国貿易においては、必須輸入品の輸入超過を、製造業部門の輸出超過で賄う構造が定着しており、この構造は過去20年程度不変である(第3-2-3図)。
また、食料品や鉱物性燃料といった必須輸入品以外の品目については、素材から機械機器類に至るまで、輸出と輸入の双方で金額が増加していることも確認できる。この背景には、アジアを中心としたグローバルバリューチェーンの構築、すなわち、各国・地域が各々の特性を活かした生産工程に特化し、生産物を中間財として輸出入することにより、国際的な付加価値のネットワークが形成されてきたことが挙げられる1。
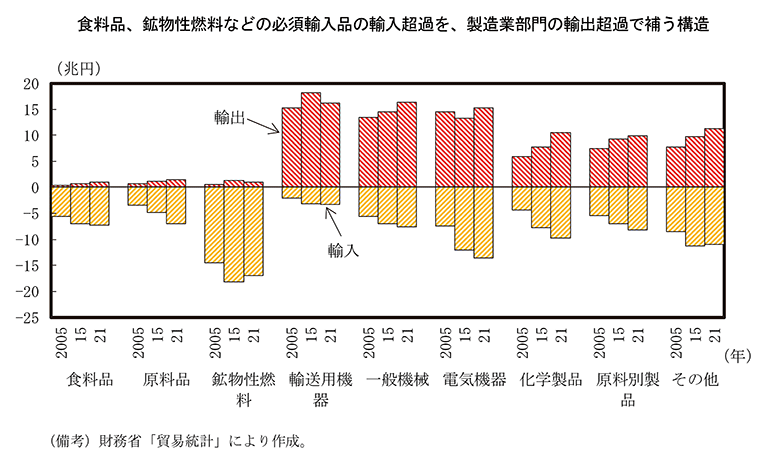
(輸出金額の増加の主因は、数量要因から価格要因へと変化)
次に、輸出入金額の変動の要因を数量と価格に分解して見てみよう。
輸出金額については、2005年以降リーマンショック前までは、円安による価格競争力の改善もあり、数量要因と価格要因の双方によって増加していたが、リーマンショックに伴い数量が大幅に減少することで2008年末から2009年にかけて大きく減少した。リーマンショック後については、数量要因は2010年を除き総じてマイナス寄与となっている一方、価格要因がとりわけ2013年以降に大きくプラス寄与となることで輸出金額の増加が形作られていることがわかる(第3-2-4図(1))。言い換えれば、我が国の輸出は、リーマンショック以降、数量で稼ぐビジネスモデルから、価格で稼ぐモデルへと変化を遂げている。
なお、為替レートの変動が輸出金額に与える影響という観点からこの間の動きをみると、リーマンショック以前にみられたような円安による輸出数量の増加は、2010年以降の円安局面ではみられない2。これは、為替変動に応じた輸出企業の価格設定行動が、現地通貨建ての価格を下げて数量で稼ぐ戦略から、現地通貨建ての価格を維持したまま円安分だけ利幅を上乗せする戦略へと変化してきたことを示唆している。このように企業が為替レートの変動を契約通貨建ての輸出価格で調整しなくなった背景の一つには、輸出財の高付加価値化、すなわち製品の差別化によって市場支配力を高めてきたことが挙げられるであろう。実際、輸出財の高付加価値化指数3の動向をみると、2000年以降すう勢的に上昇しており、日本の輸出財は高付加価値化によって輸出価格を高めていることがうかがえる(第3-2-5図)。
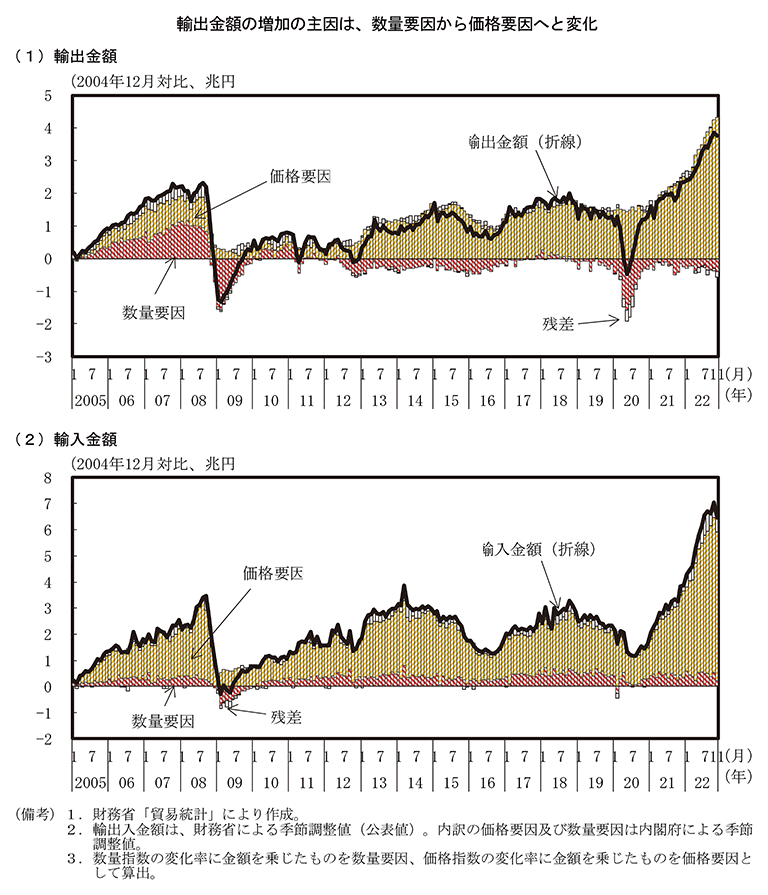
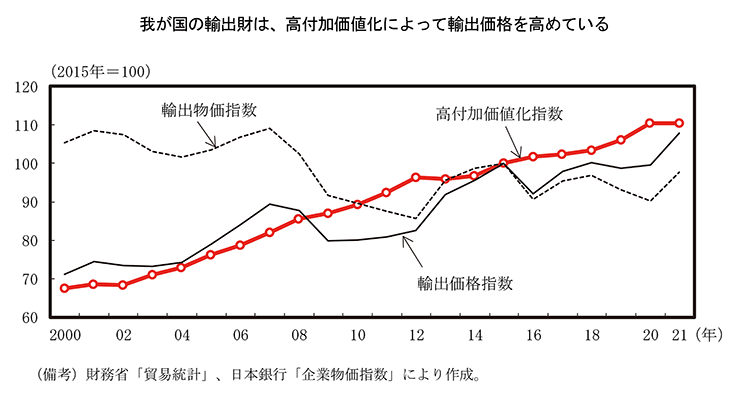
(輸入金額の変動は、原油等の鉱物性燃料の価格の影響大)
一方の輸入金額の変化要因をみると、先述のとおり、我が国の輸入超過の最たる部分が食料品や鉱物性燃料等の必須輸入品であることからもうかがえるが、2005年以降、数量要因には大きな変化がみられず、輸入金額の変動は専ら価格要因によってもたらされている(第3-2-4図(2))。さらに、輸入価格の動きは、輸入に占める原油の比率が高く、また、原油以外の鉱物性燃料の中でも天然ガスは原油価格に連動して価格付けされること等から、原油価格の動きが大きく影響する(第3-2-6図)。
ここで、改めて我が国貿易収支を品目別にみると、先述のとおり2010年以降の貿易収支は均してみればおおむね均衡しているが、2012年から2015年、2022年には赤字となっている。この間、食料品の赤字幅と輸送機器及び一般機械の黒字幅には大きな変化がみられない一方、鉱物性燃料の赤字幅は原油価格の上昇によって拡大していた(第3-2-7図)。
すなわち、我が国貿易収支の変動は、主に鉱物性燃料の輸入金額の変動によってもたらされ、鉱物性燃料の輸入金額の変動は原油価格の変動によってもたらされている。このことは、資源をもたない我が国の貿易が、いまだにエネルギー価格や為替レート変動の影響を受けやすい構造であることを示しており、こうした面からも、GXの促進などを通じて化石燃料に過度に依存しないエネルギー構造への転換を進めていくことが重要である。
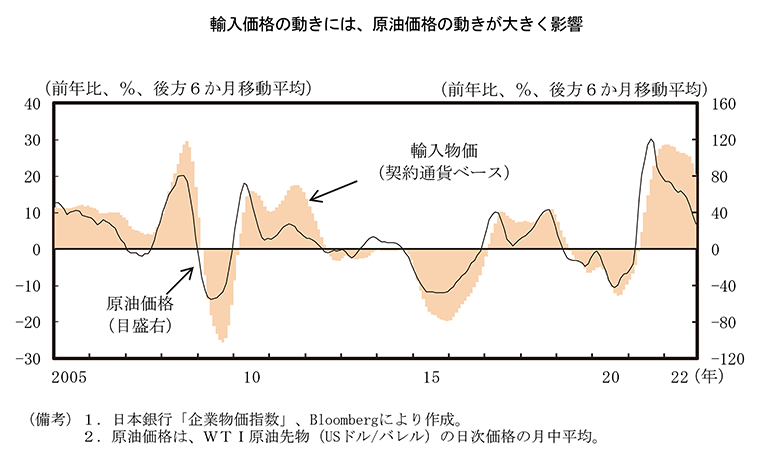
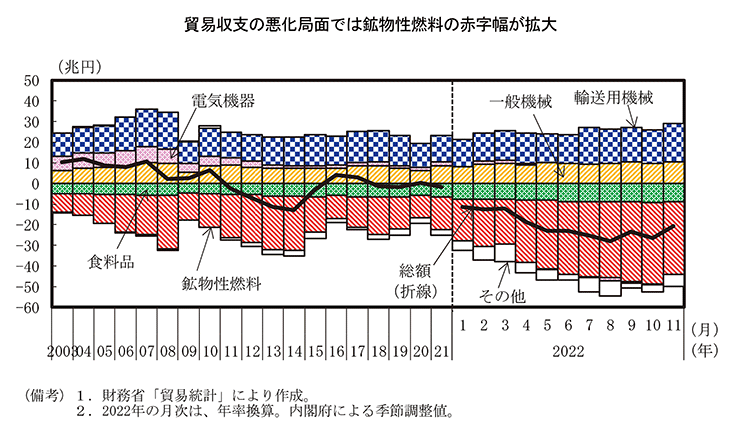
2 所得収支の動向
(所得収支の黒字は拡大を続け、対外直接投資からの収益が主因に)
次に、リーマンショック以降、我が国経常収支の黒字をけん引している第一次所得収支の動向を確認する(第3-2-8図)。
第一次所得収支の内訳をみると、債券利子や株式配当金を計上する証券投資収益は、2000年以降リーマンショック前までは黒字幅を徐々に拡大してきた。リーマンショック後は、各国中央銀行による金融緩和の下で債券利回りが低下してきたこともあり、均してみれば、GDP比2%程度でおおむね横ばいで推移している。また、海外子会社からの配当金等を計上する直接投資収益は、我が国企業の海外進出の進展等によって黒字幅を拡大しており、GDP比は1991年に0.1%であったものが2021年には3.1%と30年間で30倍以上になり、2018年以降は証券投資収益の寄与を上回っている。2022年のGDP比は、9月までの状況ではあるが、円安の進展によって配当金等が円建てで増価したこともあり、4.4%と更に拡大している。
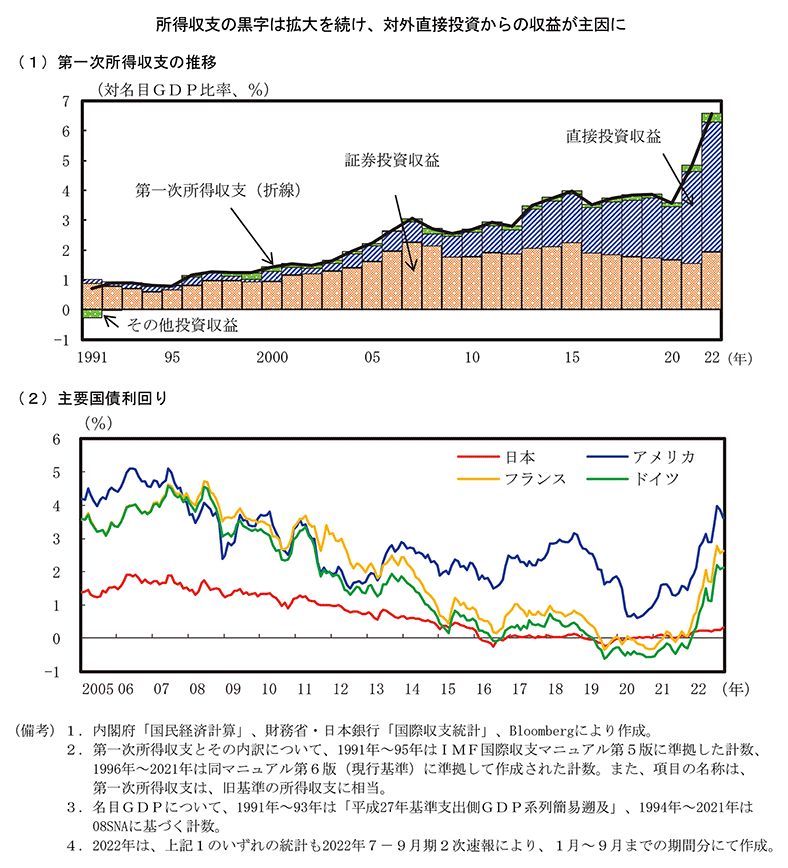
(対外純資産は直接投資を中心に増加し、31年連続で世界最大の純債権国)
続いて、所得収支の黒字拡大の背景を、ストック面から確認してみよう。
我が国の対外資産負債残高の推移をみると、資産面では証券投資と直接投資を中心に増加し、負債面では証券投資を中心に増加している(第3-2-9図(1))。このように資産負債が共に増加する中、非居住者が保有する日本の資産(対外負債)を除いた純資産ベースでみると、特に2012年以降の10年間では直接投資残高の増加が著しく、2014年には証券投資残高を、2017年には外貨準備高を上回り、2019年以降は対外純資産に占める割合は5割弱となっている(第3-2-9図(2))。
対外純資産は、2000年対比で約3倍に増加しており、内訳別には、証券投資残高が約2倍、外貨準備高が約4倍とそれぞれ相応のペースで増加しているが、直接投資残高は約7倍と証券投資や外貨準備を大きく上回るスピードで増加している。とりわけ2012年以降は、アジア等の新興国の成長とそれらの需要を獲得するための企業の海外展開の進展等を背景に、それ以前と比べて増加ペースが著しい(第3-2-9図(3))。こうした結果、我が国は31年連続で世界最大の純債権国となっている(第3-2-9図(4))。こうした対外純資産に対する収益が、上述のとおり、第一次所得収支の黒字として経常収支を支えている。今後、少子高齢化などを背景に我が国の貯蓄投資バランスが赤字化(輸入超過)していく可能性もあることを踏まえれば、資源輸入国である我が国が経済的豊かさを維持していくためには、対外純資産の収益性を一層向上させることにより、中期的に予想される経常収支黒字の縮小や対外純資産の減少を補っていくことが重要と考えられる。
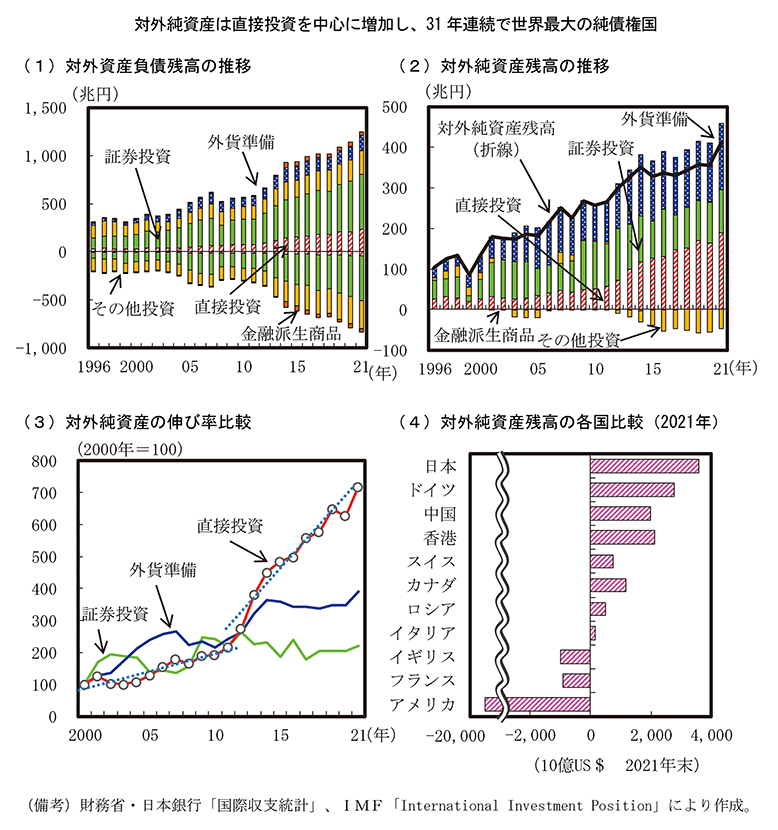
(対外資産の収益率は高水準)
そこで、ここ10年間で急速に増加している対外資産について、その収益率を確認しよう。証券投資の利回りは、先述のとおり、世界的に緩和的な金融環境の影響もあり、徐々に低下している一方で、直接投資の利回りは、振れを伴いながらも高水準かつ上昇基調で推移している。結果として、対外資産全体の利回りは、高い利回りである直接投資残高が増加することによって証券投資の利回り低下がカバーされる形となり、長期にわたっておおむね3%程度で安定的に推移している。この結果、国全体の純資産収益率は対名目GDP比で6%程度と、2000年代以降でみても高い収益性を有している(第3-2-10図)。
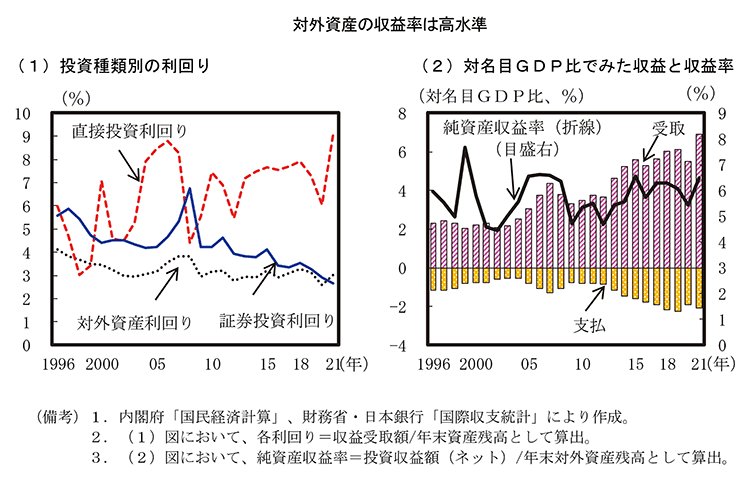
(直接投資、証券投資ともにアジア向けで増加)
こうした高い純資産利益率の背景を考える手がかりとして、我が国の対外投資を、投資先の国・地域別に見てみよう。
対外直接投資について2021年時点の残高を確認すると、最大の投資先はアメリカ及び欧州であり、両地域で全体の残高の約6割を占める(第3-2-11図(1))。一方で、2000年と比較した伸び率をみると、残高は小さいものの中国向けの伸び率が最も高く、次いでその他アジア、欧州となっている(第3-2-11図(2))。中国を含めたアジアへの直接投資は、生産拠点の移転を含めアジア域内でのサプライチェーンの構築が加速化したことが背景にあると考えられるが、こうした投資は、投資先国の高い経済成長率を背景に収益率が高く4、これが高水準の直接投資利回りを支える一因となっているものと考えらえる。
対外証券投資においても、直接投資と同様、アメリカ及び欧州が最大の投資先であり、両地域で全体の残高の7割を占める(第3-2-11図(3))。一方で、2000年と比較した伸び率では、中国、その他アジア、中南米において高くなっている(第3-2-11図(4))。リーマンショック後、欧米の中央銀行による金融緩和の下で先進国の債券利回りが低下してきたこと等を背景に、相対的に利回りの高い新興国向けの投資が加速化してきた様子がうかがえる。
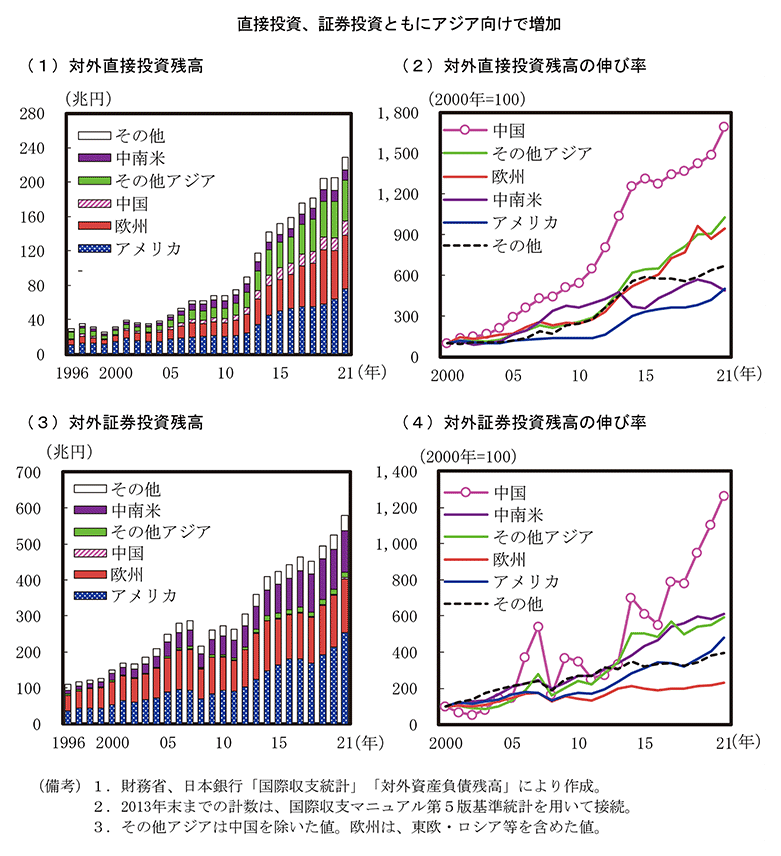
3 海外で所得を稼ぐ力
(我が国企業の海外進出が進展)
対外投資残高を保有主体別にみると、直接投資は非金融法人企業の残高が、証券投資は金融機関や一般政府の残高が大幅に増加している(第3-2-12図)。中でも、非金融法人企業の直接投資残高を業種別にみると、製造業では、投資先国や近隣地域の需要獲得を目的とした海外進出により輸送機械や電気機械、一般機械といった機械関連業種が増加しているほか、M&Aによる世界展開の進展などを背景に化学・医薬品の増加が著しい。非製造業では、商社による探鉱権益の獲得等を背景に卸売・小売が増加しているほか、個別企業による大型M&Aなどを背景として通信の増加も顕著である(第3-2-13図)。
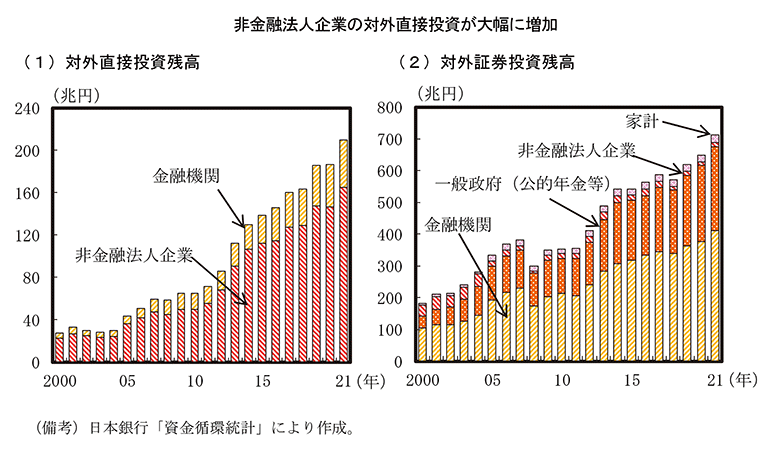
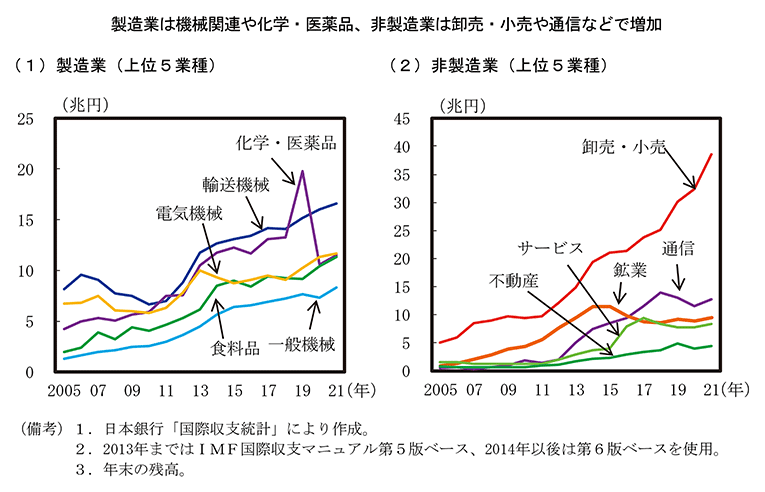
このように、我が国企業は海外進出を進める中で対外投資を拡大してきたが、これを海外現地法人の活動状況の面からも確認しよう(第3-2-14図)。海外進出企業の現地法人について、企業数や売上高、従業員数の推移をみると、売上高は感染症の影響もあって近年減少しているものの、過去30年にわたり増加を続けてきた。直近の2020年度では、企業数は25,703社(うち製造業が4割程度)、売上高は240.9兆円(うち製造業が5割弱)、従業員数は563万人5(うち製造業が7割強)となっている。特に、法人企業数は2012年に製造業・非製造業ともに大きく増加するなど、先述の対外直接投資の拡大時期と整合的である。この背景には、当時の企業が直面していたいわゆる6重苦をプッシュ要因、成長するアジア等の新興市場の需要取り込みや相対的に安い生産コストを求めることをプル要因として、海外進出を加速化させたことが挙げられる。
なお、現地法人企業数は、非製造業では増加傾向が続いている一方で、製造業では、2010年代前半までは右肩上がりに増加してきたが、2010年代後半はおおむね横ばいで推移している。これは、アジアを中心とした生産工程の分業化、グローバルバリューチェーンの構築がある程度確立されてきたことの裏返しでもあろう。製造業の海外生産比率をみても、こうした動きと整合的に、2000年度には15%弱だったものが、2010年代半ばには25%程度まで上昇し、その後はおおむね横ばいで推移している(第3-2-15図)。
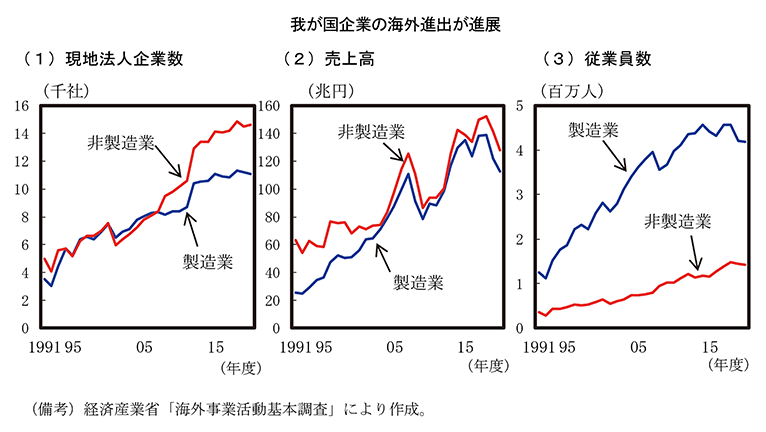
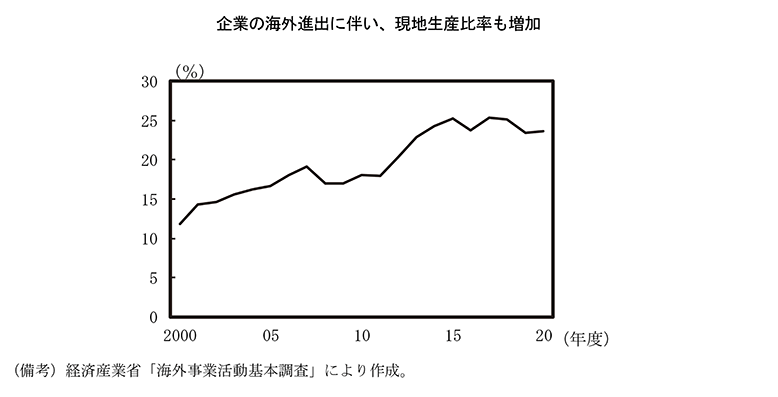
(企業の海外進出の進展は、営業外収益増の形で経常利益を押上げ)
以上でみてきた一国全体での対外資産からの収益増を企業レベルで示すものが、第1節において確認した法人企業の経常利益と営業利益との差である。営業利益は本業で生じた利益である一方、経常利益は海外子会社からの受取配当金も含むものであるが、2000年代半ば以降は、経常利益が営業利益を恒常的に上回っており、その差である営業外損益の黒字額は徐々に拡大している(第3-2-16図)。これは、企業が海外で所得を稼ぐ力を高めてきたことの成果であり、国内の需要や景気動向だけに左右されるのではなく、海外から持続的に収益を得る構造に転換していることの証左である。
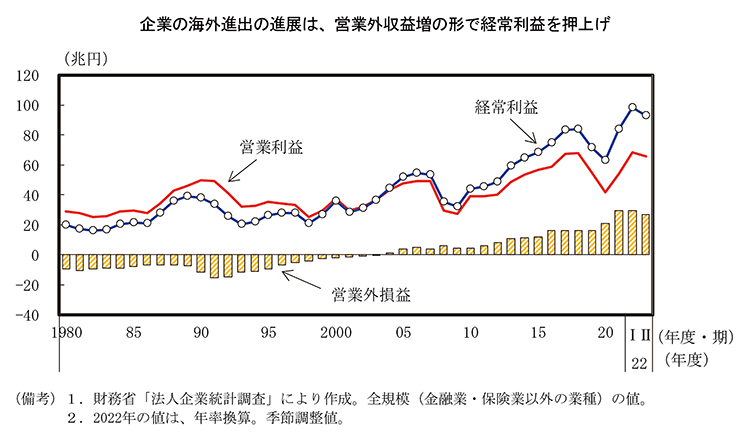
(海外で所得を稼ぐ力は大中堅企業に偏在)
一方で、こうした海外で稼ぐ力は、企業規模別にみると大中堅企業に偏っている。第1節でみたとおり、収益面において、営業外収益の増加による経常利益の押上げがみられるのは主に大中堅企業であり、中小企業ではそうした押上げが限定的であった。
さらに、先述した海外の現地法人企業の活動状況を、本社企業の資本金規模・業種別に集計した結果をみると、本社が中小企業である海外現地法人企業の数は全体の約25%を占めるものの、当該現地法人企業の売上高及び経常利益ではそれぞれ2%台となっている(第3-2-17図)。すなわち、海外現地法人の中でも、売上及び利益の大宗は大中堅企業の子会社・孫会社が生み出しており、法人企業統計ベースの営業外収益とも整合的であるが、我が国中小企業が海外において所得を稼ぐ力は限定的であるといえよう。
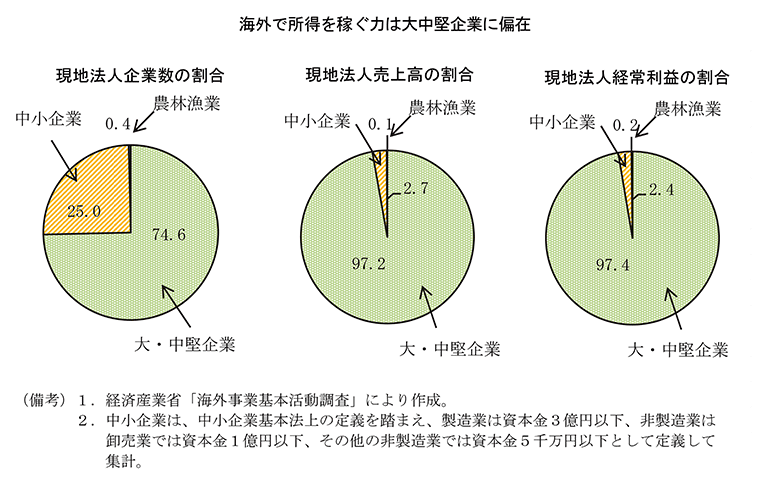
(海外での収益を国内の成長力強化につなげることが必要)
また、対外直接投資の収益は、現地法人からの配当受取という形で我が国に還流されることによって、国内経済にもプラスの効果をもたらすが、一方で、収益のすべてが国内に所得として還流されるわけではない。対外直接投資収益の内訳をみると、配当金等として我が国に還流される分は約半分であり、残りの約半分は再投資収益として海外拠点の内部留保として蓄積される(第3-2-18図)。
さらに、そうして得た海外からの配当金等が、我が国において人への投資としての賃金上昇や成長力を高めるための設備投資に活用されてきたとは言い難い。賃金については、2000年以降、長引くデフレの中で、労働分配率は低下し、実質賃金の伸びが労働生産性の伸びを総じて下回って推移するなど、企業が賃金上昇を抑制してきたことは、これまでも指摘6してきたとおりである。設備投資については、対外直接投資が拡大するのと対照的に、低調に推移してきた。対外直接投資と国内投資をストックベースの残高で比較すると、2000年を基準として、対外直接投資の残高は20年間で6.4倍に増加したのに対し、国内固定資産の残高は1.15倍の増加にとどまっている(第3-2-19図)。対外直接投資の水準が僅かなところからのスタートであるため、伸び率に大きな差がつくのは当然な面はあるが、そうした面を考慮してもなお、長引くデフレと低成長の中で、我が国企業が国内での投資機会を見いだせずにきたことを改めて認識させる結果である。
こうした過去20年間にわたる状況を踏まえると、海外で稼いだ成果をいかにして国内経済の成長力強化につなげていくかということが課題である。前節でも述べたとおり、新しい資本主義を加速化させる中で、企業の期待成長率を高め、好調な企業収益が人への投資を含めた成長分野での投資拡大につなげていくことが重要である。