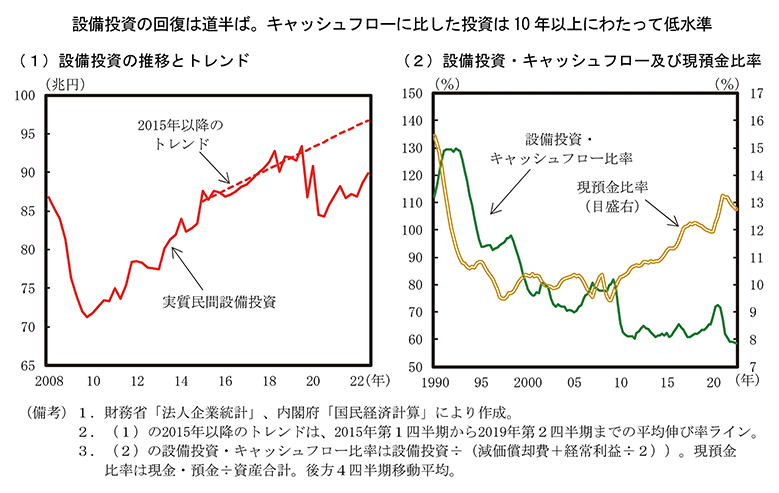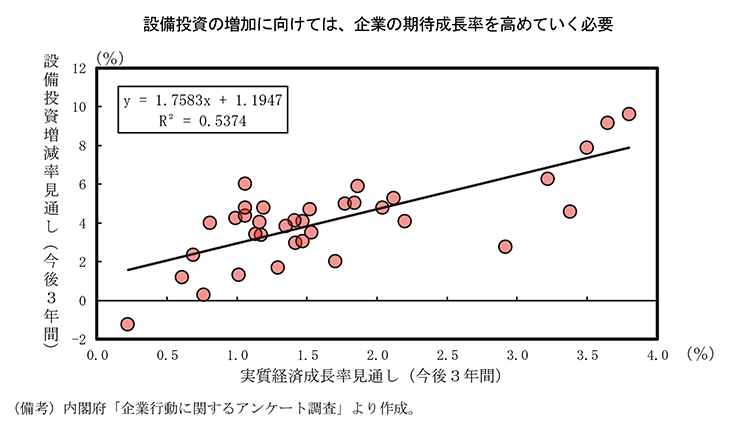第3章 企業部門の動向と海外で稼ぐ力(第1節)
第1節 企業部門の概観
本節では、我が国企業部門について、コロナ禍からの回復、世界的な物価上昇、供給制約の動向などを踏まえつつ、生産、収益、設備投資の動向を中心に確認していく。
1 鉱工業生産
(生産は供給制約の影響で一進一退の動き)
2022年の製造業の生産は、2021年から継続していた部品等の供給制約の影響に加え、春の中国でのロックダウンの影響から、年前半に水準を切り下げたものの、年後半は、ロックダウンの影響が緩和される中で、世界的に堅調な投資財の需要なども背景に持ち直しの基調が続いてきた。こうした動きを確認するため、コロナ禍以降の我が国製造業の動きを振り返ってみよう(第3-1-1図)。
鉱工業生産は、2020年4月から5月にかけて、我が国初の緊急事態宣言の発令の下で大幅に減少したが、その後は、2021年初頭まで堅調に回復した。2021年4月にはコロナ禍前である2019年12月の水準を上回るなど、経済回復が早かった中国やアメリカ等の海外需要を取り込みながら、輸出にけん引されていち早い回復が実現した。
一方で、2021年春以降の生産は半導体等の供給制約の影響を受け、一進一退の動きを続けている。特に、2021年夏のデルタ株の流行に伴う東南アジアでの工場停止、2022年春の中国でのロックダウンの影響は顕著であり、その時期に大きく生産水準を切り下げるなど、我が国の生産活動がサプライチェーンを通じて、供給面から下押しされるリスクが顕在化したといえる。もっとも、感染拡大によって生じる供給制約の影響は一時的であり、感染状況が落ち着いた後には切り下がった生産水準が早期に持ち直している。他方で、こうした状況が繰り返し生じる中において、生産は2021年春以降を均してみればコロナ禍以前より低い水準で推移しており、いまだ本格的な回復が実現したとは言い難い。
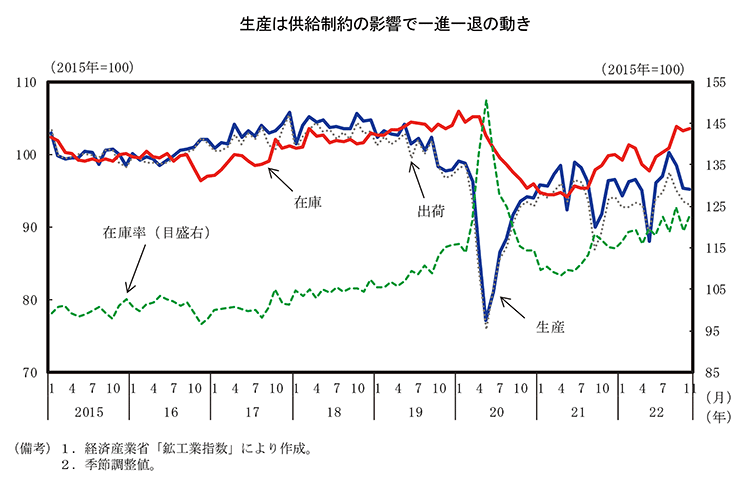
(2022年以降は、生産用機械等の投資財が生産の伸びをけん引)
次に、こうした生産の動きを主要業種別に見てみよう(第3-1-2図(1))。
自動車を中心とした輸送機械工業の生産は、2022年を通じて、コロナ禍以降の回復過程で生じた世界的な半導体供給不足の影響が続いており、徐々に緩和されてはいるものの、2022年末時点で解消の目途は立っていない。これまでの動向を振り返ると、輸送機械工業の生産は、緊急事態宣言下においてコロナ禍以前の約半分程度の水準まで減少したが、その後2020年10月にはコロナ禍以前の水準まで回復するなど、鉱工業生産全体の回復をけん引した。2021年以降は車載用半導体の供給制約によって需要に対応して生産量を増やすことができず、デルタ株及びオミクロン株の感染拡大、中国ロックダウンといったタイミングで度々減少しては反発する動きを繰り返している。こうした中、大手自動車メーカーの計画では生産の回復が見込まれている一方、中国の感染再拡大の状況等も含めて供給制約の影響が再び強まる可能性も残されており、先行きの動向を注視する必要がある。
IC(集積回路)や液晶パネル等の生産を中心とする電子部品・デバイス工業は、2020年春の落ち込みも相対的に小さく、その後はコロナ禍における巣ごもり需要の増加、PCやスマートフォン関連の市場拡大などを背景に2022年初頭まで堅調に増加を続けた。しかし、2022年に入ってからは、中国ロックダウンの影響を受けた後、夏頃から弱い動きへと転じている。半導体に対するニーズは底堅い一方で、PC・スマホ向けを中心としたコロナ禍での生産の拡大局面は一服したものと考えられる。
生産用機械工業の生産は、2020年8月以降堅調に増加を続けており、とりわけ、2022年夏には伸び率をさらに加速させて増加した。特に、半導体製造装置や建設・鉱山機械の増加がけん引しており、半導体不足の状況下での供給能力向上の設備需要やインフラ投資需要など、世界的な需要の拡大を取り込んだ動きとなっている。また、我が国企業の設備投資の回復も生産の増加に寄与している。ただし、2022年の秋以降、中国ロックダウン後の急速な増加の反動もあり、生産の増勢は鈍化している。
また、こうした動きを財別にも確認する。先述した主要業種との関係では、輸送機械工業は、乗用車が専ら消費財に、エンジンやパーツ等を含めた自動車部品が生産財に分類され、電子部品・デバイス工業は生産財に、生産用機械工業は投資財に分類される。
コロナ禍前の2019年12月を基準として、それ以降の累積変化を3つの財別寄与に分解した図をみると、2020年にみられた鉱工業生産指数の持ち直しは、生産財と消費財のマイナス寄与が縮小していくことで生じた。2021年以降は、供給制約の影響に直面する中で、消費財のマイナス寄与が増減することによって生産全体が一進一退の動きとなった。2022年に入ってからは、中国ロックダウンの影響によって5月には消費財・生産財・投資財いずれもマイナスとなった。その後は、生産用機械に代表される投資財がプラスに転じたこと、また供給制約の影響が和らぐ中で輸送機械工業を中心に消費財・生産財のマイナス寄与が縮小されたこと等によって夏場まで増加がみられたが、秋以降は生産用機械の生産調整等の影響から投資財のプラス寄与が縮小している。(第3-1-2図(2))。
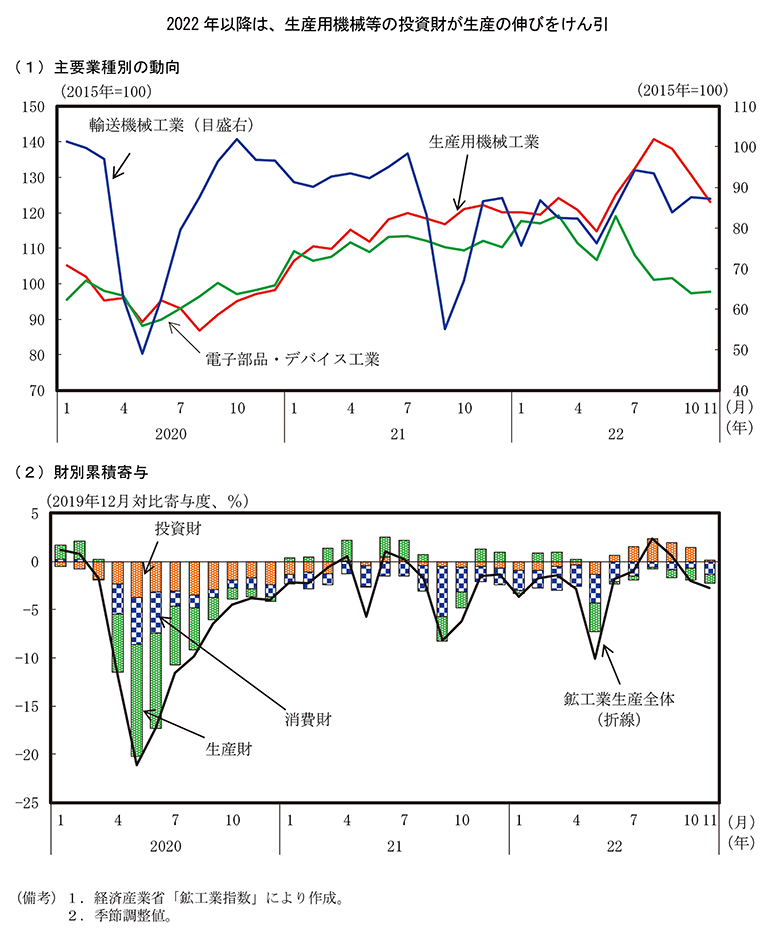
(輸出主導で生産が回復してきた中、今後の世界経済の動向に注視)
こうした製造業の生産動向は、我が国の輸出動向と連動している。
輸出数量指数をみると、自動車等の輸送用機器、半導体等電子部品や通信機等の電気機器及びエポキシ樹脂など半導体に必須となるプラスチック、半導体製造装置や建設・鉱山機械等の一般機械の動向は、鉱工業生産の主要業種別の動向と整合的であることが確認できる(第3-1-3図(1))。
これは、コロナ禍での鉱工業生産が、いち早く立ち上がる海外需要を取り込む形で回復してきたこと、また、我が国の輸出の根幹は輸送用機器や一般機械等が支えていることからも理解できる。
実際、鉱工業出荷の前年比に対する寄与度をみると、2021年は輸出向け出荷の寄与が高くなるなど、我が国の生産は輸出主導で回復してきた(第3-1-3図(2))。2022年以降は、我が国企業の設備投資の持ち直しが投資財の生産増加に寄与している面もあり、今後も企業の高い設備投資意欲の下で国内向け生産の回復が期待される一方、2023年は、世界的な金融引締めが続く中で海外景気の下振れ懸念が高まっている。欧米諸国において、金利上昇が資本財需要を下振れさせるリスクや、持続的な高い物価上昇率が消費や設備投資等を下押しする可能性も考えられる。こうした海外景気の動向が、我が国の輸出及び製造業の生産に与える影響、とりわけ、コロナ禍以降の生産活動の回復を支えてきた消費財や投資財への需要の動向には注意が必要であるといえよう。
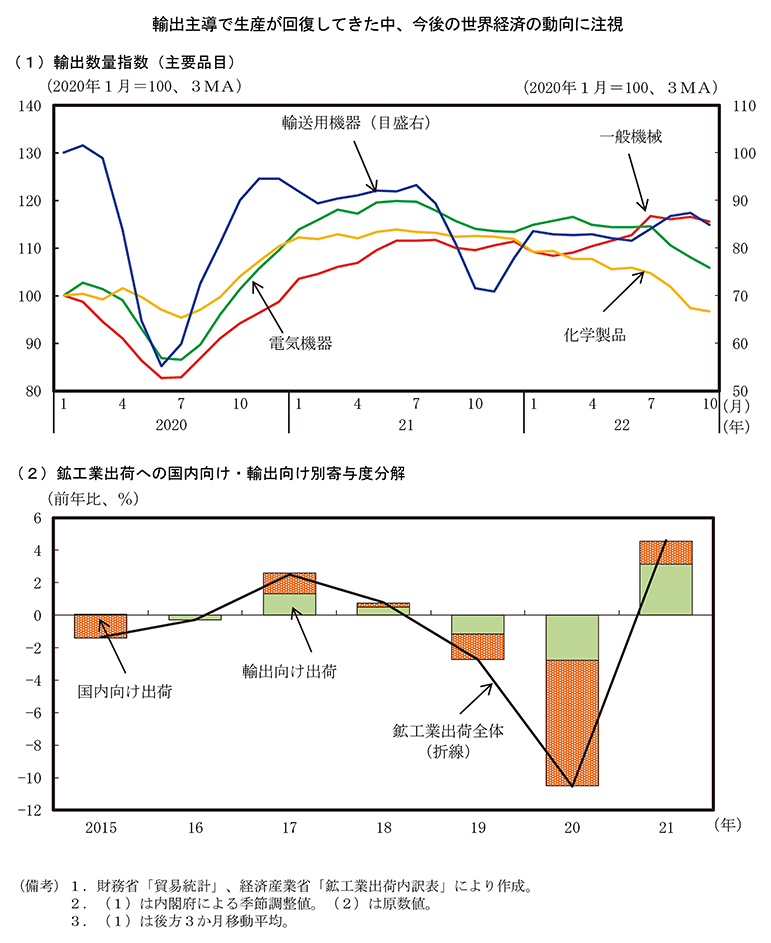
2 企業収益
(コロナ禍での企業収益の回復は製造業がけん引)
次に、企業収益の動向について、コロナ禍後の回復過程に注目しながら確認していく。
企業の経常利益は、2020年4-6月期に、我が国初の緊急事態宣言の下で大幅に減少した。経常利益の水準は、コロナ禍直前の2019年10-12月期に18.7兆円であったのに対し、2020年4-6月期は9.0兆円と半分以下になり、改めて新型コロナウイルス感染症の経済活動への影響の大きさを示す結果となっている。
しかしながら、前項でみた鉱工業生産と同様、その後の回復は早く、3四半期後の2021年1-3月期にはコロナ禍前の水準を上回るまで回復した。以降は、2021年半ばまでおおむね横ばい程度で推移したが、2021年末から再び増加基調となり、2022年4-6月期には過去最高水準となった1。2022年7-9月期は、前期比では僅かながらマイナスとなったものの、水準は高く推移しており、企業収益は総じてみて好調であるといえる(第3-1-4図(1))。
次に、こうしたコロナ禍での経常利益の回復を業種別に見てみよう。コロナ禍前を基準として経常利益の伸び率と業種別の寄与内訳をみると、製造業と非製造業とでは経済活動の制約の状況等を反映して回復過程に違いがあったことがわかる(第3-1-4図(2))。
まず、製造業では、2020年4-6月期に大きくマイナスとなった後、僅か2四半期後の2020年10-12月期にはコロナ禍前の水準を上回り、2021年前半までプラス寄与を拡大して推移した。これは、製造業の生産が海外経済を取り込んでいち早く回復したことと整合的であり、また、コロナ禍での巣ごもり需要もあり財消費が総じて堅調であったことも背景として考えられる。その後、2021年7-9月期には世界的なデルタ株の感染拡大による供給制約の影響からプラス幅を縮小したが、2021年10-12月期から2022年7-9月期までは、円安による利益の押上げもあり再びプラス幅を拡大しながら推移している。
一方、非製造業では、2021年7-9月期までコロナ禍前比でのマイナス寄与が継続している。2020年4-6月期と比べればマイナス幅を縮小させているものの、度重なる感染拡大と行動制限の下、飲食・旅行・娯楽などのサービスを中心に消費が抑制されてきたこと等により、コロナ禍前の水準回復には時間を要した。その後は、ワクチン接種の進展と感染拡大の落ち着きを背景にしたサービス消費の立ち上がりを受け、2021年10-12月期にコロナ禍前の水準を上回った。2022年以降は、ウィズコロナの下での経済社会活動の両立が進展したことに伴い、プラス寄与を維持して推移している。もっとも、年初と夏のオミクロン株の感染拡大時期にはプラス寄与の減少がみられており、感染状況によって経常利益に影響を受けるという構造自体は継続している。
このように、コロナ禍における企業収益の回復は製造業によってけん引されてきたといえる。
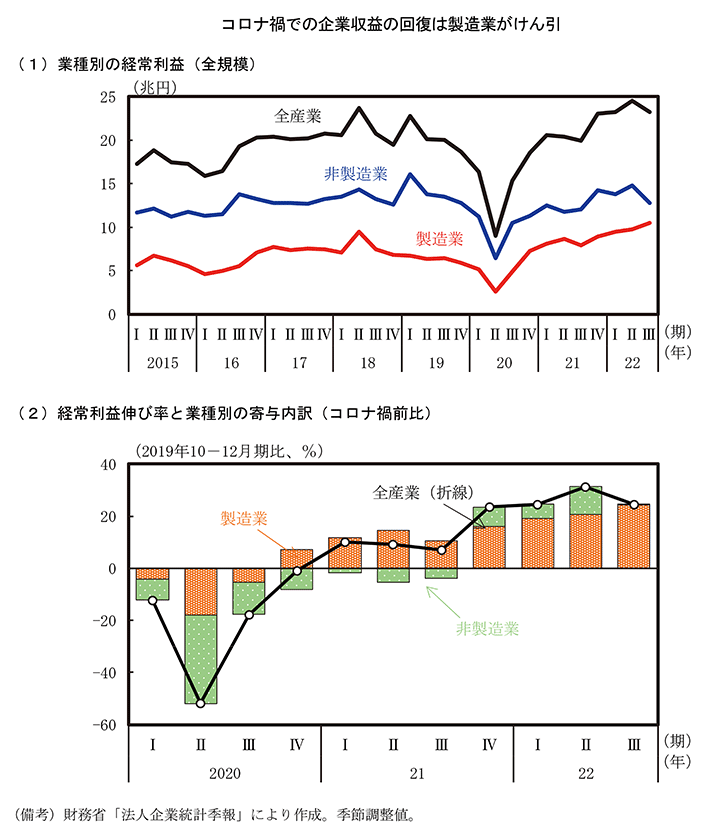
(中小企業では各種の支援策がコロナ禍での経常利益を下支え)
こうした経常利益の回復がどのような要因によってもたらされてきたか、業種別・企業規模別に見てみよう。
まず、製造業についてみていく(第3-1-5図(1))。大中堅企業では、コロナ禍前比でみた売上高要因のマイナス幅が徐々に縮小して2021年4-6月期にはプラスに転じ、その後もプラス幅を拡大して推移するなど、売上が早期に回復したことが大きな要因であったことがわかる。加えて、2022年以降は為替が円安に進んだことを背景に営業外収益要因のプラス幅も大きくなっている。一方の中小企業では、売上高要因がプラスに転じたのは2022年7-9月期であり、売上の回復に時間を要した。他方で、営業活動に係る費用の削減等によって固定費要因がプラス寄与となっているほか、持続化給付金2や事業復活支援金3等の効果もあり営業外収益もプラス寄与で推移したことにより、経常利益は2020年10-12月期以降プラスで推移している。なお、2022年度以降は、大中堅企業・中小企業ともに変動費要因が大幅なマイナス寄与となっており、原材料価格高騰に伴うコスト上昇が経常利益の圧迫要因となっている。
次に、非製造業の動向をみていく(第3-1-5図(2))。大中堅企業では、売上高要因は2020年7-9月期からの一年間で大きくは変化せず、経常利益もコロナ禍前の水準を下回って推移するなど、対面サービスなどを中心に感染症の影響を大きく受けてきた。その後、2021年10-12月期には、ワクチン接種の進展と感染状況の落ち着きを背景に売上高要因のマイナス幅は大きく縮小し、2022年以降はウィズコロナの進展の下でプラス寄与に転じており、その結果、経常利益もコロナ禍前の水準を回復した。また、2022年以降は、大手商社等の個社要因ではあるが、円安によって営業外収益要因のプラス幅が拡大している。一方、中小企業では、経常利益は2020年10-12月期以降、コロナ禍前比プラスで推移している。売上高要因は感染拡大の状況に応じて変化幅が大きく推移しながらも2021年7-9月期までマイナス寄与であり、経済活動が制限される中で売上が回復しない状況が続いた。他方、時短営業の実施等による固定費削減がプラスに寄与したほか、持続化給付金や事業復活支援金、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金4を活用した協力金等の支援策もあって営業外収益がプラス寄与となったことで、売上が低迷する中でも経常利益がプラスとなっていた。
このように、大中堅企業では、製造業が売上の回復を背景に経常利益を早期に回復させた一方で、非製造業では回復に時間を要するなど、先述した全規模の業種別動向と同様の構図となっている。中小企業では、製造業・非製造業ともに、売上高の回復には時間を要したものの、固定費の削減のほか各種の政策的な支援が相応の下支えとなって経常利益は早期にコロナ禍前比でプラスとなっており、コロナ禍での回復過程は業種や企業規模に応じてそれぞれ特徴あるものであった。
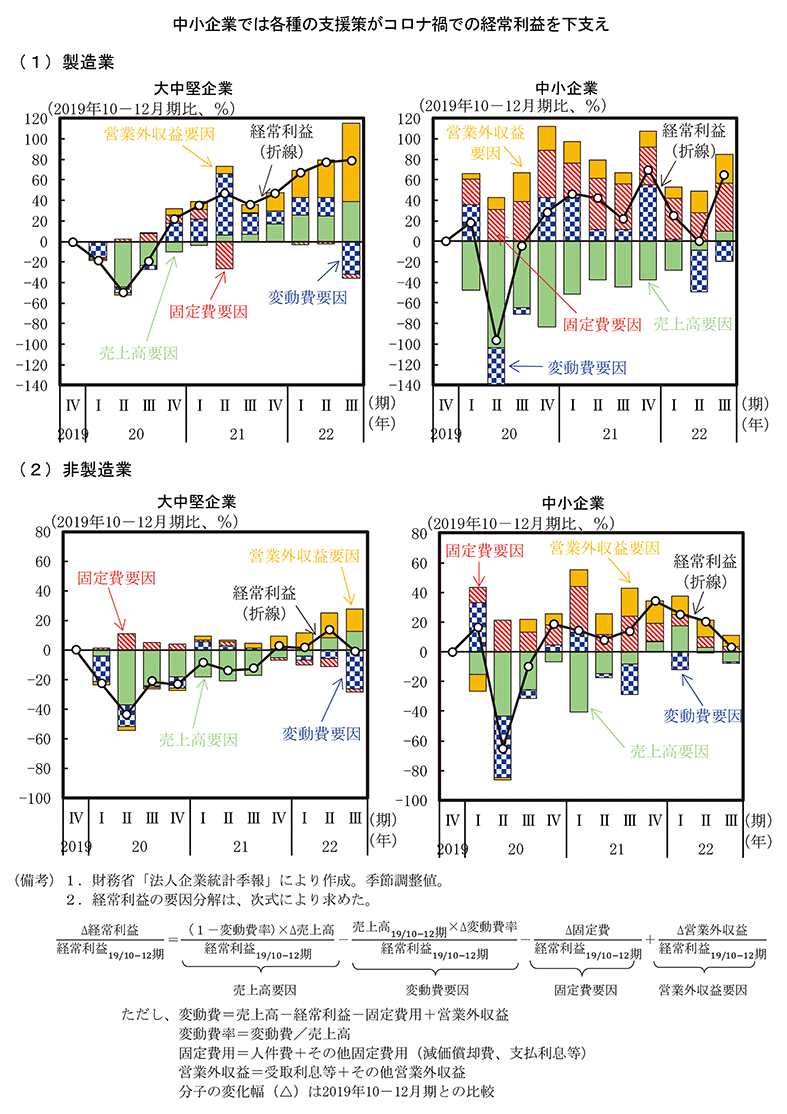
(大中堅企業では円安による収益増加が原材料価格高騰の影響を相殺)
最後に、原材料価格高騰に伴う企業収益への影響と、そうした影響への耐性を製造業で企業規模別に確認していく。具体的には、ロシアによるウクライナ侵略や円安の進行によって原材料価格の高騰に拍車がかかった後の状況をみていくため、2022年度上半期の売上総利益率(いわゆる粗利率)及び売上高経常利益率を確認する(第3-1-6図)。
製造業の売上総利益率を前年同期(2021年度上半期)と比較してみると、大中堅企業、中小企業ともに売上原価の伸びが売上の伸びを上回っており、その結果、売上総利益率の前年差はマイナスとなっている。企業規模にかかわらず、原材料価格の高騰によるコストの増加が収益を圧迫していることが確認できる。特に、中小企業では売上総利益率の悪化度合いが大中堅企業に比べて大きく、価格転嫁の環境が相対的に厳しい様子がうかがえる。
さらに、経常利益全体でみると、企業規模による差がより明確になっている。大中堅企業では、売上原価がマイナスに寄与する一方で、円安が進行したことに伴い、海外子会社からの配当金収入が円建てで増加したこと等により営業外収益等が大幅にプラス寄与となっており、その結果、全体としての売上高経常利益率の前年差はプラスとなっている。すなわち、原材料価格高騰の影響はみられるものの、それらのマイナスの影響は円安による収益増によって相殺されている。他方で、中小企業においては、販売管理費の抑制によって一部補填してはいるものの、大中堅企業に比べて売上原価のマイナス寄与が大きいことに加え、営業外収益等によるプラス寄与も小さく、売上高経常利益率の前年差はマイナスとなっている。
また、原材料価格高騰への耐性をいかに有しているかという観点では収益力が重要であるが、大中堅企業と中小企業との収益力の差は2000年代を通じて拡大している。売上高経常利益率の推移を企業規模別にみると、大中堅企業と中小企業との差は2000年初頭には僅か0.5%ポイント程度であったが、リーマンショック前には2.0%ポイント程度まで拡大し、その後、リーマンショックによる世界経済の需要減速に伴い一旦縮小したものの、2010年頃から両者の差は再び拡大している。特に2010年代後半以降は、2020年のコロナショックの影響を除き、中小企業がおおむね横ばいで推移しているのに対し、大中堅企業では上昇を続けており、その結果、2022年7-9月期時点の差は4%ポイント弱まで拡大している(第3-1-7図)。
このように、現下の物価上昇に伴う原材料コストの増加は企業の収益の圧迫要因となっているが、影響の度合い及びそうした状況への耐性という面では、大中堅企業と中小企業とで大きな差があり、したがって、現下の状況は中小企業においてより厳しい状況となっているものといえる。
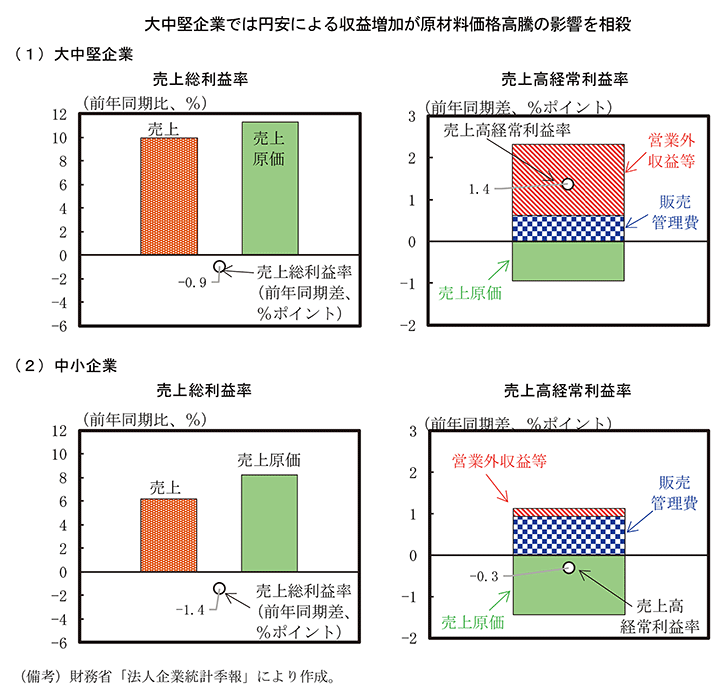
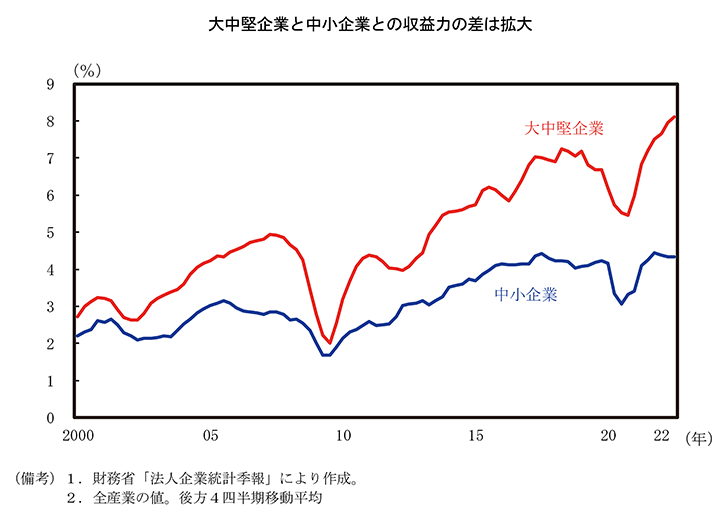
3 民間企業設備投資
(2022年度前半は、設備投資の回復に力強さ)
前項では、企業収益の回復状況をみてきたが、こうした収益の回復によって増加した現預金などの手元資金が、企業の成長につながる投資に向かっているかという観点で、民間企業設備投資の動きをコロナ禍以降の期間を通して振り返ってみよう(第3-1-8図(1))。設備投資は、2020年7-9月期に水準を切り下げ、年率換算の金額でコロナ禍以前の最高水準から9兆円以上のマイナスとなった5。その後は、2021年前半までは緩やかながら回復を続けたが、2021年7-9月期には世界的なデルタ株の感染拡大に伴う部材の供給制約に直面して再びマイナスとなり、その後も、特に実質ベースでは一進一退の動きとなるなど、回復が鈍い状況が続いた。しかし、2022年度(2022年4-6月期)に入って以降は、2四半期連続で高めの伸びでのプラス成長となった。その結果、2022年7-9月期6には、名目ベースでみればコロナ禍以前の最高水準(年率換算)を2兆円以上上回るなど、回復に力強さがうかがえる。
続いて、こうした設備投資の動向を性質別に確認してみよう。我が国の設備投資の約半分7を占める機械投資は、2020年8月を底として2021年夏頃まで増加を続け、その後、2021年後半には増勢が鈍化したものの、2022年以降は再び増勢が増している(第3-1-8図(2))。
設備投資の約4分の1を占める非住宅の建設投資について、先行指標である建築工事費予定額をみると、2022年の春頃を境に伸びを高めている(第3-1-8図(3))。用途別の動きもみると、工場等の製造業用や倉庫等の運輸業用のプラス寄与が高まっている。2021年には都市部の再開発等を含む不動産業用の寄与が高く、コロナ禍以降の回復をけん引してきたが、2022年の回復は、不動産業用の寄与が剥落する一方で、倉庫や工場の新設といった取組が出てきていることが特徴的である。
ソフトウェア投資は、増加傾向が続いている(第3-1-8図(4))。コロナ禍でのテレワークの進展やデジタル化の加速化などにより、総じてみれば2020年春以降の回復基調が続いている。
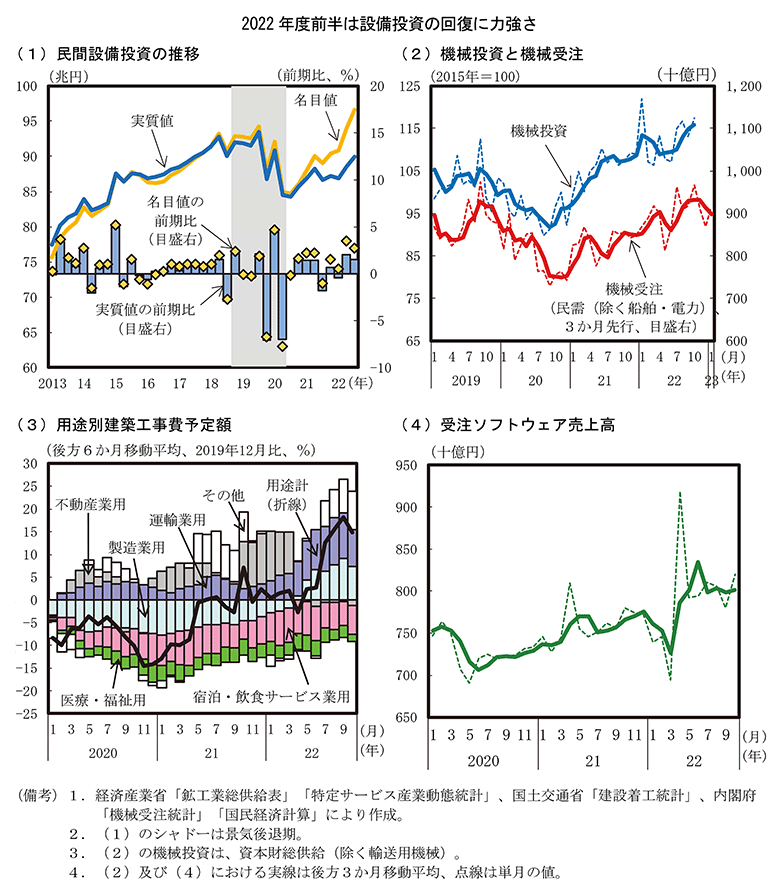
(2022年度の増勢は大中堅企業の動きによる)
次は、設備投資の動向を、企業規模別に確認する(第3-1-9図(1))。中小企業では2020年4-6月期に底をつけた後、2021年前半には既にコロナ禍以前の最高水準近くまで回復しており、その後はおおむね横ばいで推移し、2022年7-9月期に再び増加している。一方、大中堅企業も2020年4-6月期に水準を大きく切り下げたが、その後2021年後半までは、横ばいで推移し、2022年4-6月期になり、大きく増加に転じている。
業種別に2020年4-6月期以降の変化をみると(第3-1-9図(2))、中小企業では非製造業が一貫してプラス寄与を続ける中、製造業では2021年に入ってからプラスに転じている。一方、大中堅企業では、コロナ禍を通じて総じてみてマイナス寄与が続いていたが、製造業では2021年10-12月期から、非製造業では2022年4-6月期からそれぞれプラスに転じた。
このように、コロナ禍における設備投資は、中小企業においては早期に回復したのに対し、大中堅企業においては2022年度に入ってから本格的な回復が始まった。大中堅企業は2年にわたって設備投資を控えてきた中で、中小企業が支えてきたという構図の背景には、中小企業の設備不足がコロナ禍以前から大中堅企業に比べて大きかったことや、それまで遅れていたデジタル化への対応がコロナを契機に進展したこと8等が考えられる(第3-1-9図(3))。いずれにせよ、設備投資全体に占めるシェアは大中堅企業が高く、先述の2022年度に入ってからの設備投資の力強さは、中小企業のみならず、大中堅企業の設備投資の回復が始まったことによってもたらされていることが確認できる。
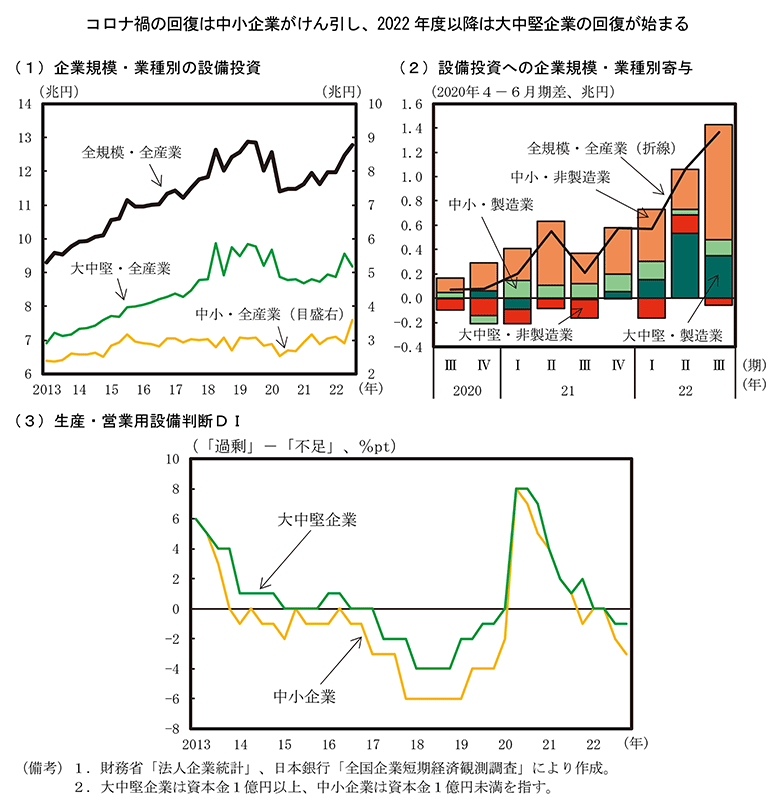
(大企業製造業の投資計画では、能力増強を中心にあらゆる動機での投資がプラス)
次に、日本政策投資銀行による大企業の調査から、設備投資の動機を目的別にみよう(第3-1-10図)。2020年度及び2021年度には、感染拡大の影響を受け投資が減少したが、中でも新商品・製品高度化や能力増強といった将来を見据えた攻めの動機による投資が大きくマイナスに寄与している。戦後最大ともいえるGDPの落ち込み、度重なる感染拡大によって先行きが見通せない中、企業が投資を手控えた様子がうかがえる。
一方で、2022年度の投資計画では、あらゆる動機での投資がプラスに転じており、中でも能力増強はコロナ禍での大幅なマイナスを取り戻すレベルとなっている。ワクチン接種の進展と医療提供体制の強化等を前提に、ウィズコロナの下、経済社会活動と感染拡大防止との両立が進んで経済が持ち直しに向かったこと、また、そうした中で、前項で述べた企業収益が堅調に推移したことなどが企業の先行き不透明感を和らげ、投資マインドを高める要因になったものと考えられる。
以上でみてきたように、コロナ禍以降の設備投資は、特に大中堅企業において能力増強等の攻めの動機による投資が先送りされてきたこと等により、2021年度までは鈍い回復であったが、2022年度に入ってからは、経済の持ち直しや堅調な企業収益等を背景に企業の投資マインドが高まり、回復に力強さがみられる。
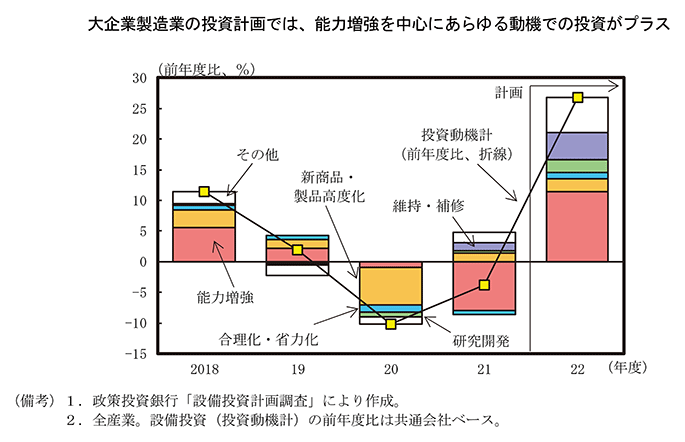
4 民間投資の拡大に向けた課題
(物価上昇の中、実質ベースの投資の回復ペースは名目ベースに比べ鈍い)
設備投資に本格的な回復がみえるまでは、初の緊急事態宣言によるショックから2年近い月日を要したが、この回復ペースを過去の景気局面(山⇒谷⇒山)と比較する。まず、名目ベースでの設備投資をみると、1997年第2四半期から2000年第4四半期までの景気局面と同様、比較的落ち込みが浅い段階で底を打ち、その後の回復は同期間に比べても早いペースで進んだことがわかる(第3-1-11図(1))。
一方で、実質ベースでみると、今回の回復過程は、2000年第4四半期から2008年第1四半期までの景気局面と同程度の回復ペースにとどまるなど、名目ベースとは異なる(第3-1-11図(2))。これは、過去の景気局面において設備投資が落ち込んだ期間は、総じて需給も緩和すると同時に為替増価の影響もあり、民間設備投資デフレーターの伸びがマイナスであった一方、今回は設備投資デフレーターの伸びがプラスになっていることによる(第3-1-11図(3))。このことは、今回の局面における大きな特徴であるといえよう。なお、設備投資デフレーターを形態別にみると、2021年以降はあらゆる分野で上昇しているが、中でも、木材や鋼材など世界的な資材価格の上昇を背景に、住宅以外の建物・構築物のデフレーターの伸びが高い(第3-1-11図(4))。
このように、コロナ禍における設備投資の回復過程は、企業が実際に投資を行う金額ベース(名目)でみると、過去の景気局面に比して早い回復が実現しており、水準でみても既に直近の景気の山の水準を回復している。一方で、その間に世界的な資材価格の上昇が進んだがゆえに、物価上昇の影響を除いたベース(実質)でみると過去に比べて回復が早いとはいえず、かついまだ直近の景気の山の水準を下回る状態にあるなど、回復は道半ばであるといえよう。
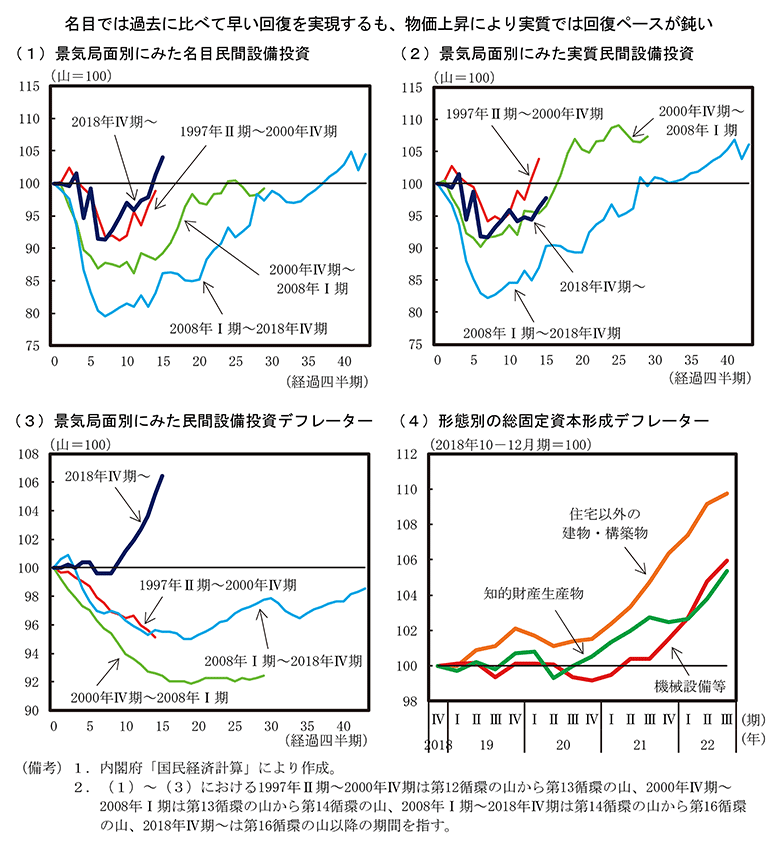
(コロナ禍からの回復過程で企業の予想成長率は上昇)
続いて、設備投資の時系列を踏まえた水準感を、資本ストック循環図9を用いて確認してみよう(第3-1-12図)。
資本ストック循環図に沿って企業の予想成長率の推移をみると、リーマンショックの後は2年近くマイナス1.0%の予想成長率に沿って推移していたが、その後景気回復が継続する中で、2011年10-12月期に0.0%の予想成長率まで回復した後、1年強その双曲線上で推移した。2013年以降は景気回復が継続する中で、企業は予想成長率を更に高めていき、2018年には1.5~2.0%の間で推移した。その後は、消費税率引上げと新型コロナウイルス感染症の影響で予想成長率は2020年には0.5%まで低下し、2021年は1.0%程度の双曲線上で推移していた。2022年度に入り、企業もソフトウェア投資やコロナ禍で先送りしていた能力増強投資などに積極的となった結果、右上方向への更なるシフトがみられ、2022年7-9月期には予想成長率として1.5%程度を見込んでいるものと考えられる。
このように、2022年度に入って以降の企業の設備投資の活発化の背景には、コロナ禍からの回復過程で企業が予想成長率を高めたことも挙げられるであろう。
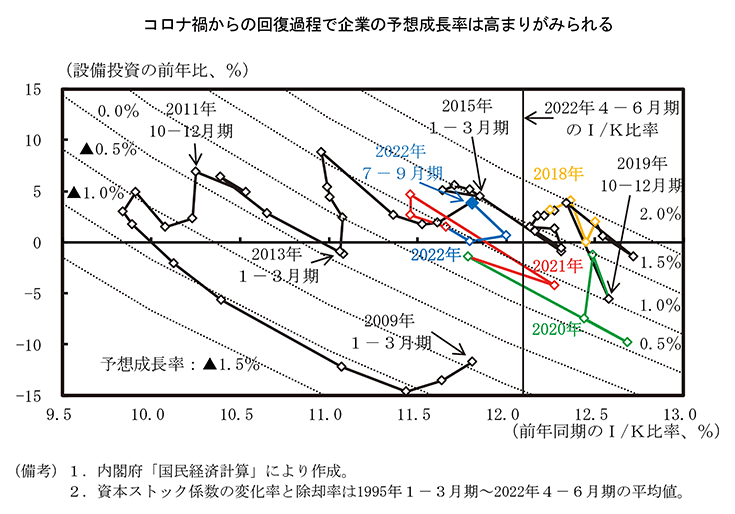
(成長に向けた投資喚起により、長年にわたる企業の投資姿勢の変革を)
実質ベースでみた設備投資の回復が道半ばであることは、直近の景気の山のレベルを回復するに至っていないという点のみならず、過去のトレンドで延伸した水準との比較をみれば一層明らかである。仮に、2015年以降の平均伸び率で設備投資が増加した場合と比較すると、直近の2022年7-9月期の設備投資はトレンドを年率換算で7兆円程度下回る水準にある(第3-1-13図(1))。
さらに、より長期的な視点から、企業の投資姿勢を検証するため、設備投資・キャッシュフロー比率を見てみよう。設備投資・キャッシュフロー比率は、1990年代半ばに100%を割って以降低下傾向にある。2010年以降は、新型コロナウイルス感染症による一時的な影響が生じた時期を除けば、総じて60%台で推移している(第3-1-13図(2))。
このように設備投資・キャッシュフロー比率が低く抑えられてきた状況は、我が国企業の投資姿勢が慎重であり続けてきたことを示唆している。企業が慎重な投資姿勢を続け、その裏で現預金を蓄積してきた背景には、長引くデフレの下で実質金利が高止まり、十分に収益性の見込める投資機会を見出すことができなかったことや、経済ショックへの備えなど様々であると考えられる。今後、我が国経済を持続可能で一段高い成長経路に乗せていくためには、こうした長期にわたる企業の投資行動を変えることができるかが重要であるといえよう。この点において、企業の期待成長率と設備投資見通しとの間には有意な相関関係がみられるところであり(第3-1-14図)、企業の期待成長率を高め、設備投資を引き出していくような政策的な後押しは意義のあるものとなろう10。令和4年10月28日に閣議決定された「物価高・経済再生実現のための総合経済対策」では、「官民連携による成長分野における大胆な投資として、科学技術・イノベーション、スタートアップ、GX、DXにおいて、呼び水となる官の投資を加速し、更なる民間投資の拡大を図っていく」こととしている。こうした対策が、成長分野における企業の予見可能性と期待成長率を高めて投資を引き出し、長年にわたる企業の投資行動を変革させる起爆剤として機能することを期待したい11。