第2章 個人消費の力強い回復に向けた課題(第2節)
第2節 労働市場の変化と賃上げに向けた課題
我が国は1990年代半ば以降の長引くデフレの下で、名目賃金が上がらない状況が継続してきた1。2000年代半ばまでには、企業部門はバブル崩壊後の課題であった三つの過剰(過剰債務、過剰設備、過剰雇用)を解消し財務体質の改善が進んだことや、2012年末以降のマクロ経済政策の転換を契機として、雇用環境の改善が進んだ。その結果、家計所得の低下に歯止めがかかり、各分野で良好な経済状況がみられるようになった2。しかしながら、前項で確認したとおり、我が国の家計消費は力強さに欠けており、コロナ禍以降の回復も緩やかである。さらに、足下の物価上昇を踏まえれば、消費の回復を継続していくためには、雇用・所得環境の更なる改善が不可欠である。本節では、こうした状況を踏まえ、感染拡大以降の我が国の労働市場の動向を整理するとともに、構造的な賃上げ環境の醸成に向けて検討するべき雇用政策を議論する。
1 足下の労働市場の動向
(経済社会活動が正常化に向かう中で、雇用環境は回復)
最近の労働市場の状況を概観するに当たり、まず、就業者数の動向を確認する。2020年の感染拡大以降、対面型サービス消費の減少等を背景に、非正規雇用者を中心に就業者が大きく減少したが3、その後、経済社会活動が回復する中で、人手不足感の強い医療・福祉業や情報通信業等を中心に就業者数は緩やかに増加している4(第2-2-1図)。非正規雇用者数についても2022年初以降は、対面型サービス業の業績の持ち直しもあり、緩やかに増加している。
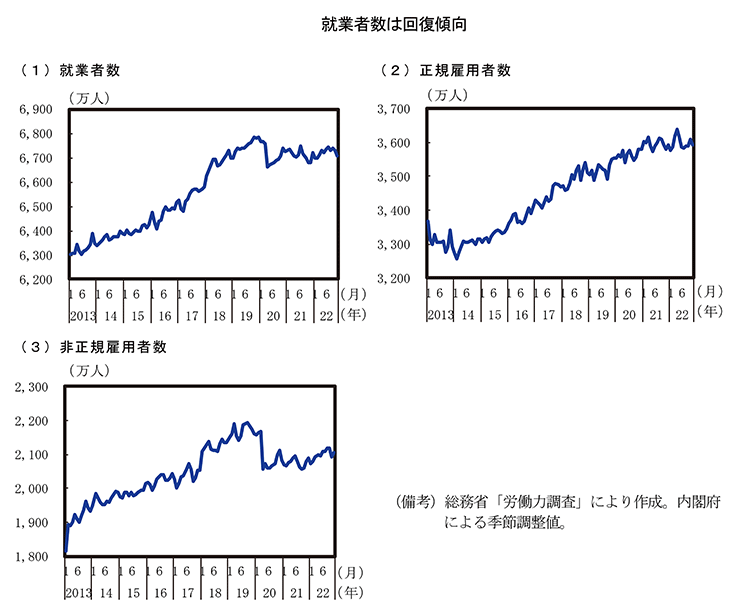
次に、労働需給の状況を確認する。まず、労働供給面の指標である労働力率の動向から確認する。労働力率は、我が国の15歳以上人口に占める労働力人口5(労働市場に参加している人口)の比率を示す。我が国の労働力率は、感染拡大を機に一時的に下落したが、2022年入り後は上昇傾向がみられる(第2-2-2図)。このように、労働供給が回復傾向にある中で、労働需要の改善に応じて上述のように就業者数が回復している。こうした推移の下で、労働力人口に占める失業者を示す完全失業率をみると、感染拡大後のピークでは3%を超える水準まで上昇したが、足下では振れを伴いつつも2%台半ばまで低下している。
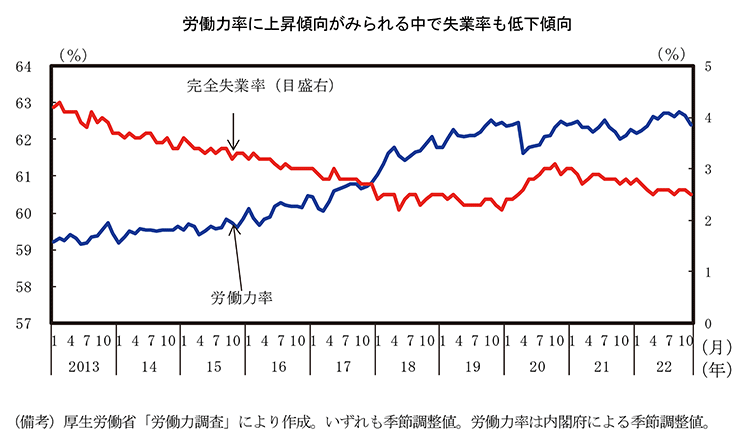
ここまでは人数ベースで労働市場の回復を確認してきたが、一人当たりの労働時間も加味した労働投入量の推移についても常用労働者を一般労働者とパートタイム労働者に分けて確認する。まず、一般労働者の労働投入量を雇用者数要因と一人当たり労働時間要因に分解すると、雇用者数は感染拡大下においても増加を続けた一方で、一人当たり労働時間が大きく減少したことから、2020年の労働投入量は減少した(第2-2-3図(1))。その後、2021年は一人当たり労働時間が持ち直すもとで、労働投入量は2019年を超える水準まで持ち直し、2022年は前年と同水準となっている。パートタイム労働者では、2020年以降は雇用者数の伸びが鈍化したほか、一人当たり労働時間も2020年に大きく減少した後にほとんど回復していないことから、労働投入量は2022年も感染拡大前を下回る状況が続いている(第2-2-3図(2))。
このように人数ベースでみると回復が鮮明な一方で、労働時間まで加味すると労働投入の回復ペースは緩慢である。一人当たり労働時間の減少は、ワークライフバランスの改善や労働生産性改善を企図して感染拡大前から推し進められてきた動きだが、感染拡大を機に労働時間が大きく減少し、その後の戻りも小幅にとどまっている。感染症による影響を除いても、労働時間の減少傾向が続いていると考えられるが、こうした労働時間の削減は、労働者の厚生や労働生産性の改善を伴って進むことが望ましい。
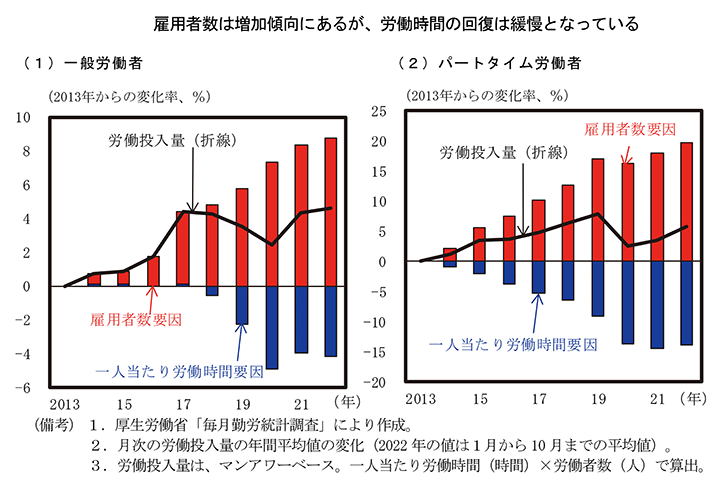
(労働需給が改善する中で、賃金も持ち直している)
上述したとおり、労働市場が全体として回復傾向にある中で、現金給与総額(労働者一人当たりの平均賃金)も持ち直している(第2-2-4図(1))。現金給与総額を、一般労働者の賃金の伸び、パートタイム労働者の賃金の伸び、パートタイム労働者の比率の三つの要因に寄与度分解すると、一般労働者とパートタイム労働者のいずれの賃金も上昇傾向にある中で、パートタイム労働者の比率の高まりがやや下押ししている(第2-2-4図(2))。
一般労働者の現金給与総額の動きを内訳別にみると、2021年以降は、経済社会活動の回復を反映し労働時間が持ち直していることから、残業代に相当する所定外給与の前年比プラス傾向が続いてきた。さらに、2022年入り後は、堅調な企業業績を反映して、所定内給与の前年比プラス幅が高まる中で、ボーナスを含む特別給与も伸びを高めている(第2-2-4図(3))。
次にパートタイム労働者についてみると、度重なる感染拡大による影響から労働時間の回復が遅れていることから、残業代に相当する所定外給与は2020年に下落した後に目立った回復がみられないが、2022年入り後には、休業等の影響を受けてきた所定内給与を中心に前年比プラス傾向が続いている(第2-2-4図(4))。
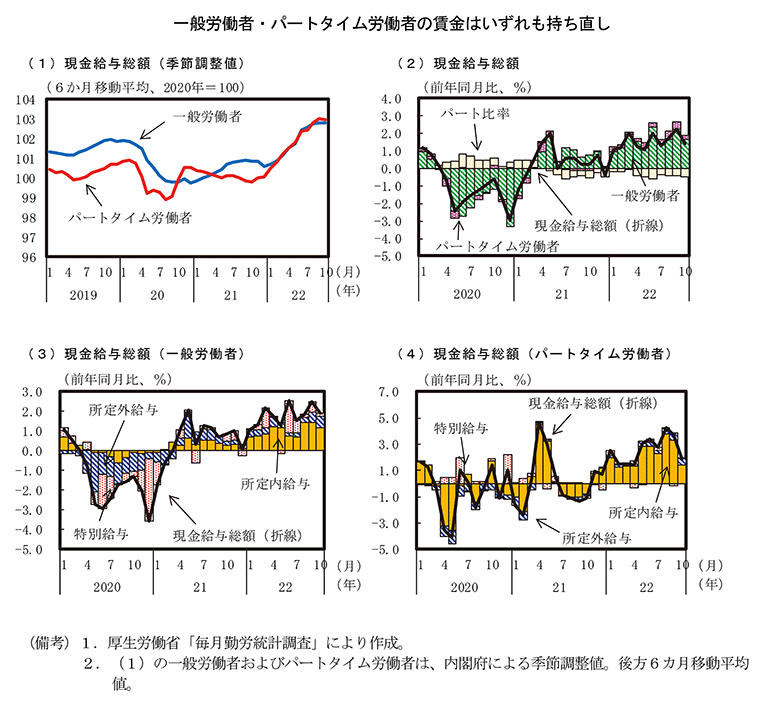
(実質賃金への交易条件の下押しが大きい中、労働生産性の引上げが急務)
このように、労働需給が改善する中で名目賃金は上昇傾向にあるものの、物価上昇を背景に実質賃金はこのところ弱含んでおり、第1章で論じたように、景気回復の足取りを確かなものとしていくためには実質賃金が上昇していくことが重要である。実質賃金の引上げに向けて重要な施策を考えるために、実質賃金(時間当たり)の変動を、労働生産性、労働分配率、交易条件、海外からの所得の純受取に要因分解してみよう(第2-2-5図)。足下の大きな動きとして、2021年後半~2022年にかけて、エネルギー・食料を中心とした輸入物価の上昇を背景に、実質賃金に対する交易条件悪化の下押し幅が拡大している点が指摘できる。すなわち、エネルギー・食料といった輸入品価格が我が国の生産する財・サービス対比で上昇したため、賃金の原資となる国内における付加価値への下押しが強まっている。また、企業収益が堅調に回復する中にあって、労働分配率要因も2021年以降は緩やかに下押し幅を拡大し、2022年には横ばいとなっている。この間、労働生産性要因は振れを伴いつつも横ばい圏内で推移しているほか、海外からの所得の純受取は緩やかにプラス方向に寄与を拡大させている。エネルギー輸入国である我が国は、資源価格が高騰する局面で交易条件の悪化が実質賃金の下押しに働くことは避けられず、中長期的にはエネルギー輸入依存度を下げていくことが肝心であるが、あわせて、こうした局面で賃金上昇率を高めていくには、人的資本投資の強化や労働移動の活性化を通じた労働生産性の引上げを図ることに加えて、物価動向や企業の事業環境とのバランスをみながら賃上げに向けた労使交渉が進められていくことも重要である。
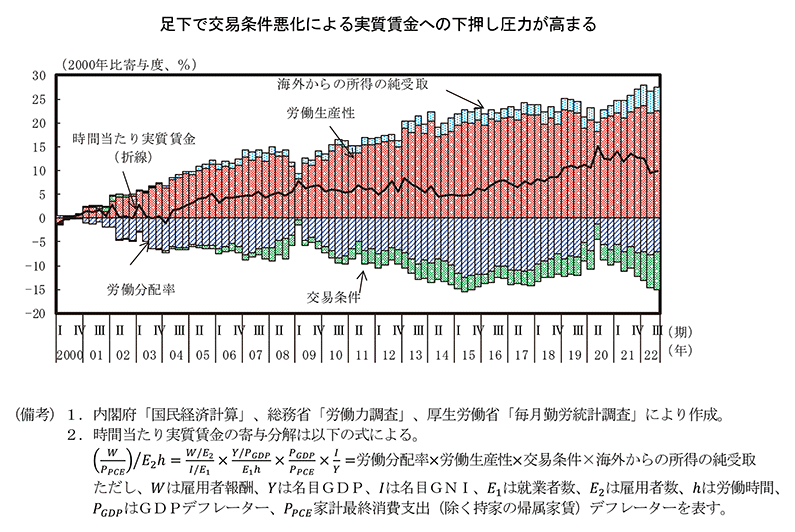
(幅広い世帯の賃上げの実現に向けて、非正規雇用者の増加も踏まえた施策が重要)
前述した賃上げ環境の整備においては、前掲第2-2-2図のとおり労働力率が高まる中で、非正規雇用者の割合が高まるなど働き方の多様化が進んでいることにも留意する必要がある(第2-2-6図(1))。非正規雇用者の割合は、感染拡大後に幾分低下しているが、依然として雇用者の4割弱を占めている。非正規雇用者比率を年齢階層別にみると、高齢者(60歳以上)では感染拡大前の2019年まで上昇傾向がみられる中で、若年層(20~39歳)や中年層(40~59歳)では、2013年以降は低下傾向となっているが、こうした現役世代でも引き続き3割弱が非正規雇用者となっている(第2-2-6図(2))。さらに、世帯主の雇用形態の推移をみると、非正規雇用者の比率は上昇傾向にあり、2021年には二人以上世帯の世帯主で2割弱、単身世帯で3割弱を占めている(第2-2-6図(3))。非正規雇用に初職で就くと、40~50代になっても男性では3割以上、女性では7割以上が非正規雇用形態にあるなど、非正規雇用に一度就くと、スキルの蓄積が進みにくいこともあり、固定化しやすい傾向がある6(第2-2-6図(4))。
こうした状況を踏まえ、第3項では、構造的な賃上げに向けた課題について、正規雇用者だけではなく非正規雇用者も併せて分析対象としている。
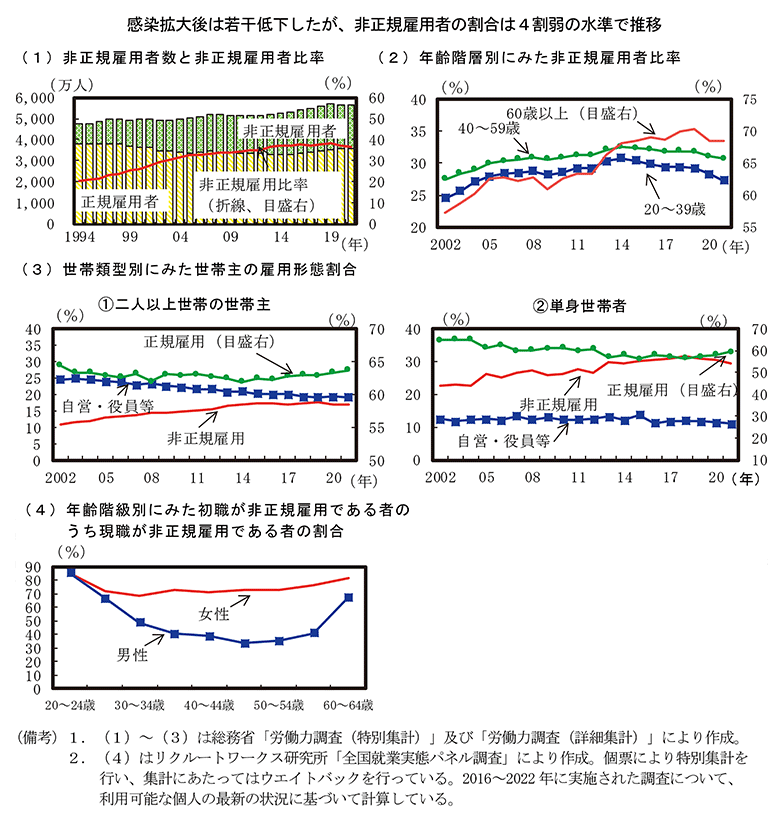
(賃金の水準について、同一雇用形態の中でのばらつきの拡大はみられない)
本項の最後に、賃金分布の推移について、正社員・短時間労働者別に確認する。具体的には、正社員の所定内給与、短時間労働者の所定内時給について、2010年以降、90%分位点(上位から数えて10%に位置する労働者の賃金)と10%分位点(下位から数えて10%に位置する労働者の賃金)の幅に拡がりがあるか、また両端の分位点と50%分位点(中央値)の距離に変化がないかという観点から分布の形状をみると、正社員・短時間労働者とも分布の拡がりは確認されない7(第2-2-7図)。
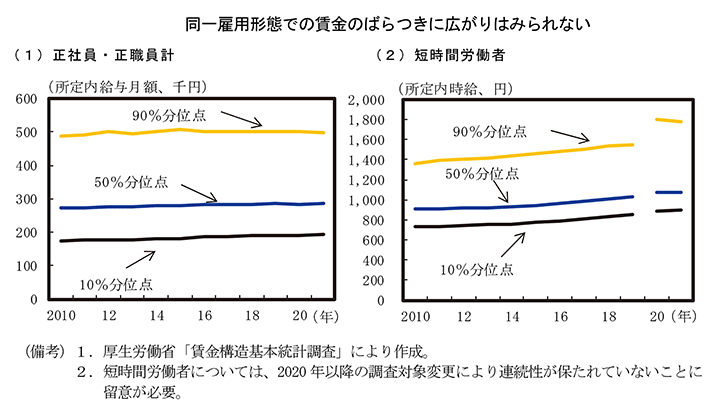
2 労働需要・労働供給別にみた構造変化の可能性
(省人化による労働需要の変化の可能性)
上述したとおり、労働市場は全体として持ち直しが続いているが、その様態はコロナ禍を経て、少なくとも一部で変化している可能性がある。本項では感染拡大を受けた企業(労働需要側)、家計(労働供給側)の労働市場における行動変化について、今後の持続性に留意しつつ整理する。
まず、企業の新たな労働需要を示す新規求人数をみると、製造業・非製造業供に2020年以降は回復が続いてきたが、足下では一服感がみられる(第2-2-8図(1))。特に、製造業では既に感染拡大前(2020年初)を上回る水準を回復しているが、非製造業では感染拡大前を依然として下回る水準にある。足下の新規求人数と各産業の労働集約度(ここでは、就業者一人当たりの経常利益で計測。)の関係でみると、緩やかではあるが労働集約度が高いほど新規求人の減少幅が大きい傾向があり、特に小売業や飲食サービス業などの労働集約度の高い一部の非製造業で新規求人の水準が感染拡大前を大きく下回っている(第2-2-8図(2))。小売業や飲食サービス業などの労働集約度の高い産業は、利益ベースでみたシェア対比で、就業者ベースでみたシェアが大きい(第2-2-8図(3))。また、一部の接客業務などは雇用者に事前に求められる専門的なスキルが比較的少なく、アルバイトなどの非正規雇用の受け皿となってきた。すなわち、こうした業種・職種は、労働需要量が大きく、相対的に低賃金の雇用機会を供給してきたことから、そうした業種や職種の労働需要に変調が生じた場合には、高齢者・学生や短時間労働を望む主婦パート等の労働参加機会への影響が特に大きいと考えられる。
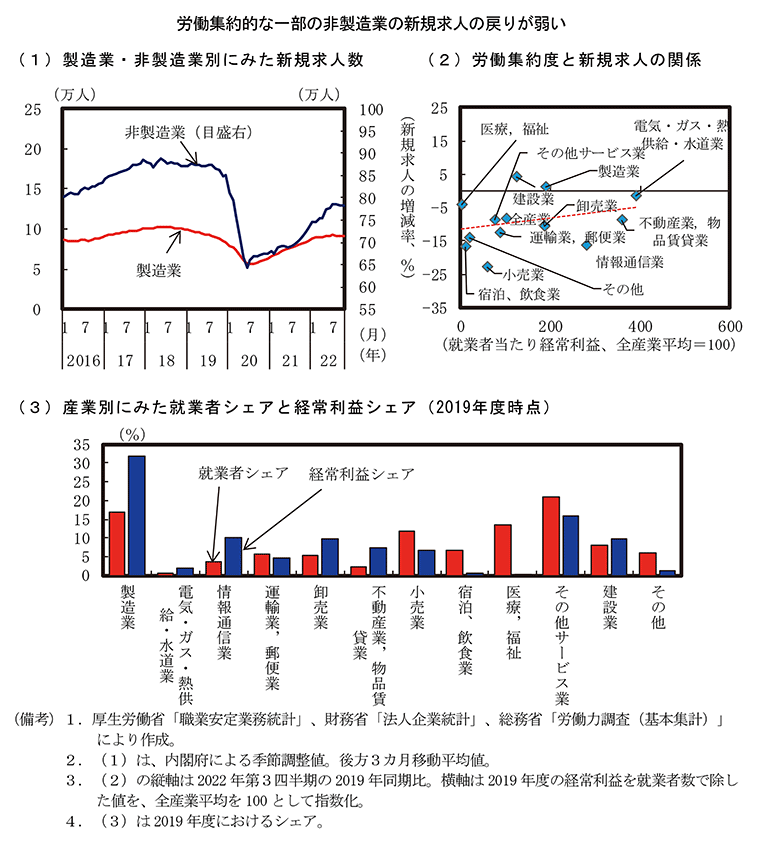
こうした労働集約度の高い業種には、2020年以降、感染拡大による業績の下押しが繰り返し強まってきた企業が多く、感染の影響が完全には収束しない中で採用スタンスが他業種に比べ保守化している可能性も考えられる。また、非製造業の店舗における省人化投資等の拡大により、労働需要が変化している可能性も指摘できる。例えば、スーパーマーケットにおけるセルフレジの導入は、感染症に対する防疫手段として急速に進んだ(第2-2-9図(1))。こうした中で、中堅・大企業の従業員一人当たりの経常利益をみると、小売業や飲食サービス業を含む非製造業で幅広く改善がみられており、足下では感染拡大前を上回っている(第2-2-9図(2))。
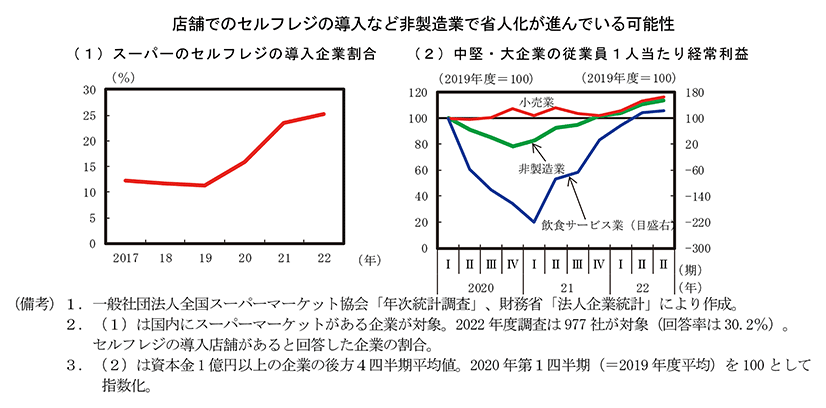
ここでみた労働需要の変化が構造的なものであるのか断定するには時期尚早と考えられる。しかし、コロナ禍を契機に比較的定型的な業務の一部が機械に置き換わったこと等により、労働需要の動向が変化していく場合には、労働者に求められるスキルも変化すると考えられる。
(雇用調整助成金による雇用保蔵が求人に影響を及ぼしている可能性)
また、労働需要の面では、休業措置により雇用維持を図る企業に対する雇用調整助成金の特例措置の導入等の政策支援の効果もあって、感染拡大の影響が大きかった業種でも雇用が一定程度維持され、失業率の抑制につながってきた(前掲第2-2-2図)。実際、雇用調整助成金の支給決定件数を業種別にみると、「飲食店」や「宿泊業」など、感染症による売上減少の大きい業種を中心に活用されてきた(第2-2-10図(1))。こうした政策は、感染拡大以前から存在した構造的に人手不足が継続することへの企業の意識もあいまって、感染拡大以降の企業の雇用保蔵8につながっていたと考えられる。ただし、ウィズコロナの取組が進む下で制度利用の申請件数は減少傾向にある。雇用調整助成金の毎月の支給決定額を毎月勤労統計の定期給与で除すことにより、簡易的に支給対象延べ人数を試算すると、2020年8月のピークと比較して、足下の人数はおよそ1割程度まで低下している(第2-2-10図(2))。支給延べ人数の試算値が労働力人口に占める割合をみると、2020年のピークである8月には3.6%と相応に失業率の抑制に寄与してきたが、2021年を通じて1%台で推移し、直近の2022年9月では0.4%となっている(第2-2-10図(3))。既に本制度の支給人数から試算される直接的な失業率の押下げ効果は相当小さく、特例措置の終了も2023年1月末に予定されているが、感染症下で続いてきた雇用保蔵が、上述した一部の非製造業の求人の水準が感染拡大前に届かない背景の一つとなっている可能性がある。一方、前掲第2-2-9図(2)でみたように、非製造業の中堅・大企業の一人当たり経常利益水準は既にコロナ前を超えており、今後の労働需要の動向が注目される。
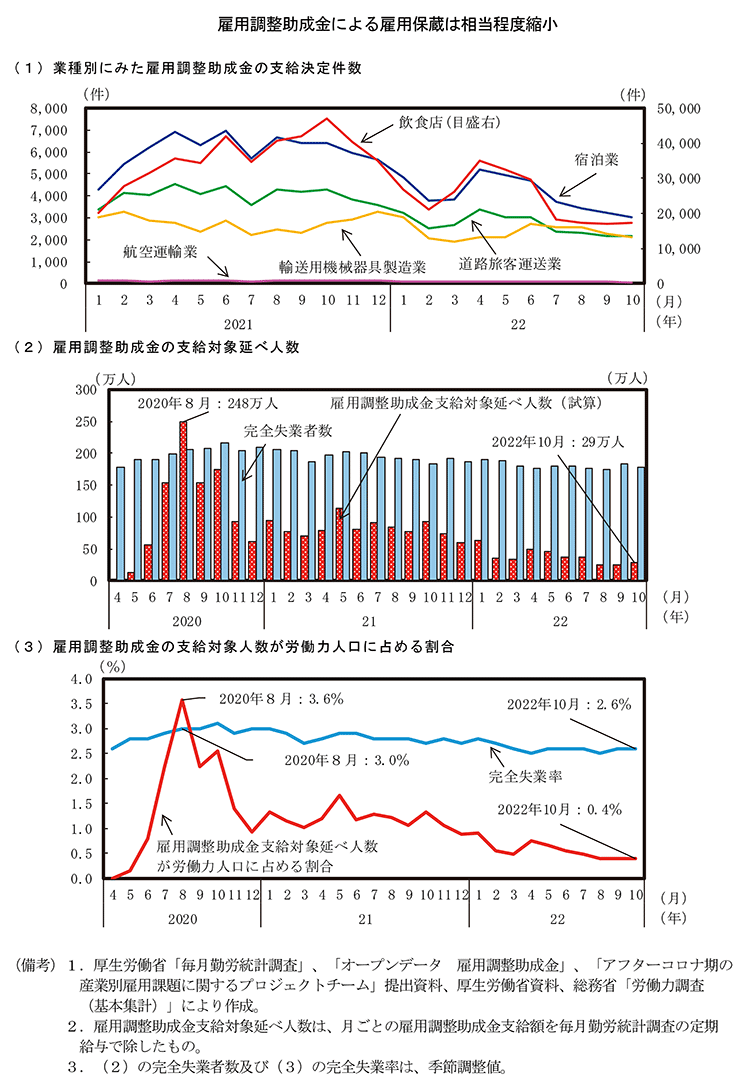
(正規・非正規間での処遇面での差は拡大)
非正規雇用者と正規雇用者間の処遇差については、同一労働同一賃金を義務付けるパートタイム・有期雇用労働法が2020年4月から大企業で、2021年4月から中小企業で適用されるなど、縮小に向けた取組が進んできたことにより、賃金面では縮小傾向にある9。他方、賃金以外の面では、感染拡大を契機に正規雇用者を中心にテレワークなどの柔軟な働き方が広がったことを受けて、正規雇用の優位性が高まった可能性がある。民間アンケートの結果をみると、感染拡大前と比較した勤務日の柔軟性は、非正規雇用者では多くの業種・職種で改善したと回答した割合が低下しているが、正規雇用者では総じて低下幅が軽微であり、むしろ改善した業種も散見される(第2-2-11図(1))。さらに、勤務時間の柔軟性・働く場所の柔軟性についても、非正規雇用者では改善したと回答した割合が低下した業種・職種が目立つが、正規雇用ではむしろ改善したと回答した割合が上昇した業種・職種が多い(第2-2-11図(2)、(3))。テレワークの導入状況の差をみても、正規・非正規の間で開きがあり、上述したような働き方の柔軟性の差につながった可能性がある(第2-2-11図(4))。
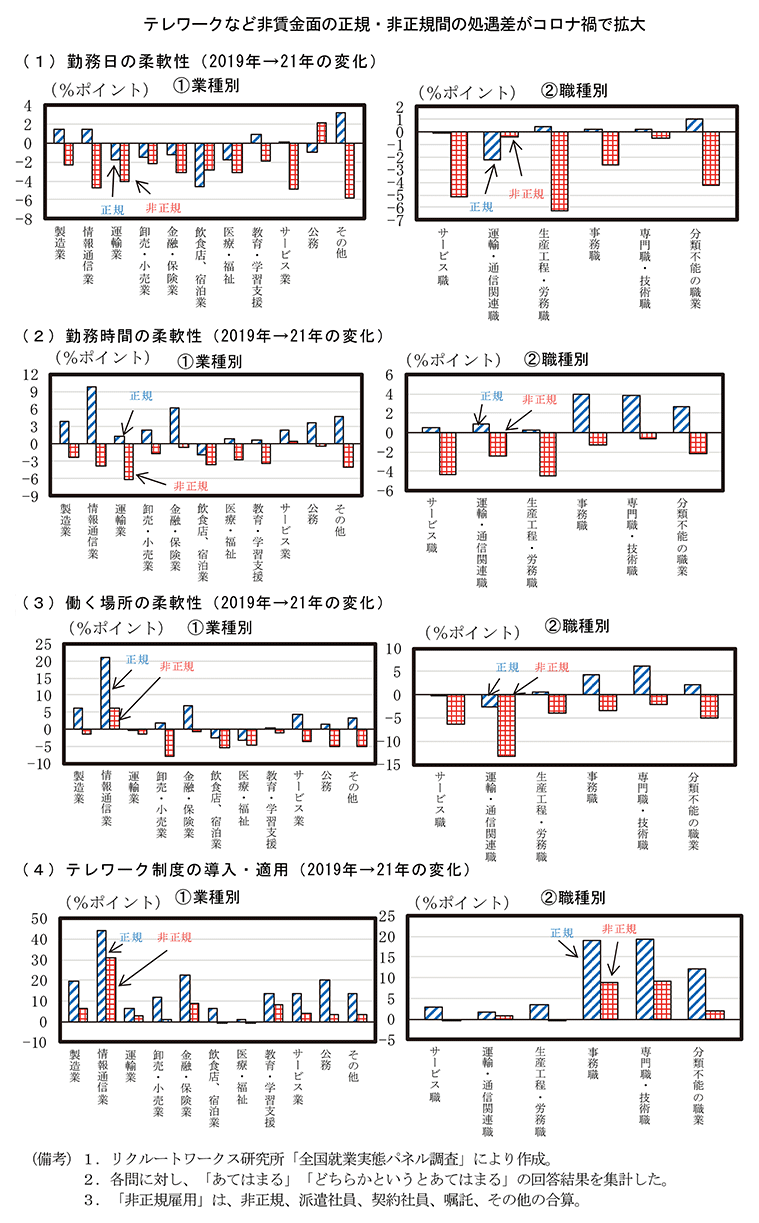
(ミスマッチを背景とした長期失業者の滞留)
厚生労働省「職業安定業務統計」を用いて、求人・求職の動向をみると、感染拡大を受け有効求人数は大きく下落した後に持ち直す中にあって、有効求職者数は高止まりしている(第2-2-12図)。この間、求人の充足率が低下する中で、求職者の就職率も感染拡大以降低下したまま推移し、求人と求職のミスマッチが大きくなっている可能性が示唆される(第2-2-13図)。
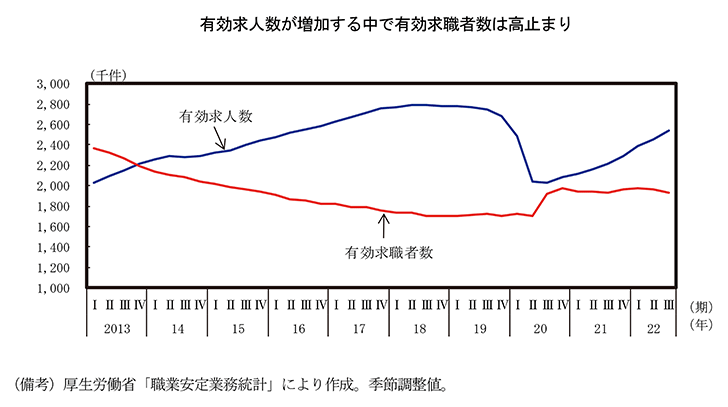
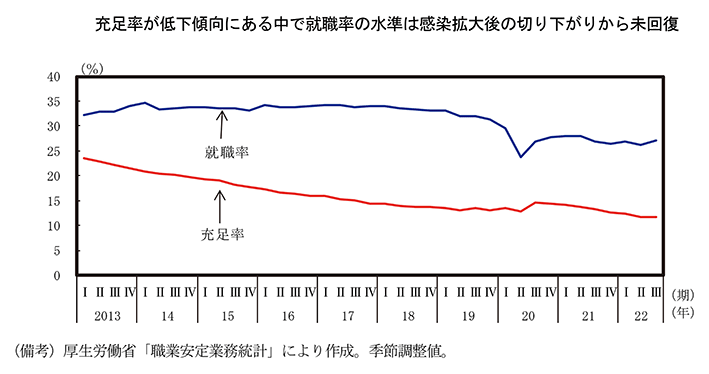
実際、失業者数の水準が足下でも感染拡大前を上回っている(第2-1-14図(1))。失業期間別にみると3カ月未満の短期失業者数では感染拡大前と比較して大きな変化はみられないが、1年以上の長期失業者数は幅広い年齢層で増加が顕著であり、2022年の水準は感染拡大前を2割以上上回っている(第2-1-14図(2))。
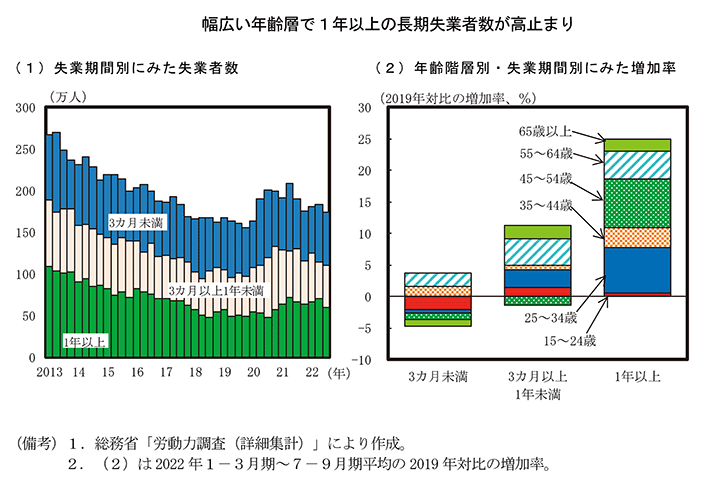
失業者が仕事を見つけられない理由について、総務省「労働力調査」を用いて、2019年からの変化をみると、「賃金・給料が希望とあわない」や「勤務時間・休日などが希望とあわない」の割合が低下している。その一方で、「希望する種類・内容の仕事がない」の増加が顕著であり、待遇ではなく職務内容のミスマッチが失業増加の要因となっている可能性がある(第2-2-15図)。
また、求職活動をしていない者にその理由を尋ねた結果についても感染拡大前からの変化をみると、「健康上の理由のため」と感染リスクを考慮した動きや「今の景気や季節では仕事がありそうにない」と景気動向を挙げる声もあるが、「自分の知識・能力にあう仕事がありそうにない」とミスマッチを理由に非労働力化した層も増加していることが分かる(第2-2-16図)。
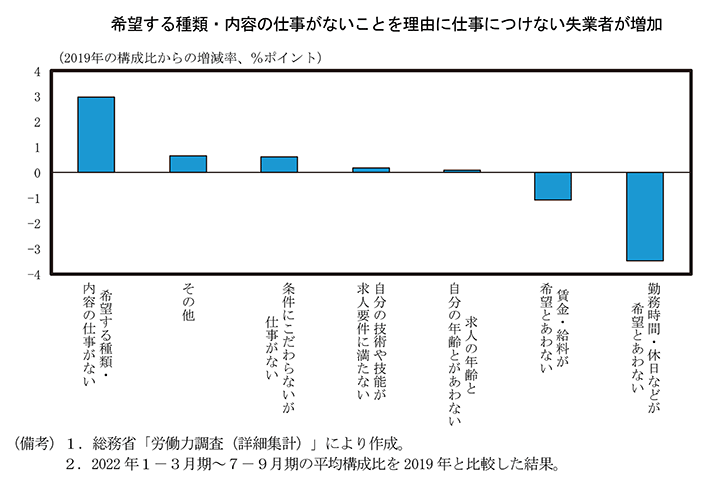
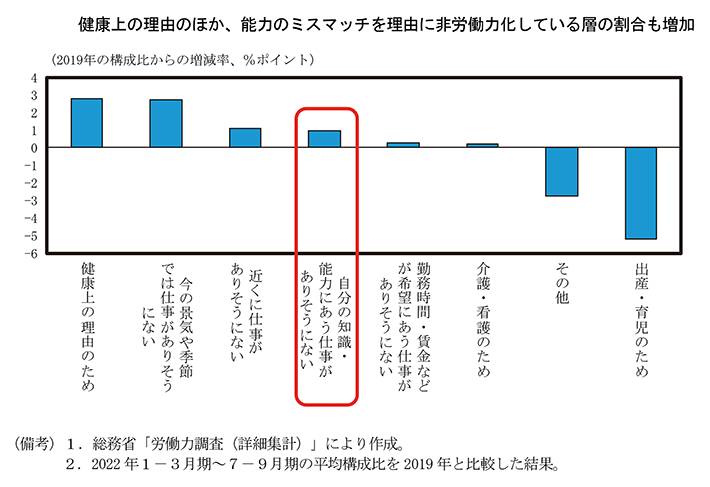
(高齢者の雇用者数の増加ペースの鈍化)
さらに、働き方改革等を背景に、高齢者の雇用機会の確保が進む中10、2010年代以降は65歳以上の高齢者の労働参加が進んできたが、感染拡大以降は増加ペースに鈍化が見受けられる。まず、同一世帯を2か月連続で調査する総務省「労働力調査」のデータを活用し、全年齢で就業状態の変化の割合を示す遷移確率を算出する(第2-2-17図)。様々な状態遷移パターンの感染拡大前と足下の水準の乖離をみると、特に「就業者から非労働人口」の遷移確率の上昇が目立つ。これは、高齢者就業が促されたことから感染拡大前は低下傾向にあった同遷移確率が、高齢者の継続就業などが鈍化したことで、感染拡大以降は上昇に転じていることによるとみられる11。また、「失業者から就業者」の遷移確率は感染拡大前対比で低下しており、前述したミスマッチによる失業増加を背景とした動きとみられる。
これを踏まえて、65歳以上の高齢者の労働力率をみると、感染拡大後の増勢鈍化が目立つ(第2-2-18図(1))。ただし、65歳以上の高齢者を「65歳~69歳」「70歳以上」別に分けて労働力率をみると、こうした鈍化は明確には観察されず、年齢階級別の構成変化の影響が大きいと推察される。実際、高齢者の年齢階級別の構成割合の推移をみると、60代の割合が低下する中で、70歳以上の人口の割合が高まっている(第2-2-18図(2))。こうした中で、雇用形態別に65歳以上の雇用者数の推移をみると、「パート・アルバイト」を中心に、2020年以降増勢鈍化がみられる(第2-2-18図(3))。ただし、前掲第2-2-18図(1)でみたとおり、高齢者についても年齢階級を子細にみれば労働力率は高まり続けており、引き続き就業を希望する高齢者の雇用確保を進めることが重要である。
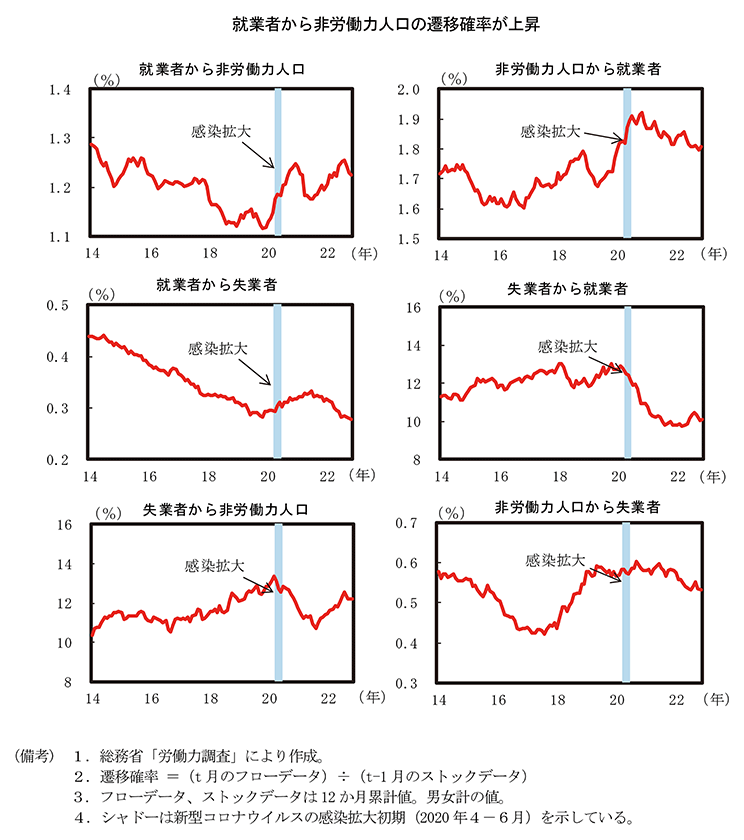
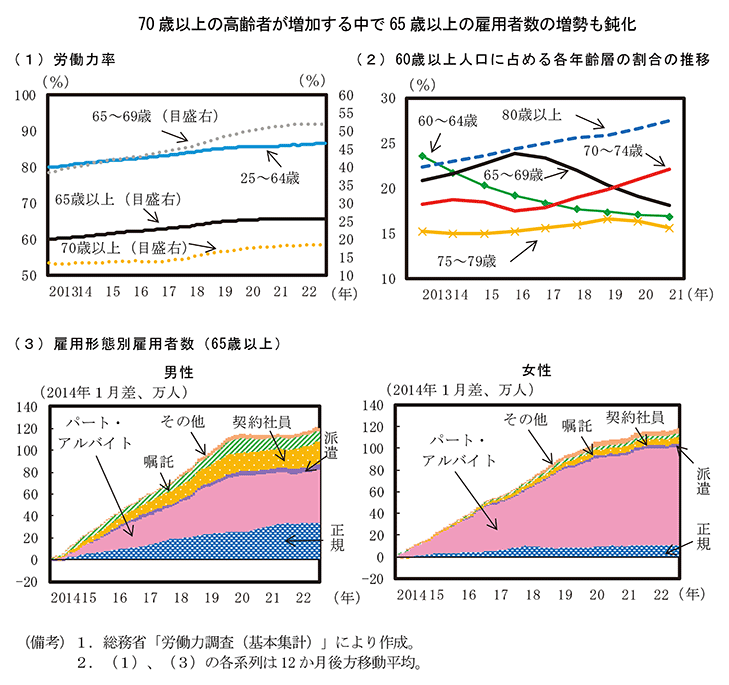
3 構造的な賃上げに向けた課題
(国際的には労働移動の円滑度が高い国ほど実質賃金上昇率が高い傾向)
労働生産性の伸びを高め構造的な賃上げを実現していく手段の一つとして、適材適所を推し進めながら、成長産業の雇用が拡大していく形で労働移動を促す必要性は高いと考えられる。
先行研究では、国際的にみると、労働移動の円滑化が高い労働生産性などの良好な経済パフォーマンスにつながる傾向が報告されている12。ここでは、OECDが公表している各国の「短期失業者数(求職期間1年未満)/長期失業者数(求職期間1年以上)」を、労働移動の円滑度を表す指標として、実質賃金上昇率との関係を確認する(第2-2-19図)。この指標は、失業者に占める長期失業者の割合が低いほど、失業を介した労働移動が円滑であると評価するものであり、労働市場のミスマッチの大小を測る概念の一つと考えられる。結果をみると、長期失業割合の高低でみた労働移動の円滑度が高い国ほど、実質ベースで賃金が上昇しやすい傾向が緩やかながらも観察された。こうした中で、我が国の労働移動の円滑度と実質賃金上昇率はいずれもデータが入手可能なOECD加盟国の平均を下回っているものの、両者の関係はおおむねOECD諸国並みと評価できる13。
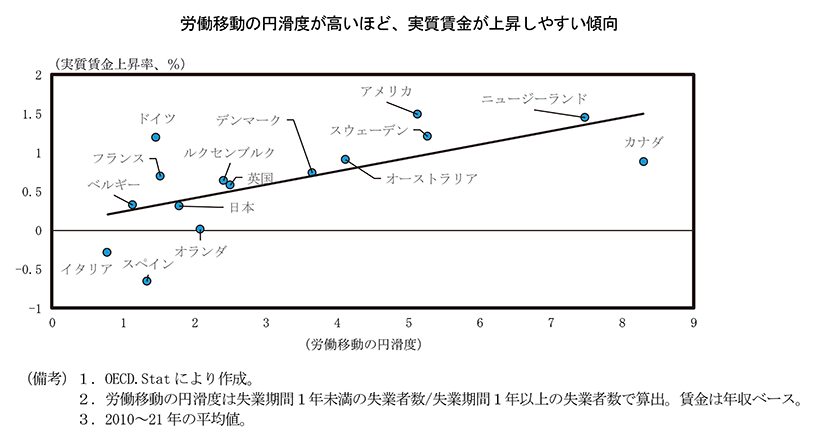
(感染拡大後に若干弱まった正規間転職、非正規の正規化には持ち直しの動き)
では、足下で、我が国の労働移動は活発化しているのであろうか。労働移動の円滑度には様々な指標が存在するが、以下の分析では主に転職者割合を用いる。具体的には、総務省「労働力調査」を用いて、過去1年以内に勤め先の変更を行った者が雇用者全体に占める割合を、転職者割合と定義する。2012年以降の転職者割合を総数でみると、2019年にかけて緩やかに上昇した後に、2020年から2021年にかけて低下し、2022年入り後は横ばいで推移しており、全体としては活発な状況にあるとは言い難い(第2-2-20図(1))。ただし、年齢階級別にみると、25~34歳や35~44歳といった若年層の転職者割合では、2022年入り後に持ち直しの動きがみられている。
次に、労働移動の内訳をみるため、主要な就業形態である正規雇用者・非正規雇用者・自営業者別に、就業形態内及び就業形態間の移動の動向をみる。正規間転職は2010年代には緩やかに増加傾向にあったほか、非正規雇用の正規化の動きは同期間に横ばい傾向で推移したが、2020~21年にかけて、正規間転職・非正規雇用の正規化の動きは若干弱まった(第2-2-20図(2))。2022年入り後は、いずれも持ち直しの動きがうかがわれており、こうした労働移動の回復が、雇用者の処遇改善につながっていくことが期待される。
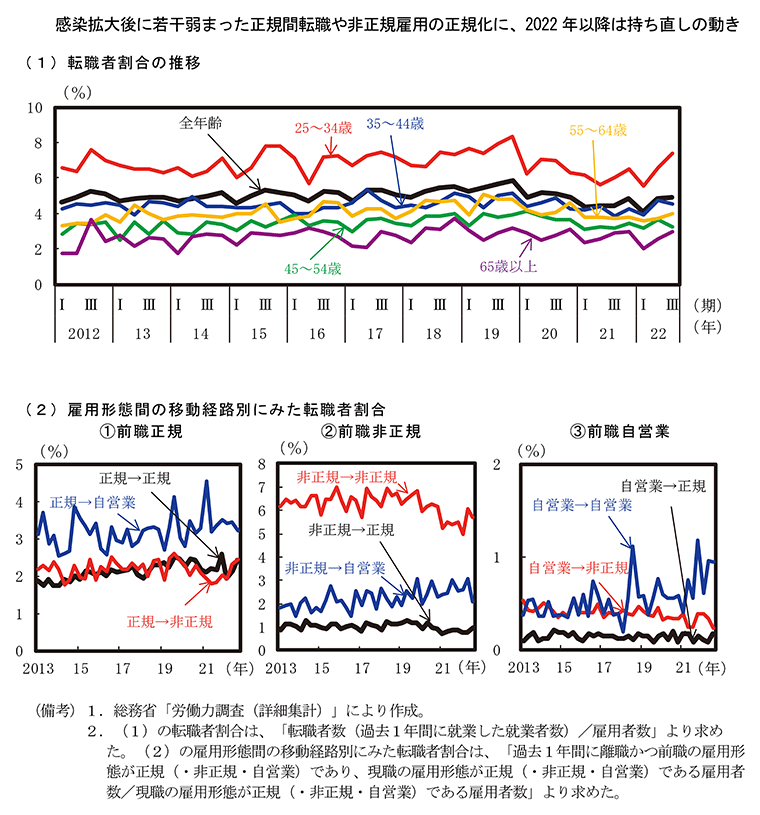
(若年層を中心に転職後に賃金が増加した労働者の割合は増加傾向)
次に、転職者の賃金動向をみていく。まずは、公的統計や民間データから確認できる転職者へのアンケート調査を基に、転職前後で賃金が上昇した雇用者の割合の推移を確認する。厚生労働省「雇用動向調査」で、「転職により賃金が増加したと回答した雇用者の割合-転職により賃金が低下したと回答した雇用者の割合」として計算されるDIの推移をみると、リーマンショックが発生した2008年から2011年頃まで「減少」超過で推移した後に、2014年以降は2018年頃まで「増加」超過で推移し、2019年以降は「減少」超過となっている(第2-2-21図(1))。ただし、各年齢階層別に推移をみると、20~40代では2018年にかけて「増加」超幅が拡大し、その後は「増加」超幅を縮小させつつも、「増加」超を維持している。50代も、2000年代以降をならしてみると「減少」超過幅が縮小傾向にある。
「雇用動向調査」の転職者の賃金の動向は2021年までしか確認できないことを踏まえて、より足下の動向については民間データも活用して確認していく(第2-2-21図(2))。このデータでは、転職により賃金が1割以上増加した者の割合しか把握することができず、賃金上昇率が1割未満の転職者の動向を把握できない等の留保条件があるものの、2022年入り後については、「接客・販売・店長・コールセンター」を除く幅広い職種において、賃金が1割以上上昇した転職者の割合が高まっており、景気が緩やかに持ち直す中で、転職を通じた所得上昇の動きは進んでいると考えられる14。
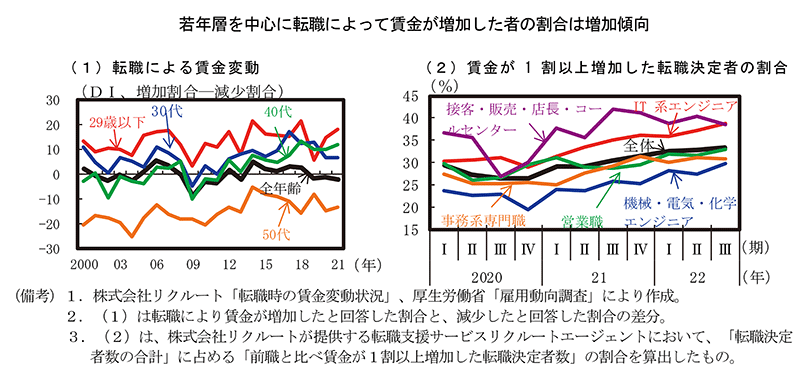
(環境改善を目的とした自発的な転職は賃金やモチベーションにプラス)
上記でみたアンケートの結果は転職者に対する賃金の変動についての単純な集計結果であるが、転職効果を測る上では、転職しなかった場合との比較の視点が重要である。そこでまず、リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査」を活用し、正規雇用者の転職者15の転職前年から転職1年後にかけての年収変化率の分布を、転職をしなかった者の分布と比較する(第2-2-22図(1))。本調査では、転職理由についても確認していることから、転職者が自発的に環境改善を目的に転職したケースを「環境改善目的転職者」と呼び、それ以外の家族都合や会社都合などによる転職者である「その他理由による転職者」と区別した。これをみると、まず、「その他理由による転職者」の賃金変化率の中央値は「非転職者」を下回っているが、「環境改善目的転職者」では「非転職者」を上回っている。次に、前職が非正規雇用だった者については転職に伴って正規転換を果たした「正規雇用への転職者」と、それ以外の転職者である「非正規雇用間転職者」に分けて、「非転職者」との比較を同様に試みた(第2-2-22図(2))。この結果をみると、「正規雇用への転職者」では「非転職者」と比べて、賃金上昇率が大幅に高い傾向があるほか、「非正規雇用間転職者」であっても「非転職者」と比べて賃金変化率の中央値は高い。
ただし、こうしたデータベースでは、転職した労働者が転職しなかった場合の仮想的な賃金変動を観察できるわけではないので、転職による賃金への効果を探る上では、おおむね同質とみなせる労働者について、転職した者と転職しなかった者のペアを作り出し、その後の動向を比較することが有効である16。結果をみると、処置群(環境改善改善目的転職者)と対照群(属性の近い非転職者)の賃金の伸び率は、(処置群の時間軸でみて)転職前年から転職年にかけてはおおむね等しいが、転職翌年にかけての処置群の年収の伸びは対照群を上回り2年累計で約7%程度上昇し、そのうち転職による効果は3%ポイント程度と推計された(第2-2-22図(3))。
さらに、転職の効果は、転職直後の短期的な賃金変動にとどまらず、労働者のモチベーションの改善につながる可能性も示唆される。同データベースの仕事の満足度に関する指標(仕事への熱心さ)について、転職者の転職前年と転職から1年後にかけての変化を、同期間の非転職者と比較すると、非転職者では平均的に僅かに低下した一方で、転職者では改善傾向がうかがえる(第2-2-22図(4))。
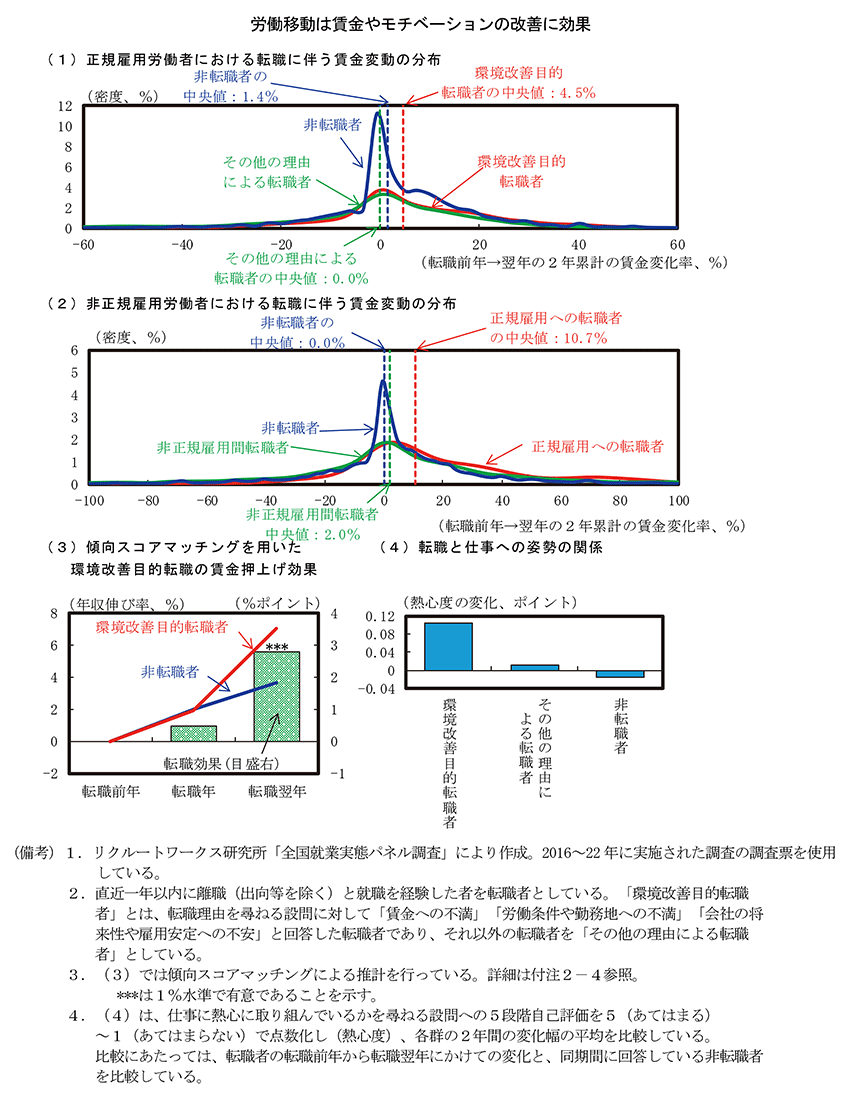
民間調査による国際比較では、我が国の労働者は、現在の就労先での勤続を希望する割合が低く、仕事への熱意も低いという調査結果がある(第2-2-23図)。我が国では中途労働市場の流動性が低く、雇用者が転職を通じて自らの能力を最大限発揮できる環境に移りにくいことが、現在の仕事に対するモチベーションの低下につながっている可能性が懸念される。労働移動の活性化を促すことにより、こうしたモチベーションの低下を防ぎ、社会全体の生産性を引き上げる効果も期待できる。
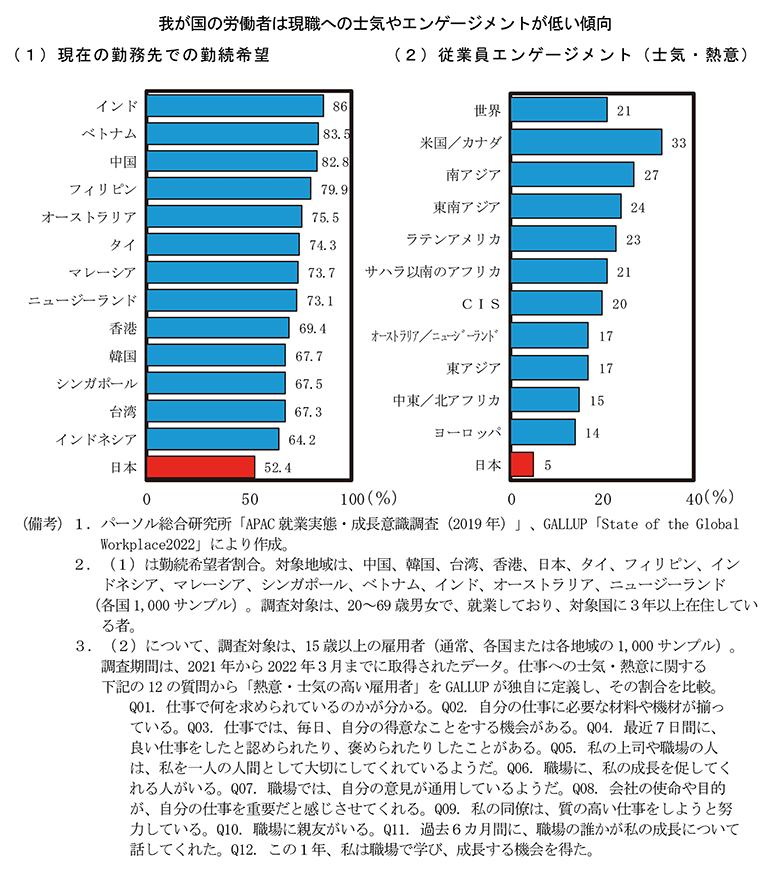
(最低賃金の引上げは時給格差の縮小に効果)
賃金は、使用者と被用者の二者間で決定されることが原則と考えられるが、賃金の低い労働者の生活の安定や労働力の質的向上、競争の確保等の観点から、我が国を始め多くの国で最低賃金制度が設けられている17。最低賃金制度は、国が賃金の最低限度額を定め、使用者に最低限度額以上の賃金の支払いを義務付ける制度であり、最低賃金近傍の賃金で働く労働者、例えばパートタイム労働者の賃金への影響が大きいと考えられる。
まず、我が国における最低賃金とパートタイム労働者の平均時給の推移をみると、最低賃金が毎年引き上げられる中で、パートタイム労働者の平均時給も連動して上昇している(第2-2-24図)。パートタイム労働者の平均時給の上昇は、この間の景気回復や生産年齢人口の減少を背景とした人手不足によってもたらされている面もあるが、最低賃金制度も一定程度の底上げに寄与してきた可能性がある。
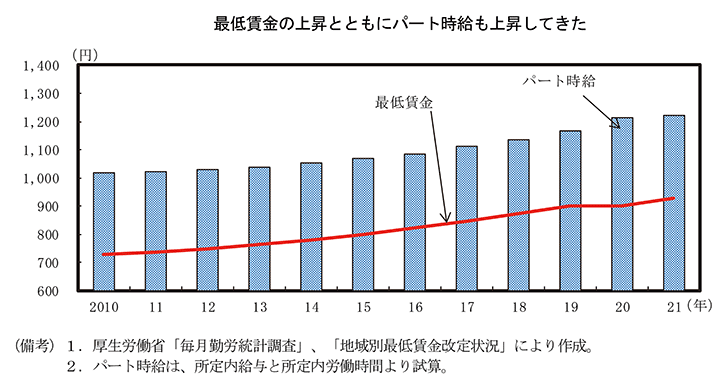
これを確かめるために、リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査」を用いて、非正規雇用者の時給の最低賃金からの乖離額の分布の変化を観察する。2015年以降、最低賃金を幾分上回るところの山が徐々に盛り上がっていることから、賃金分布の左端の裾野が圧縮され最低賃金近傍で働く労働者の割合が高まってきている(第2-2-25図(1))。すなわち、分布の形状から、最低賃金引上げによって直接的に最低賃金の影響を受ける雇用者は増えていることが推察される。最低賃金の改正後に、改正後の最低賃金を下回る労働者の割合である「影響率」の推移をみても、2019年にかけて年々上昇している(第2-2-25図(2))。
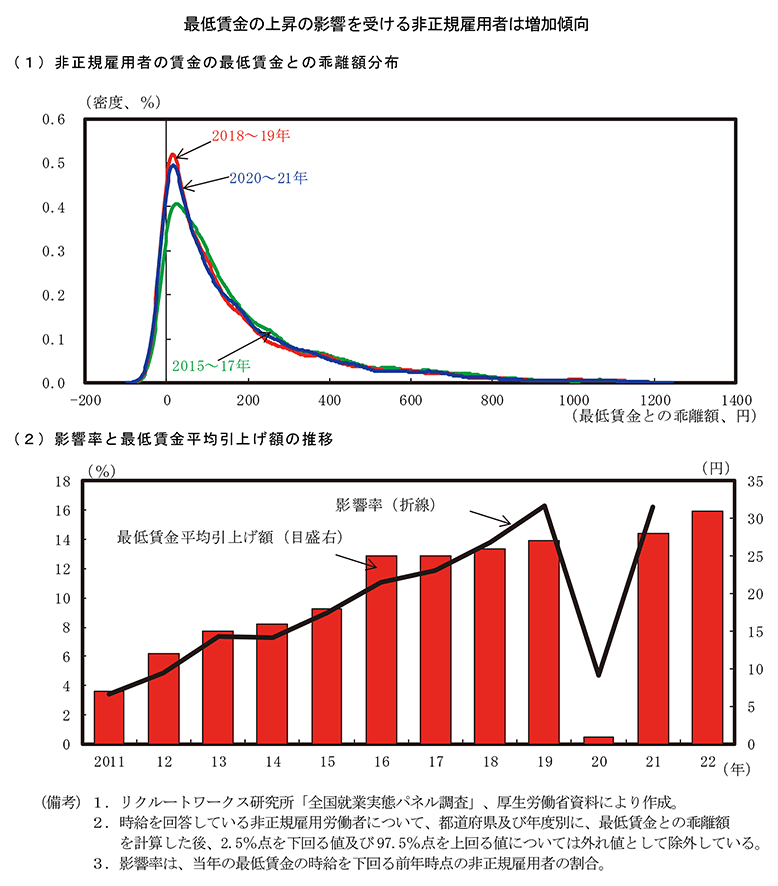
次に、視覚的に確認された最低賃金の引上げによる非正規雇用者の賃金分布の左裾近くの圧縮について、どの範囲の賃金水準の雇用者にまで及ぶのか、統計的に確認する。ここでは先行研究を参考に、70%分位点(下位から数えて70%に位置する雇用者の賃金)を基準に、他の分位点の動きを検証する18。結果をみると、①基準点より低賃金の場合、広範にわたり統計的に有意に時給の上昇が起こること、②低分位点ほど基準点へ近づく効果が大きいことが確認できる19(第2-2-26図)。
先行研究でも指摘されている通り、最低賃金の引上げは、介入の影響を直接受ける労働市場だけでなく、周辺の労働市場へのスピルオーバー効果を有しており、その効果は労働力としての代替性の強さに応じて最低賃金に近づくほど大きくなることが確認される20。また、そのスピルオーバー効果は、非正規雇用者の中では60%分位点まで統計的に有意に及び、最低賃金水準を上回る雇用者の賃金にも幅広くプラス効果がみられる。
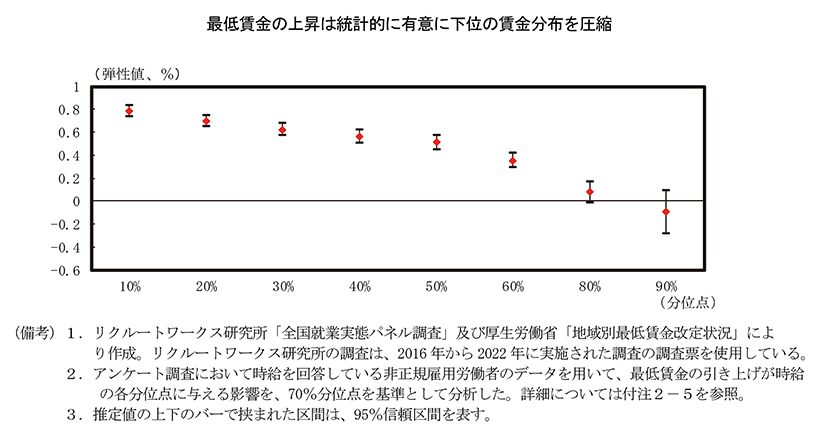
ただし、こうした時給の上昇が、非正規雇用者の所得の上昇につながっているかという観点からは留保を要する。過去の経済財政白書でも指摘した通り、社会保障制度や企業の福利厚生制度が、世帯の非主稼得者(主稼得者の配偶者等)の就業調整のインセンティブを高めており21、時給が上昇した場合に就労時間を調整する労働者が存在している可能性がある。実際、非主稼得者の週当たり労働時間の分布をみると、20時間前後と比較的労働時間の短い部分に分布の山が存在する(第2-2-27図)。さらに、2015年以降時系列で分布の変化をみると、上述した通り時給の上昇が実現する中で、20時間前後に存在する山の左側の裾野が年々厚くなっており、上述した「壁」を意識した労働時間の調整が生じている可能性が示唆される。
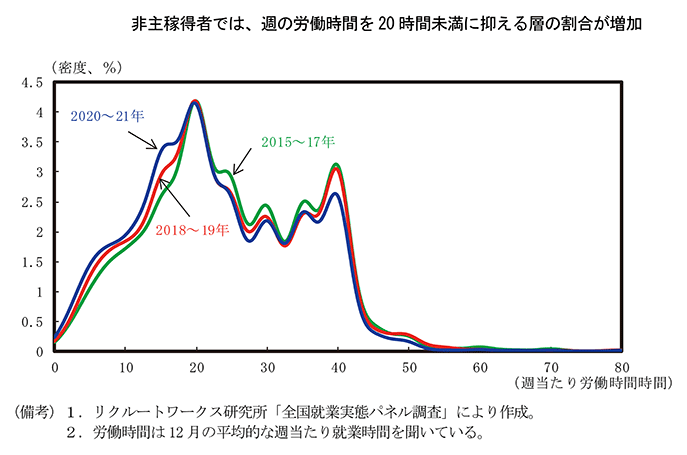
(リスキリングと労働移動の円滑化を促す取組が重要)
本節で確認した事項を基に、構造的な賃上げに向けて必要な施策について整理したい。第一に、感染拡大以降に1年以上の長期失業者が増加するとともに、ハローワークでの求人充足率の低下傾向が続いている。また、この間のデジタル化の進展を含め、企業の労働需要に変化の兆しがうかがわれ、今後求人と求職のミスマッチが拡大する可能性も考えられる。こうした中で、「求職者支援訓練22」「公共職業訓練23」といった諸制度の量・質の強化を通じ、IT関連など人手が不足している専門分野での訓練受講機会を増やす工夫などを行うとともに、前職とは異なる分野の仕事にも関心を持てるような仕組みを設けるなどリスキリングの更なる充実24によって、失業者が可能な限り早期に希望する仕事に就けるようにし、その後の就業継続につなげることが重要である。
第二に、テレワークの実施割合などの賃金以外の面での非正規雇用と正規雇用の働き方の差が広がっている可能性も指摘した。これらが両雇用形態間の不合理な処遇差の残存に起因するものなのか、タスク内容・スキルの差に起因するものなのか定かではないが、この結果を踏まえると、前者であれば同一労働同一処遇の推進の余地が、後者であればリスキリングによる非正規雇用の処遇改善の余地が残されていることを示唆しており、こうした取組を進めていくことが重要である。
第三に、賃上げ・モチベーションの改善に効果が確認された、環境改善を目的とした自発的な転職を後押しする観点からも、リスキリングによる成長産業への労働移動の促進が重要である。例えば、官民双方の訓練機関が連携して、教育訓練がどう就業に結び付いているか明らかにするとともに、成長分野で求められるスキルニーズに合うように訓練メニューを見直していくことに加えて、主体的な能力開発を支援することを目的に、企業ニーズに合った訓練を受講する個人に費用を補助するなど、労働者のリスキリングへの支援を強化することが重要である。また、こうした新たな制度の創設に加えて、労働移動を阻んできた旧来の制度を見直すことも重要である。例えば、現行の退職給付制度の下で、退職金の給付額は一般に勤続年数に比例して上昇し、税制面においても受給時の退職所得控除の算定額が勤続年数20年を境に大幅に増えるような設計となっており、転職のディスインセンティブになっている25。加えて、労働移動の円滑化には官民双方の職業紹介機関の仲介機能を一層高めることが鍵となると考えられる。なお、こうした労働移動の円滑化や、労働市場での人材配置の最適化においては、労働市場に存在する、又は新たに生まれる様々な仕事や職業の内容について、求職者や仲介機関の担当者などに対して幅広い情報提供が行われることが望ましいことから、我が国でも2020年から厚生労働省が公開している職業情報提供サイト26の拡充も重要と考えられる。
第四に、最低賃金の引上げ効果については、我が国ではこれまで継続的に最低賃金を引き上げる中にあっても相対的に賃金の低い層の失業率の著しい変化は確認されておらず、賃金格差縮小に効果を発揮したと考えられる。また、最低賃金引上げを家計の所得増加につなげていく観点からも、就労を阻害する社会保障制度等の改善を早急に図る必要があろう。

