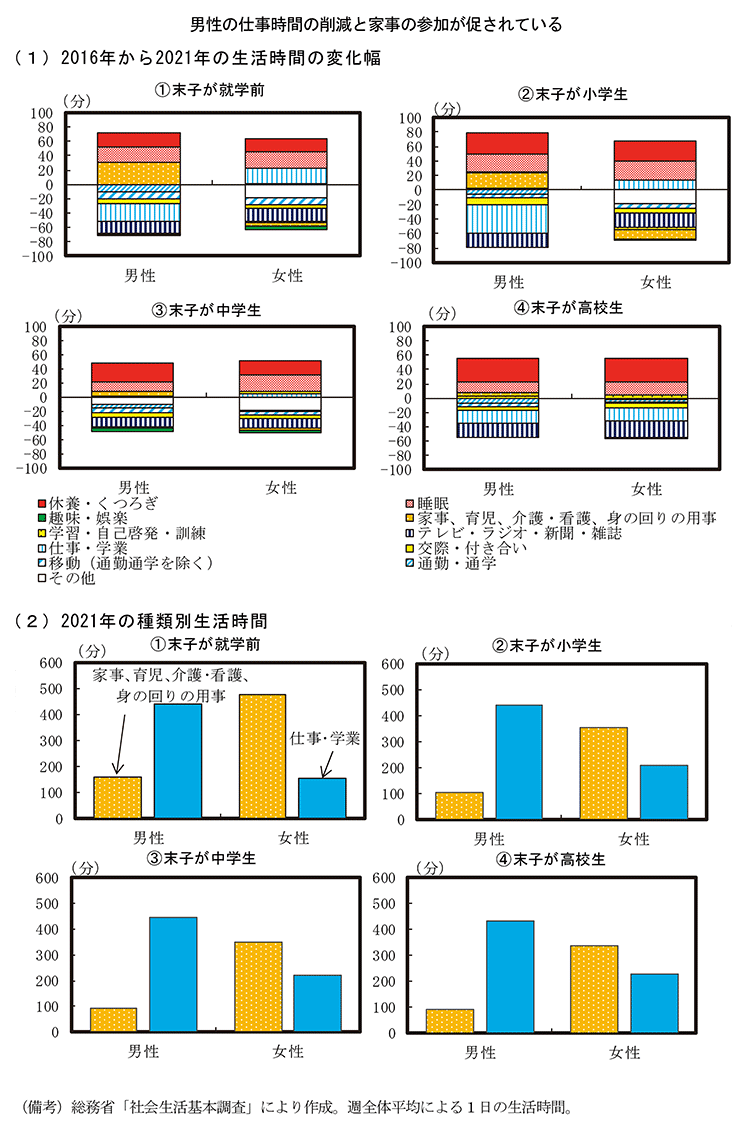第2章 個人消費の力強い回復に向けた課題(第1節)
第1節 物価上昇下の個人消費
我が国における個人消費は、感染症により抑制されてきたサービス消費を中心に緩やかな回復を続けている。他方、消費者物価指数が約40年振りの上昇率となる中で、消費者マインドが弱含んでおり、感染拡大を機に大きく低下した家計の平均消費性向(可処分所得に対する最終消費支出の比率、以下「消費性向」。)の回復ペースを注視していく必要がある。本節では、物価上昇や消費者マインドと消費性向の関係を整理した後、感染拡大に伴う行動制限等に起因する超過貯蓄の消費下支え効果について考察するとともに、感染拡大以前から指摘されてきた我が国における個人消費をめぐる構造的な課題を解消していく取組の重要性を改めて確認していく。
1 消費をめぐる物価と消費者マインド
(感染拡大以降、消費性向は低下)
第1章で確認したとおり、2022年初以降の我が国の個人消費は、感染症により抑制されてきたサービス消費を中心に持ち直しが続いているが、消費者マインド等に弱めの動きもみられている。個人消費の回復を着実なものとするためには、企業業績が過去最高の水準に達する中で、次の春闘における賃上げの実現幅に注目が集まるが、感染拡大下の消費活動の制約を背景に積み上がった家計の超過貯蓄が個人消費の下支えとして機能していくと期待する見方がある1。こうした下支えが機能すれば、物価上昇が賃金上昇を上回って推移する間も、消費性向の上昇によって個人消費が下支えされることが期待される。
こうした問題意識から、まずはマクロでみた感染拡大以降の消費性向の動向について考察を行う。消費性向は、分子の消費支出要因と、分母の可処分所得要因に分解できるが、それぞれの動向をみてみよう(第2-1-1図(1))。家計最終消費支出については、2020年4-6月期に大きく下落した。これは、緊急事態宣言が発出される等、感染拡大を防止する行動規制によってもたらされた側面が大きかった。その後、家計最終消費支出の動きは、感染者数が増減を繰り返す中で緩慢であったが、ワクチン接種が進展し、ウィズコロナの取組が社会全体で進む中で、最近では緩やかな持ち直しの動きが続いている。可処分所得については、2020年4-6月期は、雇用者報酬が感染拡大による経済活動の停滞を背景に減少した一方で、「給付金等」(特別定額給付金による「その他の経常移転要因」)により大きく押し上げられた(第2-1-1図(2))。これらを背景に、2020年4-6月期に消費性向は大幅に下落することとなった(第2-1-1図(3))。その後、消費性向は、経済社会活動が正常化に向かう中で持ち直しているが、感染拡大前との対比では依然として低い水準にとどまっている。
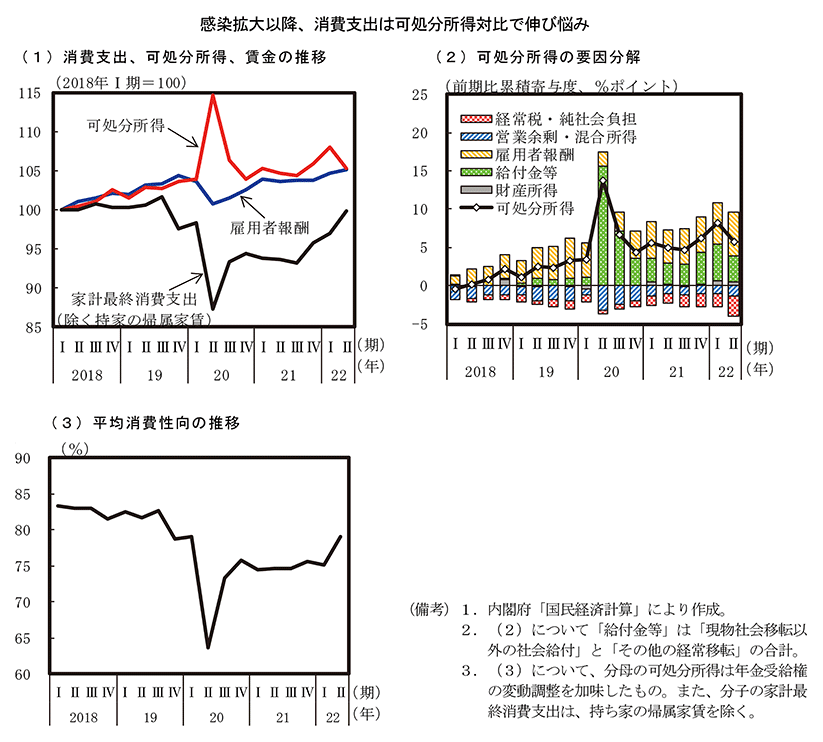
(物価上昇下で、低所得層ほど消費性向の戻りが鈍い)
ウィズコロナの取組が進む中で、足下では消費性向が上昇している点をみたが、消費性向の上昇ペースに所得階層間で違いがあるだろうか。ここでは、総務省「家計調査」を用いて、世帯(二人以上世帯のうち勤労者世帯)の所得階層別にみた消費支出と消費性向の足下の動きを確認する。これをみると、①2020年、2021年の感染拡大下での消費性向の低下幅(2019年対比)は、高所得世帯でより大きいこと、②2022年以降の物価上昇下での消費性向の上昇幅は、低所得世帯でより小さいことが分かる(第2-1-2図(1))。①については、外食や旅行などの選択的支出への支出割合は高所得世帯ほど高く、感染拡大による消費活動の抑制による下押しが、高所得世帯ほど強く出ていたことを示している。②は、足下の物価上昇に対して、低所得世帯では購入量などを削減して実質支出額を抑えていることを示している。実際、消費支出を名目・実質に分けてみると、高所得世帯では、名目消費支出が増加する中で実質消費支出も緩やかに増加を続けているが、低所得世帯では、名目消費支出がおおむね横ばい圏内で推移する中で、実質消費支出は弱含んでいる(第2-1-2図(2))。これらの結果、2022年の消費性向はどの所得階層でも2019年の水準に戻っていないが、高所得世帯では名目・実質のいずれでも消費支出が感染拡大前の水準を回復している一方で、低所得世帯では依然として感染拡大前の水準を下回っており慎重な支出スタンスが続いていることが分かる。
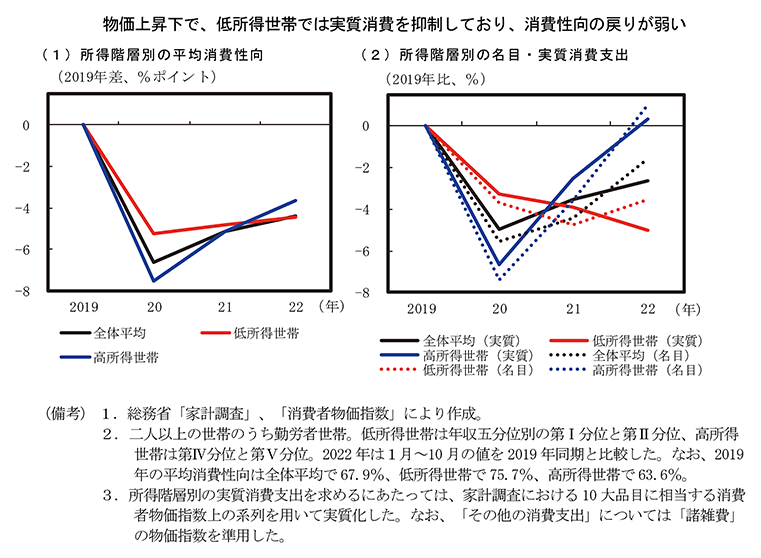
(幅広い所得階層で消費者マインドは弱い動きとなっており、その程度は低所得層でやや強い)
上述したとおり、2022年以降、所得階層により物価上昇への消費支出面での対応が異なっている。こうした所得階層間での消費支出の動向と消費者マインドの動向について、内閣府「消費動向調査」における消費者態度指数2を詳しくみていくと次の点が指摘できる。第一に、消費者態度指数は、いずれの所得階層でも2022年初以降に下落傾向にあり、幅広い家計において消費者マインドは弱含んでいる(第2-1-3図(1))。第二に、消費者態度指数を構成する内訳四項目をみると、「収入の増え方」「雇用」といった、雇用・所得関連の指標の低下は相対的に限られている一方、「暮らし向き」「耐久消費財の買い時判断」の悪化幅が相対的に大きくなっている(第2-1-3図(2))。第三に、所得階層別の違いに注目すると、特に低所得層で「収入の増え方」が悪化しており、「暮らし向き」の下落幅も相対的に大きい。
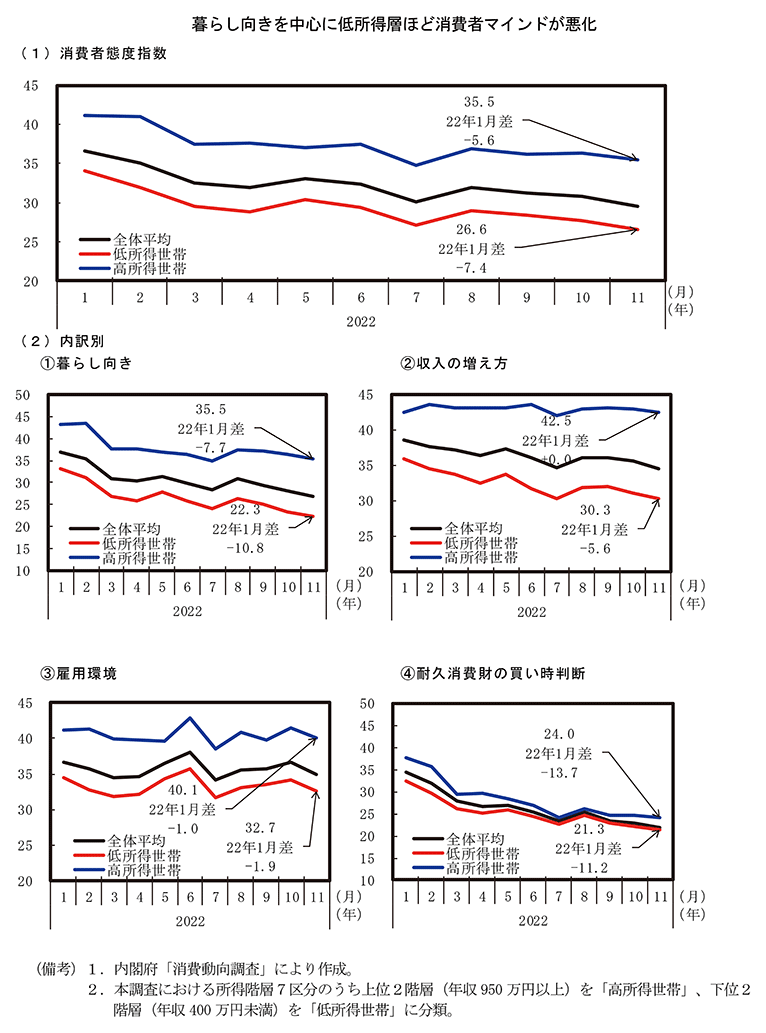
これらの結果を考察すると、2022年以降、雇用・所得環境は全体として改善方向にあるものの、物価上昇を背景に幅広い家計で生活防衛意識は高まっているとともに、子細にみると、第1章で確認したとおり生活必需品への支出割合の高い低所得者の方が物価上昇に伴う負担増が大きいことなどを背景に、「暮らし向き」や「収入の増え方」の悪化幅も大きくなっている。
「消費動向調査」では、マインドを悪化させた家計に対して直接的にその理由の回答を求めないため、消費者マインドをその背景と共に定点観測する日本銀行「生活意識に関するアンケート調査」の結果も活用して、消費者マインドの動きへの考察を深める。まず、「生活意識に関するアンケート調査」の「暮らし向きDI3」の推移をみると、消費者態度指数と同様にこのところ悪化が続いている(第2-1-4図(1))。次に、「ゆとりがなくなってきた」と回答した者に対して、その理由を訊くと、「物価が上がったから」の割合がこのところ急激に上昇しており、反対に、「給与や事業などの収入が減ったから」の割合が低下している(第2-1-4図(2))。これらを勘案すると、足下の物価上昇が消費者マインドの悪化を招いていると整理できよう。
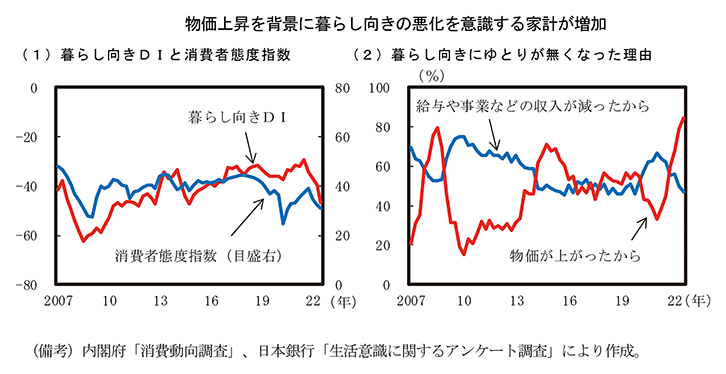
(物価上昇局面では所得階層間の消費者マインドのばらつきが大きくなりやすい)
足下の消費者態度指数を所得階層別にみると、低所得者ほど低下幅が大きくなっていたが、次に、所得階層間の消費者態度指数のばらつきは過去のどのような局面で高まってきたのかを考察する。
消費者態度指数は2004年4月から七つの年間収入階級別の数値が利用できるため、各月における年間収入階級間での変動係数をばらつきの指標として算出した(第2-1-5図)。時系列推移をみると、第一に、足下のばらつきの大きさは、既往ピークに達しており、過去に発生した他の経済的なショックと比較しても、最近の物価上昇に対する所得階層間での受け取り方の違いが大きい。第二に、エネルギー価格・食料品価格が上昇した2007年初以降、消費税率引上げが決定された2012年末以降など、物価上昇が予見される時期に所得階層間のばらつきが大きくなる傾向がある4。逆に、大きな物価変動を伴わなかった2011年の東日本大震災や、2020年の感染拡大時にはばらつきは低下している。
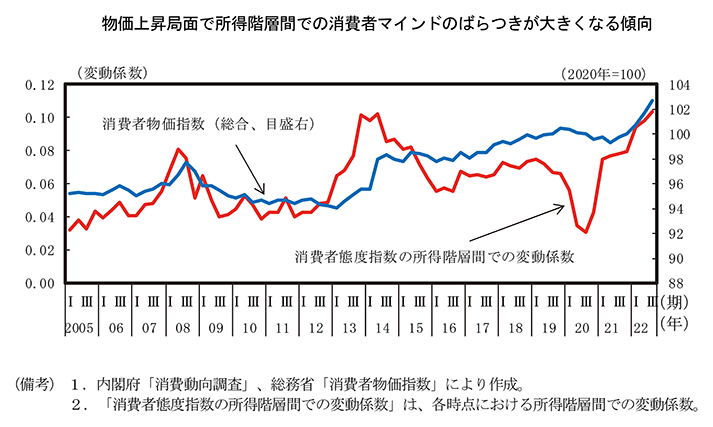
(住宅価格の高騰も消費者マインドに影響を及ぼしている可能性)
最近の物価上昇が家計の生活防衛意識を高めている点を確認したが、家計のインフレ実感は統計上の物価上昇率と乖離していると指摘する向きもある。第1章で確認したとおり、最近の消費者物価の上昇は食料品や光熱費で目立っており、先行研究によれば、こうした購入頻度の高い品目の物価上昇は家計のインフレ実感を高める傾向にある5。さらに、最近の研究では、消費者物価に含まれない住宅価格が家計のインフレ実感に大きな影響を及ぼすことも指摘されている6。
こうした問題意識から、足下の住宅市場の動向を確認すると、感染拡大以降の住宅価格上昇を背景に、持家住宅への需要が抑制されて持家住宅の着工は弱含んでいる7(第2-1-6図(1)、(2))。実際、住宅ローンの返済ペースや金利・借入期間について一般的な想定をおくことで、戸建住宅の取得のしやすさを示す住宅取得能力指数8を試算すると、住宅価格の高騰を背景に、2021年入り後に急速かつ大幅に悪化している。今次局面では、消費者物価が約40年振りの上昇率となっているが、消費者物価に含まれない住宅価格も上昇しており、特に将来の住宅購入を検討する若年層の消費者マインドへの影響が懸念される。
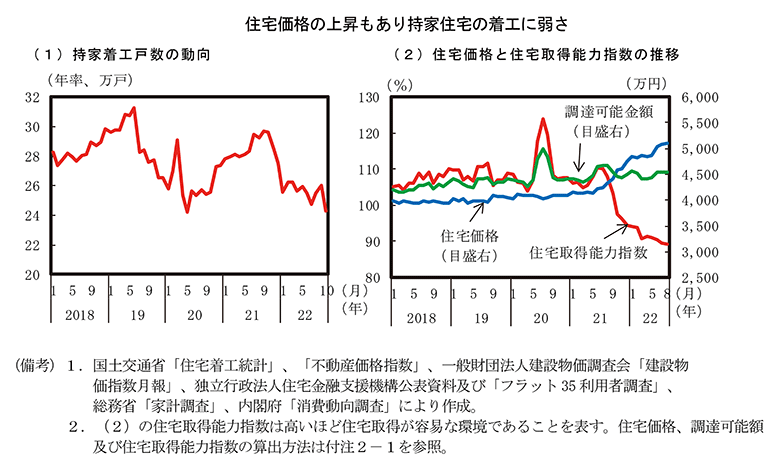
(消費者マインドはラグを伴って消費支出に影響)
以上みてきたような消費者マインドの悪化は、実際の消費支出にどのように影響を及ぼしているのだろうか。2000年以降の我が国の消費支出と消費者マインドの推移をみると、消費者マインドが悪化する局面では消費支出が下落する傾向が観察され、両者の関係性が示唆される9(第2-1-7図(1))。
そこで、消費者態度指数、実質国内最終消費支出、家計部門の実質可処分所得から成る3変数VARモデルを構築し、消費者態度指数にショックが生じた場合に、消費支出がどの程度影響を受けるかを、インパルス応答関数によって検証する10。これをみると、消費者態度指数に下落ショックが生じた場合に、翌四半期から消費支出を下押しし、その下押し幅は3四半期後(付図2-1では4四半期後)に最も大きくなる関係が観察される(第2-1-7図(2))。
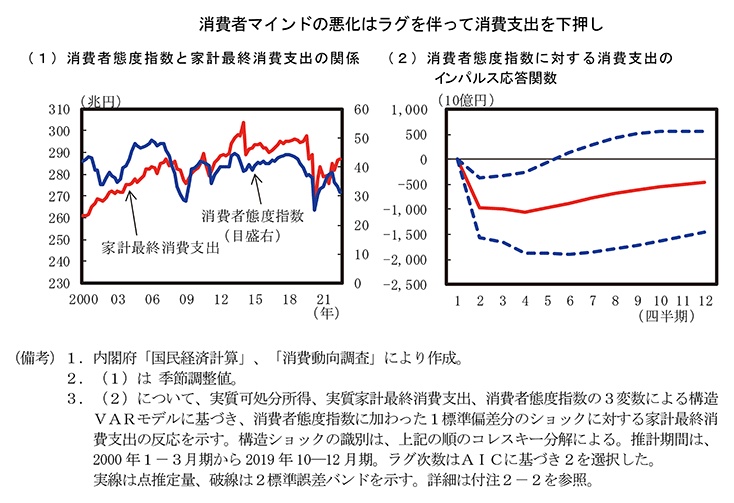
この結果を踏まえると、現状、消費者マインドが悪化する中においても、ウィズコロナ下での消費支出の回復が続いているが、感染拡大前の過去の平均的な関係をみる限りにおいて、消費者マインドの悪化はラグを伴って消費支出の下押し幅を強める傾向があり、今後の動向には注意を要する。
2 超過貯蓄と消費
(感染症下で積み上がった超過貯蓄による消費底上げ効果は現時点で限定的)
ここまで確認したとおり、足下の物価上昇は家計の生活防衛意識を高めており、消費支出に影響を与える要因である消費者態度指数が低下している。他方、感染拡大下で生じた貯蓄率の上昇(=消費性向の低下)は、本来の消費機会を逃したことなどにより生じたことから、感染症が収束に向かう過程でその一部が取り崩される可能性がかねてから指摘されており11、物価上昇による家計負担増加の影響を一部軽減する働きが期待される。
本章では、先行研究を参考に12、2015~19年の家計の消費性向を平常状態と便宜的にみなし、コロナ禍以降にこれを下回った分と可処分所得の積を累積した金額を超過貯蓄と呼ぶことにする。まず、内閣府「国民経済計算」の家計可処分所得と家計貯蓄率から、マクロでみた超過貯蓄の推移とその規模を確認する(第2-1-8図(1))。これをみると、足下の超過貯蓄の水準は約64兆円に上るが、超過貯蓄は足下で幾分ペースを鈍化させつつも増加し続けており、足下の物価上昇局面においても、取り崩されている様子は観察できない。すなわち、超過貯蓄の取り崩しによる消費の押上げ効果は現時点で明確ではないと評価できる。ちなみに、マクロでみた預金残高について、日本銀行「資金循環統計」でその推移を確認しても、コロナ禍以降に家計部門の預金残高の増加ペースは感染拡大前と比較して加速した状態が続いており、超過貯蓄の存在とそれがまだ取り崩されていない様子が観察できる(第2-1-8図(2))。
次に、総務省「家計調査」を用いて、2015~19年の世帯属性別の消費性向を平常状態と便宜的にみなし、世帯属性別に超過貯蓄の推移をみる。具体的には、勤労者世帯について所得階層別、また年金生活者が多くを占める高齢無職世帯についても所得階層別に超過貯蓄の動向を確認した。これをみると、高齢無職低所得世帯を除き、多くの世帯類型で超過貯蓄は引き続き増加傾向にある(第2-1-8図(3))。超過貯蓄を生み出す消費性向の水準低下は、参照時点より可処分所得が増加することによる効果(可処分所得要因)と、消費支出が減少することによる効果(消費支出要因)に分けて解釈することもできる。こうした整理の下で、勤労者世帯について高所得世帯と低所得世帯の超過貯蓄の動向を分解すると、高所得世帯における超過貯蓄は、消費支出の累積効果が直近の2022年7-9月期には減少に転じる(すなわち、2022年7-9月期の消費支出は参照時点である2015─19年平均を上回った)中で、可処分所得が更に増えたことで生じている(第2-1-8図(4))。この間、低所得層ではこうした現象は観察されない。すなわち、高所得層では既存の超過貯蓄と可処分所得の上昇が、一定程度の物価高騰に対するバッファーとして機能し、消費支出を下支えした可能性があるが、低所得層ではそうした効果は限定的にとどまっているとみられる。
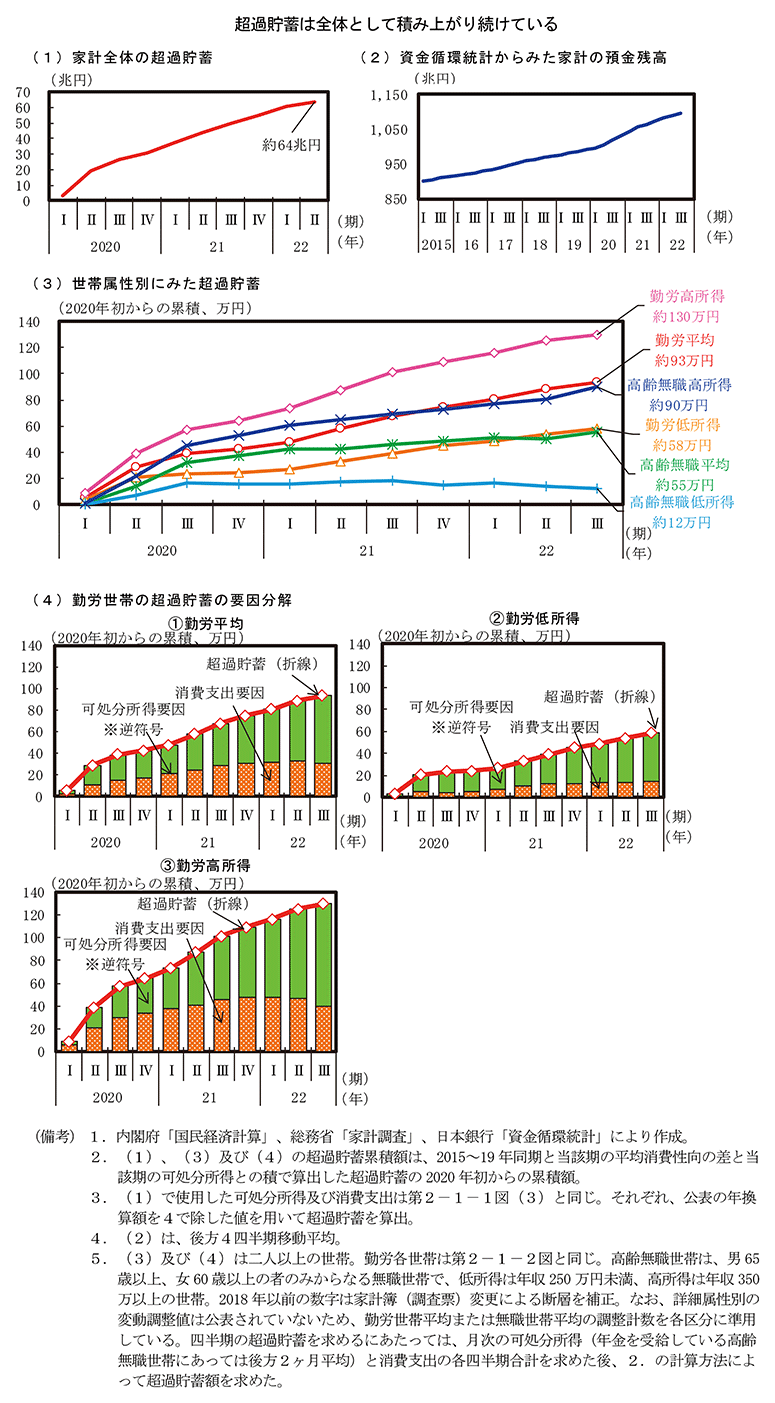
(アメリカでは超過貯蓄を取り崩す動きもみられている)
我が国では超過貯蓄を取り崩して消費に回す動きは限定的であるが、比較のため諸外国の動向を確認しよう。具体的には、アメリカとユーロ圏について、日本と同様に2015~19年の消費性向の動向が感染拡大後と比べて安定していることを確認した上で、前掲第2-1-8図と同様に同期間の消費性向との差分を用いることで超過貯蓄を定義した13。これをみると、アメリカでは2022年1-3月期に、超過貯蓄が減少に転じている一方で、ユーロ圏と我が国では超過貯蓄の積み上がりが続いている(第2-1-9図)。アメリカでは雇用環境の大幅な改善を背景に、物価上昇下にあって、家計がより積極的に超過貯蓄を取り崩して消費に振り向けてきたと考えられる。また、超過貯蓄の蓄積を、前掲第2-1-8図と同じ考え方で可処分所得要因と消費支出要因に分解し、消費支出要因が減少に転じたタイミング(すなわち、消費性向が2015~19年平均を上回ったタイミング)をみると、アメリカでは2020年7-9月期、ユーロ圏では2021年4-6月期となっているが、我が国では2022年4-6月期と大幅に遅れている。こうしてみると、超過貯蓄の蓄積が続いている観点で我が国とユーロ圏は同様であるが、消費支出の回復程度では様相が異なっている点には留意が必要だろう。なお、内閣府政策統括官(経済財政分析担当)(2022a)で紹介したとおり、欧州では、家計の期待インフレ率が高まったことで貯蓄が実質的に目減りしていることや、コロナ禍での貯蓄増加が消費性向の低い高所得層に偏っていること等を背景に消費下支え効果が限定的となる可能性も指摘されている。超過貯蓄の下支え効果の有無とその程度については、現時点で国際的なコンセンサスが確立している訳ではないが、我が国の消費の先行きを考える上では、諸外国における動向や分析事例も注視していくことが重要である。
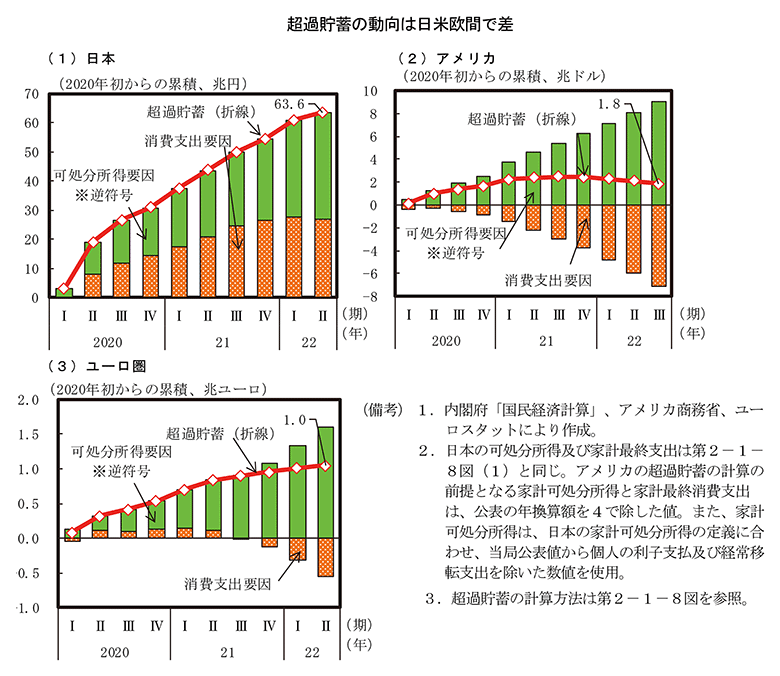
(超過貯蓄水準は、足下の物価上昇による年間負担増の10倍に相当)
次に、足下の超過貯蓄の水準を、物価上昇により見込まれる家計の負担増加分と簡便的に比較してみよう。ここでの負担増加額は、総務省「家計調査」の実際の消費支出を基に、同量の消費支出を行う上で、仮に物価上昇率の前年比が0%だった場合に必要だった支出と、現実の支出額との差分として定義した。まず、足下の物価上昇による負担増加額(家計調査の直近値である2022年10月)が同年末まで継続した場合の、二人以上勤労者世帯の2022年の負担増加額は9.6万円程度、可処分所得の1.6%と試算できる(第2-1-10図(1))。これを高所得・低所得世帯別にみると、高所得世帯の方が負担増加額は大きいが、可処分所得対比でみれば影響は相対的に軽微である。また年金生活者におおむね相当する高齢無職世帯でも所得階層間の差は同様に観察される。さらに、前掲2-1-8図で確認した超過貯蓄とこの負担増加額の比率をみると、二人以上勤労者世帯の平均的な超過貯蓄額は、年間の負担増加額の10倍程度に相当し、現状の物価上昇をカバーするのに十分な規模であることが分かる14(第2-1-10図(2))。ただし、以下の点には留意が必要である。まず、今般の物価上昇は、長年、デフレや低インフレを経験してきた我が国の家計にとっては、不慣れな物価上昇局面であり、先行きの物価上昇幅や物価上昇期間の持続性への見通しは家計によって異なると考えられる。したがって、来年度以降の所得と支出の環境に対する不安感から予備的な貯蓄動機が増大している家計も相応に存在する可能性がある。実際、上述したとおり、感染症下の行動制限が緩和される中で超過貯蓄を消費に振り向けようとする積極的な消費スタンスは観察されない。さらに、所得階層別の集計値でみると、属性間の超過貯蓄の水準差は大きく、高所得の勤労世帯では現下の年間負担増の11倍に相当する額が保有されている一方、低所得の高齢無職世帯では、1.5倍程度にすぎない(2年目中には消費水準を切り下げる必要)。また、個別の家計をみれば更に大きなばらつきがあると考えられる。以上を踏まえると、試算結果は幅をもって解釈する必要がある。
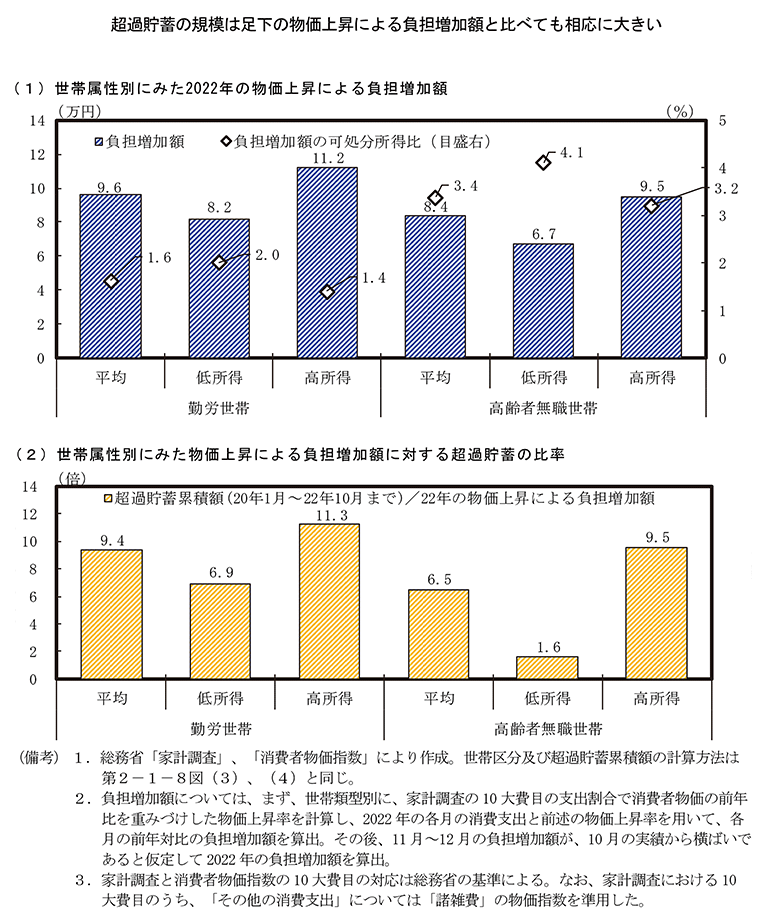
(預貯金増加の消費押上げ効果は限定的であり、ベースアップや将来不安の解消が重要)
消費性向が引き続き感染拡大前の水準を下回っている状況を踏まえ、感染拡大以降に積み上がってきた超過貯蓄が消費支出に及ぼす効果を考察することを目的に、消費関数を推計した。具体的には、総務省「家計調査」の調査票情報を活用し、可処分所得のほか世帯主年齢等の属性情報に加え、住宅ローンを含む負債額などをコントロールした上で15、預貯金額の増加が消費支出を押し上げるのかを確認した16。さらに、政府からの給付金等の一時的な可処分所得の変動ではなく、生涯を通じた所得見通しの変化こそが消費スタンスに影響を及ぼすとの見方である恒常所得仮説を踏まえ、個人の恒常所得への見通しと関係が強いとみられる定期収入比率(=定期給与/世帯主収入)の違いによる消費支出への影響もみた。消費支出とこれらの変数との関係は時期により異なると推察されるが、今回は推計期間を2012~21年の直近10年間とした。
推計結果の特徴は以下の点である。第一に、預貯金額による消費支出の押上げ効果を、所得階層別にみると、いずれの所得階層でも統計的に有意に押上げ効果が確認されるがその規模は1万円の預貯金額の増加に対して、100~250円程度である(第2-1-11図(1))。第二に、定期収入比率が高い世帯ほど、消費支出額が大きい傾向が確認できる(第2-1-11図(2))。具体的には、定期収入比率が70%未満の家計を基準にすると、70~90%の世帯では、統計的には有意ではないが約5~6万円程度、90%を超える世帯では統計的に有意に約13万円消費支出が大きい。この結果は、恒常所得仮説と整合的である。第三に、こうした諸要素をコントロールした上でもなお残る年次ダミーによる消費支出への影響(2012年対比で、他の属性が同じ場合にみられる消費支出額の差)を、年齢階層別・配偶者の就業形態別にみると、34歳以下の若年層や共働き世帯を中心に幅広い世帯類型と年次ダミーの交差項は、下押し方向に寄与してきた(第2-1-11図(3)、(4))。この結果は、今回の推計では考慮されていない、世帯共通の消費支出の押下げ要因が存在している可能性を示唆しており、具体的には次項でみていくこととしたい。
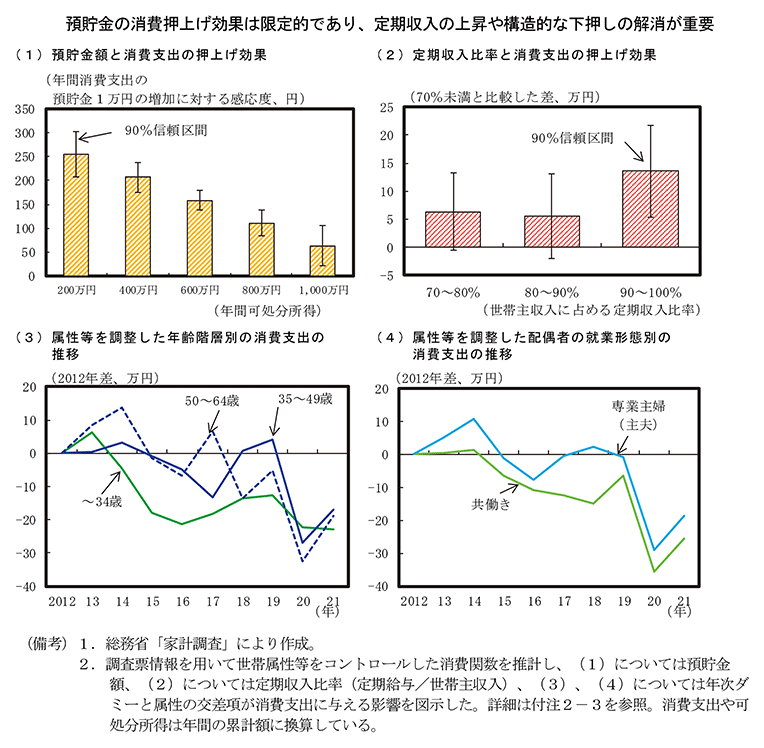
以上の結果を踏まえると、超過貯蓄の存在は家計の消費支出を下支えする効果が期待されるものの、これまでみられてきた預貯金と消費支出の関係からは、その規模は限定的である可能性が示唆される。感染拡大下で積み上がった預貯金は、行動制限下などでの消費の先送り部分が含まれ、平時に家計が目的をもって増加させた預貯金とは性質が異なっているものの、超過貯蓄が消費支出をどの程度下支えするかをみる上では過度な楽観視は控えるべきであろう。他方で、定期収入比率の上昇が消費支出の増加に効果があることを踏まえれば、ベースアップの実現など、家計が中長期的にみて所得上昇期待を抱くことができる形で賃上げを進めていくことが個人消費を促進していく観点からは重要である17。さらに、第3項で詳述するとおり、生涯所得への期待が高まらない中で老後の生活資金への不安の高まり等の構造的な要因により消費支出への下押しが存在する場合には、こうした課題を解決することも引き続き重要である。
3 個人消費の活性化に向けた構造的な課題
(近年、特に若年層と高齢層の消費性向が低下傾向)
前項では、構造的な消費下押し要因の解消が引き続き重要であることを確認した。これを踏まえ、感染拡大前の我が国の景気回復局面である2012~18年を振り返ると、諸外国と比較して我が国のGDPの伸びに対する個人消費の寄与は小さく、またGDPの成長率も低かった(第2-1-12図)。
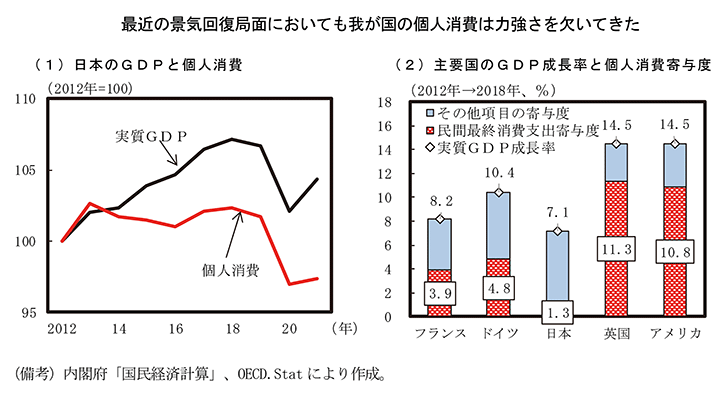
ここで、年齢階層別に2010年代の消費性向の推移をみると、34歳以下の若年層と65歳以上の高齢層の消費性向が低下しており、これらの世帯において所得対比でみた消費支出が伸びなかったことが、個人消費の勢いが乏しい一因となってきた可能性がある(第2-1-13図(1))。共働き世帯の増加や、少子化等の進行による構成変化の要素も考慮し、総務省「家計調査」の調査票情報を活用して、同一の有業人員・世帯人数ベースで測った消費性向の変化(2010~12年平均→2017~19年平均)をみても、34歳以下や65歳以上の家計では幅広く低下傾向がうかがえる(第2-1-13図(2))。
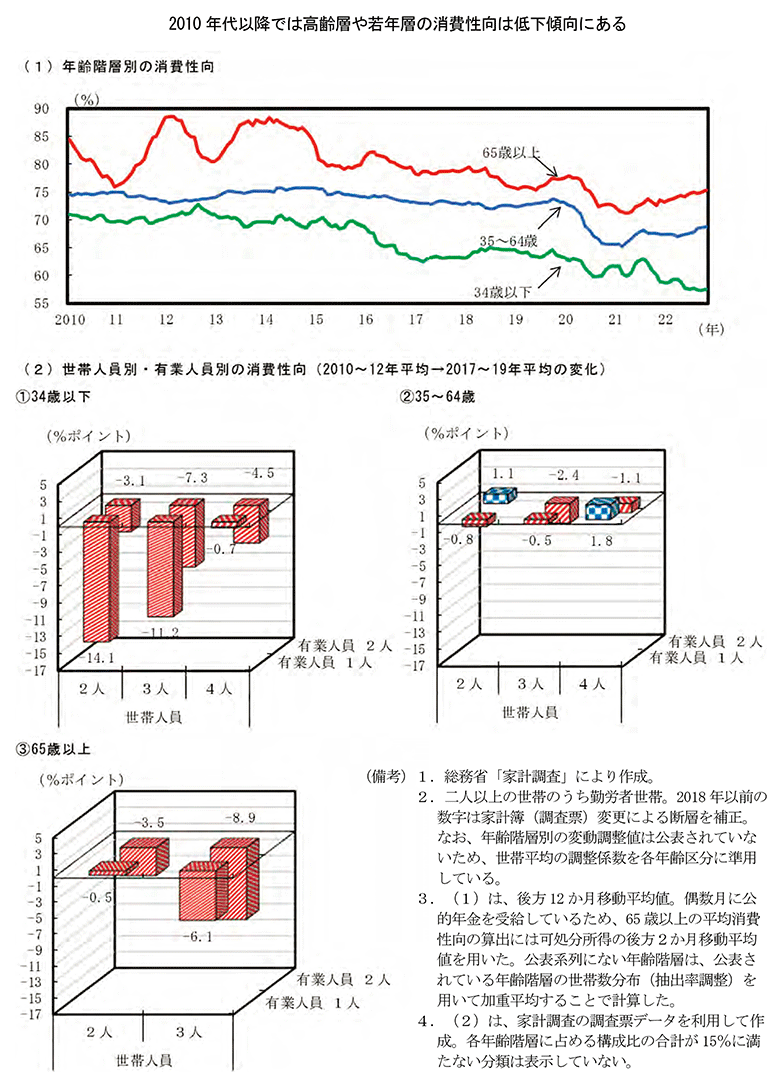
(非正規雇用比率の高まりや社会保障制度への懸念から若年層の老後への不安は上昇)
若年層の消費性向が低下傾向にある背景18については、少子高齢化の進行などを受けて、公的な社会保障制度の持続可能性や将来の給付水準に対して不安が高まっている可能性が懸念される。具体的には、給付側として被保険者数が減少した場合に年金受給額を減額するマクロ経済スライド19が2004年に導入されている。負担側では、保険料の引上げに加え、2014年、2019年と社会保障制度の維持を目的として消費税率が引き上げられた。こうした負担増と受益減が実施されてもなお、人口動態の変化に対応した制度の持続性について、将来不安が残っている可能性がある。こうした観点から、まず、金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査」を用いて、若年層の貯蓄理由の変化を確認する。2019~21年平均をみると「こどもの教育資金」を選ぶ割合が最も高いが(第2-1-14図(1))、2007~09年からの変化に注目すると「老後の生活資金」の回答割合の増加幅が最も大きくなっている(第2-1-14図(2))。この結果から、老後の生活への不安感の高まりが若年層の消費性向の低下につながっている可能性が懸念される。
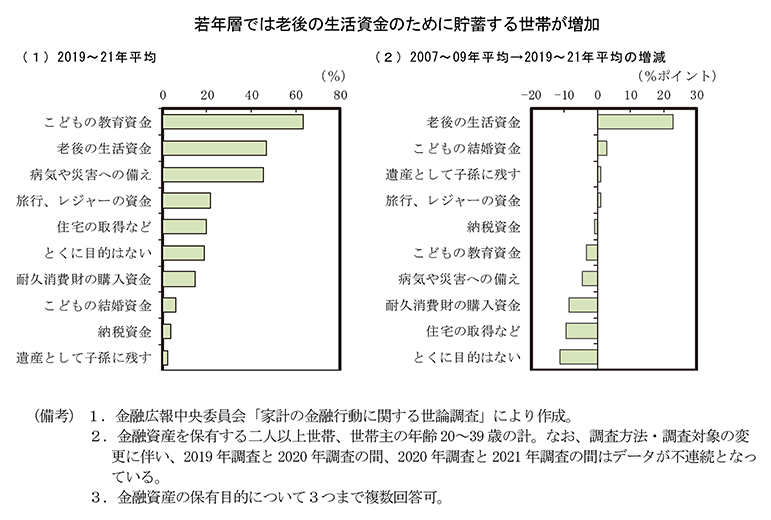
少子高齢化を背景に、現役世代が負担する社会保険料は段階的に引き上げられてきたことに加えて、上述したとおり社会保障の充実を目的として、数次の消費税率の引上げが実施されてきた。この結果、租税負担と社会保障負担の合計を所得で割り算して算出する国民負担率は上昇を続けている(第2-1-15図(1))。
他方、年金給付水準は今後も低下が見込まれる下で、金融広報中央委員会のアンケートによれば、老後を心配する世帯の割合は、2000年代前半にかけて上昇した後に、高水準で推移している20(第2-1-15図(2))。
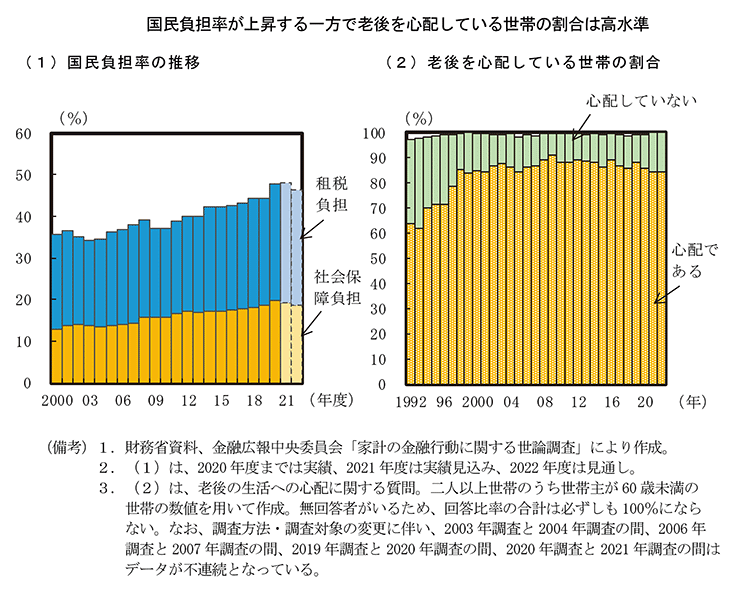
こうした老後の生活への不安の背景の1つとして、1990年代の後半から2010年代半ばにかけて続いてきた労働市場の低迷の中で、働き方の選択肢も多様化する一方、若い世代の雇用環境が悪化してきたことが指摘できる21。例えば、年齢階層別にみた非正規雇用者の割合をみると、若年期に非正規雇用に就く雇用者の割合は、生まれ年が若い世代ほど増えており、1973~82年に生まれた雇用者のおよそ3割は20~30代を非正規雇用者として過ごしており、1983~92年生まれについても足下で3割が25~34歳の若年期を非正規雇用者として過ごしている(第2-1-16図)。非正規雇用は柔軟な働き方を可能にする一方、雇用契約期間に定めがあるほか、賃金面でも正規雇用との格差があると指摘されているが22、5年を超えて契約が反復更新される有期雇用者が希望すれば無期転換できるよう定める2013年の労働契約法の改正や、同一労働同一賃金を定める2020年のパートタイム・有期雇用労働法の施行などの施策が講じられており、今後もこうした処遇差の縮小を後押しすることを通じて、若年非正規雇用者の将来不安の軽減につなげていくことが重要である23。
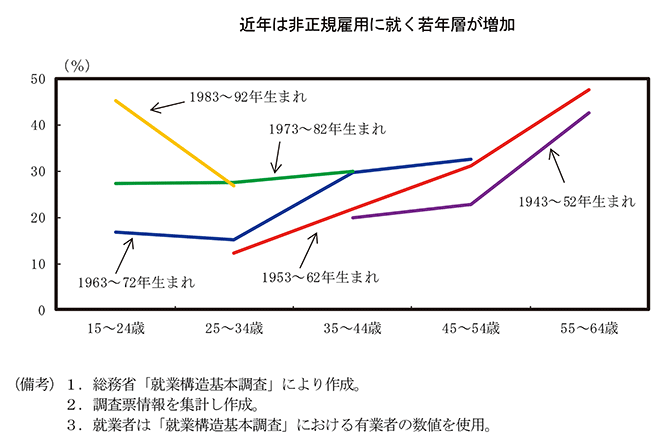
さらに、将来の社会保障制度の持続性への懸念を軽減する観点からは、以下の点が重要である。第一に、家族内扶助の役割が後退する中で社会的な世代間扶助である社会保障制度への依存が高まっていることを再認識し、世代間・所得階層間での給付と負担の割合に関する国民の理解の下で、全世代型社会保障制度改革を進めていくことである。第二に、社会保障制度の支え手を増やすために、若年女性が継続就業しやすい雇用環境の整備と高齢者の就労促進を図ることである。第三に、希望出生率の実現を目指して少子化対策を拡充することである。第四に、高齢者の一人当たり可処分所得は低下傾向にある中で、一人当たりの医療・介護費用は上昇傾向にあることを踏まえれば24、デジタル技術などを活用して、サービスの質の劣化を避けながら、社会保障関連の支出額自体を削減していくことである25。
(持家比率の高まりを背景に若年層の純金融資産はマイナスに)
さらに、家計の資産・負債の動向について、年齢階級別にみると、若年層では住宅ローン残高の増加を背景に、2000年代には平均的な純金融資産がマイナスに転化し、マイナス幅も拡大傾向にある(第2-1-17図(1)~(3))。低金利環境や住宅ローンの優遇税制の下で、若年層の住宅取得が進んだとみられるが(第2-1-17図(4))、若年期の金融資産・負債のバランスがこの20年間に急速に負債超過方向に変化したことも、若年層の予備的動機を背景とした消費性向の低下につながっている26。
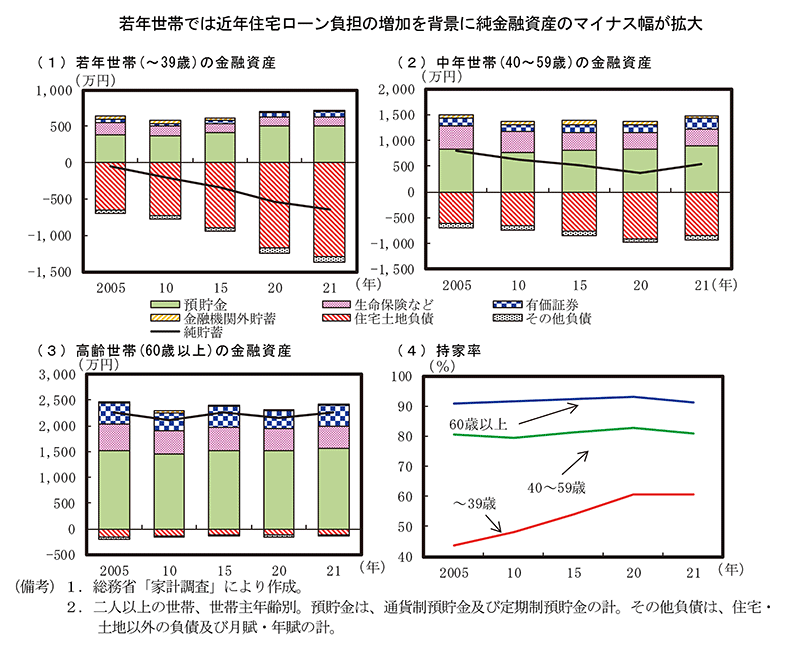
(子・孫世代への不安も高齢層の消費スタンスの慎重化に寄与)
次に高齢者の消費性向をみる。前掲第2-1-13図をみると、65歳以上の高齢者層の消費性向も、近年は緩やかな低下傾向にあった。伝統的な経済理論であるライフサイクル仮説によれば、若年期に所得の一部を貯蓄に振り向けた個人は、高齢期には貯蓄を取り崩して所得を上回る消費を行うとされる。では、足下の高齢者の貯蓄の取り崩しペースは慎重と言えるであろうか。この点を確認するため、総務省「全国消費実態調査」27を用いて、資産階級別に高齢世帯の貯蓄の取り崩しペースを検証する。これをみると、貯蓄の取り崩し額は保有している資産が大きい世帯ほど大きいが、保有資産対比でみた取り崩し率では、保有資産が大きい世帯ほど低いことがわかる(第2-1-18図(1))。更に、世帯別の構成割合を加味した平均的な貯蓄取り崩し率は近年緩やかに低下しており、感染拡大以降はさらに落ち込んでいる(第2-1-18図(2))。仮に貯蓄取り崩し額が、「家計調査」における全高齢世帯の平均である2%程度相当とすると、貯蓄を取り崩すのに掛かる年数は約50年である。あくまで平均値ではあるものの、平均年齢が70歳を超える高齢世帯の取り崩しペースとしては保守的であるとともに、近年はその保守性がより強まっていると評価できる。ただし、前掲第2-1-18図(1)でみたとおり、保有資産の規模間で取り崩し率の違いが大きく、特に保有資産300万円を境に、取り崩し率からみる余力には大きな差が生じている点には留意が必要である。
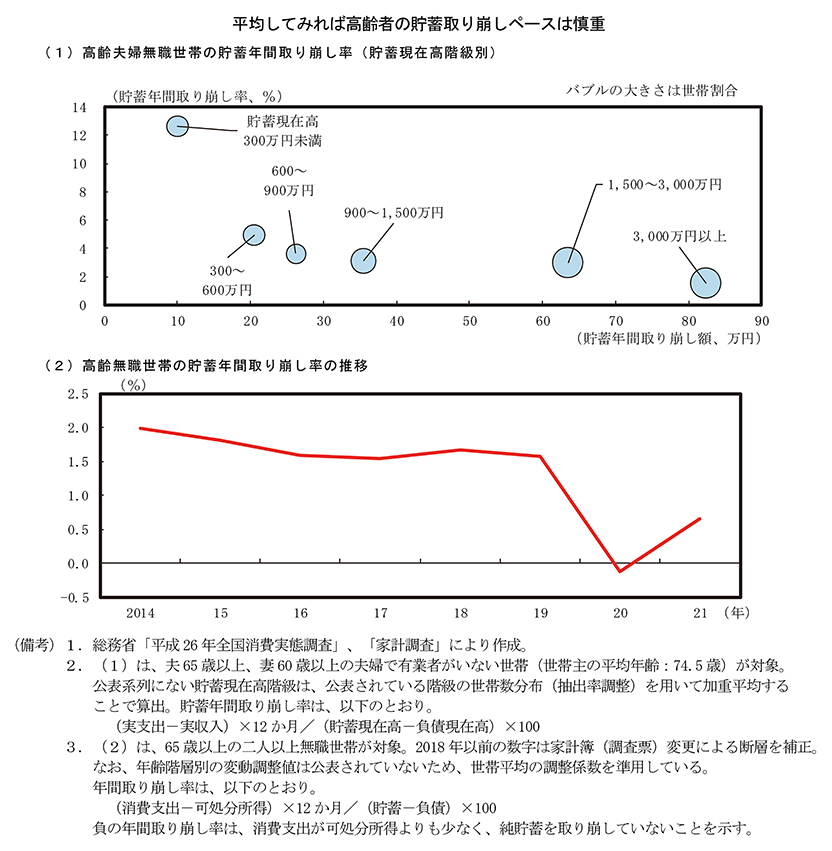
次に、若年層と同様に、高齢者についても金融広報中央委員会のアンケート調査により、貯蓄をする理由の回答割合をみると、2019~21年平均では「老後の生活資金」や「病気や災害への備え」の割合が高く、自らの生活資金を補填する意識が高い点が指摘できるが、回答割合について2007~09年から2019~21年への変化でみると、「遺産として子孫に残す」の割合の上昇幅が最も大きい(第2-1-19図(1))。この点、同アンケートの調査票を用いた先行研究によれば、自分よりも子供の将来の暮らし向きが悪くなると予想する高齢者ほど、貯蓄率が有意に高まる傾向が指摘されている28(第2-1-19図(2))。
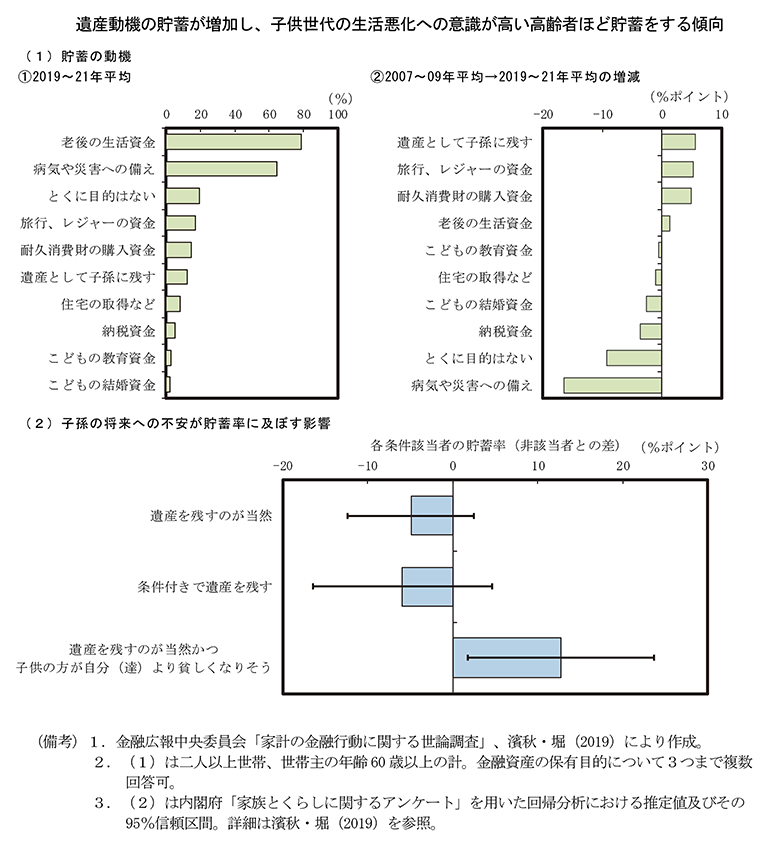
(賃上げ・多様な労働参加の促進・少子化対策等を通じた将来不安の軽減が鍵)
本節の内容をまとめると以下のとおりである。アフターコロナに向けて個人消費を力強く引き上げていくためには、第1項で論じたように足下の物価高騰への対策を講じていくことに加えて、構造的に消費を下押ししてきた将来不安を解消することも重要である。特に、若年層の消費性向が近年低下傾向にあったこと、子・孫の世代の雇用・所得環境への懸念が高齢者の消費支出への足かせとなっていることも考えれば、①現役世代の賃金が構造的に上昇する社会に変えていくこと、②多様な働き方による労働参加を促す中で高齢者が働き続けられる環境を整備29することにより、現役世代の生涯賃金に対する見通しを改善させる取組がまず重要である。さらに、社会保障制度の持続性への懸念を払拭するために、③デジタル技術の活用による医療・介護費用の抑制等や少子化対策を進めるべきである30。なお、世代間の再分配を促して消費支出を促すための相続や贈与に関する税制上のインセンティブ措置も検討材料となろう。
コラム2-1 金利上昇時の住宅ローン保有世帯への影響
歴史的なインフレの抑制に向けて、欧米の中央銀行は2022年以降、数次にわたり政策金利の引上げを実施している。我が国でも消費者物価上昇率は約40年振りの水準となっているが、需給ギャップが依然としてマイナスで推移するなど、コストプッシュインフレの側面が強く、日本銀行における長短金利操作付き量的・質的金融緩和の下で、低金利が維持されている。他方、2022年4月の住宅金融支援機構の調査によると、2021年10月時点の調査と比較して、1年後の住宅ローン金利が現在よりも上昇すると予想する家計が、約2割から約4割へと高まっている(コラム2-1-1図)。
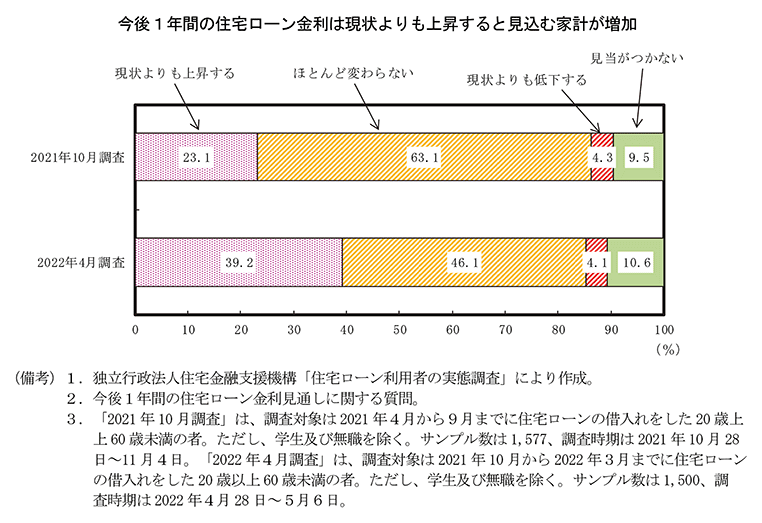
我が国では金融自由化や住宅金融公庫(現住宅金融支援機構)の改革によって、住宅金融市場は大きな変容を遂げており、必要な頭金が少額になっているほか、新築だけでなく中古住宅も融資対象となるなど、家計にとって住宅ローンの選択肢が広がってきた31。また、住宅ローンの10年固定金利は2022年以降に幾分上昇しているが、やや長い目で2000年代以降をみると、長期金利が低下する中で、住宅ローン金利も変動・固定共に低下傾向にある(コラム2-1-2図(1))。こうした緩和的な資金調達環境を背景に、我が国家計部門の住宅ローンの負債残高は増加傾向にある。
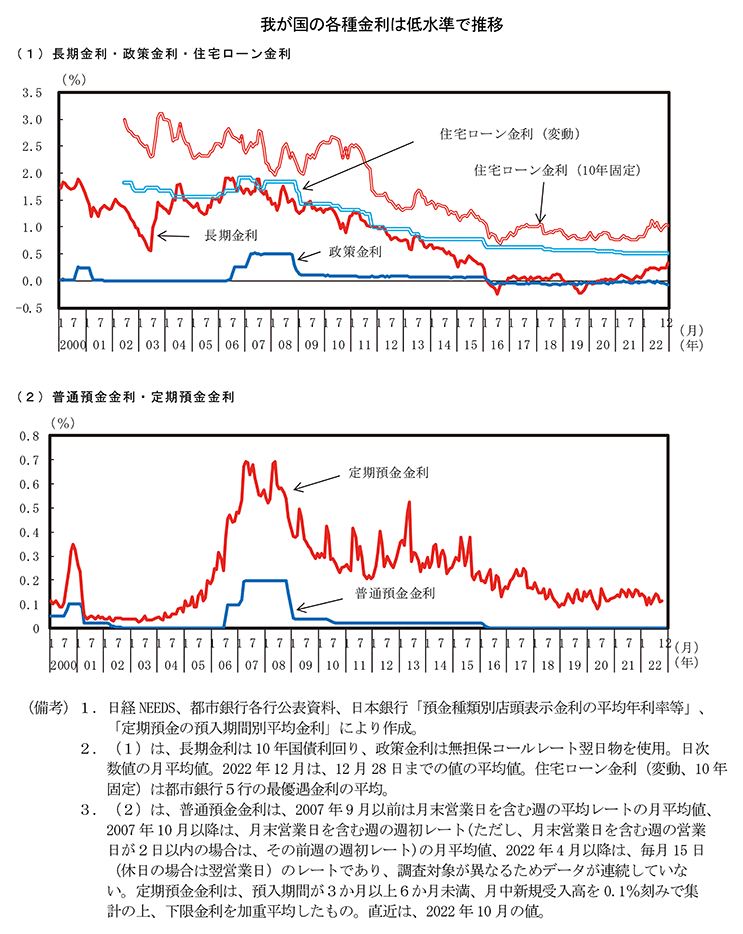
また、消費者信用等も含めた家計の負債残高は全体として増加傾向にあるが(コラム2-1-3図(1))、金利低下は家計の支払利子負担を抑制してきた。実際、家計の月々の住宅ローンの返済負担は対可処分所得対比でみると低下傾向にある32(コラム2-1-3図(3))。他方で、低金利環境は、前掲コラム2-1-2図(2)のとおり、預金金利も低下させ、家計の受取利子を押し下げてきた。実際、2006年のゼロ金利解除時33の金利上昇局面の受取利子と支払利子の動きをみると、負債サイドの住宅ローン金利と資産サイドの預金金利がいずれも小幅に上昇する中で、純受取利子(=受取利子-支払利子)のマイナス幅が縮小した(コラム2-1-4図)。前掲コラム2-1-3図(1)と(2)の比較から明らかなように、家計部門全体としてみると、預貯金残高が負債残高の約2倍の規模であり、金利上昇局面における預金金利と負債金利の上昇幅に大きな開きがなければ、受取利子の増加幅が支払利子の増加幅を上回ることになる。
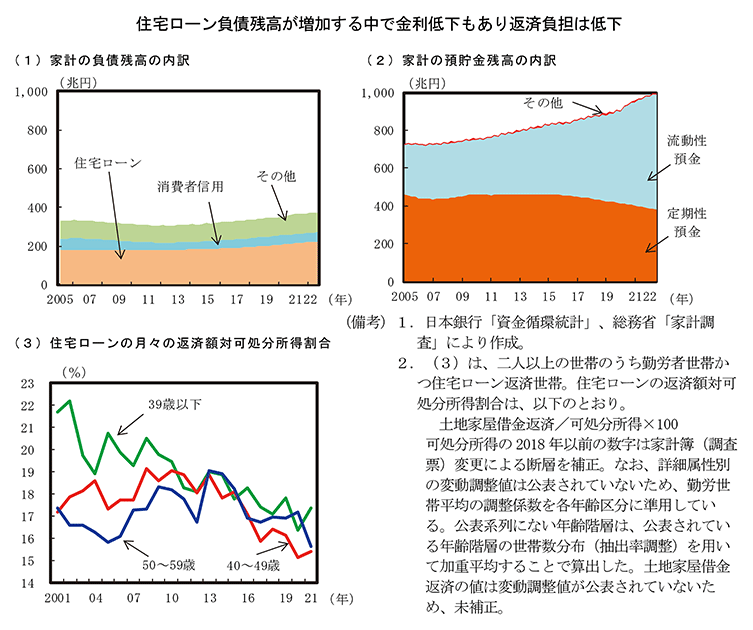
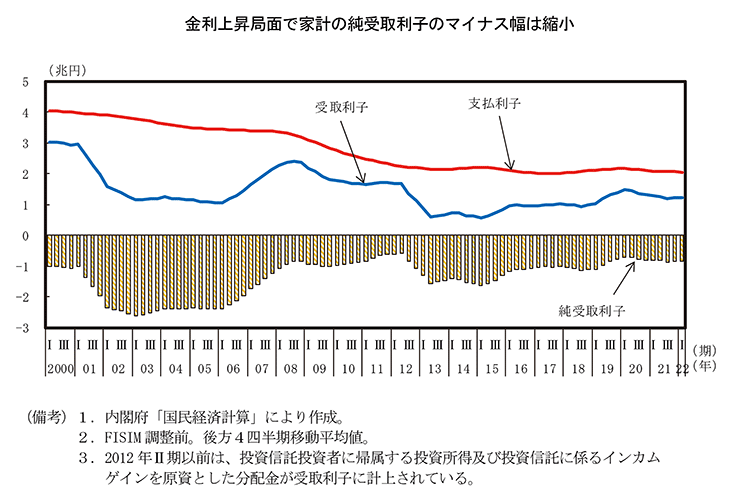
ただし、預貯金残高と負債残高を年齢階層別にみると、前掲第2-1-17図のとおり、高齢世帯では預貯金超過となっているが、若年世帯では負債超過となっており、預金金利と負債金利が同様に上昇した場合には、若年世帯の純受取利子を悪化させるが、高齢世帯では純受取利子を改善させるといった形で、世帯属性によって受ける影響が大きく異なることには留意が必要である。また、こうした年齢階層間での構造的な影響の差に加えて、最近の家計の住宅ローンの組成状況の変化を踏まえると、以下の点にも注意が必要だろう。まず、住宅価格が上昇傾向にあることもあり、中長期的な返済負担を示す負債残高対年収倍率は、39歳以下を中心に顕著に上昇している(コラム2-1-5図)。さらに、家計の住宅ローンを金利タイプ別にみると、変動金利型の割合が高まっており(コラム2-1-6図)、金利が上昇した場合の返済負担が大きく変動する世帯が増えていると考えられる。こうした中で、住宅金融支援機構の調査によれば、変動型金利を選択したローン利用者のうち、商品特性について十分に理解していない層が相応に存在している(コラム2-1-7図)。
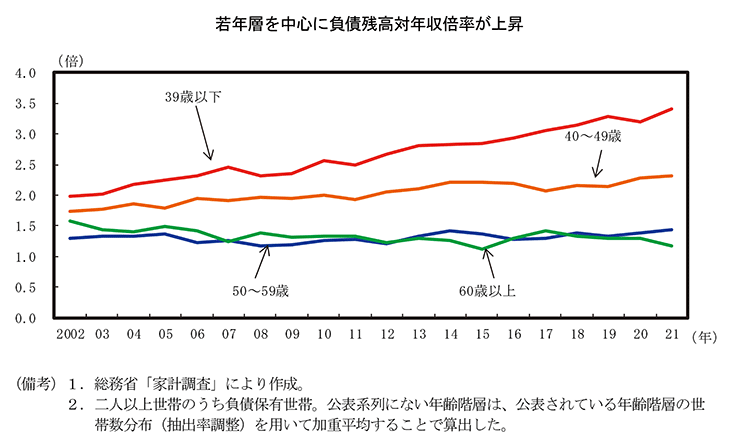
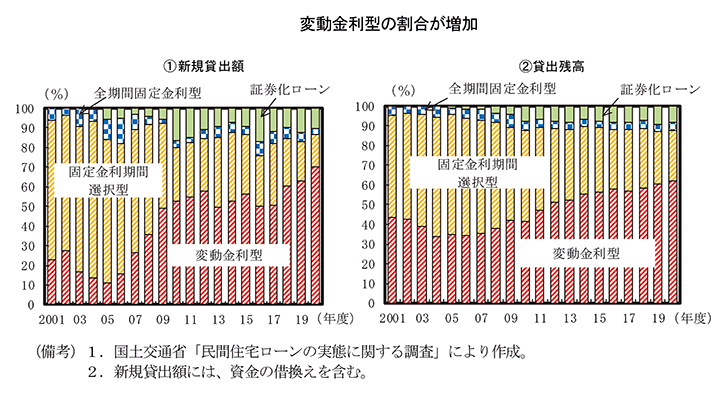
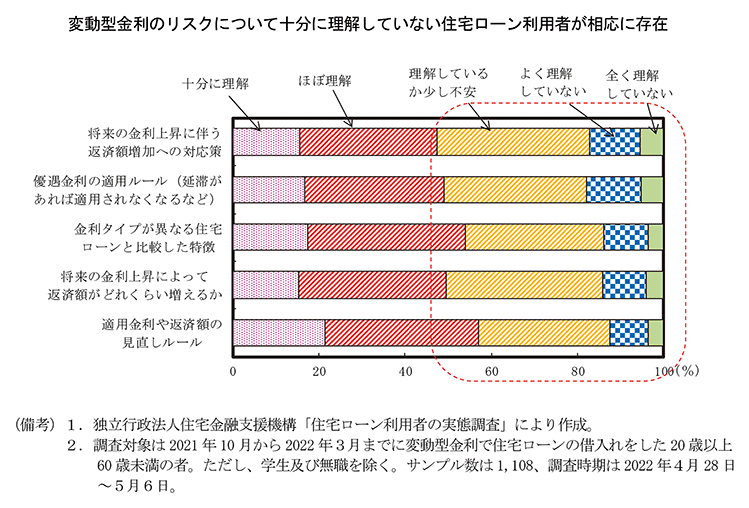
これまでのところ、住宅ローンの延滞率に著しい変化はみられていないほか、金融機関にとっても、企業向け貸出対比では貸出先が分散していることを背景としたリスク分散効果から信用コストの増大にはつながりにくく、我が国の金融仲介機能を大きく損なうリスクとはみられていないが34、住宅ローン保有者の債務特性の変化を踏まえると、変動金利型でローンを組んでいるが金利上昇時のリスクについて十分に備えていない世帯や負債残高対年収倍率が高い若年世帯など、一部の家計における金利上昇への脆弱性が高まっている可能性があり、今後の動向を注視していく必要がある。政府は、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」35の中で、金融リテラシーの向上に向けた情報発信の強化を掲げており、こうした取組等を通じて家計のリスク管理をサポートすることが重要である。
コラム2-2 感染拡大を契機とした生活時間の変化
2020年以降、感染症への対応が進む中でテレワークの増加等、働き方や消費スタイルに変化が生じている。こうした変化のうち、構造的な変化として定着するものがどの程度存在するのか不確実性が伴うが、本コラムでは、5年ごとに国民の生活時間の配分と過去1年間における活動状況を調査している総務省「社会生活基本調査」(2021年調査36)の結果を、前回調査(2016年)と比較することで、感染症の拡大がもたらした生活時間・活動状況の変化の特徴を考察する。
まず、年齢階層別に生活時間の配分の変化を概観すると以下のことが分かる(コラム2-2-1図)。第一に、現役世代(20~50代)では、「仕事・学業」や「通勤・通学」の時間が大幅に減少している。これは感染拡大下におけるテレワークの拡がり等の働き方の変化を反映した動きであると推察される。第二に、「交際・付き合い」や「移動(通勤通学を除く)」が減少している。これは、感染症下の移動制限措置や自粛行動を反映した変化であると推察される。第三に、こうした家の外で過ごす活動の減少の裏で、「睡眠」や「休養・くつろぎ」の時間が増えている。この間、働き方改革による就業時間の削減の効果として期待されていた「学習・自己啓発・訓練」の時間は微増にとどまっている37。
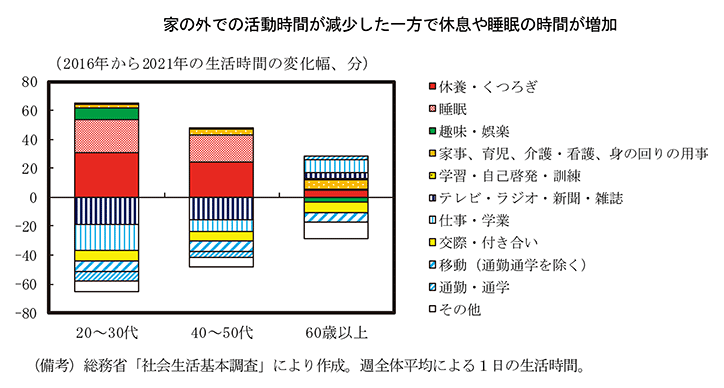
次に20~30代の生活時間として増加が目立つ「趣味・娯楽」について、具体的な活動内容別に実施者割合の変化をみると、「スマートフォン・家庭用ゲーム機などによるゲーム」の割合が最も上昇しており、次いで「CD・スマートフォンによる音楽鑑賞」となっている(コラム2-2-2図)。他方で、「カラオケ」「遊園地、動植物園、水族館などの見物」などの外出と出費を伴う活動の実施割合は大きく減少している。サブスクリプションサービスや広告収入で運営される無償のデジタルサービスは、現行の経済統計では未計測の付加価値を生んでいると指摘されており38、こうした活動内容の変化は、感染拡大以降に消費性向の低下が計測される一因となっている可能性がある。
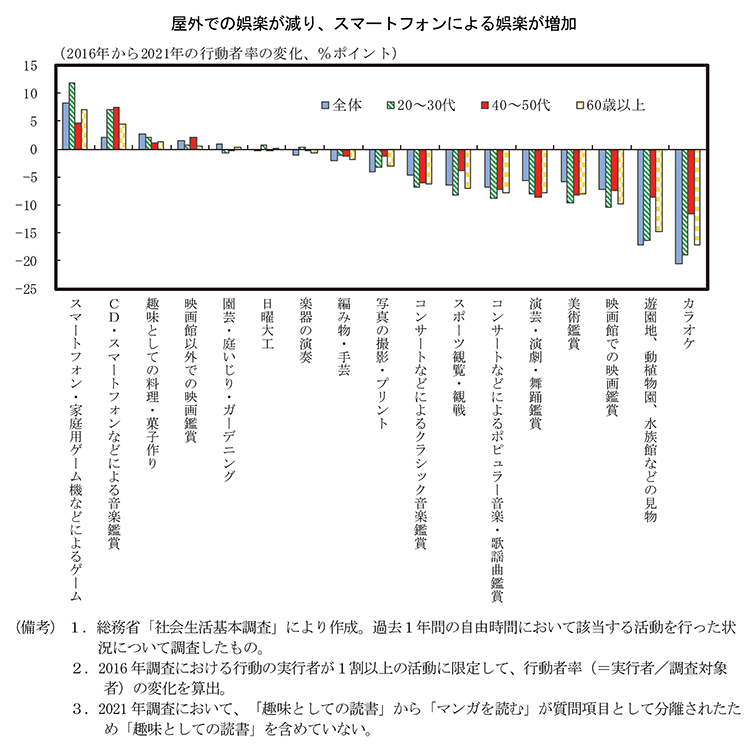
最後に、我が国の男性の育児・家事参加の促進は、女性の就労促進の観点から課題の一つとなっているが、子供がいる者の生活時間の変化をみると、末子が未就学の場合には、男性が「家事、育児、介護・看護、身の回り用事」に費やす時間が増加した一方で、女性の「仕事・学業」の時間が増加しており、男女間の家事・仕事の分担の偏りが是正方向にある(コラム2-2-3図(1))。こうした傾向は、末子の年齢が上がるほどに縮小し、中学生・高校生となると、2016年との差はほとんど生じていないが、テレワークの拡がりによる男性の在宅時間の増加が2021年入り後の変化を促した可能性がある。他方、2021年においても、家事や育児と仕事の時間を子供がいる者で比較すると、依然として男女間の格差は大きく、男性側の働き方改革や男性が育児参加をするためのインフラの整備等39を進め、男女間の役割の偏りを小さくしていく取組が重要である(コラム2-2-3図(2))。