第1章 世界経済の不確実性の高まりと日本経済の動向(第2節)
第2節 我が国の物価動向
欧米におけるコロナ禍からの需要回復とウクライナ情勢による国際商品市況の上昇等を受けた輸入物価の上昇は企業物価や消費者物価ともに約40年ぶりの上昇をもたらしている。そこで本節では、企業物価の動向と価格転嫁の状況、消費者物価の現状と家計への影響、今回の物価上昇の要因と基調の強さなどについて検証する。
1 企業物価の動向と価格転嫁の状況
(輸入物価の上昇を受け、企業物価は42年9か月ぶりの上昇)
はじめに輸入物価の推移から見てみよう。原油をはじめとする原材料価格が上昇する中で、2021年3月に前年同月比でプラスに転じて以降、上昇幅を拡大し続け、2022年7月に49.1%となった後、上昇幅が縮小した(第1-2-1図(1))。輸入物価(円ベース)上昇の内訳をみると、2022年夏までは国際商品価格の上昇を受け、「石油・石炭・天然ガス」といったエネルギー価格の上昇(契約通貨ベース)が押上げに最も大きく寄与してきたが、夏以降、2021年末ごろから進行してきた円安による為替要因の押上げ寄与がエネルギー価格上昇の寄与を上回るようになった。その結果、2022年11月時点では輸入物価の前年同月比(28.2%)における為替要因の寄与度は19.6%と上昇率の7割程度を占めている。
次に国内企業物価についてみると、輸入物価の上昇を受けて2021年3月以降、前年同月比でプラスに転じており、2022年9月には1980年12月以来42年9か月ぶりの上昇となる10.3%となった後、上昇幅を縮め、11月には9.3%となっている。内訳をみると、原油等の資源価格の上昇を受けて「電力・都市ガス・水道」が最も押上げに寄与している(第1-2-1図(2))。
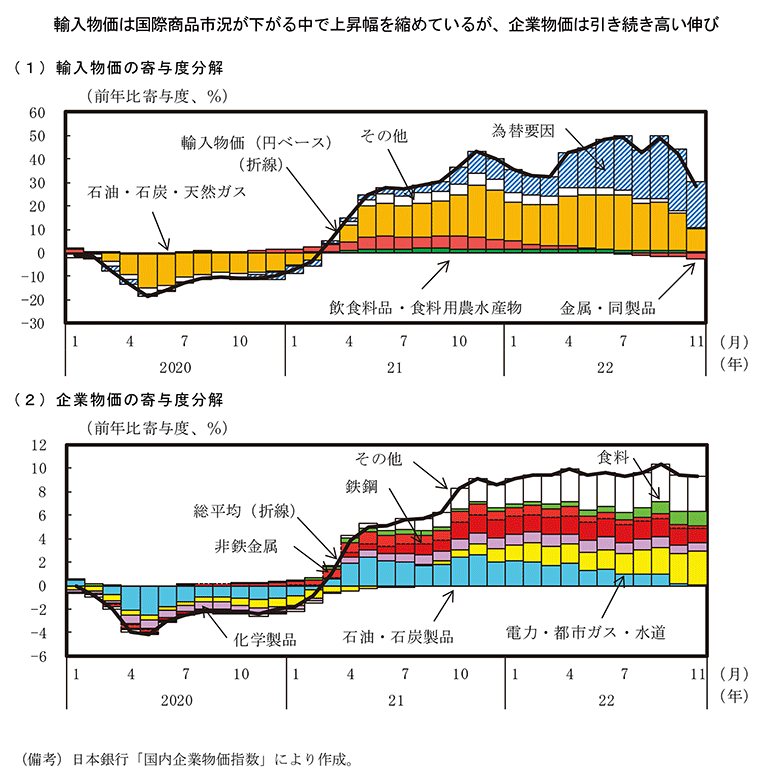
(日米の物価変動のパススルーを比較すると我が国のパススルーは相対的に小幅)
最終需要・中間需要物価指数(FD‐ID指数)を用いると、需要段階別の物価動向を詳細にみることができる。FD‐ID指数とは、企業の生産フローに投入される財・サービスを生産段階ごとに分類し、素材・原材料に最も近い段階であるステージ1から最終需要に最も近い段階のステージ4まで、中間需要の各ステージと最終需要の価格を表したものである。これを用いて、我が国における企業間の物価変動のパススルーの特徴をみるため、我が国とアメリカのFD‐ID指数を比較する。
我が国では、輸入物価の上昇により、最も川上にある中間需要ステージ1が2021年3月以降大きく上昇している一方で、最終需要の上昇は小幅にとどまっており、生産フローが川下になるにつれて物価変動が弱まっていることが分かる。一方で、アメリカでは生産フロー間の上昇率の差が小さく、我が国の物価変動のパススルーはアメリカと比べて弱いことが確認できる(第1-2-2図(1))。
我が国において、企業部門での中間需要段階と最終需要段階の投入価格へのパススルーに続いて、その先で企業における最終需要価格が、消費者が購入する段階での財やサービスの価格に対し、どの程度パススルーされているかも見てみよう。そこで、FD‐ID指数の最終需要のうち消費財の卸売価格と消費者物価指数(生鮮食品を除く財)の前年比上昇率の相関関係を確認すると、我が国の消費者物価の消費財価格に対する弾性値は2020年以降上昇しており、それ以前に比べて消費者物価への価格転嫁が進展していることが示唆される(第1-2-2図(2))。ただし、アメリカと比較すると弾性値は低く抑えられており、価格転嫁の動きが相対的に弱いことが分かる。
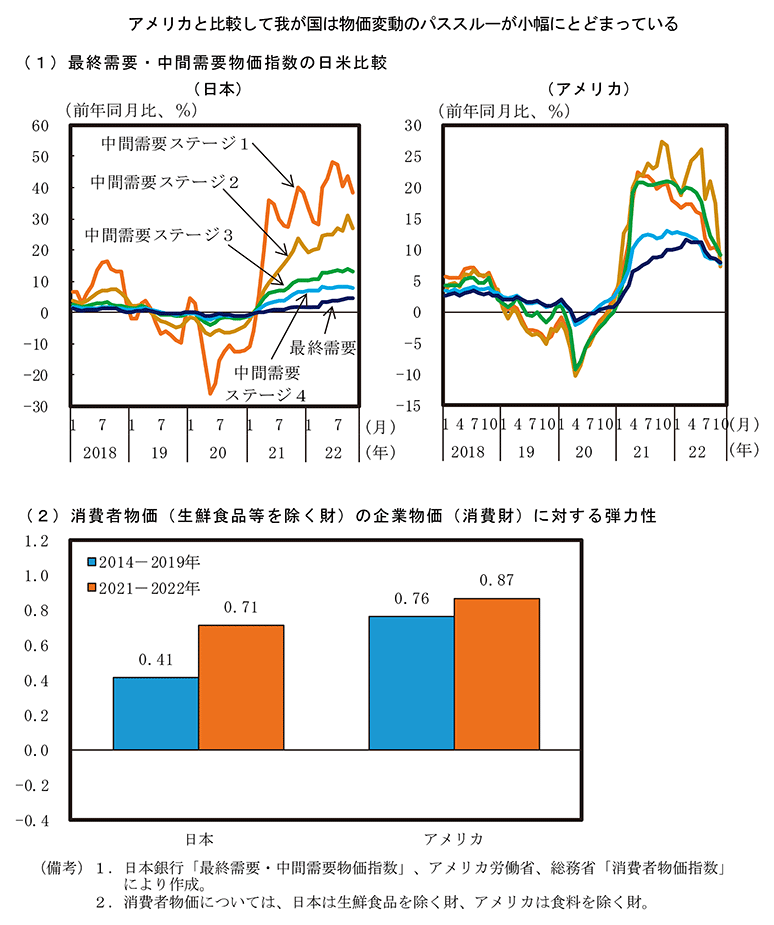
(一部で改善の兆しはあるものの、企業における疑似交易条件は総じてみると悪化)
財・サービスの投入構造には中間投入コスト以外に雇用者所得や営業余剰等が含まれるため、中間投入コストの増加を100%価格転嫁したとしても、需要段階の川上と川下の価格上昇率は一致しない。そこで、このような物価変動のパススルーの弱さについて、その背景を確認するために、日銀短観の販売価格DIから仕入価格DIを差し引いた値(以下「疑似交易条件」という。)を用いて、各業種の産出価格と投入価格の上昇幅の違いを分析する1。
2021年以降はいずれの規模・業種においても、仕入価格DIの上昇に販売価格DIが追い付いていないことから疑似交易条件が悪化してきた。こうした悪化は、過去に仕入価格が上昇した2018年前後にもみられるが、今回は当時と比べ仕入価格DIがより急速に上昇する中で悪化幅が大きくなり、素材系業種を中心に販売価格DIの上昇により疑似交易条件の改善がみられるものの、総じてみると、引き続き価格転嫁が不十分な状況である(第1-2-3図)。
これを規模別にみると、これまで同様、一般的に価格交渉力の弱いとされる中小企業において疑似交易条件の悪化が顕著な傾向にあり、価格転嫁が進展しておらず、また、今回は大企業にも疑似交易条件の悪化が及んでいるなど、規模を問わず仕入価格上昇の影響が出ていることがわかる。また、業種別にみると、製造業では、素材系に比べてより川下に近い食料品や電気機械、輸送用機械といった加工系の業種での疑似交易条件の悪化が目立つ傾向にあるが、2022年4-6月期以降は緩やかに改善している。他方、非製造業では、建設や不動産・物品賃貸業において建設資材の高騰の価格転嫁が遅れている。また、中小企業を中心に企業数が多く、個社の価格交渉力が弱い傾向にある運輸・郵便業や、需要がコロナ禍前に戻っていない宿泊・飲食サービス業などでは、大企業・中小企業ともに価格転嫁が困難な状況が続いている。加えて、2022年以降情報通信業では、仕入価格が上昇している一方で販売価格は横ばいと疑似交易条件が悪化し続けている(付図1-1)。
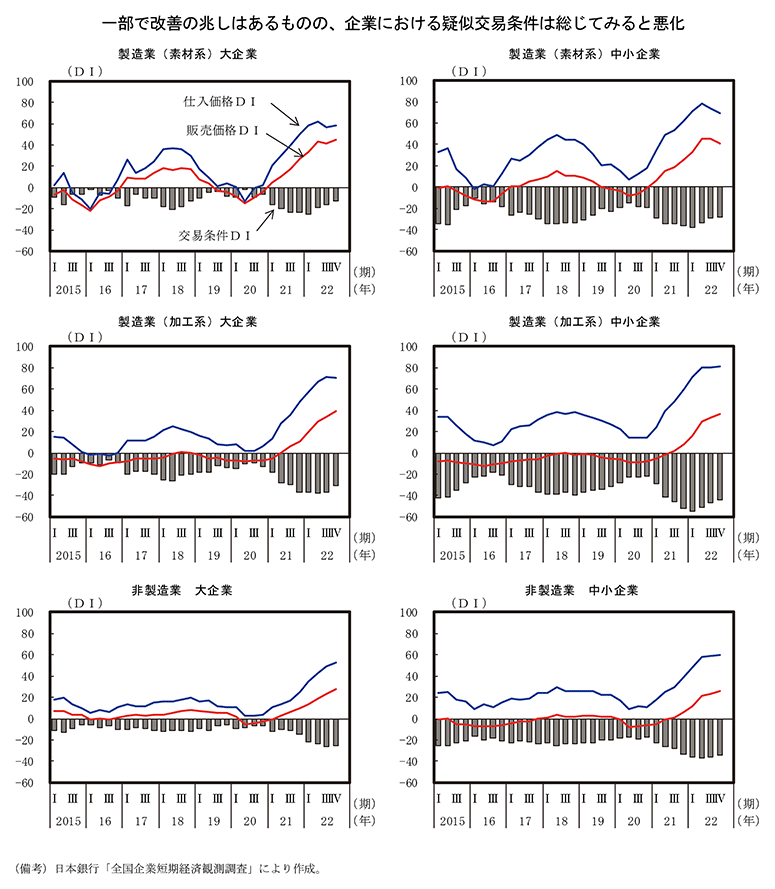
(仕入価格と販売価格の差は依然としてあるものの、2008年物価上昇局面からは改善)
次に、疑似交易条件の動向を前回大きく物価が上昇した2008年と比較してみよう(第1-2-4図)。2008年の物価上昇局面においては、製造業は2006年に入った頃には既に仕入価格が上昇していたが販売価格DIはマイナスで推移していた。2008年に入ってようやく販売価格DIがプラスとなったものの、2008年10-12月期に世界的な景気後退によって輸入物価が下落し、仕入価格が下落するまで疑似交易条件の明確な改善はみられなかった。非製造業については、中間投入に占める輸入品の割合が低いことから、製造業と比較して相対的に仕入価格の上昇は緩やかだったとはいえ、仕入価格DIが大きく上昇した2008年においても販売価格DIはマイナスで推移したまま、製造業同様、輸入物価下落に伴って仕入価格が下落することでようやく疑似交易条件が改善した。
これに対し、今回の物価上昇局面においては、輸入物価が2021年3月に前年比プラスに転じたことで、仕入価格DIについても2021年1-3月期から上昇トレンドが始まったが、販売価格DIも同年4-6月期にはプラスに転じている。また、非製造業では、販売価格DIのプラスへの転換は7-9月期と1四半期遅れたものの、その後、仕入価格DIの上昇に伴って販売価格DIも上昇している。疑似交易条件は2021年から2022年にかけて悪化しているが製造業を中心に改善の兆しがみえており、2008年の物価上昇局面と比較すると、より多くの企業が販売価格への転嫁を行っている。
このように企業部門において、価格転嫁の動きは進みつつあるが、改善の余地がある。特に中小企業では価格転嫁が抑制された結果、仕入価格の上昇に対して販売価格が追い付いていない状況となっている。今後、価格転嫁の更なる促進と適切な価格付けを通じて企業が確保した付加価値が賃上げの原資となり、これが家計に還元されることで消費者の購買力が維持され、更に価格転嫁等をしやすい状況になるという好循環を作ることで、構造的賃上げを実現していくことが重要となる。
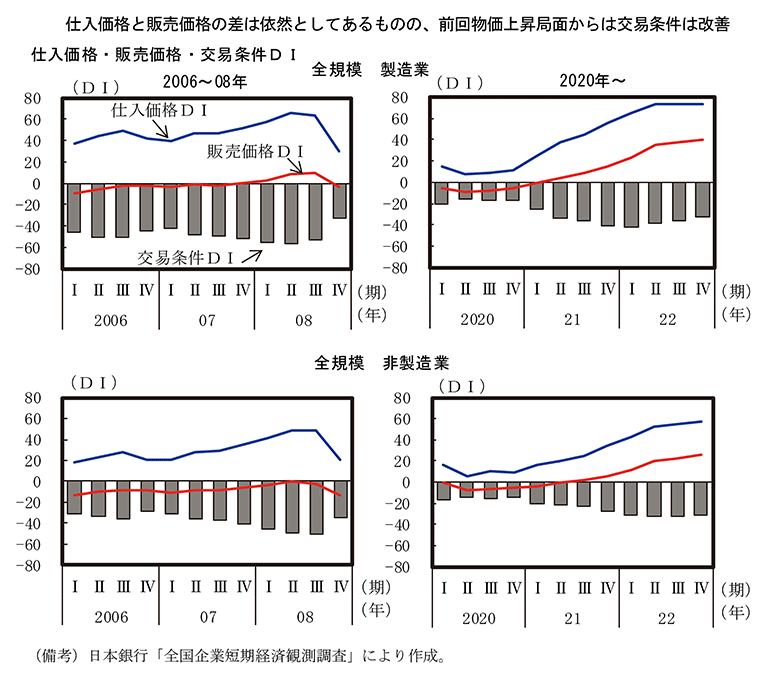
コラム1-2 為替のパススルー
2022年入り以降の輸入物価の急激な上昇において、為替変動の寄与が大きくなっている。そこで、為替変動に着目してその国内物価への影響をみるため、VARモデルを用いて国内企業物価や消費者物価へのパススルー率を推計し、川上から順に影響をみるため、為替レートの変化の輸入物価への影響からみていく。推計結果をみると、輸入物価は徐々に上昇幅を縮めながらも5か月にわたって上昇を続け、1年後には累積で1.5%ポイント上昇する(コラム1-2図)。次に企業物価への影響をみると、企業物価は最初の4か月程度の間にパススルーが進み、累積で約0.2%ポイント上昇した後、徐々にペースを緩めながら上昇を続ける結果となり、企業取引段階であっても価格転嫁に一定の時間を要している様子が窺える。しかし、2000年~19年の推計結果と比べると2022年まで含めた推計結果ではパススルー率が高まっており、足下では価格転嫁が進んでいる様子がうかがえる。
続いて、消費者物価への影響をみると、2000年~22年の推計結果では、為替変動直後の2か月以内に上昇した後、その後は徐々に価格転嫁が進むものの、1年後であってもパススルー率は累積で約0.05%ポイントにとどまっている。推計期間を2019年までに限ると、2か月目以降にはほぼパススルーはみられないことと比べると、足下の物価上昇局面においては小売価格への転嫁が進んでいる様子がうかがえる。しかし、企業物価以上に価格転嫁に時間を要すること、企業物価と比べるとパススルー率が低いことを勘案すると、円安による輸入物価上昇に対し、最終消費者への販売段階でも、企業内で物価上昇の影響が吸収されている可能性が示唆される。
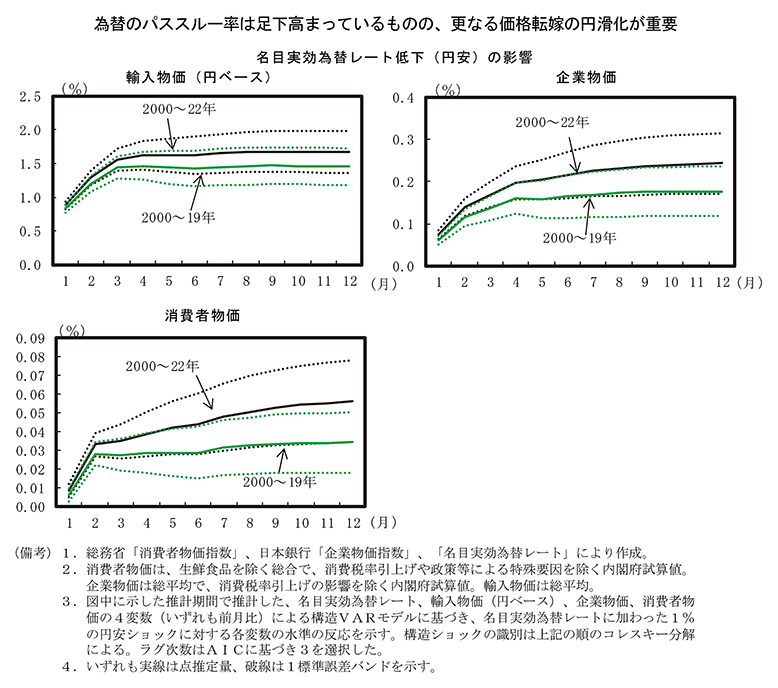
コラム1-3 品目別の価格転嫁の動向
2019年以前と比較すると、今回の物価上昇局面では、価格転嫁が進んでいる可能性が示唆される一方、品目によって差はあるものの、現状では多くの品目で、原材料価格等(仕入価格)の高騰による仕入れコストの上昇分を一部しか販売価格へ転嫁できていない、つまり交易条件が悪化していると考えられる。輸入物価、企業物価、消費者物価の上昇品目率と下落品目率の差分をDIとしてとり、その推移を比較すると、輸入物価が上昇してから企業物価、消費者物価へとラグを伴って波及していく様子がうかがえる。この関係から現在の消費者物価の状況をみると、価格転嫁が続いている段階であると考えられる。(コラム1-3図(1))
そこで、原材料価格等の上昇によるコストの増加が製品(消費者物価)に価格転嫁されるまでのラグについて、消費者物価の構成品目のうち31品目の上昇率とそれぞれの生産過程で投入することが想定される輸入物価の構成品目の上昇率との間で時差相関を確認してみる。結果をみると、品目によって異なるものの、平均的には4四半期前の相関が最も高く、輸入された原材料価格等の高騰が最終消費財の価格に転嫁されるまで、ほぼすべての品目で半年以上のラグが存在することがうかがえる(コラム1-3図(2))。
企業の価格決定プロセスとしては、原材料等の調達に当たっての輸入業者等との価格協議、社内における検討、小売店との調整等を経て、販売価格へ反映すると考えられるが、企業の価格改定のリリースは出荷価格改定の半年~3か月前頃が多いことから、1年~半年程度のラグが最も説明力が高いという推計結果は、一定の妥当性を持つと言えよう。
品目によって相関の高いラグが異なる背景としては、例えば市場構造の違いが考えられる。独占的な販売企業は価格交渉力が高いことから販売価格への価格転嫁が比較的早く進む一方、競争的な環境にある企業の価格交渉力は弱いため販売価格への価格転嫁が遅くなる。また、加工度の高い品目は個別の投入素材の価格上昇の寄与が小さいため、価格転嫁まで時間がかかることなどが考えられる。あるいは、米穀等の農産物など、想定上の需給に応じ取引価格が設定される品目は、コスト上昇を直接的に販売価格に反映できないことから、輸入物価との相関が低い結果となっている。
このように、価格転嫁に要するラグについては品目や業種によって様々な背景があるものの、価格転嫁に時間を要することで交易条件の改善が遅れる場合には、企業は価格転嫁までの間の付加価値を圧縮するため、投資や賃上げの余力を削っていることになる。そのため、競争が厳しく個別企業の価格交渉力が弱い品目や業種であっても、原材料コスト増を価格に転嫁しやすい環境の確保が、持続的な成長のためには今後重要になってくる。
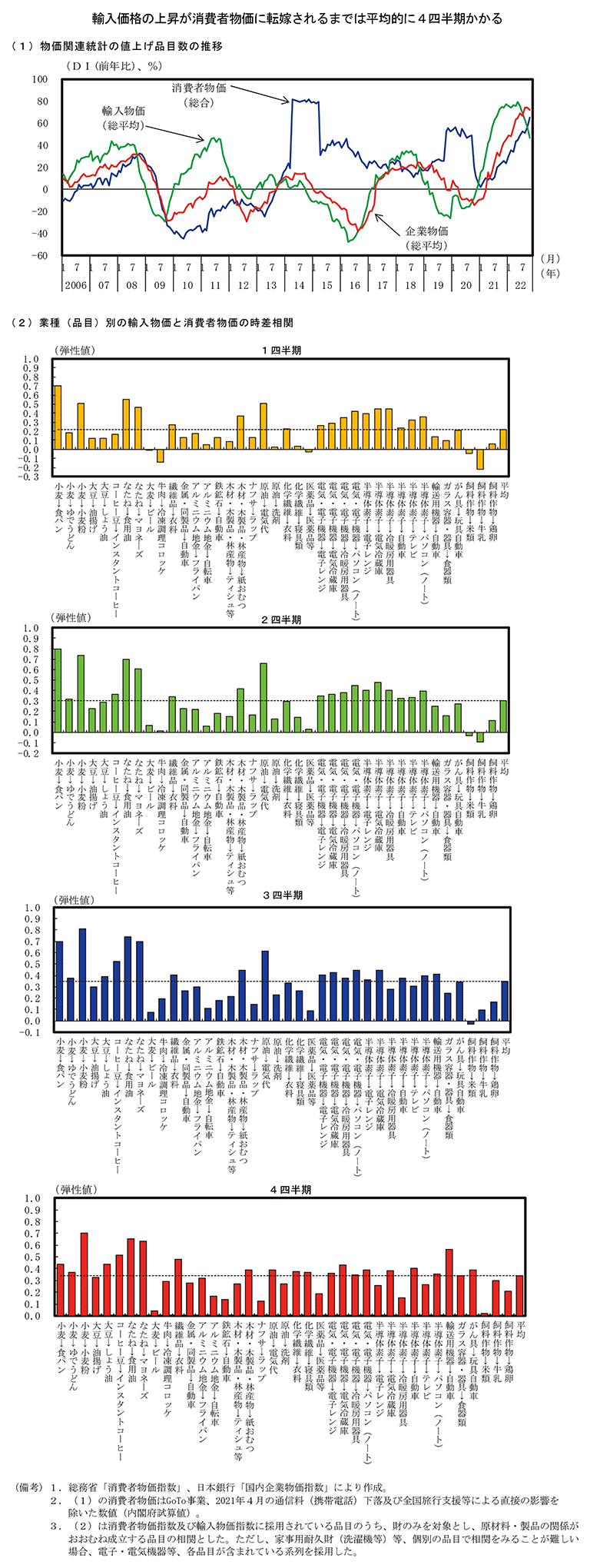
2 消費者物価の上昇と家計への影響
(今回は物価上昇のペースは緩やかながらも長期間に渡って上昇幅を拡大)
消費者物価(コア)については、企業物価の最終財価格を転嫁する形で2021年9月以降、前年同月比がプラスとなっており、「食料」や「水道・光熱」などが押し上げに主に寄与しているが、その他の品目についても徐々に寄与を高め、2022年11月には40年11か月ぶりとなる3.7%となった(前掲第1-1-4(3))。そこで、消費者物価の総合と品目分類別の動向を過去の物価上昇局面と比較してみよう。まず、消費者物価総合の動きをみると、今回の特徴として、国際商品市況における原油価格の上昇開始から消費者物価上昇率がピークを迎えるまでの期間の長さが挙げられる。第一次石油危機、第二次石油危機、2000年代半ばの物価上昇局面はいずれも、国際商品市況で原油価格が上昇に転じてから約1年で物価上昇のピークを迎えたが、今回は消費者物価の上昇率の拡大ペースは相対的に緩やかであるものの長期にわたって高まり続けており、19か月を過ぎた2022年11月においても依然として上昇基調にある(第1-2-5図)。
品目分類別に動向をみると、電気・ガス代の上昇ペースは電気料金について認可制だった第一次石油危機時よりも早く、上昇率も同程度となっている。電気代の規制料金適用部分については、電力各社の価格が燃料費調整制度に基づく上限額に達した影響もあり、2022年10月以降は頭打ちとなっている。他方、その他の品目については、コロナ禍からの需要回復等に伴う国際運送費の上昇や原材料価格の上昇、円安による輸入物価の上昇が時差を伴って消費者物価に反映されることから、食料品の上昇にやや遅れて家具家事用品、被服及び履物などにも上昇が波及してきている。その結果、これらの品目の物価上昇率は、2022年11月時点で2000年代半ばの物価上昇局面を超え、第二次石油危機時の上昇率に迫っている。長く続くデフレにおいて、価格の粘着性が強くなっていたことなどから、輸入物価の急激な上昇に比して消費者物価上昇率が抑えられてきたものの、物価上昇が長く続く中で多くの品目に価格上昇が広がっている様子がうかがえる。
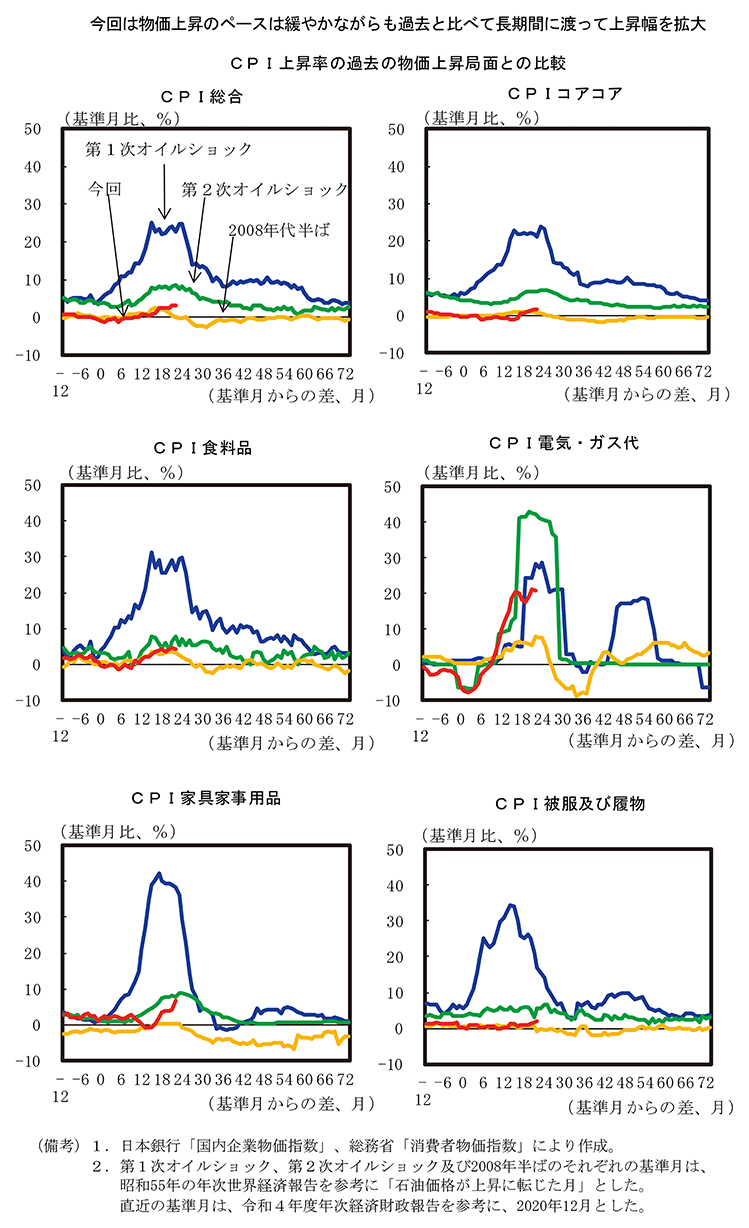
(物価上昇の品目的な広がりは第二次石油危機に近づいている)
次に、消費者物価の対象となる各品目の価格上昇率(前年比)の分布をみることで、全体として原油・原材料価格の上昇ショックに対してどのように動いたかをみる(第1-2-6図)。このグラフでは、横軸に示された物価上昇率に対応する品目の割合が縦軸の高さとして示されている。
第一次石油危機時には、危機前(1972年12月)の個別品目の価格上昇率は0%付近を頂点として、プラス(インフレ)方向になだらかな傾きで分布していた。半年後の1973年6月には山の高さが半分程度となり、インフレ方向に30%程度まで、非常になだらかに裾野が広がった。その後、更にインフレが加速し、消費者物価上昇率が前年比で最も高い水準となった1974年2月には0%近傍の頂点がなくなり、30%を超える価格上昇率までほぼ均一に分布するなど、非常に幅広い品目で高い上昇率を記録していたことがわかる。その後、消費者物価上昇率が危機前の水準に戻った1977年12月には、分布もおおむね元の形状に戻っており、収束に5年を要するなど長期間に渡って家計は高インフレに直面していたこととなる。
次に、第二次石油危機時をみると、危機前(1978年12月)は、第一次石油危機前と同様に個別品目の価格上昇率は0%近傍に頂点があった。1980年9月に物価上昇率が前年比で最も高くなったが、その際には0%から10%程度までほぼ均一に分布し、裾野も10%台後半まで広がっていた。その後、1年強経った1981年11月に危機前の物価上昇率へ戻っている。
2008年の物価上昇局面についてみると、2007年4月時点では0%近傍に分布が集中していたが、徐々に物価上昇が波及していった結果、2008年7月に物価上昇率がピークを迎えた。しかし、2度の石油危機発生時と比較しても0%近傍へ分布が集中したまま、2009年1月に物価上昇開始時の上昇率に戻った。この際は、比較的短期間で分布の形状がおおむね元に戻るなど、外生ショックの後に、物価が自律的に上昇していく力が弱かった様子がうかがえる。
今回の物価上昇局面についてみると、国際市況の原油価格が反転した2020年12月時点の分布は、前回の物価上昇局面の開始時点である2007年4月とほぼ同じ形状となっている。約2年後(2022年11月)の分布の頂点は、僅かにインフレ方向にシフトした程度であったが、前回の物価上昇局面のピーク時の2008年7月と比べると、山の高さは大きく下がり、インフレ方向へとなだらかな勾配を描き、その裾野は10%台後半まで広がるなど価格上昇が幅広い品目に及んでいる。
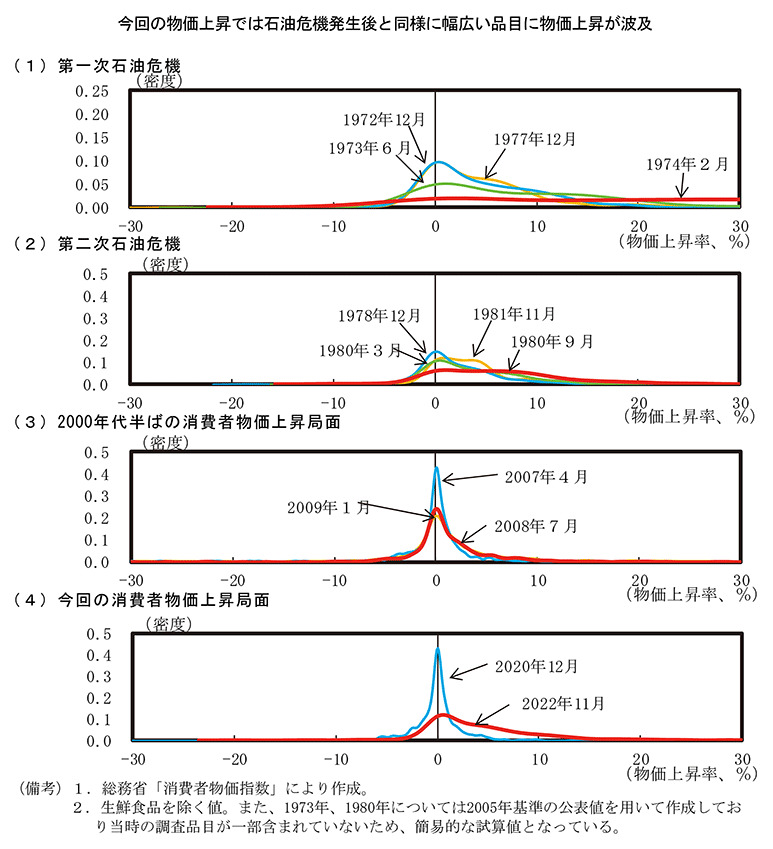
国際商品価格の急激な上昇とその後も続く不安定な動きや急速な円安の進行などを背景にコストが上昇してきたことから、消費者物価上昇率の高まりは依然として続いており、2023年に入っても当面はインフレ方向に分布の裾野がさらに広がっていく可能性がある。
(家計の価格上昇への反応は2008年よりも今回の方が大きい)
消費者物価の上昇が長期間に渡り、かつ、上昇率が前回2008年の物価上昇局面を上回る中で、物価上昇に対して家計がどのように反応しているか、過去の物価上昇局面と比較してみたい。ここではデータの制約から前回局面における購買数量の価格弾力性と比較する。家計が実際に購入した品目の単価を横軸に、当該品目の購入数量を縦軸として散布図を描く。個別品目について、価格が上昇、購入数量が減少した場合には右下の象限に、価格が下落、購入数量が増加した場合には左上の象限にプロットされるため、通常であれば右下がりの直線に沿った分布になると予想される。その際、傾きが急であれば購買数量に対する価格弾力性が高く、物価上昇に対して家計がより大きな購買行動の変化をとっていることとなる。
そこで、今回の物価上昇が本格化した2022年4月~10月の対前年同期比での平均単価上昇率と購入数量変化率の比(弾力性)をみると、マイナス0.7となっている。すなわち、電気代やガソリンなどの代替品が存在しない品目については価格上昇に数量が反応せず、むしろ右上の象限に位置しているが、平均的には単価が1%上昇した品目について、購入数量が0.7%減少する関係にある。一方、前回の物価上昇局面である2008年4月~10月について、同様に弾性値をみると、マイナス0.4と今回よりも小さい。つまり、今回の物価上昇局面では前回よりも家計が価格の上昇した品目の購入を控える傾向が平均的に強いことがみてとれる(第1-2-7図(1))。
また、消費者物価指数(CPI)は各品目での代表的な商品の価格を定点観測することで物価の動向を把握するため、同一品目内における低廉品へのシフトといった消費者の購買品の変化の影響が反映されない。そこで、スーパーにおける品目ごとの消費者の購入額ウェイトの変化を捕捉できるPOSデータ2による消費者物価とCPIを比較する。物価上昇局面において、仮に消費者が価格上昇を嫌気して、同一品目でもプライベートブランドなど相対的に低価格帯の商品に乗り換えた場合、POSデータの購入単価上昇率はCPIの同一品目の価格上昇率を下回ることが想定される。CPIとPOSデータにおける食料品の平均単価上昇率を比較すると、ほぼ一貫してCPIがPOSデータを上回って推移している3(第1-2-7図(2))。2000年以降でみると、CPIの上昇率がPOSデータの購入単価上昇率と比較して平均0.8%ポイント高く推移している一方、前回・今回の物価上昇局面では、この乖離幅が1%ポイントを超えている。想定どおり、物価上昇局面では消費者が低価格帯の同一機能商品へシフトすることで家計を防衛していることがうかがえる。さらに、前回の物価上昇局面では乖離幅が最大で1.5%ポイントあった一方、今次局面では8月~11月にかけて乖離幅が1.8~1.9%ポイントと広がっている。このように複数のデータから、今回の物価上昇局面では、安い品目を購入する家計の節約行動が顕著となっている様子がわかる。
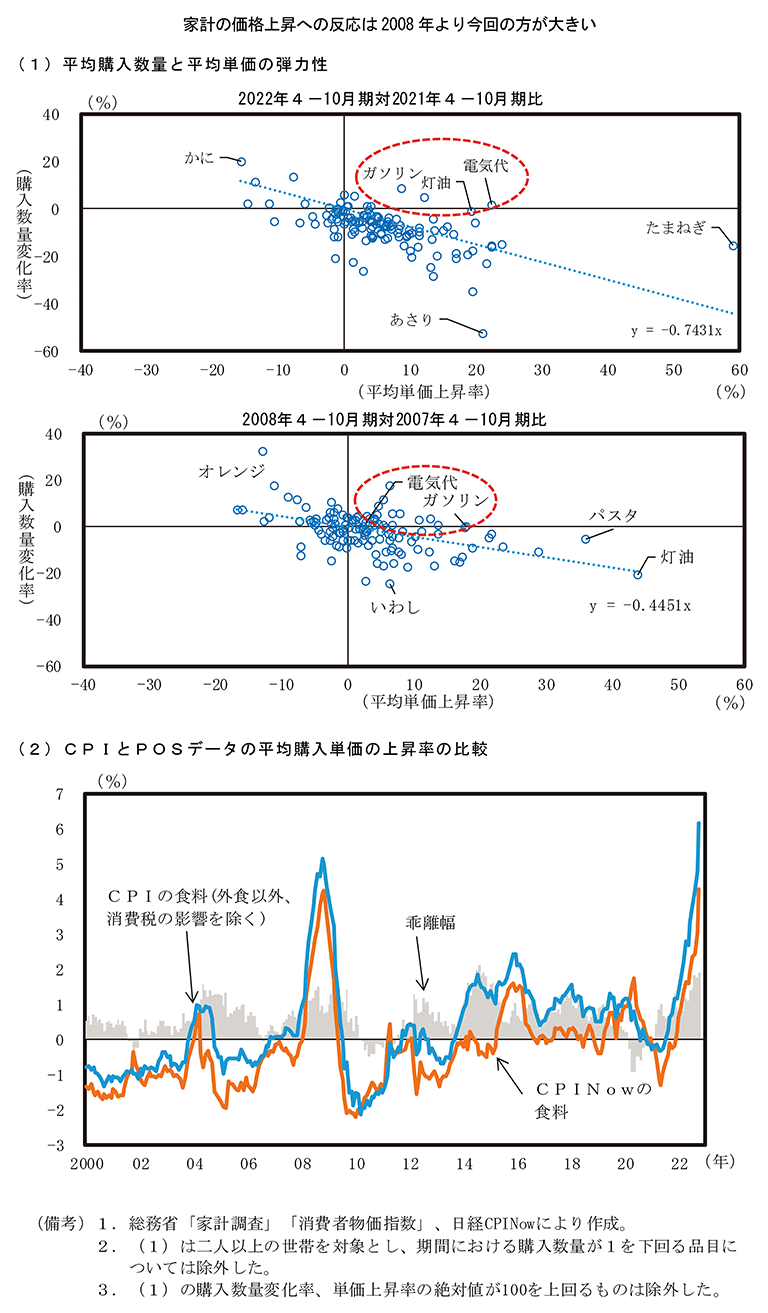
(消費者物価の上昇は低所得世帯等にとって相対的に大きな負担増)
このように、今回の物価上昇局面において、長期間に渡って物価上昇が継続し、価格上昇品目の広がりも前回の物価上昇局面を超えている中で、家計は節約行動をとっているが、具体的にどのような世帯が影響を受けているか家計調査を基に見てみよう。今回の消費者物価の上昇に大きく寄与している品目は、食料やエネルギーといった消費の価格弾力性が低い生活必需品である。そのため、世帯収入が低くなるにつれて家計全体に占める支出割合は高く、価格上昇による負担が相対的に大きくなる(第1-2-8図(1))。世帯類型別にみても、ひとり親世帯や小規模事業所に勤める世帯主世帯では収入の低い世帯割合が高く、収入対比での負担増加率は他の世帯類型に比べて高い(第1-2-8図(2)、(3))。
2022年9月に決定された低所得世帯への5万円給付や、10月28日に閣議決定された経済対策において措置された電力や都市ガス料金の激変緩和や中堅・中小企業等の賃上げ支援、フードバンク・こども宅食に対する支援は、こうした負担増加率の高い世帯の可処分所得を下支えする施策であり、着実に執行されることが期待される。
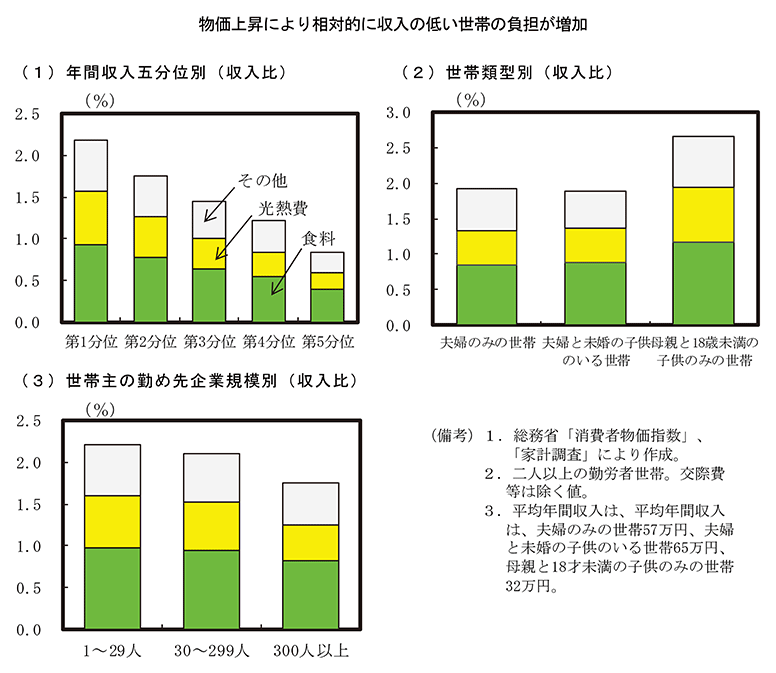
3 物価の基調的な動向からみた物価上昇の持続性
ここまで、物価上昇下の企業物価と価格転嫁の状況、消費者物価について過去との比較をしつつ、その家計への影響等をみてきた。本項では、今回の物価上昇の持続性をみるため、GDPデフレーター、GDPギャップ、単位労働コスト(ULC)の動きをみた後、それぞれと消費者物価との関係を見てみよう。
(国内需給や賃金からの物価上昇圧力は強くない)
まず、消費者物価の生鮮食品及びエネルギーを除く総合(コアコア)が前年比3.0%上昇する中、国内で生産された付加価値の物価であるGDPデフレーターについてみると、2022年7-9月期において前年同期比で内需デフレーターが3.3%、輸出デフレーターが3.3%上昇に寄与する一方、GDPの控除項目である輸入のデフレーターが6.9%下落に寄与したことにより、GDPデフレーターは0.3%下落し、2四半期連続の下落となった(第1-2-9図(1)、(2))。
次に、GDPギャップについてみるが、GDPギャップは、平均的な供給力を示す潜在GDPと実質GDPの実績値の乖離率として定義され、経済全体の需給の引締りの程度を示す指標である。一般に、潜在GDPが実質GDPを上回った状態(マイナスのGDPギャップ)であれば、価格が下落することで供給に見合う需要増が生じると期待され、実質GDPが上回っている場合(プラスのGDPギャップ)であれば価格が上昇することで需要が減退すると期待される。需給のタイト化が物価に反映されるには一定の時間がかかることを踏まえ、4期前のGDPギャップを横軸に、コアコアの前年比を縦軸にとって散布図で示すと、GDPギャップの縮小に伴い物価上昇率が高まることがわかる(第1-2-9図(3))。しかし、コロナ禍において需要が大幅に抑制された結果として、GDPギャップは大きなマイナスとなった(第1-2-9図(4))。経済社会活動の再開が進む中で、GDPギャップのマイナス幅も縮小傾向にあるものの、2021年10-12月期以降、GDPギャップはマイナス2.0%程度で推移するなど引き続き供給超過状態となっている。
ULCは、名目雇用者報酬を実質GDPで割ることで求められる生産一単位当たりに要する労働コストであり、これが増加するということは、労働生産性を上回って賃金が上昇しているということになり、賃金由来の内生的な物価上昇圧力となる。実際、ULCの前年比を横軸に、コアコアの前年比を縦軸にとって散布図を作成すると、ULCの上昇に伴ってコアコアの上昇率が高まっている(第1-2-9図(5))。しかし、2022年7-9月期のULCは、名目雇用者報酬が前年同期比1.9%上昇した一方で、実質GDPも前年同期比1.5%増加したことで0.4%の上昇にとどまり、賃金面からの物価上昇圧力は強くない(第1-2-9図(6))。
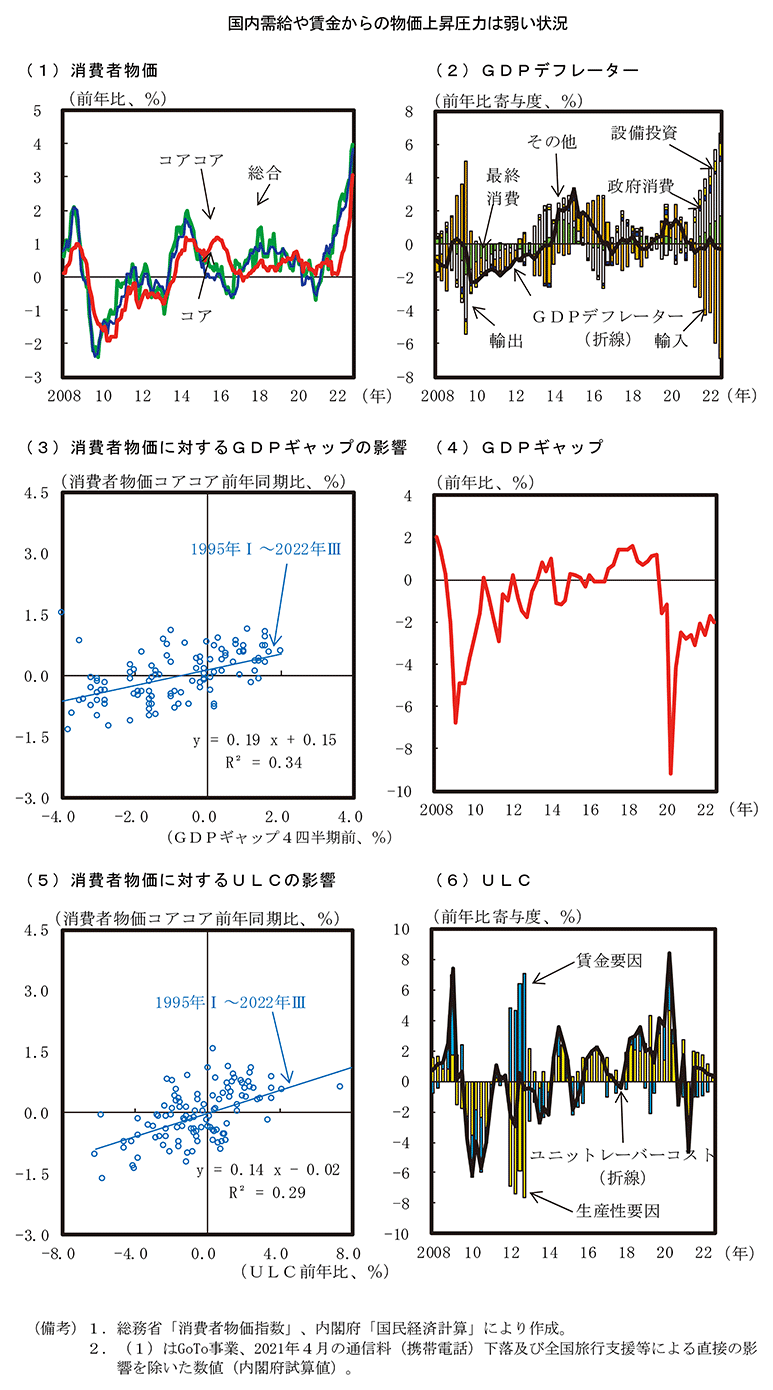
(足下の物価上昇は輸入からのコストプッシュ)
GDPギャップやULCとコアコアに一定の相関関係がみられることが確認できた。次に、GDPギャップ、ULC、さらに対外経済面からのコストとして消費者物価を押し上げる要因となる輸入物価の動きを同時にコントロールした上で、それぞれがどの程度コアコアの上昇に寄与してきたか、1980年から現在までの期間で検証する。推計結果をみると、4期前の輸入物価上昇率が1%ポイント上昇すると0.04%、4期前のGDPギャップが1%ポイント上昇すると0.22%、当期のULC上昇率が1%ポイント上昇すると0.13%、それぞれコアコアの上昇に寄与する一方、4期前の輸入物価上昇率が下落してもコアコアには影響しない結果となった(第1-2-10図(1))。当該係数を基に2022年7-9月期のコアコアの上昇率1.5%の内訳をみると、上昇寄与の大半は輸入物価によるコストプッシュであり、ULCの寄与は限定的である一方、GDPギャップは依然としてマイナスで推移していることからコアコアを押し下げる方向に寄与している。
続いて、物価上昇が継続している中で、コスト増を価格に転嫁する際のタイムラグが短くなっている可能性はないだろうか。消費者物価が一定以上上昇している局面では、価格改定しない逸失利益が価格改定に伴う諸コスト(メニューコスト)を上回ることで、価格改定頻度が高まる可能性4や、競合他社が値上げを行っている場合には、仕入価格上昇を販売価格に転嫁する傾向を個別企業が強める可能性5が指摘されている。つまり、コアコアの上昇局面においては、輸入物価の上昇に伴い、企業が高頻度で価格改定を行うことで、輸入物価上昇が消費者物価上昇へ反映されるタイムラグが短くなる可能性がある。これを確認するため、コアコアの上昇局面に着目してコアコアの上昇率と輸入物価の1期ラグから6期ラグまでについて時差相関を確認してみる。コアコアの下落局面も含む全期間で推計を行った場合は4期前の係数が最も高い結果となるが、上昇局面に絞ると3期前の係数が最も高い。また、全期間での推計結果と比べて2期前、1期前の輸入物価が消費者物価に与える影響も強く、上記仮説と整合的な結果となった(第1-2-10図(2))。
こうした結果を踏まえると、足下の物価上昇局面において、ミクロ的な動きをみると一定以上の物価上昇下で価格粘着性が弱まり、過去の物価上昇局面と比較して消費者物価が上昇しやすい状況にある。こうした中で、これまでの輸入物価の上昇によるコストプッシュによって消費者物価は上昇しているものの、国内の需要や賃金による物価上昇のモメンタムは依然として弱い状況にあることが示唆される。
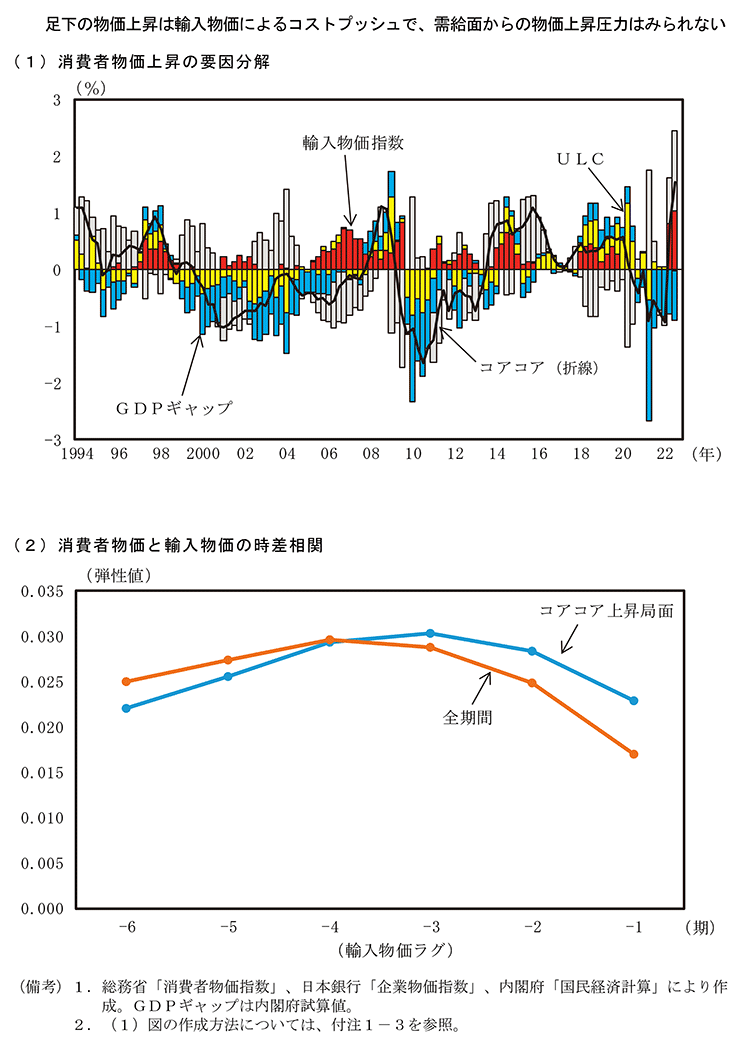
(スーパーの販売価格は、2021年末以降、供給要因が上昇に寄与)
2022年の物価上昇要因を品目別のデータを用いて別の角度から検証6してみよう。ここでは、消費者が実際にスーパーで購入している品目別の価格動向と売上高を利用できるPOSデータを用いて、購入単価の上昇の背景を需要要因と供給要因に分解する。経済学において、一般的な右下がりの需要曲線と右上がりの供給曲線を想定すると、需要ショック(需要曲線のシフト)が起きれば、販売数量の増加と価格の上昇、又は販売数量の減少と価格の低下の組合せで変動がみられると整理できる。一方、供給ショック(供給曲線のシフト)が起きれば、販売数量の増加と価格の下落、又は販売数量の低下と価格の上昇の組合せで変動がみられると整理できる。そこで、品目別に毎月の販売数量と価格変化が、前者の2つの分類に該当すれば需要要因による価格変化、後者の2つの分類に該当すれば供給要因による価格変化とする。両方の曲線のシフトが同時に起こることもありえるが、その場合であってもいずれのシフトが強く影響しているかという観点から、ここでは当該4分類で分析を行う。
まずは、POSデータでとれる217品目について、4分類に分けた時のシェアの変化をみてみると、例えば世界金融危機の影響を受けた2009年や、感染拡大から少し経過した2020年半ば以降に価格低下かつ数量減のシェアが大きく増加しており、需要ショックの影響が強く表れている一方、2006年後半から2008年にかけて原油価格の高騰により物価が上昇した時期や今次物価上昇局面では価格上昇かつ数量減少のシェアが増加しており、供給ショックの影響が強く表れていることが確認できる(第1-2-11図(1))。
これを用いて、足下の価格変化を需要要因と供給要因に寄与度分解してみる。感染症拡大以降、2020年及び2021年については、緊急事態宣言等の発出・解除に伴う需要の変動によって価格変化の大宗を説明できることがわかる(第1-2-11図(2))。しかし、輸入物価の上昇により2022年10月に幅広い品目で値上げが行われるとの報道を受け、駆け込み需要のような動きがみられた2022年9月以外は、供給要因が物価上昇の大半を説明するように推移してきたことが確認できる。
POSデータはスーパーで販売されている食料品・日用品に限定されたデータであることには留意する必要があるものの、前述したマクロの物価指数の要因分解と合わせてみても、コロナ禍からの世界的な需要の回復と供給制約による原油等の原材料価格の高騰が輸入物価の上昇をもたらしはじめた2021年末以降にみられた物価上昇はコストプッシュによるものであり、国内の需給や賃金上昇による物価上昇のモメンタムは未だ生まれていない。このため、仮に今後国際商品市況や為替市場の変動が落ち着き、輸入物価上昇による影響が剥落した後には再びデフレに戻るリスクも無くなっていない。
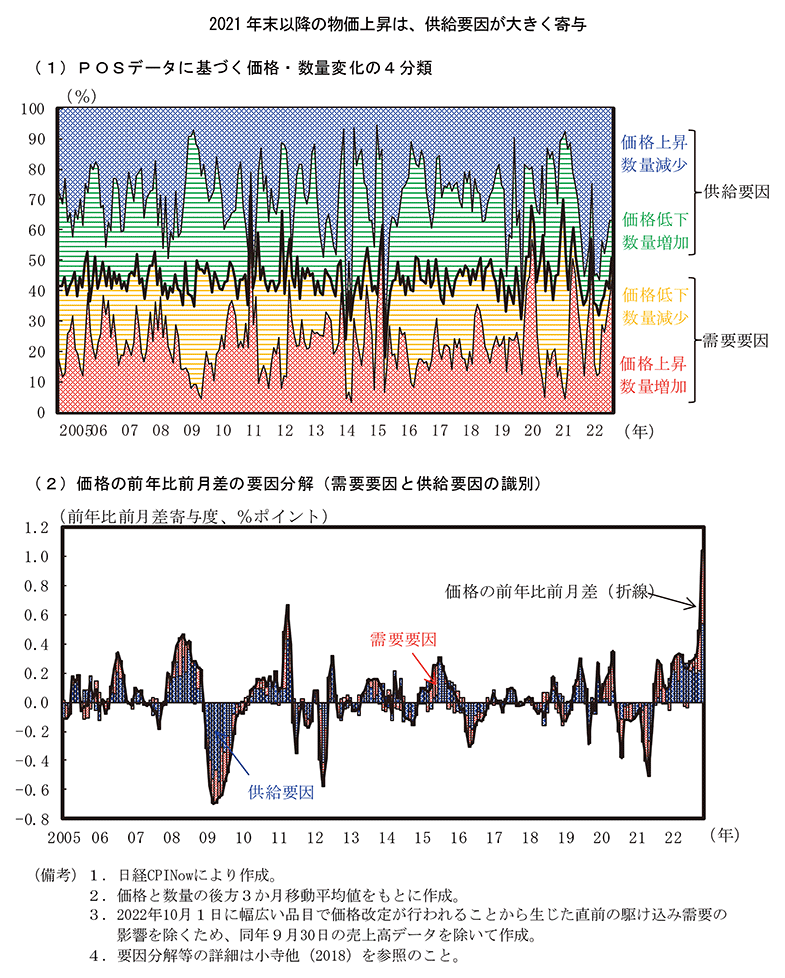
(サービス価格の動向と安定的な物価上昇)
コストプッシュインフレが財だけでなく、サービスにも起きているか確認するため、消費者物価上昇への寄与を財・サービス別に分解すると、2022年10月時点で財が3.3%寄与しているのに対してサービスは持家の帰属家賃を除くベースでみても0.6%の寄与と相対的に低い水準となっている(第1-2-12図(1))。サービス業のうち中間投入に占める財の比率が高い外食や自動車整備等の家事関連サービスなどは財価格の上昇に伴って価格が緩やかに上昇しているものの、人件費が投入コストに占める割合の高いそれ以外のサービスでは賃金上昇によるコストプッシュが起きていないとみられる(第1-2-12図(2))。
サービス業において賃金が物価に与える影響をみるため、サービス関連のCPIとサービス産業の賃金上昇率の時差相関をとると、2011年から感染拡大前の2019年までは賃金上昇が先行してCPIの上昇が続くという関係がみられていたが、2020年以降はむしろCPIが若干先行し賃金が遅れて変化しており、賃金上昇による物価上昇という姿にはなっていない(第1-2-12図(3))。一方、非製造業の需給判断DIとサービス関連のCPIの関係をみると、1990年代後半以降、相関関係は弱まっているものの、需給のタイト化に半年程度遅れてCPIが上昇する関係が確認できる(第1-2-12図(4))。サービス需要は、2022年夏頃からウィズコロナの下での経済社会活動再開が進展していた中で、10月には全国旅行支援の実施やインバウンドの解禁を通じて、特に対面サービスを中心に、増加基調にある。これがサービス業の物価上昇、続いて賃金の上昇につながることで、サービス業の投入構造の4割を占める雇用者所得を押し上げ、コスト面からの物価の持続的な上昇圧力となることが安定的な物価上昇にとって重要となると考えられる。
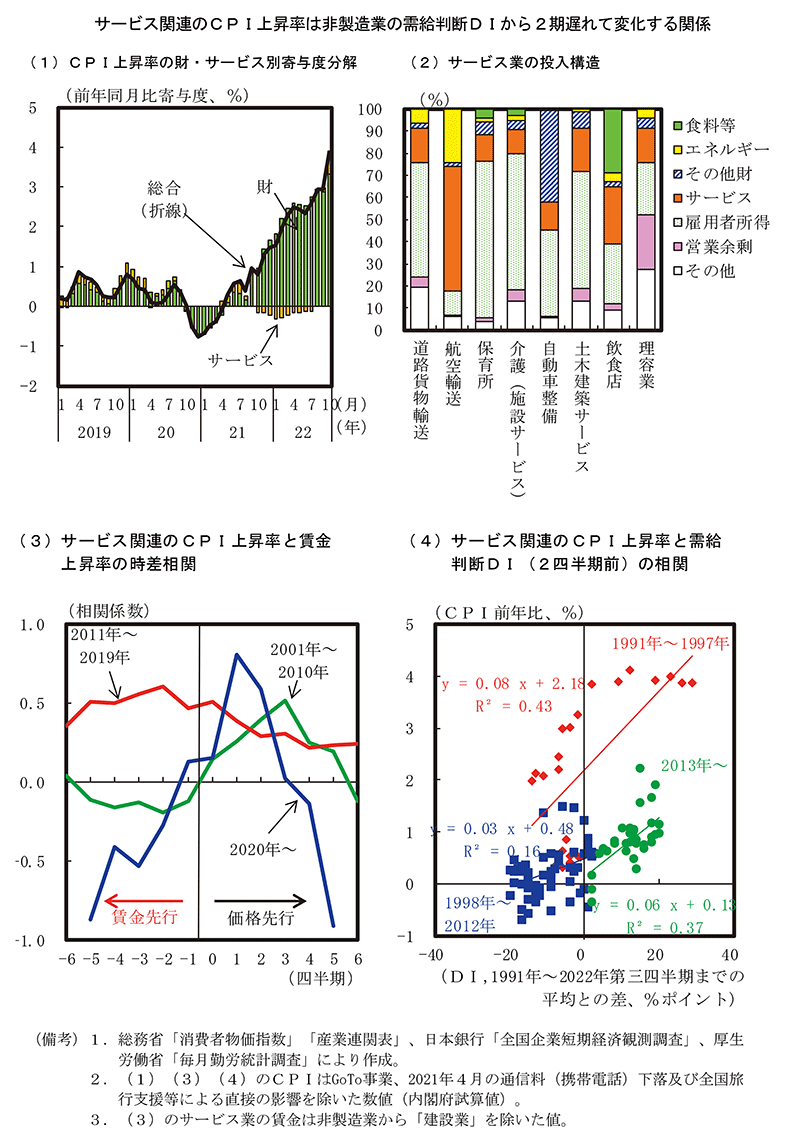
(物価上昇に負けない持続的な賃金上昇の実現が必要)
2022年の物価動向を振り返ると、輸入からの物価上昇が継続する中で、前回と比べると価格転嫁の動きが徐々に進み、価格粘着性が弱まっていることから、これまでと比較して物価が上がりやすい状況となっている。しかし、国内需給や賃金面からの物価上昇圧力は依然として弱く、サービス価格の上昇も財に比べて遅れている。これに加えて、政策による物価変動要因として、燃料油価格激変緩和対策措置や全国旅行支援がCPIを下押ししている。さらに、2023年2月からは電気・ガスの激変緩和措置が4月以降に見込まれる電気・ガス料金の値上げに先立って導入されることとなっている。いずれにせよ、需要面による物価上昇圧力は弱いことから需要増による物価上昇を懸念する状況にはないことを踏まえると、安定的な物価上昇に向けては、企業による価格転嫁や適切な価格付けを促進しつつ、付加価値を維持・増進させて賃上げを実施していく必要性がある。なお、賃金から物価への内生的な物価上昇が生じていない段階においては、緩和的な金融環境を変更する状況にはないと考えられる。

