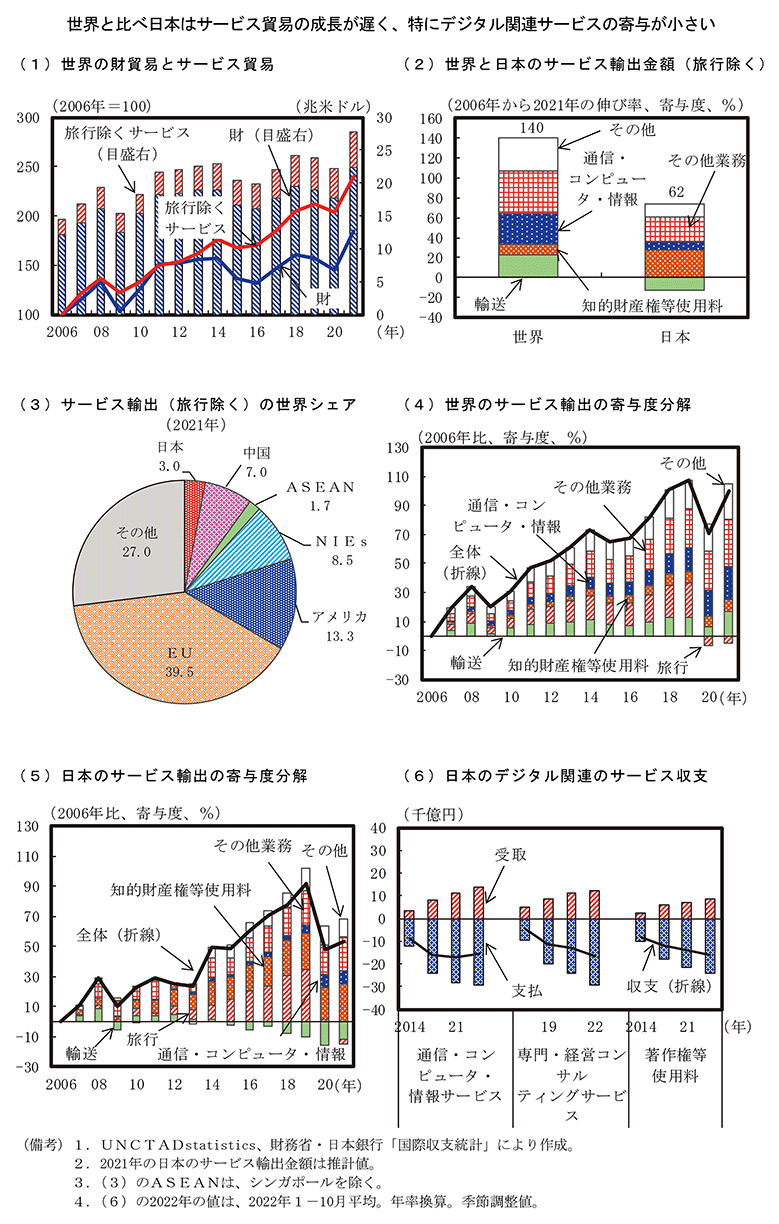第1章 世界経済の不確実性の高まりと日本経済の動向(第1節)
第1節 ロシアによるウクライナ侵略後の不確実性の高まりと日本経済
本節では、2020年第2四半期以降のマクロ経済動向について、ウクライナ情勢等を受けた物価の動向と、2022年にみられた円安の影響に焦点を当てながら、GDPや需要項目別の回復過程を欧米経済との比較も交え、振り返りたい。
1 コロナ禍以降の経済動向
(サービス部門の回復が遅れているが、2022年以降は緩やかに持ち直し)
コロナ禍からの回復状況について、GDP統計を用いて諸外国と比較しつつ、確認してみよう。まずGDP全体の動向についてみると、2020年7-9月期以降の1年間は諸外国同様、感染状況の影響を受けながら一進一退の状況が続いた。しかし、2021年7-9月期に緊急事態宣言や東南アジアの感染拡大による部品供給不足等で前期比マイナスとなった後は、同年10-12月期以降、プラス成長とマイナス成長を繰り返しながらも回復基調で推移しており、特に消費や設備投資を中心として民需は4四半期連続のプラス成長となっている(第1-1-1図(1))。主要国と回復状況を比較すると、2019年10-12月期対比で、2021年以降、2022年7-9月期までの我が国のGDPは、アメリカよりは低いが、英国やドイツよりはやや高い水準で推移している(第1-1-1図(2))。
次に、実質GDPの需要項目の動向を見てみる(第1-1-1図(3))。個人消費についてみると、我が国では2022年4-6月期にコロナ禍前水準を回復した。2021年1-3月期にコロナ禍前水準を回復し、その後も回復を続けているアメリカと比べると低水準にあるものの、英国、ドイツよりはおおむね高い水準で推移している(第1-1-1図(4))。消費のうち、財については、テレワークやオンライン会議等に対応するためのパソコンやその付属品、外出抑制下でのテレビ、エアコン等の耐久財需要が旺盛であったことから、2020年7-9月期には我が国を始め多くの国でコロナ禍前水準を超えた。その後、アメリカや我が国では安定的にコロナ禍前を超えた水準で推移する一方、欧州主要国では再び弱含み、コロナ禍前水準を下回って推移している(第1-1-1図(5))。サービスについては、欧州では2021年夏前には外出規制が大きく緩和され、飲食・宿泊をはじめとする対面型のサービス消費が急速に回復した一方、2021年9月まで緊急事態宣言が続いた我が国では回復が遅れ、2022年になっても未だコロナ禍前の水準には至っていない(第1-1-1図(6))。ただし、2022年7─9月期には感染拡大があったが、過去の感染拡大時のような消費の減少は生じておらず、ウィズコロナの下で緩やかに持ち直している。
設備投資についてみると、2021年前半にデジタル関連需要等を中心に改善がみられたが、世界的な需要の急速な回復に対する半導体の不足、新型コロナウィルスの感染再拡大による港湾等における物流の混乱、東南アジアでの工場の稼働制限などを通じた部品供給不足などにより、2021年後半から2022年初頭にかけて持ち直しの動きに足踏みがみられた。2022年4-6月期以降は、コロナ禍で先送りとなっていた能力増強投資や国内生産の強化、デジタル化や脱炭素化に向けた投資などにより持ち直しており、コロナ禍前水準を回復していない英国、ドイツと異なり、アメリカと同程度に増勢がみられる(第1-1-1図(7))。
輸出については、コロナ禍でのデジタル関連財の需要の強さを反映して半導体等製造装置や半導体等電子部品などの一般機械や電気機器等を中心に財輸出を伸ばしており1、我が国は、欧米と比べて強い動きとなっている(第1-1-1図(8)、(9))。サービス輸出については、2022年半ばより観光目的の外国人の入国規制についても段階的に緩和してきたものの、EU圏内での往来にほぼ制限がなくなりコロナ禍前水準を既に回復したドイツ、フランスと比較して、戻りが遅い。しかし、10月に水際対策が大幅に緩和されたことで、訪日外客数は10月に約50万人、11月に約93万人と9月の約21万人から大きく増加している(第1-1-1図(10))。
このように、2022年入り以降、主要国と比較するとサービス部門の回復は遅れているものの、消費や投資を中心に民需が徐々に持ち直している。
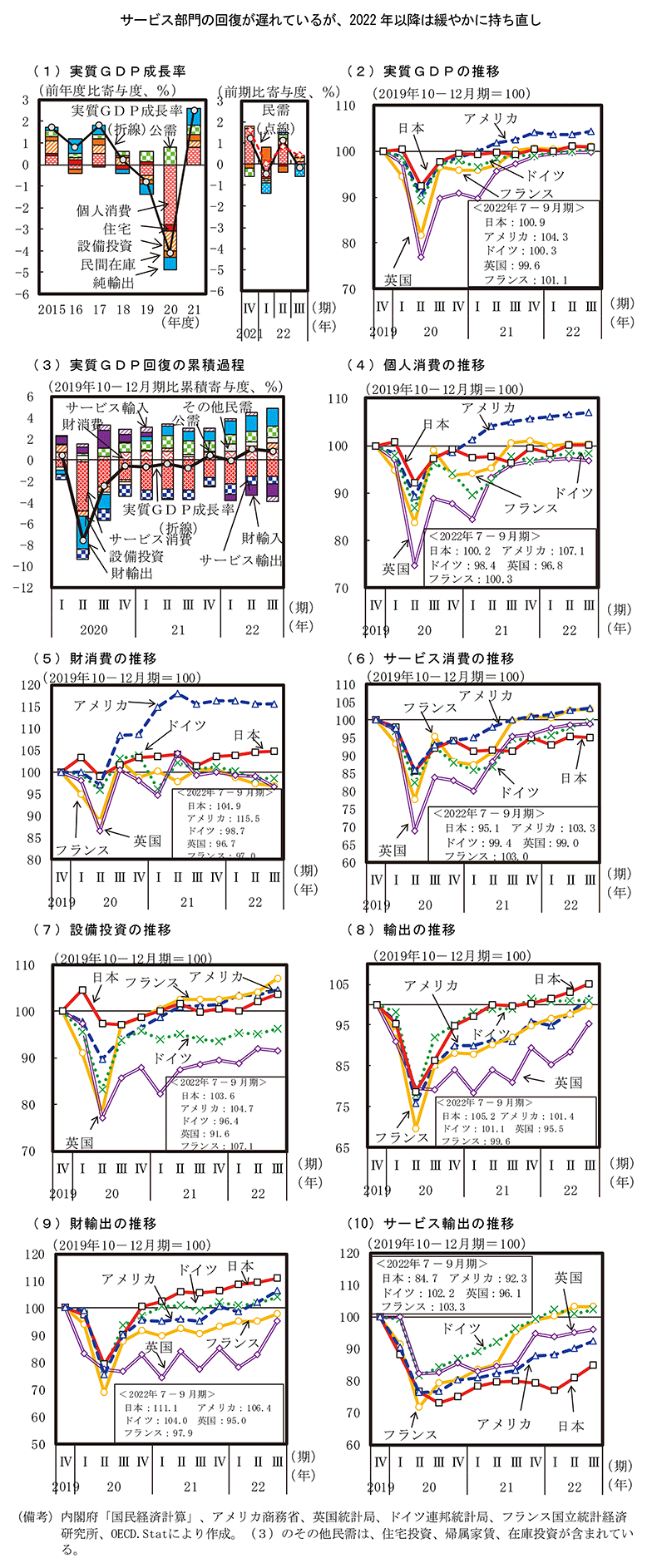
2 コロナ禍からの需要回復とウクライナ情勢がもたらした世界的な物価上昇
(需要回復と供給制約による物価上昇がロシアのウクライナ侵略で加速)
2022年は、世界にとっても我が国にとっても、物価上昇への対応が大きな課題となったことから、ここでは世界的な物価上昇の背景と我が国と各国の対応を見てみよう。2021年に入って以降、世界的に緩和的な金融環境が続く中で需要が回復する一方、サプライチェーンの混乱による供給制約が生じることで、需給がタイト化し、各国で物価が上昇した(第1-1-2図(1))。特にアメリカでは、供給制約に加え、累次の給付等の支援策と労働市場のひっ迫を背景にした所得環境の改善が相まって消費が拡大し、需給がタイト化した。こうした中、消費者物価の前年比上昇率が2022年1月に7.9%を記録するなど、物価の急速な上昇が続いた。原油をはじめとする国際商品市況でも世界的な需要回復による価格上昇がみられ、欧州の物価についても、失業率や賃金水準が改善する中でエネルギーを中心に2021年後半から上昇し始め、2022年1月の消費者物価上昇率はユーロ圏で5.1%、英国では5.5%となった。(第1-1-2図(2)~(4))
こうした状況の下、2022年2月24日にロシアがウクライナ侵略を開始したことを受け、原油や天然ガスの国際商品価格の上昇が加速した。また、ロシアやウクライナが輸出に占めるシェアの高い小麦等についても価格が上昇した(第1-1-2図(2))。こうした国際商品市況を受け、既に上昇していた各国の消費者物価は更に上昇し、アメリカでは6月に9.1%を記録した。11月に7.1%へと上昇幅を縮めたものの引き続き高水準で推移しており、欧州ではユーロ圏で11月に10.1%、英国で11月に10.7%となるなど更に高い水準で推移している(第1-1-2図(4))。
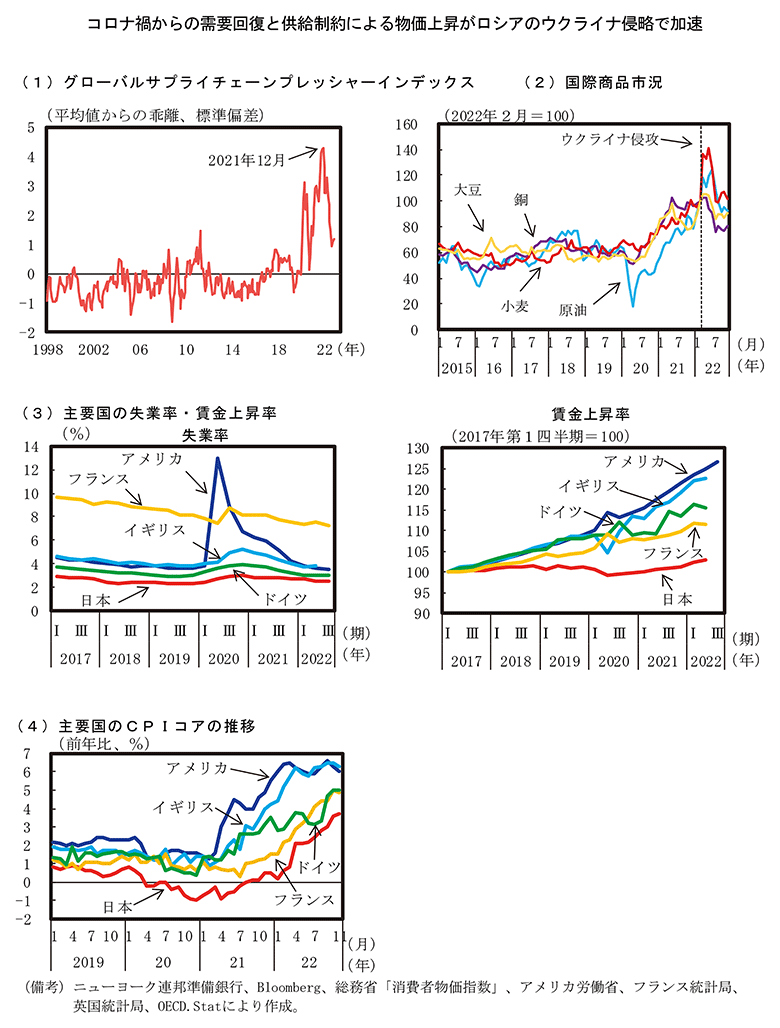
(主要国では、物価上昇に対して金融引締めを進めるとともに財政支援を実施)
急速な物価上昇に対し、各国・地域の中央銀行が金融政策の引締めを通じてインフレ抑制に努めると同時に、各国政府は財政政策を通じて低所得層や相対的に体力の弱い中小企業を中心とした支援策を講じた。
金融政策についてみると、アメリカで2022年3月以来7回の政策金利引上げが実施され、2022年12月にはFFレートが4.5%となったほか、ユーロ圏では2.5%、英国では3.0%まで政策金利を引き上げている(第1-1-3図(1))。こうした急速な政策金利の引上げは、各国での需要の減少や雇用情勢の悪化を通じた世界的な景気減速につながるリスクがある。ただし、アメリカにおいては住宅ローン金利が上昇する中で住宅着工は減少しているものの、7-9月期のGDPは3四半期ぶりにプラスとなるなど、経済全体としては緩やかな持ち直しの動きが続いている(第1-1-3図(2))。他方、欧州では依然としてエネルギー供給不足への懸念が残る中、物価上昇率の高まりが実質賃金を低下させることで小売売上高が弱い動きとなっている(第1-1-3図(3))。このため、ドイツでは家計や中小企業向けに電気代の一定額まで補助金を支給するなど総額9.1兆円のエネルギー価格高騰への対策パッケージを2022年9月にまとめたほか、フランスでは2022年内のガソリン価格の割引や、一般家庭や小規模企業に対するガス料金上昇率や電気料金上昇率の抑制などの購買力支援政策パッケージが2022年8月に公表されるなど、各国で物価上昇に対する家計や中小企業の負担軽減を目的とした財政支援策が取られている(第1-1-3図(4))。
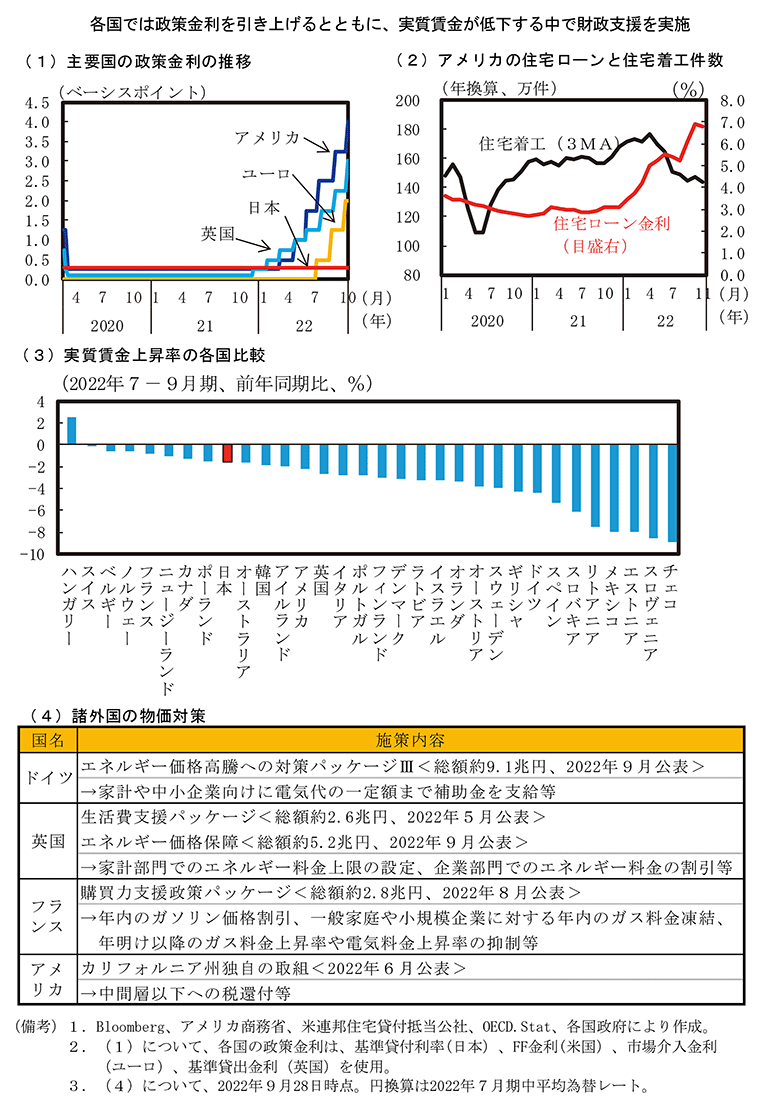
(我が国では、交易損失が拡大し、実質総雇用者所得も前年比マイナスで推移)
コロナ禍以降の世界的な需要の回復や供給制約を背景とした国際商品価格の上昇は、我が国経済にはどのような影響を与えただろうか。まず、原油をはじめとする鉱物性燃料価格の影響により輸入物価は大きく上昇したが、輸出物価への転嫁は限定的であり、2021年春以降、交易条件が急速に悪化した(第1-1-4図(1))。これにより交易損失は拡大し続け、2022年7-9月期には19.0兆円の所得流出となり、2022年入り以降、実質GNIは伸び悩んでいる(第1-1-4図(2))。
消費者物価は、輸入物価の上昇によってエネルギーや食料品を中心に上昇しているが、2022年11月の生鮮食品を除く消費者物価(コア)の上昇率は3.7%と、欧米諸国と比較すると低い(前掲第1-1-2図(4)、第1-1-4図(3))。しかし、長くデフレ又は低インフレが続いてきた我が国においては消費税率引上げによる上昇を除けば、3.7%であっても40年11か月ぶりの上昇率である。2022年10月の名目総雇用者所得は、前年比は1.7%の増加となったものの、物価上昇の影響を加味した実質はマイナス2.1%と前年を下回っている(第1-1-4図(3))。また、物価上昇の影響もあって消費者マインドは弱い動きとなるなど、消費の先行きは注意が必要な状況にある(第1-1-4図(4))。
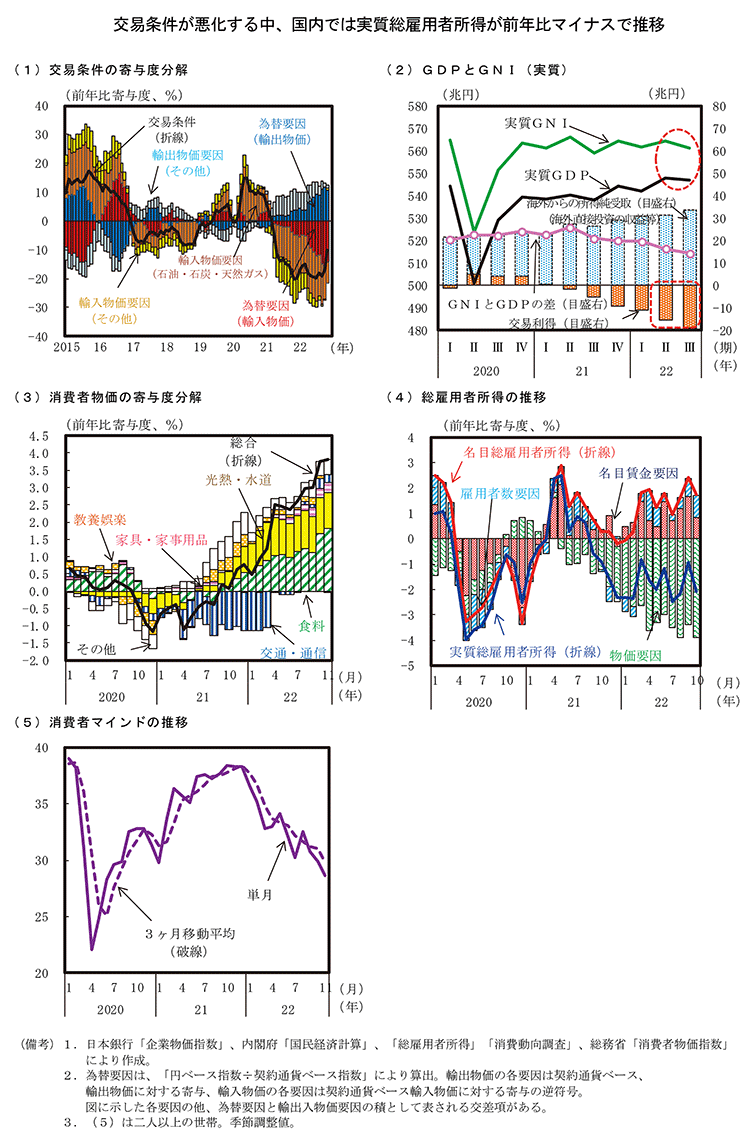
(我が国においても物価高騰対策を実施)
こうした中で、政府は2022年3月に燃料油価格激変緩和対策事業等を盛り込んだ「原油価格高騰に対する緊急対策」を、4月に激変緩和事業の継続・拡充やエネルギー・原材料・食料安定供給対策を盛り込んだ「コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」」を策定した。また、7月には物価・賃金・生活総合対策本部で肥料高騰対策等を、9月には同本部で低所得世帯5万円給付金などの追加策を取りまとめた。さらに、10月28日に電力・ガス価格激変緩和対策事業等を内容とする「物価克服・経済再生実現のための総合経済対策」を閣議決定し、12月2日に2022年度第2次補正予算が成立するなど、諸外国同様、我が国においても物価上昇の家計・事業者への影響を軽減するための対策が取られている(第1-1-5図)。
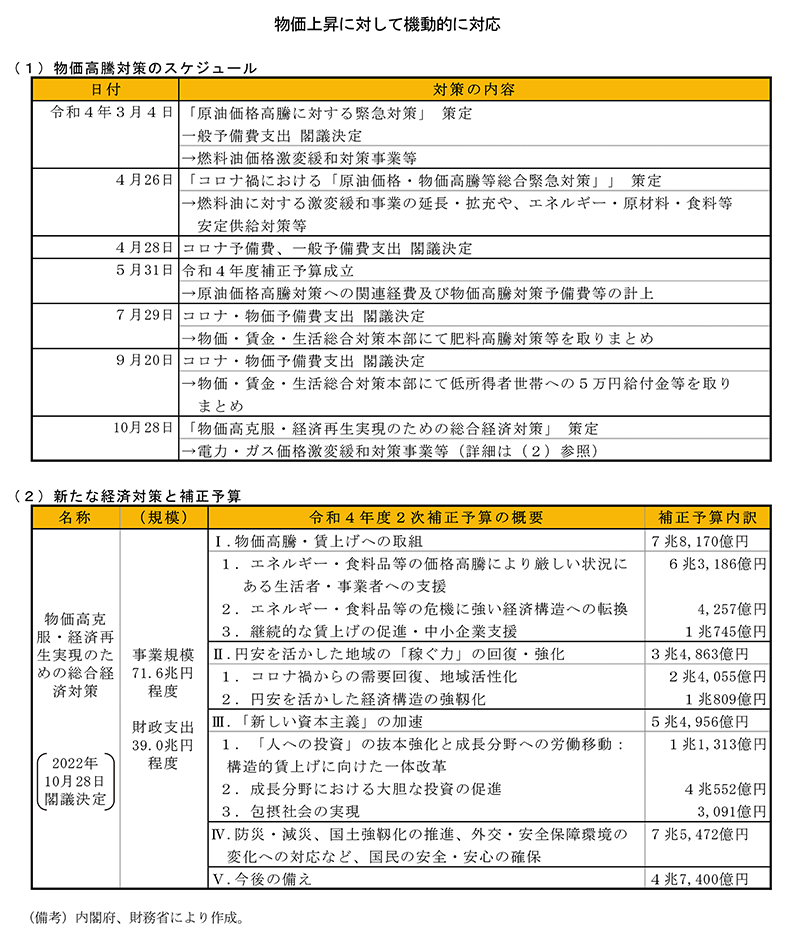
3 為替変動の背景と経常収支赤字
(為替レートは長期的には購買力平価におおむね沿って推移するが、このところ乖離が拡大)
世界的な物価高と政策金利の引上げ等は、為替レートにも影響を与え、2022年は急速に対ドルで円の減価が進んだ。為替変動は、輸入物価や輸出物価の上昇等を通じて国内の家計・企業の活動に影響を与え、結果として貿易収支や所得収支を通じて経常収支に影響を与える。
そこで本項では、最初に為替レートの変動が、ファンダメンタルズと比較してどのような動きとなっているのか見てみよう。まず、為替レートが、長期的には同一財の価格差やインフレ格差が相殺されるように変動すると考える購買力平価説と整合的な動きとなっているか確認する。日米の購買力平価を企業物価の比と仮定し、為替レートとの関係をみると、振れを伴いながらも、すう勢として購買力平価に沿う形で推移してきたことがわかる。一方で、2022年は過去50年間で購買力平価から最も大きく乖離した状態にある(第1-1-6図(1))。
相対価格比以外で為替レートに影響を与える要因としては、貨幣供給(需要)量の違いや金利差が挙げられる。まず、日米の貨幣供給量の比をマネタリーベース比としてみると、2000年代初頭から2010年代前半にかけて為替レートとおおむね連動しているものの、2016年頃から連動性を失っている。(第1-1-6図(2))また、金利差について日米の実質短期金利の差を取ると、こちらも一定の相関関係がみられるが、時期によって連動の有無が異なる。コロナ禍以降は、アメリカの金融緩和による実質金利差の拡大(円高要因)が生じたものの、ドル円レートは円安で推移しており、連動性が失われていた。ただし、2022年に入ってからは、実質金利差が縮小(円安要因)する中で、コロナ禍以前にみられた金利差と為替水準の関係が再確認されるようになっている(第1-1-6図(3))。
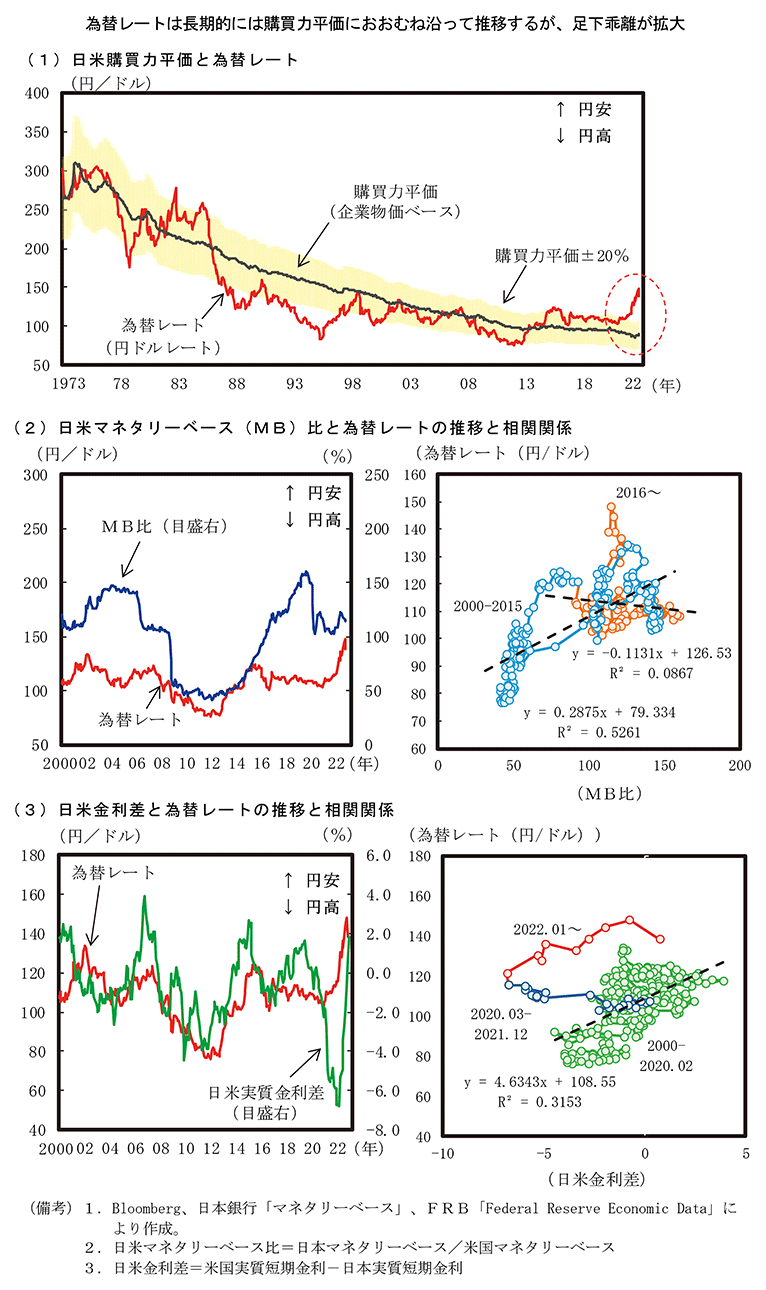
(足下の為替変動は相対価格の要因が大きい)
次に、名目金利差による裁定取引が行われる際に市場参加者が前提としている予想為替レート2を推計し、予想為替レートと金利以外の主な為替レートの決定要因と考えられる相対価格比(日米の貿易財価格比3)の関係をみよう。予想為替レートと貿易財価格比は、1987年以降の長期間に渡りおおむね連動してきたものの、コロナ禍以降、予想為替レートは貿易財価格比から見込まれる水準より減価した状態で推移している(第1-1-7図(1)、(2))。
このように、短期的な為替動向は金利差や貿易財価格比といった個別の関係だけをみても要因を特定できないが、長期的には安定的な関係も見いだせることから、各種の変数を同時にコントロールした為替レート(ドル円レート)関数を推計4することで、時期に応じた為替変動の要因を見てみる。具体的には、前期の為替レートに加え、日米の相対価格の変化を捉える貿易財価格比、政策金利の変化に伴う裁定取引や期待インフレ率の変化の影響を捉えるため、日米の実質金利差とマネタリーベース比5を用いて推計を行った(第1-1-7図(2))。
推計結果を用いてドル円レートの変動要因を分解すると、変化の7割弱は前期の為替レートの影響を引きずる一方、貿易財価格比、金利差、マネタリーベース比が影響を与えている。コロナ禍以降の動きをみると、貿易財価格比については、2021年7-9月期まで相対価格比が低下して円高要因であったが、2022年に入ってからは我が国での継続的な物価上昇によって相対価格比が上昇し、円安要因となっている。これに加えて実質金利差の変化も円安に寄与している(第1-1-7図(3))。しかし、実績値は、金利やマネタリーベース、相対価格といった構造要因で説明できない部分(誤差率)が過去と比べても大きい。自己ラグが説明する程度が大きいことを踏まえると、為替の自己実現的なファンダメンタルズからの乖離(投機的な動きの偏りやハーディング6現象)が相応に影響を与えているとも考えられる。
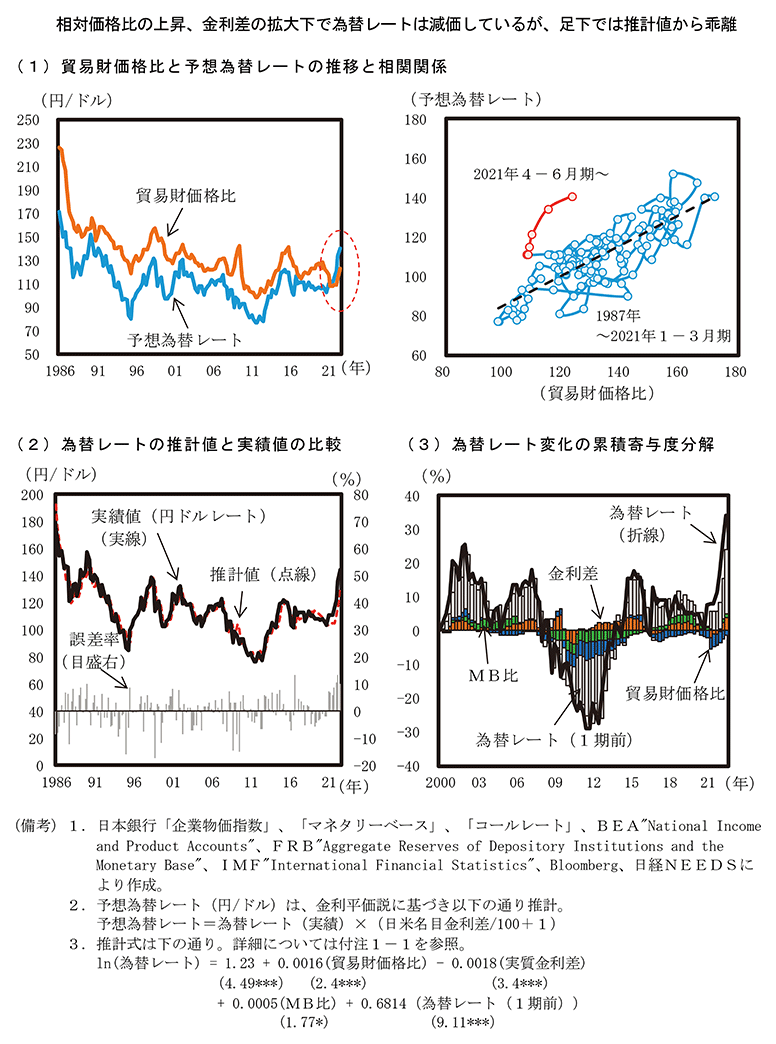
(円安は短期的には貿易収支悪化、所得収支改善の方向に寄与)
2022年度半ばにかけて急速な円安がみられたが、為替変動は、経常収支に様々なルートを通じて影響を与える。貿易収支についてみれば、円安により輸入金額、輸出金額ともに増加する可能性がある。具体的には、輸入は、仮に数量が一定であれば、円ベースの輸入価格の上昇によって金額が増加する。輸出は、企業が現地通貨建ての輸出価格を維持しながら円ベースでの単価を引き上げる、又は、現地通貨建ての輸出価格を引き下げ、円ベースでの単価を維持しつつ輸出数量を増やす、いずれの戦略を取った場合でも輸出金額が増加することが見込まれる。サービス輸出に関しては、インバウンド消費の増加等を通じた輸出金額の増加が期待される一方、アウトバウンドについても同様となるため輸入金額の増加も想定される。また、所得収支については、海外邦人企業からの配当金等の直接投資収益等が黒字超過で推移している我が国にとっては、現地通貨ベースでの支払いと比べ円ベースでの受取の増加が大きくなることなどにより、第一次所得収支の受取が増加する。
そこで、財輸出の数量と価格、財輸入の数量と価格、所得収支、サービス収支について、それぞれ為替レートの変動が短期的にどのような影響を与えるのか、簡易推計してみよう。なお、ここで短期的としているのは、時間経過を伴って生じる数量の反応(いわゆるJカーブ効果)は考慮されていないためである。また、貿易収支構造が変化し、おおむね均衡して推移するようになったリーマンショック以降を推計対象としている点も留意が必要である。
推計結果をみると、実効為替レートが減価した場合、1四半期程度の短期的な反応としては、財輸出については数量、価格ともに上昇することで輸出金額を増やす一方、輸入については、鉱物性燃料以外の品目では数量は減少するが、価格の上昇寄与が上回ることで金額が増加する。また、鉱物性燃料については、輸入数量は価格の影響を受けず、価格が上昇した分だけ輸入金額が増加する7。これらの結果を総合してみると、輸入金額の増加が輸出金額の増加を上回ることで、短期的に貿易収支の赤字幅は拡大しやすい8。なお、この結果は、先に述べたとおり短期的な変動のみを捕捉していることに加え、様々な要素が影響している可能性がある。具体的には、我が国の対外的な取引通貨における円建ての取引シェアは、輸入の25.3%に対し輸出が38.1%と、輸出が為替変動の影響を受けにくい構造となっていることや、短期的には現地通貨建ての取引価格を低下させることができたとしても国内の生産余力の範囲内でしか輸出数量を増加できないこと、また、推計期間にコロナ禍が含まれており、部品等の供給制約によって短期的な生産余力が失われ、輸出数量の弾性値が押し下げられている可能性などが挙げられる。
所得収支については、為替レートの変動に対する弾性値はおおむね1と、為替が減価する分円建ての収支が改善しやすいとの結果が得られた。第一次所得の受取は、海外邦人企業からの配当金等の直接投資収益や証券投資収益であり、短期的な為替変動によって配当比率などが大きく変わるとは想定されないことと整合的な結果と考えられる。なお、サービス収支については輸出金額の弾性値が輸入金額の弾性値を上回り、為替レートの減価は収支の改善に寄与するとの結果となった(1-1-8図)。
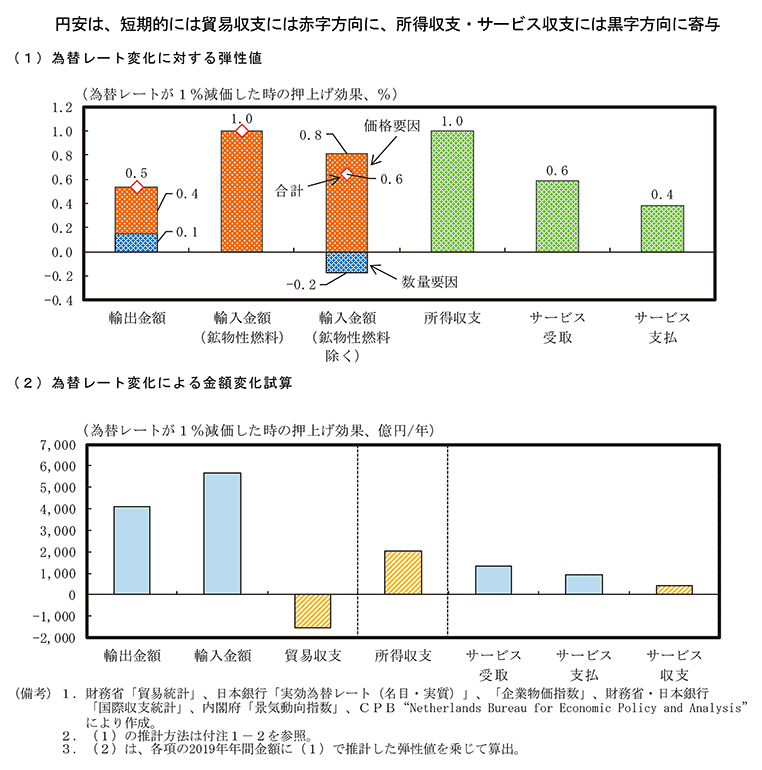
(経常収支は鉱物性燃料の価格上昇等により103か月ぶりの赤字)
ここまで収支項目別の為替レートの短期的な影響をみてきたが、経常収支の実績を確認しておきたい。経常収支は、2019年には19.3兆円の黒字だったが、貿易収支の赤字幅の拡大が所得収支の黒字幅の拡大を上回ること等により、2022年10月には103か月ぶりに赤字となった(第1-1-9図(1))。貿易収支についてみると、2022年には、原油・石炭・天然ガスといった鉱物性燃料の価格上昇が、円安とあいまって輸入金額を大きく増加させた。輸出については、供給制約もあり数量の増加が限定的な一方、電気機器や一般機械、輸送用機器などを中心に、円安もあり円ベースでの輸出金額は増加した。しかし、鉱物性燃料を中心とする輸入金額の増加が輸出金額の増加を上回った結果、2022年11月には2兆円の貿易収支赤字となった(第1-1-9図(2)~(4))。
サービス収支の赤字幅も拡大している。サービス輸出は、2019年と比べ、輸送サービスや知的財産権等使用料が増加した一方、欧米諸国と比べ厳格な水際対策を長く続けたことで旅行(外国人の訪日旅行)が大きく減少し9、全体では小幅な増加にとどまった(第1-1-9図(5))。サービス輸入は、2019年と比べ、旅行(日本人の外国旅行)が大きく減少10した一方、知的財産権等使用料に加え、インターネット利用料やデータベース利用料等から成る通信・コンピュータ・情報サービス、研究開発に係るサービス取引やウェブサイトの広告スペースの売買などを含むその他業務サービス等が伸びたことで7兆円近く増加した。それらの結果、サービス収支赤字は6兆円へと拡大している(第1-1-9図(6))。
対外収支の先行きについては、プラス要素とマイナス要素の両面が存在する。まず、財輸出については、海外経済の成長鈍化が見込まれており、これまで増加をけん引してきた機械類等の資本財の下振れが懸念される。また、主力の自動車等の輸送用機械については、需要要因に加えて半導体等の供給制約を解消できるか否かが鍵となっている。他方、サービス輸出については、海外からの旅行客が当面は増加すると期待される。
次に輸入については、原油価格が2022年半ばをピークに円ベースでも11月にはウクライナ危機前の水準に戻っているものの、地政学リスクは引き続き高く意識され、産油国の動向によって需給がひっ迫する可能性は残る。もっとも、8割以上を長期契約で買い付けている天然ガスがおおよそ3か月前の原油価格と連動する商慣行を踏まえると、当面の燃料輸入額が急増するリスクは低下している。
ただし、我が国のエネルギー供給における化石燃料への依存度の高さが解消されない限り、鉱物性燃料の商品市況の影響を強く受けて所得流出に苛まれることになる。今後は、安全の確認された原子力発電所の再稼働を進め、国産素材を利活用する再生可能エネルギーについてコストを低減させながら比率を高めることで、対外依存度を引き下げることが求められる。こうした取組は、地球温暖化対応にもかなう。また、産業分野だけでなく、一般住宅や商業施設並びに公共交通において省エネ投資を一層進めることにより、エネルギー需要を抑制していくことも重要である。さらに、人口動態の変化を踏まえると、財輸出に依存する構造、数量に依存する構造を変えていくことも求められる。具体的には、通信・コンピュータ・情報サービスやその他業務サービスといった輸入超過のデジタル関連産業の競争力強化11も重要な課題と考えられる。
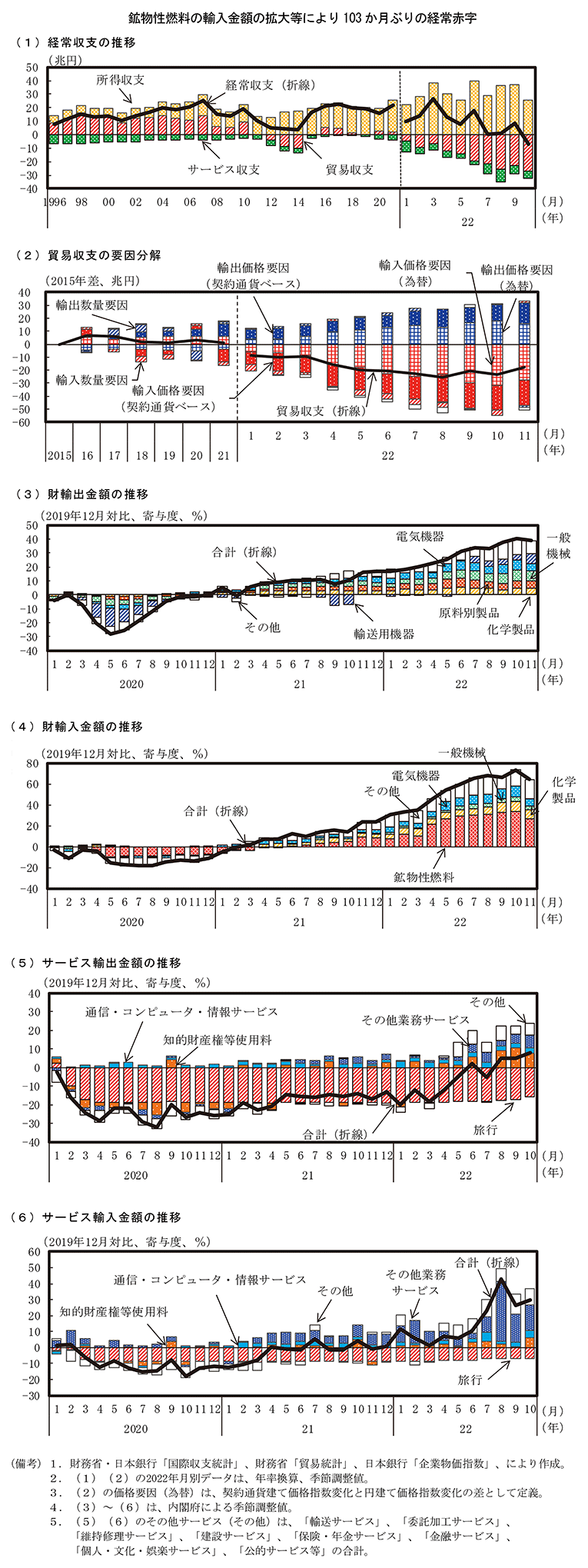
コラム1-1 世界的なサービス貿易の拡大と日本のサービス収支の動向
UNCTADによると、2006年からの15年間に、世界全体の財輸出が84%増加したのに対して、コロナ禍で一時的に落ち込んでいる旅行を除くと、サービス輸出は140%増加するなどサービスの貿易に占める割合が増加している(コラム1-1図(1))。一方、我が国でも旅行を除くサービス輸出は増加しているものの、その増加率は62%と世界全体の半分以下であり、旅行を除くサービス輸出に占める日本のシェアは2021年では3.0%にとどまっている(コラム1-1図(2)、(3))。
我が国のサービス輸出の特徴を世界との比較でみると、知的財産権等使用料がシェア・寄与度ともに高い。加えて、最近10年で旅行サービスの輸出が大きく伸び、サービス収支の改善に寄与している一方、通信・コンピュータ・情報サービスは、主にゲームの定額利用料の輸出が増加することで2019年、20年と急速に伸びたもののシェアは依然として小さく、シェアが大きいその他業務サービスの伸びは世界平均の半分にとどまっている(コラム1-1図(2)、(4)、(5))。
次に、サービス貿易の収支をみると、上述のとおり輸出の伸びが世界との比較で小さい一方で、輸入が大きく増加し赤字幅が拡大している(前掲第1-1-9図(5)、(6))。通信・コンピュータ・情報サービスの大宗はコンピュータサービス12であり、ゲーム等のサブスクリプション契約の利用料、ファイルや写真を保存・共有するクラウドサービスやウェブ会議システムの月額利用料などが含まれる。こうした分野の輸入が増加し、赤字幅は2014年の0.9兆円から2021年には1.7兆円へと拡大している。また、その他業務サービスは、研究開発サービス、専門・経営コンサルティングサービス、技術・貿易関連・その他業務サービスに分類される。このうち、検索エンジンやSNSの広告スペース利用料などが含まれる専門・経営コンサルティングサービスは、世界的に成長が顕著であるものの、我が国では輸入に比べ輸出の伸びが小さく、赤字幅が同0.5兆円から1.3兆円へと拡大している。さらに、動画や音楽配信サービスは知的財産権等利用料の中の著作権等利用料に含まれているが、こうしたサービスも含め、著作権等利用料でも輸入に比べ輸出の伸びが小さく、赤字幅が同0.8兆円から1.4兆円へと拡大している(コラム1-1図(6))。
デジタル関連サービスはこのように様々な項目に分類されているため、それだけを取り出して議論することは難しいが、例えば、通信・コンピュータ・情報サービスは世界全体で輸出額が過去15年で3倍以上に成長しており、今後も成長が続くと考えられる分野である13。このため、海外展開も視野に入れたデジタル取引における環境整備や、デジタル人材の育成等を通じ、我が国企業のデジタル関連分野における競争力を強化していくことが重要となってくる。また、デジタル関連産業は比較的社歴の浅い企業が多く、スタートアップが果たしている役割が非常に大きい。我が国においてはスタートアップ5か年計画を取りまとめたところであり、スタートアップの成長がデジタル関連サービスの輸出増につながることも期待される。