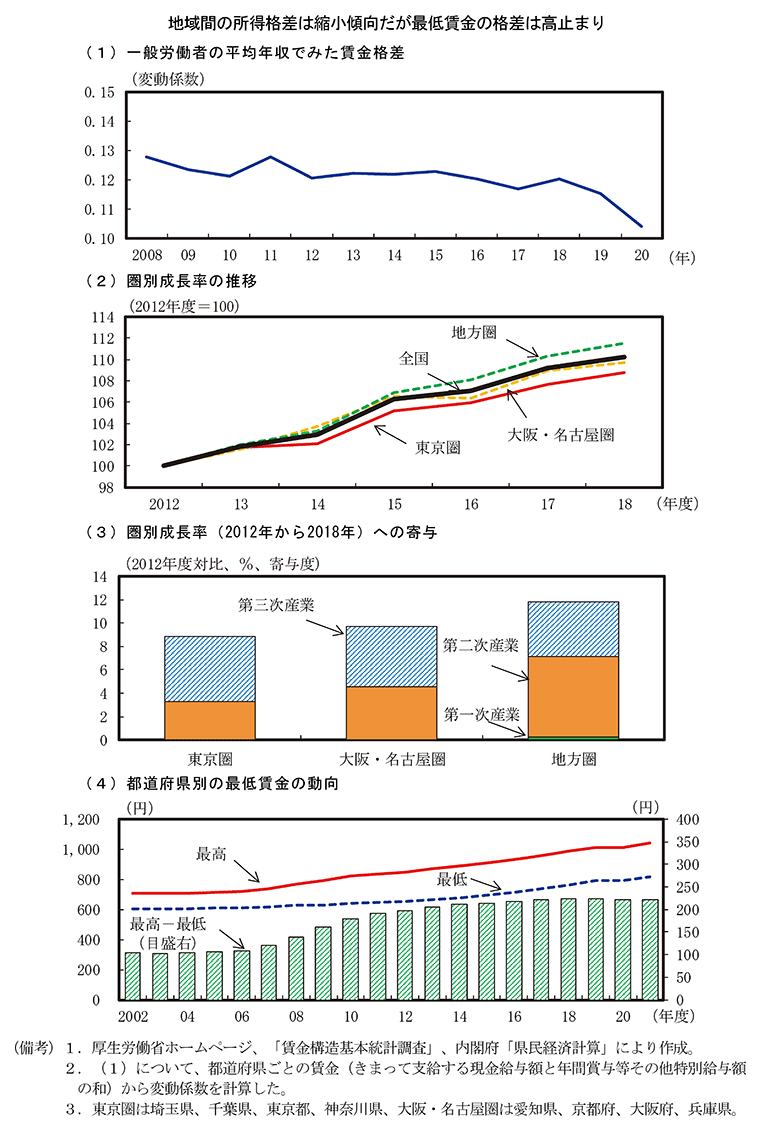第3章 成長と分配の好循環実現に向けた家計部門の課題(第3節)
第3節 格差の動向と課題
第1節において、多様な働き方が拡大してきたことを確認したが、そうした動向の下、労働所得や世帯所得、資産、資産所得の格差にどのような変化がみられるかを確認する。感染症により顕在化した教育や地域に関する格差の動向についても概観する。
1 労働所得の格差の動向
(パート・アルバイト等の非正規雇用者の増加に伴い、収入分布の二極化が進行)
非正規雇用者は、正規雇用者と比べて、平均してみれば時給が低く(前掲第3-1-10図)、労働時間は短い傾向にある。非正規雇用をはじめ、多様な働き方が広がる中で、労働所得(雇用者が仕事から得た年間収入)の分布にはどのような変化がみられるだろうか。
2019年の正規雇用者の年間収入の分布をみると、男性では200~1,000万円未満の所得層が大部分を占めており、300万円台と500~700万円未満の所得層でそれぞれピークがみられる(第3-3-1図(1))。女性の正規雇用者では200~700万円未満の所得層が大部分を占めており、200万円台でピークがみられる。2002年と2019年を比較すると、男女ともに分布のピークは変わっていないものの、女性の正規雇用者については100~200万円未満の所得層の人数が減少する一方、300~700万円未満の所得層の人数が増加している。
次に非正規雇用者の年間収入の分布をみると、2019年のパート・アルバイトは男女ともに300万円未満の所得層が大部分を占めている。2002年と2019年を比較すると、パート・アルバイトの男性の人数が少ない状況に変わりはない一方、女性の人数は50~300万円未満の幅広い所得層で増加している。ただし、女性のパート・アルバイトの年間収入のピークは50~100万円未満で変化はない。2019年の派遣や契約・嘱託の年間収入をみると、男女ともにピークは200~300万円未満の所得層となっており、2002年と比べてこの層の人数が大きく増加している。
なお、一週間の労働時間の分布をみると、正規雇用者では、男女ともに40時間以上が大部分を占めるのに対し、非正規雇用者では、パート・アルバイトは15~29時間、派遣や契約・嘱託は40~48時間がピークとなっている(第3-3-1図(2))。また、派遣や契約・嘱託においては、15~29時間も多いことがわかる。大多数の正規雇用者と同様、40~48時間働く派遣や契約・嘱託の非正規雇用者が多いにもかかわらず、収入分布には大きな差がみられる。
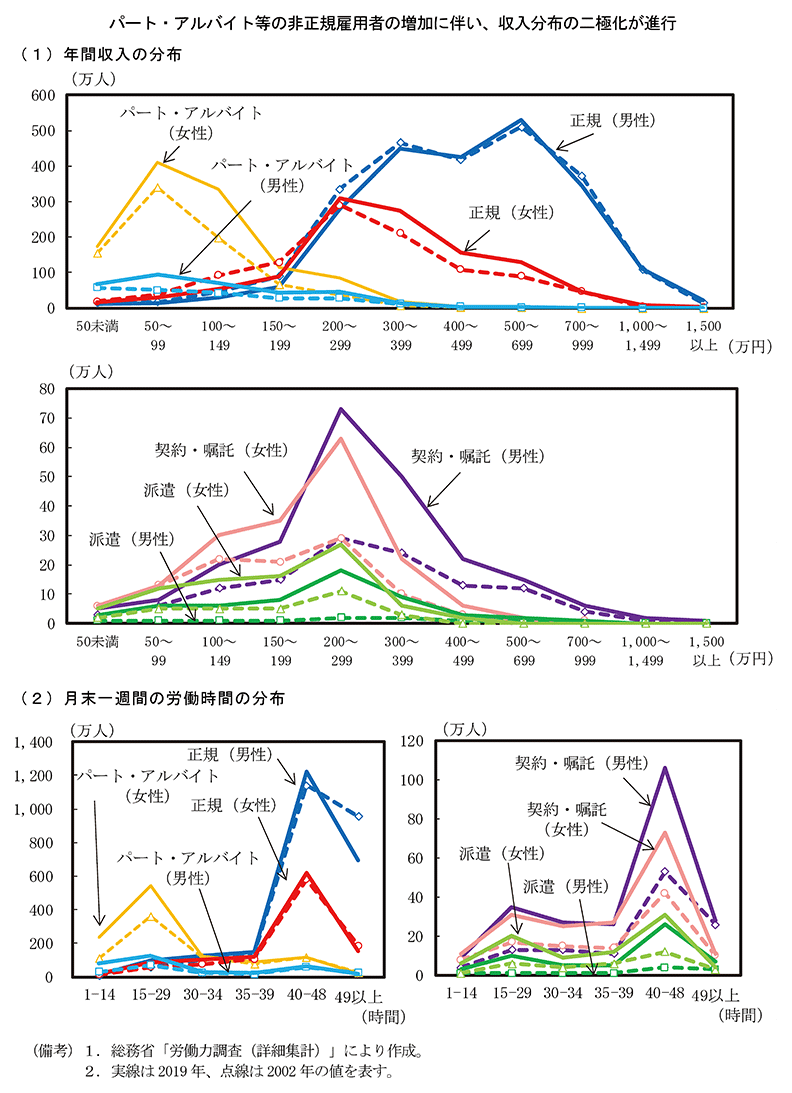
(労働所得のジニ係数は全体として緩やかに低下傾向。ただし、25~34歳で上昇傾向)
次に、我が国全体の労働所得の分布や格差にどのような変化がみられるかを確認したい。2002年以降の労働所得の分布の変化をみると、上で確認した女性のパート・アルバイトや男女の契約・嘱託、派遣労働者の増加等を背景に労働所得が300万円未満の所得層の割合が増加傾向にある(第3-3-2図(1))。一方、500万円以上の所得層の割合は、1,500万円以上の層を除いて減少傾向にある。
こうした労働所得の分布について、格差を示す代表的な経済指標であるジニ係数を計算してみると、2002年から2007年にかけて緩やかに上昇した後、2017年にかけて緩やかに低下している(第3-3-2図(2))。25~34歳以外の年齢階層においてジニ係数が低下傾向にあるほか(第3-3-2図(3))、団塊の世代が労働市場から退出したことを背景に、ジニ係数の水準が高い55~59歳の割合が低下したことが寄与しているものと考えられる。25~34歳の層でジニ係数が上昇しているが、2002年から2017年にかけて男性の非正規雇用比率が上昇し、労働時間が減少したことなどが背景にあると考えられる(第3-3-2図(4)、(5))。
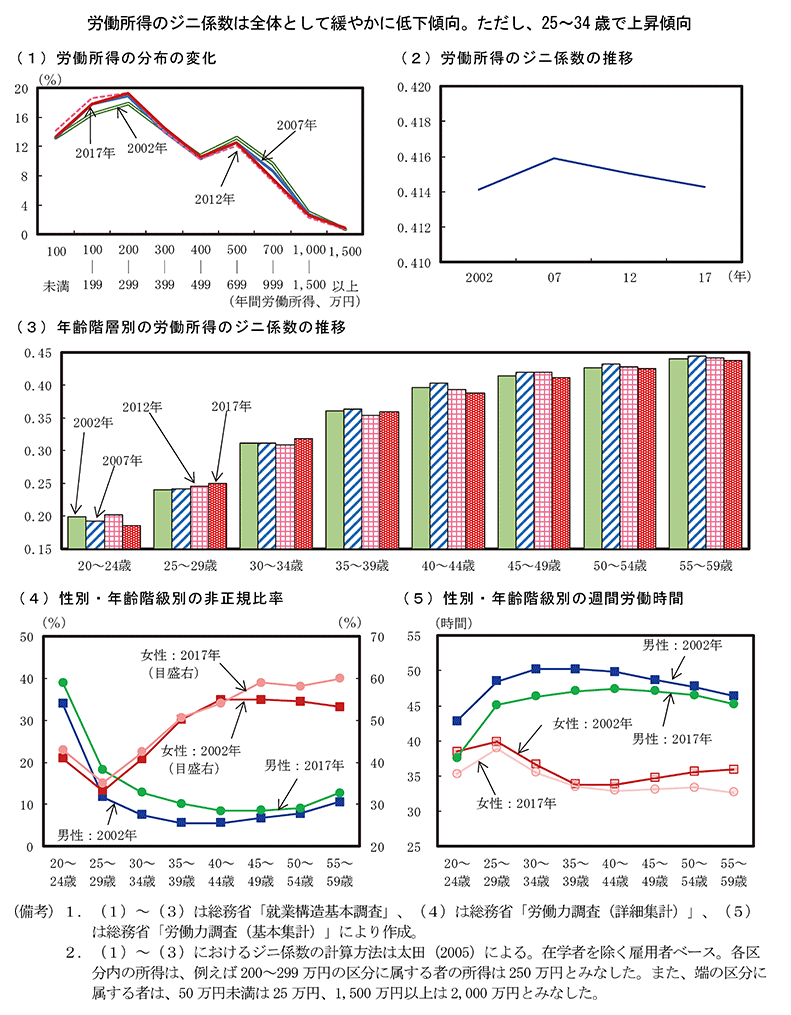
2 世帯所得の格差の動向
(世帯所得が500万円未満の25~34歳の世帯では子どもを持つ割合が大きく低下)
前項でみたとおり、非正規雇用者の増加等を背景に、収入分布の二極化は変わらず、25~34歳においては、個人単位の労働所得の格差が拡大していることがわかるが、世帯所得の分布はどのように変化しているのだろうか。
「全国家計構造調査」を用いて、個人単位の労働所得の格差拡大がみられた25~34歳の世帯に着目して、2014年及び2019年の再分配前の世帯所得の分布を確認したい1。世帯主年齢が25~34歳の世帯所得の全体の分布をみると、中央値は2014年の451万円から2019年の475万円に増加し、500万円未満の層の割合が低下している(第3-3-3図)。一方、700万円以上の層の割合が全般的に高まり、1,000万円以上も上昇している。
世帯類型別に世帯所得の分布をみると、未婚化や晩婚化の進展等を背景に単身世帯の割合が大きく高まっている。単身世帯の所得の中央値は360万円で変化しておらず、300万円台の世帯割合が引き続き最も大きい。夫婦のみの世帯をみると、共働き世帯の増加を背景に、600万円未満の世帯の割合が低下する一方、600万円以上の世帯の割合が上昇し、所得の中央値も増加している。夫婦と子どもからなる世帯についてみると、500万円未満の層の割合が大幅に低下している一方で、800万円以上の世帯分布割合が上昇し、500~800万円未満の割合にはほとんど変化がみられない。世帯所得が500万円未満の世帯では子どもを持つという選択が難しくなっていることがうかがえる2。晩婚化や少子化への対応に当たっては、結婚や子育てを控える25~34歳の層の世帯所得の増加が重要であると考えられる。
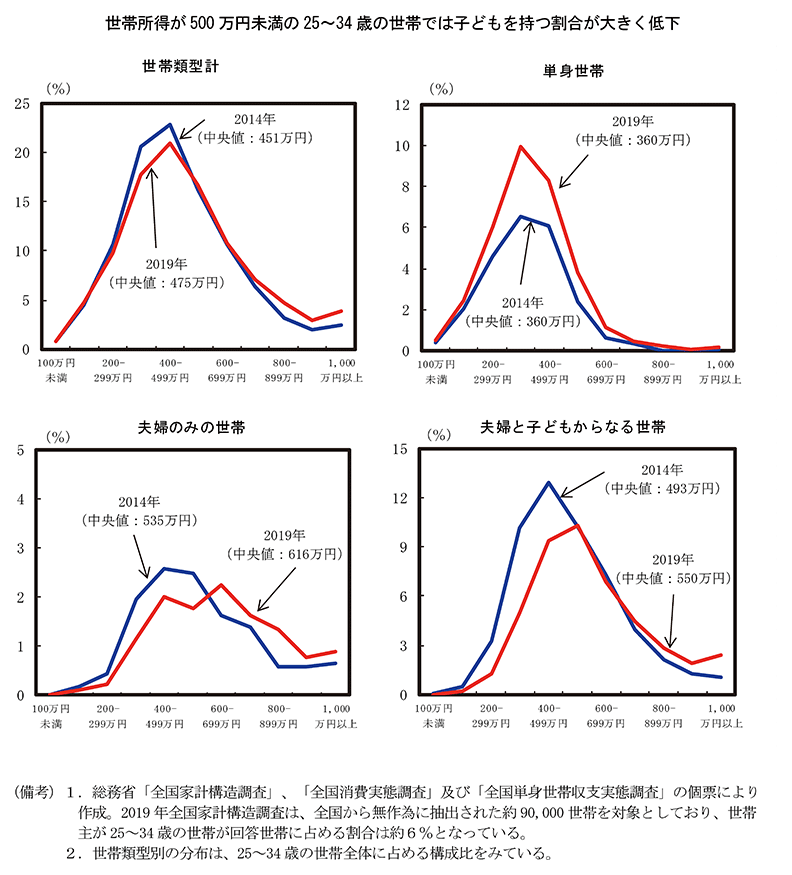
(子どもの貧困率は小幅低下しているものの、母子世帯の所得は引き続き低水準)
所得水準が相対的に低い世帯の動向を確認するため、相対的貧困率の推移をみていきたい。相対的貧困率は2000年から2012年にかけて上昇した後、2018年にかけて小幅ながら低下している(第3-3-4図(1))。また、子どもの貧困率3についても、2012年にかけて上昇を続けた後、2018年にかけて低下している。
ただし、2012年と2018年の男女別・年齢別の相対的貧困率を比較すると、多くの年齢階層で相対的貧困率が低下する中で、75歳以上の男女で上昇がみられる(第3-3-4図(2))。この背景には、高齢者の単身世帯の世帯割合が増加していることなどがあると考えられる4。
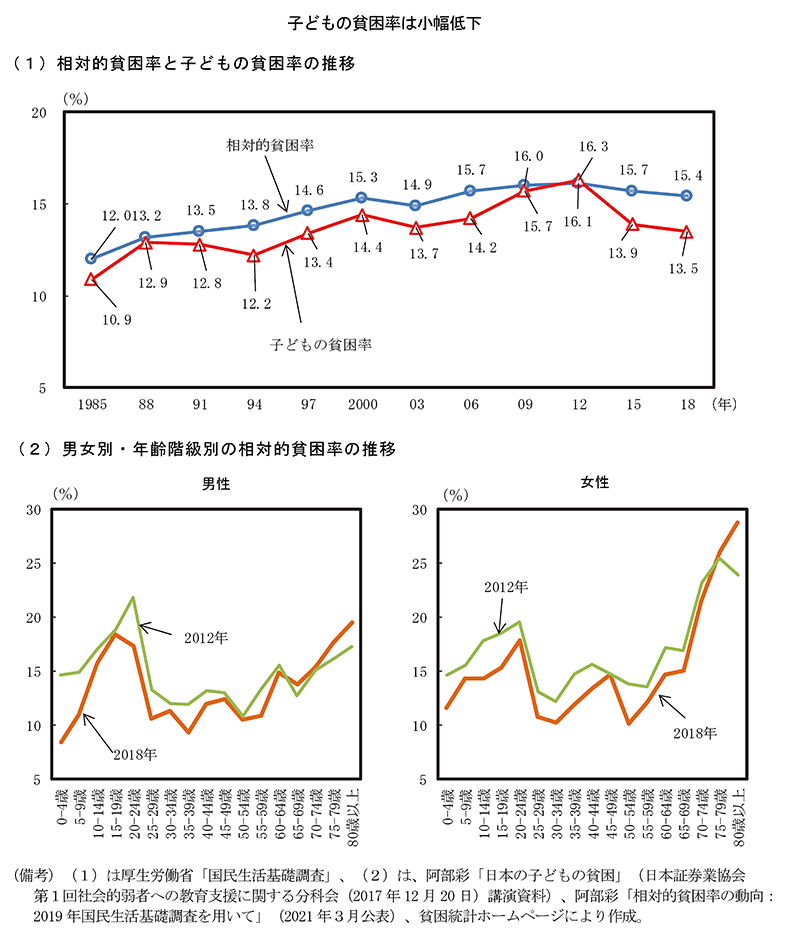
また、世帯類型別に、稼働所得や財産所得等の当初所得に社会保障給付を加えた総所得について、世帯当たり平均金額をみると、高齢者世帯5及び母子世帯6の所得水準は総世帯平均と比べて低い状況にある(第3-3-5図(1))。世帯人員一人当たりの平均所得をみると高齢者世帯は総世帯平均と同程度となる一方、母子世帯は半分程度の水準にとどまっている(第3-3-5図(2))。所得の構成をみると、高齢者世帯では年金等が約7割を占めているのに対し、母子世帯では、児童手当等による所得の下支えは1割弱程度にとどまっており、母子世帯における厳しい状況がみてとれる(第3-3-5図(3))。感染症の影響を受ける前から母子世帯の約9割が生活に苦しさを感じており(第3-3-5図(4))、後述の教育格差への対応の観点とあわせて、子どもを持ち、所得水準が相対的に低い世帯への支援の在り方を検討していく必要があると考えられる。
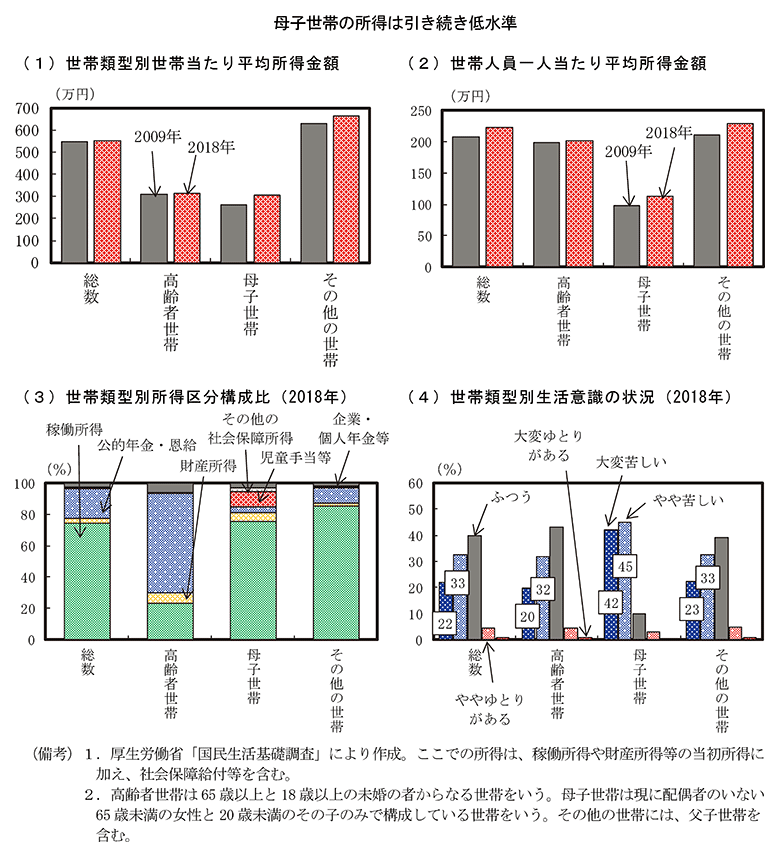
3 資産格差・資産所得格差の動向
(高額資産保有層における金融資産保有割合は小幅高まり、資産所得格差は拡大)
ミラノヴィッチ(2021)は、我が国資産所得の格差は他の主要国と比べて大きいと指摘しているが、その背景について確認してみたい。2014年及び2019年の家計資産総額7の十分位階級別に金融資産残高の分布をみると、金融資産残高全体の40%程度、世帯当たり平均では5,000万円程度を保有する第十分位の保有割合が小幅高まっている(第3-3-6図(1)、付表3-4)。
各分位における2019年の金融資産残高の内訳をみると、金融資産残高が大きい層ほど株式等の有価証券の保有割合が大きい(第3-3-6図(2))。また、2014年から2019年にかけて金利が低下する中で、預貯金等の保有割合が大きい世帯における保有金融資産の収益率が総じて低下し、0.2%を下回る一方、有価証券の保有割合が大きい第十分位の保有金融資産の収益率は、低下したものの、他の世帯に比べて高水準にある(第3-3-6図(3))。こうしたことを背景として、利子・配当金収入の分布をみると、第十分位の割合は2014年の約54%から2019年には約60%に上昇しており、2014年と比べて資産所得の格差は拡大している(第3-3-6図(4))。総じて低い金融資産の収益率と有価証券を保有する世帯が高家計資産総額世帯に偏っていることが我が国の資産所得格差が他国と比べて大きい背景にあると考えられる8。2014年から始まったNISAによる有価証券への少額投資非課税制度等の支援措置の一層の活用を含め、今後貯蓄から投資への転換を進めていくことは、資産所得の格差拡大への歯止めにつながると考えられる。
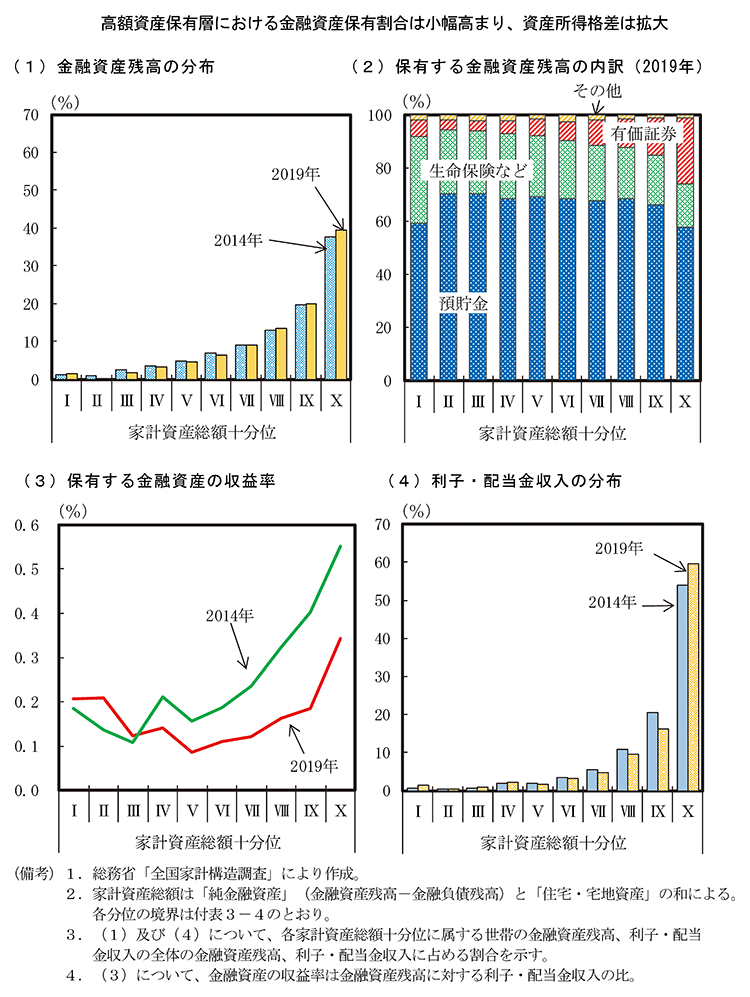
4 教育や地域に関する格差の動向
(地域間や公立・私立間でのオンライン教育へのアクセス格差が顕在化)
上述のような格差に加え、感染症下で教育面の格差も顕在化した。17~19歳を対象としたアンケート調査9によると、約半数が教育格差を感じていると回答しており、その要因として「家庭や学校のデジタル環境の差」や「教育環境の地域差」を挙げる割合がそれぞれ約9%に達した(第3-3-7図(1))。アンケート調査では、「パソコンがない家があったので、オンライン授業が少なかった」、「都心や私立の学校では、タブレット等で授業が進められるが、地方や公立校ではプリント学習になってしまう」といった指摘があった。また、小中学校における感染症下でのオンライン教育の受講状況を東京都23区と地方圏で比較すると、東京都23区の受講率は2倍以上となっており(第3-3-7図(2))、感染症の下で地域間や公立・私立間でのオンライン教育へのアクセス格差が顕在化した。
オンライン環境の整備としては、2019年度から2023年度までの計画で児童生徒一人一台端末と高速大容量の通信ネットワークの一体的整備を行うGIGAスクール構想が進められている。オンライン教育へのアクセス格差の解消に向けて、着実な取組が求められる。
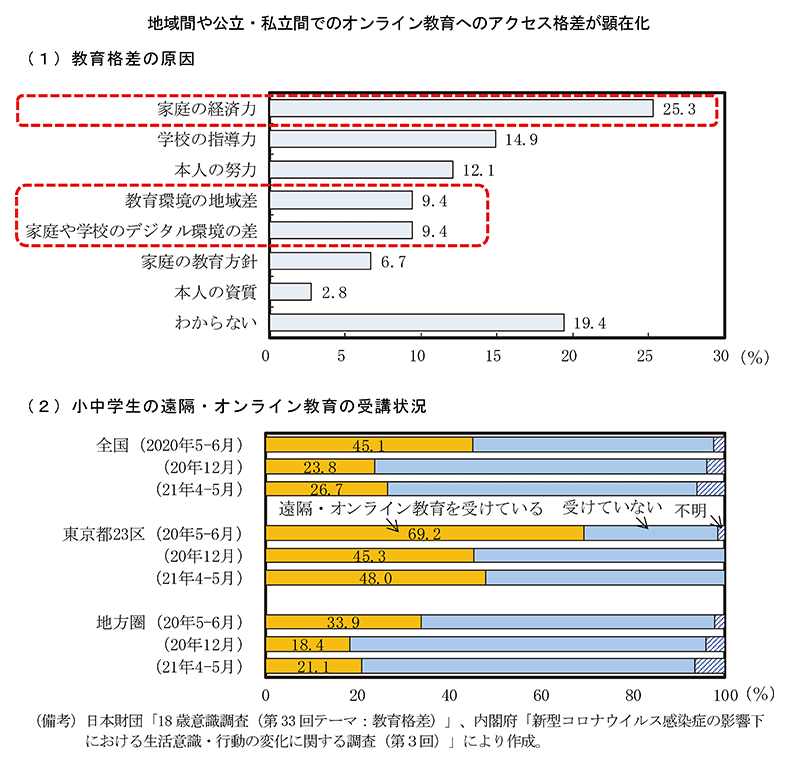
(親の学歴等の家庭環境は最終学歴に大きな影響)
感染症下で感じる教育格差の原因としては、「家庭の経済力」を挙げる割合が約3割と最も大きい(前掲第3-3-7図(1))。家庭環境はこれまでも教育格差の重要な要因として指摘されてきた。例えば、松岡(2019)によれば、本人の15歳時点での家庭の経済状況(自己評価)や本人の最終学歴(大卒・非大卒)によって、父親の大卒割合に違いがあるかどうかを比べると、総じて、経済状況が豊かかどうかにかかわらず、非大卒の者と比べて大卒の者は父親の大卒割合が高い(第3-3-8図(1))。家庭の出身階層(父親が大卒であるかどうか)によって、本人の大卒割合に格差があることが指摘されている。また、2020年の生活保護世帯における子どもの教育状況をみると、全世帯の平均と比べて、高等学校等中退率は高く、大学等進学率は低い(第3-3-8図(2))。
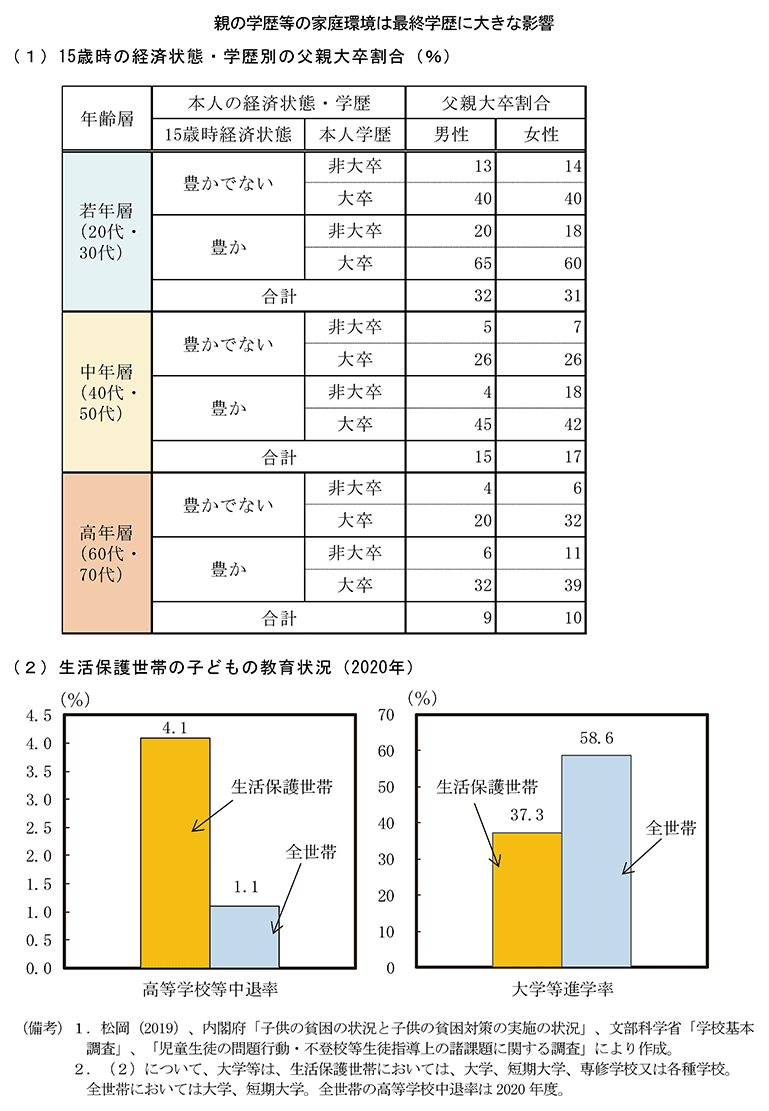
また、家庭の経済状況等を背景にアルバイトを行う大学生は8割を超えているが、感染症の影響による飲食サービス業等での就業機会の減少を背景に、2020年度のアルバイトの実施割合は2018年度から5%ポイント程度低下した(第3-3-9図(1))。また、家庭からの給付や奨学金等を含む、2020年度の大学生の収入額が2018年度から約7.4万円減少する中で、年間平均アルバイト収入も約3.5万円減少しており、家庭の経済状況が厳しい大学生は感染症による影響を強く受けた可能性がある(第3-3-9図(2))。
以上のような家庭環境、経済環境に起因する教育格差に対応する観点から、高等教育の修学支援新制度が2020年4月から開始され、住民税非課税世帯等の学生を対象に授業料等減免制度の創設・給付型奨学金の支給の拡充が行われている10。また、感染症の影響によりアルバイト収入が激減した大学生に対しては、休業支援金・給付金等による時限的な支援が実施された。感染症下での経験と施策の効果を検証しつつ、厳しい家庭環境や経済環境に置かれる大学生等への支援の在り方を検討していくことが求められる。
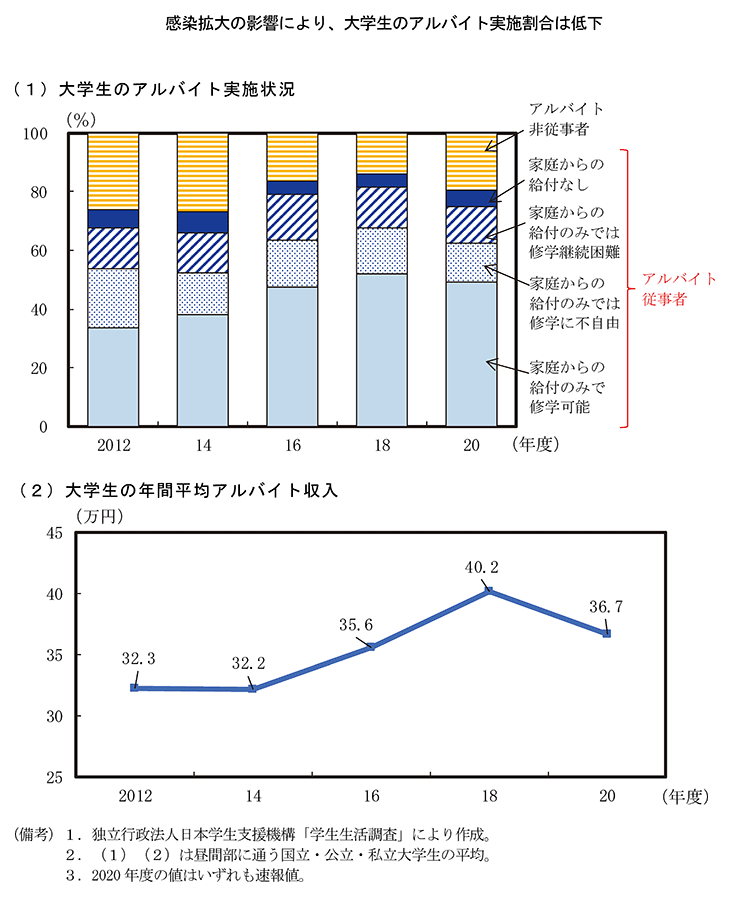
(地方移住への関心が高まったものの、仕事や収入への懸念が大きい)
感染症を契機にテレワークの実施率が高まっており、特に東京23区では2021年9~10月時点において半数以上がテレワークを実施している(第3-3-10図(1))。テレワークの活用が進む中で、東京圏在住者の地方移住への関心が高まっており、約3割が地方移住に関心があると回答している(第3-3-10図(2))。実際、地方移住への関心理由としても、「テレワークによって地方でも同様に働けると感じたため」を挙げる割合が二番目に高く、テレワークの実施が地方移住に関心を持つ大きなきっかけとなっている(第3-3-10図(3))。
その一方で、地方移住に当たっての懸念として、「仕事や収入」を挙げる割合が約5割程度と最も大きく、この点が地方移住を行動に移す際の妨げとなっている(第3-3-10図(4))。実際に2020年の人口移動の状況を確認すると、東京都における転入超過人口は、平年(2015年から2019年の5年平均)と比べて減少したものの、「就職世代(20~29歳)」は引き続き大幅な転入超過にあり、仕事や収入が東京都への人の流れを最も左右する点に大きな変化はみられない(第3-3-10図(5))。
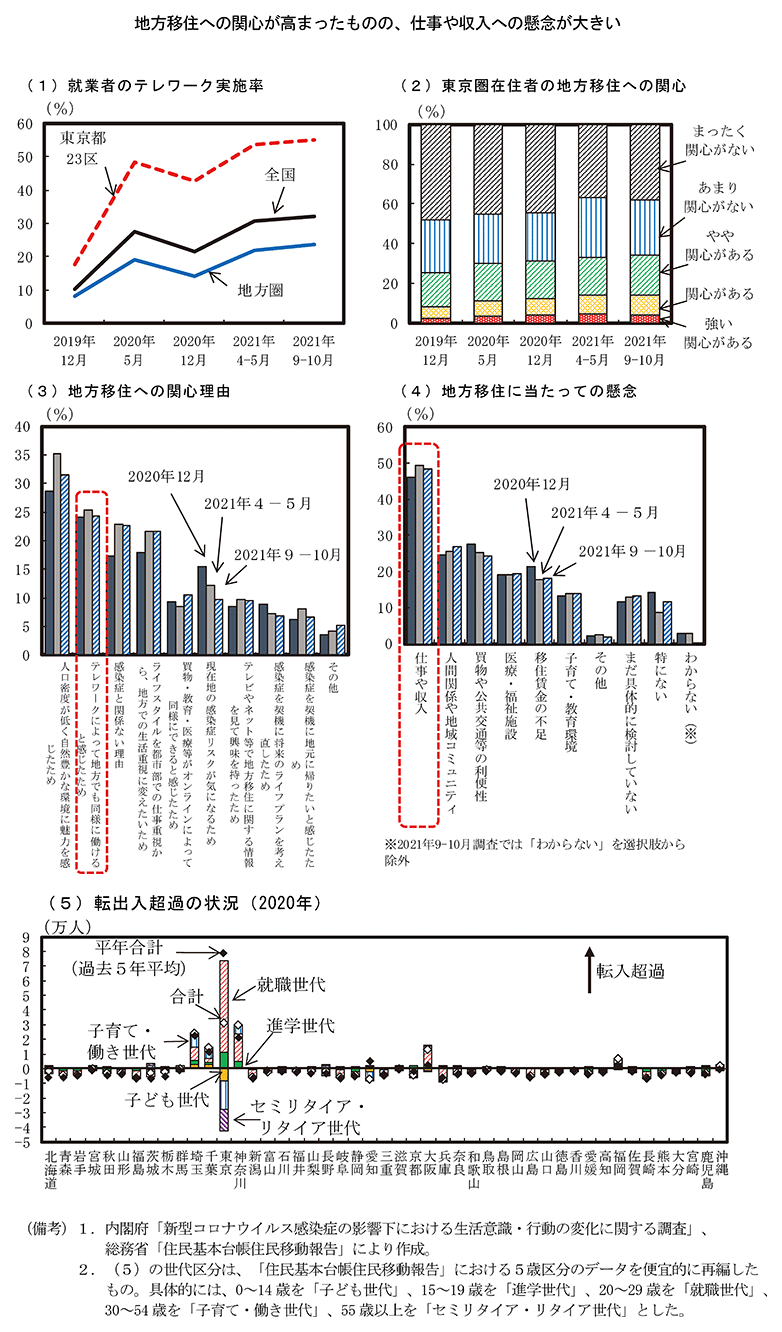
(地域間の所得格差は縮小傾向だが最低賃金の格差は高止まり)
こうした点を踏まえ、地方においてより魅力的な就業機会を創出するための取組がこれまでも進められてきたが、地域間の所得格差にどのような効果があったのだろうか。各都道府県の一般労働者の平均年収の変動係数は低下傾向にあり、地域間の所得格差は縮小傾向にある(第3-3-11図(1))。2012年以降の成長率を圏域別に比較すると、東京圏に比べて地方圏の成長率が高い傾向にあり、製造業や建設業の第二次産業がその成長に大きく寄与していることがわかる(第3-3-11図(2)、(3))。第二次産業にけん引された地方圏での成長率の高まりが地域間の所得格差の縮小に寄与してきたことがうかがえる。
一方、都道府県別の最低賃金の推移をみると、最低賃金引上げの取組により、その最高値・最低値ともに上昇しているものの、両者の格差は高止まりしている(第3-3-11図(4))。地方経済の実情を踏まえつつ、地方の最低賃金水準の底上げに向けた取組を推進することにより、地方で働くことの魅力を高め、地方への人の流れを拡大することも必要と考えられる。