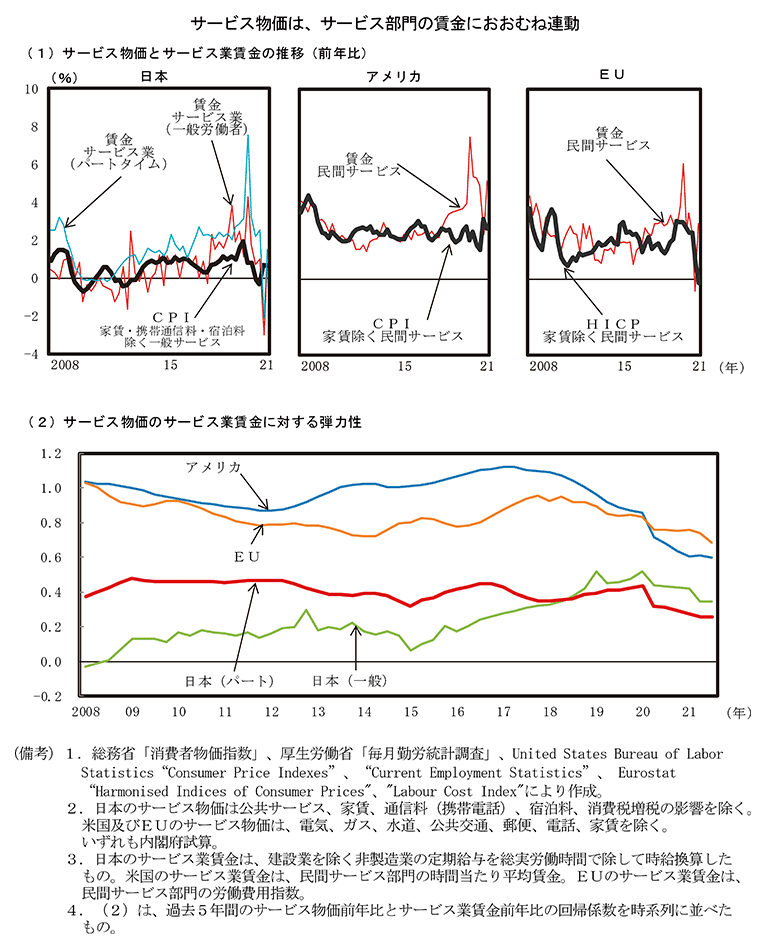第1章 感染症と経済活動の両立に向かう日本経済(第4節)
第4節 デフレ脱却に向けた進捗
前節まででみてきたように、我が国経済は、輸出や投資に足踏みがみられるとはいえ、個人消費が持ち直す中で、景気全体にも持ち直しの動きがみられている。こうした中、物価は、感染症後も底堅い動きが続いているが、デフレ脱却に向けて持続的なものといえるだろうか。本章では、デフレ脱却に向けた進捗を点検する。
1 原材料価格高騰の影響
(原油・原材料価格の上昇等を通じて企業物価は上昇)
2021年初以降、原油を含む原材料価格が高水準で推移しているが、こうした価格変化は輸入物価を通じて国内物価に影響する。
はじめに国際商品市況の動向を振り返ろう。2020年初から4月頃にかけて、感染症の流行に伴う経済活動の停滞を背景に、多くの商品価格が低下した(第1-4-1図(1))。しかし2020年半ば以降、行動制限の緩和や解除、各国の財政・金融政策等の効果もあって、世界経済が徐々に回復に向かう中で、国際商品価格も次第に持ち直していった。こうした動きは、原油等のエネルギー価格だけでなく、アルミニウムや銅等の非鉄金属、小麦等の穀物、材木といった幅広い資源価格においてみられており、2021年12月現在も、多くの商品が感染症前を上回る水準で推移している。
このような原油・原材料価格の動きは、企業が直面する海外からの輸入物価や国内企業物価の上昇につながる。国内企業物価、輸入物価の推移をみると、実際に国際商品市況が持ち直していく中で、2021年初から上昇基調にある(第1-4-1図(2))。内訳をみると、国内企業物価は「原油・エネルギー関係」、輸入物価は「石油・石炭・天然ガス」といったエネルギー関係が最も押上げに寄与している。またエネルギー以外にも、前者は「鉄鋼」や「非鉄金属」、後者は「金属・同製品」といった金属関連がプラスとなっている。金属関連について、世界的な需要回復に加えて、電気自動車や再生可能エネルギーといった脱炭素化の流れの中で、これらに使用される配線や蓄電装置向けの鉱物資源(銅やニッケルなど)への需要が増加していることも価格上昇につながっている(コラム1-3参照)。
国内企業物価と輸入物価について、同じく国際商品市況が上昇していた2007年~2008年の内訳寄与と比較してみると、今般の物価上昇は、こうした非鉄金属を中心とした金属関連の寄与度の割合が大きいことが確認できる(第1-4-1図(3))。
このように、2021年は世界経済の回復や脱炭素化の流れの中で、エネルギーやそれ以外の鉱物資源の上昇が国内企業物価や輸入物価を押し上げた。
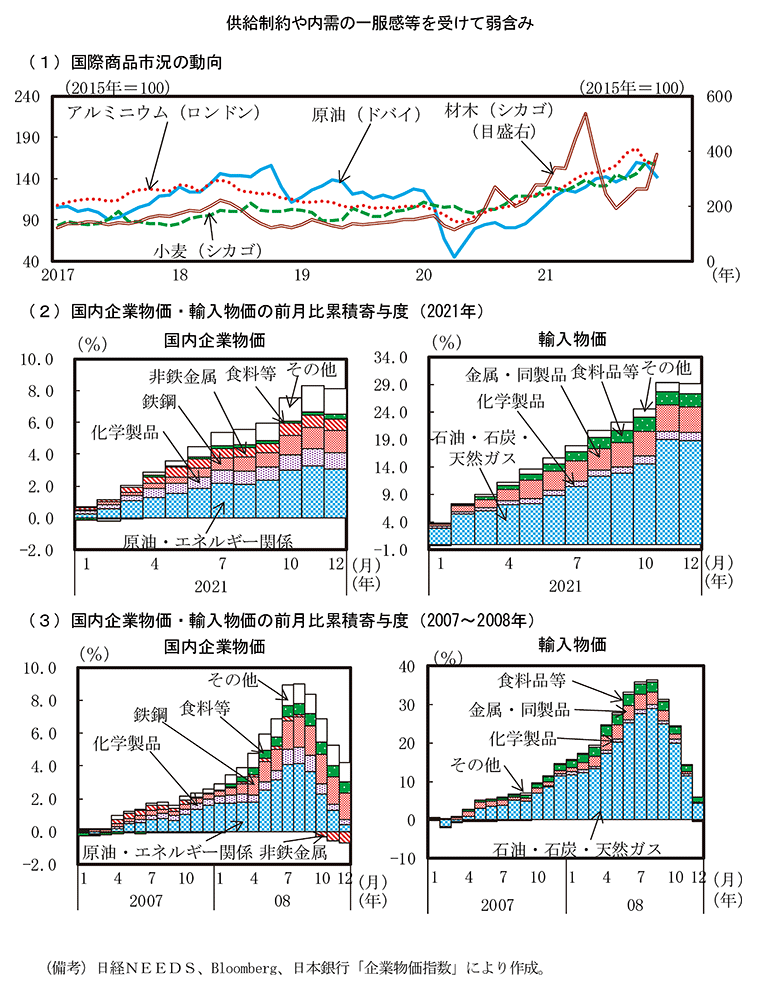
コラム1-3 脱炭素化の動きと鉱物資源需要
2021年にみられた企業価格の上昇には、原油などのエネルギー関連品目だけでなく、非鉄金属を中心とした金属関連製品も押上げに寄与している。
原油価格については、産油国が感染拡大後に大幅に減らした生産量を一定程度回復させたものの、世界的な景気回復を背景としてそれ以上に需要が多かったことなどから、価格が高騰した(コラム1-3図(1))。加えて、中長期的な化石燃料の使用量削減といった脱炭素に向けた取組や、それを見越した新規開発投資の抑制も生産量の抑制につながり、価格を押し上げた面があるとみられる。
脱炭素に向けた動きは、エネルギー以外の鉱物資源価格にも影響を及ぼしている。例えば、電気自動車や再生可能エネルギー発電施設は、これまでと比べて多くの配線や蓄電装置を必要とし、これら部材向けの銅、ニッケル、マンガン、コバルトといった多様な鉱物資源への需要拡大につながっている。国際エネルギー機関(IEA)によれば、電気自動車は従来型自動車の6倍の鉱物資源を、陸上風力発電所は同規模の火力発電所の9倍の鉱物資源を使用するとされる(コラム1-3図(2)、(3))。
我が国は、多くの化石燃料の調達を輸入に依存しているが、脱炭素に向けた取組が進む下で、それ以外の鉱物資源についても、海外からの輸入に依存せざるを得ない面がある。脱炭素化を進めるに当たっては、これら鉱物資源の安定供給確保のために供給源の多角化を図るなど、戦略的な取組が必要となる。
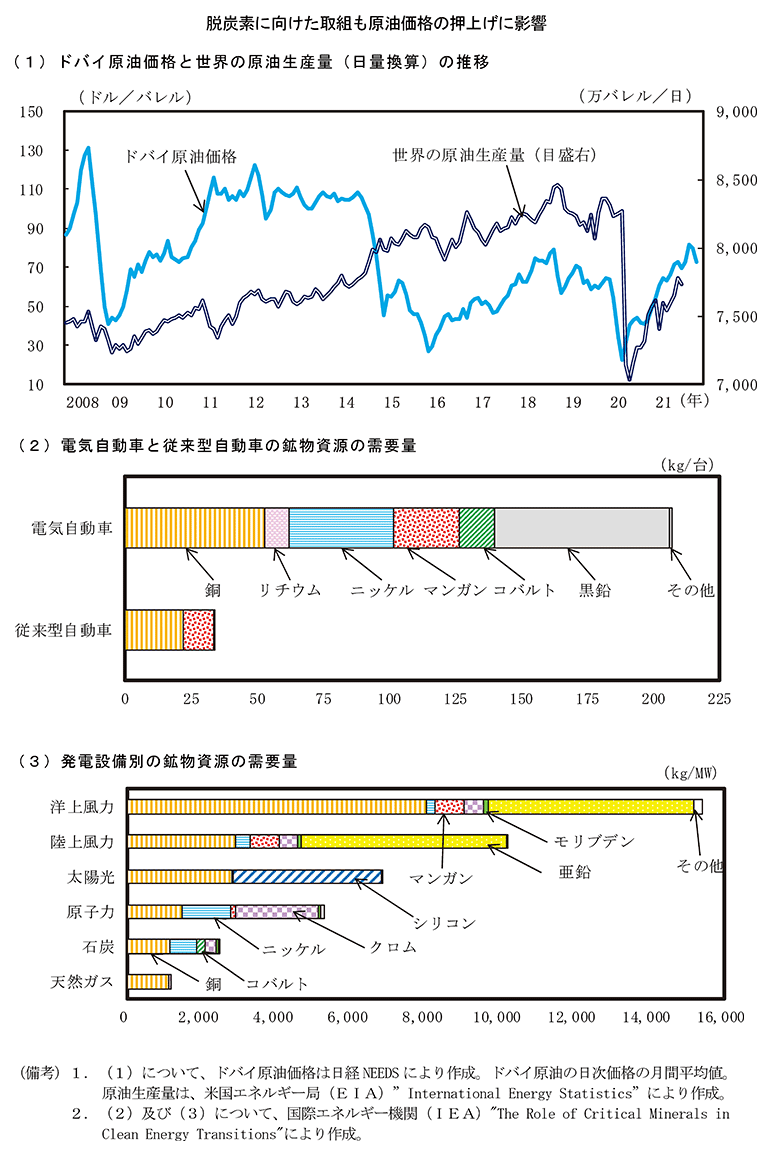
(原油等の原材料価格高騰が交易条件の悪化に寄与)
輸入価格の上昇は、交易条件(=輸出価格÷輸入価格)の悪化(低下)につながる。2021年初以降の交易条件をみると、輸出物価に比べて輸入価格が上昇しており、悪化が続いている(第1-4-2図(1))。
交易条件は、原油・原材料の価格変動だけでなく、為替レート変動の影響も受ける。2021年初以降の名目実効為替レートは、緩やかに円安方向で推移している(第1-4-2図(1))。こうした為替レートの減価(円安)は、円ベースの輸入物価の上昇要因となるため、交易条件の悪化につながる。一方で、円ベースの輸出物価も同時に上昇し得るため、両者の動きの大小関係によって、為替要因による交易条件の悪化幅が決まることになる。
こうしたメカニズムを念頭に、交易条件の要因分解を行うと、「為替要因」は輸出物価・輸入物価ともに2021年は同程度の大きさとなっており、両者が相殺して交易条件には大きな影響は及ぼしていない1(第1-4-2図(2))。
一方で、契約通貨ベースの輸入物価要因は、輸出物価要因を大きく上回って推移しており、2021年は主に輸入物価上昇が交易条件を押し下げた(第1-4-2図(2))。特に、前回の円安局面である2015年頃と比べて、2021年は為替レートの変動が小さく、交易条件に対する寄与も小さかった。一方で、原油・原材料価格が為替要因を上回るほど上昇し、交易条件の悪化に寄与した。
このように2021年は、原油等の原材料価格高騰が交易条件の悪化に寄与した。
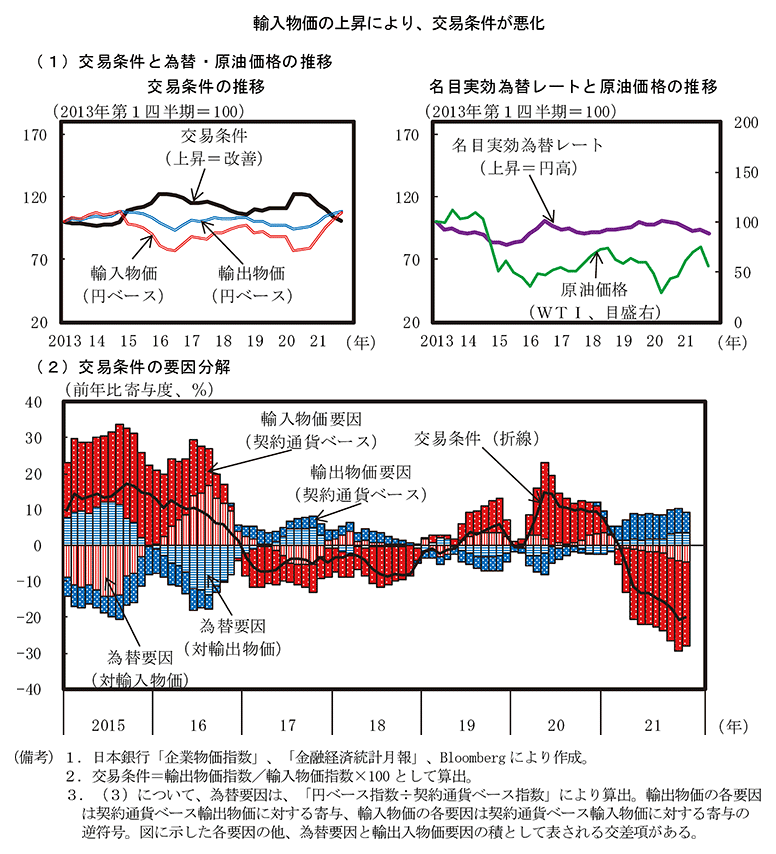
(原材料価格変動を主因として交易損失が拡大)
次に、交易条件の悪化に伴う、国内からの所得流出について考えよう。輸入価格が上昇すると、これまでと同じ量を輸入するために、より多くの輸入代金を支払う必要が生じ、所得が海外に流出する。逆に、輸入価格が下落すれば交易条件は改善し、所得が国内に流入する。こうした交易条件の変化による所得の流出入を示す概念が交易利得(流出の場合、交易損失)である。
実質GDPに交易利得、海外からの所得の純受取(受取-支払)を加えたものは、国内で得られる実質ベースの所得合計である実質GNI(国内総所得)となる。実質GNI成長率(前期比)を「実質GDP要因」と「交易利得(損失)要因」、「海外からの所得の純受取要因」に分解すると、2020年4-6月期以降、感染症後の急速な景気悪化によって実質GDP成長率は大幅に減少し、実質GNI成長率を大きく押し下げた(第1-4-3(1))。また、海外からの所得の純受取は、為替レートが前年より小幅に増価(円高)したことで、円建ての海外収益が円高分だけ減少し、GNIを押し下げた。一方で、原油安の影響で交易利得が拡大し、実質GNIの減少を緩和した。
また、2021年に入って、GDP成長率が一進一退の動きとなる中で、交易条件の悪化を通じて交易損失が拡大しており、4-6月期以降、GNI成長率を押し下げている。海外からの所得の純受取は、為替レートが前年より小幅に減価(円安)したことで、円建ての海外収益が円安分だけ上昇し、GNIを押し上げた。
交易利得の変動について、さらに「為替要因」と原油・原材料価格の変動2である「その他価格要因(資源価格等)」に分解すると、2021年は、「為替要因」のマイナス寄与が小さく、「その他価格要因(資源価格等)」が主に交易利得の動きを決めている。また、その大きさも過去に比べて比較的大きい(第1-4-3図(2))。
このように原油等の多くの鉱物資源を輸入で賄う我が国は、国際商品市況の変動の影響で企業物価が上昇したことを主因として、交易損失の急激な拡大につながっている。
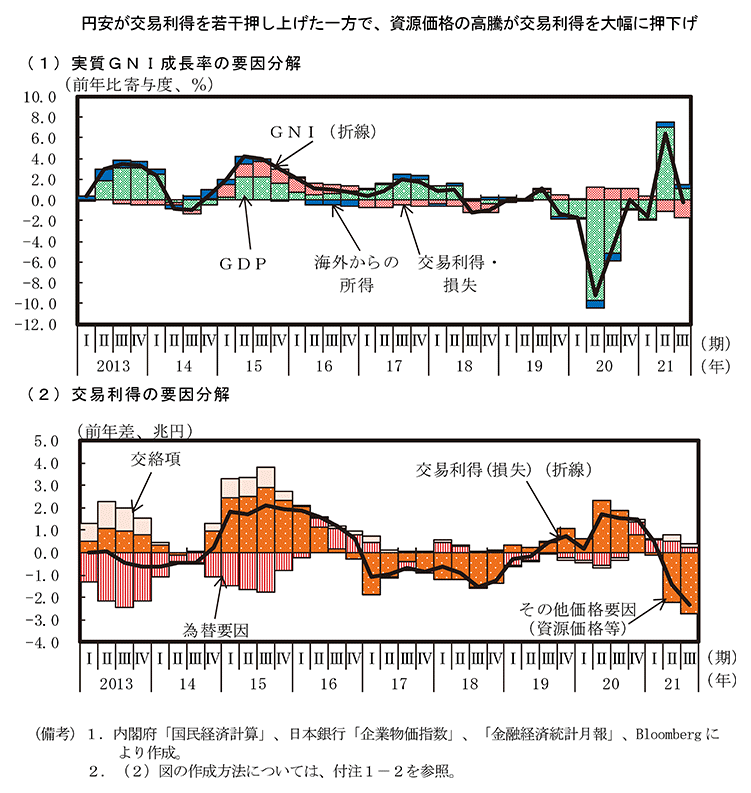
2 消費者物価の動向
(原材料価格高騰はコアを押し上げ、低所得者や寒冷地の負担増に)
原油・原材料価格の高騰を通じた企業価格の上昇は、最終財価格に転嫁されることで、消費者物価にも波及し得る。ここでは、最近の消費者物価動向を概観する。
消費者物価の動向について、生鮮食品を除く総合(以下「コア」という。)の前年比でみると、2020年後半から翌年初にかけて原油価格低下の影響もあってマイナスとなったが、2021年初以降は、ガソリン等のエネルギーがプラス寄与したことで上昇に転じ、2021年4月以降は前年比プラスで推移している(第1-4-4図(1))。特に、原油価格が一段と高水準となった2021年後半は、前年比1%弱程度で緩やかに上昇している。
家計のエネルギー価格の高騰は、低所得者に対してより大きな影響を与える。電気代をはじめとしたエネルギー関連品目は、生活に必要不可欠な必需品であり、消費の所得弾力性が低い。このため、世帯収入が低くなるにつれて、家計全体に占めるエネルギーの支出割合が高くなり、価格上昇による負担感も相対的に大きくなる。家計のエネルギー関連品目(電気代、ガス代、灯油代、ガソリン代)への消費支出額について、価格上昇による2021年11月時点の前年比負担増加額(年額換算)を年間収入分位別に試算すると、第1分位が21,190円である一方で、第5分位が29,461円となっており、高収入であるほど増額分の水準自体は大きい(第1-4-4図(2))。一方で、収入に占める割合は、所得水準が最も高い第5分位が0.2%程度であるのに対して、第1分位はその約3倍の0.8%と最も大きく、収入が低い分位ほど負担感が相対的に大きくなっている。
またエネルギー価格の高騰は、家計に占める暖房費の割合が高い地域を中心に負担増となる。地域別にコアの寄与度分解をみると、北海道、東北、北陸といった寒冷地では灯油代などの押上げ幅が他地域よりも大きい(第1-4-4図(3))。
このように消費者物価(コア)は、原油を含む資源価格上昇の影響を反映して緩やかに上昇しており、特に低所得者や寒冷地に対してより大きな影響を与えている。
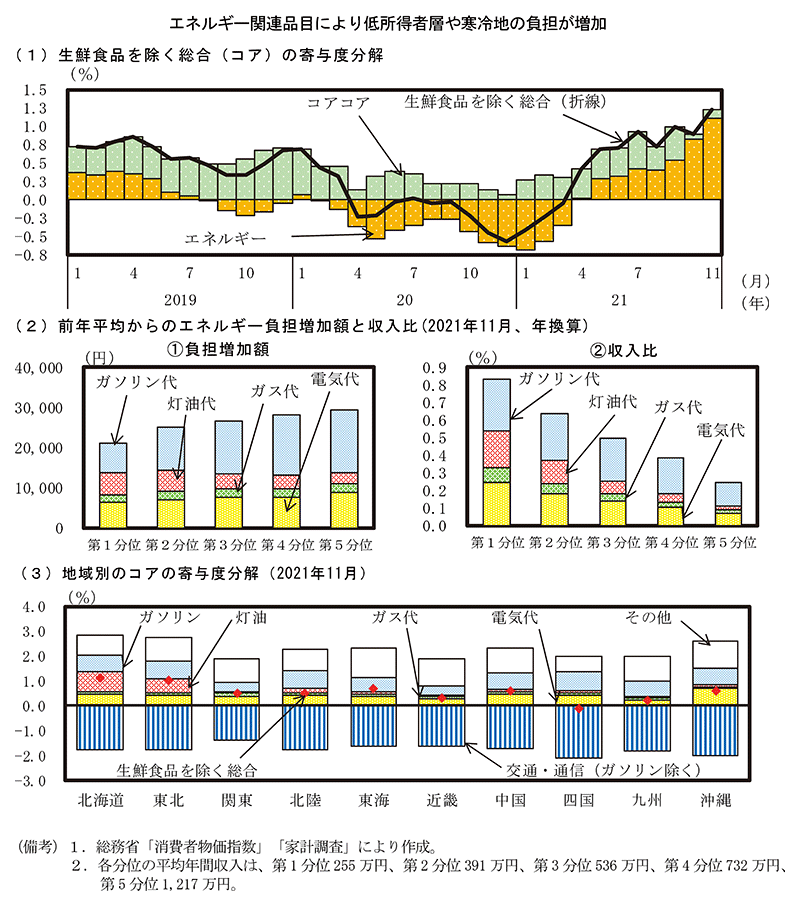
(食料品価格上昇に頻繁に直面する消費者の物価上昇期待を押し上げ)
エネルギー以外の品目にも目を向けると、2020年末以降、食料品全般の価格上昇が続いている。食料品価格高騰の背景としては、産地の天候不順など品目ごとの個別の要因に加えて、感染症からの急激な経済回復などによる海上運賃の高騰や中国の旺盛な需要などが挙げられる。例えば、北米の天候不順や中国の輸入量増加、海上運賃の上昇により輸入小麦の価格は高騰しており、各社も小麦粉等の値上げを行っている。
これら食料品の価格上昇も個人消費に影響を与える。そこでエネルギー関連品目と同様に、食料品の前年比負担増加額を試算すると、第5分位で年9,492円、収入比では第1分位で0.21%と、エネルギーに比べて相対的に小さい(第1-4-5図(1))。
ただし、食料品は購入頻度が高い品目が多く、消費者が生活の中でその価格変化に直面しやすい商品だけに、その価格上昇は消費者心理に大きな影響を与えると考えられる。消費者物価指数の品目を購入頻度別に区分けし、前月比で価格が上昇した品目数の1~11月各月の割合を平均すると、過去3年間の同時期と比較して、購入頻度が高い品目グループはその割合が大きくなっている(第1-4-5図(2))。これは購入頻度が高い品目グループほど、食料品の占める割合が高くなっているためである。特に「月2回以上」購入する品目グループは、その約9割が食料品で構成されているため、生活の中で食料品価格上昇に頻繁に直面する消費者の物価上昇期待を押し上げていると考えられる。
食料品への支出は総消費支出の約3割を占めており、このような食料品価格上昇の更なる広がりが消費者心理等に与える影響には注意が必要である。
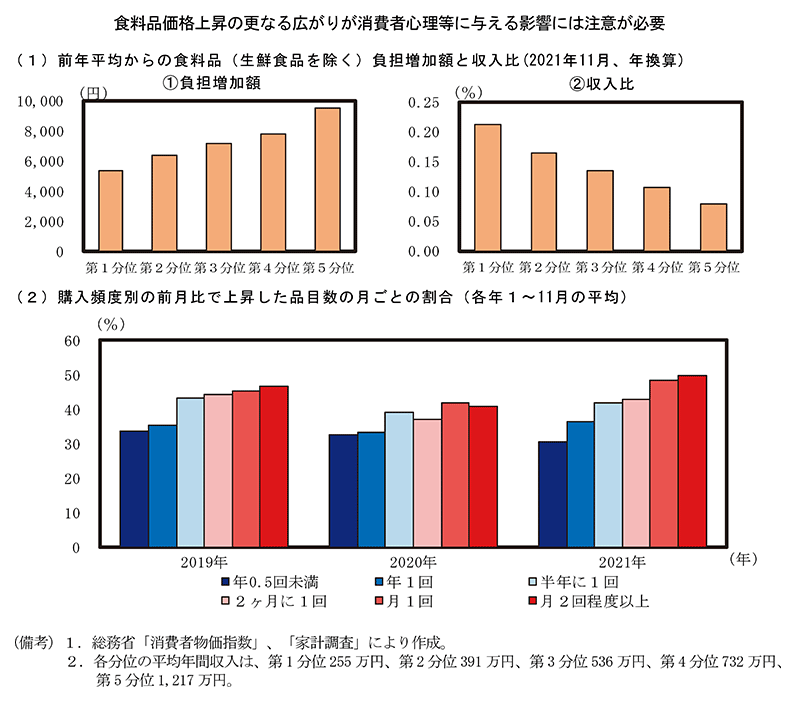
3 デフレ脱却に向けた進捗状況
(コアコアの安定上昇のためには、経済全体の需要の高まりや賃金の上昇が重要)
消費者物価指数(コア)は、エネルギー価格上昇を主因として緩やかに上昇しているが、こうした外部的な要因を除いた物価の基調として、生鮮食品及びエネルギーを除く総合(以下「コアコア」という。)の動向をみる。
2021年は、携帯電話の低料金プランの提供開始による影響で「交通・通信」がマイナス寄与となっている一方で、2020年の押下げ要因となっていた宿泊料等を含む「教養娯楽」や、電気代等の公共料金である「光熱・水道」がプラス寄与に転じたことで、底堅い動きとなった(第1-4-6図(1))。また、2021年半ば以降、前述の食料品価格もプラス寄与の幅が拡大しており、コアコアを押し上げている。
こうした物価動向の背景にあるマクロ経済的な要因をみるために、経済全体の需給動向を示すGDPギャップと、賃金面での物価上昇圧力を示すユニット・レーバー・コスト(以下「ULC」という。)の最近の動きを確認する(第1-4-6図(2))。まずGDPギャップは、感染症後の2020年4-6月は-10.4%と大幅に悪化し、その後、マイナス幅は縮小傾向にあるものの、2021年7-9月期時点でも-4.8%程度のギャップが残っている。またULCについては、2020年4-6月期にGDPが大幅に減少した影響で一時的に上昇したものの、その後は、GDPが横ばい圏内で推移する中で、名目雇用者報酬の緩やかな増加を反映し、底堅い動きとなっている。
アメリカと比較すると、GDPギャップは、アメリカが経済活動の再開に伴ってマイナス幅が急速に縮小し、プラスに転じる見込みとなっているのに対して、日本は2020年末以降、同程度のマイナス幅が続いている(付図1-9(1))。また賃金動向として、一人当たり名目賃金上昇率を比べると、日本は底堅い動きとなっているものの、アメリカと比べて低い伸びが続いている(付図1-9(2))。
こうした動向を踏まえ、GDPギャップとULCの動向がコアコアにどの程度影響を及ぼすかについて考えるため、2020年4-6月期以降の期間において、両者とコアコアの関係を比べると、正の相関関係は保たれているものの、1990年代と比べてその関係は弱まっているほか、GDPギャップがゼロとなる場合の基調的な消費者物価上昇率が大きく低下している。
消費者物価の安定的な上昇のためには、経済全体の需要の高まりや賃金の上昇に加え、基調的な物価上昇率も高めていくことが重要である。
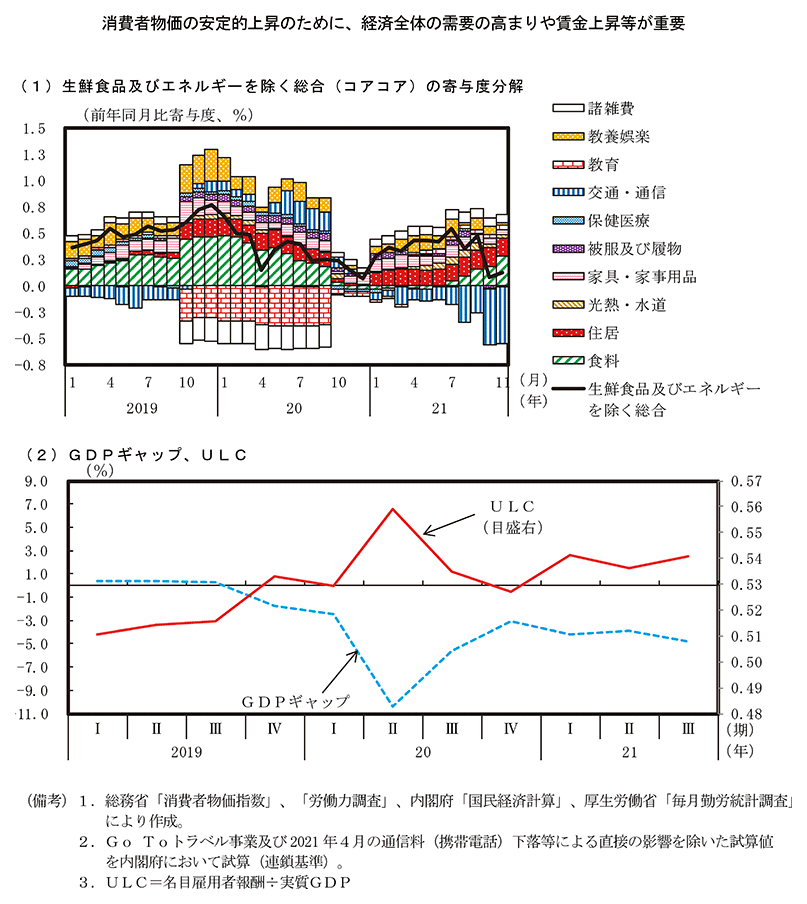
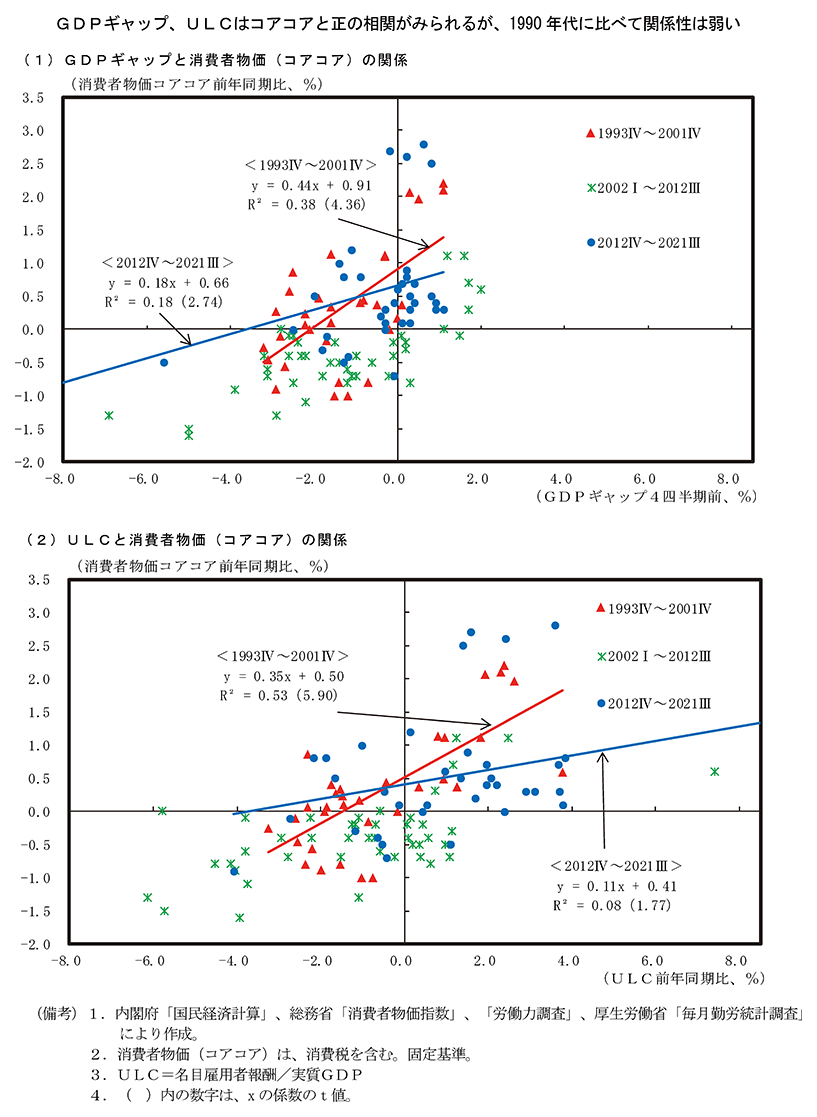
コラム1-4 サービス物価とサービス部門の賃金の関係
ULCと消費者物価の関係は正の相関が保たれているものの、コアコアの上昇率が加速しない背景には、賃金上昇率が緩やかであることも影響していると考えられる。特に、サービス物価は生産コストに占める人件費の割合が高く、財に比べて賃金の影響を受けやすいと考えられる(付図1-10)。
そこで、サービス業における時間当たり賃金と当該部門の産出物価であるCPIのサービス品目価格の関係をみる。アメリカやEUのサービス業では、賃金も物価もプラスの範囲で振幅している一方、我が国の場合はいずれもゼロを挟んで振幅している(コラム1-4図(1))。アメリカやユーロ圏に比べて、日本の賃金の伸びが小さいことが、サービス物価の伸びの低さにつながっている可能性がある。
次に、両者がどの程度連動しているかという点について、物価の賃金弾性値(5年移動平均)を求めると、我が国の一般労働者・パート労働者の賃金は、いずれもアメリカやEUに比べて連動性が小さい(コラム1-4図(2))。2013年以降、各種の賃上げに向けた取組を通じてサービス業の賃金上昇率も高まっているが、賃金弾性値はアメリカやユーロ圏に比べて低く、賃金から物価への上昇圧力が弱かったと考えられる。このため、経済全体の需要の高まりや力強い賃金の上昇に加え、適切に価格転嫁を行えるような環境を整備することで、賃金と物価がともに上昇していく好循環を実現することが重要と考えられる。