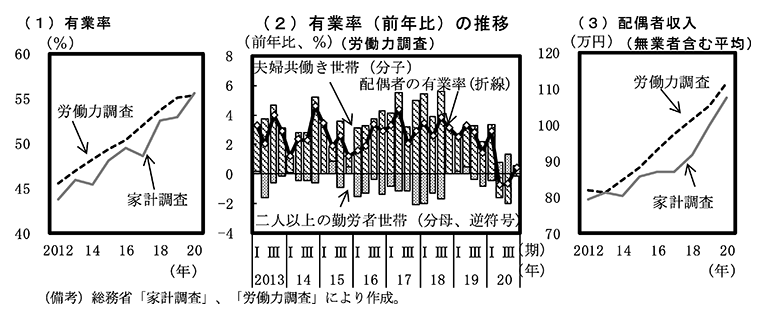第2章 感染症の影響による雇用と家計の変化(第2節)
第2節 賃金・所得への影響
前節では、感染症による雇用への影響を考察したが、本節では、雇用とともに国民生活に密接な賃金・所得への影響を分析する。また、近年、女性の就業の進展により、配偶者の有業率が上昇しており、家計所得への影響を分析する。
1 賃金への影響
(業種別では宿泊・飲食業を中心に、個人向けサービス業での落ち込みが大きい)
毎月の支給給与である現金給与総額については、2020年5月に前年同月比で大きく減少した後、経済活動の再開に伴ってマイナス幅を縮小しつつあったが、11月、12月は冬の賞与の減少が下押ししたことから、マイナス幅は拡大した(前掲1章第1-2-2図(5))。これを産業別にみると、労働時間の減少が大きい宿泊・飲食、生活関連サービス、運輸・郵便といった感染症の影響を大きく受けた業種において、4月から6月にかけて大きく減少した1。その後、10月まではマイナス幅は縮小傾向で推移したが、宿泊・飲食、生活関連サービス、運輸・郵便では回復が遅れ、12月は前年比で9~13%程度のマイナスとなっている。他方、医療・福祉、卸売・小売等の業種では相対的にマイナス幅が小さくなっている(第2-2-1図(1))。
就業形態別にみると、4月、5月は一般労働者に比べてパートタイム労働者の落ち込みが大きかった。休業者は非正規雇用者、宿泊・飲食サービス業で割合が大きいことから(前掲第2-1-8図)、パートタイム労働者比率の高い宿泊・飲食、生活関連サービスで営業自粛や営業時間の短縮に伴う出勤日数減や労働時間減少が影響している2(第2-2-1図(2))。ただし、パートタイム労働者の現金給与総額は、6月、7月には前年同月比でプラスへと転じ、12月もプラスとなっており、2020年4月から大企業に導入された同一労働同一賃金に対応した給与制度等の改定によって、平均賞与額が増加したことも反映しているものと考えられる。
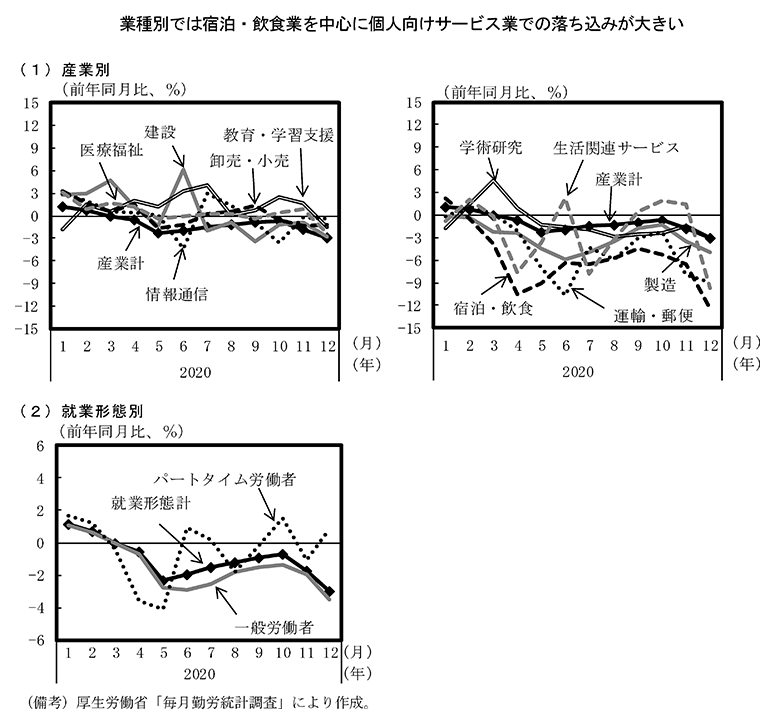
(低所得層が大きな影響を受けたが、対面サービス業を中心に中高所得層にも波及)
上記の現金給与総額は事業所単位の平均賃金であるが、就業者の側から見た収入を公益財団法人NIRA総合研究開発機構が2020年4月、6月及び12月に実施したアンケート調査から確認する。同アンケート調査では、1月から3月(4月調査)、3月から6月(6月調査)、6月から12月(12月調査)にかけての所得の増減を「大きく増加」、「増加」、「変化なし」、「減少」、「大きく減少」から回答することとなっており、これらに一定の点数を加え、回答者の構成比を乗じることでDI化した。DIが50を下回ると所得が減少していることを意味し、前期に比べてDIが下落していると、減少テンポが加速していることを意味する。
結果からは幾つかの含意を読み取ることができる。まず、所得階層別には、6月までは低所得者層ほどDIが低い傾向がみられた。ただし、3月から6月にかけては、年収階級で400万円以上の層のDIが相対的に低下している。他方、12月にかけて、低所得層のDIが相対的に改善し、全体としてDIの水準が平準化している。次に業種別には、飲食業・宿泊業のDIが極めて低く、12月に改善したものの、依然として他の業種より影響を強く受けていることがうかがえる。また、3月から6月にかけては、卸小売業の低下が目立つ結果となっている。感染症の影響が大きいと思われる業種を対面サービス業としてまとめてDI動向をみると、6月までは低所得層ほどDIが低い傾向にあったが、3月と6月の結果を比べると、年収400万円未満の層ではあまり変化がない一方、それ以上の層ではDIが低下している。また、12月にかけては、低所得層の改善に比べて、中高所得層の改善幅が小さくなっている。対面サービス業では、パート・アルバイトとして就業する者の割合が比較的高いが、調査結果を踏まえると、当初、大きな影響を受けたパート・アルバイト層に加えて、フルタイム・正規社員においても、時短や休業、賞与等の削減を通じて、感染症の影響が所得面に波及しているものと推察される(第2-2-2図(1)~(3))。
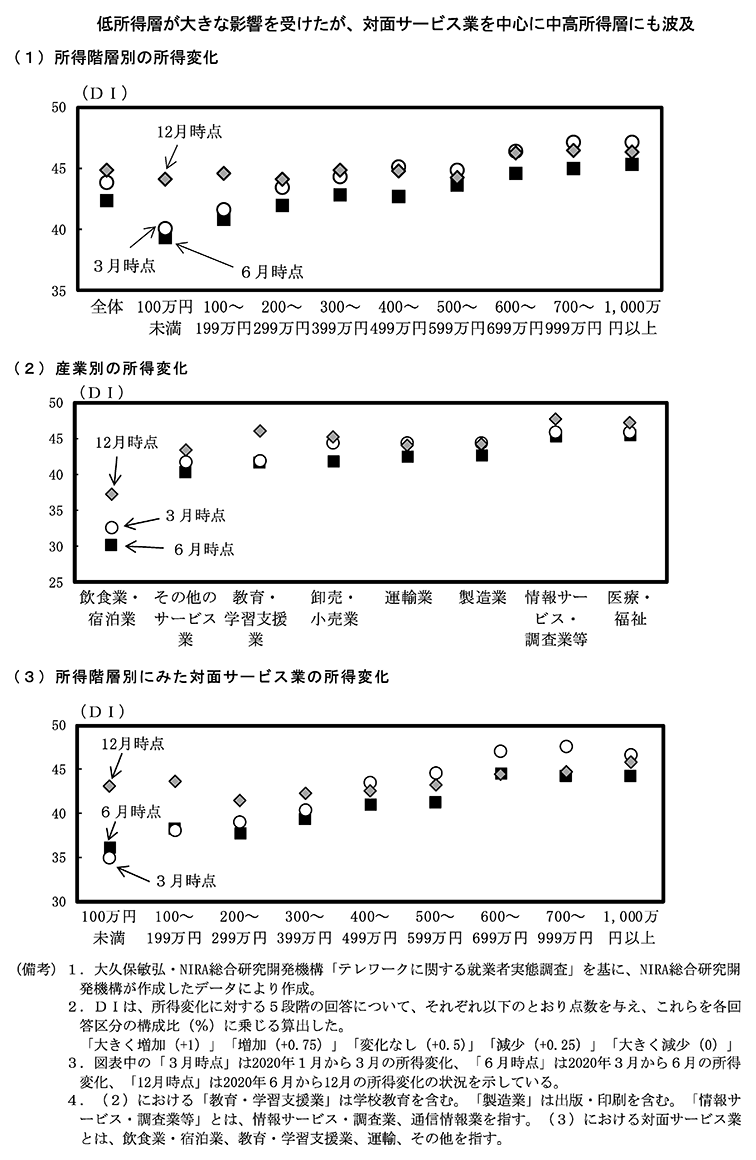
(夏の賞与の減少は小幅にとどまるも、冬は減少幅が拡大)
決まって支給される給与だけでなく、いわゆる賞与についても感染症の影響による減少がみられた。2020年の夏の賞与についても一定の影響を受け、毎月勤労統計調査の6~8月の特別給与は前年比2.6%の減少となった(第2-2-3図(1))。産業別にみると、感染症の影響を大きく受けた宿泊・飲食サービス業や生活関連サービス・娯楽業、運輸・郵便業では大きく減少した一方、建設業や教育・学習支援業では増加したこともあり、全体としては小幅な減少にとどまった(第2-2-3図(2))。
夏の賞与の減少が小幅にとどまった理由は、支給金額をその直前の春に決定する企業が多いことがあげられる。同様に、冬の支給金額はその直前の秋に決定する企業が多く、感染症の影響による企業業績の悪化は2020年の冬の賞与に本格的に反映される(第2-2-4図(1))。実際、リーマンショック時もショック発生直後の2008年冬の賞与は小幅な減少にとどまった一方、2009年夏の賞与は14.4%減と大きく減少した(第2-2-4図(2))。毎月勤労統計調査によると、2020年の冬の特別給与(11、12月合計)の前年比はマイナス5.6%と2020年夏に比べて減少幅が拡大する見込みであるが、リーマンショック直後の次期(2009年夏)に比べると減少幅は小さくなることが見込まれる(第2-2-4図(3))。
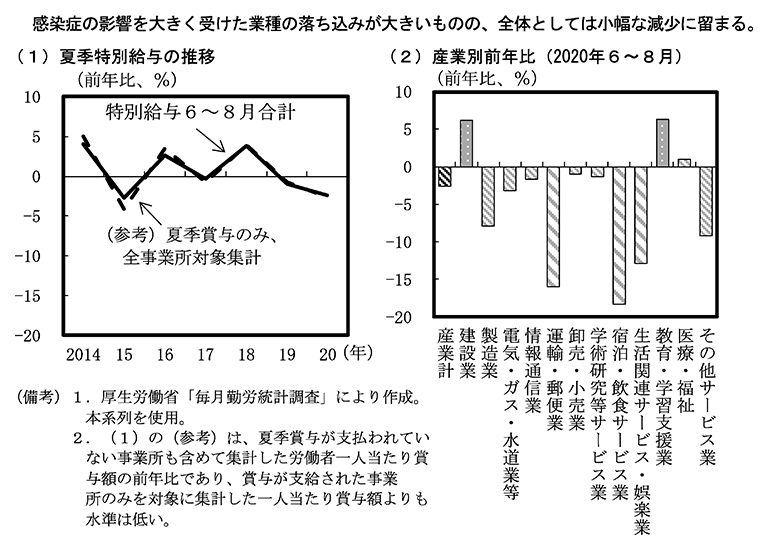
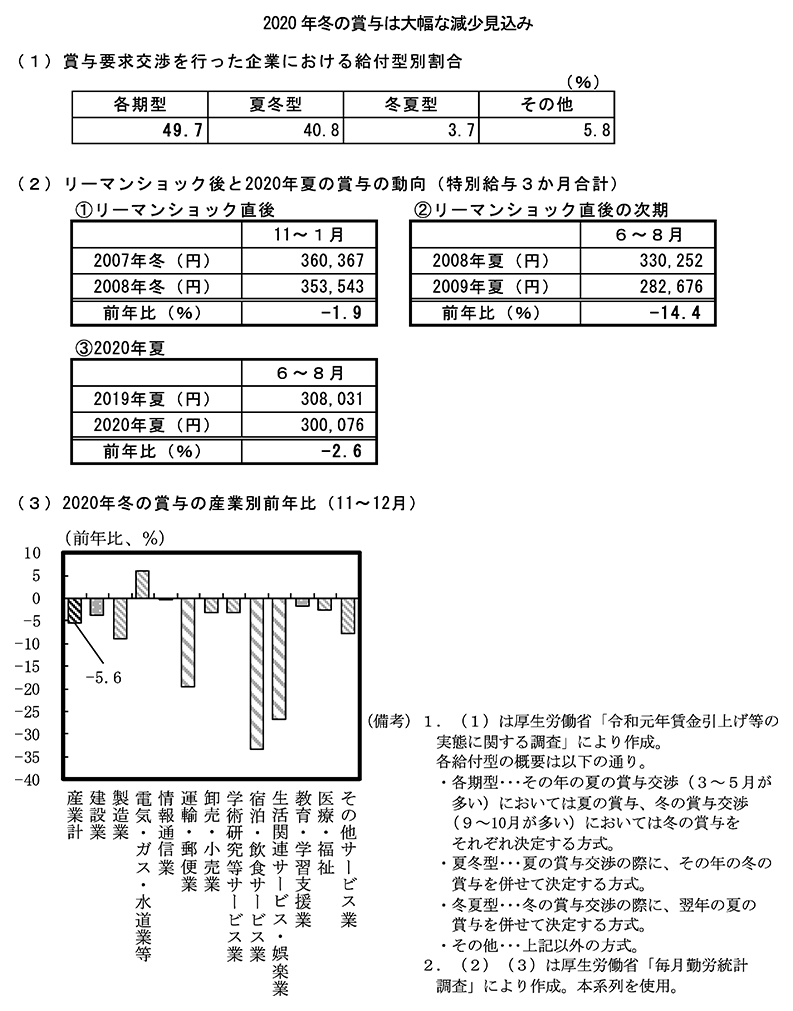
2 家計所得への影響
(世帯主収入が減少するなか、特別定額給付金、配偶者の収入増加が世帯収入を下支え)
総務省「家計調査」により、就業による収入に公的な給付措置等も含めた名目実収入の動向をみると、二人以上の勤労者世帯においては、2020年6月以降、世帯主の収入が減少寄与に転じる一方、世帯主の配偶者の収入が一貫して押上げ・下支えに寄与している。また、特別定額給付金3が含まれる特別収入が5~7月にかけて世帯収入の増加に大きく寄与した。(第2-2-5図(1))。また、単身世帯も含めた総世帯のうちの勤労者世帯や無職世帯においても4-6月期、7-9月期に特別収入が世帯収入の押上げに大きく寄与した(第2-2-5図(2)、(3))。なお、前節では、女性就業者の減少、特に配偶者の非労働力化が大きいことを指摘したが、この点と家計調査の配偶者収入の動きの関係については、第3項で考察する。
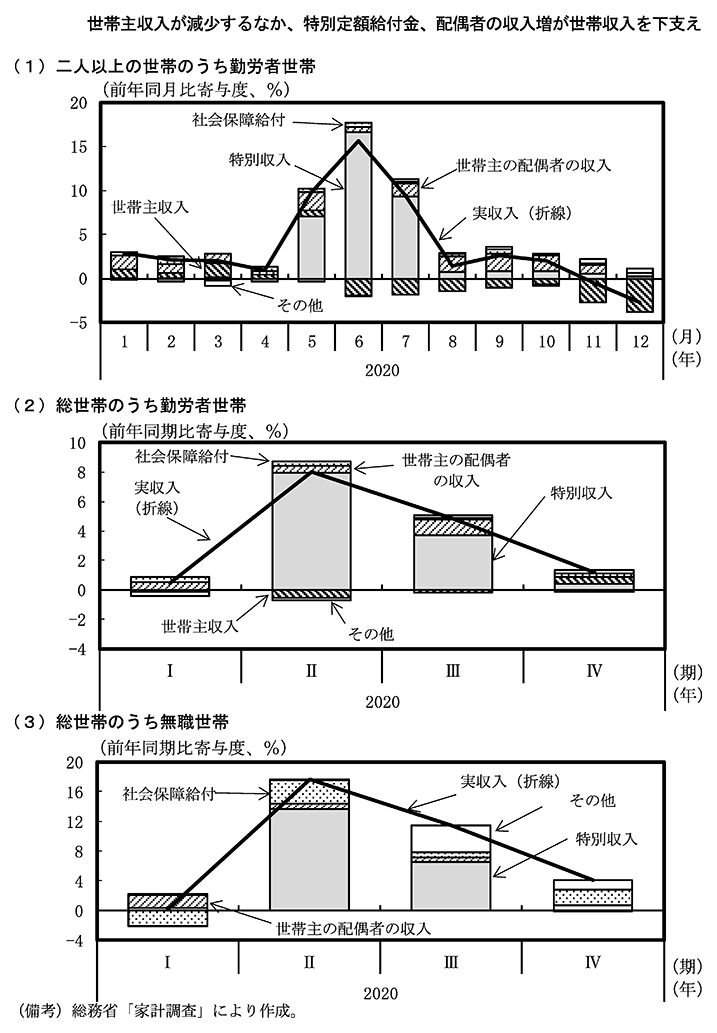
(特別定額給付金は所得の低い層の所得増に大きく寄与)
2020年の名目実収入は前年比4.0%増となっているが、所得階層別にみると、所得の最も低い層(第I層)では同9.2%増、第II層で同5.6%増、第III層で同3.7%増、第IV層で同1.8%増、そして最も所得の高い層(第V層)で同3.6%増となっている。世帯主の収入も世帯主の配偶者の収入についても、第I層、第II層ではプラスの寄与となっており、また、一人当たり定額が給付された特別収入(特別定額給付金)の寄与度は、低所得層ほど大きくなっている。特に、給付が集中した5~7月は、特別収入の寄与度が際立っており、感染症の影響により経済活動が抑制される中、低所得層を中心に生活の安心確保につながったものと考えられる(第2-2-6図(1)、(2))。
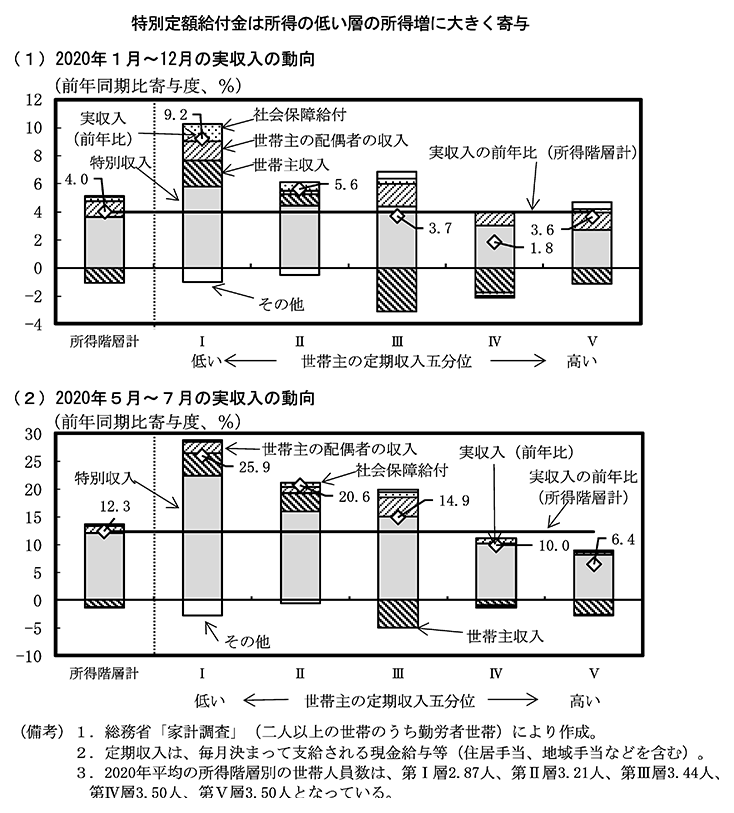
(感染拡大後においても配偶者の収入は世帯収入の押上げ要因)
配偶者の収入の寄与を確認するため、特別定額給付金の影響が含まれない世帯の勤め先収入の動向をみると、2018年以降、配偶者の収入は世帯主の収入を上回る伸びを示す傾向にあり、世帯の勤め先収入の押上げ・下支えに寄与している。感染症の影響により世帯主の収入が減少に転じた2020年6月以降においても、配偶者の収入はプラスに寄与し、8月~10月は、世帯主収入の減少を上回る寄与を示した(第2-2-7図)。
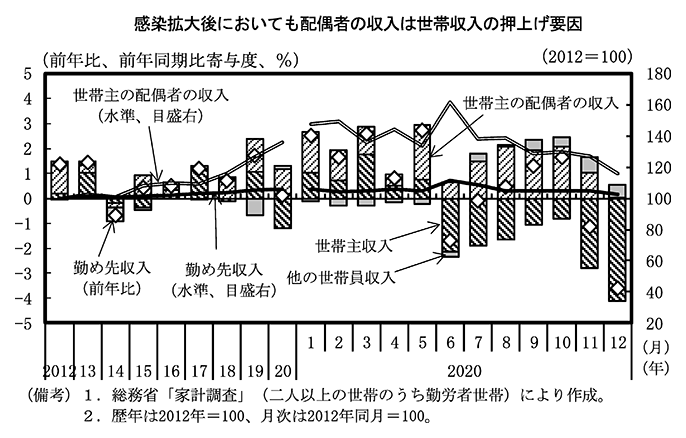
3 女性の就業と所得
(配偶者の中でも、パート・アルバイトが大幅に減少する一方で、正規雇用は増加)
これまで総務省の「家計調査」を用いながら、配偶者収入が世帯所得を押し上げていると指摘してきたが、前節で用いた総務省「労働力調査」では、続柄上は配偶者である就業者数は、前年より減少していることが示されていた。一見矛盾する現象の背後では、どういった変化が生じているのだろうか。
具体的には、配偶者の続柄にある女性の就業者数は、2020年4-6月期は前年差28万人減と1-3月期の前年差である22万人増から大幅に減少し、7-9月期、10-12月期においても減少幅はほぼ横ばいとなっている4。年齢別にみると、55~64歳の前年差が1-3月期の9万人増から、4-6月期は8万人減と大幅に減少し、45~54歳、35~44歳も大幅に減少している(第2-2-8図(1))。
他方、雇用形態別に雇用者数の動向をみると、パート・アルバイトが4-6月期に前年差46万人減と1-3月期の1万人減から減少幅が大幅に拡大し、その後、減少幅は縮小傾向にあるものの、10-12月期には前年差34万人減となっている。一方、正規雇用は増加幅が減少したものの、4-6月期は前年差21万人増と1-3月期に続いて増加し、その後も増加が続いている(第2-2-8図(2))。さらに、産業別に就業者数の動向をみると、生活関連サービス業・娯楽業、宿泊業・飲食サービス業、卸売業・小売業で前年同期差の減少幅が1-3月期から拡大したほか、製造業、情報通信業では前年同期差は1-3月期の増加から4-6月期には減少に転じた(第2-2-8図(3))。
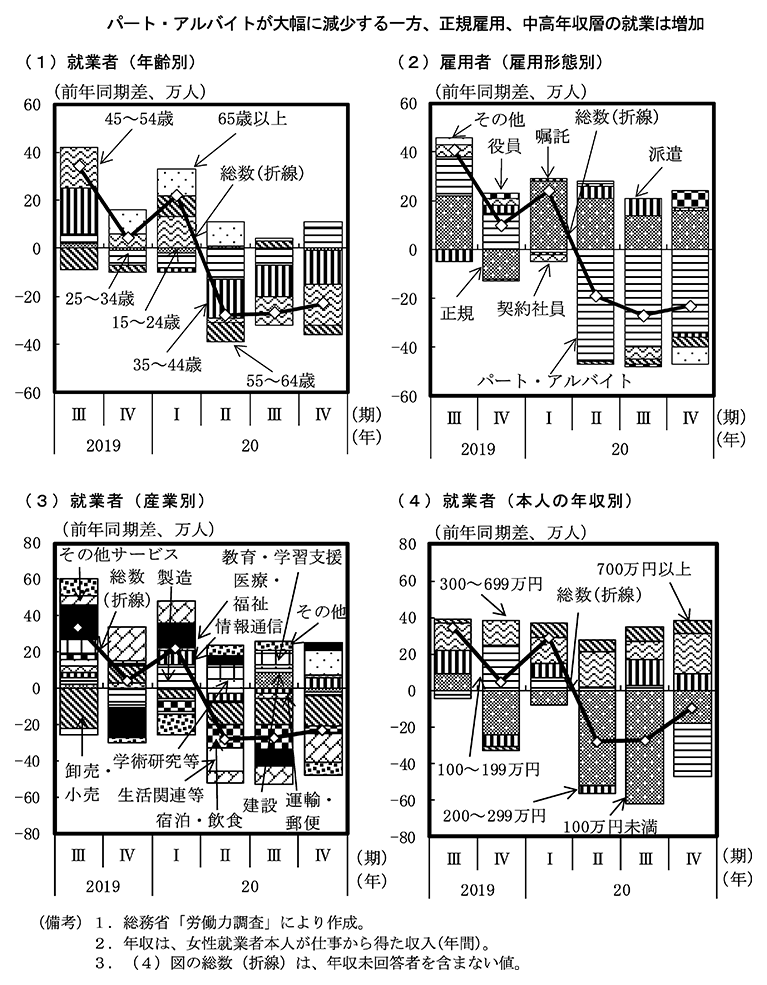
(配偶者の中でも、副次的な稼得者の就業が減少する一方、中高収入層の就業は増加)
年収別の動向を就業者数でみると、100万円未満の層が2020年4-6月期に前年差52万人減と1-3月期の小幅減から大幅に減少した。他方、300万円~699万円の層は4-6月期に前年差19万人増と1-3月期の前年差から増加幅が拡大し、その後も前年差で10~20万人程度の増加となっている。また、700万円以上の層についても、1-3月期以降、前年差8万人程度の増加が続いている(前掲第2-2-8図(4))。
このように、配偶者の続柄にある女性の中でも、感染症の影響により就業者数、雇用者数が大きく減少したのは、接触機会が多いと考えられる対個人向けサービス業である飲食・宿泊業や卸売・小売業等に従事し、年収が比較的低いパート・アルバイトとして働く副次的な所得稼得者層であることがうかがえる。一方で、中高年収入層の正規雇用者として働く配偶者は増加傾向が続いている。このため、配偶者の就業者数、雇用者数全体としては前年同期差で減少したものの、正規雇用や中高年収層の増加の効果が上回り、全体として平均的な世帯所得の下支え、増加に寄与しているものと考えられる。
(配偶者の収入増は有業率の上昇と平均収入の増加)
配偶者の収入の動向を総務省「家計調査」でみると、二人以上勤労者世帯の配偶者収入(女性)は、2012年には月額平均で65,313円であったが、43.2%であった配偶者の有業率が2020年に54.7%と約12%ポイント上昇したこともあり、2020年には月額平均87,666円と34.2%増加している。月額平均の増加を有業率の上昇による効果と有業者一人当たり平均収入の増加による効果に分解すると、34.2%の増加のうち27.4%が有業率の上昇によってもたらされており、金額換算すると17,884円となった。また、有業者一人当たり平均収入の増加は6.8%の寄与(月額4,469円)となる。8年の動きを期間に分けてみると、2012年から2016年にかけて有業率の上昇寄与が全てを占めており、平均収入の増加はむしろマイナスとなっている。他方、2016年から2020年は、引き続き有業率の上昇がプラスに寄与するのに加え、平均収入もプラスに寄与している(第2-2-9図)。その理由の1つとしては、前掲第2-2-8図(4)で示したとおり、正規化等の動きを背景に、比較的収入の高い雇用者数が増加しているのではないかと推察される5。
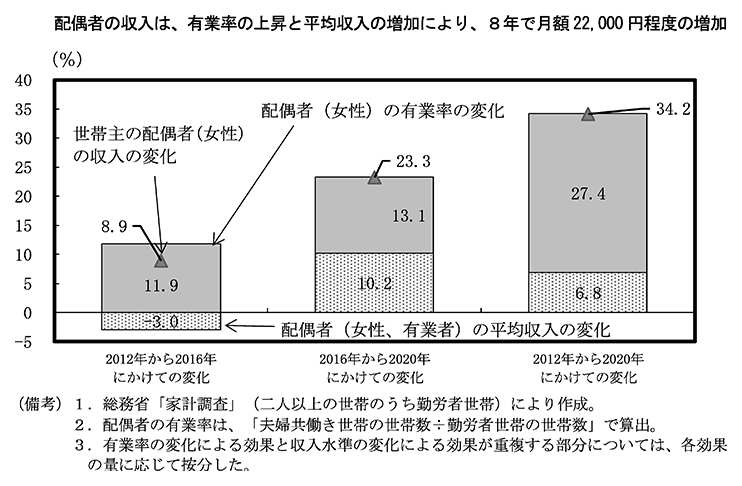
コラム2-2 有業率、配偶者収入についての家計調査と労働力調査の比較
家計調査の二人以上勤労者世帯の有業率は、女性の配偶者の就業者数が大きく減少した2020年においても前年から2.5%ポイント上昇し、54.7%となった。詳細に分析するため、労働力調査(基本集計)のデータを活用して、家計調査同様に有業率を算出した。なお、労働力調査では、世帯主に男女の区別がないため、女性が世帯主のケースも含まれる。このため、以下の比較にあたっては、家計調査も配偶者を女性に限定しない有業率を用いている。
二人以上勤労者世帯の配偶者有業率をみると、家計調査、労働力調査いずれも上昇傾向にある。他方、労働力調査の有業率は滑らかな上昇が続いているのに対して、家計調査の有業率は、2014年、17年に前年差マイナスとなるなど振れがみられる(コラム図2-2(1))。この背景には、サンプル数、単位区(調査区)の抽出方法、単位区(調査区)や調査世帯(住戸)の入替方法など統計作成方法の相違が影響しているとみられる。
労働力調査を基に有業率の変化を夫婦共働き世帯数の変化(分子)、二人以上勤労者世帯数の変化(分母、逆符号)に要因分解すると、2020年4-6月期、7-9月期は、分母の二人以上勤労者世帯数も減少したが、共働き世帯数がより大幅に減少したことから有業率は前年比マイナスとなった。ただし、10-12月期の有業率は、共働き世帯数の減少幅が縮小したこともあり、前年比プラスに戻った。この結果、2020年の有業率は前年比でプラスとなっている(コラム図2-2(2))。また、配偶者収入(無業者を含む平均)の動きを比較すると、家計調査では振れがみられるものの、均してみると労働力調査同様に上昇傾向にある(コラム図2-2(3))。
有業率や配偶者収入の動きを分析する際には、統計作成方法の相違も踏まえ、家計調査、労働力調査双方の動きをみていく必要がある。