第2章 人口減少時代における働き方を巡る課題(第2節)
第2節 働き方の変化と就業機会
前節では、労働時間の変化をみてきたが、過去30年間を振り返ってみると、現在のような労働需給の引き締まった時期ばかりではなかった。我が国においても、1990年代以降、いわゆるバブルが崩壊した後には「失われた10年」とも称される経済活動の低迷期があり、同時期には大学や高校の新卒就職率も低下した(いわゆる就職氷河期)。本節では、景気変動が特定世代の雇用に与える影響について考察し、若年人口が減少する中での新卒採用の今後や離職・転職を通じた長期的に安定した雇用機会の創出等について、特に雇い方との関係から検討していく。
1 景気変動と就業機会:「就職氷河期世代」の背景
(世界的に経済危機の後は失業率が大きく上昇し、それが長期間続く傾向)
雇用は生産活動の派生需要であるため、国や時期によって多少の違いはあれども景気変動の影響を受ける。ここでは、大きな経済危機後には、雇用者数の回復に時間を要することを示したPlotnikov(2014)を参考に、経済危機後における若年失業率の回復パターンをみると、15~24歳の失業率は、経済危機を伴う大きな景気変動が発生した後には長期間に渡って高止まりする現象がみられる(第2-2-1図)。
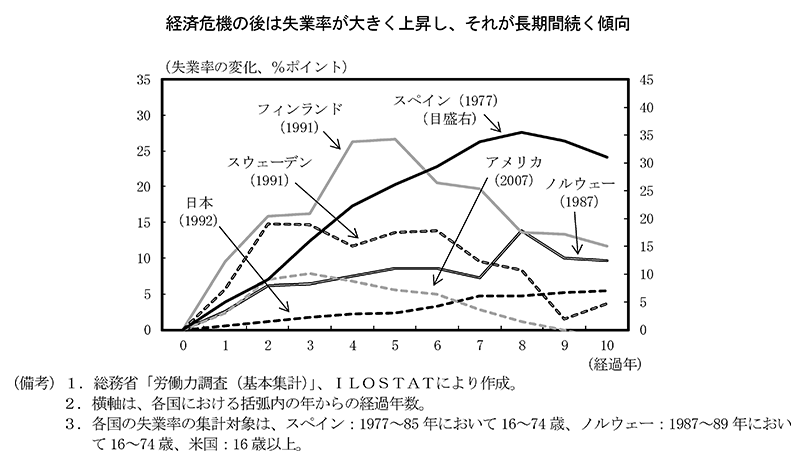
例えば、アメリカ(世界金融危機、2007年~)、日本(バブル崩壊、1992年~)及び北欧諸国(フィンランド及びスウェーデン、1991年~)の経済危機後における15~24歳の失業率をみると、危機前の水準に戻るのに10年程度要している。その他の景気循環時における若年失業率が戻るために要する時間は、我が国の場合は平均6年程度(第8循環の山(1977年)、第9循環の山(1980年)及び第10循環の山(1985年)から計測した回復期間の平均)、アメリカの場合は平均5年程度(1981年、1990年及び2001年のから計測した回復期間の平均)となり、日米ともに大きな景気変動後には、若年失業率の改善に時間を要している。
(就職氷河期世代の大学新卒就職率は平年よりも10%ポイント以上低下)
我が国において、1990年代の成長鈍化による影響を受けた世代(1974~83年生まれ、2018年時点で35歳以上45歳未満)は、いわゆる就職氷河期世代と呼ばれている。新卒就業率(新卒者から進学者を除いたうち、その年に就業した者の割合)を確認すると、大学(学部)卒業者の場合、就職氷河期の就職率が69.7%(その期間を除く1985年~2019年の平均は80.1%)と平年よりも10%ポイント以上の低下、高等学校卒業者も、平均就職率は70.9%と平年の78.1%よりも7%ポイント程度の低下となっている(第2-2-2図)。
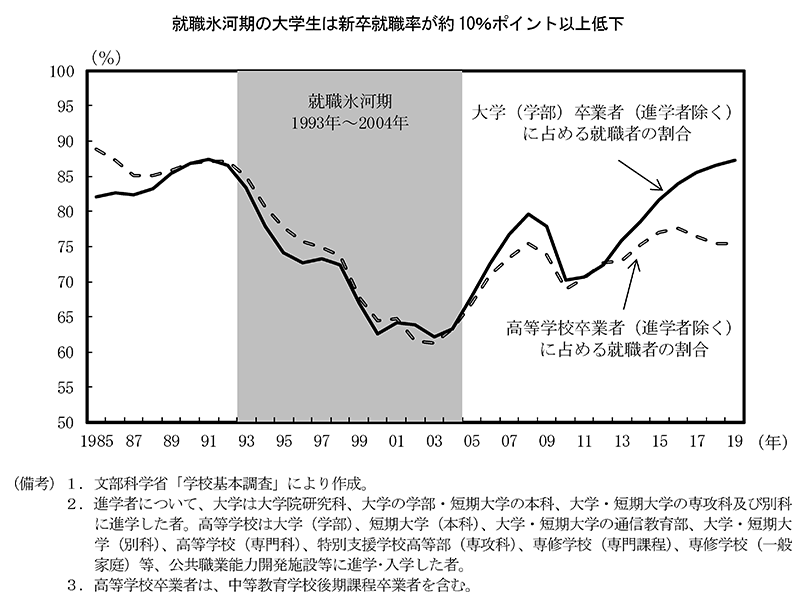
(就職氷河期世代の男性は、30歳台時の正規雇用比率も低め)
この世代(1974~83年)と他の世代(1954~63年、64~73年、84~93年)の違いについて、各世代が20~29歳であった時点で比較すると、就職氷河期世代の就業率は、男女計ではその前の世代と同水準か、若干高めではあるものの、男女別に大きな違いがある。男性の就業率はそれ以前の2世代に比べて6~8%弱低く、20歳台後半に上昇を示して30歳台の差は0.5~4%程度となり、その後はおおむね同じ水準となっている。他方、女性の就業率は社会参加促進や婚姻等を起因とする退職の減少も背景に、20歳台においては2世代前よりも6%程度高く、30歳前後は10%程度高めで推移し、低下はみられない(第2-2-3図(1))。
また、正規雇用比率は、男性ではそれ以前の世代に比べて30歳前後において10%程度低く、40歳前後になって前世代に並ぶような動きとなっているが、2世代前からは7%弱低い。女性では、20歳台の正規雇用比率は過去の2世代に比べて低いものの、過去の世代にみられていた30歳台における極端な非正規化による低下はないという特徴がある。いわゆる企業の新卒採用枠が縮小したことにより正規就業の機会に恵まれず、新卒時点での動向がその後に影響している様子がうかがえる(第2-2-3図(2))。
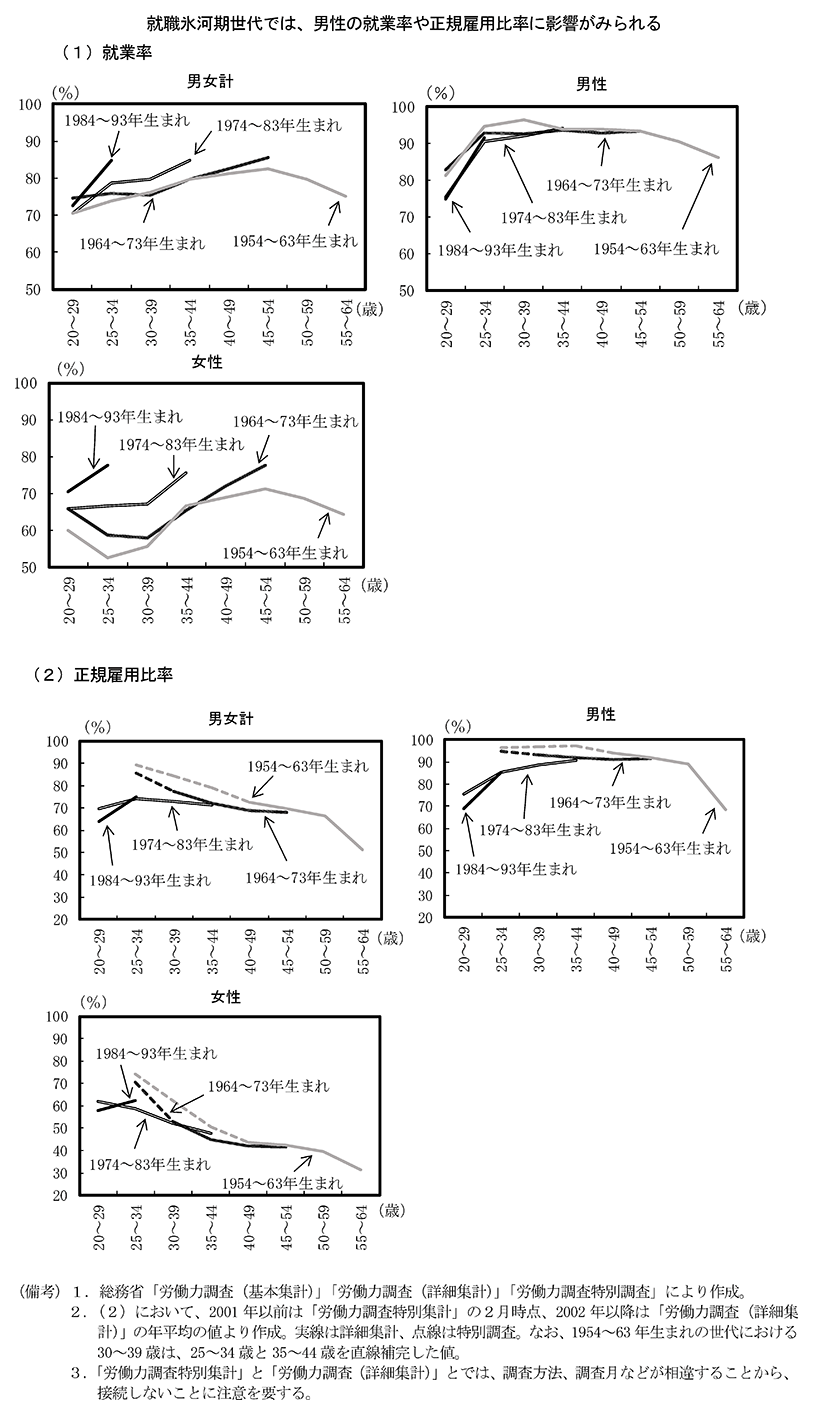
コラム2-2 就職氷河期世代への支援に係る取組について
就職氷河期世代は、雇用環境が厳しい時期に就職活動を行った世代であり、不本意に不安定な仕事に就いている等、様々な課題に直面している方々がいる。この世代の就労を支援するため、政府としては、2019年6月21日に「就職氷河期世代支援プログラム」を策定し、以下に紹介する施策を実施する予定としている1。なお、これらの取組は、同年12月に閣議決定された「安心と成長の未来を拓く総合経済対策」2に盛り込まれ、令和元年度補正予算案及び令和2年度予算案にも計上されるとともに、同月に取りまとめられた「就職氷河期世代支援に関する行動計画2019」3において施策ごとに成果目標等が定められ、今後の進捗状況を確認していくこととされている。
○安定的な就労を目指した支援
- 短期間で取得でき安定就労に有効な資格等の取得支援等、受けやすく即効性のあるリカレント教育の確立
- 民間事業者のノウハウを活かした不安定就労者の就職支援の実施等
○就職への切れ目のない支援
- ハローワークへの専門窓口設置等、きめ細かな伴走支援型の就職相談体制の確立
- 就職氷河期世代の失業者等を正社員で雇い入れた企業への助成金の拡充等、採用企業側の受入機会の増加につながる環境整備
○個々の状況に合わせた寄り添い支援
- 本人や家族への情報のアウトリーチの更なる強化等、アウトリーチの展開
- ひきこもり地域支援センターと自立相談支援機関の連携強化等、支援の輪の拡大
2 人口減少局面における雇い方・雇われ方
前項では、世界における幾つかの危機を取り上げ、失業率の長期的な高止まりと改善テンポの緩さが生じたことをみた上で、我が国における就職氷河期世代の新卒採用時期においても、同様のことが生じていたことを確認した。新卒採用の機会を失うことは、その後の雇用にも影響を与えているが、ここでは、人口減少という別の構造変化が生じている下において、新卒採用の変化と雇い方の動きをみていく。
(新卒採用枠は景気に対する変動が大きい)
我が国の企業は、景気変動に伴う雇用調整において、既存雇用者に対する大胆な雇用調整には判例上の制約もあることから、本来は長期的な事業計画に基づいて安定的になることが求められる新卒採用枠も雇用調整の手段として相当程度活用してきた。この点を検証するため、入職者数を転職と新卒に分けて景気(景気動向指数(CI一致指数)で代理)との関係を描くと、採用数の増減は景気と連動している(第2-2-4図(1))。
次に、転職数と新卒数の変化がどの程度景気に感応的かを確認すると、新卒数は転職数の2倍以上景気に感応的であることが分かる(第2-2-4図(2))。具体的には、転職数の場合、経済活動が1%低下すると0.33%程度減少し、新卒数の場合であれば、経済活動が1%低下すると、0.74%程度低下する。なお、国家公務員の採用数の変化についても、同様の方法で景気から受ける影響を確認すると、民間の新卒者変動とおおむね同程度となっている(第2-2-4図(3))。国や地方自治体においても、民間企業と同様に、景気に同調的な採用数の変動があり、結局、年代別の就業機会がばらつく原因となっている。
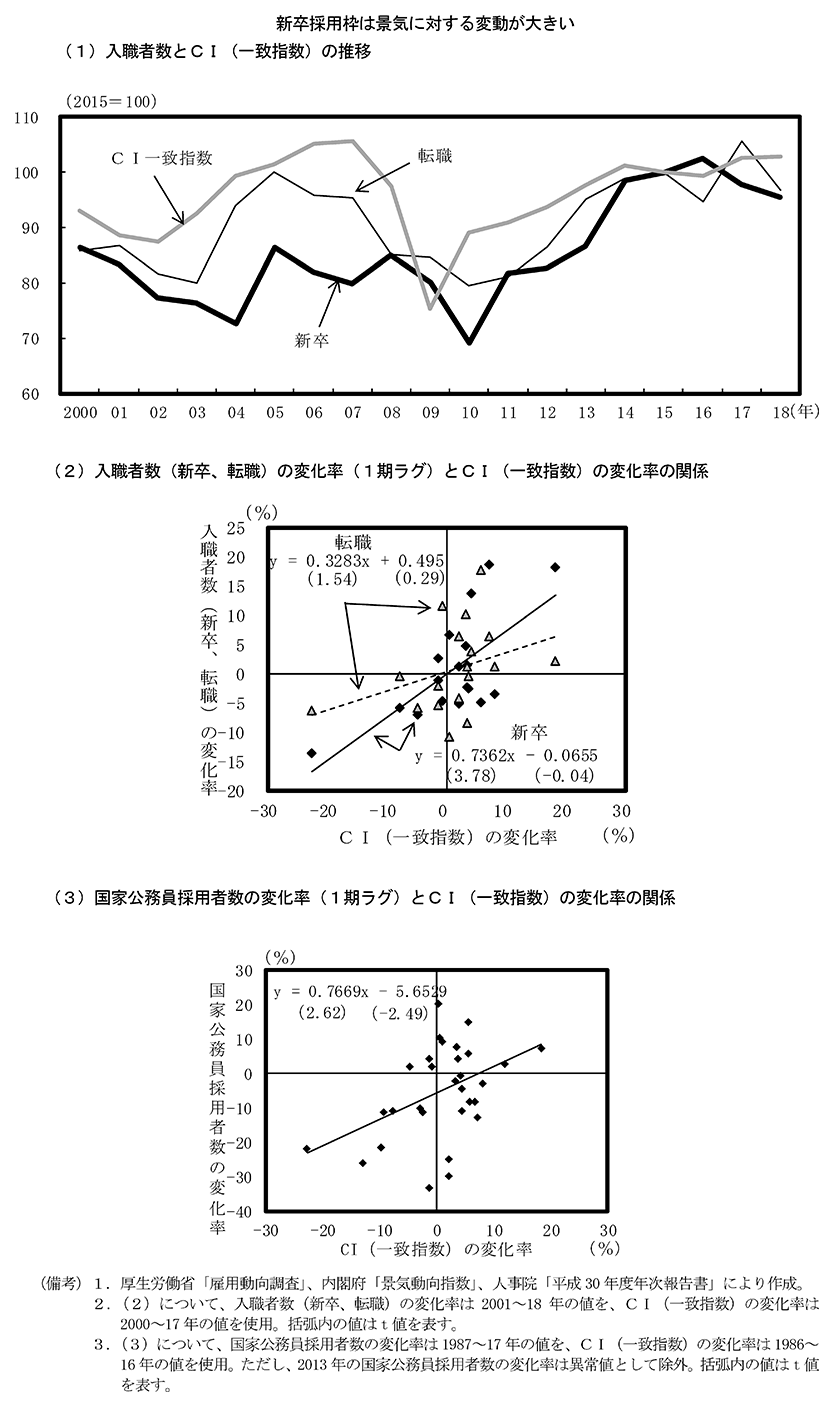
(若年層の減少に伴い、新卒採用が困難となる企業も増加)
新卒採用数が景気に感応的である一方、若年人口の減少という構造変化は続いている。新卒人口は引き続き減少していくことが見込まれ、現状120万人弱の新卒市場への労働供給は、20年後には95万人、30年後には80万人程度へと減少する(第2-2-5図(1))。企業側の新卒採用に関する充足状況等の調査結果をみると、若干あるいはかなり少ないと回答する企業の割合は年々上昇している(第2-2-5図(2))。
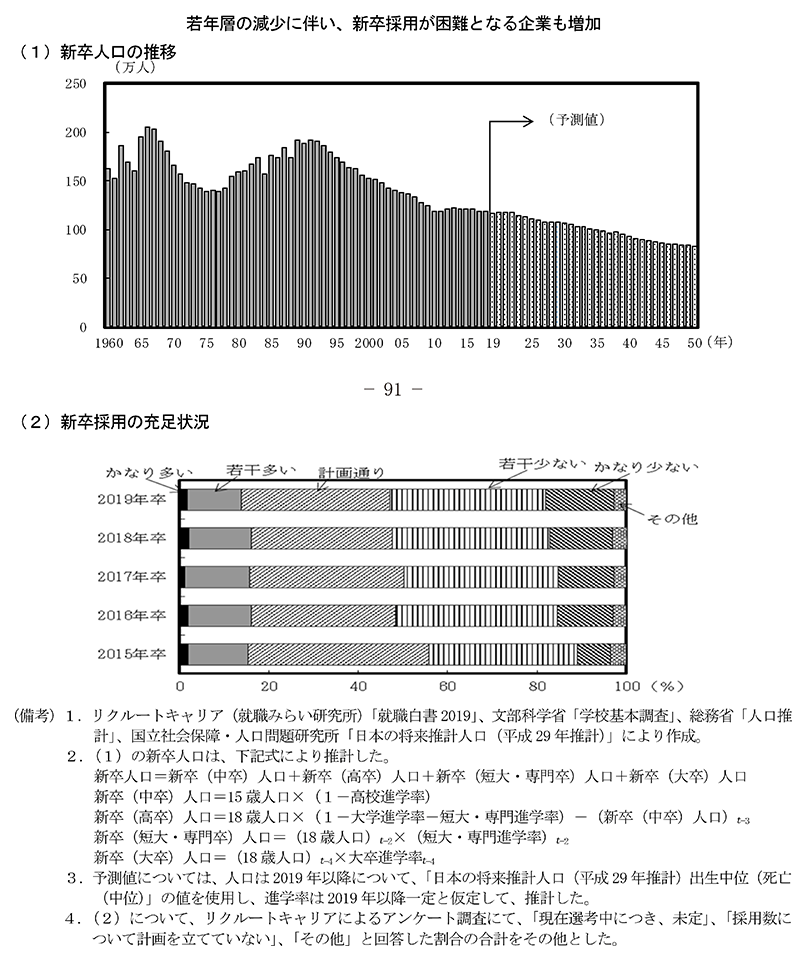
(新規入職者のうち、転職組は7割程度で未就業からの入職組は3割程度)
新卒採用に厳しさを感じる企業は、中途採用へとシフトしているのだろうか。新たに入職する者には、他の就職先から転職する者、未就業段階から就職する者がいる。また、未就業段階から就職する者には、新卒者と既卒者がいる。こうした分類による調査結果によると、転職入職者割合(年初の常用労働者のうちの一般労働者数に占める各種入職者数の割合)は景気による増減がみられ、このところ、緩やかな上昇傾向がみられる。未就業入職者の割合は、人口は減少している中で就職率の改善がみられる新卒入職者はおおむね横ばいとなっているものの、既卒入職者はこのところ減少傾向が続いている(第2-2-6図)。
なお、こうした転職入職者の転職前後における賃金変化について、同一雇用形態間での転職に伴う変化をみると、2018年の結果は2013年の結果に比べて「増加」と答える者の割合が増えているが、一般労働者の場合は増減が拮抗しており、パートタイム労働者の場合は増加超過となっている(第2-2-7図(1))。
また、異なる雇用形態間を含めた全体の転職に伴う賃金変化については、当該転職者の年齢が大きく影響しており、年齢階級別に賃金の増減割合を確認すると、若年層では賃金が「増加」したと答える者の割合が総じて高いものの、50歳以降になると、「減少」と答える者の割合が増加する傾向がみられる(第2-2-7図(2))。
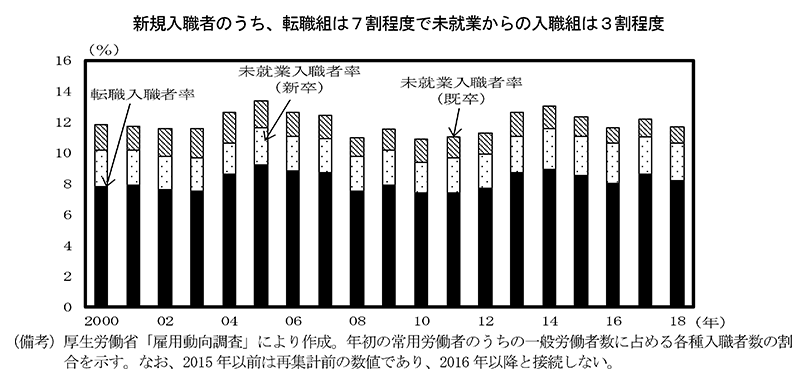
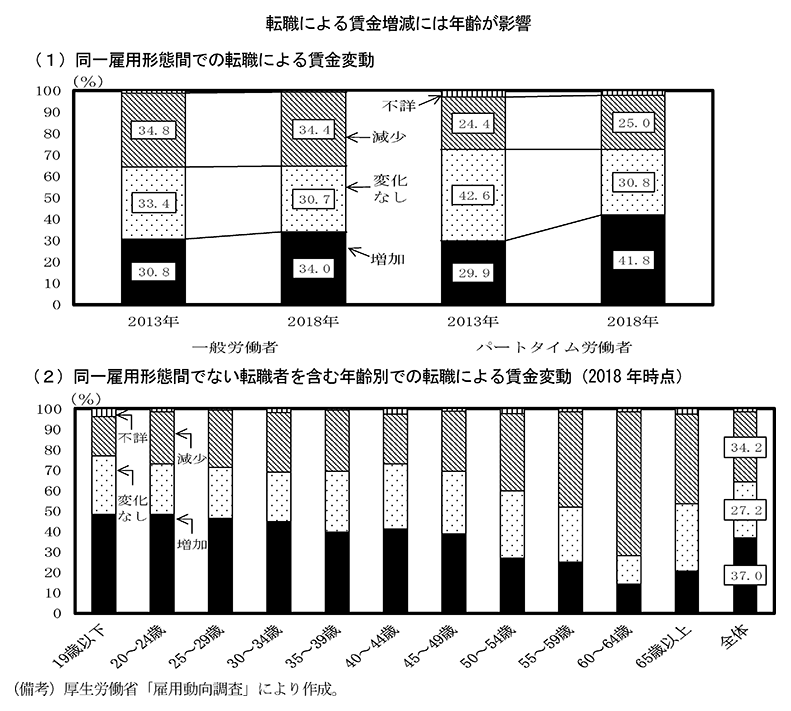
(企業が中途採用を行う理由には新卒不足や若年不足もあるが、主要因は専門性)
次に、中途採用を行う企業側のスタンスを調べた調査によると、採用理由として、新卒採用による内部での人材育成だけでは事業の必要を満たせないという回答割合が3割を超えており、また、求める人物像として若年層という回答も3割程度となっている(第2-2-8図(1)、(2))。ただし、中途採用を行う最大の理由は、専門性の高さや経験、人物像としても一定程度の知識・スキルがある即戦力を求めることが中心となっている。また、中途採用にあたり、企業として整えるべき必要な環境としては、賃金制度の透明化やキャリアパスの明確化が最上位となっている(第2-2-8図(3))。
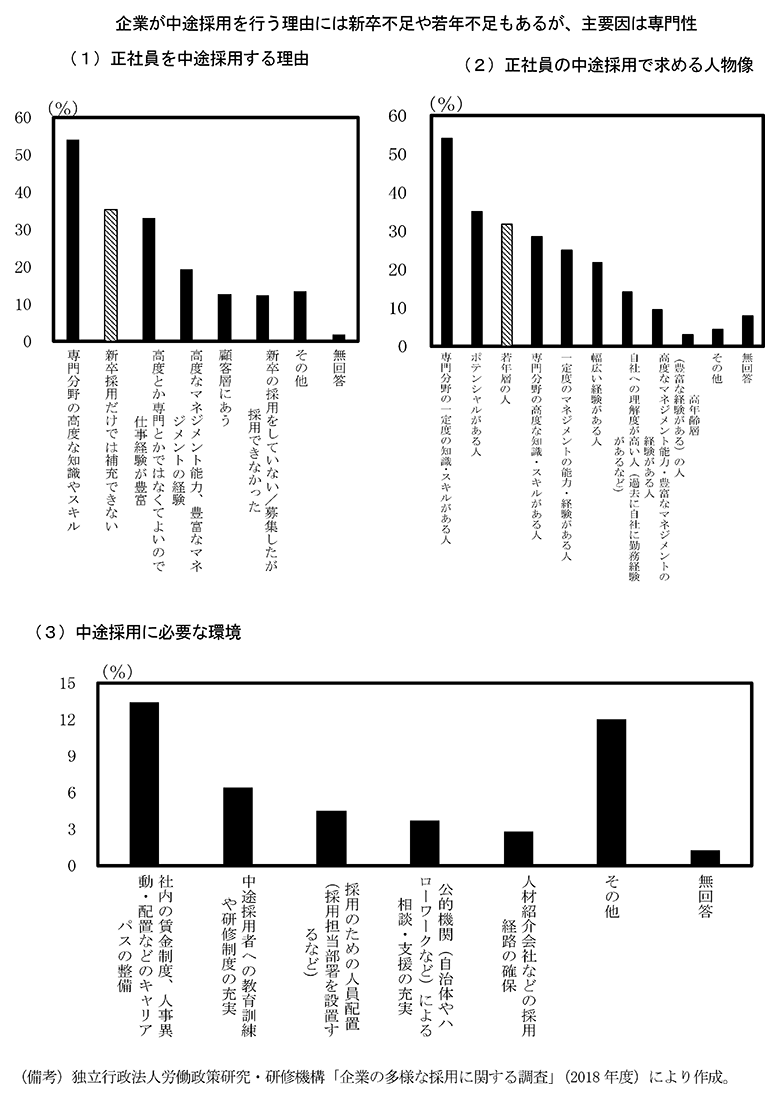
3 長期に渡る安定的な就業機会の確保
前項では、企業は中途採用を増やしたいと考えている面も垣間見えたが、動きは全体として緩やかであり、雇用管理の方向性に大きな変化が生じているとは思われない。他方、人口構造が変化し、若年数が相対的に少なくなる中において、新たな技術や商品に対応できる供給体制を変化させていくためには、新規需要に対応して労働力が適切に新たな企業や産業へ移動できる仕組みも必要となる。ここでは、長期に渡って安定的な就業機会を生み出すために必要な変化を検討する。
(企業の平均操業年数に対し、就労期間は長い)
人生100年時代において、長期に渡る安定的な就業機会を確保することは重要だが、倒産した企業の平均操業年数は24年程度であり、業歴30年以上の老舗企業も倒産件数の3割程度を占めている。また、2010~18年の平均廃業率から計算した事業の継続確率を踏まえると、40年を超えて操業する企業は全体の2割程度である(第2-2-9図)。したがって、20歳台で新規採用された者の40年以上の就労機会は、必ずしも一企業で提供されるとは限らない。
他方、雇用者の働き方としては、短時間労働者を除いた一般労働者のうち、雇用期間の定めなく働いている雇用者が86%前後である(第2-2-10図(1))。また、平均勤続年数は緩やかながらも伸びており、一般労働者は12年超、短時間労働者でも6年程度となっている(第2-1-10図(2))。また、別の調査によると、雇用者のうち、退職(転職)を経験したことのない者は正規雇用の45%程度となっている(第2-2-11図)。
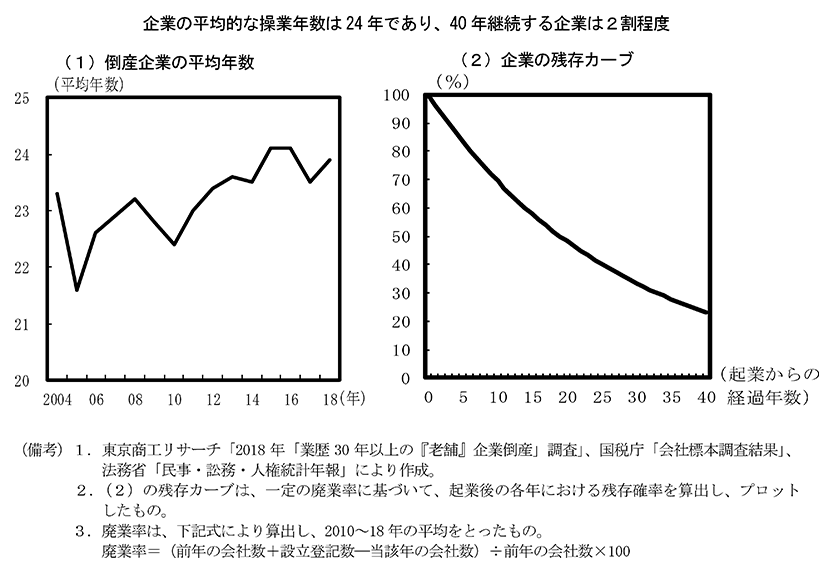
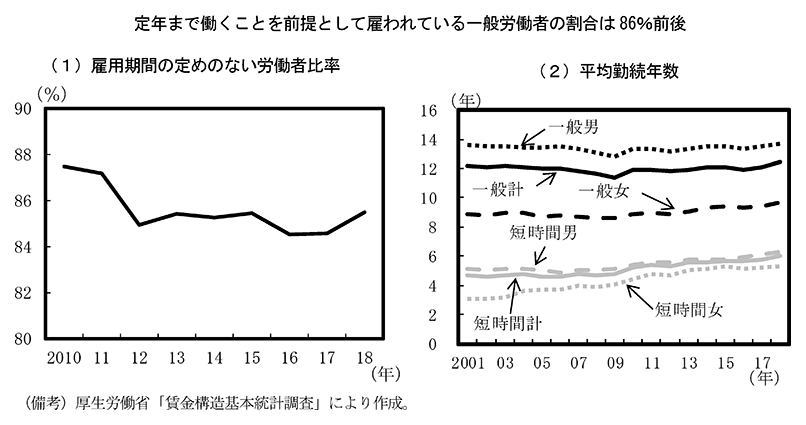
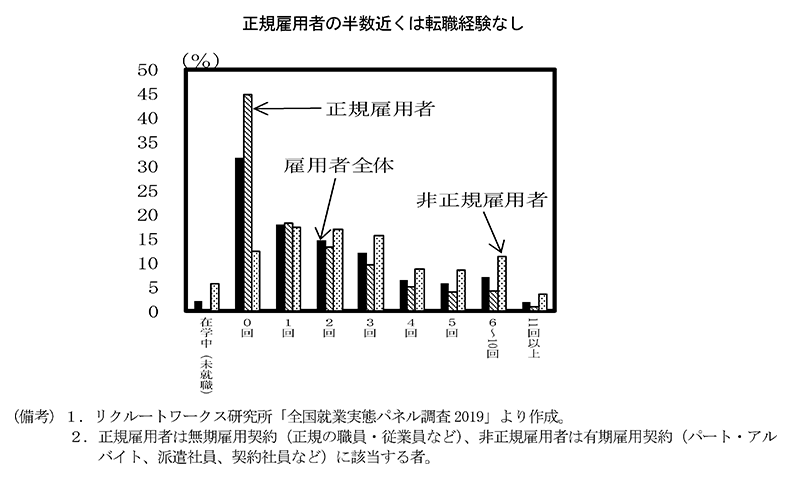
今後とも、定年制の廃止や定年年齢の延長、あるいは再雇用制度の導入等を通じ、就業期間の長期化が進んでいくと見込まれるが、新たな技術や商品への対応といった供給体制の変化に呼応するためだけでなく、働き手側の事情に鑑みても、離職・転職を通じた長期的に安定的な雇用機会の確保がより重要になっている。
(離職・転職しやすい退職金制度が必要)
雇用期間の定めのない雇用者にとって、転職の意思決定を阻害する要因は多々あると考えられる。長らく勤めた企業に関する固有のスキルは、社内では有効な資産だが、社外では付加価値を生み出せるかどうかわからない。転職件数が増え、十分な情報の蓄積を通じた評価基準の分かりやすい仕組みがあれば、自己の客観的な評価を通じて転職への意思決定も進むかもしれない。他方、こうした外的な環境制約以外にも、退職金制度による継続就業へのインセンティブ付与、あるいは転職へのディスインセンティブ付与、が挙げられる。2017年の調査結果によると、退職金の給付額は勤続年数に比例しつつも、10年~20年程度での離職転職を阻害するような傾きを有している(第2-2-12図)。こうした傾向は、10年前の退職金支給プロファイルと比べると、20年超の金額が低下することで若干緩和している傾向も見受けられるが、いまだ転職への阻害要因となっていると考えられる。勤務年数に中立、またはポータブルな退職金が望まれる。なお、退職金に関する所得税法上の控除額についても、こうした傾向がある4。
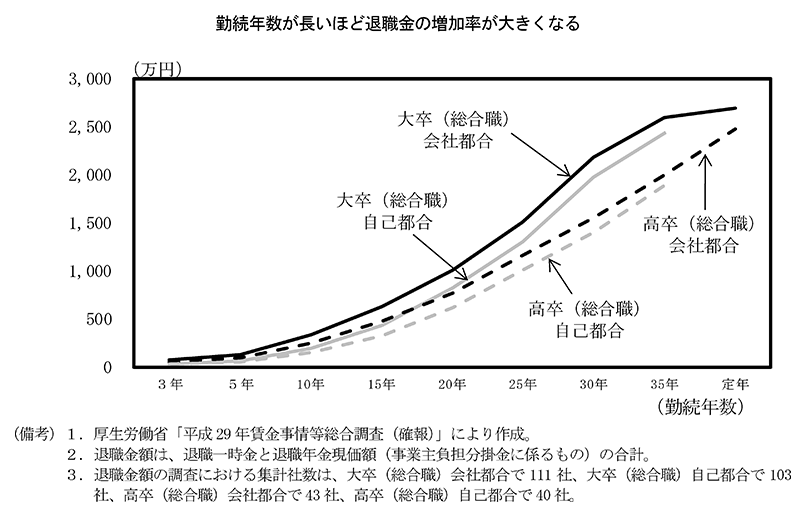
(個人の自己啓発投資を促すことも必要)
雇用期間が長期化する中では、離職・転職を含めた雇用機会の確保が重要と指摘したが、雇用が流動的になれば、従業員への教育投資を通じた人的資本の蓄積に対して、企業は消極的になるかもしれない。そこで、従業員教育の長期的な推移を確認すると、総労働費用に占める教育費の割合は、1980年代後半には0.35%前後の水準にあったものの、その後は景気循環による振れを伴いつつ、最近では0.25%前後となっており、低下傾向にある(第2-2-13図)。ただし、これには従業員が高齢化する影響も含まれているため、高齢化効果を補正すると、おおむね横ばいで推移しているように思われる。実際、雇用流動化はそこまで進んでいないことから、企業の若年雇用者に対する教育姿勢は大きく変化していないと見込まれる。併せて、従業員個人による自己教育投資の動きについても確認すると、年齢階層別の自己啓発投資の平均時間や平均投資額は、20歳台や30歳台は50歳台よりも自己啓発投資に時間をかけており、加齢に伴い自己啓発投資の時間は短くなる傾向がある。また、2012年から2017年の限られた期間ではあるが、全体として短時間化の傾向もみられる(第2-2-14図(1))。さらに、正社員と非正社員別に自己啓発の時間や費用を比較すると、正社員の方が時間と費用をかけている傾向もみられる(第2-2-14図(2))。
こうした企業と個人の教育投資の状況を踏まえると、離職・転職市場の拡大に合わせ、企業が従業員への教育投資を減少させる前に個人の教育投資を社会的にサポートすることが、過少投資に陥るリスクを避けるためには必要だと思われる。また、加齢に伴う自己啓発投資の減少は、投資の回収期間が短縮化していく中でやむを得ない面がある一方、技術の変化等の動きは早く、各種スキルの陳腐化は進みやすい。雇用期間の長期化を踏まえ、若年だけでなく、中高年に対する働きかけも必要である。
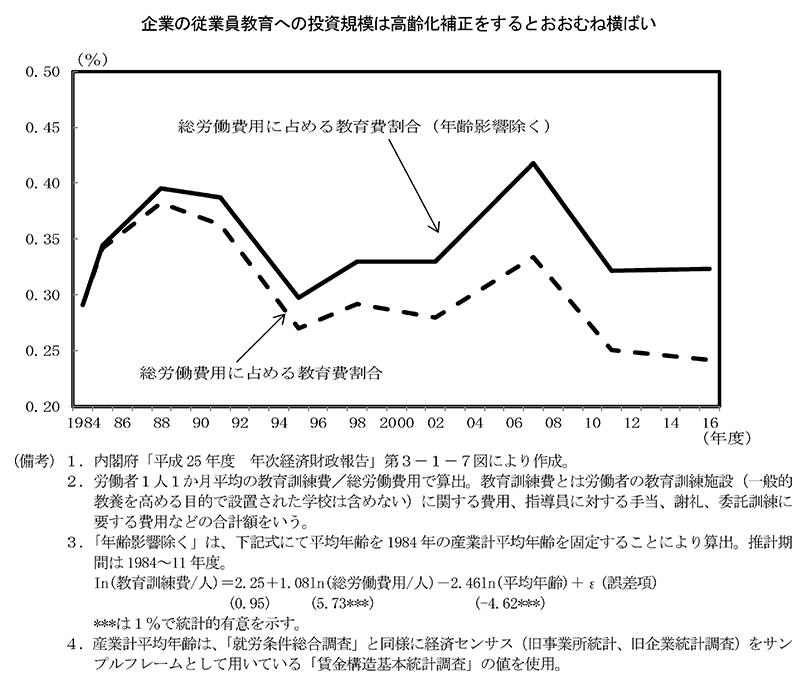
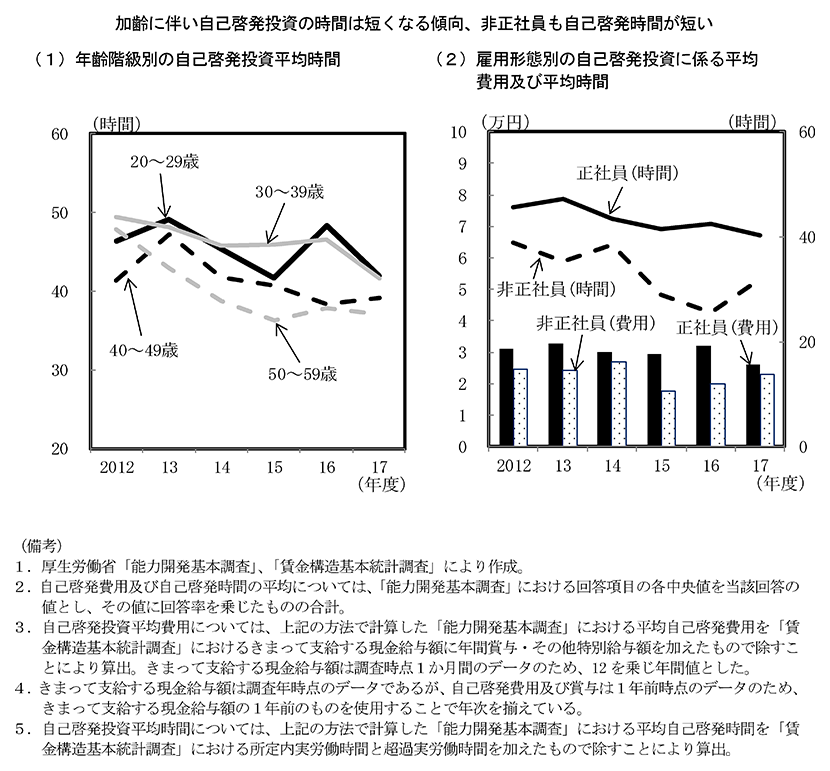
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/shushoku_hyogaki_shien/program.html
https://www5.cao.go.jp/keizai1/keizaitaisaku/keizaitaisaku.html
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/shushoku_hyogaki_shien/keikau2019/index.html
・n≦20の場合 40×n 万円
・n>20の場合 800+70×(n-20) 万円

