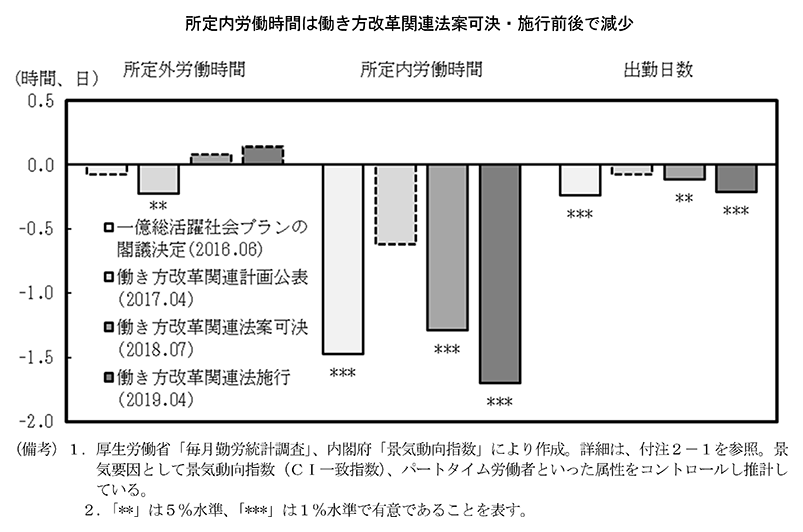第2章 人口減少時代における働き方を巡る課題(第1節)
第1節 働き方の変化と働き方改革
本節では我が国における働き方の趨勢的な変化に触れるとともに、国際比較を通じて我が国の現状を把握し、我が国固有の状況とその背景について考察を行う。具体的には、労働時間や労働参加の動きを概観し、働き方改革の取組について整理を行いつつ、その効果について、労働時間への影響、長時間労働者の変化の二つについて評価を行う。
1 労働時間の推移
(一人当たり労働時間はパートタイム労働者の増加により減少傾向)
働き方を考える上で労働時間の長さは重要である。現状、一人当たり労働時間は長期的に減少傾向にあるが、労働時間は雇用契約によってその長さが異なり、一般的に、パートタイム労働者の労働時間は短いことから、パートタイム労働者の増加が一人当たり労働時間の減少に寄与する1。そこで、一人当たり労働時間の変化について、フルタイムの一般労働者とパートタイム労働者の労働時間、そしてパートタイム労働者比率の三つの動きに分解すると、一般労働者の労働時間はおおむね横ばいか若干の減少、パートタイム労働者の労働時間は短時間化の傾向、そして、パートタイム労働者比率は継続的に上昇していることが分かる(第2-1-1図(1)、(2))。
これら三つの要素のうち、一般労働者の労働時間を所定内労働時間と所定外労働時間に分離し、4つの要素の寄与分解をすると、過去25年間での累積的な月間労働時間の減少(-17.2時間)は、パートタイム労働者比率の上昇が-10.5時間、パートタイム労働者の時間変化が-3.6時間、一般労働者の所定内労働時間と所定外労働時間の変化がそれぞれ-5.8時間と+2.2時間の寄与となっている(第2-1-1図(3))。
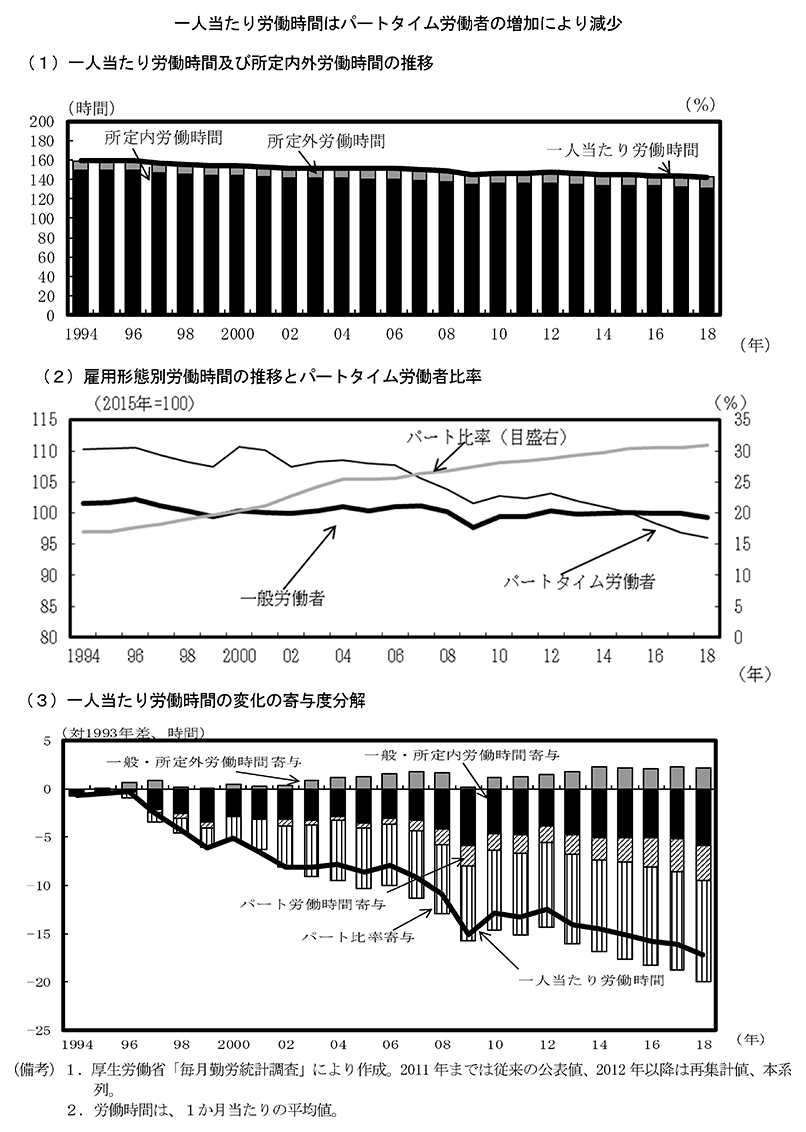
(週当たり60時間以上働く長時間労働者の割合も減少)
次に労働時間の分布について、最近の動向を確認する。2018年における労働時間階級別雇用者数の分布をみると、週当たり35~42時間、月に換算すると140時間~168時間働く雇用者の割合が多い。労働時間の分布は年によって多少変動するものの、2012~18年の間では、週当たり15~34時間働く短時間労働者の割合は増加し、週当たり60時間以上働く長時間労働者の割合は減少している(第2-1-2図(1))。また、就業者ベースの比較になるが、30時間未満と49時間以上の労働時間に該当する人数の推移を比較すると、前者の人数は増加、後者の人数は増加する傾向が顕著である(第2-1-2図(2)。
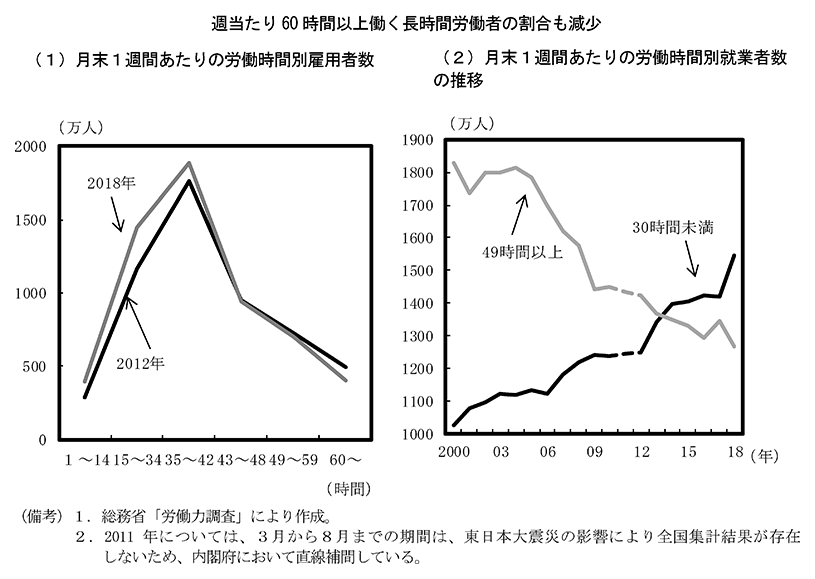
なお、本節3項で取り上げるが、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」、いわゆる働き方改革関連法の施行により、2019年4月1日から大企業における月45時間、年360時間以上の時間外労働が規制され、中小企業においても2020年4月1日より同様の規制が適用される。この場合、所定内労働時間が1日当たり8時間、月に20日働けば160時間になるが、同規制では、年360時間(月30時間)、月45時間の時間外労働が上限になることから、それに対応する月の労働時間はそれぞれ190時間、205時間となる。これを週平均にすると、47.5~51時間となり、2018年の労働時間分布を踏まえると、おおむね19%(1,098万人)の雇用者が、就業時間の調整を求められることになる。
(男性の労働時間は国際的に長い)
平均的には労働時間の短縮が進んでいるものの、我が国男性の労働時間はいまだに長く、週49時間以上働く就業者の割合は27%と、韓国の30%を除けば他のOECD諸国よりも高い(第2-1-3図(1))。なお、我が国だけでなく、週40~48時間の労働時間で就業する者が最頻値となる国は多いが、フランスでは週30~39時間程度の割合も高い。
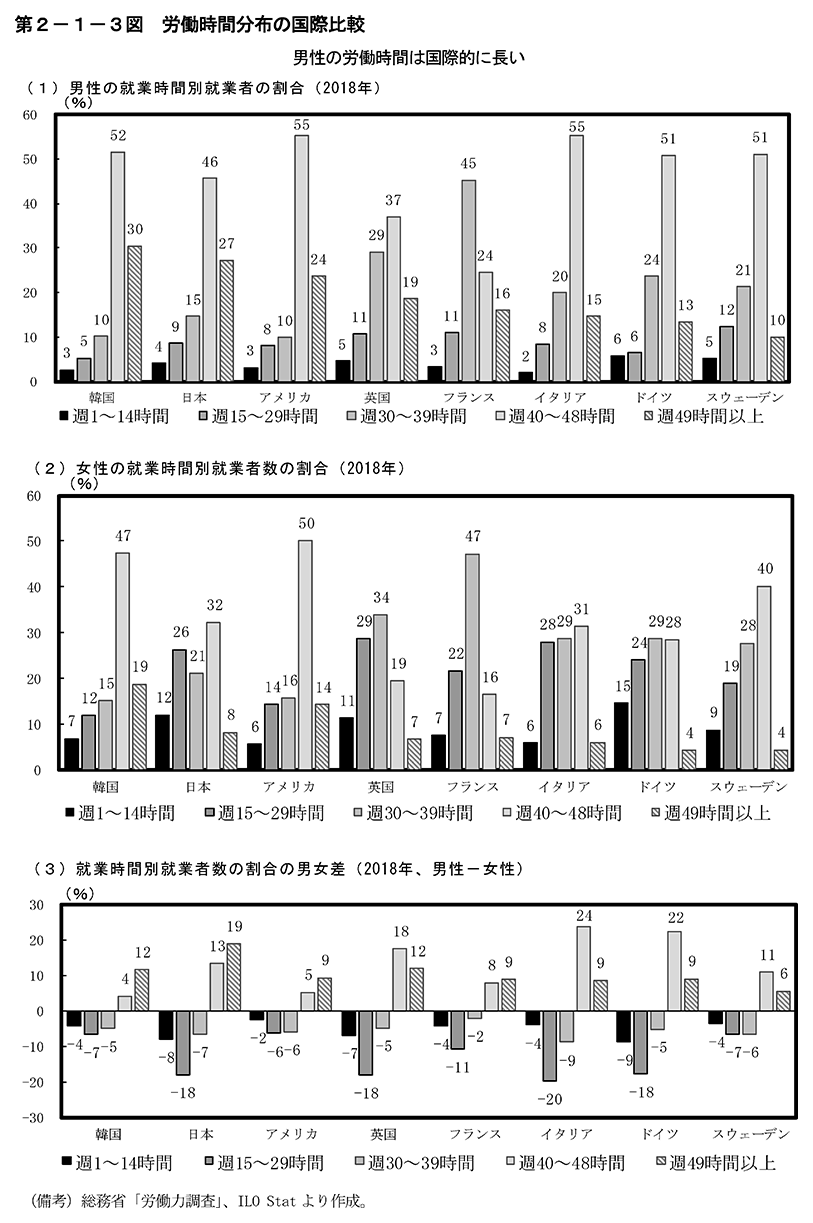
一方、女性の労働時間の分布についてみると、我が国はアメリカや韓国等に比べて週当たりの労働時間が短い階級での割合が高く、英国やドイツと同様の分布となっている(図2-1-3(2))。最後に分布の男女割合の差をみると、週49時間以上の長時間労働者は男性に偏っている傾向が全般的にみられ、15~29時間の短時間労働者は女性に偏る傾向も共通してみられる。いずれの国でも比較的長時間労働を行う者は男性が多い(第2-1-3図(3))。
(一日当たり労働時間の長い国・地域の方が労働生産性は低い)
労働時間の延長は、労働投入量の増加を通じて付加価値を生み出すが、2014年から18年の5年間のOECD加盟国のデータによると、一日当たり労働時間の長い国・地域の方が、労働生産性は低いことが示唆される(第2-1-4図(1))。製造業等の事例研究が中心だが、過去の分析によると、労働時間が一定時間を超えると労働生産性が低下することが知られている2。
また、同じくOECD加盟国における最近の労働生産性上昇率の変化をみると、労働時間の短縮が生産性上昇率の増加に寄与している国は多い(第2-1-4図(2))。特に、人口減少と高齢化がどこよりも進んでいる我が国では、労働の希少性は一層増すことからも、より効率的な働き方を追求する必要がある。
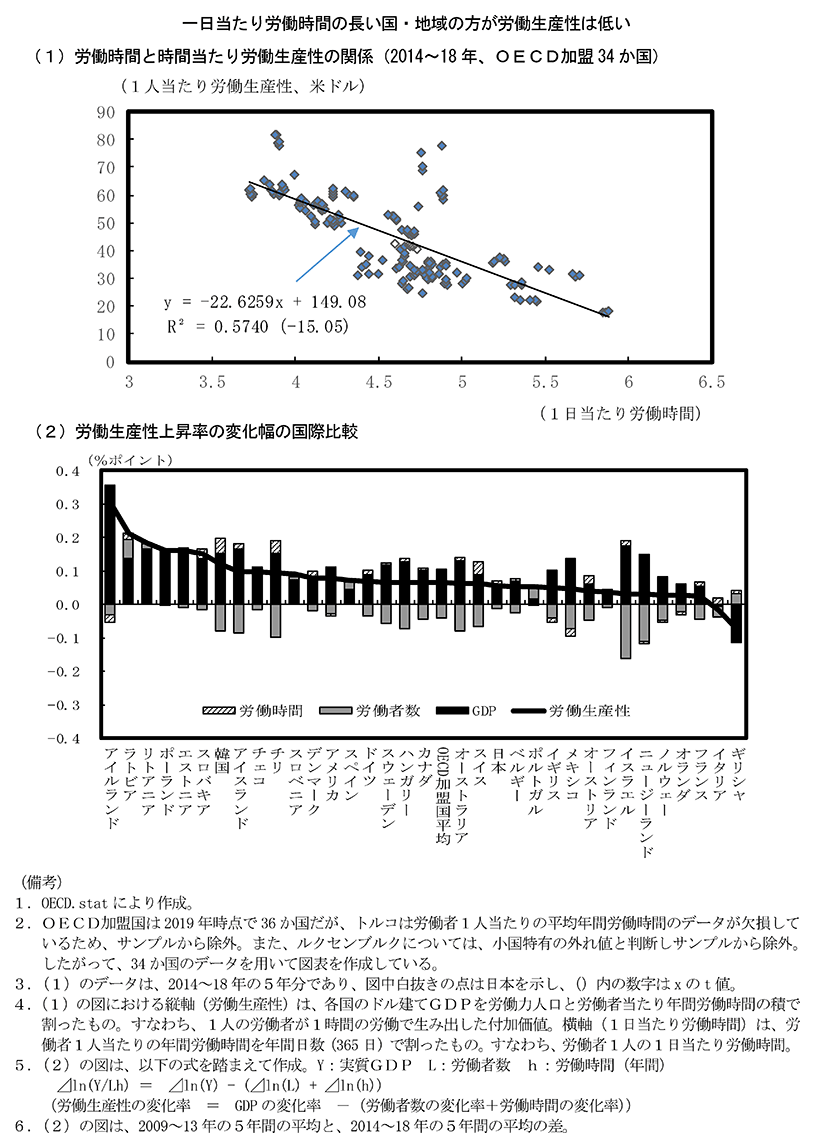
2 労働参加の推移
前項では労働時間の動きについて概観したが、それには働き手の構成変化も影響している。これまで、生産年齢人口に相当する男性労働者が中心であった我が国において、どのような変化が生じているのか、労働参加の状況について確認する。
(生産年齢人口が減少する中、女性及び高齢者の労働参加が進展)
我が国の労働参加率は、2013年以降上昇に転じている(第2-1-5図(1))。趨勢的には男性の労働参加率が低下し、女性の参加率は横ばいであったが、最近は女性の参加率が上昇傾向を強めつつ、男性の参加率も下げ止まっている。そこで、2012年を起点として性別年齢階層別の増減寄与を分析すると、64歳以下の男性は減少し、64歳以下の女性と65歳以上の男性と女性が増加している(第2-1-5図(2))。
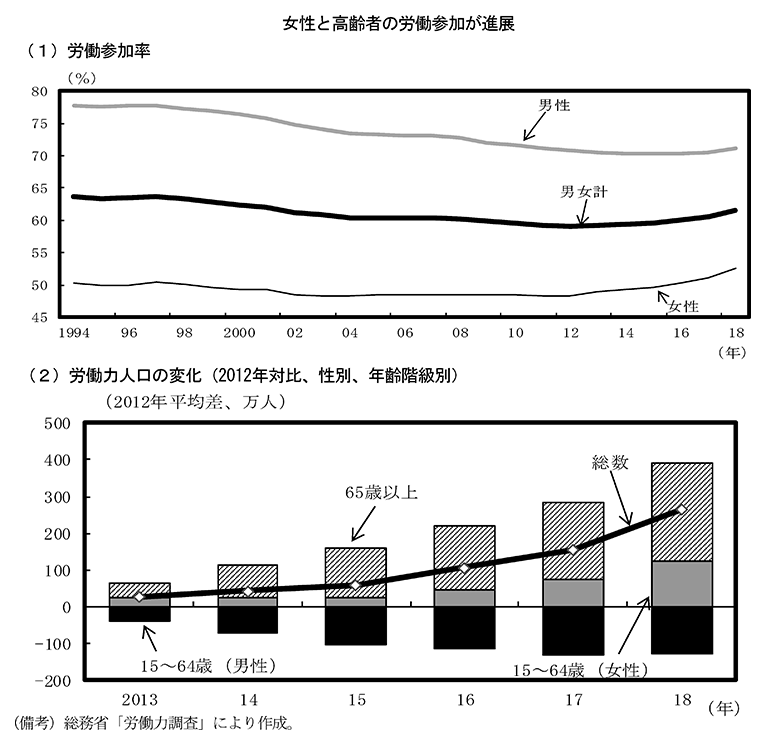
(女性の労働参加率にはM字カーブがまだ存在)
女性の労働参加は進んできたものの、OECD加盟国との比較では、30歳以上の年齢階層において労働参加率が低下する傾向が残っている。(第2-1-6図(1))。結婚や出産を機に労働市場から退出する程度(M字カーブ)は、年々解消されつつあるが、継続就業と出産や育児との両立への取組は、引き続き重要である(第2-1-6図(2))。
また、就労の形態についても、男性がいわゆる正規雇用が多い一方、女性は非正規雇用で就労する割合が30歳以上の年齢階層で高まる傾向にあり、それまでのジョブ・キャリアを中断し、再就業する際に正規雇用から非正規雇用へ移行している(第2-1-6図(3))。
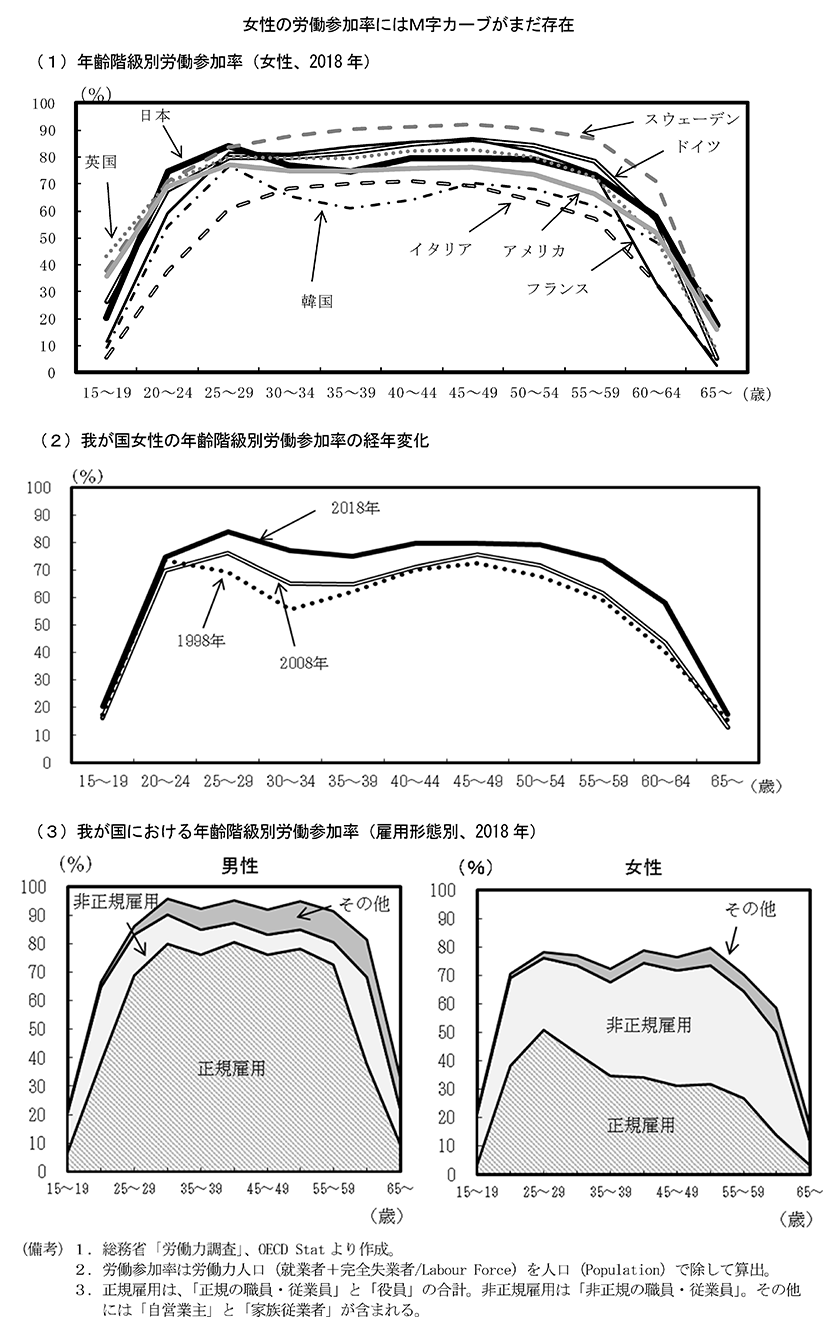
(長時間労働の男性が多い国・地域では、30歳台女性の労働参加が進んでいない)
30歳台以降の女性の労働参加が十分に進まず、また、就労形態に非正規雇用が多い背景には、世帯所得を意識した就業調整、子育てや介護といった家族事情等があると思われるが、社会における働き方、例えば、労働時間も関係している。OECD加盟国における30歳台女性の労働参加率と週49時間以上働く男性の割合をプロットすると、有意に負の相関が観察される(第2-1-7図)。
もちろん、これは30歳台女性とその配偶者の労働時間とを対にした分析ではなく、一国内の平均値を用いたものであり、家庭内における家事労働の分業を示すものではない。しかし、一般的な社会の傾向として、長時間労働の男性が多い国・地域では、30歳台女性の労働参加が進んでいない、あるいは、30歳台女性の労働参加が進んでいる国・地域では長時間労働の男性が少ない、という傾向が示唆されている。
こうした結果が生じる背景には、男性の子ども・子育てへの参加状況や働くために必要となる保育所等の社会インフラや環境条件等、様々なものが存在すると考えられる。何れにしても、女性の労働参加促進と男性の長時間労働抑制という2つの課題には、共通の社会的な要因が作用しているため、同時に解決を目指すべき課題である。
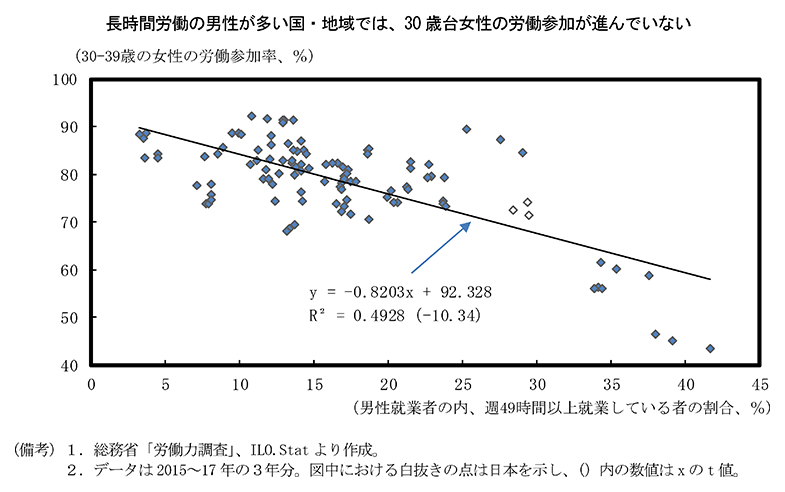
3 働き方改革とその効果
1項では、労働時間が短縮化する背景に、女性や高齢者を中心としたパートタイム労働者の増加といった構造変化があることを指摘したが、いわゆる働き方改革を巡る動きについても、労働時間を減少させる効果がある。働き方改革には幾つかの狙いがあるが、2019年において効果が観察されると見込まれる制度変更は、残業規制3と有給取得義務化4の二つである(コラム2-1参照)。本節では、各々を巡る動きについて確認していく。
(労働時間減少の主要因は所定内労働時間)
2019年の労働時間は前年から減少している。所定内労働時間は、これまでも年当たり1時間弱の減少がみられていたが、2019年は3時間程度と減少幅が拡大している。業種別の寄与をみると、製造業もさることながら、雇用者数の多い非製造業も含め、全ての業種が減少に寄与している(第2-1-8図(1))。
減少寄与の大きい非製造業の所定内労働時間については、パートタイム労働者比率の上昇もマイナス要因ではあるものの、一般労働者の所定内労働時間の減少寄与が大きく、1項でみた構造変化(前掲第2-1-1図(3))とは別の動きも同時に生じている(第2-1-8図(2))。
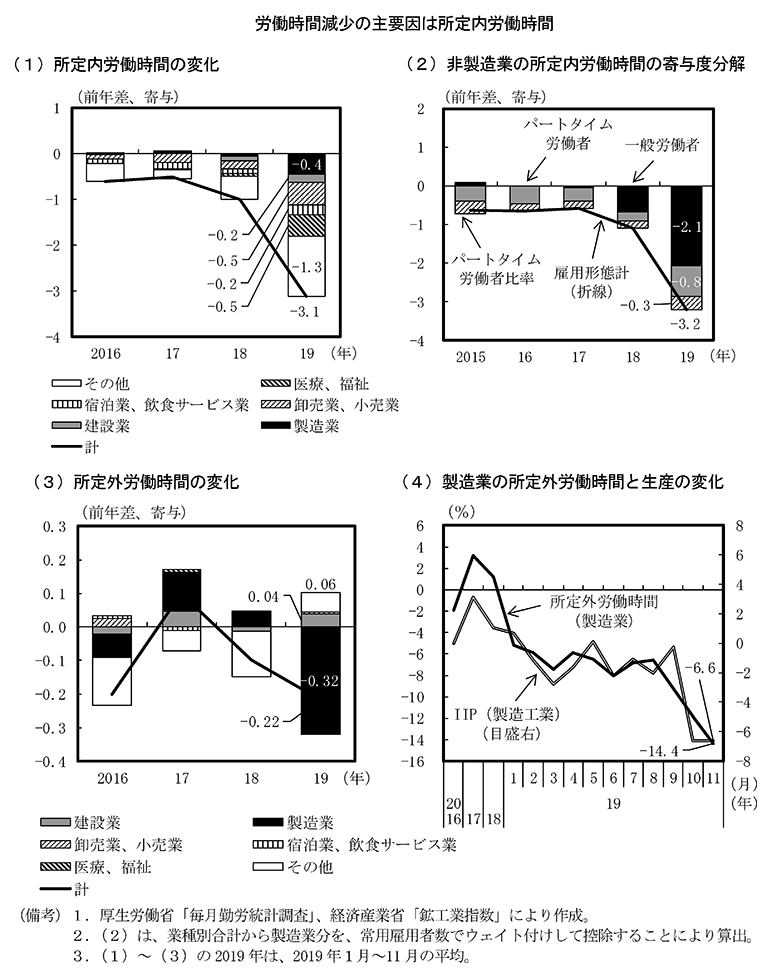
所定外労働時間の増減についても業種別の寄与をみると、建設等の一部非製造業は増加に寄与する一方、2019年の減少は専ら製造業による。製造業における所定外労働時間は、鉱工業生産と高い相関を示しており、景気要因で変動していることがうかがえる(第2-1-8図(3)、(4))。
(労働時間の減少はカレンダー要因だけでなく、有給取得等も貢献)
一人当たり労働時間の減少は所定内労働時間、それも一般労働者の寄与が大きいことは分かったが、この要因について、一人当たり労働時間を一日当たり労働時間と勤務日数に分解し、さらに、勤務日数を祝日数や土日数の増減といったカレンダーの動きと有給取得等のその他要因に分解する。要因分解の結果、500人以上の事業所では、一日当たり労働時間要因が-0.1時間、カレンダー要因が-1.5時間、そしてその他要因が-1.4時間となっている。過去3年の動きと比較すると、その他の出勤日数要因の寄与が拡大していることから、その一部には有給取得義務を踏まえた動きがあるとみられる(第2-1-9図(1))。こうした動きは500人未満の事業所においても広く観察され、有給休暇取得を含むその他要因による時短効果は、100~499人の事業所では-2.2時間、30~99人の事業所では-1.2時間、5~29人の事業所は-1.4時間となっている。
また、製造業と非製造業別に同様の分解をすると、製造業では所定外労働時間の減少を反映し、一日当たり労働時間の減少が-0.9時間程度となっている(第2-1-9図(2))。カレンダー要因とその他要因はそれぞれ-1.6、-1.0時間となっており、有給取得を含むその他要因も減少に貢献している。非製造業では、一日当たり労働時間は横ばいとなる一方、カレンダー要因とその他要因は-1.3、-1.6時間となっており、こちらにおいても、有給取得を含むその他要因による減少が貢献していることが示唆される。
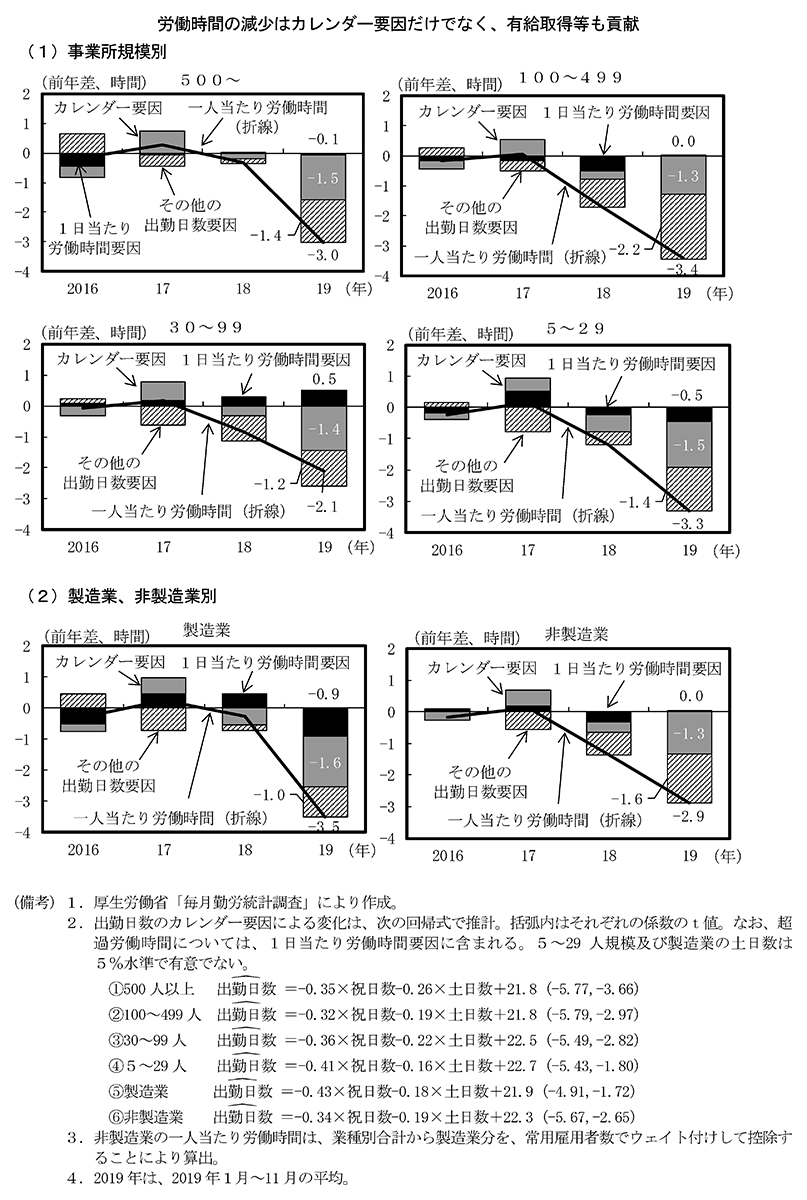
(長期間労働者の人数と割合はともに減少傾向)
続いて、働き方改革が長時間労働者の人数や割合に与える効果についてみていく。まず、製造業、非製造業のそれぞれを事業所規模別に分け、週当たり労働時間が49時間を超える者を長時間労働に該当するとして、その人数と割合を調べると、500人以上の事業所では、製造業は2018年の27.2%から2019年は23.4%(102万人から90万人)へと減少、非製造業は、19.4%から18.0%(264万人から245万人)へと減少している。他の事業所規模についても、同様の結果がみられ、100~499人の事業所規模の製造業では、22.8%から20.5%(-6万人)、非製造業では19.6%から18.0%(-13万人)、30~99人の事業所規模の製造業では21.2%から19.4%(-4万人)、非製造業では19.5%から18.4%(-7万人)、5~29人の事業所規模の製造業では18.5%から17.7%(-3万人)、非製造業では17.8%から16.6%(-11万人)へそれぞれ減少している(第2-1-10図(1))。雇用形態別では正規雇用者において顕著な減少がみられ、2018年の28.4%から26.2%、人数では967万人から886万人へと減少している(第2-1-10図(2))。
長時間労働者の割合や人数が減少している背景の一部には、働き方改革による各事業所の取組が影響していることも想像に難くない。厚生労働省による2019年11月時点の企業調査では、長時間労働是正等のために効果があると思われる主な取組について、実施企業の割合が示されている。それによると、時間外労働の事前申告制を導入した企業は48%、ノー残業デーの徹底が28%となっており、直接的な労働時間抑制への取組もみられる。また、業務効率化や省力化投資、あるいはアウトソーシングといった業務量そのものを抑制する取組も広くみられる(第2-1-10図(3))。
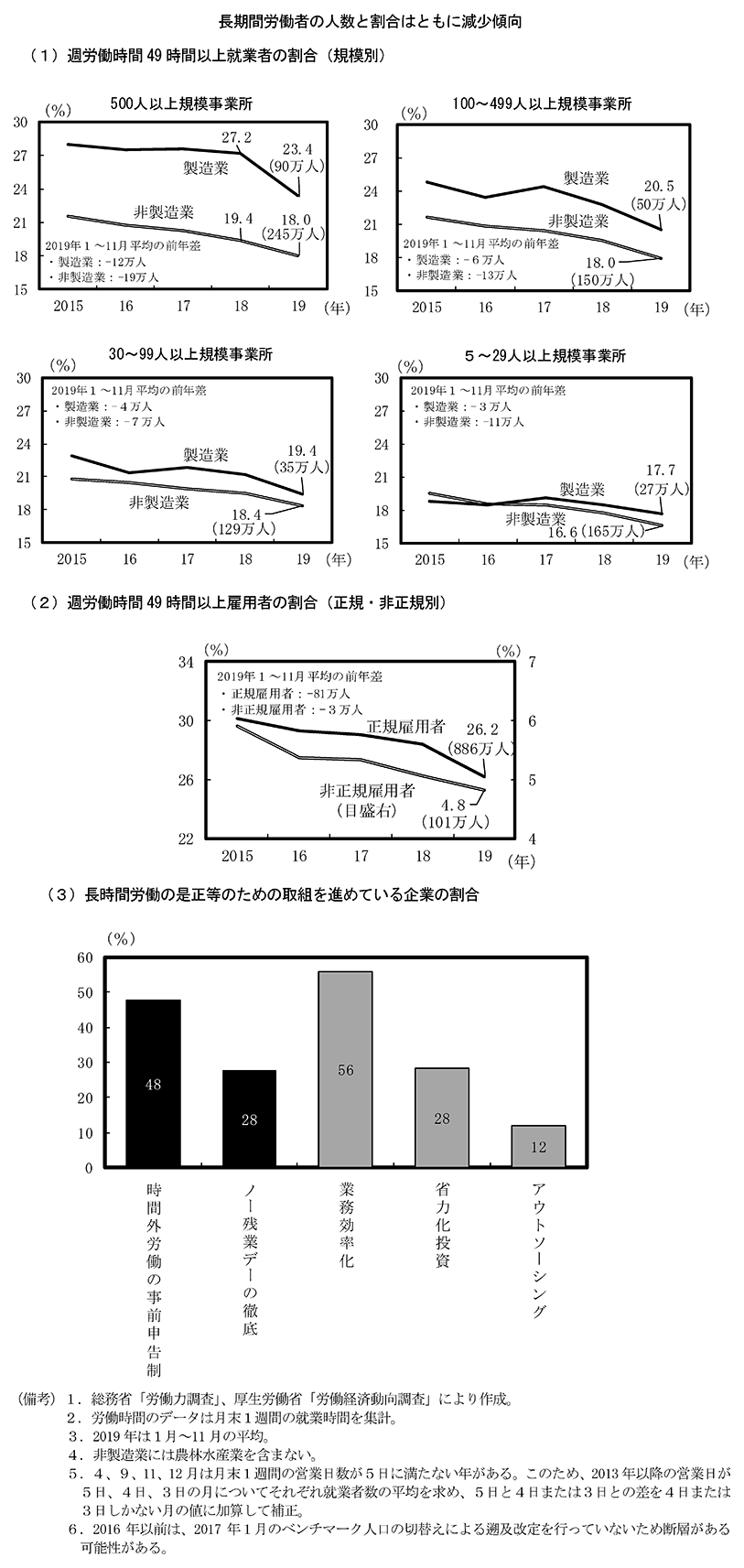
コラム2-1 「働き方改革」の経緯
厚生労働省によると、「働き方改革」とは、一億総活躍社会の実現に向け、働く人々が個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、自分で選択できるようにするための取組である5。働き方改革に係る包括的な法律の正式な名称は、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法第71号。以下「働き方改革関連法」という。)であり、2018年7月6日に成立、同日より順次施行されている。
「働き方改革」という言葉の経緯を調べると、2013年5月19日に提言がまとめられた「若者・女性活躍推進フォーラム」において、男女ともに仕事と家事・育児等の両立に向けた環境整備を促進すべきという文脈の中で、働き方の改革を進めるべきとの議論がなされたことが確認できる6。
その後、少子化危機突破のための緊急対策(2013年6月7日少子化社会対策会議決定)、日本再興戦略2013(2013年6月14日閣議決定)に記載され、2015年の一億総活躍国民会議において、働き方改革が一億総活躍社会実現に向けた最大のチャレンジと位置づけられ、同年6月2日に「ニッポン一億総活躍プラン」が閣議決定された。
同プランでは、働き方改革の一環として、同一労働同一賃金の実現など非正規雇用の待遇改善、長時間労働の是正、高齢者の就業促進に取り組むことが明記された。これを受けた「働き方改革実行計画」(17年3月28日働き方改革実現会議決定)では、同一労働同一賃金の実効性確保や罰則付き時間外労働の上限規制等を含む労働関係法令改正の検討がなされることとなった。
このようにして成立した働き方改革関連法は、以下の3点を意図している。
①働き方改革の総合的かつ継続的な推進
②長時間労働の是正及び多様で柔軟な働き方の実現等
③雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保
このうち、②と③が主たる制度改正事項であり、②は、時間外労働の上限規制、年5日の年次有給休暇の確実な取得、月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率における中小企業への猶予措置の廃止、高度プロフェッショナル制度の創設、勤務間インターバル制度の普及促進、産業医・産業保健機能の強化等を含んでいる。施行期日は、2019年4月1日を基本として、中小企業への適用時期が、時間外労働の上限規制に係る改正規定の適用は2020年4月1日、割増賃金率の見直しは2023年4月1日となっている。また、③は、同一労働同一賃金の実現のための規定の整備等であり、施行期日は2020年4月1日、中小企業への適用時期は2021年4月1日となっている。
こうした働き方改革の議論は、法令が施行される以前から人々や企業の動きに影響を与えていた可能性がある。そこで、働き方改革に関する閣議決定から法施行までのイベント毎に実際の労働時間等が変化したのか否かを確認した。所定外労働時間数は法案の動向によって変化したとはいえないが、所定内労働や出勤日数については、法案可決や施行のタイミング以降、それ以前と比べて減少している。企業や人々は、こうした政策の動きを踏まえながら、働き方改革へ対応していたのかもしれない。