第1章 日本経済の現状(第3節)
第3節 世界経済の鈍化に影響された企業部門
前節までに確認した、外需が弱く、内需が底堅いという状況は、経済の供給面でも製造業と非製造業の間に好不調のデカップリングをもたらしている。本節では、製造業と非製造業の違いに着目しながら、企業部門の生産、収益、投資の動向を確認する。
1 輸出依存度が明暗を分けた生産
(世界経済の減速を背景に輸出は弱含み)
第1章第1節で概観したとおり、2018年以降の世界経済の減速を背景に、我が国の輸出は、2018年央を境に、それまでの持ち直し基調から弱含みに転じ、2019年を通じて低調に推移した(第1-3-1図(1)、(2))。地域別にみると、我が国の輸出の過半を占めるアジア向けが、輸出全体の弱さの基調を生み出した。アジア向け輸出は、2018年初から、世界的な半導体需要の一服により情報関連財を中心に減少し始めたが、そこに中国経済の減速を背景とする資本財(工作機械等)や自動車関連財(自動車の部分品等)の輸出の減少も加わって、足元まで弱含みで推移している。
また、2019年後半からは、それまで比較的堅調に推移してきていたアメリカ向け輸出が減少に転じた(第1-3-1図(1)、(3)、(4))。財別にみると、自動車完成車(自動車関連財)の減少が大きい。他方、アメリカの自動車市場では、販売全体も、また、その中での日本車の販売も底堅く推移しており、同国における需要自体は弱くはない。このため、日本からの完成車輸出の減少には、海外への生産移管、あるいは生産代替の影響があると考えられる。生産移管に伴う輸出の減少であれば、我が国の企業収益は確保される一方、国内生産の減少を通じて、雇用等への影響は生じ得るため、その動向を注視していく必要がある。
輸出の先行きを考える上では、自動車関連財と併せて、情報関連財の動向が重要である。情報関連財については、前述のとおり、2018年以降のアジア向け輸出の弱さの原因となっていたが、このところ下げ止まっている(第1-3-1図(5))。半導体の在庫調整が進展する中、スマートフォン向けを中心に需要が高まっており、IC(集積回路)の輸出には、2019年夏以降、持ち直しの動きがみられる。また、IC等の半導体の増産に必要な半導体製造装置の輸出についても、ICの持ち直しからラグを伴って増加に転じている。世界の半導体売上げは、2019年を底に2020年には持ち直しに転じることが見込まれており、今後、世界的に情報関連財の需要が増せば、アジア向けを中心に、我が国の輸出を下支えすることも期待される(第1-3-1図(6))。
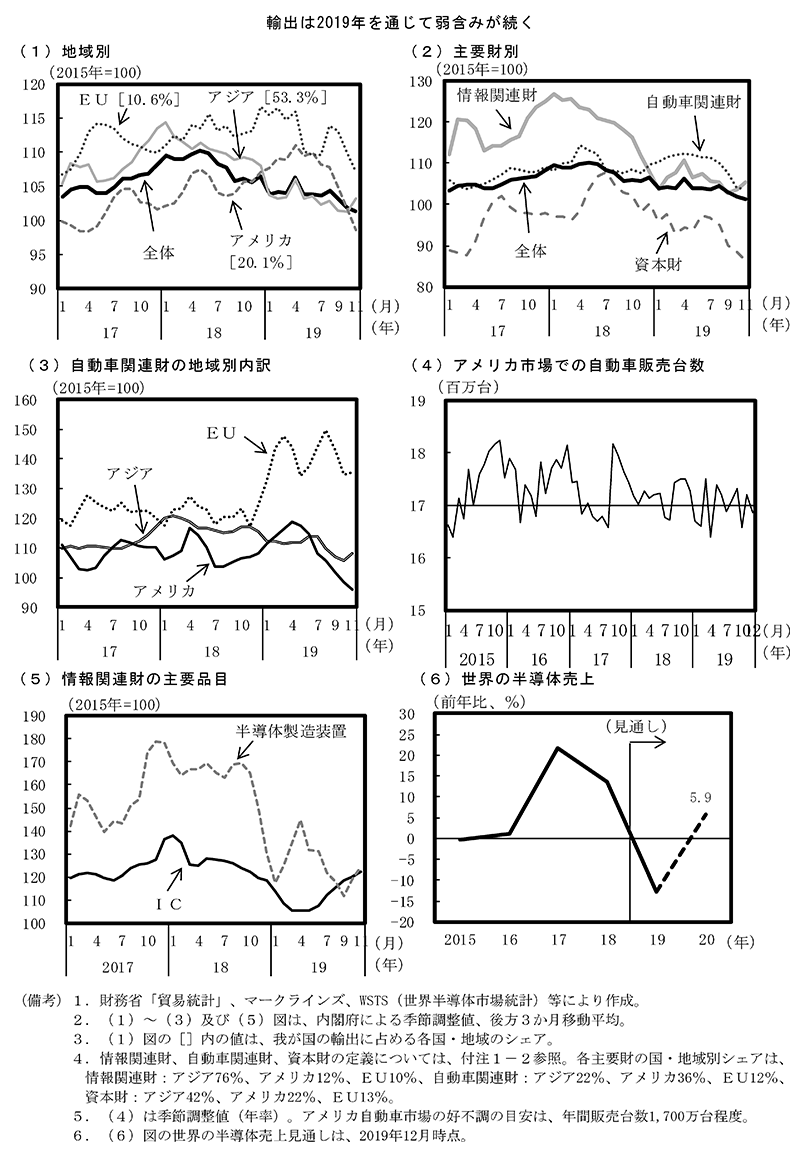
(輸出の弱さを受けて、製造業の生産も弱含み)
輸出の動きは、製造業の生産に直結する。2019年に入り、鉱工業生産指数には、一時的に横ばいの動きもみられたが、年初は電子部品・デバイスや生産用機械、後半からは輸送機械等が減少となり、持ち直すことはなかった。輸出向け出荷の累積寄与をみると、年の前半までは輸送機械がプラスではあったものの、夏場以降はマイナスに転じている。他の産業はおしなべてマイナス寄与となっており、輸出ウエイトの高い業種を中心に減少となった(第1-3-2図)。
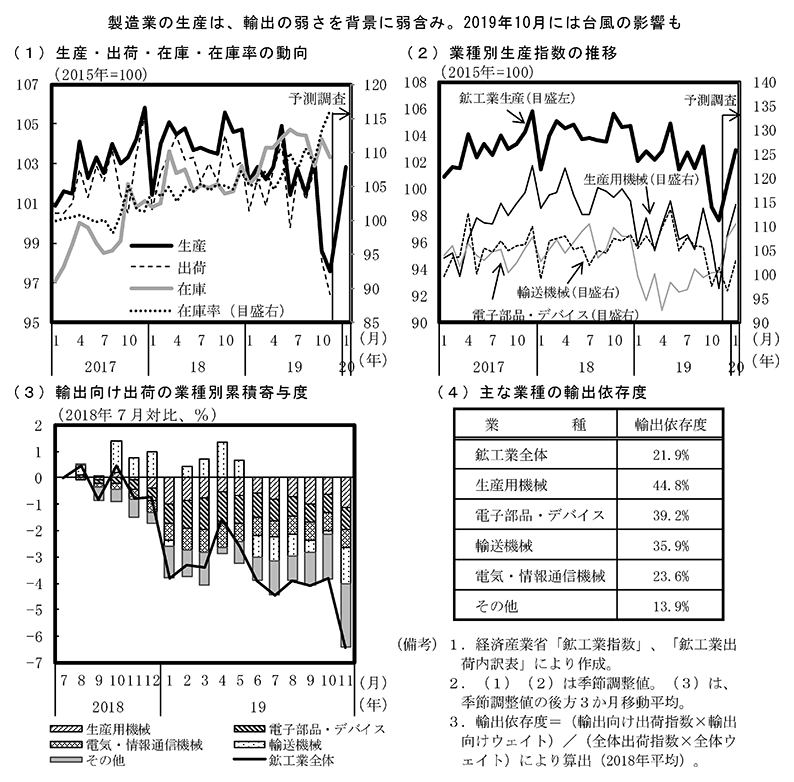
他方、年初に弱さの主因であった電子部品・デバイスの生産には、在庫調整圧力の軽減と次世代通信規格「5G」も見据えた海外需要の持ち直しもあって、このところ明るさがみえている。中でも、スマートフォン関連品目は急速な回復をみせており、それ以外の品目とは異なる動き方をしている。また、半導体製造装置の生産についても、半導体の世界出荷額が反転増加に転じたのち、緩やかながらも増加している(第1-3-3図)。
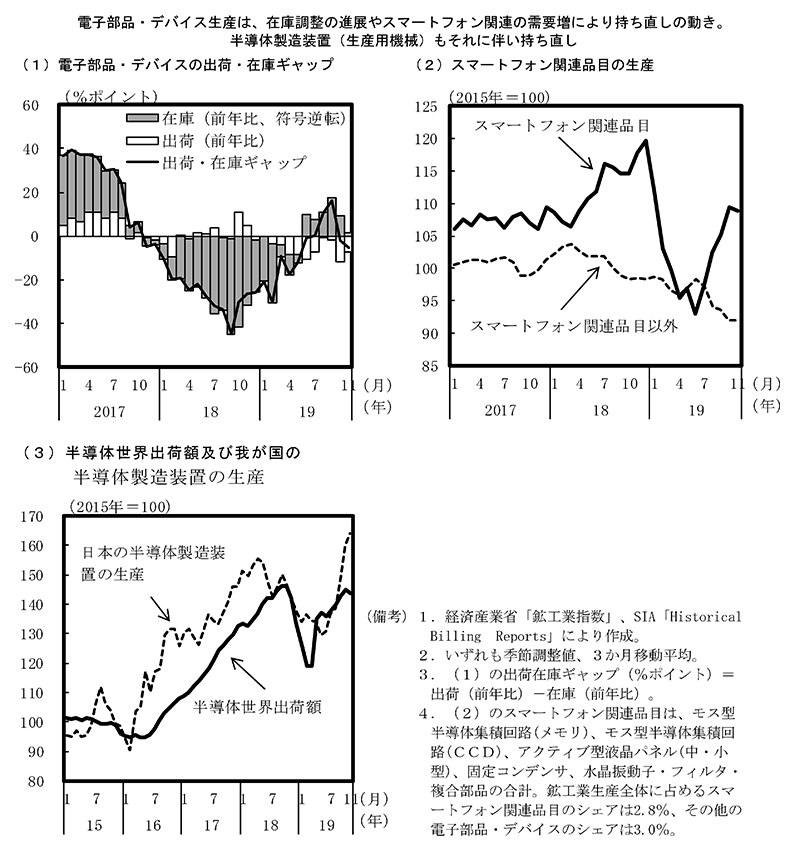
(内需向けサービスを中心とした非製造業は堅調)
海外情勢に左右されやすい製造業とは異なり、非製造業は相対的に堅調な動きで推移している。非製造業は、家計消費の約8割を供給する一方で、サービスを含む輸出の4割弱を供給する業種でもある。したがって、製造業に連動する面もある卸売業等で伸び悩みがみられるものの、情報通信業等は好調であり、全体のトレンドよりも高い伸びとなっている。なお、個人消費にみられた2019年10月の消費税率引上げに伴う駆け込み需要とその反動減に対応する形で、非製造業の生産活動も2019年9月以降振れが生じている(第1-3-4図)。
なお、増加傾向が続く訪日外国人も非製造業の堅調さを下支えしており、2018年の訪日外国人による消費、いわゆるインバウンド消費は、年間4.5兆円に上る(第3章コラム3-1を参照)。
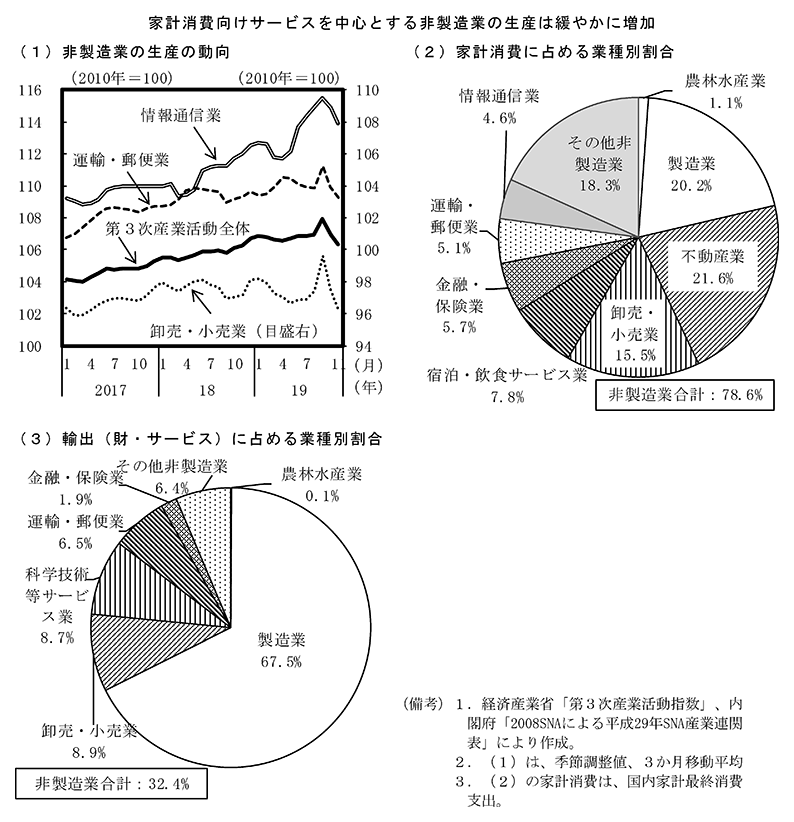
2 製造業と非製造業の生産活動の違いは企業収益にも波及
(企業収益は製造業を中心に弱さがみられる)
続いて企業収益の動向についてみていこう。増勢が続いてきた企業収益は、2019年に入り製造業を中心に弱さがみられ、横ばい感のある動き方となっている。
経常利益の変動について、製造業と非製造業に分けて要因を分解すると、製造業では、2018年第3四半期以降、海外経済が減速する中で、徐々に売上高のプラス寄与が縮小し、2019年第2四半期からはマイナス寄与に転じた。また、コスト面については、仕入コスト等を反映する変動費要因のマイナス寄与が続いている一方、人件費要因は変動が小さく、2019年に入ってからは目立った影響はみられない。
非製造業では、内需の底堅さを背景に、製造業に比べて2018年を通じ売上高要因のプラス寄与が大きく、2019年第2四半期までプラス寄与が続いた。直近の第3四半期ではマイナス寄与に転じているが、これは、前年同期の売上高要因が強かったことの反動と、原油価格の下落等により取引価格が低下したためとみられる。現に、同じ第3四半期の変動費も減少しており(経常利益にはプラス寄与)、売上高要因のマイナス寄与の一部を相殺している1。なお、労働集約的な非製造業では、人件費要因のマイナス寄与が製造業と比べて大きく、経常利益の下押し要因となっていたが、2019年7-9月期はプラス寄与となった。これは、2019年の夏季賞与が、高水準だった前年に比べて減少したことも影響している(第1-3-5図)。
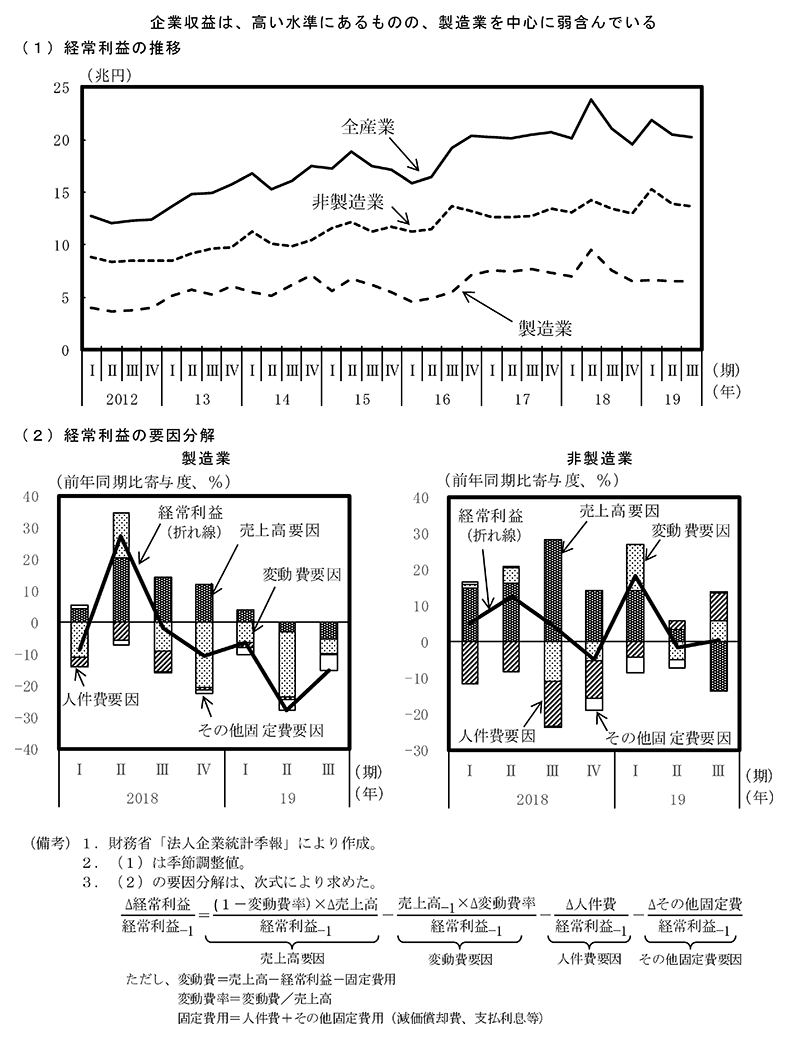
(賃金と利益をともに伸ばす価格設定が重要)
このように、収益面でも製造業と非製造業との明暗は分かれているが、これを企業の価格設定の視点からみると、どのような違いがあるだろうか。コストと価格の関係をみるために、マクロ的な付加価値価格(GDPデフレーター)の動きを単位労働費用(ULC)と単位利潤の寄与に分解すると、産業全体では2012年第4四半期以降、2015年頃まではGDPデフレーターの上昇は単位利潤の上昇につながっていたが、2016年以降は、GDPデフレーターが伸び悩む中で、次第にULCが上昇し、その結果、単位利潤は圧迫されてきた(第1-3-6図(1))。
これを製造業と非製造業に分けてみると、双方の動きは対照的である(第1-3-6図(2))。製造業は、ULCの伸びが抑制されていたが、それ以上に単位利潤要因が大きく上昇することによってGDPデフレーターが強めに推移していた。もっとも、2017年以降は、単位利潤が低下してきており、GDPデフレーターも2012年対比では非製造業と同程度にまで低下している。製造業の抑制的なULCは、更なる賃上げの余力があるとみることもできるが、今後、賃上げによるULCの上昇が起こった場合には、単位利潤を低下させることなく、GDPデフレーターの上昇に結びつけていくことが、企業収益の確保とデフレからの脱却を両立させる上で重要である。
また、非製造業では、GDPデフレーターの上昇が緩やかな中、ULCが上昇し、単位利潤が圧迫されている。第1-1-11図でみたように、2019年に入ると、非製造業のULCの伸びは労働生産性の上昇を通じて一服するが、それだけでは単位利潤が圧迫されている姿は変わらない。2020年以降も労働生産性の向上を継続するとともに、GDPデフレーターを上昇させ、単位利潤も確保していくことが求められる(第1-3-6図)。
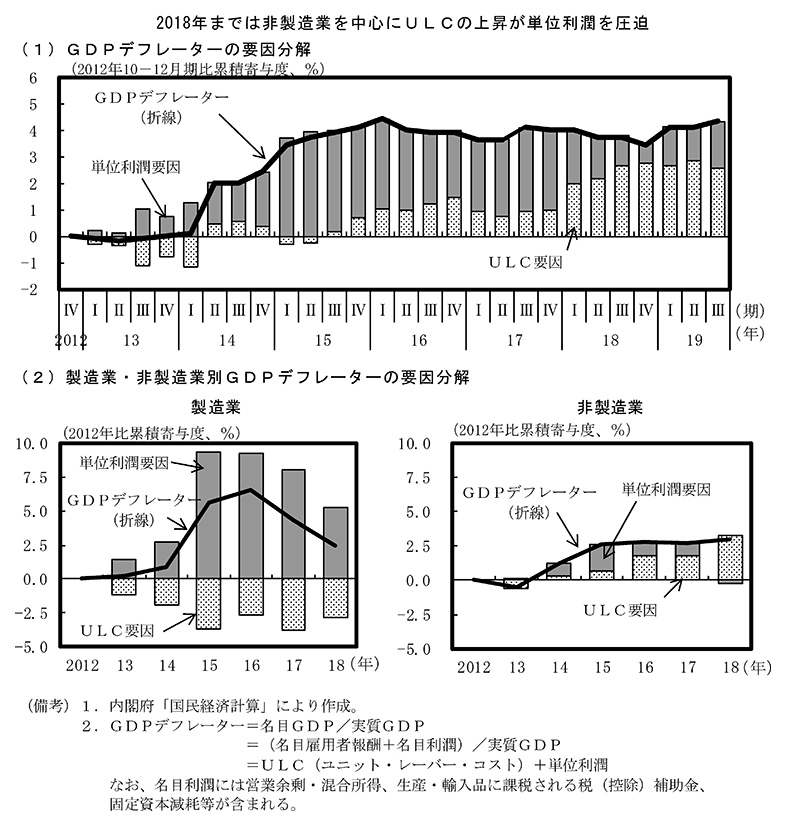
(為替レートの変化が企業収益に与える影響は、リーマンショック前より低下)
ここまでにみたように、企業収益は、海外経済の減速の影響を受けて、製造業を中心に弱含んでいるが、更なる外的リスクとして、為替レートの変動が企業収益に与える影響について点検する。まず、一国の経済全体への影響を内閣府の「短期日本経済マクロモデル」における乗数(円の対ドルレートが10%減価した場合)で確認すると、最新の推計結果(2018年公表)では、実質GDPへの効果は1年目0.2%程度、2年目0.7%程度、3年目0.7%程度とされている(第1-3-7図(1))。モデルが線形であれば円高は真逆の結果となる。過去20年間の推計履歴をみても、為替の減価は、輸出の増加や、企業収益の回復に伴う設備投資の増加等により、GDPを押し上げる結果となっている。ただし、3年目までを通してみた円安のプラス効果は、推計期間が1999年代以前のものに比べて、影響度が減衰している。
次に、円安の効果が企業収益に与える影響に的を絞って検証してみよう。企業の想定為替レートが1円円安になった場合の経常利益の変化について、リーマンショック前の景気循環(2002~2008年度)と現在の景気回復局面(2013~2019年度)の2期間に分けてみると、全産業、製造業(更に製造業の内訳として素材業と加工業)、非製造業のいずれも企業の想定よりも円安が進めば経常利益を押し上げる効果を持つことが分かる(第1-3-7図(2))。ただし、その効果の程度は、過去の期間よりも現在の期間の方が低下しており、特に、素材型の製造業や非製造業については現在の期間では統計的に有意な関係がみられない収益構造となっている。加工型の製造業でも影響度は低下しており、2010年以降に急速に伸長した直接投資、海外での現地生産体制の構築が、為替レートの変動に対する収益の安定性の確保につながっていると考えられる(第3章第1節第2項参照)。
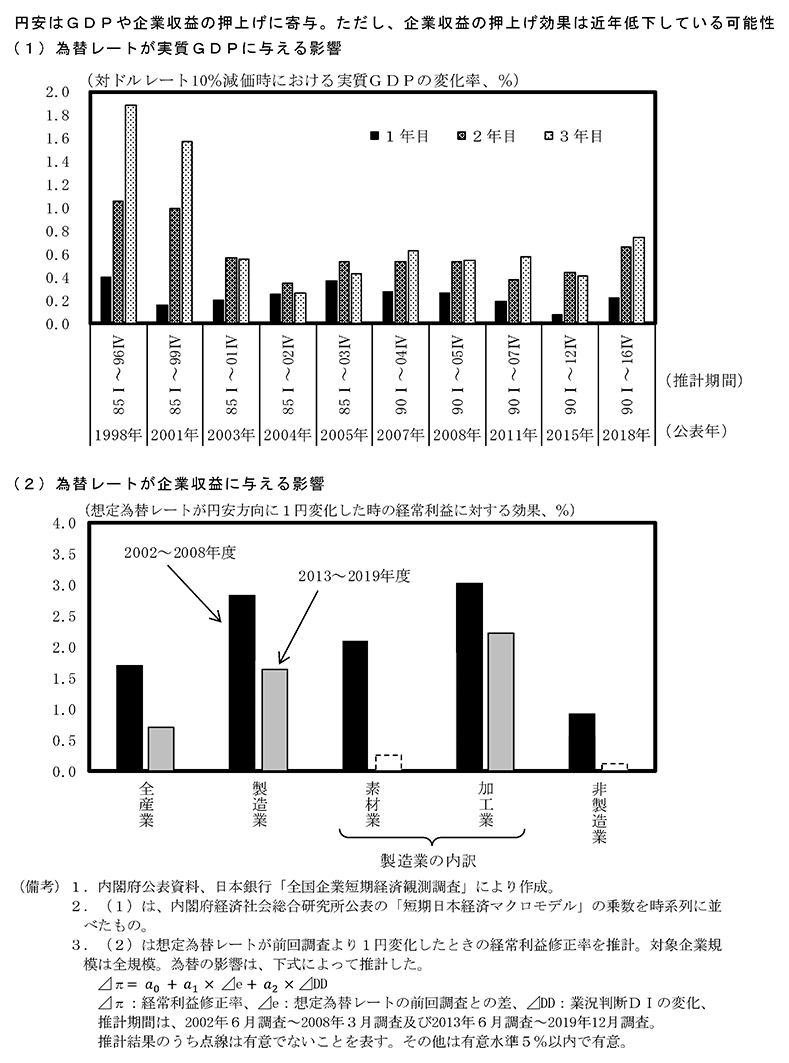
3 質的変化がみられる企業の投資
(生産減少を背景に機械投資には弱さも、構築物投資は底堅く推移)
2019年の企業の生産と収益は、製造業を中心に弱さがみられたが、それが設備投資に波及するか否かが景気動向の動きには重要である。2019年第3四半期までのところ、設備投資は、高水準の経常利益にも支えられて増勢を維持している。特に、非製造業の設備投資は強めの増勢を維持しており、全体を支える形となっている2(第1-3-8図)。
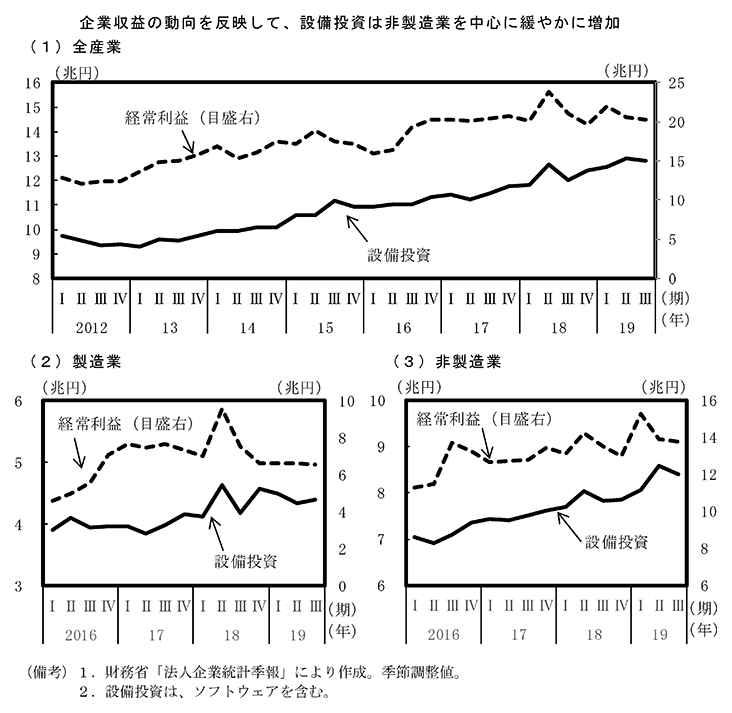
それでは、どのような設備投資が増加しているのだろうか。まず我が国の設備投資の約半分を占める機械投資については、2018年後半に力強く増加した後、2019年前半に大きく減少した。機械投資は、製造業のシェアが比較的大きく、2019年初めに輸出や生産が急減した影響が表れたものと考えられ、その後、半年ほどかけてようやく2018年前半並みの水準を取り戻した。このように、2019年を総じてみれば、機械投資には弱さがみられた。次に、我が国の設備投資の4分の1を占める構築物投資は、非製造業のシェアが比較的大きく、機械投資のような大きな落ち込みをみせることなく底堅く推移したが、年の後半に入り、増勢が失われている。
また、R&D投資については、2018年度まで増加傾向で推移している。R&D投資は、その多くが製造業によるものであり、製品の国際競争力の維持・強化が求められる中で、企業にとっての重要性が増しているものと考えられる。日本政策投資銀行「設備投資計画調査」によれば、2019年度の研究開発費も前年度比6.9%増と高い伸びが見込まれている3(第1-3-9図)。
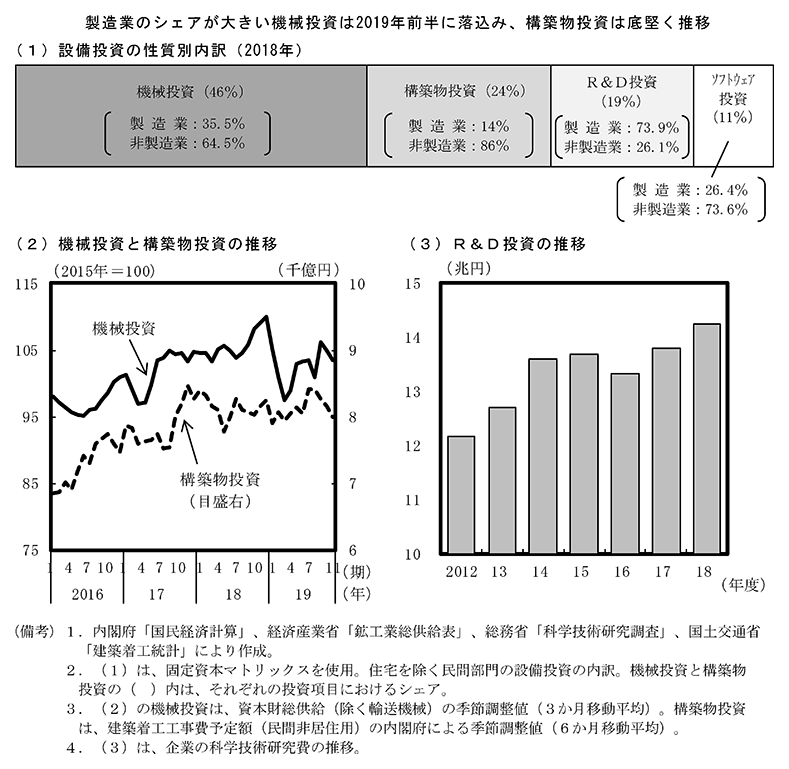
(ソフトウェア投資は拡大)
設備投資の11%を占めるソフトウェア投資も増加傾向が続いており、特に、最近の伸びは力強い。ソフトウェア投資とは、システムやアプリケーションに関するコンピュータ・プログラムの外部調達や自社開発が相当し、具体的には、在庫管理や財務管理のシステムの導入、ロボットやAI、IoTによる業務の自動化等が含まれると考えられる。ソフトウェア投資全体の70%以上を非製造業が占めており、また、近年の伸びも非製造業が中心となっている。業種別にみると、人手不足が顕著な宿泊・飲食サービス業や建設業、小売業において増加率が高い傾向がみられる。人員の過不足感と合理化・省力化投資の変化には高い相関がみられることから、現在の人手不足の状況が合理化・省力化投資を誘発し、ソフトウェア投資の増加につながっていると考えられる(第1-3-10図)。
我が国企業は、世界経済減速の下、生産能力増強や維持・補修を目的とする生産設備の設置や工場施設の建設といった従来型の設備投資には弱さがあるものの、長期的な課題に対応する投資需要は堅調であり、研究開発やソフトウェア投資といったAIやロボット等の新技術実装を始めとする「Society 5.0」の実現に向けた取組を着実に進めているものと考えられる。
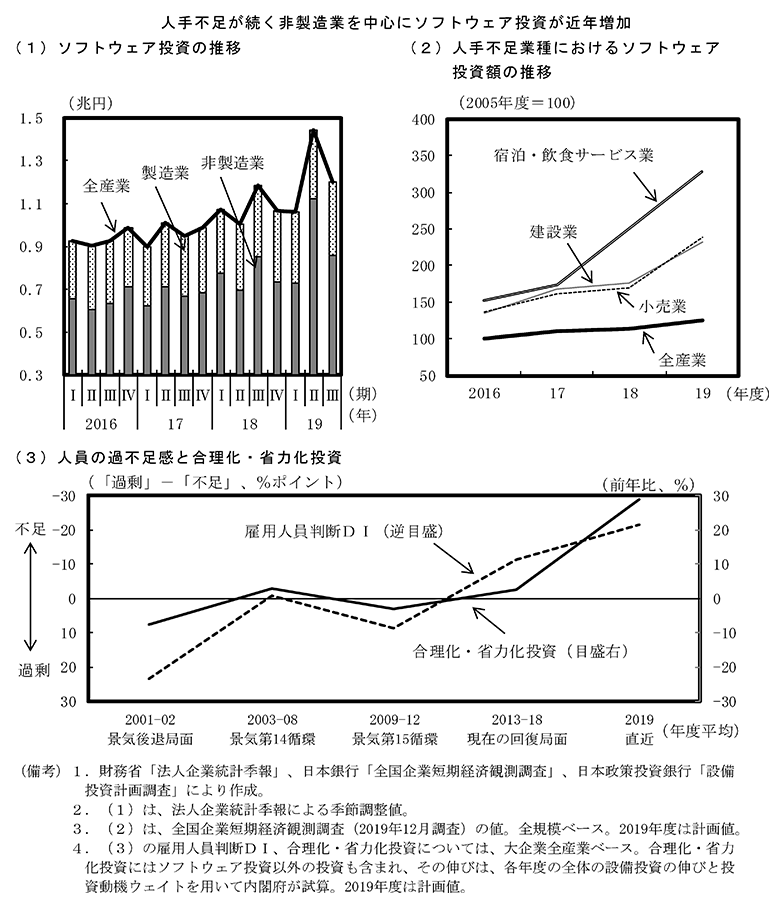
(資本コストの低下と投資収益率の上昇が投資を後押し)
ソフトウェア投資のニーズが高まっている背景として、人手不足の状況があることを確認したが、そうしたニーズも、投資増強によって得られる採算と見合わなければ、実行には移されないはずである。そこで、我が国の設備投資が全体として増加している要因を、資本コストと投資収益率の観点から確認すると、資本コスト4は、ゼロ金利政策と近年の物価上昇により実質金利が低下していること等から、低い水準で推移している。また、資本ストック一単位当たりの収益率をみた設備の投資収益率5は2010年度以降高まっている(第1-3-11図)。
こうした資本コストと投資収益率が与える設備投資への影響度をみるために、設備投資関数の推計を行ったところ、設備投資比率(=設備投資/資本ストック)と資本コスト及び投資収益率の間には統計的に有意な関係が得られた(第1-3-12図)。具体的には、資本コスト1%ポイントの上昇は設備投資比率を0.14%低下させ、投資収益率1%ポイントの上昇は設備投資比率を0.22%上昇させる関係にある。この結果から、企業の設備投資に対して、これまでの投資収益率の上昇はプラスの影響を与え、また、近年横ばいとなっている資本コストはニュートラルに働いたと考えられる。例えば、実質金利の低下を通じて、資本コストを更に抑制させることができれば、設備投資の増加を後押しすることができるが、そのためにもデフレから脱却し、安定した物価上昇を実現していくことが重要である。
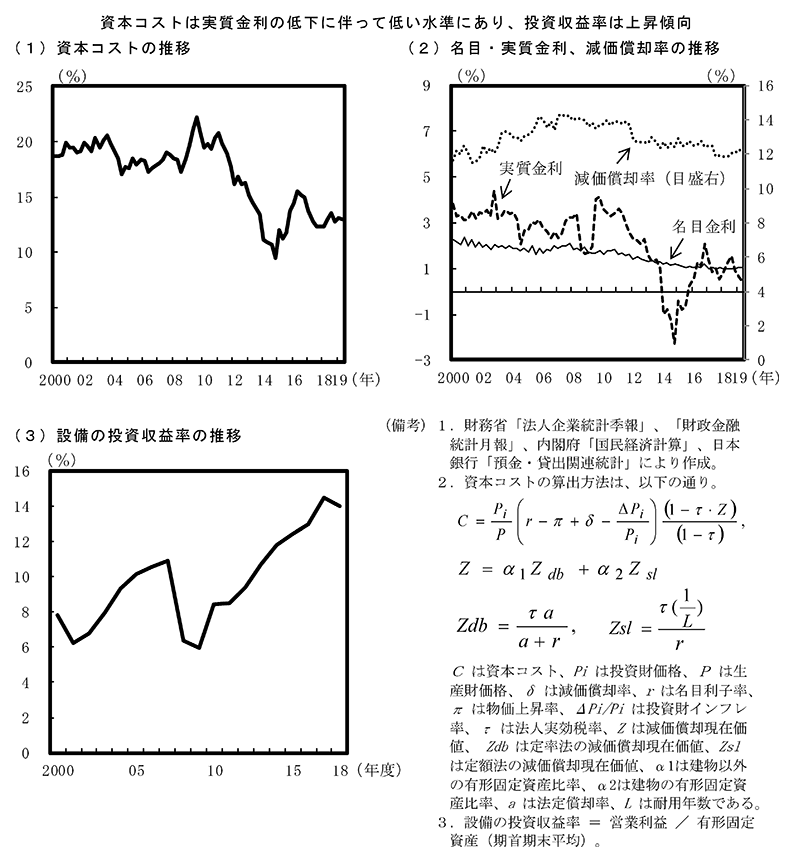
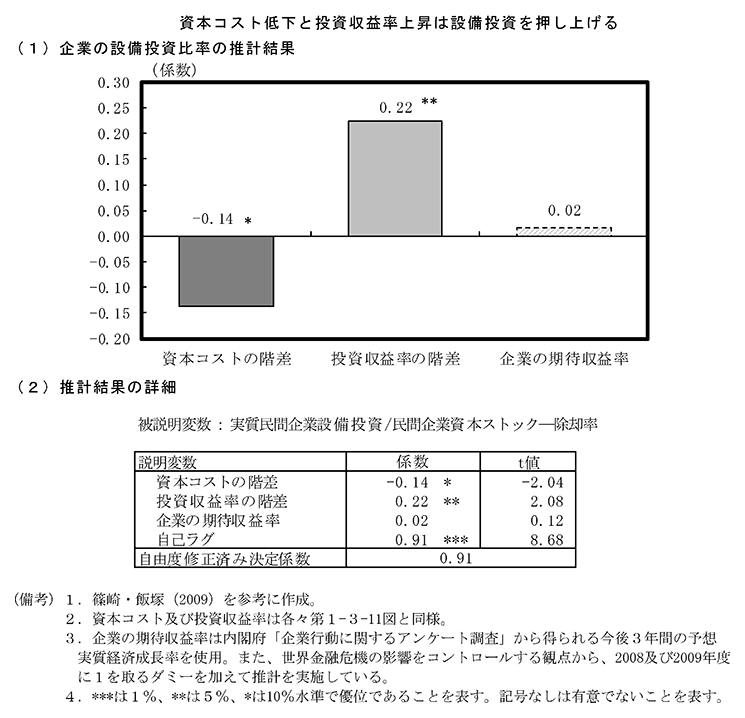
(現在の設備投資増加の前提となっている成長期待の腰折れに留意)
最後に、設備投資の先行きリスクについて点検する。資本ストックに対する設備投資の水準と設備投資増加率の関係をみた資本ストック循環図6を確認すると、設備投資水準は今回の景気回復局面で最も高い水準となっており、その投資水準が必要とする成長率は1.5~2%となっている7(第1-3-13図)。潜在GDP成長率は1%前後であることを踏まえれば、企業は、高い成長期待の下、設備投資を増加させている可能性がある。このため、企業の成長期待が下押しされるようなことがあれば、資本ストックの増加テンポが抑制されるよう設備投資が減速するおそれがある。また、2019年12月の設備投資の過不足感をみると、製造業では過剰超に転じている。海外経済の減速に起因する輸出、生産、収益の下押しが、今後更に設備投資を下押しすることがないか、十分に注意していく必要がある。
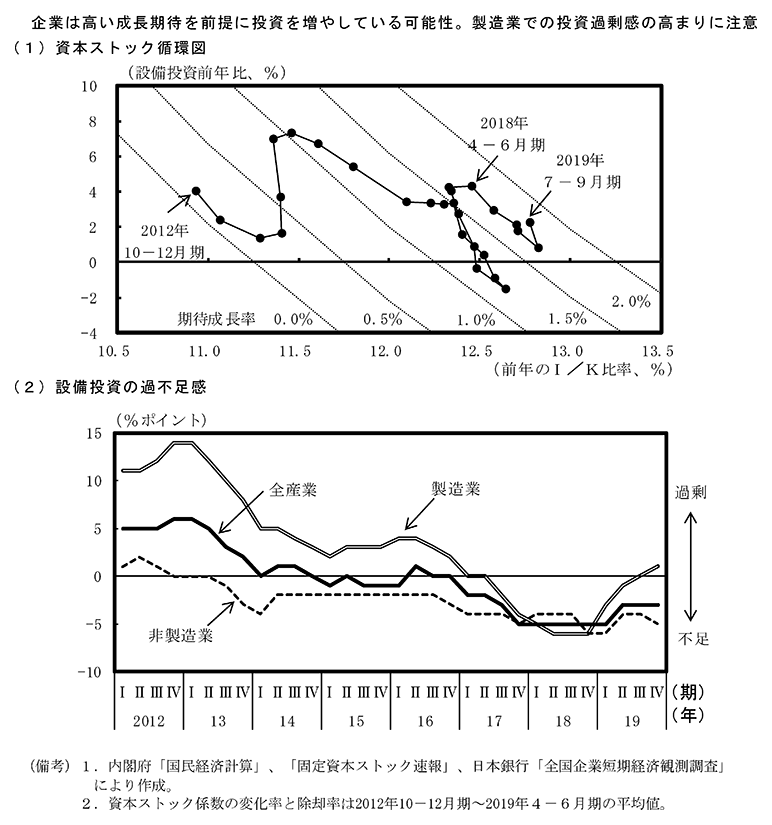
全産業 (前年比)6.9%
製造業 (前年比)6.8% (全産業に対する寄与度)6.7%
非製造業 (前年比)13.8% (全産業に対する寄与度)0.2%

