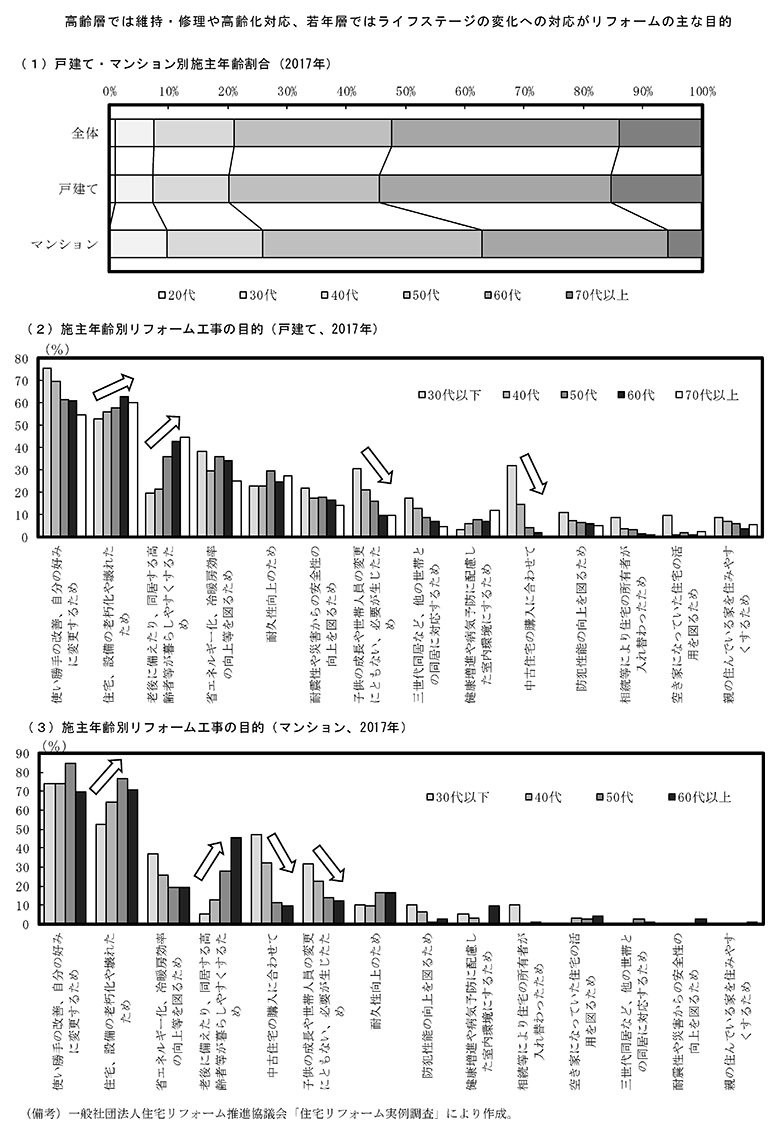第1章 日本経済の現状(第2節)
第2節 人口減少・高齢化が進む家計部門の動向
前節では、我が国経済全体を取り巻く世界経済の環境変化が外需を下押しする一方、内需は底堅く推移することで、GDPのプラス成長を2019年第3四半期まで4四半期連続で実現してきた姿を概観した。2019年10月には消費税率の引上げや大型台風による広域に渡る被害も発生したことから、第4四半期は厳しいとの見方が多いものの、週次や月次の動きをみる限り、経済活動の基調的な変化は認められず、四半期値が減少に転じたとしても一時的なものにとどまる可能性が高い。
本節では、こうした底堅さを実現してきた家計部門の動きについて、まずは消費や住宅投資を支える所得環境の動向を確認する。その後、消費について、世帯構成といった構造的な変化を勘案した動向を概観する。同様に、住宅投資についても同様の視点から動向を概観する。
1 雇用と所得の動向
(賃金上昇と雇用増を通じて総所得は緩やかに増加)
消費や住宅投資の基礎となる所得について、総所得を構成する就業や雇用をみると、人口減少の影響もあり、64歳以下の男性就業者はおおむね横ばいとなっているが、労働参加率の継続的な上昇に支えられ、64歳以下の女性就業者数は増加が続いている。また、65歳以上の高齢者については、男女ともに増加が続いており、これは人口と労働参加率の両面から底上げが図られている(第1-2-1図)。
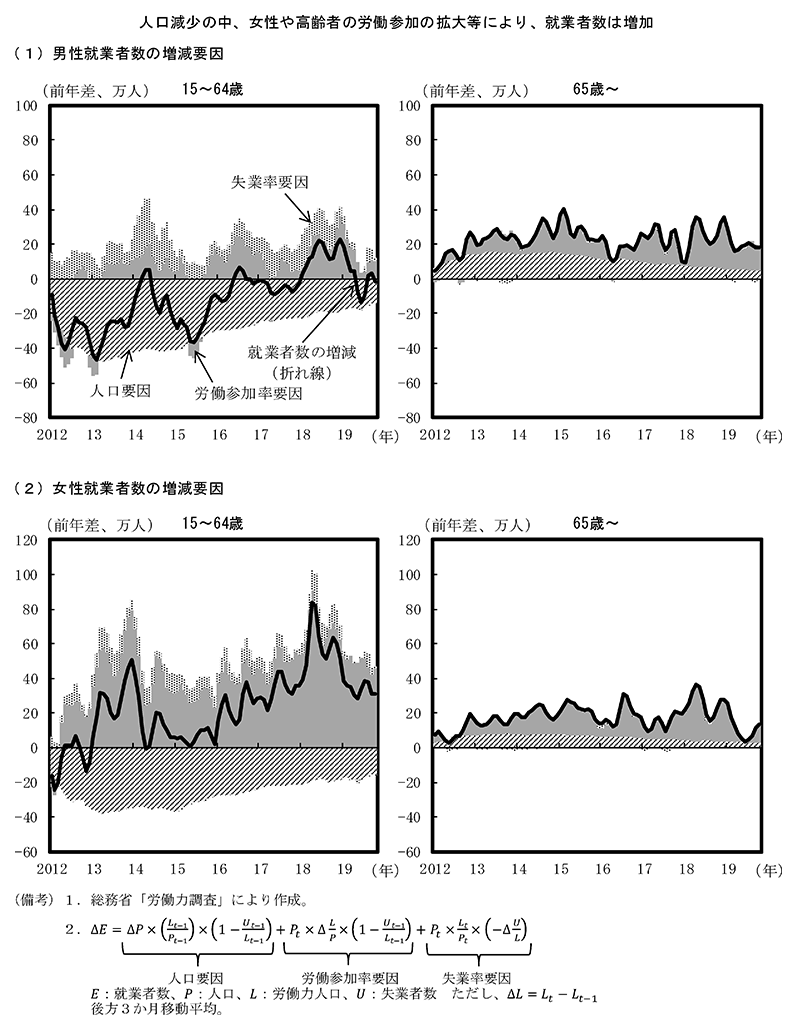
こうした人数要因に加え、名目賃金も継続的な増加(前掲第1-1-6図)を続けていることから、両者の積である名目総雇用者所得も増加が続いている。また、物価上昇率が低調であることから、実質総雇用者所得についても増勢が継続している(第1-2-2図)。
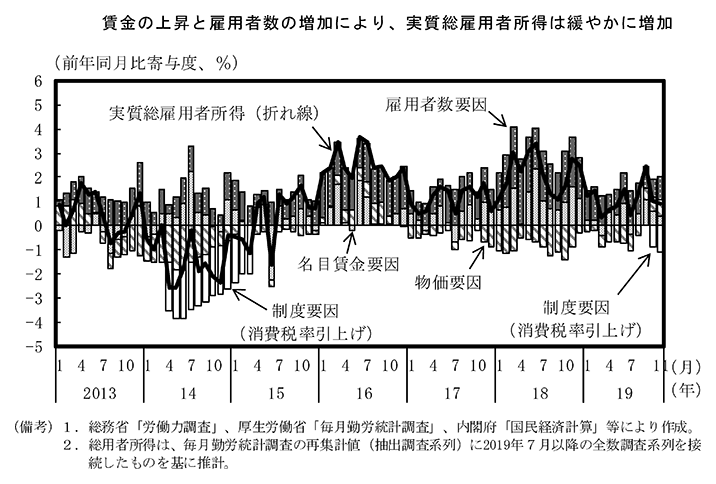
ただし、第1節でも触れたとおり、海外経済の減速によって外需依存度の高い製造業部門の生産が弱い動きとなっていることから、2019年年央以降、新規求人数といった先行性のある指標には弱い動きがみられるようになっている。また、民間転職市場の求人数についても、全体としては緩やかな増勢がみられるが、製造業に含まれるとみられるメーカーからの求人数は頭打ちとなっている。日銀短観の雇用判断DIは、不足超が続いているものの、製造業の不足超幅は縮小しており、外需の弱さが雇用環境に波及するか否か、注視が必要な状況である(第1-2-3図)。
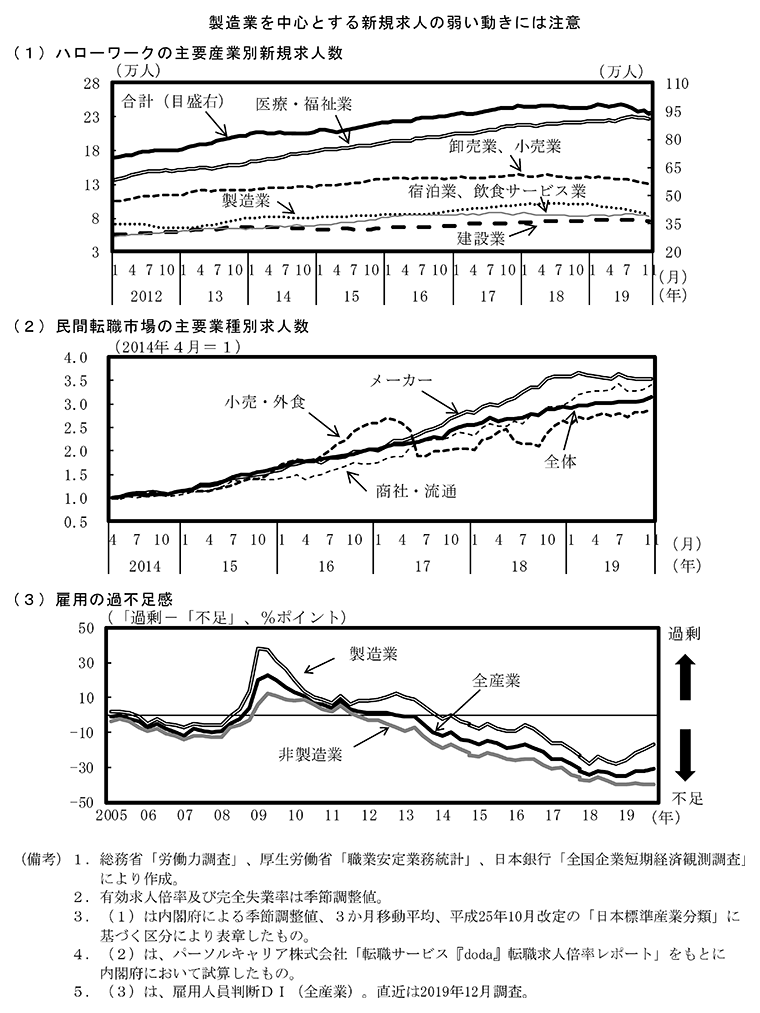
(税や社会負担は増加したものの、可処分所得は増加し、家計資産も増加)
家計レベルでの所得動向について、国民経済計算上の家計可処分所得の推移をみると、税や社会負担は増加しているものの、雇用者報酬等の増加が大きく上回っており、可処分所得は2018年度まで増勢を維持している。また、可処分所得には含まれない医療・介護給付等の現物給付(現物社会移転)も年々増加している。こうした動きもあり、家計の金融資産残高は10年連続の増加となり、2018年度には1,800兆円を超える水準となっている(第1-2-4図)。2019年についても、月次の雇用及び賃金動向を踏まえると、マクロ的には可処分所得の増勢が見込まれる。
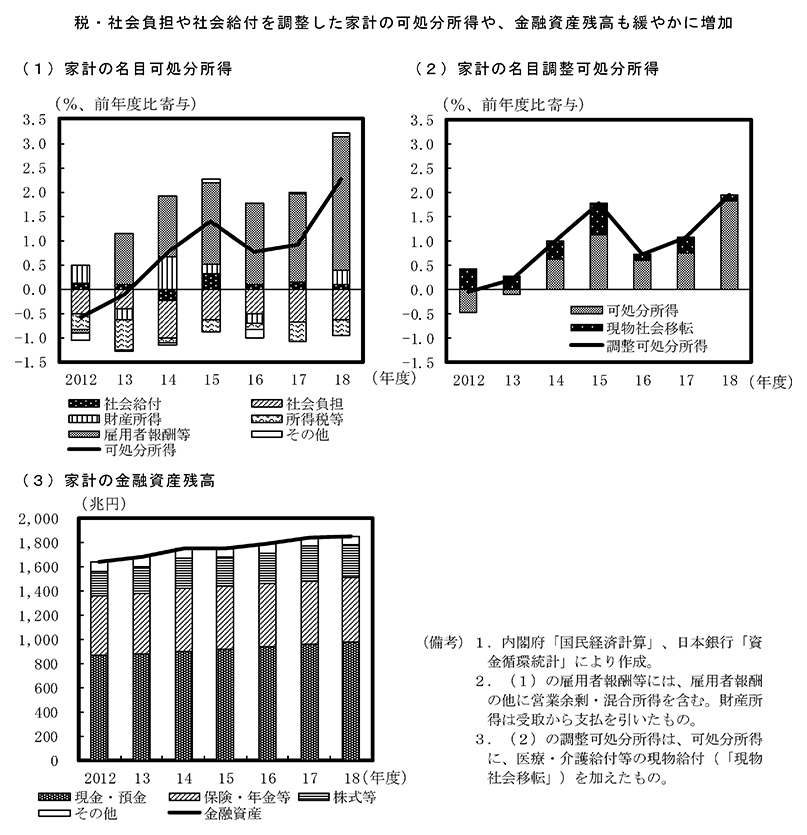
次に、こうした所得の動きを世帯の類型別にみていこう。総務省「家計調査」の総世帯のうち勤労世帯について、世帯主年齢を3つ(若年、中年、高齢)に区分して可処分所得の変化を2016年からの累積でみると、世帯主年齢39歳以下の若年世帯と40歳から59歳の中年世帯では、勤め先の収入が堅調に増加している。一方、直接税や社会保険料等の負担は、中年世帯よりも若年世帯の方が軽く、それらを差し引いた可処分所得は、中年世帯では毎年1%を下回る伸びにとどまるものの、若年世帯では1%を超える増加となっている。世帯主年齢が60歳を超える高齢世帯においては、社会保障給付(年金)があるものの、この伸びは小さい。ただし、ここ数年は、高齢者の就業が進む中で、勤め先の収入増が大きく貢献しており、可処分所得は、他の年齢階層を上回る増加となっている(第1-2-5図)。
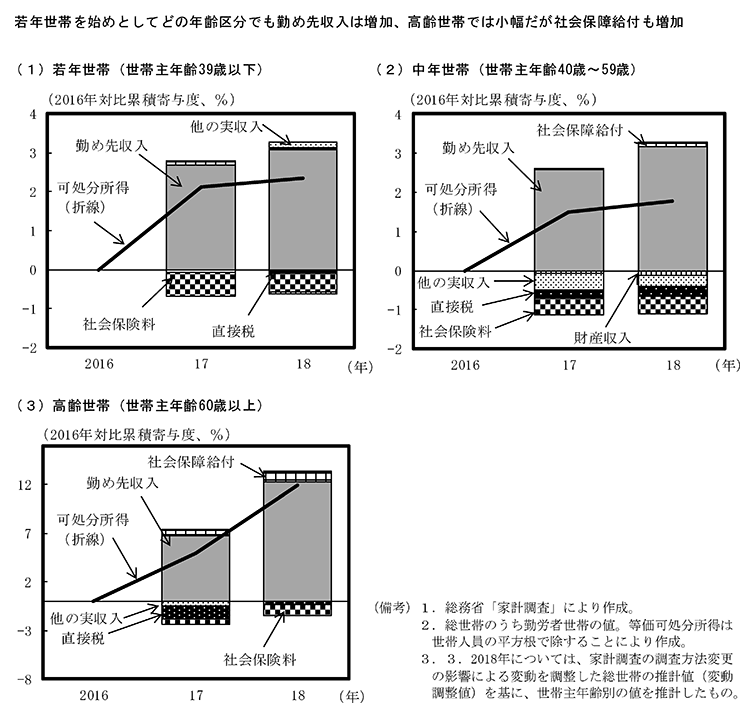
最後に、同じく世帯主年齢別の資産動向も確認すると、中年世帯や高齢世帯では大きな変化はみられず、それぞれ資産が負債を上回っており、純資産保有状態が継続している。特に、高齢世帯の平均的な純資産残高は2,000万円前後で推移しているが、保有資産の大半は現預金に振り向けられており、有価証券投資は大きくない。若年世帯は従前より負債超過となっているが、ここ数年は負債額を増やしており、純資産のマイナス幅が拡大している。この背景には持ち家率の上昇があり、若年世帯の持ち家率は2012年からの6年間で10%ポイント程度の上昇となっている。金利水準がゼロ近傍にあること、また、雇用所得環境が良好なことが何れも若年世帯の住宅購入を後押ししているとみられる(第1-2-6図)。
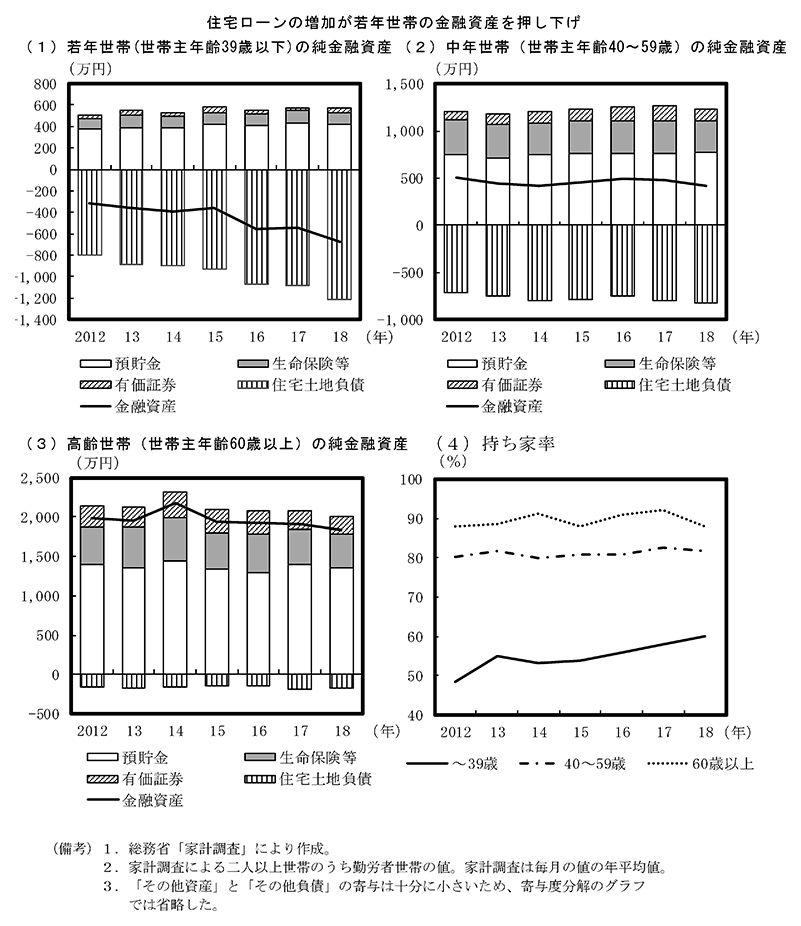
2 緩やかな持ち直しの続く消費
(消費税率引上げの影響は限定的)
前項では、ここ数年の雇用・所得環境が底堅いこと等を確認した。これらの基礎的な条件の好調さを背景に、家計消費は、振れを伴いながらも、緩やかな増勢を維持している(第1-2-7図)。
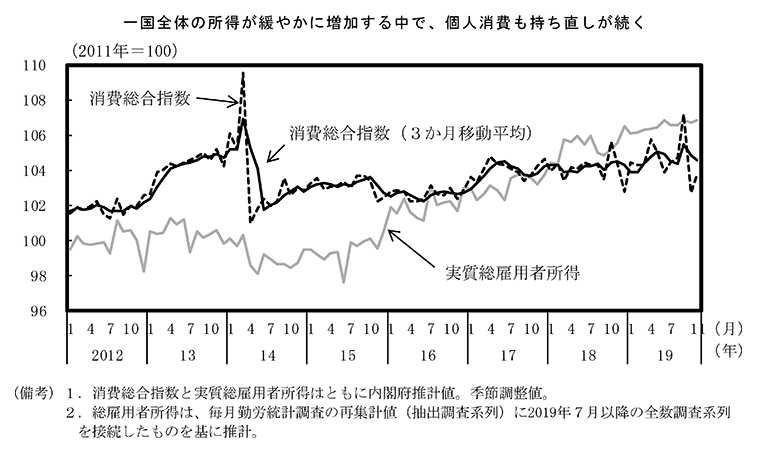
こうしたなか、2019年10月には消費税率の引上げが実施された。食料品等は8%据置きの軽減税率が適用されるが、基本的には10%となったことから、2%ポイント分の影響について、2014年4月の5%から8%への引上げ時のような変動が生じるか否かに関心が高まっていた。全体的な評価を下すには、十分なデータが揃ったとはいえないものの、2019年1月半ばまでの小売販売の動向を商品別に確認する限りにおいて、総じてみれば、消費税率引上げに伴う駆け込み需要とその反動減は前回ほどではないとみられる。
具体的な商品別販売動向をみると、消費税率引上げに伴う対応として、自動車税の減税措置により購入者の実質負担が相殺されていると考えられる自動車販売については、駆け込み幅は前回に比べて大きくなかった。しかし、10月は、一部自動車メーカーの部品の不具合に伴う自動車の生産台数の減少や台風被害に伴う工場の生産停止といった供給側の影響もあり、結果として大幅な落ち込みとなった。ただし、11月以降、前年比のマイナス幅は縮小しており、我が国の年間販売台数を踏まえた実勢を勘案すると、今後は自律的な回復をみせることが期待される。
次に、家電販売については、9月に大きく増加した点は2014年と同じであるが、7月前半の天候不順に伴うエアコン等の販売不振が同月後半から8月上旬に振り替わったことで、税率引上げ前の売上げ増加の一因となった。このため、10月以前の3か月程度を均してみた家電の販売の増加は前回ほどではなかったことが、図からもうかがえる。10月の家電販売は、台風とその後の大雨による販売機会の喪失があったことから低迷したものの、月を追うごとに水準は回復しており、反動減は限定的と見込まれる。
また、業態別にみると、化粧品を中心に駆け込みによる売上増がみられたドラッグストアについては、家電販売と同様に、台風等の影響もあって、10月に売上げが減少したが、その後は前年並みにまで持ち直してきている。最後に、軽減税率品目を多く取り扱うスーパーの販売額は、酒類を中心として若干の駆け込みとその反動減がみられたものの、11月以降は持ち直しの動きが続いており、均してみれば、基調に影響はないと見込まれる(第1-2-8図)。
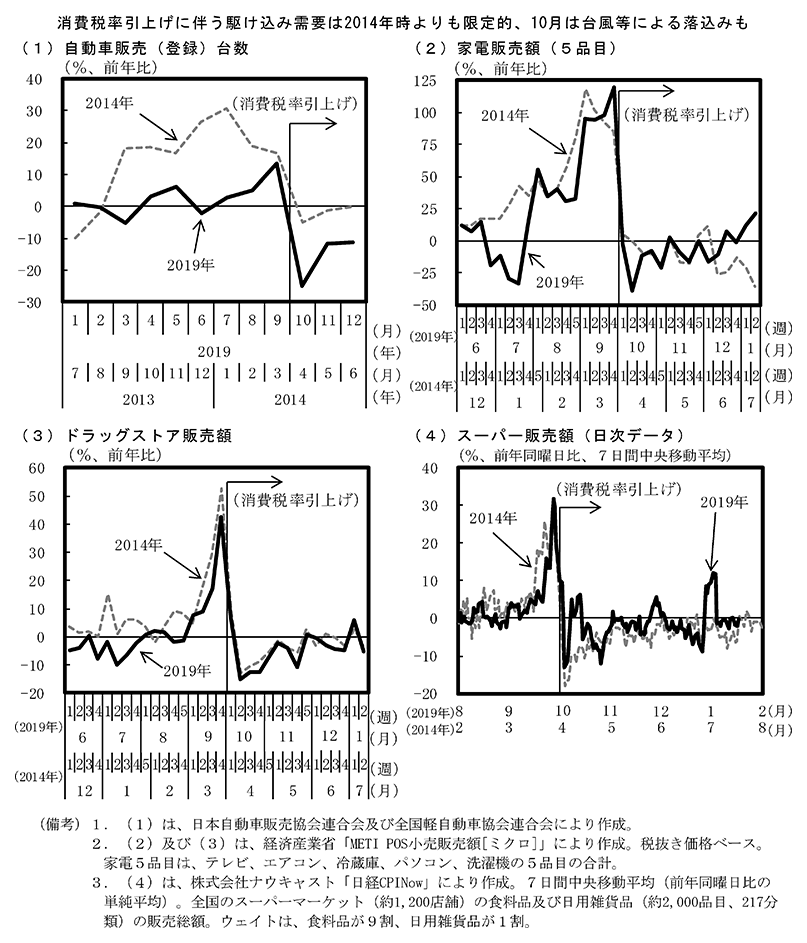
次に、サービス消費についても、旅行や外食といった代表例について、消費税率引上げ前後の動きを確認すると、旅行は、消費税率よりも、春の10連休や天候不順の影響によって振れている様子が明らかである。特に、10連休に伴う4月の増加、長雨の影響のあった7月や台風の影響のあった8月や10月の減少が年間の動きを大きく規定している。
他方、外食については、財消費で生じた駆け込みと反動減に連動して客足が9月と10月で増減したとの指摘もみられるが、台風とその後の大雨の影響が顕著な10月においても、客単価は上昇しており、11月には客数と客単価のいずれもプラスに寄与することで前年比は伸長している(第1-2-9図)。
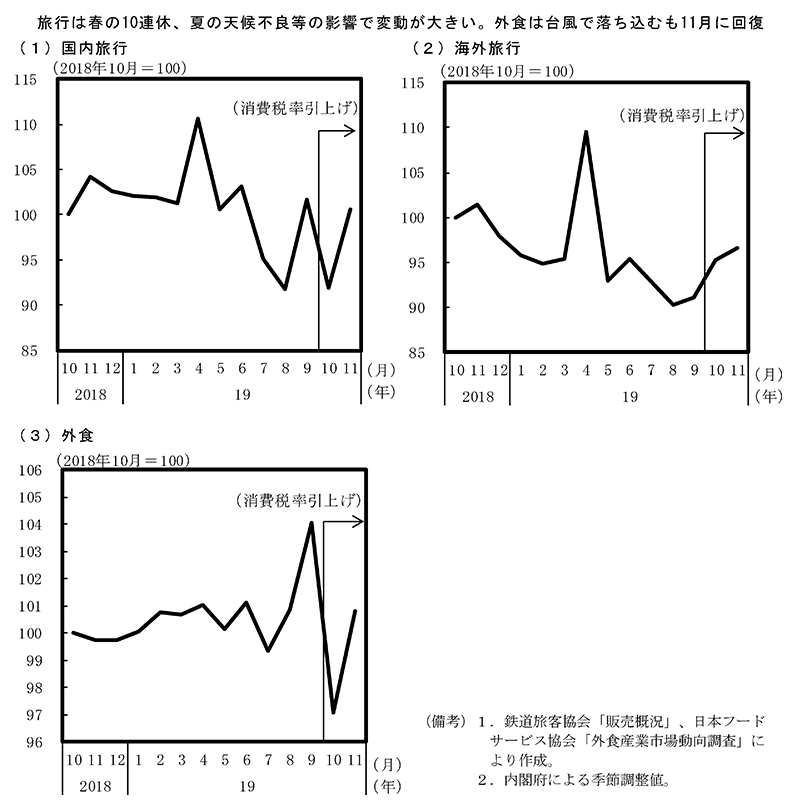
まとめると、商品やサービスの販売動向について、迅速に確認できるデータをみる限り、消費税率引上げ後にみられた落ち込みには天候要因が大きく作用しており、そうした影響が無くなった11月には、平年並みの動きへと転じつつあることが確認される。
また、消費者物価指数は、軽減税率や幼児教育・保育の無償化の影響もあり、消費税率引上げ後もほとんど上昇していないため、実質所得の減少を経由した効果については、大きくないと見込まれる(前掲第1-1-9図)。もちろん、幼児教育・保育の無償化を通じた実質所得のプラス効果を受ける世帯と、そうした効果のない世帯の間では、所得効果の現れ方が異なる点には留意が必要であろう。
なお、前回に比べて緩やかながらも長期間にわたって低下を続けた消費者マインドは、10月以降上昇に転じている。12月段階では、過去平均の41.7という水準を回復するには至っておらず、引き続き注意は必要だが、マインド面から消費を下押しする恐れは次第に低下しており、消費税率引上げが消費低迷のきっかけとなる可能性は高くないと見込まれる。
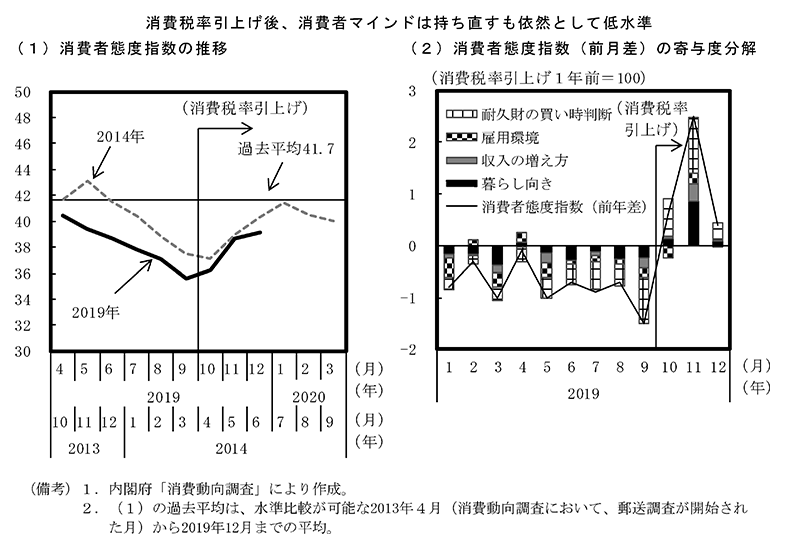
(消費の増加テンポが鈍化する要因には高齢世帯数の増加)
消費税率の引上げは、2019年の消費動向を概観する上で重要なイベントであったが、より長い目で家計消費全体の推移をみると、所得の増加に対する増勢が緩やかになっているとも見受けられる。そこで、家計消費全体の動きについて、可処分所得や金融資産といった所得・資産面からの影響に加え、高齢化要因を含めて分解すると、過去17年の間に消費全体の累積増加が10%程度であったのに対し、可処分所得要因は7%程度のプラス、純金融資産要因は6%程度のプラスとなっている。しかし、高齢化要因の押し下げが続いており、累積では3%程度下押ししていることが分かる(第1-2-11図)。
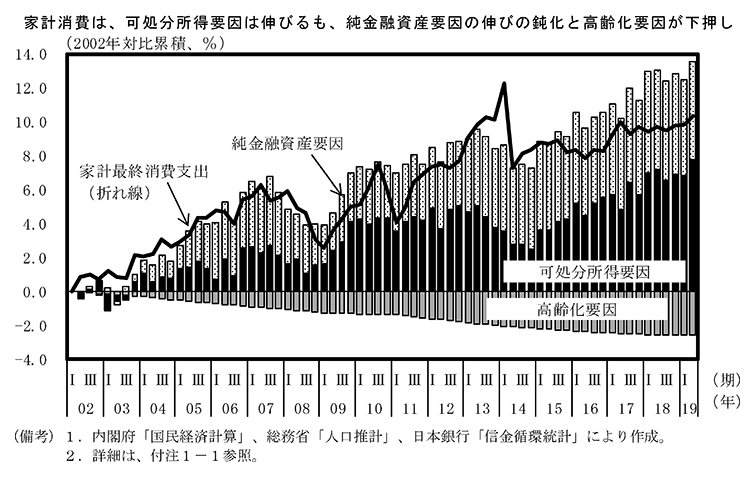
では、高齢化要因が消費を下押しする、とは具体的にどういうことなのだろうか。そこで、総世帯を世帯主の年齢によって高齢世帯(世帯主年齢が65歳以上)と現役世帯(同64歳以下)に分けて、高齢化の影響を考察する。まず、高齢世帯と現役世帯の世帯数について確認すると、我が国は、現役世帯数が減少する一方、それを上回るペースで高齢世帯が増加しており、その結果、総世帯数も年々増加している。こうした世帯構成の変化と両世帯の平均消費額のデータを基に、マクロの消費額(家計最終消費支出)を世帯属性ごとに按分すると、世帯構成と同様に、現役世帯の総消費(世帯数×世帯当たり消費)は減少傾向にあり、高齢世帯の総消費は増加傾向にあることが分かる。
では、それぞれの総消費額を世帯数で割った世帯当たりの消費額はどうだろうか。その動向をみると、現役世帯、高齢世帯のいずれも、2002年以降長い目でみれば、おおむね横ばいとなっている。これは、一人当たりの消費額1は、現役世帯、高齢世帯のいずれも緩やかに増加している一方、世帯人員が減少しているためである。
次に、世帯当たり消費額の水準をみると、現役世帯が年額600万円程度である一方、高齢世帯は450万円程度にとどまる。このことは、世帯当たり消費額の少ない高齢世帯の割合が増すことで、総世帯の平均的な世帯当たり消費額が低下することを意味する(第1-2-12図)。
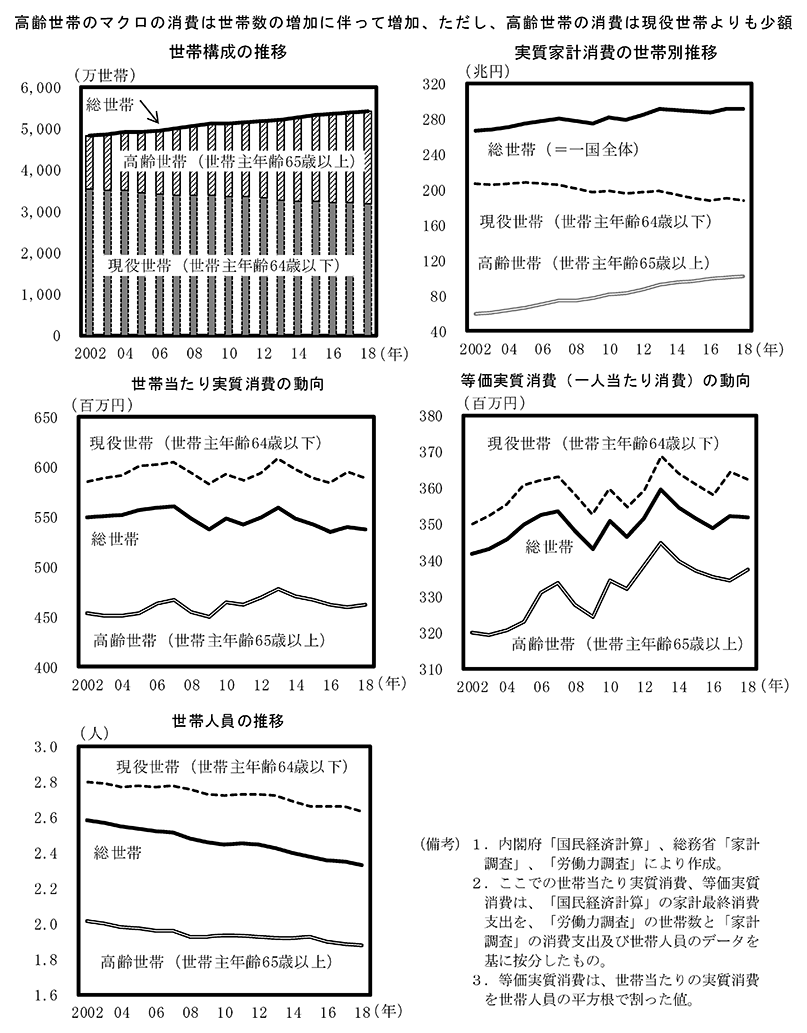
そこで、マクロの家計消費の変化を、①現役世帯の世帯当たり消費の変動要因、②高齢世帯の世帯当たり消費の変動要因、③世帯数の増加要因、④高齢世帯の構成比上昇要因(=世帯構成の変化による平均消費額の押下げ効果)の4つに分解すると、第1-2-12図と同じく17年間の累積で10%程度増えた家計消費に対し、①~③の3つの要因はプラスに寄与しているものの、④の高齢世帯の構成比が上昇することがマイナスに寄与していることが分かる(第1-2-13図)。このように、我が国の消費は、高齢世帯の増加という構造的な要因により、その伸びが抑制されていると考えられる。
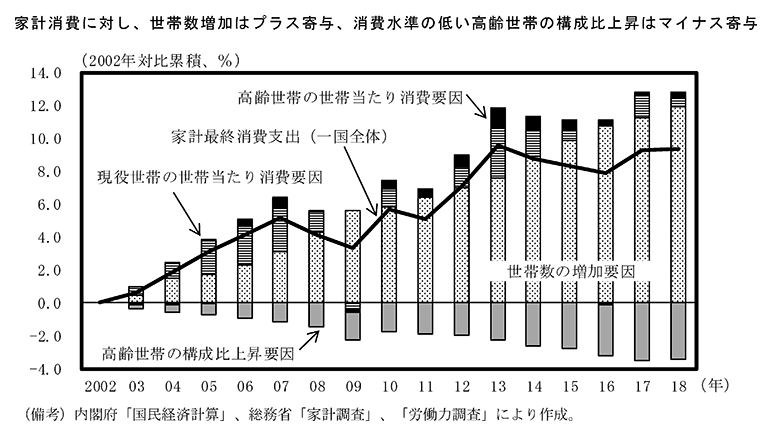
3 弱含みとなった住宅投資
(住宅投資は弱含んでいるが、消費税率引上げの影響は限定的)
2019年の住宅投資について、着工戸数の動向により振り返ると、幾つかの変動要因が指摘できる。まず、2017年から減少傾向が生じている貸家は、2019年に入っても変わらずに減少が続いている。借入金利の低下による採算性の改善に加え、2015年の相続税に係る税制改正の影響などから、貸家は、2015~16年頃にブームが生じていたが、事業者の不正建築問題、金融機関の不正融資問題等が次々に発生したことから投資家が離れ、金融機関においても融資態度の厳格化が進んだ2。こうしたことを背景にいまだ底入れのみえない動きとなっている。
二つ目は戸建及び共同分譲住宅の動向である。全体として、戸建分譲に対して共同分譲は、開発案件の都合から振れの大きな動きをするが、共同分譲の価格は相対的に高水準となっており、例えば、首都圏等のマンション販売動向をみると、高額物件は引き続き好調ではあるものの、いわゆる中価格帯の物件を中心に、成約率の低下と在庫の増加といった調整色のある動きもみられている。
最後の要因は消費税率の引上げと持家の動向である。住宅購入に際しても消費税は課せられるため、税率引上げの影響は生じる。ただし、今回の引上げに際しては、住宅ローン減税の対象期間の延長3等が図られており、購入者の実質負担は相殺されることから、税率変更を意識した購買タイミングの調整は必要ないとされる。しかし、ローンを伴わない購入や高額な持家購入等は措置の対象外になることから、限界的な駆け込みが生じることは想定されていた。そこで、消費税率の引上げの影響について、前回との比較をすると、貸家の継続的な減少もあり、総戸数には駆け込みやその反動といった動きはみられない。しかし、持家については、消費税率引上げの半年前にあたる3月末を見越した受注の増加の影響により、着工戸数は6月頃まで増勢をみせたのちに、減少へと転じている。ただし、増減の程度は前回ほど大きくはない姿となっている。なお、戸建分譲についても同様の影響が生じ得ることから確認すると、ほとんどそれらしい山谷は確認できない。価格帯として、政策措置の対象外になる物件が含まれる比率が、持家では高く、戸建分譲では低いことが影響したものと考えられる(第1-2-14、15図)。
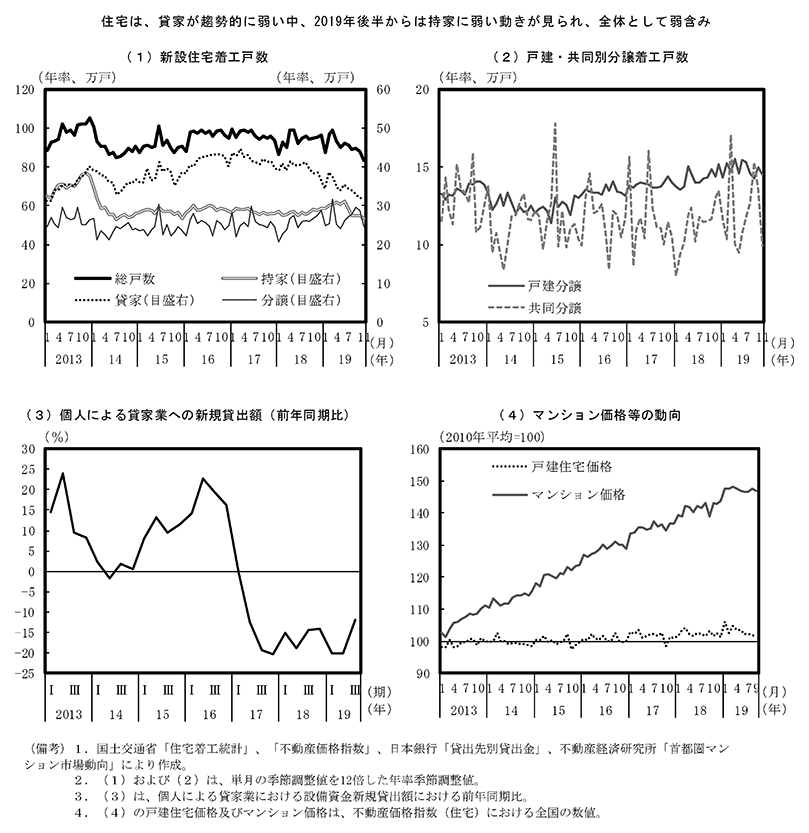
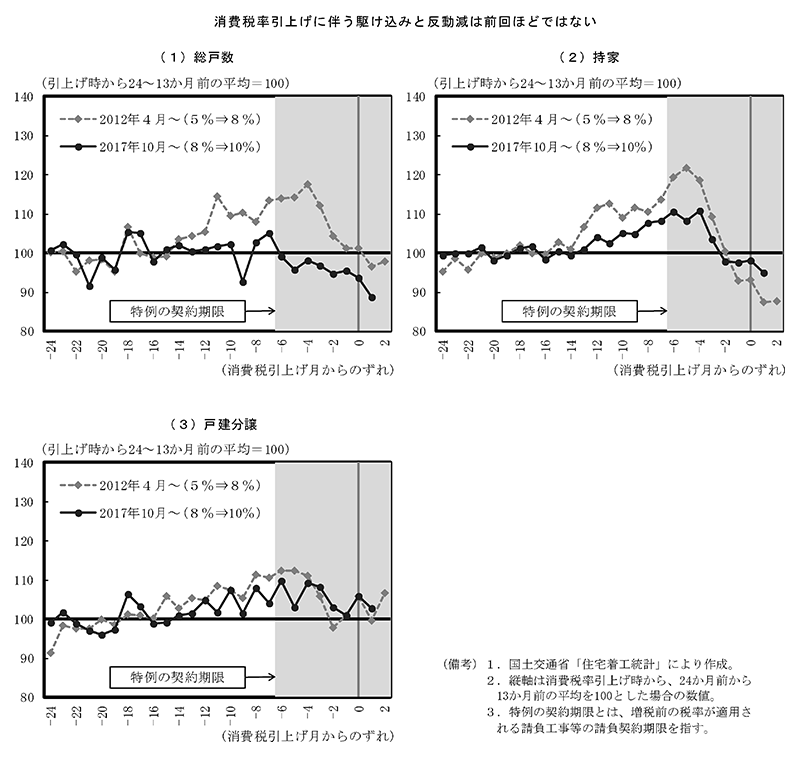
(世帯数がピークを迎える中、重要性を増す中古住宅)
住宅投資についても、人口減少や高齢化といった構造的な変化が影響していることは明らかであり、その先行きを考える上では重要である。特に、総世帯数は今のところ増加しているものの、その世帯規模は小さくなり、かつ、今後は総数が減少に転じていくことが見込まれている。一方、新築の持ち家志向が強かったこともあり、住宅ストック(戸数)は増加が続いている。2018年時点では、世帯数が5,389万世帯である一方、住宅戸数は6,241万戸となっており、世帯数以上の住宅が存在していることになる。こうした動きを背景に、空き家戸数も増加が続いており、2018年には849万戸、全戸数に占める空き家率は13.6%となっている(第1-2-16図)。
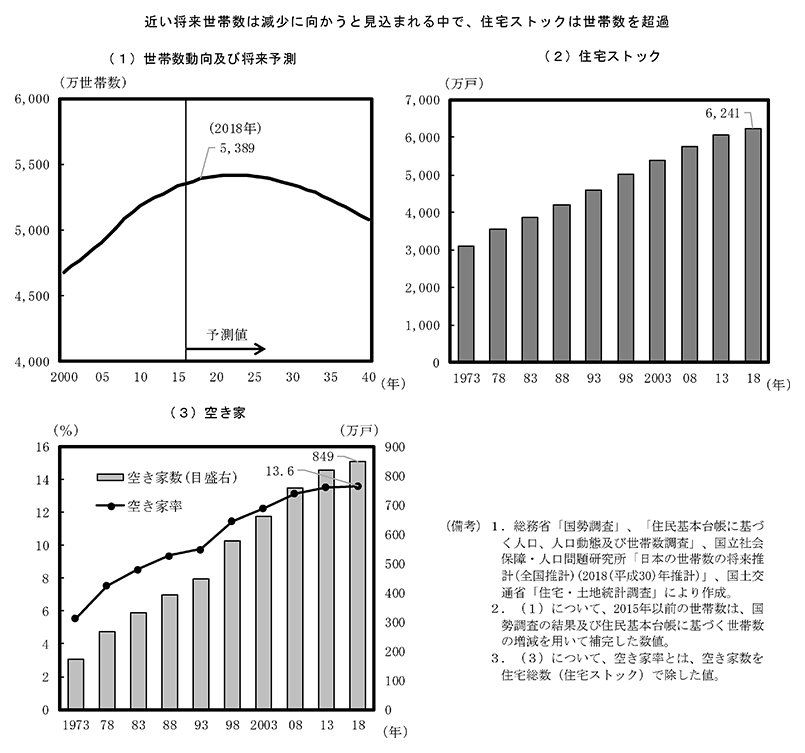
こうした過剰ストックを抱える状況において、緩やかながらも中古住宅市場は拡大を続けている。中古マンションの売買成約件数は、首都圏では2010年の3.0万戸から2019年には3.9万戸へと増加し、近畿圏では同じく1.4万戸から1.8万戸へと増加すると見込まれている。中古戸建の売買件数はマンションほどの件数には至らないものの、いずれの地域においても増加している。こうした中古住宅市場の拡大は、購入者側の新築志向が薄れてきたことも影響している。国土交通省が実施した意識調査によると、新築を購入したいとする者の割合は、2011年に6割を超えていたものの、2018年には56%と約4%ポイントの低下となっている(第1-2-17図)。
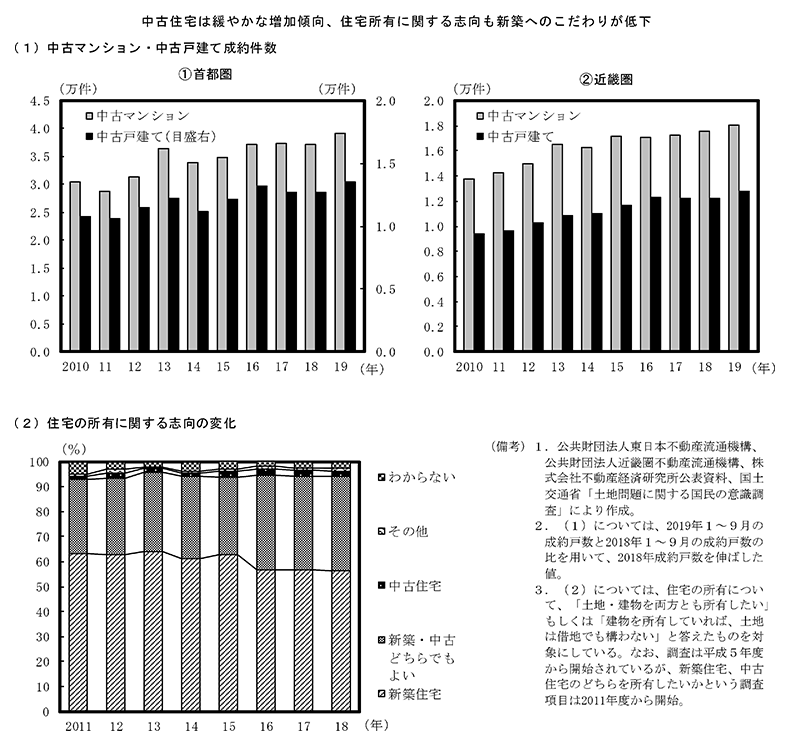
中古住宅市場の拡大には、意識だけでなく、価格や立地といった物件固有の購買要因が重要であることは言うまでもない。事実、中古住宅の購入を決めた理由を問う調査結果からは、回答者の6割弱が立地環境の良さを指摘している。また、中古物件固有の課題については、リフォームをすることによって、あるいはリフォーム済となっていることによって快適さが確保できると回答している者が3割を超えている。さらに、中古マンションと新築マンションの価格(東京都区部)を比べると、価格差で2,600万円、比率では中古マンションの価格は新築マンションの6割程度となっており、こうした価格差も市場拡大を支える要因となっている(第1-2-18図)。
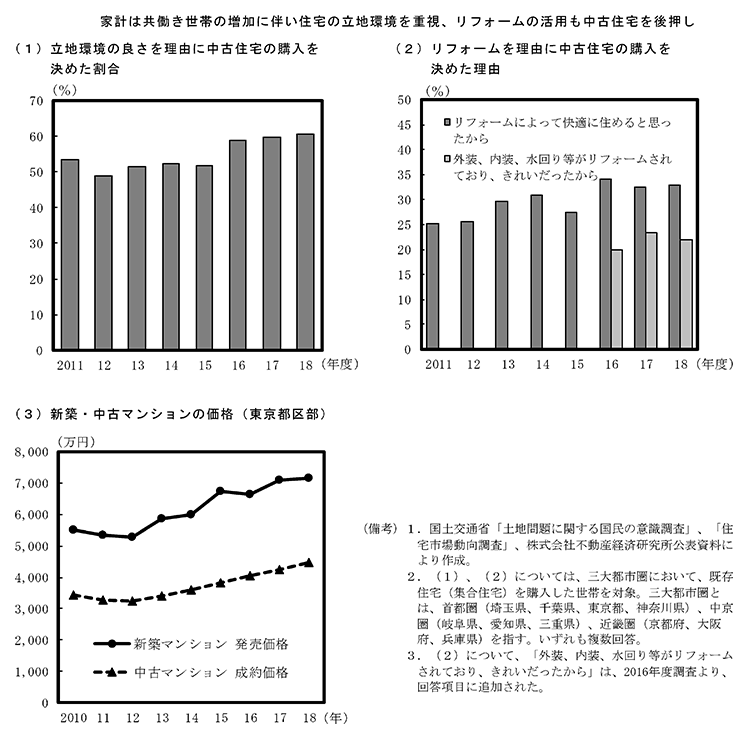
(ライフステージに応じた住替えを促す住宅リフォーム)
中古マンションや中古戸建市場が拡大し、取引件数の増加によって価格設定の透明性と持ち込み物件の増加が実現すれば、副次的に拡大が期待されるのはリフォームサービス需要である。リフォーム市場の規模について、受注件数と金額から確認すると、2019年第2四半期において、住宅向けは年630万件、3.8兆円、非住宅4向けは同320万件、8.2兆円程度となっている。住宅向けの630万件のうち、210万件、3.1兆円程度は改装や改修であり、420万件、0.7兆円程度は施設の維持修理となっている(第1-2-19図)。市場規模はいまだ小さいが、ストック戸数と世帯数からすれば、大きな伸びしろのある状態ともいえる。
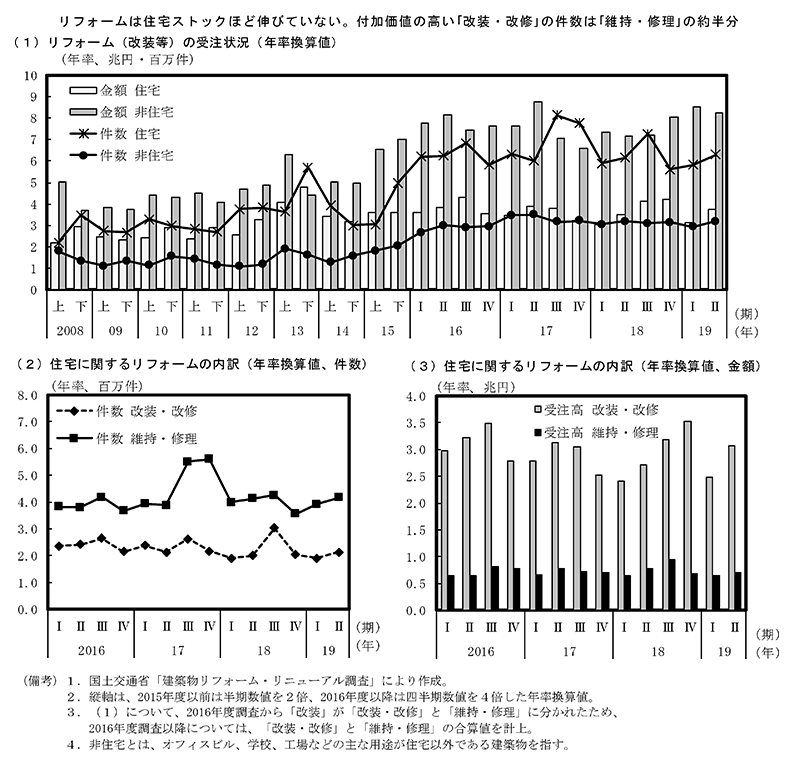
リフォームを依頼する施主の年齢や工事内容について調べると、施主年齢については、戸建の方が高めとなっており60歳台が中心、マンションでは50歳台が中心となっている。このうち、戸建やマンションのリフォーム内容と年齢の関係をみると、いずれにおいても、加齢とともに目的の中心となるのは、住宅の老朽化対応や損壊の修理、あるいは同居人の傷病都合による改修である一方、世帯人員数変化や中古住宅の購入そのものに伴うリフォームは若年層の比率が高く、加齢とともに減少していく。
今後の住宅投資をみる上では、高齢化や人口減少によって生じている需要内容の変化を踏まえ、新規の着工戸数だけでなく、既存ストックへの投資である各種リフォーム需要の動向についても注視していくことが必要である。