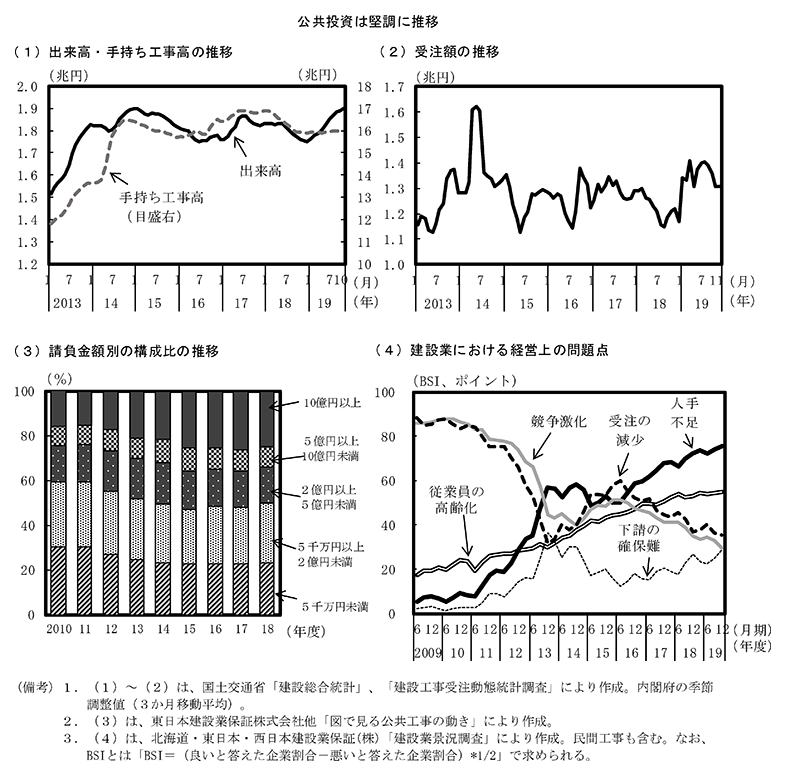第1章 日本経済の現状(第1節)
第1節 日本経済の概観
本節では、2019年における我が国経済の動きを概観し、外需が弱い一方で内需が底堅い状況、いわゆる「内外需のデカップリング」を始めとする特徴や課題について論じる。
1 厳しい対外環境の下で成長を続けた日本経済
(外需が弱い中で、内需を中心に緩やかな回復が続く)
2019年度の我が国経済は、前年同様、外需が弱い中で、内需がけん引する姿となっている(第1-1-1図(1))。四半期別に実質GDP成長率の動向をみると、4-6月期から7-9月期にかけては、消費だけでなく、設備投資や公共投資等の公需も堅調に推移したことから、内需全体の実質GDP成長率に対する前期比寄与度は、4-6月期0.8%増、7-9月期0.6%増と強めに推移した(第1-1-1図(2))。
その一方、この期間の外需(純輸出)は、輸出の弱さに加えて、輸入が増加したことで、前期比寄与度が4-6月期-0.3%ポイント、7-9月期-0.2%ポイントと成長下押し要因となった。輸入の増加については、4-6月期は、暖冬の影響で1-3月期に燃料の輸入が減少していたことの反動増が、7-9月期は、2019年10月に実施された消費税率引上げ前の駆け込み需要に対応するための商品の仕入増が、それぞれ要因となっている。
これらの結果、2019年度前半の実質GDP成長率は、内需の強さが外需の弱さを上回り、前期比プラスで推移した。このように、我が国の景気は、外需は弱いものの、雇用・所得環境の改善等により、内需を中心に緩やかに回復している。
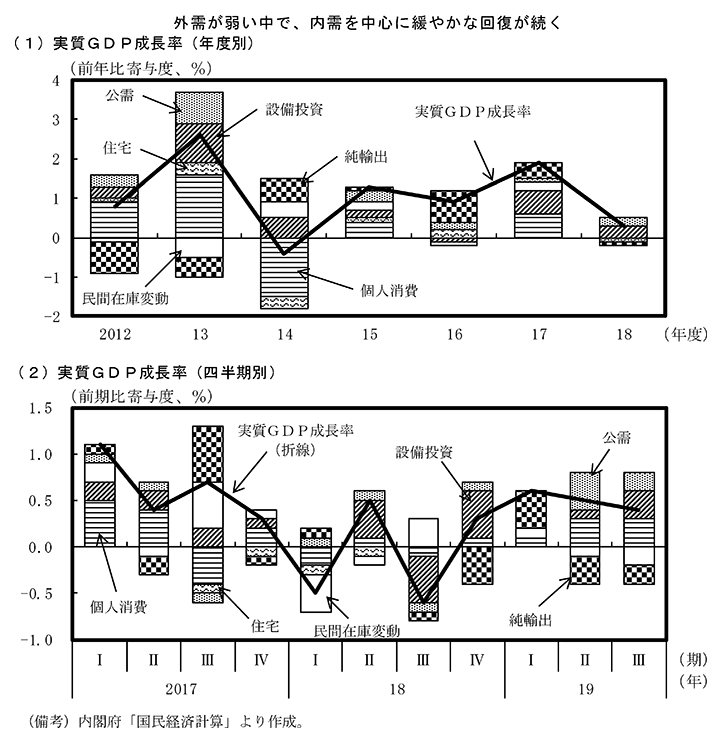
(外需が弱い動きとなった背景には世界経済の減速)
1年半もの長きにわたり、我が国経済の重石となっている外需の動向について、より詳しく確認する。
まず、我が国を取り巻く世界経済の状況をみると、世界の実質GDP成長率は、2017年3.8%から2018年に3.6%と低下し、さらに、2020年1月時点のIMF見通しによると、2019年は2.9%まで急減速する見通しとなっている(第1-1-2図(1))。特に、2019年は、見通し改定の度に下方修正が繰り返され、世界経済の減速は、2019年の年初から月を追うごとに、その深刻さを増していった。
国・地域別に実質GDP成長率の動向をみると、中国経済は、2016年から2017年にかけて、世界経済が回復する中で成長ペースの鈍化が一服していた。しかし、2018年以降、過剰債務の削減を進める中で、いわゆる米中貿易摩擦の影響が加わり、成長率が再び低下した(第1-1-2図(2))。中国経済減速の影響は、米中貿易摩擦の当事国であるアメリカよりも、中国向け輸出比率が相対的に高いドイツを含むユーロ圏に先に現れ、同地域も2018年以降、成長率が伸び悩んだ。アメリカ経済は、内需の力強さに支えられ、2018年までは成長率は堅調に推移したものの、2019年には中国向けを中心に輸出が弱い動きとなり、成長率は低下に転じた。このように、2019年は、いずれの主要国・地域の経済も減速しており、我が国の輸出にとっては、厳しい対外環境であったといえる。
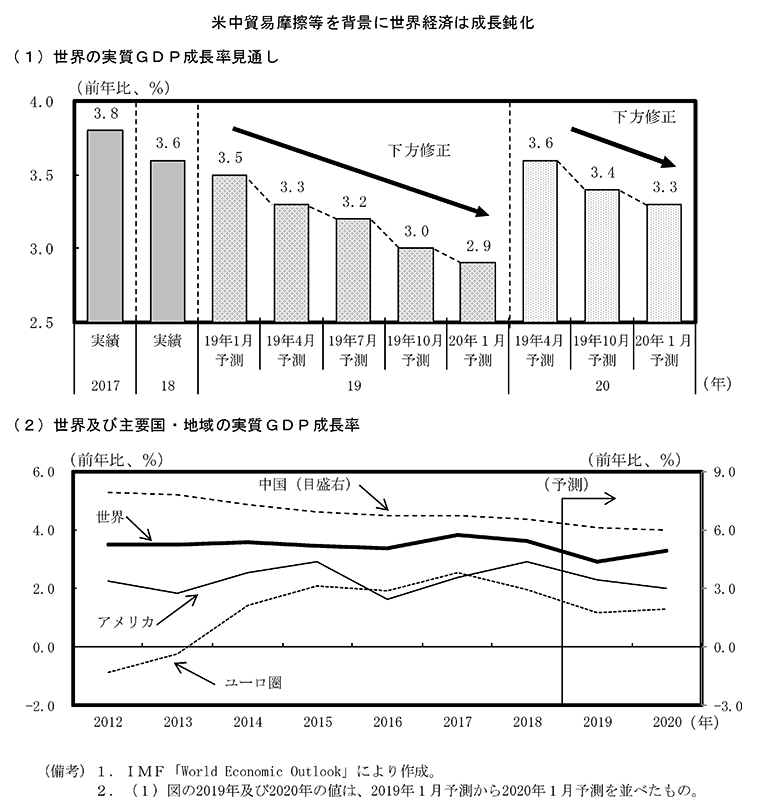
(内外需のデカップリングの背景には外生ショックの弱さと自律性の高い循環の存在)
以上で確認した外需の弱さは、輸出減少を通じて、生産を減少させるとともに、企業収益を悪化させ、設備投資の下押し要因となり得る。また、生産や企業収益の減少が起これば、雇用や賃金への悪影響を通じて個人消費も下押しされかねない。このように、外需の不振が深刻化すれば、その影響は内需ヘと波及していくと懸念されるものの、2019年第3四半期までのところ、内需は緩やかな持ち直しを続けている。そこで、2019年の我が国経済の特徴である内外需のデカップリングの状況について、過去の景気循環との比較で更に詳しくみてみよう。
まず、現在と過去3回の景気循環において、輸出が減少傾向を示した期間を比較することで、今回の設備投資や個人消費の動向に関する特徴を確認する。具体的には、各景気循環について、輸出がピークとなる四半期を基準期として指数化し、基準期前後の動向を比較する。
この分析から、設備投資や企業部門については、以下の特徴が指摘できる(第1-1-3図)。
第一に、今回の輸出は、ピークアウトしてから5四半期が経過したものの、その下落ペースは過去の景気循環と比べて緩やかなものにとどまっている。アメリカのITバブル崩壊や、リーマンショックといった需要を急激に縮小させる経済ショックに見舞われた第13循環や第14循環とは対照的である。また、輸出の影響を受けやすい鉱工業生産の減少も、今回は過去の循環時の動きと比べれば緩やかなものにとどまっており、企業収益(営業利益)も底堅く推移している。
第二に、過去の景気循環では、輸出の減少が、生産を減少(=設備稼働率を低下)させるとともに、企業収益を下押しすることで、設備投資の抑制につながっていた。しかし、今回の設備投資は、2018年に振れがみられたものの、その後は増勢を維持している。例えば、第13循環の設備投資は、輸出が減少し始めてから2四半期後までは増加を続けたが、その後に減少へと転じ、景気は後退局面を迎えた。今回の設備投資は、第13循環時よりも息の長い増加を続けており、その背景としては、本章第3節で論じるとおり、生産能力増強を目的とする投資ではなく、人手不足が進む中で、合理化・省力化を目的とするソフトウェア投資等の伸長が寄与していると考えらえる。
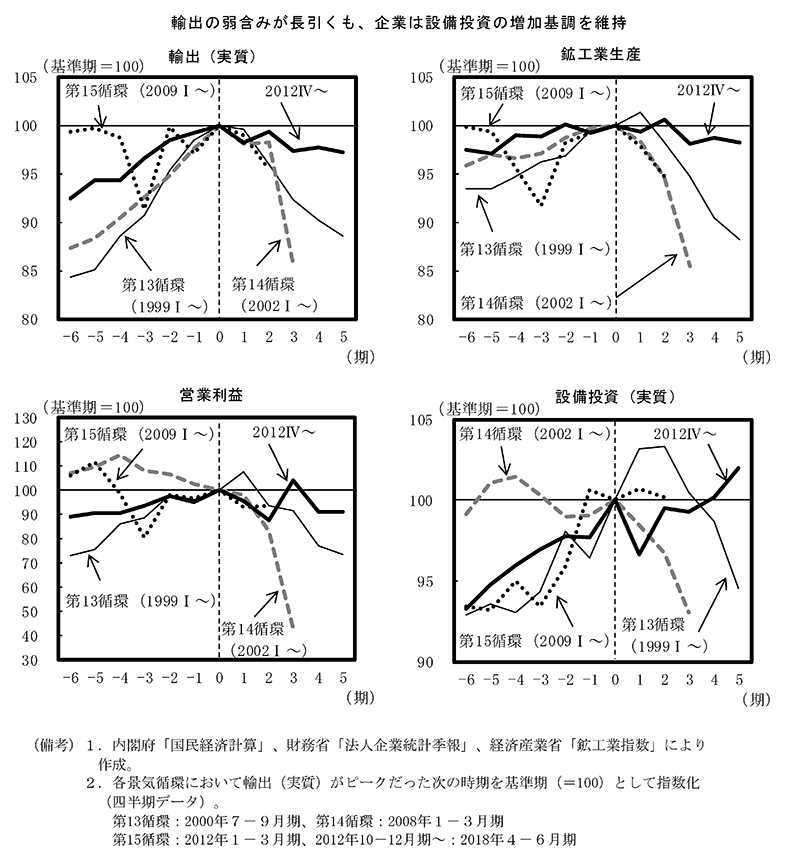
同様に、雇用や個人消費については、次の特徴が指摘できる(第1-1-4図)。
第一に、雇用の前提となる生産活動は、輸出の影響を受けやすい製造業の生産(鉱工業生産)の減少ペースが緩やかなものにとどまっており、また、非製造業の生産活動は緩やかな増加を続けている。非製造業は相対的に海外経済の影響を受けにくいが、第13循環や第14循環時には、輸出の減少からほどなくして非製造業の生産活動も低下していた。こうした非製造業の増勢の継続は企業収益の底堅さにも寄与している。
第二に、雇用者数の約8割が属する非製造業の生産活動が増加基調にある中で、今回は雇用者数の増加が続いており、その結果、雇用者報酬も増加している。過去の循環では、例えば、輸出が減少に転じた後に景気が底入れするまでに時間を要した第13循環では、生産の低下に伴い雇用者数も減少していた。また、景気後退期間が短く、雇用者数の調整に至らなかった第14循環でも、雇用者報酬は減少していた。
第三に、こうした雇用者報酬の動向も反映し、今回の個人消費は、過去の循環とは異なり、輸出が減少に転じてからも1年以上にわたって持ち直しの動きが続いている。過去においても、第13循環では、輸出の減少後、雇用者報酬が伸びている間は個人消費も増加したが、雇用者報酬が減少に転じてからは、消費も頭打ちとなった。
以上を踏まえると、外需が弱い中で設備投資と個人消費の増加基調が続いている要因としては、①外需の減少ペースが景気を一気に冷え込ませるような急激なものではないこと、②外需の影響を受けにくい非製造業の堅調さが企業収益や雇用・所得環境といった我が国のファンダメンタルズを支えていること、が指摘できる。非製造業の堅調さが雇用・所得環境を支え、雇用・所得環境の改善が個人消費を支え、そしてまた個人消費の底堅さが非製造業さらには内需向けの製造業の生産を支えるという、自律的な経済の好循環が機能している面がうかがえる。しかし、こうした循環が今後も持続するかどうかは引き続き注視する必要がある。
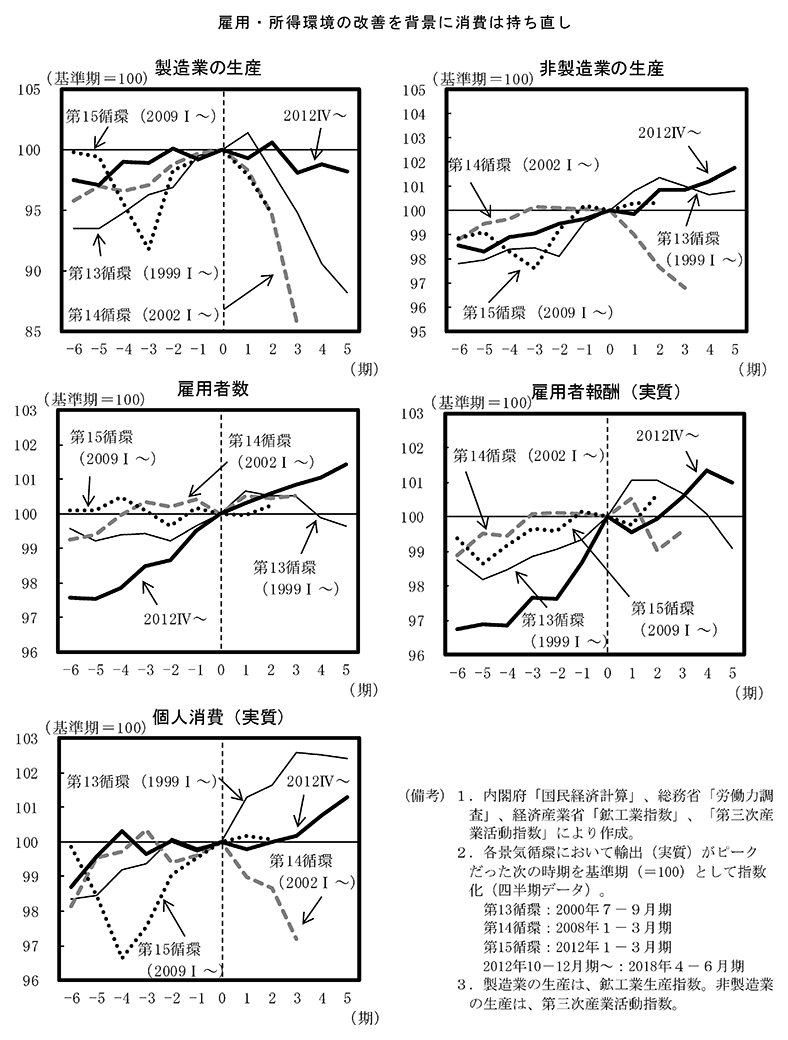
2 人手不足にもかかわらず弱い物価上昇圧力
前項では内需によって外需の弱さを補い、全体としてプラスの成長を続けてきた姿を概観したが、ここでは労働市場の需給環境や賃金の動向、また、その影響を受ける物価動向をみていく。
(労働需給は需要超過が継続)
まず、労働市場の需給を表す指標の動きからみていく。ハローワークを経由する労働需給を示す有効求人倍率は、2018年に過去最高水準の1.63となったが、その後も高水準を維持しており、2019年11月は1.57となっている。一時期の増勢は失われているが、数年単位でみると、需要超過状態が継続している。なお、正社員の有効求人倍率についても、同月1.13となっており、過去と比べれば高水準にある。
こうした労働需要の強さを背景として、2019年の完全失業率も1994年以来の2%台で推移している。完全失業者の求職理由別の人員動向をみると、総数が減少する中、旺盛な労働需要を反映して、非自発的失業よりも自発的失業が多い状態が続いている。また、新たに求職する者は、総人口の減少が進むなかにあっても、労働参加率の上昇により横ばいで推移している。
また、雇用者側の労働状況を示す雇用失業率と雇主側の労働状況を示す欠員率の交点の推移は、UV曲線(ビバレッジカーブ)1として知られている。1980年代や90年代に比べると、2010年代の曲線と45度線との交点は1%程度原点から離れており、2000年代に高まった均衡失業率はあまり変化していない様子がうかがえる。しかし、2019年は、欠員率と雇用失業率がともに低下する傾向がみられていることから、長期的な雇用改善が進む中で、構造的な失業者の減少が生じている可能性も示唆される(第1-1-5図)。
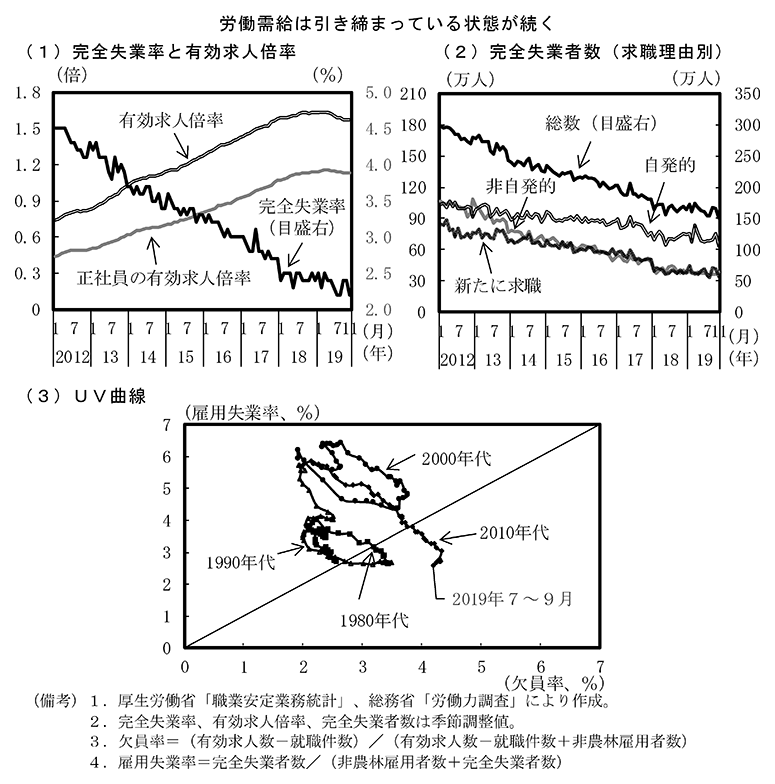
(労働需給は引き締まり、労働時間が減少する中、賃金は緩やかに上昇)
次に賃金の動きを確認しよう。現金給与総額は、特別給与に振れのあった7月を除き、2019年は前年比プラスで推移した。その内訳を所定内給与、所定外給与、そして特別給与の寄与に分解すると、所定内労働時間は減少する中(2章1節を参照)で、所定内給与が安定的に増加していることが分かる。所定外給与は、残業時間の減少もあって、2019年は前年比で小幅なマイナスで推移してきた。専らボーナスによって構成される特別給与については、支給のタイミングが前年と変わる影響が生じることから単月では振れを伴いつつ、前年が大幅に増加したこともあって、均してみればマイナス寄与となった。
このうち、所定内給与と所定外給与から構成される定期給与について、一般労働者、パートタイム労働者、そしてパートタイム労働者比率に要因分解すると、パートタイム労働者比率の上昇という構造的な押し下げ要因は残るものの、過去に比べると小幅に止まっている。全体としては、給与水準の高い一般労働者の寄与が大きく、定期給与の総額は前年比プラスで推移している(第1-1-6図)。
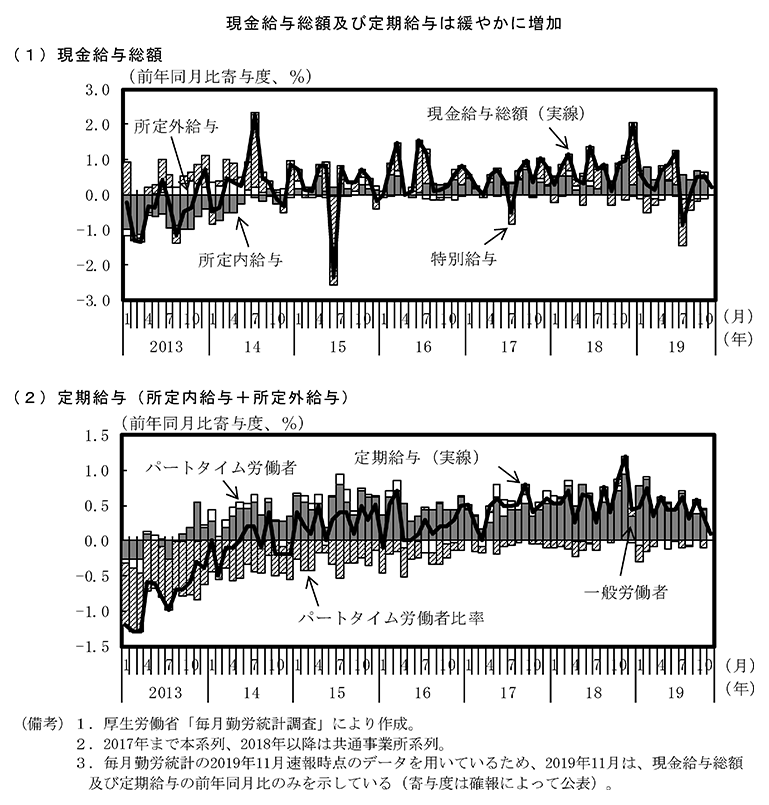
さらに、労働需給のタイトさが賃金上昇につながっているか否かを確認するため、労働需給の変化を表す指標として欠員率2と賃金上昇率(時間当たり所定内給与の変化率)の関係を業種別にみると、一般・パートタイム労働者の違いを問わず、欠員率が上昇している業種では賃金も上昇している傾向がみられる。2016年から2018年にかけて、特に、宿泊業・飲食サービス業、建設業の欠員率が大きく高まっており、こうした人手不足業種では賃金上昇率も高くなっている。また、同じ欠員率でも、一般労働者よりもパートタイム労働者の賃金上昇率が高くなる傾向がある。
では、業種別にみた賃金の水準はどうだろうか。賃金上昇率が高い業種を確認すると、建設業については全産業の平均と同程度の賃金水準となっているものの、宿泊業・飲食サービス業は、一般労働者の月給とパートタイム労働者の時給の双方で最も低いグループに属している。反対に、賃金水準の高い教育・学習支援業では、欠員率の低さを受けて賃金は上昇しておらず、対照的な動きとなっている。
我が国全体の賃金上昇は、労働需要の強さに対して、緩やかなペースにとどまっているが、業種別にみれば、労働需給の引締りと賃金上昇率の関係はよりはっきりする。しかしながら、賃金水準の低い業種やパートタイム労働者の賃金上昇が強まっているため、加重平均された一国全体の賃金が力強く増加するには至っていない。今後の更なる賃金上昇には、一般労働者やより幅広い業種で賃上げの動きが広がっていくことが必要である(第1-1-7図)。
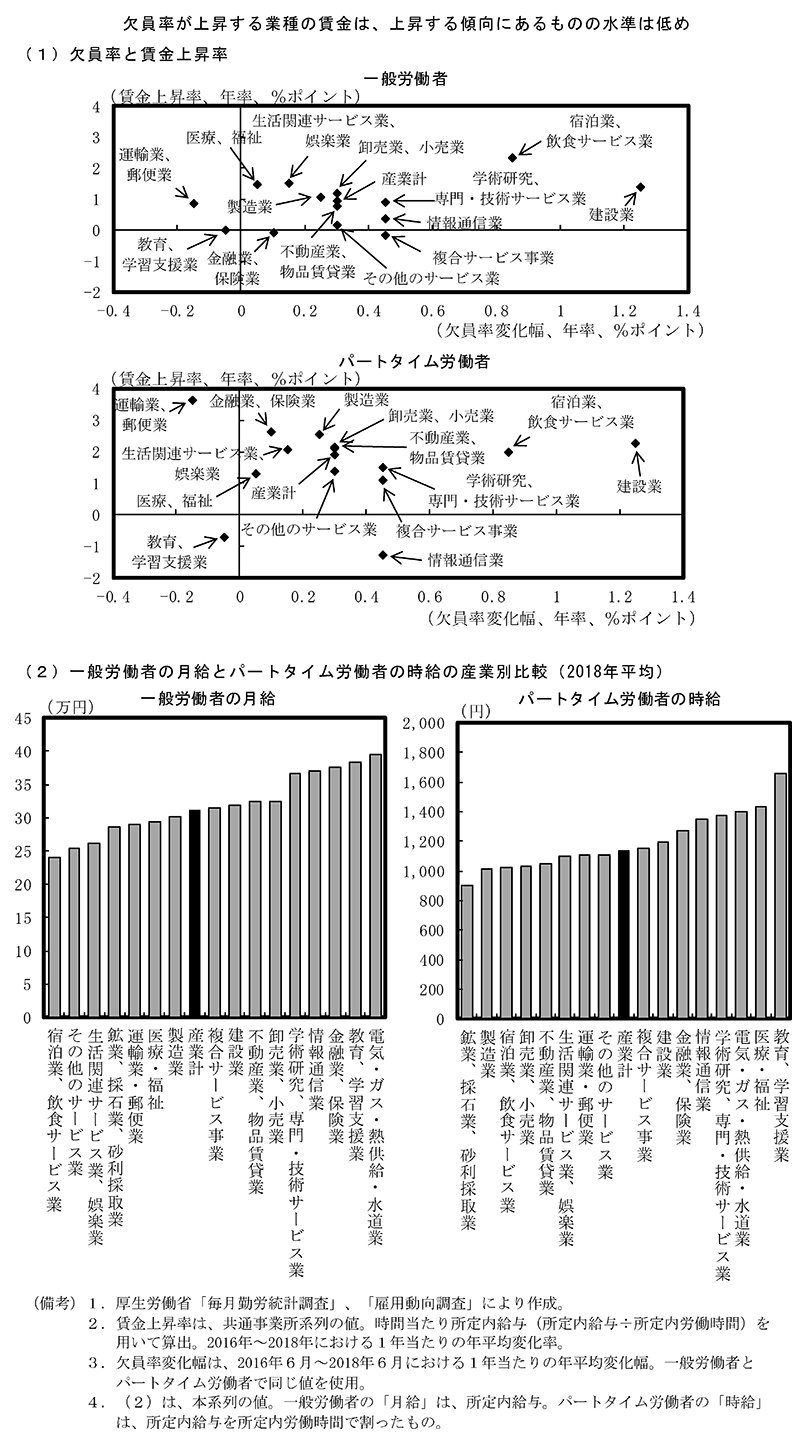
(物価は低い伸びで安定的に推移)
続いて物価動向を概観する。2%の物価上昇率目標を達成するためには、企業の価格設定が前向きになり、そうしたことによって生じる収益増を賃金上昇の原資としていくメカニズムが働くことが必要となるが、2019年の動きはどうであったのだろうか。
まず、消費者物価の推移からみていこう。総合、生鮮食品を除く総合(コア)、そして基調判断に用いている生鮮食品及びエネルギーを除く総合(コアコア)の3系列のうち、前者2つは、エネルギー価格の変動により、2019年は前年比変化率のプラス幅を縮小させてきた。他方、コアコアは、おおむね安定的な前年比のプラスを維持しており、緩やかながらも上昇を続けている。構成品目別の増減寄与をみると、原材料や輸送コストの上昇の転嫁もあって、食料品のプラス寄与が大きい。また、耐久消費財や個人サービスについても、小幅ながらプラスに寄与している(第1-1-8図)。
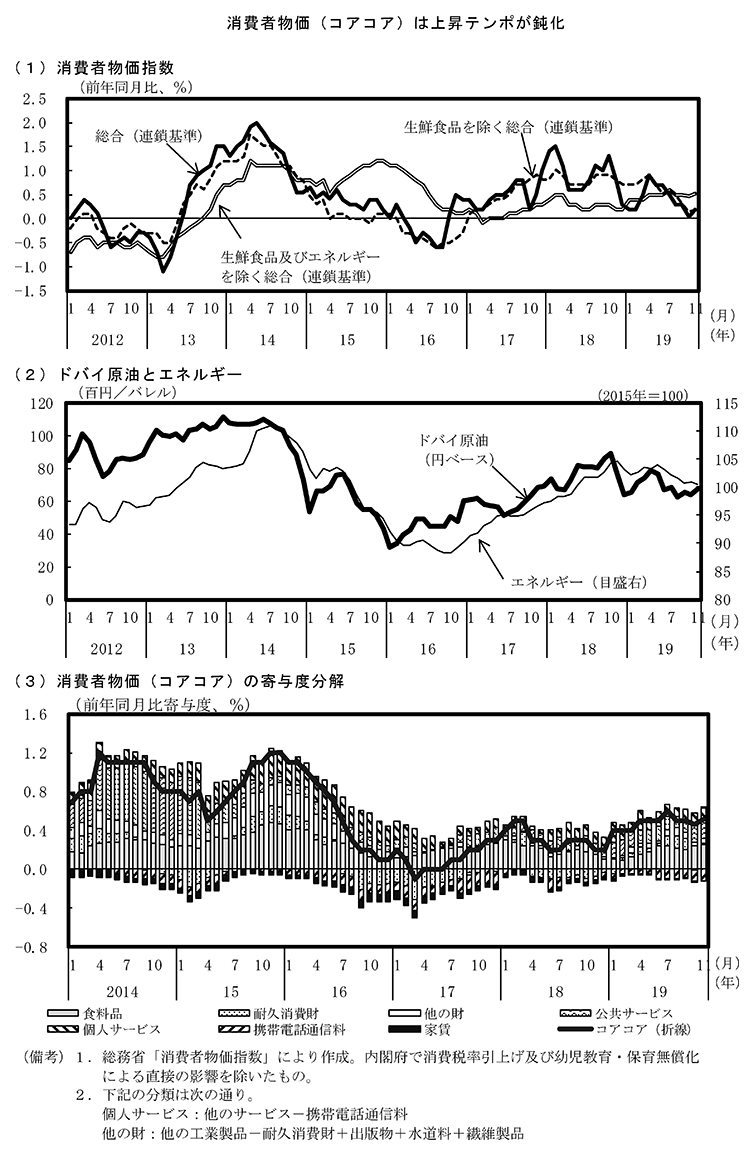
2019年10月には、消費税率の引上げもあったが、今回は、軽減税率の導入により、引上げ品目から食料品等が除外され、また、幼児教育・保育の無償化が同時に実施されたことから、消費者物価指数(総合)は小幅な上昇にとどまっている。消費税率そのものの影響は、前回では、3%ポイントの税率変化によって1.8%ポイントの上昇寄与となっていたが、今回は、軽減税率の導入と税率の上昇幅が2%ポイントにとどまっていることから、上昇寄与は0.8%にとどまっている。また、幼児教育・保育の無償化は0.6%ポイントの押下げ寄与となったことから、制度改正による変化は0.2%ポイントの上昇にとどまっている。なお、消費税率引上げ等以外の物価が前年同月比0%となっているのは、コアコア部分が同0.5%とプラスであったものの、10月のエネルギーの寄与が-0.3%、生鮮食品の寄与が-0.2%であったことが影響している3(第1-1-9図)。
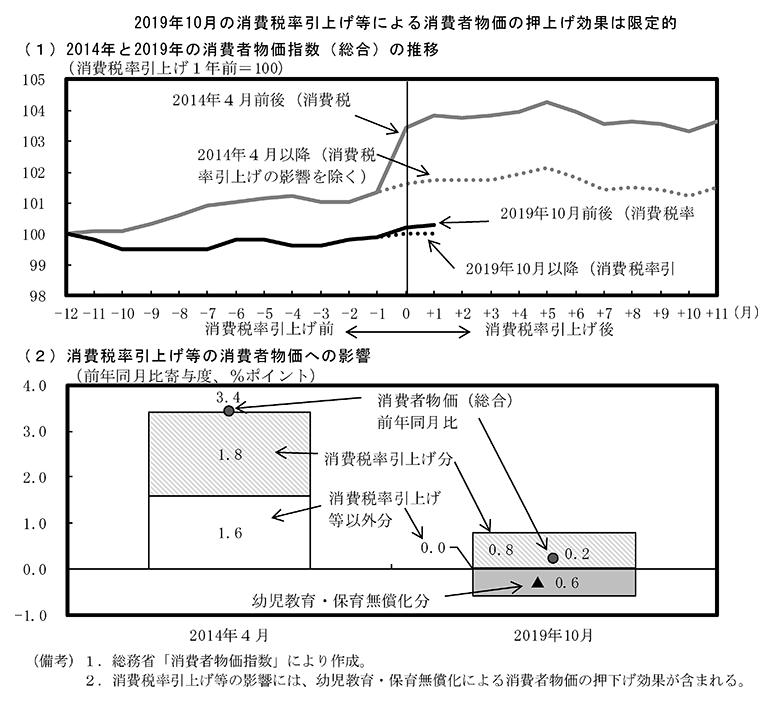
(生産性向上を上回る賃金上昇の継続が物価上昇の鍵)
消費者物価の上昇率は、目標とする2%を下回る動きとなっているが、この要因について関係指標によって分解してみよう。ここでは生鮮食品を除いた総合(コア)の動きについて、慣性を示す前期の動き、輸入物価や為替レートといった外生的な影響、需給環境を示すGDPギャップ、そして人々の先行きの期待物価上昇率によって推計している。その結果、2019年は慣性が働くことや期待物価上昇率の高まり、あるいは需給環境がタイトに推移したことを背景にプラスが維持されていることがうかがえる(第1-1-10図)。この式において、基調形成に重要となるのは慣性と期待物価上昇率であり、こうした項目がプラス寄与となっている点は評価できるが、その水準は低い。個別の小売物価の形成において、企業や家計のデフレマインドが残っており、経済全体としては価格が上がりにくい体質である点は大きく変わっていないとみられる。
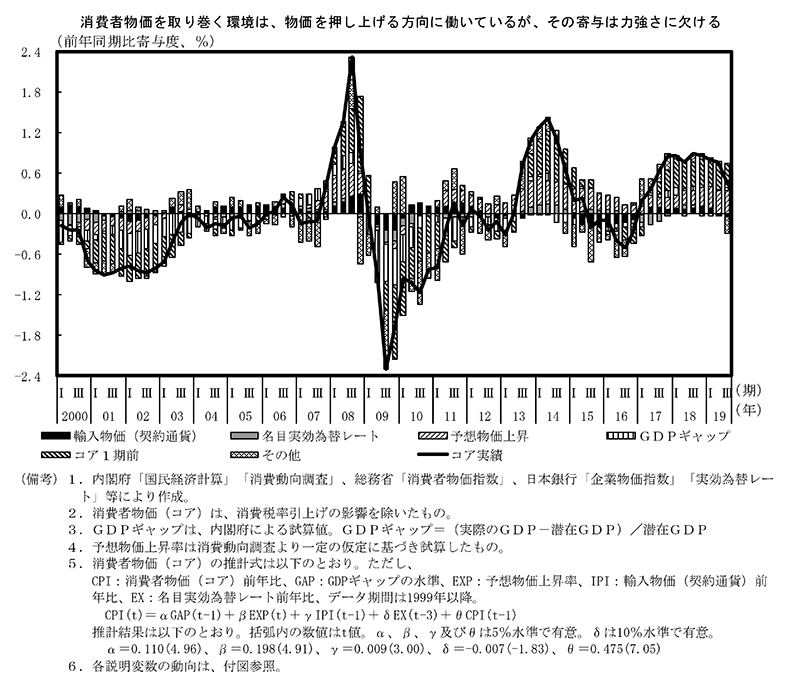
次に、賃金を起点とするマクロ的な物価上昇の原動力となる単位労働費用(ULC)の動きをみると、2018年以降、賃金要因は継続的にULCの押し上げに寄与してきたものの、2019年は労働生産性の上昇が大きく、労働コストの吸収が為されたことにより、物価への押し上げ要因となるULCは小幅なプラスにとどまっている(第1-1-11図)。
製造業と非製造業に分けてULCの要因分解をすると、一般的には、労働集約的な業種が多い非製造業部門の労働生産性上昇率は製造業に比べて低めに推移し、その結果、賃金要因によってULCは押し上げられると考えられる。他方、2019年については、製造業において、生産の弱含みもあって労働生産性の上昇率が抑制された結果、ULCは賃金上昇を受けて上昇基調を維持する一方、非製造業においては、労働生産性が大きく上昇したことにより、賃金上昇から物価への上昇圧力が大幅に緩和されたことがうかがえる。
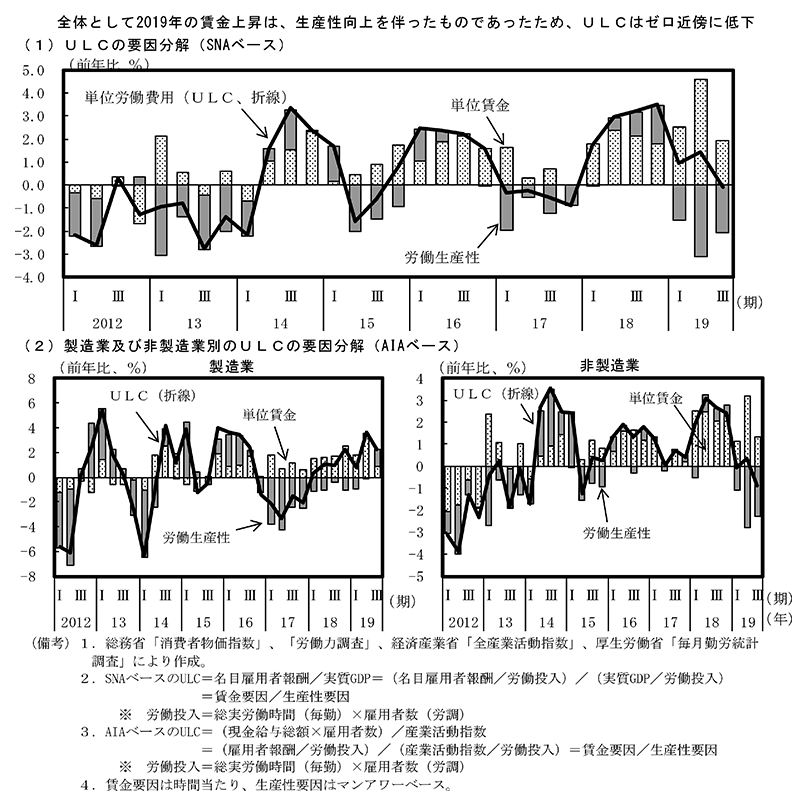
加えて、こうしたULCとコアコアで測った消費者物価の関係は、過去2回の景気循環時と比べると、その連動性が低下している。コアコアの前年比上昇率はULCの変化とは関係なく高まっているものの、ULCの上昇によって消費者物価が変動する程度は、0.14から0.08へと低下している4(第1-1-12図)。賃金上昇には労働生産性の上昇が必須ではあるが、デフレを脱却し、安定的な物価上昇の世界へと移行するまでの間は、労働生産性の伸びを上回る賃金上昇が許容できるような販売価格・消費者物価の上昇が連動していくことが求められる。
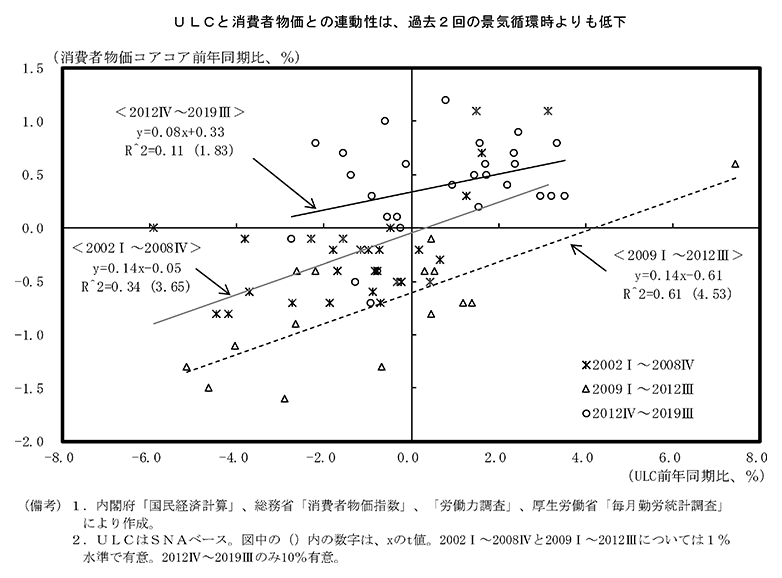
3 世界経済減速下でのマクロ経済運営
(政府支出は増加しているものの、これまでのところ財政健全化も進展)
世界経済の減速によって外需の成長寄与がマイナスとなるなか、堅調な内需の一翼を担うのは政府支出である。他方、政府は財政健全化目標も掲げており、基礎的財政収支の黒字化にも取り組んでいる。デフレ脱却を目指し、大胆な金融緩和を実施しつつ、機動的に財政政策を活用してきたが、2012年以降、基礎的財政収支の赤字幅は4%弱も縮小している。収支改善の要因をみると、歳出面のGDP比は減少こそしないものの、その増加寄与はおおむねゼロに抑えられており、改善の下支えをしている。赤字縮小の主要因は歳入の増加であり、消費税率の引上げといった制度変更要因が含まれるものの、経済の活性化を通じた所得要因が大きく寄与している(第1-1-13図)。これまでのところ、経済再生と財政健全化の両立を目指す政策方針は、二兎を得る結果を生み出せているといえる。
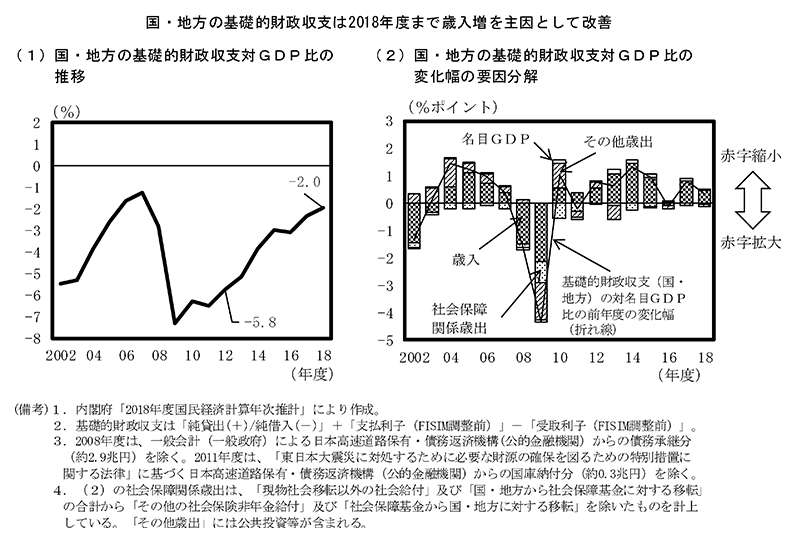
こうしたなか、政府支出である公需の動向をGDP統計でみると、個人消費や設備投資といった民需とともに、経済成長に寄与している(前掲第1-1-1図)。公需の実質GDP成長率に対する寄与度は、2019年4-6月期、7-9月期に、それぞれ0.4%増、0.2%増と強めのプラスとなったが、2四半期を通算して過年度と比べると、政府消費の寄与が高まっている5。政府消費は、社会保障関係費のうち医療費、介護費の保険給付分等が実物給付として含まれるため、再分配的な要素の強い支出でもあり、民需を下支えする効果もあると考えられる。もう一方の政府投資についても増加寄与となっているが、これには2018年度に生じた自然災害への対応等の支出が含まれている(第1-1-14図)。
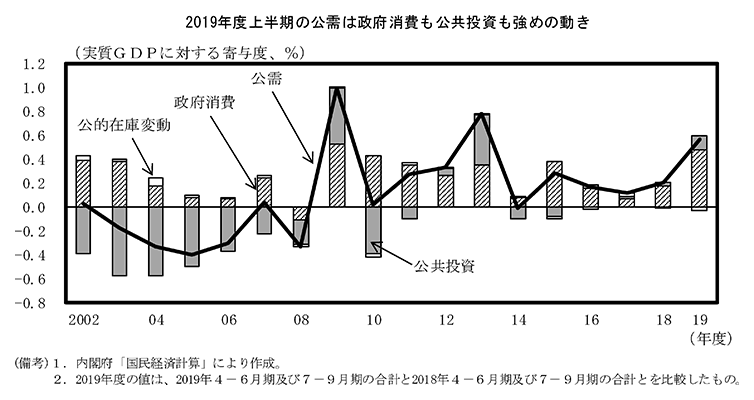
(国土強靭化、災害からの復旧・復興への対応のため公共投資は堅調)
公共投資の動きについて詳しくみていこう。公共投資は、「防災・減災、国土強靭化のための3か年緊急対策」を2018年度からの3年間で集中的に実施するため、2018年度補正予算及び2019年度当初予算の「臨時・特別の措置」が手当てされており、その執行を背景として堅調に推移している。
事業の進捗状況について公共工事出来高の推移をみると、2019年に入って増勢が加速しており、2019年10月には1.9兆円台の高い水準に至っている。手持ち工事高についても、交通インフラ等を中心に大型工事の受注が増加していること等を背景に、引き続き高い水準が維持されている(第1-1-15図(1)(3))。
他方、公共投資の先行指標である公共工事受注額は、2019年の夏以降に頭打ち感がみられている。その背景を探るため、建設業における経営上の問題点を調査したアンケート結果をみると、「受注の減少」と回答する企業数は減る一方、「人手不足」や「高齢化」を挙げる企業数が増加している。したがって、受注額の伸び悩みは、事業量不足ではなく、受注側の制約によるところがあるとみられる(第1-1-15図(2)(4))。今後は、こうした制約に対し、建設業の担い手確保やICTなどを活用した生産性向上による公共事業の円滑な施行が求められる。
また、公共投資の先行きについて、予算面から考えると、「安心と成長の未来を拓く総合経済対策」(令和元年12月5日閣議決定)に基づき、令和元年度補正予算案で1.6兆円が、また、令和2年度当初予算案における「臨時・特別の措置」として0.8兆円が、通常の公共事業関係費に加えて措置されており、今後の公共投資を支えていくものと考えられる。